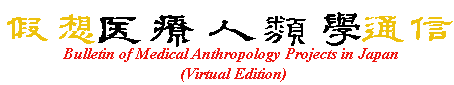
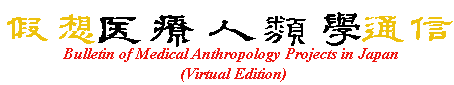
第6号(2000年8月)
シャーマニズム研究における「治療効果」再考
---ボルネオ島カリス社会のバリアン儀礼を事例として---
奥野克巳 Katzumi OKUNO, Copyright 2000
I はじめに
アトキンソンは、「シャーマニズムの現在」と題する1992年の論文( ATKINSON 1992 )の冒頭で、シャーマニズム研究が、ほんの2、30年前にはいったんアメリカ人類学において取り上げられるべき主要なトピックではなくなったが、1980年代に入ってから再び活性化したことを指摘している。彼女は、その再活性化が、意識の変容状態に対する学際的関心および精神の別形態への大衆的関心によるものだと見ている。
彼女によれば、現在、人類学は基本的にはこのようなシャーマニズムの理論化に与するのではなく、シャーマニズムのカテゴリー自体を脱構築しつつあるところなのである。それは、人類学者が、地球上のさまざまな地域に多様な形態をもつシャーマニズムに対して(外部から)一般化がなされてきたことに対して不信を抱いているからなのだという。
アトキンソンがいうように、人類学が、多様な形態をシャーマニズムというカテゴリーのもとで論じることを脱構築するために、シャーマニズムの置かれた固有の歴史的・文化的・社会的な文脈に配慮することは重要なことである。ところが、この点に集中するあまり、シャーマニズムという術語のもとで捉えられる現象には、共通した特徴が認められてきたという点を見逃してしまってはならない。シャーマニズムというカテゴリーを脱構築する前に、共通性のもとにシャーマニズムをひとまとめに論じてきたシャーマニズム研究の枠組がどのようなものであったのかをいま一度問い直してみる必要がある。
以上の点を踏まえれば、いま真に脱構築すべきなのは、シャーマニズム研究という研究のための枠組を支えてきた見方やそこで使用されている諸概念であり、また、強く求められるべきなのは、そのことを通じて、シャーマニズムという術語のもとで捉えられる多様な形態をもつ現象を、その個別性に配慮しながら、よりよく理解するための有効な視点を切り拓いてゆくことなのではないだろうか。この観点から、小論は、とりわけ、シャーマニズムに病気治療の可能性を読み解こうとする人類学のシャーマニズム研究の枠組を俎上にのせて批判的に検討し、シャーマニズム研究の新たな展開に向けての予備的考察を行なうことを企図する。
さて、ヒポクラテスは、紀元前四世紀に、病気が超自然的な力によって引き起こされるという考えを否定し、病気には全て自然発生的な原因があると説いて、合理的な治療科学の発展の基礎を築いたとされる。その考えはやがて、19世紀後半に欧米諸国を中心に興隆した「科学的医学」1)へと至った。しかし、身体を機械として捉え、身体面に関心を集中してきた科学的医学は、病気治療において幾つもの限界に直面することになった。その結果、それは、次第に、精神的次元をも含めた全人的存在を斟酌することによって治療にあたるべきだとの認識から、シャーマニズムや心霊治療などに目を向けるようになった( cf.ワイル 1993[1988] )。
科学的医学におけるこのような傾向と並んで、地球上の諸社会の人びとの生活の諸側面を研究対象としてきた人類学も、シャーマニズムの「治療効果」について、これまで大きな関心を寄せてきた( cf. ATKINSON 1991: 313-314 )。レヴィ=ストロースは、シャーマンは、病気によって混乱した病者の象徴的な意味世界の秩序回復を図ることによって病気治療を行なうと指摘した( LEVI=STRAUSS 1963 )。また、ターナーの儀礼論を継承し、発展させたパフォーマンス論では、病者が儀礼に参加することによって、病気に関わる象徴的意味、病者を取り巻く社会的関係が再確認され、変容させられる結果として病気が治ると論じてきた( KAPFERER 1983, SCHIEFFELIN 1985, DESJARLAIS 1989 )。アトキンソンは、これらの議論を踏まえつつ、シャーマニズムの「治療効果」が、象徴、劇および治療の相互作用において理解されるべきであると唱えた( ATKINSON 1987 )。フィンクラーは、レヴィ=ストロースに依拠しながら、メキシコの神霊術寺院で行なわれる儀礼のもつシンボルが「治療効果」を促進する傾向にあることを論じた(フィンクラー 1989[1983] )。さらに、上田は、身体レベルのコミュニケーションに依拠しつつ、イメージ心理学的な観点から、シャーマンによる儀礼の癒しの効果について考察した( 上田: 1990 )。
これらに先行する人類学のシャーマニズム研究が、シャーマンのトランス状態の研究やシャーマンの異世界への旅などの詳細な記録に傾注してきた( cf. 波平 1992: 3 )のに対して、これらの諸研究が儀礼に照準をあてて、儀礼の過程が人びとにとってもつ意味を明らかにしてきたという点で、シャーマニズム研究の進展に対する寄与は大きい。ところが、これらの人類学のシャーマニズム研究に見られる共通した問題点は、シャーマニズムに「治療効果」があるはずだという前提を持ち込んで「なぜシャーマンによって癒されるのか」という点に集中して議論してきたことにあるのではないだろうか2)。
以下では、筆者が調査研究を行なったボルネオ島のカリス( Kalis )社会3)のシャーマニズムの事例を記述・分析することを通じて、シャーマニズム研究が縛りつけられてきたこの問題点の編制過程に対する一つの見方を明らかにしてみたい。そして、そのことによって、シャーマニズム研究において脱構築されるべき問題の所在を示した上で、シャーマニズム研究に新たな見通しを開くための準備作業を行なうことが小論の目的である。なお、以下では「シャーマニズム研究」という語を、とりわけ「人類学のシャーマニズム研究」の意味において使用する。
II カリス社会のシャーマニズム
カリスは、インドネシア領西カリマンタン州(ボルネオ島)を東から西に流れるカプアス河に注ぎ込むマンダイ川の支流カリス川流域とその周辺に居住する、人口二千人弱の焼畑稲作民である。
カリス人居住地には、科学的医学の知識に基づいて体系的に診療を行なえる医師はいない。病気や怪我が深刻なものである場合、病者は、医師が常駐する、インドネシア政府管轄下の「社会保健センター( Pusat Kesehatan Masyarakat )」のある、15ー30kmほど離れた村に運ばれなければならない。ところが、カリス人居住地では、村と村を結ぶ道が未整備で、かつ、河川を通じた公共の交通手段がないため、重病者の移送は困難を極める。たとえ医療機関で治療を開始できたとしても、大抵の場合経済的な理由から、それに継続的に頼ることは難しい。
このような事情から、カリス人居住地では、1986年にインドネシア政府による「巡回医療サービス( Puskesmas Keliling )」が始められた。ところが、1995年に至るまで、医師の巡回は不定期である。例えば、一ヶ月に一度ずつ医師が来ていたかと思うと、次の数ヶ月は来なかったりする。医師が来るという情報が伝えられると、人びとは列をなして診療用の小屋を訪れる。あらゆる心身の変調がこの機会を利用して医師に相談され、即効を期待して注射と投薬が熱望される。
一般に、薬草による初次的な処置や、近代医療に基づく治療を施しても症状に変化がなければ、その病気や怪我は、(1)「精霊に打ち負かされる( kana antu )」ことによるものか、(2)「人間に打ち負かされる( kana tau )」ことによるもののどちらかであると考えられる傾向にある4)。場合によっては、病気の症状が現われたり、怪我をした初期の段階から、そのどちらかに原因が求められることがある。
カリスは、病気や怪我が「精霊に打ち負かされる」ことによるものではないかと類推した場合、「バリアン( balian )」5)と呼ばれるシャーマンを病者の家に招いて夜通し儀礼を行なう。筆者が現地調査を行なった1994-5年の時点で、カリス人居住地には男性4人、女性6人、合計10人のバリアンが現存しており、そのうち男性1人、女性3人が現役のバリアンとして活動していた。 以下では、バリアンが行なう儀礼(小論では、バリアン儀礼と呼ぶ)に参加するバリアン以外の病者、その家族および見物客を、集合的にクライアントと呼ぶことにする。また、バリアンが推論と行為の基礎とする精霊が跋扈する領域を「霊界( a realm of spirits )」と呼ぶことにする。バリアン儀礼の記述は他のところで行なったので6)、ここではバリアン儀礼のパフォーマンスについて手短に触れておきたい。
バリアン儀礼は、日没から翌朝あるいは翌昼にかけて行なわれる7)。バリアン儀礼の最大の見所は、バリアンが、病者の霊魂を捕らえている「精霊の殺害( mamuno' boo )」のパフォーマンス、および、精霊に捕らえられている病者の「霊魂を取り戻す( maningkam sumangat )」パフォーマンスを行ない、続いて、病者の頭頂部を通じて、取り戻した「霊魂を身体へと戻す( mananami sumangat )」パフォーマンスを行なうくだりである。他のプログラム(脚注7参照)は省略されることがあっても、「精霊の殺害と病者の霊魂の奪回」および「奪回した霊魂の病者の身体への再定位」の二つのプログラムは、決して省略されることはない。この意味で、これらがバリアン儀礼のパフォーマンスの主要テーマであるということができる。
次節では、具体的な二つのバリアン儀礼の事例を引きながら、主要テーマの一つである「精霊の殺害と病者の霊魂の奪回」を中心に、病因についての発話に着目しつつ、儀礼がどのように構成されるのかについて記述する。さらに、人びとがシャーマニズムに関してどう考えているかについての語りを検討しない議論は「治療効果」についての理解をもたらさないと主張するバレットに倣って( BARRET 1993: 235 )、語りを材料として、儀礼後に人びとがバリアン儀礼をいかに捉えているのかについて見てゆきたい。
III バリアン儀礼の事例から
Ⅲー1.ある幼児の場合
ある日の午後、マルン( Marung )という名前の男性の生後二年に満たない幼児(男)が死に瀕していると聞いてマルンの家に駆けつけると、母親ミアン( Mian )は、その子を二の腕に抱きながら「子どもの意識がなくなった( damate anakku )!」と大声で泣き叫んでいた。夕刻に容態を持ち直したその幼児のために、父親マルンは翌晩バリアン儀礼を催すことを決めた。
翌夕、ブライ( Burai )という名の女性のバリアンはマルンの家に到着するや、幼児の身体を右手でこすりながら幼児の首が(霊界で)精霊に縛られていることを告げ、彼の首から葉っぱのような「もの」を取り出した。病気を実体化して取り出すことは、バリアンの典型的な技法である。その後、ブライは「依り代( sangkaai )」8)の前に両足を伸ばして座り、「スピリットフレンド( aboo' )」9)を呼び出した。
①続いて、ブライは、幼児が「バニヤンの霊( antu nunuk )」10)に脅かされて病気になったと説明した。その直後、精霊に捕らえられている病者の霊魂を取り戻すことを宣言し、右手に刀を振りかざして、戸外に勢いよく走り出てばったりと倒れるというパフォーマンスを行なった11)。
②次に、ブライは鶏を右手に持って病者の祓い清めをして、その鶏を屠った。彼女は、皿の中に垂らされた鶏の血の形状を見て「この彼ら(=幼児の家族)のブユ( buyu' )12)は雌の回虫( tantadu )です。その夫は毛虫( epong )なのです・・さっき彼(=毛虫)はここに座っていましたよ」と述べ、幼児を病気にしたのはブユであると説明した。その後、ブライは依り代の周囲を踊り回って、突然腰に刺した鞘から刀を抜きとって、刀で空を切った。彼女はその場に倒れ、刀の刃には何ものかの血糊がべっとりと付着していた。 ③ブライは、その後、依り代の前に座り込んで「この子どもの魂はバニヤンの霊に悩まされている」と唱えた。ここで、ブライは、再び、病者の霊魂が「バニヤンの霊」に脅かされていると語ったのである。
暫くしてから、隣室で幼児の面倒を見ていたミアンが、子どもの様子がおかしいと訴えかけてきた。すぐさま、ブライは隣室に入り、母親の手から幼児をもぎ取るようにして連れ出して、依り代の周りを踊り回った。ブライによって床に横たえられた幼児は小刻みに身体を揺らし、不自然に手足をばたばたと動かし、目をグルグル回転させ、ついには、口を大きく開けたままになった。ブライは、すでに幼児の身体が熱くなりすぎていてどうしてやることもできないと大声で繰り返し、儀礼そのものを放棄することを宣言した。ブライの指示で依り代が片づけられ、同時に人が死にかけていることを広く知らせるために銅鑼が打ち鳴らされた。幼児は、その夜はなんとか容態を持ち直し、儀礼の翌日町の病院に運ばれたものの、その翌朝そこで息を引き取った13)。
このバリアン儀礼における筆者の疑問は、①「バニヤンの霊」→②「ブユ」→③「バニヤンの霊」が順番に、バリアンによって、病気をもたらした行為主として説明された点にあった。「バニヤンの霊」と「ブユ」は、どちらかが上位の概念であるとか、同一の行為主の別の見え姿であるということはなくて、同等に精霊というクラスのメンバーである。だとすれば、そこで持ち出された複数の行為主は、幼児の病気の経過を説明するためのものとしてどのように理解すればいいのであろうか。バリアンは「バニヤンの霊」を攻撃したのだけれどもそれが誤りであることが分かり、「ブユ」を行為主として捉え直したことを意味するのだろうか。もしそうだとすると、その後、彼女が「バニヤンの霊」を再び行為主として持ち出したことが理解できなくなる。
このことを人びとがどのように捉えているのかを知るために、筆者は後日、その儀礼に最初から最後まで参加していたクライアントのうちの三人に対して、別々に、幼児は何に悩まされていたのかを尋ねてみた。彼らは皆、幼児が「ブユに悩まされていたと思う( danu buyu' saku )」と答えた。「バニヤンの霊」はどうなったのかという筆者の質問に対して、一人はぽかんと聞いているだけだったし、他の二人は「バニヤンの霊」もまた病気の行為主とされたことをかろうじで覚えていた。彼らは、どうやら、そのバリアン儀礼における病気の行為主の複数性をめぐって、筆者が抱いたような疑問を感じなかったようである。
さらに重要なことは、この儀礼以降、家人たちの間で「バニヤンの霊」も「ブユ」もどちらも、幼児の病気の行為主として、再び一切言及されることはなかったことである。筆者が知る限り、マルンの家族は、死んだ幼児のことを思い出して語るものの、当のバリアン儀礼に言及して、精霊に思い至り、それらと病気の関係について語ることはなかった。つまり、マルンの家族によって、幼児の死に至る病いは、事後的には、バリアン儀礼において行なわれたパフォーマンスを通じて経験されることがなかったのである。
そして、その儀礼から約10ヶ月後、マルンの家の隣に住む彼の実兄イマン( Iman )が体調不良を訴えた時、次に見るように、彼の病気に対して(別の)バリアンが招かれて儀礼が行なわれることになった。
Ⅲー2.ある男性の場合
イマンは、最初、森の中で伐採した材木を肩の上に担ぎ上げようとした時、腰部に痛みが走ったのだという。彼は、町から市販の消炎薬を取り寄せて服用し始めたが、薬を飲んでも、腰痛に変化が見られないどころか、その症状はますます悪化し、数日後には立ち上がることさえできなくなった。イマンの実弟マルンたちが、病床のイマンを囲んでこれからの対応を話し合った時に、市販薬が効かないのであれば病気に精霊が関与しているのではないかと推測し、バリアンを呼んで儀礼を行なうことを取り決めた。
翌朝、サンブルン( Samburung )という名の女性のバリアンを儀礼に呼ぶために、隣村に向けて使いが出された。夕刻には儀礼が始まり、最初、サンブルンはイマンの腰部に「バリアンの石( batu balian )」14)をこすりつけながら、イマン(の霊魂)が「バニヤンの霊」にものすごく殴られ、また、それに牛のように括られていると言った。このサンブルンの言葉によって「バニヤンの霊」がイマンを病気にした行為主であることが明かされたことになる。
その後、サンブルンは、家の出入り口から外へ走り出て、刀で空を切って精霊殺害のパフォーマンスを行なった。彼女は右手に何ものかを携えて居室に戻り、その「もの」を茶碗の中におさめると同時に、どこで「バニヤンの霊」が人間(の霊魂)を解放したのかと問うた。サンブルンによって一瞬開かれた茶碗の中を覗くと、それは、水の中に浮かぶ黒っぽい色をした無定型な何かで、暗い灯油ランプの下で、筆者には泳いでいるように見えた。それが何であるのかという筆者の質問に対して、クライアントは「(取り戻された)彼(=イマン)の霊魂( sumagata )」だと口々に答えた。バリアン自身は「もの」が病者の霊魂であると断言することはない。そのことは、クライアントの語りと行為を通じてそのつど構成される社会的な事実である。続いて、サンブルンは、奪回したその病者の霊魂を身体へ戻すパフォーマンスを行ない、翌朝には儀礼は滞りなく終了した。
バリアン儀礼後、イマンは、ずっと床に臥せったままで、起き上がることができなかった。ようやくイマンが起き上がれるようになったという噂を耳にした筆者は、儀礼後33日目に、見舞いを兼ねて話を聞くためにイマンの家を訪ねた。彼は座ったままだったが、筆者を快く迎え入れてくれた。
イマンは、その一週間ほど前から症状が軽くなって、起き上がれるようになったと語った。さらに、彼は、バリアン儀礼において彼の霊魂を捕らえているとされ、それゆえバリアンによって攻撃された「バニヤンの霊」と、バリアンのことを以下のように述べた。
「バニヤンの霊は死んだはずです。もし死んでなかったら、(バニヤンの)木の方が倒れるでしょう。(その場合)おそらく(病気は)繰り返したはずです。あなた方もバリアン(儀礼)には満足したでしょう。皿の中の霊魂など見たことがなかったのでしょうから。あの年寄り(=サンブルン)は、本当にマスターシャーマン( balian madaran )なのですよ」
イマンによれば、「バニヤンの霊」が死滅し、霊魂が身体に戻されたので腰痛が治ったのである。もしその精霊がバリアン儀礼において死ななかったとしても、バリアンに攻撃されたのだから、宿っているその木から逃げ出しただろうし、その結果主を失った当のバニヤンの木は倒壊するだろうというのである。その場合、「バニヤンの霊」は生きているので病気は繰り返したはずなのである。さらに、イマンは、腰痛が治って起き上がることができたのはサンブルンのおかげであり、彼女はマスターシャーマンとして評価できるのだという。その後、イマンは順調に回復したようで、それから一週間ほどして、筆者は彼が村の中を歩いている姿を目にした。
IV バリアン儀礼は「治療」のための儀礼か?
さて、Ⅲー1において、死に至った幼児のケースで見たように、病気は、バリアン儀礼を行なったからといって必ずしも治るとは限らない。他方、Ⅲー2のイマンのケースで見たように、バリアン儀礼を行なった後、バリアンによって病気が回復したのだと語る場合もある。これらの事例からは、バリアンが、バリアン儀礼を行なうことによって病気を治すことができるかどうかについて確実なことをいうことはできないように思える。
バリアン儀礼が必ずしも病気を治すための機会にはなっていないというこのような事実が、カリス社会において一般化できるかどうかかを確かめるために、筆者が仔細に観察した合計15回のバリアン儀礼の「治療効果」に関するデータを取り上げてみよう。病気とは自己限定的なものであるという指摘を踏まえて(フィンクラー 1989[1983]: 116 )、バリアン儀礼の「治療効果」に関して、ここでは病者およびその家族の語りに注目してみたい。
15回のバリアン儀礼のうち、儀礼後に病気が治ったと考えられるケースは7回あった。内訳は、「儀礼後、病者自らがバリアン儀礼で治ったと語ったケース」が2回、「病者が幼児の場合で、家人が、病者がバリアン儀礼で治ったと語ったケース」が1回、「バリアン儀礼の終了時点において、すでに病気が治っていることが明白だったケース」が1回、「バリアン儀礼後、徐々に病気が回復したケース」が3回(この場合、筆者は、彼らから直接にバリアンによって病気が治ったとは聞いていない)である。この中には、バリアン儀礼が終わってからすぐに町の病院で診察してもらったり、市販薬を併用したケースを5回含む。したがって、バリアン儀礼後に病気が治ったと考えられる7回のうち、バリアン儀礼だけによって病気が治ったと考えてもよいのは、僅か2回だけである。
他の8回は、バリアン儀礼が「治療効果」をもたらさなかったと考えられるケースである。そのうち「儀礼の直後、または暫く後に病者が死亡したケース」が3回、「儀礼後、病状に変化がなく、病者がバリアン儀礼では治らなかったと語り、その後バリアン儀礼以外の療法を採用したケース」が3回、残る2回は「子どもを授かることを目的として行なわれたが、その結果が得られなかったと語ったケース」である。
このデータは、バリアン儀礼が病気を治すことができるかどうかについて確かなことをいうことができないという、前節の事例から導出された上述の見解を追認する結果となっている。言葉をかえて言えば、バリアン儀礼は、必ずしも病気を治すための機会ではありえないということになる。
だとすれば、カリスの人びとは、「治療効果」があるかどうかもはっきりしないそのような儀礼に、なぜ病気の回復を委ねることがあるのだろうかという素朴な疑問が浮かんでくる。はたして、バリアン儀礼を含むシャーマニズムの当事者において、そもそも「治療効果」が期待されていると考えてよいのだろうか。小論では、このような疑問を含むシャーマニズムの「治療効果」の問題に対して解決の糸口を見出すために、以下の節で、カリスのバリアン儀礼のデータを基礎としながら、シャーマニズム研究の枠組について検討してみたい。
V シャーマニズムの手続きにみられる特性
バリアン儀礼のパフォーマンスにおいて行なわれていることはいったい何であったのか。科学的医学の「治療」において行なわれているのが、身体上の疾患に対する直接的な処置であるという点を手がかりとして分析的に考えてみよう。
Ⅲー1で見たように、ブライという名のバリアンは、病者の霊魂が「バニヤンの霊」や「ブユ」によって悩まされているのだとその時々に説明して、その霊魂をそれらの行為主から奪い返すというパフォーマンスを行なっている。Ⅲー2で見たように、サンブルンという名のバリアンは、病者の霊魂が「バニヤンの霊」によって縛りつけられているのだと説明し、その霊魂を奪い返すというパフォーマンスを行なっている。このようなパフォーマンスのあり方に注目すれば、バリアン儀礼で行なわれているのは、病気の発生した身体上の器官に対する直接的な処置ではなくて、病気に置き換えられた霊界の出来事に対する処置だということができる。バリアン儀礼で、バリアンは、病者の身体に現われる病気そのものの処置を行なうのではなく、経験される病気を、それと構造上類似の関係にある霊界の出来事に置き換え、その出来事の処置を行なうのである。
シャーマンは、身体上に起こる病気を、不可視の次元で病者の身体に矢が突き刺されたために起こったのだという別の次元の出来事に置き換えた上で、その矢を取り除こうとしたり( BROWN 1988 )、病者を取り巻く地理的状況において霊魂が喪失したという、別の次元の出来事に置き換えた上で、霊魂を取り戻そうとする( DESJARLAIS 1989 )などという、シャーマニズムの手続きに対する見取り図がこれまでにも提出されてきた。一般に、シャーマニズムの手続きとは、病者によって経験される症状を、人びとが一般には見ることができない別の次元の出来事に置き換えた上で、その出来事を処理することなのである( cf. VITEBSKY 1995: 148 )。このことから、シャーマニズムの手続きは、科学的医学でいうところの「治療」と同じではないということができよう。
バリアンが、病者に経験された症状を霊界の出来事に置き換えた上でその出来事を処置するのだとすれば、カリスの人びとが、その病気のなりゆきを霊界の出来事のメタファーを用いて過去遡及的に語る時に、病気はシャーマニズムを通じて経験されるのではないだろうか。Ⅲー2で見たように、バリアン儀礼後にバリアンの力を通じて病気が治ったと考えられる場合、人びとによって、霊界の出来事の処置に続く経過が病気の過程と同じものとして捉えられる傾向にある15)。反対に、バリアン儀礼後に病気が治らなかったⅢー1のような場合には、病気が霊界の出来事に結びつけられて語られるようなことはない。そこで見たように、儀礼におけるバリアンの病因の説明については、人びとの間では顧みられることさえなかったのである。それは、その説明が曖昧であったという理由からではなく、病気が治らなかった場合、その事実がバリアン儀礼に関連づけて考えられることがないためであると思われる16)。病気とそれに置き換えられた霊界の出来事を、人びとがこのようにして関連づけて、同一視するようになる機制については十分な注意が必要であり、また、シャーマニズム現象そのものを理解していく上で非常に重要である。この点については、後でもう一度取り上げることにしたい。
IV. シャーマニズム研究における「治療効果」の編制過程
シャーマニズムの手続きが、病者によって経験される症状を別次元の出来事に置き換えて、その出来事を処理することなのだとすると、それは、医師による病者個人の身体および身体の器官に生じた症状への直接的な働きかけという、科学的医学の病気治療の手続きとは似て非なるものであるということになる。ところが、これまでのシャーマニズム研究では、一般にシャーマンは呪術を操る医師のイメージで捉えられていて、シャーマンもまた「治療」を行ない、人びとによって「治療効果」が期待されているという共通した見方がなされてきた( cf. ATKINSON 1992: 313-314 )。だとすれば、シャーマニズム研究において、シャーマニズムの手続きが科学的医学のそれと何ら変らないものであると考えられるようになった編制の過程が、人類学のシャーマニズム研究そのものの成立を問うことの中に見出せるはずである。
すでに見たように、19世紀以降の科学的医学は、病気の在り処としての身体に関心を集中し、身体および身体器官に「治療」を施して「治療効果」を高めるための技術を向上させることで、治療科学としての地位を確立してきた。その後次第に病気治療面での限界に直面するようになった科学的医学は、いったんは非科学的だとして軽視したシャーマニズムの中に科学的医学の知の枠組を持ち込んで、それを病気治療に活用するという目的において研究し始めたのである。このように、科学的医学は、合理的な治療科学者ではないシャーマンが、なぜ病気を治すことができるのかという問いを、自らの研究の指針として立ち上げた。その結果、シャーマニズムは、現状としては、科学的医学に対して従属的な立場に置かれたままなのである( cf. 池田 1992: 161 )。
このような科学的医学側のシャーマニズムへの接近に対して、今世紀半ば以降の人類学におけるシャーマニズム研究も、科学的医学が立てた問いを、研究の指針として暗黙のうちに継承することになった。言い換えれば、シャーマニズム研究は、科学的医学を下敷きとして、シャーマンの病者に対する働きかけを「治療」として、また、治ったり、治らなかったりすることを「治療効果」として見る視点を図らずも最初から研究の指針の中に刷り込んでしまったのである。人類学のシャーマニズム研究が科学的医学の概念を無批判に受け入れるに至った背景として、客観主義的な観点から人間社会の研究を行なった今世紀半ば以降の人類学のスタイルに思い至ることはそう難しくないはずである。
このように、シャーマニズムを観察・分析するシャーマニズム研究の中に、「治療」や「治療効果」といった用語を通じて、あらかじめ科学的医学の視点が持ち込まれてしまったのである。すなわち、人類学のシャーマニズム研究は、シャーマニズムの「治療効果」を研究対象の属性ではなくて、研究のための基本語彙として前提してしまったということになる。この前提は、今日においては、シャーマニズム研究集団の中で、あまりにも当然視されているがゆえに誰一人として問おうとしないという「実定性」(フーコー 1995)を獲得してしまったようである。
人類学のシャーマニズム研究は、地球上のあらゆるタイプのシャーマニズムを研究対象としながら、「なぜシャーマンによって癒されるのか」という問いを出発点に置くことによって、これまでのところ、小論の冒頭で見たような、シャーマニズムの「治療効果」に関する諸理論を築き上げてきた。それらの理論は、シャーマンの諸行為からなる「治療」と、その結果としての「治療効果」の間に横たわる「謎」に合理的な説明を与えるために、個別社会のシャーマニズムの実践形態を大きく越えて、外部から導き入れられた体系的知識だったのである。
さらに、特定の社会・文化的文脈における病気の原因の説明体系を「災因論」(長島 1982)と捉えるならば、科学的医学における病気治療の基礎をなす考えは「西洋近代」特有の、身体に基礎を置くタイプの一つの災因論であることになる。ここでは、これまでのシャーマニズム研究が、地球上でシャーマニズムとして捉えられる現象を評価するために「西洋近代」の災因論の枠組を用いるという、対象を科学的知識を用いて再構成しようとする認識論的態度によって、「知の植民地主義」( cf. 太田 1998 )に荷担することになっている点に注意を喚起しておきたい。
VII. 問題の在り処と新たな研究への代案
Ⅴ節およびⅥ節では、シャーマニズムのパフォーマンスにおいて別次元の出来事が処置されるということと、科学的医学において身体への直接的な働きかけが行なわれていることの間の相異に細心の注意を払わないで、両者が類似的な「治療」の過程であると見なすようになった人類学のシャーマニズム研究の枠組の編制過程を析出し、人類学のシャーマニズム研究もまた、科学的医学に対して従属的な立場にあるということを見てきた。
そのことを通じて、シャーマニズムが科学的医学とは別ものであるという一般図式を提出しようとしたのではない。そうではなくて、シャーマニズムと科学的医学を対比してみることで、人類学者がシャーマニズム研究において脱構築すべきなのは、シャーマニズム研究を支えてきた科学的医学ゆずりの研究枠組であるという点を示そうとしたのである。シャーマニズム研究が、科学的医学への従属的な位置から解き放たれ、シャーマニズムに関する明晰な結論を導いていくためには、「治療」や「治療効果」といったシャーマニズム研究で当然のごとく使われている鍵用語をまず疑ってみる必要があるのだ。
これまでの議論から明らかなように、シャーマニズムにおいて「治療効果」が期待されているということを前提としてシャーマニズムについて論じるための明白な根拠はどこにもなかったことになる。この意味で、バリアン儀礼の「治療効果」に関する筆者の調査データの分析(Ⅳ節)の中には、シャーマニズムに「治療効果」があるのかどうかを読み解こうとするシャーマニズム研究側にあらかじめ用意されていたもくろみが潜んでいたことになる。実は、バリアン儀礼を通じて人びとが治るのか、治らないのかを問題とするという研究枠組の有効性こそが問わなければならない問題だったのである。
重要なことは、「治療」や「治療効果」という科学的医学において普通に使われている用語を、バリアン儀礼およびその他のシャーマニズムに対して一切用いてはならないということではない。そうではなくて、そのような用語がもしシャーマニズムに適用されるならば、それらに対して十全な注意が払われなければならないということであり、多くの場合、「治療」や「治療効果」という用語だけでなく、科学的医学の臨床形態をも相対化する視点に立って、シャーマニズムについて考えてゆかねばならないということである。なぜならば、「治療」や「治療効果」が、科学的医学から人類学のシャーマニズム研究に対して何ら細密な検討を経ることなく引き渡された用語だからである。
ここで、最後に、シャーマニズム研究の脱構築のための代替案として、カリス社会のバリアン儀礼のデータを下敷きとして、一つの可能な研究方略の概要を示しておきたい。それは、Ⅴ節で一部述べたように、人びとの経験に接近しながら、語られた内容は語りに先立つように見えるという語りの持つ特質に注目することによって、儀礼のパフォーマンスにおいて病気に置き換えられた出来事が病気そのものに重ね合わされて語られるようになる、相互行為場面における実践的な知識が展開する機制を詳細に記述・分析するというものである。その場合、当該社会における科学的医学の受容の程度の問題、またその措定をも含めた研究者のポジションの問題に対して細心の注意が払われなければならないだろう。そのことを通じて、科学的医学経由で持ち込まれた状況超越的な知識に捕らわれないで、シャーマニズムを通じていったい何がなされているのかに関して全く新しい知見を提出する道が開かれることが期待されるのである。
VIII. むすび
小論は、人類学者はシャーマニズムというカテゴリーの脱構築を行ないつつあるというアトキンソンの指摘を端緒として、ボルネオ島カリス社会のバリアン儀礼の事例研究を引きながら、粗削りに、シャーマニズムに病気治療の可能性を読み解こうとする人類学的なシャーマニズム研究の枠組自体の脱構築の必要性を説いた。
顧みれば、これまでの人類学のシャーマニズム研究は、身体への直接的な働きかけとしての「治療」に対して「治療効果」を期待する科学的医学の図式を暗黙に継承して「なぜシャーマンによって癒されるのか」という問いを追究してきたがゆえに、シャーマンによる儀礼の過程が病気の治癒に結びつくために「都合のいい理論」を探すことに、あまりにも性急でありすぎた。小論で見たように、シャーマンの諸行為が科学的医学における「治療」行為とは相容れないものであれば、シャーマニズムの諸問題を考察するためには、まず、科学的医学の「治療」と同種・同型のものとして無条件に前提されてきたシャーマニズム研究のシャーマニズムへの見方を再検討し、是正しなければ、シャーマニズム研究において捉えられるべき結論を取り逃がしてしまうことになりかねないのである。
小論は、同時に、「治療」や「治療効果」という、シャーマニズム研究で当然のごとく使われている用語を脱構築した上で、シャーマニズムを享受する人びとの観点に立って、病気と病気に置き換えられた別次元の出来事が結びつけられるようになる社会的な過程を詳細に検討することを、シャーマニズム研究の新たな展開に向けての代案として提唱した。しかし、これについてはここでは十分論じることができなかった。この方向でシャーマニズムの仕組みを徹底的に検証してゆくためには、当該社会における科学的医学の受容程度とその措定の問題や分析的な視点の問題など、検討すべき問題はまだまだ多い。
小論が、全体として、シャーマニズム研究をその研究枠組を含めて再吟味し、進展させるための叩き台となることができれば、予備的考察としての小論の役割は果たされたことになるだろう。
脚注
1)小論でいうところの「科学的医学」は、主に、アロパシー( allopathy )を指す。アロパシーでは、病気は身体に外在する作因によって引き起こされたゆえに、その疾患とは「異なる」薬剤を身体に投与し、治療を行なう。
2)この見方に関しては、一橋大学の長島信弘教授、浜本満教授の示唆によるところが大きい。
3)小論は、1994年1月から1995年12月の24ヶ月間に行なわれた現地調査で得られた資料に基づいている。
4)カリス社会において「精霊に打ち負かされる」ことに起因する病気や怪我のうち、その原因が、特に、出された食べ物・飲み物を断るさいに適切な処置をしなかったために精霊に打ち負かされたのだと説明される場合がある。この点については、奥野 1997b を参照のこと。
5)バリアン儀礼を指すカリス語はない。バリアンは人物と儀礼の両方を指す。
6)バリアン儀礼のパフォーマンスの詳細については、奥野 1998 参照のこと。
7)儀礼は、①病者や依り代(脚注8)に対してバリアンが行なう「祓い清め( sauti )」や、「おしの霊( bisu )」「腰の曲がった爺さんの霊( mongkok )」などに憑依されたバリアンが行なう施薬を通じて、病気という負性を帯びた状況を正性へと転換させる仕掛け、②ハーブ油に浸したバリアンの石(脚注14参照)を患部周辺にこすりつけて、バリアンが病者に対して行なう「ブブティ( bubuti )」と呼ばれる処置を通じて、病気を実体化して排除する仕掛け、③「鶏の血の占い( tanungan dara manuk )」「ビンロウジュの肉穂占い( tanungan mayang pinang )」などの病状理解のための占いから構成される。
8)それは、バリアン儀礼が行なわれる居室の中央に、長さ約2メートルの槍を基礎に15種類の植物の葉を巻きつけて立てられる。それを通じて、バリアンは霊界と交信する。
9)スピリットフレンドはカリス語の「アボー」からの翻訳。バリアン候補者は、心身異常を伴う成巫過程で、守護霊として、数多くのスピリットフレンドを獲得する。バリアンの成巫過程については、奥野 1997c: 97-101 を参照のこと。
10)バニヤン( nunuk )は、桑科の常緑高木で、他の木に寄生して成長するという特徴がある。「バニヤンの霊」は、バニヤンの木に宿る精霊のこと。
11)精霊殺害のパフォーマンスについては、フリーマンが、ボルネオ島北西部のイバン( Iban )のシャーマニズムに関する論文で報告している( FREEMAN 1967 )。
12)ブユは、妊娠期にある胎児および離乳期以前の幼児(の霊魂)を奪い去って、妊婦や幼児に病気や死をもたらす邪悪な精霊。
13)この幼児の死とその解決については、奥野 1997a を参照のこと。
14)成巫過程で獲得されたスピリットフレンドは、バリアンのところに石となってやって来るとされる。それは、バリアン儀礼の中の「ブブティ」において、病者の身体をこするのに使われる。
15)あるバリアン儀礼で、バリアンは病者に対して、体調がすぐれないのは「精霊に銃で撃たれた( datimbak antu )」せいであると説明した。病者は、儀礼後に病気が治ってから筆者に対して、バリアンによって弾丸が取り除かれたために病気は治ったはずだと語った。また、60歳代のある女性は、二十年くらい前に罹った病気は、彼女の霊魂が「水の霊( antu ae' )」に捕まえられたために起こったのだと語った。彼女によれば、当時のバリアンが、水の霊から霊魂を取り戻して、病気を治したのである。興味深いことに、彼女はそれがどんな症状を伴う病気であったのかをすでに失念していた。
16)筆者は、バリアン儀礼後に病気が治らなかった幾つかの事例において、病者自身およびその家族に対して、病気が治らなかったことの理由を尋ねてみた。その質問に対して、彼らは一様に「(バリアン儀礼が)合わなかったのだと思う( asaku bea'na cocok )」と応じた。彼らは、それ以上当のバリアン儀礼について語ろうとはしなかった
参考文献
ATKINSON, Jane Monnig 1987 'The Effectiveness of Shamans in an Indonesian Ritual' American Anthropologist 89(2): 342-355
1992 'Shamanism Today', Annual Review of Anthropology 21: 307-30
BARRET, Robert J. 1993 'Performance, Effectiveness and the Iban Manang', in R.L. Winzeler(ed.) The Seen and the Unseen: Shamanism, Mediumship and Possession in Borneo. Borneo Research Council
BROWN, Micheal Fobes 1988 'Shamanism and Its Discontents', Medical Anthropological Quarterly 2(2): 102-20
DESJARLAIS, Robert R. 1989 'Healing through Images: The Magical Flight and Healing Geography in Nepali Shamans', Ethos 17(3): 289-307
フィンクラー、K. 1989[1983] 「メキシコの神霊術治療の効果についての考察」『医療の人類学:新しいパラダイムに向けて』L.ロマヌッチ=ロス他(編)、波平恵美子監訳、pp.115-142
フーコー、ミッシェル 1995 『知の考古学』中村雄二郎訳、河出書房出版社
FREEMAN, Derek 1967 'Shaman and Incubus', The Psychoanalytic Study of Society 4: 315-44, 1967
池田光穂 1992 「シャーマン」『文化現象としての医療』医療人類学研究会編、メディカ出版
KAPFERER, Bruce 1983 A Celebration of Demons: Exorcism and the Healing in Sri Lanka. Smithsonian Institutuion Press
LEVI-STRAUSS, Claude 1963 'Effectiveness of Symbols', Structural Anthropology. Anchor Books
長島信弘 1982 「解説」『ヌアー族の宗教』エヴァンズ=プリチャード著、向井元子訳、岩波書店
波平恵美子 1992 「まえがき」『人類学と医療』弘文堂
太田好信 1998 『トランスポジションの思想:文化人類学の最想像』世界思想社
奥野克巳 1997a 「ボルネオ島・カリス社会における死とその解決<下>死者の仇を討つ」『SOGI(葬儀)』7(5): 75-78、表現社
1997b 「ボルネオ島カリスにおける災いの説明と災いへの対処---民俗知識としてのカタベアアン---」『一橋論叢』118(2): 141-156、一橋大学一橋学会
1997c 「ラオラオとマウノ---ボルネオ島カリスの狂気の分類について---」『アジア・アフリカ言語文化研究』54: 77-104、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
1998 「バリアン儀礼---ボルネオ島カリスにおける病気治療---」『季刊民族学』83: 76-89、千里文化財団
SCHIEFFELIN, E.L. 1985 'Performance and the Construction of Reality', American Ethnologist 12(4): 707-724
上田紀行 1990 「イメージの治癒力:治療儀礼と深層のネットワーク」波平恵美子編著『病むことの文化』海鳴社
VITEBSKY, Piers 1995 The Shaman: Voyages of the Soul Trance, Ecstacy, and Healing from Siberia to the Amazon. Duncan Barid Publishers Ltd.
ワイル・アンドルー 1993[1988] 『人はなぜ治るのか<増補改訂版>現代医学と代替医学にみる治癒と健康のメカニズム』上野圭一訳、日本教文社
*この論文は、奥野克巳さんの同名論文(『民族学研究』63(3):326-337.1998)のハイパーテキスト版です。この論文は先に、奥野さんのウェブページで公開されていたもの(www.obirin.ac.jp/~okuno/effectiveness.html)です。転載を許可していただいた奥野克巳さんに感謝します(池田光穂 2000.09.02)
Copyright Katzumi Okuno, 2000
| 電脳蛙 | 池田蛙 | 授業蛙 | 医療人類学蛙 |