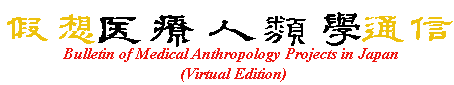
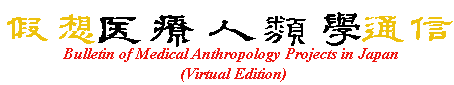
第7号(2001年5月)
ES細胞研究推進の論理への疑問
柘植あづみ Azumi Tsuge, Copyright 2001
ES細胞研究推進の論理への疑問
柘植あづみ
2001年4月19日の朝日新聞の記事によれば、文部科学省が「ヒトES細胞」の研究指針 案を総合科学技術会議に諮問し、同会議が6月までに答申する方針、とのことである。 また「指針ができれば再生医療研究が本格化し、新たな治療法開発につながる」とも ある。
4月19日というのは、文部科学省が旧科学技術会議(現総合科学技術会議) のヒト胚研究小委員会が中心になってまとめた「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する 指針(案)」に対する国民からの「ご意見募集」の結果をまとめた日であり、その結 果は総合科学技術会議に提出され、今後の議論やヒアリングの参考にされるはずであっ た。新聞記事の通りならば、総合科学技術会議は各団体や個人から提出された意見 書67件(団体15、個人52)は、無視された、ということになる。
再生医学、その中でも特にES細胞研究はミレニアム・プロジェクトの一環として、日 本社会の高齢化に対応するために、産官学共同で技術革新を進めようという政府の計 画である。二〇〇〇年度から特別枠の予算が組まれ、さまざまな事業が実行に移され ている。再生医学とは、病気や事故で損傷した骨や血管、神経、皮膚などの組織また は臓器の自己修復をめざす研究であり、二十一世紀の医学として期待される。
再生医学の中でもっとも脚光を浴びているのが、ES細胞(万能細胞)だろう。培養条 件によって、あらゆる組織や臓器細胞に変化する可能性があり、動物実験ではすでに 血管や神経細胞などがつくられている。また、生命維持に必須なホルモンや生体物質 を産出させることもでき、新しい治療薬ができる。夢のような細胞だ。実現可能性が 高いと見做されているのは、神経難病と呼ばれる病気または痴呆に対する脳神経細胞 の再生、事故による脊椎損傷の場合の再生も期待されている。糖尿病においては、イ ンシュリンを産生するすい臓細胞を体外でつくり、細胞をカプセルに入れ、薬の変わ りに体内に埋込むという可能性も検討されている。
しかし、実現には、技術的な問題だけではなく、倫理的な課題も山積している。その ために研究を進める前に指針の準備が必要とされ、先の指針案が作られたのである。 私は、現在準備中の指針案には、3つの大きな問題点があると考える。
第一点は制度的問題である。ES細胞研究に関する指針案は、まずは基礎研究のみを認 めるという理由から、文部科学省のみが担当省である。だが、この研究は再生医学と 密接につながり、また、材料となる胚は医療機関にあるため、厚生労働省の所管機関 とも関わる。さらに、ES細胞は医薬品の開発において人体実験の代替としても期待さ れている。これは経済産業省の所管の企業にも関係する。よって、文部科学省のみで 指針を出さず、少なくとも関連する三省が合同で指針を出すべきである。4省庁(旧 科技庁を含む)合同での指針の作成は、すでに、同じミレニアム・プロジェクトの 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」において実現したので、可能なは ずである。
第二点は、ES細胞の材料となる胚を研究に使用するまでの手続きの問題であるES細胞 をつくるには、人間の胚(受精卵が細胞分裂を繰り返し、胎児になる前の段階)が必 要になる。そこで着目されるのが、子どもができない夫婦が体外受精のために冷凍保 存した胚である。
胚とは、受精卵が細胞分裂を開始し、胎児に発達するまでの段階を指す医学・生物学 用語だ(医学ではその間にさらに胎芽という状態がある)。ふつうは女性のからだの 中にあり、受精卵が分裂してできた細胞のかたまりの状態から、人間の組織や臓器の もととなる部分が決まり、次第に胎児へと発達していく。女性にとっては、妊娠に気 づく前に胚の段階で発達が止まり、知らずに自然流産していることも少なくない。私 (女)の実感としては、胚は「人間とは言い切れないけれど、子どもが欲しいと思う ときには、人間になる可能性のある大切な存在だが、欲しくないときには、それが体 内にあると心理的・社会的問題のきっかけとなる存在」というところだろうか。この 女の実感は、その時の自分が置かれている状況によって大きく変化する。
この女の実感を他所に、胚を研究に使いたい側は、「ヒト胚」という生物学的な呼び 方を採用し、実験材料にする対象を「余剰胚」と表現する。逆に、胚の研究使用に慎 重な側は「ヒト胚は生命の萌芽」という表現を使う。これは胚が、自身の身体の一部 ではなく、他者とみなす「男」の論理だ。
体外受精の成功率は高くはないので、一回で妊娠・出産する人は少ない。その上、排 卵誘発剤や卵巣からの採卵による身体的負担もある。そこで、胚が多く得られた場合 には冷凍保存しておけば、次は冷凍胚を融かして子宮に戻すだけである。これらの中 には、使い切る前に出産したなどの理由から、子宮に戻されずに棄てられる、つまり 「余剰胚」もある。これを研究に提供してもらおうというのである。出産して育児が 一段落した後に、冷凍胚を子宮に戻すこともできる。だが、体外受精では、妊娠率を 高めるために複数の受精卵を子宮に戻すことが多いため、双子、三つ子の出産率が高 い。また、不妊治療の末の出産の場合には、出産年齢が高くなる傾向がある。三〇代 後半で双子が生まれたなら、さらに子どもを欲しいと思う人は少ないだろう。
これまで、「余剰胚」は棄てられるか、生殖医療の研究に使われてきた。現在、胚を 使った研究は、産婦人科学会のガイドラインに従って、患者の同意を得て行われてい るはずである。もちろん、指針案では、十分な説明がなされた上で、夫婦が提供する かしないかを決める、インフォームドコンセントの手続きも明記されている。しかし、 胚を冷凍保存した経験のある人々に尋ねると、保存期限が来て「棄てる」ことに同意 した経験のある人はいたが、「研究に使いたいので同意して欲しい」と説明された人 は、私が尋ねた限りではいなかった。さらに、もし「余った胚を研究のために提供し て欲しいと依頼されたら、どうするか」を尋ねたところ、「お世話になった医師から 頼まれれば、また、それで病気が治る人がいるのなら、胚を提供するだろう。でも、 心の中は複雑です」という意見が聴かれた。
また、棄てるのと実験材料として提供するのは意味が違う。ES細胞は、癌細胞と同じ く増え続ける性質があり、卵巣や精巣となって卵や精子を作り出すかもしれない。夫 婦の受精卵に由来する細胞が、多様な形で生き続けるのである。それに、複雑な想い を抱く人もいるだろう。提供後の不安にどう応えられるのか、という課題もある。
そこで、提供の意思確認は、主治医や研究機関に所属する人ではなく、双方と利害関 係のない第三者機関が行うべきだ、と考える。イギリスには生殖医学や研究における 人間の胚の取り扱い状況を監視する第三者機関(HFEA)が設けられている。提供者や、 将来、新たな治療方法を試そうとする人々の疑問や不安に、この第三者機関が対応で きるようにして欲しい。それが無理ならせめて、臓器移植のドナーカードのように自 主性を尊重するシステムが採用されるべきだと考える。
ES細胞研究指針を設けて研究を進めることが急がれる理由として、国際競争に負けな いため、とよく説明される。科学者の国際競争、特許競争等の経済的な問題、などを 考慮したとしても、なぜ、それほどまでにES細胞樹立の国際競争に負けないことが重 要なのか、も疑問である。実際、樹立されたES細胞を輸入でき、共同研究ならば無償 提供される状況である。科学技術や医療不信を招いては、かえって遅れる結果を招くことになるのではないか。
第三点は、研究推進の大義名分として語られる、その治療を開発する必要性、につ いてである。ひとことで表すなら「かわいそうな患者のため」と考えられていること の問題だ。「この治療が早く可能になるのを患者さんはこんなに大変な思いで待って いる」。これは、あらゆる先端医療が応用される際に医師たちが語ってきた。体外受 精、臓器移植、遺伝子治療、そしていま、再生医学である。
これまでに対症療法しかなかった病気や障害に対して、効果も安全性も高い治療法は、 当然、多くの人が待ち望む医療である。しかし、それを研究・開発しようとしている 人々は、その病気や障害をもつ人々の自身の身体観、日々の生活や想い、についてど れだけ理解しているのだろうか。私は、ES細胞をめぐる議論の中で、治せない病気や 障害をもっていれば、無条件に「かわいそう」であり、「治してあげたい」という論 理が持ち込まれている、と感じてきた。そういう人々の中に、真摯に患者と向き合っ ている医師もいるが、だが、治療の対象となる患者の意見をきいたことがない人も少 なくないようである。診療しているだけでは、意見を聞いたとは言えない。
このような考えは、さらに、「余剰胚」を提供したくない女性・カップルにも圧力を 与える。あなたが棄てようとしている胚が、「かわいそうな患者のため」になるのに、 提供したくないなんて、自分のことしか考えていない奴だ、とされる可能性がある。 ヒト胚研究小委員会の中でも、そこまで露骨ではないが、それに近い論理は臨床医た ちが何度か用いていた。繰り返すが、棄てるのと実験材料として提供するのは意味が 違うのである。
このような問題を解決しないまま、21世紀の医療という名目で研究が進められようと している。これは単に、胚の提供者となる不妊治療をした人々と、治療対象疾患を抱 える人だけの問題ではない。日本の科学技術・医学技術が、誰のために、どのように 発展させるのか、それを誰が決めるのか、に関わる根本となる問題である。また、科 学・医学が、女の身体を女の実感と切り離していくひとつの過程として見ることも必 要である。このミレニアム・プロジェクトを注視し、意見を発信していきたい。
*本稿は『女たちの21世紀』アジア女性資料センター、No.25、2001年2月所収の柘植 あづみ著「21世紀の医学・科学技術―誰のための先端医療か」に加筆したものである。
Copyright Azumi Tsuge, 2001