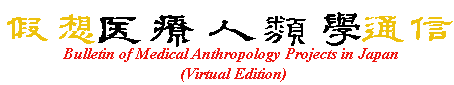 |
top かならず読んでください
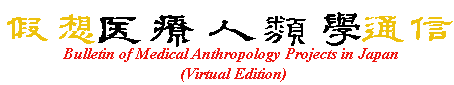 |
イギリス医療人類学の教育事情
オックスフォードだより
島薗洋介
2002年11号
イギリス医療人類学の教育事情
北米には、多くの大学に医療人類学の修士や博士のコースがある。イギリスでも、徐々に各大学に医療人類学の修士コースが開設されるようになってきている。私が知るだけでも、ユニバーシティ・カレッジ・オブ・ロンドン、ダラム大学、ブルネル大学、オックスフォード大学などで医療人類学が専門として学べるようになっている。私は昨年度からそのなかのオックスフォード大学の修士課程に在籍している。今回は、日本で医療人類学を学んでいる人や学びたいと思っている人たちにイギリスの事情にかんする情報提供という趣旨で、医療人類学ニュースレターにエッセーを書かせていただくことになった。ただ、私は他大学のことはまったく知らないので、以下に書くのは昨年度の私の身近な体験のレポートである。 オックスフォード大学に医療人類学の修士課程が開設されたのは昨年度である。初年度入学してきたのは、イギリス人2人、アメリカ人2人、日本人1人(私)、計5人の学生。私は、学部で社会学、大学院で社会人類学を学んでいたが、他の学生は社会人類学、芸術史、生物学、化学を学部時に専攻していた。
昨年度は、初年度ということもあり、学生の数も少なかったが、今年度は学生も12人に増え、それにともないバックグランドも年齢層もさらに多様になった。学生のなかには、医師の人も含まれる。北米でもそうなのだろうが、医師や看護士の人々が実践的な関心から医療人類学を大学院で勉強するというケースも、イギリスでも珍しくないようだ。
医療人類学専攻の学生は、社会人類学科に所属する。社会人類学専攻の学生たちは社会人類学の基礎にかんする講義やゼミに参加するほか、自分の興味にそって、地域やテーマ別の授業を選択するが、医療人類学専攻の学生の場合、社会人類学専攻の学生たちと一緒に社会人類学の基礎を学びつつ、そのほかに医療人類学の特別講義を受けるという仕組みになっている。
昨年度から医療人類学の4つの講義を受けもっているのは、2人の教官である。教官の1人Hさんは、中国の伝統医療にかんする社会人類学的研究を行ってきた人。スイスでも医療人類学を教えていたことがある。もう1人の教官であるUさんは、生物人類学や生態人類学が専門。パプア・ニューギニアやバングラデッシュなどで調査をしていた。このことからも分かるように、医療人類学専攻の学生は、医療、保健にたいする二つの異なった視点を学ぶのである。
昨年度の医療人類学の講義の内容について、かいつまんでのべてみよう。
H教官の第1学期目の授業では、disease, illness, sicknessの概念や、解釈学・マルクス主義など医療人類学における異なったアプローチについて学んだ。また、植民地主義と医療、伝統医療とナショナリズムといった現代的なテーマについての講義も受けた。第2学期の講義では、伝統医療にたいするパフォーマンス論的アプローチや文化現象学的アプローチといったより教官の現在の研究関心に沿ったテーマが中心的に取り上げられた。
Uさんの授業では、一学期目に、結核、下痢、マラリア、HIV/AIDSといった疾患についての生物学的、疫学的な知識を学んだ。二学期目には、栄養と成長・発達や、糖尿病や心循環器疾患などの疾患についての講義があった。また、季節性と健康・疾患、移住と健康、都市化と疾患といった生態学的なテーマもカバーされた。
2人の教官ほかに、他分野の専門家がゲスト講師として授業をすることもあった。医療史の専門家から感染症の歴史についての講義を受けたり、神経生理学の専門から、脳と痛みの知覚についての話などを聞いたりした。また、遺伝子治療にかんする特別セミナーや出産と生殖にかんする研究会に参加する機会もあった。
こうしたカリキュラムは、医療人類学という学問が、一方で社会人類学と深い関係をもちながら、その下位分野というのにとどまらず、学際的な領域であるという性格を反映したものとなっているわけだ。
カリキュラムには、社会人類学的な視点と生物人類学的な視点が連結するようにという工夫が施されていた。たとえば、結核、下痢、HIV/AIDSといったテーマについては、主に生物人類学それぞれの観点から学ぶと同時に、社会人類学的な視点から、それぞれの病の民族誌についても学ぶといった具合。ただ、社会人類学系の授業と生物人類学系の授業のあいだには、生物医学にたいするスタンスや認識論的な前提にかなり温度差があり、学生たちは、これによって混乱したり困惑したりもしたのである。
社会人類学系の授業の内容は、私には、すでにある程度なじみのあるものがあったし、そうでないものでも、比較的理解しやすいものだった。逆に、生物学や化学を専攻していた人にとっては、社会人類学系の授業には当初はかなり戸惑ったり、理解するのが難しかったところもあるらしい。とくに、ある1人の学生は、生物医学をひとつの社会現象として相対化し、批判的に扱う必要性を強調する批判的なアプローチにたいして、強い違和感を覚えていたみたいだった。
私にとって問題だったのは、何といっても生物人類学系の講義だ。これらの講義は、生物人類学科のカリキュラムの一部でもあった。私のような医学・生物学な背景をもたない人間に、生物人類学を専攻する学生と同じ程度に理解しろといわれても、それは無理である。学部生時代に芸術史を専攻していた人と文化人類学を専攻していた人たちも生物学的な授業についていくのに必死だといっていた。ただ、私の場合、言語の問題もあったのでさらに大変だった。なじみ深い社会人類学系の概念なら英語でも知っているが、細胞やら病名となると英語でははじめて耳にするものばかり。はじめは悪戦苦闘で、休みの期間中に結構時間をかけて復習しなければならなかった。とはいえ、多くの話題が新鮮で、新たな興味関心を喚起され、生物人類学の授業から学ぶことも大変多かった。
講義のカリキュラムにひとつ不満点をあげるとすれば、やはり学生の背景知識も全くことなっているのだから、その多様性を鑑みてもう少し何らかのフォローが欲しいところだったということになる。
学生にとっては本当に大変なのは、講義に出席することではない。小論文の提出である。ほぼ毎週のように、二人の教官どちらかから、小論文の課題が与えられた。Hさんから昨年度与えられた課題は、「医療生態学における適応概念にどのような批判がなされてきたか」、「伝統医療の効果はいかにして語りうるか」、「フーコーにおけるclinical gaze概念はどういうものか」など。Uさんからは、「どのような環境要因が糖尿病のリスクを増加させるのか」「環境の季節性は、子どもの健康にどのように影響を与えるのか」など。それぞれ授業の内容と連関している。
もともと生物学や化学をやっていた人たちはH教官に提出する小論文を書くにあたって、existentialやらphenomenologicalやらstructuralistやらといった概念がはっきりと定義が示されないまま使われる文系の文献にむかついたこともあったようだ。しばしばこうした概念についての彼女らから説明を求められ、ときには私も返答に窮した。とはいえ、私としては、Hさんから与えられた課題については、リストにあげられた文献にざっと目をとおせば、どういった論点があって、どういったことを書けば小論文になりそうかぐらいは分かった。
しかし、生物人類学系のほうの小論文となると事情は別だった。文献のどこからなにを理解すればよいのか文章が書けるのか、はじめはよく途方にくれたものである。Uさんは、私に「君は生物学者ではないのだから、疾患の生物学的メカニズムについてすべてを理解する必要はない。社会科学的な視点が重要なのだ」と言ってくれたが、では、生物学的メカニズムについてどれだけ理解すればよいのか、というのが一筋縄ではいかなかったのである。このあたりの雰囲気が徐々につかめてきたのは、ようやく年度末になってから。
小論文をとおして学んだことは、課題にかんする知識だけではなく、じつはこうした暗黙知というか感覚的なものも含まれる。最後のほうには、社会人類学系、生物人類学系それぞれの小論文を書く際に、異なったデータへの言及の仕方や論述のスタイルを使い分けるコツもほんの少しではあるが飲み込めてきた。自然科学系出身の学生たちも文系の言葉遣いや議論のスタイルに徐々になれたことだと思う。
以上が昨年度のコースの概要と私を含めた学生側の経験である。この短文を書くにあたって、昨年度とくに苦労したことは何か、と教官の側はどうだったのだろうと思い、簡単に話をきいてみた。Uさんによれば、新しいコースを立ち上げるときはいつも難しいもので、とくに今回、特別に苦労したということはなかった、という。また、学生を信頼し、分からなさそうだったら個人的に丁寧に指導するよう心がけているのもいつもと同じだったと言っていた。Hさんは、生物学や医学をやっていた学生でも、豊富な社会的な経験があれば、よく社会人類学的な視点の意義を理解するが、今回は、若い学生たちばかりだった(20台後半の私が最年長)、そのあたりで少し難しかったこともある、と語っていた。やはり教官の側からすれば、自分の専門の立場から見た医療人類学を教えるわけなので、とくに特別に変わったことはないのかもしれない。
しかし、学生としての観点からすると、やはり、健康や病にたいする二つの異なった視点に同時に触れることは、いろいろな意味での困難をともなっていたといえるだろう。学生たちのあいだには、二つの異なった世界をどう接続すればよいのか、そのはっきりとした答えが与えられないままに、知らない世界に放り出された感覚も当初はあった。ただ、こうした答えはそもそも与えられる類のものではなく、それぞれが見つけるべきものなのだろう。そして、それはたしかに難しい課題だが、医療人類学を学ぶ上でもっとも興味深い部分でもあるのではないだろうか。
医療人類学のコースに入ってきた学生のバックグランドは多様である。したがって、目的や関心もさまざまだ。医療人類学はさまざまな声が重大事を論じ合っている「ロンドン」だというメタファーがグッドの本のどこかに書いてあったが、集まってくる学生と話していると、まさにそのような気がしてくる。研究を志向する人もいれば、NGOに関わっていた人たちもいる。そうした人たちが医療、病気、健康にたいする異なったアプローチを学ぶなかで、興味・関心を広げたり、考え方を変えたりしていく。それが必ずしも一定の方向ではなく、人によってさまざまだったりするわけである。たとえば、生物学からより社会人類学的な分野に関心を広げていく人もいれば、社会人類学を学んでいたが、公衆衛生にたずさわりたいと思うようになった人もいる。この点が面白いところだ。
どんな学問にも多様な理論やものの見方が含まれている。ただ、医療人類学において、それはとくに重要な意味をもっているのかもしれない。生物学や近代医療の言語と社会科学の言語、その二つはつねに対立するわけではないが、しばしば緊張をはらんだものともなる。この緊張はさまざまな仕方で医療人類学のなかにも反映されている。それは応用的/批判的アプローチのあいだの緊張はそのひとつであろう。いずれにせよ、二つの言語のあいだの境界を、医療人類学を学ぶ学生たちは横断しなくてはならなかった。その横断には、人によっていろいろなかたちがある。学生は実際、そうした経験のなかで考え方や関心をさまざまな方向に変化させていった。私自身の体験のなかで、また他の学生たちと交流していて面白かったのは、こういう点だった。
以上、私の体験したイギリスの医療人類学の教育事情についてざっくばらんに書いてみた。日本で医療人類学を学んでいる学生の方々や学びたいと思っている方々に、何か役に立つ情報が少しでも含まれてはいるのだろうか。そう願いつつ、体験レポートを終えることにしたい。
島薗洋介
Copyright Yosuke Shimazono, 2002.
【編集部解説】
オックスフォード大学院で医療人類学を勉強する島薗洋介さんからメールが来ました。
英国のオックスフォード大学での医療人類学教育ははじまったばかりと聞きます。北米の医療人類学については、日本との関係の深さもあり、さまざまなかたちで紹介されていますが、英国のそれは、まだまだ馴染みがありません。
島薗さんのエッセーは、英国で医療人類学を学ぶことがどのようなことを意味するのか、ということについて示唆に富むレポートになっています。まさに「医療人類学を学ぶことの民族誌」とでも言えるものです。