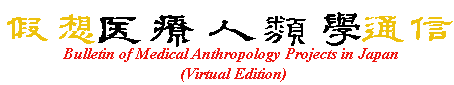Copyright Hidetosih KONDO, 2003
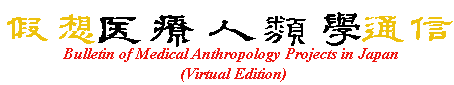
現代医療の民族誌
近藤英俊
Copyright, Hidetoshi KONDO, 2003
近藤英俊「現代医療の民族誌」目次
本稿では主として1960年代から今日に至る欧米の医療社会学理論をふりかえり、そこで検討されている現代医療の特徴、医療を通して見た 現代社会のあり方、さらに理論のもつ現代医療・社会に対する批判性について吟味したい。そしてこの作業を通じて民族誌的研究の意義を浮き彫りにすることが できればと考える。
ここで「現代」という言葉はしばしば定式化されてきた「近代(modernity)」と「ポストモダン(postmodernity)」の両要素を含む 社会的特徴を表すものとする。「近代医療」と言った場合は病と身体をめぐる文化、社会関係、そして実践の総体が近代性を帯びていることを、「ポストモダン 医療」といったときはそれらがポストモダン的特徴をもっていることを示す。社会学上の近代、ポストモダンの意味については後述する。また「生物医療」は西 欧に起源をもち20世紀に入って世界大に広がった生物学と隣接諸科学に基盤をおく医療、その知識体系、技術、組織、機関、そして専門家の実践を指す。生物 医療は確かに近代性を強く帯び近代医療とイコールのものとして理論化されてきたが、ここでは概念的に区別したい。本稿の論点の一つは、近代、ポストモダ ン、さらに伝統という社会学において区別されてきた社会的特徴が、一方向的な歴史的な変化として現れているのではなくむしろ同時に混在しうる点にある。
アメリカの医療社会学において医療並びに医療をめぐる社会のあり方に対する批判性が高まったのは1960年代から1970年代にかけてのことである。批 判の鉾先は第一に生物医療に向けられたものだが、それは同時にアメリカの社会学にそれまで多大な影響を及ぼしていたタルコット・パーソンズの理論に対する 批判でもあった。パーソンズ(PARSONS 1951)理論における医師とは基本的に利他的でクライアントを平等に扱う専門家である。医師は病人を病気という逸脱状態(deviance)から社会に 復帰させるために、普遍的かつ基準化された知識・技術を用いて最良の治療を行う義務を負っている。一方病人は通常の社会的義務からは解放されるが自分のた めだけでなく社会のためにも回復する義務を負う。このように専門家と非専門家がその与えられた役割を果たすことによって維持されるシステムこそ、パーソン ズが理論化した近代社会のモデルといっていい。
こうした構造機能主義的な医療論に対して医師と患者のあいだの不平等な力関係に着目したのが象徴的相互作用論の系譜を引く社会学者である(SZASZ 1960, SHEFF 1966, LEMERT 1972, ROSENHAN 1973, GERHARDT 1989: 73-173)。彼らの見解では医師は診断と治療を通して病人をコントロールする。つまり診断とは個人に抜き差しならぬ逸脱者のラベルを貼ることであり、 治療とは逸脱状態からの解放ではなくむしろその恒常化を意味する。この議論は主として精神病、麻薬中毒、アルコール依存症、視覚障害、言語障害などの病気 や障害に関する医療、つまり長期的な施設への収容をしばしば伴う医療の研究に基づいている。例えばゴフマン(GOFFMAN 1961[1984])の研究は精神病院の入院患者の全生活が規律化され、患者であること以外のアイデンティティーが捨象されていく過程を追っている。ま たこうした隔離によって通常のコミュニケーションする能力は阻害され、退院後も社会復帰が困難となる点も指摘される。スコットの研究(SCOTT 1969)はいったん施設に入った視覚障害者が施設なしでは生活できなくなることを明らかにしている。このいわゆるラベリング(labelling)理論 は反精神医学・反専門家という当時の思想潮流・運動と軌を一にする。
この医療批判の延長線上に位置付けられるのが医療化(medicalization)論である。医療化論は一つの明確な理論的基盤をもっているわけでは ない。それは広く様々な論者によって取り上げられてきた。後に述べるフーコーも医療化論に接近しているといっていい。大筋において医療化とは生物医療の知 識と技術が臨床の場を超えて人々の日常生活に浸透し、直接的には医療と関わりのない様々な活動においても医療専門家が大きな権限をもつようになることと定 義できよう。医療化という言葉を初めて使ったのは社会学者のゾラ(ZOLA 1972)だといわれているが、この問題への関心が一般化したのはイリッチの著作に負うところが大きい。
イリッチ(ILLICH 1975[1998])は生物医療による医療化が医原病をもたらしているとして徹底的に批判する。生物医療は歴史的にみて必ずしも健康状態を向上させてき たわけではなく、むしろ臨床の場では副作用や事故により健康が損なわれている(臨床的医原病)。増加の一途をたどる公的医療費は国家の生物医療への依存 を、薬の消費量の増大は消費者の薬への嗜癖を示すものであり、また就職、入学、資格の獲得、裁判、生死の判定等々、日常生活の様々な局面において人々は医 療専門家の診断を仰がねばならないようになっている(社会的医原病)。また生物医療による痛みの排除は、痛みのもつ人類社会に根源的な文化的意義を消滅さ せるものである(文化的医原病)。イリッチはこの医療化が労働者の再生産と生産性の向上という工業化社会の論理と合致していると指摘する。
医療化に関してはこの他に逸脱現象の医療化の歴史的な過程を吟味したコンラッドとシュナイダーの研究(CONRAD and SHNEIDER 1992)をあげることができよう。彼らによれば西欧史が明らかに示すのは宗教、道徳、法その他様々な分野における逸脱現象が、近代とともに病気とみなさ れるようになったことである。例えば旧約聖書の中では神の啓示、15世紀には魔女の証しとしてとらえられていた狂気が、18世紀末には医者が治療すべき精 神病として規定されるようになる。さらに精神病は20世紀に入ると大脳の器質的障害としてとらえられる傾向が顕著であるという。コンラッドとシュナイダー の研究は後に述べるフーコーの研究と重なるものである。
医療の権力の問題はまた専門職(profession)という視点からも考察されている。フリードソン(FRIEDSON 1970[1992])によれば医師の公的権威は国家によって付与された資格と大学医学部という教育機関に多くを負っている。医師はこの公的権威を背景に 医療組織のヒエラルヒーの頂点に立ち、自律性を確保するとともに病人を合理的に管理する。しかしこの医師の権力は西欧社会では医師が様々な戦略を通して勝 ち取ったものである。いいかえればそれは専門職化(professionalization)の結果である。すなわち専門職化とは、1)高等教育機関で学 習した、2)専門的な知識・技術、そして3)国家による資格化を通して、4)雇用者及びクライアントからの一定の自律性を保ちつつ、5)市場の独占を目指 す職業集団の戦略と定義することできる(TURNER 1987: 140)。医療の専門職化は西欧では19世紀後半に始まった。まず大学医学部出身の医師が強力な医師団を結成し国家へのロビー活動を始める。そして資格と 処方等に関する権限を通して他の様々な医療を駆逐し、ついには医療市場において決定的に優位な位置に立ったといわれる。
医療化論が生物医療による社会の従属化を主張するなら、マルクス主義医療社会学は医療が資本主義社会の一構成要素となっていく点を強調する (NAVARRO 1976, DOYAL 1979[1990], WAITZKIN 2000)。このマルクス主義的アプローチには、1)資本主義経済がもたらす健康問題、2)資本主義国家の医療政策、そして3)医療の商業化という主に三 つの研究対象がある。
資本主義社会における仕事・労働は、効率性、ノルマ、規律で特徴づけられる。また利潤極大化の論理は鉱山労働にしばしば見られるように劣悪な環境での労 働を強いることがある。こうした労働条件は労働者にストレスや過労にとどまらず様々な疾病をもたらす。また利益優先の生産活動は公害や環境破壊を招き、製 品そのものが人体に有害(タバコからファーストフードにいたるまで)であることも少なくない。重要な点はマルクス主義的アプローチにおいて健康問題とはす ぐれて階級の問題でもあるということである。すなわち究極的には資本家・経営者階級による労働者階級の搾取がこうした健康問題を労働者にもたらしていると みなされている。
このアプローチでは国家の医療政策も基本的に資本・経営に有利なものとみなされる。例えば国は一般に労災認定に関しては厳しい基準を設けるが、有害物質を 含む製品の規制には消極的である。産業の振興に結びつかない公的医療への支出は削減しながら同時に健康問題に関する国民の個人的な責任を強調する。 そして三つ目の重要なテーマは医療の商業化である。日本の医療関連産業の売上が農林水産業全体の売上をはるかに上回ることからわかるように、医療には巨大 市場が存在する。このため医療産業はいうまでもなく病院や医師の活動までが商業化しつつある。医療産業は消費者に対してはメディアを通して購買意欲を喚起 し、医療専門家に対しては製品の販売だけでなく研究の委託を通して相互依存の関係を作っている。このようにマルクス主義医療社会学の目的は今日医療が資本 主義経済の論理に従って営まれていることを批判的に検証することにある。
しかしながらこれらの諸理論は1980年代以降精彩を欠きつつあるように思われる。かわって医療社会学に多大な影響を及ぼすようになった のがミシェエル・フーコーである。ここでフーコーの残した巨大な足跡を辿ることは不可能である。医療社会学への影響がとくに大きい初期の「狂気の歴史」 「臨床医療の誕生」、中期の「監獄の誕生」及び「知への意志」に限定して述べていきたい。
「狂気の歴史」(フーコー 1975)では西欧史のなかに精神病と心理学が同時に成立する過程が辿られる。17世紀のフランス絶対王政下、狂人は社会に不穏を与える者として浮浪者や 貧者とともに一般救貧院に隔離される。この空間的な隔離によって二項対立的な認識構造が強まるが、この時まだ狂人は病者ではない。やがて工業化の進展に伴 う労働力不足から「監禁の時代」は終わり、狂人はその労働を担うことのできない者として初めて治療の対象となる。治療はしかしかえって正常者と異常者を峻 別することになる。ピネルの道徳治療は病者を拘束から解放したが同時に彼らに病者としての自覚を促し内面化した。こうして精神病と心理学が成立する。この 研究は狂気が社会的歴史的に多様であること指摘することを超え、異常性や病気の克服のために構築されているとみなされる人間科学が、実はむしろ異常・病気 を実体あるものとして構築し、これらの対象抜きには存在しえない構造のうちにある点を明らかにしているといえる。
病気がなぜ死をもたらすのか、逆に生とは何か、フーコー(1969)は医師がこの問いを身体の内部に求め死体を解剖するに及んで臨床医学が誕生したと考 える。18世紀まで病気とは身体の表面に現れる症状を分類した、いわば表によって認識されるものだった。ところがフランス革命後の混乱期に、実践と教育が 同時に行われる新たな医療施設が国家によって組織されることで事情が一変する。今や施設で解剖する機会を与えられた医師は身体の内部を目で確認しそして名 称を与える。それは生体組織と器官という認識対象をつくり、部分と部分の機能的関係性を明るみに出す実践である。こうして「死の高みからこそ、ひとは生体 内の依存関係や病理的な系列を見て分析することができるのだ。・・・それ(医学的まなざし)はもはや生ける眼のまなざしではなく、死を見てしまった眼のま なざしである。生の結び目をほどいてしまう、大いなる白い眼である。」とフーコー(1969: 198-199)は言う。死を通して生を理解する臨床医学は、非理性を通して理性を考察する心理学の構造と重なる。
中期のフーコーの研究は知識と主体のもつ自明性を解体し、そこに権力を読みとることに主眼を置いている。フーコー(1977)によれば18世紀に入ると 西欧社会では人々の行為(実践)が、工場、兵舎、学校、そして監獄等において空間的・時間的に細部にわたって統御され標準化されるようになる。言いかえれ ば従順かつ労働にとって最適な身体が作られるようになる。この規律化の文脈のなかで刑罰としての監禁の普及を理解すべきだと、フーコーは「監獄の誕生」に おいて議論している。しかし重要な点は規律化が外部からの暴力的な強制によらず、個人が自ら行為を律することで進められるようになることである。一望監視 装置パノプティコンは囚人を個別的に見られる客体とすることによって管理するが、その効率性は囚人が心のなかに常に見られているという意識を抱くことに よって高まっている。他方規律化とは規律化されない者を異常者として規定する過程でもある。つまり監禁は囚人を矯正して社会に帰すだけでなく、矯正が必要 な性向としての「非行」の概念の生産と維持に役立っている。
「監獄の誕生」は監獄という特定の装置に焦点を置いていたが、「知への意志」(フーコー 1986)は多様な言説が特定の主体化を招く過程を探求している。18世紀後半から19世紀にかけて西欧では性に関する抑制的な言説が様々な分野で増殖す る。すなわち教育においては少年の性行為のもつ健康への影響について、臨床医学では女性のヒステリーと性的欲求の関連について、精神医学では性的倒錯とい う病理について、そして産児制限の重要性について盛んに論じられるようになる。これらの多様な言説に共通するのは科学性と医学性であり、語ることが治療と して捉えられている点である。フーコーによれば注目すべきはこれらの言説が性行為を抑制したことではなく(同時にそれは欲望を煽動している)、個人が自ら の行為や想念に性的異常性が無いかどうか常に懸念するような主体となったことである。それはまた個人が自らを規律化し、さらに健康を管理し出産を調整する ような主体となることを意味する。こうした主体化は規律的な労働だけでなく健康管理と人口調整に基盤を置く資本主義の要請と合致する。身体を規律化する権 力と人口を調整する権力がともに個人と集団の生を経営・管理することから、フーコーはそれらを合わせて生-権力と呼ぶ。
フーコーにとって権力とは特定の個人・グループ(階級)が所有し意図的に行使するものではない。また特定の機関・制度(行政、法、警察、軍)に還元でき るものでもない。フーコーはむしろそうした諸制度・組織の運営を秩序づける知識と言説により力点を置いている。つまりフーコーにとって権力とは知識・言説 を使うことによって行為(実践)が方向づけられること、個人がしばしば無自覚のうちにそのように行為する主体と化していることを意味する。
フーコーは確かに主体化を導く複数の知識と言説について語り、言説と言説の矛盾や抵抗についても触れている。しかしながらその著作には知識と言説によっ て人々の実践が同一の傾向を帯びることが全面に現れているといってよかろう。またフーコーが取り上げる知識・言説は主に生物医療と近接の人間科学のもので ある。その意味でフーコーのアプローチは医療化論に接近している。これらの点はフーコーを援用する医療社会学者の研究にも当てはまる(ARMSTRONG 1983, TURNER 1984, 1987, LUPTON 1995, PETERSEN and BANTON eds. 1997)。例えばラプトン(LUPTON 1995)の研究では、健康増進と病のリスクに関する生物医療と保健学の諸言説、そしてそれらに基づく政策、検査、メディアによるキャンペーン等が、今日 イギリス、アメリカやオーストラリアにおいて、合理的かつ責任をもって健康管理に励むような主体をつくりだす圧力となっている点が力説されている。
以上1980年代までの医療社会学の諸理論を概観した。これらの理論には当然相容れぬところがある。しかしながらこれらの理論において特徴づけられる医 療、医療を取り巻く社会、そして医療と社会のもつ問題には明らかに共通点がある。それは一言でいえば近代(modernity)の諸特徴でありそれらに対 する批判性である。以下その共通点を文化のカタチと流れ、社会的関係構造、そして行為の傾向という三つのレベルで整理したい。
ここで文化のカタチと流れとは知識の形態と認識構造、そしてその空間的・時間的な伝播と流通のあり方のことを意味するものとする。ラベリング理論と医療 化論では生物医療知識が高度で体系的かつ普遍主義的であり、不平等につまり専門家にのみ広まっていることが前提とされている。フーコー理論の場合、複数の 言説の社会的カテゴリーを超えた流通が重視されるが、ここで議論されている言説は押し並べて医学的かつ科学的特徴を共有している。一方これら三つの理論が 共通に問題にするのは健康(正常)と病気(異常)という二項対立的な認識構造である。
社会的関係構造とは社会関係、組織、社会的アリーナ、市場等の総体を指すものとする。まずこれらの理論が問題視する社会組織の共通の特徴として、分業化 され合理的に組織されたウェーバーの言う意味での官僚制を上げることができよう。病院はその典型であるが、マルクス主義理論における工場、フーコー理論の パノプティコンも合理的官僚制の範疇に入るものと思われる。フリードソン(FRIEDSON 1970[1992])は専門職を中核とする組織と官僚制とは区別されるべきだと主張するが、それらがともに合理的に組織されており、クライアントを客体 化する傾向がある点に共通性を認めている。一方フーコーを除けば医師-患者、資本-労働というような二項対立的で不平等な社会関係を問題視している点もこ れらの理論に共通する。
むろんこの点に関して無視することのできない理論的特徴も存在する。マルクス主義の場合、商品関係と市場という資本主義における社会関係を研究対象として 欠かすことはできない。またフーコーの権力観は個人が意図的に個人を支配するという権力観の否定の上に成り立っており、ラベリング理論とは相容れぬ部分が ある。
行為の傾向とは時間的に見た個人の行為の特徴とさしあたり定義したい。それにはルーティンや習慣性の強い行為のように既存の構造(知識・ 認識構造や社会関係など)による規制を強く受ける行為、流入する情報や遭遇する社会状況に合わせて変わっていく流動的で現在時制的な行為、目標を遂げるた めにあるいは目標を作るために計算し計画を立てあるいは反省する未来指向の行為、さらに繰り返されパターン化された所作が変化する現在の状況と未来の目的 に柔軟に対応する儀礼的な行為等々、様々な傾向がありうる。
まず程度の差こそあれ全ての理論で扱われているのは規律的な行為である。それは細部にいたるまで規制された過去指向の行為といえる。この行為の傾向を最 も深く吟味したのはフーコーであるが、ラベリング理論における入院患者の行為、マルクス主義理論における健康問題を発生させる労働形態等は規律的とみなす ことができる。
規律化が患者・クライアントに顕著な行為の傾向なら、専門家の行為は他者の客体化の過程としてしばしばとらえられている。客体化とは他者を特定の抽象的な 知識体系においてのみ分析しそして扱うことと定義していいだろう。フーコーのまなざしの場合人体を生物医学の対象としてつまり組織と器官の集合体として客 体化する。客体化はまた他者におとなしく対象としてふるまうことを要請する。すなわち客体化と規律化はしばしば表裏一体の関係にある。
客体化はまた明らかに未来指向の目的合理的行為とも関係がある。その目的が治癒であろうと商業的利益であろうと目的合理的行為が他者に向け られたとき、他者は手段として客体化されかねないからである。つまり客体化、目的合理性、規律性は医療実践においてそれぞれ密接に関わっているといえよ う。
一方フーコー理論の主体化に関しては、ラプトンの研究にあるようにそれを個人が自らの健康を自らの責任において合理的に追求する過程とみな すなら、後述する「個人化」というポストモダン的な要素を多分に含んでいる。客体化、合理化、主体化の三つを推移する近代医療の特徴としてあげるバリー (Bury 1998: 5-16)も、主体化にポストモダン的要素の萌芽を見ている。しかしながら主体化は基本的にはおしなべて人々を駆り立てるような普遍的過程であり、また行 為の傾向としては明らかに目的合理性や規律性を伴うものとみなされている。すなわち主体化には近代的要素も顕著に存在するといってよかろう。
さてこれらの理論に共通する批判性だが、その批判性とは第一に個人の能動性・多面性が一元的に抽象化されること、そうした意味における個 人の「自由」の剥奪に向けられているといって間違いないだろう。すなわち高度で普遍的な知識・言説、それらに由来する技術(診断、治療、機械)及びその担 い手である専門家、そして目的達成のために最適化した官僚的組織(病院、工場、監獄)、これらの抽象的な構造によって、個人の実践が外側からも内側からも (言説を通して)一元的に規定されることがこれらの理論のもつ批判性の中核にある。規律化はマルクスの言う疎外につながる。専門家システムによって日常生 活全体が統御されるなら、それはハーバマスが生活世界の植民地化と呼ぶ危機状況に他ならない。
この抽象的なシステムが生物医療に依拠するのか資本主義に依拠するのかは理論に応じて力点の置き方が異なる。フーコーの場合主体化を導く諸言説が一つのシ ステムを構成しているとはみなさないだろう。またラベリング理論では抽象的システムよりも具体的な専門家による支配により重点があるといえるだろう。しか し個人の実践の抽象化に対する危惧感は全ての理論に共通するのではないだろうか。
もう一つの批判は正常(健康)-異常(病気、逸脱)といった二項対立的な人間類型に向けられている。この点はラベリング理論、医療化論、 フーコー理論に共通するが、前二者が社会的差別と逸脱の恒常化を問題視しているのに対して、フーコーは二項対立的な認識構造そのものの解体を目指している といえよう。このことはまたフーコーの批判が外部の社会ではなくその社会の一部を構成している自分自身に、つまり主体の自明性に向けられていることとも関 連している。
以上見てきた諸理論が共有する医療、社会、批判性の特徴はバウマン(2000[2001])が「固体的近代」と呼ぶ近代の特徴でありそれに対する批判で ある。したがってこれらの理論は基本的には近代医療に関する批判理論とみなすことができよう。しかしながらこれら近代医療論にはいくつかの問題点があるよ うに思われる。
第一にこれらの理論では生物医療、国家、そして資本主義経済を共謀関係、あるいはほぼ同じ方向へ向かったベクトルとしてとらえられている。言説や権力装 置の多様性を強調し、抵抗の可能性すら示唆するフーコーでさえもこれらが親和するものとしてとらえている。つまりそれぞれの文化的論理や言説のあいだの矛 盾、政策・方針の相違、医師、役人、経営者の利害の対立といったことについての具体的な考察がない。しかしそこに矛盾や対立を見出すのはさほど難しいこと ではない。例えば日本では医療費の三割負担をめぐって政府と医師会が対立している。狂牛病をめぐる厚生労働省と農林水産省の足並み揃わぬ対応は、これらの 省が消費者と生産者の利益をそれぞれ反映していることを示している。つまり国家と資本は必ずしも一枚岩としてとらえられない。資本主義経済は生物医療だけ でなく代替医療も商業化し発展させる(佐藤編 2000)。生物医療は医療産業と協力関係にあるが同時にその戦略にも制限をくわえるだろう。身体を生物学的人体としてとらえることと、商品としてとらえ ることはともに抽象的な認識という意味で共通するが、それらはあくまでも異なった知識体系に属す。社会的実践をする中でそれらが矛盾を来しても不思議では ない。
第二にこれらの理論に依拠する多くの研究者はジェンダーと階級の問題については検討している。しかし専門家と病人の医療行為にはこの他にも血縁関係、地 縁関係、宗教、市民グループ、患者会、その他様々な社会関係、さらにメディアを通して作られ流布する多様な情報や知識が影響を及ぼしている可能性がある。 これらの諸関係と諸文化は確かに生物医療と資本主義の影響の下にあるとはいえ逆に後者のありようも規定しているのではなかろうか。例えば日本では医師とい う職業が親から子へ継がれる傾向が顕著であるが、家族-親族のファクターは医療専門家の再生産を考察する上で重要であろう。同様に日本では病院や医療組織 の構造を考える上で学閥というインフォーマルなネットワークの存在を無視することはできない。また民族、宗教等に応じた医療実践の相違は医療人類学が強調 してきたことである。
第三に医療社会学的研究には診療のもつ儀礼性について検討が欠けている。診療という社会的空間は専門家のまなざしによって病人が客体化する場、あるいは 病人の生活世界が植民地化する場としてのみとられることはできないだろう。それは言語的コミュニケーションだけでなく非言語的コミュニケーションが顕著な 空間、白衣、アルコールの臭い、触診、聴診器、その他様々なシンボルによって織りなされる境界域でもある。これらはおそらく繰り返されるモチーフであり、 病人はそこに身の引き締まるものを感じるのではなかろうか。医師もまた正確な機械のような専門家ではなく、人間関係の機微を知り尽くし人生の意味を諭すこ とのできる呪術師として振舞うことで患者の信頼を勝ち取ることができるのではないか。患者同士が共有するある種の一体感・同朋意識にコミュニタスの要素を 見てとることもできよう。しかしながら生物医療の実践において儀礼性を強調し過ぎるのも誤りである。それは絶えず進化する医療技術の実験場でもある。ヴィ クター・ターナー(TURNER 1974: 15-17)の用語を使えばそこにはリミナリティー(liminality: 境界)とリミノイド(liminoid: 進化)のせめぎあいがある。
そして第四に第二点と関連して医療化と資本主義社会のあり様は地域的に多様であり歴史的に変化する。医師の専門職化が一般に市場の独占を目指すもので あっても、そのあり方は国家の政策、経済状況、消費者を取り巻く社会関係のあり方によって左右される。例えばアメリカやフランスでは国家は生物医療に大き な権限を与え、代替医療は基本的には医療として認知しないが、イギリス、ドイツや日本のような国では代替医療に寛容な政策をとっている(LAST 1996)。専門職化のあり方はまた歴史的に推移する。アメリカでは明らかに医師の脱専門職化、すなわち賃労働者化が進んでいる(KRAUSE 1996)。ここでは賃金と引き換えに病院という合理的官僚的組織のなかで医師もまた疎外されつつあるといえよう。
一方マルクス主義医療社会学では工場労働者や鉱山労働者の健康問題を重視している(もちろん無視していいことではないが)ことからわかるように、いまだ重 厚長大の資本主義のイメージを引きずっている。しかしブライアン・ターナー(TURNER 1987: 176-180)も指摘するように資本主義社会は歴史的に変化しており、それに伴って医療問題も変化している。マルクス主義医療社会学はポストフォーディ ズム、情報化社会、消費社会における医療の現実に追いついていない。資本主義の地域的多様性も無視することはできないだろう。アメリカに見られる自由主 義、北欧諸国に特徴的な高福祉社会、日本の法人資本主義、これらの諸特徴がそれぞれの国と地域の医療と健康問題のあり方に反映する可能性は否定できない。
そしてこの地域的多様性は主体化の問題にも当てはまる。フーコーの規律化する主体、そして性を懸念し健康を管理する主体は日本社会におけ る主体の形成を確かに部分的には説明できるだろう。しかし日本には他の様々な主体化への圧力がある。例えば日本人の行動指針を特徴づける概念としてよく登 場する「場」や「間」の問題である(中根1967: 25-68, 木村1971)。「場」とはその時その場に居合わせた人々にかかる無言の社会的規制、それは同時に場を下りてしまえばたちまち解消してしまう状況主義的な 社会的な規制であるが、われわれは幼い頃から「場」に合わせることが身体化しているかもしれない。しかしながら身体化しているのは「合わせる」ことであっ て従わなければならない秩序は「場」によって千差万別だろう。この点、社会的場の如何を問わず常に行為を決定づけるフーコーの規律や調整とは異なる。
このように1980年代までの医療社会学理論にみられる近代批判には現状にそぐわぬ点がある。こうしたなかで時代はもはや近代を超えているといった議論 が出てくるのは自然の成り行きかもしれない。
上記の近代医療論の批判点を一言でいうなら、現代社会及び医療のもつ複数性、複雑性への視点に欠けるということだろう。そしてこの複数性 の焦点におくのがポストモダン理論といえる。1990年代以降現在の医療状況は近代医療の枠組ではおさまらないとする見解が強まりつつあるように思われ る。ここでポストモダン医療論について述べる前にポストモダン社会論について触れる必要があろう。そもそもポストモダンを定義することが困難なことがいか にもポストモダン的といえるのかもしれない。またその名称もハイモダン、激化したモダン、新しいモダン、晩期資本主義にいたるまで多様である。しかしなが らその主要な論点をいくつか指摘することは可能である。
第一にあげられるのは普遍性の喪失だろう。現代社会では、それが科学的客観性であれ、啓蒙主義的真実であれ、あるいは社会主義的理想であ れ、普遍性をもった言説、リオタール(1986)のいうメタ物語は信憑性を失っている。あらゆる知識と言説にもはや真実を問うことはできない。全ては解釈 の問題であり、したがって文化の問題である。ある言説が広まっているとすればそれは正しいからではなく権力があるからである。こうした見方は多くのポスト モダン論に共通する。
第二にポストモダン社会の特徴としてしばしばあげられるのは情報化社会である。電子メディアと情報技術の飛躍的な発展によって大量の情報が瞬時に提供さ れる。これによって現在文化のグローバルな同質化が起こっているのか、それとも多様化に向っているのか、見解の一致を見ないが、多様化論のほうがよりポス トモダン的といえるだろう。一方ボードリヤール(1984)は情報化社会のなかで現実感が喪失していると主張する。情報は他の情報についての情報である。 全てはコピーのコピーのコピー…つまりシミュレーションの産物に過ぎない。ボードリヤールによればわれわれはシニフィアンによってのみ構成されるハイパー リアリティーを生きていることになる。
第三によく議論されるのは消費社会である。共通の目標を一致団結して追求する時代は終わり、かわって現在の自分だけの関心や感覚的な欲求を満たす行為が 支配的になりつつある。バウマン(BAUMAN 2000[2001])は現代人の姿を刹那的な気持ち良さを求め瞬間的に商品を選択する消費者に見ているが、この行為のもつ流動性と現在時制的性格は、過 去に決めたこと正確に繰り返す規律とも、将来の目的のために計画をたてる合理性とも程遠い行為の傾向といえる。メルッチ(1997)に倣いそうした行為の あり方を「現在に生きるノマド」と呼ぶこともできそうである。
第四に取り上げるべきは再帰性とリスクの問題である。再帰的近代化とはベックとギデンズがそれぞれ独自に発展させた概念である。ベック(BECK 1992)によれば工業化社会はまさにその成功の代償として環境破壊などグローバルな規模の問題を発生させた。この予期せぬ帰結に人々は対応を迫られるが それまでの目的合理的な方法がリスクを伴っていることを自覚せずにはいられない。この予期せぬ帰結が再帰的に自らの基盤を揺るがす今日の社会をベックはリ スク社会と呼ぶ。リスク社会において政治家、企業、専門家の活動はリスクを常に負っており、したがって批判に晒されやすい。一方ギデンズ(GIDDENS 1990[1993], 1994[1997])によれば個人が自らの行為に向ける反省性を高めた結果、行為を可能ならしめる構造と制度そのものが反省の対象となり不断の変化が始 まっている。それは普遍的妥当性を建前とするグローバル化した専門家システムが地域社会や消費者のレベルで変貌を遂げ、今度はその変化に呼応して専門家自 身がシステムを変革すること、その結果一つのシステム対する信用が維持されないこと意味する。
第五にギデンズ、ベック、メルッチ、そしてバウマンなど多くの理論社会学者の指摘するのは個人化の現象である。彼らによれば新しい近代社会において人と 人の絆は多様化するとともに短命化している。それは個人の行為を強く規制する社会関係がもはや存在しないこと、また高まる再帰性のなかで頼るべき権威や信 用に足る知識が存在しないことを意味する。こうした状況において個人は自らの判断と責任において全て決めていかねばならない。
そして第六にカルチュラルスタディーズなどでしばしば議論されるのが、文化のハイブリッド化、クレオール化の概念である。西欧社会、とくに都市に居住す る人々の多くは移民である。彼らは必ずしもホスト社会に同化しているわけではなく、さりとて故郷の文化をそのまま踏襲しているわけでもない。彼らは複数の 文化を様々に節合し流用している。また今日国境を超えるのはビジネスをする者だけではない。パパスタギアディス(PAPASTERGIADIS 2000)は定住ではなく移動が常態になりつつことを指摘する。こうした移動民は特定の文化へのこだわりを捨てているかのようである。ロンドンに行った日 本人が昼はイタリア料理、夜は中華料理を食べたとしても少しも奇異ではない。こうした新たな社会状況に関する新たな解釈は医療研究にも影響を与えざるをえ ない。ポストモダン医療の登場である。
ポストモダン医療の論者の一人であるモーリス(MORRIS 1998)はまずポストモダンの徴候として生物医療の揺らぎを指摘する。今日生物医療が効果的に対処できない疾病の種類は減少しているどころか増加してい るように見える。多種多様なアレルギー性の疾患、心身症、その他様々な慢性的な疾患、ガン、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病等々、これらの病にはいまだに決定的 な治療法はない。さらに新種の病気が毎年このリストに加わっている。こうした生物医療が治せないそして理解できない病気をモーリスはポストモダン的病気と 呼ぶ。ポストモダン的病気の特徴は生物医療の限界を示しているだけでなく、代表的な病を特定できないほど多数ある点、その複数性は情報化社会とも関連して いる点(コンゴで発生したエボラ出血熱に関する情報は短時間のうちに日本に伝わるという事実)、それでいてこれらの病の多くには顕著な環境・社会的因子が 見とめられる点が上げられる。
この環境と社会的因子に関しては、いわゆる公害病から化学物質過敏症や環境ホルモンの問題にいたるまで、環境破壊と人工的な環境作り出した病が多い。ま た拒食症のように消費社会や個人化現象と密接に関連した病も存在する。モーリスによれば共同体的ユートピアが喪失した現在、人々は自らの身体にユートピア を求める傾向があるという。自分の身体だけは自分のために自分でコントロールできる。なかには完全な身体を求め絶えず身体に変更を加える者も現れる。そし てその一つの帰結がスリムな身体を追求するあまりに起こる拒食症であるというのだ。 生物医療の揺らぎは病気(異常)と健康(正常)二項対立的な認識構造がもはや支配的でなくなっている点にも現れている。バウマン(BAUMAN 1998, 2000[2001])によれば病気(異常)との対の概念である健康(正常)は規律的な工業中心の古い「固体的な」近代社会において重要なものであった が、今日の「液体的な」近代社会においてはその重要性を失いつつあるという。かわって重要なっているのは体力(fitness)であるという。体力には社 会的な基準が存在しない。それは個人の自己満足の問題であって際限なく追求しうる。
フランク(FRANK 1995[2002])も病気と健康という近代的な二分法が時代遅れになりつつあると主張する論者である。フランクによれば大多数の人々は完治することの ない何らかの病をもっており、その病と付き合って生きている。この病気と付き合うことに対する認識の広まったポストモダン社会をフランクは「寛解者の社会 (remission society)」と呼ぶ。したがって寛解者の社会においては「治す」「延命する」という生物医療の至上命題に対しても疑義が差し挟まれざるをえない。こ こでは病といかに生きていくか、病の経験にいかに積極的な意味を与えるかが重要となる。フランクの主眼は病へのしたがって人生そのものへの積極的な意味づ けをする上で語りがいかに重要であるかを示すことにある。フランクによれば語ることで病人は新たな自己となる。その語りは不特定多数へ向けた真理について の語りではなく、特定の他者に対し「インスピレーション」を与えるような語りである。こうした語りを一つの主体化の過程ととらえるなら、それは還元しよう もない個人的な主体となることだろう。フーコーの人々の行為をおしなべてある方向へ向かわせる主体化とは異なる。
一方ポストモダン的医療専門家は患者の語りについて聞くつまり医療知識によってその語りを分析するのではなく、語り手とともに聞く、その 語りを自らの経験のなかに取りこんで自らのために活かすという態度が必要とされる。ここではフーコーのまなざしを超える試みが示唆されているといえる。 フランクはいくつかの例をあげて現実にこうした語りが行なわれていることを示そうとするが、おそらく最も説得力のある例はガンに侵されながら著述活動を続 けるフランク自身の語りといえるだろう。
ポストモダン的医療の現れとしては生物医療のもつリスクに対する認識の広まりを上げることもできるだろう。明らかに今日リスクの問題抜き に生物医療を語ることも実践することも難しくなっている。それは医療実践と専門家・組織のもつリスクに対する消費者の懸念と批判の高まりだけでなく、医療 者側と行政の医療リスクへの対応にも現れている。リスクに対する医療社会学の研究もここ数年増えつつある。興味深いことにベック自身はリスク社会論の中で 生物医療がその専門職化によって一般の懐疑を免れていると主張している。しかしながらリスクと医療に関するゲイブ編(GABE ed. 1995)の論集の中にはいささか異なった見解が見られる。レイン(LANE 1995)の研究は産科医がリスク極小化を最優先するあまりクライアントを客体化する一方、彼らは賠償請求を受けるなどしばしば批判に晒されていることを 明らかにしている。ロジャーズとピルグリム(ROGERS and PILGRIM 1995)の研究は専門家と行政の指導にもかかわらず子供の予防接種を避ける親が現れてきたこと指摘し、専門家システムに対する信用の欠如を見ている。ま たスコットとフリーマン(SCOTT and FREEMAN 1995)の研究では、エイズ予防に関して専門家システムは効力を欠いており、それはもっぱら個人の手に委ねられるつまりリスク管理の個人化が見られると している。
最後に代替医療への関心の高まりも生物医療の揺らぎを示唆するものだろう。しかしこのことは生物医療の利用が相対的に減少していることを意味するもので はない。医療人類学による多元的医療の研究が示しているように、人々は生物医療を放棄することなく様々な代替医療も試みている。こうした複数医療の利用は ポストモダンのハイブリッド性を想起させる。ギデンズ(GIDDENS 1991: 139-141)は腰痛の女性が複数の医療を選択する状況を想定し、決定的な権威を欠いた専門家システムが個人の自律性を高める(empower)という 今日的なハイモダニティーの特徴を描いている。またメルッチ(1997: 170-171)も医療の複数化の拓く新たな医療の可能性について示唆している。一方モーリス(MORRIS 1998: 66-75)はアメリカの生物医療機関が代替医療研究プロジェクトを発足させるなどその存在を無視できなくなっている状況について触れている。
以上見てきたように確かに現代医療には新たな事態が加わりつつあるように見える。しかしながらポストモダン医療論の問題点は、第一に、生物医療は揺らい でいるとはいえいまだ強大な権力を保持している事実を過少評価している点にある。客観性と回復・延命への信仰、つまり普遍主義的傾向が生物医療から消滅し たわけではない。患者の客体化、機械的身体観、臨床の場における病人の身体の規律化、これらも依然として存在する。医療施設によってはその運営の仕方にマ クドナルド化といもいえる超合理主義すら見られる。
また情報化社会と消費社会は文化の複数化とその個人的かつ刹那的選択を促すが、同時に普遍的同質的文化と基準化を迫っている。拒食症は確かに共同体的 ユートピアの喪失、個人化とシニフィアン・感覚指向の現れともいえるが、美的身体のあり方には白人のファッションモデルや女優を範とするようなグローバル 化した基準が明らかに広まりつつある。一方ヒッグズ(HIGGS 2001)は今日のリスクに関する言説の増殖が、自らリスクを回避する模範的な市民と、そうでない、国家・専門家の介入を要する者との差別化を生んでいる と指摘する。その意味ではリスクとはポストモダン的不確実性ではなくむしろ近代的な主体化と二項対立的認識構造の現れとして理解すべきということになる。
代替医療の隆盛と複数化は確かにハイブリッド性を窺わせるが、多くの代替医療は同時に商業化つまり貨幣をもって一元的にその良し悪しを比較し得るものと なりつつあるようにも見える。つまりこれらの医療は比較しようのない独自の「文化」であることを止めつつあるのかもしれない。
ブライアン・ターナー(TURNER 1997)は現代医療の分析の鍵を握るのは医療におけるマクドナルド化とリスク社会という相矛盾する変化をどのように理解すべきかにあると述べているが、 今日の医療には近代医療とポストモダン医療の両要素が混在しているといってよかろう。すなわち先の方法に従って以下のように整理することができる。まず文 化のカタチと流れの次元においては、一方においてシニフィアンあるいはブリコラージュ的な知識、そして相矛盾する複数の言説の存在し、他方において高度に 体系的な知識(生物医療における教科書的知識)がグローバル化するとともに再帰的に変化している。社会的関係構造においては個人化、複数化とネットワーク 化が進展するものの、組織の超合理化も同時に進んでいる。行為の傾向のレベルでは未来指向の自己反省性が強まりながらも同様に未来指向の目的合理性も以前 存在している。現在時制的で流動的な行為が広まる一方で規律性の高い過去指向のルーティンも存在し続けている。
確かに過去数十年西欧社会ではポストモダンと呼ばれる現象が顕著に現れているのかもしれない。しかしそれは近代からポストモダンへの一方的な変化を必ず しも意味するものではないのではなかろうか。そもそもポストモダン的な社会現象は近代が始まった当初から存在していた可能性がある。ボードレールのフラ ヌールに見られる移ろいやすい消費者的行為、デュルケームが規範性の弛緩によって生じるとしたアノミー、ウェーバーが「職業としての学問」において語った 人間の営為・活動の正当性を何人も問うことができない相対主義的な社会状況、「共産党宣言」のなかでマルクスが描いた全ての伝統と文化を破壊し続け、自分 をとりまく社会を冷ややかに見詰め続ける資本の再帰的実践、これらは十分にポストモダンのカテゴリーで括ることのできる現象といえる。
近代的現象とポストモダン的現象が混在しているのが現代社会のあり様だとすれば、その混在の仕方は歴史的・地域的に多様であろう。そしてその組み合わせ のあり方はある程度まで特徴づけることが可能だろう。しかしながらその全般的な傾向がその地域と時代に生きる人々に一様に当てはめるとみなすべきではない だろう。なぜなら同一地域内においてさえ個々人の関わる社会関係は多様であり、彼らのもつ文化的レパートリーや彼らが新たに遭遇する文化は部分的に重なり はしても決して同じであるあてはないからである。 例えば病院勤めの医師の行為は経営の論理のもとでルーティン化を強めているかもしれない。しかし同じ医師でも救急病棟の宿直医の急病人への対応は不確実 性に満ち流動的かもしれない。一方救急医療を改善しようとしている有志の医師たちの行為は再帰的である。
一方病人の側は、増殖する生物医療の知識・言説と医薬産業のメディア戦略によってその治療実践には高い同質性がみられるかもしれない。入院患者は多くの 場合従順な身体と化している。しかし生物医療の限界を認識する多くの人々にとっては、生物医療の知識と技術は彼らの経験する複数の医療文化の一構成要素に 過ぎないだろう。彼らの医療行為はメディカルショッピングという個人性と流動性の高いものとなっている可能性がある。人によっては治療実践が自分の創意工 夫を生かせる数少ない場の一つとなっているかもしれない。逆に宗教性の高い治療に専念している人はその身を組織(宗教団体)にゆだねているともいえる。そ の場合彼らの医療行為には近代ともポストモダンともいえない儀礼性があるだろう。
医療人類学が明らかにしてきたように人々の病因観と治療実践には民族、宗教、階級、ジェンダー、その他様々な社会的カテゴリーに応じた特徴がみられる。 つまり彼らの医療行為はお互い似た部分はあっても同一視することはできない。しかしながらその彼らが患者会では一致団結して医療制度に変更を迫っているか もしれない。そしてその実践は明らかに同質性が高いといえる。付け加えるなら多様性は空間的な問題だけでなく時間的な変化の問題でもある。歴史的変化はい うまでもなく、同一個人の治療実践のなかにも近代的要素、ポストモダン的要素、さらには儀礼的要素が時間とともに交互に現れるかもしれない。
以上見てきたように現代医療、現代社会のもつ複雑性、空間的時間的多様性は、近代医療とポストモダン医療の諸理論がどれも部分的にしか有効でないことを 示している。複雑性の理解は、空間的時間的に対象を限定し仔細にその動向を検討することによってのみ可能となるのではないか。まさにこの意味において民族 誌的研究といういわゆる「前近代社会」研究のために編み出された手法が、皮肉にも今日ますますその重要性を増しつつあるように思われる。
医療社会学は往々にして抽象度の高い理論をもって現実を把握する。民族誌的研究では空間的・時間的に限定的な対象を仔細に見るが、それは 個別のケースをもって理論を批判することだけを目的とするのではない。むしろこれらの理論を有効に利用することこそ重要であろう。問題とすべきは一つの理 論によって個人の行為の細部まで説明させるそのまなざしを放棄することである。要請されているのは複数のレベルからなる多層的な抽象化と理論の応用であ る。
かつてマリノフスキーは民族誌が社会の骨組つまり構造の発見だけに終始するのは片手落ちであり、社会の血や肉の部分、つまり個人が社会的規範や慣習をど のように実践するのかを観察すべきであるとしたが、今日の民族誌家はより複雑な構造のモデルを必要としている。社会全体の一つの平面図として描き得るよう な構造とそれに縛られつつも同時に無視する個人の行為という二元的な枠組は成り立たない。構造は複数の次元での抽象化の産物によって構成される寄木細工あ るいはコラージュとして理解すべきではなかろうか。われわれには一点から一望的に見渡すのではなく複数の視点をもって対象を見ることが要請されている。わ れわれは階級という視点だけで対象を十分に理解することができないことを知っている。同様のことはジェンダー、民族、宗教、地縁的関係その他諸々の社会的 カテゴリーにも当てはまる。
このことは民族誌家が専門家の視点を捨て普通の人々の視点に近づくことを意味すると筆者は考える。木を見て森を見ないというが専門家・理論家は森だけを 相手にしがちである。しかし普通の人の視点は木と森は言うに及ばず極めて多数の次元の対象に注がれる。新緑の森のなかで人は森の一角が明るく黄緑色をして いるのに他の一角はまだ薄茶色の梢だけであることに気づくだろう。しかし明るい緑の一角もよく見ると様々な色のモザイクをなしていることに気づく。そこに 赤味を帯びた楓の一群を見出すかもしれない。人はさらに楓の一本一本が個性をもって枝をはっていることを見とめるだろう。それどころか葉の一つ一つが光と 風によって多様な輝きを見せていることに気づく。そして人は目の前の森が世界中で唯一の存在であることを知っているが、同時にどこかしら他の森と似ている ことも知っている。
森全体の色合いに焦点をおくことで葉の個性を失わせることがもはや時代遅れの構造・システム論的専門家の見方だとしても、その逆、つまり生きている個々 の葉の揺らぐ様だけに着目し、その幾百千万もの総体として森を描く現象論的な試みも同様に専門家的だと言わざるをえない。そうして描かれた複雑な連鎖とし ての世界は見る側に解釈し抽象化することを許さず、それ自体として受け入れることを要請する。問題はそれでは見る側がそれを理解し批判することさえできな い点にある。
筆者は民族誌家の仕事は森から葉にいたる複眼的認識を意識的にやることだと考える。そして筆者はそうした民族誌が批判性を十分もちうるものだとも考え る。しかし民族誌の批判性の出発点は近代やポストモダンといった抽象的なレベルではなく、民族誌的研究の対象となっている人々が自ら認識する具体的な苦 悩、危機、困難であるべきだと考える。バウマン(BAUMAN 2000[2001])はこれまでの批判理論が古い固体的近代を対象としており、もはや現状の流体的近代にはそぐわないとして批判理論の再考を主張してい る。しかしすでに触れたように固体的近代はその勢力を弱めたとはいえ今でも存在している。したがってバウマンの主張は部分的にしか有効でない。言いかえれ ば個々の人々の直面する危機状況は彼らを包む社会関係、文化のカタチと流れ、そして行為の傾向を複眼的かつ具体的に見ていく以外に理解を深めることはでき ないだろう。その仕事をすることこそ民族誌的批判といえる。
社会全体を説明し尽くす高度に抽象的な批判理論は、問題の解決をユートピアとして描くかさもなければニヒリズムに陥りがちである。しかしもはや一つの理 論におさまることのない多様な現代社会は自らのうちに希望を秘めているのかもしれない。すなわち社会の多様性はある人々が危機状況に陥る一方で、他の人々 が同一ではなくとも類似した危機状況を克服する可能性があることを示唆している。フランクの言葉を使えばわれわれは社会のなかから「インスピレーション」 を得ることができるかもしれない。そしてそれは民族誌的研究によって発見しうるものではなかろうか。こうした民族誌の可能性を示す模範として本報告にある 研究をみなすなら、筆者の思い入れが強過ぎるであろうか。以下に各民族誌の要旨を述べたい。
まず浮ヶ谷論文は糖尿病(IDDM:インスリン依存型)をめぐる患者の複数の戦術について考察している。近年行政は生物医療の見地から 「生活習慣病」という概念の普及につとめている。その結果糖尿病のようにすでに一般に否定的なイメージのある病はそのイメージが助長される可能性がある。 つまり生活習慣のだらしない者がなる病というイメージである。それは生物医療の言説の流布による正常と異常の峻別、そして正しい生活習慣の規律化という近 代的な圧力と解釈することもできよう。だが就職、進学その他様々な社会生活の局面において差別される可能性のある患者は、こうした事態に従順に従っている わけではない。彼らは患者会を通して糖尿病に関する啓蒙活動、さらに病名変更運動を展開している。ギデンズ理論に従うなら彼らは自らを規定する社会制度を 再帰的に変更しようとしているといえるだろう。しかしこの運動は患者を団結させる一方で自らを健常者と強く区別し、さらにNIDDM(インスリン非依存 型)の患者を差別する可能性を秘めている。
しかしながら患者は個々人のレベルでは病気であることに対して実に多様かつ流動的な態度をとっている。彼らにとって糖尿病は治す対象ではなく、日常生活に おいて付き合っていくいわばポストモダン的な病である。社会生活の様々な局面においてある者は糖尿病であることを隠蔽し、またある者は告白する。彼らは一 貫とした態度をとっているわけではなく、状況に応じて病をもっていることを隠蔽しまた告白する。したがって規律化の圧力を受けながらも彼らはそれをかわす 術(セルトーの戦術)を知っている。つまり彼らの主体は生物医療の言説によって決定づけられてはいない。彼らは多様な言説と複数の社会的アリーナに応じ複 数の主体のあいだをスイッチしているといえるかもしれない。
川添論文は日本の美容外科をめぐる複雑な社会的関係構造と文化の態様について論じたものである。今日美容外科技術はグローバル化しつつあ り、そこで求められる容姿にもメディアによって作られた基準が生まれつつある。しかしながら日本の場合は事情が少々異なる。日本ではまず美容外科に顕著な 境界性がまとわりついている。美容外科には美と医療、医療とビジネスという二重の意味での境界性があるが、日本では大学病院が美容整形を行なってこなかっ たことが、美容外科を金儲けのための非正統的な医療(=美容)という側面、すなわちいかがわしさを強調している。日本の美容外科をめぐっては生物医療と資 本主義の論理が必ずしも合致していないといえよう。
美容整形を受ける者もファッションモデルのような「美」を追求しているわけではない。日本で美容整形を受ける大多数の者は「普通」の容姿になることを希望 している。また韓国では美容整形を受けたことをとくに隠さないのにくらべ、日本ではそれを隠す傾向が強い。このことにも日本の普通文化が反映しているとい える。つまり美容整形を受けることがいまだ普通とはみなされないからである。しかし手術を受けた者のなかにはより良い容姿を求め手術を繰り返す者もいると いう。それはデュルケームのアノミーあるいはバウマンの主張する流動的な行為に近いといえる。普通文化は今のところ美容整形に対する抑止力として働いてい るようである。しかしそれは諸刃の剣といえる。美容整形自体が普通化する可能性があるからである。
加藤論文は脳死-臓器移植の問題を扱う。脳の機能停止を死亡の判断基準とすること、病んだ臓器を健康な臓器と取りかえる治療、これらはとも に生物医療の機械的身体観・生命観を現しているといっていいだろう。脳死の判定から臓器移植にいたる一連のプロセスはまた専門家の分業とチームワークそし て高度な技術を伴う。したがってこの医療実践はきわめて近代的な実践といっていい。しかし加藤論文はこの近代的医療実践の内実が不確実性と複数性に満ちて いることを明かにしている。参加した専門家・スタッフたちの死に対する認識は必ずしも一様ではない。脳死をもって人の死とすることに疑念を交えなかったの は脳死判定をした脳外科医と神経内科医だけのようである。看護職は判定が下った後もドナーの身体の温もりに死を感じきれない。この思いはドナーの家族に感 情移入することでさらに強まっているようだ。一方麻酔医は普通の手術において患者に投与する麻酔薬の量をつまり患者が痛みを感じているかどうかを血圧と脈 拍よって判定する。この同じ測定を麻酔医は臓器摘出手術中のドナーに対しても行なう。したがって手術の進行とともに上下する数値に麻酔医はやはり死を感じ られない。つまり温もりや血圧・脈拍はそれぞれ非言語的な生の象徴である。
参加者全員にとってレシピエントの治療が唯一正当化の根拠だが、そこにはどうしても割り切れないものが残る。ここには本当に正しいのかどう かおそらく誰にも確信することのできないポストモダン的な不確実性がある。しかしこの不確実性には生物医療における死と生の言説と日本人が一般にもってい る死生観との矛盾という側面がある。脳死を死とみなすことが大きな争点とはならないアメリカでは比較的低い不確実性といえるかもしれない。
間宮論文はガン検診に携わる保健師の活動に関する論考である。健康診断や集団検診は医療化論でもフーコー的アプローチにおいても社会を医 療化し人々の行為を規律化する重要な装置の一つとしてみなされよう。厚生省はガンの早期治療を重視しガン検診を全国的に奨励した。こうしたなかで新潟県守 門村はとりわけ高い検診率を誇るが、それは保健師の活動に負うところが大きい。守門村の保健師は芝居を通して検診の普及に努めた。この芝居では保健師が村 人を演じ、身体的演技と日常生活のイディオムを通して健康問題と検診の重要性を訴えた。この芝居に保健師の人柄や熱意が加わって村人は検診に出向くように なったのである。このことは人々が何に信頼を寄せるのかを物語っているだけでなく、保健師がグローバル化した生物医療の知とローカルな日常の知とをまたに かけた両義的な存在であることを示している。確かに検診率の向上だけに着目すると結局のところ彼らは医療化を推進したといえそうである。しかし彼らは生物 医療の知をいわばブリコラージュ化しながら検診を普及させていった。注目すべきはその後検診率が下がっているという事実である。この背景には村の世代替わ りによって芝居が人気を失ったこと、カリスマ的な保健師がもういないことがある。つまり生物医療の言説それ自体は必ずしも人々の行為を規律化しないといえ るだろう。
武井論文は老人に対する抑制の問題を扱っている。抑制とは病院で介護・診療を受ける老人の怪我を防止するためにベッドや車椅子に固定する技術のことをい う。抑制を施すのは主として看護師であり、彼らはそれを基本的なケア技術の一つとして教科書で学ぶ。したがって抑制を徹底することは、老人に関しては外部 からの露骨な規律化として、看護師に関しては内部からの主体的な規律化としてそれぞれとらえることができるだろう。しかしながら1990年代後半以降、こ の抑制が廃止される傾向が全国の病院に見られる。この廃止運動はある民間病院の看護師のイニシアチブで始まったものである。それは日常化し疑念を差し挟む 余地もなかった生物医療の実践に対する再帰的な変革であるとともに、生物医療組織のヒエラルヒー対する異議申立てともとらえることができよう。しかし武井 論文はこの廃止化が生物医療の知識にフィードバックされ教科書的知識の一部となる可能性を示唆している。つまり将来看護師は抑制を極力避けるという規律化 を受けることになるのかもしれない。
本稿を結ぶに当たって日本人研究者が日本で医療人類学的研究をすることの意義について若干触れたい。現地人文化人類学者が現地人インフォーマントを対象 に研究を行なった場合、文化人類学者はまずインフォーマントと自分とのあいだに共通する何らかの文化的要素や権力関係を確認することとなろう。しかしなが ら文化人類学者はインフォーマントのなかに必ずや「異文化」を発見する。いいかえれば前者は後者のなかに「自分」と「他者」を同時に見る。ポストモダン人 類学者が議論するハイブリッドな世界は当たり前のことだが目と鼻の先にある。
第二に日本ではインフォーマントはしばしば「語る」ことができる。インフォーマントが研究報告や論文の提出を研究者に求めるのは珍しいことではない。仮 に提出を求めなくとも彼らには大抵これらの研究に対してアクセスがある。そして彼らは研究を批判し訂正を要求する場合もある。研究者が謝罪せねばならぬこ とすらある。したがって研究者は研究上の倫理と責任に敏感にならざるをえない。つまりここでは文化人類学が自己批判の学問となる必要はない。実際に批判さ れるからである。
そして第三に医療人類学研究者の場合、病をもった人々を研究対象とすることで研究の意義を一層強く意識せざるをえない。身体的・精神的苦痛をもった人々 の声に耳を傾けるが、しかし直接的には彼らに対して何もすることができない。それどころか研究結果を発表し何らかの利益さえ得ようとしている。一方しばし ば批判の俎上にのぼる医師は明らかに病人に対して直接的に貢献することができる。真剣な医療人類学研究者でこのジレンマに悩まぬ者はいないだろう。いった い何のために研究するのか、その答えを報告者たちはそれぞれ模索し続けている。そして筆者自身の考えについては暫定的ながらこの場を借りて述べたつもりで はある。
ボードリヤール、ジャン
1984 『シュミラークルとシミュレーション』竹原あき子訳:法政大学出版局。
BAUMAN, Zygmunt
1998 Postmodern Adventures of Life and Death. In Modernity, Medicine and Health: Medical Sociology towards 2000. Graham SCAMBLER and Paul HIGGS (eds.) London: Routledge.
2000[2001] Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press. (『リキッドモダニティ:液状化する社会』 森田典正訳:大月書店)
BECK, Ulrich.
1992 Risk Society. London: Sage Publication.
BECK, Ulrich and GIDDENS, Anthony and LASH, Scott.
1994[1997] Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Stanford: Stanford University Press. (『再帰的近代化』 松尾精文、小幡正敏、叶堂隆三訳:而立書房) BURY, Michael
1997 Health and Illness in a Changing Society. London: Routledge.
1998 Postmodernity and Health. In Modernity, Medicine and Health: Medical Sociology towards 2000. SCAMBLER, Graham and Paul HIGGS (eds.) London: Routledge. CANT, Sarah and SHARMA, Urshula (eds.)
1996 Complementary and Alternative Medicines: Knowledge and Practice. London: Free Association Books.
セルトー、ド・ミシェル
1987 『日常実践のポイエティーク』 山田登世子訳:国文社。
CONRAD, Peter and SCHNEIDER, Joseph W.
1992 Deviance and Medicalization: From Badness to Illness. Philadelphia: Temple University Press.
DOYAL, Lesley
1979[1990] The Political Economy of Health. London: Pluto Press 『健康と医療の経済学:より健康な社会をめざして』 青木郁夫訳:法律文化社。
フーコー、ミシェル
1975 『狂気の歴史:古典主義時代における』 田村訳:新潮社。
1969 『臨床医学の誕生:医学的まなざしの考古学』 神谷恵美子訳:みすず。
1977 『監獄の誕生:監視と処罰』 田村訳:新潮社。
1986 『性の歴史・:知への意志』 渡辺守章訳:新潮社。
FRANK, Arthur W.
1995[2002] The Wounded Storyteller: Body, Illness and Ethics. Chicago: University of Chicago Press. (『傷ついた物語の語り手:身体・病・倫理』 鈴木智之訳 ゆみる出版)
FRIEDSON, Eliot
1970[1992] Professional Dominance: the Social Structure of Medical Care. New York: Atherton Press (『医療と専門家支配』 進藤雄三、宝月誠訳:恒星社厚生閣)
GABE, Jonathan (ed.)
1995 Medicine, Health and Risk: Sociological Approach. Oxford: Blackwell.
GERHARDT, Uta
1989 Ideas about Illness: an Intellectual and Political History of Medical Sociology. New York: New York University Press.
GIDDENS, Anthony
1990 [1993]The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford Univ. Press. (『近代とはいかなる時代か』 松尾精文、小幡正敏訳:而立書房)
1991 [1995]Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press. (『親密性の変容』 松尾精文、松川昭子訳:而立書房)
GOFFMAN, Erving
1961[1984] Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. London: Penguin. (『アサイラム』石黒毅訳:誠信書房)
グロ、フレデリック
1998 『ミシェル・フーコー』 露崎俊和訳:白水社。
HIGGS, Paul
1998 Risk, Governmentality and the Reconceptualization of Citizenship. In Modernity, Medicine and Health: Medical Sociology towards 2000. SCAMBLER, Graham and Paul HIGGS (eds.) London: Routledge.
ILLICH, Ivan
1976[1998] Limits to Medicine, Medical Nemesis: the Expropriation of Health. London: Calder and Boyars. (『脱病院化社:医療の限界』 金子嗣郎訳 晶文社)
今村仁司、栗原仁
1999 『フーコー』 清水書院。
木村敏
1971 『人と人の間:精神病理的日本論』 弘文堂。
KRAUSE, Elliot A.
1996 Death of the Guilds: Professions, States, and the Advance of Capitalism, 1930 to the Present. New Haven: Yale University Press.
LANE, Karen
1995 The Medical Model of the Body as a Site of Risk: a Case Study of Childbirth. In Medicine, Health and Risk: Sociological Approach. Jonathan GABE (ed.) Oxford: Blackwell.
LAST,Murray
1996 The Professionalisation of Indigenous Healers. In Medical Anthropology. Carolyn F. Sargent and Thomas M. Johnson (eds.) Westport: Praeger.
LEMERT, Edwin M.
1972 Human Deviance, Social Problems and Social Control. Second Edition. Eaglewood Cliffs: Prentice-Hall.
LUPTON, Deborah
1995 The Imperative of Health: Public Health and Regulated Body. London: Sage.
1997 Foucault and Medicalisation Critique. In Foucault Health and Medicine. Alan PETERSEN and Robin BUNTON (eds.) London: Routledge.
リオタール、ジャン=フランソワ
1986 『ポストモダンの条件:知、社会、言語ゲーム』 小林康夫訳:水声社。
メルッチ、アルベルト
1997 『現在に生きるノマド:新しい公共空間の創出に向けて』 山之内靖、貴堂嘉之、宮崎かすみ訳:岩波書店。 MORRIS, David
1998 Illness and Culture in the Postmodern Age. Berkeley: Univ. of California Press.
中根千枝
1967 『タテ社会の人間関係:単一社会の理論』 講談社。
NAVARRO, V.
1976 Medicine under Capitalism. New York: Prodist.
PAPASTERGIADIS, Nikos
2000 The Turbulence of Migration. Cambridge: Polity Press.
PARSONS, Talcott
1951 The Social System. Glencoe: Free Press.
PETERSEN Alan and Robin BUNTON(eds)
1997 Foucault Health and Medicine. London: Routledge.
RITZER, George
1996 [1999] The McDonaldization of Society, Revised Edition. London: Pine Forge Press. (『マクドナルド化する社会』 正岡寛司監訳:早稲田大学出版部)
ROGERS, Anne and David PILGRIM
1995 The Risk of Resistance: Perspectives on the Mass Childhood Immunisation Programme. In Medicine, Health and Risk: Sociological Approach. Jonathan GABE (ed.) Oxford: Blackwell.
ROSENHAN, D.L. 1973 On Being Sane in Insane Places. Science 179: 250-258.
佐藤純一編
2000 『文化現象としての癒し:民間医療の現在』 メディカ出版。
SCAMBLER, Graham (ed.)
1987 Sociological Theory and Medical Sociology. London: Tavistock.
SCAMBLER, Graham and Paul HIGGS (eds.)
1998 Modernity, Medicine and Health: Medical Sociology towards 2000. London: Routledge.
SHEFF, T.
1966 Being Mentally Ill: a Sociological Theory. Chicago: Aldine.
SCOTT, Robert A.
1969 The Making of Blind Men. New York: Russell Sage.
SCOTT, Sue and Richard FREEMAN
1995 Prevention as a Problem of Modernity: the Example of HIV and AIDS. In Medicine, Health and Risk: Sociological Approach. Jonathan GABE (ed.) Oxford: Blackwell.
SZASZ, Thomas S.
1960 The Myth of Mental Illness. American Psychologist 15: 113-118.
TURNER, Bryan S.
1984 The Body and Society: Explorations in Social Theory. Oxford: Basil Blackwell (『身体と文化:身体社会学試論』 小口信吉、藤田弘人、泉田渡、小口孝司訳:文化書房博文社) 1987 Medical Power and Social Knowledge. London: SAGE.
1997 From Governmentality to Risk: Some Reflections on Foucault’s Contribution to Medical Sociology. In Foucault Health and Medicine. Alan PETERSEN and Robin BUNTON (eds.) London: Routledge.
TURNER, Victor
1974 Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society. New York: Cornell University Press.
WAITZKIN, Howard
2000 The Second Sickness: Contradictions of Capitalist Health Care, Revised and Updated Edition. Lanham: Rowman and Littlewood.
ZOLA, Irving
1972 Medicine as an Institution of Social Control, Sociological Review 20: 487-503.
{編集者による注記}
このウェブ論文は武井秀夫 編『身体の比較文化誌』社 会文化科学研究科・研究プロジェクト報告書、第23集、千葉市:千葉大学大学院社会文化科学研究科、 2003年に収載された巻頭論文がもとになっています。ひろくポストモダンについての議論は多くみられますが、医療のポストモダン状況についてこれだけ詳 しく書かれた日本語の論文はなかなか見つからないでしょう。この論文のウェブ公開を機会に、医療におけるポストモダン状況に関する医療人類学/医療社会学 に関する議論がもりあがらんことを!(池田光穂、2003年4月16日)
Copyright Hidetosih KONDO, 2003