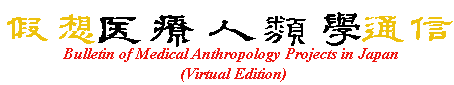 |
お灸をすえる:
鹿児島県三島村の「ヤイトヤキ」の医療人類学的考察・序説
渡山恵子・池田光穂
第13号(2005年9月)
1.はじめに
お灸をすえる、とは日本では一般的に(1)治療行為として「もぐさ」(ヨモギ属の草本[Artemisia sp.]の茎葉を乾燥させよく搗いた綿状の繊維)を皮膚の上で燃やすこと、(2)お灸の熱さに辛抱しなければならないことから(権威をもった人による) 「懲らしめ」という意味がある。
お灸はしばしば火傷の瘢痕を残すので、それを嫌う傾向が近年では増加したり、苦痛的治療が徐々に避けられるようになったりしている。そ のため現代の日本ではお灸は、直接肌に据える方法ではなく、さまざまな無機物あるいは有機物を皮膚との間に置いて間接的に暖める「温灸」(おんきゅう)と いう手法がより一般的になってきた。また家庭内療法としてさまざまな灸を販売する会社の新製品などには「火を使わない」灸も登場するに至っている。灸は針 治療と同様、身体のツボ(経穴)を刺激する中医学あるいは漢方医学の理論にもとづく治療実践であり、また針治療よりも素人により容易に扱えるため、多様な 現代的温灸の普及は、お灸をすえるという表現が本来もっていたマイナーだが一定の苦痛を伴った身体経験は今後ますます衰退ゆくものと予想される。
苛烈なお灸の経験がやがて好まれなくなり衰退してゆくことは、我々の社会が選択した帰結として考えると、特段のノスタルジーを思い起 こす必要も、またそれを「保存」してゆく必要もないだろう。灸の技法やそれに使われている素材に関する博物学的記述の豊富に存在するため「絶滅したお灸の 技術」を復元することはそれほど困難になるとは思えないからである。しかしながら、そのようにお灸を理解することは、実はお灸を伝統的療法の一技術とし て、お灸を据える行為が持っている社会性について忘却することに他ならない。現実に我々は、本稿の研究対象である鹿児島県三島村での「ヤイトヤキ」に関す る聞き書きをするまでは、それが忘却されつつある数多くの日本の伝統的施術のひとつであるということ、それ以上の特別の感慨を持たなかった。
しかしながら、他の日本の多くの村落社会においてみられた、灸(ヤイト)や灸焼き(ヤイトヤキ)とは、治療の施術であると同時に、山 仕事や農作業などが終わって、お互いが疲れを癒し、相互に灸を据え合う、地域の相互交流の場でもあった。お灸を治療技術(すなわち施術)と観ると同時に、 それがおこなわれる社会的場(social space)での人間的交流とみると、そこではお灸に関するノウハウ知識が交換されるだけでなく、熱さからの苦痛を紛らわすために好んで行われた村落での さまざまな世間話や出来事などの情報の交換、そして、共同で相互に灸を据えてあげる(過酷な筋肉労働には背中に施術することが多いため複数の人数でおこな われやすい)という、治療行為の相互作用がみられることがわかる。近代医療の医療者のみならず、伝統的施術師においても技術内容が専門化すれば、お互いに 病んだ者同士が相互に治療し合うという相互施術の要素はみられなくなる。灸をおこなう集団は治療共同体(therapeutic community)であると声高に主張するつもりは我々にはないが、身体経験を共有する人たちの共同治療行為という観点からお灸をみる視点が、これまで の先行研究には皆無であった。ヤイトヤキの社会的経験は、鍼灸の技術に関する記録のように事物やスケッチまたは写真として残すことはできない。その社会的 経験は、行為者の記憶や身体の瘢痕の中にかろうじて残されているにすぎない。
本稿は、施術体験の記憶に関する村人の語りを通してヤイトヤキがいったいどのようなものであったのか、ささやかな事例報告をおこな う。しかしながら、その記述のねらいは、記録される前からすでに忘却されてきた、この〈施術の社会性〉に関する考察のための資料を提示することにある。
ヤイトヤキは、鹿児島県三島村で行われている灸施術のことである。三島村は、2000年に医師の常駐化が開始になるまで無医村であ り、この地域では昔から、手養生として灸の治療が重宝されてきた。灸は昔から行われている民間療法であり、つい最近まで雨天などで仕事休みの日に、誰かの 家に3人から4人程度集まって、互いに灸を据えあうヤイトヤキという「交流施術」が盛んに行われていた。「交流施術」とは、決まった施術者(施術を専門に する人)によって行われる施術ではなく、寄り合った人々が互いに交替で施術を行いあうことである。しかし村の近代化が始まり、経済力や交通事情の改善、へ き地医療が充実してくると灸の治療は次第に衰退し、「やいと焼き」は、現在では「黒島」の一部の住民によって行われているのが現状である。
2.三島村の概観
三島村は、薩摩半島の南南西約40kmに位置する「竹島」「硫黄島」「黒島」の3島からなる村である。2004年3月現在、人口 377人、60歳以上の人口が171人を占める高齢化率(人口に占める60歳以上の割合)が45%の過疎の村である。村は小離島の集まりで構成されてお り、役場が島内ではなく鹿児島市内にあるのは全国でも珍しい。 三島村は2000年に医師の常駐化が開始になるまで無医村であった。硫黄島診療所に医師1名が配属されていた1950年当時の村の人口は1379人であっ たが、1965年に村の人口は874人と減少し、翌年無医村となった。2000年に医師の常駐化が開始になるまでの間は、各島の診療所には看護師のみが配 属され、この間は多くの保健医療機関の協力を得ながら、住民の健康保持と地区公衆衛生の増進がはかられた。看護師がいない島では、この頃小中学校に配属さ れるようになった養護教諭が看護師の役割を兼務している。
医師の常駐化とは、3つの島で構成されている村という行政地区に1人医師がいるということであり、各島の診療所にいつも医師が滞在し ているわけではない。医師は各島の診療所を巡回診療している。
三島村の島々を外から眺めると、海岸は海蝕崖の絶壁をなし、ほぼ全島を竹林が覆っている。集落内の地形は坂道が多く、硫黄島以外は平 坦な場所が少ない。定期船が接岸できるようになったのは硫黄島1974年、黒島大里1975年、黒島片泊1980年、竹島1976年である。
港湾整備に伴い道路が舗装されると島内の運搬手段は車に替わったが、それまでは全て人が荷を担ぐか、背負い籠による運搬であった。現 在、村の主要産業は畜産、漁業、島に自生する筍の加工であるが、1980年代までは、竹が主な現金収入源となっていた。島に自生する竹は、昔から物干し 竿・支柱竹・棚竹・側溝竹等としての需要があり出荷されていた。棚竹は、1935年頃から鹿児島本土の漁村に、土壁用支柱竹は北海道あたりに需要があり 1985年頃まで続いた。棚竹は太さ親指大・長さ4m、土壁用支柱竹は太さ小指大・長さ3mの竹を選んで切り出し、100本束・200本束にして、急な坂 道・山道・崖道を担いで港まで運び、伝馬船に乗せ、定期船に積み込んでいたという。
竹は島の共有であり、初めは割り当ての本数だけを出荷していたが、後は自由に出荷できたという。棚竹の値段は1935年当時一束5銭 から10銭(当時の白米の値段は10kg2円50銭)、支柱竹は全盛期の1950年代には200本束800円から1000円(当時の白米の値段は 10kg3000〜3400円)で出荷していたという。
3.高齢者の健康事象
「やいと焼き」の体験を持つ住民や、役場から派遣されるはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施療を受ける住民は、現在では 60歳代以上の人達である。
島の高齢者は働き者で、70歳代半ばまでは竹の伐採や農作業に従事している。集落内で見かける高齢者は、杖を手にしながらもテゴ(背 負い籠)を背負い、かくしゃくと歩いている。しかし、高齢者の多くは膝の痛みを訴え、正座が困難であると訴える。室内では椅子に腰掛けているか、又は下肢 を伸ばした座位姿勢である。診療所の診療記録に記載されている診断名には、変形性膝関節症、腰痛、座骨神経痛、肩関節周囲炎等が多い。
高齢者は、膝関節痛や膝の運動障害、腰痛等の原因として、過去に行われた竹の出荷作業等の重労働と道路事情の悪さをあげる。その治療 として行われていたのが「やいと焼き」であるという。現在でも「やいと焼き」を行っており、「やいと」が上手だと言われている78歳の男性は、「やいと」 について次のように話す。
黒島では、昔からやいとが盛んだった。雨の日など仕事休みの日に、誰かの家に集まって「やいと焼き」をするのが常だった。体が痛い、 肩へき痛、疲れているとき、目がさ(目の炎症)等に良く効いた。昔はハライタ(腹痛)も多かった。背中の大筋が棒のように固くなるとハライタの前兆なので 「やいと」をした。体を楽にして(休養する)、それでも良くならないときや、風邪引きからなかなか立ち直れないとき、神経痛のときに、毎日やいとをする。 モグサは、昔から鹿児島市内の「紅モグサ」の店から仕入れている。
住民は「やいと」は自分達の手養生であり、肩・腰・腕・膝・へき(肩と背部)等の体の痛み、疲労感、腹痛、目がさ、何でも「やいと」 で治した、医者のいない島でできる養生と言えば「やいと」しかなかったと話す。この言葉を裏付けるように、三島村で灸の治療が重宝されていたことは『拾島 状況録』[笹森1895]に、次のように記されている。
「赤痢ニ在テハ主トシテ炙治ヲ為シ、又売薬感應丸、清心丹等ヲ服用セシメ、粥湯ヲ飲 マシメタリト。凡ソ腹中ノ疾患ニ在テハ、其何タルヲ問ハス、総テ炙炎セサルナシ。故ニ拾五六歳ニ至ル者体中炙痕ヲ止メサルモノ一人モ見ル能ス」[笹森 1973:119]。
4.やいと焼きの実際
それでは、「やいと焼き」はどのように行われていたのか、住民の具体的な体験について紹介する。紹介する事例は、筆者の一人、渡山恵 子が2003年8月から2004年7月の1年間に黒島で行ったフィールドワークによるものである。
事例−(1) 女性(82歳)
もう今は形も無いですよね。あん頃の事は、その目で見た人でないとわからないです よね。女の人でも、岩ん所を担いで降り寄ったんですよ。『私は忘れない』という映画にもあることはありますよね。あの時代は、私達はあんなして仕事はし よったんだけどね。
私は「痛い(熱感痛)」からあまり焼く方ではなかったけど、私の同級生達はしょっ ちゅう雨が降る度に、「やいと」を焼いていました。天気の日は仕事が忙しいから、雨が降れば自分たちの手養生だと言うて、「やいと」しか養生はなかったん ですよ。「やいと」を焼いとらんと疲れがくると言ってね。もう親達にそう誘われて、もう昔の時代は「やいと」をずっと焼いとらんと疲れが来ると言ってね。 「やいと」をすえる人は身が強いと言って、雨が降る度に「やいと」をすえていたんですよ。「やいと焼き」が仕事だったんですよ。だけど私は臆病かなんかし らんけど、「やいと」が「痛い」方(熱の痛みを強く感じる方)だったからあまりせんかったけど、たまにはほら、「やいと」をすえんと体がもてんと言われる ものだから、たま〜にはしよったけど、「痛さ(熱感痛)」が我慢できなくて。
自分達で、交替で、今度は私を焼いて、その友達がまた相手を焼いて。「体が疲れて 痛い(筋肉痛)」ところをこうやって押さえて、もうそいこそ点々にどこそこ、どことなく体中しよったんですよ。今のお灸ちゅうのは、つぼつぼを押さえて、 そんだけしかしないけど、そん時代の親達の「やいと」は、背中一杯もうどことなく据えよったんですよね。自分達は子供なりに見とって、あんだけ火を点けて 焼いても、よう痛くないねえと思って見とったのが、自分達が据える気にはならんわけよ。
もうこん島の人達はずっと昔から「やいと」で。「やいと」を焼いた痕はもう火傷の 水ぶくれができて、それが潰れたら、もう傷になってとろけるわけよね。また、そいの上に、また「やいと」を据えるわけよ、あれを見てたら、見ちょっただけ で体が痛くなって。あいでも我慢して、「やいと」をしよったがねと今思う。
この事例の「やいと焼き」の記憶の心象として伝わってくるのは、「やいと焼き」をめぐる身体状況である。やいと焼きの背景には、身体を 酷使する重労働があり、やいとは身体疲労がたまるのを予防し、労働に耐える強い身体を保つために必要な養生法として住民に認識されていたことがわかる。
また事例の強烈な身体観として残っているのは、モグサの火の熱感痛である。筋肉痛の部位を圧して特に強い痛みを感じる箇所に灸をすえ るという経穴に関係のない広範囲に点在して行う施術と、灸の合併症である火傷による水疱や潰瘍は、事例の経験した熱感痛の記憶と共に「やいと焼き」の身体 心象として強烈に残っている。
事例−(2) 女性(84歳)
「やいと」は、親の代も、昔からしていた。集まって「やいと焼き」をした後は、み んなお茶を飲んで帰りよった。集まる場所は、決まってはいなかったけど、雨の降る日は暗いから、明るいところが良い。電気がなかったので、明るい家でして いた。みんな集まって、いろんな話をしながら、楽しみでもあったよね。今ではそういうことはないですね。
お灸をしたときは、牛が千里行って千里帰るまで休まないと、お灸をしても効果はな いもんだと、昔の人は言うて聞かせるものだった。牛はのっこのっこ、のっこのっこだから、お茶を飲んでゆっくり休むもんだったの。
正月の月は門松が立っているから、門松が倒れないとお灸はしたら駄目と言われるも のだった。線香の臭いがするからでしょうね。13日に門松を倒すので、門松が倒れてからしていた。
30代の頃だったかな、牧場作りに竹を伐採して焼いて、その後に肥料とか石灰とか を播いて、そこに牧草の種を蒔きよったの。肥料とか石灰とかを背中に背負って、山ん岳までさるきよったら(行ったり来たりしていたら)、膝の裏のとこが腫 れて疼いた。それで足がこんなになった。昔は200本束・300本束の竹切り出しとか、重労働が続いていた。その頃は、こんなして、膝の回りを押さえて、 「痛い(筋肉痛)」ところに自分で「やいと」を据えていた。痛みは一時止むけど、仕事をしたらまたそんなになるから、繰り返し、繰り返しだった。 「やいと」は、スジスジ(つぼ)があるから、背骨の脇を押さえて、痛いところにしよったんですよ。打ったりしたところは、灸をすると二度とその病気が出な いものだと言いよったけどね。
前は自分達で「やいと」を焼いていたけど、今はしない。昔の「やいと焼き」は、焼 いてもらったら、今度は次の人を交替で焼いてあげよったから、疲れよったけど、今は先生に(鍼灸師)焼いてもらえば、ゆっくりして疲れないからいい。昔ほ ど仕事もしないからでしょうけど。
今は役場から来てもらうから助かります。肩と腰にしてもらっています。鍼灸師の人 に鍼や灸をしてもらったり、診療所から湿布をもらうだけです。
この事例は、50歳代まで積極的に「やいと焼き」を行っていた方である。「やいと」をすえる部位は、「つぼ(経穴)」を意識してすえ ている。この事例の記憶に残る「やいと焼き」の心象は、社交的な場であり、交流の場であった「やいと焼き」の風景である。集まって「やいと」をすえた後、 お茶を飲みながら話をし、くつろいだことを楽しみであったと述べている。
重労働に追われる日々の中で、雨天の日は唯一の休養日である。「やいと」をしながら身体の疲れ具合や痛みの部位等を訴えあう。身体感 覚を共有し、お茶を飲み、世間話をする。このような「やいと焼き」の場は、ストレス解消の場であり、社交の場であったことがわかる。
現在は、労働に従事していた頃のようには、「やいと」の必要性は感じていないが、役場から派遣されるはり師・きゅう師・あん摩マッ サージ指圧師の施術を受けるだけの立場を心地よく感じている。また、診療所を受診し、湿布等の処方も受けている。
事例−(3) 女性(80歳)
体が痛いとき(筋肉痛)、雨降りに2、3人集まって「やいと」を焼いている。「やい と」をするのが一番良い。体操をしたりして、それでも良くならないときは、今でも「やいと」を焼くよ。
昔は竹切り出しで、200本束を担いでいたよ。腰を痛めてぎっくり腰になって、痛く て、トイレも外にある時代だったから、手足に草履を履いて、這ってトイレに行くものだった。「焼き」を当てたら(つぼ)、いっぺんで良くなるものだった。
「やいと」は1日したって効かない。3日間はしてもらったほうがいいね。御飯もおい しいし。3日ぐらいするとしばらくは良い。腕が痛いので、自分でも据えることはあるよ。蝋燭に火を点けて、痛いところに自分でも据えるの。灸をする人に、 痛いところが灸点だと聞きますよ。消えた場合は、すぐ取ると火傷みたいに膨れるから、そのまましておくの。そのままして置いたら自分で落ちるから。
千年灸もする。気持ちがいいですよ。あんまり、お灸としたら、そんなに痛くない し。これは(もぐさ)ちょっとまあ天気によってか、痛いときがあるのだけど、良く効きますよ。夏は暑いからあまりしないけどね。
鍼灸の先生が来たときもしてもらうし、診療所から湿布ももらうし、子供達も湿布を 送ってくれる。
この事例は灸を好み、現在でも積極的に施術を受けている方である。
「やいと」をすえる部位は、経穴というよりは圧して痛い部位に意識的にすえている。「焼き」を当てたら一遍で良くなるものだったと述べ ているように、すえた部位がうまいぐあいに経穴だったとき、より効果があったものと推測する。
しかし、翌年訪問したときは、老化と体力の衰えを感じさせ、自分達で行う「やいと焼き」はもうしていないと言われた。その替わり、お 金を払って集落のTさん(女性)に「やいと」をしてもらっていると話された。その他、役場から派遣されるはり師・きゅう師・マッサージ師の施術や腕や下肢 など自分ですえることのできる部位は自分でも灸をすえている。また、診療所を受診し、湿布等の処方も受けている。
5.考察
体験談からは、当時の「やいと焼き」をめぐる情景が彷彿とされる。人々の往時の記憶に共通する話題は、道路事情の悪さと竹の出荷等の 重労働である。「やいと焼き」が必要とされた生活背景には、関節を痛める坂道や崖道が多い島の地形と、身体疲労をためる竹の出荷等の重労働がある。「やい と」には疲労感や筋肉痛・関節痛等を予防・改善し、労働に耐える強い体力を保つ効果があるという治療観・価値観があり、重労働に耐えるために必要な養生法 として認識されていたことがわかる。
「やいと焼き」の方法は、中国医学に定義される経穴には関係なく、押して痛いところに灸を据えるという素人施術が行われた。専門的な 技術に依存しない素人施術ではあったが、症状を改善したことによって治療・養生手段が今日まで残ったと考えられる。医療機関が無い、経済的にも裕福ではな い、交通事情も悪い、辺鄙な離島へき地に住む住民にとって、「やいと」は安価で手軽にできる手養生として、また効果を期待できる、頼りになる治療法として 重宝されてきた。
「やいと焼き」は、小グループで互いに「やいと」をすえ合う交流施術ということに特徴づけられる。重労働に追われる日々の中で、雨天 の日は唯一の休養日になる。気の合う仲間が集まって互いに「やいと」をすえながら、身体の疲れ具合いや痛みの部位など、身体の状態について訴えあう。それ は互いに身体感覚を共有できる。身体状態を訴え、お茶を飲み、世間話をする、このような「やいと焼き」の場は、ストレス解消の場でもあり、明日への活力の 場にもなっていた。少メンバーが集まって行う「やいと焼き」は、単に施術治療を行うだけの場ではなく、ストレス解消の場であり、健康に関する情報交換や健 康維持に貢献した健康探求実践の場であり、社交の場であったことがわかる。
しかし、治療実践であると同時に社会慣行であった「やいと焼き」は次第に行われなくなり、現在では竹島、硫黄島、黒島片泊では見るこ とがなく、黒島大里においても一部の人達によってのみ行われているだけである。代わって重宝されるようになったのが、役場から派遣されるはり師・きゅう 師・あん摩マッサージ師による施術と、「千年灸」などの登録商標で売られている一般消費者用に改善された灸を薬局から購入して行う自己施術である。
「やいと焼き」は集団で行う交流施術から、「個人で行うセルフケア・タイプと治療施術タイプ」[佐藤2000:12]の形態に変化して おり、今後はさらに衰退していくものと思われる。その理由は、村の近代化による社会的・経済的変化があげられる。港湾整備、道路舗装、生活環境の向上は重 労働からの解放をもたらし、交通事情の改善、診療所の設置、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の派遣事業は、医療資源選択の自由をもたらした。も う一つの要因は、「やいと焼き」を必要とした年代の高齢化である。事例2、事例3は、加齢による体力の衰えから、鍼灸師や第三者に施術を受けるだけの立場 を心地よく感じている。加齢による体力の衰えは、互いに灸を据え合う体力を失った。
また村の近代化への過程は近代医療導入の過程である。医師のいない島で、手養生として重宝されてきた「やいと」は、村の近代化による 社会的・経済的変化、へき地医療がより日常的な疾患に関わるようになる過程で次第に衰退していったものと思われる。
ささやかではあるが、本稿の事例から得られる結論とはこうである。ヤイトヤキの現場は、社会的な治療の場を形成していたことである。
他方、我々が温灸などの施術行為について思いを馳せるとき、それは佐藤[2001]のいう「個人でおこなうセルフケア・タイプ」の治 療実践しか思い起こせない。利用できる治療資源が限られ、その個々の治療のパフォーマンスが悪いとき、苦痛を伴った患者への最善と思われていたケアとは、 患者が苦しむその場に立ち会い、同情と共感をもってその苦痛を看病する人たちと共に分かちあうことであった。ヤイトヤキは瀕死の患者に施術することではな いが、お互いにヤイトの苦痛を辛抱しあう姿は、(セルフケアとして)一人で施術する経験とは異なったより社会的な経験であろう。
我々が人間社会に広くみられる治療実践を理解しようとする時、我々は知らない間に、身の回りに見られる「医師−患者関係」 (doctor-patient relation)のモデルを当てはめ、患者の苦悩と治療を極めてパーソナライズしたものとしてみる偏見がともすれば見られるのではないだろうか。そして よりよい治療モデルとは、行動科学的に裏付けられた苦痛ないしは苦悩を除去する〈快適さ〉を追求するものだと考えてしまう。このような現代状況の中で、 〈痛み〉を共有することに主眼がおかれ社会性が強調される、交流施術としてのヤイトヤキの社会経験を観念的に想像することは極めて難しい。ヤイトヤキを常 識的に理解することが難しい現在、その学問的考察はさらに難しいものとなるだろう。
しかしながら、僅かに残された三島村のヤイトヤキの事例の考察は、あらゆる治療実践の背景にある社会性について、我々医療人類学を勉強 する者に対して常に忘れることのないように「お灸をすえてくれる社会現象」なのだ。苛烈なお灸の瘢痕が、その痛みを思い起こしてくれるように、ヤイトヤキ の調査経験もまた、医療人類学の研究がどのようなものであるべきなのかを我々に教えてくれるのである。
参考文献
佐藤純一編 2000『文化現象としての癒し』メディカ出版
笹森儀助 1973「拾島状況録」『日本庶民生活資料集成第一巻』:三一書房
M.ロック 1990『都市文化と東洋医学』中川米造訳:思文閣出版
写真 【掲載準備中】
1、やいと焼きに使用されるもぐさと線香
2、やいとやき
3、やいと焼き痕跡
Copyright Keiko WATARUYAMA and Mitsuho IKEDA, 2005
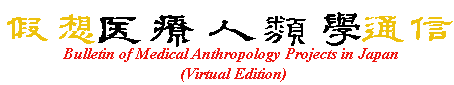 |