Ideology and Terror, a novel form of government
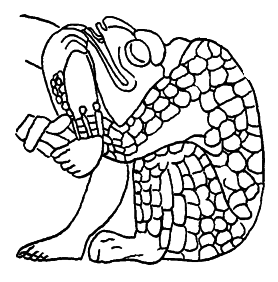
アーレント「イデオロギーとテロル:新しい統治形式」ノート
Ideology and Terror, a novel form of government
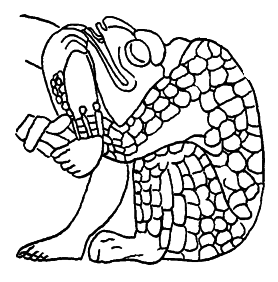
池田光穂
ハンナ・アーレント「イデオロギーとテロルーー新しい統治形
式」ノート
■全体主義の独自性
「……全体主義は暴制、圧制、独裁制のような私たち
に知られて来た他の政治的抑圧の形式とは本質的に異なるものであることを[著者は]くりかえし強調して
来た。どこで政権を掌握しようと、それはまったく新しい政治制度を発展させ、その国のすべての社会的、法的、また政治的伝統を破壊した。そのイデオロギー
の持つ民族特有の伝統がどうであれ、またその特殊な精神的源泉が何であれ、全体主義的統治は常に階級を大衆に変え、政党制に代えるに一党による独裁制では
なく大衆運動をもってし、権力中枢を軍から警察に移し、公然と世界支配を指向する対外政策を確立した。現在の全体主義的統治は単一政党制から発展した。こ
の制度は真に全体主義的になると、常に他のすべての価値体系とは根本的に違う或る価値体系に従って働きはじめた。そのためわれわれの伝統的な法的、道徳
的、もしくは常識的功利主義的なカテゴリーのいずれをもってしても、これらの体制の行動方針に協調し、もしくはそれについて判断し、予見する助けには全然
ならなかったのである[アーレント 1981:301]。
■政治的表現としての全体主義支配
「全体主義的支配をもってその政治的表現としている
基本的経験があるとすれば、この全体主義的な統治形式というものが新しいものである以上、その経験はど
んな理由によるにもせよこれまで一度も一個の政治体の基礎となったことのない経験でなければならない。そしてまたその経験が持つ基調はーーたといそれが他
のすべての点で人々に無縁なものではなかったとしてもーーこれまで一度も公共の事柄に影響したことがなく、またそうした事柄の処理に当って決定的なもので
なかったと考えねばならない」[アーレント 1981:302]。
■統治のオルタナティブを全体主義は覆す
「全体主義的統治は先例のないものだったと言うかわ
りにわれわれは、政治哲学において統治の本質のすべての定義の基礎をなしていたオルタナティヴそのもの
を全体主義的統治はくつがえしてしまったと言うこともできたろう。つまりそれは、法による統治か法なき統治か、専断的権力か合法的権力かのオルタナティヴ
である。一方での法による統治と合法的権力、他方での法なき統治と専断的権力とが、たがいに他を必要として不可分のものであることは嘗て疑問とされたこと
がなかった。ところが全体主義の支配によってわれわれはまったく別の種類の統治に直面させられたのである」[アーレント 1981:302]。
■ナチス政権とワイマール憲法
「ナチス政府が遂に撤回しなかったワイマール憲法の
ごとき」[アーレント 1981:303]。
■全体主義と法
「〈無法〉であるどころか、実定法にその究極的な正
当性を与える源泉にまでさかのぼり、専断的であるどころか、超人間的なあのカに対してはこれまでのいか
なる統治よりも従順であり、一人の人間の利益のために権力を揮(ふる)うどころか、歴史の法もしくは自然の法とみなされるものの実現のためにはすべての人
間の最も切実な利益をも犠牲にして顧みないというのが、全体主義的支配の建前なのだが、この建前はまことに途方もないものであり、一見反駁のしようはない
ように見える。実定法を無視するその論拠は、こちらこそより高い形での合法性であり、源泉そのものに即している以上せせこましい遵法主義など無視していい
ということである」[アーレント 1981:303]。
■全体主義の法の遵守レトリック
「全体主義の遵法は、地上における正義の支配ーー実
定法の遵守をもってしてはあきらかに遼し得ないものーーを確立する道を見出したと主張する。遵法主義と
正義との差はどうしても取除けない。なぜなら、実定法は自分の認める権威の源泉||全宇宙を支配する〈自然法〉であれ、人間の歴史のなかに啓示される神の
法であれ、あるいはまたすべての人間の感情に共通する法を表現する習慣と伝統であれーーを引合に出して正邪の基準を作ろうとするが、この基準は必然的に普
遍的なものでなければならず、想像もできないほど無数の例に一々あてはまらねばならないが、しかし同一ということのあり得ないさまざまの状況下にある一つ
一つの具体的な事例は何らかの形でそれから逸脱してしまうからである」[アーレント 1981:303]。
■法の合意(consensus iuris)の破壊
「全体主義の国々と文明世界とをつなぐ環が全体主義
体制の犯した恐るべき犯罪によって断たれてしまったということが事実ならば、この犯罪性は単なる攻撃性
や非情さや戦争行為や裏切によるものではなく、キケロに言わせれば/「人民」を形造り、また国際法として戦争中においてすらも国際関係の礎石たりつづける
かぎり文明世界を形造っているあの〈consensus
iuris〉(全員の合意による法の承認)なるものの、意識的な破壊によるものだということも事実である。道徳的判断も法的制裁も上記の基本的合意を前提
している。犯罪者はみずから 法の合意(consensus
iuris)に加わっているからこそ公正な裁きを受けられるのであり、そして神によって啓示された法すらも、それが人間のあいだで機能を果し得るのは人々
に傾聴され同意される場合のみなのだ」[アーレント 1981:303-304]。
■全体主義の政治と法
「全体主義の政治は或る法体系に代えるに他の法体系
をもってするわけではないし、それ自身の consensus iuris
を作り出すわけでも、革命をおこなって新しい法形式を生み出すわけでもない。自分自身の実定法をも含めてあらゆる実定法を無視するその態度は、何らの法の
合意(consensus
iuris)なしにあらゆることをなし得るとそれが信じており、しかもなお無法と専断と恐怖の専制国家に陥るなどとは思っていないことを意味している。そ
れが法の合意(consensus
iuris)なしでやって行けるのは、法の実施をすべての人間の行動および意志から切離して行くと約束しているからなのだ。そしてそれが地上における正義
を約束するのは、人類そのものを法の具現にすることができると自負しているからである」[アーレント 1981:304]。
■人間と法の同一化について
「人間と法とのこの同一化は、古代以来の法思想の悩 みの種だった合法性と正義との差を解消するもののように見えるが、これは〈自然の光〉(lumen naturale)もしくは良心の声とは何一つ共通するものを持たない。自然権(ius naturale)もしくは歴史を通じて啓示された神の掟の権威の源泉としての〈自然〉もしくは〈神〉は、〈自然の光〉(lumen naturale) もしくは良心の声を通じて、その権威を人間自身の内面に告知すると考えられているのだが、しかしこのことは決して人間を法の生きた具現にはせず、反対に法 は人間に同意と服従を要求する権威として人間とは異なるものとされていたのである」[アーレント 1981:304]。
"This identification of
man and law, which seems to cancel the discrepancy
between legality and justice that has plagued legal thought since
ancient
times, has nothing in common with the lumen naturale or the voice of
conscience,
by which Nature or Divinity as the sources of authority for the ius
naturale or the historically revealed commands of God are supposed to
announce their authority in man himself. This never made man a walking
embodiment of the law, but on the contrary remained distinct from him
as the
authority which demanded consent and obedience. " (Adendt 2004:596)
■実定法(ius positivum )の機能
「実定法の権威の源泉としての〈自然〉もしくは
〈神〉は永遠不易なものと考えられていた。実定法はその時その時の事情によって変化しつつあるもの、可変的
なものだったが、しかしもっと急速に変る人間の営為にくらべれば相対的な不変性を持っていた。そしてこの不変性は、その権威の源泉が永遠に存在することか
ら来ていた。だから実定法は本来、絶えず変る人間の動きを安定化する要因として機能するように考えられていたのだ」[アーレント 1981:304]。
■運動の法則概念
「全体主義の解釈によれば、すべての法は運動の法則
になっている。ナチが自然の法則を、あるいはボルシェビキが歴史の法則を語るときには、自然も歴史も人
間の行動にとっての安定的な権威の源泉ではもはやない。それらは運動そのものなのだ。自然法則の人間における表現としての人種法則について/のナチの信念
の基底には、現生の人間という種ではかならずしも停止しない自然の発展の産物としての人間というダーウィンの観念がひそんでいるが、それとまったく同じく
歴史法則の表現としての階級闘争についてのボルシェビキの信念の基底には、それ自身の運動法則に従って消滅する歴史的時代の終末ーーそこでは歴史の動きそ
のものが消滅するーーにむかつて突っ走る巨大な歴史の動きの所産としての社会というマルクスの観念があるのだ」[アーレント
1981:304-305]。
■マルクス主義と進化論と法(則)概念の変化
「エンゲルスには、マルクスを「歴史学のダーウィ
ン」と呼ぶことに優る、マルクスの学問的業績に対する讃辞は考えられなかった。この二人の人間の実際の功
績ではなく、彼らの基本的な哲学を考えるならば、歴史の動きと自然の動きは結局のところ同一であることがあきらかになる。ダーウィンが進化の観念を自然の
なかに導入したこと、すくなくとも生物学の領域においては自然の運動は循環的ではなく直進的であり、無限の前進をおこなうという彼の断言は、自然が謂わば
歴史のなかにのみこまれ、自然の生命は歴史的なものであるとみなされていることを事実上意味する。適者生存の〈自然〉法則は、マルクスの最も進歩した階級
が生き残るという法則とまったく同じ程度に歴史的法則であり、そういうものとして人種主義によって利用された。他方では、マルクスの言う歴史の駆動力とし
ての階級闘争は生産力の発展のあらわれにすぎず、そしてその生産力もまた人間の〈労働力〉に源を持つ。マルクスに従えば労働は歴史的なカではなく、人間が
それによって自分の個体的生命を維持し種を繁殖させるーー人間と「自然とのあいだの代謝」によって解発されるーー自然的・生物学的な力である。エンゲルス
はこの二人の人間の基本的な信条の近似性を非常にはっきりと見て取っていたが、それは発展(進化)の概念が両者の理論のなかで演ずる決定的な役割を理解し
ていたからだった。十九世紀中葉におこなわれた巨大な知的変化は、すべてのものを〈あるがままに〉見、もしくは受容れることを拒み、すべてのものを今後も
なおつづく発展の一段階であると首尾一貫してみなすことにあった。この発展の動力が自然と呼ばれたか歴史と呼ばれたかは、どちらかといえば二義的なことで
ある。これらのイデオロギーにおいては〈法〉という言葉そのものが意味を変えた。人間の行為や運動がそのなかでおこなわれる静止した枠組を表現するもの
だったのが、運動そのものの表現となったのである」[アーレント 1981:305]。
■終焉=殺戮の思考と運動法則の継続
「生きるに適しない有害なものをすべて除去するのが
自然の法則だとすれば、それは新しい種類の有害で生きるに適しないものが見つからないときには自然その
ものの終末を意味するだろう。階級闘争において或る階級が〈凋落する〉ことが歴史の法則だとすれば、新しい階級が形成され、次いでその階級がまた全体主義
的支配者の手にかかって〈凋落する〉ということがない場合には、それは人間の歴史そのものの終末を意味するだろう。換言すれば、それによって全体主義運動
が権力を奪取し行使する殺しの法則は、たとい全体主義が人類全体をその支配の下に置くことに成功した暁にも依然として運動法則でありつづけるだろう」
[アーレント 1981:306]。
■法による統治
「法による統治という言葉でわれわれが理解している ものは、不変の自然権(ius naturale)もしくは永遠の神の提を善悪の基準に翻訳して実現するために実定法を必要とする政治体である。このような基準のなかでのみ、神の掟は真 に政治的現実となるのである」[アーレント 1981:306]。
"By lawful government we understand a body politic in which positive laws are needed to translate and realize the immutable ius izaturale or the eternal commandments of God into standards of right and wrong." (Adendt 2004:598)
■全体主義のおけるテラー(暴力性)と政治の関係
「テラー(暴力性)はすべての反対派と無関係に存在
するようになると全体的になる。それを臨むものが1人もなくなってしまうとテラーは完全な支配権を握
る。法を持つことが非専制的支配の本質であり無法が専制の本質であるとすれば、テラーは全体的支配の本質なのである。/テラーは運動法則の実現である。そ
の第一の目的は、自然もしくは歴史のカがいかなる自発的な人間の行為にも妨げられずに自由に人類に法透できるようにすることにある。だからテラーは、自然
もしくは歴史の力を解放するために人間を〈静止〉させようと努める。この運動の結果特定の人類の敵が選び出され、彼らにむかつてテラーの暴威がふるわれ
る。そして人間の自由な反対もしくは共感が、〈歴史〉もしくは〈自然〉の、階級もしくは人種の〈客観的な敵〉の排除を妨げることは許されない。有罪や無罪
は無意味な観念となる。〈劣等人種〉や〈生きるに値しない〉個人や〈死滅しつつある階級と頽廃した民族〉に判決を下した自然の、もしくは歴史の過程を妨げ
るものこそ有罪なのだ。テロルはこの判決を執行する」[アーレント 1981:306]。
■全体主義と自由
「人間たちをぎゅうぎゅう締めつけることによって全
体的テラー(total
terror)は彼らのあいだの空間をなくしてしまう。この鉄の帯(=タガ、箍)に締めつけられた状態にくらべれば、専制の沙漠もまだ何らかの空間である
かぎりにおいて自由の保証であるかのように見える。全体主義の統治はかならずしも自由を削減したり基本的な自由を廃棄したりするわけではないし、すくなく
とも筆者の限られた知識の範囲では、人間の心から自由への愛を消し去ることに成功してもいない。ただ全体主義の統治はすべての自由の欠かすことのできない
一つの前提条件を抹殺するのだが、何のことはない、その条件とは空間なしには存在し得ない動く能力というものにほかならないのだ」[アーレント
1981:308]。
■人間性を奪う暴力性(テラー)
「全体主義的統治の本質である全体的テラーは、人間
のために存在するのでも人間に敵対して存在するのでもない。それは自然もしくは歴史のカに、その運動を
促進する最上の手段を与えるものとされている。それ自身の法則に従って進行する運動は長い時間のうちに歯止めをかけられるようなことはない。結局のところ
この運動のカは、人間の行動もしくは意志によって生み出された最も強いカよりもさらになお強大であることが常に証明されるだろう。しかしこのカも減速され
ることはあるし、また事実人間の自由によってほとんど不可避的に減速される。この自由は全体主義的支配者といえども否定し得ないが、それはこの自由がーー
支配者たちにはいかに場違いな勝手なものに見えようともーー、人間が生れて来ており、だから彼らの一人一人は新しい始まりであり、或る意味では世界を新し
く創始するという事実そのものにほかならないからである」[アーレント 1981:308]。
■人間と生とテラー
「全体主義の見地からすれば、人間が生れそして死ぬ
という事実は高次のカに対する余計な干渉としか見られないかもしれない。だから、自然もしくは歴史の運
動の従順な僕(しもべ)としてのテラーは、その運動の過程から、何か特定の意味の自由だけではなく、人間の誕生という事実そのものとともに与えられ、新し
い始まりを生み出すという能力そのもののうちにある自由の源泉をも取除かねばならない。人間の複数性を消滅させ、それ自身が歴史もしくは自然の歩みの一部
であるかのように確実に働く〈ひとつの者〉を作り上げるテラーの鉄の帯(=箍、タガ)とは、歴史と自然のカを解き放つだけではなく、そのままでは決して到
達し得なかったような速度にまでそのカを加速させる装置だったのである」[アーレント 1981:308]。
■統治と法
「統治の本質が適法ということであるとすれば、そし
て法とは人間の公共的問題における安定化の力だという風に理解されているとすれば(事実プラトンがその
『法律』のなかで境界づけの神であるゼウスの名を挙げて以来、法はいつもそういうものだったのだ)、政治体の運動とそこに住む市民の行動の問題がそこに出
て来る。適法性は人間の行動に限界を設けるが、行動を鼓舞しはしない。自由社会における法の偉大さとともにその不都合な点は、もっぱら何をしてはならない
かということのみを教えて、何をすべきかということは決して教えないことである」[アーレント 1981:309]。
■全体主義支配の統治
「現下の状況においては全体主義的支配はまだ他のい
ろいろの統治形式と同様に、市民の公的問題における行動をみちぴくものを必要としているけれども、厳密
に一寄って行動原理は必要としていないし、またこの原理を使ってもいない。なぜなら全体主義的支配はまさに人間の行動能力を取除こうとしているから
である。全体的テラーの条件のもとでは、恐怖さえもはやいかに行動すべきかについての助言者になり得ない。なぜならテラーは個人の行動もレくは思想を考慮
してその犠牲者を選ぶのではなく、もっぱら自然もしくは歴史の過程の客観的な必然性に従って犠牲者を選ぶからである。全体主義の条件下では恐怖はそれ以前
のいかなる時代よりもひろがっているだろう。しかし恐怖によってみちぴかれる行動が人々の恐れている危険を避けるのにもはや役立ち得ないときには、恐怖は
その実際的な効用を失っているのだ」[アーレント 1981:310]。
■観念の論理=イデオロギー
「理神論は神的な啓示を否定しはするが、観念にすぎ
ない神についての〈学問的〉な論述をするだけではなく、世界の進行を説明するために神の観念を利用する
のである。さまざまのイズムの持出す観念ーー人種主義における人種、理神論における神などーーは決してイデオロギー(イデオロジー)の取扱う対象をなすの
ではなく、ロジーという語尾は決して単に〈学問的〉論述の体系を意味するのではない。/イデオロギーとはまさに文字どおりその名の示すものなのだ。つまり
観念の論理なのである。その取扱う対象は歴史であるが、その歴史に〈観念〉という言葉がくっつけられるものとする」[アーレント 1981:311]。
■イデオロギーとしての人種概念
「イデオロギーは存在の神秘には決して興味を寄せな
い。歴史を何らかの〈自然法則〉によって説明しようとするにせよ、イデオロギーは歴史的なものであっ
て、文化の生成と滅亡、その興廃にもっぱら関心を持つ。人種主義における〈人種〉という言葉は、学問的研究の一分野としての人種についての何らかの純粋な
好奇心を意味するのではなく、歴史の運動がそれによって一つの首尾一貫した過程として説明される〈観念〉であるにすぎない」[アーレント
1981:312]。
■観念と内在的運動
「或るイデオロギーの主題をなす〈観念〉は、精神の
目で捉えられたプラトンの永遠的な本質でもカントの言う理性の調整的原理でもなく、説明の手段となって
しまっている。イデオロギーにとっては、歴史は或る観念の光を浴ぴてあらわれて来る(このことは、歴史がそれ自身歴史の動きを超越している何らかの観念的
な永遠性の姿において見られているということではないが)のではなく、観念によって計測され得るものとしてあらわれて来るのである。〈観念〉がこの新しい
役割を演ずることを可能にするものは、観念そのものの持つ〈論理〉、すなわち〈観念〉そのものの帰結であり、それを発動するのには何ら外的な要因を必要と
しない運動である。人種主義とは人種という観念そのもののなかに内在的な運動がひそんでいるという確信であり、まったく同様に理神論は神という観念そのも
ののなかに或る運動が内在しているという信念なのだ」[アーレント 1981:312]。
■強制的論理としてのイデオロギー
「哲学的思想に必然的にそなわる不確実さを捨ててイ
デオロギーとその世界観(Weltanschaung)による全体的説明を取ることの危険は、何らかの
大抵は月並な、しかも常に無批判な臆断にはまりこんでしまうということよりも、人間の思考能力に固有の自由を捨てて強制的論理を取るということである。人
間はこの強制的論理をもって、何らかの外力によって強制されるのとほとんど同じくらい乱暴に自分自身に強制を加えるのだ」[アーレント
1981:313]。
■イデオロギー的思考にある3つの全体主義的要素
1.「全体を説明しつくして見せる、という全体主義
の自負には、存在するものではなく、生成するもの、生れかつ死ぬものを説明しようとする傾向がある」
[アーレント 1981:313]。
2.「そのようなカを持つイデオロギー的思考は一切の経験から独立し、今仕方起ったばかりのことについても経験によって何か新しいことを知るということは
なくなってしまう。それ故イデオロギー的思考はわれわれが五感によって知覚する現実から解放される。そしてこの思考は、すべての知覚し得る事象のかげに隠
れて、その隠れ場所からそれらを支配している〈より真実な〉現実があると主張する。われわれがこの現実を認識することができるようになるためには第六感が
必要だというのである」[アーレント 1981:314]。
3.「イデオロギーは現実を変えるカを持たないから、経験からの思想のこの解放は或る種の論証方法によってなしとげられる。イデオロギー的思考は事実を、
機械的に受容れられた一つの前提から出発し、他のすべてのものをこの前提から演鐸する純粋に論理的な手続に従って整序する。つまり、現実の領域のなかには
どこにも存在しない首尾一貫性をもって事に当るのである」[アーレント 1981:314]。
■孤立化のちから
「孤立化した人間の集団をその鉄の錨で締めつけ、そ
して彼らにとって沙漠となってしまった世界のなかに彼らを生かしておく全体的テラーの強圧と、各個人を
して他のすべての人間からの孤独な隔絶に慣れさせる論理的演揮の自己強制力とは、テラーに支配された運動を発進させ、絶えず活動させるために、たがいに呼
応し、たがいに他を必要としあっている」[アーレント 1981:317]。
■テラーは人々を孤立させ、人々を団結させない
「テラーが思うまま支配し得るのはもっぱらたがいに
孤立さられた人々だけであること、だからすべての専制的政府の第一の関心事の一つはこの孤立を作り出す
ことだということはしばしば指摘されて来た。孤立はテラーの始まりであるとも言えよう。たしかにそれはテロルの最も肥沃な地盤であり、テラーは常に孤立の
結果なのである。この孤立は謂わぱ全体主義以前のものである。その特徴は無力ということだが、カというものは常に共同して行動する人々の、つまり
《acting in concert》(エドマンド・バーク)の所産であるという意味でそうなのだ。孤立した人々は本来カを持たない」[アーレント
1981:318]。
■人民の孤立と無力が専制の特徴[Arendt 2004:611]
「孤立と無力、すなわちそもそも行動する能力を根本
的に欠いているということは、これまでずっと専制の特徴だった。人と人とのあいだの政治的接触は専制的
統治においてはたちきられ、行動をおこないカを示す人間の能力は発揮されずに終る。しかし人間間の関係のすべてが絶たれ、人間のすべての能力が破壊される
わけではない。経験することや物を作ることや考えることの能力を含めて私生活の領域はそっくり無傷のまま残っているのだ。しかし私たちは、全体的テ
ロルの鉄のタガ(箍)がそのような私生活の存在する余地を残さず、全体主義的論理の自己強制は人間の行動能力と同じくらい確実に経験と思考の能力をも破壊
してしまうことを知っている」[アーレント 1981:318]。
Isolation and impotence, that is the fundamental inability to act at
all, have always been characteristic of tyrannies. Political contacts
between men are severed in tyrannical government and the human
capacities for action and power are frustrated. But not all contacts
between men are broken and not all human capacities destroyed. The
whole sphere of private life with the capacities for experience,
fabrication, and thought are left intact. We know that the iron band of
total terror leaves no space for such private life and that the
self-coercion of totalitarian logic destroys man's capacity for
experience and thought just as certainly as his capacity for
action.[Arendt 2004:611]
■政治領域における隔離(isolation)が、社会的交わりにおける孤立=ロンリネス(loneliness)だが、隔離と孤立は同じではない。
[Arendt 2004:611-612]
アーレントの3つの用語
1)隔離(isolation)[大久保訳:孤立]:社会生活=政治領域においておこる;私は一緒に行動できる人がいないので行動できない。
2)孤立(loneliness)[大久保訳:ロウンリネス]:人間生活全般でおこる:隔離されていなくても孤立を感じる(疎外感を感じる)ことがある。
3)孤独(solitude)[大久保訳:孤独]1人(alone)でいることを必要とする[アレント 1981:320; Arendt
2004:613]
【43】What we call isolation in the political sphere is called loneliness
in the sphere of social intercourse. Isolation and loneliness are not
the same. I can be isolated -- that is in a situation in which I cannot
act, because there is nobody who will act with me -- without being
lonely; and I can be lonely that is in a situation in which I as a
person feel myself deserted by all human companionship -- without being
isolated. Isolation is that impasse into which men are driven when the
political sphere of their lives, where they act together in the pursuit
of a common concern, is destroyed. Yet isolation, though destructive of
power and the capacity for action, not only leaves intact but is
required for all so-called productive activities of men. Man insofar as
he is homo faber tends to isolate himself with his work, that is to
leave temporarily the realm of politics. Fabrication (poiesis, the
making of things), as distinguished from action (praxis) on one hand
and sheer labor on the other, is always performed in a certain
isolation from common concerns, no matter whether the result is a piece
of craftsmanship or of art. In isolation,/ man remains in contact with
the world as the human artifice; only when the most elementary form of
human creativity, which is the capacity to add something of one's own
to the common world, is destroyed, isolation becomes
altogether unbearable. This can happen in a world whose chief values
are dictated by labor, that is where all human activities have been
transformed into laboring. Under such conditions, only the sheer effort
of labor which is the effort to keep alive is left and the relationship
with the world as a human artifice is broken. Isolated man who lost his
place in the political realm of action is deserted by the world of
things as well, if he is no longer recognized as homo faber but treated
as an animal laborans whose necessary "metabolism with nature" is of
concern to no one. Isolation then becomes loneliness. Tyranny based on
isolation generally leaves the productive capacities of man intact; a
tyranny over "laborers," however, as for instance the rule over slaves
in antiquity, would automatically be a rule over lonely, not only
isolated, men and tend to be totalitarian. [Arendt 2004:611-612]
【43】=第43パラグラフ
【43】「われわれが政治の領域で孤立と呼ぶもの
は、社会的な人間関係の領域では loneliness
と呼ばれる。孤立とロウンリネスは/同一じものではない。私は lonely
ではなくても孤立しているーーつまり、私と一緒に行動する人聞が一人もいないから行動することができない状態にいるーーかもしれない。また私は孤立してい
なくても lonely
であるーーつまり、一人の個人として自分があらゆる人間的なつきあいから疎外されているように感ずる状態にあるーーかもしれない。孤立とは、人々が共同の
利益を追って相共に行動する彼らの生活の政治的領域が破壊されたときに、この人々が追いこまれるあの袋小路のことである。けれども孤立は、力を破壊し行動
能力を破壊しはするが、いわゆる人間の生産活動なるものに手をつけないばかりか、むしろこの生産活動のために必要なのである。人間は homo
faber
(工作人)たるかぎり自分の仕事とともに孤立しようとする傾向がある。つまり一時的に政治の領域から逃れようとするのだ。一方では行動(praxis)と
も、他方では純粋な労働とも異なるものとしての製作(吉富山由ll
物を作ること)は、そこに作り出されるものが工芸品であると芸術作品であるとにかかわりなく、常に人間共通の関心事からの或る程度の孤立のなかでなしとげ
られる。孤立のなかでも人は人間の営為としての世界と接触を保っている。人間の創造性の最も根源的な形式は、共同の世界に自分自身の手による何ものかをつ
けくわえる能力であるが、この形式が破壊されたときにはじめて孤立はまったく堪えがたいものになるのである。こういうことは、その主要な価値が労働によっ
て決定される、言い換えればすべての人間活動が労働に転化されてしまっている世界では起り得る。そのような条件のもとでは純粋な労働の努力||それは命を
つな守ための努力にほかならないーーだけが残されており、人間の営為としての世界との関係は絶たれている。行動の政治的領分のなかで自分の席を失った孤立
した人聞は、もはやhomo faber としては認められず、その不可欠の「自然との代謝」のことなど誰も心配してくれないようなanimal
laboranse (辛苦する動物)として扱われるならば、物の世界からも見捨てられる。そうなると孤立は loneliness
となる。孤立の上に成立っている専制は一般に人間の生産能力を無疲のままに残しておいてくれる。ところが、たとえば古代の奴隷に対する支配のような〈辛苦
する人々〉に対する専制は自動的に、単に孤立しているだけではなく lonely
でもある人々に対する支配となり、そして全体主義的な傾向を/持つだろう」[アレント 1981:319-320]
■隔離・孤立・孤独
1)隔離(isolation)[大久保 訳:孤立]:政治領域においておこる;私は一緒に行動できる人がいないので行動できない。「アイソレーションと は、人々が共同の利益を追って相共に行動する彼らの生活の政治的領域が破壊された時に、この人々が追い込まれるあの袋小路のことである」[アレント 1981:319]。
2)孤立(loneliness)[大久 保訳:ロウンリネス]:人間生活全般にかかわる[アレント 1981:320]。隔離されていなくても孤立を感じる(疎外感を感じる)ことがある。
3)孤独(solitude)[大久保
訳:孤独]1人(alone)でいることを必要とする[アレント 1981:320; Arendt
2004:613]
■人間的孤立は最も根本的で最も絶望的な経験の一つ
【44】「【隔離】は人間生活の政治的領域に関係す
るにすぎないが、【孤立】=loneliness
は全体としての人間生活に関係する。たしかに全体主義的統治はすべての専制と同様、人間生活の公共的領域を破壊することなしには、つまり人々を【隔離】さ
せることによって彼らの政治的能力を破壊することなしには存在し得なかった。しかし全体主義的支配は、統治形式としては、この【隔離】だけでは満足せずに
私生活をも破壊するという点で前例のないものである。全体主義的支配は【孤立】= lonlyness
の上に、すなわち人間が持つ最も根本的で最も絶望的な経験の一つである、自分がこの世界にまったく属していないという経験の上に成立っている」[アレント
1981:320]【44パラグラフ:訳語は変えてあります】
While isolation concerns only the political realm of life, loneliness
concerns human life as a whole. Totalitarian government, like all
tyrannies, certainly could not exist without destroying the public
realm of life, that is,without destroying, by isolating men, their
political capacities. But totalitarian domination as a form of
government is new in that it is not content with this isolation and
destroys private life as well. It bases itself on loneliness, on the
experience of not belonging to the world at all, which is among the
most radical and desperate experiences of man[Arendt 2004:612].
■全体主義はアイソレーションのみならずロンリネスを恐怖をもって作り出す
【45】「テラーを生む一般的な地盤であり、全体主 義的統治の本質であり、そしてイデオロギーもしくは論理性にとっては、その執行者および犠牲者を作り上 げるものである lonelyness は、産業革命以来現代の大衆の宿業(しゅくごう)となっていた、そして前世紀末の帝国主義の興隆およぴ現代における政治制度および社会的伝統の崩壊ととも に鮮明になった、根を絶たれた余計者的な人間の境遇と密接に関係している。根を絶たれたというのは、他の人々によって認められ保障された席をこの世界に 持っていないという意味である。余計者ということは、全然この世界に属していないということを意味する。孤立が loneliness の予備条件であり得る(あらねばならぬ、ではない)のとまったく同様にを絶たれていることは余計者であることの予備条件であり得る。それを生んだ最近の歴 史的原因や政治のなかでそれが演ずる新しい役割を捨象してそれ自体について見れば、lonelyness は人間の条件の基本的な要求に背馳すると同時に、すべての人間の生活の根源的な経験の一つなのである」[アレント 1981:320]。
※【45】=第45パラグラフ
Loneliness, the common
ground for terror, the essence of totalitarian
government, and for ideology or logicality, the preparation of its
executioners and victims, is closely connected with uprootedness and
superfluousness which have been the curse of modern masses since the
beginning of the industrial revolution and have become acute with the
rise of imperialism at the end of the nineteenth century and the
break-down of political institutions and social traditions in our own
time. To be uprooted means to have no place in the world, recognized
and guaranteed by others; to be superfluous means not to belong to the
world at all. Uprootedness can be the preliminary condition for
superfluousness, just as isolation can (but must not) be the
preliminary condition for loneliness. Taken in itself, without
consideration of its recent historical causes and its new role in
politics, loneliness is at the same time contrary to the basic
requirements of the human condition and one of/ the fundamental
experiences of every human life. Even the experience of the materially
and sensually given world depends upon my being in contact with other
men, upon our common sense which regulates and controls all other
senses and without which each of us would be enclosed in his own
particularity of sense data which in themselves are unreliable and
treacherous. Only because we have common sense, that is only because
not one man, but men in the plural inhabit the earth, can we trust our
immediate sensual experience. Yet, we have only to remind ourselves
that one day we shall have to leave this common world which will go on
as before and for whose continuity we are superfluous in order to
realize loneliness, the experience of being abandoned by everything and
everybody.[Arendt 2004:612-613].
■孤立は孤独ではない(Loneliness is not solitude)
【46】「【孤立=loneliness】は【孤独
=solitude】ではない。孤独は一人でいることを必要とするに反して、【孤立】は他の人々と一緒
にいるときに最もはっきりとあらわれて来る。これについてはいくつ/かの感想が散見するがーーそれらは大抵、《nunquam minus solum
esse quam cum solus
esset》すなわち「彼は一人でいたときほど孤独でなかったことはなかった」、もっと精確には「彼は孤独でいたときほど【孤立して】なかったことはな
かった」というカトーの言葉( Cicero, De Re Publica, I,
17に引用されている)のように逆説的な言い方で言われているのだがーー、それらを別にすれば、【孤立】と孤独との区別を最初におこなったのはギリシャ生
れの解放奴隷で哲学者だったエピクテトスであったらしい。彼が主として興味を抱いたのは孤独でも【孤独】でもなく、絶対的自立という意味で〈独り〉
(monos)であるということだったのだから、或る意味では彼の発見は偶然だった。エピクテトスの見ているように、【孤立した】人間(eremos)
は他人に囲まれながら、彼らと接触することができず、あるいはまた彼らの敵意にさらされている。これに反して孤独な人間は独りであり、それ故「自分自身と
一緒にいることができる」。人聞は「自分自身と話す」能力を持っているからである。換言すれば、孤独においては私は「私自身のもとに」、私の自我と一緒に
おり、だから〈一者のうちにあるニ者〉である
が、それに反して【孤立】のなかでは私は実際に一者であり、他のすべてのものから見捨てられているのだ。厳密に言えばすべての思考は孤独のうちになされ、
私と私自身との対話である。しかしこの一者のうちにある二者〉の対話は、私の同胞たちの世界との接触を失うことはない。なぜなら彼らは、私がそれを相手に
思考の対話をおこなう私の自己に代表されているからである。孤独が担っている問題は、この〈一者のうちにあるニ者〉がふたたび一者ーー他のものと決して混
同されることのない不変の一者ーーとなるためには他者を必要とするということだ。私が自分のアイデンティティを確立しようとすれば、全面的に他の人々に頼
らねばならない。そして友情というものが孤独な人々にとって最大の救いであるのは、この友情が彼らの分裂を解消させ、彼らを思考の対話ーーこの対話のなか
では人間はあくまで唆昧な存在たるにとどまるーーから救い出し、アイデンティティを回復させるからである。このアイデンティティのおかげで彼らは交換不可
能な人格
の単一の声で語ることができるのだ」[アレント 1981:320-321]。
【46】
Loneliness is not solitude. Solitude requires being alone whereas
loneliness shows itself most sharply in company with others. Apart from
a few stray remarks- -- usually framed in a paradoxical mood like
Cato's statement (reported by Cicero, De Re Puhlica, I, 17): numquam
minus solum esse quam cum solus esset, "never was he less alone than
when he was alone," or, rather, "never was he less lonely than when he
was in solitude"-it seems that Epictetus, the emancipated slave
philosopher of Greek origin, was the first to distinguish between
loneliness and solitude. His discovery, in a way, was accidental, his
chief interest being neither solitude nor loneliness, but being alone
(monos) in the sense of absolute independence. As Epictetus sees it
(Dissertationes, Book 3, chapter 13) the lonely man (eremos) finds
himself surrounded by others with whom he cannot establish contact or
to whose hostility he is exposed. The solitary man, on the contrary, is
alone and therefore "can be together with himself" since men have the
capacity of "talking with themselves." In solitude, in other words, I
am "by myself," together with my self, and therefore two-in-one,
whereas in loneliness I am actually one, deserted by all others. All
thinking, strictly speaking, is done in solitude and is a dialogue
between me and myself; but this dialogue of the two-in-one does not
lose contact with the world of my fellow-men because they are
represented in the self with whom I lead the dialogue of thought. The
problem of solitude is that this two-in-one needs the others in order
to become one again: one unchangeable individual whose identity can
never be mistaken for that of any other. For the confirmation of my
identity I depend entirely upon other people; and it is the great
saving grace of companionship for solitary men that it makes them
"whole" again, saves them from the dialogue of thought/ in which one
remains always equivocal, restores the identity which makes them speak
with the single voice of one unexchangeable person [Arendt
2004:613-614].
■孤独が孤立になることもある
「孤独 solitude が【孤立 lonelyness】になることもある。そうなるのは、私が完全に自分だけを頼りにするようになって、その結果自分の自己から打捨てられているときであ る。孤独な人々には、彼らを二重性と唆味性と疑惑から救ってくれる友情という救済をもはや見出し得ないときにはいつも【孤立 lonelyness】におちいる危険があった。歴史的に言えば、この危険が増大して人々に注目され、歴史に記録されるほどになったのは、ようやく十九世 紀になってからだったようだ。孤独というものを一つの生き方とし、仕事をするための条件としているのは哲学者だけだが、その哲学者/たちがもはや「哲学は 少数者のためにのみ存在する」という事実に満足できなくなり、誰も自分たちを〈理解〉してくれないと主張しはじめたときに、この危険ははっきりとあらわれ て来た。この間の事情をよく物語っているのはへーゲルの臨終の際の或る逸話であるが、彼以前のいかなる大哲学者についてもこういう逸話が語られることはま ずないだろう。「ただ一人を除いて私を理解してくれたものはな かった。そしてその一人も私を誤解していた」と彼は言ったと言うのだ」[アレント 1981:321-322]。
Solitude. can become
loneliness; this happens when all by myself I am
deserted by my own self. Solitary men have always been in danger of
loneliness, when they can no longer find the redeeming grace of
companionship to save them from duality and equivocality and doubt.
Historically, it seems as though this danger became sufficiently great
to be noticed by others and recorded by history only in the nineteenth
century. It showed itself clearly when philosophers, for whom alone
solitude is a way of life and a condition of work, were no longer
content with the fact that "philosophy is only for the few" and began
to insist that nobody "understands" them. Characteristic in this
respect is the anecdote reported from Hegel's deathbed which hardly
could have been told of any great philosopher before him: "Nobody has
understood me except one; and he also misunderstood."[Arendt 2004:614].
■孤立した人間が自分自身を発見し、孤独の対話的思考をはじめる
[T]here is always the
chance that a lonely man finds himself and starts
the thinking dialogue of solitude. This seems to have happened to
Nietzsche in Sils Maria
when he conceived Zarathustra. In two poems ("Sils Maria" and "Aus
hohen Bergen") he tells of the empty expectation and the yearning
waiting of the lonely until suddenly <'"um Mittag war's da wurde
Eins tu Zwei ... / Nun feiern wir, vereinten Siegs gewiss, / das Fest
der Feste; / Freund Zarathustra kam, der Gast der Gaste!" ("Noon was,
when One became Two ... Certain of united victory we celebrate the
feast of feasts; friend Zarathustra came, the guest of guests.")
[Arendt 2004:614].
■孤立の自己喪失
「【孤立 lonelyness】をこれほど堪えがたいものにするのは自己喪失ということである。自己は孤独のなかで現実化され得るが、そのアイデンティティを擁認 してくれるのは、われわれを信頼してくれ、そしてこちらからも信頼することができる同輩たちの存在だけなのだ。【孤立 lonely】な状況においては、人間は自分の思考の相手である自分自身への信頼と、世界へのあの根本的な信頼というものを失う。人間が経験をするために 必要なのはこの信頼なのだ。自己と世界が、思考と経験をおこなう能力が、ここでは一挙に失われてしまうのである」[アレント 1981:322]。
What makes loneliness
so unbearable is the loss of one's own self which
can be realized in solitude, but confirmed in its identity only by the
trusting and trustworthy company of my equals. In this situation, man
loses trust in himself as the partner of his thoughts and that
elementary confidence in the world which is necessary to make
experiences at all. Self and world, capacity for thought and experience
are lost at the same time [Arendt 2004:614].
■世界の自明性の喪失が、人をして思考の経路を開かせしめる
「【孤立 lonelyness】の条件のもとでは、自明性というものはもはや単なる悟性の手段ではなくなり、生産的になりはじめ、それ自身の〈思考〉の経路を展開 させはじめる。ど/う見ても何らの逃げ道もない厳密な自明的論理性によって特徴づけられる思考過程が【孤立 lonelyness】と何らかの関係を持つことは、「人間が孤独であることはよくない」という聖書の言葉についてのあまり知られていない註解のなかで、 ルターがつとに指摘していることである(孤独と【孤立 lonelyness】について彼自身がなめた経験はおそらく何びとにも劣らぬものだったろうし、彼は一度「人間には彼が信頼することができる存在が必要 だから、神が存在しなければならない」とまで言った)。【孤立した lonly】人間は「いつも次から次へと演鐸をおこない、すべてを最も悪く考える」とルターは言っている。全体主義運動の有名な極端主義(エクストレミズ ム)は、真のラディカリズムと何らかの関係があるどころか、実はこの「すべてを最も悪く考えること」、常に最悪の結論に達するこの演鐸の過程にほかならな いのである」[アレント 1981:323]。
Under the conditions of
loneliness, therefore, the self-evident is no
longer just a means of the intellect and begins to be productive, to
develop its own lines of "thought." That thought processes
characterized by strict self-evident logicality, from which apparently
there is no escape, have some connection with loneliness was once
noticed by Luther (whose experiences in the phenomena of solitude and
loneliness probably were second to no one's and who once dared to say
that "there must be a God because man needs one being whom he can
trust") in a little known remark on the Bible text "it is not good that
man should be alone": A lonely man, says Luther, "always deduces one
thing from the other and thinks everything to the worst." The famous
extremism of totalitarian movements, far from having anything to do
with true radicalism, consists indeed in this "thinking everything to
the worst," in this deducing process which always arrives at the worst
possible conclusions. [Arendt 2004:615].
■【孤立 lonelyness】が日常経験となること
「非全体主義の世界のなかで人々に全体主義支配を受
容れさせてしまうものは、普通はたとえば老齢というような或る例外的な社会条件のなかで人々の嘗める限
界的経験だった【孤立 lonelyness】が、現代の絶えず増大する大衆の日常的経験となってしまったという事実である」[アレント
1981:323]。
■孤独にさせず【孤立 lonelyness】させる
「しかも全体主義的支配は、独房に監禁するという極
端な場合を除いて決して人間を一人にしておこうとはしない。人間と人間とのあいだの一切の空間をなく
し、人間と人間とを押しつけることで、孤立の持つ生産的な可能性すらも無に帰せられてしまう。【孤立 lonelyness】
のなかでは、すべての過程の出発点にあった最初の前提を取逃してしまったら完全に破滅してしまうことがわかっているのだが、そのような【孤立
lonelyness】の論理の働きを教え、それを讃美することによって、【孤立
lonelyness】が孤独に変り論理が思想に変るほんのわずかの可能性も消し去られてしまう。このやりかたを専制のやりかたと比較すると、砂漠そのも
のを動かし、無人の地球のありとあらゆる部分を蔽いかねない砂嵐をまきおこす方法がこれで見つかったというように見える」[アレント
1981:323]。
「ちょうど恐怖と、恐怖を生みだす無/力とが反政治的な原理であり、政治的行動とは両立しない状況に人間を投げこむのと同様に、【孤立
lonelyness】、そこから最悪のものを論理的=イデオロギー的に演鐸することは、反社会的状況を意味し、人間の共同生活すべてを破壊する原理を秘
めている。けれども組織された【孤立
lonelyness】は、一人の人間の専制的なほしいままの意志に支配されている人々の組織されていない無力よりもはるかに危険なのだ」[アレント
1981:323-324]。
■始まりとしての人間
「歴史におけるすべての終りは必然的に新しい始まり を内含するという真理も残る。この始まりは約束であり、終りがもたらし得る唯一の〈メッセージ〉なので ある。始まりは、それが歴史的事件になってしまわぬうちは、人間の最高の能力なのだ。政治的には始まりは人間の自由と同一のものである。《Initium ut esset homo creatus est》ーー「始まりが為されんために人間は創られた」とアウグスティヌスは言った。この始まりは一人々々の人間の誕生ということによって保障されてい る。始まりとは実は一人々々の人間なのだ」[アレント 1981:323-324]。
[T]here remains also
the truth that every end in history necessarily
contains a new beginning; this beginning is the promise, the only
"message" which the end can ever produce. Beginning, before it becomes
a historical event, is the supreme capacity of man; politically, it is
identical with man's freedom. Initium ut esset homo creatus est-" that
a beginning be made man was created" said Augustine. This beginning is
guaranteed by each new birth; it is indeed every man.(De Civitale Dei,
Book 12, chapter 20.) [Arendt 2004:616].
■文献