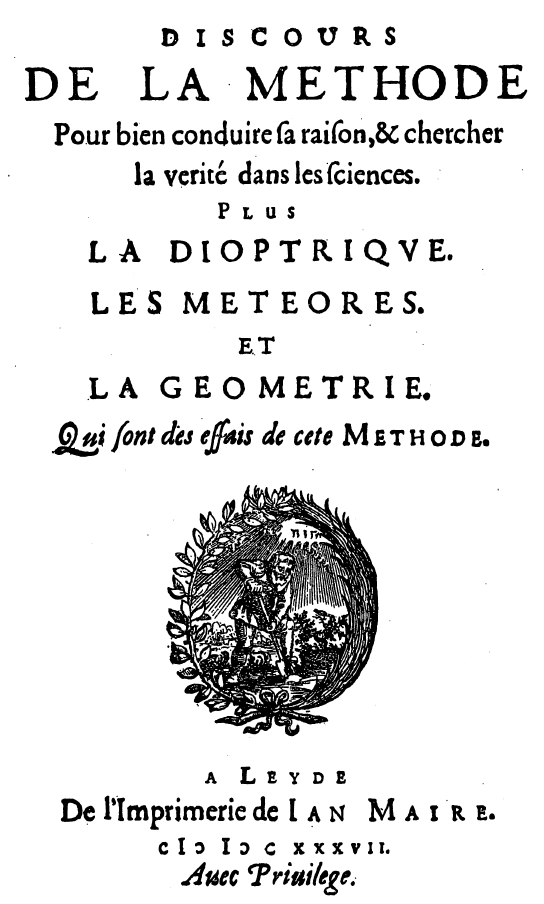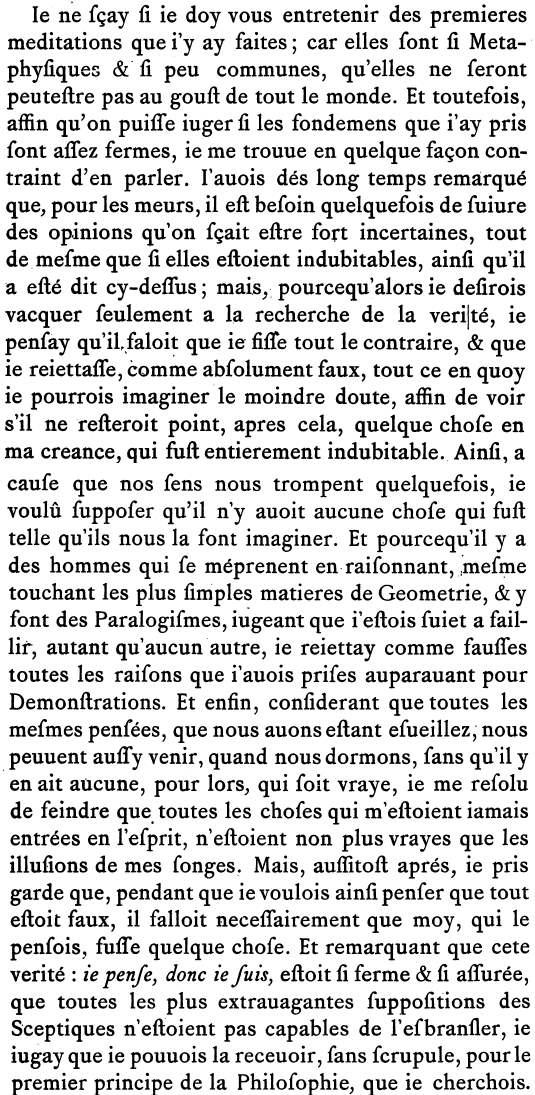私の(マイ)音読ブーム
世はまさに音読ブーム。年寄り――失礼!もとい高齢 者――に音読が脳の活力を回復させ老化を防ぐと福音を説く「脳研究者」たち。保守文化論と見まがうば かりの『声に出してよむ○○』シリーズの盛況。テレビを点ければパソコンをつかった文章推敲講座である。これらは様々な「営業」活動に直結していることは 明らかだ。音読すれば頭脳明晰に、人間関係は円滑に、はたまた高収入も夢ではない!という勢いである。まさに音読バイブル商法といっても過言ではない。し かし、かつて国語の授業で、みんなの前で音読するという一種の拷問を受けた私にとっては、なんでこんなことで日本中が大騒ぎするのか一向にわからない。人 間は音読から解放され〈黙読〉という技法により読書量を増大させることができた。このような人類の栄光の歴史は私自身の経験でもある。音読など糞食らえと いう心境だ。
しかし他方で私は音読(=朗読)という技法により福 音を受けた一人でもある。それは学会発表を原稿にもとづいて朗読することにより、最近よく友人からプ レゼンが巧くなったと褒められるようになったからである。音読するようになった動機は、十分に練られた論理構成を誤解されることなく伝えるには原稿の朗読 以外にはありえないという論理的必然性に基づいたものだ。もちろん最初は「棒読み」モードで不評だった。おまけに書き言葉を音読すれば、耳から入ると分か りにくい衒学的漢語や同音異義語によって意味不明になりやすい。改善の第一歩は(後から考えれば自明の理なのだが)音読原稿は書き言葉の論文原稿とは全く 異なった論理構成により受け手に理解されることを前提に書かれることにある。きちんとした論証の手続きを踏むことは言うまでもないが、リニアーな時間的秩 序の中で自分の議論を理解してもらうには、思い切った技法――論証より論点を先取提示したり、全体の主張を明示したりする隠喩を冒頭に連発すること――が 功を奏する。また、事前の音読リハーサルを繰り返しおこない文章を磨くことは、書くための論文とは多少異なった技法である。
私は音読(=朗読)に〈ハマる〉ことで、これまで人 を騙(だま)くらかす技法と浅薄にも理解してきた〈修辞法〉が、実は〈言葉によって人を動かす技芸〉 であったことを思い出した。修辞に精通することは、さまざまな考え方に到達するための言語的技法を直接体験することなのだ。学会発表の音読は弁論の一種だ から、修辞に熟達することはプレゼン能力向上に直結する。
右のような私の経験は、言語や文学に精通している本 誌読者には稚気に映るかも知れまい。そうであるなら、日本語学研究者の皆様には昨今の音読ブームの表 層的事象からもう一歩進んで発言していただきたいものだ。つまりお手軽な健康欲求や自己陶酔的日本文化という背景のもとで〈音読にふさわしい文章〉の消費 に、このブームを終わせてはならないと。音読という技法のインフラストラクチャーとしての文章生産を読者自身が取り戻し、その基盤になる修辞法に熟達する ように時勢(トレンド)を展開させることではないだろうか。
学会発表における音読は、ある一定の時間を演者の声 と論理で独占的に埋め尽くすことだ。このことは表層的な現今の音読ブームがまさに表に出したがらない 〈深層的機能〉があることを示唆する。それは〈声〉がもつ根源的な暴力的支配の機能である。質疑応答までは決して聴衆に邪魔をさせない独占的な時空間にお いて修辞は内容以上の影響力を人びとに与えることができる。歴史上の独裁者が欲しいままにしてきた雄弁だけによる〈真空の支配〉の恐ろしさに気づくことで もある。モノロジックかつモノローグは最終的に必ず破綻する。(私の)マイ・ブームとしての音読は〈声を出すこと〉の楽しさとともに、〈声がもつ根源的暴 力〉についても我々に教えてくれた。
出典: ぶらり日本語、『日本語学』2004年10月号
【課題】
1.デカルトの「方法序説」(三宅徳嘉・小池健男 訳、『デカルト著作集』第1巻、Pp.38-45、白水社、1973年)第4部、ヴィトゲンシュタイン 「はじめに」(丘沢静也訳『哲学探究』Pp.3-5、2013年)、魚津郁夫「はじめに」(出典別記)、みんなで音読してみよう!
2.皆さんが聞いた、デカルトとヴィトゲンシュタイ ンのそれぞれの話の中で、いったい何が最も印象に残ったでしょうか?そのことをめぐって、どうして印象 に残ったのか? その経験(肯定的なものでも否定的なものでもかまいません)その経験を、各グループでまとめてみましょう。
3.各グループでは、司会者と報告書(レポーター)
を互選して、役割分担してください。報告者は、総合討論の時に報告してください。
《デカルトのテキスト》
Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditations que j'y ai faites; car elles sont si métaphysiques et si peu communes, qu'elles ne seront peut-être pas au goût de tout le monde. Et toutefois, afin qu'on puisse juger si les fondements que j'ai pris sont assez fermes, je me trouve en quelque façon contraint d'en parler. J'avais dès longtemps remarqué que, pour les mœurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu'on sait fort incertaines, tout de même que si elles étaient indubitables, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; mais, parce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensai qu'il fallait que je fisse tout le contraire, et que je rejetasse, comme absolument faux, tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute afin de voir s'il ne resterait point, après cela, quelque chose en ma créance, qui fût entièrement indubitable. Ainsi, à cause que nos sens nous trompent quelquefois, je voulus supposer qu'il n'y avait aucune chose qui fût telle qu'ils nous la font imaginer. Et parce qu'il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant, même touchant les plus simples matières de géométrie, et y font des paralogismes, jugeant que j'étais sujet à faillir, autant qu'aucun autre, je rejetai comme fausses toutes les raisons que j'avais prises auparavant pour démonstrations. Et enfin, considérant que toutes les mêmes pensées, que nous avons étant éveillés, nous peuvent aussi venir, quand nous dormons, sans qu'il y en ait aucune, pour lors, qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais, aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité :je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de la philosophie que je cherchais.
その地でおこなった最初の省察をお話しすべきかどう かはわかりません。というのもこの省察は〈形而上学〉で扱うようなひどく現実ばなれのした、ありふれて いないものなので、おそらくみなさんの好みにあわないでしょうから。ところが、私の選んだ基礎がじゅうぶんしっかりしているかどうかを判断していただける ためには、どうしてもそれをお話ししなければならない、いわばそういうはめに陥っているのに気がついたのです。だいぶまえから私は、生き方については、ひ どく不確かだとわかっている意見でも、疑う余地のないものだったばあいとまったく同じように、それに従う必要がときにはあると気づいていました。これはま えにも申しあげたとおりです。しかし、そのころはただひたすら真理の探求に打ち込みたいと願っていましたので、その正反対のことをやり、ほんの少しでも疑 いをふくむと想像されるおそれのあるものはみな、ぜったいにまちがっているとしてしりぞけるのが必要だと考えました。どこにも疑いをさしはさむ余地のない ものが、そのあとで、何か私の信念に残りはしないかを見ようとして、そう考えたのです。たとえば私たちの感覚はときどき私たちを欺くので、どんなものでも 感覚が私たちに想像させるとおりのものはないと私は想定しようと思ったのです。そして〈幾何学〉のどんなに単純な素材を扱うときにも、推論をするうちに勘 ちがいをし、〈誤謬推理〉をする人がいるのですから、私もほかのどんな人とも同じだけまちがいを犯しやすいのだと判断して、それ以前に〈論証〉とみなして いた論拠をどれもこれもまちがったものとしてしりぞけました。そして最後に、私たちが目を覚ましていていだく同じ考えがどれもみな眠っているときにそのと きには何ひとつほんとうのものはないということを考えめぐらして、私は、やってくることもありうるが、それまでに自分の精神にはいりこんでいたものはみ な、私の夢のまぼろし以上にほんとうではないと仮想することに決めました。しかし、すぐあとで、そんなふうにどれもまちがいだと考えたいと思っているあい だにも、そう考えている自分は何かであることがどうしても必要だということに気づきました。そしてこの「私は考える、だから私は有る」という真理はいかに もしっかりしていて、保証つきであるため、〈懐疑論者たち〉のどんなに並みはずれた想定を残らず使ってもこれをゆるがすことができないのを見てとって、私 はこの真理を、求めていた〈哲学〉の第一の原理として、疑惑なしに受け入れることができると判断しました。
1637年の《方法序説》のテキスト部分(第4部第 一パラグラフ、J.Vrin,社のDiscours de la méthode / René Descartes ; texte et commentaire par Etienne Gilsonによる)
《ヴィトゲンシュタインのテキスト》
もともと進歩なんてやつは、実際より、うんとりっぱに見えるものなんです。――ネストロイ
はじめに
この本で発表する考えは、この16年間、私がやって きた哲学探究の結果である。たくさんのテーマについて考えた。意味の概念、理解の概念、文の概念、論 理の概念、数学の基礎、意識の状態などなど。これらについての考えはすべて、コメントとして、短いパラグラフとして書きつけた。おなじテーマについて、コ メントが長めにつながっていることもあれば、ひとつの領域から別の領域へ突然ジャンプしていることもある。――最初は、すべてを1冊の本にまとめてしまう つもりだった。どんな形の本にするか、いろんな時期にいろいろ思い描いた。しかし基本方針にゆらぎはなく、考えというものは、ひとつのテーマから別のテー マへ、自然に破綻なくつながって、すすんでいくべきものだと思っていた。
16年間の成果をまとめようとしては何度か失敗し て、気がついた。この方針では絶対にうまくいかないだろう。もしも、私の考えたことを、自然の傾向に逆 らって、ひとつの方向に無理やりすすめていこうとすれば、私が書くことのできた最上のものでさえ、哲学的なコメントにとどまるだけではないか。そのうち私 の考えも麻痺してしまうのではないか。――そしてそれは、もちろん探究そのものの性質と関係があった。つまり探究をはじめれば、どうしても、ひろい思考領 域をあちこちあらゆる方向に旅して回らざるをえなくなるのだから。――この本の哲学的なコメントは、いわば、長くて錯綜したその旅で描かれた、たくさんの 風景スケッチのようなものである。
おなじ場所、またはほとんどおなじ場所について、い ろんな方向からいつもあらためて言及され、つねに新しいスケッチが描かれる。それらのうち数多くのス ケッチは、描きそこないであったり、特徴のないものであったりで、へっぽこ画家のあらゆる欠点をそなえていた。できそこないのスケッチを捨てると、なんと かましなスケッチが何枚か残ったので、ともかくそれらの配置を考えたり、なんども切りそろえたりして、1枚の風景画に見えるようにした。――というわけ で、この本はじつはアルバムにすぎない。
生きているあいだに自分の仕事を本にすることは、つ い最近まで、じつはあきらめていた。しかし、本にしたいという思いが、ときどき頭をもたげてきた。そ のおもな理由は、講義や口述ノートやディスカッションで私が伝えた仕事の成果が、さまざまに誤解され、程度の差はあれ薄められたり、切り刻まれたまま、流 布しているのを見聞きするようになったからである。おかげで私は自分の考えをきちんと伝えたいと思うようになり、その気持ちを静めるのに苦労した。
4年前に、私の最初の本(『論理哲学論考』)を読み なおし、『論考」の考えを説明する機会があった。そのとき突然ひらめいた。以前の『論考』の考えと新 しい考えとをひとつの本として出すべきではないか。新しい考えは、以前の私の考え方と対比され、それを背景にしてはじめて、正しい光のもとでながめられる のではないか。
というのも16年前にふたたび哲学と取り組みはじめ てから、私は、あの最初の本に書きつけたことに、たいへんなまちがいがあることに気づかざるをえな かったからだ。まちがいに気づいたのは、フランク・ラムジーが私のアイデアを批判してくれたおかげである。――その批判にどれくらい助けられたのか、私自 身はほとんど判断することができないが――ラムジーとは、彼の死ぬ前の2年間、『論考』のアイデアについて何度も何度も議論を重ねたものだ。ラムジーはい つも強力で確かな批判をしてくれたが、ラムジー以上に私を助けてくれたのが、ここケンブリッジ大学の教員、P・スラッファさんである。長年にわたって、た えず『論考』の考えを批判してくれた。その批判に刺激されて、この本のなかでもっとも実り豊かなアイデアが生まれたのである。
私がこの本で書いていることは、ほかの人がいま書い ていることと重なるだろうが、その理由は、ひとつだけではない。――私のコメントで、私のものだとい うスタンプが押されていないものについては、――これからも私のオリジナルだと主張するつもりはない。
私の考えたことをここに公表するわけだが、あまり自 信がない。私の仕事はみすぼらしく、この時代は暗い。誰かの脳に光を投げかけたいのだが、それは不可 能ではないにしても、もちろん、なかなかむずかしい。
私の書いたものによって、ほかの人が考えなくてすむ ようになることは望まない。できることなら、読んだ人が刺激され、自分の頭で考えるようになってほし い。
いい本をつくりたかった。けれどもそうならなかっ
た。だが私には手を入れる時間が、もうない。
1945年1月、ケンブリッジ ルードヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン
___________________
《魚津郁夫のテキスト》
まえがき
現代アメリカ思想を代表し、かつその根幹を形成する 思想はプラグマティズムである。それは19世紀後半にはじまって、20世紀に集大成され、21世紀へ とひきつがれた。本書はこうしたプラグマティズムの展開をあとづけたものである。「プラグマティズム」という名称は、現代の若者にはあまりなじみがなく、 たとえばコンピューター関係の用語に間違えられることも多いといった時勢のもとではあるが、あえてタイトルを「プラグマティズムの思想」とした。
19世紀前半に活躍したフランスの政治思想家A・ト クヴィルは、『アメリカの民主政治』(1835-1940年)のなかで次のような指摘をしている。 「文明世界のうちでアメリカ合衆国ほど[いわゆる体系的な]哲学が人びとの心を少ししか占めていない国はない。……しかし彼らのほとんどすべてが、ある種 の哲学的方法を身につけている。」(第2巻第1部第1章)そしてその哲学的方法の特徴は、(1)体系を排すること、(2)眼前の事実を重視すること、 (3)物事の理由を権威にたよらずに独力で探究し、結果をめざして前進すること、(4)定式をとおして物事の本質を見ぬくことである、と。
本書がとりあげるプラグマティズムが誕生するのは 19世紀後半であるから、トクヴィルの指摘はそれ以前の時代にかんするものである。しかしそれは、現代 もふくめてアメリカ思想全体の特徴をいいあてている。
アメリカ合衆国は世界各地からの移民によって開拓さ れ発展した国である。そして開拓がいかに厳しい条件のもとでの苛酷な作業であったかは、1620年ア メリカ東岸のプリマスに上陸したピルグリム・ファーザーズの例がしめしている。開拓民にとっては、どんな抽象的な思想も、それにもとづいて行動した結果が どうであるかという観点からとらえられることになる。したがってトクヴィルが指摘するように、体系的、伝統的な観念にしばられることなく、眼前の事実を直 視し、結果をめざして前進し、定式をとおして環境の本質を見ぬくことによって環境を変えていくことが、人びとの哲学的方法(考えかた)となるのは当然とい わなければならない。
アメリカ合衆国における世界各地からの移民の状況に ついては第1章で概説したが、ピルグリムズの入植後わずか20年をへた1640年代には、現在ニュー ヨークとよばれている地域で18もの異なる言語が話されていたという。このことは人種の多様化が急速にすすみ、相互の寛容が増大したことを意味している。 このようなさまざまな人種の移民によって形成された社会では、ひとつの原理によって統一する一元論ではなく、相互に異なった価値観をみとめあう多元主義的 傾向がうまれる。そしてこれは現代にまでつづくアメリカの思想の伝統である。
たとえばウィリアム・ジェイムズは、たとえどのよう な観念でも、それを信じることがその人に宗教的な慰めをあたえるならば、「その限りにおいて」これを 真理としてみとめなければならないという真理観をとなえた。また最近ではリチャード・ローティーが、多元主義の立場から、それぞれの人種が自分たちの文化 を中心に生活しながら合意」をめざして「会話」をつづけるべきことを説いている。
しかし本書があきらかにするように、プラグマティズ ムにはC・S・パース以来の「可謬主義」が現在にいたるまで伝統としてうけつがれている。それは認識 能力に限りある私たち人間は誤謬をおかす可能性をつねにもっているという主張である。
そしてこうした可謬主義は、ほとんどすべてのプラグ マテイストにおいて、次のような「実在仮説」によってささえられている。すなわち、現実の問題を解決 するためにくりかえし「探究」をかさねることによって、究極において、実在という「外部の力によってひとつのおなじ結論にみちびかれる」という信念であ る。こうした実在仮説は、探究の前提であって、探究によって証明することはできない。それは超越的存在にたいする信仰ともいうべきものである。プラグマ ティズムの実際的な考えかたが、こうした信仰にささえられていることは興味深い事柄である。
ただしローティーの場合、とくに実在仮説はとらない けれども、その反面、より徹底した「反体系主義」をつらぬいていることは注目に値する。哲学者は、実 際生活とは無関係な専門的な論争にあけくれる「退廃した専門主義」におちいることなしに、「人びとの心を、自分たちの周囲の生活にたいしてより鋭敏にす る」という役割をになうべきだ、とローティーは主張する。トクヴィルの指摘以来150年以上経過した現在、アメリカ人の哲学的方法の特徴のひとつである 「反体系主義」は、いまなお健在であるといえよう。
しかしながら、相互に違った価値観をみとめあうアメ リカ思想の多元主義的な伝統は、2001年ニューヨークでおこったいわゆる9・11事件以降、急速に うすれつつあるように思われる。あるいは、アメリカ合衆国の全世界におよぶ支配の根もとにある思想がそうした伝統から遠ざかりつつあるゆえに、それにたい する反撃がおこり、さらに再反撃がくわえられる、といった悪夢の連鎖が、多元主義的な考え方の衰退を加速させつつある、というべきかも知れない。
いずれにしても、私たちはアメリカ思想の伝統から多
くを学ぶとともに、アメリカ合衆国がもう一度アメリカ思想の源流に立ちかえることを強く望みたい。
2005年11月 魚津郁夫(うおず・いくお)
『プラグマティズムの思想』ちくま文庫、Pp.11 -15、筑摩書房、2006年