Der Liebesbegriff bei Augustin : Versuch einer philosophischen Interpretation
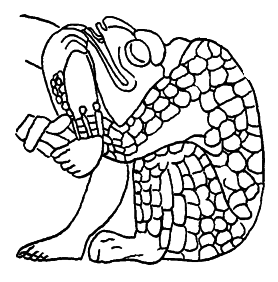
ハンナ・アーレント「アウグスティヌスの愛の概念」ノート
Der Liebesbegriff bei Augustin : Versuch einer philosophischen Interpretation
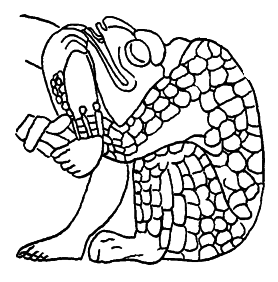
池田光穂
ハンナ・アーレント「アウグスティヌスの愛の概念」 (または「アウグスチヌスの愛の概念[Der Liebesbegriff bei Augustin : Versuch einer philosophischen Interpretation]」) ノート
| 0 |
はじめに |
1 |
この研究の一つの眼目は、アウグスティ
ヌス哲学においてたいていは矛盾するものとみなされている種々の思想や理論の並存した状況を、正当に評価すること
である。そのためにわたしは、主題が示す領域を三つの章に分けつつ、愛の問題が決定的な役割を果たす三つの概念上の関係軸を明らかにしたいと考える。それ
によってこの研究は、とくに隣人愛の意味および意義を絶えず問いただしながら、これら三つの関係軸をそれぞれ浮き彫りにするであろう。キリスト教の戒めで
ある隣人愛は、信仰によって把捉される神への愛、ならびにそこから生じる自己そのものへの新しい態度に依拠している。したがって最初の二つの章はそれぞ
れ、神および自己自身を愛するとはいったいどのようなことなのか、という問いから始められねばならないであろう(pp.1-2)。 |
| 1 |
1.欲求としての愛 Amor qua
appetitus |
13 |
・アウグスティヌスが聖書と教会の権威
に教義学的に拘束されているという見方に対して、われわれの分析は、それとはおよそ異なった立場に立っている。 ・「この人々は……「あなたは、自分にしてもらいたくないことを他人にしてはならない」という教えは民族の相違によっても変わることが決してあり得ないこ と を認識していない。この教えが神の愛に結びつけられる時、すべての悪念は消え去り、またそれが隣人愛に結びつけられる時、すべての罪業はなくなるのであ る」『キリスト教の教え』3-14-22 |
| 1.1
欲求(appetitus)の基本構造 |
13 |
・こうして「愛(アモール)」の求める
「善きもの」とは、失われることの決してあり得ないものとして規定される(p.18)。 |
|
| 1.2
愛(caritas)と欲求(cupiditas) |
24 |
・わたしは、自己を探求し始めるやいな
や、もはやこの世界に帰属することをやめ——この点についてはこれまでの議論から明らかである——、すでに神に帰属し
ているということである(p.31)。 ・最高善(summum bonum)p.34 ・『ヨハネ福音書講解説教』38篇・16における、時間の「非存在」non esse に関するかなり長い議論の後に、次のような言葉が見られる。「したがって、あなた自身が存在するために、時間を超越しなさい」。それ故に、自己を超越する とは、まさしく時間を超え出ることにほかならない。われわれが時間を忘れるならば、われわれは自らが死すべき定めにあることを忘れ、また自己自身をも忘れ て、永遠を想うのである(pp.36-37)。 ・神への愛と自己への愛とは共存するのであって、そこにはみじんの対立もない。人間は神を愛することによって自己を愛し、神に帰属することへの憧憬を通じ て、未来の存在としての自己を愛するのである。それはつまるところ、永遠の存在になるものとして自己を愛することを意味する(p.39)。 |
|
| 1.3 秩序づけられた愛(
Ordinata dilectio) |
48 |
・愛(dilectio)p.50
——愛にはいくつかの語彙の違いがある ・世界から、すなわち、絶えず同時に世界と自己自身への囚われから自己を解放しようとしない者は、もはやこの客観性を持つとは見なされない。自己自身の忘 却は、ここでは際立って現実的なものとなる。ここではかの擬似キリスト教的な自己否定が、実現されているといえよう(p.55)。 ・われわれは「隣人愛」dilectio proximi の考察をすすめていく中で、もはや「欲求」ではない一つの愛(リーベ:ドイツ語)に逢着したのである。アウグスティヌスも、この愛をこの「隣人愛」の関連 に引きつけて考察しているが、彼はこの愛を第二義的であると説明し、すべての愛が、「使用」か「享受」か、の二者択一の前に立たされると述べている。しか しながら、アウグスティヌスのこうした規定にもかかわらず、この関連では「愛(ディレクティオ)」の意味を理解することは不可能である。つまり、「愛 (ディレクティオ)」がいかなる起源を有するのかが、これでは理解できないのである(p.55)。 ・「隣人愛」の議論においては、いつも根本的に異質な愛の概念が描き上げられるのであり、以下においてわれわれはその問題について見ていきたいと思う (p.55)。 |
|
| 1.4 付論01 |
56 |
・同一の自由概念——つまり、「強要さ
れることなく」(『ニコマコス倫理学』1110a I
を参照)——から出発するアリストテレスは、すでに「行為」のこの問題性を指摘している。しかもアリストテレスは、すでに『ニコマコス倫理学』1110a
I において、明らかに厳密に自らの立場を規定することなく、「混合的な性質の活動」という用語を使用している(pp.58-59)。 |
|
| 1.5 付論02 |
58 |
||
| 2 |
2.創造者(Creator)と被造者
(creatura) |
61 |
・われわれは、永遠から立ち帰って考察
した時の秩序づけに基づくことによって、「欲求」appetitus から生み出される「自己愛」amor sui
を二次的なものと見なしたのである。「欲求」とその構造に即してみるならば、「自己愛」と「隣人愛」dilectio proximi
とは、やがてはとび超えられていくはずのもの、すなわち、それら自身の根源的関係性がさらに追求されていくのではなく、それらはむしろ事後になって実現さ
れる「最高善」summum bonum の視点から整序されていくものとなる。「自己愛」は、世界を秩序づけるために方向性を暗示する(p.61)。 |
| 2.1
被造者の起源(Ursprung)としての創造者 |
61 |
・「われわれの意志によって生起する」
とは、「世界への愛」によって構成されることを意味する。この「世界への愛」によって初めて、「神に造られたもの」
である世界は、人間にとって自明な「住まい/故郷」Heimat
となる。人間の生はそれが生み落とされた被造世界の所与性の中で営まれていくが、その人間の生それ自身が、この神の「造られたもの」fabricaを「世
界」mundusへと作り上げていくのである。「世界を愛する行為」diligere mundrum
は、世界をまさに世界化していく行為である。この行為は、「世界に帰属する」de mundo
存在に基礎づけられた行為であるといえよう(『ヨハネ福音書講解説教』三八篇・4 を参照)(p.82)。 ・人間が「被造的存在」creatum esse であるということは、この世界との関係では「被造者」にとって二重の意味を持っている。第一の意味は、「被造者」は世界の中に造られた者であり、したがっ て「世界の後に」吉弘自g 含自存在しているということである。この「後に」post ということに世界への被造者の依存性が基礎づけられており、それは被造者が世界化される可能性を含意しているといえよう(p.86)。 ・存在は、始まりにおいてあったと同様に、終わりにおいても存在する。人間の生が向かっていく方位は、自らの起源と同一なのである(p.98)。 ・今やわれわれは、「終極」finis の二重性の意味を十分に理解できる段階に到達した、アウグスティヌスは、「自ら終極に立ち戻る」se referre ad finem との表現に関して「存在への傾向」に言及しつつ、そこでは「終極」が同時に起源でもあるという意味で、包摂的「存在」、つまり純然たる永遠性が示唆されて いると理解している(p.98)。 |
|
| 2.2 愛(caritas)と欲求(cupiditas) | 101 |
・「神の恩寵」は、「被造者」を世界か
ら導き出すのであり、それこそ「世界からの選び」である。この選びの恩寵において「被造者」は、世界に帰属するので
はなく、神に帰属するものとして自己を理解する。まさにここに、つまり、この「愛(ディレクティオ)」のこの機能において、われわれは、いま一度さらに深
く、被造性の存在の開示において死が果たした決定的な役割を把握することができる。死は、神以外に人々を世界から取り除くことのできる唯一のものであり、
したがって「世界からの選び」を指し示している(p.104)。 ・「世界からの選び」は、「神に従って生きる」可能性を賦与する。「愛」の把捉においてこそ、すべての被造的なものによって必然的かつ存在論的に基礎づけ られた「模倣行為」 imitari がなされる(p.105)。 ・この「神によって造られた存在」の「神によって」a Deoは、同時に必然的に「神への」 ad Deumでもある(p.108)。 ・要するに、人間には本来の創造的「権能」——それは同時に「純然たる存在」でもある——が欠けているので、人間に唯一残された可能性は、「世界への帰 属」という自らの存在を基盤としながら、この世界を自らの「住まい/故郷」 Heimat ——あるいは「祖国」patria——となしていくことである(p.110)。 ・「習慣」とそれが付与する「安全性」に対して、「律法」は「良心」 conscientia を喚起する(p.114)。 ・神にあっては「能力」potentia と「意志」voluntas とは統一されている。これに対して「能力」と「意志」との乖離は、自らの存在がそれ自身「権能」を所持していない被造性の特徴にほかならない。「被造者」 は、「可能性」posse を意のままに処理することができないので、なお一層より決定的な仕方で「創造者」に依存するようになる(p.120)。 ・たとえ被造者がすでに自らの存在を探求する問いかけの途上にあったとしても、被造者がはたして世界から自己を離反させたか否か、また自己自身が自ら掲げ た目標に到達したか否か、さらにこの世界からの孤立に成功したか否かを判定するのは、ひとり創造者の権能に属する(p.120)。 |
|
| 2.3 隣人愛 Dilectio
proximi |
128 |
||
| 2.4 付論03 |
136 |
||
| 3 |
3.社会生活(Vita
socialis) |
140 |
・要するに、平等性は恩寵の平等性とな
る。しかし、それはもはや同じ均一性ではない。というのは、キリストの前ですべての人々を結びつける結合関係が
「出生によって」generatione、アダムから獲得されたとしても、まさにここには万人に同様の罪あるい過去を開示することで、万人を均一なものと
なす神の思寵が啓示されるからである。したがって、平等性は思寵において初めて目に見えるものとされるとしても、しかし平等性それ自体は過去の事柄に根拠
づけられている。最も広汎な意味でこの「世界」そのものであるといえる過去の事実に照らしてのみ、「神の前で」すらも認められる人々の均一性、すなわち、
人々の責務を負い合う上での均一性が、理解可能なものとなる(p.156)。 |
リンク
【文献】
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099