自己を嫌悪し別の自己を願望することの意味
What it means to hate the self and to desire to become another self
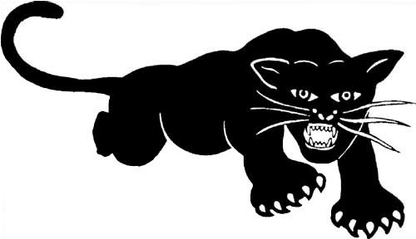
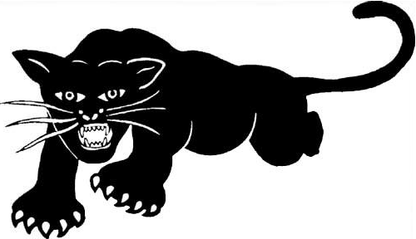
自己を嫌悪し別の自己を願望することの意味
What it means to hate the self and to desire to become another self
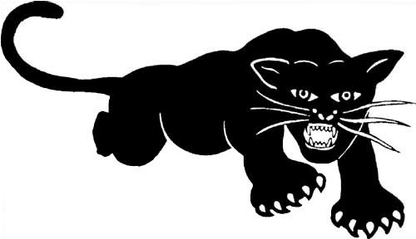
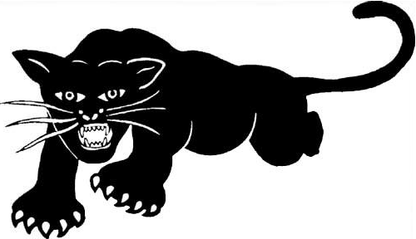
「行かないで。わたしを独りにしないで。わ たしがあれを手に入れたら、帰ってきてくれる?
手二入レルッテ、何ヲ?
いちばん青い眼よ。そうしたら帰ってきてく
れる?
モチロン、帰ッテクルサ。シバラクノ間、 行ッテシマウダケヨ。
約束する?
モチロ
ン。帰ッテクルヨ。アンタノ眼ノ
マン前ニネ」——(モリスン 2001:300, 大社訳)
カラーブラインドあるいはカラーブラインドネスとは、肌の違い、すなわち人種の違いがあるに も関わらず、そのような人種的差異——しばしば社会的差別が前提とされる——をあたかもないように振る舞うこと。あるいは、そのようなカルチャー、さらに は個人の意識のことをさす。ウィキペディアには「米国におけるカラーブランドネス(人種)という項目があり、その冒頭で次のように記されている。
"Color blindness (also called race blindness) is a sociological term for the disregard of racial characteristics when selecting which individuals will participate in some activity or receive some service. In practice, color-blind operations use no racial data or profiling and make no classifications, categorizations, or distinctions based upon race. An example of this would be a college processing admissions without regard to or knowledge of the racial characteristics of applicants."
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_blindness_(race)_in_the_United_States
ここで取りあげるのは、通常の(人種)差別における、カラーブランドネスのことよりも、被抑 圧者が夢見る抑圧者の理想的な容姿への羨望のことについて考える。
トニ・モリスン(あるいはモリソン, Toni Morrison, 1931- 2019)の小説『青い眼がほしい(The Bluest Eye)』(大社淑子訳、早川書房、2001年)[原著1970]の小説は、自分の不幸の原因が自分の容姿にあると思い込み「青い眼にあこがれる」少女ピ コーラが、父親の強姦と妊娠により気が触れて(やがて死産にいたるのだが)、ようやく、青い眼になったと思い込むが、想像上の少女と語り、「もっと青い眼 になりたい」——タイトルThe Bluest Eyeの由来——と願望する、ある意味で哀悼的かつ悲劇的な小説である。
この小説は1970年に完成しているが、モリスンが 書き始めたのは1962年頃だという。
私が興味あるのは、冒頭のピコーラの虚しい空想上の 友人との会話の後に、この物語が終わり、「著者あとがき」にある。著者の激しい怒りや糾弾の論調である。
1960年代から黒人の公民権運動が盛んになり、黒 人による意識の覚醒や、自分たちがもつ美の意識の覚醒——あるいは社会的構築——が、その後10年近く続き、さまざまな芸術運動もまた豊かに展開していく ようになる。しかし、モリスンのあとがきには、「青い眼がほしい」という羨望に対する、屈折した黒人の自己嫌悪に対する糾弾にも似た論調がある。
「ちょうど小学校が始まったばかりのときだった。彼 女が青い眼がほしい、と言った。それでわたしは、青い眼をした彼女の姿をいろいろ考えてみた。そして、願いがかなったときの彼女の姿を想像して、はげしい 嫌悪感をおぽえた。彼女の声にこもっていた悲しみは同情を求めているように思え、わたしは同情するふりをしようとしたが、彼女がもちだした冒涜的な願いに 驚いて、同情するかわりに「腹が立ってきた」。
その瞬間までわたしは、きれいなもの、愛らしいもの の、すてきなもの、醜いものを見てきたし、たしかに「美しい」という言葉を使いはしたものの、その衝撃を経験したのは、それがはじめてだった——その衝撃 は、それまで他の誰も「美しさ」がどういうものか、はっきりとは知らず、とくに、それを持っている当の本人にさえわかっていない、ということが明らかに なったときと同じほどはげしかった。
この件に作用したのは、わたしが仔細(しさい)に眺 めていた顔だけではなかったにちがいない。正午を過ぎたばかりの午後の通りの静けさ、光、告白がなされたときの雰囲気。とにかく、わたしが「美しさ」を 知ったのは、それが最初だった。つまり自分で想像してみたのは、それがはじめてだった。美というものは、たんに目に見えるものではなかった。それは、人が 「美しくする」ことのできるものだった。
『青い眼がほしい』は、それについて何かを言おうと
した努力の結果だった。どうして彼女には自分が持っている美しさがわからなかったのか、あるいは、おそらくその後もけっしてわからないのか、また、どうし
てそれほど根本的に自分を変えてもらいたいと祈ったのか、といったことについて何かを言おうとする試みだった。彼女の欲求の底には、人種的な自己嫌悪がひ
そんでいた。そして、二十年のちになっても、わたしはまだ、どういうふうにして人はその嫌悪感を学びとるのだろう、と考えていた。誰が彼女に教えたのか。
誰が、本物の自分であるより偽物であるほうがいいと彼女に感じさせたのか。誰が彼女を見て、美しさが欠けている、美の尺度の上では取るに足りない重さしか
ないときめたのか。この小説は、彼女を弾劾(だんがい)したまなざしを突ついてみようとしている」。
この「彼女」が誰であるのか?この、あとがきの冒頭 に登場する「彼女」はだれであるのか、わからない。フィクションの主人公であるピコーラではなく、彼女の親しい子供なのかもしれない。いずれにせよ。カ ラーブランドネス以上に、自分の身体を「より美しいもの」——だがそれは自分たちを抑圧する人たちの姿でもある——に変身させたいという、屈折した精神性 から脱却していないということだ。ピコーラの幻想は、彼女に憐憫の情を覚える人には哀れな姿に思える。だが、ピコーラ自身は、自分がもっと青い眼を持てる ことを信じていることで、満足しているようにもみえる。いずれにしても、私たち自身もまた、モリスンに似て「青い眼にあこがれる倒錯的な願望」に腹立つと 同時に、そのような欲望をつくりだす社会構造に対して強い怒りを覚えることを禁じえない。
モリスンのこの作品は、おぞましい悲劇を孕むフィク ションではあるが、同時に、我々の他者に対する屈折した羨望の姿を映しだす鏡として読み解くことも可能である。
モリスンのあとがきが、作品の余韻に浸るまもなく、 突如として登場する。この作品は、その作品全体がもつ絶望感と共に、彼女が、黒人がおかれた自己の容姿を否定し、白人を羨望するという屈折した人種主義 を、どのように克服するのかということを、それにひきつづく「あとがき」に赤裸々に、かつ力強く描かれているために、読者もまた、黒人の意識の覚醒にエン パワーされるのである。
最後に、この本の出版の4年後に、詩人で彼女の共著 者であるスレイド・モリソン(「本をひらいて」「子供たちに自由を!」という素敵な共著がある)と、アンジェラ・デイビスが映ったクールな写真があるの で、掲げて、このエッセーを閉じることにしよう。

"Toni Morrison (right) outside her Random House Office (which was then on 50th Street) with her younger son, Slade, and Angela Davis."(March 28, 1974.)
http://www.newyorksocialdiary.com/guest-diary/2009/jill-krementz-photo-journal-toni-morrison-at-bn
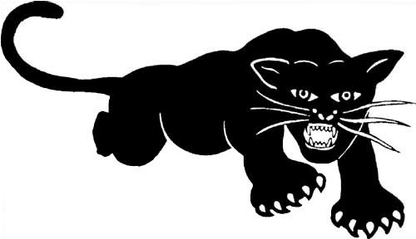
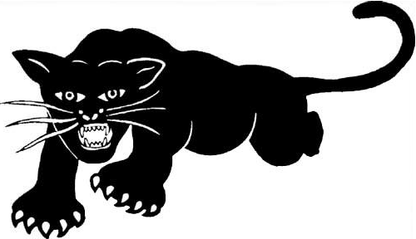
Black Panther Party, 1966-1982
●クレジット:池田光穂「自己を嫌悪し別の自己を願望することの意味、あるいは、意識/無意識としてのカラーブラインド」
リ ンク
文献
その他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099