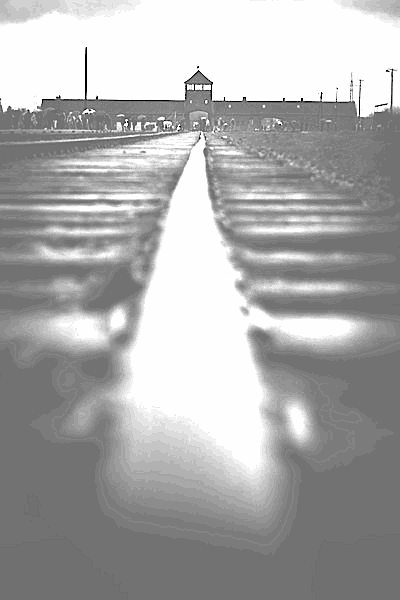| 「私はほかにも何度か絞首刑をみた。これ
らの死刑囚のたった一人でも涙
を流すところを、私は見たことがない。これらの枯れきった肉体は、とうのむかしに涙の苦い味わいことがない。これらの枯れきった肉体は、とうのむかしに涙
の苦い味わいを忘れてしまっていたのである。 一度だけ例外がある。第52電線作業班のオーベルカポはオランダ人で、二メートルを越える巨人であった。700名の囚人が彼の指揮のもとに作業し、全員が 彼を兄弟のように愛していた。だれひとりとして、彼の手から平手打ちを、また彼の口から罵声を浴びた者はいなかった。 彼は幼い少年を「奉仕」させていた、少年はいわゆる「ピーペル」であった。この収容所にこんな子がいるとは信じられないような、ほっそりして美しい顔だち の子であった。 (ブーナではピーペルたちは憎まれていた。彼らはしばしば、大人よりも残酷な態度を示したからである。私はある日、彼らのひとりで十三歳になる子どもが、 きちんと寝床をつくってくれなかったからといって、自分の父親を殴っているところを見かけたことがある。老人が静かに涙を流していると、子どものほうはこ う言って喚き散らしていた。「もしすぐに泣きやまなければ、もうパンを持ってきてやらないよ。わかったかい。」しかし、例のオランダ人のもとにいた少年給 仕はみんなから熱愛されていた。その子は不幸な天使のような顔をしていた。〉 ある日、ブーナの発電所が爆発した。現場に呼び寄せられたゲシュタポは、破壊活動による事故だという結論を出した。証跡が発見せられた。それを辿っていく と、オランダ人のオーベルカポをいただくブロックまで行きついた。そこで捜索が行なわれたところ、大量の兵器が発見せられた!オーベルカポはたちどころに 逮捕せられた。彼は何週間も続けて拷問を受けたが、その拷問はむだであった。彼はだれひとり名前を洩らさなかったのである。彼はアウシュヴィッツに移され た。それっきり彼の噂は聞かれなくなった。 しかし、彼の幼いピーペルは、収容所の闇牢に留まっていた。同様に拷問を受けたが、彼もまた、沈黙を守ったのである。そこで親衛隊は、武器を隠匿している のが発見されたほかの二名の囚人とともに、彼にも死刑の判決をくだした。 ある日、私たちは作業から戻ってきたときに、三羽の黒い烏のごとく、点呼広場に三本の絞首台が立っているのを見た。点呼。私たちのまわりには、機関銃の銃 先を向けた親衛隊員——伝統的儀式。縛りあげられた三人の死刑囚——そして彼らのなかに、あの幼いピーペル、悲しい目をした天使。 親衛隊員は、いつもより気がかりで、不安を覚えているように見受けられた。何千名もの見物人の前で男の子を絞首刑にするのは些細な仕事ではなかった。収容 所長は判決文を読みあげた。すべての目が子どもに注がれていた。彼は血の気がなく、ほとんど落ち着いており、唇を噛みしめていた。絞首台の影が彼を覆いか くしていた。 今度は、ラーゲルカポは死刑執行人の役を果たすことを拒否した。三人の親衛隊員が彼に代わった。 三人の死刑囚は、いっしょにそれぞれの椅子にのぼった。三人の首は同時に絞索の輪のなかに入れられた。 「自由万歳!」と、二人の大人は叫んだ。 子どもはというと、黙っていた。 「神さまはどこだ、どこにおられるのだ。」私のうしろでだれかがそう尋ねた。 収容所長の合図で三つの椅子が倒された。 全収容所内に絶対の沈黙。地平線には、太陽が沈みかけていた。 「脱帽!」と、収容所長がどなった。その声は疲れていた。私たちはというと涙を流していた。 「着帽!」 ついで行進が始まった。二人の大人はもう生きてはいなかった。脹れあがり、蒼みがかつて、彼らの舌はだらりと垂れていた。しかし三番めの綱はじっとしては いなかった——子どもはごく軽いので、まだ生きていたのである……。 三十分あまりというもの、彼は私たちの目のもとで臨終の苦しみを続けながら、そのようにして生と死とのあいだで闘っていたのである。そして私たちは、彼を まっこうからみつめねばならなかった。私が彼のまえを通ったとき、彼はまだ生きていた。彼の舌はまだ赤く、彼の目はまだ生気が消えていなかった。 私のうしろで、さっきと同じ男が尋ねるのが聞こえた。 「いったい、神はどこにおられるのだ。」 そして私は、私の心のなかで、ある声がその男にこう答えているのを感じた。 「どこだって。ことにおられる——ここに、この絞首台に吊るされておられる……。」 その晩、スープは屍体の味がした。」 (pp.107-110) |
I WATCHED other
hangings. I
never saw a single victim weep. These withered bodies had long forgotten the bitter taste of tears. Except once. The Oberkapo of the Fifty-second Cable Kommando was a Dutchman: a giant of a man, well over six feet. He had some seven hundred prisoners under his command, and they all loved him like a brother. Nobody had ever endured a blow or even an insult from him. In his "service" was a young boy, a pipel, as they were called. This one had a delicate and beautiful face—an incredible sight in this camp. (In Buna, the pipel were hated; they often displayed greater cruelty than their elders. I once saw one of them, a boy of thirteen, beat his father for not making his bed properly. As the old man quietly wept, the boy was yelling: "If you don't stop crying instantly, I will no longer bring you bread. Understood?" But the Dutchman's little servant was beloved by all. His was the face of an angel in distress.) One day the power failed at the central electric plant in Buna. The Gestapo, summoned to inspect the damage, concluded that it was sabotage. They found a trail. It led to the block of the Dutch Oberkapo. And after a search, they found a significant quantity of weapons. The Oberkapo was arrested on the spot. He was tortured for weeks on end, in vain. He gave no names. He was transferred to Auschwitz. And never heard from again. But his young pipel remained behind, in solitary confinement. He too was tortured, but he too remained silent. The SS then condemned him to death, him and two other inmates who had been found to possess arms. One day, as we returned from work, we saw three gallows, three black ravens, erected on the Appelplatz. Roll call. The SS surrounding us, machine guns aimed at us: the usual ritual. Three prisoners in chains—and, among them, the little pipel, the sad-eyed angel. The SS seemed more preoccupied, more worried, than usual. To hang a child in front of thousands of onlookers was not a small matter. The head of the camp read the verdict. All eyes were on the child. He was pale, almost calm, but he was biting his lips as he stood in the shadow of the gallows. This time, the Lagerkapo refused to act as executioner. Three SS took his place. The three condemned prisoners together stepped onto the chairs. In unison, the nooses were placed around their necks. "Long live liberty!" shouted the two men. But the boy was silent. "Where is merciful God, where is He?" someone behind me was asking. At the signal, the three chairs were tipped over. Total silence in the camp. On the horizon, the sun was setting. "Caps off!" screamed the Lagerälteste. His voice quivered. As for the rest of us, we were weeping. "Cover your heads!" Then came the march past the victims. The two men were no longer alive. Their tongues were hanging out, swollen and bluish.But the third rope was still moving: the child, too light, was still breathing… And so he remained for more than half an hour, lingering between life and death, writhing before our eyes. And we were forced to look at him at close range. He was still alive when I passed him. His tongue was still red, his eyes not yet extinguished. Behind me, I heard the same man asking: "For God's sake, where is God?" And from within me, I heard a voice answer: "Where He is? This is where—hanging here from this gallows … " That night, the soup tasted of corpses. (Pp.63-65.) |
| ウィーゼル、エリ『夜』村上光彦訳、みす
ず書房、1984年(Wiesel, Elie. 1958. La Nuit. Paris: Les Editiones de Minuit.) |
Wiesel, Elie. Night, Night. (trans, Marion Wiesel) New York: Hill and Wang. 2006. |
この文章は4章の末尾にある収容所でのエピソードである。引用した直前の節では、ウィーゼル が目撃したSS(親衛隊)によるユダヤ人「反乱者」の処刑のシーンがある。収容所のユダヤ人(=囚人)たちは、その処刑を脱帽して見学しなければならない ことが示されている。行進をして、処刑された同胞の姿を眺めることを強制されるのである。そして、処刑をみせられた後に食事が与えられる。引用されていな い、この直前のパラグラフの最後の文章は「その晩、スープがすてにうまいと思ったのを、私は覚えている……。(英訳:I remember that on that evening, the soup tasted better than ever...)」。スープの味は、この引用部分では、そ れとは百八十度異なり、「屍体の味」がするという、長い長い文章を挟んだ一種の「対句」の構造をなす。
また、こ のエピソードでは、収容者ならびにSSたちが、収容者の子供からピーペル(pipel)という、児童性愛の対象者がいて、その売春の対価として、SSやカ ポ(収容者から選ばれた監督でしばしば横暴に振る舞った)からは厚遇されていた、おぞましい物語にも触れられている。その子供たちは、厚遇され、権力を与 えられているために、収容所にいる肉親とりわけ父親——収容者は男女に分けられている——に対しても、横柄に振る舞まったことが示唆されている。しかし、 このエピソードの反乱者の処刑に、見せしめに殺される美しい男児は、皆から「愛され」(=エロス的とアガペー的という二重の意味がある)、極めて不幸で不 憫な殺され方——半時間も仮死のまま(罪もなく)首吊り処刑される——をする。

"The pipel child's during the holocaust were lucky because they lived
in better conditions than the others." --
http://holocaust122.weebly.com/vocabulary.html
+++
私のこの箇所を読んで浮かんだ不吉な疑問は次のとお りである。
1.SSや収容所長たちは、なぜユダヤ人同胞たちの 処刑を自分たちだけで愉しむだけなく、その光景を ユダヤ人たちに目撃させようとしたのか?
2.政治犯や反乱を企てた、あるいは(でっちあげら れた)被疑者たちは、わざわざ、処刑の理由を、ユダヤ人収容者の前で、その罪状を叫び、その後で、立たせた椅子を蹴飛ばし彼らを処刑するのにかかわらず、 この無垢な犠牲者は、何もその処刑の理由を述べられずに——あたり前である無垢の犠牲者だから——殺されるのか? 動物や女官を副葬するような殉死を要求 しているのか?
3.日本では、中国大陸で、少年兵に対して、侵攻し た地域で少女を陵辱したり、または、自分(=上官)たちが陵辱した後に、少女たちを殺すことを命じたという(『蟻の兵隊』参照)。その時に、日本兵の上官たち が、少年兵たちを巻き込んだ論理は「勇気を試させる」というものだった。だが、この場合、ユダヤ人たちに勇気を試させるような理由は、SSにはもともとな い。もし、考えさせられるとすれば、「刃向かうものは同じ運命にあう」と震撼させることにあるが、SSは、それを秩序をつくって、あたかも「社会見学」さ せるかのように、収容者たちに要求する。このような倒錯して、一貫性のない犠牲者への要求は、SSたちが、集団的狂気のもとにあったのか、それとも、我々 の精神性にも通底する(共通した)人間性の「闇」の部分なのだろうか?
+++
行為それ自体がもたらす「生の充実」と、行為の道徳
評価は絶対に相いれないとニーチェは考える。「同情は格率にもとづいているのではなく、欲情にもとづいていおり、それは病理的である。他人の苦痛は私たち
に伝染する、同情とは一つの伝染である」(WP. 368)——『権力への意志(上)』(原佑訳、p.355)
+++
それらの理由をかんがえよ。これらの課題には、真実 によって立証されるような答えがない。我々には、解釈行為を通して、その行為の意味を考え、また、真実がわからなくても、考えることで、未曾有のあるい は、ひょっとしたら、ミクロなかたちで、そしてかなり薄まったかたちで、われわれの身の回りでおこなっていること(例:いじめ)との、類似点や「ぜったい 交錯しないよ」と確信を持てる相違点を、明らかにすることで、暴力行為とその反道徳性の性質を、我々に納得できるかたちで、議論することができるように思 われる。
■エリ・ヴィーゼル(1928-2016)の収容所時代の写真

1945年4月16日ブーヘンヴァルト強制収容所にて。下から2段目、左から7番目がエリ・ヴィーゼル[Jewish Virtual Libraryより]
文 献
- ウィーゼル、エリ『夜』村上光彦訳、みすず書房、1984年(Wiesel, Elie. 1958. La Nuit. Paris: Les Editiones de Minuit.)
- Wiesel, Elie. Night, Night. (trans, Marion Wiesel) New York: Hill and Wang. 2006.