ひとは、おのれの知の尖端でしか書かない、すなわち、わたしたちの知とわたしたちの無知を 分かちながら、しかもその知とその無知をたがいに交わらせるような極限的な尖端でしか書かないのだ。——ジル・ドゥルーズ『反復と差異』(財津理 訳)
1. 健康の政治経済学
1.1 世界システム論
世界医療システムとは、I・ウォーラスティンが提唱した世界システムという概念から影響を受けてM・シンガーとH・ベアがはじめて言及した用 語である(Singer M., and H.Baer, Critical Medical Anthropology, Baywood Publishing, 1995, p.68.)。ウォーラスティンによれば、我々の歴史の中で唯一存在するシステムは「世界システム」に他ならない。したがってシンガーらの言う世界医療シ ステムという表現は、世界システムの内部に別の自律的なシステムがあるかのような印象を与える点で不適切である。
用語概念の混乱にも関わらず、世界医療システムという言葉の響きは、低開発地域のヘルスケアの批判的分析を志す学究に対して、容易には放棄し がたい魅力がある。新奇の概念が生み出す構想力がそこにある。なぜならウォーラスティンの主張は、我々の身の回りで起こっていること——ここでは医療—— を、ローカルな領域における自律的運動としてみるのではなく、それにまつわるグローバルな現象と関連づけて見るように要請しているからである。この論文の 目的は、その構想力の可能性についての思考実験である。したがって、シンガーらの説明にとらわれずに、私はこの章で世界医療システムという用語とその概念 を新たに提起しなおし、その可能性と限界について議論を深めたい。本論文でいう世界医療システムとはシンガーらの主張とは接点をもたない独自のものである
まず、ウォーラスティンの世界システムの概念について整理しておこう。世界システムとは、全地球的経済システムとして資本主義の起源と発展を とらえようとする見方である。世界システム論は以下の基本的命題に整理できる。
(1)現代の資本主義の発展の基盤は国民国家にはなく、単一の分業体制にもとづく地球 全体におよぶ世界システムとよばれるものにある。
(2)世界システムは、完全に孤立した自給経済を除けば、人間の歴史の中で唯一存在し たシステムである。
(3)世界システムは、政治的にも経済的にも支配的な「中核」と、中核に経済的に従属 する「辺境」からなり、その中間に中核と辺境の両方の経済 的・政治的性格が混在する「半辺境」があるという三つの構成要素を想定する。
(4)中核は辺境より原料を供給されて工業生産が可能になる。したがって辺境で産出さ れる原料供給は中核における価格設定に従属する。そこでは 不均等交換が生じている。
(5)この世界経済システムは、一五世紀ヨーロッパの資本主義的農業、つまり「農業資 本主義」から発展が始まった。
ウォーラスティン理論の要諦は、世界の辺境で見られる社会諸現象は中核で生起する社会現象と深く連動し、それは地球規模で生起している経済現 象とセットで考察する必要があるということだ。これらの社会諸現象とは、我々の関心においてはヘルス・ケア全般に関わる社会現象に他ならない。
1.2 理論的含意
本論文における世界医療システムを定義しよう。世界医療システムとは、中核と辺境、および半辺境で起こっているヘルス・ケアから構成される世 界システム内におけるサブシステムのことである。世界医療システムは世界システムに組み込まれており、それ自体で自律性をもつ実体であるとは想定しない。 これは別の角度から見れば、世界システム論からみた地球規模のヘルス・ケアを分析するための認識論的枠組であることを意味する。
世界医療システムにおいて、辺境で生起しているヘルス・ケアに関わる現象は、国家という境界で区切られた枠組で作動する、自律したユニークな 活動であるとは考えない。むしろ、その現象が経済を基盤にする中核で生起する現象と密接に連動していると見る。
ところが、このように世界医療システムを定義し、現実のヘルス・ケアに関わる経験的事実に照合してみると、従来の研究の認識論的枠組がある境 界(=限界)に突き当たることがわかる。その第一点は、従来の国際保健に関する医療社会学の研究領野は、国民国家によって境界づけられた領域と同じ輪郭を とっていることである。医療政策の社会学的な考察というマクロの研究にせよ、病院内の医師と患者の会話分析といったミクロの研究にせよ、医療社会学が準拠 するデータは、国家が提供する諸統計(例:死亡統計)であったり、国家内において制度が規定する集団(例:病院患者)から抽出されたものに他ならない。こ れらの研究は、資料が国家を基盤とする権力構造の中で正当性を与えられているのみならず、国家という共同性を作り上げ維持する実体として作動している事実 について無自覚である(B・アンダーソン『想像の共同体』白石さや・白石隆訳、NTT出版、一九九七年、二七五−二九三頁)。国家枠組によって境界づけら れた領域の中で「自由に」議論することができる医療社会学は、それを保障してくれる国家枠組の自明性を忘却することで、はじめて存立が可能となる。医療社 会学とは、誕生の当初からきわめてナショナルな学問として定立していたのである。
これは「国際保健」を医療社会学から考察する際に、明らかになる点である。国際保健の医療社会学的研究は、この問題に取り組むことを放棄して きた。世界医療システムの観点を我々がとることによって、国際間の比較という研究枠組がもつ危うさを指摘することができる。国際医療保健(学)は、分析と しても実践の観点としても国家の境界を超えようとするものではなく、国民国家の枠組を前提として、国家利害の功利計算の上に立った政治(学)以外の何もの でもない。その典型例を、国際協力事業団監修になる、小早川隆敏編『国際保健医療協力入門』国際協力出版会、一九九八年に見ることができる。そこでは、先 進開発国間による医療援助レースの中で、日本国の威信をどこまで高められるかという理念のもとに、援助を実践するという倫理性や現地社会の当事者性の問題 がほとんど省みられていない。
では、世界医療システムという観点から、どのように医療社会学は再想像されなければならないのだろうか。残念ながらその具体的な代案は用意さ れていない。それどころか、世界システム論を強力に自らの理論装置として援用する研究者ですら、自分たちの研究が生み出した落とし穴に足元をすくわれてい る。先行研究にそれがある。図は、冒頭にあげたベアらが、ヘルス・ケア・システムの水準について指摘したものである(Baer, H., M. Singer and I. Susser, Medical Anthropology and the World System, Bergin & Garvey, 1997、ただし図中の用語は池田が一部改変した)。
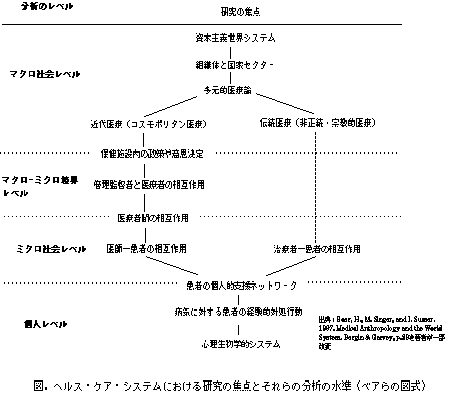
そこで、彼女らは世界システム内部のサブシステムとしてのヘルス・ケアを、医療人類学の古典的な慣習に則って、近代医療(=コスモポリタン医 療)と伝統医療(=非正統的・宗教的医療)に区分する。そして、近代医療の様相を医療社会学の諸研究の古典的テーマに関連づけて配置している。そのため、 伝統医療は、それらに対応するものが欠けた単純なものとして描かれている(図中の右)。
しかし、ここには伝統医療と見なされてきたものが近代医療との社会力学的関係の中で生産された認識論上の産物であるという観点が欠落してい る。近代医療を構成するサブ・システムを持たない医療が伝統医療であり、それがあたかも実体視されるようになったのだ。伝統医療とは、近代医療がすでに克 服したもの、すでに放棄したもの、そして近代医療にないもの等々、近代医療の要素が欠如したものとして定義されている。ここで見られる理論と経験における 倒錯とは、「伝統医療」がモデルとして先にあって、そのカテゴリーに入るものだけが伝統医療とされてきた点にある。
実際、長年の間、伝統医療は、あたかもどこかに実在するものとされ、人類学者はその事例の採集に明け暮れることになった。我々は「民間医療」 を定義する際においても同じ様な状況に直面する(池田光穂「非西洋医療」黒田浩一郎編『現代医療の社会学』世界思想社、一九九五年)。したがって伝統医療 とは、近代医療の欠如態として、最初から構想されていたものであって、近代医療の原理論的な探究の結果生み出された「近代医療のネガ」にすぎない。実際 「伝統医療」の特徴について指摘した最も初期の研究は、近代医療との比較の中でその性格を確認するという作業をおこなっているからである(Rivers, W.H.R. , Medicine, Magic, and Religion. Kegan, Paul, Trench, Trubner & Co., 1924)。
だから図で示された伝統医療には、西洋医療に対応するような組織内部の意思決定や管理者と医療者の関係、医療者間の相互作用などが欠如したも のとして描かれる。伝統医療は近代医療によって発明されたものに他ならない。近代医療がある空間には必ず伝統医療がある。ところが、この2つの医療システ ムは論理的には相互に排除するために、「伝統医療だけの世界」「伝統医療から近代医療への進歩が生じている世界」「未だに伝統医療が残存する近代医療の世 界」「伝統医療が駆逐された近代医療の世界」など様々な幻想が共有され、それらの医療システムの特性について議論されてきた。この異質の2つの医療システ ムが共存するという経験的事実の前に立ちながらも論理的には排除したいという認知的不協和を軽減するために人類学者によって考案された用語が「多元的医療 論」にほかならない。このモデルを採用する研究では、患者が両方のシステムを横断する行動の様態を描き出すことが可能になった。しかし、近代医療と伝統医 療の相互補完関係についての認識論的枠組に到達することは困難である。
その例を、一九八〇年に出版されたA・クラインマンの台湾における医療民族誌にみることができる。彼は、患者がさまざまな医療体系を横断する という現象を提示して、患者とその家族は病気と原因と治療方法について理解のモデルを予め持っており、それを充足するためであるかのごとく解釈する。また 患者たちに診断や治療を通して知識を提供するのは近代医療の医療者や伝統医療の施術者である。つまり治療者たちも独自の理解のためのモデルをもっている。 クラインマンは、それらを説明モデル(Explanatory Model, EM)という術語で説明した(A・クラインマン(大橋英寿ほか訳)『臨床人類学』弘文堂、一九九二年)。
説明モデルは、ここにあげた病気と治療をめぐるさまざまな役割を担う人々によって保有されていることが基本的前提となっている。彼らの間で、 情報が相互に交換されたり交渉されるために、そこには意味の互換性が保証されなければならない。クラインマンは説明モデルにおける共通の要素を、(1)病 的状態の原因、(2)発現の時期と様式、(3)病態生理的過程、(4)病気の過程と重症度、(5)治療法から構成されるという経験則を提示しているが、そ れは近代医療の疾病における因果論的理解を前提にするものである。ところがこれには問題がある。説明モデルでは、伝統的施術者が治療の現場で患者とその家 族に対して柔軟に対応したり、近代医療との折衷的共存を容認するという、現象面における因果論理解からの逸脱に適切な解釈を与えることができない。伝統医 療が近代医療との競合や共存、あるいは交渉の産物として構築されている見方をとらず、利用者である患者とその周辺の人びとにとっての静態的な資源としてし か医療体系を見ていないからである。このような混乱から脱出するためには、「医療的多元論」における人びとの行動と人びとが利用する医療資源を区分して考 えることが重要である(池田光穂「医療的多元論」『保健医療行動科学辞典』メヂカルフレンド社、近刊)。
2. ヘルス・ケアの諸概念の再考
2.1 健康と病気
世界医療システム論は、医療社会学が当然として受け入れている概念が世界システム内にどのように布置されているかを明らかにすることによっ て、我々をそれまでとは異なった認識へと誘う。
第二次大戦後に確立された世界保健機関による健康の定義は、一方では人権概念の身体レベルへの拡張の結果であると見なせるが、同時に他方で身 体の外部に健康を保障する社会を求めるという点で、健康の達成を社会の課題とする可能性を切り開いた。この定義は健康を人間の先験的な属性(=権利)であ ると認めつつ、そこから疎外されていることを常に我々に思い起こさせる言語遂行的効果をもつからだ。別の角度からいうと、世界保健機関以前には、病気の欠 如態が健康であると理解されていたものが、病気の欠如態以外に健康があるという形で積極的に獲得されるべき属性として登場したのである。この健康概念の延 長上にあるのが、近代医療批判としての「医療化」論である。医療化とは現代社会の中で近代医療がその対象領域を拡大してゆくことをさす。しかし、医療化が 論じられる近代医療批判の文脈の中では「医療化」は近代医療による社会統制(I・ゾラ)であったり、病気が医療によって作りだされ、人びとがますます医療 の専門家へとその依存を増大させてゆく現象(I・イリッチ)を内包する。「医療化」とは政治的次元における言語遂行的概念に他ならない。健康はどの人間に も先験的に与えられていたものが、近代医療の専門職集団によって剥奪され、彼ら抜きには健康は達成することができないという事態が引き起こされたと考える のである。好むと好まざるを問わず、臨床家のクリニックの空間にとどまっていた健康と病気の概念が、公共の社会空間の中で意識されることを可能にした。
世界保健機関の健康の概念は、通常の社会生活を送る人間にとって、経験的に了解することは困難である。健康は、一般的には個人的体験のレベル では病気の欠如態として考えられているからである(池田光穂「ヘルス・プロモーションとヘルス・イデオロギー」『日本保健医療行動科学会年報』 五巻、一九九〇年;池田光穂「日本人にみられる『禁忌の健康観』」『教育と医学』三八巻一〇号、一九九〇年)。その意味でWHOの健康の定義は、社会集団 によって病気と健康の概念が異なるという見解をとる人類学者にとってもまた、まったく不十分なものだ。この定義は主観的経験からは遠く、学問的論理として は不完全なものであるが、それは——「医療化」と同様に——学問的言明ではなく政治的言明だからである。
この理想的(=政治的)ではあるが現実とはかけ離れた世界保健機関の「健康の定義」は、当時の国際保健行政に携わった革新的な人たちの独創に よってつくり出されたものではない。二〇世紀の初頭から始まっていた宗主国から植民地に対しておこなわれるようになった「医療援助」が、大戦後の国際関係 の中で再編成される際に、一種の共通言語として理解されてきたものの延長としてみなすべきである(池田光穂「『健康の開発』史」『文学部論叢』熊本大学文 学会、第四九号、一九九六年、四一−七二頁)。N・ルーマンのシステム論の顰みに倣えば、社会的な公共財として再定義されたこの「健康」とは、国際保健と いう政治世界における一種のメディアであり、それを獲得する/損失するというのがこの政治世界におけるコミュニケーションの形式なのである。
2.2 病いの体験
医療社会学者は病人の個々人の体験がどのような形で社会的なものになるのかについて細心の注意を払ってきた。それが、文化や社会集団の差異に 基づく可能性があるものであれば、その研究テーマは、社会科学の問題構成において共通点を持ちうる重要な課題となる。それらの分析のためにいくつかの概念 区分を設けてきた。例えば、個人ないしはその文化に属する人びとが感じる「病い」(illness)と、近代医療が定義する「疾患」(disease)の 区分がそれである。
病いと疾患の二分法が認識論的に問題をはらんだ用法であることは、その提唱当時から指摘されてきた(Young, A., "The Anthropology of Illness and Sickness", Annual Review of Anthropology Vol.12, 1982.)。しかし、ここでは、それがもたらした社会的効果のほうに注目しよう。二つの疾病の概念が相互に独立なものとして、病気の社会的・文化的定義 と臨床的定義の二種類に分類が固定されて、その間の相互関係についての考察が省みられなかったことである。
医療人類学者は、研究対象とする人たちがもつ病いの文化的パターンを強調し、それを特権化しようとする傾向が強い(Kleinman,A., Writing at the Margin, University of California Press, 1995, pp.100-1.)。このような研究傾向は何を生んだのだろうか。その答えは、疾患の専門家としての医療者と病いの専門家としての社会学(人類学者)の 間の分業を生み、そして、両者を架橋する研究の不在を生んだということだ。この境界ゆえに、医療社会学者は「医療における社会学」(Sociology in Medicine)と「医療を対象とする社会学」(Sociology of Medicine)の区別をわざわざ断らねばならない。
低開発地域の医療社会学者の観点から言えば、これは研究対象を明瞭に区分して議論を先鋭化させる試みというよりも、問題解決を先送りにする態 度の表明のことではないかと思われる。医療社会学が自律した学問として確立している北米先進開発世界と、そのような学問領域の細分化が問われることのない 後進低開発地域では、学問の構成と社会的受容のパターンから根本的に異なっているからだ(例えばメキシコの保健衛生問題と社会科学者の関与に関する次の文 献を参照のこと、Almada Bay, I. ed., Salud y Crisis en Mexico. Centro de Investigacion Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM. 1990. )。先進開発地域における「医療を対象とする社会学」は、「医療における社会学」が研究対象からの偏りから自由になっていないとし、前者の中立性や判断能 力を保証する研究上の認識論的立場の優位を主張しようとした。ところが、「医療を対象とする社会学」は、近代医療制度を保持する国家という枠内に留まって いるという観点から、今度は後進低開発地域の医療を視座に入れた社会学から批判される運命にある。ナショナルな境界意識の範囲に留まっている従来の医療社 会学からの脱皮することが要請されている。
病い研究と疾患研究の分業体制が生み出す結果として、病いの研究者は、疾患についての知識がきわめて貧困であり、生物医学 (biomedicine)の診断過程を首尾一貫した一枚岩的なものとして把握するという傾向が生じる。ところが、日々の診断過程に従事している医療者た ちの現場では、誤診つまり病名と予後の予知に失敗することは日常茶飯事であり、また疾患への対処という個人的経験は、後の診断過程に大きく依存する。した がって医療者の治療実践における疾患は、世代間のみならず同じ教育を受けた医療者の間でも相当な多様性がある。社会学者や人類学者は、インフォーマントが 「何々すべしと指摘すること」と「実際の人びとの行動」を峻別すべきである、ということを厳しく教育されているはずなのだが、疾患についてのイメージ、ひ いては生物医学そのもののイメージは極めて紋切り型なものになっている。生物医学においてすでに解決ずみと見なされる人間の疾患についての一枚岩的イメー ジから解放されて、多様で複数の声をもった知識と実践の総体としての医療についての関心が喚起される必要がある(M. Lock and D. Gordon eds., Biomedicine Examined. Kluwer Academic Publishers. 1988)。
3. 分析のための視点——ドクトリン・テクノロジー・ヘゲモニー
前節で指摘した認識論的な反省の立場にたつならば、新しい医療社会学には従来の分析枠組とは異なるものが要請されるはずである。世界医療シス テムにおける中核から辺境にむかうモーメントのなかで発現する主要な3つの様相(modality)についてここで考察してみたい。
3.1 ドクトリン
ドクトリンの原義はキリスト教に起源をもつ教育や指導のことであるが、現在ではモンロー・ドクトリンに代表される政治的教書、つまり政策を言 説の形で集約したものをドクトリンと呼ぶ。先の世界保健機関の健康の定義のほかに、プライマリーヘルスケアの理念を謳った一九七八年のアルマアタ宣言もド クトリンである。また世界保健機関はHIV感染症やマラリアに対する「戦略」について広報するが、これらもドクトリンである。各国の政府は、そのような地 球レベルでのドクトリンを受けて、国内向けに、施政の内容や達成されるべき目標を立てる(冷戦期には東西両陣営の2つのヴァージョンの健康の開発に関する ドクトリンが共存していた)。これらの具体的な施策の内容もまたドクトリンである。ドクトリンは、どのような階層レベルにおいても、中核から周辺に向かっ て発せられる施策の理念なのである。
ドクトリンは、それを表明する主体にとって明確に意識化された「イデオロギー」である(C・ギアツ『文化の解釈学II』岩波書店、一九八七 年、四頁)。ドクトリンには、それまでの政策の課題とこれからの方針が含まれているが、多声的な批判精神によって書かれているわけではない。そうではな く、政治的文書の正しい使用法であるところの、人びとを保健施策に向わしめるという単声的な啓蒙精神によって書かれているのである。ドクトリンは明文化さ れたものをプロトタイプとするが、同時に公共空間における統治者や保健施策の現場で働く中核に属する人びとの発話などにも、ドクトリンの諸断片をみること が可能である。したがってドクトリンは医療の言説的活動の一形態である。
ドクトリンについて考察することは、世界医療システムの遂行面での研究に欠かせない。冷戦期末期の一九八〇年代中期の中央アメリカの村落医療 において、もっとも中核をなしていたドクトリンはプライマリーヘルスケアの理念にもとづくものであった。しかしながら政治体制の異なる国家間では、住民に 対する公衆衛生教育の中で説かれる「健康」の意味が国家が定義するドクトリンから影響を受け、主張される健康の意味内容が異なっていた(池田光穂「健康の 概念が伝えられる時」『メディカルヒューマニティ』四巻二号、一九八九年)。つまり、国民への健康政策を通して国家の境界が維持されるわけだが、健康の意 識を注入する基本政策はそれぞれ異なったドクトリンを介して作動するのである。
3.2 テクノロジー
医療の実践とは身体への技術的介入を基盤にしている。したがってドクトリンを定立するための手段は、その歴史的社会的文脈において確立され た、あるいは確立されつつあるテクノロジーに依存する。テクノロジーをカタカナ書きにする理由は、テクノロジーの細部を構成する技巧 (technique)よりも、一連の技巧の体系性やその総体がもつ特性について着目したいからである。
テクノロジーがうける社会決定と、それとは矛盾するテクノロジー独自の創造性に着目しよう。テクノロジーは利用者の目的を遂行するための道具 を人びとに提供するが、同時に、テクノロジーの利用形態は、長期的に見れば利用者の目的を新たに創出し、社会を変化させてゆくという弁証法的な展開をとげ る。
事例として注射の受容について考えてみよう。西洋で開発された皮下注射ないしは静脈注射は、近代医療の導入時には多くの低開発地域で人びとか ら拒絶された。注射をおこなう病院は、人びとにとって死の場所を意味した。また「白人」は注射をおこなうと称して、現地住民から血液を奪っているという流 言や信仰が発生したこともある(G・フォスターとB・アンダーソン『医療人類学』中川米造監訳、リブロポート、一九八七年、特に第十三章を参照)。後者 は、植民地における搾取主体である白人と、被搾取者の現地住民の関係を注射という行為の中に表象したとしばしば人類学的に解釈されてきた。
ところが、「外来の白人が使う恐ろしいテクノロジー」という象徴的意味が消失ないし後退すると、注射は低開発途上国では、もっとも簡便な治療 法として定着し、住民に受け入れられた。つまり人びとのあいだで、注射に対してより積極的な解釈が登場し、それが多数の支持を得ることとなった。たとえ ば、より痛みを伴えば治療効果があがるという土着的解釈などは、その一つである。また、民間療法者が注射器を手に入れ、注射の技術を会得し、ディスポーザ ブルの注射針を使いまわしをするという非正規的な受容が世界の各地で見られる。薬物利用者が薬物の薬理作用をより効果的にするために静脈注射をおこなうよ うになり、それが定着する。さらに薬物利用の非合法化にともないシューティング・ギャラリーというサブカルチャーが登場したのは、その社会的局面の創造的 流用がおこなわれた一事例である( J.B. Page et al.,"Intravenous drug use and HIV infection in Miami." Medical Anthropology Quarterly (NS) Vol. 4, 1990. )。さらにHIV感染の流行とそれに対する予防知識の大衆化に伴ってシューティング・ギャラリーにおける注射針の共有に関する積極的意味づけは後退した。 近代医療が期待しないテクノロジーの流用がそこでは常におこなわれている。近代医療による統制(=取締)は結果的に薬物利用者のサブカルチャーを同時に産 出しているのである。
3.3 ヘゲモニー
グラムシは、レーニンの著述から得たアイディアをもとに、資本主義社会において政治的支配を維持するためには、力による統治以上に被支配層の 同意が重要な機能を果たすことを指摘した。世界医療システムの分析視角としてグラムシのヘゲモニー概念を導入する最大の理由は、資本主義社会における同意 と強制という力の配分が、医療においては社会によって多様に変化するということが、経験的事実としてよく知られているからである。
予防注射の事例をとり上げると、その事情がよく理解できる。予防注射は、感染症予防に関する住民の理解が得られ、またそれに対する異議申し立 てがないときに接種率は高くなる。あるいは、感染症予防に関する知識を住民がもっていなくても、住民に対する近代医療の象徴的価値が高ければ、つまり近代 医療のヘゲモニーが確立していていれば、比較的高い接種率を維持することができる。
医療政策の目的が感染症の罹患率を低下させるためだけであれば、集団の予防接種率は一定以上の割合であればよい。しかし、低開発地域(辺境) における予防接種率は、保健医療政策の指標となるものであり、国際的な医療援助や経済援助を受けるためにも重要な社会の厚生の指標として機能している。そ のため接種率を上げるということが自己目的と化してゆく。末端の保健センターのレベルでは、接種率は医療スタッフの業績評価として反映されるので、時にス タッフ間や保健地域間での競争を引き起こす。これらの活動は結果的に、現地における近代医療のヘゲモニーの確立を促す。ただし、接種率の高率化がヘゲモ ニーの確立の直接の原因となるのではなく、高率化のための実践を通して近代医療の象徴的価値が住民に伝達されるのである。低開発地域での住民に対する予防 接種をみることは、国家主導の公衆衛生政策を通して、近代医療のヘゲモニーが確立したり、挫折する過程を観察することに他ならない。
他方、予防接種の高比率が達成されている開発地域(中核)では、言うまでもなく近代医療のヘゲモニーが確立されている。そこで、問題化される のは、予防接種による事故であり、これは社会防衛よりも個人の福祉が優先したときに初めて論争可能なテーマとなる。また、そのような医療的事象の社会問題 化は、近代医療の言説の中から紡ぎ出されてくるので、当該の社会における近代医療のヘゲモニーが脅威に曝されるわけではなく、その内部における医療の諸言 説がヘゲモニーをめぐって争うという状況が生じる。もちろん、これはグローバルに見れば近代医療のヘゲモニーが後進低開発地域に確立したことを意味する。 近代医療のヘゲモニーが確立された社会空間で着目すべき点は「このシステム内部の統制力が、ただ抑止的なだけではなく生産的であるということを理解しなけ ればならない」ということである(E・サイード(今沢紀子訳)『オリエンタリズム』平凡社、一九八六年、一五頁)。
4. 結論
世界医療システムとは、世界システム内部に組み込ま れ、それ自体では完全に自律構造を持たないサブシステム(=実体)のことであり、同時に医 療をめぐる権力のミクロな布置構造を広い歴史的・社会的観点から分析する視座(=認識論)のことであった。この論文を通して、私は世界医療 システムの考え 方の基本構造を素描した。最後に、この議論のもつ問題点と可能性について示唆する。
まず世界システム論が浴びている批判は、そのまま我々の議論にも当てはまる。それを私は、(1)経済決定の過大評価と、(2)中核の一方的な 辺境に対する「搾取」構造の妥当性への疑問という2点に絞るが、この2つの批判は相互に関係している。世界システム論における経済決定の特徴は、中核が辺 境を単線的に組み込んでゆくのではなく、中核内部の社会発展のレベルや歴史上の諸要因によって複雑な動きをするが、それを最終的に経済現象の動きの中に主 に見ていこうとする。そのため、文化的な要因の独自性や文化自体の変動が経済現象に比べて過小評価されてきたという批判がある(Robertson, R. and F. Lechner,, "Modernization, Globalization and World-Systems Theory", Theory, Culture and Society Vol.2(3), 1985)。
そのとおりである。マルクス主義的、あるいは批判的医療社会学における問題は、経済的関係が変化(=改善/悪化)すれば、社会関係が変わる (=良くなる/悪くなる)という経済を上位の審級とする機械論を払拭できずにいる。キューバの医療システムの歴史において、階級闘争の延長上にある革命と いう全体システムの改変というプログラムは、近代医療の優位性と権威を一層高めた。客観的な科学として近代医療はキューバの生物医学の技術的水準を上げ、 公衆衛生状況を改善したからである(Diaz-Briquets, S., The Health Revolution in Cuba, University of Texas Press, 1983)。経済システムの改変と近代医療の成功は、キューバの位置する地政学的な関係の中で考えなければならない(J.M. Feinsilver. "World Medical Power". Latin America Research Review Vol.XXIV, 1989.)。
近代医療は、マルクス主義的な経済決定よりも、むしろ一定の自律性を前提とした文化現象と経済現象の相互作用のほうにより影響を受ける。世界 医療システムの強みは、医療をめぐる権力のミクロな布置構造を広い歴史的・社会的観点から分析することによって見えてくる事象の多様な広がりを教えてくれ る点にある。世界医療システムという分析枠組を採用してはじめて、人びとの近代医療への具体的な献身、参画、嫌悪、抵抗などの微細な日々の実践の中に、よ り巨大なシステムの影を発見する可能性への道が開かれる。もちろん、近代医療に抵抗している人びとを我々が発見しても、その運動の当事者が必ずしも、より 広い文脈を意識しながら行動しているという保証はない。かと言って研究者が一歩進んだ認識論的優位に立つわけでもない。研究者は、より大きな文脈の中で、 そのような運動がどのような可能性をもつのかということを示唆することができるだけだ。世界医療システムに関する論議とは、そのような医療の運動の当事者 と研究者をつなぎ合わせる認識論的な闘技場(arena)に他ならない。
参考文献
- 池田光穂「健康の概念と医療人類学の再想像」『医療人類学』、第二一号、一九九六年
- 医療人類学研究会編『文化現象としての医療』メディカ出版、一九九二年
- I・ウォーラスティン(川北稔 訳)『近代世界システムI・II』岩波書店、一九八一・一九八二年
- I・ウォーラスティン(川北稔 訳)『近代世界システム1600-1750』名古屋大学出版会、一九九三年
- I・ウォーラスティン(川北稔 訳)『近代世界システム1730-1840s』名古屋大学出版会、一九九七年
- 黒田浩一郎「文化としての現代医療」『現代文化を学ぶ人のために』井上俊編、世界思想社、一九九三年
- 波平恵美子編『人類学と医療』弘文堂、一九九二年
- 福島真人「文化からシステムへ」『社会人類学年報』第二四巻、一九九八年
- A・マッケロイとP・タウンゼント(丸井英二 監訳)『医療人類学』大修館書店、一九九五年