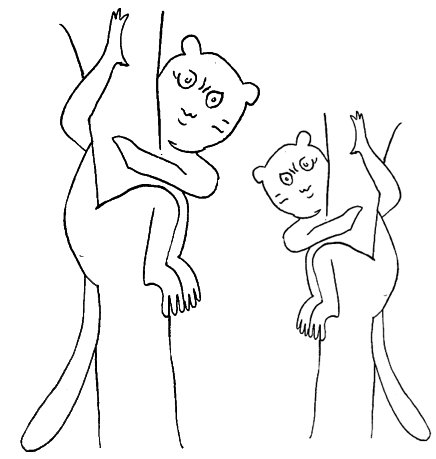
アローの不可能性定理
Arrow's impossibility
theorem
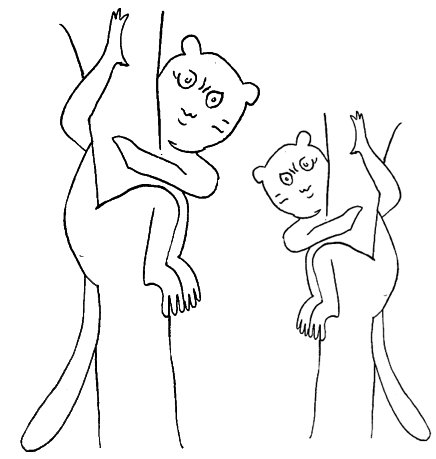
☆アローの不可能性定理(Arrow's
impossibility theorem)
は社会選択理論における重要な結果であり、集団意思決定のための順位選択手続きは合理的な選択の要件を満たせないことを示している[1]。具体的には、ア
ローは「無関係な選択肢の独立性」という原則を満たすルールが存在しないことを証明した。この原則とは、選択肢AとBの間の選択が、第三の無関係な選択肢
Cの質に依存してはならないというものだ[2][3][4]。
この結果は投票規則の議論で頻繁に引用される[5]。そこでは順位付け投票規則では妨害効果を消去法による排除ができないことが示される[6][7]
[8]。この結果は最初にコンドルセ侯爵によって示された。彼の投票のパラドックスは論理的に一貫した多数決規則の不可能性を示した。アローの定理はコン
ドルセの知見を一般化し、集団指導や合意形成のような非多数決規則も含むようにした。[1]
不可能性定理は全ての順位付け投票規則に妨害者が存在することを示すが、妨害者の頻度は規則によって劇的に異なる。単記投票や順位選択投票(即時決選投
票)のような多数決規則は妨害者に極めて敏感であり[9][10]、数学的に必要でない状況(例:中道圧迫)でも妨害者を生み出す。[11][12]
これに対し、順位付け投票における多数決(コンドルセ)方式は、投票サイクルに限定することで[11]、イデオロギー主導の選挙では稀な現象である投票サ
イクルに限定することで[12]、選挙の台無しになるケースを唯一最小化する[12]。有権者選好の特定モデル(中位有権者定理で想定される左右スペクト
ルなど)では、これらの方式では妨害者が完全に消滅する[15]。[16]
各候補者に個別に評価を付与する評点投票規則は、アローの定理の影響を受けない。[17][18][19]
アローは当初、これらの制度が提供する情報は無意味であり、したがって逆説を防ぐために利用できないと主張した。これが彼にこれらの制度を見落とさせる原
因となった[20]。しかしアローは後にこれを誤りだと述べ[21][22]、基数効用に基づく規則(スコア投票や承認投票など)は彼の定理の対象外であ
ることを認めた[23][24]。
| Arrow's
impossibility theorem is a key result in social choice theory showing
that no ranked-choice procedure for group decision-making can satisfy
the requirements of rational choice.[1] Specifically, Arrow showed no
such rule can satisfy independence of irrelevant alternatives, the
principle that a choice between two alternatives A and B should not
depend on the quality of some third, unrelated option, C.[2][3][4] The result is often cited in discussions of voting rules,[5] where it shows no ranked voting rule can eliminate the spoiler effect.[6][7][8] This result was first shown by the Marquis de Condorcet, whose voting paradox showed the impossibility of logically-consistent majority rule; Arrow's theorem generalizes Condorcet's findings to include non-majoritarian rules like collective leadership or consensus decision-making.[1] While the impossibility theorem shows all ranked voting rules must have spoilers, the frequency of spoilers differs dramatically by rule. Plurality-rule methods like choose-one and ranked-choice (instant-runoff) voting are highly sensitive to spoilers,[9][10] creating them even in some situations where they are not mathematically necessary (e.g. in center squeezes).[11][12] In contrast, majority-rule (Condorcet) methods of ranked voting uniquely minimize the number of spoiled elections[12] by restricting them to voting cycles,[11] which are rare in ideologically-driven elections.[13][14] Under some models of voter preferences (like the left-right spectrum assumed in the median voter theorem), spoilers disappear entirely for these methods.[15][16] Rated voting rules, where voters assign a separate grade to each candidate, are not affected by Arrow's theorem.[17][18][19] Arrow initially asserted the information provided by these systems was meaningless and therefore could not be used to prevent paradoxes, leading him to overlook them.[20] However, Arrow would later describe this as a mistake,[21][22] admitting rules based on cardinal utilities (such as score and approval voting) are not subject to his theorem.[23][24] |
アローの不可能性定理は社会選択理論における重要な結果であり、集団意
思決定のための順位選択手続きは合理的な選択の要件を満たせないことを示している[1]。具体的には、アローは「無関係な選択肢の独立性」という原則を満
たすルールが存在しないことを証明した。この原則とは、選択肢AとBの間の選択が、第三の無関係な選択肢Cの質に依存してはならないというものだ[2]
[3][4]。 この結果は投票規則の議論で頻繁に引用される[5]。そこでは順位付け投票規則では妨害効果を消去法による排除ができないことが示される[6][7] [8]。この結果は最初にコンドルセ侯爵によって示された。彼の投票のパラドックスは論理的に一貫した多数決規則の不可能性を示した。アローの定理はコン ドルセの知見を一般化し、集団指導や合意形成のような非多数決規則も含むようにした。[1] 不可能性定理は全ての順位付け投票規則に妨害者が存在することを示すが、妨害者の頻度は規則によって劇的に異なる。単記投票や順位選択投票(即時決選投 票)のような多数決規則は妨害者に極めて敏感であり[9][10]、数学的に必要でない状況(例:中道圧迫)でも妨害者を生み出す。[11][12] これに対し、順位付け投票における多数決(コンドルセ)方式は、投票サイクルに限定することで[11]、イデオロギー主導の選挙では稀な現象である投票サ イクルに限定することで[12]、選挙の台無しになるケースを唯一最小化する[12]。有権者選好の特定モデル(中位有権者定理で想定される左右スペクト ルなど)では、これらの方式では妨害者が完全に消滅する[15]。[16] 各候補者に個別に評価を付与する評点投票規則は、アローの定理の影響を受けない。[17][18][19] アローは当初、これらの制度が提供する情報は無意味であり、したがって逆説を防ぐために利用できないと主張した。これが彼にこれらの制度を見落とさせる原 因となった[20]。しかしアローは後にこれを誤りだと述べ[21][22]、基数効用に基づく規則(スコア投票や承認投票など)は彼の定理の対象外であ ることを認めた[23][24]。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Arrow%27s_impossibility_theorem |
☆概要
|
☆日本語ウィキペディア「アローの不可能性定理」 アローの不可能性定理(アローのふかのうせいていり、英: Arrow's impossibility theorem)、アローの(一般)可能性定理、または単にアローの定理とは、社会的選択理論における不可能性定理(英語版)の一つである。 |
|
| 非独裁性. 社会的選好関数は複数の投票者の意志を反映しなければならない。単に誰か1人の意志を模倣するだけに留まることはできない。 |
|
| 定義域の非限定性
(普遍性).
個人の選好を組み合わせた如何なる集合に対しても、社会的選好関数は社会的選択の一意で完備な順序付けを出力せねばならない。従って、社会的に完備な選好
の順序付けを出力できねばならず、投票者の選好が同一である場合は、同一の結果を決定論的に出すことができなければならない。 |
|
| 無関係な選択肢か
らの独立性(英語版)(IIA). 選択肢 x と y
にかかわる社会的選好が、それら2つの選択肢に関する個人の選好のみで決まること。また一般に、個人の選好がその他の「無関係な」選択肢 z
(ある特定の部分集合の外にあるもの)について変化したとしても、元の部分集合に関する社会的選好が影響されないこと。これは例えば、候補者が2人である
選挙に第3の候補が追加されたとしても、その第3の候補者が勝つ場合を除いて選挙結果が影響されないことである。 |
|
| パレート効率性 (全会一致性). 社会の全員の選好が「x は y よりも望ましい」と一致している場合、社会的選好も「x は y よりも望ましい」となること |
|
| なお、以上の4条件は1963年に発表された第2版に基づく。1952年の初版では、パレート効率性に代えて次の2つの条件が挙げられており、計5条件とされていた。 |
|
| 単調性(英語版)
(社会と個人の価値観の正相関):もし何れかの個人がある選択肢の評価を上げて選好順位を変えたなら、社会的選好順位も同じ選択肢の順位を上げるかまたは
変化なしとなり、順位を却って下げる結果にはならないこと。如何なる個人も選択肢の評価を「上げる」ことで却って損ねることはできないこと。 |
|
| 非賦課性(主権在民):可能な全ての社会的選好順位は、何らかの個人的な選考順位に対応すること。これは社会的厚生関数が全射であることを意味する。値空間の大きさは無制限である。 | |
| 1963年版の方が条件が弱いのでより一般的である。単調性、非賦課性、IIA、の3つを合わせればパレート効率性が導かれるが、パレート効率性(それ自体が非賦課性を持つ)とIIAを合わせても単調性は導かれない。 |
|
| アローの定理と
は、2人以上の投票者と3つ以上の選択肢があるとき、上述した社会的選好に関する2つの公理と公正な選挙のための4つの条件をすべて満たす社会厚生関数は
存在しないことを示した定理である。すなわち社会が選択肢を合理的に選べるための 2つの公理 (社会的選好が完備で推移的であること)
と公正な選挙が満たすべきと考えられる4条件とが互いに矛盾することを示した。 |
|
| この否定的結論は「社会的決定の合理性と民主制の両立は困難である」と
か「民主主義は不可能である」といった (それ自体は誤りとは言えない)
主張に単純化されて理解されることもあった。定理の内容が正しく理解されたにせよそうでなかったにせよ、この定理が「一般意思」「社会的善」「公共善」
「人民の意思」といった主張に疑いを投げかけたことは間違いない[7]。この定理をアロー自身は「一般可能性定理」と呼んだ。しかしこの定理が持つ否定的
含意から、「アローの不可能性定理」と呼ばれるのが一般的となった。 |
|
| 定理の解釈 |
|
| アローの定理は数学的な結果だが、これはよく数学的とは言えない表現で
人口に膾炙してきた。例えば「公正な選挙制度は存在しない」「全ての順位選好方式には欠陥がある」「唯一欠陥のない投票制度とは独裁制である」などである
[8]。これらはアローの定理を単純化したものであり、一般には正しいとは考えられていない。アローの定理が実際に述べているのは、決定的な選好投票制度
――つまり、選好順位が投票に唯一関わる情報であって、かつ、全ての投票の組み合わせがそれぞれ一意の結果をもたらす場合――においては、上記の条件を全
て同時に満たすことは出来ないということである。 様々な研究者がこのパラドックスを逃れる手段としてIIA条件を弱めることを提案してきた。順位選好方式の研究者の間にはIIAが不必要に強い基準だと強 固に主張する向きがある。この基準は殆どの実用的な選挙制度で満足されていない。この立場を採る論者によれば、元のIIA基準が欠陥含みであることは循環 選好の可能性から明らかだと言う。投票者が次のように投票したとしよう: 1人はA > B > Cと投票 1人はB > C > Aと投票 1人はC > A > Bと投票 すると、2つの選択肢の間を取り出した多数票は、AはBに勝ち、BはCに勝ち、CはAに勝つことから、3すくみの関係になっている。この状況では、「多数 票を得た候補が選挙に勝つ」という極めて基本的な多数決の要件を満たすような集計ルールは、社会的選好が推移的(または非循環的)でなければならないとす ると、IIA基準を満足できない。つまり、仮にそのようなルールがIIA基準を満たすとすると、多数票は尊重されるので、社会的選好としてAはBに勝ち (A > Bが2票に対してB > Aは1票)、BはCに勝ち、CはAに勝つので循環が生じる。これは社会的選好が推移的であるとする仮定に矛盾する。 従って、アローの定理が本当に述べているのは多数決制の選挙制度が非自明なゲームだということで、殆どの選挙制度の結果を予見するにはゲーム理論を援用す べきだということである[註 2]。任意のゲームには効率的な均衡が存在するとは限らないので、これは不本意な結果と見ることもできる。例えば、票は投じたものの本来誰1人として望ん でいなかったような結果が出てしまう場合がある。 |
|
| その他の可能性の探求 |
|
| 以下は https://x.gd/qp8vO を参照 |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099