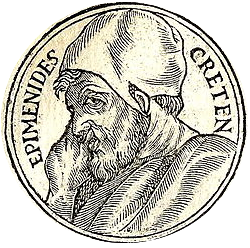
クレタ島人のパラドックス
The Cretan Paradox, or
Epimenides paradox
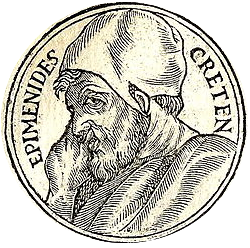
☆嘘つきクレタ島人のパラドックスは、エピメニデスのパラドックス(Epimenides
paradox)ということが多い。エ
ピメニデスのパラドックスは、論理学における自己言及の問題を明らかにする。この名称は、この命題を最初に述べたとされるクレタ島の哲学者、クノッソスの
エピメニデス(紀元前600年頃生存)に由来する。[1]
この問題の典型的な説明は、ダグラス・ホフスタッターの著書『ゲーデル、エッシャー、バッハ』にある:
エピメニデスはクレタ人であり、不滅の言葉を残した。「クレタ人は皆、嘘つきである」[a]
自己言及のパラドックスは、エピメニデスが真実を語った可能性について考察する際に生じる。
| The Epimenides
paradox reveals a problem with self-reference in logic. It is named
after the Cretan philosopher Epimenides of Knossos (alive circa 600 BC)
who is credited with the original statement.[1] A typical description
of the problem is given in the book Gödel, Escher, Bach, by Douglas
Hofstadter: Epimenides was a Cretan who made the immortal statement: "All Cretans are liars."[a] A paradox of self-reference arises when one considers whether it is possible for Epimenides to have spoken the truth. |
エピメニデスのパラドックスは、論理学における自己言及の問題を明らか
にする。この名称は、この命題を最初に述べたとされるクレタ島の哲学者、クノッソスのエピメニデス(紀元前600年頃生存)に由来する。[1]
この問題の典型的な説明は、ダグラス・ホフスタッターの著書『ゲーデル、エッシャー、バッハ』にある: エピメニデスはクレタ人であり、不滅の言葉を残した。「クレタ人は皆、嘘つきである」[a] 自己言及のパラドックスは、エピメニデスが真実を語った可能性について考察する際に生じる。 |
| Mythology of lying Cretans According to Ptolemaeus Chennus, Thetis and Medea had once argued in Thessaly over which was the most beautiful; they appointed the Cretan Idomeneus as the judge, who gave the victory to Thetis. In her anger, Medea called all Cretans liars, and cursed them to never say the truth.[2] |
クレタ人の嘘つき神話 プトレマイオス・ケヌスによれば、テティスとメデアはかつてテッサリアでどちらが最も美しいか言い争った。二人はクレタ人のイドメネウスを審判に任命し、 彼はテティスに勝利を与えた。怒ったメデアは全てのクレタ人を嘘つき呼ばわりし、真実を決して語れぬよう呪いをかけました。[2] |
| Logical paradox Thomas Fowler (1869) states the paradox as follows: "Epimenides the Cretan says, 'that all the Cretans are liars,' but Epimenides is himself a Cretan; therefore he is himself a liar. But if he is a liar, what he says is untrue, and consequently, the Cretans are veracious; but Epimenides is a Cretan, and therefore what he says is true; saying the Cretans are liars, Epimenides is himself a liar, and what he says is untrue. Thus we may go on alternately proving that Epimenides and the Cretans are truthful and untruthful."[3] If we assume the statement is false and that Epimenides is lying about all Cretans being liars, then there must exist at least one Cretan who is honest. This does not lead to a contradiction since it is not required that this Cretan be Epimenides. This means that Epimenides can say the false statement that all Cretans are liars while knowing at least one honest Cretan and lying about this particular Cretan. Hence, from the assumption that the statement is false, it does not follow that the statement is true. So we can avoid a paradox as seeing the statement "all Cretans are liars" as a false statement, which is made by a lying Cretan, Epimenides.[4] The mistake made by Thomas Fowler (and many other people) above is to think that the negation of "all Cretans are liars" is "all Cretans are honest" (a paradox) when in fact the negation is "there exists a Cretan who is honest", or "not all Cretans are liars". The Epimenides paradox can be slightly modified as to not allow the kind of solution described above, as it was in the first paradox of Eubulides but instead leading to a non-avoidable self-contradiction. Paradoxical versions of the Epimenides problem are closely related to a class of more difficult logical problems, including the liar paradox, Socratic paradox and the Burali-Forti paradox, all of which have self-reference in common with Epimenides. The Epimenides paradox is usually classified as a variation on the liar paradox, and sometimes the two are not distinguished. The study of self-reference led to important developments in logic and mathematics in the twentieth century. In other words, it is not a paradox once one realizes "All Cretans are liars" being untrue only means "Not all Cretans are liars" instead of the assumption that "All Cretans are honest". Perhaps better put, for "All Cretans are liars" to be a true statement, it does not mean that all Cretans must lie all the time. In fact, Cretans could tell the truth quite often, but still all be liars in the sense that liars are people prone to deception for dishonest gain. Considering that "All Cretans are liars" has been seen as a paradox only since the 19th century, this seems to resolve the alleged paradox. If 'all Cretans are continuous liars' is actually true, then asking a Cretan if they are honest would always elicit the dishonest answer 'yes'. So arguably the original proposition is not so much paradoxical as invalid. A contextual reading of the contradiction may also provide an answer to the paradox. The original phrase, "The Cretans, always liars, evil beasts, idle bellies!" asserts not an intrinsic paradox, but rather an opinion of the Cretans from Epimenides. A stereotyping of his people not intended to be an absolute statement about the people as a whole. Rather it is a claim made about their position regarding their religious beliefs and socio-cultural attitudes. Within the context of his poem the phrase is specific to a certain belief, a context that Callimachus repeats in his poem regarding Zeus. Further, a more poignant answer to the paradox is simply that to be a liar is to state falsehoods, nothing in the statement asserts everything said is false, but rather they're "always" lying. This is not an absolute statement of fact and thus we cannot conclude there's a true contradiction made by Epimenides with this statement. |
論理的パラドックス トーマス・ファウラー(1869年)はこのパラドックスを次のように述べている:「クレタ人のエピメニデスは『クレタ人は皆嘘つきだ』と言う。しかしエピ メニデス自身もクレタ人である。したがって彼自身も嘘つきである。しかし彼が嘘つきならば、彼の言うことは真実ではなく、結果としてクレタ人は真実を語る 者となる。だがエピメニデスはクレタ人であり、したがって彼の言うことは真実である。クレタ人は嘘つきだと述べることで、エピメニデス自身が嘘つきとな り、彼の言うことは真実ではない。こうして我々は交互に、エピメニデスとクレタ人が真実を語る者と嘘つきであることを証明し続けられる。」[3] この主張が偽であり、エピメニデスが「すべてのクレタ人は嘘つきである」と嘘をついていると仮定すれば、少なくとも一人の正直なクレタ人が存在しなければ ならない。このクレタ人がエピメニデスである必要はないため、矛盾は生じない。つまりエピメニデスは、少なくとも一人の正直なクレタ人を知りつつ、この特 定のクレタ人については嘘をつきながら、『全てのクレタ人は嘘つきである』という虚偽の主張を述べ得る。したがって、この主張が虚偽であるという前提か ら、その主張が真実であるとは導かれない。こうして『全てのクレタ人は嘘つきである』という主張を、嘘をつくクレタ人であるエピメニデスによる虚偽の主張 と見なすことで、パラドックスを回避できるのだ。[4] トーマス・ファウラー(及び多くの人民)が犯した誤りは、「クレタ人は皆嘘つきである」の否定が「クレタ人は皆正直である」(これは逆説となる)と考えら れた点にある。実際の否定は「正直なクレタ人が存在する」あるいは「クレタ人は皆嘘つきではない」である。エピメニデスのパラドックスは、上述の解決法 (エウブリデスの最初のパラドックスに見られるような)を許容せず、代わりに回避不可能な自己矛盾に導くよう、わずかに修正できる。エピメニデスの問題の パラドクサルの変種は、より困難な論理的問題群(嘘つきパラドックス、ソクラテスのパラドックス、ブラーリ=フォルティのパラドックスなど)と密接に関連 しており、これら全てはエピメニデスと同様に自己言及性を共有している。エピメニデスのパラドックスは通常、嘘つきパラドックスの変種として分類され、両 者は区別されないこともある。自己言及の研究は、20世紀の論理学と数学における重要な発展をもたらした。 言い換えれば、「すべてのクレタ人は嘘つきである」が偽であるということは、「すべてのクレタ人が正直である」という前提ではなく、「すべてのクレタ人が嘘つきであるわけではない」ことを意味するだけだと気づけば、それはもはやパラドックスではない。 より正確に言えば、「クレタ人は皆嘘つきである」という命題が真である場合、全てのクレタ人が常に嘘をついている必要はない。実際、クレタ人は頻繁に真実 を語るかもしれないが、それでも「不誠実な利益を得るために欺瞞に走る人々」という意味では、全員が嘘つきと言えるのだ。「クレタ人は皆嘘つきだ」がパラ ドックスと見なされるようになったのは19世紀以降であることを考慮すると、この議論は問題とされる矛盾を解消するようだ。もし「クレタ人は皆、継続的に 嘘をつく」という主張が実際に真実なら、クレタ人に「あなたは正直か」と尋ねても、常に不誠実な答え「はい」が返ってくる。したがって、元の命題はパラ ドックスというよりむしろ無効だと言える。 文脈に基づく矛盾の解釈も、このパラドックスへの答えとなり得る。元の表現「クレタ人は常に嘘つき、邪悪な獣、怠惰な腹持ちめ!」は本質的な矛盾ではな く、エピメニデスによるクレタ人への見解を主張している。これは民族全体に対する絶対的な主張ではなく、ステレオタイプ化された見方だ。むしろ彼らの宗教 的信念や社会文化的態度に関する主張である。彼の詩の文脈では、この表現は特定の信仰に限定されており、カリマコスがゼウスに関する詩で繰り返す文脈と一 致する。さらに、この逆説に対するより核心的な答えは、嘘つきとは虚偽を述べる者であり、この主張は「常に」嘘をついていると述べているだけで、発言の全 てが虚偽だと断言しているわけではない。これは絶対的な事実の表明ではないため、エピメニデスのこの発言に真の矛盾があるとは結論づけられない。 |
| Origin of the phrase Epimenides was a 6th-century BC philosopher and religious prophet who, against the general sentiment of Crete, proposed that Zeus was immortal, as in the following poem: They fashioned a tomb for thee, O holy and high one The Cretans, always liars, evil beasts, idle bellies! But thou art not dead: thou livest and abidest forever, For in thee we live and move and have our being. — Epimenides, Cretica Denying the immortality of Zeus, then, was the lie of the Cretans. The phrase "Cretans, always liars" was quoted by the poet Callimachus in his Hymn to Zeus, with the same theological intent as Epimenides: O Zeus, some say that thou wert born on the hills of Ida; Others, O Zeus, say in Arcadia; Did these or those, O Father lie? -- "Cretans are ever liars". Yea, a tomb, O Lord, for thee the Cretans builded; But thou didst not die, for thou art for ever. — Callimachus, Hymn I to Zeus |
この言葉の由来 エピメニデスは紀元前6世紀の哲学者であり宗教的預言者で、クレタ島の一般的な見解に反し、ゼウスは不死であると主張した。次の詩のように: 聖なる高き者よ、汝のために墓を築いた クレタ人どもは、常に嘘つきで邪悪な獣、怠惰な腹持ちめ! だが汝は死んでおらず 汝は生き 永遠に存続する 我らは汝の中に生き 動き 存在しているのだから ―エピメニデス『クレティカ』 つまりゼウスの不死性を否定することこそが、クレタ人の嘘だったのだ。 「クレタ人は常に嘘つき」という表現は、詩人カリマコスが『ゼウス賛歌』で引用したもので、エピメニデスと同じ神学的意図を持っていた: おおゼウスよ、ある者は汝がイダ山の丘で生まれたと言う おおゼウスよ、別の者はアルカディアで生まれたと言う 父よ、どちらが嘘をついているのか?――「クレタ人は常に嘘つき」 ああ、主よ、クレタ人は汝のために墓を築いた。 だが汝は死ななかった、汝は永遠なる者だからだ。 ―カッリマコス『ゼウスへの第一の賛歌』 |
| Emergence as a logical contradiction The logical inconsistency of a Cretan asserting all Cretans are always liars may not have occurred to Epimenides, nor to Callimachus, who both used the phrase to emphasize their point, without irony, perhaps meaning that all Cretans lie routinely, but not exclusively. In the 1st century AD, the quote is mentioned by the author of the Epistle to Titus as having been spoken truly by "one of their own prophets." "One of Crete's own prophets has said it: 'Cretans are always liars, evil brutes, idle bellies'. He has surely told the truth. For this reason correct them sternly, that they may be sound in faith instead of paying attention to Jewish fables and to commandments of people who turn their backs on the truth." — Epistle of Paul to Titus, 1:12–14 Clement of Alexandria, in the late 2nd century AD, fails to indicate that the concept of logical paradox is an issue: In his epistle to Titus, Apostle Paul wants to warn Titus that Cretans don't believe in the one truth of Christianity, because "Cretans are always liars". To justify his claim, Apostle Paul cites Epimenides. — Stromata 1.14 During the early 4th century, Saint Augustine restates the closely related liar paradox in Against the Academicians (III.13.29), but without mentioning Epimenides. In the Middle Ages, many forms of the liar paradox were studied under the heading of insolubilia, but these were not explicitly associated with Epimenides. Finally, in 1740, the second volume of Pierre Bayle's Dictionnaire Historique et Critique explicitly connects Epimenides with the paradox, though Bayle labels the paradox a "sophisme".[5] |
論理的矛盾としての出現 「クレタ人は皆嘘つきだ」と主張するクレタ人自身の論理的不整合は、エピメニデスにもカリマコスにも気づかなかったかもしれない。両者とも皮肉抜きでこの言葉を用い、おそらく「クレタ人は日常的に嘘をつくが、例外もある」という意味で強調したのだろう。 紀元1世紀、この引用は『テトスへの手紙』の著者によって「彼ら自身の預言者の一人」が真実を語ったものとして言及されている。 「クレタの預言者の一人がこう言った。『クレタ人は常に嘘つきで、悪しき獣、怠惰な腹持ちだ』 彼は確かに真実を語った。ゆえに厳しく戒めよ。ユダヤ人の作り話や、真理に背を向ける人々、すなわち人々自身の教えに耳を傾ける代わりに、信仰において健全であるように。」 — パウロのテトスへの手紙 1:12–14 アレクサンドリアのクレメンスは、紀元2世紀後半において、論理的パラドックスの概念が問題であることを示していない: 使徒パウロはテトスへの書簡で、クレタ人はキリスト教の唯一の真理を信じていないとテトスに警告しようとしている。なぜなら「クレタ人は常に嘘つきだから」だ。この主張を正当化するため、使徒パウロはエピメニデスを引用している。 ―『ストロマータ』1.14 4世紀初頭、聖アウグスティヌスは『アカデメイア派への反論』(III.13.29)で、これと密接に関連する嘘つきパラドックスを再述するが、エピメニデスには言及していない。 中世においては、様々な形の嘘つきパラドックスが「不可解な問題」として研究されたが、これらはエピメニデスと明示的に結びつけられることはなかった。 ついに1740年、ピエール・ベールの『歴史的・批判的辞典』第2巻において、エピメニデスとこのパラドックスが明示的に結びつけられた。ただしベールはこのパラドックスを「詭弁」と呼んでいる。[5] |
| References by other authors All of the works of Epimenides are now lost, and known only through quotations by other authors. The quotation from the Cretica of Epimenides is given by R.N. Longenecker, "Acts of the Apostles", in volume 9 of The Expositor's Bible Commentary, Frank E. Gaebelein, editor (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Corporation, 1976–1984), page 476. Longenecker in turn cites M.D. Gibson, Horae Semiticae X (Cambridge: Cambridge University Press, 1913), page 40, "in Syriac". Longenecker states the following in a footnote: The Syr. version of the quatrain comes to us from the Syr. church father Isho'dad of Merv (probably based on the work of Theodore of Mopsuestia), which J.R. Harris translated back into Gr. in Exp ["The Expositor"] 7 (1907), p 336.[6] An oblique reference to Epimenides in the context of logic appears in "The Logical Calculus" by W. E. Johnson, Mind (New Series), volume 1, number 2 (April, 1892), pages 235–250. Johnson writes in a footnote, Compare, for example, such occasions for fallacy as are supplied by "Epimenides is a liar" or "That surface is red," which may be resolved into "All or some statements of Epimenides are false," "All or some of the surface is red." The Epimenides paradox appears explicitly in "Mathematical Logic as Based on the Theory of Types", by Bertrand Russell, in the American Journal of Mathematics, volume 30, number 3 (July, 1908), pages 222–262, which opens with the following: The oldest contradiction of the kind in question is the Epimenides. Epimenides the Cretan said that all Cretans were liars, and all other statements made by Cretans were certainly lies. Was this a lie? In that article, Russell uses the Epimenides paradox as the point of departure for discussions of other problems, including the Burali-Forti paradox and the paradox now called Russell's paradox. Since Russell, the Epimenides paradox has been referenced repeatedly in logic. Typical of these references is Gödel, Escher, Bach by Douglas Hofstadter, which accords the paradox a prominent place in a discussion of self-reference. It is also believed that the "Cretan tales" told by Odysseus in The Odyssey by Homer are a reference to this paradox. In The Second Sex (1949) Simone de Beauvoir writes "I think certain women are still best suited to elucidate the situation of women. It is a sophism to claim that Epimenides should be enclosed within the concept of Cretan and all Cretans within the concept of liar: it is not a mysterious essence that dictates good or bad faith to men and women".[7] |
他の著者による引用 エピメニデスの著作は全て現存せず、他の著者の引用を通じてのみ知られる。エピメニデスの『クレティカ』からの引用は、R.N. ロングネッカー著『使徒言行録』(『解説聖書注解』第9巻、フランク・E・ゲーベライン編、グランドラピッズ、ミシガン州:ゾンダーヴァン社、1976- 1984年)476ページに収録されている。ロンゲネッカーはさらにM.D.ギブソンの『Horae Semiticae X』(ケンブリッジ大学出版局、1913年)40頁「シリア語で」を引用している。ロンゲネッカーは脚注で次のように述べている: この四行詩のシリア語訳は、シリア教父メルブのイショダド(おそらくモプスエスティアのテオドロスの著作に基づく)によって伝えられ、J.R.ハリスが『エクスポジター』7号(1907年)336頁でギリシャ語に逆訳したものである。[6] 論理学の文脈におけるエピメニデスへの間接的な言及は、W. E. ジョンソンの『論理計算』(『マインド』新シリーズ第1巻第2号、1892年4月、235-250頁)に見られる。ジョンソンは脚注で次のように記している: 例えば「エピメニデスは嘘つきである」や「あの表面は赤い」といった誤謬の機会を比較してみよ。これらは「エピメニデスの主張の全てまたは一部は偽である」「表面の全てまたは一部は赤い」と分解できる。 エピメニデスの逆説は、バートランド・ラッセルの『類型論に基づく数学的論理学』(『アメリカ数学雑誌』第30巻第3号、1908年7月、222–262頁)に明示的に登場する。同論文は次のように始まる: この種の最も古い矛盾はエピメニデスの逆説である。クレタ人エピメニデスは「全てのクレタ人は嘘つきである」と述べた。またクレタ人が発した他の全ての主張は確かに嘘であった。これは嘘だったのか? 同論文でラッセルは、エピメニデスの逆説を出発点として、ブラーリ=フォルティの逆説や現在ラッセルの逆説と呼ばれる問題など、他の論題の議論を展開して いる。ラッセル以降、エピメニデスの逆説は論理学において繰り返し言及されてきた。こうした言及の典型がダグラス・ホフスタッターの『ゲーデル、エッ シャー、バッハ』であり、自己言及の議論においてこのパラドックスを重要な位置に置いている。 またホメロスの『オデュッセイア』でオデュッセウスが語る「クレタ島の物語」も、このパラドックスへの言及であると考えられている。 シモーヌ・ド・ボーヴォワールは『第二の性』(1949 年)でこう記している。「女性の状況を解明するのに、今なお女性こそが最も適していると思う。エピメニデスは『クレタ人』という概念に、また全てのクレタ 人は『嘘つき』という概念に包含されるべきだと主張するのは詭弁だ。男女に善意か悪意かを決定づけるのは、神秘的な本質などではない」[7] |
| Notes a. Greek: Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται |
注記 a. ギリシャ語: Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται |
| 1.
Diels-Kranz: Die Fragmente der Vorsokratiker, 2005, I 3B1 (a fragment
attributed to Epimenides and quoted by Clement of Alexandria). 2. Ptolemaeus Chennus, New History Book 5, as epitomized by Patriarch Photius in Myriobiblon 190.36 3. Fowler, Thomas (1869). The Elements of Deductive Logic (3rd ed.). Oxford: Clarendon Press. p. 163. Retrieved 1 April 2011. epimenides. 4. "wolfram.com". 5. Bayle, Pierre (1740). Dictionnaire Historique et Critique. Vol. 2 (5th ed.). p. 414. Retrieved 1 April 2011. Dictionnaire Historique et Critique at Wikipedia. 6. Harris, J. Rendel (April 1907). "A further note on the Cretans". The Expositor, Seventh Series. 3: 332–337. Retrieved 9 April 2020. 7. de Beauvoir, Simone (2009). The Second Sex. Jonathan Cape. p. 15. |
1. ディールス=クランツ編『前ソクラテス派哲学者断章集』2005年版、I巻3B1(エピメニデスに帰せられる断章で、アレクサンドリアのクレメンスが引用したもの)。 2. プトレマイオス・ケヌス『新歴史』第5巻。パトリアルコス・フォティオスが『ミリオビブロン』190.36で要約したもの。 3. ファウラー、トーマス(1869年)。『演繹論理学の要素』(第3版)。オックスフォード:クラレンドン・プレス。p. 163。2011年4月1日取得。エピメニデス。 4. 「wolfram.com」 5. ピエール・ベイル(1740年)『歴史的・批判的辞典』第2巻(第5版)414頁。2011年4月1日取得。Wikipedia「歴史的・批判的辞典」 6. ハリス、J. レンデル(1907年4月)。「クレタ人に関するさらなる注記」。『エクスポジター』第7シリーズ。3: 332–337。2020年4月9日取得。 7. ド・ボーヴォワール、シモーヌ(2009)。『第二の性』。ジョナサン・ケープ。p. 15。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Epimenides_paradox |
|
| A paradox
is a logically self-contradictory statement or a statement that runs
contrary to one's expectation.[1][2] It is a statement that, despite
apparently valid reasoning from true or apparently true premises, leads
to a seemingly self-contradictory or a logically unacceptable
conclusion.[3][4] A paradox usually involves
contradictory-yet-interrelated elements that exist simultaneously and
persist over time.[5][6][7] They result in "persistent contradiction
between interdependent elements" leading to a lasting "unity of
opposites".[8] In logic, many paradoxes exist that are known to be invalid arguments, yet are nevertheless valuable in promoting critical thinking,[9] while other paradoxes have revealed errors in definitions that were assumed to be rigorous, and have caused axioms of mathematics and logic to be re-examined. One example is Russell's paradox, which questions whether a "list of all lists that do not contain themselves" would include itself and showed that attempts to found set theory on the identification of sets with properties or predicates were flawed.[10][11] Others, such as Curry's paradox, cannot be easily resolved by making foundational changes in a logical system.[12] Examples outside logic include the ship of Theseus from philosophy, a paradox that questions whether a ship repaired over time by replacing each and all of its wooden parts one at a time would remain the same ship.[13] Paradoxes can also take the form of images or other media. For example, M. C. Escher featured perspective-based paradoxes in many of his drawings, with walls that are regarded as floors from other points of view, and staircases that appear to climb endlessly.[14] Informally, the term paradox is often used to describe a counterintuitive result. |
パ
ラドックスとは、論理的に自己矛盾する主張、あるいは予想に反する主張である[1][2]。真または真に見える前提から一見妥当な推論を経ても、自己矛盾
あるいは論理的に受け入れがたい結論に至る主張を指す[3][4]。パラドックスは通常、矛盾しつつも相互に関連する要素が同時に存在し、時間を超えて持
続する現象を伴う[5][6]。[7] それらは「相互依存する要素間の持続的な矛盾」をもたらし、永続的な「対立物の統一」へと至る。[8] 論理学においては、無効な議論と知りつつも批判的思考を促進する上で価値あるパラドックスが数多く存在する。[9] 一方、厳密と想定されていた定義の誤りを暴き、数学や論理学の公理の再検討を促したパラドックスもある。一例がラッセルパラドックスである。これは「自身 を含まない全てのリストのリスト」が自身を含むかどうかを問い、集合を性質や述語と同一視する集合論の基礎付けが欠陥を抱えていることを示した。[10] [11] カリーパラドックスのような他の例は、論理体系の基礎的変更によって容易に解決できない。[12] 論理学以外の例としては、哲学におけるテセウスの船がある。これは、船の木製部品を一つずつ交換しながら修理を続けた場合、その船が依然として同じ船であ るかという疑問を投げかけるパラドックスだ。[13] パラドックスは画像や他の媒体の形で現れることもある。例えば、M・C・エッシャーは多くの作品で遠近法に基づくパラドックスを描いた。ある視点では床に 見える壁が別の視点では床となり、階段が無限に上り続けるように見えるものだ。[14] 非公式には、直感に反する結果を「パラドックス」と呼ぶことが多い。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Paradox |
パラドックスと呼ばれるものの一般的な構造(左側)、そして解決の基本的な三つのパターン(右側)[1]。図では示されていないが、前提には明示されるものと、そうでないものがある。パラドックスを取り扱う際は、明示されていない前提にも注意を払っていく必要がある。
Vicious circularity illustrated
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099