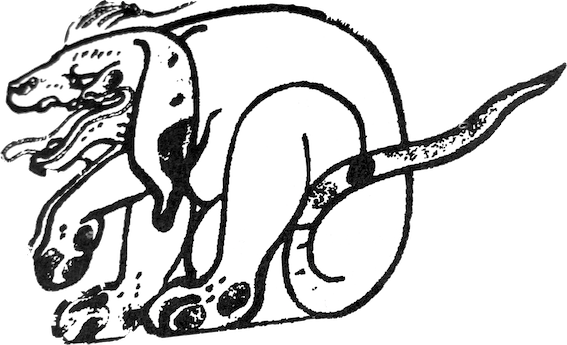
医療人類学の11のキーコンセプト
Eleven Key Concepts in Medical Anthropology
☆医療人類学の11のキーコンセプトを提示しよう。このキーコンセプトは伏木信次ほか編『生命倫理と医療倫理』金芳堂(2020-2026)のなかで記載されているものである。
| 1. 医療人類学 |
|
| 医
学と人類学を架橋する学問を医療人類学と呼ぶ。この学問には3つの目標がある。それは(1)人間の健康や病気という現象に、その人びとが属している文化や
社会はどのように関わっているか、(2)過去の人間の健康や病気という現象は今と違っているか。もし違っていたらなぜそうなるのか、共通しているのであれ
ば、その理由はなにか、そして(3)人間の健康や病気を扱う現象は歴史的にも空間的にも異なる文化や歴史で、これまでどれくらい多様であるのか、また、そ
れらの未来はどのようなものか、などという問題関心をもつ。 |
|
| 2. 生物-心理-社会モデル |
|
| バ
イオメディシン(生物医学)が、あまりにも生物学的着想と技術に傾斜しすぎているためにジョージ・エンゲルは1977
年『サイエンス』誌において「新しい医療モデルの必要性:生物医学への挑戦」という論文を書き,自然科学中心の「疾病」に過度に焦点化した生物医学に対し
て、《生物-心理-社会モデル》の優位性を強調した。これは、人間は生物学的実体であると同時に、心をもつ個人であり、また帰属する社会や文化にも影響を
受けるという全体論的な人間観にもとづく医療・保健の見方である。 |
|
| 3. 文化 |
|
| 文
化とは,人間が後天的に学ぶことができ,集団が創造し継承している認識と実践のゆるやかな「体系」ないしは,そう理解できる概念上の構築物のこと。人間の
社会的活動,およびその産物とされている。ある文化に属する人および集団は、その社会の文化を当たり前のものとして受け入れることができるが、異なる文化
に属する人は、それに無関心であったり、時には嫌悪感を覚えたりする。つまり倫理観や道徳観は、その人の属する社会の文化と関連する。 |
|
| 4. 文化的感受性 |
|
| 保健に関わる専門家の仕事において重要なことは,患者の文化的背景,知識水準や意図を事前に十分に把握し,状況に応じて反応の観察や対話を通して,適切な保健に関わる活動(医療・看護・介護福祉)を柔軟に行うことにある。 |
|
| 5. 文化的ステレオタイプ |
|
| 相
手の文化を深く理解することなく、他者の行動や考え方を一方的に決めつけることを「文化的ステレオタイプ」と呼ぶ。文化的ステレオタイプは,自文化中心主
義から生まれることが多く,また,異文化・異民族への差別の偏見の原因になるものもある。自文化中心主義とは、自分の属している社会の価値や規範を最上の
ものとみなし、他者の文化を低く見下す態度である。その反対語は、文化相対主義とよぶ(→7.倫理的相対主義を参照) |
|
| 6. 多元的医療システム |
|
| 世界の医療は西洋近代医療だけでない。西洋近代医療が生まれる前には、
西洋でも伝統医療が占める部分が多く、また、家庭菜園などの薬草の伝統は伝統社会のみならず西洋近代社会にも残っている。人びとの病気の治療と健康維持に
関わる制度や考え方が複数あり、それが共存していることを多元的医療システム(あるいは医療的多元論)という。また、それらの利用者たちが、複数の医療シ
ステム横断的に使っている(例:西洋近代医療のがん治療を受けているひとが、漢方薬や除痛のための鍼治療を受ける)場合、それを多元的医療行動とよぶ。 |
|
| 7. 倫理的相対主義 |
|
| 他者に対して、自己とは異なった存在であることを容認し、自分たちの価値や見解において問われていないことがらを問い直し、他者に対する理解と対話をめざす倫理的態度のことを倫理的相対主義と呼ぶ。倫理的普遍主義の反対語である。 |
|
| 8. 倫理的普遍主義 |
|
| 人間の道徳は単一ないしは限られた原理から導き出せるという立場を倫理的普遍主義と呼ぶ。この立場は西洋社会で長く議論されてきたので、異文化や少数派の態度を認めない傾向にあるのでしばしば西洋中心主義と批判される(→9.西洋倫理学の3つの伝統)。 |
|
| 9. 西洋倫理学の3つの伝統 |
|
| 西洋倫理学には大きく分けて3つの伝統がある。まず、(i)その人が
持っている徳という属性で判断して、どのようなタイプのものが、徳があるつまり人の道(=倫理)に叶っていると判断する「徳の倫理学」(アリストテレ
ス)。(ii)自分の考えが普遍法則であると考え、かつそのように意欲することを自分の行為原則としなさいという「義務論」(カント)。(iii)ある行
為が正しく望ましいと言えるのは、その行為の結果が生み出す効用(=有用性)によって決まるのだという「功利主義の倫理学」(ベンサム)である。1970
年代にはじまる生命倫理学は、このような論理から入る倫理をいったん棚上げする。そして、脳死や臓器移植、インフォームドコンセント、安楽死など具体的な
問題から倫理を考えた。そのような発想法の展開を「経験的転回(empirical turn)」と言われる。 |
|
| 10. 医療人類学者が考える相対的倫理 |
|
| 医療人類学者は倫理的相対主義(→7.)の立場に立ち、自分が調査して
いる異文化の社会の基準に合わせて文化現象を描こうとする。ただし、完全に相手の文化に合わせるがあまり、自分の文化を忘れるというものではなく、最終的
に自分のもつ文化との距離や乖離に自覚的になり、読者(第三者)に説明する責務を貫くことを理想的な態度とする。したがって、医療人類学者が描く、人々の
倫理や道徳は、西洋倫理学の伝統のように合理的推論や思考実験よりも、経験的調査(→11.)にもとづく事例の分析や解説を通して倫理的相対主義を通して
描かれることが多い。 |
|
| 11. 質的調査法 |
|
| 医療人類学者の研究は、量的な研究よりも、訪問調査によるインタビュー
や、長期の住み込み調査による参与観察による質的研究の比重が高い。それらの調査をとおして、人々の生活や制度などの全般的な記述すなわちエスノグラ
フィー(民族誌)を書くことができるのは、質的調査法を駆使したフィールドノートや録音や録画記録を手がかりにすることができるからである。 |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099