
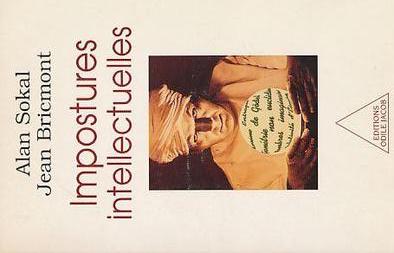 ☆
☆ ☆
☆

ファッショナブルなセンスとナンセンス
Fashionable Sense and Nonsense

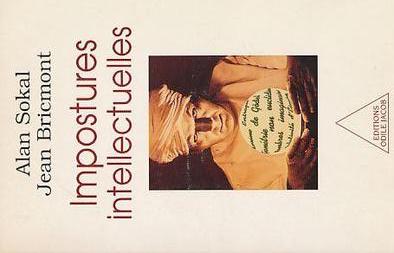 ☆
☆ ☆
☆

☆ アラン・ソーカルとジャン・ブリクモンが、最初はフランス語(1997)で、その後に英語(1998)で、ポストモダンと称する哲学者や思想家が〈よく理 解もできないくせに〉自然科学や数学のメタファーを使って議論しているのはケシカラン(=怪しからん)として、代表的な思想家の著作を摘んで、〈そーら、 理解がめちゃくちゃでしょう、支離滅裂でしょう?〉と揶揄した本。彼らは、この本が、そのまま出版されると、他のポスモ(=ポストモダンを小馬鹿にする ジャーゴン)のジャンク本と一緒くたにされて、話題にならないと(思われる)判断され市場で売れないことを危惧して、刊行前に一発大逆転の仕掛けを拵(こ しら)えた。
★ それが、アメリカのカルスタ(=これもカルチュラル・スタディーズ研究を揶揄する外野からのレッテル)の著名雑誌『ソーシャル・テキスト』に「境界を侵犯 すること:量子重力の変換解釈学に向けて」をアラン・ソーカルが投稿し、査読を経て、見事掲載とあいなったわけである。この論文の主要テーゼは「解放的科 学は数学の根本原理の深遠なる変革なしには成し遂げられない」というものである。常識的に、そもそも〈解放的科学〉ってのが、怪しいし、また〈深遠なる変 革〉という言葉もなかなかニューエイジ風で、ポストモダン研究者でも、〈そりゃ怪しいやろ〉と思うような代物だが、いずれせよ、覆面査読者の面目丸つぶ れ、編集委員会に泥を塗ったようなものである。もちろん、これらが、博士課程院生やポスドクで、その分野の就職したいと希望する若い人に書かれたら、それ はそれで、筋は通るものだ。しかし、問題は、投稿者のソーカル自身が(そのアイディアや使っているレトリックは)『知的詐欺(フランス語版原題)』におい て「ぜんぶでっちあげ」と確信犯的に表明したしたものだから、日頃からポスモの著作に不審感を抱いていた多くの読書家を悦ばしめた。
☆ よーするに、ソーカルとブリクモンは、ポスモという〈裸の王様〉に、「王様は裸だ」と言わしめたわけなので、当のポスモ系の思想家は、1)何もわからない 自然科学者のバカな揶揄で、『ソーシャル・テクスト』誌もはためいわくだけど、擁護には至らず、せいぜい〈アホな匿名の査読者よ、まんまと騙されたね〉と 冷笑するか、2)ソーカルはまじめに、支離滅裂な議論をするポストモダン思想界の研究者を騙すとはけしからん。それに、自然科学者でも、詐欺を前提に詐術 を働くのは、それそのものが「研究不正」だと息巻いた。ただし、後者の人でも、やはり、論文の内容は及第点だろうが、擁護すれば、自分のバカも証明されて しまうので、「学術発表行為への裏切り」つまり「知的詐欺」は、ポスモのバカな研究者ではなく、首謀者ソーカルと付和雷同のブリンクモンだろと見下した。 つまり、ソーカルの行為をあっぱれと言うものはおらず、かといって、彼を学術界から追放にちかい扱いをすべきという意見も出てこなかったので、結果的に ソーカルとブリクモンは、20世紀末の学術道化に終わってしまった。ニューミレニアムに入り、ジュリアン・バジーニとジェレミー・スタンルームという哲学 的啓蒙家が『哲学者は何を考えているのか』(2006[2003])が、ソーカルに(大胆勇敢にも)インタビューをしてその消息を伝えている(バジーニとス タンルーム 2003)。
★ ソーカルは自分たちの告白録『知的詐欺』のフランス語版の公刊の11 年後に『だましを超えて(Beyond the Hoax)』という、柳の下の2匹 目の「どぜう」を狙って自らの「知的犯罪」のクロニクルたる著作を出版したが、その時にはすでにブームも過ぎ去り、それほど注目されることはなかった。骨 太のジャーナリズムあるいは自然科学ではなくて、フェイクでチープなアカデミック・バラック・ジャーナリズムのなれの果てを見るようである。良い子は真似 をしてはいけません。
☆結
局、研究者という生き物は、どうも同僚や人民を騙すことに長けているようで、「不平不満研究」のほうは、もっと組織的な知的詐術によって、いくつかの学術
誌を騙して、掲載の栄誉を獲得し、その後に「詐術」であることを表明し、結局、論文そのものは(プロジェクトに関わる研究者の予想どおり)取り下げ、社会
の木鐸を大いに本人たちは鳴らしたが、それにくらべて、社会と学術界は、その苦い経験がから、何も学んでいないように思える。
| Fashionable
Nonsense, by Wiki in English |
「知」の欺瞞(ウィキペディア日本語) |
| Fashionable Nonsense: Postmodern
Intellectuals' Abuse of Science (1998; UK: Intellectual Impostures),
first published in French in 1997 as Impostures intellectuelles, is a
book by physicists Alan Sokal and Jean Bricmont.[1] As part of the
so-called science wars, Sokal and Bricmont criticize postmodernism in
academia for the misuse of scientific and mathematical concepts in
postmodern writing. The book was published in English in 1998, with revisions to the original 1997 French edition for greater relevance to debates in the English-speaking world.[2] According to some reports, the response within the humanities was "polarized";[3] critics of Sokal and Bricmont charged that they lacked understanding of the writing they were scrutinizing. By contrast, responses from the scientific community were more supportive. Similar to the subject matter of the book, Sokal is best known for his eponymous 1996 hoaxing affair, whereby he was able to get published a deliberately absurd article that he submitted to Social Text, a critical theory journal.[4] The article itself is included in Fashionable Nonsense as an appendix.[5] |
『「知」
の欺瞞――ポストモダン思想における科学の濫用』(ちのぎまん ポストモダンしそうにおけるかがくのらんよう、英: Fashionable
Nonsense: Postmodern Intellectuals' Abuse of Science, 仏: Impostures
Intellectuelles)は、物理学者のアラン・ソーカルとジャン・ブリクモンの著書。ソーカルはいわゆるソーカル事件で知られている。学術誌の
ソーシャル・テクストに意図的に無意味な論文を投稿し、そしてそれが実際に掲載されてしまったのである[1][2]。 この本がフランス語で出版されたのは1997年である(英語版はその翌年の1998年)。英語圏での議論へ周到にそなえ、英語版は書き改められている [3]。本書はサイエンス・ウォーズと呼ばれる論争の一部であり、ポストモダンの著作において科学や数学の概念が誤用されていると考えたソーカルとブリク モンは、学問の世界におけるポストモダニズムをおおいに批判している。二人の批判は、自分でも理解していないことを書いているポストモダニストの告発で あった。科学者コミュニティからの反応はおおむね好意的であった。人文学者による本書への反応は「二分」されたともいわれている[注釈 1]。 |
| Summary Fashionable Nonsense examines two related topics: the allegedly incompetent and pretentious usage of scientific concepts by a small group of influential philosophers and intellectuals; and the problems of cognitive relativism—the idea that "modern science is nothing more than a 'myth', a 'narration' or a 'social construction' among many others"[1]—as found in the Strong programme in the sociology of science. |
要約 『「知」の欺瞞』は、隣接する2つのテーマを分析している。 非常に影響力をもった哲学者や知識人には、科学的概念の不完全かつ欺瞞的な使い方をしている者がいないか 認識的相対主義の問題、つまり「現代科学は『神話』や『物語』、『社会的構築物』以上の何かではない」(科学社会学におけるストロング・プログラム(英語版)にみられるような)という立場について |
| Incorrect use of scientific
concepts versus scientific metaphors The stated goal of the book is not to attack "philosophy, the humanities or the social sciences in general", but rather "to warn those who work in them (especially students) against some manifest cases of charlatanism."[1]: 5 In particular, the authors aim to "deconstruct" the notion that some books and writers are difficult because they deal with profound and complicated ideas: "If the texts seem incomprehensible, it is for the excellent reason that they mean precisely nothing."[1]: 6 Set out to show how numerous key intellectuals have used concepts from the physical sciences and mathematics incorrectly, Sokal and Bricmont intentionally provide considerably lengthy extracts in order to avoid accusations of taking sentences out of context. Such extracts pull from such works as those of Jacques Lacan, Julia Kristeva, Paul Virilio, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Luce Irigaray, Bruno Latour, and Jean Baudrillard, who—in terms of the quantity of published works, invited presentations, and of citations received—were some of the leading academics of continental philosophy, critical theory, psychoanalysis, and/or the social sciences at the time of publication. The book provides a chapter to each of the above-mentioned authors, "the tip of the iceberg" of a group of intellectual practices that can be described as "mystification, deliberately obscure language, confused thinking and the misuse of scientific concepts."[1]: xi For example, Luce Irigaray is criticised for asserting that E=mc2 is a "sexed equation" because "it privileges the speed of light over other speeds that are vitally necessary to us"; and for asserting that fluid mechanics is unfairly neglected because it deals with "feminine" fluids in contrast to "masculine" rigid mechanics.[6] Similarly, Lacan is criticized for drawing an analogy between topology and mental illness that, in Sokal and Bricmont's view, is unsupported by any argument and is "not just false: it is gibberish."[1]: 23 Sokal and Bricmont claim that they do not intend to analyze postmodernist thought in general. Rather, they aim to draw attention to the abuse of concepts from mathematics and physics, their areas of specialty. Sokal and Bricmont define this abuse as any of the following behaviors: Using scientific or pseudoscientific terminology without bothering much about technical meanings. Importing concepts from the natural sciences into the humanities without justification for their use. Displaying superficial erudition by using technical terms where they are irrelevant, presumably to impress and intimidate non-specialist readers. Manipulating meaningless words and phrases. Self-assurance on topics far beyond the competence of the author and exploiting the prestige of science to give discourses a veneer of rigor. |
科学的概念の不正確な用法か科学的メタファーか 本書の目的は、「哲学、人文科学、あるいは、社会科学一般」を攻撃しようとしているのではなく、「〔それとは正反対で〕明らかにインチキだとわかる物につ いて、この分野に携わる人々(特に学生諸君)に警告を発」することだとソーカルたちは書いている[4]。特に「脱構築」概念について書いている本や思想家 にあてはまる。そこでは深遠かつ難解な思考が繰り広げられているために理解が困難だとされているからである。「テクストが理解不能に見えるのは、他でもな い、中身がないという見事な理由のためだ」[5]。 この本には、ジャック・ラカン、ジュリア・クリステヴァ、ポール・ヴィリリオ、ジル・ドゥルーズ、フェリックス・ガタリ、リュス・イリラガイ、ブルーノ・ ラトゥール、ジャン・ボードリヤールなどの著作から長文の引用が行われている。彼(女)らは、出版物の量だけでなく招待講演、被引用回数からいっても、大 陸哲学、批評理論、精神分析、社会科学といった学問における中心人物であった。ソーカルとブリクモンは、上記の知識人がいかに物理学や数学の概念を不正確 に使用しているかを示そうとする。文脈から切り取られているという批判を避けるために、あえて長文で引用が行われている。 ソーカルたちは、ポストモダニストの思想一般を論じるつもりはないと語る。そうではなく、数学と物理という著者二人が研究や教育のためその生涯をささげてきた学問の科学的概念が濫用されていることを知ってほしいのだという。 ソーカルとブリクモンは、その濫用を次のように定義する[6]。 科学(あるいは疑似科学)的な用語を、それがまさに何を意味しているのか気にすることなく使用すること 自然科学の概念を、最低限の正当化を経ることなく、またそれを用いる理由も提示しないまま、人文科学に持ち込むこと 無関係な文章に恥ずかしげもなく専門用語をちりばめて、博識に見せかけること。おそらく、専門家ではない読者を感心させるだけでなく威圧しようとしている 深遠にみえて実際には無意味な言葉や文章を綴ること 著者の能力をはるかに超えた話題についても自信を持ち、その言説に浅薄な厳密さを加えたいがために、科学について払われている敬意を利用すること 本書では、上記の著者たちにそれぞれ章が割かれ、「神秘的にみせたり、わざとあいまいな言葉遣いをしているもの、乱雑な議論、科学概念の誤用」[7] と呼ばれる、知識人たちの営為からその「氷山の一角」が描かれる。例えば、リュス・イリラガイはE = mc2 が「われわれがそれなしでは生きていけない他のさまざまな速度をさしおいて特権化する」ゆえに、それが「性化された方程式」であると書いた文章が引用さ れ、批判されている(イリラガイについては「流体力学は不当になおざりにされている、なぜなら流体が女性的であるのに対して、固体は男性的であるからだ」 という主張についても批判がされている)[8]。同様に、トポロジーと神経症のあいだにアナロジーを見出すラカンも、ソーカルとブリクモンの見解では何の 根拠もなく数学の用語を用いており、「単に間違っているという代物ではない。意味不明なのだ」[9]。 |
| The postmodernist conception of
science Sokal and Bricmont highlight the rising tide of what they call cognitive relativism, the belief that there are no objective truths but only local beliefs. They argue that this view is held by a number of people, including people who the authors label "postmodernists" and the Strong programme in the sociology of science, and that it is illogical, impractical, and dangerous. Their aim is "not to criticize the left, but to help defend it from a trendy segment of itself."[1]: xii Quoting Michael Albert, [T]here is nothing truthful, wise, humane, or strategic about confusing hostility to injustice and oppression, which is leftist, with hostility to science and rationality, which is nonsense.[1]: xi |
ポストモダニストによる科学の理解 ソーカルとブリクモンは、二人が認識的相対主義と呼ぶ、客観的な真実は存在せず、ただ個々人の信念があるのみだという思想がはびこっていることを強調して やまない。二人によれば、「ポストモダニスト」と呼ばれる人々や科学の社会学におるストロングプログラムの立場をとる人など、多くの人々がこの相対主義を 支持しているが、非論理的で地に足がついておらず、危険な考え方である。本書の狙いは、「左派全体を批判することではなく、流行りにのるその一部から左派 それ自体を守ること」である[3]。英語版の序文ではマイケル・アルバートの言葉が引用されている。「不正と抑圧への敵意つまり左派と、科学と合理性への 敵意つまりナンセンスとを混同することに、正しさや賢さや人間性や戦略性などない」[3]。 |
| Reception Main article: Sokal affair. According to New York Review of Books editor Barbara Epstein, who was delighted by Sokal's hoax, the response to the book within the humanities was bitterly divided, with some delighted and some enraged;[3] in some reading groups, reaction was polarized between impassioned supporters and equally impassioned opponents of Sokal.[3] Support Philosopher Thomas Nagel has supported Sokal and Bricmont, describing their book as consisting largely of "extensive quotations of scientific gibberish from name-brand French intellectuals, together with eerily patient explanations of why it is gibberish,"[7] and agreeing that "there does seem to be something about the Parisian scene that is particularly hospitable to reckless verbosity."[8] Several scientists have expressed similar sentiments. Richard Dawkins, in a review of this book, said regarding the discussion of Lacan:[6] We do not need the mathematical expertise of Sokal and Bricmont to assure us that the author of this stuff is a fake. Perhaps he is genuine when he speaks of non-scientific subjects? But a philosopher who is caught equating the erectile organ to the square root of minus one has, for my money, blown his credentials when it comes to things that I don't know anything about. Noam Chomsky called the book "very important", and said that "a lot of the so-called 'left' criticism [of science] seems to be pure nonsense."[9] Criticism This article's Criticism or Controversy section may compromise the article's neutrality by separating out potentially negative information. Please integrate the section's contents into the article as a whole, or rewrite the material. (June 2023) Limiting her considerations to physics, science historian Mara Beller[10] maintained that it was not entirely fair to blame contemporary postmodern philosophers for drawing nonsensical conclusions from quantum physics, since many such conclusions were drawn by some of the leading quantum physicists themselves, such as Bohr or Heisenberg when they ventured into philosophy.[11] Regarding Lacan Bruce Fink offers a critique in his book Lacan to the Letter, in which he accuses Sokal and Bricmont of demanding that "serious writing" do nothing other than "convey clear meanings".[12] Fink asserts that some concepts which Sokal and Bricmont consider arbitrary or meaningless do have roots in the history of linguistics, and that Lacan is explicitly using mathematical concepts in a metaphoric way, not claiming that his concepts are mathematically founded. He takes Sokal and Bricmont to task for elevating a disagreement with Lacan's choice of writing styles to an attack on his thought, which, in Fink's assessment, they fail to understand. Fink says that "Lacan could easily assume that his faithful seminar public...would go to the library or the bookstore and 'bone up' on at least some of his passing allusions."[12] Similar to Fink, a review by John Sturrock in the London Review of Books accuses Sokal and Bricmont of "linguistic reductionism", claiming that they misunderstood the genres and language uses of their intended quarries.[13] This point has been disputed by Arkady Plotnitsky (one of the authors mentioned by Sokal in his original hoax).[14] Plotnitsky says that "some of their claims concerning mathematical objects in question and specifically complex numbers are incorrect",[15]: 112–3 specifically attacking their statement that complex numbers and irrational numbers "have nothing to do with one another".[1]: 25 Plotnitsky here defends Lacan's view "of imaginary numbers as an extension of the idea of rational numbers—both in the general conceptual sense, extending to its ancient mathematical and philosophical origins...and in the sense of modern algebra."[15]: 146 The first of these two senses refers to the fact that the extension of real numbers to complex numbers mirrors the extension of rationals to reals, as Plotnitsky points out with a quote from Leibniz: "From the irrationals are born the impossible or imaginary quantities whose nature is very strange but whose usefulness is not to be despised."[16] Plotnitsky nevertheless agrees with Sokal and Bricmont that the "square root of −1" which Lacan discusses (and for which Plotnitsky introduces the symbol \scriptstyle (L)\sqrt{-1}) is not, in spite of its identical name, "identical, directly linked, or even metaphorized via the mathematical square root of −1", and that the latter "is not the erectile organ".[15]: 147 Regarding Irigaray While Fink and Plotnitsky question Sokal and Bricmont's right to say what definitions of scientific terms are correct, cultural theorists and literary critics Andrew Milner and Jeff Browitt acknowledge that right, seeing it as "defend[ing] their disciplines against what they saw as a misappropriation of key terms and concepts" by writers such as Jacques Lacan and Luce Irigaray.[17] However, they point out that Irigaray might still be correct in asserting that E = mc2 is a "masculinist" equation, since "the social genealogy of a proposition has no logical bearing on its truth value."[17] In other words, gender factors may influence which of many possible scientific truths are discovered. They also suggest that, in criticising Irigaray, Sokal and Bricmont sometimes go beyond their area of expertise in the sciences and simply express a differing position on gender politics.[17] Derrida In his response, first published in Le Monde as "Sokal and Bricmont Aren't Serious", Jacques Derrida writes that the Sokal hoax is rather "sad", not only because Alan Sokal's name is now linked primarily to a hoax rather than science, but also because the chance to reflect seriously on this issue has been ruined for a broad public forum that deserves better.[18]: 70 Derrida reminds his readers that science and philosophy have long debated their likenesses and differences in the discipline of epistemology, but certainly not with such an emphasis on the nationality of the philosophers or scientists. He calls it ridiculous and weird that there are intensities of treatment by the scientists, in particular, that he was "much less badly treated", when in fact he was the main target of the US press.[18]: 70 Derrida then proceeds to question the validity of their attacks against a few words he made in an off-the-cuff response during a conference that took place thirty years prior to their publication. He suggests there are plenty of scientists who have pointed out the difficulty of attacking his response.[18]: 71 He also writes that there is no "relativism" or a critique of Reason and the Enlightenment in his works. He then writes of his hope that in the future this work is pursued more seriously and with dignity at the level of the issues involved.[18]: 72 |
受容 詳細は「ソーカル事件」を参照 ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス編集部のバーバラ・エプスタインによれば、彼女自身はソーカルの悪戯を歓迎したが、人文科学の内部での本書への反 応は極端に分かれた。喜ぶ者もいれば、怒りを露わにする者もいた[注釈 1]。読書会を開催すると、熱烈な支持者もいれば、同じくらい熱烈にソーカルを批判する者もあらわれ、まさに二分されたという[注釈 1]。 評価 哲学者のトマス・ネーゲルは、本書を評価した。曰くこの本は「フランスの知識人のネームバリューに頼った、意味不明な科学に関する言辞の膨大な引用で出来 ており、なぜそれが無意味なのかについて薄気味悪いほど粘り強く説明してくれる」[10]。さらに、「とりとめない饒舌さをとにかくよしとする、パリ的な 風土についての重要な一冊になっているように思われる」と歓迎している。 同じような好意でもって迎えた科学者の一人が、例えばリチャード・ドーキンスである。彼はこの本を取り上げて、ラカンの議論について以下のように評価している。 ソーカルとブリクモンのような数学的な専門知識を持たない者にも、この手の著者が偽物であることを教えてくれる。おそらく彼は非科学的なテーマについて語るときは天才になるのだろう。しかし、勃起性の器官が − 1 {\displaystyle \scriptstyle {\sqrt {-1}}}と等価であると語る哲学者が、私の知らない分野について何を書こうと、その信用は消し飛んでしまったというのが私の考えだ[11]。 ノーム・チョムスキーもとても重要な本と評価しており、「いわゆる左派にかまびすしい〔科学に対する〕批判は純粋にナンセンスだと思われる」と述べている[12]。 批判 ポストモダンの哲学者や大陸哲学に連なる学者はこの本を批判している。ブルース・フィンクは『「エクリ」を読む』のなかで本書を評して、「真面目な文章」 に「明解な意味を伝える」以上のものを求めないソーカルとブリクモンを批判している[13]。フィンクによれば、ソーカルとブリクモンが恣意的だったり無 意味であると考えた概念は歴史をたどれば言語学にそのルーツを持っており、ラカンも数学的な概念を明らかにメタファーの一種として使っていて、数学的な裏 付けがあると主張しているわけではない。ソーカルとブリクモンがラカンの選択した著述スタイルと相性が合わなかったことをもって、その思想に対する攻撃に まで話を大きくしたことをフィンクは批判しており、また彼の意見では二人はただ理解できなかっただけである。フィンクによれば「真摯なる〔ラカンの〕セミ ネールの読者が、図書館か書店に行くかして、自分の思いついた暗喩のごく一部でも理解しようと一生懸命勉強する姿をラカンは容易に思い浮かべることができ たのである」[13]。同様に、ロンドン・レビュー・オブ・ブックスのジョン・スターロックはソーカルとブリクモンの「言語学的な還元主義」を批判し、二 人が目をつけた相手の分野や使用する言語を誤解していると述べている[14]。 ラカンと複素数 [icon] この節の加筆が望まれています。 (2018年11月) アルカーディ・プロトニツキー(ソーカルのパロディー論文でも言及されたカルチュアル・スタディーズの研究者)も本書を論難している[15]。プロトニツ キーは「問題になっている数学に関する文章についての主張の一部、とくに複素数に関する記述は不正確だ」と語っており[16]、なかでも「虚数と無理数に は何の関係もない」という記述を批判している[17]。彼はラカンの「合理的な数(rational numbers)というアイデアの延長としての虚数」という観点を擁護している。いわく「一般的な概念としてみれば、どちらも古代の数学や哲学に起源をも つが…現代における代数学における概念としても同じことがいえる」[18]。前者については、実数から複素数への拡張は有理数から実数への拡張に酷似して いるという事実に言及し、プロトニツキーはライプニッツの言葉を引用している。いわく「無理数から不可能あるいは空虚な数が生まれた。その性質は非常に不 思議であるが、その有用性については論を俟たない」[19]。 プロトニツキーも、「マイナス1の平方根」に関するラカンの議論についてはソーカルとブリクモンに同意している(そのためにプロトニツキーは ( � ) − 1 {\displaystyle \scriptstyle (L){\sqrt {-1}}}という記号を導入している)。ラカンのいうマイナス1の平方根は、名前こそ同じだが、「数学的なマイナス1の平方根とは同じものでもなく、直 接の関係もなく、メタファーですら」ない[20]。まして数学的なマイナス1の平方根は「勃起性の器官ではない」[20]。 しかし、代数学的な意味においてプロトニツキーは「すべての虚数および複素数は、定義上は無理数である」と述べているが、数学者たちは複素数を無理数とは みなさないソーカルとブリクモンの側に立っている[21][22][23]。実際、有理数という概念は、ガウス整数とガウス有理数においては複素数の領域 に拡張される。 その他の批判 ソーカルとブリクモンが科学的用語の定義の正しさを語ることの権利について疑問を呈したフィンクとプロトニツキーに対して、文化理論研究者で文芸批評家の アンドリュー・ミルナーとジェフ・ブロウィッツはその権利を否定せず、ラカンやイリラガイのような書き手によって「鍵となる用語や概念の不適切な使用が行 われているとみなすことができるだけの専門的訓練を二人が受けていることを認めている」[24]。一方で、ミルナーたちはリュス・イリラガイによる E = mc2 が「男性的」な方程式であるという主張はそれでも正しい可能性があると指摘する。なぜなら「ある命題の社会における系譜は、その真偽とは論理的に無関係 に」たどることができるからである[24]。言い換えると、ジェンダーという要素は今後発見されうる無数の科学的真理のいずれかに影響を与えるのである。 ミルナーたちは、イリラガイを批判するソーカルとブリクモンが時に科学における自分たちの専門領域を飛び越えて、単にジェンダーの政治学において異なる立 場にあることを表明しているだけである可能性を示唆している[24]。 ル・モンド紙に最初に掲載されたジャック・デリダの「ソーカルとブリクモンは真面目じゃない」において、デリダはソーカルのパロディー論文はむしろ「悲し むべき」であると述べている。なぜならアラン・ソーカルという名前はいまや科学ではなくこの種のジョークを連想させるものになっただけでなく、この問題は もっと社会的に開かれた場で取り上げるべきであったのに、ソーカル事件のせいで真面目に語られるチャンスが台無しになってしまったからである[25]。認 識論において科学と哲学はその類似点と相違点が長年にわたって議論されてきたこと、そのなかで哲学者や科学者の国籍、国民性が問題になることなどなかった ことをデリダは読者に思い出させようとする。また、科学者によって取り扱いに差があることは馬鹿げているし、おかしいとデリダはいう。とりわけ、彼が実際 にアメリカのマスコミの取材ターゲットになっていたときは「扱われ方に悪い思いをしたことはほとんどなかった」[25]。彼はさらに、本書が出版される 30年も前の会議の中で即席でした返事のいくつかを拾い上げて攻撃することの妥当性に疑問を呈し、そうした発言を攻撃することの難しさを指摘する科学者は いくらでもいるとデリダはいう[26]。また彼によれば、自身の著作には「相対主義」など存在せず、理性と啓蒙も批判していない。デリダは、将来的にこの 本がもっと真面目に読まれるようになり、そのときは扱われている問題にふさわしい品位がその読み方にそなわっていてほしいという希望を述べている [27]。 |
| The Sokal affair,
also called the Sokal hoax,[1] was a demonstrative scholarly hoax
performed by Alan Sokal, a physics professor at New York University and
University College London. In 1996, Sokal submitted an article to
Social Text, an academic journal of cultural studies. The submission
was an experiment to test the journal's intellectual rigor,
specifically to investigate whether "a leading North American journal
of cultural studies—whose editorial collective includes such luminaries
as Fredric Jameson and Andrew Ross—[would] publish an article liberally
salted with nonsense if (a) it sounded good and (b) it flattered the
editors' ideological preconceptions."[2] The article, "Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity",[3] was published in the journal's spring/summer 1996 "Science Wars" issue. It proposed that quantum gravity is a social and linguistic construct. The journal did not practice academic peer review and it did not submit the article for outside expert review by a physicist.[3][4] Three weeks after its publication in May 1996, Sokal revealed in the magazine Lingua Franca that the article was a hoax.[2] The hoax caused controversy about the scholarly merit of commentary on the physical sciences by those in the humanities; the influence of postmodern philosophy on social disciplines in general; and academic ethics, including whether Sokal was wrong to deceive the editors or readers of Social Text; and whether Social Text had abided by proper scientific ethics. In 2008, Sokal published Beyond the Hoax, which revisited the history of the hoax and discussed its lasting implications. Background Sokal in 2011 In an interview on the U.S. radio program All Things Considered, Sokal said he was inspired to submit the bogus article after reading Higher Superstition (1994), in which authors Paul R. Gross and Norman Levitt claim that some humanities journals will publish anything as long as it has "the proper leftist thought" and quoted (or was written by) well-known leftist thinkers.[5][a] Gross and Levitt had been defenders of the philosophy of scientific realism, opposing postmodernist academics who questioned scientific objectivity. They asserted that anti-intellectual sentiment in liberal arts departments (especially English departments) caused the increase of deconstructionist thought, which eventually resulted in a deconstructionist critique of science. They saw the critique as a "repertoire of rationalizations" for avoiding the study of science.[6] Article Sokal reasoned that if the presumption of editorial laziness was correct, the nonsensical content of his article would be irrelevant to whether the editors would publish it. What would matter would be ideological obsequiousness, fawning references to deconstructionist writers, and sufficient quantities of the appropriate jargon. After the article was published and the hoax revealed, he wrote: The results of my little experiment demonstrate, at the very least, that some fashionable sectors of the American academic Left have been getting intellectually lazy. The editors of Social Text liked my article because they liked its conclusion: that "the content and methodology of postmodern science provide powerful intellectual support for the progressive political project" [sec. 6]. They apparently felt no need to analyze the quality of the evidence, the cogency of the arguments, or even the relevance of the arguments to the purported conclusion.[7] Content of the article "Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity"[3] proposed that quantum gravity has progressive political implications, and that the "morphogenetic field" could be a valid theory of quantum gravity. (A morphogenetic field is a concept adapted by Rupert Sheldrake in a way that Sokal characterized in the affair's aftermath as "a bizarre New Age idea.")[2] Sokal wrote that the concept of "an external world whose properties are independent of any individual human being" was "dogma imposed by the long post-Enlightenment hegemony over the Western intellectual outlook." After referring skeptically to the "so-called scientific method", the article declared that "it is becoming increasingly apparent that physical 'reality'" is fundamentally "a social and linguistic construct." It went on to state that because scientific research is "inherently theory-laden and self-referential", it "cannot assert a privileged epistemological status with respect to counterhegemonic narratives emanating from dissident or marginalized communities", and that therefore a "liberatory science" and an "emancipatory mathematics", spurning "the elite caste canon of 'high science'", needed to be established for a "postmodern science [that] provide[s] powerful intellectual support for the progressive political project." Moreover, the article's footnotes conflate academic terms with sociopolitical rhetoric, e.g.: Just as liberal feminists are frequently content with a minimal agenda of legal and social equality for women and "pro-choice", so liberal (and even some socialist) mathematicians are often content to work within the hegemonic Zermelo–Fraenkel framework (which, reflecting its nineteenth-century liberal origins, already incorporates the axiom of equality) supplemented only by the axiom of choice. Publication Sokal submitted the article to Social Text, whose editors were collecting articles for the "Science Wars" issue. "Transgressing the Boundaries" was notable as an article by a natural scientist; biologist Ruth Hubbard also had an article in the issue.[8] Later, after Sokal revealed the hoax in Lingua Franca, Social Text's editors wrote that they had requested editorial changes that Sokal refused to make,[4] and had had concerns about the quality of the writing: "We requested him (a) to excise a good deal of the philosophical speculation and (b) to excise most of his footnotes."[9] Still, despite calling Sokal a "difficult, uncooperative author", and noting that such writers were "well known to journal editors", based on Sokal's credentials Social Text published the article in the May 1996 Spring/Summer "Science Wars" issue.[4] The editors did not seek peer review of the article by physicists or otherwise; they later defended this decision on the basis that Social Text was a journal of open intellectual inquiry and the article was not offered as a contribution to physics.[4] Responses Follow-up between Sokal and the editors In the May 1996 issue of Lingua Franca, in the article "A Physicist Experiments With Cultural Studies", Sokal revealed that "Transgressing the Boundaries" was a hoax and concluded that Social Text "felt comfortable publishing an article on quantum physics without bothering to consult anyone knowledgeable in the subject" because of its ideological proclivities and editorial bias.[2] In their defense, Social Text's editors said they believed that Sokal's essay "was the earnest attempt of a professional scientist to seek some kind of affirmation from postmodern philosophy for developments in his field" and that "its status as parody does not alter, substantially, our interest in the piece, itself, as a symptomatic document."[10] Besides criticizing his writing style, Social Text's editors accused Sokal of behaving unethically in deceiving them.[11] Sokal said the editors' response demonstrated the problem that he sought to identify. Social Text, as an academic journal, published the article not because it was faithful, true, and accurate to its subject, but because an "academic authority" had written it and because of the appearance of the obscure writing. The editors said they considered it poorly written but published it because they felt Sokal was an academic seeking their intellectual affirmation. Sokal remarked: My goal isn't to defend science from the barbarian hordes of lit crit (we'll survive just fine, thank you), but to defend the Left from a trendy segment of itself. ... There are hundreds of important political and economic issues surrounding science and technology. Sociology of science, at its best, has done much to clarify these issues. But sloppy sociology, like sloppy science, is useless, or even counterproductive.[4] Social Text's response revealed that none of the editors had suspected Sokal's piece was a parody. Instead, they speculated Sokal's admission "represented a change of heart, or a folding of his intellectual resolve." Sokal found further humor in the idea that the article's absurdity was hard to spot: In the second paragraph I declare without the slightest evidence or argument, that "physical 'reality' (note the scare quotes) [...] is at bottom a social and linguistic construct." Not our theories of physical reality, mind you, but the reality itself. Fair enough. Anyone who believes that the laws of physics are mere social conventions is invited to try transgressing those conventions from the windows of my apartment. I live on the twenty-first floor.[12] Book by Sokal and Bricmont Main article: Fashionable Nonsense In 1997, Sokal and Jean Bricmont co-wrote Impostures intellectuelles (US: Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals' Abuse of Science; UK: Intellectual Impostures, 1998).[13] The book featured analysis of extracts from established intellectuals' writings that Sokal and Bricmont claimed misused scientific terminology.[14] It closed with a critical summary of postmodernism and criticism of the strong programme of social constructionism in the sociology of scientific knowledge.[15] In 2008, Sokal published a followup book, Beyond the Hoax, which revisited the history of the hoax and discussed its lasting implications.[16] Jacques Derrida The French philosopher Jacques Derrida, whose 1966 statement about Einstein's theory of relativity was quoted in Sokal's paper, was singled out for criticism, particularly in U.S. newspaper coverage of the hoax.[17][18] One weekly magazine used two images of him, a photo and a caricature, to illustrate a "dossier" on Sokal's paper.[18] Arkady Plotnitsky commented:[17] Even given Derrida's status as an icon of intellectual controversy on the Anglo-American cultural scene, it is remarkable that out of thousands of pages of Derrida's published works, a single extemporaneous remark on relativity made in 1966 (before Derrida was "the Derrida" and, in a certain sense, even before "deconstruction") . . . is made to stand for nearly all of deconstructive or even postmodernist (not a term easily, if at all, applicable to Derrida) treatments of science. Derrida later responded to the hoax in "Sokal et Bricmont ne sont pas sérieux" ("Sokal and Bricmont Aren't Serious"), first published on 20 November 1997 in Le Monde. He called Sokal's action "sad" for having trivialized Sokal's mathematical work and "ruining the chance to carefully examine controversies" about scientific objectivity.[18] Derrida then faulted him and Bricmont for what he considered "an act of intellectual bad faith" in their follow-up book, Impostures intellectuelles: they had published two articles almost simultaneously, one in English in The Times Literary Supplement on 17 October 1997[19] and one in French in Libération on 18–19 October 1997,[20] but while the two articles were almost identical, they differed in how they treated Derrida. The English-language article had a list of French intellectuals who were not included in Sokal's and Bricmont's book: "Such well-known thinkers as Althusser, Barthes, and Foucault—who, as readers of the TLS will be well aware, have always had their supporters and detractors on both sides of the Channel—appear in our book only in a minor role, as cheerleaders for the texts we criticize." The French-language list, however, included Derrida: "Des penseurs célèbres tels qu'Althusser, Barthes, Derrida et Foucault sont essentiellement absents de notre livre" ("Famous thinkers such as Althusser, Barthes, Derrida and Foucault are essentially absent from our book"). According to Brian Reilly, Derrida may also have been sensitive to another difference between the French and English versions of Impostures intellectuelles. In the French, his citation from the original hoax article is said to be an "isolated" instance of abuse,[21] whereas the English text adds a parenthetical remark that Derrida's work contained "no systematic misuse (or indeed attention to) science."[22][23] Sokal and Bricmont insisted that the difference between the articles was "banal."[24] Nevertheless, Derrida concluded that Sokal was not serious in his method, but had used the spectacle of a "quick practical joke" to displace the scholarship Derrida believed the public deserved.[25] Social science criticism Sociologist Stephen Hilgartner, chairman of Cornell University's science and technology studies department, wrote "The Sokal Affair in Context" (1997),[26] comparing Sokal's hoax to "Confirmational Response: Bias Among Social Work Journals" (1990), an article by William M. Epstein published in Science, Technology, & Human Values.[27] Epstein used a similar method to Sokal's, submitting fictitious articles to real academic journals to measure their response. Though much more systematic than Sokal's work, it received scant media attention. Hilgartner argued that the "asymmetric" effect of the successful Sokal hoax compared with Epstein's experiment cannot be attributed to its quality, but that "[t]hrough a mechanism that resembles confirmatory bias, audiences may apply less stringent standards of evidence and ethics to attacks on targets that they are predisposed to regard unfavorably."[26] As a result, according to Hilgartner, though competent in terms of method, Epstein's experiment was largely muted by the more socially accepted social work discipline he critiqued, while Sokal's attack on cultural studies, despite lacking experimental rigor, was accepted. Hilgartner also argued that Sokal's hoax reinforced the views of well-known pundits such as George Will and Rush Limbaugh, so that his opinions were amplified by media outlets predisposed to agree with his argument.[28] The Sokal Affair extended from academia to the public press. Anthropologist Bruno Latour, who was criticized in Fashionable Nonsense, described the scandal as a "tempest in a teacup." Retired Northeastern University mathematician-turned social scientist Gabriel Stolzenberg wrote essays criticizing the statements of Sokal and his allies,[29] arguing that they insufficiently grasped the philosophy they criticized, rendering their criticism meaningless. In Social Studies of Science, Bricmont and Sokal responded to Stolzenberg,[30] denouncing his representations of their work and criticizing his commentary about the "strong programme" of the sociology of science. Stolzenberg replied in the same issue that their critique and allegations of misrepresentation were based on misreadings. He advised readers to slowly and skeptically examine the arguments of each party, bearing in mind that "the obvious is sometimes the enemy of the true."[31] Influence Sociological follow-up study In 2009, Cornell sociologist Robb Willer performed an experiment in which undergraduate students read Sokal's paper and were told either that it was written by another student or that it was by a famous academic. He found that students who believed the paper's author was a high-status intellectual rated it better in quality and intelligibility.[32] Sokal III In October 2021, the scholarly journal Higher Education Quarterly published a bogus article "authored" by "Sage Owens" and "Kal Avers-Lynde III". The initials stand for "Sokal III".[33] The Quarterly retracted the article.[34] https://en.wikipedia.org/wiki/Sokal_affair |
ソーカル事件はソーカル・デマとも呼ばれ[1]、ニュー
ヨーク大学とユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの物理学教授アラン・ソーカルによって行われた実証的な学術的デマである。1996年、ソーカルは文化研
究の学術誌『ソーシャル・テキスト』に論文を投稿した。この投稿は、同誌の知的厳密性をテストするための実験であり、特に「フレデリック・ジェイムソンや
アンドリュー・ロスといった著名人が編集部に名を連ねる北米を代表するカルチュラル・スタディーズ誌が、(a)響きがよく、(b)編集者のイデオロギー的
先入観に沿うものであれば、ナンセンスをふんだんに盛り込んだ論文を掲載するかどうか」を調査するためのものであった[2]。 その論文「境界を越える: Transgressing Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity」[3]は、同誌の1996年春夏号「Science Wars」に掲載された。この論文では、量子重力は社会的かつ言語的な構築物であると提唱している。同誌は学術的な査読を行っておらず、物理学者による外 部専門家の査読に論文を提出しなかった[3][4]。1996年5月の出版から3週間後、ソーカルは雑誌『リンガフランカ』において、この論文がデマで あったことを明らかにした[2]。 このデマは、人文科学者による物理科学の解説の学問的価値、ポストモダン哲学の社会分野全般への影響、ソーカルが『ソーシャル・テキスト』の編集者や読者 を欺くことは間違っていたのか、『ソーシャル・テキスト』は適切な科学倫理を守っていたのかなど、学問倫理に関する論争を引き起こした。 2008年、ソーカルは『Beyond the Hoax』を出版し、デマの歴史を再検討し、その永続的な意味を論じた。 背景 2011年のソーカル 著者のポール・R・グロスとノーマン・レヴィットは、人文科学雑誌の中には、「適切な左翼思想」を持ち、有名な左翼思想家が引用した(あるいは書いた)ものであれば、何でも出版するものがあると主張している。 グロスとレヴィットは科学的実在論の哲学の擁護者であり、科学的客観性に疑問を呈するポストモダニズムの学者に反対していた。彼らは、リベラルアーツ学部 (特に英語学部)における反知性主義的な感情が脱構築主義的な思想を増加させ、最終的に脱構築主義的な科学批判をもたらしたと主張した。彼らはこの批判 を、科学の研究を避けるための「合理化のレパートリー」とみなした[6]。 論文 ソーカルは、編集者の怠慢という推定が正しければ、彼の論文の無意味な内容は、編集者がそれを出版するかどうかには関係ないだろうと考えた。重要なのは、 イデオロギー的な卑屈さ、脱構築主義の作家への媚びた言及、適切な専門用語の十分な量であろう。記事が掲載され、デマが明らかになった後、彼はこう書い た: 私の小さな実験の結果は、少なくとも、アメリカのアカデミック・レフトの一部のファッショナブルなセクターが知的怠慢に陥っていることを示している。ソー シャル・テキスト』誌の編集者たちが私の論文を気に入ったのは、「ポストモダン科学の内容と方法論は、進歩的な政治プロジェクトに強力な知的支援を提供す る」[sec.6]という結論が気に入ったからである。彼らはどうやら、証拠の質、議論の説得力、あるいは主張と結論との関連性を分析する必要性すら感じ ていなかったようだ[7]。 記事の内容 「境界を越える: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity」[3]は、量子重力が進歩的な政治的意味合いを持ち、「形態形成場」が量子重力の有効な理論になりうると提案している。(形態形成場と は、ルパート・シェルドレイクが、事件の余波でソーカルが「奇妙なニューエイジの考え」と特徴づけた方法で脚色した概念である)[2]。ソーカルは、「個 々の人間から独立した性質を持つ外界」という概念は、「西洋の知的展望に対する長い啓蒙主義以降のヘゲモニーによって押し付けられたドグマ」であると書い た。 いわゆる科学的方法」に懐疑的に言及した後、「物理的な "現実 "は基本的に "社会的かつ言語的な構築物 "であることがますます明らかになってきている」と宣言した。さらに、科学的研究は「本質的に理論が多く、自己言及的」であるため、「反体制的あるいは周 縁化されたコミュニティから発せられる反ヘゲモニー的な物語に関して、特権的な認識論的地位を主張することはできない」とし、それゆえ「解放的科学」と 「解放的数学」は、「『高等科学』というエリート・カーストの規範」を排し、「進歩的政治プロジェクトに強力な知的支援を提供する(ポストモダン)科学」 のために確立される必要があると述べている。 さらに、論文の脚注は学術用語と社会政治的レトリックを混同している: リベラルなフェミニストたちが、女性の法的・社会的平等と「プロチョイス」という最小限のアジェンダで満足することが多いように、リベラルな(そして一部 の社会主義者さえも)数学者たちは、選択の公理によってのみ補完された覇権的なツェルメロ=フレンケルの枠組み(19世紀のリベラルな起源を反映し、すで に平等の公理が組み込まれている)の中で働くことで満足することが多い。 出版 ソーカルは、編集部が「サイエンス・ウォーズ」号用の論文を集めていたソーシャル・テキスト社に論文を投稿した。境界を越える」は自然科学者の論文として 注目され、生物学者のルース・ハバードもこの号に論文を寄稿していた[8]。後にソーカルが『リンガフランカ』でデマを暴露した後、ソーシャル・テキスト の編集者は、ソーカルが拒否した編集上の変更を要求し[4]、文章の質について懸念があったと書いている: 「それでも、ソーカルを「気難しく、非協力的な著者」と呼び、そのような著者は「ジャーナル編集者にはよく知られている」と指摘したにもかかわらず、ソー シャル・テキストはソーカルの信任に基づいて、1996年春夏号の「サイエンス・ウォーズ」に論文を掲載した。 [4]編集者は、物理学者などによる査読を求めなかった。後に編集者は、ソーシャル・テキストは開かれた知的探求のジャーナルであり、この論文は物理学へ の貢献として提供されたものではないとして、この決定を擁護した[4]。 回答 ソーカルと編集者との間のフォローアップ 1996年5月号のリンガフランカの記事「A Physicist Experiments With Cultural Studies」の中で、ソーカルは「Transgressing the Boundaries」がデマであったことを明らかにし、ソーシャルテキストはそのイデオロギー的傾向や編集の偏りから、「量子物理学に詳しい人にわざわ ざ相談することなく、安心して量子物理学の記事を掲載した」と結論づけた[2]。 ソーシャル・テキスト社の編集者は、ソーカルのエッセイは「自分の分野の発展に対してポストモダン哲学に何らかの肯定を求めようとするプロの科学者の真摯 な試み」であり、「パロディであるからといって、この作品それ自体に対する私たちの関心が、徴候的な文書として大きく変わるわけではない」と弁明している [10]。ソーシャル・テキスト社の編集者は、ソーカルの文体を批判するだけでなく、ソーカルが自分たちを欺く非倫理的な行為をしていると非難している [11]。 ソーカルは、編集者の対応は、彼が明らかにしようとした問題を実証していると述べた。ソーシャル・テキストは学術誌として、その論文が主題に忠実で、真実 で、正確であったからではなく、「学問的権威」が書いたからであり、不明瞭な文章の見栄えのために掲載したのである。編集者たちは、稚拙な文章だと思った が、ソーカルが自分たちの知的肯定を求める学者だと感じたので掲載したという。ソーカルはこう言った: 私の目的は、批評家という野蛮な大群から科学を守ることではなく(私たちはうまく生き残ることができる、ありがとう)、左翼を流行に敏感な層から守ること なのだ。... 科学技術を取り巻く重要な政治的・経済的問題は何百とある。科学社会学は、その最良のものであれば、これらの問題を明らかにするために多くのことをしてき た。しかし、杜撰な社会学は、杜撰な科学と同様、無益であり、逆効果でさえある。 Social Textの回答から、編集者の誰一人としてソーカル の論文がパロディであると疑っていなかったことが明ら かとなった。その代わりに、彼らはソーカルの告白が「心境の変化、あるいは知的決意の折れを表している」と推測した。ソーカルは、記事の不条理を見破るの が難しいという考えに、さらなるユーモアを見出した: 第2段落で私は、わずかな証拠も論拠もなく、"物理的な「現実」(引用符に注意)は[...]、つまるところ社会的で言語的な構築物である "と宣言している。物理的現実についての理論ではなく、現実そのものなのだ。なるほど。物理法則が単なる社会的慣習に過ぎないと考える人は、私のアパート の窓からその慣習を破ってみてほしい。私は21階に住んでいる。 ソーカルとブリクモンの著書 主な記事 ファッショナブル・ナンセンス 1997年、ソーカルとジャン・ブリモンは共著で『Impostures intellectuelles』(米:ファッショナブル・ナンセンス: Postmodern Intellectuals' Abuse of Science; UK: 同書は、ソカルとブリモンが科学用語を誤用していると主張する既存の知識人の著作の抜粋の分析を特集した[14]。ポストモダニズムの批判的な要約と、科 学的知識の社会学における社会構築主義の強力なプログラムへの批判で締めくくられている[15]。 2008年、ソーカルは続刊『Beyond the Hoax』を出版し、デマの歴史を再検討し、その永続的な意味を論じた[16]。 ジャック・デリダ アインシュタインの相対性理論に関する1966年の声明がソーカルの論文で引用されたフランスの哲学者ジャック・デリダは、特にデマに関するアメリカの新 聞報道において批判の対象として取り上げられた[17][18]。ある週刊誌はソーカルの論文に関する「書類」を説明するために彼の写真と風刺画の2つの 画像を使用した。 英米の文化シーンにおける知的論争の象徴としてのデリダの地位を考えても、何千ページにも及ぶデリダの出版物の中で、1966年(デリダが「デリダ」であ る以前、ある意味では「脱構築」以前)に相対性理論について即興的に発せられたたった一つの発言が、......ほぼすべてのことを物語っているようにさ れているのは驚くべきことである。デリダが "デリダ "になる前であり、ある意味では "脱構築 "よりも前である)。 デリダは後に、1997年11月20日にル・モンド紙に発表した「ソーカルとブリクモンは本気ではない」("Sokal et Bricmont ne sont pas sérieux")で、このデマに反論している。彼はソーカルの数学的研究を矮小化し、科学的客観性に関する論争を「注意深く検討する機会を台無しにし た」として、ソーカルの行動を「悲しい」と呼んだ。 [18]デリダはその後、彼とブリックモンがその続刊『Impostures intellectuelles』において「知的不誠実な行為」とみなしたことを非難している。彼らは1997年10月17日付の『タイムズ・リテラ リー・サプリメント』誌の英語版[19]と10月18-19日付の『リベラシオン』誌のフランス語版[20]の2本の記事をほぼ同時に発表したが、2本の 記事はほぼ同じ内容であったものの、デリダに対する扱い方は異なっていた。 英語の記事には、ソーカルとブリモンの著書には含まれていないフランスの知識人のリストがあった: 「アルチュセール、バルト、フーコーといったよく知られた思想家たちは、TLSの読者ならよくご存知のように、海峡の両岸で常に支持者と否定者を抱えてき た。しかし、フランス語のリストにはデリダも含まれている: 「アルチュセール、バルト、デリダ、フーコーのような有名な思想家は、基本的に我々の本には登場しない」。 ブライアン・ライリーによれば、デリダは『知性の迷信』(Impostures intellectuelles)のフランス語版と英語版のもうひとつの違いにも敏感だったのかもしれない。フランス語版では、デマの元となった論文から の引用は「孤立した」濫用例であるとされている[21]が、英語版では、デリダの著作には「科学の体系的な誤用は(あるいは科学への注意は)ない」という 親展的な記述が加えられている。 「22][23]ソーカルとブリックモンは、論文の違いは「凡庸なもの」であると主張していた[24]。それにもかかわらず、デリダは、ソーカルはその方 法において真剣ではなく、「手っ取り早い実用的な冗談」という見世物を用いて、デリダが大衆にふさわしいと信じていた学問を置き換えたのだと結論づけた [25]。 社会科学批判 コーネル大学の科学技術研究学科長である社会学者スティーヴン・ヒルガートナーは、「The Sokal Affair in Context」(1997年)を書き、ソーカルのデマを「確証的反応」と比較した[26]: Science、Technology、& Human Values』誌に掲載されたウィリアム・M・エプスタインの論文「Bias Among Social Work Journals」(1990年)と比較している[27]。エプスタインはソーカルと同様の方法を用い、架空の論文を実際の学術雑誌に投稿し、その反応を 測定した。ソーカルの研究よりもはるかに体系的であったが、メディアの注目はほとんど集められなかった。ヒルガートナーは、エプスタインの実験と比較して 成功したソーカルのデマの「非対称」効果は、その質に起因するものではなく、「確証バイアスに似たメカニズムによって、視聴者は、不利に評価する素因があ る対象への攻撃に対して、証拠と倫理に関するより厳密でない基準を適用する可能性がある」と主張した[26]。 「その結果、ヒルガートナーによれば、エプスタインの実験は、方法論としては有能であったものの、彼が批判した社会福祉学という、より社会的に受け入れら れている学問分野によって、大方黙殺されたのに対し、ソーカルのカルチュラル・スタディーズに対する攻撃は、実験的な厳密さを欠いていたにもかかわらず、 受け入れられた。ヒルガートナーはまた、ソーカルのデマがジョージ・ウィルやラッシュ・リンボーといった有名な識者の見解を補強し、彼の意見が彼の主張に 同調する傾向のあるメディアによって増幅されたと主張した[28]。 ソーカル事件は学術界から一般紙にまで拡大した。人類学者のブルーノ・ラトゥールは、『ファッショナブル・ナンセンス』の中で、このスキャンダルを "茶碗の中の揉め事 "と表現した。ノースイースタン大学を定年退職し、数学者から社会科学者に転身したガブリエル・ストルツェンバーグは、ソーカルとその盟友の発言を批判す るエッセイを執筆し[29]、彼らが批判した哲学を十分に理解していないため、批判が無意味なものになっていると主張した。ブリックモンとソーカルは『科 学の社会学』の中で、ストルツェンベルクに反論し、自分たちの研究に対する彼の表現を非難し、科学社会学の「強力なプログラム」についての彼の論評を批判 した[30]。ストルツェンバーグは同じ号で、彼らの批評と誤報の主張は誤読に基づいていると答えている。彼は読者に対して、「明白なことは時として真実 の敵である」ことを念頭に置き、ゆっくりと懐疑的に各党の主張を吟味するよう助言した[31]。 影響力 社会学的追跡調査 2009年、コーネル大学の社会学者ロブ・ウィラーは、学部生がソーカルの論文を読み、それが他の学生によって書かれたものであるか、有名な学者によって 書かれたものであるかを知らされるという実験を行った。彼は、論文の著者が地位の高い知識人であると信じた学生の方が、論文の質とわかりやすさにおいて評 価が高いことを発見した[32]。 ソーカル3世 2021年10月、学術誌『ハイヤー・エデュケーション・クォータリー』は、「セージ・オーウェンズ」と「カル・アヴァース=リンデ3世」が「執筆した」 偽の論文を掲載した。このイニシャルは「ソーカル3世」の略である[33]。クォータリー誌はこの論文を撤回した[34]。 https://www.deepl.com/ja/translator |
| Beyond the Hoax Cargo cult science List of scientific metaphors Nonscience Not even wrong Postmodernism Generator Pseudoscience Science wars The Dictionary of Fashionable Nonsense Materialism and Empirio-Criticism – 1909 book by Vladimir Lenin |
Beyond the Hoax Cargo cult science List of scientific metaphors Nonscience Not even wrong Postmodernism Generator Pseudoscience Science wars The Dictionary of Fashionable Nonsense Materialism and Empirio-Criticism – 1909 book by Vladimir Lenin |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Fashionable_Nonsense |
|
| Beyond the Hoax: Science,
Philosophy, and Culture is a 2008 book by Alan Sokal detailing the
history of the Sokal affair in which he submitted an article full of
"nonsense" to a journal and was able to get it published.[1] |
『デマを超えて
科学、哲学、文化』は、アラン・ソーカルが2008年に出版した本で、「ナンセンス」だらけの論文を雑誌に投稿し、掲載させることができたソーカル事件の
経緯を詳しく説明している[1]。 |
| Reception Robert Matthews (scientist) on The Times writes that "Sokal's essays—and his hoax—achieve their purpose of reminding us all that, in the words of the Victorian mathematician-philosopher William Kingdon Clifford, 'It is wrong, always, everywhere and for any one, to believe anything upon insufficient evidence.'" But it also notes that Beyond the Hoax: fails to reflect the fact that Sokal's concerns are now widely shared—and that progress is being made in addressing them, the emergence of evidence-based social policy being an obvious example. His critique would also gain more credibility from encompassing his own community: the failure of scientific institutions to address the abuse of statistical methods or promote systematic reviews is no less of a threat to progress than the ramblings of postmodernists or fundamentalists.[2] Michael Shermer[3] praised the book as "an essential text" and summarized the argument, writing that: There is progress in science, and some views really are superior to others, regardless of the color, gender, or country of origin of the scientist holding that view. Despite the fact that scientific data are "theory laden," science is truly different than art, music, religion, and other forms of human expression because it has a self-correcting mechanism built into it. If you don't catch the flaws in your theory, the slant in your bias, or the distortion in your preferences, someone else will, usually with great glee and in a public forum—for example, a competing journal! Scientists may be biased, but science itself, for all its flaws, is still the best system ever devised for understanding how the world works. Physicist and historian of science Allan Franklin, for whom Sokal was "a hero" to "many [...] of us working in the history and philosophy of science in the mid-1990s", described the publication as "somewhat disappointing". He also noted that Sokal's book's "sticking point is the possible reconciliation of Sokal’s view of religion, which he regards a ‘‘massive delusion,’’ having no evidential basis, with the ethical and moral values that religious believers espouse."[4] Cornell University solid-state physicist N. David Mermin wrote in Nature (journal) that Sokal "has an admirable passion for clarity of thought, and is commendably opposed to those who would pass off nonsense as profundity" yet maintained that "Sokal's unwillingness to expand his frame of reference to accommodate legitimately different points of view undermines his effectiveness as a scourge of genuine rubbish." Mermin wrote that Sokal's book was itself similar to the literary theory that Sokal criticised. Sokal's book begins with a reprint of the famous parody, accompanied by a rambling commentary that could itself be a parody of pedantic literary explication. [...] Hoax fans ought to enjoy it.[5] Mermin continued that, In a preface, Sokal announces his “visceral distaste for books that have been confected by pasting together a collection of loosely connected, previously published essays”. His book, he explains, is different. These ten essays (seven previously published) “form, I believe, a coherent whole”. But virtually everyone who publishes a collection of essays believes they form a coherent whole. Sokal's obliviousness to this is an early indication of a complacency about his own views, and a lack of imagination about what others might be thinking, that undermines much of what follows.[5] Mermin states that "I would like to think that we are not only beyond Sokal's hoax, but beyond the science wars themselves. This book might be a small step backwards."[5] |
レセプション 『タイムズ』紙のロバート・マシューズ(科学者)は、「ソーカルのエッセイと彼のデマは、ヴィクトリア朝の数学者であり哲学者であったウィリアム・キング ドン・クリフォードの言葉を借りれば、"不十分な証拠に基づいて何かを信じることは、常に、どこでも、誰にとっても間違いである "ということを私たちに思い起こさせるという目的を達成した」と書いている。しかし、『Beyond the Hoax: は、ソーカルの懸念が現在では広く共有され、エビデンスに基づく社会政策の出現がその明らかな例であるように、それへの取り組みが進展しているという事実 を反映していない。統計的手法の濫用に対処したり、システマティック・レビューを推進したりする科学機関の失敗は、ポストモダニストや原理主義者の放言に 劣らず、進歩に対する脅威である[2]。 マイケル・シャーマー[3]は、この本を「不可欠なテキスト」と賞賛し、議論を要約して次のように書いている: 科学には進歩があり、ある見解は、その見解を持つ科学者の肌の色、性別、出身国に関係なく、他の見解より本当に優れている。科学的データは "理論ありき "であるにもかかわらず、科学は芸術、音楽、宗教、その他の人間の表現とは真に異なっている。もしあなたが自分の理論の欠陥や偏見の傾き、嗜好のゆがみを 見抜けなかったとしても、他の誰かが大喜びで、例えば競合誌のような公の場で、それを見抜くだろう!科学者は偏っているかもしれないが、科学そのものは、 その欠点はあるにせよ、世界の仕組みを理解するために考案された最高のシステムであることに変わりはない。 物理学者で科学史家のアラン・フランクリンは、ソーカルが「1990年代半ばに科学史と科学哲学に携わっていた多くの人々」にとって「英雄」であったと し、今回の出版を「いささか失望した」と評している。彼はまた、ソーカルの本の「難点は、彼が''大規模な妄想''であり、証拠となる根拠がないとみなし ているソーカルの宗教観と、宗教信者が信奉している倫理的・道徳的価値観との和解の可能性である」と指摘した[4]。 コーネル大学の固体物理学者であるN.デイヴィッド・マーミンは『ネイチャー』誌に、ソーカルは「明晰な思考に対する立派な情熱を持っており、ナンセンス を深遠と言い換えるような人々とは立派に対立している」としながらも、「正当に異なる視点を受け入れるために自分の参照枠を広げようとしないソーカルの姿 勢は、本物の屑の掃討者としての彼の有効性を損なっている」と主張している。マーミンは、ソーカルの本自体が、ソーカルが批判した文学理論と類似している と書いた。ソーカルの本 は、有名なパロディの再版で始まり、それ自体が衒学的な文学的説明のパロディともいえる、とりとめのない解説が添えられている。[...]デマファンなら 楽しめるはずだ[5]。 マーミンはこう続けた、 序文でソーカルは、「ゆるくつながった既刊のエッセイを貼り合わせて作られた本に対する直感的な嫌悪感」を表明している。彼の本は違うと彼は説明する。こ の10編のエッセイ(7編は既刊)は「首尾一貫した全体を形成していると私は信じている」。しかし、エッセイ集を出版する者は事実上誰でも、それらが首尾 一貫した全体を形成していると信じている。ソーカルがこのことに気づかないのは、彼自身の見解に対する自己満足と、他の人が考えているかもしれないことに ついての想像力の欠如の初期段階での表れであり、それがこの後の内容の多くを台無しにしている[5]。 マーミンは、「私たちはソーカルのデマを超えただけでなく、科学戦争そのものを超えたと思いたい」と述べている。本書は小さな後退の一歩かもしれない」 [5]。 |
| Pseudoscience Cargo cult science Grievance studies affair |
|
| The grievance studies affair was
the project of a team of three authors—Peter Boghossian, James A.
Lindsay, and Helen Pluckrose—to highlight what they saw as poor
scholarship and erosion of standards in several academic fields. Taking
place over 2017 and 2018, their project entailed submitting bogus
papers to academic journals in cultural, queer, race, gender, fat, and
sexuality studies to determine whether they would pass through peer
review and be accepted for publication. Several of these papers were
subsequently published, which the authors cited in support of their
contention. Prior to the affair, concerns about the intellectual validity of much research influenced by postmodern philosophy and critical theory were highlighted by various academics who composed nonsensical hoax articles parodying the language and types of content that are often found in the modern humanities and succeeded in having these articles accepted for publication in academic journals. One of the most noted previous examples of this was Alan Sokal's 1996 hoax in Social Text, a cultural studies journal, which inspired Boghossian, Lindsay, and Pluckrose. The trio set out with the intent to expose problems in what they called "grievance studies", referring to academic areas where they claim "a culture has developed in which only certain conclusions are allowed… and put social grievances ahead of objective truth".[1][2][3] As such, the trio, identifying themselves as leftists and liberals, described their project as an attempt to raise awareness of what they believed was the damage that postmodernism and identity politics-based scholarship was having on leftist political projects as well as on on science and academia more broadly. Boghossian, Lindsay, and Pluckrose wrote 20 articles that promoted deliberately absurd ideas or morally questionable acts and submitted them to various peer-reviewed journals. Although they had planned for the project to run until January 2019, the trio admitted to the hoax in October 2018 after journalists from The Wall Street Journal revealed that "Helen Wilson", the pseudonym used for their article published in Gender, Place & Culture, did not exist. By the time of the revelation, 4 of their 20 papers had been published; 3 had been accepted but not yet published; 6 had been rejected; and 7 were still under review. Included among the articles that were published were arguments that dogs engage in rape culture and that men could reduce their transphobia by anally penetrating themselves with sex toys, as well as Adolf Hitler's Mein Kampf rewritten in feminist language.[2][4] The first of these had won special recognition from the journal that published it. The hoax received a polarized reception within academia. Some academics praised it for exposing flaws that they saw as widespread among sectors of the humanities and social sciences influenced by postmodernism, critical theory, and identity politics. Others criticised what they perceived as the unethical nature of submitting deliberately bogus research. Some critics also asserted that the work did not represent a scientific investigation, given that the project did not include a control group, further arguing that invalid arguments and poor standards of peer-review were not restricted to "grievance studies" subjects but found across much of academia. |
不平不満研究事件は、ピーター・ボゴシアン、ジェームズ・A・リンゼ
イ、ヘレン・プラックローズの3人の著者チームによるプロジェクトで、いくつかの学問分野における稚拙な学問や基準の低下と見られるものを浮き彫りにする
ために行われた。2017年から2018年にかけて行われた彼らのプロジェクトは、文化研究、クィア研究、人種研究、ジェンダー研究、脂肪研究、セクシュ
アリティ研究の学術誌に偽の論文を投稿し、査読を通過して出版が認められるかどうかを見極めるというものだった。これらの論文のうち数本はその後出版さ
れ、著者たちはそれを自分たちの主張を裏付けるものとして引用した。 この事件以前にも、ポストモダンの哲学や批評理論に影響された多くの研究の知的妥当性に対する懸念が、現代人文学によく見られる言葉や内容のタイプをパロ ディにした無意味なデマ論文を作成し、学術誌に掲載させることに成功した様々な学者によって浮き彫りにされた。その最も有名な例のひとつが、アラン・ソー カルが1996年に文化研究誌『ソーシャル・テキスト』に掲載したデマで、ボゴシアン、リンゼイ、プラックローズの3人はこれに触発された。この3人組 は、彼らが「不平不満研究」と呼ぶ学問分野の問題を暴くことを意図して出発した。 [1][2][3]このように、自らを左翼・リベラル派と名乗る3人組は、自分たちのプロジェクトを、ポストモダニズムとアイデンティティ政治に基づく学 問が、左翼の政治的プロジェクトや、より広く科学や学問に与えていると信じている損害に対する認識を高める試みであると説明した。 ボゴシアン、リンゼイ、プラックローズの3人は、意図的に不合理な考えや道徳的に問題のある行為を推進する論文を20本書き、さまざまな査読付きジャーナ ルに投稿した。彼らはこのプロジェクトを2019年1月まで実施する予定だったが、『Gender, Place & Culture』誌に掲載された論文に使用されたペンネーム「ヘレン・ウィルソン」が実在しないことがウォール・ストリート・ジャーナル紙のジャーナリス トによって明らかになったため、3人は2018年10月にデマを認めた。発覚までに、彼らの20本の論文のうち4本は出版され、3本は受理されたがまだ出 版されておらず、6本はリジェクトされ、7本はまだ査読中だった。掲載された論文の中には、犬がレイプ文化に従事しているという議論や、男性がセックスの おもちゃで自分自身を肛門で貫くことによってトランスフォビアを減らすことができるという議論、アドルフ・ヒトラーの『我が闘争』をフェミニズムの言葉で 書き直したものなどが含まれていた[2][4]。 このデマは学界で賛否両論があった。一部の学者は、ポストモダニズム、批評理論、アイデンティティ・ポリティクスの影響を受けた人文科学や社会科学の分野 に蔓延していると見られる欠陥を暴いたとして賞賛した。また、意図的にインチキ研究を提出するという非倫理性を批判する者もいた。また、このプロジェクト には対照群が含まれていないことから、この研究は科学的な調査ではないと主張する批評家もおり、さらに、無効な議論や査読の水準の低さは「苦情研究」の対 象に限ったことではなく、学界の多くで見られることだとも主張している。 |
| "Grievance studies" and "applied
postmodernism" Through their series of hoax articles, James A. Lindsay, Peter Boghossian, and Helen Pluckrose intended to expose issues in what they term as "grievance studies", a subcategory of academic areas where the three believe "a culture has developed in which only certain conclusions are allowed ... and put social grievances ahead of objective truth".[1][2][3] The trio referred to several academic fields—postcolonial theory, gender studies, queer theory, critical race theory, intersectional feminism, and fat studies—as "grievance studies" because, according to Pluckrose, such areas begin "from the assumption of a grievance" and then bend "the available theories to confirm it".[5] Pluckrose argued that all of these fields derive their underlying theoretical perspectives from the postmodern philosophy that developed in the late 1960s. Focusing on the work of French postmodern philosopher Michel Foucault, she highlighted how he argued that knowledge and power were interwoven and emphasised the role of discourse in society.[5] Pluckrose suggested that fields such as postcolonial theory and queer theory could be called "applied postmodernism" in that they sprung up largely in the late 1980s as a means of pushing the gains of the civil rights movement, gay rights movement, and liberal feminism from the arena of legislative change and into the territory of reshaping discourse.[5] She argued that these fields adapted postmodernism to suit their activist agendas. From postmodernism, they adopted the idea that knowledge is a social construct, but at the same time they held to the modernist view that "no progress could be made unless some things were objectively true". Thus, the "applied postmodernists", Pluckrose argued, insisted that "systems of power and privilege that oppressed women, people of colour and the LGBT" are objectively real and could be revealed by analysing discourses. At the same time, she argued, they retained postmodernism's scepticism toward science and objective knowledge, its view of "society as a system of power and privilege" and "commitment to the belief that all imbalances are socially constructed", rather than arising from biological reality.[5] Pluckrose described herself and her collaborators as being "left-wing liberal sceptics". She stated that a core reason for why they wanted to carry out the project was to convince other "leftist academics" that there was a problem with "corrupted scholarship" in academic fields that were "based on identity politics and postmodernism."[5] She argued that in rejecting modernism, much postmodernist-derived scholarship was also rejecting science, reason, and liberal democracy, and thus undermining many important progressive gains.[5] Pluckrose also expressed concern that, in both foregrounding the importance of group identity and facilitating the growth of post-truth by claiming that there is no objective truth, this postmodernist theory was contributing to "the reactionary surge to the right" seen in many countries during the 2010s.[5] In 2020, Pluckrose and Lindsay further investigated the effects of critical theory in their book Cynical Theories: How Universities Made Everything About Race, Gender, and Identity—and Why This Harms Everybody.[6] |
"苦情(不平不満)研究 "と "応用ポストモダニズム" ジェームズ・A・リンゼイ、ピーター・ボゴシアン、ヘレン・プラックローズの3人は、一連のデマ記事を通じて、彼らが「苦情研究」と呼ぶ学問分野のサブカ テゴリーにおける問題を暴露することを意図していた。 [1][2][3]プラックローズは、ポストコロニアル理論、ジェンダー研究、クィア理論、批判的人種理論、インターセクショナル・フェミニズム、ファッ ト・スタディーズといった学問分野を「不満研究」と呼んでいる。フランスのポストモダンの哲学者であるミシェル・フーコーの仕事に焦点を当て、彼がいかに 知識と権力が織り交ざっていると主張し、社会における言説の役割を強調したかを強調した[5]。 プラックローズは、ポストコロニアル理論やクィア理論といった分野は、1980年代後半に公民権運動や同性愛者の権利運動、リベラル・フェミニズムの成果 を法改正の場から言説の再構築の領域へと押し進める手段として生まれたという点で、「応用ポストモダニズム」と呼ぶことができると示唆した。彼らはポスト モダニズムから、知識は社会的構成物であるという考え方を取り入れたが、同時に「あることが客観的に真実でなければ進歩はありえない」というモダニズムの 考え方も堅持した。従って、「応用ポストモダニスト」であるプラックローズは、「女性や有色人種、LGBTを抑圧する権力と特権のシステム」は客観的に実 在し、言説を分析することで明らかにできると主張した。同時に、彼らは科学や客観的知識に対するポストモダニズムの懐疑、「社会は権力と特権のシステムで ある」という見方、そして生物学的現実から生じるのではなく、「すべての不均衡は社会的に構築されたものであるという信念へのコミットメント」を保持して いる、と彼女は主張した[5]。 プラックローズは、自分自身と彼女の共同研究者たちを「左翼リベラル懐疑論者」であると述べている。彼女は、自分たちがこのプロジェクトを遂行しようと 思った理由の中心は、「アイデンティティ政治とポストモダニズムに基づく」学問分野における「腐敗した学問」に問題があることを、他の「左翼の学者」に納 得させることであったと述べている。 [5]プラックローズはまた、集団のアイデンティティの重要性を強調し、客観的な真実は存在しないと主張することでポスト・トゥルースの成長を促進するこ とで、このポストモダニズムの理論が2010年代に多くの国で見られた「右派への反動的な躍進」の一因となっていることに懸念を表明していた[5]。 2020年、プラックローズとリンゼイは、著書『シニカル・セオリー』(Cynical Theories)で批評理論の影響をさらに調査した: 大学はいかにして人種、ジェンダー、アイデンティティについてすべてを作り上げたのか、そしてなぜそれがすべての人に害を及ぼすのか[6]。 |
| Sequence of events By the time of the reveal, 7 of their 20 papers had been accepted for publication, 7 were still under review, and 6 had been rejected.[3] Included among the articles that were published were arguments that dogs engage in rape culture and that men could reduce their transphobia by anally penetrating themselves with sex toys, as well as Adolf Hitler's Mein Kampf rewritten in feminist language.[2][4] One of the published papers in particular had won special recognition from the journal that published it.[4] Attempts Prior to the affair, various academics highlighted concerns about the intellectual validity of much research influenced by postmodern philosophy and critical theory by publishing hoax articles in various journals. It was the 1996 hoax by Alan Sokal in Social Text, in particular, that influenced James A. Lindsay and Peter Boghossian to publish a hoax article of their own. On May 19, 2017, peer-reviewed journal Cogent Social Sciences published "The conceptual penis as a social construct",[7] which argued that penises are not "male"; rather, they should be analyzed as social constructs instead.[8] The same day, Lindsay and Boghossian revealed it to be a hoax aimed at discrediting gender studies, although Cogent Social Sciences is not exclusively a gender-studies journal.[9] While the journal did conduct a postmortem, both authors concluded the "impact [of the hoax] was very limited, and much criticism of it was legitimate".[10] The authors claim to have started their second attempt on August 16, 2017,[11] with Helen Pluckrose joining them in September.[10] The new methodology called for the submission of multiple papers, each of which would be submitted to "higher-ranked journals"; if it were rejected, feedback from the peer-review process was used to revise the paper before it was submitted to a lower-ranked journal. This process was repeated until the paper was accepted, or until the three authors gave up on that paper.[11] The authorship of each paper was either fictional—such as "Helen Wilson" of "Portland Ungendering Research Initiative"—or real people willing to lend their name, such as Richard Baldwin, professor emeritus of history at Gulf Coast State College.[2] Over the course of the project, 20 papers were submitted and 48 "new submissions" of those papers were made.[11] The first acceptance, "Human Reactions to Rape Culture and Queer Performativity at the Dog Park", was achieved five months after the project began. During the initial peer review for its second, and ultimately successful, attempt at publication in Gender, Place & Culture, what the hoaxers called the "Dog Park" paper was praised by the first reviewer as "incredibly innovative, rich in analysis, and extremely well-written and organized".[10] Similar respectful feedback was provided for other accepted papers.[12] Discovery of hoax The project was intended to run until January 31, 2019, but came to a premature end.[10] On June 7, 2018, the Twitter account "New Real Peer Review" discovered one of their papers.[13] This brought it to the attention of reporters at The College Fix, Reason, and other news outlets who began trying to contact the fictional author and journal it was published in.[14][15] The journal Gender, Place & Culture published a note on August 6, 2018, stating that it suspected "Helen Wilson" had breached their contract to "not [fabricate] or [misappropriate] anyone's identity, including [their] own", adding that "the author has not responded to our request to provide appropriate documentation confirming their identity".[16] According to the trio, another journal and a reporter at The Wall Street Journal were also asking for proof of identity at this point, and that it was the right time to go public; they admitted the hoax to the journalist in early August.[10] When The Wall Street Journal report went public on October 2,[17] the trio released an essay describing their project, as well as a Google Drive archive of most of their papers and email correspondence which included reviewer comments.[10] Simultaneously, filmmaker Mike Nayna released a video on YouTube revealing the story behind the project. As of 2019, Nayna and producer Mark Conway were working on a documentary film about the project.[1][18] |
経緯 暴露されるまでに、20本の論文のうち7本が受理され、7本が審査中で、6本が却下された[3]。掲載された論文には、犬がレイプ文化に関与しているとい う主張や、男性が性玩具で肛門を貫通させることでトランスフォビアを軽減できるという主張、アドルフ・ヒトラーの『我が闘争』をフェミニスト言語で書き直 したものなどが含まれていた[2][4]。特に掲載された論文の1本は、それを掲載した雑誌から特別な評価を得ていた[4]。 試み この事件に先立ち、様々な学者がポストモダン哲学や批評理論の影響を受けた多くの研究の知的妥当性に対する懸念を、様々なジャーナルにデマ論文を発表する ことで浮き彫りにした。特に、ジェームズ・A・リンゼイとピーター・ボゴシアンが自分たちのデマ論文を発表するきっかけとなったのは、1996年に『ソー シャル・テキスト』に掲載されたアラン・ソーカルによるデマだった。 2017年5月19日、専門誌『Cogent Social Sciences』は「社会的構築物としての概念的ペニス」[7]を発表し、ペニスは「男性」ではなく、むしろ社会的構築物として分析されるべきであると 主張した。 [8] 同日、リンゼイとボゴシアンは、コージェント・ソーシャル・サイエンシズが専らジェンダー研究誌ではないものの、それがジェンダー研究の信用失墜を狙った デマであることを明らかにした[9]。同誌は事後調査を行ったが、両著者は「(デマの)影響は非常に限定的であり、それに対する多くの批判は正当であっ た」と結論づけた[10]。 著者たちは、2017年8月16日に2度目の試みを開始したと主張しており[11]、9月にはヘレン・プラックローズも加わった[10]。新しい方法論で は、複数の論文を投稿することが求められ、それぞれの論文は「よりランクの高いジャーナル」に投稿され、リジェクトされた場合は、査読プロセスからの フィードバックを用いて論文を修正してから、よりランクの低いジャーナルに投稿された。このプロセスは、論文が受理されるか、3人の著者がその論文に見切 りをつけるまで繰り返された[11]。各論文の著者は、「ポートランド・アンゲンダリング研究イニシアチブ」の「ヘレン・ウィルソン」のような架空の人物 か、ガルフコースト州立大学の歴史学名誉教授であるリチャード・ボールドウィンのような、名前を貸してくれる実在の人物であった[2]。 プロジェクト期間中、20本の論文が投稿され、それらの論文の「新規投稿」が48本行われた[11]。最初の採択論文「Human Reactions to Rape Culture and Queer Performativity at the Dog Park」は、プロジェクト開始から5ヵ月後に達成された。Gender, Place & Culture』誌への掲載を目指した2回目の、そして最終的に成功した最初の査読の際、デマ投稿者たちが「ドッグパーク」と呼んでいた論文は、最初の査 読者から「信じられないほど革新的で、分析に富み、非常によく書かれ、整理されている」と称賛された[10]。 デマの発見 このプロジェクトは2019年1月31日まで実施される予定であったが、早々に終了した[10]。 2018年6月7日、Twitterアカウント「New Real Peer Review」が彼らの論文の一つを発見した[13]。これにより、The College Fix、Reason、その他の報道機関の記者の目に留まり、架空の著者と掲載誌に連絡を取ろうとし始めた。 [14][15]ジャーナル『Gender, Place & Culture』は2018年8月6日、「ヘレン・ウィルソン」が「[自分自身を含む]誰の身元も[捏造]または[流用]しない」という契約に違反した疑 いがあるとする注釈を発表し、「著者は身元を確認する適切な書類を提出するよう求めた私たちの要求に応えていない」と付け加えた。 [16]3人組によると、別のジャーナルとウォール・ストリート・ジャーナルの記者もこの時点で身元証明を求めており、公表するには適切なタイミングだっ た。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道が10月2日に公開されると[17]、3人組は自分たちのプロジェクトを説明するエッセイと、自分たちの論文の 大部分と査読者のコメントを含む電子メールのやりとりのグーグルドライブ・アーカイブを公開した[10]。同時に、映画監督のマイク・ネイナが YouTubeでプロジェクトの裏話を明かすビデオを公開した。2019年現在、ネイナとプロデューサーのマーク・コンウェイは、このプロジェクトに関す るドキュメンタリー映画を制作中である[1][18]。 |
| Reactions The project drew both praise and criticism. The science writer Tom Chivers suggested that the result was a "predictable furore", whereby those already sceptical of gender studies hailed it as evidence for "how the whole field is riddled with nonsense", while those sympathetic to gender studies thought it was "dishonestly undermining good scholarship."[19] The political scientist Yascha Mounk dubbed it "Sokal squared" in reference to the Sokal affair hoax accomplished by Alan Sokal, and said that the "result is hilarious and delightful. It also showcases a serious problem with big parts of academia." The psychologist Steven Pinker said the project posed the question "is there any idea so outlandish that it won't be published in a Critical/PoMo/Identity/'Theory' journal?"[8] In contrast, Joel P. Christensen and Matthew A. Sears, both classicists, referred to it as "the academic equivalent of the fraudulent hit pieces on Planned Parenthood" produced in 2015, more interested in publicity than valid argumentation.[20] In The Atlantic, Mounk said that "Like just about everything else in this depressing national moment, Sokal Squared is already being used as ammunition in the great American culture war." He characterized two sets of responses to the affair as "intellectually dishonest": right-wing responses that used the affair to discredit wider academia and left-wing responses that treated it as a politically motivated attack on academia. He said the former overlooked that "There are many fields of academia that have absolutely no patience for nonsense", including the fact that all the papers submitted to sociology journals had been rejected, while the latter attacked the motives behind the hoax instead of refuting it.[3] Responses by the editors of the publishing journals Ann Garry, a co-editor of Hypatia, which had accepted one of the hoax papers ("When the Joke's on You", which purported to be a feminist critique of hoaxes) but had not published it yet, said she was "deeply disappointed" by the hoax. Garry told The New York Times that "Referees put in a great deal of time and effort to write meaningful reviews, and the idea that individuals would submit fraudulent academic material violates many ethical and academic norms."[2] Nicholas Mazza, editor of the Journal of Poetry Therapy, said: "Although a valuable point was learned regarding the authenticity of articles/authors… the authors of the 'study' clearly engaged in flawed and unethical research."[2] Praise Yascha Mounk of Johns Hopkins University said that while the authors received no favors for preparing the hoax, they demonstrated mastery in postmodern jargon and not only ridiculed the journals in question, but, more importantly, outed double standards of gender studies which happily welcome hoaxes against "morally suspect" fields like economics, but are unable to accept a criticism of their own methods. He also noted the "sheer amount of tribal solidarity it has elicited among leftists and academics" and the fact that many of the reactions were purely ad hominem, while few have actually noted that there is an actual problem highlighted by the hoax: "some of the leading journals in areas like gender studies have failed to distinguish between real scholarship and intellectually vacuous as well as morally troubling bullshit".[21] Rejecting complaints that the trio, lacking a control group, engaged in a "confused attempt to import statistics into a question where it doesn't apply", Mounk stated that the trio had promised "nothing of the sort" in the first place, and had instead successfully accomplished their goal of demonstrating that "it's possible [...] to get bullshit published" in the journals in question.[8] Justin E. H. Smith defended hoaxing as an intellectual or scholarly practice, providing a series of examples of hoaxes ranging from the Italian Renaissance to the 2000s. In The Chronicle of Higher Education, Heather E. Heying pointed out that the hoax helped to expose many pathologies of the modern social sciences, such as "repudiation of science and logic" and "extolling activism over inquiry".[21] Upon Boghossian's employer Portland State University initiating a research misconduct inquiry on the grounds of conducting human subject-based research without approval, and further considering a charge of fabricating data,[22] a number of prominent academics submitted letters of support to him[23] and defended the motive of the hoax, including Steven Pinker and various Portland State students.[24] Richard Dawkins compared Boghossian to a novelist, pointing out that George Orwell's novel Animal Farm could be criticized for its many "falsehoods" regarding the capabilities of animals to speak English.[23] He asked: Do your humourless colleagues who brought this action want Portland State to become the laughing stock of the academic world? Or at least the world of serious scientific scholarship uncontaminated by pretentious charlatans of exactly the kind Dr Boghossian and his colleagues were satirising? The psychologist Jonathan Haidt stated that the inquiry would be "a profound moral error—an injustice—that will be obvious to all who hear about your decision, and that will have bad effects upon the public perception of PSU and of universities in general", and concluded that Boghossian and his co-authors are whistleblowers, who undertook a "career-risking project to stand up for academic integrity by exposing what is, arguably, an academic subculture that tolerates intellectual fraud."[25][26] Philosopher Daniel Dennett stated that Boghossian's targets "could learn a few things about academic integrity" from his "fine example", undertaken "in good faith".[25] Alan Sokal and Jordan Peterson also supported Boghossian.[25] The World Socialist Web Site's Eric London said the hoax was "a well-timed blow" against the "identity politics industry" and postmodernism.[27] Criticism On Slate, Daniel Engber wrote that the hoaxers' project "say[s] nothing whatsoever about the fields [the hoaxers] chose to target". Since "[w]e know from long experience that expert peer review offers close to no protection against outright data fraud", Engber asserted that "one could have run this sting on almost any empirical discipline and returned the same result" even if such disciplines' journals were peer-reviewed,[12] echoing Tim Smith-Laing's The Daily Telegraph article.[a][28] Sarah Richardson, Harvard University professor of women's studies, criticized the hoaxers for not including a control group in their experiment, telling BuzzFeed News: "By their own standards, we can't scientifically conclude anything from it."[29] Evolutionary biologist Carl T. Bergstrom in The Chronicle of Higher Education wrote that "the hoaxers appear woefully naïve about how the system actually works", adding that peer review is not designed to remove fraud or even absurd ideas, and that replication will lead to self-correction.[21] In the same article, David Schieber said he was one of the two anonymous reviewers for "Rubbing One Out", and argued that the hoaxers selectively quoted from his review. "They were turning my attempt to help the authors of a rejected paper into an indictment of my field and the journal I reviewed for, even though we rejected the paper."[21] Ten Portland State University professors signed an open letter saying the hoax was not comparable to the Sokal affair, the latter taking place during "a time of debate and exploration in the field of philosophy and science", and that the trio were only exploiting "credulous journalists interested mainly in spectacle" to conduct academic fraud. They compared the trio's style to "Trumpist politics" and wrote that "[d]esperate reasoning, basic spite and a perverse interest in public humiliation seem to have overridden any actual scholarly goals."[30] The authors asked to remain anonymous, alleging Boghossian had targeted academics at other institutions and that they would likely receive "threats of death and assault from online trolls".[30] An n+1 article pointed out "blatant manipulation of its own “data,” the lack of meaningful controls".[31] In UnHerd, Chivers noted that while the so-called "grievance studies" fields "probably" contain more "bullshit [...] than most scientific fields", the hoax project distracted attention from problems of shoddy scholarship across the entirety of academia, including the "whole of science, especially psychology and medicine". He highlighted that several weeks prior to the project's public revelation, professor of food behaviour Brian Wansink had resigned from his position at Cornell University following exposure of instances of scientific misconduct on his part.[19] Mikko Lagerspetz analyzed the project's experimental design and its possible results, based on the peer reviews and editorial decisions available through the project's website. He sums it up on the journal Science, Technology, and Human Values:[32] (1) journals with higher impact factors were more likely to reject papers submitted as part of the project; (2) the chances were better, if the manuscript was allegedly based on empirical data; (3) peer reviews can be an important asset in the process of revising a manuscript; and (4) when the project authors, with academic education from neighboring disciplines, closely followed the reviewers' advice, they were able to learn relatively quickly what is needed for writing an acceptable article. The boundary between a seriously written paper and a "hoax" gradually became blurred. Finally (5), the way the project ended showed that in the long run, the scientific community will uncover fraudulent practices. He concludes that the experiment was flawed both experimentally and ethically, and failed to provide the evidence it sought.[33] It is unclear, on what grounds the project group decided what journals to target.[34] One third (7) of the 21 final editorial decisions the authors received were positive, two thirds of the decisions were negative. In the absence of a control group, it is impossible to tell whether this proportion would have been lower or higher within other disciplines.[35] |
反応 このプロジェクトは賞賛と批判の両方を呼んだ。科学ライターのトム・チヴァースは、ジェンダー研究にすでに懐疑的な人々が「この分野全体がいかにナンセン スにまみれているか」を示す証拠として歓迎する一方で、ジェンダー研究に同情的な人々は「優れた学問を不誠実に損なっている」と考え、「予想通りの大騒 動」になったと示唆した[19]。 政治学者のヤッシャ・モウンクは、アラン・ソーカルが成し遂げたソーカル事件のデマにちなんで「ソーカルの二乗」と名付け、「結果は愉快で楽しい。また、 学問の大部分が抱える深刻な問題を示している」と述べた。心理学者のスティーブン・ピンカーは、このプロジェクトは「クリティカル/ポーモ/アイデンティ ティ/『理論』ジャーナルに掲載されないような突飛なアイデアはあるのだろうか」という疑問を投げかけていると述べた[8]。対照的に、古典学者である ジョエル・P・クリステンセンとマシュー・A・シアーズは、これを2015年に作成された「家族計画連盟に関する詐欺的なヒットピースと学術的に同等」で あり、正当な議論よりも宣伝に関心があると言及した[20]。 アトランティック』誌でマウンクは、「この憂鬱な国家的瞬間における他のあらゆるものと同様に、『ソーカル・スクエアード』はすでにアメリカの偉大な文化 戦争の弾薬として使われている」と述べた。彼は、この事件に対する2つの反応を "知的不誠実 "であるとし、それは、この事件を広く学界の信用を失墜させるために利用した右派の反応と、政治的動機による学界への攻撃として扱った左派の反応である。 前者は、社会学の学術誌に投稿された論文がすべてリジェクトされたという事実を含め、「学術界にはナンセンスにまったく我慢ならない分野がたくさんある」 ことを見落としているとし、後者はデマに反論する代わりにその背後にある動機を攻撃していると述べた[3]。 出版ジャーナル編集者の反応 デマ論文のひとつ(「When the Joke's on You」、デマに対するフェミニスト批判と称している)を受理したものの、まだ出版していなかったHypatiaの共同編集者であるアン・ギャリーは、こ のデマには「深く失望した」と述べた。ギャリーはニューヨーク・タイムズ紙に対し、「査読者は有意義な批評を書くために多大な時間と労力を費やしており、 個人が不正な学術的資料を提出するという考えは、多くの倫理的・学術的規範に違反している」と述べた[2]: 論文/著者の信憑性に関して貴重な点が学ばれたが......『研究』の著者は明らかに欠陥のある非倫理的な研究に従事していた」[2]。 称賛 ジョンズ・ホプキンス大学のヤッシャ・モウンク氏は、著者たちはデマを準備したことで好意を受けたわけではないが、ポストモダンの専門用語に習熟している ことを示し、問題のジャーナルを嘲笑しただけでなく、より重要なことは、経済学のような「道徳的に疑わしい」分野に対するデマは喜んで歓迎するが、自分た ちの方法に対する批判は受け入れられないジェンダー研究の二重基準を明らかにしたことだと述べた。彼はまた、「このデマが左翼や学者の間で引き起こしてい る部族的連帯の多さ」と、反応の多くが純粋に中傷的なものである一方、デマによって浮き彫りにされた実際の問題があることを実際に指摘しているものはほと んどないという事実を指摘した: 「ジェンダー研究のような分野の一流ジャーナルのいくつかは、本当の学問と、知的空虚で道徳的に問題のあるでたらめを区別できていない」。 [21]対照群を欠いた3人組が、「統計学が適用されない問題に統計学を持ち込もうとする混乱した試み」に従事したという苦情を拒否し、マウンクは、3人 組はそもそも「その種のことは何も」約束しておらず、その代わりに、問題のジャーナルに「でたらめを掲載させることは可能である[......]」ことを 実証するという彼らの目標を成功裏に達成したと述べた[8]。 ジャスティン・E・H・スミスは、イタリア・ルネサンスから2000年代までの一連のデマの例を示しながら、デマを知的あるいは学術的な行為として擁護し た。クロニクル・オブ・ハイヤー・エデュケーション』誌において、ヘザー・E・ヘイングは、このデマが「科学と論理の否定」や「探究よりも活動主義を称揚 する」といった近代社会科学の多くの病理を暴くのに役立ったと指摘している[21]。 ボゴシアンの雇用主であるポートランド州立大学が、ヒトを対象とした研究を無許可で行ったという理由で研究不正行為の調査を開始し、さらにデータを捏造し たという容疑も検討した[22]ところ、スティーブン・ピンカーやポートランド州立大学の様々な学生を含む多くの著名な学者が彼を支持する書簡を提出し [23]、デマの動機を擁護した。 [24] リチャード・ドーキンスはボゴシアンを小説家になぞらえ、ジョージ・オーウェルの小説『動物農場』は動物が英語を話す能力に関して多くの「虚偽」があるた め批判される可能性があると指摘した[23]: この訴訟を起こしたユーモアのない同僚たちは、ポートランド州立大学が学界の笑いものになることを望んでいるのか?少なくとも、ボゴシアン博士と彼の同僚 が風刺していたような、気取ったチャラ男たちに汚染されていない、まじめな科学研究の世界にしたいのだろうか? 心理学者のジョナサン・ハイトは、この調査は「深遠な道義的誤り-不正義-であり、この決定を耳にする者すべてに明らかであり、PSUや大学全般に対する 社会的認識に悪影響を及ぼすだろう」と述べ、ボゴシアンと共著者は「キャリアを賭して、知的不正を容認する学問のサブカルチャーを暴露することによって、 学問の誠実さのために立ち上がるプロジェクト」を行った内部告発者であると結論づけた[25][26]。 「25][26]哲学者のダニエル・デネットは、ボゴシアンのターゲットは「誠意を持って」取り組んだ彼の「素晴らしい模範」から「学問的誠実さについて いくつかのことを学ぶことができる」と述べた[25]。 世界社会主義者ウェブサイトのエリック・ロンドンは、このデマは「アイデンティティ政治産業」とポストモダニズムに対する「タイミングのいい一撃」である と述べた[27]。 批判 ダニエル・エングバーはSlate誌上で、デマ発信者のプロジェクトは「(デマ発信者が)ターゲットに選んだ分野については何も語っていない」と書いた。 専門家による査読は、明らかなデータ詐欺に対してほとんど何の防御にもならないことを、我々は長い経験から知っている」ので、Engberは、たとえその ような学問分野の雑誌が査読を受けていたとしても、「ほとんどどのような経験的な学問分野に対しても、この囮捜査を行うことができ、同じ結果を返すことが できた」と主張し[12]、Tim Smith-LaingのThe Daily Telegraphの記事を反響させた[a][28]。 ハーバード大学のサラ・リチャードソン教授(女性学)は、デマを流した側が実験に対照群を含まなかったことを批判し、BuzzFeed Newsに語った: 「彼ら自身の基準では、そこから科学的に何かを結論づけることはできない」[29]。 進化生物学者のカール・T・バーグストロムは、『クロニクル・オブ・ハイヤー・エデュケーション』誌に、「デマ投稿者たちは、システムが実際にどのように 機能しているかについて、ひどくナイーブに見える」と書き、査読は不正行為や不合理なアイデアさえ取り除くようには設計されておらず、再現は自己修正につ ながると付け加えた[21]。 同じ記事の中で、デイヴィッド・シーバーは、自分が『Rubbing One Out』の2人の匿名査読者のうちの1人であったと述べ、デマ投稿者たちは彼の査読から選択的に引用していると主張した。"彼らは、リジェクトされた論文 の著者を助けようとした私の試みを、論文をリジェクトしたにもかかわらず、私の分野と私が査読したジャーナルに対する非難に変えていた"[21]。 ポートランド州立大学の10人の教授が公開書簡に署名し、このデマはソーカル事件とは比較にならず、ソーカル事件は「哲学と科学の分野で議論と探究が盛ん な時期」に起こったものであり、3人組は「主に見世物に興味を持つ信心深いジャーナリスト」を利用して学術的詐欺を行ったに過ぎないと述べた。彼らは3人 組のスタイルを「トランプ主義政治」と比較し、「絶望的な推論、基本的な腹いせ、公衆の屈辱に対する倒錯した関心が、実際の学問的目標に優先しているよう だ」と書いている[30]。著者たちは匿名を希望し、ボゴシアンが他の研究機関の学者を標的にしたことがあり、「オンラインの荒らしから殺害や暴行の脅 迫」を受ける可能性が高いと主張している[30]。 n+1の記事は「自らの「データ」の露骨な操作、意味のある管理の欠如」を指摘した[31]。 UnHerd』においてチヴァースは、いわゆる「苦情研究」の分野には「おそらく」「ほとんどの科学分野よりも」多くの「でたらめ[...]」が含まれて いるが、このデマプロジェクトは、「科学全体、特に心理学と医学」を含む学界全体の粗雑な学問の問題から注意をそらすものであったと指摘した。彼は、この プロジェクトが公になる数週間前に、ブライアン・ワンシンク教授(食行動学)がコーネル大学の職を辞し、彼の科学的不正行為が暴露されたことを強調した [19]。 ミッコ・ラガーペッツは、プロジェクトのウェブサイトを通じて入手可能な査読と編集上の決定に基づいて、プロジェクトの実験デザインとその可能性のある結 果を分析した。彼は学術誌『Science, Technology, and Human Values』で次のようにまとめている[32]。 (1)インパクトファクターの高いジャーナルは、プロジェクトの一環として投稿された論文をリジェクトする可能性が高い。(2)経験的データに基づくとさ れる原稿であれば、その可能性はより高い。(3)査読は、原稿を修正するプロセスにおいて重要な資産となり得る。(4)近隣の学問分野の教育を受けたプロ ジェクトの著者が査読者のアドバイスに忠実に従った場合、受け入れられる論文を書くために必要なことを比較的早く学ぶことができた。真面目に書かれた論文 と "デマ "の境界は次第に曖昧になっていった。最後に(5)、このプロジェクトの結末は、長い目で見れば科学界は不正行為を摘発することを示した。 彼は、この実験は実験的にも倫理的にも欠陥があり、求めていた証拠を提供することができなかったと結論づけている[33]。プロジェクトグループがどのよ うな根拠に基づいて対象とするジャーナルを決定したかは不明である[34]。対照グループがないため、この割合が他の学問分野ではもっと低かったのか高 かったのかはわからない[35]。 |
| List of hoax papers Accepted Published Following the discovery of the hoax, all four papers were retracted: Helen Wilson (pseudonym) (2018). "Human Reactions to Rape Culture and Queer Performativity at Urban Dog Parks in Portland, Oregon". Gender, Place & Culture: 1–20. doi:10.1080/0966369X.2018.1475346. (Retracted) Richard Baldwin (borrowed identity) (2018). "Who Are They to Judge? Overcoming Anthropometry and a Framework for Fat Bodybuilding". Fat Studies. 7 (3): i–xiii. doi:10.1080/21604851.2018.1453622. (Retracted) M. Smith (pseudonym) (2018). "Going in Through the Back Door: Challenging Straight Male Homohysteria and Transphobia through Receptive Penetrative Sex Toy Use". Sexuality & Culture. 22 (4): 1542. doi:10.1007/s12119-018-9536-0. (Retracted) Richard Baldwin (borrowed identity) (2018). "An Ethnography of Breastaurant Masculinity: Themes of Objectification, Sexual Conquest, Male Control, and Masculine Toughness in a Sexually Objectifying Restaurant". Sex Roles. 79 (11–12): 762. doi:10.1007/s11199-018-0962-0. (Retracted) Not yet published Richard Baldwin (borrowed identity). "When the Joke Is on You: A Feminist Perspective on How Positionality Influences Satire". Hypatia. Carol Miller (pseudonym). "Moon Meetings and the Meaning of Sisterhood: A Poetic Portrayal of Lived Feminist Spirituality". Journal of Poetry Therapy. Maria Gonzalez, and Lisa A. Jones (pseudonyms). "Our Struggle Is My Struggle: Solidarity Feminism as an Intersectional Reply to Neoliberal and Choice Feminism". Affilia. Considered Revise and resubmit Richard Baldwin (borrowed identity). "Agency as an Elephant Test for Feminist Porn: Impacts on Male Explicit and Implicit Associations about Women in Society by Immersive Pornography Consumption". Porn Studies. Maria Gonzalez (pseudonym). "The Progressive Stack: An Intersectional Feminist Approach to Pedagogy". Hypatia. Stephanie Moore (pseudonym). "Super-Frankenstein and the Masculine Imaginary: Feminist Epistemology and Superintelligent Artificial Intelligence Safety Research". Feminist Theory. Maria Gonzalez (pseudonym). "Stars, Planets, and Gender: A Framework for a Feminist Astronomy". Women's Studies International Forum. Under review Carol Miller (pseudonym). "Strategies for Dealing with Cisnormative Discursive Aggression in the Workplace: Disruption, Criticism, Self-Enforcement, and Collusion". Gender, Work and Organization. Rejected Lisa A. Jones (pseudonym). "Rubbing One Out: Defining Metasexual Violence of Objectification Through Nonconsensual Masturbation". Sociological Theory. Carol Miller (pseudonym). "My Struggle to Dismantle My Whiteness: A Critical-Race Examination of Whiteness from within Whiteness". Sociology of Race and Ethnicity. Carol Miller (pseudonym). "Queering Plato: Plato's Allegory of the Cave as a Queer-Theoretic Emancipatory Text on Sexuality and Gender". GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies. Richard Baldwin (borrowed identity). "'Pretty Good for a Girl': Feminist Physicality and Women's Bodybuilding". Sociology of Sport Journal. Richard Baldwin (borrowed identity). "Grappling with Hegemonic Masculinity: The Roles of Masculinity and Heteronormativity in Brazilian Jiu Jitsu". International Review for the Sociology of Sport. Richard Baldwin (borrowed identity). "Hegemonic Academic Bullying: The Ethics of Sokal-style Hoax Papers on Gender Studies". Journal of Gender Studies. Richard Baldwin (borrowed identity). "Self-Reflections on Self-Reflections: An Autoethnographic Defense of Autoethnography". Journal of Contemporary Ethnography. Brandon Williams (pseudonym). "Masculinity and the Others Within: A Schizoethnographic Approach to Autoethnography". Qualitative Inquiry. Helen Wilson (pseudonym). "Rebraiding Masculinity: Redefining the Struggle of Women Under the Domination of the Masculinity Trinity". Signs. |
デマ論文のリスト 受理 掲載 デマが発見された後、4本の論文はすべて撤回された。 ヘレン・ウィルソン(ペンネーム)(2018)。「オレゴン州ポートランドの都市型ドッグパークにおけるレイプ文化とクィア・パフォーマティビティに対す る人間の反応」。Gender, Place & Culture: 1–20. doi:10.1080/0966369X.2018.1475346. (撤回) リチャード・ボールドウィン(借用した身元)(2018)。「誰が彼らを裁くのか?人体測定学と太ったボディビルディングの枠組みの克服」。Fat Studies. 7 (3): i–xiii. doi:10.1080/21604851.2018.1453622. (撤回) M. スミス(偽名)(2018)。「裏口から入る:受容的な挿入型大人のおもちゃの使用を通じて、ストレートの男性のホモヒステリーとトランスフォビアに挑戦 する」。セクシュアリティ&カルチャー。22 (4): 1542. doi:10.1007/s12119-018-9536-0. (撤回) リチャード・ボールドウィン(仮名)(2018)。「ブレストレストランの男らしさの民族誌:性的客観化レストランにおける客観化、性的征服、男性の支 配、男らしいタフさのテーマ」。Sex Roles. 79 (11–12): 762. doi:10.1007/s11199-018-0962-0. (撤回) 未発表 リチャード・ボールドウィン(借用名)。「冗談の矛先が自分に向いたとき:立場が風刺に与える影響に関するフェミニスト的視点」。ヒュパティア。 キャロル・ミラー(仮名)。「月の会合と姉妹愛の意味:生きたフェミニストの精神性を詩的に描く」。詩療法ジャーナル。 マリア・ゴンザレス、リサ・A・ジョーンズ(仮名)。「私たちの闘いは私の闘いである:新自由主義と選択的フェミニズムに対する交差的応答としての連帯フェミニズム」。アフィリア。 検討中 修正して再提出 リチャード・ボールドウィン(借用したアイデンティティ)。「フェミニストポルノの象のテストとしての主体性:没入型ポルノ消費が、社会における女性に関する男性の明示的および暗黙的な連想に与える影響」。ポルノ研究。 マリア・ゴンザレス(ペンネーム)。「プログレッシブ・スタック:教育学に対する交差的フェミニスト的アプローチ」。ヒュパティア。 ステファニー・ムーア(ペンネーム)。「スーパーフランケンシュタインと男性的想像力:フェミニスト認識論と超知能人工知能の安全性研究」。フェミニスト理論。 マリア・ゴンザレス(ペンネーム)。「星、惑星、そしてジェンダー:フェミニスト天文学の枠組み」。女性学国際フォーラム。 審査中 キャロル・ミラー(仮名)。「職場におけるシス規範的言説的攻撃への対処戦略:妨害、批判、自己強制、共謀」。『ジェンダー、労働、組織』。 却下 リサ・A・ジョーンズ(仮名)。「自慰行為:非合意的自慰による客体化のメタ性的暴力を定義する」。『社会学理論』。 キャロル・ミラー(ペンネーム)。「白人としての自分の白さを解体するための私の闘い:白人内部からの白人に対する批判的人種学的考察」。人種と民族の社会学。 キャロル・ミラー(ペンネーム)。「プラトンをクィア化する:プラトンの洞窟の寓話を、セクシュアリティとジェンダーに関するクィア理論的解放のテキストとして」。GLQ:ゲイ・レズビアン研究ジャーナル。 リチャード・ボールドウィン(借りたアイデンティティ)。「女の子にしてはなかなかいい」:フェミニストの身体性と女性のボディービル」。スポーツ社会学ジャーナル。 リチャード・ボールドウィン(借りたアイデンティティ)。「覇権的な男らしさと格闘する:ブラジリアン柔術における男らしさと異性愛規範の役割」。スポーツ社会学国際レビュー。 リチャード・ボールドウィン(借りたアイデンティティ)。「ヘゲモニックなアカデミックいじめ:ジェンダー研究におけるソカル式デマ論文の倫理」。ジェンダー研究ジャーナル。 リチャード・ボールドウィン(借りたアイデンティティ)。「自己反省についての自己反省:オートエスノグラフィのオートエスノグラフィ的擁護」。現代エスノグラフィジャーナル。 ブランドン・ウィリアムズ(偽名)。「男らしさとその内なる他者たち:オートエスノグラフィに対する統合失調エスノグラフィ的アプローチ」。『Qualitative Inquiry』。 ヘレン・ウィルソン(偽名)。「男らしさの再構築:男らしさの三位一体の支配下における女性の闘争の再定義」。『Signs』。 |
| List of scholarly publishing
stings Postmodernism Generator Science wars |
学術出版の詐欺リスト ポストモダニズム生成器 科学戦争(サイエンス・ウォーズ) |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Grievance_studies_affair |
リ ンク
文 献
そ の他の情報

A
typical 19th-century phrenology
chart: During the 1820s, phrenologists claimed the mind was located in
areas of the brain, and were attacked for doubting that mind came from
the nonmaterial soul. Their idea of reading "bumps" in the skull to
predict personality traits was later discredited. Phrenology was first
termed a pseudoscience in 1843 and continues to be considered so.
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆ ☆
☆