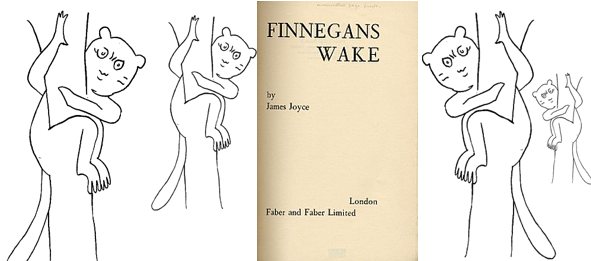
フィネガンズ・ウェイク
Finnegans Wake, 1939
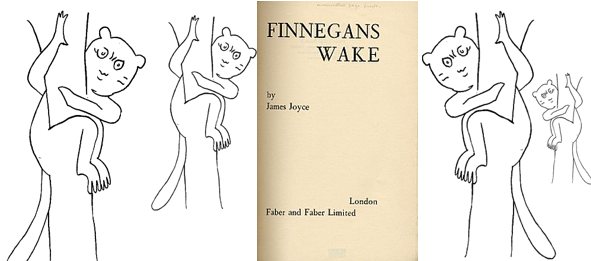
☆ フィネガンズ・ウェイク』は、アイルランドの作家ジェイムズ・ジョイスの小説。17年の歳月をかけて書かれ、1939年に出版されたジョイスの遺作であ る。この小説は、標準的な英語と、新造語、ポルトマンテー語、アイルランドのマナー、複数の言語によるダジャレを混ぜ合わせた、主に特異な言語で書かれて いる。多くの批評家は、この手法が夢や催眠術の経験を再現するジョイスの試みであり、概念、記憶、人々、場所が夢の中で融合していく様を再現していると考 えている。批評家たちはこの作品を意味不明だと評したが、ジョイスはすべての音節が正当化できると主張した。その言語学的実験、意識の流れの文体、文学的引用、自由な夢の連想、物語の慣習の放棄のために、『フィネガンズ・ウェイク』は一般大衆にはほとんど読まれ ないままである。
| Finnegans
Wake is a novel by Irish writer James Joyce. It is known for its
experimental style and its reputation as one of the most difficult
works of fiction in the Western canon.[1] Written over a period of
seventeen years and published in 1939, the novel was Joyce's final
work. It is written in a largely idiosyncratic language that blends
standard English with neologisms, portmanteau words, Irish mannerisms,
and puns in multiple languages. It has been categorized as "a work of
fiction which combines a body of fables [...] with the work of analysis
and deconstruction";[2] many critics believe the technique was Joyce's
attempt to recreate the experience of dreams and hypnagogia,
reproducing the way in which concepts, memories, people, and places
become amalgamated in dreaming.[3] It has also been regarded as an
attempt by Joyce to combine many of his prior aesthetic ideas, with
references to other works and outside ideas woven into the text.
Although critics have described it as unintelligible, Joyce asserted
that every syllable could be justified.[4]: 125 Due to its linguistic
experiments, stream of consciousness writing style, literary allusions,
free dream associations, and abandonment of narrative conventions,
Finnegans Wake remains largely unread by the general public.[5][6] Despite the obstacles, readers and commentators have reached a broad consensus about the book's central cast of characters and, to a lesser degree, its plot, but key details remain elusive.[7][8] The book explores, in an unorthodox fashion, the lives of the Earwicker family, comprising the father HCE, the mother ALP, and their three children Shem the Penman, Shaun the Postman, and Issy. Following an unspecified rumour about HCE, the book, in a nonlinear dream narrative,[9] follows his wife's attempts to exonerate him with a letter, his sons' struggle to replace him, Shaun's rise to prominence, and a final monologue by ALP at the break of dawn. The opening line of the book is a sentence fragment that continues from the book's unfinished closing line, making it cyclical.[10] Scholars have linked this cyclical structure to the influence of Giambattista Vico's The New Science, upon which they argue the structure of Finnegans Wake is based.[11][12] Joyce began working on Finnegans Wake shortly after the 1922 publication of Ulysses. By 1928 installments of Joyce's new avant-garde work began to appear, in serialized form, in Parisian literary journals The Transatlantic Review and transition [sic], under the title "fragments from Work in Progress". The actual title of the work remained a secret until the book was published in its entirety, on 4 May 1939.[13] The initial reception of Finnegans Wake, both in its serialized form and especially in its final published form, was largely negative, ranging from bafflement at its radical reworking of the English language to open hostility towards its seeming pointlessness and lack of respect for literary conventions.[14] The work has since come to assume a preeminent place in English literature. Anthony Burgess has lauded Finnegans Wake as "a great comic vision, one of the few books of the world that can make us laugh aloud on nearly every page".[15] Literary scholar Harold Bloom called it Joyce's masterpiece, and, in The Western Canon (1994), wrote that "if aesthetic merit were ever again to center the canon, [Finnegans Wake], like Proust's [In Search of Lost Time], would be as close as our chaos could come to the heights of Shakespeare and Dante".[16] |
フィ
ネガンズ・ウェイク』は、アイルランドの作家ジェイムズ・ジョイスの小説。17年の歳月をかけて書かれ、1939年に出版されたジョイスの遺作である。こ
の小説は、標準的な英語と、新造語、ポルトマンテー語、アイルランドのマナー、複数の言語によるダジャレを混ぜ合わせた、主に特異な言語で書かれている。
多くの批評家は、この手法が夢や催眠術の経験を再現するジョイスの試みであり、概念、記憶、人々、場所が夢の中で融合していく様を再現していると考えてい
る[3]。批評家たちはこの作品を意味不明だと評したが、ジョイスはすべての音節が正当化できると主張した[4]: 125
その言語学的実験、意識の流れの文体、文学的引用、自由な夢の連想、物語の慣習の放棄のために、『フィネガンズ・ウェイク』は一般大衆にはほとんど読まれ
ないままである[5][6]。 このような障害にもかかわらず、読者やコメンテーターは、この本の中心的な登場人物と、それほどでもないがそのプロットについて、大まかなコンセンサスを 得ているが、重要な詳細については、まだ掴みどころがない[7][8] 。HCEに関する不特定多数の噂に続き、本書は非線形夢物語[9]で、彼の妻が手紙で彼の容疑を晴らそうとする様子、彼に取って代わろうとする息子たちの 闘い、ショーンの出世、そして夜明けのALPによる最後の独白を描く。本書の冒頭の一行は、未完のまま本書を閉じる一行から続く文章の断片であり、循環構 造になっている[10]。学者たちはこの循環構造をジャンバティスタ・ヴィーコの『新科学』の影響と結びつけており、『フィネガンズ・ウェイク』の構造が それに基づいていると主張している[11][12]。 ジョイスは1922年に『ユリシーズ』を出版した直後に『フィネガンズ・ウェイク』の執筆を開始した。1928年までに、ジョイスの新しい前衛的な作品の 断片が、パリの文芸誌『トランスアトランティック・レヴュー』と『トランジション』[訳注]に、「進行中の作品からの断片」というタイトルで連載され始め た。フィネガンズ・ウェイク』の最初の受容は、連載の形でも、特に最終的に出版された形でも、その英語の急進的な手直しに対する困惑から、その無意味さと 文学的な慣習に対する敬意の欠如に対する公然の敵意まで、大部分が否定的だった[14]。 その後、この作品はイギリス文学の中で傑出した地位を占めるようになった。アンソニー・バージェスは『フィネガンズ・ウェイク』を「偉大なコミカル・ビ ジョンであり、ほとんどすべてのページで声をあげて笑わせることのできる、世界でも数少ない本のひとつ」と称賛している[15]。 [15] 文学者のハロルド・ブルームはこの作品をジョイスの最高傑作と呼び、『The Western Canon』(1994年)の中で、「もし美的価値が再び正典の中心となることがあるとすれば、プルーストの『失われた時を求めて』のように、(『フィネ ガンズ・ウェイク』は)我々の混沌がシェイクスピアやダンテの高みに到達できるのと同じくらい近いものになるだろう」と書いている[16]。 |
Background and composition Head
and shoulders drawing of a man with a slight moustache and narrow
goatee in a jacket, low-collared shirt and bow tie. He wears round
glasses and an eye patch over his right eye, attached by a string
around his head. Head
and shoulders drawing of a man with a slight moustache and narrow
goatee in a jacket, low-collared shirt and bow tie. He wears round
glasses and an eye patch over his right eye, attached by a string
around his head.A drawing of Joyce (with eyepatch) by Djuna Barnes from 1922, the year in which Joyce began the 17-year task of writing Finnegans Wake[17] Having completed work on Ulysses, Joyce was so exhausted that he did not write a line of prose for a year.[18] On 10 March 1923, he wrote a letter to his patron, Harriet Weaver: "Yesterday I wrote two pages—the first I have since the final Yes of Ulysses. Having found a pen, with some difficulty I copied them out in a large handwriting on a double sheet of foolscap so that I could read them."[19] This is the earliest reference to what would become Finnegans Wake.[20] The two pages in question consisted of the short sketch "Roderick O'Conor", concerning the historic last king of Ireland cleaning up after guests by drinking the dregs of their dirty glasses.[21] Joyce completed another four short sketches in July and August 1923, while holidaying in Bognor. The sketches, which dealt with different aspects of Irish history, are commonly known as "Tristan and Isolde", "Saint Patrick and the Druid", "Kevin's Orisons", and "Mamalujo".[22] While these sketches would eventually be incorporated into Finnegans Wake in one form or another, they did not contain any of the main characters or plot points which would later come to constitute the backbone of the book. The first signs of what would eventually become Finnegans Wake came in August 1923 when Joyce wrote the sketch "Here Comes Everybody", which dealt for the first time with the book's protagonist HCE.[23] Over the next few years, Joyce's method became one of "increasingly obsessional concern with note-taking, since [he] obviously felt that any word he wrote had first to have been recorded in some notebook."[24] As Joyce continued to incorporate these notes into his work, the text became increasingly dense and obscure. By 1926 Joyce had largely completed both Parts I and III. Geert Lernout asserts that Part I had, at this early stage, "a real focus that had developed out of the HCE ["Here Comes Everybody"] sketch: the story of HCE, of his wife and children. There were the adventures of Humphrey Chimpden Earwicker himself and the rumours about them in chapters 2–4, a description of his wife ALP's letter in chapter 5, a denunciation of his son Shem in chapter 7, and a dialogue about ALP in chapter 8. These texts [...] formed a unity."[25] In the same year, Joyce met Maria and Eugène Jolas in Paris, just as his new work was generating an increasingly negative reaction from readers and critics, culminating in The Dial's refusal to publish the four chapters of Part III in September 1926.[25] The Jolases gave Joyce valuable encouragement and material support throughout the long process of writing Finnegans Wake,[26] and published sections of the book in serial form in their literary magazine transition, under the title Work in Progress. For the next few years, Joyce worked rapidly on the book, adding what would become chapters I.1 and I.6, and revising the already written segments to make them more lexically complex.[27] By this time some early supporters of Joyce's work, such as Ezra Pound and the author's brother Stanislaus Joyce, had grown increasingly unsympathetic to his new writing.[28] In order to create a more favourable critical climate, a group of Joyce's supporters (including Samuel Beckett, William Carlos Williams, Rebecca West, and others) put together a collection of critical essays on the new work. It was published in 1929 under the title Our Exagmination Round His Factification for Incamination of Work in Progress.[29] In July 1929, increasingly demoralised by the poor reception his new work was receiving, Joyce approached his friend James Stephens about the possibility of Stephens completing the book. Joyce wrote to Weaver in late 1929 that he had "explained to [Stephens] all about the book, at least a great deal, and he promised me that if I found it madness to continue, in my condition, and saw no other way out, that he would devote himself, heart and soul, to the completion of it, that is the second part and the epilogue or fourth."[30] Apparently Joyce chose Stephens on superstitious grounds, as he had been born in the same hospital as Joyce, exactly one week later, and shared both the first names of Joyce himself and his fictional alter-ego Stephen Dedalus.[31] In the end, Stephens was not asked to finish the book. In the 1930s, as he was writing Parts II and IV, Joyce's progress slowed considerably. This was due to a number of factors including the death of his father John Stanislaus Joyce in 1931;[32] concern over the mental health of his daughter Lucia;[33] and his own health problems, chiefly his failing eyesight.[34] Finnegans Wake was published in book form, after seventeen years of composition, on 4 May 1939. Joyce died twenty months later in Zürich, on 13 January 1941. |
背景と構図 ジャケット、襟の低いシャツ、蝶ネクタイ姿の、少し口ひげを生やし、細いあごひげを生やした男性のヘッド・アンド・ショルダー・ドローイング。丸眼鏡をかけ、右目に眼帯をつけ、紐で頭に巻いている。 ジャケット、襟の低いシャツ、蝶ネクタイ姿の、少し口ひげを生やし、細いあごひげを生やした男性のヘッド・アンド・ショルダー・ドローイング。丸眼鏡をかけ、右目に眼帯をつけ、紐で頭に巻いている。ジョイスが『フィネガンズ・ウェイク』執筆のために17年の歳月を費やし始めた1922年に描かれた、ジュナ・バーンズによるジョイスの絵(眼帯をしている)[17]。 1923年3月10日、ジョイスはパトロンのハリエット・ウィーバーに手紙を書いた。ペンを見つけたので、少し苦労して、読めるようにフールスキャップの二枚に大きな字で書き写した」[19]。これが後の『フィネガンズ・ウェイク』への最古の言及である[20]。 ジョイスは1923年7月から8月にかけて、ボグナーで休暇を過ごしている間に、別の4つの短いスケッチを完成させた[21]。これらのスケッチは、アイ ルランドの歴史のさまざまな側面を扱ったもので、一般に「トリスタンとイゾルデ」、「聖パトリックとドルイド」、「ケヴィンのオリゾン」、「ママルーヨ」 として知られている[22]。これらのスケッチは、最終的に何らかの形で『フィネガンズ・ウェイク』に取り入れられることになるが、後にこの本の骨格を構 成することになる主要な登場人物やプロットは含まれていなかった。最終的に『フィネガンズ・ウェイク』となる最初の兆候は、ジョイスが1923年8月にス ケッチ「Here Comes Everybody」を書いたときに現れた。 その後数年にわたり、ジョイスの手法は「メモを取ることにますます執着するようになり、自分が書いた言葉はまず何らかのノートに記録されていなければならないと明らかに感じていた」[24]。 1926年までに、ジョイスは第一部と第三部の両方をほぼ完成させた。ゲールト・レルナウトは、この初期の段階で、第Ⅰ部には「HCE[「Here Comes Everybody」]のスケッチから発展した本当の焦点があった。第2章から第4章にはハンフリー・チムプデン・アーウィッカー自身の冒険とその噂、第 5章には妻ALPの手紙の描写、第7章には息子セムの糾弾、第8章にはALPについての対話があった。同年、ジョイスはパリでマリア・ジョラスとウジェー ヌ・ジョラスに出会うが、ちょうどその頃、ジョイスの新作は読者や批評家からますます否定的な反応を引き起こしており、1926年9月には『ダイヤル』誌 が第3部の4章の出版を拒否するという事態にまで発展していた[25]。その後数年間、ジョイスはこの本の執筆を急ピッチで進め、第I.1章と第I.6章 となるものを追加し、すでに書かれていた部分をより語彙的に複雑にするために改訂した[27]。 この頃までに、エズラ・パウンドやジョイスの弟スタニスラウス・ジョイスなど、ジョイスの作品を初期から支持していた人たちは、ジョイスの新しい文章に対 してますます冷淡になっていた[28]。より好ましい批評的風潮を作り出すために、ジョイスの支持者たち(サミュエル・ベケット、ウィリアム・カルロス・ ウィリアムズ、レベッカ・ウェストなど)のグループは、新しい作品についての批評エッセイ集をまとめた。1929年7月、新作の評判の悪さに意気消沈して いたジョイスは、友人のジェイムズ・スティーヴンスにスティーヴンスがこの本を完成させる可能性を打診する。ジョイスは1929年末にウィーヴァーに、 「(スティーヴンスに)この本についてすべて、少なくとも多くのことを説明し、もし私がこの状態で続けることに狂気を感じ、他に道がないと判断したなら、 彼はこの本の完成、つまり第2部とエピローグ、第4部の完成に心血を注ぐと約束してくれた」と書いている[30]。 「ジョイスがスティーブンスを選んだのは、彼がジョイスと同じ病院でちょうど1週間後に生まれ、ジョイス自身と彼の架空の分身であるスティーヴン・デダラ スと同じ名字だったからである。 1930年代、第Ⅱ部と第Ⅳ部の執筆中、ジョイスの進行はかなり遅くなった。これは1931年の父ジョン・スタニスラウス・ジョイスの死[32]、娘ルシ アの精神的健康に対する懸念[33]、そして彼自身の健康問題、特に視力の衰えなど、多くの要因によるものであった[34]。 フィネガンズ・ウェイク』は1939年5月4日、17年の構想を経て単行本として出版された。ジョイスはその20ヵ月後、1941年1月13日にチューリッヒで死去。 |
| Chapter summaries Finnegans Wake consists of seventeen chapters, divided into four Parts or Books. Part I contains eight chapters, Parts II and III each contain four, and Part IV consists of only one short chapter. The chapters appear without titles, and while Joyce never provided possible chapter titles as he had done for Ulysses, he did title various sections published separately (see Publication history below). The standard critical practice is to indicate part number in Roman numerals, and chapter title in Arabic, so that III.2, for example, indicates the second chapter of the third part. Given the book's fluid and changeable approach to plot and characters, a definitive, critically agreed-upon plot synopsis remains elusive (see Critical response and themes: Difficulties of plot summary below). Therefore, the following synopsis attempts to summarise events in the book, which find general, although inevitably not universal, consensus among critics. Part I "In the first chapter of Finnegans Wake Joyce describes the fall of the primordial giant Finnegan and his awakening as the modern family man and pub owner H.C.E." – Donald Phillip Verene's summary and interpretation of the Wake's episodic opening chapter[35] The entire work forms a cycle: the last sentence—a fragment—recirculates to the beginning sentence: "a way a lone a last a loved a long the / riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs." Joyce himself revealed that the book "ends in the middle of a sentence and begins in the middle of the same sentence."[36] The introductory chapter (I.1) establishes the book's setting as "Howth Castle and Environs" (i.e. the Dublin area), and introduces Dublin hod carrier "Finnegan", who falls to his death from a ladder while constructing a wall.[37][38] Finnegan's wife Annie puts out his corpse as a meal spread for the mourners at his wake, but he vanishes before they can eat him.[38] A series of episodic vignettes follows, loosely related to the dead Finnegan, most commonly referred to as "The Willingdone Museyroom",[39] "Mutt and Jute",[40][41] and "The Prankquean".[42] At the chapter's close a fight breaks out, whiskey splashes on Finnegan's corpse, and "the dead Finnegan rises from his coffin bawling for whiskey and his mourners put him back to rest",[43] persuading him that he is better off where he is.[44] The chapter ends with the image of the HCE character sailing into Dublin Bay to take a central role in the story.  Figure of a young woman sitting on a slope with legs crossed. It is in the middle of a rectangular fountain, surrounded by flowing water. Fountain in Dublin representing Anna Livia Plurabelle, a character in Finnegans Wake I.2 opens with an account of "Harold or Humphrey" Chimpden receiving the nickname "Earwicker" from the Sailor King, who encounters him attempting to catch earwigs with an inverted flowerpot on a stick while manning a tollgate through which the King is passing. This name helps Chimpden, now known by his initials HCE, to rise to prominence in Dublin society as "Here Comes Everybody". He is then brought low by a rumour that begins to spread across Dublin, apparently concerning a sexual trespass involving two girls in the Phoenix Park, although details of HCE's transgression change with each retelling of events. Chapters I.2 through I.4 follow the progress of this rumour, starting with HCE's encounter with "a cad with a pipe" in Phoenix Park. The cad greets HCE in Gaelic and asks the time, but HCE misunderstands the question as an accusation, and incriminates himself by denying rumours the cad has not yet heard. These rumours quickly spread across Dublin, gathering momentum until they are turned into a song penned by the character Hosty called "The Ballad of Persse O'Reilly". As a result, HCE goes into hiding, where he is besieged at the closed gate of his pub by a visiting American looking for a drink after hours.[45] HCE remains silent – not responding to the accusations or verbal abuse – dreams, is buried in a coffin at the bottom of Lough Neagh,[46] and is finally brought to trial, under the name Festy King. He is eventually freed, and goes once more into hiding. An important piece of evidence during the trial – a letter about HCE written by his wife ALP – is called for so that it can be examined in closer detail. ALP's letter becomes the focal point as it is analysed in detail in I.5. This letter was dictated by ALP to her son Shem, a writer, and entrusted to her other son Shaun, a postman, for delivery. The letter never reaches its intended destination, ending up in a midden heap where it is unearthed by a hen named Biddy. Chapter I.6 digresses from the narrative in order to present the main and minor characters in more detail, in the form of twelve riddles and answers. In the eleventh question or riddle, Shaun is asked about his relation to his brother Shem, and as part of his response, tells the parable of the Mookse and the Gripes.[47]: 117–122 In the final two chapters of Part I, we learn more about the letter's writer Shem the Penman (I.7) and its original author, his mother ALP (I.8). The Shem chapter consists of "Shaun's character assassination of his brother Shem", describing the hermetic artist as a forger and a "sham", before "Shem is protected by his mother [ALP], who appears at the end to come and defend her son."[48] The following chapter concerning Shem's mother, known as "Anna Livia Plurabelle", is interwoven with thousands of river names from all over the globe, and is widely considered the book's most celebrated passage.[49] The chapter was described by Joyce in 1924 as "a chattering dialogue across the river by two washerwomen who as night falls become a tree and a stone."[50] These two washerwomen gossip about ALP's response to the allegations laid against her husband HCE, as they wash clothes in the River Liffey. ALP is said to have written a letter declaring herself tired of her mate. Their gossip then digresses to her youthful affairs and sexual encounters, before returning to the publication of HCE's guilt in the morning newspaper, and his wife's revenge on his enemies: borrowing a "mailsack" from her son Shaun the Post, she delivers presents to her 111 children. At the chapter's close, the washerwomen try to pick up the thread of the story, but their conversation is increasingly difficult as they are on opposite sides of the widening Liffey, and it is getting dark. Finally, as they turn into a tree and a stone, they ask to be told a Tale of Shem or Shaun.[51] Part II While Part I of Finnegans Wake deals mostly with the parents HCE and ALP, Part II shifts that focus to their children, Shem, Shaun and Issy. II.1 opens with a pantomime programme, which outlines, in relatively clear language, the identities and attributes of the book's main characters. The chapter then concerns a guessing game among the children, in which Shem is challenged three times to guess by "gazework" the colour which the girls have chosen.[52] Unable to answer due to his poor eyesight, Shem goes into exile in disgrace, and Shaun wins the affection of the girls. Finally, HCE emerges from the pub and in a thunder-like voice calls the children inside.[53] Chapter II.2 follows Shem, Shaun and Issy studying upstairs in the pub, after having been called inside in the previous chapter.[54][55] The chapter depicts "[Shem] coaching [Shaun] how to do Euclid Bk I, 1", structured as "a reproduction of a schoolboys' (and schoolgirls') old classbook complete with marginalia by the twins, who change sides at half time, and footnotes by the girl (who doesn't)".[56][57] Once Shem (here called Dolph) has helped Shaun (here called Kev) to draw the Euclid diagram, the latter realises that he has drawn a diagram of ALP's genitalia, and "Kev finally realises the significance of the triangles [..and..] strikes Dolph." After this "Dolph forgives Kev" and the children are given "[e]ssay assignments on 52 famous men."[58] The chapter ends with the children's "nightletter" to HCE and ALP, in which they are "apparently united in a desire to overcome their parents."[59] "Section 1: a radio broadcast of the tale of Pukkelsen (a hunchbacked Norwegian Captain), Kersse (a tailor) and McCann (a ship's husband) in which the story is told inter alia of how HCE met and married ALP. Sections 2–3: an interruption in which Kate (the cleaning woman) tells HCE that he is wanted upstairs, the door is closed and the tale of Buckley is introduced. Sections 4–5: the tale, recounted by Butt and Taff (Shem and Shaun) and beamed over the television, of how Buckley shot the Russian General (HCE) – Danis Rose's overview of the extremely complex chapter 2.3, which he believes takes place in the bar of Earwicker's hotel[60]" II.3 moves to HCE working in the pub below the studying children. As HCE serves his customers, two narratives are broadcast via the bar's radio and television sets, namely "The Norwegian Captain and the Tailor's Daughter",[61][62] and "How Buckley Shot the Russian General". The first portrays HCE as a Norwegian Captain succumbing to domestication through his marriage to the Tailor's Daughter. The latter, told by Shem and Shaun ciphers Butt and Taff, casts HCE as a Russian General who is shot by Buckley, an Irish soldier in the British army during the Crimean War.[63] Earwicker has been absent throughout the latter tale, having been summoned upstairs by ALP. He returns and is reviled by his customers, who see Buckley's shooting of the General as symbolic of Shem and Shaun's supplanting their father.[64] This condemnation of his character forces HCE to deliver a general confession of his crimes, including an incestuous desire for young girls.[65][66][67][68] Finally a policeman arrives to send the drunken customers home, the pub is closed up,[69] and the customers disappear singing into the night as a drunken HCE, clearing up the bar and swallowing the dregs of the glasses left behind, morphs into ancient Irish high king Rory O'Connor, and passes out.[70][71] II.4, portraying the drunken and sleeping Earwicker's dream, chronicles the spying of four old men (Matthew, Mark, Luke and John) on Tristan and Iseult's journey.[72] The short chapter portrays "an old man like King Mark being rejected and abandoned by young lovers who sail off into a future without him",[73] while the four old men observe Tristan and Isolde, and offer four intertwining commentaries on the lovers and themselves which are "always repeating themselves".[74] Part III Part III concerns itself almost exclusively with Shaun, in his role as postman, having to deliver ALP's letter, which was referred to in Part I but never seen.[75][76] III.1 opens with the Four Masters' ass narrating how he thought, as he was "dropping asleep",[77] he had heard and seen an apparition of Shaun the Post.[78] As a result, Shaun re-awakens and, floating down the Liffey in a barrel, is posed fourteen questions concerning the significance and content of the letter he is carrying. Shaun, "apprehensive about being slighted, is on his guard, and the placating narrators never get a straight answer out of him."[79] Shaun's answers focus on his own boastful personality and his admonishment of the letter's author – his artist brother Shem. The answer to the eighth question contains the story of the Ondt and the Gracehoper, another framing of the Shaun-Shem relationship.[80]: 229–231 After the inquisition Shaun loses his balance and the barrel in which he has been floating careens over and he rolls backwards out of the narrator's earshot, before disappearing completely from view.[81] In III.2 Shaun re-appears as "Jaunty Jaun" and delivers a lengthy and sexually suggestive sermon to his sister Issy, and her twenty-eight schoolmates from St. Brigid's School. Throughout this book Shaun is continually regressing, changing from an old man to an overgrown baby lying on his back, and eventually, in III.3, into a vessel through which the voice of HCE speaks again by means of a spiritual medium. This leads to HCE's defence of his life in the passage "Haveth Childers Everywhere". Part III ends in the bedroom of Mr. and Mrs. Porter as they attempt to copulate while their children, Jerry, Kevin and Isobel Porter, are sleeping upstairs and the dawn is rising outside (III.4). Jerry awakes from a nightmare of a scary father figure, and Mrs. Porter interrupts the coitus to go comfort him with the words "You were dreamend, dear. The pawdrag? The fawthrig? Shoe! Hear are no phanthares in the room at all, avikkeen. No bad bold faathern, dear one."[82] She returns to bed, and the rooster crows at the conclusion of their coitus at the Part's culmination.[83] Part IV "1: The waking and resurrection of [HCE]; 2: the sunrise; 3: the conflict of night and day; 4: the attempt to ascertain the correct time; 5: the terminal point of the regressive time and the [Shaun] figure of Part III; 6: the victory of day over night; 7: the letter and monologue of [ALP] – Roland McHugh's summary of the events of Part IV[84]" Part IV consists of only one chapter, which, like the book's opening chapter, is mostly composed of a series of seemingly unrelated vignettes. After an opening call for dawn to break,[85] the remainder of the chapter consists of the vignettes "Saint Kevin", "Berkely and Patrick" and "The Revered Letter".[86][87] ALP is given the final word, as the book closes on a version of her Letter[88] and her final long monologue, in which she tries to wake her sleeping husband, declaring "Rise up, man of the hooths, you have slept so long!",[89] and remembers a walk they once took, and hopes for its re-occurrence. At the close of her monologue, ALP – as the river Liffey – disappears at dawn into the ocean. The book's last words are a fragment, but they can be turned into a complete sentence by attaching them to the words that start the book: A way a lone a last a loved a long the / riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs. |
各章の要約 フィネガンズ・ウェイク』は17章から成り、4つのパート(本)に分かれている。第I部には8章、第II部と第III部にはそれぞれ4章、第IV部には短 い1章のみが収められている。ジョイスは『ユリシーズ』のように章ごとにタイトルをつけることはしなかったが、別々に出版されたさまざまな部分にタイトル をつけている(下記の出版史を参照)。標準的な批評のやり方は、ローマ数字で部数を示し、アラビア数字で章のタイトルを示すというもので、例えば III.2は第3部の第2章を示す。 プロットや登場人物に対する本書のアプローチが流動的で変化しやすいことを考えると、批評的に合意された決定的なあらすじは、依然としてつかみどころがな い(以下の「批評家の反応とテーマ:プロット要約の難しさ」を参照)。そのため、以下のあらすじは、批評家の間で普遍的ではないにせよ、一般的なコンセン サスを得られるような、本書における出来事の要約を試みている。 第一部 「フィネガンズ・ウェイク』の第1章では、ジョイスは原初の巨人フィネガンの没落と、現代の家庭人でありパブの主人であるH.C.E.としての目覚めを描いている。- ドナルド・フィリップ・ヴェレーンの『ウェイク』エピソード的序章の要約と解釈[35]。 作品全体が一つのサイクルを形成している:最後の文(断片)は冒頭の文へと循環する: 「イヴとアダムの家を過ぎ、海岸のうねりから湾の曲がり角まで、一筋の道、最後の道、愛した長い道、/リヴァーランは、循環のコモディウス・ヴィカスに よって、ハウズ城とその周辺へとわれわれを連れ戻す」。ジョイス自身、この本は「文の途中で終わり、同じ文の途中で始まる」と明かしている[36]。 序章(I.1)では、本書の舞台が「ハウズ城とその周辺」(すなわちダブリン地域)であることが明らかにされ、壁を建設中に梯子から転落死したダブリンの ホッドキャリア「フィネガン」が紹介される。 [フィネガンの妻アニーは、通夜の弔問客のために彼の亡骸を撒き餌として出すが、彼は食べられる前に消えてしまう[38]。一連のエピソード的な小話は、 死んだフィネガンに緩やかに関連しながら続き、最も一般的には「ウィリングドン・ミュージールーム」[39]、「マットとジュート」[40][41]、 「悪戯小僧」と呼ばれる。 [42]章の終わりに喧嘩が起こり、ウイスキーがフィネガンの死体にかかり、「死んだフィネガンはウイスキーを求めて泣き叫びながら棺桶から起き上がり、 弔問客は彼を安置する」[43]ことで、彼は今いる場所が良いのだと説得する[44]。この章は、HCEのキャラクターが物語の中心的役割を果たすために ダブリン湾に出航するイメージで終わる。  足を組んで斜面に座る若い女性の姿。長方形の噴水の中央にあり、流れる水に囲まれている。 フィネガンズ・ウェイク』の登場人物、アンナ・リヴィア・プラベルを表すダブリンの噴水。 I.2は、「ハロルドまたはハンフリー」チンプデンが、船乗り王から「イヤーウィッカー」というあだ名をつけられた話で始まる。彼は、王が通行する料金所 で、逆さにした植木鉢を棒に刺して耳かきを捕まえようとしている彼に出会う。この名前によって、今ではイニシャルHCEで知られるチンプデンは、 「Here Comes Everybody 」としてダブリン社交界で頭角を現す。フェニックス公園で2人の少女が性的な不法行為を働いたという噂がダブリン中に広まる。 I.2章からI.4章は、HCEがフェニックス公園で「パイプを持った不良」と出会うところから、この噂の経過を追っている。士官候補生はゲール語で HCEに挨拶し、時間を尋ねるが、HCEはその質問を非難と誤解し、士官候補生がまだ聞いていない噂を否定することで自らを罪に陥れる。この噂は瞬く間に ダブリン中に広まり、勢いを増して、ホスティという人物が書いた 「The Ballad of Persse O'Reilly 」という歌にまでなってしまう。その結果、HCEは身を隠すことになり、パブの閉ざされた門の前で、営業時間外に酒を飲みに来たアメリカ人に包囲される [45]。HCEは黙秘を続け、非難や暴言には答えず、夢を見、ニーグ湖の湖底に棺に埋葬され[46]、ついにフェスティ・キングという名で裁判にかけら れる。最終的に彼は釈放され、再び身を隠す。裁判中に重要な証拠となる、彼の妻ALPが書いたHCEに関する手紙が、より詳細に調べられるよう要求され る。 ALPの手紙が焦点となり、I.5で詳しく分析される。この手紙は、ALPが文筆家である息子のセムに口述し、郵便配達人であるもう一人の息子ショーンに 託したものである。手紙は目的地に届くことなく、ビディという名の雌鶏によって発掘された山中に埋もれてしまう。第I.6章では、物語から脱線して、12 の謎と答えという形で、主要人物と脇役をより詳しく紹介している。第11問のなぞなぞでは、ショーンは兄セムとの関係を問われ、その答えの一部として、 ムックセとグリップスのたとえ話をする[47]: 117-122 第1部の最後の2章では、手紙の筆者である筆記者セム(I.7)と、その原作者である母親アルプ(I.8)について詳しく知ることができる。セムの章は 「ショーンの弟セムに対する人格攻撃」で構成され、密閉芸術家を贋作者で「偽物」であると描写し、その前に「セムは母親(ALP)によって保護され、最後 に母親は息子を擁護するために現れる」[48]。 [この章は1924年にジョイスによって「夜が更けると木と石になる二人の洗濯婦による、川を挟んでのおしゃべりな対話」と表現された[50]。この二人 の洗濯婦はリフィー川で洗濯をしながら、夫HCEにかけられた疑惑に対するALPの反応について噂をする。ALPは、夫に飽きたと宣言する手紙を書いたと 言われている。二人のゴシップはその後、彼女の若い頃の浮気や性的な出会いへと脱線し、HCEの罪が朝刊に掲載されたこと、そして彼の妻が敵に復讐するこ と、つまり息子のショーン・ザ・ポストから「メールサック」を借りて111人の子供たちにプレゼントを届けることに戻る。この章の終わりで、洗濯女たちは 物語の糸をつかもうとするが、彼女たちの会話はますます難しくなる。最後に、彼らは木と石に変わりながら、セムかショーンの物語を教えてくれるように頼む [51]。 第二部 フィネガンズ・ウェイク』の第I部が主に両親のHCEとALPを扱っているのに対し、第II部はその焦点を彼らの子供たち、セム、ショーン、イッシーに移している。 II.1はパントマイムのプログラムで始まり、比較的明確な言葉で、この本の主要登場人物の身元と属性を概説している。その中でセムは、女の子たちが選ん だ色を 「gazework 」で当てるというゲームに3回挑戦する。最後にHCEがパブから現れ、雷のような声で子供たちを中に呼び込む[53]。 第II.2章 セム、ショーン、イッシーの3人は、前章でパブの中に呼ばれた後、パブの2階で勉強している[54][55]。この章では、「(セムが)(ショーンに) 『ユークリッド』Bk I, 1の解き方を教える」様子が描かれ、「小学生(と女子生徒)の古い教科書を再現し、双子が半分の時間で左右を変え、(そうでない)女の子が脚注をつける」 という構成になっている。 [56][57]セム(ここではドルフと呼ばれる)がショーン(ここではケヴと呼ばれる)がユークリッド図を描くのを手伝った後、後者は彼がアルプの性器 の図を描いたことに気づき、「ケヴは三角形の意味にようやく気づき[...]ドルフを殴る」。この後、「ドルフはケヴを許し」、子どもたちは「52人の有 名な男性についての作文の課題」を与えられる[58]。この章は、子どもたちがHCEとALPに宛てた「夜の手紙」で終わるが、そこでは子どもたちは「両 親を克服したいという願望で一致しているらしい」[59]。 「セクション1:プッケルセン(猫背のノルウェー人船長)、ケルセ(仕立て屋)、マッカン(船の夫)の物語のラジオ放送。 セクション2-3:ケイト(掃除婦)がHCEに2階で指名手配されていることを告げ、ドアが閉められ、バックリーの物語が紹介される。 セクション4-5:バットとタフ(セムとショーン)によって語られ、テレビで放映される、バックリーがロシアの将軍(HCE)を射殺するまでの物語。 - ダニス・ローズによる極めて複雑な2.3章の概要。彼はアールヴィッカーのホテルのバーが舞台だと考えている[60]。 II.3は、勉強している子供たちの下のパブで働くHCEに移る。HCEが客に給仕をしているとき、バーのラジオとテレビを通じて、「ノルウェーの大尉と 仕立て屋の娘」[61][62]と「バックリーはいかにしてロシアの将軍を撃ったか」という2つの物語が放送される。前者は、HCEが仕立て屋の娘との結 婚によって家畜化に屈したノルウェー人船長として描かれている。後者は、セムとショーンの暗号であるバットとタフによって語られ、HCEをクリミア戦争中 にイギリス軍のアイルランド人兵士バックリーに撃たれたロシア人将軍に見立てている[63]。バックリーが将軍を射殺したことは、セムとショーンが父親に 取って代わられたことを象徴していると彼らは見ている[64]。このように彼の人格が非難されると、HCEは若い女の子に対する近親相姦的な欲望を含む彼 の罪の一般的な告白をせざるを得なくなる。 [65][66][67][68]最後に、酔っ払った客たちを家に帰すために警官が到着し、パブは閉鎖され[69]、客たちは歌いながら夜の中に消えてい く。酔っ払ったHCEは、バーを片付け、残されたグラスのかすを飲み込むと、古代アイルランドの覇王ローリー・オコナーに変身し、気を失う[70] [71]。 酔って眠っているアールヴィッカーの夢を描いたII.4は、トリスタンとイゾルデの旅路を4人の老人(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)が覗き見している様 子を描いている[72]。この短い章では、「マルコ王のような老人が、彼なしの未来へと船出する若い恋人たちに拒絶され、見捨てられる」様子が描かれ [73]、4人の老人はトリスタンとイゾルデを観察し、恋人たちと自分自身について「常に繰り返される」4つの絡み合った解説を述べている[74]。 第三部 第III部は、郵便配達人としてのショーンが、第I部で言及されながら一度も目にすることのなかったアルプの手紙を配達しなければならないことに、ほぼ独占的に関係している[75][76]。 その結果、ショーンは再び目を覚まし、樽に乗ってリフィー川を下りながら、彼が運んでいる手紙の意味と内容に関する14の質問を投げかけられる。ショーン は「軽んじられることを恐れ、警戒しており、なだめる語り手たちは彼からまともな答えを引き出すことはない」[79]。ショーンの答えは、彼自身の自慢げ な性格と、手紙の作者である芸術家の兄セムへの戒めに焦点を当てている。審問の後、ショーンはバランスを崩し、浮遊していた樽が横転し、ナレーターの 耳の届かないところで後方に転がり、視界から完全に消える[81]。 III.2でショーンは「ジャーンティ・ジャーン」として再登場し、妹のイッシーと聖ブリギッド学園の28人の同級生に、長々と性的に示唆的な説教をす る。本書を通じてショーンは絶えず退行し、老人から仰向けに横たわる成長しすぎた赤ん坊へと変化し、最終的にはIII.3で、霊媒によってHCEの声が再 び語りかける器となる。これが、「Haveth Childers Everywhere 」の一節におけるHCEの人生擁護へとつながっていく。ジェリー、ケヴィン、イゾベルの3人の子供たちが2階で眠り、外では夜明けが昇っている中、ポー ター夫妻が交尾を試みるところで第3部は終わる(III.4)。ジェリーは怖い父親像の悪夢から目覚め、ポーター夫人は交尾を中断して「夢を見ていたの よ、あなた」と彼を慰めに行く。ポードラッグ?フォースリグ?靴よ!この部屋には幻獣はいませんよ、アビキーン。彼女はベッドに戻り、雄鶏が二人の性交の 終わりに鳴く。 第4部 「1: [HCE]の目覚めと復活、2: 日の出、3: 夜と昼の対立、4: 正しい時間を確かめようとする試み、5: 逆行する時間の終着点と第III部の[ショーン]の姿、6: 夜に対する昼の勝利、7: [ALP]の手紙と独白。 - ローランド・マクヒューによる第四部の出来事の要約[84]」 第IV部は1章のみで構成され、その大部分は本書の序章と同様、一見無関係な一連の小話で構成されている。夜明けを告げる冒頭の呼びかけ[85]の後、章 の残りは「聖ケヴィン」、「バークリーとパトリック」、「敬愛される手紙」というヴィネットで構成されている。 [その中で彼女は眠っている夫を起こそうとし、「起きなさい、フースの人、あなたはとても長く眠っていたのよ!」と宣言し[89]、かつて二人で歩いた散 歩道を思い出し、その再来を願う。彼女の独白の終わりに、アルプは--リフィー川のように--夜明けに海へと消えていく。この本の最後の言葉は断片的なも のだが、冒頭の言葉とくっつけることで完全な文章にすることができる: イヴとアダムの店を通り過ぎ、海岸のうねりから湾の曲がり角まで、リヴァーランは私たちをハウズ城とその周辺へと循環のコモディウス・ヴィカスで連れ戻してくれる。 |
| Critical response and themes Difficulties of plot summary "Thus the unfacts, did we possess them, are too imprecisely few to warrant our certitude..."[90] Commentators who have summarised the plot of Finnegans Wake include Joseph Campbell, John Gordon,[91] Anthony Burgess, William York Tindall, and Philip Kitcher. While no two summaries interpret the plot in the same way, there are a number of central "plot points" upon which they find general agreement. A number of Joyce scholars question the legitimacy of searching for a linear storyline within the complex text.[92]: 165 As Bernard Benstock highlights, "in a work where every sentence opens a variety of possible interpretations, any synopsis of a chapter is bound to be incomplete."[93] David Hayman has suggested that "For all the efforts made by critics to establish a plot for the Wake, it makes little sense to force this prose into a narrative mold."[94] The book's challenges have led some commentators into generalised statements about its content and themes, prompting critic Bernard Benstock to warn against the danger of "boiling down" Finnegans Wake into "insipid pap, and leaving the lazy reader with a predigested mess of generalizations and catchphrases."[95] Fritz Senn has also voiced concerns with some plot synopses, saying "we have some traditional summaries, also some put in circulation by Joyce himself. I find them most unsatisfactory and unhelpful, they usually leave out the hard parts and recirculate what we already think we know. I simply cannot believe that FW would be as blandly uninteresting as those summaries suggest."[96] The challenge of compiling a definitive synopsis of Finnegans Wake lies not only in the opacity of the book's language but also in the radical approach to plot which Joyce employed. Joyce acknowledged this when he wrote to Eugène Jolas that: "I might easily have written this story in the traditional manner [...] Every novelist knows the recipe [...] It is not very difficult to follow a simple, chronological scheme which the critics will understand [...] But I, after all, am trying to tell the story of this Chapelizod family in a new way.[97] This "new way" of telling a story in Finnegans Wake takes the form of a discontinuous dream-narrative, with abrupt changes to characters, character names, locations and plot details resulting in the absence of a discernible linear narrative, causing Herring to argue that the plot of Finnegans Wake "is unstable in that there is no one plot from beginning to end, but rather many recognizable stories and plot types with familiar and unfamiliar twists told from varying perspectives."[98] Patrick A. McCarthy expands on this idea of a non-linear, digressive narrative with the contention that "throughout much of Finnegans Wake, what appears to be an attempt to tell a story is often diverted, interrupted, or reshaped into something else, for example, a commentary on a narrative with conflicting or unverifiable details."[99] In other words, while crucial plot points – such as HCE's crime or ALP's letter – are endlessly discussed, the reader never encounters or experiences them first hand, and as the details are constantly changing, they remain unknown and perhaps unknowable. Suzette Henke has accordingly described Finnegans Wake as an aporia.[100] Joyce himself tacitly acknowledged this radically different approach to language and plot in a 1926 letter to Harriet Weaver, outlining his intentions for the book: "One great part of every human existence is passed in a state which cannot be rendered sensible by the use of wideawake language, cutanddry grammar and goahead plot."[101] Critics have seen a precedent for the book's plot presentation in Laurence Sterne's digressive The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, with Thomas Keymer stating that "Tristram Shandy was a natural touchstone for James Joyce as he explained his attempt "to build many planes of narrative with a single esthetic purpose" in Finnegans Wake".[102] Part II is usually considered the book's most opaque section, and hence the most difficult to synopsize. William York Tindall said of Part II's four chapters that "nothing is denser."[103]: 153 Similarly, Patrick Parrinder has described Part II as the "worst and most disorienting quagmire [...] in the Wake."[104] Despite Joyce's revolutionary techniques, the author repeatedly emphasized that the book was neither random nor meaningless; with Richard Ellmann quoting the author as having stated: "I can justify every line of my book."[105] To Sisley Huddleston he stated "critics who were most appreciative of Ulysses are complaining about my new work. They cannot understand it. Therefore they say it is meaningless. Now if it were meaningless it could be written quickly without thought, without pains, without erudition; but I assure you that these 20 pages now before us [i.e. chapter I.8] cost me twelve hundred hours and an enormous expense of spirit."[106]: 490 When the editor of Vanity Fair asked Joyce if the sketches in Work in Progress were consecutive and interrelated, Joyce replied "It is all consecutive and interrelated."[107] Themes Fargnoli and Gillespie suggest that the book's opening chapter "introduces [the] major themes and concerns of the book", and enumerate these as "Finnegan's fall, the promise of his resurrection, the cyclical structure of time and history (dissolution and renewal), tragic love as embodied in the story of Tristan and Iseult, the motif of the warring brothers, the personification of the landscape and the question of Earwicker's crime in the park, the precise nature of which is left uncertain throughout the Wake."[108] Such a view finds general critical consensus, viewing the vignettes as allegorical appropriations of the book's characters and themes; for example, Schwartz argues that "The Willingdone Museyroom" episode represents the book's "archetypal family drama in military-historical terms."[109] Joyce himself referred to the chapter as a "prelude",[110] and as an "air photograph of Irish history, a celebration of the dim past of Dublin."[111] Riquelme finds that "passages near the book's beginning and its ending echo and complement one another",[112] and Fargnoli and Gillespie representatively argue that the book's cyclical structure echoes the themes inherent within, that "the typologies of human experience that Joyce identifies [in Finnegans Wake] are [..] essentially cyclical, that is, patterned and recurrent; in particular, the experiences of birth, guilt, judgment, sexuality, family, social ritual and death recur throughout the Wake.[113] In a similar enumeration of themes, Tindall argues that "rise and fall and rise again, sleeping and waking, death and resurrection, sin and redemption, conflict and appeasement, and, above all, time itself [...] are the matter of Joyce's essay on man."[114] Henkes and Bindervoet generally summarise the critical consensus when they argue that, between the thematically indicative opening and closing chapters, the book concerns "two big questions" which are never resolved: what is the nature of protagonist HCE's secret sin, and what was the letter, written by his wife ALP, about?[115] HCE's unidentifiable sin has most generally been interpreted as representing man's original sin as a result of the Fall of Man. Anthony Burgess sees HCE, through his dream, trying "to make the whole of history swallow up his guilt for him" and to this end "HCE has, so deep in his sleep, sunk to a level of dreaming in which he has become a collective being rehearsing the collective guilt of man."[116] Fargnoli and Gillespie argue that although undefined, "Earwicker's alleged crime in the Park" appears to have been of a "voyeuristic, sexual, or scatological nature".[108] ALP's letter appears a number of times throughout the book, in a number of different forms, and as its contents cannot be definitively delineated, it is usually believed to be both an exoneration of HCE, and an indictment of his sin. Herring argues that "[t]he effect of ALP's letter is precisely the opposite of her intent [...] the more ALP defends her husband in her letter, the more scandal attaches to him."[117] Patrick A. McCarthy argues that "it is appropriate that the waters of the Liffey, representing Anna Livia, are washing away the evidence of Earwicker's sins as [the washerwomen speak, in chapter I.8] for (they tell us) she takes on her husband's guilt and redeems him; alternately she is tainted with his crimes and regarded as an accomplice".[118] A reconstruction of nocturnal life Throughout the book's seventeen-year gestation, Joyce stated that with Finnegans Wake he was attempting to "reconstruct the nocturnal life",[3] and that the book was his "experiment in interpreting 'the dark night of the soul'."[119] According to Ellmann, Joyce stated to Edmond Jaloux that Finnegans Wake would be written "to suit the esthetic of the dream, where the forms prolong and multiply themselves",[120] and once informed a friend that "he conceived of his book as the dream of old Finn, lying in death beside the river Liffey and watching the history of Ireland and the world – past and future – flow through his mind like flotsam on the river of life."[121][122] While pondering the generally negative reactions to the book Joyce said: I can't understand some of my critics, like Pound or Miss Weaver, for instance. They say it's obscure. They compare it, of course, with Ulysses. But the action of Ulysses was chiefly during the daytime, and the action of my new work takes place chiefly at night. It's natural things should not be so clear at night, isn't it now?[123] Joyce's claims to be representing the night and dreams have been accepted and questioned with greater and lesser credulity. Supporters of the claim have pointed to Part IV as providing its strongest evidence, as when the narrator asks "You mean to see we have been hadding a sound night’s sleep?",[124] and later concludes that what has gone before has been "a long, very long, a dark, very dark [...] scarce endurable [...] night".[125] Tindall refers to Part IV as "a chapter of resurrection and waking up",[126] and McHugh finds that the chapter contains "particular awareness of events going on offstage, connected with the arrival of dawn and the waking process which terminates the sleeping process of [Finnegans Wake]."[127] This conceptualisation of the Wake as a dream is a point of contention for some. Harry Burrell, representative of this view, argues that "one of the most overworked ideas is that Finnegans Wake is about a dream. It is not, and there is no dreamer." Burrell argues that the theory is an easy way out for "critics stymied by the difficulty of comprehending the novel and the search for some kind of understanding of it."[128] The point upon which a number of critics fail to concur with Burrell's argument is its dismissal of the testimony of the book's author on the matter as "misleading... publicity efforts".[129] Parrinder, equally skeptical of the concept of the Wake as a dream, argues that Joyce came up with the idea of representing his linguistic experiments as a language of the night around 1927 as a means of battling his many critics, further arguing that "since it cannot be said that neologism is a major feature of the dreaming process, such a justification for the language of Finnegans Wake smacks dangerously of expediency."[130] While many, if not all, agree that there is at least some sense in which the book can be said to be a "dream", few agree on who the possible dreamer of such a dream might be.[131] Edmund Wilson's early analysis of the book, The Dream of H. C. Earwicker, made the assumption that Earwicker himself is the dreamer of the dream, an assumption which continued to carry weight with Wakean scholars Harry Levin, Hugh Kenner, and William Troy.[131][132]: 270–274 Joseph Campbell, in A Skeleton Key to Finnegans Wake, also believed Earwicker to be the dreamer, but considered the narrative to be the observances of, and a running commentary by, an anonymous pedant on Earwicker's dream in progress, who would interrupt the flow with his own digressions.[133] Ruth von Phul was the first to argue that Earwicker was not the dreamer, which triggered a number of similarly minded views on the matter, although her assertion that Shem was the dreamer has found less support.[133][134] J.S.Atherton, in a 1965 lecture, 'The Identity of the Sleeper', suggested that the dreamer of Finnegans Wake was the Universal Mind: 'As I see FW it is everyone’s dream, the dream of all the living and the dead. Many puzzling features become clear if this is accepted. Obviously we will hear many foreign languages....To my mind, the most revealing statement Joyce ever made about his work was: 'Really it is not I who am writing this crazy book. It is you, and you, and you, and that man over there, and that girl at the next table.' This is stressed, once you start looking for it, in the Wake itself. It is 'us.' who are brought back to 'Howth Castle and Environs' in the third line of the book. The washerwoman says: 'of course, we all know Anna Livia'. It is easy to miss the 'we'. Chapter 2 has 'we are back' in line 3. In fact all the first five chapters use "us" or "we" by the ninth line at the latest—and the sixth chapter ends 'Semus sumus.' We are Shem. All of us....It is the universal mind which Joyce assumes as the identity of the dreamer; he, of course, is writing it all down but everyone else contributes.'[135] The assertion that the dream was that of Mr. Porter, whose dream personality personified itself as HCE, came from the critical idea that the dreamer partially wakes during chapter III.4, in which he and his family are referred to by the name Porter.[136] Anthony Burgess representatively summarized this conception of the "dream" thus: "Mr. Porter and his family are asleep for the greater part of the book [...] Mr. Porter dreams hard, and we are permitted to share his dream [...] Sleeping, he becomes a remarkable mixture of guilty man, beast, and crawling thing, and he even takes on a new and dreamily appropriate name – Humphrey Chimpden Earwicker."[137] Harriet Weaver was among the first to suggest that the dream was not that of any one dreamer, but was rather an analysis of the process of dreaming itself. In a letter to J.S. Atherton she wrote: In particular their ascription of the whole thing to a dream of HCE seems to me nonsensical. My view is that Mr. Joyce did not intend the book to be looked upon as the dream of any one character, but that he regarded the dream form with its shiftings and changes and chances as a convenient device, allowing the freest scope to introduce any material he wished—and suited to a night-piece.[138] Bernard Benstock also argued that "The Dreamer in the Wake is more than just a single individual, even if one assumes that on the literal level we are viewing the dream of publican H.C. Earwicker."[139] Other critics have been more skeptical of the concept of identifying the dreamer of the book's narrative. Clive Hart argues that "[w]hatever our conclusions about the identity of the dreamer, and no matter how many varied caricatures of him we may find projected into the dream, it is clear that he must always be considered as essentially external to the book, and should be left there. Speculation about the 'real person' behind the guises of the dream-surrogates or about the function of the dream in relation to the unresolved stresses of this hypothetical mind is fruitless, for the tensions and psychological problems in Finnegans Wake concern the dream-figures living within the book itself."[140] John Bishop has been the most vocal supporter of treating Finnegans Wake absolutely, in every sense, as a description of a dream, the dreamer, and of the night itself; arguing that the book not only represents a dream in an abstract conception, but is fully a literary representation of sleep. On the subject Bishop writes: The greatest obstacle to our comprehension of Finnegans Wake [...has been...] the failure on the part of readers to believe that Joyce really meant what he said when he spoke of the book as a "reconstruction of the nocturnal life" and an "imitation of the dream-state"; and as a consequence readers have perhaps too easily exercised on the text an unyielding literalism bent on finding a kind of meaning in every way antithetical to the kind of meaning purveyed in dreams.[141]: 309 Bishop has also somewhat brought back into fashion the theory that the Wake is about a single sleeper; arguing that it is not "the 'universal dream' of some disembodied global everyman, but a reconstruction of the night – and a single night – as experienced by 'one stable somebody' whose 'earwitness' on the real world is coherently chronological."[142]: 283 Bishop has laid the path for critics such as Eric Rosenbloom, who has proposed that the book "elaborates the fragmentation and reunification of identity during sleep. The masculine [...] mind of the day has been overtaken by the feminine night mind. [...] The characters live in the transformation and flux of a dream, embodying the sleeper’s mind."[143] |
批評家の反応とテーマ プロット要約の難しさ 「このように、事実でないものは、私たちが持っていたとしても、私たちの確信を保証するには、あまりにも不正確で少ない...」[90]。 フィネガンズ・ウェイク』のプロットを要約した批評家には、ジョセフ・キャンベル、ジョン・ゴードン、アンソニー・バージェス、ウィリアム・ヨーク・ティ ンダル、フィリップ・キッチャーなどがいる[91]。2つの要約が同じように筋を解釈することはないが、一般的に一致する中心的な「筋」がいくつかある。 多くのジョイス研究者は、複雑なテクストの中に直線的なストーリーを探すことの正当性に疑問を呈している[92]: 165 バーナード・ベンストックが強調しているように、「一文一文が様々な解釈の可能性を開く作品においては、一章のあらすじは不完全なものにならざるを得な い」[93]。デイヴィッド・ヘイマンは、「批評家たちが『航跡』の筋書きを確立しようと努力した割には、この散文を物語の型に押し込めることはほとんど 意味をなさない」と示唆している[94]。 批評家バーナード・ベンストックは、『フィネガンズ・ウェイク』を「煮詰めた」ような「無味乾燥な戯言」にしてしまう危険性を警告している。それらはたい てい、難しい部分を省いて、私たちがすでに知っていると思っていることを再循環させている。それらの要約が示唆するように、FWが当たり障りのない面白み のない人物であるとは、単純に信じられない」[96]。 フィネガンズ・ウェイク』の決定的なあらすじを編纂することの難しさは、この本の言葉の不透明さだけでなく、ジョイスが採用したプロットに対する急進的なアプローチにもある。ジョイスはウジェーヌ・ジョラスにこう書いている: 「私はこの物語を伝統的な方法で簡単に書くことができたかもしれない[......]。すべての小説家はそのレシピを知っている[......]。批評家たちが理解できるような単純な時系列的スキームに従うことはそれほど難しくはない[......]。 この『フィネガンズ・ウェイク』における物語の「新しい語り方」は、不連続な夢物語の形をとっており、登場人物、登場人物の名前、場所、プロットの詳細が 突然変更され、その結果、識別可能な直線的な物語が不在となるため、ヘリングは『フィネガンズ・ウェイク』のプロットは「最初から最後まで一つのプロット が存在するわけではなく、むしろ、様々な視点から語られる、なじみのある、あるいはなじみのないひねりを加えた、多くの認識可能な物語やプロットの型が存 在するという点で不安定である」と論じている[98]。マッカーシーは、「『フィネガンズ・ウェイク』の大部分を通じて、物語を語ろうとする試みと思われ るものが、しばしば迂回されたり、中断されたり、別のもの、例えば、矛盾する、あるいは検証不可能な詳細を持つ物語についての解説に形を変えられたりす る。 「言い換えれば、HCEの犯罪やALPの手紙のような重要な筋書きが延々と議論される一方で、読者がそれらに直接遭遇したり体験したりすることはなく、細 部が絶えず変化するため、それらは未知のままであり、おそらく知ることもできない。シュゼット・ヘンケはそれに従って、『フィネガンズ・ウェイク』をアポ リアと表現している[100]。ジョイス自身、1926年にハリエット・ウィーバーに宛てた手紙の中で、言語と筋に対するこの根本的に異なるアプローチを 黙認し、この本に対する彼の意図を概説している: すべての人間存在の大部分は、覚醒した言語、冗長な文法、先が読めない筋書きでは理解できない状態で過ぎていく」[101]。 101]批評家たちは、ローレンス・スターンの『紳士トリストラム・シャンディの人生と意見』(The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman)にこの本の筋書きの表現の先例があると見ており、トマス・キーマーは「トリストラム・シャンディは、ジェイムズ・ジョイスが『フィネ ガンズ・ウェイク』において「一つの美的な目的で多くの物語の平面を構築する」試みを説明する際の自然な試金石であった」と述べている[102]。 第Ⅱ部は通常、この本の中で最も不透明な部分であり、それゆえ要約するのが最も難しいと考えられている。ウィリアム・ヨーク・ティンドールは第二部の4つ の章について「これほど密度の濃いものはない」と述べている[103]: 153 同様に、パトリック・パリンダーは第Ⅱ部を「『航跡』の中で最悪の、そして最も混乱させる泥沼[...]」と評している[104]。 ジョイスの革命的な手法にもかかわらず、作者はこの本が無作為でも無意味でもないことを繰り返し強調していた: リチャード・エルマンは著者の言葉を引用し、「私は自分の本のすべての行を正当化することができる」と述べている[105]。シスレイ・ハドルストンに対 しては「『ユリシーズ』を最も高く評価していた批評家たちが、私の新作に文句を言っている。彼らはそれを理解できない。だから無意味だと言う。しかし私 は、いま目の前にあるこの20ページ[すなわち第I章8節]は、私に1200時間と莫大な精神的出費を費やしたことを保証する」[106]: 490 『ヴァニティ・フェア』誌の編集者がジョイスに、『進行中の仕事』のスケッチは連続し、相互に関連しているのかと尋ねたところ、ジョイスは「すべて連続 し、相互に関連している」と答えた[107]。 テーマ ファルグノーリとギレスピーは、この本の冒頭の章が「この本の主要なテーマと関心を紹介している」と指摘し、「フィネガンの堕落、復活の約束、時間と歴史 の循環構造(溶解と再生)、トリスタンとイゼウルトの物語に体現される悲恋、争う兄弟のモチーフ、風景の擬人化、公園でのアールウィッカーの罪の問題(そ の正確な性質は『航跡』全体を通して不確かなままである)」と列挙している。 例えば、シュワルツは「ウィリングドン・ミュジールーム」のエピソードは、この本の「軍事史的用語における典型的な家族ドラマ」を表していると論じてい る。 ジョイス自身はこの章を「前奏曲」と呼び[110]、「アイルランドの歴史の航空写真、ダブリンのおぼろげな過去の祝典」と呼んでいる[111]。リケル メは「この本の冒頭と結末に近い箇所は互いに響き合い、補完し合っている」と見出しており[112]、ファーニョーリとギレスピーは代表的に、この本の循 環的な構造はこの本に内在するテーマと呼応しており、「ジョイスが(『フィネガンズ・ウェイク』で)識別している人間経験の類型は[...]本質的に循環 的である」と論じている。 特に、誕生、罪悪感、裁き、セクシュアリティ、家族、社会的儀式、死の体験は『航跡』全体を通して繰り返されている」[113]。同様のテーマの列挙とし て、ティンダルは「上昇と下降と再度の上昇、眠りと目覚め、死と復活、罪と贖罪、葛藤と鎮め、そして何よりも時間そのものがジョイスの人間についてのエッ セイの主題である」と論じている[114]。 ヘンクスとビンダーヴォエは、テーマ的に示唆的な序章と終章の間に、本書は解決されることのない「2つの大きな疑問」、すなわち主人公HCEの秘密の罪の 本質とは何か、そして妻ALPによって書かれた手紙とは何であったのか、について論じており、批評家のコンセンサスを概ね要約している[115]。 HCEの正体不明の罪は、最も一般的には、人間の堕落の結果としての人間の原罪を表していると解釈されてきた。アンソニー・バージェスは、HCEが夢を通 して「歴史全体に自分の罪を飲み込ませようとしている」と見ており、この目的のために「HCEは眠りの深いところで、夢想のレベルにまで沈んでしまった。 「ファーニョーリとギレスピーは、定義されてはいないものの、「公園におけるアールヴィッカーの犯罪とされるもの」は「覗き、性的、あるいはスカトロ的な 性質のもの」であったようだと論じている[108]。ヘリングは、「ALP の手紙の効果は、彼女の意図とは正反対である[...]ALP が手紙の中で夫を擁護すればするほど、彼にスキャンダルが付きまとう」と論じている[117][117] 。パトリック・A・マッカーシーは、「アンナ・リヴィアを表すリフィー川の水が、アールウィッカーの罪の 証拠を洗い流しているのは適切である。 というのも、彼女は夫の罪を引き受け、彼を贖うのであり、その代わりに彼女は夫の罪に染まり、共犯者とみなされるのである」[118]。 夜間生活の再現 ジョイスは本書の17年間の構想を通じて、『フィネガンズ・ウェイク』では「夜行性の生活の再構築」を試みていると述べており[3]、本書は「『魂の闇 夜』を解釈する実験」であったとしている。 エルマンによれば、ジョイスはエドモン・ジャルーに『フィネガンズ・ウェイク』は「形式がそれ自身を延長し、増殖させる夢の美学に合うように」書かれるだ ろうと述べており[120]、友人に「彼は自分の本を、リフィー川の傍らで死にながら横たわり、アイルランドと世界の歴史-過去と未来-が人生の川の漂流 物のように心の中を流れていくのを眺めている、年老いたフィンの夢として構想していた」と告げたことがある[121]。 「121][122]ジョイスは、この本に対する一般的に否定的な反応について考えつつ、次のように述べている: たとえばパウンドやウィーヴァーさんのような批評家たちが理解できない。たとえばパウンドやウィーヴァーさんのように。彼らはもちろん『ユリシーズ』と比 較する。しかし、『ユリシーズ』は主に昼間に描かれ、私の新作は主に夜に描かれる。夜に物事がはっきりしないのは当然だろう? 夜と夢を表現しているというジョイスの主張は、大なり小なり信憑性をもって受け入れられ、また疑問視されてきた。この主張の支持者たちは、語り手が「私た ちが熟睡していたことがお分かりになるでしょ うか」と問いかけ[124]、後にそれまでのことが「長い、とても長い、暗い、とても暗い[......]耐え難い[......]夜」であったと結論づ けているように、第 4 部がその最も強力な証拠になると指摘している[125]。 ティンダルは第Ⅳ部を「復活と目覚めの章」と呼び[126]、マクヒューはこの章が「夜明けの到来と、[フィネガンズ・ウェイク]の眠りのプロセスを終わ らせる目覚めのプロセスと結びついた、舞台の外で起こっている出来事に対する特別な意識」を含んでいると見なしている[127]。 夢としての『覚醒』のこのような概念は、ある人々にとっては論点である。この見方を代表するハリー・バレルは、「最も酷使されている考え方のひとつは、 『フィネガンズ・ウェイク』が夢について描いているというものだ。そうではないし、夢想家もいない」。バレルは、この理論は「この小説を理解することの難 しさと、それに対するある種の理解の探求に行き詰まった批評家」にとって、安易な逃げ道であると主張している[128]。多くの批評家がバレルの主張に同 意できない点は、この問題についてのこの本の著者の証言を「誤解を招くような......宣伝活動」として退けていることである。 [129] Parrinderも同様に夢としての『航跡』の概念に懐疑的であり、ジョイスは多くの批評家と戦う手段として、1927年頃に自分の言語実験を夜の言語 として表現するというアイデアを思いついたと主張し、さらに「新造語が夢を見ているプロセスの主要な特徴であるとは言えないので、『フィネガンズ・ウェイ ク』の言語に対するそのような正当化は危険なほど便宜的な匂いがする」と論じている[130]。 すべてではないにせよ、この本が「夢」であると言える少なくとも何らかの意味があることには多くの人が同意しているが、そのような夢の夢想家が誰である可 能性があるのかについて同意する人はほとんどいない[131]。 エドマンド・ウィルソンのこの本についての初期の分析である『H.C.アールウィッカーの夢』は、アールウィッカー自身が夢の夢想家であるという仮定を立 てており、この仮定はウェイクの研究者であるハリー・レヴィン、ヒュー・ケナー、ウィリアム・トロイの間で重みを持ち続けている。 [131][132]:270-274ジョセフ・キャンベルも『フィネガンズ・ウェイクの秘密の鍵』(A Skeleton Key to Finnegans Wake)の中で、アールウィッカーが夢想家であると信じていたが、この物語はアールウィッカーの進行中の夢に対する匿名の女衒の観察であり、女衒が自分 の脱線で流れを中断させながら進行する解説であると考えていた[133]。 ルース・フォン・フルは、アールヴィッカーが夢想家ではないと最初に主張し、この問題に関して多くの類似した見解を引き起こしたが、セムが夢想家であるという彼女の主張はあまり支持されていない[133][134]。 J.S.アサートンは1965年の講義「眠れる者の正体」の中で、『フィネガンズ・ウェイク』の夢想家は普遍的な心であると示唆した: 私の見るところ、FWはすべての人の夢であり、生者と死者すべての夢である。これを受け入れれば、多くの不可解な特徴が明らかになる。私の考えでは、ジョ イスが自分の作品について語った最も明白な言葉は、『本当にこの狂った本を書いているのは私ではない。このクレイジーな本を書いているのは、私ではなく、 あなたであり、あなたであり、あなたであり、あそこにいる男であり、隣のテーブルにいる女なのだ』。これは、一度探し始めると、ウェークそのものに強調さ れている。この本の3行目で「ハウズ城とその周辺」に連れ戻されるのは「私たち」である。もちろん、私たちはみんなアンナ・リヴィアを知っている」。私た ち」を見逃すのは簡単だ。第2章では3行目に'we are back'がある。実際、第1章から第5章まではすべて「私たち」または「私たち」を使っている。私たちはセムだ。ジョイスが夢想家のアイデンティティと して想定しているのは普遍的な心であり、彼はもちろんすべてを書き留めているが、他の誰もが貢献している」[135]。 夢はポーター氏のものであり、その夢の人格はHCEとして擬人化されているという主張は、彼と彼の家族がポーターという名で呼ばれている第III章4節で 夢想家が部分的に目覚めるという批判的な考えから来ている[136]。アンソニー・バージェスはこの「夢」の概念を代表的にこう要約している: 「ポーター氏とその家族は、この本の大部分において眠っている[......]。ポーター氏は懸命に夢を見、われわれは彼の夢を共有することを許される [......]。眠っている彼は、罪深い人間、獣、這うものの驚くべき混合物となり、新しい、夢のように適切な名前、すなわちハンフリー・チンプデン・ アールウィッカーさえ名乗るようになる」[137]。 ハリエット・ウィーバーは、この夢は特定の夢想家のものではなく、むしろ夢を見るプロセスそのものを分析したものであることを示唆した最初の人物の一人であった。J.S.アサートンへの手紙に彼女はこう書いている: 特に、HCEの夢だとする彼らの主張は、私にはナンセンスに思えます。私の考えでは、ジョイス氏はこの本を誰か一人の登場人物の夢として見ることを意図し ていたのではなく、移り変わりや変化やチャンスを伴う夢の形式を、彼が望むあらゆる素材を自由に導入できる便利な装置、そして夜の作品に適したものと考え ていたのである[138]。 バーナード・ベンストックもまた、「『航跡』の夢想家は、文字通りのレベルでは風俗営業者H.C.アールヴィッカーの夢を見ていると仮定しても、単なる一個人以上の存在である」と論じている[139]。 他の批評家は、この本の物語の夢主を特定するという概念に懐疑的である。クライブ・ハートは、「夢想家の正体についてどのような結論を出そうとも、また夢 に投影された夢想家の風刺画がどれほど多様であろうとも、夢想家はつねにこの本の本質的な外部にいるものと考えなければならず、そのままにしておくべきな のは明らかである」と論じている。フィネガンズ・ウェイク』における緊張と心理的な問題は、本そのものの中に生きている夢の人物に関係しているからであ る」[140]。 ジョン・ビショップは、『フィネガンズ・ウェイク』を、あらゆる意味で、夢、夢想家、そして夜そのものの描写として絶対的に扱うことを最も声高に支持している。この件に関してビショップはこう書いている: フィネガンズ・ウェイク』を理解する上での最大の障害は、ジョイスがこの本を「夜間生活の再現」であり「夢状態の模倣」であると語ったときに、読者の側が、ジョイスが本心からそう言ったのだと信じることができなかったことである: 309 ビショップはまた、『航跡』が一人の睡眠者について書かれたものであるという説を、いくらか流行らせることになった。ビショップは、『航跡』は「実体のな い世界的な常人の『普遍的な夢』ではなく、『一人の安定した誰か』によって経験された夜の、しかもたった一晩の再現であり、その『耳の証言』が現実世界に おいて時系列的に首尾一貫している」と論じている[142]: 283。男性的な[...]昼の心は、女性的な夜の心に追い越された。[登場人物たちは夢の変容と流動の中で生きており、睡眠者の心を体現している」 [143]。 |
| Characters "Whence it is a slopperish matter, given the wet and low visibility [...] to idendifine the individuone"[144] Critics disagree on whether discernible characters exist in Finnegans Wake. For example, Grace Eckley argues that Wakean characters are distinct from one another,[145] and defends this with explaining the dual narrators, the "us" of the first paragraph, as well as Shem-Shaun distinctions[146] while Margot Norris argues that the "[c]haracters are fluid and interchangeable".[147] Supporting the latter stance, Van Hulle finds that the "characters" in Finnegans Wake are rather "archetypes or character amalgams, taking different shapes",[148] and Riquelme similarly refers to the book's cast of mutable characters as "protean".[149] As early as in 1934, in response to the recently published excerpt "The Mookse and the Gripes", Ronald Symond argued that "the characters in Work in Progress, in keeping with the space-time chaos in which they live, change identity at will. At one time they are persons, at another rivers or stones or trees, at another personifications of an idea, at another they are lost and hidden in the actual texture of the prose, with an ingenuity far surpassing that of crossword puzzles."[150] Such concealment of character identity has resulted in some disparity as to how critics identify the book's main protagonists; for example, while most find consensus that Festy King, who appears on trial in I.4, is a HCE type, not all analysts agree on this – for example Anthony Burgess believes him to be Shaun.[151] While characters are in a constant state of flux—constantly changing names, occupations, and physical attributes—a recurring set of core characters, or character types (what Norris dubs "ciphers"), are discernible. During the composition of Finnegans Wake, Joyce used signs, or so-called "sigla", rather than names to designate these character amalgams or types. In a letter to his Maecenas, Harriet Shaw Weaver (March 1924), Joyce made a list of these sigla.[148] For those who argue for the existence of distinguishable characters, the book focuses on the Earwicker family, which consists of father, mother, twin sons and a daughter. Humphrey Chimpden Earwicker (HCE) Kitcher argues for the father HCE as the book's protagonist, stating that he is "the dominant figure throughout [...]. His guilt, his shortcomings, his failures pervade the entire book".[6] Bishop states that while the constant flux of HCE's character and attributes may lead us to consider him as an "anyman," he argues that "the sheer density of certain repeated details and concerns allows us to know that he is a particular, real Dubliner." The common critical consensus of HCE's fixed character is summarised by Bishop as being "an older Protestant male, of Scandinavian lineage, connected with the pubkeeping business somewhere in the neighbourhood of Chapelizod, who has a wife, a daughter, and two sons."[152]: 135 Bernadette Lowry in her book, "Sounds of Manymirth on the Night's Ear Ringing, Percy French (1854-1930) His Jarvey Years and Joyce's Haunted Inkbottle" believes that HCE is mainly modelled on Percy French, whom she identifies as the singular Finnegan within the HCE "general omnibus character". Lowry believe there are central models from Dublin for the book, and that they are all based of Percy French and his circle, especially in his Jarvey years but concedes that all are fluid. She argued that HCE is an overblown, inflated abstraction, inspired by nasty and baseless rumours that circulated about French. The Jarvey was a highly literary, weekly comic journal, which French edited from January 1889- January 1891. It was controversial, in that it lampooned Parnell during the crisis in the IPP, which brought The Jarvey down suddenly. Lowry believes Joyce's father was involved. Lowry found the crucial reference to French's death in Liverpool on page 73-74 for the first time in over eighty years since the Wake was published. It is described as the passage of the giant, Finn- Finnegan and he is interchangeably with Finn McCool. Joyce pays tribute to French, in a very lyrical passage in referencing two of Moore's melodies. French did numerous parodies of Moore's Melodies in The Jarvey and the Irish Cyclist. Elsewhere, in the Wake, French is referred to as "the trumpadour (troubadour) who mangled Moore's melodies". Ten parts of Dublin are mentioned in the passage, including the Coombe, Kilmainham, Pembroke, Baldoyle, Rathfarnham and Enniskerry. She believes that French is the sleeping giant in the Dublin landscape and that in saying "he skall (shall) wake from earthsleep" Joyce pledged to resurrect French. The Jarvey, she believes is a forerunner of Bloom and several of its passages were detected by her in Finnegans Wake. Joyce declared his intention to resurrect French and make him "Finn again. " After publishing her book, Lowry decoded the portmanteau word, "Bussoftlhee" in the final three lines of the ALP monologue, as Kiss of Ethel. Ethel was Percy French's tragic first wife who died three weeks after giving birth to her daughter, aged only twenty. Ethel had contributed a weekly fashion and gossip column to The Jarvey with beautiful drawing, mainly of the Liffey at Leixlip, Lucan and Chapelizod, especially in the final six months of The Jarvey. Ethel had been extremely distressed by the sudden and unexpected collapse of The Jarvey and it contributed to her tragedy. Her name has been detected now 18 times in the Wake. Lowry believes the Wake is an encomium to French and that he is the sleeping giant on the Dublin landscape especially in his brilliant Jarvey years - the Jarvey is itself a paean to Dublin. Dublin is the omphalos of the book and it has Dublin models which spawns to the cosmic but Dublin and its discreet models are the umbilicus. Magrath she believes is mainly Richard J Mecredy who set up The Jarvey and wrote against Parnell, hiding behind French as editor. In chapter 1, the overture Chapter, the giant is described as Phil the Fluter, a song Percy French stretching from Howth to Phoenix Park. She notes that Vivian Mercier had picked up on the significance of this in his book, "The Irish Comic Tradition". Lowry believes that Joyce intended an epic resurrection for French, to correct many injustices done to him by persons associated with his own father. HCE is referred to by literally thousands of names throughout the book; leading Terence Killeen to argue that in Finnegans Wake "naming is [...] a fluid and provisional process".[153] HCE is at first referred to as "Harold or Humphrey Chimpden";[154] a conflation of these names as "Haromphreyld",[155] and as a consequence of his initials "Here Comes Everybody".[156] These initials lend themselves to phrase after phrase throughout the book; for example, appearing in the book's opening sentence as "Howth Castle and Environs". As the work progresses the names by which he may be referred to become increasingly abstract (such as "Finn MacCool",[157] "Mr. Makeall Gone",[158] or "Mr. Porter"[159]). Some Wake critics, such as Finn Fordham, argue that HCE's initials come from the initials of the portly politician Hugh Childers (1827–96), who had been nicknamed "Here Comes Everybody" for his size.[160] Many critics see Finnegan, whose death, wake and resurrection are the subject of the opening chapter, as either a prototype of HCE, or as another of his manifestations. One of the reasons for this close identification is that Finnegan is called a "man of hod, cement and edifices" and "like Haroun Childeric Eggeberth",[161] identifying him with the initials HCE. Parrinder for example states that "Bygmester Finnegan [...] is HCE", and finds that his fall and resurrection foreshadows "the fall of HCE early in Book I [which is] paralleled by his resurrection towards the end of III.3, in the section originally called "Haveth Childers Everywhere", when [HCE's] ghost speaks forth in the middle of a seance."[162] Anna Livia Plurabelle (ALP) Patrick McCarthy describes HCE's wife ALP as "the river-woman whose presence is implied in the 'riverrun' with which Finnegans Wake opens and whose monologue closes the book. For over six hundred pages, Joyce presents Anna Livia to us almost exclusively through other characters, much as in Ulysses we hear what Molly Bloom has to say about herself only in the last chapter."[163] The most extensive discussion of ALP comes in chapter I.8, in which hundreds of names of rivers are woven into the tale of ALP's life, as told by two gossiping washerwomen. Similarly hundreds of city names are woven into "Haveth Childers Everywhere", the corresponding passage at the end of III.3 which focuses on HCE. As a result, it is generally contended that HCE personifies the Viking-founded city of Dublin, and his wife ALP personifies the river Liffey, on whose banks the city was built. Shem, Shaun and Issy ALP and HCE have a daughter, Issy – whose personality is often split (represented by her mirror-twin). Parrinder argues that "as daughter and sister, she is an object of secret and repressed desire both to her father [...] and to her two brothers."[164] These twin sons of HCE and ALP consist of a writer called Shem the Penman and a postman by the name of Shaun the Post, who are rivals for replacing their father and for their sister Issy's affection. Shaun is portrayed as a dull postman, conforming to society's expectations, while Shem is a bright artist and sinister experimenter, often perceived as Joyce's alter-ego in the book.[165] Hugh Staples finds that Shaun "wants to be thought of as a man-about-town, a snappy dresser, a glutton and a gourmet... He is possessed of a musical voice and is a braggart. He is not happy in his work, which is that of a messenger or a postman; he would rather be a priest."[166] Shaun's sudden and somewhat unexpected promotion to the book's central character in Part III is explained by Tindall with the assertion that "having disposed of old HCE, Shaun is becoming the new HCE."[167] Like their father, Shem and Shaun are referred to by different names throughout the book, such as "Caddy and Primas";[168] "Mercius" and "Justius";[169][170] "Dolph and Kevin";[171] and "Jerry and Kevin".[172] These twins are contrasted in the book by allusions to sets of opposing twins and enemies in literature, mythology and history; such as Set and Horus of the Osiris story; the biblical pairs Jacob and Esau, Cain and Abel, and Saint Michael and the Devil – equating Shaun with "Mick" and Shem with "Nick" – as well as Romulus and Remus. They also represent the oppositions of time and space,[173] and tree and stone.[174]: 224 Minor characters The most commonly recurring characters outside of the Earwicker family are the four old men known collectively as "Mamalujo" (a conflation of their names: Matt Gregory, Marcus Lyons, Luke Tarpey and Johnny Mac Dougall). These four most commonly serve as narrators, but they also play a number of active roles in the text, such as when they serve as the judges in the court case of I.4, or as the inquisitors who question Yawn in III.4. Tindall summarises the roles that these old men play as those of the Four Masters, the Four Evangelists, and the four Provinces of Ireland ( "Matthew, from the north, is Ulster; Mark, from the south, is Munster; Luke, from the east, is Leinster; and John, from the west, is Connaught").[175]: 255 According to Finn Fordham, Joyce related to his daughter-in-law Helen Fleischmann that "Mamalujo" also represented Joyce's own family, namely his wife Nora (mama), daughter Lucia (lu), and son Giorgio (jo).[176]: 77 In addition to the four old men, there are a group of twelve unnamed men who always appear together, and serve as the customers in Earwicker's pub, gossipers about his sins, jurors at his trial and mourners at his wake.[177]: 5 The Earwicker household also includes two cleaning staff: Kate, the maid, and Joe, who is by turns handyman and barman in Earwicker's pub. Tindall considers these characters to be older versions of ALP and HCE.[178]: 4–5 Kate often plays the role of museum curator, as in the "Willingdone Museyroom" episode of 1.1, and is recognisable by her repeated motif "Tip! Tip!" Joe is often also referred to by the name "Sackerson", and Kitcher describes him as "a figure sometimes playing the role of policeman, sometimes [...] a squalid derelict, and most frequently the odd-job man of HCE's inn, Kate's male counterpart, who can ambiguously indicate an older version of HCE."[179]: 39 |
登場人物 「フィネガンズ・ウェイク』に登場する人物を特定できるかどうかは、批評家の間でも意見が分かれるところである。 フィネガンズ・ウェイク』に識別可能なキャラクターが存在するかどうかについては、批評家の間でも意見が分かれている。例えば、グレース・エクリーはウェ イクの登場人物は互いに区別されていると主張し[145]、二重の語り手、最初の段落の「私たち」、セム=ショーンの区別を説明することでこれを擁護して いる[146]が、マーゴット・ノリスは「登場人物は流動的で交換可能である」と主張している[147]。 147]後者の立場を支持するヴァン・ヒュールは、『フィネガンズ・ウェイク』の「登場人物」はむしろ「原型あるいは登場人物のアマルガムであり、さまざ まな形をとっている」と見なしており[148]、リケルメも同様に、この本の変幻自在な登場人物のキャストを「プロテアン」と呼んでいる[149]。 [149]1934年には早くも、最近発表された抜粋「The Mookse and the Gripes」に対して、ロナルド・シモンドは、「『仕掛人』の登場人物は、彼らが生きている時空の混沌に合わせて、自在にアイデンティティを変えてい る。ある時は人物であり、またある時は川や石や木であり、またある時はアイデアの擬人化であり、またある時はクロスワードパズルを遥かに凌ぐ独創性をもっ て、散文の実際の質感の中に迷い隠されている」[150]。このような人物の正体の隠蔽は、批評家たちがこの本の主要な主人公をどのように識別するかにつ いて、多少のばらつきをもたらす結果となった、 例えば、I.4で裁判に登場するフェスティ・キングはHCEタイプであるという点では大方の意見が一致しているが、全ての分析者がこれに同意しているわけ ではなく、例えばアンソニー・バージェスは彼をショーンであると考えている[151]。 登場人物は常に流動的であり、名前、職業、身体的属性は絶えず変化しているが、繰り返し登場する核となる人物、あるいは登場人物のタイプ(ノリスは「暗 号」と呼んでいる)は識別可能である。フィネガンズ・ウェイク』の執筆中、ジョイスはこうした登場人物のアマルガムやタイプを指定するのに、名前ではなく 記号、いわゆる「シグラ」を用いた。区別可能な登場人物の存在を主張する人々にとって、本書は父、母、双子の息子と娘からなるアールウィッカー家に焦点を 当てている。 ハンフリー・チンプデン・アーウィッカー(HCE) キッチャーは、父親であるHCEがこの本の主人公であると主張し、彼が「全体を通して支配的な人物である[...]」と述べている。ビショップは、HCE の性格や属性が常に流動的であることから、彼を 「anyman 」とみなすことができるかもしれないが、「繰り返される細部や懸念事項の密度の高さによって、彼が特定の実在のダブリナーであることを知ることができる」 と論じている[6]。HCEの固定的な人物像に関する批評家たちの共通のコンセンサスは、ビショップによって「スカンジナビア人の血筋を引く年配のプロテ スタントの男性で、チャペリゾッド近辺のどこかでパブ業に携わっており、妻と娘と二人の息子がいる」と要約されている[152]: 135 バーナデット・ローリーはその著書『夜の耳鳴りに響く多幸の音、パーシー・フレンチ(1854-1930)彼のジャーヴェイ時代とジョイスの呪われたイン クボトル』の中で、HCEは主にパーシー・フレンチをモデルにしていると考えており、彼女はパーシー・フレンチをHCEの「一般的なオムニバス・キャラク ター」の中の特異なフィネガンとしている。ローリーは、この本にはダブリンの中心的なモデルが存在し、それらはすべてパーシー・フレンチと彼のサークル、 特に彼のジャーヴィー時代に基づいていると考えているが、すべてが流動的であることは認めている。彼女は、HCEはフレンチについて流布された根拠のない 悪い噂に触発された、大げさで膨張した抽象的なものだと主張した。ジャーベイは、フレンチが1889年1月から1891年1月まで編集していた、非常に文 学的な週刊コミック誌である。IPPの危機の最中にパーネルを揶揄したことで物議を醸し、『ジャーベイ』は突然廃刊となった。ローリーはジョイスの父親が 関与していたと考えている。 ローリーは、『航跡』が出版されてから80年以上経って初めて、リバプールでのフレンチの死に関する重要な記述を73-74ページで見つけた。そこは巨人 フィン・フィネガンの通過点として記述されており、彼はフィン・マックールと入れ替わっている。ジョイスは、ムーアの2つのメロディに言及した非常に叙情 的な一節で、フレンチに敬意を表している。フレンチは『ジャービー』と『アイルランドの自転車乗り』の中で、ムーアのメロディーのパロディーを数多く作っ ている。他の箇所では、『ウェイク』の中で、フレンチは「ムーアのメロディーをこねくり回したトランパドール(吟遊詩人)」と呼ばれている。クーム、キル メイナム、ペンブローク、バルドイル、ラスファーナム、エニスケリーなど、ダブリンの10箇所がその一節で言及されている。彼女は、フレンチはダブリンの 風景の中で眠れる巨人であり、ジョイスは「彼は大地の眠りから目覚めるだろう(he skall (shall) wake from earthsleep)」と言って、フレンチの復活を誓ったのだと考えている。ジャーヴィーはブルームの前身であり、『フィネガンズ・ウェイク』ではその 詩句のいくつかが彼女に発見されたと彼女は信じている。ジョイスはフレンチを復活させ、「フィンの再来 」とすることを宣言した。「本を出版した後、ローリーはALPのモノローグの最後の3行にある 「Bussoftlhee 」という合言葉を、Kiss of Ethelと解読した。エセルとはパーシー・フレンチの悲劇の最初の妻で、娘を出産した3週間後にわずか20歳で亡くなった。エセルは週刊誌『ジャーベ イ』にファッションとゴシップのコラムを寄稿し、主にレイクスリップ、ルカン、チャペリゾッドのリフィー川の美しい絵を描いていた。エセルは『ジャーベ イ』の突然の倒産に非常に心を痛めており、それが彼女の悲劇を招いた。彼女の名前はウェイクの中で18回検出されている。ローリーは、『ウェイク』はフレ ンチへの賛辞であり、彼がダブリンの風景に眠る巨人であると信じている。ダブリンはこの本のオムファロスであり、ダブリンのモデルが宇宙的なものへと産み 落とされるが、ダブリンとその控えめなモデルが臍である。マグラスは、主にリチャード・J・メクレディのことだと彼女は考えている。 第1章序曲の章では、巨人はフィル・ザ・フルーターと表現され、パーシー・フレンチがハウズからフェニックス・パークまで伸ばした歌である。彼女は、ヴィ ヴィアン・メルシエがその著書『アイルランドのコミックの伝統』の中でこの意味を取り上げていたことを指摘している。ローリーは、ジョイスがフレンチのた めに壮大な復活を意図したのは、実父の関係者が彼に行った多くの不正を正すためだと考えている。 テレンス・キリーンは『フィネガンズ・ウェイク』において、HCEは文字通り何千もの名で呼ばれており、「名付けは[...]流動的で暫定的なプロセスで ある」と論じている。 [HCE は最初「ハロルドまたはハンフリー・チンプデン」と呼ばれ[154]、これらの名前が混同されて「ハロムフレイ ルド」と呼ばれ[155]、彼のイニシャルの結果として「ヒア・カムズ・エヴリバディ」と呼ばれる[156]。作品が進むにつれて、彼が呼ばれることがあ る名前はますます抽象的になっていく(「フィン・マックール」[157]、「ミスター・メイクオール・ゴーン」[158]、「ミスター・ポーター」 [159]など)。 フィン・フォーダムのようなウェイクの批評家の中には、HCEの頭文字は、その体格から「Here Comes Everybody」というニックネームをつけられていた大柄な政治家ヒュー・チルダーズ(1827-96)の頭文字に由来すると主張する者もいる[160]。 多くの批評家は、序章の主題である死、通夜、復活を遂げたフィネガンを、HCEの原型、あるいはHCEのもう一つの現れと見ている。この密接な同一性の理 由の一つは、フィネガンが「ホッド、セメント、建造物の男」、「ハロウン・チルデリック・エッゲバースのような」と呼ばれ[161]、HCEのイニシャル と同一視されていることである。例えばパリンダーは「バイグメスター・フィネガンは......HCEである」と述べ、彼の没落と復活が「第Ⅰ巻の初期に おけるHCEの没落は、第Ⅲ.3の終わり、本来は 「Haveth Childers Everywhere 」と呼ばれる部分において、降霊会の最中に[HCEの]亡霊が語り出す際の彼の復活と並行する」[162]予兆であると見出している。 アンナ・リヴィア・プルラベル(ALP) パトリック・マッカーシーはHCEの妻ALPを「『フィネガンズ・ウェイク』の冒頭を飾る 「riverrun 」でその存在が暗示され、そのモノローグで本書を閉じる川の女」と表現している。Ulysses(ユリシーズ)』において、モリー・ブルームが自分自身に ついて語るのを聞くのは最後の章だけであるのと同じように。同様に、HCEに焦点を当てたIII.3の最後にある対応する一節、「Haveth Childers Everywhere 」にも何百もの都市名が織り込まれている。その結果、一般にHCEはヴァイキングが築いた都市ダブリンを擬人化し、彼の妻ALPはその都市が築かれたリ フィー川を擬人化していると主張されている。 セム、ショーン、イッシー ALPとHCEには娘のイッシーがいる。イッシーの人格はしばしば分裂している(鏡の双子によって表現されている)。HCEとALPの双子の息子たちは、 ペンマンのセムと郵便配達のショーンという名の作家で構成されており、彼らは父親の代わりと妹イッシーの愛情をめぐってライバル関係にある。ショーンは社 会の期待に応える冴えない郵便配達員として描かれ、セムは聡明な芸術家で不吉な実験者であり、しばしばこの本の中ではジョイスの分身として認識されてい る。彼は音楽的な声を持っており、自慢屋である。彼はメッセンジャーや郵便配達という自分の仕事に満足しておらず、むしろ司祭になりたがっている」 [166]。第III部でショーンが突然、やや予期せぬ形で本書の中心人物に昇進したことについて、ティンダルは「古いHCEを処分したショーンは、新し いHCEになりつつある」という主張で説明している[167]。 父親と同様に、セムとショーンは「キャディとプリマス」[168]、「メルシウス」と「ユスティウス」[169][170]、「ドルフとケヴィン」 [171]、「ジェリーとケヴィン」など、本書を通して異なる名前で呼ばれている。 [172]これらの双子は、オシリス物語のセトとホルス、聖書のヤコブとエサウ、カインとアベル、聖ミカエルと悪魔のペア(ショーンを「ミック」、セムを 「ニック」と同一視)、ロムルスとレムスなど、文学、神話、歴史における対立する双子や敵のセットを暗示することによって、この本の中で対比されている。 また、時間と空間[173]、木と石の対立も表している[174]。 マイナーキャラクター アールウィッカー家以外で最もよく登場するのは、「Mamalujo 」と総称される4人の老人たち(彼らの名前を合体させたもの: マット・グレゴリー、マーカス・ライオンズ、ルーク・ターペイ、ジョニー・マック・ドーガル)。この4人は語り手として登場することが多いが、I.4の法 廷で裁判官を務めたり、III.4でヨーンを尋問する審問官を務めるなど、本文中でも積極的な役割を果たす。ティンダルは、これらの老人が果たす役割を、 四人の主人、四人の福音書記者、アイルランドの四つの州(「北から来たマタイはアルスター、南から来たマルコはマンスター、東から来たルカはレンスター、 西から来たヨハネはコンノート」)と要約している。 [175]: 255 フィン・フォーダムによれば、ジョイスは義理の娘ヘレン・フライシュマンに、「ママルーヨ」はジョイス自身の家族、すなわち妻ノラ(ママ)、娘ルシア (ル)、息子ジョルジョ(ジョ)をも表していると語っている[176]: 77。 4人の老人に加えて、いつも一緒に登場する12人の無名の男たちがおり、アールウィッカーのパブの客、彼の罪についての噂話相手、彼の裁判の陪審員、彼の 通夜の弔問客となっている[177]: 5 アールウィッカー家には2人の掃除係もいる: メイドのケイトと、便利屋であると同時にアールウィッカーのパブのバーテンでもあるジョーである。ティンダルは、これらの登場人物をALPとHCEの古い バージョンだと考えている[178]: 4-5ケイトは、1.1の 「Willingdone Museyroom 」のエピソードのように、しばしば博物館の学芸員の役を演じており、彼女が繰り返す "Tip!チップ!」 また、ジョーはしばしば 「Sackerson 」という名で呼ばれ、キッチャーは彼を「時には警察官、時には[...]汚らしい廃人、そして最も頻繁にはHCEの宿屋の雑用係であり、ケイトの相方の男 性であり、HCEの古いバージョンを曖昧に示すことがある」と表現している[179]: 39 |
| Language and style "riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs." —The opening line of Finnegans Wake, which continues from the book's unfinished closing line:[180] , "A way a lone a last a loved a long the"  The Franciscan Church of the Immaculate Conception in Dublin, popularly known as Adam & Eve's, referred to in the opening of Finnegans Wake Joyce invented a unique polyglot-language or idioglossia solely for the purpose of this work. This language is composed of composite words from some sixty to seventy world languages,[181] combined to form puns, or portmanteau words and phrases intended to convey several layers of meaning at once. Senn has labelled Finnegans Wake's language as "polysemetic",[96] and Tindall as an "Arabesque".[182] Norris describes it as a language which "like poetry, uses words and images which can mean several, often contradictory, things at once"[183] The style has also been compared to rumour and gossip, especially in the way the writing subverts notions of political and scholarly authority.[184] An early review of the book argued that Joyce was attempting "to employ language as a new medium, breaking down all grammatical usages, all time space values, all ordinary conceptions of context [...] the theme is the language and the language the theme, and a language where every association of sound and free association is exploited."[185] Seconding this analysis of the book's emphasis on form over content, Paul Rosenfeld reviewed Finnegans Wake in 1939 with the suggestion that "the writing is not so much about something as it is that something itself [..] in Finnegans Wake the style, the essential qualities and movement of the words, their rhythmic and melodic sequences, and the emotional color of the page are the main representatives of the author's thought and feeling. The accepted significations of the words are secondary."[186] While commentators emphasize how this manner of writing can communicate multiple levels of meaning simultaneously, Hayman and Norris contend that its purpose is as much to obscure and disable meaning as to expand it. Hayman writes that access to the work's "tenuous narratives" may be achieved only through "the dense weave of a language designed as much to shield as to reveal them."[187] Norris argues that Joyce's language is "devious" and that it "conceals and reveals secrets."[183] Allen B. Ruch has dubbed Joyce's new language "dreamspeak," and describes it as "a language that’s basically English, but extremely malleable and all-inclusive, a fusion of portmanteau words, stylistic parodies, and complex puns."[188] Although much has been made of the numerous world languages employed in the book's composite language, most of the more obscure languages appear only seldom in small clusters, and most agree with Ruch that the latent sense of the language, however manifestly obscure, is "basically English".[189][190] Burrell also finds that Joyce's thousands of neologisms are "based on the same etymological principles as standard English."[191] The Wake's language is not entirely unique in literature; for example critics have seen its use of portmanteaus and neologisms as an extension of Lewis Carroll's Jabberwocky.[192] Although Joyce died shortly after the publication of Finnegans Wake, during the work's composition the author made a number of statements concerning his intentions in writing in such an original manner. In a letter to Max Eastman, for example, Joyce suggested that his decision to employ such a unique and complex language was a direct result from his attempts to represent the night: In writing of the night I really could not, I felt I could not, use words in their ordinary connections. Used that way they do not express how things are in the night, in the different stages – the conscious, then semi-conscious, then unconscious. I found that it could not be done with words in their ordinary relations and connections. When morning comes of course everything will be clear again [...] I'll give them back their English language. I'm not destroying it for good.[193] Joyce is also reported as having told Arthur Power that "what is clear and concise can't deal with reality, for to be real is to be surrounded by mystery."[194] On the subject of the vast number of puns employed in the work Joyce argued to Frank Budgen that "after all, the Holy Roman Catholic Apostolic Church was built on a pun. It ought to be good enough for me",[193] and to the objection of triviality he replied "Yes. Some of the means I use are trivial – and some are quadrivial."[193] A great many of the book's puns are etymological in nature. Sources tell us that Joyce relished delving into the history and the changing meanings of words, his primary source being An Etymological Dictionary of the English Language by the Rev. Walter W. Skeat (Oxford, at the Clarendon Press; 1879). For example, one of the first entries in Skeat is for the letter A, which begins: "...(1) adown; (2) afoot; (3) along; (4) arise; (5) achieve; (6) avert; (7) amend; (8) alas; (9) abyss..." Further in the entry, Skeat writes: "These prefixes are discussed at greater length under the headings Of, On, Along, Arise...Alas, Aware, Avast..." It seems likely that these strings of words prompted Joyce to finish the Wake with a sentence fragment that included the words: "...a way a lone a last a loved a long..."[195]: 272ff. Samuel Beckett collected words from foreign languages on cards for Joyce to use, and, as Joyce's eyesight worsened, wrote down the text from his dictation.[196] Beckett described and defended the writing style of Finnegans Wake thus: "This writing that you find so obscure is a quintessential extraction of language and painting and gesture, with all the inevitable clarity of the old inarticulation. Here is the savage economy of hieroglyphics".[197] Faced with the obstacles to be surmounted in "understanding" Joyce's text, a handful of critics have suggested readers focus on the rhythm and sound of the language, rather than solely on "meaning." As early as 1929, Eugène Jolas stressed the importance of the aural and musical dimensions of the work. In his contribution to Our Exagmination Round His Factification for Incamination of Work in Progress, Jolas wrote: Those who have heard Mr. Joyce read aloud from Work in Progress know the immense rhythmic beauty of his technique. It has a musical flow that flatters the ear, that has the organic structure of works of nature, that transmits painstakingly every vowel and consonant formed by his ear.[198] Allusions to other works 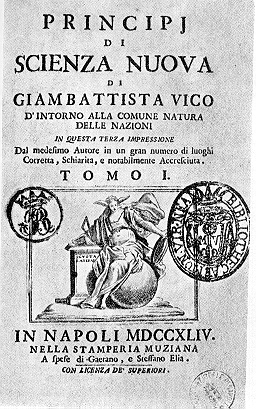 Giambattista Vico's La Scienza Nuova (The New Science), an influence on the structure of Finnegans Wake. Finnegans Wake incorporates a high number of intertextual allusions and references to other texts; Parrinder refers to it as "a remarkable example of intertextuality" containing a "wealth of literary reference."[199] Among the most prominent are the Irish ballad "Finnegan's Wake" from which the book takes its name, Italian philosopher Giovanni Battista Vico's La Scienza Nuova,[200] the Egyptian Book of the Dead, the plays of Shakespeare,[201] and religious texts such as the Bible and Qur'an.[202]: 166–167 These allusions, rather than directly quoting or referencing a source, normally enter the text in a contorted fashion, often through humorous plays on words. For example, Hamlet Prince of Denmark becomes "Camelot, prince of dinmurk"[203] and the Epistle to the Hebrews becomes a "farced epistol to the hibruws".[204] The book begins with one such allusion to Vico's New Science: "riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs". "Commodius vicus" refers to Giambattista Vico (1668–1744), who proposed a theory of cyclical history in his work La Scienza Nuova (The New Science). Vico argued that the world was coming to the end of the last of three ages, these being the age of gods, the age of heroes, and the age of humans. These ideas recur throughout Finnegans Wake, informing the book's four-part structure. Vico's name appears a number of times throughout the Wake, indicating the work's debt to his theories, such as "The Vico road goes round and round to meet where terms begin".[205] That a reference to Vico's cyclical theory of history is to be found in the opening sentence which is a continuation of the book's closing sentence – thus making the work cyclical in itself – creates the relevance of such an allusion. One of the sources Joyce drew from is the Ancient Egyptian story of Osiris,[206] and the Egyptian Book of the Dead, a collection of spells and invocations. Bishop asserts that "it is impossible to overlook the vital presence of the Book of the Dead in Finnegans Wake, which refers to ancient Egypt in countless tags and allusions."[207] Joyce uses the Book of the Dead in Finnegans Wake, "because it is a collection of the incantations for the resurrection and rebirth of the dead on the burial".[208] At one of their final meetings, Joyce suggested to Frank Budgen that he write an article about Finnegans Wake, entitling it "James Joyce's Book of the Dead". Budgen followed Joyce's advice with his paper "Joyce's Chapters of Going Forth by Day", highlighting many of the allusions to Egyptian mythology in the book.[209] The Tristan and Iseult legend – a tragic love triangle between the Irish princess Iseult, the Cornish knight Tristan and his uncle King Mark – is also oft alluded to in the work, particularly in II.4. Fargnoli and Gillespie argue that "various themes and motifs throughout Finnegans Wake, such as the cuckoldry of Humphrey Chimpden Earwicker (a King Mark figure) and Shaun's attempts at seducing Issy, relate directly to Tristan and Isolde [...] other motifs relating to Earwicker's loss of authority, such as the forces usurping his parental status, are also based on Tristan and Isolde."[210] The book also alludes heavily to Irish mythology, with HCE sometimes corresponding to Fionn mac Cumhaill,[211] Issy and ALP to Gráinne, and Shem/Shaun to Dermot (Diarmaid). Not only Irish mythology, but also notable real-life Irish figures are alluded to throughout the text. For example, HCE is often identified with Charles Stewart Parnell, and Shem's attack on his father in this way mirrors the attempt of forger Richard Pigott to incriminate Parnell in the Phoenix Park Murders of 1882 by means of false letters. But, given the flexibility of allusion in Finnegans Wake HCE assumes the character of Pigott as well, for just as HCE betrays himself to the cad, Pigott betrayed himself at the inquiry into admitting the forgery by his spelling of the word "hesitancy" as "hesitency"; and this misspelling appears frequently in the Wake. Finnegans Wake also makes a great number of allusions to religious texts. When HCE is first introduced in chapter I.2, the narrator relates how "in the beginning" he was a "grand old gardener", thus equating him with Adam in the Garden of Eden. Spinks further highlights this allusion by highlighting that like HCE's unspecified crime in the park, Adam also "commits a crime in a garden".[212]: 130 Norwegian influence With Dublin, an early Viking settlement, as the setting for Finnegans Wake, it is perhaps not surprising that Joyce incorporated a number of Norwegian linguistic and cultural elements into the work (e.g., Riksmål references). One of the main tales of chapter II.3 concerns a Norwegian tailor, and a number of Norwegian words such as bakvandets, Knut Oelsvinger and Bygmester Finnegan (the latter a reference to Ibsen's Bygmester Solness)[213]: 210 are used throughout. Indeed, most of Ibsen's works, many of his characters and also some quotations are referenced in the Wake. While Joyce was working on Finnegans Wake, he wanted to insert references to Scandinavian languages and literature, hiring five teachers of Norwegian.[214]: 121–122 The first one turned out to be the poet Olaf Bull. Joyce wanted to read Norwegian works in the original language, including Peter Andreas Munch's Norrøne gude- og heltesagn (Norse tales of gods and heroes). He was looking for puns and unusual associations across the barriers of language, a practice Bull well understood. Lines from Bull's poems echo through Finnegans Wake, and Bull himself materializes under the name "Olaph the Oxman", a pun on his surname.[215] Hundred-letter words An extreme example of the Wake's language are a series of ten one-hundred letter words spread throughout the text (although the tenth in actuality has a hundred and one letters). The first such word occurs on the text's first page; all ten are presented in the context of their complete sentences, below. -The fall (bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk!) of a once wallstrait oldparr is retaled early in bed and later on life down through all christian minstrelsy.[216] -And the duppy shot the shutter clup (Perkodhuskurunbarggruauyagokgorlayorgromgremmitghundhurthrumathunaradidillifaititillibumullunukkunun!)[217] -The (klikkaklakkaklaskaklopatzklatschabattacreppycrottygraddaghsemmihsammihnouithappluddyappladdypkonpkot!).[218] -Bladyughfoulmoecklenburgwhurawhorascortastrumpapornanennykocksapastippatappatupperstrippuckputtanach, eh?[219] -Thingcrooklyexineverypasturesixdixlikencehimaroundhersthemaggerbykinkinkankanwithdownmindlookingated.[220] -Wold Forrester Farley who, in deesperation of deispiration at the diasporation of his diesparation, was found of the round of the sound of the lound of the Lukkedoerendunandurraskewdylooshoofermoyportertooryzooysphalnabortansporthaokansakroidverjkapakkapuk.[221] -Bothallchoractorschumminaroundgansumuminarumdrumstrumtruminahumptadumpwaultopoofoolooderamaunstrunup![222] -For hanigen with hunigen still haunt ahunt to finnd their hinnigen where Pappappapparrassannuaragheallachnatullaghmonganmacmacmacwhackfalltherdebblenonthedubblandaddydoodled and anruly person creeked a jest.[223] -Let us here consider the casus, my dear little cousis (husstenhasstencaffincoffintussemtossemdamandamnacosaghcusaghhobixhatouxpeswchbechoscashlcarcarcaract) of the Ondt and the Gracehoper.[224] -Ullhodturdenweirmudgaardgringnirurdrmolnirfenrirlukkilokkibaugimandodrrerinsurtkrinmgernrackinarockar![225] These ten words have come to be known as thunders, thunderclaps, or thunderwords, based upon interpretation of the first word as being a portmanteau of several word-forms for thunder, in several languages.[226] The Canadian media theorist Marshall McLuhan (with Quentin Fiore and Jerome Agel) made this connection explicit in his War and Peace in the Global Village, where he identified the ten words as "thunders",[227] reproducing them in his own text.[228] For the purposes of his book, McLuhan appropriated the ten words and interpreted them as symbolizing various forms of human technology, which together with other liberal quotations from the Wake form a parallel rhetoric which McLuhan used to discuss technology, warfare, and human society. Marshall's son Eric McLuhan carried on his father's interpretation of the thunders, publishing The Role of Thunder in Finnegans Wake, a book expressly devoted to the meaning of the ten words.[229] For [Eric] McLuhan, the total letter count of the above ten words (1001) intentionally corresponds to the One Thousand and One Nights of Middle Eastern folklore, which buttresses the critical interpretation of the Wake as being a book of the night.[230] -The hundredlettered name again, last word of perfect language. But you could come near it, we do suppose, strong Shaun O', we foresupposed. How?[225] |
言語と文体 「リヴァーランは、イヴとアダムを過ぎ、岸辺のうねりから湾の曲がり角へと、循環のコモディウス・ヴィカスによって我々をハウズ城とその周辺へと連れ戻す。」 -フィネガンズ・ウェイク』の冒頭の一節で、この本の未完の終わりから続く[180]。  『フィネガンズ・ウェイク』の冒頭で言及され、アダムとイヴの教会として親しまれているダブリンの無原罪の聖母フランシスコ会教会 ジョイスはこの作品のためだけに、独自の多言語(イディオグロシア)を発明した。この言語は、60から70ほどの世界言語の合成語[181]で構成されて おり、駄洒落や、いくつかの意味の層を一度に伝えることを意図したポートマント語やフレーズを形成するために組み合わされている。センはフィネガンズ・ ウェイクの言語を「多義的」[96]、ティンドールを「アラベスク」[182]と評し、ノリスは「詩のように、いくつかの、しばしば矛盾することを同時に 意味しうる言葉やイメージを使う」言語であると述べている[183]。 [184]初期の書評では、ジョイスは「あらゆる文法的用法、あらゆる時間的空間的価値、文脈に関する通常の概念を打ち壊し、新しいメディアとして言語を 使おうとしている。 ...テーマは言語であり、言語はテーマであり、音のあらゆる連想と自由な連想が利用される言語である」[185]。内容よりも形式を重視するこの本の分 析に次いで、ポール・ローゼンフェルドは1939年に『フィネガンズ・ウェイク』を評して、「文章は何かについてというよりも、その何かそのものである [...]。 フィネガンズ・ウェイク』では、文体、言葉の本質的な特質と動き、リズムと旋律の連続、そしてページの感情的な色彩が、作者の思考と感情の主な代表であ る。言葉の意味は二の次である」[186]。 解説者たちは、このような書き方がいかに複数のレベルの意味を同時に伝えることができるかを強調しているが、ヘイマンとノリスは、その目的は意味を拡大す ることよりも、意味を不明瞭にし、無効にすることにあると主張している。ヘイマンは、作品の「希薄な物語」へのアクセスは、「それを明らかにするのと同様 に、それを遮蔽するように設計された言語の緻密な織り目」[187]によってのみ達成されるかもしれないと書いている。 Allen B. Ruchはジョイスの新しい言語を「dreamspeak」と名付け、「基本的には英語であるが、極めて可鍛性で包括的な言語であり、ポートマントー語、 文体的パロディ、複雑な駄洒落の融合である」と表現している[183]。 「188]この本の合成言語に採用されている数多くの世界の言語について多くのことが語られているが、より無名な言語のほとんどは、小さなクラスターで めったに登場しないだけであり、その言語の潜在的な意味は、どんなに明らかに無名であっても、「基本的には英語」であるというルッチに同意する人がほとん どである。 [189][190]またバレルはジョイスの何千もの新語は「標準的な英語と同じ語源学的な原理に基づいている」と見なしている[191]。 ジョイスは『フィネガンズ・ウェイク』の出版直後に死去したが、この作品の執筆中に、作者はこのような独創的な方法で執筆する意図について多くの発言をし ている。例えば、マックス・イーストマン宛ての手紙の中で、ジョイスは、このような独特で複雑な言語を用いることにしたのは、夜を表現しようとしたことが 直接の原因であると示唆している: 夜について書くにあたって、私は本当に言葉を普通のつながりの中で使うことができなかった。そのような使い方をすると、意識、半意識、無意識といったさま ざまな段階における、夜の物事のあり方を表現できない。普通の関係や結びつきの言葉では表現できないことがわかった。朝が来れば、もちろんまたすべてがク リアになる。私は永久にそれを破壊しない」[193]。 ジョイスはまた、アーサー・パワーに「明確で簡潔なものは現実を扱うことができない。私が使う手段のいくつかはつまらないものであり、いくつかは四重苦で ある」[193]と答えている。情報源によれば、ジョイスは言葉の歴史や意味の変化を掘り下げるのが好きだったようで、彼の主要な情報源はウォルター・ W・スキート師による『英語語源辞典』(オックスフォード、クラレンドン・プレス、1879年)であった。例えば、Skeatの最初の項目のひとつは、A という文字についてである: 「(1) adown; (2) afoot; (3) along; (4) arise; (5) achieve; (6) avert; (7) amend; (8) alas; (9) abyss..." と始まる。これらの接頭辞については、「Of, On, Along, Arise... Alas, Aware, Avast... 」という見出しでさらに詳しく論じている。ジョイスが『航跡』の最後を、このような単語を含む文章の断片で締めくくるように促したのは、おそらくこのよう な単語列であろう: 「...道......孤独......最後......愛......長い......」[195]: 272ff. サミュエル・ベケットはジョイスのために外国語の単語をカードに集め、ジョイスの視力が悪化すると、彼の口述からテキストを書き下ろした[196]: 「あなたが曖昧だと感じているこの文章は、言語と絵画と身振りの真髄を抽出したものであり、旧来の無言の必然的な明瞭さを備えている。ここには象形文字の 野蛮な経済がある」[197]。 ジョイスのテクストを「理解」する上で乗り越えなければならない障害に直面した一握りの批評家たちは、読者に対して「意味」だけに注目するのではなく、む しろ言語のリズムと響きに注目することを提案してきた。早くも1929年には、ウジェーヌ・ジョラスが作品の聴覚的、音楽的側面の重要性を強調している。 ジョラスは、『私たちのエクサグミネーション』への寄稿文の中で、次のように書いている: ジョイス氏の『仕掛人』の朗読を聴いたことのある人なら、彼の技法の絶大なリズムの美しさを知っているだろう。それは耳を喜ばせる音楽の流れを持ってお り、自然の作品の有機的な構造を持っており、彼の耳によって形成されたすべての母音と子音を丹念に伝えている」[198]。 他の作品への引用 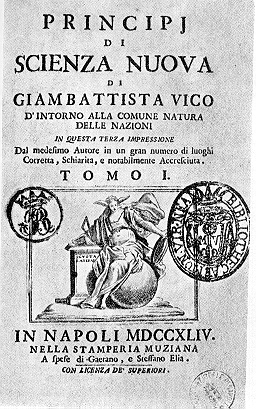 『フィネガンズ・ウェイク』の構造に影響を与えたジャンバッティスタ・ヴィーコの『新しい科学』(La Scienza Nuova)。 フィネガンズ・ウェイク』には、他のテクストへの引用や言及が数多く取り入れられている。パリンダーはこの作品を、「豊富な文学的参照」を含む「間テクス ト性の顕著な例」としている。 最も顕著なものの中には、この本の名前の由来となったアイルランドのバラッド「フィネガンズ・ウェイク」、イタリアの哲学者ジョヴァンニ・バッティスタ・ ヴィーコの『La Scienza Nuova』[200]、エジプトの『死者の書』、シェイクスピアの戯曲[201]、聖書やコーランのような宗教的テキストがある[202]: 166- 167 これらの引用は、出典を直接引用したり参照したりするのではなく、しばしばユーモラスな言葉遊びを通して、歪んだ形でテキストに入り込むのが普通である。 例えば、『ハムレット・プリンス・オブ・デンマーク』は「キャメロット、ディンマルクの王子」[203]となり、『ヘブライ人への手紙』は「ヒブル人への 遠回しの書簡」[204]となる。 本書はヴィーコの『新科学』へのそのような引用から始まる: 「イヴとアダムを過ぎ、海岸のうねりから湾の曲がり角まで、リヴァーランはコモディウス・ヴィカス(commodius vicus)という循環路を経て、ハウズ城とその周辺へと我々を連れ戻してくれる」。 Commodius vicus」とは、ジャンバッティスタ・ヴィーコ(1668-1744)のことで、彼はその著作『La Scienza Nuova(新しい科学)』で循環史観を提唱した。ヴィーコは、世界は3つの時代(神の時代、英雄の時代、人間の時代)の最後の時代の終わりに近づいてい ると主張した。こうした考え方は『フィネガンズ・ウェイク』全体に繰り返し登場し、この本の4部構成に影響を与えている。ヴィーコの名前は『航跡』全体を 通して何度も登場し、「ヴィーコの道は巡り巡って、項が始まるところで出会う」[205]といったように、彼の理論にこの作品が負っている負い目を示して いる。 ジョイスが引用した資料のひとつは、古代エジプトのオシリスの物語であり[206]、呪文と呪文を集めたエジプトの死者の書である。ビショップは「『フィ ネガンズ・ウェイク』における『死者の書』の重要な存在を見過ごすことはできない。 ジョイスは『死者の書』を『フィネガンズ・ウェイク』で用いているが、それは「死者が埋葬される際の復活と再生のための呪文集だからである」[208]。 ジョイスはフランク・バドゲンに『フィネガンズ・ウェイク』についての記事を書くことを提案し、そのタイトルを「ジェイムズ・ジョイスの死者の書」とし た。バドゲンはジョイスの助言に従い、論文「ジョイスの一日一往復の章」を書き、本書におけるエジプト神話への多くの暗示を強調した[209]。 トリスタンとイゼウルトの伝説-アイルランドの王女イゼウルト、コーンウォール人の騎士トリスタン、叔父のマーク王の悲劇的な三角関係-も、特にII.4 において、作品中でしばしば言及されている。ファーニョーリとギレスピーは、「『フィネガンズ・ウェイク』全体を通しての様々なテーマやモチーフ、例えば ハンフリー・チンプデン・アールウィッカー(マーク王の人物)の寝取られや、ショーンがイッシーを誘惑しようとする試みは、『トリスタンとイゾルデ』に直 接関連している......また、アールウィッカーの権威喪失に関連する他のモチーフ、例えば彼の親としての地位を簒奪する勢力もまた、『トリスタンとイ ゾルデ』に基づいている」と論じている[210]。 また、本書はアイルランド神話にも大きく言及しており、HCEはフィオン・マック・カムハイルに、イッシーとALPはグレーンヌに、セム/ショーンはダー モット(ディアマイド)に対応することがある[211]。アイルランドの神話だけでなく、実在の著名な人物も本文中で言及されている。例えば、HCEはし ばしばチャールズ・スチュワート・パーネルと同一視され、セムがこのように父親を攻撃するのは、1882年のフェニックス・パーク殺人事件で、偽の手紙を 使ってパーネルを有罪にしようとした贋作者リチャード・ピゴットの試みを反映している。しかし、『フィネガンズ・ウェイク』における暗示の柔軟性を考える と、HCEはピゴットの性格をも想定している。HCEがカドに自分自身を裏切ったように、ピゴットもまた、偽造を認めるための調査において、「ためらい」 という言葉を「ためらい」と綴ることで自分自身を裏切ったのであり、この綴り間違いは『ウェイク』の中で頻繁に登場する。 フィネガンズ・ウェイク』はまた、宗教的な文章への言及も多い。HCEがI.2章で初めて紹介されるとき、語り手は彼が「初めは」いかに「壮大な老庭師」 であったかを語り、彼をエデンの園のアダムと同一視している。スピンクスはさらに、公園でのHCEの不特定多数の犯罪のように、アダムもまた「庭で犯罪を 犯している」ことを強調することによって、この暗示を強調している[212]: 130 ノルウェーの影響 初期のヴァイキング入植地であったダブリンが『フィネガンズ・ウェイク』の舞台であることから、ジョイスがこの作品にノルウェーの言語的・文化的要素を数 多く取り入れたことは、おそらく驚くべきことではないだろう(例えば、リクスモール語の引用)。II.3章の主な物語のひとつはノルウェー人の仕立屋に関 するもので、bakvandets、Knut Oelsvinger、Bygmester Finnegan(後者はイプセンの『Bygmester Solness』への言及)[213]:210といったノルウェー語が随所で使われている。実際、イプセンの作品のほとんど、彼の登場人物の多く、そして いくつかの引用が『航跡』の中で参照されている。ジョイスは『フィネガンズ・ウェイク』の執筆中、スカンジナビアの言語と文学への言及を挿入しようと考 え、ノルウェー語の教師を5人雇った[214]: 121-122 最初の教師は詩人のオラフ・ブルであった。ジョイスは、ピーター・アンドレアス・ムンクの『Norrøne gude- og heltesagn(北欧の神々と英雄の物語)』など、ノルウェー語の作品を原語で読みたかった。彼は言葉の壁を越えたダジャレや珍しい連想を探していた が、それはブルもよく理解していた。フィネガンズ・ウェイク』にはブルの詩の一節が登場し、ブル自身も「オラフ・ザ・オックスマン」という名で登場する。 百文字の言葉 ウェイクの言語の極端な例として、テキスト中に散在する10個の100文字の単語がある(ただし、10番目の単語は実際には100と1文字である)。最初の百文字単語は本文の最初のページに出てくる。 -嘗ての壁砦のような老パーの転落(バババダルガラグタカムミナロンコンブロントナーロントゥオントゥオントロヴァルホウンズカウントゥホーホーデンセンターヌク!)は、早寝早起きで語り継がれ、後にキリスト教の吟遊詩人を通して生涯語り継がれる[216]。 -そしてダッピーはシャッターを切った(Perkodhuskurnbarguyagokgorlayorgromgrmitghundhurthrumathunaradillifaititillibumullunukkunun!)[217]。 -その(klikklakkklakklopatzklatshabtacreppycrottygraddaghsemmihsammihnouithappluddyappladdypkonpkot!)[218]。 |にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。 |にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。 |にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。 -ウルホードゥルデン・ヴァイムドゴーアードグリングニルルドゥルモルニルフェンリルルクキロクキバウギマンドゥルレールインスルトクリンゲルンラックナロッカー![225]。 これらの10個の単語は、最初の単語がいくつかの言語で雷を意味するいくつかの単語形式の合成語であるという解釈に基づいて、雷鳴、雷鳴、または雷言葉と して知られるようになった[226]。カナダのメディア理論家マーシャル・マクルーハンは(クエンティン・フィオーレとジェローム・アゲルとともに)『地 球村の戦争と平和』の中でこの関連性を明示し、そこで彼は10個の単語を「雷鳴」として同定し、彼自身のテキストでそれらを再現した[227]。 [マクルーハンは自身の著書の目的のために、この10個の言葉を流用し、それを人間のテクノロジーの様々な形態を象徴するものとして解釈し、『航跡』から の他の自由主義的な引用とともに、マクルーハンがテクノロジー、戦争、人間社会について論じるために用いた並列的なレトリックを形成している。マーシャル の息子であるエリック・マクルーハンは父親の雷の解釈を引き継ぎ、『フィネガンズ・ウェイク』における雷の役割(The Role of Thunder in Finnegans Wake)という10個の単語の意味に特化した本を出版した[229]。エリック・マクルーハンにとって、上記の10個の単語の文字数の合計(1001) は意図的に中東の民間伝承の千夜一夜物語に対応しており、これは『ウェイク』が夜の本であるという批判的な解釈を補強している[230]。 -百文字の名前をもう一度、完璧な言語の最後の言葉。しかし、あなたはそれに近づくことができたと、私たちは推測する。どうやって? |
| Literary significance and criticism The value of Finnegans Wake as a work of literature has been a point of contention since the time of its appearance, in serial form, in literary reviews of the 1920s. Initial response, to both its serialised and final published forms, was almost universally negative. Even close friends and family were disapproving of Joyce's seemingly impenetrable text, with Joyce's brother Stanislaus "rebuk[ing] him for writing an incomprehensible night-book",[231] and former friend Oliver Gogarty believing the book to be a joke, pulled by Joyce on the literary community, referring to it as "the most colossal leg pull in literature since Macpherson's Ossian".[232] When Ezra Pound, a former champion of Joyce's and admirer of Joyce's Ulysses, was asked his opinion on the text, he wrote "Nothing so far as I make out, nothing short of divine vision or a new cure for the clap can possibly be worth all the circumambient peripherization."[233] H. G. Wells, in a personal letter to Joyce, argued that "you have turned your back on common men, on their elementary needs and their restricted time and intelligence [...] I ask: who the hell is this Joyce who demands so many waking hours of the few thousands I have still to live for a proper appreciation of his quirks and fancies and flashes of rendering?"[234] Even Joyce's patron Harriett Weaver wrote to him in 1927 to inform him of her misgivings regarding his new work, stating "I am made in such a way that I do not care much for the output from your Wholesale Safety Pun Factory nor for the darknesses and unintelligibilities of your deliberately entangled language system. It seems to me you are wasting your genius."[235] The wider literary community were equally disparaging, with D. H. Lawrence declaring in a letter to Maria and Aldous Huxley, having read sections of the Wake appearing as "Work in Progress" in Transition, "My God, what a clumsy olla putrida James Joyce is! Nothing but old fags and cabbage-stumps of quotations from the Bible and the rest, stewed in the juice of deliberate journalistic dirty-mindedness – what old and hard-worked staleness, masquerading as the all-new!"[101] Vladimir Nabokov, who had also admired Ulysses, described Finnegans Wake as "nothing but a formless and dull mass of phony folklore, a cold pudding of a book, a persistent snore in the next room [...] and only the infrequent snatches of heavenly intonations redeem it from utter insipidity."[101] In response to such criticisms, Transition published essays throughout the late 1920s, defending and explaining Joyce's work. In 1929, these essays (along with a few others written for the occasion) were collected under the title Our Exagmination Round His Factification for Incamination of Work in Progress and published by Shakespeare and Company. This collection featured Samuel Beckett's first commissioned work, the essay "Dante... Bruno. Vico.. Joyce",[236] along with contributions by William Carlos Williams, Stuart Gilbert, Marcel Brion, Eugene Jolas and others. As Margot Norris highlights, the agenda of this first generation of Wake critics and defenders was "to assimilate Joyce's experimental text to an already increasingly established and institutionalized literary avant-garde" and "to foreground Joyce's last work as spearhead of a philosophical avant-garde bent on the revolution of language".[237] Upon its publication in 1939, Finnegans Wake received a series of mixed, but mostly negative reviews. Louise Bogan, writing for Nation, surmised that while "the book's great beauties, its wonderful passages of wit, its variety, its mark of genius and immense learning are undeniable [...], to read the book over a long period of time gives one the impression of watching intemperance become addiction, become debauch" and argued that "Joyce's delight in reducing man's learning, passion, and religion to a hash is also disturbing."[238] Edwin Muir, reviewing in Listener wrote that "as a whole the book is so elusive that there is no judging it; I cannot tell whether it is winding into deeper and deeper worlds of meaning or lapsing into meaningless", although he too acknowledged that "there are occasional flashes of a kind of poetry which is difficult to define but is of unquestioned power."[239] B. Ifor Evans, writing in the Manchester Guardian, similarly argued that, due to its difficulties, the book "does not admit of review", and argued that, perhaps "in twenty years' time, with sufficient study and with the aid of the commentary that will doubtless arise, one might be ready for an attempt to appraise it." Taking a swipe at many of the negative reviews circulating at the time, Evans writes: "The easiest way to deal with the book would be [...] to write off Mr. Joyce's latest volume as the work of a charlatan. But the author of Dubliners, A Portrait of the Artist and Ulysses is not a charlatan, but an artist of very considerable proportions. I prefer to suspend judgement..."[240] In the time since Joyce's death, the book's admirers have struggled against public perception of the work to make exactly this argument for Finnegans Wake. One of the book's early champions was Thornton Wilder, who wrote to Gertrude Stein and Alice Toklas in August 1939, a few months after the book's publication: "One of my absorptions [...] has been James Joyce's new novel, digging out its buried keys and resolving that unbroken chain of erudite puzzles and finally coming on lots of wit, and lots of beautiful things has been my midnight recuperation. A lot of thanks to him".[241] The publication in 1944 of the first in-depth study and analysis of Joyce's final text—A Skeleton Key to Finnegans Wake by mythologist Joseph Campbell and Henry Morton Robinson—tried to prove to a skeptical public that if the hidden key or "Monomyth" could be found, then the book could be read as a novel with characters, plot, and an internal coherence. As a result, from the 1940s to the 1960s critical emphasis moved away from positioning the Wake as a "revolution of the word" and towards readings that stressed its "internal logical coherence", as "the avant-gardism of Finnegans Wake was put on hold [and] deferred while the text was rerouted through the formalistic requirements of an American criticism inspired by New Critical dicta that demanded a poetic intelligibility, a formal logic, of texts."[237] Slowly the book's critical capital began to rise to the point that, in 1957, Northrop Frye described Finnegans Wake as the "chief ironic epic of our time"[242] and Anthony Burgess lauded the book as "a great comic vision, one of the few books of the world that can make us laugh aloud on nearly every page."[15] Concerning the importance of such laughter, Darragh Greene has argued that the Wake through its series of puns, neologisms, compounds, and riddles shows the play of Wittgensteinian language-games, and by laughing at them, the reader learns how language makes the world and is freed from its snares and bewitchment.[243] In 1962, Clive Hart wrote the first major book-length study of the work since Campbell's Skeleton Key, Structure and Motif in "Finnegans Wake" which approached the work from the increasingly influential field of structuralism. However through the 1960s it was to be French post-structuralist theory that was to exert the most influence over readings of Finnegans Wake, refocussing critical attention back to the work's radical linguistic experiments and their philosophical consequences. Jacques Derrida developed his ideas of literary "deconstruction" largely inspired by Finnegans Wake (as detailed in the essay "Two Words for Joyce"), and as a result literary theory—in particular post-structuralism—has embraced Joyce's innovation and ambition in Finnegans Wake.[244] Derrida tells an anecdote about the two books' importance for his own thought; in a bookstore in Tokyo, an American tourist of the most typical variety leaned over my shoulder and sighed: "So many books! What is the definitive one? Is there any?" It was an extremely small book shop, a news agency. I almost replied, "Yes, there are two of them, Ulysses and Finnegans Wake.[245]: 265 The text's influence on other writers has grown since its initial shunning, and contemporary American author Tom Robbins is among the writers working today to have expressed his admiration for Joyce's complex last work: the language in it is incredible. There's so many layers of puns and references to mythology and history. But it's the most realistic novel ever written. Which is exactly why it's so unreadable. He wrote that book the way that the human mind works. An intelligent, inquiring mind. And that's just the way consciousness is. It's not linear. It's just one thing piled on another. And all kinds of cross references. And he just takes that to an extreme. There's never been a book like it and I don't think there ever will be another book like it. And it's absolutely a monumental human achievement. But it's very hard to read.[246] More recently, Finnegans Wake has become an increasingly accepted part of the critical literary canon, although detractors still remain. As an example, John Bishop described the book's legacy as that of "the single most intentionally crafted literary artifact that our culture has produced [...] and, certainly, one of the great monuments of twentieth-century experimental letters."[189] The section of the book to have received the most praise throughout its critical history has been "Anna Livia Plurabelle" (I.8), which Parrinder describes as being "widely recognized as one of the most beautiful prose-poems in English."[104] |
文学的意義と批評 フィネガンズ・ウェイク』の文学作品としての価値は、1920年代の文芸批評に連載形式で掲載されたときから論争の的だった。連載版も最終出版版も、当初 の反応はほとんど否定的だった。親しい友人や家族でさえも、ジョイスの難解に見える文章には否定的で、ジョイスの弟スタニスラウスは「理解不能な夜の本を 書いていると叱責」し[231]、かつての友人オリヴァー・ゴガティはこの本をジョイスが文学界に引っ掛けた冗談だと考え、「マクファーソンの『オシア ン』以来、文学界で最も巨大な足の引っ張り合い」と言及した[232]。 [ジョイスのかつての擁護者であり、ジョイスの『ユリシーズ』を賞賛していたエズラ・パウンドは、この本について意見を求められたとき、「私の知る限り、 神のヴィジョンか、淋病の新しい治療法でもない限り、このような周縁的な周縁化に値するようなものはない」と書いた[233]。ウェルズはジョイスに宛て た私信の中で、「あなたは庶民に背を向け、庶民の初歩的な欲求や限られた時間と知性に背を向けている。 「ジョイスのパトロンであったハリエット・ウィーバーでさえ、1927年にジョイスに手紙を書き、彼の新作に対する不安を伝えた。あなたは天才を無駄にし ているように思える」[235]。 D.H.ローレンスはマリアとオルダス・ハックスリーに宛てた手紙の中で、『トランジション』の「ワーク・イン・プログレス」として掲載された『ウェイ ク』の一部を読んで、「なんてことだ、ジェイムズ・ジョイスはなんて不器用なオッラ・プトリダなんだ!聖書やその他からの引用の古いホモとキャベツの切り 株を、意図的なジャーナリスティックな汚れた心の汁で煮込んだものにすぎない--まったく新しいものの仮面をかぶった、なんという古くて働きづめの陳腐さ だ!」[101] ウラジーミル・ナボコフもまた『ユリシーズ』を賞賛していたが、『フィネガンズ・ウェイク』を「形がなく退屈なインチキ民俗学の塊にすぎず、本としては冷 たいプリンで、隣の部屋ではしつこいいびきをかいている。 このような批判に対して、トランジションは1920年代後半を通じてジョイスの作品を擁護し、説明するエッセイを発表した。1929年、これらのエッセイ は(この機会に書かれた他のいくつかのエッセイとともに)『Our Exagmination Round His Factification for Incamination of Work in Progress』というタイトルで集められ、シェイクスピア・アンド・カンパニー社から出版された。この作品集には、サミュエル・ベケットの最初の依頼 作品であるエッセイ「ダンテ...」が収録されている。ブルーノ ヴィーコ。ジョイス」、ウィリアム・カルロス・ウィリアムズ、スチュアート・ギルバート、マルセル・ブリオン、ユージン・ジョラスなどの寄稿がある。マー ゴット・ノリスが強調しているように、このウェイクの批評家と擁護者の第一世代の課題は「ジョイスの実験的なテクストを、すでに確立され制度化されつつあ る文学的前衛に同化させること」であり、「言語の革命に傾倒する哲学的前衛の先鋒としてジョイスの遺作を前景化すること」であった[237]。 1939年に出版された『フィネガンズ・ウェイク』は、さまざまな評価を受けたが、そのほとんどは否定的なものであった。ネイション』誌に寄稿したルイー ズ・ボーガンは、「この本の偉大な美しさ、機知に富んだ素晴らしい文章、多様性、天才と膨大な学識の印は否定できないが、長期にわたってこの本を読むと、 不摂生が中毒になり、堕落になるのを見ているような印象を受ける」と推察し、「人間の学識、情熱、宗教をハッシュに還元するジョイスの喜びもまた不愉快で ある」と主張した。 「238]エドウィン・ミュアーは『リスナー』誌の批評で、「全体としてこの本はつかみどころがなく、判断することができない。 マンチェスター・ガーディアン』紙に寄稿したB・アイフォー・エヴァンスも同様に、その困難さゆえにこの本は「批評を許さない」と主張し、「20年後、十 分な研究と間違いなく生まれるであろう解説の助けを借りれば、この本を評価する準備ができるかもしれない」と論じた。当時流布していた多くの否定的な批評 を一刀両断して、エヴァンズはこう書いている。「この本を扱う最も簡単な方法は、ジョイス氏の最新作をチャラ男の作品と書き捨てることだろう。しかし、 『ダブリナーズ』、『芸術家の肖像』、『ユリシーズ』の作者は、チャラ男ではなく、かなりの割合の芸術家である。私は判断を保留したい......」 [240]。 ジョイスの死後、『フィネガンズ・ウェイク』を支持する人々は、作品に対する世間の評価と闘いながら、まさに『フィネガンズ・ウェイク』についてこのよう な主張をしてきた。この本の初期の支持者の一人はソーントン・ワイルダーで、彼はこの本の出版から数カ月後の1939年8月にガートルード・スタインとア リス・トクラスに手紙を書いている: 「埋もれていた鍵を掘り出し、切れ目のない博学なパズルの連鎖を解き明かし、最終的にたくさんのウィットとたくさんの美しいものを手に入れることができ た。1944年、神話学者ジョセフ・キャンベルとヘンリー・モートン・ロビンソンによる、ジョイスの最後のテクストに関する初の詳細な研究と分析『フィネ ガンズ・ウェイクの骸骨の鍵』(Skeleton Key to Finnegans Wake)が出版された。その結果、1940年代から1960年代にかけて、批評家たちは『ウェイク』を「言葉の革命」と位置づけることから離れ、「内的 な論理的一貫性」を強調する読解へと重点を移していった。 そして1957年、ノースロップ・フライは『フィネガンズ・ウェイク』を「現代の主な皮肉な叙事詩」[242]と評し、アンソニー・バージェスはこの本を 「偉大なコミカルなヴィジョンであり、ほとんどすべてのページで声をあげて笑わせることのできる、世界でも数少ない本のひとつ」と称賛した。 このような笑いの重要性について、ダラー・グリーンは、一連の駄洒落、新語、複合語、なぞなぞを通して、『ウェイク』はウィトゲンシュタイン的な言語ゲー ムの遊びを示しており、それらを笑うことによって、読者は言語がどのように世界を作っているかを学び、その罠や妖しさから解放されると主張している [243]。 1962年、クライヴ・ハートはキャンベルの『フィネガンズ・ウェイク』における「スケルトン・キー」、「構造とモチーフ」以来となる長編の研究を執筆 し、ますます影響力を増している構造主義の分野から作品にアプローチした。しかし、1960年代を通じて、『フィネガンズ・ウェイク』の読解に最も大きな 影響を及ぼしたのは、フランスのポスト構造主義理論であり、批評家の関心を作品の急進的な言語実験とその哲学的帰結に向け直した。ジャック・デリダは、 『フィネガンズ・ウェイク』に触発されて文学的「脱構築」の思想を発展させ(エッセイ「ジョイスに贈る二つの言葉」で詳述)、その結果、文学理論、特にポ スト構造主義は、『フィネガンズ・ウェイク』におけるジョイスの革新性と野心を受け入れた[244]、 東京の書店で、最も典型的な種類のアメリカ人旅行者が私の肩越しに身を乗り出し、ため息をついた!決定的な本は何ですか?決定的な本は何?そこは極めて小さな書店で、通信社だった。ユリシーズ』と『フィネガンズ・ウェイク』の2冊です」[245]: 265 この文章が他の作家に与えた影響は、最初に敬遠されたときから大きくなっており、現代アメリカの作家トム・ロビンスも、ジョイスの複雑な遺作への賞賛を表明している作家の一人である: この作品の言葉は信じられない。ダジャレや神話や歴史への言及が何層にも重なっている。しかし、これまでに書かれた中で最も現実的な小説だ。それこそが、 この作品が読めない理由なんだ。彼はあの本を、人間の心が働くように書いた。知的で探究心旺盛な。意識とはそういうものだ。直線的ではない。ひとつのこと が積み重なっている。そして、あらゆる種類の相互参照。そして、彼はそれを極限まで追求している。このような本は今までなかったし、これからも出てこない と思う。そして、これは人間として絶対に偉大な業績だ。しかし、読むのはとても難しい。 最近では、『フィネガンズ・ウェイク』は批評的な文学の正典の一部として受け入れられつつあるが、否定的な意見もまだ残っている。その一例として、ジョ ン・ビショップはこの本の遺産を「我々の文化が生み出した最も意図的に作られた唯一の文学的芸術品[...]であり、20世紀の実験的書簡の偉大な記念碑 の一つであることは間違いない」と評している[189]。この本の批評的な歴史を通して最も賞賛を受けてきたのは「アンナ・リヴィア・プララベル」 (I.8)の部分であり、パリンダーはこれを「英語で最も美しい散文詩の一つとして広く認められている」と評している[104]。 |
Publication and translation history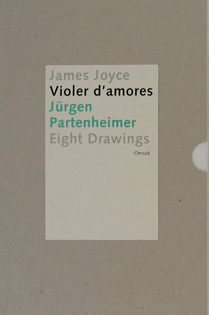 Jürgen Partenheimer's "Violer d'amores", a series of drawings inspired by Joyce's Finnegans Wake Throughout the seventeen years that Joyce wrote the book, Finnegans Wake was published in short excerpts in a number of literary magazines, most prominently in the Parisian literary journals Transatlantic Review and Eugene Jolas's transition. It has been argued that "Finnegans Wake, much more so than Ulysses, was very much directly shaped by the tangled history of its serial publication."[247] In late October 1923 in Ezra Pound's Paris flat, Ford Madox Ford convinced Joyce to contribute some of his new sketches to the Transatlantic Review, a new journal that Ford was editing. The eight-page "Mamalujo" sketch became the first fragment from the book to be published in its own right, in Transatlantic Review 1.4 in April 1924.[248] The sketch appeared under the title "From Work in Progress", a term applied to works by Ernest Hemingway and Tristan Tzara published in the same issue, and the one by which Joyce would refer to his final work until its publication as Finnegans Wake in 1939.[247] The sketch appeared in the final published text, in radically altered form, as chapter 2.4.[249] In 1925 four sketches from the developing work were published. "Here Comes Everybody"[250] was published as "From Work in Progress" in the Contact Collection of Contemporary Writers, edited by Robert McAlmon. "The Letter"[251] was published as "Fragment of an Unpublished Work" in Criterion 3.12 (July 1925), and as "A New Unnamed Work" in Two Worlds 1.1. (September 1925).[249] The first published draft of "Anna Livia Plurabelle"[252] appeared in Le Navire d'Argent 1 in October, and the first published draft of "Shem the Penman"[253] appeared in the Autumn–Winter edition of This Quarter.[249] In 1925-6 Two Worlds began to publish redrafted versions of previously published fragments, starting with "Here Comes Everybody" in December 1925, and then "Anna Livia Plurabelle" (March 1926), "Shem the Penman" (June 1926), and "Mamalujo" (September 1925), all under the title "A New Unnamed Work".[249] Eugene Jolas befriended Joyce in 1927, and as a result serially published revised fragments from Part I in his transition literary journal. This began with the debut of the book's opening chapter, under the title "Opening Pages of a Work in Progress", in April 1927. By November chapters I.2 through I.8 had all been published in the journal, in their correct sequence, under the title "Continuation of a Work in Progress".[254] From 1928 Part's II and III slowly began to emerge in transition, with a brief excerpt of II.2 ("The Triangle") published in February 1928, and Part III's four chapters between March 1928 and November 1929.[254] At this point, Joyce started publishing individual chapters from Work in Progress. In 1929, Harry and Caresse Crosby, owners of the Black Sun Press, contacted James Joyce through bookstore owner Sylvia Beach and arranged to print three short fables about the novel's three children Shem, Shaun and Issy that had already appeared in translation. These were "The Mookse and the Gripes",[255] "The Triangle",[256] and "The Ondt and the Gracehoper".[254][257] The Black Sun Press named the new book Tales Told of Shem and Shaun for which they paid Joyce US$2,000 for 600 copies, unusually good pay for Joyce at that time.[258]: 286 Their printer Roger Lescaret erred when setting the type, leaving the final page with only two lines. Rather than reset the entire book, he suggested to the Crosby's that they ask Joyce to write an additional eight lines to fill in the remainder of the page. Caresse refused, insisting that a literary master would never alter his work to fix a printer's error. Lescaret appealed directly to Joyce, who promptly wrote the eight lines requested.[259] The first 100 copies of Joyce's book were printed on Japanese vellum and signed by the author. It was hand-set in Caslon type and included an abstract portrait of Joyce by Constantin Brâncuși,[260] a pioneer of modernist abstract sculpture. Brâncuși's drawings of Joyce became among the most popular images of him.[261] Faber and Faber published book editions of "Anna Livia Plurabelle" (1930), and "Haveth Childers Everywhere" (1931), HCE's long defence of his life which would eventually close chapter III.3.[262][263] A year later they published Two Tales of Shem and Shaun, which dropped "The Triangle" from the previous Black Sun Press edition. Part II was published serially in transition between February 1933 and May 1938, and a final individual book publication, Storiella as She Is Syung, was published by Corvinus Press in 1937, made up of sections from what would become chapter II.2.[263] By 1938 virtually all of Finnegans Wake was in print in the transition serialisation and in the booklets, with the exception of Part IV. Joyce continued to revise all previously published sections until Finnegans Wake's final published form, resulting in the text existing in a number of different forms, to the point that critics can speak of Finnegans Wake being a different entity to Work in Progress. The book was finally published simultaneously by Faber and Faber in London and by Viking Press in New York on 4 May 1939, after seventeen years of composition. In March 2010, a new "critically emended edition" was published in a limited edition of 1,000 copies by Houyhnhnm Press[264] in conjunction with Penguin. This edition was published in a trade edition in 2012.[265] Edited by Danis Rose and John O'Hanlon, is the "summation of thirty years' intense engagement by textual scholars Danis Rose and John O’Hanlon verifying, codifying, collating and clarifying the 20,000 pages of notes, drafts, typescripts and proofs." In the publisher's words the new edition "incorporates some 9,000 minor yet crucial corrections and amendments, covering punctuation marks, font choice, spacing, misspellings, misplaced phrases and ruptured syntax." According to the publisher, "Although individually minor, these changes are nonetheless crucial in that they facilitate a smooth reading of the book’s allusive density and essential fabric." Despite its linguistic complexity, Finnegans Wake has been translated into French,[266] German,[267] Greek,[268] Japanese,[269] Korean,[270] Latin,[271] Polish,[272] Spanish (by M. Zabaloy),[273] Dutch,[274] Portuguese,[275] Turkish,[276][277] and Swedish (by B. Falk).[278] Well-advanced translations in progress include Chinese,[279] Italian,[280] and Russian.[281] |
出版と翻訳の歴史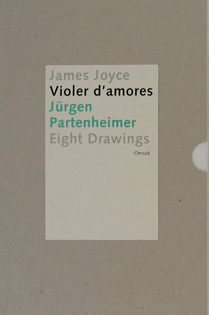 ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』にインスパイアされたユルゲン・パルテンハイマー(Jürgen Partenheimer)の連作『Violer d'amores』。 ジョイスが『フィネガンズ・ウェイク』を執筆した17年間を通じて、『フィネガンズ・ウェイク』は多くの文芸誌に短い抜粋で掲載された。特にパリの文芸誌 『トランスアトランティック・レヴュー』や『ユージン・ジョラスの変遷』に掲載された。1923年10月下旬、フォード・マドックス・フォードはエズラ・ パウンドのパリのアパートで、フォードが編集していた新しい雑誌『トランスアトランティック・レヴュー』に新しいスケッチを寄稿するようジョイスを説得し た。 8ページに及ぶ「ママルーヨ」のスケッチは、1924年4月の『トランスアトランティック・レヴュー』1.4に掲載され、『ママルーヨ』から独立して出版 された最初の断片となった。 [248]このスケッチは「進行中の作品から」というタイトルで掲載されたが、この言葉は同じ号に掲載されたアーネスト・ヘミングウェイやトリスタン・ ツァラの作品に適用されたものであり、ジョイスは1939年に『フィネガンズ・ウェイク』として出版されるまで、このタイトルで最終作を呼ぶことになる [247]。 1925年、発展途上の作品から4つのスケッチが出版された。「Here Comes Everybody」[250] は、ロバート・マカルモン編集の『現代作家接触集』に「進行中の作品から」として掲載された。手紙「[251]は『クライテリオン』3.12号(1925 年7月)に「未発表作品の断片」として、『トゥー・ワールズ』1.1号(1925年9月)に「無名の新作」として掲載された[249]。」Anna Livia Plurabelle「[252]の初出草稿は10月の『ル・ナヴィール・ダルジャン』1号に、」Shem the Penman"[253]の初出草稿は『This Quarter』秋冬号に掲載された[249]。 1925年から6年にかけて『二つの世界』は、1925年12月の 「Here Comes Everybody 」を皮切りに、「Anna Livia Plurabelle」(1926年3月)、「Shem the Penman」(1926年6月)、「Mamalujo」(1925年9月)など、以前に発表された断片を再編集したものを発表し始めた。 ユージン・ジョラスは1927年にジョイスと親しくなり、その結果、彼の移行期の文芸誌に第一部から改訂された断片を連載した。1927年4月、「進行中 の作品の冒頭」というタイトルで、この本の冒頭の章が発表された。1928年から第Ⅱ部と第Ⅲ部が徐々に移行期に現れ始め、1928年2月に第Ⅱ部第2章 (「三角形」)の短い抜粋が発表され、1928年3月から1929年11月にかけて第Ⅲ部の4章が発表された[254]。 この時点で、ジョイスは『進行中の仕事』から個々の章を出版し始めた。1929年、ブラック・サン・プレスのオーナーであるハリー・クロスビーとカレス・ クロスビーは、書店主のシルヴィア・ビーチを通じてジェイムズ・ジョイスに連絡を取り、すでに翻訳版が出版されていた小説の3人の子供セム、ショーン、 イッシーについての3つの短い寓話を印刷するよう手配した。ブラック・サン・プレスはこの新刊を『Tales Told of Shem and Shaun』と名付け、ジョイスに600部2,000米ドルを支払う。彼は本全体を作り直すのではなく、残りのページを埋めるためにジョイスに追加の8行 を書いてもらうことをクロスビー夫妻に提案した。カレスは、文学の巨匠が印刷所のミスを修正するために自分の作品を改変することはないと主張し、これを拒 否した。レスカレはジョイスに直訴し、ジョイスは要求された8行を即座に書いた[259]。ジョイスの本の最初の100部は日本のベラムに印刷され、著者 の署名があった。この本はカスロン活字で手組みされ、モダニズム抽象彫刻の先駆者であるコンスタンチン・ブラニュシによるジョイスの抽象的な肖像画が添え られていた[260]。ブランチュイのジョイスの絵は、ジョイスの最も人気のあるイメージのひとつとなった[261]。 フェイバーとフェイバーは、「Anna Livia Plurabelle」 (1930)と 「Haveth Childers Everywhere」 (1931)の書籍版を出版する。第II部は1933年2月から1938年5月にかけて変遷しながら連続出版され、1937年にはコルヴィナス・プレスか ら最終的な単行本『彼女が詠むストリエラ』が出版され、第II.2章となる部分から構成された[263]。 1938年までには、『フィネガンズ・ウェイク』のほぼすべてが、第4部を除いて、移行期の連載と小冊子で印刷された。ジョイスは『フィネガンズ・ウェイ ク』の最終的な出版形態に至るまで、以前に出版されたすべての部分を改訂し続け、その結果、テキストは多くの異なる形態で存在することになり、批評家たち は『フィネガンズ・ウェイク』を『仕掛人』とは別の存在であると語ることができるほどであった。フィネガンズ・ウェイク』は、構想から17年を経て、 1939年5月4日、ロンドンのFaber and FaberとニューヨークのViking Pressから同時に出版された。 2010年3月、ペンギンと共同でHouyhnhnm Press社[264]から1,000部限定で新しい「批判的に編集された版」が出版された。ダニス・ローズとジョン・オハンロンが編集したこの版は、 「テキスト研究者であるダニス・ローズとジョン・オハンロンが、2万ページに及ぶノート、草稿、活字稿、校正刷りを検証し、体系化し、照合し、明確化し た、30年に及ぶ集中的な取り組みの集大成」である[265]。出版社の言葉を借りれば、新版は 「句読点、フォントの選択、スペルミス、言い間違い、構文の崩れなどを網羅し、約9,000の細かい、しかし重要な修正と訂正が盛り込まれている」。出版 社によれば、「ひとつひとつは些細なことではあるが、それでもこれらの変更は、この本のとらえどころのない密度と本質的な構造をスムーズに読みやすくする という点で、極めて重要である」。 その言語的な複雑さにもかかわらず、『フィネガンズ・ウェイク』はフランス語、[266] ドイツ語、[267] ギリシャ語、[268] 日本語、[269] 韓国語、[270] ラテン語、[271] ポーランド語、[272] スペイン語(M. 278]現在進行中の翻訳には、中国語、[279]イタリア語、[280]ロシア語がある[281]。 |
| Dramatic and musical adaptions Thornton Wilder's play The Skin of Our Teeth (1942) uses many devices from Finnegans Wake, such as a family that represents the totality of humanity, cyclical storytelling, and copious Biblical allusions.[282] A musical play, The Coach with the Six Insides by Jean Erdman, based on the character Anna Livia Plurabelle,[283] was performed in New York in 1962.[284][285] Parts of the book were adapted for the stage by Mary Manning as Passages from Finnegans Wake, (1965) which was in turn used as the basis for a film of the novel by Mary Ellen Bute.[286] In recent years Olwen Fouéré's solo performance play riverrun, based on the theme of rivers in Finnegans Wake, has received critical accolades around the world.[287][288][289] Adam Harvey has also adapted Finnegans Wake for the stage.[290] Martin Pearlman's three-act Finnegan's Grand Operoar is for speakers with an instrumental ensemble.[291][292] A version adapted by Barbara Vann with music by Chris McGlumphy was produced by The Medicine Show Theater in April 2005.[293] John Cage's The Wonderful Widow of Eighteen Springs became the first musical setting of words from Finnegans Wake, approved by the Joyce Estate in 1942. He used text taken from page 558.[294] Roaratorio: an Irish circus on Finnegans Wake (1979) combines a collage of sounds mentioned in Finnegans Wake - including farts, guns and thunderclaps - with Irish jigs and Cage reading his text Writing for the Second Time through Finnegans Wake. Cage also set Nowth upon Nacht to music in 1984.[295] In 1947 Samuel Barber set an excerpt from Finnegans Wake as the song Nuvoletta for soprano and piano. He also composed a piece for orchestra in 1971 entitled Fadograph of a Yestern Scene, the title a quote from the first part of the novel. Luciano Berio set much Joyce, and was an admirer of Finnegans Wake,[296] but only one of his pieces, A-Ronne (1975) directly refers to it (heard in the vocal fragment “run,” derived from “riverrun”). Influenced by Berio, British composer Roger Marsh set selected passages concerned with the character Anna Livia Plurabelle in his 1977 Not a soul but ourselves for amplified voices using extended vocal techniques.[297] Marsh went on to direct the unabridged (29 hour) audiobook of Finnegans Wake issued by Naxos in 2021.[298] The Japanese composer Toru Takemitsu used several quotes from the novel in his music: its first word for his composition for piano and orchestra, riverrun (1984). His 1980 piano concerto is called Far calls. Coming, far! taken from the last page of Finnegans Wake. Similarly, he entitled his 1981 string quartet A Way a Lone, taken from the last sentence of the work.[299]: 521 Other composers from the experimental classical tradition with settings include Fred Lerdahl (Wake, 1967-8), and Tod Machover (Soft Morning, City!, 1980). André Hodeir composed a jazz cantata on Anna Plurabelle (1966). Scottish group The Wake's second album is called Here Comes Everybody (1985). Phil Minton set passages of the Wake to music, on his 1998 album Mouthfull of Ecstasy.[300] In 2015 Waywords and Meansigns: Recreating Finnegans Wake [in its whole wholume] set Finnegans Wake to music unabridged, featuring an international group of musicians and Joyce enthusiasts.[301] In 2000, Danish visual artists Michael Kvium and Christian Lemmerz created a multimedia project called "the Wake", an eight-hour-long silent movie based on the book.[302] Between 2014–2016 in Poland, many adaptations of Finnegans Wake saw completion, including publication of the text as a musical score,[303] a short film Finnegans Wake//Finneganów tren,[304] a multimedia adaptation First We Feel Then We Fall[305] and K. Bartnicki's intersemiotic translations into sound[306] and verbovisual.[307] In October 2020, Austrian illustrator Nicolas Mahler presented a small-format (ISO A6) 24-page comic adaptation of Finnegans Wake with reference to comic figures Mutt and Jeff.[308] |
ドラマ化とミュージカル化 ソーントン・ワイルダーの戯曲『The Skin of Our Teeth』(1942年)には、『フィネガンズ・ウェイク』の多くの仕掛けが用いられている。 [本書の一部はメアリー・マニングによって舞台化され、『フィネガンズ・ウェイクからの手紙』(1965年)として上演された。 近年では、『フィネガンズ・ウェイク』に登場する川をテーマにしたオルウェン・フエレのソロ・パフォーマンス劇『riverrun』が世界中で批評家の称 賛を浴びている[287][288][289]。 [290]マーティン・パールマンの3幕からなる『フィネガンズ・グランド・オペラ』は、器楽アンサンブルを伴うスピーカーのための作品である[291] [292]。 バーバラ・ヴァンが脚色し、クリス・マクグランフィが音楽を担当したバージョンは、2005年4月にメディスン・ショー・シアターによって上演された [293]。 ジョン・ケージの『The Wonderful Widow of Eighteen Springs』は、『フィネガンズ・ウェイク』の言葉を音楽化した最初の作品となり、1942年にジョイス・エステートによって承認された。 Roaratorio: an Irish circus on Finnegans Wake』(1979年)は、フィネガンズ・ウェイクで言及された音(屁、銃、雷鳴など)のコラージュとアイルランドのジグ、そしてケージがフィネガン ズ・ウェイクを通して自身のテキスト『Writing for the Second Time』を朗読している。1947年、サミュエル・バーバーは『フィネガンズ・ウェイク』からの抜粋をソプラノとピアノのための歌曲 『Nuvoletta』として作曲。彼はまた、1971年にオーケストラのために『Fadograph of a Yestern Scene』というタイトルの曲を作曲している。 ルチアーノ・ベリオはジョイスの作品を多く作曲し、『フィネガンズ・ウェイク』の崇拝者であった[296]が、彼の作品の中で『フィネガンズ・ウェイク』 に直接言及しているのは『A-Ronne』(1975)の1曲のみである(ヴォーカル・フラグメントの 「run 」は 「riverrun 」に由来する)。ベリオの影響を受けたイギリスの作曲家ロジャー・マーシュは、1977年に発表した《Not a soul but ourselves》の中で登場人物のアンナ・リヴィア・プルラベルに関係する選択されたパッセージを、拡張された声楽技法を用いた増幅された声のために 作曲した[297]。 日本の作曲家である武満徹は、ピアノとオーケストラのための作品『riverrun』(1984年)の冒頭で、この小説からいくつかの引用を引用してい る。彼の1980年のピアノ協奏曲のタイトルは「Far calls」。フィネガンズ・ウェイク』の最後のページからの引用である。同様に、1981年の弦楽四重奏曲のタイトルは『A Way a Lone』で、この作品の最後の一文から取られている[299]: 521 他に、実験的クラシックの伝統に基づく作曲家としては、フレッド・レルダール(『ウェイク』、1967-8年)、トッド・マコーヴァー(『柔らかな朝、街 へ!』、1980年)などがいる。 アンドレ・ホデイルはジャズ・カンタータをAnna Plurabelle(1966年)で作曲している。スコットランドのグループ、ザ・ウェイクのセカンド・アルバムは『Here Comes Everybody』(1985年)。フィル・ミントンは1998年のアルバム『Mouthfull of Ecstasy』でウェイクの一節を音楽にした[300]: Recreating Finnegans Wake [in its whole volume]』は、国際的な音楽家とジョイスの熱狂的なファンをフィーチャーし、フィネガンズ・ウェイクを無修正で音楽化した[301]。 2000年には、デンマークのヴィジュアル・アーティストであるマイケル・クヴィウムとクリスチャン・レンメルツが、この本を題材にした8時間の無声映画 「the Wake」と呼ばれるマルチメディア・プロジェクトを制作した[302]。 ポーランドでは2014年から2016年にかけて、楽譜としてのテキストの出版[303]、短編映画『Finnegans Wake//Finneganów tren』[304]、マルチメディア化された『First We Feel Then We Fall』[305]、そしてK. 307]。2020年10月、オーストリアのイラストレーターであるニコラ・マーラーは、コミックの人物であるMuttとJeffを参照しながら、『フィ ネガンズ・ウェイク』を小型フォーマット(ISO A6)24ページのコミックに翻案した作品を発表した[308]。 |
| Cultural impact Finnegans Wake is a difficult text, and Joyce did not aim it at the general reader.[309] Nevertheless, certain aspects of the work have made an impact on popular culture beyond the awareness of it being difficult.[310] Similarly, the comparative mythology term monomyth, as described by Joseph Campbell in his book The Hero with a Thousand Faces,[311] was taken from a passage in Finnegans Wake.[312] The work of Marshall McLuhan was inspired by James Joyce; his collage book War and Peace in the Global Village has numerous references to Finnegans Wake.[313] The novel was also the source of the title of Clay Shirky's book Here Comes Everybody.[314] Esther Greenwood, Sylvia Plath's protagonist in The Bell Jar, is writing her college thesis on the "twin images" in Finnegans Wake, although she never manages to finish either the book or her thesis.[315] According to James Gourley, Joyce's book features in Plath's "as an alienating canonical authority".[316] "Finnegan's Wake" is a traditional Irish song that has been recorded in more recent years by bands including the Dubliners and Dropkick Murphys. It predates Finnegans Wake and inspired Joyce's title. Finnegans Wake provided the name for the quark, one of the elementary particles proposed by physicist Murray Gell-Mann.[317] Specifically Gell-Mann's coinage derives Joyce's phrase in which the outdated English word meaning to croak[318] is intoned by a choir of birds mocking King Mark of Cornwall in the legend of Tristan and Iseult.[319] – Three quarks for Muster Mark! Sure he hasn't got much of a bark And sure any he has it's all beside the mark. |
文化的影響 フィネガンズ・ウェイク』は難解なテキストであり、ジョイスは一般読者を対象としていなかった[309]。にもかかわらず、この作品のある側面は、難解であるという認識を超えて大衆文化に影響を与えた[310]。 同様に、ジョセフ・キャンベルがその著書『千の顔を持つ英雄』の中で説明している比較神話学用語のモノミスは、『フィネガンズ・ウェイク』の一節から引用 されている[312]。 マーシャル・マクルーハンの仕事はジェイムズ・ジョイスに触発されたものであり、彼のコラージュ本『地球村の戦争と平和』には『フィネガンズ・ウェイク』 への多くの言及がある[313]。この小説はまた、クレイ・シャーキーの著書『Here Comes Everybody』のタイトルの由来でもある[314]。 ベル・ジャー』のシルヴィア・プラスの主人公であるエスター・グリーンウッドは、『フィネガンズ・ウェイク』における「双子のイメージ」について大学の論 文を書いているが、彼女は本も論文も完成させることができなかった[315]。 ジェイムズ・ゴーリーによれば、ジョイスの本はプラースの中で「疎外的な正典的権威として」取り上げられている[316]。 「フィネガンズ・ウェイク」はアイルランドの伝統的な歌であり、近年ではダブリナーズやドロップキック・マーフィーズなどのバンドによって録音されている。フィネガンズ・ウェイク』よりも古く、ジョイスのタイトルに影響を与えた。 フィネガンズ・ウェイク』は、物理学者マレー・ゲルマンによって提唱された素粒子のひとつであるクォークの名前を提供した[317]。特にゲルマンの造語 は、トリスタンとイゼウルトの伝説の中で、コーンウォールのマーク王をあざ笑う鳥の合唱団によって、しゃがれ声[318]を意味する時代遅れの英語がイン トネーションされるジョイスのフレーズに由来している[319]。 - マスタ-・マークに3つのクオーク! 確かに彼はあまり吠えないが そして確かに彼が持っているものは、すべて的外れなものだ。 |
| Altus Prosator |
アルタス・プロセイター |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Finnegans_Wake |
|
| Altus Prosator On a much more intelligible level, the sixth-century abecedarian hymn Altus prosator shows many of the features of Hiberno-Latin: the word prosator, the "first sower" meaning creator, refers to God using an unusual neologism.[1] The text of the poem also contains the word iduma, meaning "hands;" this is probably from Hebrew ידים (yadaim, "two hands"). The poem is also an extended alphabetical acrostic, another example of the wordplay typical of Hiberno-Latin. Irish (but not Continental) manuscripts traditionally attributed the poem to the sixth-century Irish mystic Saint Columba, but this attribution is doubtful.[2] Marking with an asterisk (*) words that are learned, neologisms, unusually spelled, or unusual in the context they stand, the poem begins: Altus *prosator, *vetustus dierum et ingenitus erat absque origine primordii et *crepidine est et erit in sæcula sæculorum infinita; cui est unigenitus Xristus et sanctus spiritus coæternus in gloria deitatis perpetua. Non tres deos *depropimus sed unum Deum dicimus, salva fide in personis tribus gloriosissimis. High creator, Ancient of Days, and unbegotten, who was without origin at the beginning and foundation, who is and shall be in infinite ages of ages; to whom was only begotten Christ, and the Holy Ghost, co-eternal in the everlasting glory of Godhood. We do not propose three gods, but we speak of one God, saving faith in three most glorious Persons. https://en.wikipedia.org/wiki/Hiberno-Latin#Altus_Prosator |
アルタス・プロセイター より理解しやすいレベルでは、6世紀のアベケダ派の賛美歌Altus prosatorは、ヒベルノ=ラテン語の特徴の多くを示している。この詩のテキストには、「手」を意味するidumaという単語も含まれており、これは おそらくヘブライ語のידים(yadaim、「両手」)に由来する。これはヘブライ語のידים(yadaim、「両手」)に由来すると思われる。この 詩はまた、ヒベルノ・ラテン語に典型的な言葉遊びのもう一つの例である、アルファベットのアクロスティックを拡張したものでもある。アイルランド語(大陸 語ではない)の写本では伝統的に、この詩は6世紀のアイルランドの神秘主義者聖コロンバの作とされているが、この説には疑問がある[2]。 学習語、新造語、珍しい綴りの単語、文脈上珍しい単語をアスタリスク(*)で示すと、詩はこう始まる: Altus *prosator, *vetustus dierum et ingenitus erat absque origine primordii et *crepidine その起源は sæculorum infinita; これは一元的なものである。 Xristus et sanctus spiritus 栄光の中で 永遠なる神である。 3つの神々ではなく を唱えよ、 人において敬い 栄光の部族。 いと高き創造主、いにしえの 日の創造主、生れ出づる者、 起源なき方 始まりと礎において 無限に存在し 世々限りなく キリストと聖霊は キリストと聖霊 神性の永遠の栄光において 神性の永遠の栄光において、共に永遠であった。 私たちは3つの神々を提案するのではない、 唯一の神について語るのである、 三人の 最も栄光に満ちたお方である。 https://en.wikipedia.org/wiki/Hiberno-Latin#Altus_Prosator |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆