
ニーチェ『道徳の系譜』ノート
On the Genealogy of Morality; Zur
Genealogie der Moral, 1887

☆ 『道徳の系譜について:ひとつの極論』は、フリードリヒ・ニーチェによる1887年の哲学書である。 序文と3つの「論考」から成るこの1887年の著作は、ニーチェの著作の中で最も影響力のあるもののひとつである。ニーチェはここで、他の著作のようにア フォリズム(格言)を提示するのではなく、徹底した科学的アプローチによる、より長く体系的なテキストを提示した。古典的な道徳哲学者とは異なり、ニー チェは道徳を導き出したり正当化したりするのではなく、ある道徳的価値観の歴史的発展と心理的前提条件をたどることを望んだ。それゆえ彼は、人がどのよう に行動すべきかを問うのではなく、なぜ人(個人または集団)が、自分はある行動をとるべきだと信じるのか、あるいは他人にある行動をとらせたいと思うのか を問うのである。 第一論文に登場する「奴隷道徳」と「主人道徳」の対比は、少なくともキャッチフレーズの形ではよく知られている。ニーチェが禁欲的な理想を詳細な批判にさ らした第三の論考は、それ以降の著作を理解する上で基本となるものである。 系図』はジークムント・フロイトやミシェル・フーコーなど多くの思想家に影響を与えた。この著作は、特に20世紀後半のフランスにおけるニーチェ受容にお いて、多くの議論を呼んだ。
| Inhalt Die Genealogie der Moral besteht aus einer Vorrede und drei Abhandlungen, von denen die dritte die längste ist. Vorrede In den ersten sieben Abschnitten der Vorrede erläutert Nietzsche die Motivation seiner Arbeit: „Sprechen wir sie aus, diese neue Forderung: wir haben eine Kritik der moralischen Werthe nöthig, der Werth dieser Werthe ist selbst erst einmal in Frage zu stellen – und dazu thut eine Kenntniss der Bedingungen und Umstände noth, aus denen sie gewachsen, unter denen sie sich entwickelt und verschoben haben (Moral als Folge, als Symptom, als Maske, als Tartüfferie, als Krankheit, als Missverständniss; aber auch Moral als Ursache, als Heilmittel, als Stimulans, als Hemmung, als Gift), wie eine solche Kenntniss weder bis jetzt da war, noch auch nur begehrt worden ist.“ – Vorrede, Abschnitt 6:KSA 5, S. 253 Er verweist dazu – wie in der ganzen Schrift noch häufiger – auf einige seiner früheren Werke und kritisiert Paul Rées Der Ursprung der moralischen Empfindungen (1877). Rée und seinesgleichen seien viel zu sehr voreingenommen für moderne, utilitaristische und altruistische Moralvorstellungen, um die Genealogie der moralischen Werte zu verstehen. Im achten und letzten Abschnitt der Vorrede geht Nietzsche auf das Problem der Verständlichkeit seiner Schriften ein und fordert ein genaues Lesen, eine „Kunst der Auslegung“. Als Beispiel habe er der dritten Abhandlung einen Aphorismus vorangestellt, die Abhandlung selbst sei dessen langsame, systematische Auslegung. |
内容 『道徳の系譜』は、序文と3つの論文で構成されており、そのうちの3番目の論文が最も長い。 序文 序文の最初の7つの段落で、ニーチェは自分の労働の動機について次のように説明している。 「この新しい要求を、はっきりと言おう。道徳的価値観に対する批判が必要だ。まず、その価値観の価値そのものを疑問視すべきだ。そのためには、その価値観 が生まれた背景や状況、それが発展し変化してきた経緯(道徳は結果であり、症状であり、仮面であり、偽善であり、病気であり、誤解である)を理解する必要 がある。しかし、道徳は原因、治療薬、刺激剤、抑制剤、毒でもある)、そのような知識はこれまで存在しなかっただけでなく、求められたこともなかった。」 – 前書き、第 6 節:KSA 5、253 ページ 彼は、この文章全体を通して頻繁にそうしているように、自身の以前の著作のいくつかを引用し、ポール・レーの『道徳感情の起源』(1877年)を批判して いる。レーやその同類は、現代的な功利主義的、利他主義的な道徳観に偏りすぎており、道徳的価値観の系譜を理解することはできないと彼は述べている。 序文の第 8 節、つまり最後の節で、ニーチェは自分の著作の理解しやすさの問題について触れ、正確な読解、つまり「解釈の芸術」を求めている。例として、彼は第 3 論文の前に格言を置いたが、論文自体は、その格言をゆっくりと体系的に解釈したものだとしている。 |
| Erste Abhandlung: »Gut und Böse«, »Gut und Schlecht«. Hier wird der von Nietzsche seit Menschliches, Allzumenschliches (Nr. 45) angedeutete Unterschied zwischen einer Herren- und Sklavenmoral erläutert. Diesen unterschiedlichen Arten der Moral entspricht jeweils ein Gegensatzpaar: Privilegierte Gesellschaftsschichten haben nach Nietzsche ihre eigenen Handlungen als „gut“ definiert; „gut“ in der Bedeutung von „edel“, „vornehm“, „mächtig“, „glücklich“ etc. Dagegen schätzen diese „Herren“ die Handlungen der anderen, niedrigeren Menschen als „schlecht“ im Sinne von „schlicht“, „(all)gemein“, „unvornehm“ ab, ohne ihnen daraus einen Vorwurf zu machen. Umgekehrt geht die Wertung der Unterprivilegierten, Niedrigen, Armen, Kranken, der „Sklaven“ vor: Ihre Empfindung beruht auf Ressentiment, sie schätzen zuerst die anderen als die „Bösen“, den „bösen Feind“ ab. Sich selbst definieren sie erst danach als die „Guten“ eben im Gegensatz zu jenen Bösen – das heißt, sie selbst sind „gut“, weil sie nicht „böse“ sind, ihr Begriff von „Gut“ ist reaktiv statt aktiv wie bei den Vornehmen und beruht auf einer Wertumkehr. Die zweite Art der Wertung sieht Nietzsche im Judentum und Christentum, der ersten ordnet er das römische Reich, aber auch noch die Renaissance und Napoléon zu. Freilich würde der Gegensatz zwischen diesen Arten der Moral immer noch in einzelnen, zwiespältigen Menschen ausgekämpft; in den höheren und geistigeren Naturen seien heute beide Arten der Wertschätzung vorhanden und im Kampf miteinander. Im ganzen sei allerdings die Sklavenmoral siegreich gewesen. Nietzsche selbst drückt mehrfach – wenn auch nicht ohne Vorbehalte und Differenzierungen – seine deutlich stärkere Sympathie für die „vornehme“ Weltsicht aus und scheint zu hoffen, dass sie dank seiner Philosophie den Kampf gegen die „pöbelhafte“ Moral wieder aufnehmen kann. |
最初の論文:「善と悪」、「良と悪」。 ここでは、ニーチェが『人間的な、あまりにも人間的な』(第 45 号)で示唆した、主人道徳と奴隷道徳の違いについて解説している。これらの異なる道徳観には、それぞれ対照的な 2 つの概念がある。 ニーチェによれば、特権階級は自分たちの行動を「善」と定義している。「善良」とは「高貴」、「上品」、「権力」、「幸福」などの意味だ。一方、これらの 「主人」たちは、他の、より低い立場の人々の行動を「悪」と評価する。その意味は「質素」、「(一般的な)平凡」、「下品」であり、彼らを非難するもので はない。 逆に、恵まれない人々、低層階級、貧しい人々、病気の人々、「奴隷」たちの評価は、まず彼らの感情が恨みに基づいており、彼らはまず他の人々を「悪者」、 「邪悪な敵」と評価する。彼らは、その悪者たちとは対照的に、自分たちを「善」と定義する。つまり、彼らは「悪」ではないから「善」であり、彼らの「善」 の概念は、高貴な人々のような能動的なものではなく、受動的なものであり、価値観の逆転に基づいている。 ニーチェは、2番目のタイプの価値観をユダヤ教とキリスト教に見ており、1番目のタイプにはローマ帝国だけでなく、ルネサンスやナポレオンも分類してい る。もちろん、これらのタイプの道徳の対立は、依然として個々の人間の葛藤の中で争われている。今日、より高次で精神的な性質を持つ人間には、両方のタイ プの価値観が存在し、それらが争い合っている。しかし、全体としては、奴隷的道徳が勝利を収めた。ニーチェ自身は、留保や差別化はあるものの、何度も「高 貴な」世界観に対する強い共感を表明し、自分の哲学のおかげで「下層階級的な」道徳との戦いを再開できることを望んでいるようだ。 |
| Zweite Abhandlung: »Schuld«, »schlechtes Gewissen« und Verwandtes. Hierin untersucht Nietzsche die Herkunft der Idee, Menschen könnten „Verantwortung“ für etwas übernehmen, und das im Tierreich außergewöhnliche menschliche Gedächtnis überhaupt. Den moralischen Begriff der „Schuld“ sieht er im materiellen Begriff der „Schulden“ gegen einen Gläubiger begründet. Er deutet die vielfältigen vorgeblichen und realen Zwecke an, die die Strafe in der Geschichte diverser Kulturen gespielt habe. Sie sei, wie alle Tatbestände, unter neuen Machtkonstellationen immer neuen Interpretationen unterworfen gewesen. Das schlechte Gewissen hat nach Nietzsche seinen Ursprung in der Zivilisierung des Menschen, der unter dem Druck, in einer organisierten Gesellschaft zu leben, seinen aggressiven Trieb nach innen und gegen sich selbst lenke. Der Abschnitt 12 dieser Abhandlung sticht etwas heraus, da Nietzsche hier vergleichsweise ausführlich auf seine Lehre des „Willens zur Macht“ eingeht. |
第二論文:「罪悪感」、「良心の呵責」および関連事項。 ここでニーチェは、人間が何かに対して「責任」を引き受けることができるという考えの起源、そして動物界では非常に珍しい人間の記憶そのものを考察してい る。彼は、道徳的な概念である「罪悪感」は、債権者に対する物質的な概念である「負債」に由来すると考えている。彼は、さまざまな文化の歴史において、罰 が果たしてきた、表向きおよび実際の多様な目的について言及している。罰は、他のあらゆる事実と同様、新しい権力構造の下では、常に新しい解釈の対象と なってきた。ニーチェによれば、良心の呵責は、組織化された社会で生活するという圧力のもと、人間がその攻撃的な衝動を内面および自分自身に向けさせる、 人間の文明化に起源がある。 この論文の第 12 節は、ニーチェが「権力への意志」の理論について比較的詳しく述べている点で、特に注目に値する。 |
| Dritte Abhandlung: was bedeuten asketische Ideale? Diese Abhandlung weist eine formale Besonderheit auf, worauf Nietzsche in der Vorrede hingewiesen hat: im ersten Abschnitt präsentiert er in knapper, aphoristischer Form seine Ergebnisse, um dann – nach Protest eines fiktiven Lesers – in der eigentlichen Abhandlung eine genauere Herleitung und Ausarbeitung davon zu geben. Nietzsche untersucht die unterschiedlichen Gestalten, in denen asketische Ideale in der Geschichte aufgetreten sind und heute auftreten, sowie ihre vielfältigen (vermeintlichen und tatsächlichen) Zwecke. Er deutet und bewertet das Verfolgen solcher Ideale bei Künstlern – Richard Wagners Parsifal als Beispiel –, Philosophen – besonders Schopenhauers Willensverneinung –, bei Priestern, bei den nach eigener Einschätzung „Guten und Gerechten“, bei Heiligen und schließlich auch bei modernen vermeintlichen Gegen-Idealisten, Atheisten, Wissenschaftlern und kritischen, antimetaphysischen Philosophen. Deren unbedingter „Wille zur Wahrheit“ sei die letzte, feine Gestalt des asketischen Ideals. Nach einer Betrachtung des gegenwärtigen und kommenden Nihilismus in Europa gibt Nietzsche einen letzten Grund an, warum bisher das asketische Ideal fast als einziges geehrt worden sei: nämlich schlicht in Ermangelung eines besseren Ideals. Der Mensch könne nicht „nicht wollen“, und so habe er bisher lieber noch in Nihilismus und Askese „das Nichts gewollt“. Alle drei Abhandlungen enden mit der Aussicht auf eine neue Moral, für die Nietzsche auf seinen Zarathustra verweist. Diese neue Moral ist allerdings nach Ansicht aller Rezipienten nicht so klar und deutlich zu erkennen wie Nietzsches Kritik der bisherigen „Moralen“. |
第三論文:禁欲主義の理想とは何なのか? この論文は、ニーチェが序文で指摘したように、形式的に特徴がある。最初のセクションでは、彼は簡潔で格言的な形で自分の結論を提示し、その後、架空の読者からの抗議を受けて、実際の論文の中で、その結論のより詳細な導出と展開を行っている。 ニーチェは、禁欲的な理想が歴史上、そして現代においてさまざまな形で現れていること、またその多様な(想定される、そして実際の)目的について考察して いる。彼は、芸術家(リヒャルト・ワーグナーの「パルジファル」を例に挙げている)、哲学者(特にショーペンハウアーの意志の否定)、聖職者、自らを「善 良で正義」と評価する人々、 聖人、そして最終的には、現代の反理想主義者、無神論者、科学者、批判的で反形而上学的な哲学者たちによる、そうした理想の追求を解釈し、評価している。 彼らの無条件の「真実への意志」は、禁欲的な理想の最たる、洗練された形態である。ヨーロッパにおける現在および将来のニヒリズムについて考察した後、 ニーチェは、これまで禁欲的な理想がほぼ唯一尊重されてきた最後の理由を、より優れた理想がないという単純な理由であると述べている。人間は「望まない」 ことができないため、これまでニヒリズムと禁欲主義の中で「無を望んできた」のだ。 3つの論文はすべて、ニーチェがツァラトゥストラで言及している新しい道徳の展望で終わっている。しかし、この新しい道徳は、ニーチェのこれまでの「道徳」に対する批判ほどはっきりと認識できるものではないと、すべての読者たちは考えている。 |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Zur_Genealogie_der_Moral |
★ジョルジュ・バタイユによると、ニーチェはヘーゲルを通俗紹介書以上についてなにも知らなかったと主張する。つまり、ヘーゲルの「主人と奴隷の弁証法」について、ニーチェは完全に誤解し、無知だという(バタイユ 1998:253)。
| Zur Genealogie der
Moral. Eine Streitschrift ist ein philosophisches Werk von Friedrich
Nietzsche aus dem Jahr 1887. Das Werk, das aus einer Vorrede und drei „Abhandlungen“ besteht, gehört zu den einflussreichsten Schriften Nietzsches. Er legte hier keine Aphorismen vor wie in den meisten anderen seiner Werke, sondern längere, systematische Texte mit durchaus wissenschaftlichem Anspruch: Er stellt darin soziologische, historische und psychologische Thesen auf. Nietzsche wollte anders als klassische Moralphilosophen keine Moral herleiten oder begründen, sondern die geschichtliche Entwicklung und die psychischen Voraussetzungen bestimmter moralischer Wertvorstellungen nachvollziehen. Er fragt also nicht, wie die Menschen handeln sollten, sondern warum Menschen (Einzelne oder Gruppen) glauben, sie sollten auf bestimmte Weise handeln, oder andere dazu bringen wollen, so oder so zu handeln. Der Gegensatz einer „Sklavenmoral“ und einer „Herrenmoral“ aus der ersten Abhandlung ist, zumindest schlagwortartig, recht bekannt geworden. Die dritte Abhandlung, in der Nietzsche die asketischen Ideale einer ausführlichen Kritik unterzieht, ist grundlegend für das Verständnis aller seiner Spätschriften. Die Genealogie beeinflusste zahlreiche Denker, unter anderem Sigmund Freud und Michel Foucault. Insbesondere in der französischen Nietzsche-Rezeption in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war sie ein vielbesprochenes Werk. Das übliche Sigel der Schrift ist GM. 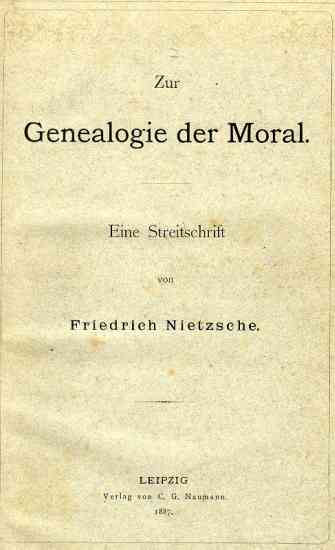 |
『道徳の系譜について:ひとつの極論』(Zur Genealogie der
Moral. Eine Streitschrif)は、フリードリヒ・ニーチェによる1887年の哲学書である。 序文と3つの「論考」から成るこの著作は、ニーチェの著作の中で最も影響力のあるもののひとつである。ニーチェはここで、他の著作のようにアフォリズム (格言)を提示するのではなく、徹底した科学的アプローチによる、より長く体系的なテキストを提示した。古典的な道徳哲学者とは異なり、ニーチェは道徳を 導き出したり正当化したりするのではなく、ある道徳的価値観の歴史的発展と心理的前提条件をたどることを望んだ。それゆえ彼は、人がどのように行動すべき かを問うのではなく、なぜ人(個人または集団)が、自分はある行動をとるべきだと信じるのか、あるいは他人にある行動をとらせたいと思うのかを問うのであ る。 第一論文に登場する「奴隷道徳」と「主人道徳」の対比は、少なくともキャッチフレーズの形ではよく知られている。ニーチェが禁欲的な理想を詳細な批判にさ らした第三の論考は、それ以降の著作を理解する上で基本となるものである。 系図』はジークムント・フロイトやミシェル・フーコーなど多くの思想家に影響を与えた。この著作は、特に20世紀後半のフランスにおけるニーチェ受容にお いて、多くの議論を呼んだ。 スクリプトの通常のシグルムはGMである。 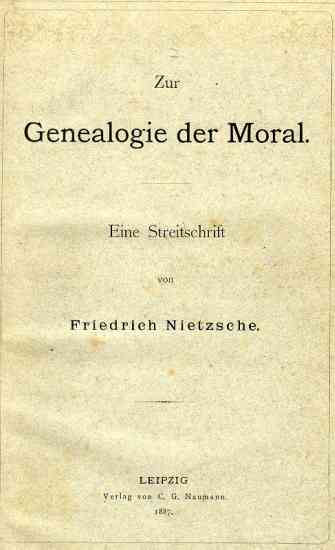 |
| 1 Inhalt 1.1 Vorrede 1.2 Erste Abhandlung: »Gut und Böse«, »Gut und Schlecht«. 1.3 Zweite Abhandlung: »Schuld«, »schlechtes Gewissen« und Verwandtes. 1.4 Dritte Abhandlung: was bedeuten asketische Ideale? 2 Entstehung und Einreihung in Nietzsches Schriften 3 Wirkungsgeschichte 4 Siehe auch 5 Ausgaben 6 Literatur 7 Weblinks |
1 目次 1.1 序文 1.2 第一論:「善と悪」、「善と悪」。 1.3 第二の論考:「罪悪感」、「悪い良心」とそれに関連する話題。 1.4 第三の論考:禁欲的理想とは何を意味するのか? 2 ニーチェの著作における起源と分類 3 影響の歴史 4 関連項目も参照のこと 5 エディション 6 文献 7 ウェブリンク |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Zur_Genealogie_der_Moral |
冒頭、上掲 |
| Entstehung und Einreihung in Nietzsches Schriften Nietzsche hatte eigentlich mit Jenseits von Gut und Böse und den 1886/87 gedruckten, veränderten Neuauflagen früherer Schriften sein Werk als vorläufig abgeschlossen angesehen und wollte sich Zeit fürs Durchdenken neuer Themen nehmen. Im Sommer 1887 war er in sehr niedergedrückter Stimmung und schrieb dann recht plötzlich (zwischen dem 10. und 30. Juli) die drei Abhandlungen der Genealogie, wobei er allerdings auf frühere Aufzeichnungen zurückgriff. Er ließ es auf eigene Kosten beim Verlag C. G. Naumann in Leipzig drucken und las gemeinsam mit Heinrich Köselitz Korrektur, wobei noch einige Änderungen vorgenommen wurden. In einer Auflage von 600 Exemplaren erschien das Buch im November 1887. Nietzsche legte Wert darauf, dass das Buch auch äußerlich dem vorherigen Jenseits von Gut und Böse „zum Verwechseln ähnlich“ sein sollte. Der Erstdruck enthielt auf der Rückseite des Titelblatts den Hinweis „Dem letztveröffentlichten „Jenseits von Gut und Böse“ zur Ergänzung und Verdeutlichung beigegeben.“ Nietzsche hatte sich schon von Jenseits erhofft, neue Leser zu finden, und ließ auch Exemplare der Genealogie an mehrere kulturell einflussreiche Personen senden. Die vielen Verweise auf frühere Schriften sollten wohl auch als Werbung dienen; Nietzsche selbst nannte seine Schriften ab Jenseits von Gut und Böse „Angelhaken“. Das Werk wurde für ihn noch einmal im folgenden Jahr bedeutsam, als er seinen Plan aufgab, Der Wille zur Macht zu schreiben. Es wird vermutet, dass ihn die erneute Lektüre der Genealogie dazu brachte oder darin bestärkte. Sein Spätwerk Der Antichrist, das gewissermaßen ein Ersatz für den Willen zur Macht war, weist stilistisch große Ähnlichkeit zur Genealogie auf und bezieht sich auch inhaltlich darauf. Zu Nietzsches Kritik an Paul Rées Ursprung der moralischen Empfindungen in der Vorrede ist zu bemerken, dass Rée und Nietzsche in den späten 1870er Jahren eng befreundet waren und viele, auch die beiden selbst, das genannte Werk Rées und Nietzsches Menschliches, Allzumenschliches als nächstverwandt gesehen hatten. Die Freundschaft mit Rée war 1882 zerbrochen. |
ニーチェの著作における起源と分類 善悪の彼岸』と1886/87年に印刷された以前の著作の修正新版によって、ニーチェは自分の著作がひとまず完成したと考え、新たなテーマについて考える 時間を取りたいと考えていた。1887年の夏、ニーチェは非常に憂鬱な気分になり、突然(7月10日から30日の間)、以前のメモを参考にしながらも、 『系図』の3つの論考を書き上げた。ライプツィヒの出版社C.G.ナウマンに自費で印刷させ、ハインリヒ・ケーセリッツとともに校正し、さらにいくつかの 変更を加えた。この本は1887年11月に600部出版された。 ニーチェは、この本が前作『善悪の彼岸』と「紛らわしいほど似ている」ことも強調した。初版のタイトルページの裏には、「補足と明確化のために、前回出版 された『善悪の彼岸』に追加された 」と記されていた。ニーチェはすでに『善悪の彼岸』の新しい読者を見つけることを望んでおり、『系図』のコピーを文化的に影響力のある何人かの人々に送っ ていた。ニーチェ自身、『善悪の彼岸』以降の著作を「釣り針」と呼んでいる。 ニーチェ自身、『善悪の彼岸』以降の著作を「釣り針」と呼んでいた。翌年、『力への意志』の執筆を断念したニーチェにとって、この著作は再び重要な意味を 持つようになった。系図』の再読がそれを促した、あるいは後押ししたと推測されている。彼の晩年の作品『反キリスト者』は、ある程度『力への意志』に取っ て代わるものであったが、文体的には『系図』に非常に似ており、内容的にも『系図』を参照している。 序文でニーチェがパウル・レの『道徳的発見』(Ursprung der moralischen Empfindungen)を批判していることについては、レとニーチェが1870年代後半に親しい友人であったこと、そして二人自身を含む多くの人が、 前述のレの著作とニーチェの『人間論』(Menschliches, Allzumenschliches)を密接に関連したものとして見ていたことに留意すべきである。レーとの友情は1882年に破局した。 |
| Wirkungsgeschichte Starken Einfluss übte das Werk auf Sigmund Freud aus, der aus dem Gedanken der Wiederaufnahme des Gewissens wegen der Grausamkeiten Das Unbehagen in der Kultur schrieb. Ebenfalls regte Nietzsches Genealogie Max Scheler dazu an, Das Ressentiment im Aufbau der Moralen zu verfassen. Die Genealogie gilt als Wegbereiter der postmodernen Philosophie. So ist zum Beispiel das Werk Michel Foucaults von Bezügen zur Genealogie der Moral durchzogen. Ebenfalls lässt sich für die französischen postmodernen Denker das jüngere Werk Die feinen Unterschiede von Pierre Bourdieu auf Ideen aus der Genealogie der Moral zurückverfolgen. Hierbei geht der Kerngedanke von den herrenmoralischen Ressentiments aus, nämlich das Schlechte durch feine Unterschiede auf vielen Ebenen des Lebens vom Guten abzugrenzen. |
影響の歴史 この著作はジークムント・フロイトに強い影響を与え、彼は残酷さゆえに良心を開き直すという考えに基づいて『文化における不快』を書いた。ニーチェの系譜はまた、マックス・シェラーに『道徳のアウフバウにおける不快感』を書かせた。 系図』はポストモダン哲学の先駆者とされている。例えば、ミシェル・フーコーの著作は、道徳の系譜への言及に満ちている。フランスのポストモダン思想家で は、ピエール・ブルデューの近著『微妙な差異』もまた、『道徳の系譜』のアイデアに遡ることができる。ここで核となる考え方は、人間の道徳的な憤り、すな わち、生活のさまざまなレベルにおける微妙な違いによって悪と善を区別することに基づいている。 |
| Siehe auch Blonde Bestie Ausgaben Siehe Nietzsche-Ausgabe für allgemeine Informationen. In der von Giorgio Colli und Mazzino Montinari gegründeten Kritischen Gesamtausgabe ist Zur Genealogie der Moral zu finden in Abteilung VI, Band 2 (zusammen mit Jenseits von Gut und Böse). ISBN 978-3-11-005175-9. Ein Nachbericht, d. h. kritischer Apparat, fehlt zu diesem Band noch. Denselben Text liefert die Kritische Studienausgabe in Band 5 (zusammen mit Jenseits von Gut und Böse und mit einem Nachwort von Giorgio Colli). Dieser erscheint auch als Einzelband unter der ISBN 978-3-423-30155-8. Der zugehörige Apparat befindet sich im Kommentarband (KSA 14), S. 377–382. Ebenfalls auf dieser Edition basiert die aktuelle Ausgabe bei Reclam, ISBN 978-3-15-007123-6. Sie enthält ein Nachwort von Volker Gerhardt. Kommentierte Neuausgabe mit Vor- und Nachwort von Elmar Dod in Perlen der Literatur, Band 22: Nietzsches Moral (= Zur Genealogie der Moral), Hamburg 2023, ISBN 978-3-941905-56-6. |
関連記事 ブロンド・ビースト エディション 一般的な情報はニーチェ版を参照のこと。 ジョルジョ・コッリとマッツィーノ・モンティナーリによって創刊された完全批評版では、『道徳の系譜』は次のセクションに収められている。 第VI章、第2巻(『善悪の彼岸』とともに)に収められている。ISBN978-3-11-005175-9。この巻には批評、すなわち批評的装置がまだない。 クリティカル・スタディ版では、第5巻(『善悪の彼岸』とともに、ジョルジョ・コッリによるあとがき付き)に同じテキストが収録されている。対応する注釈書は注釈書(KSA 14)の377-382頁にある。 Reclam社から出版されている現行版(ISBN 978-3-15-007123-6)もこの版に基づいており、フォルカー・ゲルハルトによる後書きがある。 注釈付き新版、エルマー・ドッドによる序文とあとがき(Perlen der Literatur, vol.22: Nietzsches Moral (= Zur Genealogie der Moral), Hamburg 2023, ISBN 978-3-941905-56-6. |
| Literatur Alle großen Monographien zu Nietzsche behandeln auch Zur Genealogie der Moral, siehe deswegen grundsätzlich die Literaturliste im Artikel „Friedrich Nietzsche“. Für eine ausführliche Bibliographie siehe Weblinks. Lars Niehaus: Das Problem der Moral: Zum Verhältnis von Kritik und historischer Betrachtung im Spätwerk Nietzsches. Königshausen u. Neumann, Würzburg 2009, ISBN 978-3-8260-4132-7. Richard Schacht (Hrsg.): Nietzsche, Genealogy, Morality. Essays on Nietzsche's “On the Genealogy of Morals”. University of California Press, Berkeley 1994, ISBN 978-0-520-08318-9. Andreas Urs Sommer: Kommentar zu Nietzsches Zur Genealogie der Moral (= Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Hg.): Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich Nietzsches Werken, Bd. 5/2). Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2019, ISBN 978-3-11-029308-1, E-Book: ISBN 978-3-11-038892-3 (Umfassender Kommentar, der die Forschungsgeschichte ebenso detailliert aufarbeitet wie die argumentative Struktur des Textes und die zahlreichen intertextuellen Bezüge). Werner Stegmaier: Nietzsches ›Genealogie der Moral‹. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994, ISBN 978-3-534-10410-9. |
文献 ニーチェに関する主要なモノグラフはすべて『道徳の系譜』も扱っている。詳細な参考文献については、Weblinksを参照のこと。 Lars Niehaus: Das Problem der Moral: Zum Verhältnis von Kritik und historischer Betrachtung im Spätwerk Nietzsches. Königshausen u. Neumann, Würzburg 2009, ISBN 978-3-8260-4132-7. Richard Schacht (ed.): Nietzsche, Genealogy, Morality. ニーチェの『道徳の系譜』に関する論考。University of California Press, Berkeley 1994, ISBN 978-0-520-08318-9. Andreas Urs Sommer: Kommentar zu Nietzsches Zur Genealogie der Moral (= Heidelberger Akademie der Wissenschaften (ed.): Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich Nietzsches Werken, vol. 5/2). Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2019, ISBN 978-3-11-029308-1, E-Book: ISBN 978-3-11-038892-3(本文の論旨構成や多数の引用文献と同様に、研究史を詳細に分析した包括的な解説書)。 Werner Stegmaier: ニーチェの「道徳の系譜」. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994, ISBN 978-3-534-10410-9. |
| Weblinks Nietzsche Source, Colli / Montinari-Ausgabe (Vollständiger Text) Literatur zu Zur Genealogie der Moral, Verzeichnis der Weimarer Nietzsche-Bibliographie(リンク切れ) |
リンク ニーチェ資料、コッリ/モンティナーリ版(全文) 道徳の系譜』に関する文献、ワイマール・ニーチェ文献目録 崩壊 |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Zur_Genealogie_der_Moral |
|
| On
the Genealogy of Morality: A Polemic (German: Zur Genealogie der Moral:
Eine Streitschrift; sometimes also translated as On the Genealogy of
Morals) is an 1887 book by German philosopher Friedrich Nietzsche. It
consists of a preface and three interrelated treatises ('Abhandlungen'
in German) that expand and follow through on concepts Nietzsche
sketched out in Beyond Good and Evil (1886). The three treatises trace
episodes in the evolution of moral concepts with a view to confronting
"moral prejudices", specifically those of Christianity and Judaism. Some Nietzschean scholars[who?] consider Genealogy to be a work of sustained brilliance and power as well as his masterpiece.[1] Since its publication, it has influenced many authors and philosophers. |
『道
徳の系譜学について:論争』(ドイツ語:『道徳の系譜学について:論争論文』)は、1887年にドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェによって書かれた本
である。本書は序文と3つの相互に関連する論文(ドイツ語では「Abhandlungen」)から構成されており、ニーチェが『善悪を超えて』(1886
年)で概略を示した概念をさらに掘り下げ、展開している。3つの論文は、道徳概念の進化におけるエピソードをたどり、「道徳的偏見」、特にキリスト教とユ
ダヤ教のそれらと対峙することを目的としている。 ニーチェ学者の一部は、この『系譜学』を、持続的な輝きと力強さを持つ作品であり、またニーチェの最高傑作であると考えている。[1] 出版以来、多くの作家や哲学者に影響を与えている。 |
| Summary Preface Nietzsche's treatise outlines his thoughts "on the origin of our moral prejudices" previously given brief expression in his Human, All Too Human (1878) and Beyond Good and Evil (1886). Nietzsche attributes the desire to publish his "hypotheses" on the origins of morality to reading his friend Paul Rée's book The Origin of the Moral Sensations (1877) and finding the "genealogical hypotheses" offered there unsatisfactory. Nietzsche decided that "a critique of moral values" was needed, that "the value of these values themselves must be called into question". To this end Nietzsche provides a history of morality, rather than a hypothetical account in the style of Rée, whom Nietzsche classifies as an "English psychologist"[2] (using "English" to designate an intellectual temperament, as distinct from a nationality). |
概要 序文 ニーチェの論文は、彼の著書『人間的、あまりに人間的な』(1878年)と『善悪の彼岸』(1886年)で簡潔に表現されていた「我々の道徳的偏見の起 源」に関する彼の考えを概説している。ニーチェは、道徳の起源に関する「仮説」を公表したいと考えたのは、友人のポール・レーの著書『道徳感情の起源』 (1877年)を読み、そこで提示された「系譜学上の仮説」に満足できなかったからである。 ニーチェは「道徳的価値の批判」が必要であり、「これらの価値自体の価値が問われなければならない」と判断した。この目的のために、ニーチェはレーのスタ イルによる仮説的な説明ではなく、道徳の歴史を提供している。ニーチェはレーを「英国の心理学者」と分類している[2](「英国人」という表現は、国民性 とは異なる知的な気質を示すために使用されている)。 |
| First Treatise: "'Good and Evil', 'Good and Bad'" See also: Good and evil In the "First Treatise", Nietzsche demonstrates that the two pairs of opposites "good/evil" and "good/bad" have very different origins, and that the word "good" itself came to represent two opposed meanings. In the "good/bad" distinction of the aristocratic way of thinking, "good" is synonymous with nobility and everything that is powerful and life-affirming; "bad" has no inculpatory implication and simply refers to the "common" or the "low" and the qualities and values associated with them, in contradistinction to the warrior ethos of the ruling nobility (§3). In the "good/evil" distinction, which Nietzsche calls "slave morality", the meaning of "good" is made the antithesis of the original aristocratic "good", which itself is re-labelled "evil". This inversion of values develops out of the ressentiment felt by the weak towards the powerful. Nietzsche rebukes the "English psychologists" for lacking historical sense. They seek to do moral genealogy by explaining altruism in terms of the utility of altruistic actions, which is subsequently forgotten as such actions become the norm. But the judgment "good", according to Nietzsche, originates not with the beneficiaries of altruistic actions. Rather, the good themselves (the powerful) coined the term "good". Further, Nietzsche sees it as psychologically absurd that altruism derives from a utility that is forgotten: if it is useful, what is the incentive to forget it? Such meaningless value-judgment gains currency by expectations repeatedly shaping the consciousness. From the aristocratic mode of valuation, another mode of valuation branches off, which develops into its opposite: the priestly mode. Nietzsche proposes that longstanding confrontation between the priestly caste and the warrior caste fuels this splitting of meaning. The priests, and all those who feel disenfranchised and powerless in a lowly state of subjugation and physical impotence (e.g., slavery), develop a deep and venomous hatred for the powerful. Thus originates what Nietzsche calls the "slave revolt in morality", which, according to him, begins with Judaism (§7), for it is the bridge that led to the slave revolt, via Christian morality, of the alienated, oppressed masses of the Roman Empire (a dominant theme in The Antichrist, written the following year). To the noble life, justice is immediate, real, and good, necessarily requiring enemies. To slave morality, justice is a deferred event, ultimately taking the form of an imagined revenge that will result in everlasting life for the weak and punishment for the strong. Slave morality grows out of impotence, world-weariness, indignation and envy; it purports to speak for the oppressed masses who have been wronged, deprived of the power to act with immediacy by the masters, who thrive on their subjugation. The men of ressentiment, in an inversion of values, redefine the "good" in their own image. They say: "he is good who does not outrage, who harms nobody, who does not attack, who does not requite, who leaves revenge to God, who avoids evil and desires little from life, like us, the patient, humble, and just."(§13) According to Nietzsche, this is merely a transformation of the effects and qualities of impotence into virtues, as if these effects and qualities were chosen – the meritorious deeds of the "good" man. The deeds of the powerful man, known to themselves as "good", are re-cast by the men of ressentiment as "evil", taking on a mystical moral-judgemental element entirely absent from the aristocratic "bad", which to the noble was simply a descriptor for the inferior qualities of the lower classes. In the First Treatise, Nietzsche introduces one of his most controversial images, the "blond beast". He had previously employed this expression to represent the lion, an image that is central to his philosophy and made its first appearance in Thus Spoke Zarathustra. Beyond the metaphorical lion, Nietzsche expressively associates the "blond beast" with the Aryan race of Celts and Gaels which he states were all fair skinned and fair-haired and constituted the collective aristocracy of the time. Thus, he associates the "good, noble, pure, as originally a blond person in contrast to dark-skinned, dark-haired native inhabitants" (the embodiment of the "bad"). Here he introduces the concept of the original blond beasts as the "master race" which has lost its dominance over humanity but not necessarily permanently. Though, at the same time, his examples of blond beasts include such peoples as the Japanese and Arabic nobilities of antiquity (§11), suggesting that being a blond beast has more to do with one's morality than one's race. Peter Sloterdijk asserts: "There is no 'eugenics' in Nietzsche." Nietzsche insists that it is a mistake to hold beasts of prey to be "evil", for their actions stem from their inherent strength, rather than any malicious intent. One can not blame them for their "thirst for enemies and resistances and triumphs" because, according to Nietzsche, there is no "subject" separate from the action: A quantum of force is equivalent to a quantum of drive, will, effect—more, it is nothing other than precisely this very driving, willing, effecting, and only owing to the seduction of language (and the fundamental errors of reason that are petrified in it) which conceives and misconceives all effects as conditioned by something that causes effects, by a "subject", can it appear otherwise. For just as the popular mind separates the lightning from its flash and takes the latter for an action, for the operation of a subject called lightning, so popular morality also separates strength from expressions of strength, as if there were a neutral substratum behind the strong man, which was free to express strength or not do so. But there is no such substratum; there is no "being" behind doing, effecting, becoming; "the doer" is merely a fiction added to the deed—the deed is everything.(§13) The "subject" (or soul) is only necessary for slave morality. It enables the impotent man to sanctify the qualities of his impotence by making them into "good" qualities, chosen for moral reasons, and the actions of his oppressor into morally "evil" choices. Nietzsche concludes his First Treatise by hypothesizing a tremendous historical struggle between the Roman dualism of "good/bad" and that of the Judaic "good/evil", with the latter eventually achieving a victory for ressentiment, broken temporarily by the Renaissance, but then reasserted by the Reformation, and finally confirmed by the French Revolution when the "ressentiment instincts of the rabble" triumphed. The First Treatise concludes with a note calling for further examination of the history of moral concepts and the hierarchy of values. |
第1論文:「『善と悪』、『善と悪』」 関連項目:善と悪 「第1論文」において、ニーチェは「善/悪」と「善/悪」という2つの対立概念がまったく異なる起源を持っていること、そして「善」という言葉自体が2つ の対立する意味を表すようになったことを示している。貴族的なものの考え方における「善/悪」の区別では、「善」は高貴さと同義であり、力強く、生命を肯 定するものすべてを意味する。「悪」には罪を意味する含みはなく、単に「平凡」または「低俗」を意味し、それらに関連する性質や価値を指す。支配階級の戦 士道精神とは対照的である(§3)。ニーチェが「奴隷道徳」と呼ぶ「善悪」の区別では、「善」の意味は本来の貴族的な「善」の対義語とされ、それ自体は 「悪」と再定義される。この価値観の転倒は、弱者が強者に対して抱くルサンチマンから発展する。 ニーチェは「英国の心理学者」たちを歴史感覚の欠如を理由に非難している。彼らは利他主義を利他的行動の有用性という観点から説明することで、道徳の系譜 を明らかにしようとしているが、そのような行動が規範となるにつれ、その有用性は忘れ去られてしまう。しかし、ニーチェによれば、「善」という判断は、利 他的行動の恩恵を受けた人々によって生み出されたものではない。むしろ、「善」そのもの(権力者)が「善」という言葉を作り出したのである。さらに、ニー チェは、利他主義が忘却される効用から派生するということが心理学的には不合理であると見ている。もしそれが有用であるならば、それを忘れる動機は何なの か?このような無意味な価値判断は、繰り返される期待が意識を形成することで広まっていく。 貴族的な価値判断の様式から、別の価値判断の様式が枝分かれし、それがその反対の様式へと発展する。すなわち、聖職者の様式である。ニーチェは、聖職者階 級と戦士階級の長年にわたる対立が、この意味の分裂を煽っていると提案している。聖職者、および、従属的な地位や肉体的無力感(例えば、奴隷制)の中で権 利を剥奪され、無力感を抱くすべての人々は、権力者に対して深い憎悪を抱く。こうしてニーチェが「道徳における奴隷の反乱」と呼ぶものが始まる。彼によれ ば、それはユダヤ教から始まる(§7)。なぜなら、それは奴隷の反乱へと導く架け橋であり、キリスト教道徳を通じて、疎外され、抑圧されたローマ帝国の民 衆の反乱へとつながるからだ(翌年に書かれた『反キリスト』の主要テーマ)。 高貴な人生にとって、正義は即時的で現実的で、善である。必然的に敵が必要となる。奴隷道徳にとって、正義は先延ばしにされた出来事であり、究極的には弱 者の永遠の生命と強者の処罰という想像上の復讐という形を取る。奴隷道徳は、無力感、世の中に対する倦怠感、憤り、そして嫉妬から生じる。それは、抑圧さ れた大衆の代弁者であると主張する。その大衆は、支配者たちによって不当に扱われ、即座に行動する力を奪われている。逆恨みの男たちは、価値観をひっくり 返し、自分たちのイメージ通りに「善」を再定義する。彼らは言う。「怒りを爆発させず、誰にも危害を加えず、攻撃せず、仕返しせず、復讐を神に委ね、悪を 避け、人生に多くを求めず、我々のように忍耐強く、謙虚で、公正な人間こそが善人である。」と彼らは言う(§13)。ニーチェによれば、これは無力さの影 響と性質が美徳へと変化したに過ぎず、あたかもそれらの影響と性質が選択されたかのように見える。つまり、「善人」の功徳ある行為である。「善」として自 らを認識する権力者の行為は、ルサンチマンの男たちによって「悪」として再解釈され、貴族の「悪」にはまったく存在しなかった神秘的な道徳的判断の要素が 加わる。貴族にとって「悪」とは、単に下層階級の劣った性質を表す記述子にすぎなかった。 『第一論文』において、ニーチェは最も物議を醸したイメージのひとつである「ブロンドの野獣」を提示している。彼は以前にもこの表現をライオンを象徴する ものとして用いており、それは彼の哲学の中心的なイメージであり、『ツァラトゥストラはこう語った』で初めて登場している。ニーチェは、比喩的なライオン を超えて、「ブロンドの野獣」をケルト人とゲール人のアーリア人種と表現し、彼らは皆色白で金髪であり、当時の貴族階級を構成していたと述べている。した がって、彼は「善良で高貴で純粋な、もともとブロンドの人間(「悪」の体現である)と対照的な、色黒で黒髪の土着の住民」と関連付けている。ここで彼は、 元来のブロンドの獣を「支配者民族」として紹介し、その民族は人類に対する支配力を失ったが、必ずしも永遠に失ったわけではないと述べている。しかし同時 に、ブロンドの獣の例として、古代の日本やアラブの貴族階級を挙げている(§11)ことから、ブロンドの獣であるかどうかは、人種よりもむしろその人の道 徳性に関係していることが示唆されている。ピーター・スローターダイクは、「ニーチェには『優生学』はない」と主張している。 ニーチェは、肉食獣を「悪」とみなすのは間違いであると主張している。なぜなら、彼らの行動は悪意からではなく、彼らに内在する強さから生じるものだから だ。ニーチェによれば、行動とは切り離された「主体」は存在しないため、彼らの「敵や抵抗、勝利への渇望」を責めることはできない。 力は、推進力、意志、効果の量に等しい。さらに、それはまさにこの推進力、意志、効果にほかならず、言語(および言語に固着した理性の根本的な誤り)の誘 惑によるものにほかならない。言語は、あらゆる効果を、効果をもたらす何らかの原因、すなわち「主体」によって条件づけられたものとして考え、誤解させ る。大衆の心は、稲妻をその閃光から切り離し、後者を稲妻と呼ばれる主体の作用、つまり行動とみなす。同様に、大衆道徳も強さを強さの表現から切り離し、 あたかも強者の背後に強さを表現しても表現しなくてもよい中性的な基盤があるかのようにみなす。しかし、そのような基盤は存在しない。行動、影響、変化の 背後には「存在」はなく、「行動者」は行為に付け加えられた単なる虚構であり、行為こそがすべてである。 「主体」(あるいは魂)は奴隷道徳においてのみ必要である。それは、無力な男が、自分の無力の性質を道徳的理由から選ばれた「善」の性質とすることで、その性質を神聖化することを可能にする。また、その男の抑圧者の行動を道徳的に「悪」の選択とすることも可能にする。 ニーチェは『第一論文』の結論で、ローマの「善/悪」二元論とユダヤ教の「善/悪」二元論の間の歴史的な壮絶な闘争を仮定し、後者がルネサンスによって一 時的に打ち砕かれたものの、宗教改革によって再び主張され、最終的に「民衆のルサンチマン本能」が勝利したフランス革命によって確認されたと結論づけてい る。 『第一論文』は、道徳的概念と価値のヒエラルキーの歴史について、さらなる調査を求める注釈で締めくくられている。 |
| Second Treatise: "'Guilt', 'Bad Conscience', and Related Matters" According to Nietzsche, what we call "the conscience" is the end product of a long and painful socio-historical process that began with the need to create a memory in the human animal. For its own psychic health and functionality, the human organism is naturally forgetful. Forgetfulness is "an active and in the strictest sense positive faculty of repression, which is responsible for the fact that what we experience and absorb enters our consciousness as little while we are digesting it (one might call the process 'inpsychation') as does the thousandfold process involved in physical nourishment – so-called incorporation"(§1). But social existence, to the extent that the social organism must function as a unity to survive and prosper, requires that certain things be not forgotten, that individuals must remember their place relative to the whole. Memory in this sense, the social conscience in its rudimentary form, was forged with great difficulty over a long period of time, by what Nietzsche refers to as man's mnemotechnics, the underlying principle of which is "If something is to stay in the memory it must be burned in: only that which never ceases to hurt stays in the memory"(§3). This long pre-historic process allows a "morality of customs" to establish itself, and through it man becomes calculable, regular, and predictable. Its "ripest fruit" is 'the sovereign individual', a human being whose 'social responsibility' has become flesh and blood, an individual with such hard-won mastery over himself that he is capable of determining and guaranteeing his own future actions. Such an individual has a free will: by virtue of his self-mastery he has the right to make promises. The conscience in this sense is the self-discipline of social responsibility made into a dominating instinct; to such an individual all other individuals, things and circumstances are evaluated from the perspective of this instinct.(§2) It was in the contractual relationship, a relationship based on mutual promises, that one person first "measured himself against another... setting prices, determining values, contriving equivalences, exchanging – these preoccupied the earliest thinking of man to so great an extent that in a certain sense they constitute thinking as such" (§8). 'Law' and 'justice', a society's codes, judgements and commands in relation to individual and inter-personal rights and obligations, are formed in the context of this contractual-evaluating conceptual paradigm. The strength of one's 'conscience', one's ability to make promises and not break them, to personally guarantee one's future actions, to fulfil ones obligations to others, is thus a vital factor in determining individual social status. The concepts of guilt and punishment likewise have their origins in the contractual relationship. Here 'guilt' (schuld) simply meant 'debt' (schulden): the guilty person was simply the person who was unable to discharge their debt. In punishment, the creditor acquires the right to inflict harm on the guilty person. Such a transaction is made possible, according to Nietzsche, by pleasure in cruelty. Its logic is not related in any way to considerations about the free will, moral accountability etc, of the wrong-doer: it is nothing more than a special form of compensation for the injured party. The creditor receives recompense "in the form of a kind of pleasure—the pleasure of being allowed to vent his power freely upon one who is powerless" (§5). Such punishment was a legally enforceable right of the creditor, and some law books had exact quantifications of what could be done to the debtor's body relative to the debt. It was in this civil law validation of cruelty that 'guilt' first became intertwined with 'suffering'. In criminal law, punishment and the debtor/creditor relationship have been transferred onto the relation in which the individual stands to the community. The individual enjoys a number of benefits from communal life, the most obvious of which is protection from the hostile world outside the community: a pledge is made to the community and its mores and laws in return for this protection. If that pledge is broken the community, as the offended creditor, demands repayment. A warlike and survival-based community, dealing constantly with danger or scarcity, will be violent and merciless in its treatment of law-breakers. As a community's security and self-confidence increases, the harm of one individual's transgressions decreases correspondingly, and the continuance of the more harmonious state requires that excessively violent responses be controlled and regulated. The nature of such a community's penal law will involve a compromise between this requirement and the angry forces seeking blood and violence. Its principal way of achieving it is to separate the deed from the doer via the concept of 'the crime', a transformation of the actual deed into an abstract legal category implying a 'debt to society', a debt that is ultimately dischargeable through an appropriate 'punishment'. According to Nietzsche, one must not equate the origin of a thing and its utility. The origin of punishment, for example, is in a procedure that predates the many possible uses and interpretations of it. Punishment has not just one purpose, but a whole range of "meanings" which "finally crystallizes into a kind of unity that is difficult to dissolve, difficult to analyze and ... completely and utterly undefinable" (§13). Nietzsche lists eleven different uses (or "meanings") of punishment, and suggests that there are many more. One utility it does not possess, however, is awakening remorse. The psychology of prisoners shows that punishment "makes hard and cold; it concentrates; it sharpens the feeling of alienation" (§14). The feeling of guilt, the bad conscience, had quite different origins and had no place whatsoever in the institutions of crime and punishment for the greater part of their history. The criminal was dealt with merely as something harmful, as an "irresponsible piece of fate", and the person upon whom punishment was administered, though his body encountered something shocking and violent, was entirely unacquainted with 'moral' pain. The only 'lesson' learned from punishment was that of prudence and memory. Punishment produces "an increase in fear, a heightening of prudence, mastery of the desires: thus punishment tames men, but it does not make them "better"."(§15) In Nietzsche's theory, the bad conscience was the serious illness that the animal man was bound to contract when he found himself finally enclosed within the walls of a politically organized society. It begins with the institution of the 'state', in its original form a violent subjugation of a people by a highly organized and remorseless military machine: "the wielding of a hitherto unchecked and shapeless populace into a firm form was not only instituted by an act of violence but carried to its conclusion by nothing but acts of violence"(§17). Thus the human animal became subjected, enclosed within a system of externally imposed functions and purposes, and its outward-pressing drives and impulses were turned inward: "the instinct for freedom pushed back and incarcerated within and finally able to discharge and vent itself only on itself".(§16) It is the will to power, the same active force that is at work in the artists of violence and builders of states, but deprived of its object and turned upon itself. This inner world of "self-ravishment" and "artists' cruelty", became "the womb of all ideal and imaginative phenomena", the soul of man.(§18) To understand how the bad conscience became bound up with guilt and punishment, it is necessary to examine how these concepts acquired religious significance. Nietzsche accounts for the genesis of the concept "God" by considering what happens when a tribe becomes ever more powerful. Each successive generation maintains an ethos of indebtedness (guilt) to the original founders of the tribe, the ancestors. The tribe's very existence is thought to depend on a continued acknowledgement and repayment of the ancestor, whose powerful spirit is still present in all customs and daily activities. As the power of the tribe grows, the debt to the ancestor likewise increases. The invisible yet omnipresent figure of the ancestor takes on an ever-increasing power and mystique, until eventually, in the paranoid imaginations of his debtors, he begins to "recede into the darkness of the divinely uncanny and unimaginable: in the end the ancestor must necessarily be transfigured into a god." (§19) The historical advance toward universal empires brought with it the advance toward monotheistic religions, and it was with Christianity that the feeling of guilty indebtedness achieved its non plus ultra. Christianity is the religion that has sought, successfully, to permanently bind the concept of 'guilt' to the bad conscience: the aim now is to preclude pessimistically, once and for all, the prospect of a final discharge; the aim now is to make the glance recoil disconsolately from an iron impossibility; the aim now is to turn the concepts "guilt" and "duty" back—back against whom?… against the "debtor" first of all, in whom from now on the bad conscience is firmly rooted, eating into him and spreading within him like a polyp, until at last the irredeemable debt gives rise to the conception of irredeemable penance, the idea that it cannot be discharged ("eternal punishment"). (§21) The entire condition of mankind becomes guilt-ridden, whether that condition is the primal ancestor who becomes the perpetrator of "original sin", or "nature", the mother, who becomes characterized as evil or shameful, or existence in general, which is now considered "worthless as such". Christianity's expedient, its "stroke of genius" in the shadow of this looming eternal nightmare, was to proclaim that God himself, in the person of Jesus, sacrificed himself for the guilt of mankind. God pays the unpayable debt, the new religion teaches, out of love—love for his debtor. Thus guilt, which originally merely signified debt in a contractual sense, attained an essential moral-metaphysical significance in mankind’s understanding of itself and its relation to God. Nietzsche ends the Treatise with a positive suggestion for a counter-movement to the "conscience-vivisection and cruelty to the animal-self" imposed by the bad conscience: this is to "wed to bad conscience the unnatural inclinations", i.e. to use the self-destructive tendency encapsulated in bad conscience to attack the symptoms of sickness themselves. It is much too early for the kind of free spirit—a Zarathustra-figure—who could bring this about, although he will come one day: he will emerge only in a time of emboldening conflict, not in the "decaying, self-doubting present" (§24). |
第二論文:「『罪悪感』、『悪い良心』、および関連事項」 ニーチェによれば、我々が「良心」と呼ぶものは、人間に記憶を創り出す必要が生じたことに端を発する、長く苦痛に満ちた社会史的過程の最終産物である。精 神の健康と機能性を保つために、人間という生物は生まれつき忘れっぽい。忘却とは、「能動的かつ厳密な意味で肯定的な抑圧の能力であり、私たちが経験し吸 収したものが、それを消化している間は、意識にほとんど入らない(このプロセスを「インシュペイション」と呼ぶかもしれない)という事実を担っている。し かし、社会が存続し繁栄するためには社会組織が統一体として機能しなければならないという程度において、社会的な存在は、ある特定の事柄を忘れてはならな いことを要求し、個人は全体との相対的な位置を記憶していなければならない。この意味での記憶、すなわち社会的な良心の初歩的な形は、ニーチェが人間の記 憶術と呼ぶものによって、長い年月をかけて多大な困難を伴いながら形成されてきた。その基本原則は「記憶にとどめるためには焼き付けなければならない。記 憶にとどまるのは、いつまでも痛みが消えないものだけだ」というものである(§3)。 この長い先史時代のプロセスにより、「慣習の道徳性」が確立され、それを通じて人間は計算可能となり、規則的になり、予測可能になる。その「最も熟した果 実」は「主権者たる個人」であり、その「社会的責任」が血肉となった人間、つまり、自己を支配する術を獲得し、自らの将来の行動を決定し、保証することが 可能な個人である。そのような個人は自由意志を持つ。自己統制力があるからこそ、約束をする権利がある。この意味での良心とは、社会責任の自己規律が支配 的な本能となったものであり、そのような個人にとっては、他のすべての個人、物、状況は、この本能の観点から評価される。 契約関係、すなわち相互の約束に基づく関係において、ある人物が初めて「他者と自分を比較し...価格を設定し、価値を決定し、同等性を考案し、交換す る」ようになった。これらは、ある意味で思考そのものを構成するほど、人類の最も初期の思考を非常に強く占領していたのである。(§8) 「法」と「正義」、すなわち社会の規範、個人および個人間の権利と義務に関する判断や命令は、この契約的評価の概念的パラダイムの文脈において形成され る。 したがって、良心の強さ、約束を守り破らない能力、将来の行動を個人的に保証する能力、他人に対する義務を果たす能力は、個人の社会的地位を決定する上で 重要な要素となる。 罪と罰の概念も同様に、契約関係に起源を持つ。ここでいう「罪(schuld)」とは単に「負債(schulden)」を意味し、罪を犯した者は単に負債 を返済できない者のことを指していた。罰においては、債権者は罪を犯した者に危害を加える権利を得る。このような取引は、ニーチェによれば、残酷さに対す る快楽によって可能になる。その論理は、加害者の自由意志や道徳的責任能力などに関する考察とは一切関係がない。それは、被害者に対する特別な形の補償に すぎない。債権者は「ある種の快楽、すなわち無力な者に自由に力をふるうことを許される快楽」という形で報いを受ける(§5)。このような処罰は債権者の 法的強制力のある権利であり、債務者の身体にどのようなことが可能かについて、債務額に応じた厳密な定量化が法律書に記載されていた。このような民法上の 残虐性の正当化において、「罪」が初めて「苦しみ」と絡み合うようになった。 刑法では、処罰と債務者/債権者の関係は、個人と社会の関係に移行した。個人には共同生活から多くの恩恵がもたらされるが、その最も明白なものは共同社会 の外にある敵対的な世界からの保護である。この保護と引き換えに、共同社会とその慣習や法律に誓約を立てる。もしその誓いが破られた場合、共同体は被害を 受けた債権者として返済を要求する。戦争的で生存を基盤とする共同体は、常に危険や欠乏と向き合っているため、法を破った者に対しては暴力的で容赦のない 対応を取る。共同体の安全と自信が高まれば、個人の違反による被害は相応に減少する。より調和の取れた状態を継続させるためには、過度に暴力的な対応を抑 制し、規制する必要がある。そのような社会の刑法の性質は、この要求と、血と暴力を求める怒りの勢力との妥協点となる。その主な達成方法は、「犯罪」とい う概念によって行為と行為者を切り離すことである。つまり、実際の行為を「社会に対する負債」を意味する抽象的な法的カテゴリーに変換することであり、そ の負債は適切な「処罰」によって最終的に返済される。 ニーチェによれば、物事の起源と有用性を同一視してはならない。例えば、刑罰の起源は、その刑罰の多くの使用法や解釈に先立つ手続きにある。刑罰にはただ 一つの目的があるのではなく、さまざまな「意味」があり、それらは「最終的に、溶解も分析も困難な、ある種の結晶へと結晶化する。ニーチェは、罰の11の 異なる用途(または「意味」)を挙げ、さらに多くの用途があることを示唆している。しかし、罰が備えていない効用として、後悔を促すというものがある。受 刑者の心理を見ると、罰は「人を頑なで冷淡にし、集中させ、疎外感を強める」ことが分かる(§14)。罪の意識、つまり良心の呵責は、まったく異なる起源 を持ち、犯罪と刑罰の制度の歴史の大半において、まったく存在しなかった。犯罪者は単に有害な存在、すなわち「無責任な運命の産物」として扱われ、刑罰が 科せられた者は、肉体が衝撃的で暴力的なものを経験するとはいえ、「道徳的な」苦痛とはまったく無縁であった。刑罰から学んだ唯一の「教訓」は、慎重さや 記憶力であった。処罰は「恐怖の増大、慎重さの増大、欲望の抑制」をもたらす。したがって、処罰は人間を飼い慣らすが、人間を「より良く」はしない。(§ 15) ニーチェの理論では、良心の呵責は、動物的な人間が、政治的に組織化された社会の壁に囲い込まれたことに気づいたときに罹患する深刻な病気である。それは 「国家」の制度とともに始まる。その原型は、高度に組織化され、無慈悲な軍事機構による人々への暴力的な服従である。「それまで抑制も形もなかった大衆 を、強固な形に作り上げることは、暴力行為によって始められただけでなく、暴力行為によってのみ完遂されたのである」(§17)。こうして人間は従属し、 外から課せられた機能と目的の体系に囲い込まれ、外に向かう衝動と衝動は内に向きを変えられた。「自由への本能は押し戻され、内に幽閉され、最終的に自分 自身に対してのみ発散し、発散することができるようになった」(§16)。それは力への意志であり、暴力の芸術家や国家建設者たちに作用するのと同じ活動 力であるが、対象を奪われ、自己に向けられている。この「自己陶酔」と「芸術家の残酷さ」という内面世界は、「あらゆる理想と想像上の現象の母体」、すな わち人間の魂となったのである。 (§18) 罪の意識がどのようにして罪と罰と結びついたのかを理解するには、これらの概念がどのようにして宗教的な意味を持つようになったのかを検証する必要があ る。ニーチェは、部族がますます強力になっていくときに何が起こるかを考察することで、「神」という概念の起源を説明している。各世代は、部族の創始者で ある祖先に対して負い目(罪悪感)を抱き続ける。部族の存在は、祖先への認識と返済を継続することに依存していると考えられ、その強力な精神は、あらゆる 慣習や日常的な活動に今もなお存在している。部族の力が強まるにつれ、祖先への負債も同様に増加する。目に見えないが遍在する祖先の姿は、ますます強大な 力と神秘性を帯びていき、ついには、負債者の偏執的な想像の中で、祖先は「神聖な超常現象と想像を絶する闇の中に退いていく。最終的には、祖先は必然的に 神へと変容しなければならない」のである。 普遍的な帝国への歴史的な前進は、一神教への前進をもたらし、キリスト教において負債の罪悪感は究極の到達点に達した。キリスト教は「罪」の概念を「良心の呵責」に永続的に結びつけることを成功裏に目指してきた宗教である。 今や悲観的に、最終的な返済の見込みを完全に排除することが目的となっている。今や鉄壁の不可能から落胆して目をそらすことが目的となっている。今や「罪 悪感」と「義務」という概念を逆戻りさせることが目的となっている。誰に対して逆戻りさせるのか?まず第一に「債務者」に対して、今後は彼の中にしっかり と根付き、彼をむしばみ、ポリプのように彼の中で広がっていく、最後には償いようのない負債が償いようのない苦行という概念を生み出し、それは決して返済 できないという考え(「永遠の罰」)に至るまで。(§21) 人類全体の状況は罪にまみれたものとなる。その状況とは、原初の祖先が「原罪」の加害者となること、あるいは「自然」、つまり母なるものが悪や恥と特徴づ けられること、あるいは存在一般が「それ自体では価値がない」とみなされることである。キリスト教がこの永遠の悪夢の影の中で見出した「天才的な」策は、 神自身がイエスの姿で人類の罪のために自らを犠牲にしたと宣言することだった。新しい宗教は、神が負い切れない負債を、負債者への愛から支払うと教える。 こうして、もともとは契約上の負債を意味するに過ぎなかった罪は、人類が自らを理解し、神との関係を理解する上で、本質的な道徳的・形而上学的意義を持つ に至った。 ニーチェは、良心の呵責によって強制される「自己への生体解剖と残酷さ」に対する反動として、前向きな提案を論文の最後に提示している。すなわち、「不自 然な傾向を良心の呵責と結びつける」こと、つまり、良心の呵責に内包された自己破壊的な傾向を利用して、病気の症状そのものを攻撃することである。このよ うなことを実現できる自由な精神、すなわちツァラトゥストラのような人物が現れるには、まだ早すぎる。いつかは現れるだろうが、それは「腐敗し、自信を 失った現在」ではなく、勇気づけられるような葛藤の時代にのみ現れるだろう(§24)。 |
| Third Treatise: "What do ascetic ideals mean?" Nietzsche's purpose in the "Third Treatise" is "to bring to light, not what [the ascetic] ideal has done, but simply what it means; what it indicates; what lies hidden behind it, beneath it, in it; of what it is the provisional, indistinct expression, overlaid with question marks and misunderstandings" (§23). As Nietzsche tells us in the Preface, the Third Treatise is a commentary on the aphorism prefixed to it. Textual studies have shown that this aphorism consists of §1 of the Treatise (not the epigraph to the Treatise, which is a quotation from Nietzsche's Thus Spoke Zarathustra).[citation needed] This opening aphorism confronts us with the multiplicity of meanings that the ascetic ideal has for different groups: (a) artists, (b) philosophers, (c) women, (d) physiological casualties, (e) priests, and (f) saints. That the ascetic ideal has been so powerful and meant so many different things is an expression of the basic fact of the human will: "its horror vacui [horror of a vacuum]: it needs a goal—and it will rather will nothingness than not will." (a) For the artist, the ascetic ideal means "nothing or too many things". Nietzsche selects the composer Richard Wagner as example. Artists, he concludes, always require some ideology to prop themselves up. Wagner, we are told, relied on Schopenhauer to provide this underpinning; therefore we should look to philosophers if we are to get closer to finding out what the ascetic ideal means. (b) For the philosopher, it means a "sense and instinct for the most favorable conditions of higher spirituality", which is to satisfy his desire for independence. It is only in the guise of the ascetic priest that the philosopher is first able to make his appearance without attracting suspicion of his overweening will to power. As yet, every "true" philosopher has retained the trappings of the ascetic priest; his slogans have been "poverty, chastity, humility." (e) For the priest, its meaning is the "'supreme' license for power". He sets himself up as the "saviour" of (d) the physiologically deformed, offering them a cure for their exhaustion and listlessness (which is in reality only a therapy which does not tackle the roots of their suffering). Nietzsche suggests a number of causes for widespread physiological inhibition: (i) the crossing of races; (ii) emigration of a race to an unsuitable environment (e.g. the Indians to India); (iii) the exhaustion of a race (e.g. Parisian pessimism from 1850); (iv) bad diet (e.g. vegetarianism); (v) diseases of various kinds, including malaria and syphilis (e.g. German depression after the Thirty Years' War) (§17). The ascetic priest has a range of strategies for anesthetizing the continuous, low-level pain of the weak. Four of these are innocent in the sense that they do the patient no further harm: (1) a general deadening of the feeling of life; (2) mechanical activity; (3) "small joys", especially love of one's neighbour; (4) the awakening of the communal feeling of power. He further has a number of strategies which are guilty in the sense that they have the effect of making the sick sicker (although the priest applies them with a good conscience); they work by inducing an "orgy of feeling" (Gefühls-Ausschweifung). He does this by "altering the direction of ressentiment," i.e. telling the weak to look for the causes of their unhappiness in themselves (in "sin"), not in others. Such training in repentance is responsible, according to Nietzsche, for phenomena such as the St Vitus' and St John's dancers of the Middle Ages, witch-hunt hysteria, somnambulism (of which there were eight epidemics between 1564 and 1605), and the delirium characterized by the widespread cry of evviva la morte! ("long live death!"). Given the extraordinary success of the ascetic ideal in imposing itself on our entire culture, what can we look to oppose it? "Where is the counterpart to this closed system of will, goal, and interpretation?" (§23) Nietzsche considers as possible opponents of the ideal: (a) modern science; (b) modern historians; (c) "comedians of the ideal" (§27). (a) Science is in fact the "most recent and noblest form" of the ascetic ideal. It has no faith in itself, and acts only as a means of self-anesthetization for sufferers (scientists) who do not want to admit they suffer. In apparent opposition to the ascetic ideal, science has succeeded merely in demolishing the ideal's "outworks, sheathing, play of masks, ... its temporary solidification, lignification, dogmatization" (§25). By dismantling church claims to the theological importance of man, scientists substitute their self-contempt [cynicism] as the ideal of science. (b) Modern historians, in trying to hold up a mirror to ultimate reality, are not only ascetic but highly nihilistic. As deniers of teleology, their "last crowings" are "To what end?," "In vain!," "Nada!" (§26) (c) An even worse kind of historian is what Nietzsche calls the "contemplatives": self-satisfied armchair hedonists who have arrogated to themselves the praise of contemplation (Nietzsche gives Ernest Renan as an example). Europe is full of such "comedians of the Christian-moral ideal." In a sense, if anyone is inimical to the ideal it is they, because they at least "arouse mistrust" (§27). The will to truth that is bred by the ascetic ideal has in its turn led to the spread of a truthfulness the pursuit of which has brought the will to truth itself in peril. What is thus now required, Nietzsche concludes, is a critique of the value of truth itself (§24). |
第3論文:「禁欲主義の理想とは何を意味するのか? ニーチェの「第3論文」の目的は、「禁欲主義者の理想が何をしたかではなく、それが何を意味するのか、何を指し示すのか、その背後に、下に、内に何がある のか、それがどのような暫定的で不明瞭な表現であり、疑問符や誤解が重ねられているのかを明らかにすること」である(§23)。 ニーチェが序文で述べているように、『第三論文』は、その冒頭に付された格言についての注釈である。テキスト研究により、この格言は『第三論文』の第1項 から構成されていることが明らかになっている(ただし、論文の題目はニーチェの『ツァラトゥストラはこう語った』からの引用である)。 この冒頭の格言は、禁欲主義の理想が異なる集団に対して持つ多様な意味を私たちに突きつける。(a) 芸術家、(b) 哲学者、(c) 女性、(d) 生理的な敗者、(e) 司祭、そして(f) 聖人。禁欲主義の理想がこれほどまでに強力で、多くの異なる意味を持つようになったのは、人間の意志の基本的な事実の表現である。「ホラー・ヴァキュー (空虚への恐怖):それは目標を必要とし、目標を持たないくらいならむしろ無を望む。」 (a) 芸術家にとって禁欲主義の理想とは、「無」または「あり余るほどの物事」を意味する。ニーチェは作曲家リヒャルト・ワーグナーを例として挙げている。芸術 家は常に、自分自身を支える何らかのイデオロギーを必要とする、と彼は結論づけている。ワーグナーは、この支えをショペンハウアーに求めたと伝えられてい る。したがって、禁欲主義の理想が何を意味するのかをより深く理解しようとするのであれば、哲学者に目を向けるべきである。 (b) 哲学者にとって禁欲主義とは、「より高次の精神性の最も好ましい条件に対する感覚と本能」を意味し、それは独立への欲求を満たすことである。 哲学者が、その強欲な権力への欲望を疑われることなく初めて表舞台に登場できるのは、禁欲的な聖職者の仮面を被っているときだけである。 しかし、いまだかつて「真の」哲学者が禁欲的な聖職者の仮面を被っていないことはなく、彼らのスローガンは「貧困、貞操、謙虚」であった。 (e) 聖職者にとって、その意味は「権力のための『最高の』免罪符」である。彼は、(d) 生理的に奇形のある人々を「救世主」と位置づけ、彼らに疲労と無気力の治療法を提供している(実際には、それは苦悩の根源に立ち向かわない療法にすぎない)。 ニーチェは、広範囲にわたる生理的抑制の原因として、いくつかの要因を挙げている。(i) 人種の交配、(ii) 人種が不適切な環境への移住(例えば、インド人によるインドへの移住)、(iii) 人種の疲弊(例えば、1850年以降のパリの悲観主義)、(iv) 粗悪な食生活(例えば、菜食主義)、(v) さまざまな種類の病気(例えば、マラリアや梅毒)、(vi) 30年戦争後のドイツのうつ病(§17)などである。 禁欲的な司祭は、弱者の継続的な低レベルの痛みを麻酔するさまざまな戦略を持っている。そのうちの4つは、患者にそれ以上の害を与えないという意味では無 実である。すなわち、(1)生命の感覚の一般的な鈍麻、(2)機械的な活動、(3)「ささやかな喜び」、特に隣人愛、(4)共同体の力の感覚の覚醒であ る。彼はさらに、病人をさらに病気にさせるという意味で罪深い戦略をいくつか持っている(ただし、司祭は良心的にそれらを適用している)。それらは「感情 の乱痴気騒ぎ」(Gefühls- Ausschweifung)を誘発することで機能する。彼は「ルサンチマンの方向を変える」ことによってこれを実行する。すなわち、弱者に対して、自分 たちの不幸の原因を他人ではなく自分自身(の「罪」)に求めるように教えるのである。このような悔恨の訓練が、中世の聖ヴィート舞踏病や聖ヨハネ舞踏病、 魔女狩りによるヒステリー、夢遊病(1564年から1605年の間に8回も流行した)、「死を讃えよ!」という叫び声が響き渡るせんもう状態などの現象を 引き起こしたと、ニーチェは考えている。 禁欲主義の理想が我々の文化全体に強制的に押し付けられたという異常な成功を考えると、それに対抗するものは何だろうか?「意志、目標、解釈という閉鎖的 なシステムに対抗するものは何だろうか?」 (§23) ニーチェは、理想の対抗勢力となり得るものとして、(a) 近代科学、(b) 近代の歴史家、(c) 「理想の道化師」 ( §27 ) を挙げている。 (a) 科学は、実際には禁欲的理想の「最も新しく、最も高貴な形」である。科学はそれ自体を信頼しておらず、苦しんでいることを認めようとしない苦悩する人々 (科学者)が自己を麻酔する手段としてのみ機能する。禁欲主義の理想とは明らかに反対の立場に立つ科学は、その理想の「外皮、鞘、仮面の遊び、... その一時的な凝固、木化、教条化」を打ち壊すことに成功したにすぎない(§25)。科学者たちは、人間が神学的に重要であるという教会の主張を打ち壊すこ とによって、自己嫌悪[シニシズム]を科学の理想に置き換えている。 (b) 究極の現実を映し出す鏡になろうとする近代の歴史家は、禁欲的であるだけでなく、きわめて虚無的である。目的論を否定する彼らの「最後の勝利」は、「何のために?」「無駄だ!」「ナダ!」である。 (c) さらに悪い種類の歴史家は、ニーチェが「観想家」と呼ぶ人々である。すなわち、観想の賞賛を独り占めした自己満足の安楽椅子ヘドニストである(ニーチェは アーネスト・レナンの例を挙げている)。ヨーロッパにはこのような「キリスト教道徳的理想の道化師」が溢れている。ある意味では、理想に敵対する者がいる とすれば、それは彼らである。なぜなら、彼らは少なくとも「不信を呼び起こす」からだ(§27)。 禁欲主義の理想によって育まれた真理への意志は、その一方で、追求すること自体が真理への意志を危険にさらすような誠実さの蔓延につながった。ニーチェは結論として、今こそ必要なのは、真理そのものの価値に対する批判であると述べている(§24)。 |
| Reception and influence The work has received a multitude of citations and references from subsequent philosophical books as well as literary articles, works of fiction, and the like. On the Genealogy of Morality is considered by many academics[3] to be Nietzsche's most important work, and, despite its polemical content, out of all of his works the one that perhaps comes closest to a systematic and sustained exposition of his ideas.[4] Some of the contents and many symbols and metaphors portrayed in On the Genealogy of Morality, together with its tripartite structure, seem to be based on and influenced by Heinrich Heine's On the History of Religion and Philosophy in Germany.[citation needed] In philosophy, the genealogical method is a historical technique in which one questions the commonly understood emergence of various philosophical and social beliefs by attempting to account for the scope, breadth or totality of ideology within the time period in question, as opposed to focusing on a singular or dominant ideology. In epistemology, it has been first used by Nietzsche and later by Michel Foucault, who tried to expand and apply the concept of genealogy as a novel method of research in sociology (evinced principally in "histories" of sexuality and punishment). In this aspect Foucault was heavily influenced by Nietzsche. Others have adapted "genealogy" in a looser sense to inform their work. An example is the attempt by the British philosopher Bernard Williams to vindicate the value of truthfulness using lines of argument derived from genealogy in his book Truth and Truthfulness (2002). Daniel Dennett wrote that On The Genealogy of Morality is "one of the first and still subtlest of the Darwinian investigations of the evolution of ethics".[5] Stephen Greenblatt has said in an interview that On The Genealogy of Morality was the most important influence on his life and work.[6] |
受容と影響 この著作は、その後の哲学書や文学記事、小説などから多数の引用や言及を受けている。『道徳の系譜』は多くの学者たちによって[3]ニーチェの最も重要な 著作とみなされており、その論争的な内容にもかかわらず、彼の著作のなかで最も体系的に持続的な彼の思想の展開に最も近いものと考えられている[ 4] 『道徳の系譜学について』の内容の一部と、数多くの象徴や隠喩は、その三部構成とともに、ハインリヒ・ハイネの『ドイツの宗教と哲学の歴史について』を基 にしており、影響を受けていると思われる。 哲学において、系譜学的方法とは、単一または支配的なイデオロギーに焦点を当てるのではなく、問題となっている時代におけるイデオロギーの範囲、広さ、ま たは全体性を説明しようと試みることで、一般的に理解されている様々な哲学や社会的な信念の発生を問う歴史的な手法である。認識論では、ニーチェが最初に 用いたこの用語は、後にミシェル・フーコーによって社会学における新たな研究方法として系譜学の概念を拡大し応用する試みが行われた(主に「性の歴史」や 「処罰の歴史」に顕著である)。この点において、フーコーはニーチェから多大な影響を受けている。 また、より緩やかな意味で「系譜学」を自身の研究に適用した人物もいる。その一例として、イギリスの哲学者バーナード・ウィリアムズが著書『真理と誠実 さ』(2002年)で、系譜学から導き出された論拠を用いて、誠実さの価値を正当化しようとした試みが挙げられる。ダニエル・デネットは『道徳の系譜』に ついて、「倫理の進化に関するダーウィニズムの研究の最初期のものであり、今なお最も緻密なもののひとつである」と書いている。[5] スティーヴン・グリーンブラットはインタビューで、『道徳の系譜』が自身の人生と作品に最も大きな影響を与えたと語っている。[6] |
| Editions The Birth of Tragedy & the Genealogy of Morals, translated by Francis Golffing, Anchor Books, 1956, ISBN 0-385-09210-5 On The Genealogy of Morals and Ecce Homo, translated and edited by Walter Kaufmann (translation of On the Genealogy in collaboration with R. J. Hollingdale), New York: Vintage, 1967; this version also included in Basic Writings of Nietzsche, New York: Modern Library, 2000, ISBN 0-679-72462-1. On the Genealogy of Morality, translated by Carol Diethe and edited by Keith Ansell-Pearson, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, ISBN 0-521-87123-9. On the Genealogy of Morals, translated and edited by Douglas Smith, Oxford: Oxford World's Classics, 1996, ISBN 0-19-283617-X. On the Genealogy of Morality, translated and edited by Maudemarie Clark and Alan J. Swensen, Indianapolis: Hackett, 1998, ISBN 0-87220-283-6. Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der Moral, edited by Giorgio Colli and Mazzino Montinari, Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2002. The Genealogy of Morals, translated by Horace Barnett Samuel, New York: Courier Dover Publications, 2003, ISBN 0-486-42691-2. On the Genealogy of Morals, translated by Michael A. Scarpitti and edited by Robert C. Holub (Penguin Classics) 2013. ISBN 0141195371 |
エディション 『悲劇の誕生』および『道徳の系譜学』、フランシス・ゴルフィング訳、Anchor Books、1956年、ISBN 0-385-09210-5 『道徳の系譜学』と『 Ecce Homo』の翻訳および編集はウォルター・カウフマン(『系譜学』の翻訳はR. J. ホリンデイルとの共訳)、ニューヨーク:ヴィンテージ、1967年。このバージョンは『ニーチェ著作集』にも収録されている。ニューヨーク:モダン・ライ ブラリー、2000年、ISBN 0-679-72462-1。 『道徳の系譜学』、キャロル・ダイス訳、キース・アンセル=ピアソン編、ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、1994年、ISBN 0-521-87123-9。 『道徳の系譜学』、ダグラス・スミス訳、オックスフォード:オックスフォード・ワールド・クラシックス、1996年、ISBN 0-19-283617-X。 『道徳の系譜学』、モーダマリー・クラークとアラン・J・スウェンセン訳、インディアナポリス:ハケット、1998年、ISBN 0-87220-283-6。 『善悪の彼岸』、ジョルジョ・コッリとマッジーノ・モンティーナリ編、ミュンヘン:ドイツ・タッシェンブッハ・ヴェルラグ、2002年。 『道徳の系譜』、ホレス・バーネット・サミュエル訳、ニューヨーク:Courier Dover Publications、2003年、ISBN 0-486-42691-2。 『道徳の系譜について』、マイケル・A・スカルピッティ訳、ロバート・C・ホラブ編(ペンギン・クラシックス)、2013年。ISBN 0141195371 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Genealogy_of_Morality |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆