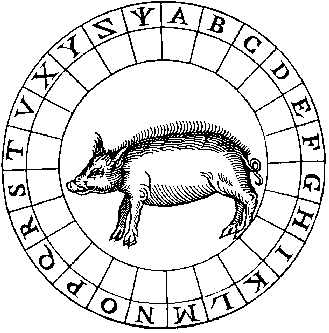ingles..

グローバル化する近代医療と民族医学の再検討
ingles..

1.はじめに
さて私は、本プロジェクトに参画する以前に、「世界医療システム」(拙著『実践の医療人類学』第3章、2001年)という文章のなかで、グローバル化す
る近代医療を「世界医療システム」と名付け、考察をおこなった。ウォーラスティンの世界システムの理論からすると、そのシステムの中に分節化され自律的な
システムを含意する「世界医療システム」を概念化するのは形容矛盾であるように思われる。この用語法はシンガーとベアの提唱した用語だが、私が言わんとし
たのは、彼らの理論が前提とする近代医療と伝統医療の二元論の理論的批判を通して、この概念を脱構築したいからであった。彼らの理論に対する私の論難はた
だ1点である。彼らが世界医療システムという概念を提示する際に、その用語を通して(それもかなり道徳的非難を込めた)近代医療批判をおこないためであ
り、そのために伝統医療の概念が「近代医療に欠けているもの」という理論的空虚(theoretical
vacuum)に訴えるという修辞法をとっていることであった。このような伝統医療のイメージの理解は、文化人類学の学説史における医療人類学の最初の勃
興時に好んで使われた近代医療批判の起爆剤として伝統医療という一種のルートメタファーとも言えるもので、今日までつづく医療現象における多元性をすべて
文化の差異で片づけようとする際に人類学者が大衆に訴えかけるもののひとつである。
フィールドワークの現場においてはほとんどありえ ない伝統医療のユートピアがそこにはある。しかし誰もそのような理論的理想が生起する場(フィールド)に立ち会うことはほとんど稀であろう。現実は、なに なに医療という峻別がむなしいほど概念が混雑しており、また個々の病気の発生は偶発的であると同時に、その処遇は事後的にみるかぎり唯一なものである。概 念的に区分される近代医療と伝統医療はもっと補完的であり、全体論的な行為実践のなかに包摂されている。また先の文書の中で、言い足りないと事後的に私が 思ったのは、世界医療システムの中に包摂されたと思しき(シンガーとベアを含めた)我々がおこなっている営為は、そのシステムの外に立って容易に批判の対 象とできるようなものではなく、我々じしんそのものが世界医療システムという環境(=世界 Welt)に住まうエージェントそのものではないかという自己批判が、我々には欠けている[のではないか]という認識である。
このような自己反省に立てば、次に何をやるべきか は明らかになる。全地球的拡張を目標にする(あるいはそのように見える)医療を、シンガーとベアの視点ではないもうひとつの〈世界医療システム〉論という 観点から眺めることである。彼らの対抗概念である、もうひとつの〈世界医療システム〉を明確に定義したいというのが私の理論的悪あがき(つまり未だ成功し ていない)なのであるが、そのためにコスモポリタンという一度マーガレット・ロックに使われた医学のカテゴリーを指した用語を掘り起こして考えた。奥野先 生らと始めた帝国医療や植民地医療、あるいは開拓医学(飯島 2000)という一連の歴史学から提唱された医療概念の研究がある。国際協力ボランティア (池田 投稿準備中)はグローバルポリティクスという世界医療システムを実現するエージェントの重要なひとつであると考えている。また、存在の普遍性とい う観点から考えると、亡霊や幻覚(ファントム)の存在に関する意味論の研究が重要になり、ファントム・メディシン(『熊本文化人類学』第4号、Pp.93 -98)という枠組みで、医療システムが我々に与える偏見を相対化してくれるかもしれない。
このようなことを私がこだわり続ける理由は、世界
医療システムのエージェントかもしれない人類学者の社会的役割について、単に研究対象を観相するだけでなく(でないとシンガーとベアの陥った穴に戻ること
になる)まさに同時進行的に考えたいということである。それは「すでに研究しつくされたこと/すでに判っていることをなぜ私は延々とおこなうのか」という
諦めからくる倦怠に抗して、能動的無為(今村 2005)を実践するひとつの方法になりうることを私は願っているからである。
2.人類学の役割
人類学理論の変化は、人類学者に期待されている社会的役割概念(social roll
concept)の変化と関連しているだろうか。人類学理論の推移において、ある研究対象を採用し別の対象を忘却することは、人類学者自身の実践的関与の
タイプを変形(transform)させることに繋がるのだろうか。研究対象が変われば、研究の視座は変化するが、同時にその研究者の実践的関与の形態も
変わるだろうか。私にとって検討が必要であると考えるのは、これらの事柄である。
専門家がこのような発想をナイーブなものとして退 けることは十分に考えられる。なぜなら、これらの事態を容認することは、人類学者が生産する民族誌に対して実証的ではないというある種の不完全性を証明す ることに繋がり、他の研究領域に対して科学の客観性を保証できないことを意味するからだ。他方で、これらの事態――研究対象の変化に伴う、研究者の実践的 関与の形態の変化――を容認するとしても、人類学という学問の独自性の根拠が失われるという非難が、またもや専門家から表明されよう。なぜなら、この新し い人類学の生成は、例えばカルチュラルスタディーズや社会学などの学問領域と人類学分野の境界線を曖昧にしてしまうからである。研究対象の相同は、研究態 度の相同を意味するからである。このような学問のアイデンティティに関わる専門家が抱く危惧を生み出す背景にあるのは、元をただせば、研究対象の限定から 研究者の役割概念が構築されてきたノーマルサイエンス独特の政治的運用という現状肯定の論理に他ならない。研究者の誰もが常識には背きたくはないのだ。し かし、トーマス・クーンが想定した科学者集団の内的な異常科学の台頭のみならず、彼が認めたがらなかった科学者集団の外部にある社会的要因によっても、 ノーマルな科学の運用論理もまた変化し、時には瓦解することがある。断固として依拠しなければならない学問のアイデンティティは、実はぐらぐらとふらつく 浮島のような存在であった。
しかも、それは何も人類学分野だけが陥っている行 き詰まりや難問なのではなく、今日では社会科学全般が抱えている、ないしは抱えうる状況そのものである。クリフォード・ギアーツの指摘によれば、このこと は遅くとも1960年代にはじまっており、社会科学が自然科学的な合理的モデルよりも、人文科学的な修辞の彩という類比的想像力を動員する傾向が増えるこ とに特徴づけられている(ギアーツ 1991)。
とにかく、人類学の研究対象は次々と新しく生ま れ、それに伴い、さまざまな理論用語が考案されてきた。今を生きる人類学者は、それらを使って理論構築(つまり理論を消費)しつつ、自分の「フィールド データ」を使って民族誌論文を生産しなければならない。このスタイルはこれからも続いていくだろう。ここから離脱することは、研究者のコミュニティにおい ては、特異な研究者として位置づけられるか、学界から葬り去られることを意味する。
理論用語をフィールドデータを使って明確に説明、 解釈し、民族誌論文に仕立てあげる実践と、その生産の〈手口〉を同時に考察の対象にすることは、由緒正しい実証主義の伝統からの逸脱を意味する。だが、し かし英語圏の人類学ではすでに1980年代から、このような試みは活発におこなわれている(cf.クリフォード 2002; Marcus and Fischer 1999)。そうした時に、浮かび上がるのは次のような疑問である。例えば、調査者でも被調査者でもよい、民族誌調査に関わる行為主体のアイデンティ ティ・ポリティクスについての反省から、グローバル化するさまざまな社会的文脈における新しい理論言語が生産されている。それらは研究対象のみならず、研 究対象を構築する調査者自身のポジションの変化あるいは、行為主体の内的変化を起こすはずだということを私は予感する(cf. ギアーツ 1996)。このような状況の中で、いったい人類学者は何を問題にすべきなのか。
それは、行為主体(agency)の変形に関わる
問題であると私は考える。私自身の専門領域である医療人類学において、研究主体と研究対象というものが、どのような過程を経て、変形していることを示唆す
るのか、ということである。
3.コスモポリタンの思想圏
私がこの問題系において、常々気になっている理論用語がある。それは行為主体のアイデンティティの編制に深く関わる用語であり、また、形容詞となって事
物の様態を指し示すものにもなる言葉である。コスモポリタン(cosmopolitan)という言葉がそれだ。
この言葉は、紀元前5世紀頃の古代ギリシャの都市シノペ出身のディオゲネスに由来する。彼は禁欲と質素を旨とし、奴隷の身にやつしながらも、自己のプラ
イドを高くもち、精神と行動の自由を謳歌する実践的態度を貫いた人だと、後の評伝は伝える。3世紀初めに彼について短い消息を書いたディオゲネス・ラエル
ティオスによると次のごとくである(ディオゲネス・ラエルティオス 1984;なお、ページ数は引用文献の該当箇所を、/は改行を表す])。
「とにかく自分[=シノペのディオゲネス―引用者]は、/祖国を奪われ、国もなく、家もない者。/日々の糧をもの乞いして、さすらい歩く人間。/なのだか
ら。しかし彼は、運命には勇気を、法律慣習には自然本来のものを、情念には理性を対抗させるのだと主張していた」(p.141)。
「あなたはどこの国の人なのかと訊ねられると「世界 市民(コスモポリテース)だ」と彼は答えた」(p.162)。
「彼は、高貴な生まれとか、名声とか、すべてそのよ
うなものは、悪徳を目立たせる飾りであると言って冷笑していた。/また、唯一の正しい国家は世界的な規模のものであると。/さらにまた、婦人は共有である
べきだと言い。そして結婚という言葉も使わないで、口説き落とした男が口説かれた女と一緒になればいいのだと語っていた。そしてそれゆえに、子供もまた共
有であるべきだと。/また神殿から何かを持ち去るとか、あるいは、ある種の動物の肉を味わうとかすることは、少しも異様なことではないし、さらに、人肉を
食べることさえも、異国の風習から明らかなように、不敬なことではないとした」(p.170)。
ディオゲネスの生き方を、今日的に表現すれば既述したように、禁欲と質素を旨とし、自己のプライドを高くもち、精神と行動の自由を謳歌する実践的態度を
貫くということであろう。もちろんここで問題としたいのは、世界市民つまりコスモポリタンが意識する自己の帰属集団とアイデンティティについてである。コ
スモポリタンが帰属する「唯一の正しい国家は世界的な規模のもの」である。世界的な規模とは、包摂するものがないことと紙一重である。「自分は世界市民で
ある」という言明は、人間の属する集団としてもっとも広い集団に属するが、他方ではそれは「自分は人類だ」と言明するのと同じで、世界市民を包摂する現実
的社会集団は、現実にはどこにも存在しないということになる。
コスモポリタンを包摂する社会集団を、我々が脅迫
的にほとんど毎日のように反復して想起している国民国家(西川 1998)や政治、宗教集団あるいは文明(Huntington
1993)との対比の中で見ると、我々の想像力の有限性がかいま見える。今日の政治言語だと、類的な存在としての人間のもっとも広い帰属集団を想定はする
が、国際主義者(internationalist)よりももっと強度のある無政府主義者としか言いようがないものになるからだ。昭和12(1937)年
に三木清は、コスモポリタンにおける自由主義の立場が、政治システムでもなく、かといって文化主義でもないと説明し、「コスモポリタンとは政治への信頼を
失つた人間のことである」と主張している(三木 1967)。もっともな見解であろう。実際、コスモポリタンという言葉は、現実の政治的帰属集団から最も
遠いところにいるというニュアンスで使われる。あるいは、政治的な集団に帰属しないと考えられている信条や実践――以下で展開する〈医術〉(イアトリ
ケー・テクネー)もそのひとつである――の行使者が、特権的に享受することができる、つまり政治的イデオロギーから免疫された〈政治的標識〉と言うことも
できよう。
4.コスモポリタン医療
コスモポリタンという形容詞は、医療人類学では、医学や医療という名詞に冠されて、西洋近代医療のことを指す言葉として流通している。コスモポリタン医
学あるいはコスモポリタン医療(cosmopolitan
medicine)がそれである。この用語法では、2つのニュアンスを見いだすことができる。まず最初に、(1)医療者の間では西洋近代医療はすでに十分
な世界覇権を確立したものであるという意識の共有だ。このことは、西洋近代医療が現実には様々な理論と技術の混成体であり、時間的にも全く異なった概念や
治療法が次々と生み出されてきたにも関わらず、一枚岩の理念と実践をもつ医療システムであるという社会的合意が確立していることを示唆している。他方、こ
の医療は、コスモポリタンを普遍的な政治不信として定義した三木清の用語法になぞらえて、(2)政治的に中立な立場、つまりイデオロギーから自由である医
療を暗示している。これがもうひとつの意味である。
医療と医療者がコスモポリタンになる理由のひとつ は、その治療の有効性と普遍性への揺るぎない信仰にある。もちろん西洋社会の内部からも正統派医学に対する反発はあった。19世紀初頭のドイツのホメオパ シーに代表される対抗概念としての代替医療。20世紀の後半に登場する、反精神医学(e.g. レインとエスターソン 1972)、反近代医療(e.g. イリッチ 1979)などの主知主義的反発。公衆衛生的観点からの抗生物質の有効性への批判(e.g. マキューン 1992)を通して、近代医療の治療有効性を再考する学派の登場など。これらの思潮が繰り返し歴史の舞台に登場するにも関わらず、西洋近代医 療の有効性への信仰が揺るいだ時期はじつは極めて少ない。
西洋近代医療が、コスモポリタンとして認められう る証拠は少なからずある。まず、世界の多くの近代国家において公的に採用され、それに準じた医学教育がなされていること。さらに、全世界での西洋近代医療 の実施形態は、多様性があるにも関わらず基本的には同質であると考えられていること。繰り返すが、現実には西洋近代医療――類比としての〈遺伝型〉――の 要素がパッチワークされているにもかかわらず、それは西洋近代医療のあり方――類比としての〈表現型〉――の多様性とは見なされていない。多様性の違い は、ただ単に(高い/低いという表現を用いた)医療の水準の違いで表されている。この表現は、経済人類学の実体主義派(substantibist)が強 調して止まない〈経済〉システムの多様性を形式主義者(formalist)が忘却して、半ダースほどの経済指標の高低で表現するやり方と同じだ。医療者 になるには、医療の水準の〈低い〉ほうから〈高い〉地域の教育機関に留学や研修に出かける。また〈高い〉水準の医療者が〈低い〉水準の地域に対して援助を おこなったり、医学生を教育実習するために派遣される。コスモポリタン医療の内部には不均衡や不平等があるにもかかわらず、この医療システムで教育をうけ た医療者は、世界中どこでも有効な治療者として機能することが期待されている。その典型的な例は飛行機の客室乗務員による次のようなアナウンスだ:「どな たかこの機内に医師の方はいらっしゃいませんか?」
コスモポリタンとしての西洋近代医療が、国境を越 えた医療的実践として、正当化されるのは、戦場や災害現場における赤十字、赤新月などの団体による緊急医療支援活動やODAやNGOによる国際医療協力の 現場においてである。あるいは、第二次大戦後のナチスの人体実験を教訓にして提言されたヘルシンキ宣言や核兵器の廃絶を訴える医学者たちの社会運動にも、 そのような特質が現れている。コスモポリタン医療は、その利用現場における倫理の確立においても制度化されてきたのである。コスモポリタンとしての医師 は、しばしばヒューマニストとしての医師像と重なる。コスモポリタンの医師は患者を治療すると同時に、病いの原因をつくる社会の病理をも治療するのであ る。私は、このような行為原則と理念を、19世紀ドイツ自由主義的ブルジョアジーの論客であった医学者の名前を冠して「ウィルヒョウ・ドクトリン」と名付 けたことがある(池田 2001:298)。冷戦期には、第三世界の医師や医学生が国際共産主義運動やゲリラ戦争に参入していったが、この実践的医療者の アイドルになったのはノーマン・ベチューン(1890-1939)やチェ・ゲバラ(1928-67)であった。
しかし、国際政治の現場でイデオロギー的に中立な 立場を表明しようが――人間の生き方としてのコスモポリタンとは異なり――制度としてのコスモポリタン医療が権力そのものを呪ったり、そこから完全に自由 になれる訳でもない。SARS(Severe Acute Respiratory Syndrome、重症急性呼吸器症候群)対策をおこなう中国政府や北京市の衛生当局へのWHOの行使した国際的圧力にみられるように、医療の人道的概念 を武器に国際政治を現実には行なっているし、その行使もまた特殊なものとは言えない。他方、コスモポリタン医療を、世界中で誰にでもアクセス可能で平等な 医療として考えることも限界がある。フランツ・ファノン(1984)によれば、普遍性をもつ西洋近代医療も、植民地解放闘争の文脈において統治者が被植民 者に行使すれば、治療のシステムは容易に拷問のシステムに変わりうる。これらの批判は、コスモポリタン医療の行使を、社会的文脈から切り離して政治的に中 立化(=免疫化)して捉えることができないことを表している(cf. 池田 2001:325-7)。
コスモポリタン医療をめぐるさまざまなエピソード
から明らかになったことは、次の3点である。(1)コスモポリタンとしての医師像にみられる政治的理想主義ないしはラディカリズム。これはシノペのディオ
ゲネスが二千数百年前に〈生き方〉をもって提示した神話的原型とさほど違いはない。そして(2)形容詞としてのコスモポリタンが冠された西洋近代医療の存
在形態としての〈世界性〉や〈普遍性〉、あるいはそのように見える現在の社会的性格の標識。これは、それ自体では自己反省機能をもたず、ただ現在を席巻し
ている支配的なイデオロギーの一つにしかすぎない。そして、最後に(3)この両者の間の驚くべき落差である。〈生き方〉と〈普遍性の標識〉という対比は、
このエッセーの冒頭で述べた人類学者の〈実践的関与〉と〈人類学理論〉の対比に相当する。この両者の間の落差、とくに前者に対する後者が「堕落」したよう
に見えるのはなぜか。我々はコスモポリタンという形容詞の使い方をただ単に誤っただけなのだろうか。つまり、西洋近代医療がグローバル化した社会状況の中
で自らのヘゲモニーを確立したとき、それを(どこにも故郷を持たないという〈普遍性〉を真似て)コスモポリタンと呼んでいるにすぎないのだろうか。歴史的
相対主義以外の別の回路を通して、西洋近代医療のコスモポリタン性を解明する必要がありそうだ。
5.普遍化する方法としての帝国主義
医療と医療者のコスモポリタン化に貢献した可能性はいくつかあるが、その要因のひとつが帝国医療(imperial medicine)である。
近代西洋医療がなぜ19世紀後半から急速に全世界 に普及し、コスモポリタンとしての地位を獲得するようになったのだろうか(池田 2002:313-4)。帝国医療の歴史研究者によれば、それは帝国統治 の道具(tool)として近代医療がフルスロットルで作動したからだと説明される。このような説明は、軍陣医学(military medicine)の先駆けの時期に勃発したクリミア戦争(1853-56)の傷病兵の死亡率をフローレンス・ナイチンゲールが著しく改善したという逸話 が、今日では神話に属する物語(スモール 2003)にすぎないなど、さまざまな反証事例(negative instance)から、十分に適切なものとは言えない。ちなみにクリミア戦争の兵士の傷病率/死亡率は、近代戦争における軍陣医学の科学的指標として標 準化されたものの一つである(cf. 陸軍軍医学校 1988[1936]:250-252)。
帝国医療は、西洋近代医療の有効性により支配の道 具になったというよりも、帝国が西洋近代医療に託した統治術(art of governance)の発達と普及の結果、人々をして、その有効性を信じさせる道具であったのだ。少なくとも、帝国医療の有効性に関する研究は端緒につ いたばかりであり、現在のところ、その効力――しばしば公衆衛生的指標によって測定される――についての議論において、決定的な結果が出ているわけではな い。国家総力戦と同様、遂行中の戦争がどのような帰結をもたらすかは誰にも解らない。そしてまた帝国医療システムが歴史的に示した有効性と科学的手続きに よる個別要素の〈有効性〉の確証を得ることは難しいだろう。
ところで帝国医療とはいったいどのような医療のこ とを指すのだろう。帝国医療の用語法の観点からここで整理してみよう。
近代医療や熱帯医療には教科書があり、教育内容に はディシプリンがある。しかし、帝国医療や植民地医療(colonial medicine)には教科書はない(cf. 飯島 2000)。また教育内容においても独自のディシプリンは存在しないように思われる。ディシプリンとは、ここでは原理にもとづいた訓練と理論の混成 集合体のことを指す。近代医療と帝国医療の違いは、まず単純にそう言えるのではないだろうか。前者、つまり近代医療や熱帯医療は実体化された医療であり、 後者つまり帝国医療や植民地医療は抽象化された分析概念である。帝国医療は、ある政治空間のなかに居場所をみつけた医療であり、統治性という技術体系との 隠喩的連関から払拭できない医療のことである(フーコー 2000:258-260)。
したがって、近代社会の統治術概念から導き出され た植民地の医療システムとしての「帝国医療」を研究するとは、なによりもそれが使われる歴史・社会的文脈の中に位置づけて具体的に議論しなければならない ことになる。脇村孝平(2002)らの歴史家たちが、この用語を鍵概念にして解き明かそうとしているのは、英国のインドを中心とする帝国統治のシステム が、中心地で論じられていたイデオロギー以上に、臣民(subject)への身体や集団への管理の具体的諸相に着目することにあった。
他方、人類学研究において、生産的議論を導く装置 として帝国医療の概念を流用することは可能であろうか。その際には、歴史家たちが提唱していた概念にもともと含まれていた歴史ならびに社会的文脈から自由 になれる代償として、帝国医療を近代医療や熱帯医療と同一視したり、それらの相互の「医療」に含まれる諸々の特徴を相互に交換可能な要素として拡大解釈す るという危険をあえて犯さねばならないかも知れない(奥野 印刷中)。
あるいは、もはや歴史的には終焉したと宣言されて いる事柄に、人類学者は未だに異議を申し立てているのかも知れない。かつての新帝国主義論や新植民地主義(neo-colonialism)による世界経 済批判のように、帝国医療や植民地医療は終わっていないと人類学者は自分のフィールドでの経験をもとに、敢えて主張しているのかも知れない(ルクレール 1976;太田 2003)。
そのような理論の無制限な拡張および用語法の政治
的先鋭化という危険を承知で、今しばらく知的冒険を試みることが許されるならば、我々は帝国医療がもつ主要な特徴をさまざまな諸事例から抽出・検討し、あ
る歴史・社会的文脈の中でその医療システムが帝国医療として作動可能になる社会的条件を明らかにしなければならない。歴史学における「帝国医療」という専
門用語と区別して、このような医療システムのモデルを「帝国医療システム」というふうに呼び、帝国医療という用語と緩やかに使い分けておく。
6.日本という問題系
さて、帝国医療や植民地医療は分析概念としてよく言及されるようになってきたが、かつては近代生物医療(modern
bio-medicine)による帝国支配や植民地支配への非難や罵倒という価値判断をたっぷり含んだ政治用語であった。他方、近代医療は西欧の由緒正し
き医療であり、それを利用する民族や人種を超えて利用可能なコスモポリタンな医療と見なされている。熱帯医療(tropical
medicine)は、帝国や植民地統治のエージェントが関与したという点では手垢にまみれているが、研究対象と達成すべき目標――熱帯病の征圧――が社
会的合意を得られやすかったゆえに、旧植民地からの非難を受けることはこれまで少なかったと言える。しかし、現在においてもなお、熱帯医学/熱帯医療の研
究の随所に、熱帯起源の病気と現地の社会を「未開な文化的慣習」「遅れた社会制度」「怠惰な住民」といった植民地言説に無反省に関連づけることをしばしば
目撃することがある。
そういう中に、我々の医療はどのように位置づけら れるのであろうか。日本の医療は、独自な文化慣習や行動様式によって今なおその進歩を妨げられているのだろうか。日本の旧態依然とした医療制度によって日 本人は健康の達成を妨げられたのだろうか。日本の帝国医療における日本人とは、それを実施する主体であろうか、それとも帝国医療の対象だったのだろうか。 そしてまた、私が日本ないしは日本人という用語を連発する時、それらはどのような空間を指し、どのような種類の人間のことを言っているのだろうか。
私の結論を先に指摘しておこう。
後発帝国主義国であった日本は、欧米の帝国主義的 近代の様々な社会的諸装置をパッチワーク的に導入しながら、同時に強い人種拝外主義によって、独自でユニークな帝国医療システムを作り上げた。その中で医 療制度もまた創意工夫され独自の発展を遂げてゆく。しかしながら、制度や理念の変化に社会の側は追いついていかず、医療はつねに未来に向かう健康達成のプ ロジェクト(cf. 高橋 1969)であるという幻想を人々に懐かせたまま、第二次大戦の終結を迎える。これが日本の帝国医療が「未完の」プロジェクトであったと私が信ずる 点である。このプロジェクトは、西欧の近代化プログラムの模倣であり、普遍的な方法を現地社会に適合させようとする時におきる、現地側からの反応に基づい て、独自の展開をとげていった。
西洋近代医療の普及過程にみられる、我が国のユ ニークな特性を3つ指摘しておこう。つまり、まず最初に(1)医療の西洋近代化の過程は、かつて言われてきたようなシステムの全面入れ替えではなく、試行 錯誤を踏まえた漸進的な変化であった。そのため、漢方のような医療システムも完全に駆逐されることなく、むしろ医療の多元化をおしすすめることに貢献した ということ。つぎに(2)統治技術としての西洋近代医療は最初から成功を収めていたという認識は、医療者たちの間には、それほどなかったということ。そし て(3)医療化を推進させる根拠としては、医療を通して国民および帝国の臣民を壮健にする目的よりも、医療をより科学化することに強い動機が置かれていた ということ。
これらのプロジェクトの理念は、国家医療
(national state
medicine)から帝国医療に展開するときにも、それらの展開パターンを引き継ぎ、そして帝国医療そのものの枠組みが消滅しても、つまり大日本帝国が
実質上消滅しても、戦後一貫して継承されていったというのが私の見解である。
7.未完的継続の諸特性:コスモポリタンの探求
いましばらく、この帝国医療システムの3つの特性の現在までの継承性について、言葉を重ねてゆこう。
(1)近代日本の医療は、明治維新以降、激烈にシステム変換したと言われるが、これは国家が採用する公的な医療システムにおいてである。実際には近代医療
を採用する以前から蘭方医療(オランダ経由の近代医学)が存在し、天然痘対策の種痘にはこの医療システムが有効に機能した。また、公的医療から排除された
漢方医も直接根絶対象となったわけでもない。漢方医の教育が公教育によってなされなかったゆえに、後継者のリクルートができず、影響力の基盤であるマンパ
ワーが枯渇していったのである。社会における医療システムの移行という観点から見れば、近代医療への移行は緩やかに進行したと考えられる。これは、今日に
おける多元的医療状況の原因であり、クライアントも治療資源の選択には仮定法的態度がひろくみられるという医療行為からも示唆することができる。
(2)国家の統治技術としての近代医療の適用が、もっとも激烈におこなわれたのは、「避病院」(伝染病隔離)や「癲狂院」(精神病者の拘禁)への収容政策
であり、当初は患者や家族による抵抗に出会う。しかしながら、共同体は国家政策のエージェント機能の末端としてその役割を十全に担い、全国で広範囲に行わ
れた散発的な反抗――たとえばコレラ騒動における外国人排斥や医療者さらには癩病者へのリンチ事件など――が最終的に集合的な行為としての医療批判運動に
発展しなかったし、そのどの反抗もまた制度を機能不全にまで陥らせるには至らなかった。これらの住民の偶発的な反発に対して、国家は警察権力をもって鎮圧
しただけで、統治システム改善のための教訓とはせず、また法的な整備も行わなかった。この種の国家的伝統は、今日における病者差別や国家賠償制度の不備と
いう事態に色濃く継承反映されている。例えば、水俣病認定やハンセン病者への国家賠償責任などは、当事者からみれば未だ係争中の問題であることでも明らか
である。
(3)近代医療はつねに輸入されつつその中身は欧米の水準に追いつくべきものであるという一貫した国家政策は、結果的に医療者のイメージを、草の根レベル
の実践家ではなく研究をおこなう科学者として定着させた。そのため国家の医療政策は、医科学を常に向上させる政策に傾き続け、医療を福祉サービスのエー
ジェントとして転換することができなかったのである。世界の近代国家の中でも近代医療が定着したにもかかわらず、日本では常に人々に根強い近代医療不信と
医療化被害に見舞われた社会となった。
8.近代合理化の袋小路
言うまでもなく日本の植民地統治は歴史的には後発の部類に属し、また帝国を構築していた周辺部分では1930年代以降、事実上交戦状態にあったために、
帝国の社会基盤整備の装置として近代医療を十分に発動機能させることができなかった。これらの特徴は日本の植民地人類学の事情にも通底すると言える(中生
2000)。また万能科学としての医療に対する専門家たちの信仰は、とくに1930年代以降、今日ではいかにも奇妙で歪(いびつ)ともいえる現象を引き
起こした。
例えば京都帝国大学出身の石井四郎[1892- 1959]は陸軍に軍医として入り、1933年東京の陸軍軍医学校の防疫研究室を経て、1936年(昭和16年)に関東軍防疫部長に昇進し、細菌兵器の開 発に中国人やモンゴル人をつかった人体実験を組織的におこなった(cf. 常石 1999)。京都帝国大学で石井の研究指導をおこなっていた清野謙次[1885-1955]は専門の病理学以外にも、人骨の解剖学研究や統計的手法 による日本人の起源論に一石を投じた人として知られているが、1940年代に大学を辞職してから、太平洋協会に属し、膨大な民族医療の文献を渉猟して、 『インドネシアの民族医学』という、今日の医療人類学の先駆けとも言える研究をしている(清野 2001[1943])。もちろん清野は土着医療(「固有 医学」「民族医学」)に対する西洋医療(「真正医学」)の勝利を信じて疑わないのだが、後者の普及のためには現地人社会の理解が欠かせないと主張する。ま た毒矢の塗り薬などに代表される生薬の知識を、今日で言うところの生物資源としてきちんと記録し、それらの成分を化学分析を通して明らかにすることが「真 正医学」への貢献となることを的確に指摘している。清野を太平洋協会に招いたのは、講座派マルクス主義経済学者であり戦後はアジアの自由と民主主義の擁護 者として神格化される平野義太郎[1897-1980]である。清野謙次は平野の妻が姉妹という義兄弟の関係にあった。平野は太平洋調査会部長の当時、 『大東亜民族誌』において、優生学にもとづく人種主義的蘊蓄を遺憾なく披瀝し、帝国内における日本人と外国人の混血がいかに種族の保存にとって危険である のかを主張していた(平野 2001[1944]:234)。
他方で、日本の国内(および朝鮮半島の一部)で は、それまでになかったさまざまな医療の社会化の運動が試みられた。これらは、戦前のファシズム体制に対する一種の草の根レベルでのカウンター運動とこれ まで評価されてきたものである。例えば1920年代から30年代にかけておこなわれるようになった無産者診療運動。これは都市部における社会主義労働活動 の一環として、医療が労働者の福利向上に寄与するものと考えられたが、40年代に当局によって閉鎖された。医療利用組合運動もほとんど同時期に生まれ農山 村における医療の大衆化に貢献したと評価されている。これらの運動を通して、結核や乳幼児死亡の実態の把握が進み、病気の社会的起源や健康の達成には臨床 医学ではなく栄養条件の改善が重要であるという今日の常識となった見解がこの頃すでに共有されていた。しかし、後に述べるように、国家が主導する公的な医 療制度もまた貧困層や農山村における健康の水準の低下を危惧していた。同じ時期に、まったく異なった角度からではあるが、医療のまなざしがこれらの日本社 会の周縁化された社会集団に向けられていたことを忘れてはならない。
これらの社会改良の理念に裏付けられた、医療の社
会化のプロジェクトは戦後の民主主義の復活とGHQ指導の公衆衛生政策の状況の中で、戦前の医療者のヒューマニズムの伝統が絶やされなかったと好意的に評
価されてきた。しかし、現在では患者の人権論や医療の権力論というリビジョニスト的再検討の中で、彼らが抱いていた医療者のパターナリズムや近代科学とし
ての医療の特権意識などが批判に晒されつつある。
9.理想追求の継続
では何故、日本の植民地統治へと飛翔するはずの帝国医療プロジェクトは第二次大戦終了において終焉したのではなく、これらの理念が戦後までも命脈を保ち
続けたと言えるのだろうか。その設問の解法へのヒントを最後に示唆しておきたい。
1874年(明治7年)の76箇条の「医制」の公 布以降、帝国医療システムは順調に発展、整備されていった。つまり具体的には、伝染病対策、衛生制度の創設と整備、帝国大学の医学研究システムの改善、ド イツを中心にした海外留学における研究水準の向上、極東熱帯医学会や国際連盟衛生会議等のアジアにおける医療情報の交換と蓄積等を通してである。これらは アジアの周辺地域を帝国内に組み込む地政学的発展とパラレルであった。この当時までは、さらに帝国の威光を臣民に享受させるといった救貧対策を含む福祉保 健制度の構想が練られ萌芽的なプロジェクトが試みられようとしていた。今から想像することは困難であり、また我々にとって驚くべきことであるが、女性のヘ ルス・ボランティア制度(当時は「保健婦」「指導員」などと呼ばれていた)すら動き始めていたのである。
しかし1930年の中国大陸での交戦を皮切りに、
いわゆる総力戦体制に突入してゆき、日本国内における物資の不足から、日本人の栄養状態は徐々に悪化していった。それは結核の罹患率や乳幼児死亡率の増加
を引き起こした。帝国の末端に日本の成年男子を送るための徴兵検査においても、兵士の健康の質の低下は避けられず、大きな政策課題になりつつあった(清水
1988)。その結果、それまでの救貧的な医療福祉政策から、帝国臣民とりわけ青年男子の健康の質の向上に、努力が向けられるようになった。しかし栄養
条件を改善する資源もなく、いわゆる精神の肉体化――壮健な精神が壮健な身体を造る――に空しく政策は進んでいった。ラジオ体操が国民の総動員によって敢
行されるようになったが、結局のところ、栄養条件の悪化が制限要因となって、これらの対策はほとんど成功を収めなかった。もちろん海外の植民地において
も、帝国の保健システムは有効に機能を果たすことはできなかった。実際の例としては、「南方」における民間衛生のマニュアルの出版はようやく1940年代
になってからである(e.g. 南崎 1942)。
つまり理想的な帝国医療システムは、1930年以降すでに崩壊の道を歩み始めていたと言ってもよい。ところが、それに取って代わる保健運動の国民の総動
員体制は末端において活動していた医療者をして、日本社会の隅々まで保健プログラムを実践させることになった。そして、そのことが皮肉なことに、現場の悲
惨さに直面して実践していた医療者たちをヒューマニスト〈兼〉コスモポリタン的精神をもつ医療者として育てることになった。その一例として夭折した女医・
小川正子[1902-1943]が癩病すなわちハンセン病患者の生活描写した書物『小島の春』があげられる。この書物は、当時の医学生のバイブルになり、
ヒューマニズム(すなわち国家主義体制における唯一許されたコスモポリタン的形相)の理想に燃える医学生を、前線の軍陣医学や農山村の僻地医療に駆り立て
たのである。このような社会実践を積んだ人たちが、敗戦後の保健衛生改革に際して即戦力のマンパワーとして登用されて、戦後の農村保健運動において指導的
役割を果たしたことは皮肉なことである。医療は知識と権力の混成体に他ならないが、敗戦の審判によってもなお、その権力の問題性が不問にされ、そのまま戦
後まで継続してゆくことがありえるからだ。
このように見てくると、明治以降、約半世紀にわ
たって成長しつづけた帝国医療は、敗戦前の10数年間のみ、その機能不全を起こしていただけになる。日本の帝国医療システムはGHQの占領政策の下におい
て、むしろ1930年以前の状態にリセットされ、この理想を継続、発展してきたと解釈するほうが、長期的な観点からはよく理解できる。私の視点は戦後の解
放を保健政策上のルネサンスとしてみるのではなく――例えばサムス(1982)――むしろ敗戦前15年間を医療政策にとって特殊な時期として捉えているこ
とが解るだろう。つまりリビジョニスト的見解をとるのだ。
10.結論――未完のコスモポリタニズム――
日本の帝国医療システムは、「人種」を超えた帝国の臣民全員にあまねく福利を授けるというコスモポリタンが理想とするプログラムを持っていなかった。そ
のようにみると、日本人による日本人のための日本人の医療を、はたして帝国医療システムと呼べるのかという疑問も沸いてくるだろう。我が国の高度経済成長
期以降、本格化する、ODAによる医療援助協力のプログラムを見てみよう。私の見解ではそれは帝国医療システムがモラトリアムされた像を結ぶが、しかし他
方で、現地の文化制度を尊重する、まさに新・帝国医療システムの真骨頂を発揮するようなものは、どれ一つとして見あたらないのは、不思議なくらいだ。戦後
の我が国の医療は、技術はコスモポリタン、適用の範囲はナショナルなドメイン――すなわち〈国民医療〉――に留まりつづけるという独特の態勢を維持し続け
た。
そのような歴史的反省も経ることなく、現在では、 グローバル化するネオリベラルな経済の医療制度改革が進行しつつある。その時になって初めて、医療は人間の健康の質を高めるために無制限に適応させるべき であるというコスモポリタン医療の理念は、簡単に忘却、放棄されてしまった。現在では、医療は社会資本のコスト投入に見合った効果を引き出すアウトカムと して評価されるという見方が代わって登場し、医療は経済という、統治技法の目的以外により制御されるべき技術体系として、初めて試練に曝されることになっ たのではないだろうか。
帝国医療を通したコスモポリタン医療の理想の実現 は失敗に終わった。それは、16世紀に起源をもち19世紀に華開いた西洋の統治術の隆盛と失敗のモデルを短期的に再演したものだった(フーコー 2000 [1978])。システムではない生き方の実践としてのコスモポリタン医学は我々のもっとも遠いところにあり、その実像はネオリベラル経済原理の前で、ま すます薄れゆく影のような存在になっている(池田 2002)。経済のナショナルな境界を警邏し、微かな差益をグローバルにこまめに回収する今日のネオリ ベラルな医療産業の仕組みが、どこまでこの現象を推し進めるか、我々には未だ見通しは立ってはいないのである。
このエッセーを通して私が問題にしたかった問いは 次のようなものである。まず最初の問いでは、グローバル化する社会的文脈のなかで、医療人類学者がその社会的役割概念を変化させている事態がおこっている のか。次の問い、研究者の視座の変化が研究対象の社会的性格づけ(=本質としての文化的標識)に変化をもたらすことはないだろうか。そして最後の問い、研 究対象からすでに排除されてしまった人々や事物が、我々の考察の圏外においてさらなる変化を起こし、最終的に研究対象に再編入されるようになった事態の意 味はどのように考えることができるのだろうか、と。
私の用意した回答は次のとおりである。人類学者が
その社会的役割概念を変化させている事態はまさに起こっている。なぜなら医療人類学は民族医療を文化主義に基づいて解釈することから研究をはじめ、次に西
洋近代医療を同じ手法において研究する方向に転じ、そして最後にそれまでの文化主義をより政治経済的な批判概念に鋳込み治すようになってきた(cf.
池田 2001)。研究対象の変化は、対象を取り扱う問題系に向かおうとする時に、研究者に変化を引き起こしたのだ。今日の人類学では、解釈的転回(ギ
アーツ 1991:38)から実践的転回がおこりつつあると言ってよい(cf. 田邊 2003;
太田 2003)。このような主張は保守的主流派からは反発を喰らうことになるが、バックラッシュにおいてすら、批判派の論理に対抗するために主流派もま
た人類学の実践的関与の問題系を取り込んだコメントを行うようになっている。つまり異質な批判的意見に耳が傾けられることが、その必要不可欠な条件の証で
ある。人類学者の社会的性格付けは変化しつつあるのだ。かつて人類学者によって考慮されることのなかった歴史的過去の痕跡――ここでは人類学がいまだかつ
て考量の対象として想定もしなかった帝国医療――が、現在においてまさに検討に値する問題系として浮上することがあり得ることを、私たちは身をもって体験
していると言えば、大げさになるだろうか。私は決してそのことが大げさであるとは思っていない。
文献
クリフォード,J.(Clifford, James)
2002「空間的実践」『ルーツ』毛利嘉孝ほか訳,東京:月曜社.
ディオゲネス・ラエルティオス(Diogenes Laertius)
1989『ギリシア哲学者列伝(中)』加来彰俊 訳,岩波文庫,東京:岩波書店
ファノン,F.(Fanon, Franz)
1984『革命の社会学』宮ヶ谷徳三ほか訳,東京:みすず書房.
フーコー,M.(Foucault, Michel)
2000[1978]「統治性」『ミッシェル・フーコー思考集成 VII』東京:筑摩書房.
ギアーツ,C.(Geertz, Clifford)
1991「薄れゆくジャンル」『ローカル・ノレッジ』梶原影昭ほか訳,東京:岩波書店.
1996『文化の読み方/書き方』森泉弘次 訳,東京:岩波書店.
平野 義太郎(Hirano, Yoshitaro)
2001[1944]「文化」『大東亜民族誌』東亜経済懇談会編(復刻版),東京:クレス出版.
Huntington, Samuel P.
1993. THE CLASH OF CIVILIZATIONS , Foreign Affairs.
Summer 1993, 72(3):22,28.
飯島 渉(Iijima, Wataru)
2000「近代日本の「植民地医学(colonial medicine)」に関する覚書」『中国研究彙報』
22:65-81.
池田 光穂(Ikeda, Mitsuho)
2001『実践の医療人類学』京都:世界思想社.
2002「民族医療の領有について」『民族学研究』 63(3):309-327.
投稿準備中「グローバルポリティクス時代の国際医療協力」『地域研究』
イリッチ,I.(Illich, Ivan)
1979『脱病院化社会』金子嗣郎 訳,東京:晶文社.
今村 仁司(Imamura, Hitoshi)
2005『抗争する人間』東京:講談社.
清野 謙次(Kiyono, Kenji)
2001[1943]『インドネシアの民族醫學』太平洋協會編(復刻版),東京:クレス出版.
レイン,R.D.とA.エスターソン(Laing, Ronald David and Aaron Esterson)
1972『狂気と家族』笠原嘉・辻和子 訳,東京:みすず書房.
ルクレール,G.(Leclerc, Gerard)
1976『人類学と植民地主義』宮治一雄・宮治美江子 訳,東京:平凡社.
Marcus, George E. and Michael M.J. Fischer
1999. Anthropology as cultural critique. 2nd. ed.,
Chicago : University of Chicago Press.
マキューン,T.(McKeown, Thomas)
1992『病気の起源』酒井シズ・田中靖夫 訳,東京:朝倉書店.
三木 清(Miki, Kiyoshi)
1967[1937]「新しいコスモポリタン」『三木清全集』第15卷,東京:岩波書店
南崎 雄七(Minamisaki, Yushichi)
1942『南方生活必携』東京:教材社.
中生 勝美(Nakao, Katsumi)編
2000『植民地人類学への展望』東京:風響社.
西川 長夫(Nishikawa, Nagao)
1998『国民国家論の射程』東京:柏書房.
奥野 克巳(Okuno, Katsumi)
in press. 「近代医療の世界拡張と人類学」『社会人類学年報』第29巻(印刷中).
太田 好信(Ota, Yoshinobu)
2003『人類学と脱植民地化』東京:岩波書店.
陸軍軍医学校(Rikugun Gun-i Gakko; Japanese Imperial Army Medical School)
1988[1936]『陸軍軍醫學校五十年史』(復刻版)東京:不二出版.
サムス,C.F.(Sams, Crawford F.)
1986『DDT革命』竹前栄治編訳,東京:岩波書店.
清水 勝嘉(Shimizu, Katsuyoshi)編
1988『戦争栄養失調症関係資料(所謂戦争栄養失調症ニ関スル研究調査報告(大阪陸軍病院研究調査委員,
昭和14年3月28日)』(復刻版),東京:不二出版.
スモール,H.(Small, Hugh)
2003『ナイチンゲール』田中京子 訳,東京:みすず書房.
高橋 晄正(Takahashi, Kohsei)
1969『社会のなかの医学』東京:東京大学出版会.
田邊 繁治(Tanabe, Shigeharu)
2003『生き方の人類学』講談社現代新書,東京:講談社.
常石 敬一(Tsuneishi, Kei-ichi)
1999『医学者たちの組織犯罪』朝日文庫,東京:朝日新聞社.
脇村 孝平(Wakimura, Kohei)
2002『飢饉・疫病・植民地統治』名古屋:名古屋大学出版局.
リンク
文献
その他の情報