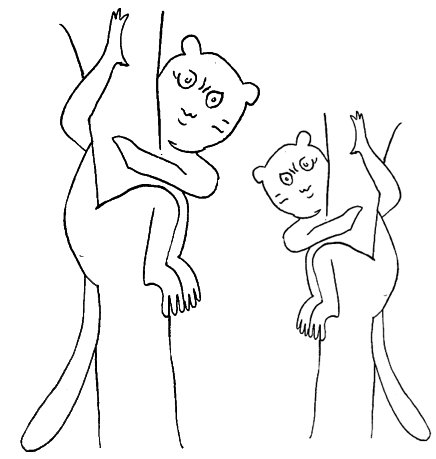
文化の概念の人間の概念への影響
The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man
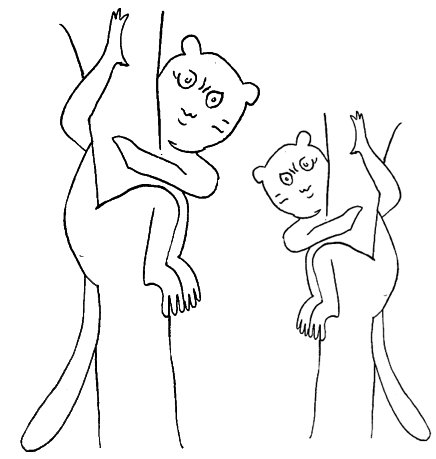
☆The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man By Clifford Geertz
| The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man By Clifford Geertz |
|
| I Toward the end of his recent study of the ideas used by tribal peoples, La PensÈe Sauvage, the French anthropologist LÈvi-Strauss remarks that scientific explanation does not consist, as we have been led to imagine, in the reduction of the complex to the simple. Rather, it consists, he says, in a substitution of a complexity more intelligible for one which is less. So far as the study of man is concerned, one may go even further, I think, and argue that explanation often consists of substituting complex pictures for simple ones while striving somehow to retain the persuasive clarity that went with the simple ones. Elegance remains, I suppose, a general scientific ideal; but in the social sciences, it is very often in departures from that ideal that truly creative developments occur. Scientific advancement commonly consists in a progressive complication of what once seemed a beautifully simple set of notions but now seems an unbearably simplistic one. It is after this sort of disenchantment occurs that intelligibility, and thus explanatory power, comes to rest on the possibility of substituting the involved but comprehensible for the involved but incomprehensible to which LÈvi-Strauss refers. Whitehead once offered to the natural sciences the maxim "Seek simplicity and distrust it"; to the social sciences he might well have offered "Seek complexity and order it." Certainly the study of culture has developed as though this maxim were being followed. The rise of a scientific concept of culture amounted to, or at least was connected with, the overthrow of the view of human nature dominant in the Enlightenment--a view that, whatever else may be said for or against it, was both clear and simple--and its replacement by a view not only more complicated but enormously less clear. The attempt to clarify it, to reconstruct an intelligible account of what man is, has underlain scientific thinking about culture ever since. Having sought complexity and, on a scale grander than they ever imagined, found it, anthropologists became entangled in a tortuous effort to order it. And the end is not yet in sight. The Enlightenment view of man was, of course, that he was wholly of a piece with nature and shared in the general uniformity of composition which natural science, under Bacon's urging and Newton's guidance, had discovered there. There is, in brief, a human nature as regularly organized, as thoroughly invariant, and as marvelously simple as Newton's universe. Perhaps some of its laws are different, but there are laws; perhaps some of its immutability is obscured by the trappings of local fashion, but it is immutable. A quotation that Lovejoy (whose magisterial analysis I am following here) gives from an Enlightenment historian, Mascou, presents the position with the useful bluntness one often finds in a minor writer: The stage setting [in different times and places] is, indeed, altered, the actors change their garb and their appearance; but their inward motions arise from the same desires and passions of men, and produce their effects in the vicissitudes of kingdoms and peoples.1 Now, this view is hardly one to be despised; nor, despite my easy references a moment ago to "overthrow," can it be said to have disappeared from contemporary anthropological thought. The notion that men are men under whatever guise and against whatever backdrop has not been replaced by "other mores, other beasts." Yet, cast as it was, the Enlightenment concept of the nature of human nature had some much less acceptable implications, the main one being that, to quote Lovejoy himself this time, "anything of which the intelligibility, verifiability, or actual affirmation is limited to men of a special age, race, temperament, tradition or condition is [in and of itself] without truth or value, or at all events without importance to a reasonable man."2 The great, vast variety of differences among men, in beliefs and values, in customs and institutions, both over time and from place to place, is essentially without significance in defining his nature. It consists of mere accretions, distortions even, overlaying and obscuring what is truly human--the constant, the general, the universal--in man. Thus, in a passage now notorious, Dr. Johnson saw Shakespeare's genius to lie in the fact that "his characters are not modified by the customs of particular places, unpractised by the rest of the world; by the peculiarities of studies or professions, which can operate upon but small numbers; or by the accidents of transient fashions or temporary opinions."3 And Racine regarded the success of his plays on classical themes as proof that "the taste of Paris . . . conforms to that of Athens; my spectators have been moved by the same things which, in other times, brought tears to the eyes of the most cultivated classes of Greece."4 The trouble with this kind of view, aside from the fact that it sounds comic coming from someone as profoundly English as Johnson or as French as Racine, is that the image of a constant human nature independent of time, place, and circumstance, of studies and professions, transient fashions and temporary opinions, may be an illusion, that what man is may be so entangled with where he is, who he is, and what he believes that it is inseparable from them. It is precisely the consideration of such a possibility that led to the rise of the concept of culture and the decline of the uniformitarian view of man. Whatever else modern anthropology asserts--and it seems to have asserted almost everything at one time or another--it is firm in the conviction that men unmodified by the customs of particular places do not in fact exist, have never existed, and most important, could not in the very nature of the case exist. There is, there can be, no backstage where we can go to catch a glimpse of Mascou's actors as "real persons" lounging about in street clothes, disengaged from their profession, displaying with artless candor their spontaneous desires and unprompted passions. They may change their roles, their styles of acting, even the dramas in which they play; but--as Shakespeare himself of course remarked--they are always performing. This circumstance makes the drawing of a line between what is natural, universal, and constant in man and what is conventional, local, and variable extraordinarily difficult. In fact, it suggests that to draw such a line is to falsify the human situation, or at least to misrender it seriously. Consider Balinese trance. The Balinese fall into extreme dissociated states in which they perform all sorts of spectacular activities--biting off the heads of living chickens, stabbing themselves with daggers, throwing themselves wildly about, speaking with tongues, performing miraculous feats of equilibration, mimicking sexual intercourse, eating feces, and so on--rather more easily and much more suddenly than most of us fall asleep. Trance states are a crucial part of every ceremony. In some, fifty or sixty people may fall, one after the other ("like a string of firecrackers going off," as one observer puts it), emerging anywhere from five minutes to several hours later, totally unaware of what they have been doing and convinced, despite the amnesia, that they have had the most extraordinary and deeply satisfying experience a man can have. What does one learn about human nature from this sort of thing and from the thousand similarly peculiar things anthropologists discover, investigate, and describe? That the Balinese are peculiar sorts of beings, South Sea Martians? That they are just the same as we at base, but with some peculiar, but really incidental, customs we do not happen to have gone in for? That they are innately gifted or even instinctively driven in certain directions rather than others? Or that human nature does not exist and men are pure and simply what their culture makes them? It is among such interpretations as these, all unsatisfactory, that anthropology has attempted to find its way to a more viable concept of man, one in which culture, and the variability of culture, would be taken into account rather than written off as caprice and prejudice, and yet, at the same time, one in which the governing principle of the field, "the basic unity of mankind," would not be turned into an empty phrase. To take the giant step away from the uniformitarian view of human nature is, so far as the study of man is concerned, to leave the Garden. To entertain the idea that the diversity of custom across time and over space is not a mere matter of garb and appearance, of stage settings and comedic masques, is to entertain also the idea that humanity is as various in its essence as it is in its expression. And with that reflection some well-fastened philosophical moorings are loosed and an uneasy drifting into perilous waters begins. Perilous, because if one discards the notion that Man with a capital "M," is to be looked for "behind," "under," or "beyond" his customs and replaces it with the notion that man, uncapitalized, is to be looked for "in" them, one is in some danger of losing sight of him altogether. Either he dissolves, without residue, into his time and place, a child and a perfect captive of his age, or he becomes a conscripted soldier in a vast Tolstoian army, engulfed in one or another of the terrible historical determinisms with which we have been plagued from Hegel forward. We have had, and to some extent still have, both of these aberrations in the social sciences--one marching under the banner of cultural relativism, the other under that of cultural evolution. But we also have had, and more commonly, attempts to avoid them by seeking in culture patterns themselves the defining elements of a human existence which, although not constant in expression, are yet distinctive in character. |
I 部族の人々が用いる考え方に関する最近の研究『野生の思考』の終わりに、フランスの人類学者レヴィ=ストロースは、科学的な説明とは、私たちが想像するよ うに、複雑なものを単純なものに還元することではないと述べている。むしろ、科学的な説明とは、より理解しやすい複雑さの代用であると彼は言う。人間を研 究する限りにおいては、さらに一歩進んで、説明とはしばしば単純な絵を複雑な絵に置き換えることであるが、単純な絵に付随していた説得力のある明瞭さを何 とかして維持しようと努力するものであると主張することもできるだろう。 私は、エレガンスは依然として科学における一般的な理想であると考えているが、社会科学においては、真に創造的な発展は、その理想から離れたところから生 じる場合が非常に多い。科学の進歩は、かつては美しくシンプルな概念の集合体であったものが、今では耐え難いほど単純化されたものに見えるような、段階的 な複雑化によって成り立っているのが一般的である。このような幻滅が起こった後に、理解可能性、そして説明力が、複雑だが理解可能なものを複雑だが理解不 可能なものに置き換える可能性に依存するようになる。ホワイトヘッドはかつて自然科学に対して「単純性を求め、それを疑え」という格言を提示したが、社会 科学に対しては「複雑性と秩序を求めよ」と提示したかもしれない。 確かに、文化研究はあたかもこの格言に従うかのように発展してきた。文化に関する科学的概念の台頭は、啓蒙主義で支配的だった人間性に関する見解の転覆、 あるいは少なくともそれに繋がるものであった。この見解は、それに対して賛否両論あるにせよ、明確かつ単純なものであった。そして、より複雑なだけでな く、はるかに明確さに欠ける見解に取って代わられた。それを明確にしようとする試み、人間とは何かを理解できる形で再構築しようとする試みは、それ以来、 文化に関する科学的思考の根底にある。複雑性を求め、そして想像を絶する規模でそれを見出した人類学者たちは、それを体系化しようと複雑な努力に巻き込ま れていった。そして、その終わりはまだ見えていない。 啓蒙思想における人間観は、もちろん、人間は自然と完全に一体であり、自然科学がベーコンの奨励とニュートンの指導の下で発見した、そこにある一般的な構 成の均一性を共有しているというものであった。簡単に言えば、ニュートンの宇宙のように規則正しく組織化され、完全に不変で、驚くほどシンプルな人間の本 性がある。おそらくその法則の一部は異なるが、法則は存在する。おそらくその不変性の一部は、その土地の流行の装飾によって覆い隠されているが、それは不 変である。 ラブジョイ(私はここで彼の権威ある分析を踏襲している)が啓蒙主義の歴史家マスクーの言葉を引用しているが、これは、あまり著名でない作家の著作によく見られる、有益な率直さを備えた立場を示している。 「(異なる時代や場所における)舞台設定は確かに変化し、役者たちは衣装や外見を変える。しかし、彼らの内面の動きは、人間が抱く同じ欲望や情熱から生じ、王国や民族の盛衰に影響を及ぼす。 さて、この見解は軽視されるべきものではない。また、先ほど私が「打倒」という言葉を手軽に用いたにもかかわらず、現代の人類学思想からそれが消え去った わけではない。どのような装いであれ、どのような背景であれ、人間は人間であるという考え方は、「他の慣習、他の獣」に取って代わられたわけではない。 しかし、啓蒙思想が描き出した人間の本質という概念には、それほど受け入れられていない含みがあり、主なものは、ラブジョイ自身の言葉を引用すると、「理 解可能性、検証可能性、または実際の肯定が、特別な時代、人種、気質、 真実性や価値を持たない、あるいは、少なくとも理性的な人間にとって重要ではない」2。 人間同士の信念や価値観、習慣や制度における、時間的にも地理的にも大きな多様性は、本質的には人間の本質を定義する上で重要ではない。 それは、人間の本質である普遍的なもの、一般的なもの、恒常的なものを覆い隠し、歪めてしまう単なる蓄積でしかない。 したがって、今では悪名高い一節で、ジョンソン博士は、シェイクスピアの天才は「登場人物が特定の土地の風習、世界では一般的ではないもの、少数の人々し か関心を持たない学問や職業の特殊性、あるいは一過性の流行や一時的な意見によって修正されていない」という事実にあると見なした。3 また、ラシーヌは古典をテーマにした劇の成功を、「パリの好みが アテネのそれと一致している。私の観客は、かつてギリシャの教養ある階級の人々の目頭に涙を浮かべさせたのと同じものに感動しているのだ。」4 ジョンソンやラシーヌのような人物が言うと滑稽に聞こえるという事実を除けば、この種の考え方の問題は、時間、場所、状況、学問や職業、一過性の流行や一 時的な意見とは無関係な、不変の人間の本質というイメージは幻想である可能性があるということだ。人間とは、自分がどこにいるか、自分が何者か、何を信じ ているかによって、それらと切り離せないほど複雑に絡み合っている可能性がある。まさにそのような可能性を考慮したことが、文化という概念の台頭と、人間 に対する均質説の衰退につながったのである。 現代の人間学が何を主張しようとも、そして、それはある時期にはほとんどすべてを主張してきたように思われるが、特定の場所の風習によって変化していない 人間は、実際には存在せず、これまで存在したこともなく、そして何よりも、本質的に存在しえないという確信は揺るぎない。マスコウの役者たちが、職業から 離れ、私服でくつろぎながら、自然な欲求や自発的な情熱を飾り気のない率直さで表している「現実の人間」として垣間見られるような楽屋裏など、存在したこ ともないし、今後も存在しえない。彼らは役柄や演技スタイル、演じるドラマを変えることはあっても、シェイクスピア自身が言及しているように、常に演技を しているのだ。 この状況により、人間の本質的、普遍的、かつ不変的なものと、慣習的、局地的、かつ可変的なものとの間に線を引くことが非常に難しくなる。実際、そのような線を引くことは、人間の状況を偽る、あるいは少なくともそれを深刻に誤って伝えることになる。 バリのトランスを考えてみよう。バリ人は極度の解離状態に陥り、そこで彼らは、生きた鶏の首を噛みちぎったり、短剣で自分を刺したり、荒々しく身を投げ出 したり、異言を話したり、驚異的な平衡感覚を発揮したり、性交の真似をしたり、糞便を食べたりなど、ありとあらゆる壮観な行動を、私たち大半が眠りに落ち るよりもはるかに簡単に、はるかに突然に行う。トランス状態は、あらゆる儀式において重要な要素である。中には、50人から60人が次々と倒れ(ある観察 者は「爆竹が次々と鳴るような」と表現した)、5分から数時間後に意識を取り戻すものもある。彼らは自分が何をしていたのかまったく覚えておらず、記憶喪 失にもかかわらず、人間が経験しうる最も非凡で深い満足感を得たという確信を持っている。このようなことや、人類学者が発見、調査、記述した同様の奇妙な 出来事の数々から、人間性について何が分かるのだろうか? バリ人は変わった種族であり、南洋の火星人なのか? 彼らは根本的には我々と同じだが、我々にはない奇妙な、しかし本当に偶然の風習を持っているだけなのか? 彼らは生まれつき才能に恵まれているか、あるいは本能的に特定の方向に導かれているのか? それとも人間の本質など存在せず、人間は純粋に、その文化によって形作られているだけなのか? このような、いずれも満足のいくものではない解釈のなかで、文化や文化の多様性を気まぐれや偏見として切り捨てるのではなく、それらを考慮した、より実現 可能な人間像の概念を見出す道を人類学は模索してきた。同時に、この分野の支配的な原則である「人類の基本的な統一性」を空虚な言葉にしないものでもあ る。人間の本質に関する均一説から離れることは、人間研究に関して言えば、楽園を離れることである。時と空間を超えた習慣の多様性は、単に服装や外見、舞 台装置や喜劇の仮面劇の問題ではないという考えを受け入れることは、人間の本質も表現と同様に多様であるという考えを受け入れることでもある。そして、そ の考察により、しっかりと固定されていた哲学的な拠り所が緩み、危険な海域への不安定な漂流が始まる。 危険なのは、大文字の「M」で始まる「人間」という概念を、その習慣の「背後」、「下」、「向こう側」に求めるのではなく、小文字の「man」という概念 を、その習慣の「内」に求めるという考え方に置き換えると、人間という存在を完全に見失ってしまう危険性があるからだ。彼は、その時代の子どものように、 その時代に完全に捕らわれた存在として、その時代と場所に跡形もなく溶け込んでしまうか、あるいは、膨大な数のトルストイ的軍隊に徴兵された兵士となり、 ヘーゲル以降の時代を悩ませてきた恐ろしい歴史的決定論のひとつに飲み込まれてしまうかのどちらかである。社会科学には、この2つの異常な傾向が存在して きた。1つは文化相対主義の旗印のもと、もう1つは文化進化論の旗印のもとで進んできた。しかし、私たちはまた、文化パターン自体に人間の存在を定義する 要素を求め、それらを回避しようとする試みも行ってきた。その要素は、表現は一定ではないが、性格的には際立ったものである。 |
| II Attempts to locate man amid the body of his customs have taken several directions, adopted diverse tactics; but they have all, or virtually all, proceeded in terms of a single overall intellectual strategy: what I will call, so as to have a stick to beat it with, the "stratigraphic" conception of the relations between biological, psychological, social, and cultural factors in human life. In this conception, man is a composite of "levels," each superimposed upon those beneath it and underpinning those above it. As one analyzes man, one peels off layer after layer, each such layer being complete and irreducible in itself, revealing another, quite different sort of layer underneath. Strip off the motley forms of culture and one finds the structural and functional regularities of social organization. Peel off these in turn and one finds the underlying psychological factors--"basic needs" or what-have-you--that support and make them possible. Peel off psychological factors and one is left with the biological foundations--anatomical, physiological, neurological--of the whole edifice of human life. The attraction of this sort of conceptualization, aside from the fact that it guaranteed the established academic disciplines their independence and sovereignty, was that it seemed to make it possible to have one's cake and eat it. One did not have to assert that man's culture was all there was to him in order to claim that it was, nonetheless, an essential and irreducible, even a paramount ingredient in his nature. Cultural facts could be interpreted against the background of noncultural facts without dissolving them into that background or dissolving that background into them. Man was a hierarchically stratified animal, a sort of evolutionary deposit, in whose definition each level--organic, psychological, social, and cultural--had an assigned and incontestable place. To see what he really was, we had to superimpose findings from the various relevant sciences--anthropology, sociology, psychology, biology --upon one another like so many patterns in a moirÈ; and when that was done, the cardinal importance of the cultural level, the only one distinctive to man, would naturally appear, as would what it had to tell us, in its own right, about what he really was. For the eighteenth century image of man as the naked reasoner that appeared when he took his cultural costumes off, the anthropology of the late nineteenth and early twentieth centuries substituted the image of man as the transfigured animal that appeared when he put them on. At the level of concrete research and specific analysis, this grand strategy came down, first, to a hunt for universals in culture, for empirical uniformities that, in the face of the diversity of customs around the world and over time, could be found everywhere in about the same form, and, second, to an effort to relate such universals, once found, to the established constants of human biology, psychology, and social organization. If some customs could be ferreted out of the cluttered catalogue of world culture as common to all local variants of it, and if these could then be connected in a determinate manner with certain invariant points of reference on the subcultural levels, then at least some progress might be made toward specifying which cultural traits are essential to human existence and which merely adventitious, peripheral, or ornamental. In such a way, anthropology could determine cultural dimensions of a concept of man commensurate with the dimensions provided, in a similar way, by biology, psychology, or sociology. In essence, this is not altogether a new idea. The notion of a consensus gentium (a consensus of all mankind)--the notion that there are some things that all men will be found to agree upon as right, real, just, or attractive and that these things are, therefore, in fact right, real, just, or attractive--was present in the Enlightenment and probably has been present in some form or another in all ages and climes. It is one of those ideas that occur to almost anyone sooner or later. Its development in modern anthropology, however--beginning with Clark Wissler's elaboration in the 1920s of what he called "the universal cultural pattern," through Bronislaw Malinowski's presentation of a list of "universal institutional types" in the early forties, up to G. P. Murdock's elaboration of a set of "common--denominators of culture" during and since World War II--added something new. It added the notion that, to quote Clyde Kluckhohn, perhaps the most persuasive of the consensus gentium theorists, "some aspects of culture take their specific forms solely as a result of historical accidents; others are tailored by forces which can properly be designated as universal."5 With this, man's cultural life is split in two: part of it is, like Mascou's actors' garb, independent of men's Newtonian "inward motions"; part is an emanation of those motions themselves. The question that then arises is: Can this halfway house between the eighteenth and twentieth centuries really stand? Whether it can or not depends on whether the dualism between empirically universal aspects of culture rooted in subcultural realities and empirically variable aspects not so rooted can be established and sustained. And this, in turn, demands (1) that the universals proposed be substantial ones and not empty categories; (2) that they be specifically grounded in particular biological, psychological, or sociological processes, not just vaguely associated with "underlying realities"; and (3) that they can convincingly be defended as core elements in a definition of humanity in comparison with which the much more numerous cultural particularities are of clearly secondary importance. On all three of these counts it seems to me that the consensus gentium approach fails; rather than moving toward the essentials of the human situation it moves away from them. The reason the first of these requirements--that the proposed universals be substantial ones and not empty or near-empty categories--has not been met is that it cannot be. There is a logical conflict between asserting that, say, "religion,""marriage," or "property" are empirical universals and giving them very much in the way of specific content, for to say that they are empirical universals is to say that they have the same content, and to say they have the same content is to fly in the face of the undeniable fact that they do not. It one defines religion generally and indeterminately--as man's most fundamental orientation to reality, for example--then one cannot at the same time assign to that orientation a highly circumstantial content; for clearly what composes the most fundamental orientation to reality among the transported Aztecs, lifting pulsing hearts torn live from the chests of human sacrifices toward the heavens, is not what comprises it among the stolid ZuÒi, dancing their great mass supplications to the benevolent gods of rain. The obsessive ritualism and unbuttoned polytheism of the Hindus express a rather different view of what the "really real" is really like from the uncompromising monotheism and austere legalism of Sunni Islam. Even if one does try to get down to less abstract levels and assert, as Kluckhohn did, that a concept of the afterlife is universal, or as Malinowski did, that a sense of Providence is universal, the same contradiction haunts one. To make the generalization about an afterlife stand up alike for the Confucians and the Calvinists, the Zen Buddhists and the Tibetan Buddhists, one has to define it in most general terms, indeed--so general, in fact, that whatever force it seems to have virtually evaporates. So, too, with any notion of a sense of Providence, which can include under its wing both Navajo notions about the relations of gods to men and Trobriand ones. And as with religion, so with "marriage," "trade," and all the rest of what A. L. Kroeber aptly called "fake universals," down to so seemingly tangible a matter as "shelter." That everywhere people mate and produce children, have some sense of mine and thine, and protect themselves in one fashion or another from rain and sun are neither false nor, from some points of view, unimportant; but they are hardly very much help in drawing a portrait of man that will be a true and honest likeness and not an unteneted "John O. Public" sort of cartoon. My point, which should be clear and I hope will become even clearer in a moment, is not that there are no generalizations that can be made about man as man, save that he is a most various animal, or that the study of culture has nothing to contribute toward the uncovering of such generalizations. My point is that such generalizations are not to be discovered through a Baconian search for cultural universals, a kind of public-opinion polling of the world's peoples in search of a consensus gentium that does not in fact exist, and, further, that the attempt to do so leads to precisely the sort of relativism the whole approach was expressly designed to avoid. "ZuÒi culture prizes restraint," Kluckhohn writes; "Kwakiutl culture encourages exhibitionism on the part of the individual. These are contrasting values, but in adhering to them the ZuÒi and Kwakiutl show their allegiance to a universal value; the prizing of the distinctive norms of one's culture."6 This is sheer evasion, but it is only more apparent, not more evasive, than discussions of cultural universals in general. What, after all, does it avail us to say, with Herskovits, that "morality is a universal, and so is enjoyment of beauty, and some standard for truth," if we are forced in the very next sentence, as he is, to add that "the many forms these concepts take are but products of the particular historical experience of the societies that manifest them"?7 Once one abandons uniformitarianism, even if, like the consensus gentium theorists, only partially and uncertainly, relativism is a genuine danger; but it can be warded off only by facing directly and fully the diversities of human culture, the Zufii's restraint and the Kwakiutl's exhibitionism, and embracing them within the body of one's concept of man, not by gliding past them with vague tautologies and forceless banalities. Of course, the difficulty of stating cultural universals which are at the same time substantial also hinders fulfillment of the second requirement facing the consensus gentium approach, that of grounding such universals in particular biological, psychological, or sociological processes. But there is more to it than that: the "stratigraphic" conceptualization of the relationships between cultural and noncultural factors hinders such a grounding even more effectively. Once culture, psyche, society, and organism have been converted into separate scientific "levels," complete and autonomous in themselves, it is very hard to bring them back together again. The most common way of trying to do so is through the utilization of what are called "invariant points of reference." These points are to be found, to quote one of the most famous statements of this strategy--the "Toward a Common Language for the Areas of the Social Sciences" memorandum produced by Talcott Parsons, Kluckhohn, O. H. Taylor, and others in the early forties--: "in the nature of social systems, in the biological and psychological nature of the component individuals, in the external situations in which they live and act, in the necessity of coordination in social systems. In [culture] ... these "foci" of structure are never ignored. They must in some way be "adapted to" or "taken account of." Cultural universals are conceived to be crystallized responses to these unevadable realities, institutionalized ways of coming to terms with them. Analysis consists, then, of matching assumed universals to postulated underlying necessities, attempting to show there is some goodness of fit between the two. On the social level, reference is made to such irrefragable facts as that all societies, in order to persist, must reproduce their membership or allocate goods and services, hence the universality of some form of family or some form of trade. On the psychological level, recourse is had to basic needs like personal growth--hence the ubiquity of educational institutions--or to panhuman problems, like the Oedipal predicament--hence the ubiquity of punishing gods and nurturant goddesses. Biologically, there is metabolism and health; culturally, dining customs and curing procedures. And so on. The tack is to look at underlying human requirements of some sort or other and then to try to show that those aspects of culture that are universal are, to use Kluckhohn's figure again, "tailored" by these requirements. The problem here is, again, not so much whether in a general way this sort of congruence exists, but whether it is more than a loose and indeterminate one. It is not difficult to relate some human institutions to what science (or common sense) tells us are requirements for human existence, but it is very much more difficult to state this relationship in an unequivocal form. Not only does almost any institution serve a multiplicity of social, psychological, and organic needs (so that to say marriage is a mere reflex of the social need to reproduce, or that dining customs are a reflex of metabolic necessities, is to court parody), but there is no way to state in any precise and testable way the interlevel relationships that are conceived to hold. Despite first appearances, there is no serious attempt here to apply the concepts and theories of biology, psychology, or even sociology to the analysis of culture (and, of course, not even a suggestion of the reverse exchange) but merely a placing of supposed facts from the cultural and subcultural levels side by side so as to induce a vague sense that some kind of relationship between them --an obscure sort of "tailoring"--obtains. There is no theoretical integration here at all but a mere correlation, and that intuitive, of separate findings. With the levels approach, we can never, even by invoking "invariant points of reference," construct genuine functional interconnections between cultural and noncultural factors, only more or less persuasive analogies, parallelisms, suggestions, and affinities. However, even if I am wrong (as, admittedly, many anthropologists would hold) in claiming that the consensus gentium approach can produce neither substantial universals nor specific connections between cultural and noncultural phenomena to explain them, the question still remains whether such universals should be taken as the central elements in the definition of man, whether a lowest-common-denominator view of humanity is what we want anyway. This is, of course, now a philosophical question, not as such a scientific one; but the notion that the essence of what it means to be human is most clearly revealed in those features of human culture that are universal rather than in those that are distinctive to this people or that is a prejudice we are not necessarily obliged to share. Is it in grasping such general facts--that man has everywhere some sort of "religion"--or in grasping the richness of this religious phenomenon or that--Balinese trance or Indian ritualism, Aztec human sacrifice or ZuÒi rain--dancing--that we grasp him? Is the fact that "marriage" is universal (if it is) as penetrating a comment on what we are as the facts concerning Himalayan polyandry, or those fantastic Australian marriage rules, or the elaborate bride-price systems of Bantu Africa? The comment that Cromwell was the most typical Englishman of his time precisely in that he was the oddest may be relevant in this connection, too: it may be in the cultural particularities of people--in their oddities--that some of the most instructive revelations of what it is to be generically human are to be found; and the main contribution of the science of anthropology to the construction--or reconstruction --of a concept of man may then lie in showing us how to find them. |
II 人間の習慣の体系の中で人間を見つけ出そうとする試みは、いくつかの方向性を取り、多様な戦術を採用してきた。しかし、それらはすべて、あるいはほぼすべ て、単一の包括的な知的戦略に基づいて進められてきた。私はそれを「層位学的」と呼ぶが、それは人間の生活における生物学的、心理学的、社会的、文化的な 要因の関係についての概念である。この概念では、人間は「レベル」の複合体であり、各レベルは下位のレベルに重なり合い、上位のレベルを支えている。人間 を分析する際には、層を一枚ずつはがしていく。各層はそれ自体で完全かつ不可分であり、その下にまったく異なる種類の層があることを明らかにする。文化の 多様な形態をはぎ取ると、社会組織の構造的および機能的な規則性が現れる。これらを順番に剥がしていくと、それらを支え、可能にしている根本的な心理的要 因、すなわち「基本的ニーズ」やその他諸々が見えてくる。心理的要因を剥がしていくと、人間の生活の全体的な基盤である生物学的基礎、すなわち解剖学的、 生理学的、神経学的基礎が残る。 この種の概念化の魅力は、確立された学問分野に独立性と主権を保証するという事実を除けば、一石二鳥であるように思われたことだ。人間の文化が人間にとっ てすべてであると主張しなくても、それにもかかわらず、人間の性質において本質的で不可欠な、さらには最も重要な要素であると主張することが可能だった。 文化的事実は、非文化的事実を背景として解釈することが可能であり、その際、文化的事実を背景に溶かし込むことも、背景を文化的事実に溶かし込むこともな い。人間は階層的に層化された動物であり、進化の過程で蓄積された一種の遺産である。その定義において、有機的、心理的、社会的、文化的な各レベルには、 それぞれ割り当てられた、議論の余地のない場所がある。人間の本質を理解するには、人類学、社会学、心理学、生物学など、さまざまな関連科学の知見を、ま るでモアレ模様のように重ね合わせる必要があった。そして、それが完了したとき、人間に特有な唯一の文化レベルの重要性が自然に明らかになる。それは、人 間の本質について、私たちに伝えるべきことを、当然のように伝えるだろう。文化的な衣装を脱ぎ捨てた裸の思索者としての18世紀の人間像に代わって、19 世紀後半から20世紀初頭の人類学は、文化的な衣装を身にまとった変貌した動物としての人間像を提示した。 具体的な研究や特定の分析のレベルでは、この大戦略は、まず、文化における普遍性の追求、すなわち、世界中の、そして時代を超えた多様な慣習のなかで、ほ ぼ同じ形態で至る所に見出される経験的な均一性へと帰着した。次に、そのような普遍性を、いったん見出されたならば、人間の生物学、心理学、社会組織にお ける確立された定数と関連付ける試みへと帰着した。もし、世界の文化の雑然としたカタログから、そのすべての地域的変種に共通する慣習をいくつか探し出す ことができ、さらに、それらをサブカルチャーのレベルにおける特定の不変の参照点と明確な方法で結びつけることができるのであれば、少なくとも、人間の存 在にとって本質的な文化特性と、単に偶発的、周辺的、装飾的なものとの区別を明確にする上で、ある程度の進歩が遂げられるかもしれない。そうすれば、人類 学は生物学や心理学、社会学が提供する次元に匹敵する人間概念の文化的な次元を決定することができるだろう。 本質的には、これはまったく新しい考え方ではない。コンセンサス・ゲニウム(全人類のコンセンサス)という概念、すなわち、すべての人間が正しい、現実 的、公正、または魅力的であると同意するであろう事柄が存在し、それゆえ、それらの事柄は実際、正しい、現実的、公正、または魅力的であるという考え方 は、啓蒙主義の時代にも存在していたし、おそらくは、あらゆる時代や地域において、何らかの形で存在してきたであろう。それは、遅かれ早かれ、ほとんどの 人が思い浮かべるような考え方のひとつである。しかし、現代の人類学におけるその発展は、1920年代にクラーク・ウィスラーが「普遍的文化パターン」と 呼ぶものを詳細に説明したことから始まり、40年代初頭にブロニスワフ・マリノフスキーが「普遍的制度的類型」のリストを発表し、第二次世界大戦中および 戦後にG. P. モルダックが「文化の共通項」のセットを詳細に説明したことによって、新たな何かが加わった。それは、おそらくコンセンサス・ゲンティウム理論の研究者の 中で最も説得力のあるクライド・クルックホーンの言葉を引用すると、「文化のいくつかの側面は、歴史的な偶然の結果として特定の形を取る。他は、適切に 『普遍的』と指定できる力によって形作られる」という考え方を加えた。。5 これによって、人間の文化的生活は2つに分かれる。その一部は、マスコウの役者の衣装のように、ニュートン的な「内面的な動き」とは無関係であり、一部 は、その動き自体の発露である。そこで生じる疑問は、18世紀と20世紀の中間にあるこの中途半端なものは、本当に存在しうるのか、ということである。 それが可能かどうかは、サブカルチャーの現実を基盤とする文化の経験的に普遍的な側面と、そうではない経験的に可変的な側面との二元論が確立され、維持さ れるかどうかにかかっている。そして、そのためには、(1) 提案される普遍的概念が実質的なものであり、空虚なカテゴリーではないこと、(2) それらが特定の生物学的、心理学的、あるいは社会学的プロセスに明確に根ざしており、「根本的な現実」と漠然と関連しているだけではないこと、(3) それらが、より数多く存在する文化的な特殊性と比較して、はるかに重要な人類の定義の中核的要素として、説得力を持って擁護できること、が求められる。こ れら3つの点において、私には、gentiumアプローチは失敗しているように思える。むしろ、人間の状況の本質から離れてしまっている。 これらの要件の最初のもの、すなわち、普遍的とされるものが実質的なものであり、空虚なカテゴリーやそれに近いカテゴリーではないこと、という要件が満た されていない理由は、それが不可能だからである。例えば「宗教」、「結婚」、「財産」を経験普遍的であると主張し、それらにきわめて具体的な内容を与える ことは論理的に矛盾している。なぜなら、それらを経験普遍的であると主張することは、それらが同じ内容を持っていると主張することであり、同じ内容を持っ ていると主張することは、それらが同じではないという否定できない事実を無視することだからである。宗教を一般的に、かつ漠然と定義するならば、例えば 「人間にとって最も根本的な現実への志向」などと定義するならば、同時にその志向にきわめて状況依存的な内容を割り当てることはできない。なぜなら、明ら かに、 生贄の胸から引きちぎった脈打つ心臓を天に向かって掲げるアステカ族の移住者たちにとって、最も根本的な現実への志向を構成するものは、雨の恵みをもたら す慈悲深い神々への偉大な集団祈願の踊りを踊るズールー族の頑固な人々にとってのそれとは明らかに異なる。ヒンズー教徒の強迫的な儀式主義と開放的な多神 教は、スンニ派イスラム教の妥協を許さない一神教と厳格な律法主義とはかなり異なる「本当に現実的なもの」のあり方を表現している。たとえ、より抽象度の 低いレベルにまで掘り下げて、クルクホーンがしたように死後の世界という概念は普遍的であると主張したり、マリノフスキーがしたように摂理という感覚は普 遍的であると主張したりしようとしても、同じ矛盾が付きまとう。死後の世界に関する一般化を、儒教徒やカルヴァン主義者、禅仏教徒やチベット仏教徒にも等 しく当てはまるものにするためには、それを最も一般的な用語で定義しなければならない。実際、あまりにも一般的であるため、それが事実上持つと思われる力 はすべて蒸発してしまう。同様に、神の摂理に関する概念も、ナバホ族の神と人間との関係に関する概念と、トロブリアンド族の概念の両方を包含する。そし て、宗教と同様に、「結婚」、「貿易」、その他A. L. クローバーが「偽の普遍」と呼んだものすべて、さらには「住居」のような一見具体的な事柄までが当てはまる。人々がどこでも交尾をし、子供を産み、ある程 度の私とあなたの感覚を持ち、雨や日差しから何らかの方法で自分自身を守っていることは、偽りでもなければ、ある観点から見れば重要でもない。しかし、そ れらは、真実かつ誠実な肖像画であり、根拠のない「ジョン・O・パブリック」のような漫画ではない人間像を描く上で、ほとんど役には立たない。 私の主張は明確であり、これからさらに明確になると思うが、人間について一般化できることは何もないということではなく、人間は最も多様な動物であるとい うこと、あるいは文化の研究がそのような一般化の発見に貢献しないということでもない。私が言いたいのは、このような一般化は、ベーコン流の文化普遍性の 追求によって発見されるものではないということだ。それは、実際には存在しない「人類の総意」を求める世論調査のようなものであり、さらに言えば、そのよ うな試みは、まさに相対主義につながるものであり、そのアプローチ全体が明示的に回避するように設計されていたものなのだ。クルクホーンは「ズィー族の文 化は自制を重んじるが、クワキウトル族の文化は個人の露出を奨励する。これらは対照的な価値観であるが、ズィー族とクワキウトル族は、自らの文化の独特な 規範を重んじるという普遍的価値に忠実であることを示している」と書いている。6 これは単なる回避策であるが、一般的な文化の普遍性に関する議論よりも、より明白であるだけで、より回避的であるわけではない。結局のところ、ハーコ ウィッツの言うように「道徳は普遍的であり、美の享受も真理の基準も同様である」と主張したところで、そのすぐ次の文章で、彼と同じように 「これらの概念が取る多くの形態は、それらを明示する社会の特定の歴史的経験の産物に過ぎない」と付け加えなければならないとしたら?7 一度均一説を放棄すれば、たとえコンセンサス・ゲンティウム理論家のように部分的に、そして不確実なものであっても、相対主義は本物の危険である。しか し、 人間の文化の多様性、ズーフィー族の自制心やクワキウトル族の露出狂に真正面から、そして完全に立ち向かい、それらを曖昧な同語反復や説得力のない平凡な 表現で回避することなく、人間の概念の体系にそれらを取り入れることによってのみ、その危険性を回避することができる。 もちろん、実質的な文化普遍性を表現することの難しさは、gentium(全人類)のコンセンサスを求めるアプローチにおける2つ目の要件、すなわち、そ のような普遍性を特定の生物学的、心理学的、あるいは社会学的なプロセスに根拠づけることの達成をも妨げる。しかし、それ以上に重要なことがある。文化的 な要因と非文化的な要因の関係を「層位学的に」概念化することは、そのような根拠づけをさらに効果的に妨げる。文化、精神、社会、有機体がそれぞれ独立し た科学的「レベル」に変換され、それ自体が完全かつ自律的なものとなってしまうと、それらを再び統合することは非常に困難となる。 そうしようとする最も一般的な方法は、「不変の参照点」と呼ばれるものの利用である。この戦略の最も有名な文句を引用すると、この参照点は、タルコット・ パ-ソンズ、クルックホーン、O.H.テイラー、およびその他によって1940年代初頭に作成された「社会科学の分野における共通言語を目指して」という 覚書に見られる。 「社会システムの性質、構成員である個人の生物学的および心理学的性質、彼らが生活し行動する外的状況、社会システムにおける調整の必要性。文化におい て、... 構造のこれらの「焦点」は決して無視されることはない。それらは何らかの形で「適応」または「考慮」されなければならない。 文化の普遍性は、これらの避けられない現実に対する結晶化した反応であり、それらと折り合いをつけるための制度化された方法であると考えられている。 分析とは、想定される普遍性を仮定された根本的な必要性に一致させ、両者の間に適合性があることを示す試みである。社会レベルでは、すべての社会が存続す るためには、その構成員を再生産するか、商品やサービスを分配しなければならないというような、議論の余地のない事実が参照される。したがって、何らかの 形態の家族や何らかの形態の取引が普遍的に存在することになる。心理的なレベルでは、個人の成長のような基本的ニーズに頼る。そのため、教育機関が至る所 にある。あるいは、エディプスコンプレックスのような全人類的な問題に頼る。そのため、罰を与える神や育む女神が至る所にある。生物学的に見れば、新陳代 謝と健康がある。文化的に見れば、食事の習慣と治療法がある。などなど。 したがって、何らかの人間としての基本的ニーズに目を向け、普遍的な文化の側面は、クルックホーンの表現を再び借りれば、それらのニーズによって「調整」 されていることを示すことが重要である。 ここで問題となるのは、この種の一致が一般的に存在するかどうかというよりも、それが緩やかで不確定な一致以上のものなのかどうかということである。科学 (または常識)が人間の存在に必要なものとして示すものと、いくつかの人間制度とを関連付けることは難しくないが、この関係を明確な形で示すことは非常に 難しい。ほとんどあらゆる制度が、社会的、心理的、そして有機的な多様なニーズを満たしているからである(結婚は単に社会的な生殖のニーズの反射であると か、食事の習慣は代謝の必要性から生じた反射であるなどと言うのは、パロディを招くようなものだ)。また、想定される各レベル間の関係を、正確かつ検証可 能な方法で表現することは不可能である。一見したところとは裏腹に、生物学、心理学、さらには社会学の概念や理論を文化の分析に適用しようという真剣な試 みはここには見られない(もちろん、その逆の交換の示唆さえもない)。ただ、文化レベルとサブカルチャーレベルから想定される事実を並列に配置し、それら の間に何らかの関係があるのではないかという漠然とした感覚を誘発しようとしているだけである。そこには理論的な統合はまったくなく、単なる相関関係、そ して直感的な、別々の発見の相関関係があるだけである。レベル・アプローチでは、「不変の参照点」を呼び起こすことによってさえ、文化要因と非文化要因の 間に真の機能的相互関係を構築することは決してできず、説得力のある類似性、平行性、示唆、親和性のみが得られるにすぎない。 しかし、もし私が間違っているとしても(多くの人類学者がそう考えるであろうが)、コンセンサス・ジェンティウムのアプローチでは、実質的な普遍性も、文 化現象と非文化現象の間の特定の関連性も、それを説明するものも生み出せないという主張は、それでもなお、そのような普遍性を人間の定義における中心的な 要素として捉えるべきか、人間性の最低公約数的な見方が、我々が望むものなのかという疑問は残る。もちろん、これは今や哲学的な問いであり、科学的な問い ではない。しかし、人間であることの本質は、特定の民族に特有なものではなく、普遍的な人間文化の特徴において最も明確に示されるという考え方は、必ずし も共有すべき偏見ではない。人間にはどこでも何らかの「宗教」があるというような一般的な事実を理解することなのか、あるいは、バリのトランス状態やイン ドの儀式性、アステカの人身御供やズーイの雨乞いダンスといった宗教現象の豊かさを理解することなのか。「結婚」が普遍的なものであるという事実(もしそ うであるなら)は、ヒマラヤ地方の一妻多夫制や、オーストラリアの奇妙な結婚のルール、あるいはバントゥー系アフリカの複雑な結納金制度に関する事実と同 様に、私たち自身に対する鋭い洞察となっているだろうか? クロムウェルが、その時代における最も典型的な英国人であったという指摘は、まさに彼が最も奇妙な人物であったという点において、この点にも関連している かもしれない。人々の文化的な特殊性、すなわち彼らの奇妙さの中にこそ、 人間一般とは何かという最も示唆に富む発見のいくつかは、人々の文化的な特殊性、つまり彼らの奇妙さの中に見出されるのかもしれない。そして、人類学とい う科学が人間という概念の構築(または再構築)に果たす主な貢献は、それらを見つける方法を私たちに示すことにあるのかもしれない。 |
| III The major reason why anthropologists have shied away from cultural particularities when it came to a question of defining man and have taken refuge instead in bloodless universals is that, faced as they are with the enormous variation in human behavior, they are haunted by a fear of historicism, of becoming lost in a whirl of cultural relativism so convulsive as to deprive them of any fixed bearings at all. Nor has there not been some occasion for such a fear: Ruth Benedict Patterns of Culture, probably the most popular book in anthropology ever published in this country, with its strange conclusion that anything one group of people is inclined toward doing is worthy of respect by another, is perhaps only the most outstanding example of the awkward positions one can get into by giving oneself over rather too completely to what Marc Bloch called "the thrill of learning singular things." Yet the fear is a bogey. The notion that unless a cultural phenomenon is empirically universal it cannot reflect anything about the nature of man is about as logical as the notion that because sickle-cell anemia is, fortunately, not universal, it cannot tell us anything about human genetic processes. It is not whether phenomena are empirically common that is critical in science--else why should Becquerel have been so interested in the peculiar behavior of uranium?--but whether they can be made to reveal the enduring natural processes that underly them. Seeing heaven in a grain of sand is not a trick only poets can accomplish. In short, we need to look for systematic relationships among diverse phenomena, not for substantive identities among similar ones. And to do that with any effectiveness, we need to replace the "stratigraphic" conception of the relations between the various aspects of human existence with a synthetic one; that is, one in which biological, psychological, sociological, and cultural factors can be treated as variables within unitary systems of analysis. The establishment of a common language in the social sciences is not a matter of mere coordination of terminologies or, worse yet, of coining artificial new ones; nor is it a matter of imposing a single set of categories upon the area as a whole. It is a matter of integrating different types of theories and concepts in such a way that one can formulate meaningful propositions embodying findings now sequestered in separate fields of study. In attempting to launch such an integration from the anthropological side and to reach, thereby, a more exact image of man, I want to propose two ideas. The first of these is that culture is best seen not as complexes of concrete behavior patterns--customs, usages, traditions, habit clusters--as has, by and large, been the case up to now, but as a set of control mechanisms--plans, recipes, rules, instructions (what computer engineers call "programs")--for the governing of behavior. The second idea is that man is precisely the animal most desperately dependent upon such extragenetic, outside-the-skin control mechanisms, such cultural programs, for ordering his behavior. Neither of these ideas is entirely new, but a number of recent developments, both within anthropology and in other sciences (cybernetics, information theory, neurology, molecular genetics) have made them susceptible of more precise statement as well as lending them a degree of empirical support they did not previously have. And out of such reformulations of the concept of culture and of the role of culture in human life comes, in turn, a definition of man stressing not so much the empirical commonalities in his behavior, from place to place and time to time, but rather the mechanisms by whose agency the breadth and indeterminateness of his inherent capacities are reduced to the narrowness and specificity of his actual accomplishments. One of the most significant facts about us may finally be that we all begin with the natural equipment to live a thousand kinds of life but end in the end having lived only one. The "control mechanism" view of culture begins with the assumption that human thought is basically both social and public--that its natural habitat is the house yard, the marketplace, and the town square. Thinking consists not of "happenings in the head" (though happenings there and elsewhere are necessary for it to occur) but of a traffic in what have been called, by G. H. Mead and others, significant symbols--words for the most part but also gestures, drawings, musical sounds, mechanical devices like clocks, or natural objects like jewels--anything, in fact, that is disengaged from its mere actuality and used to impose meaning upon experience. From the point of view of any particular individual, such symbols are largely given. He finds them already current in the community when he is born, and they remain, with some additions, subtractions, and partial alterations he may or may not have had a hand in, in circulation after he dies. While he lives he uses them, or some of them, sometimes deliberately and with care, most often spontaneously and with ease, but always with the same end in view: to put a construction upon the events through which he lives, to orient himself within "the ongoing course of experienced things," to adopt a vivid phrase of John Dewey's. Man is so in need of such symbolic sources of illumination to find his bearings in the world because the nonsymbolic sort that are constitutionally ingrained in his body cast so diffused a light. The behavior patterns of lower animals are, at least to a much greater extent, given to them with their physical structure; genetic sources of information order their actions within much narrower ranges of variation, the narrower and more thoroughgoing the lower the animal. For man, what are innately given are extremely general response capacities, which, although they make possible far greater plasticity, complexity, and, on the scattered occasions when everything works as it should, effectiveness of behavior, leave it much less precisely regulated. This, then, is the second face of our argument: Undirected by culture patterns--organized systems of significant symbols--man's behavior would be virtually ungovernable, a mere chaos of pointless acts and exploding emotions, his experience virtually shapeless. Culture, the accumulated totality of such patterns, is not just an ornament of human existence but--the principal basis of its specificity--an essential condition for it. Within anthropology some of the most telling evidence in support of such a position comes from recent advances in our understanding of what used to be called the descent of man: the emergence of Homo sapiens out of his general primate background. Of these advances three are of critical importance: (1) the discarding of a sequential view of the relations between the physical evolution and the cultural development of man in favor of an overlap or interactive view; (2) the discovery that the bulk of the biological changes that produced modern man out of his most immediate progenitors took place in the central nervous system and most especially in the brain; (3) the realization that man is, in physical terms, an incomplete, an unfinished, animal; that what sets him off most graphically from nonmen is less his sheer ability to learn (great as that is) than how much and what particular sorts of things he has to learn before he is able to function at all. Let me take each of these points in turn. The traditional view of the relations between the biological and the cultural advance of man was that the former, the biological, was for all intents and purposes completed before the latter, the cultural, began. That is to say, it was again stratigraphic: Man's physical being evolved, through the usual mechanisms of genetic variation and natural selection, up to the point where his anatomical structure had arrived at more or less the status at which we find it today; then cultural development got under way. At some particular stage in his phylogenetic history, a marginal genetic change of some sort rendered him capable of producing and carrying culture, and thenceforth his form of adaptive response to environmental pressures was almost exclusively cultural rather than genetic. As he spread over the globe, he wore furs in cold climates and loin cloths (or nothing at all) in warm ones; he didn't alter his innate mode of response to environmental temperature. He made weapons to extend his inherited predatory powers and cooked foods to render a wider range of them digestible. Man became man, the story continues, when, having crossed some mental Rubicon, he became able to transmit "knowledge, belief, law, morals, custom" (to quote the items of Sir Edward Tylor's classical definition of culture) to his descendants and his neighbors through teaching and to acquire them from his ancestors and his neighbors through learning. After that magical moment, the advance of the hominids depended almost entirely on cultural accumulation, on the slow growth of conventional practices, rather than, as it had for ages past, on physical organic change. The only trouble is that such a moment does not seem to have existed. By the most recent estimates the transition to the cultural mode of life took the genus Homo several million years to accomplish; and stretched out in such a manner, it involved not one or a handful of marginal genetic changes but a long, complex, and closely ordered sequence of them. In the current view, the evolution of Homo sapiens--modern man-out of his immediate presapiens background got definitely under way nearly four million years ago with the appearance of the now famous Australopithecines--the so-called ape men of southern and eastern Africa--and culminated with the emergence of sapiens himself only some one to two or three hundred thousand years ago. Thus, as at least elemental forms of cultural, or if you wish protocultural, activity (simple toolmaking, hunting, and so on) seem to have been present among some of the Australopithecines, there was an overlap of, as I say, well over a million years between the beginning of culture and the appearance of man as we know him today. The precise dates--which are tentative and which further research may later alter in one direction or another--are not critical; what is critical is that there was an overlap and that it was a very extended one. The final phases (final to date, at any rate) of the phylogenetic history of man took place in the same grand geological era--the so-called Ice Age--as the initial phases of his cultural history. Men have birthdays, but man does not. What this means is that culture, rather than being added on, so to speak, to a finished or virtually finished animal, was ingredient, and centrally ingredient, in the production of that animal itself. The slow, steady, almost glacial growth of culture through the Ice Age altered the balance of selection pressures for the evolving Homo in such a way as to play a major directive role in his evolution. The perfection of tools, the adoption of organized hunting and gathering practices, the beginnings of true family organization, the discovery of fire, and, most critically, though it is as yet extremely difficult to trace it out in any detail, the increasing reliance upon systems of significant symbols (language, art, myth, ritual) for orientation, communication, and self-control all created for man a new environment to which he was then obliged to adapt. As culture, step by infinitesimal step, accumulated and developed, a selective advantage was given to those individuals in the population most able to take advantage of it--the effective hunter, the persistent gatherer, the adept toolmaker, the resourceful leader--until what had been a small-brained, protohuman Australopithecus became the largebrained fully human Homo sapiens. Between the cultural pattern, the body, and the brain, a positive feedback system was created in which each shaped the progress of the other, a system in which the interaction among increasing tool use, the changing anatomy of the hand, and the expanding representation of the thumb on the cortex is only one of the more graphic examples. By submitting himself to governance by symbolically mediated programs for producing artifacts, organizing social life, or expressing emotions, man determined, if unwittingly, the culminating stages of his own biological destiny. Quite literally, though quite inadvertently, he created himself. Though, as I mentioned, there were a number of important changes in the gross anatomy of genus Homo during this period of his crystallization--in skull shape, dentition, thumb size, and so on--by far the most important and dramatic were those that evidently took place in the central nervous system; for this was the period when the human brain, and most particularly the forebrain, ballooned into its present top-heavy proportions. The technical problems are complicated and controversial here; but the main point is that though the Australopithecines had a torso and arm configuration not drastically different from our own, and a pelvis and leg formation at least well-launched toward our own, they had cranial capacities hardly larger than those of the living apes--that is to say, about a third to a half of our own. What sets true men off most distinctly from protomen is apparently not overall bodily form but complexity of nervous organization. The overlap period of cultural and biological change seems to have consisted in an intense concentration on neural development and perhaps associated refinements of various behaviors--of the hands, bipedal locomotion, and so on--for which the basic anatomical foundations--mobile shoulders and wrists, a broadened ilium, and so on--had already been securely laid. In itself, this is perhaps not altogether startling; but, combined with what I have already said, it suggests some conclusions about what sort of animal man is that are, I think, rather far not only from those of the eighteenth century but from those of the anthropology of only ten or fifteen years ago. Most bluntly, it suggests that there is no such thing as a human nature independent of culture. Men without culture would not be the clever savages of Golding Lord of the Flies thrown back upon the cruel wisdom of their animal instincts; nor would they be the nature's noblemen of Enlightenment primitivism or even, as classical anthropological theory would imply, intrinsically talented apes who had somehow failed to find themselves. They would be unworkable monstrosities with very few useful instincts, fewer recognizable sentiments, and no intellect: mental basket cases. As our central nervous system--and most particularly its crowning curse and glory, the neocortex--grew up in great part in interaction with culture, it is incapable of directing our behavior or organizing our experience without the guidance provided by systems of significant symbols. What happened to us in the Ice Age is that we were obliged to abandon the regularity and precision of detailed genetic control over our conduct for the flexibility and adaptability of a more generalized, though of course no less real, genetic control over it. To supply the additional information necessary to be able to act, we were forced, in turn, to rely more and more heavily on cultural sources--the accumulated fund of significant symbols. Such symbols are thus not mere expressions, instrumentalities, or correlates of our biological, psychological, and social existence; they are prerequisites of it. Without men, no culture, certainly; but equally, and more significantly, without culture, no men. We are, in sum, incomplete or unfinished animals who complete or finish ourselves through culture--and not through culture in general but through highly particular forms of it: Dobuan and Javanese, Hopi and Italian, upper-class and lower-class, academic and commercial. Man's great capacity for learning, his plasticity, has often been remarked, but what is even more critical is his extreme dependence upon a certain sort of learning: the attainment of concepts, the apprehension and application of specific systems of symbolic meaning. Beavers build dams, birds build nests, bees locate food, baboons organize social groups, and mice mate on the basis of forms of learning that rest predominantly on the instructions encoded in their genes and evoked by appropriate patterns of external stimuli: physical keys inserted into organic locks. But men build dams or shelters, locate food, organize their social groups, or find sexual partners under the guidance of instructions encoded in flow charts and blueprints, hunting lore, moral systems and aesthetic judgments: conceptual structures molding formless talents. We live, as one writer has neatly put it, in an "information gap." Between what our body tells us and what we have to know in order to function, there is a vacuum we must fill ourselves, and we fill it with information (or misinformation) provided by our culture. The boundary between what is innately controlled and what is culturally controlled in human behavior is an ill-defined and wavering one. Some things are, for all intents and purposes, entirely controlled intrinsically: we need no more cultural guidance to learn how to breathe than a fish needs to learn how to swim. Others are almost certainly largely cultural; we do not attempt to explain on a genetic basis why some men put their trust in centralized planning and others in the free market, though it might be an amusing exercise. Almost all complex human behavior is, of course, the interactive, nonadditive outcome of the two. Our capacity to speak is surely innate; our capacity to speak English is surely cultural. Smiling at pleasing stimuli and frowning at unpleasing ones are surely in some degree genetically determined (even apes screw up their faces at noxious odors); but sardonic smiling and burlesque frowning are equally surely predominantly cultural, as is perhaps demonstrated by the Balinese definition of a madman as someone who, like an American, smiles when there is nothing to laugh at. Between the basic ground plans for our life that our genes lay down--the capacity to speak or to smile--and the precise behavior we in fact execute--speaking English in a certain tone of voice, smiling enigmatically in a delicate social situation--lies a complex set of significant symbols under whose direction we transform the first into the second, the ground plans into the activity. Our ideas, our values, our acts, even our emotions, are, like our nervous system itself, cultural products--products manufactured, indeed, out of tendencies, capacities, and dispositions with which we were born, but manufactured nonetheless. Chartres is made of stone and glass. But it is not just stone and glass; it is a cathedral, and not only a cathedral, but a particular cathedral built at a particular time by certain members of a particular society. To understand what it means, to perceive it for what it is, you need to know rather more than the generic properties of stone and glass and rather more than what is common to all cathedrals. You need to understand also--and, in my opinion, most critically--the specific concepts of the relations among God, man, and architecture that, since they have governed its creation, it consequently embodies. It is no different with men: they, too, every last one of them, are cultural artifacts. |
III 人類学者が人間を定義するにあたり文化の特殊性から遠ざかり、代わりに血の通わない普遍性に逃げ込んできた主な理由は、彼らが人間の行動における膨大な変 化に直面しているため、歴史主義への恐怖に悩まされ、文化相対主義の渦に飲み込まれ、固定観念を一切失うことになるという激しい不安に駆られているからで ある。このような恐怖心を抱く理由がないわけではない。ルース・ベネディクト著『文化のパターン』は、おそらくこの国で出版された人類学の書籍の中で最も 人気のある本であるが、その奇妙な結論は、ある集団が好むものは何であれ、他の集団も尊重に値するというものだ。これは、マーク・ブロックが「特異なこと を学ぶスリル」と呼んだものに完全に身をゆだねることによって陥る厄介な状況の最も顕著な例である。しかし、この恐怖心は杞憂である。文化現象が経験的に 普遍的でなければ、人間の性質について何も反映できないという考え方は、鎌状赤血球貧血症が幸いにも普遍的ではないから、人間の遺伝的プロセスについて何 も教えてくれないという考え方と同じくらい論理的である。科学において重要なのは、現象が経験的に共通しているかどうかではなく、それらの現象が、その背 後にある永続的な自然のプロセスを明らかにできるかどうかである。砂粒の中に天国を見出すことは、詩人だけができる芸当ではない。 つまり、類似したもの同士の本質的な同一性ではなく、多様な現象間の体系的な関係性を求める必要があるのだ。そして、それを効果的に行うためには、人間の 存在のさまざまな側面間の関係性に対する「層位学的」な考え方を、統合的な考え方に置き換える必要がある。つまり、生物学的、心理学的、社会学、文化的な 要因を、分析の単一システム内の変数として扱うことができるような考え方である。社会科学における共通言語の確立とは、用語の調整や、さらに悪いことに は、人為的に新しい用語を考案することではない。また、その分野全体に単一のカテゴリーを押し付けることでもない。それは、異なるタイプの理論や概念を統 合し、現在では個別の研究分野に分断されている知見を体現する意味のある命題を構築することである。 人類学の側からこのような統合を試み、それによってより正確な人間像に到達しようとする中で、私は2つの考えを提案したい。その第一は、文化とは、これま で概ねそうであったように、習慣、慣習、伝統、習性といった具体的な行動様式の集合体としてではなく、行動を統制するための一連の制御メカニズム、すなわ ち計画、処方、規則、指示(コンピューター技術者が「プログラム」と呼ぶもの)として捉えるのが最善であるという考えである。2つ目の考えは、人間はまさ に、自身の行動を秩序立てるために、このような遺伝によらない、外的な制御メカニズム、つまり文化プログラムに最も強く依存している動物であるということ だ。 これらの考え方はどちらもまったく新しいものではないが、人類学やその他の科学(サイバネティクス、情報理論、神経学、分子遺伝学)における最近の多くの 進展により、これらの考え方はより正確に表現できるようになり、また以前にはなかった程度の経験的な裏付けも得られるようになった。そして、文化の概念 や、人間の生活における文化の役割の再定義から、人間を定義する新たな定義が生まれる。それは、場所や時代によって異なる人間の行動の経験的な共通点では なく、むしろ、人間の本質的な能力の幅広さや不確定さが、その能力を実際の成果の狭さや特異性に還元するメカニズムを強調するものである。私たちに関する 最も重要な事実の一つは、最終的には、私たちは皆、千種類もの人生を送るための自然な素質を備えて生まれてくるが、結局は一つの人生しか生きないというこ とかもしれない。 文化の「制御メカニズム」という見方は、人間の思考は基本的に社会的かつ公共的なものであり、その自然な生息地は家屋敷、市場、広場であるという仮定から 始まる。思考は「頭の中で起こる出来事」から成るのではなく(とはいえ、頭の中で、あるいは他の場所で起こる出来事は、思考が起こるために必要である)、 G.H.ミードや他の人々によって「重要な象徴」と呼ばれたもののやりとりから成る。そのほとんどは言葉であるが、ジェスチャー、絵、音楽、時計のような 機械装置、あるいは宝石のような自然物など、あらゆるものが含まれる。つまり、単なる現実から切り離され、経験に意味を与えるために用いられるものすべて である。特定の個人から見ると、そのようなシンボルはほとんど与えられたものである。その人は自分が生まれたときにはすでにコミュニティで広く使われてい たそれらを見つけ、自分が手を加えたか加えなかったかに関わらず、多少の追加や削除、部分的な変更を加えながら、自分が死んだ後もそれらは流通し続ける。 彼が生きている間、彼はそれらを使う。時には意図的に注意深く、そしてほとんどの場合は自然に、そして容易にそれらを使うが、常に同じ目的のために使う。 すなわち、彼が生きている出来事の上に構造を築き、ジョン・デューイの鮮やかな表現を借りれば、「経験される事柄の進行中の流れ」の中で自らを方向づける ためである。 人間は、世界で自分の位置を見つけるために、このような象徴的な啓発の源を必要としている。なぜなら、人間の身体に本質的に染みついている非象徴的なもの は、あまりにも拡散した光を放つからだ。下等動物の行動パターンは、少なくともはるかに大きな程度において、その物理的構造によって与えられる。遺伝的な 情報源は、その行動をより狭い範囲の変化の中で秩序づける。その範囲は、動物がより低級であるほど、より狭く徹底したものとなる。人間の場合、生得的に与 えられているのは極めて一般的な反応能力であり、それによってはるかに大きな可塑性、複雑性、そしてすべてが意図した通りに機能するごくまれな場面での行 動の有効性が可能になるが、行動ははるかに正確に制御されないままになる。これが、私たちの議論の第二の側面である。文化パターン(重要な象徴の体系化さ れたシステム)の指揮を受けない人間の行動は、事実上統制不能であり、無意味な行為と爆発する感情の混沌にすぎず、その経験は事実上形のないものとなる。 文化とは、このようなパターンの蓄積された全体であり、人間の存在を装飾するだけでなく、その特異性の主な基盤であり、人間にとって不可欠な条件である。 人類学において、このような立場を裏付ける最も説得力のある証拠のいくつかは、かつて「人類の進化」と呼ばれていたものの理解が近年進んだことによる。そ の進化とは、霊長類全般の背景からホモ・サピエンスが出現したことである。これらの進歩のうち、特に重要なものは以下の3つである。(1) 人間の身体的進化と文化発展の関係について、連続的な見方を捨て、重複または相互作用的な見方を支持するようになったこと。 (2) 現生人類を最も近い先祖から生み出した生物学的変化の大部分が、中枢神経系、特に脳で起こったという発見 (3)人間は物理的には不完全で未完成な動物であるという認識。人間を人間以外の動物と最も際立って区別しているのは、その学習能力の高さ(それは素晴ら しいことだが)というよりも、人間が機能を発揮できるようになるまでに、どれだけの量の、そしてどのような種類のことを学ばなければならないかということ である。これらの点を順番に見ていこう。 生物学的進化と文化的な進歩の関係に関する従来の考え方は、生物学的進化は文化的な進化が始まる前にあらゆる意味で完了しているというものだった。つま り、それはまた地層のようなもので、遺伝子変異と自然淘汰の通常のメカニズムを通じて、人間の身体は進化し、解剖学的構造はほぼ今日見られるような状態に まで達した。そして、文化的な発展が始まった。進化の歴史のある特定の段階で、ごくわずかな遺伝的変化が、文化を生み出し、継承する能力を人間にもたらし た。それ以来、環境からの圧力に対する適応反応の形は、ほぼ遺伝的というよりも文化的となった。地球上に広がった人間は、寒冷地では毛皮をまとい、温暖な 地域では腰布(あるいは何も身に着けず)で過ごした。また、受け継いだ捕食能力をさらに伸ばすために武器を作り、より幅広い種類の食物を消化できるように 調理した。人間は、精神的なルビコン川を渡り、教えることで「知識、信念、法、道徳、慣習」(エドワード・テイラー卿による文化の古典的定義の項目を引 用)を子孫や隣人に伝え、学ぶことでそれらを祖先や隣人から習得できるようになって、人間となった。その魔法のような瞬間以降、人類の進化は、過去何世紀 にもわたってそうであったような肉体的な有機的変化ではなく、文化の蓄積、慣習の緩やかな成長にほぼ完全に依存するようになった。 唯一の問題は、そのような瞬間は存在しなかったように思われることだ。最新の推定によると、文化的生活様式への移行は、ホモ属が数百万年かけて達成したも のであり、その過程では、限界的な遺伝的変化が1つや数個ではなく、長期間にわたって複雑かつ綿密に秩序立てられた形で生じた。 現在の見解では、ホモ・サピエンス(現生人類)の進化は、その直前のプレサピエンスの時代から、今では有名なアウストラロピテクス(いわゆるアフリカ南部 および東部の類人猿)が出現した約400万年前に確実に始まり、サピエンス自身が出現したのがわずか10万~20万~30万年前という短期間でピークに達 した。したがって、文化活動の少なくとも初歩的な形態、あるいはプロト文化活動(単純な道具作りや狩猟など)が、アウストラロピテクスの一部には存在して いたと思われることから、私が言うところの文化の始まりと、今日私たちが知るような人間の登場との間には、100万年以上の重複があったことになる。正確 な年代は暫定的なものであり、今後のさらなる研究によっていずれかの方向に変更される可能性があるが、重要なのは、重複があったということ、そしてそれが 非常に長期にわたるものであったということである。人類の系統発生史の最終段階(少なくとも現時点での最終段階)は、人類の文化史の初期段階と同じ壮大な 地質年代、すなわちいわゆる氷河期に起こった。人間にも誕生日があるが、人類にはない。 つまり、文化は、いわば完成した、あるいはほぼ完成した動物に付け加えられるものではなく、その動物自体の生産における主要な要素であったということだ。 氷河期を通じてゆっくりと着実に、氷河のごとく成長した文化は、進化するホモ・サピエンスに対する選択圧のバランスを変化させ、進化に大きな方向性を与え る役割を果たした。道具の完成、組織化された狩猟採集の実践の採用、真の家族組織の始まり、火の発見、そして最も重要なこととして、まだ詳細を辿るのは非 常に困難であるが、方向性、コミュニケーション、自己制御のための重要なシンボル(言語、芸術、神話、儀式)の体系への依存の増加が、すべて人間にとって 新たな環境を作り出し、人間はそれに適応せざるを得なくなった。文化が、無限小のステップを踏みながら蓄積され、発展するにつれ、その恩恵を最大限に活用 できる個人が有利になっていった。すなわち、有能なハンター、根気強い採集者、熟練した道具製作者、機転の利くリーダーなどである。そして、頭の小さな原 人であったアウストラロピテクスは、頭の大きな完全な人間ホモ・サピエンスへと進化していった。文化パターン、身体、脳の間には、それぞれが他方の進歩を 形作るポジティブ・フィードバック・システムが生まれた。このシステムは、道具の使用の増加、手の解剖学的な変化、大脳皮質における親指の表現の拡大と いった相互作用の例を挙げることができる。人工物を生産したり、社会生活を組織化したり、感情を表現したりするための象徴的な媒介プログラムによる統治に 自らを委ねることで、人間は知らず知らずのうちに、自身の生物学的運命の絶頂期を決定した。文字通り、まったくの偶然ではあるが、人間は自らを創造したの だ。 しかし、私が述べたように、この人類の結晶化の期間中、属ホモの全体的な解剖学には、頭蓋骨の形状、歯列、親指の大きさなど、多くの重要な変化があった。 しかし、最も重要で劇的な変化は、明らかに中枢神経系で起こったものであり、この期間に人間の脳、特に前頭葉が現在のトップヘビーな比率にまで肥大化し た。技術的な問題は複雑で議論の余地があるが、要点はこうだ。アウストラロピテクスは胴体と腕の形状が我々と大きく変わらず、骨盤と脚の形成も少なくとも 我々に向かって順調に発達していたが、頭蓋容積は現生類人猿のそれとほとんど変わらず、つまり我々の3分の1から半分程度であった。真の人間を原人から最 も明確に区別しているのは、身体全体の形ではなく、神経組織の複雑さである。文化と生物の変化が重複した時期は、神経の発達に集中的に取り組んだ時期であ り、おそらくは、手の動きや二足歩行など、さまざまな行動の洗練化にも取り組んだ時期であった。その基礎となる解剖学的基盤、すなわち、可動式の肩や手 首、広がった腸骨などは、すでにしっかりと確立されていた。それ自体は、それほど驚くようなことではないかもしれない。しかし、私がすでに述べたことと組 み合わせると、人間とはどのような動物であるかについての結論を示唆している。それは、18世紀の考え方だけでなく、わずか10年か15年前の人類学の考 え方からも、かなりかけ離れていると思う。 端的に言えば、文化から独立した人間の本性など存在しないということだ。文化を持たない人間は、ゴールディングの『蝿の王』に登場する賢い野蛮人たちのよ うに、残酷な本能の知恵に立ち返ることはないだろう。また、啓蒙主義的原始主義の自然の貴族であることも、古典的な人類学理論が暗示するように、本質的に 才能のある類人猿が何らかの理由で自分自身を見失っているということもないだろう。彼らは、ほとんど役に立たない本能と、さらに少ない認識可能な感情、そ して知性を持たない、手に負えない怪物である。精神的に異常な人間である。私たちの中枢神経系、特にその頂点にある呪いと栄光、新皮質は、文化との相互作 用によって大部分が成長したため、重要なシンボルの体系による指針なしには、私たちの行動を導いたり、経験を整理したりすることができない。氷河期に私た ちに起こったことは、行動に対する詳細な遺伝子制御の規則性と正確性を、より一般的な、もちろんそれほど現実的ではない遺伝子制御の柔軟性と適応性のため に放棄せざるを得なかったことだ。行動するために必要な追加情報を得るために、私たちは、重要なシンボルの蓄積された資金である文化的な情報源にますます 頼らざるを得なくなった。このような象徴は、したがって、単なる表現や道具、あるいは生物学的、心理学的、社会的存在の相関物ではない。それらは、それら の存在の前提条件なのである。人間がいなければ文化は存在しないが、同様に、より重要なのは、文化がなければ人間も存在しないということだ。 つまり、私たちは、文化を通じて自らを完成させ、あるいは完成させる、不完全な、あるいは未完成の動物なのである。ただし、文化一般を通じてではなく、き わめて特殊な形態の文化を通じて、である。ドブアンとジャワ人、ホピ族とイタリア人、上流階級と下流階級、学術と商業などである。人間の学習能力の高さ、 可塑性についてはよく言われているが、さらに重要なのは、人間が特定の学習に極度に依存していることである。概念の獲得、特定の象徴的意味体系の理解と応 用などである。ビーバーはダムを築き、鳥は巣を作り、ミツバチは餌を見つけ、ヒヒは社会集団を組織し、ネズミは交尾を行う。これらは主に遺伝子にコード化 された指示に基づいており、有機的な錠に物理的な鍵を差し込むといった適切な外部刺激のパターンによって引き起こされる学習形態である。しかし、人間はダ ムや避難所を建設し、食料を見つけ、社会集団を組織し、あるいは性的パートナーを見つけるにあたっては、フローチャートや設計図に記された指示、狩猟の知 識、道徳体系、美的判断などの指針に従う。 ある作家がうまく表現しているように、私たちは「情報ギャップ」の中で生きている。身体が私たちに伝えることと、機能するために知っておかなければならな いこととの間には、自ら埋めなければならない空白がある。そして、私たちは文化から得た情報(または誤った情報)でそれを埋める。人間行動において、生得 的に制御されているものと文化的に制御されているものとの境界は、あいまいかつ揺れ動くものである。呼吸の仕方を学ぶのに魚が泳ぎ方を学ぶ必要がないよう に、呼吸の仕方は生まれつき完全に制御されている。一方、中央計画に信頼を置く人と自由市場に信頼を置く人がいる理由を遺伝子的な観点から説明しようとす る人はいないだろう。もちろん、ほとんどの複雑な人間の行動は、この2つの相互作用によるものであり、足し算ではない。話す能力は生まれつき備わっている が、英語を話す能力は文化によって培われる。好ましい刺激には微笑み、好ましくない刺激にはしかめっ面をするのは、ある程度遺伝的に決定されている(有害 な臭いに対して顔をしかめるのはサルでも同じ)。しかし、皮肉な微笑みや茶番じみたしかめっ面は、文化的な要素が強い。バリ島では、アメリカ人のように、 笑うべきことが何もないのに笑う人を狂人だと定義している。私たちの遺伝子が定める、私たちの生活の基本的な設計図――話す能力や微笑む能力――と、私た ちが実際に行う正確な行動――ある口調で英語を話す、微妙な社会的状況で謎めいた微笑みを浮かべる――の間には、重要な象徴の複雑な集合があり、その集合 の指示に従って、私たちは前者を後者に、設計図を活動に変える。 私たちの考え、価値観、行動、そして感情さえも、私たちの神経系そのものと同様に、文化的な産物である。つまり、生まれながらに備わっている傾向、能力、 性向から生み出された産物である。シャルトルは石とガラスでできている。しかし、それは単なる石とガラスではなく、大聖堂であり、単なる大聖堂ではなく、 特定の社会の特定の構成員が特定の時代に建てた特別な大聖堂である。その意味を理解し、ありのままに認識するためには、石やガラスの一般的な性質や、すべ ての聖堂に共通する特徴以上の知識が必要である。また、私の意見では最も重要なこととして、神、人間、建築の関係という特定の概念を理解する必要がある。 この関係は、建築物の創造を支配してきたものであり、その結果、建築物はそれを体現している。人間も同様である。人間もまた、一人残らず文化的な産物であ る。 |
| IV Whatever differences they may show, the approaches to the definition of human nature adopted by the Enlightenment and by classical anthropology have one thing in common: they are both basically typological. They endeavor to construct an image of man as a model, an archetype, a Platonic idea or an Aristotelian form, with respect to which actual men--you, me, Churchill, Hitler, and the Bornean headhunter--are but reflections, distortions, approximations. In the Enlightenment case, the elements of this essential type were to be uncovered by stripping the trappings of culture away from actual men and seeing what then was left--natural man. In classical anthropology, it was to be uncovered by factoring out the commonalities in culture and seeing what then appeared --consensual man. In either case, the result is the same as that which tends to emerge in all typological approaches to scientific problems generally: the differences among individuals and among groups of individuals are rendered secondary. Individuality comes to be seen as eccentricity, distinctiveness as accidental deviation from the only legitimate object of study for the true scientist: the underlying, unchanging, normative type. In such an approach, however elaborately formulated and resourcefully defended, living detail is drowned in dead stereotype: we are in quest of a metaphysical entity, Man with a capital "M," in the interests of which we sacrifice the empirical entity we in fact encounter, man with a small "m." The sacrifice is, however, as unnecessary as it is unavailing. There is no opposition between general theoretical understanding and circumstantial understanding, between synoptic vision and a fine eye for detail. It is, in fact, by its power to draw general propositions out of particular phenomena that a scientific theory--indeed, science itself--is to be judged. If we want to discover what man amounts to, we can only find it in what men are: and what men are, above all other things, is various. It is in understanding that variousness--its range, its nature, its basis, and its implications--that we shall come to construct a concept of human nature that, more than a statistical shadow and less than a primitivist dream, has both substance and truth. It is here, to come round finally to my title, that the concept of culture has its impact on the concept of man. When seen as a set of symbolic devices for controlling behavior, extrasomatic sources of information, culture provides the link between what men are intrinsically capable of becoming and what they actually, one by one, in fact become. Becoming human is becoming individual, and we become individual under the guidance of cultural patterns, historically created systems of meaning in terms of which we give form, order, point, and direction to our lives. And the cultural patterns involved are not general but specific--not just "marriage" but a particular set of notions about what men and women are like, how spouses should treat one another, or who should properly marry whom; not just "religion" but belief in the wheel of karma, the observance of a month of fasting, or the practice of cattle sacrifice. Man is to be defined neither by his innate capacities alone, as the Enlightenment sought to do, nor by his actual behaviors alone, as much of contemporary social science seeks to do, but rather by the link between them, by the way in which the first is transformed into the second, his generic potentialities focused into his specific performances. It is in man's career, in its characteristic course, that we can discern, however dimly, his nature, and though culture is but one element in determining that course, it is hardly the least important. As culture shaped us as a single species--and is no doubt still shaping us--so too it shapes us as separate individuals. This, neither an unchanging subcultural self nor an established cross-cultural consensus, is what we really have in common. Oddly enough--though on second thought, perhaps not so oddlymany of our subjects seem to realize this more clearly than we anthropologists ourselves. In Java, for example, where I have done much of my work, the people quite flatly say, "To be human is to be Javanese." Small children, boors, simpletons, the insane, the flagrantly immoral, are said to be ndurung djawa, "not yet Javanese." A "normal" adult capable of acting in terms of the highly elaborate system of etiquette, possessed of the delicate aesthetic perceptions associated with music, dance, drama, and textile design, responsive to the subtle promptings of the divine residing in the stillnesses of each individual's inward-turning consciousness, is sampun djawa, "already Javanese," that is, already human. To be human is not just to breathe; it is to control one's breathing, by yogalike techniques, so as to hear in inhalation and exhalation the literal voice of God pronouncing His own name--"hu Allah." It is not just to talk, it is to utter the appropriate words and phrases in the appropriate social situations in the appropriate tone of voice and with the appropriate evasive indirection. It is not just to eat; it is to prefer certain foods cooked in certain ways and to follow a rigid table etiquette in consuming them. It is not even just to feel but to feel certain quite distinctively Javanese (and essentially untranslatable) emotions--"patience," "detachment," resignation," "respect." To be human here is thus not to be Everyman; it is to be a particular kind of man, and of course men differ: "Other fields," the Javanese say, "other grasshoppers." Within the society, differences are recognized, too--the way a rice peasant becomes human and Javanese differs from the way a civil servant does. This is not a matter of tolerance and ethical relativism, for not all ways of being human are regarded as equally admirable by far; the way the local Chinese go about it is, for example, intensely dispraised. The point is that there are different ways; and to shift to the anthropologist's perspective now, it is in a systematic review and analysis of these--of the Plains Indian's bravura, the Hindu's obsessiveness, the Frenchman's rationalism, the Berber's anarchism, the American's optimism (to list a series of tags I should not like to have to defend as such)--that we shall find out what it is, or can be, to be a man. We must, in short, descend into detail, past the misleading tags, past the metaphysical types, past the empty similarities to grasp firmly the essential character of not only the various cultures but the various sorts of individuals within each culture, if we wish to encounter humanity face to face. In this area, the road to the general, to the revelatory simplicities of science, lies through a concern with the particular, the circumstantial, the concrete, but a concern organized and directed in terms of the sort of theoretical analyses that I have touched upon--analyses of physical evolution, of the functioning of the nervous system, of social organization, of psychological process, of cultural patterning, and so on --and, most especially, in terms of the interplay among them. That is to say, the road lies, like any genuine Quest, through a terrifying complexity. "Leave him alone for a moment or two," Robert Lowell writes, not as one might suspect of the anthropologist but of that other eccentric inquirer into the nature of man, Nathaniel Hawthorne. Leave him alone for a moment or two, and you'll see him with his head bent down, brooding, brooding, eyes fixed on some chip, some stone, some common plant, the commonest thing, as if it were the clue. The disturbed eyes rise, furtive, foiled, dissatisfied from meditation on the true and insignificant.8 Bent over his own chips, stones, and common plants, the anthropologist broods, too, upon the true and insignificant, glimpsing in it, or so he thinks, fleetingly and insecurely, the disturbing, changeful image of himself. |
IV 啓蒙思想と古典的人間学が採用した人間性の定義へのアプローチには、どのような違いがあるにせよ、1つの共通点がある。それは、両者とも基本的に類型論的 であるということだ。彼らは、人間をモデル、原型、プラトニックな理念、あるいはアリストテレス的な形として捉え、そのイメージを構築しようとする。その イメージに対して、実際の人間、すなわちあなた、私、チャーチル、ヒトラー、ボルネオの首狩り族は、その反映、歪曲、近似にすぎない。啓蒙主義の場合、こ の本質的なタイプの要素は、実際の人間から文化的な装飾を剥ぎ取り、何が残るかを見ることで明らかにされる。古典的人類学では、文化における共通項を排除 し、何が現れるかを見ることで明らかにされる。いずれの場合も、科学的な問題に対する類型論的アプローチで一般的に見られる傾向と同じ結果となる。すなわ ち、個人間および個人グループ間の相違は二次的なものとして扱われる。個性は偏屈として、独自性は真の科学者にとって唯一の研究対象である、不変の規範的 タイプからの偶然の逸脱として見られるようになる。しかし、そのようなアプローチでは、どんなに精巧に理論化され、機知に富んだ形で擁護されたとしても、 生き生きとした細部は死んだ固定観念に埋もれてしまう。私たちは、大文字の「M」で表される形而上学的存在としての人間を追い求めている。そのために、実 際に遭遇する経験的な存在である小文字の「m」で表される人間を犠牲にしているのだ。 しかし、その犠牲は不必要であると同時に無益でもある。一般的な理論的理解と状況的理解、全体像を把握する視野と細部にこだわる目の間には、何の対立もな い。実際、特定の現象から一般的な命題を引き出す力によって、科学的理論、つまり科学そのものが評価されるのである。人間とは何かを解明したいのであれ ば、人間が何であるかを見出さなければならない。そして、人間とは何であるか、とりわけ他のあらゆるものよりも、多様である。その範囲、性質、基礎、含意 といった多様性を理解することによって、統計的な影よりも、原始主義者の夢よりも、実体と真実を兼ね備えた人間の本質という概念を構築することができるだ ろう。 ここでようやく、私のタイトルに戻ることになるが、文化という概念が人間という概念に影響を与えるのはこの点である。行動を制御するための象徴的な手段の 集合体として捉える場合、身体の外にある情報源として捉える場合、文化は人間が本質的に成り得るものと、実際に一人一人が実際になるものとの間のつながり を提供する。人間になることは個性的になることであり、私たちは文化的なパターン、すなわち歴史的に形成された意味体系の指導の下で個性的になる。この体 系は、私たちが人生に形を与え、秩序を整え、要点を明らかにし、方向性を示すためのものである。そして、関与する文化的パターンは一般的なものではなく、 特定のものです。「結婚」というだけでなく、男女とはどのような存在か、配偶者同士はどのように接するべきか、誰と誰が結婚すべきかといった特定の概念の 集合体です。「宗教」というだけでなく、因果応報の輪への信仰、1ヶ月間の断食の遵守、家畜の生け贄の儀式などです。人間は、啓蒙主義が追求したような生 まれながらの能力のみによって定義されるものではなく、また、現代の社会科学の多くが追求しているような実際の行動のみによって定義されるものでもない。 むしろ、それらの間のつながり、すなわち、前者が後者に変換される方法、一般的な潜在能力が具体的なパフォーマンスに集約される方法によって定義されるべ きである。人間のキャリア、その特徴的な経過において、私たちは人間の性質を、たとえぼんやりとではあるが、見分けることができる。文化はその経過を決定 する要素の一つにすぎないが、しかし、それは最も重要でない要素というわけではない。文化が私たちを一つの種として形作ってきたように、そして今も形作っ ているように、文化は私たちを個々の個人としても形作っている。これは、不変のサブカルチャー的な自己でも、確立されたクロスカルチャー的なコンセンサス でもない。これが、私たちが本当に共有しているものである。 奇妙なことに、よく考えてみると、おそらくそれほど奇妙なことではないが、私たち人類学者よりも多くの被験者がこのことをより明確に理解しているように見 える。例えば、私が多くの時間を費やしたジャワでは、人々ははっきりとこう言う。「人間であるということはジャワ人であることだ」と。幼い子供、粗野な 人、愚か者、狂人、あからさまに不道徳な人々は、ンドゥルン・ジャワ(ndurung djawa)、「まだジャワ人ではない」人々である。高度に洗練された礼儀作法に従って行動でき、音楽、舞踊、演劇、織物デザインなどに関する繊細な美的 感覚を持ち、各自の内面に向かう意識の静寂の中に宿る神のささやきに敏感に反応できる「正常な」大人は、sampun djawa、「すでにジャワ人」、つまりすでに人間である。人間であるということは、ただ呼吸することだけではない。ヨガのようなテクニックによって呼吸 をコントロールし、吸気と呼気の中で、神がご自身の名を「アッラー」と発する文字通りの声を聞くことである。また、ただ話すだけではなく、適切な社会的状 況において、適切な口調で、適切な言葉やフレーズを、適切な回避的な間接性をもって発することである。ただ食べるだけではなく、特定の食べ物を特定の調理 法で好み、それを食べる際には厳格なテーブルマナーに従うことである。また、ただ感じるだけではなく、忍耐、無欲、諦観、尊敬といった、かなり独特なジャ ワ人(そして本質的には翻訳不可能な)感情をはっきりと感じることである。 つまり、ここでは人間であるということは、万人であることではない。それは特定の人間であることであり、もちろん人間には違いがある。「他の分野、他のキ リギリス」とジャワ人は言う。社会内でも違いは認識されている。米農民が人間として、ジャワ人として人間らしくなる方法は、公務員とは異なる。これは寛容 や倫理相対主義の問題ではない。なぜなら、人間としてのあり方すべてが等しく賞賛に値するわけではないからだ。例えば、現地の中国人のやり方は激しく非難 されている。重要なのは、異なるやり方があるということだ。ここで人類学者の視点に切り替えると、平原インディアンの華麗さ、ヒンドゥー教徒の執着心、フ ランス人の 合理主義、ベルベル人の無政府主義、アメリカ人の楽観主義(私がこのように定義されることを望まないような一連のタグを挙げてみよう)など、これらの体系 的なレビューと分析を行うことで、人間とは何か、あるいは人間とは何になり得るのかが明らかになるだろう。 つまり、誤解を招くようなタグや形而上学的な類型、空虚な類似性を乗り越えて、詳細に立ち入らなければならない。そうしなければ、人間性を直視することは できない。この分野において、一般的なもの、すなわち科学の啓示的な単純性への道は、特定のもの、状況的なもの、具体的なものへの関心を通っているが、そ れは私が触れたような理論的分析の種類、すなわち物理的な進化、神経系の機能、社会組織、心理的プロセス、文化のパターン化などの分析、そしてとりわけそ れらの相互作用という観点から組織化され、方向づけられた関心である。つまり、真の探求の道は、恐ろしいほどの複雑さを通り抜けるのだ。 「彼をしばらく放っておいてあげなさい」とロバート・ロウェルは書いている。それは人類学者に対してではなく、人間の本質を探究したもう一人の変わり者、ナサニエル・ホーソーンに対してである。 彼をしばらく放っておいてあげなさい。 そうすれば、彼が頭を垂れて 考え込んでいるのが見えるだろう。考え込んでいるのだ。 目を何かのかけら、 石、ありふれた植物に、 最もありふれたものに、 まるでそれが手がかりであるかのように。 揺れ動く目は、 こそこそと、失敗し、不満を募らせながら、 真実と取るに足らないものについて熟考する。 8 自分のチップや石、ありふれた植物に身をかがめながら、人類学者もまた、真実と取るに足らないものについて熟考し、その中に、あるいはそう考えながら、不安定で移り気な自身の姿を垣間見る。 |
| 1 A. O. Lovejoy, Essays in the History of Ideas (New York, 1960), p. 173. 2 Ibid., p. 80 . 3 Preface to Shakespeare, Johnson on Shakespeare (London, 1931), pp. 11-12. 4 From the Preface to IphigÈnie. 5 A. L. Kroeber. ed.. Athropology (sic!) Today (Chicago. 1953). p. 516. 6 C. Kluckhohn, Culture and Behavior (New York, 1962), p. 280. 7 M. J. Herskovits, Cultural Anthropology (New York, 1955), p. 364. 8 Reprinted with permission of Farrar, Straus & Giroux, Inc., and Faber & Faber, Ltd., from "Hawthorne," in For the Union Dead, p. 39. Copyright © 1964 by Robert Lowell. |
1 A. O. Lovejoy, Essays in the History of Ideas (New York, 1960), p. 173. 2 同書、p. 80. 3 Shakespeare, Johnson on Shakespeare (London, 1931), pp. 11-12. 4 IphigÈnieの序文より。 5 A. L. Kroeber. ed.. Athropology (sic!) Today (Chicago. 1953). p. 516. 6 C. Kluckhohn, Culture and Behavior (New York, 1962), p. 280. 7 M. J. Herskovits, Cultural Anthropology (New York, 1955), p. 364. 8 Farrar, Straus & Giroux, Inc.およびFaber & Faber, Ltd.の許可を得て、「For the Union Dead」の「Hawthorne」より転載。39ページ。著作権 © 1964 Robert Lowell。 |
| The
impact of the concept of culture on the concept of man, in: Bulletin of
the Atomic Scientists (Chicago/Il./USA: The Atomic Scientists of
Chicago), vol. 22 no. 4 (1966), pp. 2-8. cf. in: The interpretation of cultures: selected essays, New-York/N.Y./USA etc. 1973: Basic Books, pp. 33-54. |
|
| http://hypergeertz.jku.at/GeertzTexts/Impact_Culture.htm |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099