
ジョセフ・コンラッド
Joseph Conrad, 1857-1924

☆ ジョゼフ・コンラッド(Józef Teodor Konrad Korzeniowski、 ポーランド生まれ: [ˈjuzɛ tɔdɔr kɔɛˈɔkɔnrat kɔɛˈɲɔfskʲi]; 1857年12月3日 - 1924年8月3日)はポーランド系イギリス人の小説家、物語作家である。彼は英語における最も偉大な作家の一人と見なされており、20代まで英語を流暢 に話せなかったが、非英語的な感覚を英文学に持ち込んだ散文の名手となった。彼は小説や物語を書いたが、その多くは航海を舞台にしたもので、無関心で不可 解で非道徳的な世界と見なした中での人間の個性の危機を描いている。 コンラッドは、ある人からは文学的印象派、他の人からは初期モダニストとみなされているが、彼の作品には19世紀のリアリズムの要素も含まれている。多く の劇映画が彼の作品から脚色され、影響を受けている。多くの作家や批評家が、20世紀の最初の20年間に書かれた彼のフィクション作品は、後の世界の出来 事を先取りしていたようだとコメントしている。 大英帝国の絶頂期に近い時期に執筆したコンラッドは、祖国ポーランドの国民的経験、ほぼ全生涯を通じて3つの占領帝国の間で小分けにされていた、フランス とイギリスの商船隊での自身の経験をもとに、帝国主義や植民地主義を含むヨーロッパ支配の世界の側面を反映し、人間の心理を深く探求する短編や小説を創作 した。
| Joseph Conrad (born
Józef Teodor Konrad Korzeniowski, Polish: [ˈjuzɛf tɛˈɔdɔr ˈkɔnrat
kɔʐɛˈɲɔfskʲi] ⓘ; 3 December 1857 – 3 August 1924) was a Polish-British
novelist and story writer.[2][note 1] He is regarded as one of the
greatest writers in the English language and although he did not speak
English fluently until his twenties, he became a master prose stylist
who brought a non-English sensibility into English literature.[note 2]
He wrote novels and stories, many in nautical settings that depict
crises of human individuality in the midst of what he saw as an
indifferent, inscrutable and amoral world.[note 3] Conrad is considered a literary impressionist by some and an early modernist by others,[note 4] though his works also contain elements of 19th-century realism.[9] His narrative style and anti-heroic characters, as in Lord Jim, for example,[10] have influenced numerous authors. Many dramatic films have been adapted from and inspired by his works. Numerous writers and critics have commented that his fictional works, written largely in the first two decades of the 20th century, seem to have anticipated later world events.[note 5] Writing near the peak of the British Empire, Conrad drew on the national experiences of his native Poland—during nearly all his life, parceled out among three occupying empires[16][note 6]—and on his own experiences in the French and British merchant navies, to create short stories and novels that reflect aspects of a European-dominated world—including imperialism and colonialism—and that profoundly explore the human psyche.[18] |
ジョゼフ・コンラッド(Józef Teodor Konrad
Korzeniowski、ポーランド生まれ: [ˈjuzɛ tɔdɔr kɔɛˈɔkɔnrat kɔɛˈɲɔfskʲi] ⓘ;
1857年12月3日 - 1924年8月3日)はポーランド系イギリス人の小説家、物語作家である。 [2][注釈
1]彼は英語における最も偉大な作家の一人と見なされており、20代まで英語を流暢に話せなかったが、非英語的な感覚を英文学に持ち込んだ散文の名手と
なった。 [注2]
彼は小説や物語を書いたが、その多くは航海を舞台にしたもので、無関心で不可解で非道徳的な世界と見なした中での人間の個性の危機を描いている[注3]。 コンラッドは、ある人からは文学的印象派、他の人からは初期モダニストとみなされているが[注釈 4]、彼の作品には19世紀のリアリズムの要素も含まれている。多くの劇映画が彼の作品から脚色され、影響を受けている。多くの作家や批評家が、20世紀 の最初の20年間に書かれた彼のフィクション作品は、後の世界の出来事を先取りしていたようだとコメントしている[注釈 5]。 大英帝国の絶頂期に近い時期に執筆したコンラッドは、祖国ポーランドの国民的経験-ほぼ全生涯を通じて3つの占領帝国の間で小分けにされていた[16] [注釈 6]-と、フランスとイギリスの商船隊での自身の経験をもとに、帝国主義や植民地主義を含むヨーロッパ支配の世界の側面を反映し、人間の心理を深く探求す る短編や小説を創作した[18]。 |
| Life Early years 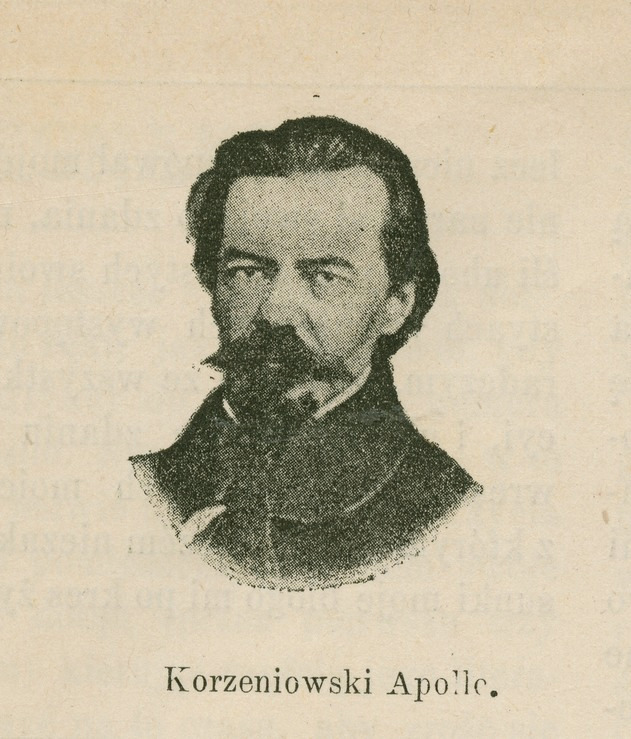 Conrad's writer father, Apollo Korzeniowski Conrad was born on 3 December 1857 in Berdychiv (Polish: Berdyczów), Ukraine, then part of the Russian Empire; the region had once been part of the Crown of the Kingdom of Poland.[19] He was the only child of Apollo Korzeniowski—a writer, translator, political activist, and would-be revolutionary—and his wife Ewa Bobrowska. He was christened Józef Teodor Konrad Korzeniowski after his maternal grandfather Józef, his paternal grandfather Teodor, and the heroes (both named "Konrad") of two poems by Adam Mickiewicz, Dziady and Konrad Wallenrod. His family called him "Konrad", rather than "Józef".[note 7] Though the vast majority of the surrounding area's inhabitants were Ukrainians, and the great majority of Berdychiv's residents were Jewish, almost all the countryside was owned by the Polish szlachta (nobility), to which Conrad's family belonged as bearers of the Nałęcz coat-of-arms.[22] Polish literature, particularly patriotic literature, was held in high esteem by the area's Polish population.[23] Poland had been divided among Prussia, Austria and Russia in 1795. The Korzeniowski family had played a significant role in Polish attempts to regain independence. Conrad's paternal grandfather Teodor had served under Prince Józef Poniatowski during Napoleon's Russian campaign and had formed his own cavalry squadron during the November 1830 Uprising of Poland-Lithuania against the Russian Empire.[24] Conrad's fiercely patriotic father Apollo belonged to the "Red" political faction, whose goal was to re-establish the pre-partition boundaries of Poland and that also advocated land reform and the abolition of serfdom. Conrad's subsequent refusal to follow in Apollo's footsteps, and his choice of exile over resistance, were a source of lifelong guilt for Conrad.[25][note 8]  Nowy Świat 47, Warsaw, where three-year-old Conrad lived with his parents in 1861. Because of the father's attempts at farming and his political activism, the family moved repeatedly. In May 1861 they moved to Warsaw, where Apollo joined the resistance against the Russian Empire. He was arrested and imprisoned in Pavilion X[note 9] – the dread Tenth Pavilion – of the Warsaw Citadel.[27] Conrad would write: "[I]n the courtyard of this Citadel—characteristically for our nation—my childhood memories begin."[28] On 9 May 1862 Apollo and his family were exiled to Vologda, 500 kilometres (310 mi) north of Moscow and known for its bad climate.[29] In January 1863 Apollo's sentence was commuted, and the family was sent to Chernihiv in northeast Ukraine, where conditions were much better. However, on 18 April 1865 Ewa died of tuberculosis.[30] Apollo did his best to teach Conrad at home. The boy's early reading introduced him to the two elements that later dominated his life: in Victor Hugo's Toilers of the Sea, he encountered the sphere of activity to which he would devote his youth; Shakespeare brought him into the orbit of English literature. Most of all, though, he read Polish Romantic poetry. Half a century later he explained that "The Polishness in my works comes from Mickiewicz and Słowacki. My father read [Mickiewicz's] Pan Tadeusz aloud to me and made me read it aloud.... I used to prefer [Mickiewicz's] Konrad Wallenrod [and] Grażyna. Later I preferred Słowacki. You know why Słowacki?... [He is the soul of all Poland]".[31] In the autumn of 1866, young Conrad was sent for a year-long retreat for health reasons, to Kyiv and his mother's family estate at Novofastiv [de].[32] In December 1867, Apollo took his son to the Austrian-held part of Poland, which for two years had been enjoying considerable internal freedom and a degree of self-government. After sojourns in Lwów and several smaller localities, on 20 February 1869 they moved to Kraków (until 1596 the capital of Poland), likewise in Austrian Poland. A few months later, on 23 May 1869, Apollo Korzeniowski died, leaving Conrad orphaned at the age of eleven.[33] Like Conrad's mother, Apollo had been gravely ill with tuberculosis.[34]  Tadeusz Bobrowski, Conrad's maternal uncle, mentor, and benefactor The young Conrad was placed in the care of Ewa's brother, Tadeusz Bobrowski. Conrad's poor health and his unsatisfactory schoolwork caused his uncle constant problems and no end of financial outlay. Conrad was not a good student; despite tutoring, he excelled only in geography.[35] At that time he likely received only private tutoring, as there is no evidence he attended any school regularly.[32] Since the boy's ill health was clearly of nervous origin, the physicians supposed that fresh air and physical work would harden him; his uncle hoped that well-defined duties and the rigors of work would teach him discipline. Since he showed little inclination to study, it was essential that he learn a trade; his uncle thought he could work as a sailor-cum-businessman, who would combine maritime skills with commercial activities.[36] In the autumn of 1871, thirteen-year-old Conrad announced his intention to become a sailor. He later recalled that as a child he had read (apparently in French translation) Leopold McClintock's book about his 1857–59 expeditions in the Fox, in search of Sir John Franklin's lost ships Erebus and Terror.[note 10] Conrad also recalled having read books by the American James Fenimore Cooper and the English Captain Frederick Marryat.[37] A playmate of his adolescence recalled that Conrad spun fantastic yarns, always set at sea, presented so realistically that listeners thought the action was happening before their eyes. In August 1873 Bobrowski sent fifteen-year-old Conrad to Lwów to a cousin who ran a small boarding house for boys orphaned by the 1863 Uprising; group conversation there was in French. The owner's daughter recalled: He stayed with us ten months... Intellectually he was extremely advanced but [he] disliked school routine, which he found tiring and dull; he used to say... he... planned to become a great writer.... He disliked all restrictions. At home, at school, or in the living room he would sprawl unceremoniously. He... suffer[ed] from severe headaches and nervous attacks...[38] Conrad had been at the establishment for just over a year when in September 1874, for uncertain reasons, his uncle removed him from school in Lwów and took him back to Kraków.[39] On 13 October 1874 Bobrowski sent the sixteen-year-old to Marseilles, France, for Conrad's planned merchant-marine career on French merchant ships,[36] providing him with a monthly stipend of 150 francs.[32] Though Conrad had not completed secondary school, his accomplishments included fluency in French (with a correct accent), some knowledge of Latin, German and Greek; probably a good knowledge of history, some geography, and probably already an interest in physics. He was well read, particularly in Polish Romantic literature. He belonged to the second generation in his family that had had to earn a living outside the family estates. They were born and reared partly in the milieu of the working intelligentsia, a social class that was starting to play an important role in Central and Eastern Europe.[40] He had absorbed enough of the history, culture and literature of his native land to be able eventually to develop a distinctive world view and make unique contributions to the literature of his adoptive Britain.[41] Tensions that originated in his childhood in Poland and increasing in his adulthood abroad contributed to Conrad's greatest literary achievements.[42] Zdzisław Najder, himself an emigrant from Poland, observed: Living away from one's natural environment—family, friends, social group, language—even if it results from a conscious decision, usually gives rise to... internal tensions, because it tends to make people less sure of themselves, more vulnerable, less certain of their... position and... value... The Polish szlachta and... intelligentsia were social strata in which reputation... was felt... very important... for a feeling of self-worth. Men strove... to find confirmation of their... self-regard... in the eyes of others... Such a psychological heritage forms both a spur to ambition and a source of constant stress, especially if [one has been inculcated with] the idea of [one]'s public duty...[43] Some critics have suggested that when Conrad left Poland, he wanted to break once and for all with his Polish past.[44] In refutation of this, Najder quotes from Conrad's 14 August 1883 letter to family friend Stefan Buszczyński, written nine years after Conrad had left Poland: ... I always remember what you said when I was leaving [Kraków]: "Remember"—you said—"wherever you may sail, you are sailing towards Poland!" That I have never forgotten, and never will forget![45] Merchant marine Main article: Joseph Conrad's career at sea In Marseilles Conrad had an intense social life, often stretching his budget.[32] A trace of these years can be found in the northern Corsica town of Luri, where there is a plaque to a Corsican merchant seaman, Dominique Cervoni, whom Conrad befriended. Cervoni became the inspiration for some of Conrad's characters, such as the title character of the 1904 novel Nostromo. Conrad visited Corsica with his wife in 1921, partly in search of connections with his long-dead friend and fellow merchant seaman.[46][unreliable source?] 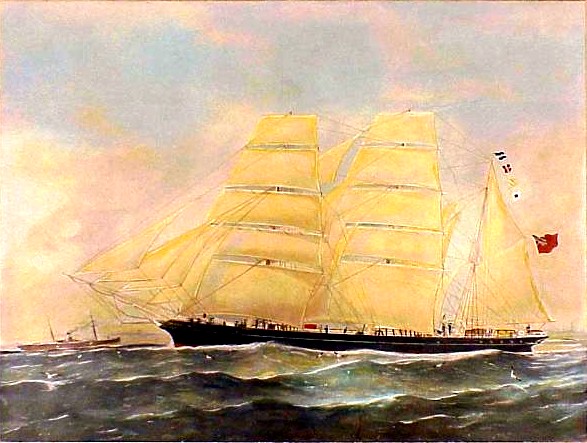 Otago, the barque captained by Conrad in 1888 and first three months of 1889 In late 1877, Conrad's maritime career was interrupted by the refusal of the Russian consul to provide documents needed for him to continue his service. As a result, Conrad fell into debt and, in March 1878, he attempted suicide. He survived, and received further financial aid from his uncle, allowing him to resume his normal life.[32] After nearly four years in France and on French ships, Conrad joined the British merchant marine, enlisting in April 1878 (he had most likely started learning English shortly before).[32] For the next fifteen years, he served under the Red Ensign. He worked on a variety of ships as crew member (steward, apprentice, able seaman) and then as third, second and first mate, until eventually achieving captain's rank. During the 19 years from the time that Conrad had left Kraków, in October 1874, until he signed off the Adowa, in January 1894, he had worked in ships, including long periods in port, for 10 years and almost 8 months. He had spent just over 8 years at sea—9 months of it as a passenger.[47] His sole captaincy took place in 1888–89, when he commanded the barque Otago from Sydney to Mauritius.[48] During a brief call in India in 1885–86, 28-year-old Conrad sent five letters to Joseph Spiridion,[note 11] a Pole eight years his senior whom he had befriended at Cardiff in June 1885, just before sailing for Singapore in the clipper ship Tilkhurst. These letters are Conrad's first preserved texts in English. His English is generally correct but stiff to the point of artificiality; many fragments suggest that his thoughts ran along the lines of Polish syntax and phraseology. More importantly, the letters show a marked change in views from those implied in his earlier correspondence of 1881–83. He had abandoned "hope for the future" and the conceit of "sailing [ever] toward Poland", and his Panslavic ideas. He was left with a painful sense of the hopelessness of the Polish question and an acceptance of England as a possible refuge. While he often adjusted his statements to accord to some extent with the views of his addressees, the theme of hopelessness concerning the prospects for Polish independence often occurs authentically in his correspondence and works before 1914.[50] 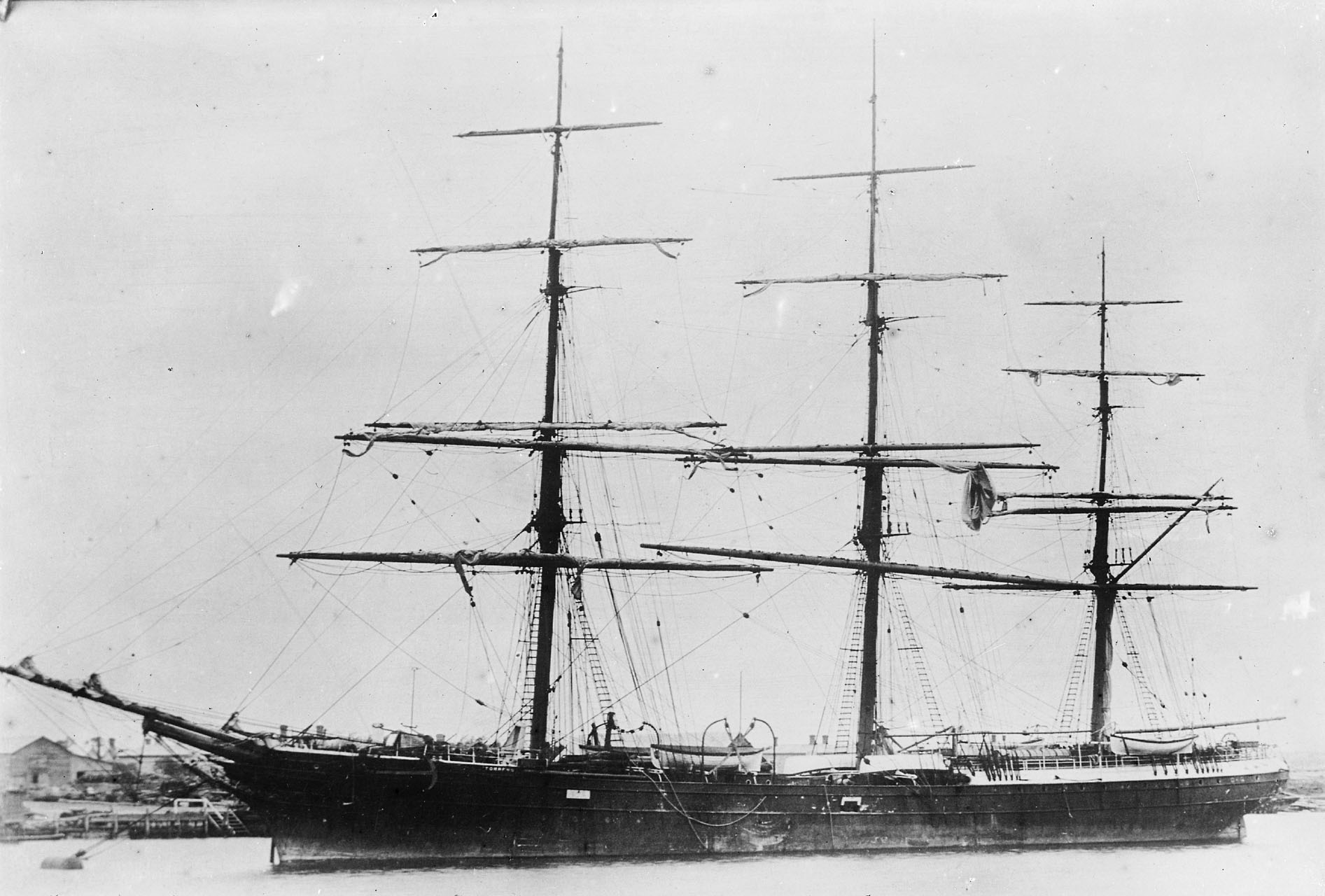 Conrad lived at 17 Gillingham Street, Pimlico, central London after returning from the Congo The year 1890 marked Conrad's first return to Poland, where he would visit his uncle and other relatives and acquaintances.[48][51] This visit took place while he was waiting to proceed to the Congo Free State, having been hired by Albert Thys, deputy director of the Société Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo.[52] Conrad's association with the Belgian company, on the Congo River, would inspire his novella, Heart of Darkness.[48] During this 1890 period in the Congo, Conrad befriended Roger Casement, who was also working for Thys, operating a trading and transport station in Matadi. In 1903, as British Consul to Boma, Casement was commissioned to investigate abuses in the Congo, and later in Amazonian Peru, and was knighted in 1911 for his advocacy of human rights. Casement later became active in Irish Republicanism after leaving the British consular service.[53][note 12] Torrens: Conrad made two round trips as first mate, London to Adelaide, between November 1891 and July 1893. Conrad left Africa at the end of December 1890, arriving in Brussels by late January of the following year. He rejoined the British merchant marines, as first mate, in November.[56] When he left London on 25 October 1892 aboard the passenger clipper ship Torrens, one of the passengers was William Henry Jacques, a consumptive Cambridge University graduate who died less than a year later on 19 September 1893. According to Conrad's A Personal Record, Jacques was the first reader of the still-unfinished manuscript of Conrad's Almayer's Folly. Jacques encouraged Conrad to continue writing the novel.[57]  John Galsworthy, whom Conrad met on Torrens Conrad completed his last long-distance voyage as a seaman on 26 July 1893 when the Torrens docked at London and "J. Conrad Korzemowin"—per the certificate of discharge—debarked. When the Torrens had left Adelaide on 13 March 1893, the passengers had included two young Englishmen returning from Australia and New Zealand: 25-year-old lawyer and future novelist John Galsworthy; and Edward Lancelot Sanderson, who was going to help his father run a boys' preparatory school at Elstree. They were probably the first Englishmen and non-sailors with whom Conrad struck up a friendship and he would remain in touch with both. In one of Galsworthy's first literary attempts, The Doldrums (1895–96), the protagonist—first mate Armand—is modelled after Conrad. At Cape Town, where the Torrens remained from 17 to 19 May, Galsworthy left the ship to look at the local mines. Sanderson continued his voyage and seems to have been the first to develop closer ties with Conrad.[58] Later that year, Conrad would visit his relatives in Poland and Ukraine once again.[48][59] Writer  Conrad in 1916 (photo by Alvin Langdon Coburn) In the autumn of 1889, Conrad began writing his first novel, Almayer's Folly.[60] [T]he son of a writer, praised by his [maternal] uncle [Tadeusz Bobrowski] for the beautiful style of his letters, the man who from the very first page showed a serious, professional approach to his work, presented his start on Almayer's Folly as a casual and non-binding incident... [Y]et he must have felt a pronounced need to write. Every page right from th[e] first one testifies that writing was not something he took up for amusement or to pass time. Just the contrary: it was a serious undertaking, supported by careful, diligent reading of the masters and aimed at shaping his own attitude to art and to reality.... [W]e do not know the sources of his artistic impulses and creative gifts.[61] Conrad's later letters to literary friends show the attention that he devoted to analysis of style, to individual words and expressions, to the emotional tone of phrases, to the atmosphere created by language. In this, Conrad in his own way followed the example of Gustave Flaubert, notorious for searching days on end for le mot juste—for the right word to render the "essence of the matter." Najder opined: "[W]riting in a foreign language admits a greater temerity in tackling personally sensitive problems, for it leaves uncommitted the most spontaneous, deeper reaches of the psyche, and allows a greater distance in treating matters we would hardly dare approach in the language of our childhood. As a rule it is easier both to swear and to analyze dispassionately in an acquired language."[62] In 1894, aged 36, Conrad reluctantly gave up the sea, partly because of poor health, partly due to unavailability of ships, and partly because he had become so fascinated with writing that he had decided on a literary career. Almayer's Folly, set on the east coast of Borneo, was published in 1895. Its appearance marked his first use of the pen name "Joseph Conrad"; "Konrad" was, of course, the third of his Polish given names, but his use of it—in the anglicised version, "Conrad"—may also have been an homage to the Polish Romantic poet Adam Mickiewicz's patriotic narrative poem, Konrad Wallenrod.[63] Edward Garnett, a young publisher's reader and literary critic who would play one of the chief supporting roles in Conrad's literary career, had—like Unwin's first reader of Almayer's Folly, Wilfrid Hugh Chesson—been impressed by the manuscript, but Garnett had been "uncertain whether the English was good enough for publication." Garnett had shown the novel to his wife, Constance Garnett, later a translator of Russian literature. She had thought Conrad's foreignness a positive merit.[64] While Conrad had only limited personal acquaintance with the peoples of Maritime Southeast Asia, the region looms large in his early work. According to Najder, Conrad, the exile and wanderer, was aware of a difficulty that he confessed more than once: the lack of a common cultural background with his Anglophone readers meant he could not compete with English-language authors writing about the English-speaking world. At the same time, the choice of a non-English colonial setting freed him from an embarrassing division of loyalty: Almayer's Folly, and later "An Outpost of Progress" (1897, set in a Congo exploited by King Leopold II of Belgium) and Heart of Darkness (1899, likewise set in the Congo), contain bitter reflections on colonialism. The Malay states came theoretically under the suzerainty of the Dutch government; Conrad did not write about the area's British dependencies, which he never visited. He "was apparently intrigued by... struggles aimed at preserving national independence. The prolific and destructive richness of tropical nature and the dreariness of human life within it accorded well with the pessimistic mood of his early works."[65][note 13] Almayer's Folly, together with its successor, An Outcast of the Islands (1896), laid the foundation for Conrad's reputation as a romantic teller of exotic tales—a misunderstanding of his purpose that was to frustrate him for the rest of his career.[note 14] Almost all of Conrad's writings were first published in newspapers and magazines: influential reviews like The Fortnightly Review and the North American Review; avant-garde publications like the Savoy, New Review, and The English Review; popular short-fiction magazines like The Saturday Evening Post and Harper's Magazine; women's journals like the Pictorial Review and Romance; mass-circulation dailies like the Daily Mail and the New York Herald; and illustrated newspapers like The Illustrated London News and the Illustrated Buffalo Express.[68] He also wrote for The Outlook, an imperialist weekly magazine, between 1898 and 1906.[69][note 15] Financial success long eluded Conrad, who often requested advances from magazine and book publishers, and loans from acquaintances such as John Galsworthy.[70][note 16] Eventually a government grant ("civil list pension") of £100 per annum, awarded on 9 August 1910, somewhat relieved his financial worries,[72][note 17] and in time collectors began purchasing his manuscripts. Though his talent was early on recognised by English intellectuals, popular success eluded him until the 1913 publication of Chance, which is often considered one of his weaker novels.[48] Personal life  Time, 7 April 1923 Temperament and health Conrad was a reserved man, wary of showing emotion. He scorned sentimentality; his manner of portraying emotion in his books was full of restraint, scepticism and irony.[74] In the words of his uncle Bobrowski, as a young man Conrad was "extremely sensitive, conceited, reserved, and in addition excitable. In short [...] all the defects of the Nałęcz family."[75] Conrad suffered throughout life from ill health, physical and mental. A newspaper review of a Conrad biography suggested that the book could have been subtitled Thirty Years of Debt, Gout, Depression and Angst.[76] In 1891 he was hospitalised for several months, suffering from gout, neuralgic pains in his right arm and recurrent attacks of malaria. He also complained of swollen hands "which made writing difficult". Taking his uncle Tadeusz Bobrowski's advice, he convalesced at a spa in Switzerland.[77] Conrad had a phobia of dentistry, neglecting his teeth until they had to be extracted. In one letter he remarked that every novel he had written had cost him a tooth.[78] Conrad's physical afflictions were, if anything, less vexatious than his mental ones. In his letters he often described symptoms of depression; "the evidence", writes Najder, "is so strong that it is nearly impossible to doubt it."[79] Attempted suicide In March 1878, at the end of his Marseilles period, 20-year-old Conrad attempted suicide, by shooting himself in the chest with a revolver.[80] According to his uncle, who was summoned by a friend, Conrad had fallen into debt. Bobrowski described his subsequent "study" of his nephew in an extensive letter to Stefan Buszczyński, his own ideological opponent and a friend of Conrad's late father Apollo.[note 18] To what extent the suicide attempt had been made in earnest likely will never be known, but it is suggestive of a situational depression.[81] Romance and marriage In 1888 during a stop-over on Mauritius, in the Indian Ocean, Conrad developed a couple of romantic interests. One of these would be described in his 1910 story "A Smile of Fortune", which contains autobiographical elements (e.g., one of the characters is the same Chief Mate Burns who appears in The Shadow Line). The narrator, a young captain, flirts ambiguously and surreptitiously with Alice Jacobus, daughter of a local merchant living in a house surrounded by a magnificent rose garden. Research has confirmed that in Port Louis at the time there was a 17-year-old Alice Shaw, whose father, a shipping agent, owned the only rose garden in town.[82] More is known about Conrad's other, more open flirtation. An old friend, Captain Gabriel Renouf of the French merchant marine, introduced him to the family of his brother-in-law. Renouf's eldest sister was the wife of Louis Edward Schmidt, a senior official in the colony; with them lived two other sisters and two brothers. Though the island had been taken over in 1810 by Britain, many of the inhabitants were descendants of the original French colonists, and Conrad's excellent French and perfect manners opened all local salons to him. He became a frequent guest at the Schmidts', where he often met the Misses Renouf. A couple of days before leaving Port Louis, Conrad asked one of the Renouf brothers for the hand of his 26-year-old sister Eugenie. She was already, however, engaged to marry her pharmacist cousin. After the rebuff, Conrad did not pay a farewell visit but sent a polite letter to Gabriel Renouf, saying he would never return to Mauritius and adding that on the day of the wedding his thoughts would be with them.  Westbere House, in Canterbury, Kent, was once owned by Conrad. It is listed Grade II on the National Heritage List for England.[83] On 24 March 1896 Conrad married an Englishwoman, Jessie George.[48] The couple had two sons, Borys and John. The elder, Borys, proved a disappointment in scholarship and integrity.[84] Jessie was an unsophisticated, working-class girl, sixteen years younger than Conrad.[85] To his friends, she was an inexplicable choice of wife, and the subject of some rather disparaging and unkind remarks.[86] (See Lady Ottoline Morrell's opinion of Jessie in Impressions.) However, according to other biographers such as Frederick Karl, Jessie provided what Conrad needed, namely a "straightforward, devoted, quite competent" companion.[68] Similarly, Jones remarks that, despite whatever difficulties the marriage endured, "there can be no doubt that the relationship sustained Conrad's career as a writer", which might have been much less successful without her.[87] The couple rented a long series of successive homes, mostly in the English countryside. Conrad, who suffered frequent depressions, made great efforts to change his mood; the most important step was to move into another house. His frequent changes of home were usually signs of a search for psychological regeneration.[88] Between 1910 and 1919 Conrad's home was Capel House in Orlestone, Kent, which was rented to him by Lord and Lady Oliver. It was here that he wrote The Rescue, Victory, and The Arrow of Gold.[89] Except for several vacations in France and Italy, a 1914 vacation in his native Poland, and a 1923 visit to the United States, Conrad lived the rest of his life in England. Sojourn in Poland  In 1914 Conrad and family stayed at the Zakopane Willa Konstantynówka, operated by his cousin Aniela Zagórska, mother of his future Polish translator of the same name.[90]  Conrad's nieces Aniela Zagórska (left), Karola Zagórska; Conrad The 1914 vacation with his wife and sons in Poland, at the urging of Józef Retinger, coincided with the outbreak of World War I. On 28 July 1914, the day war broke out between Austro-Hungary and Serbia, Conrad and the Retingers arrived in Kraków (then in the Austro-Hungarian Empire), where Conrad visited childhood haunts. As the city lay only a few miles from the Russian border, there was a risk of being stranded in a battle zone. With wife Jessie and younger son John ill, Conrad decided to take refuge in the mountain resort town of Zakopane. They left Kraków on 2 August. A few days after arrival in Zakopane, they moved to the Konstantynówka pension operated by Conrad's cousin Aniela Zagórska; it had been frequented by celebrities including the statesman Józef Piłsudski and Conrad's acquaintance, the young concert pianist Artur Rubinstein.[91] Zagórska introduced Conrad to Polish writers, intellectuals, and artists who had also taken refuge in Zakopane, including novelist Stefan Żeromski and Tadeusz Nalepiński, a writer friend of anthropologist Bronisław Malinowski. Conrad aroused interest among the Poles as a famous writer and an exotic compatriot from abroad. He charmed new acquaintances, especially women. However, Marie Curie's physician sister, Bronisława Dłuska, wife of fellow physician and eminent socialist activist Kazimierz Dłuski, openly berated Conrad for having used his great talent for purposes other than bettering the future of his native land.[92][note 19] [note 20] But thirty-two-year-old Aniela Zagórska (daughter of the pension keeper), Conrad's niece who would translate his works into Polish in 1923–39, idolised him, kept him company, and provided him with books. He particularly delighted in the stories and novels of the ten-years-older, recently deceased Bolesław Prus[95][96] (who also had visited Zakopane[97]), read everything by his fellow victim of Poland's 1863 Uprising—"my beloved Prus"—that he could get his hands on, and pronounced him "better than Dickens"—a favourite English novelist of Conrad's.[98][note 21] Conrad, who was noted by his Polish acquaintances to still be fluent in his native tongue, participated in their impassioned political discussions. He declared presciently, as Józef Piłsudski had earlier in 1914 in Paris, that in the war, for Poland to regain independence, Russia must be beaten by the Central Powers (the Austro-Hungarian and German Empires), and the Central Powers must in turn be beaten by France and Britain.[100][note 22] After many travails and vicissitudes, at the beginning of November 1914 Conrad managed to bring his family back to England. On his return, he was determined to work on swaying British opinion in favour of restoring Poland's sovereignty.[102] Jessie Conrad would later write in her memoirs: "I understood my husband so much better after those months in Poland. So many characteristics that had been strange and unfathomable to me before, took, as it were, their right proportions. I understood that his temperament was that of his countrymen."[103] Politics Biographer Zdzisław Najder wrote: Conrad was passionately concerned with politics. [This] is confirmed by several of his works, starting with Almayer's Folly. [...] Nostromo revealed his concern with these matters more fully; it was, of course, a concern quite natural for someone from a country [Poland] where politics was a matter not only of everyday existence but also of life and death. Moreover, Conrad himself came from a social class that claimed exclusive responsibility for state affairs, and from a very politically active family. Norman Douglas sums it up: "Conrad was first and foremost a Pole and like many Poles a politician and moralist malgré lui [French: "in spite of himself"]. These are his fundamentals." [What made] Conrad see political problems in terms of a continuous struggle between law and violence, anarchy and order, freedom and autocracy, material interests and the noble idealism of individuals [...] was Conrad's historical awareness. His Polish experience endowed him with the perception, exceptional in the Western European literature of his time, of how winding and constantly changing were the front lines in these struggles.[104] The most extensive and ambitious political statement that Conrad ever made was his 1905 essay, "Autocracy and War", whose starting point was the Russo-Japanese War (he finished the article a month before the Battle of Tsushima Strait). The essay begins with a statement about Russia's incurable weakness and ends with warnings against Prussia, the dangerous aggressor in a future European war. For Russia he predicted a violent outburst in the near future, but Russia's lack of democratic traditions and the backwardness of her masses made it impossible for the revolution to have a salutary effect. Conrad regarded the formation of a representative government in Russia as unfeasible and foresaw a transition from autocracy to dictatorship. He saw western Europe as torn by antagonisms engendered by economic rivalry and commercial selfishness. In vain might a Russian revolution seek advice or help from a materialistic and egoistic western Europe that armed itself in preparation for wars far more brutal than those of the past.[105]  Conrad's bust by Jacob Epstein, 1924. Conrad called it "a wonderful piece of work of a somewhat monumental dignity, and yet—everybody agrees—the likeness is striking"[106] Conrad's distrust of democracy sprang from his doubts whether the propagation of democracy as an aim in itself could solve any problems. He thought that, in view of the weakness of human nature and of the "criminal" character of society, democracy offered boundless opportunities for demagogues and charlatans.[107] Conrad kept his distance from partisan politics, and never voted in British national elections.[108] He accused social democrats of his time of acting to weaken "the national sentiment, the preservation of which [was his] concern"—of attempting to dissolve national identities in an impersonal melting-pot. "I look at the future from the depth of a very black past and I find that nothing is left for me except fidelity to a cause lost, to an idea without future." It was Conrad's hopeless fidelity to the memory of Poland that prevented him from believing in the idea of "international fraternity", which he considered, under the circumstances, just a verbal exercise. He resented some socialists' talk of freedom and world brotherhood while keeping silent about his own partitioned and oppressed Poland.[107] Before that, in the early 1880s, letters to Conrad from his uncle Tadeusz[note 23] show Conrad apparently having hoped for an improvement in Poland's situation not through a liberation movement but by establishing an alliance with neighbouring Slavic nations. This had been accompanied by a faith in the Panslavic ideology—"surprising", Najder writes, "in a man who was later to emphasize his hostility towards Russia, a conviction that... Poland's [superior] civilization and... historic... traditions would [let] her play a leading role... in the Panslavic community, [and his] doubts about Poland's chances of becoming a fully sovereign nation-state."[109] Conrad's alienation from partisan politics went together with an abiding sense of the thinking man's burden imposed by his personality, as described in an 1894 letter by Conrad to a relative-by-marriage and fellow author, Marguerite Poradowska (née Gachet, and cousin of Vincent van Gogh's physician, Paul Gachet) of Brussels: We must drag the chain and ball of our personality to the end. This is the price one pays for the infernal and divine privilege of thought; so in this life it is only the chosen who are convicts—a glorious band which understands and groans but which treads the earth amidst a multitude of phantoms with maniacal gestures and idiotic grimaces. Which would you rather be: idiot or convict?[110] Conrad wrote H. G. Wells that the latter's 1901 book, Anticipations, an ambitious attempt to predict major social trends, "seems to presuppose... a sort of select circle to which you address yourself, leaving the rest of the world outside the pale. [In addition,] you do not take sufficient account of human imbecility which is cunning and perfidious."[111][note 24] In a 23 October 1922 letter to mathematician-philosopher Bertrand Russell, in response to the latter's book, The Problem of China, which advocated socialist reforms and an oligarchy of sages who would reshape Chinese society, Conrad explained his own distrust of political panaceas: I have never [found] in any man's book or... talk anything... to stand up... against my deep-seated sense of fatality governing this man-inhabited world.... The only remedy for Chinamen and for the rest of us is [a] change of hearts, but looking at the history of the last 2000 years there is not much reason to expect [it], even if man has taken to flying—a great "uplift" no doubt but no great change....[112] Leo Robson writes: Conrad... adopted a broader ironic stance—a sort of blanket incredulity, defined by a character in Under Western Eyes as the negation of all faith, devotion, and action. Through control of tone and narrative detail... Conrad exposes what he considered to be the naïveté of movements like anarchism and socialism, and the self-serving logic of such historical but "naturalized" phenomena as capitalism (piracy with good PR), rationalism (an elaborate defense against our innate irrationality), and imperialism (a grandiose front for old-school rape and pillage). To be ironic is to be awake—and alert to the prevailing "somnolence." In Nostromo... the journalist Martin Decoud... ridicul[es] the idea that people "believe themselves to be influencing the fate of the universe." (H. G. Wells recalled Conrad's astonishment that "I could take social and political issues seriously.")[113] But, writes Robson, Conrad is no moral nihilist: If irony exists to suggest that there's more to things than meets the eye, Conrad further insists that, when we pay close enough attention, the "more" can be endless. He doesn't reject what [his character] Marlow [introduced in Youth] calls "the haggard utilitarian lies of our civilisation" in favor of nothing; he rejects them in favor of "something", "some saving truth", "some exorcism against the ghost of doubt"—an intimation of a deeper order, one not easily reduced to words. Authentic, self-aware emotion—feeling that doesn't call itself "theory" or "wisdom"—becomes a kind of standard-bearer, with "impressions" or "sensations" the nearest you get to solid proof.[114] In an August 1901 letter to the editor of The New York Times Saturday Book Review, Conrad wrote: "Egoism, which is the moving force of the world, and altruism, which is its morality, these two contradictory instincts, of which one is so plain and the other so mysterious, cannot serve us unless in the incomprehensible alliance of their irreconcilable antagonism."[115][note 25] Death  Conrad's grave at Canterbury Cemetery, near Harbledown, Kent On 3 August 1924, Conrad died at his house, Oswalds, in Bishopsbourne, Kent, England, probably of a heart attack. He was interred at Canterbury Cemetery, Canterbury, under a misspelled version of his original Polish name, as "Joseph Teador Conrad Korzeniowski".[117] Inscribed on his gravestone are the lines from Edmund Spenser's The Faerie Queene which he had chosen as the epigraph to his last complete novel, The Rover: Sleep after toyle, port after stormie seas, Ease after warre, death after life, doth greatly please[118] Conrad's modest funeral took place amid great crowds. His old friend Edward Garnett recalled bitterly: To those who attended Conrad's funeral in Canterbury during the Cricket Festival of 1924, and drove through the crowded streets festooned with flags, there was something symbolical in England's hospitality and in the crowd's ignorance of even the existence of this great writer. A few old friends, acquaintances and pressmen stood by his grave.[117] Another old friend of Conrad's, Cunninghame Graham, wrote Garnett: "Aubry was saying to me... that had Anatole France died, all Paris would have been at his funeral."[117] Conrad's wife Jessie died twelve years later, on 6 December 1936, and was interred with him. In 1996 his grave was designated a Grade II listed structure.[119] |
生涯 生い立ち 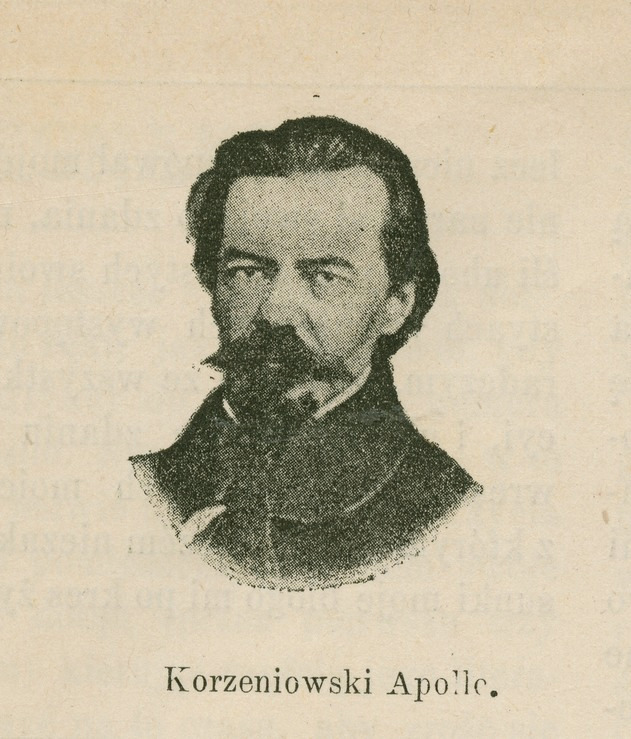 コンラッドの作家の父、アポロ・コルツェニウスキ コンラッドは1857年12月3日、当時ロシア帝国の一部であったウクライナのベルディチュフ(ポーランド語: Berdyczów)で生まれた[19]。作家、翻訳家、政治活動家、革命家志望であったアポロ・コルツェニヨフスキとその妻エワ・ボブロフスカの間の一 人っ子であった。洗礼名は、母方の祖父ヨゼフ、父方の祖父テオドール、そしてアダム・ミツキェヴィチの2つの詩の主人公(いずれも「コンラート」という名 前)にちなんで、ヨゼフ・テオドール・コンラート・コルツェニヨフスキと命名された。家族は彼を「ヨーゼフ」ではなく「コンラート」と呼んだ[注釈 7]。 周辺地域の住民の大多数はウクライナ人であり、ベルディチフの住民の大多数はユダヤ人であったが、ほぼすべての田園地帯はポーランドのシュラハタ(貴族) の所有地であり、コンラッドの一族はナウ・カノーラの紋章を持つ者としてこれに属していた[22]。ポーランド文学、特に愛国的な文学は、この地域のポー ランド人の間で高く評価されていた[23]。 ポーランドは1795年にプロイセン、オーストリア、ロシアに分割されていた。コルゼニウスキー家は、ポーランドの独立回復の試みにおいて重要な役割を果 たした。コンラッドの父方の祖父テオドルは、ナポレオンのロシア遠征時にヨゼフ・ポニャトフスキ公の部下として従軍し、1830年11月のロシア帝国に対 するポーランド・リトアニアの蜂起の際には自ら騎兵隊を編成した[24]。その後、コンラッドがアポロの足跡をたどることを拒否し、抵抗よりも亡命を選ん だことは、コンラッドにとって生涯の罪の意識となった[25][注 8]。  1861年、3歳のコンラッドが両親と暮らしたワルシャワのNowy Świat 47番地。 父親の農業への挑戦と政治活動のため、一家は引っ越しを繰り返した。1861年5月、一家はワルシャワに移り住み、アポロはロシア帝国に対する抵抗運動に 参加した。彼は逮捕され、ワルシャワ城塞のパヴィリオンX[注釈 9]、つまり恐るべき第10パヴィリオンに収監された[27]: 「1862年5月9日、アポロと家族はモスクワの北500キロに位置し、気候が悪いことで知られるヴォログダに流刑となった。しかし、1865年4月18 日、エワは結核で亡くなった[30]。 アポロは自宅でコンラッドを教えることに全力を尽くした。ヴィクトル・ユーゴーの『海の労働者たち』では、彼が青春時代を捧げることになる活動領域に出会 い、シェイクスピアは彼をイギリス文学の軌道に引き込んだ。シェイクスピアは彼を英文学の軌道に乗せたが、何よりも彼はポーランドのロマン派の詩を読ん だ。半世紀後、彼は次のように語っている。 「私の作品におけるポーランドらしさは、ミツキェヴィチとスウォヴァツキに由来する。父は[ミキェヴィチの]『パン・タデウシュ』を音読し、私に読ませ た......。ミツキェヴィチの)コンラート・ワレンロド(とグラジナ)を好んで読んでいた。その後、私はスウォヴァツキを好んだ。なぜスウォヴァツキ なのかわかるか?[彼は全ポーランドの魂なのだ」[31]。 1866年秋、若きコンラッドは健康上の理由から、キエフと母親の実家であるノヴォファスチフ[デ]に1年間の静養を命じられた[32]。 1867年12月、アポロは息子を連れて、2年前からかなりの自由と自治を享受していたポーランドのオーストリア領に赴いた。ルヴフやいくつかの小さな地 方での滞在を経て、1869年2月20日、同じくオーストリア領ポーランドのクラクフ(1596年までポーランドの首都)に移った。数カ月後の1869年 5月23日、アポロ・コルツェニヨフスキが亡くなり、コンラッドは11歳で孤児となった[33]。コンラッドの母同様、アポロも結核を患っていた [34]。  タデウシュ・ボブロフスキ、コンラッドの母方の叔父、指導者、恩人 幼いコンラッドは、エワの兄であるタデウシュ・ボブロフスキに預けられた。コンラッドは健康状態が悪く、学業も満足にできなかったため、叔父は常に問題を 抱え、金銭的な出費も絶えなかった。当時、コンラッドが定期的に学校に通っていた形跡がないことから、個人指導を受けていた可能性が高い[32]。コン ラッドの体調不良は明らかに神経性のものであったため、医師たちは新鮮な空気と肉体労働がコンラッドを丈夫にすると考え、叔父は明確な職務と仕事の厳しさ がコンラッドの規律を教えると期待した。叔父は、明確な職務と労働の厳しさが彼に規律を教えるだろうと期待した。彼は勉強する気がほとんどなかったため、 職業を学ぶことが不可欠だった。叔父は、彼が船乗り兼ビジネスマンとして働くことができると考え、海洋技術と商業活動を組み合わせた[36]。1871年 の秋、13歳のコンラッドは船乗りになる意思を表明した。コンラッドはまた、アメリカのジェイムズ・フェニモア・クーパーやイギリスのフレデリック・マリ ヤット船長の本も読んだと回想している[37]。青年時代の遊び仲間は、コンラッドがいつも海を舞台にしたファンタジックな物語を紡ぎ、聞き手が目の前で 起こっていると思うほどリアルに表現していたと回想している。 1873年8月、ボブロフスキは15歳のコンラッドを、1863年の蜂起で孤児となった少年たちのために小さな寄宿舎を経営していた従兄弟のもとへルヴフに送った。そこでの会話はフランス語であった: コンラッドは10ヶ月間私たちのところにいた...。知性的には非常に優れていたが、(彼は)学校の規則正しい生活が嫌いで、疲れるし退屈だと感じてい た。彼はあらゆる制約を嫌っていた。家でも、学校でも、居間でも、彼は無遠慮にのたうち回った。彼は...ひどい頭痛と神経発作に苦しんでいた... [38]。 1874年9月、コンラッドは1年余り施設にいたが、理由は定かではないが、叔父は彼をルヴフの学校から追い出し、クラクフに連れて帰った[39]。 1874年10月13日、ボブロフスキは16歳のコンラッドをフランスのマルセイユに送り、コンラッドが計画していたフランスの商船での海運業に従事させ [36]、150フランの月給を支給した[32]。コンラッドは中等学校を卒業していなかったが、フランス語に堪能であり(正しいアクセントがあった)、 ラテン語、ドイツ語、ギリシア語の知識もあった。彼は読書家で、特にポーランドのロマン派文学に造詣が深かった。彼は、一族の領地の外で生計を立てなけれ ばならなかった一族の二代目に属していた。祖国の歴史、文化、文学を十分に吸収した彼は、やがて独自の世界観を確立し、養子となったイギリスの文学に独自 の貢献をするようになる[41]。 ポーランドでの幼少期に端を発し、成人後に外国で増大した緊張が、コンラッドの最大の文学的業績に寄与した[42] : 家族、友人、社会集団、言語など、生まれ育った環境から離れて生活することは、たとえそれが意識的な決断によるものであったとしても、通常、...内的な 緊張を生む。ポーランドのスラハタや知識階級は、社会的な名声が...自己価値を感じるために...非常に重要であると...感じられる社会階層であっ た。男たちは、他人の目に映る自分の自尊心を確認しようと努力した。このような心理的遺産は、野心に拍車をかけると同時に、絶え間ないストレスの源とな る。 批評家の中には、コンラッドがポーランドを離れたとき、ポーランドの過去ときっぱりと決別したかったのだと指摘する者もいる[44]。これに対する反論と して、ナジェデルは、コンラッドがポーランドを離れた9年後に書かれた、コンラッドが家族の友人ステファン・ブシチンスキに宛てた1883年8月14日の 手紙から引用している: ... クラクフを去るときにあなたが言ったことをいつも覚えている: 「どこを航海しようとも、ポーランドに向かって航行するのだ。私はその言葉を忘れたことはないし、これからも忘れることはないだろう![45]」。 商船 主な記事 ジョセフ・コンラッドの海でのキャリア マルセイユでは、コンラッドは激しい社交生活を送り、しばしば予算を使い果たした[32]。この頃の面影はコルシカ島北部の町ルリに残っており、そこには コンラッドが親交を深めたコルシカ商船の船員ドミニク・セルヴォニの記念碑がある。セルヴォニは、1904年の小説『ノストロモ号』の主人公など、コン ラッドの登場人物のインスピレーションの源となった。1921年、コンラッドは妻とともにコルシカ島を訪れたが、その理由のひとつは、長い間死別していた 友人であり商船仲間であったセルヴォーニとのつながりを求めてのことであった[46][信頼できない情報源?] 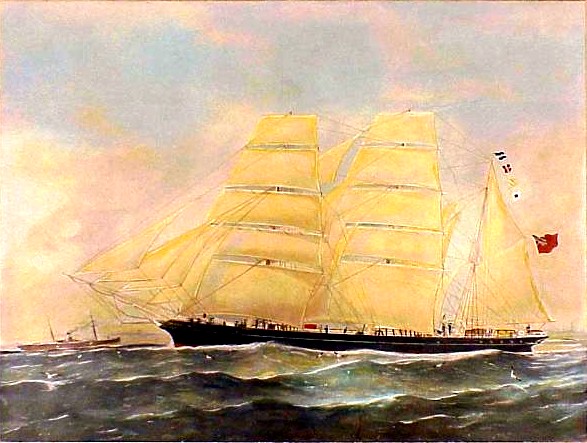 1888年と1889年の最初の3ヶ月間、コンラッドが船長を務めたオタゴ号 1877年後半、コンラッドの海運業は、ロシア領事がコンラッドの勤務継続に必要な書類の提出を拒否したために中断された。その結果、コンラッドは借金を 抱え、1878年3月に自殺を図った。一命を取り留めたコンラッドは、叔父からさらなる経済援助を受け、普通の生活を取り戻すことができた[32]。フラ ンスで4年近くフランス船に乗った後、コンラッドはイギリス商船に入隊し、1878年4月に入隊した(その少し前から英語を学び始めていた可能性が高い) [32]。 その後15年間、彼は赤の星章の下で勤務した。乗組員(スチュワード、見習い、乗組員)、三等航海士、二等航海士、一等航海士としてさまざまな船で働き、 最終的には船長の地位に就いた。コンラッドが1874年10月にクラクフを出航してから1894年1月にアドワ号で航海を終えるまでの19年間に、長期間 の入港を含めて10年と8ヶ月近く船で働いていた。彼の唯一の船長職は1888年から89年にシドニーからモーリシャスへ向かうオタゴ号で行われた [48]。 1885年から86年にかけてインドに短期間寄港した際、28歳のコンラッドは、クリッパー船ティルクハーストでシンガポールに向かう直前の1885年6 月にカーディフで親しくなった8歳年上のポーランド人ジョセフ・スピリディオン[注釈 11]に5通の手紙を送っている。これらの手紙はコンラッドにとって初めて残された英語の文章である。彼の英語は概して正しいが、人工的なまでに堅い。多 くの断片は、彼の思考がポーランドの構文や言い回しに沿っていたことを示唆している。 さらに重要なことに、この手紙には、1881年から83年にかけての書簡に暗示されていたものとは明らかに異なる見解が示されている。彼は「未来への希 望」や「ポーランドに向かって航海する」という考え、そしてパンスラヴィア的な考えを捨てたのである。ポーランド問題の絶望を痛感し、避難先としてイギリ スを受け入れたのである。彼はしばしば宛先の意見とある程度一致するように発言を調整したが、ポーランドの独立の見通しに関する絶望感というテーマは、 1914年以前の彼の書簡や作品にしばしば忠実に現れている[50]。 コンラッドはコンゴから帰国後、ロンドン中心部ピムリコのジリンガム・ストリート17番地に住んでいた。 1890年、コンラッドは初めてポーランドに戻り、叔父をはじめとする親戚や知人を訪ねた[48][51]。この訪問は、コンラッドがコンゴ自由国に向か うのを待っている間に行われた。 [この1890年のコンゴ滞在中に、コンラッドはロジャー・ケースメントと親しくなる。彼は同じくティスの下で働き、マタディで貿易と輸送のステーション を運営していた。1903年、ボマの英国領事として、ケースメントはコンゴでの虐待、後にペルーのアマゾンでの虐待の調査を依頼され、人権擁護のため 1911年にナイトの称号を授与された。ケースメントは後に英国領事職を辞した後、アイルランド共和主義で活動するようになる[53][注釈 12]。 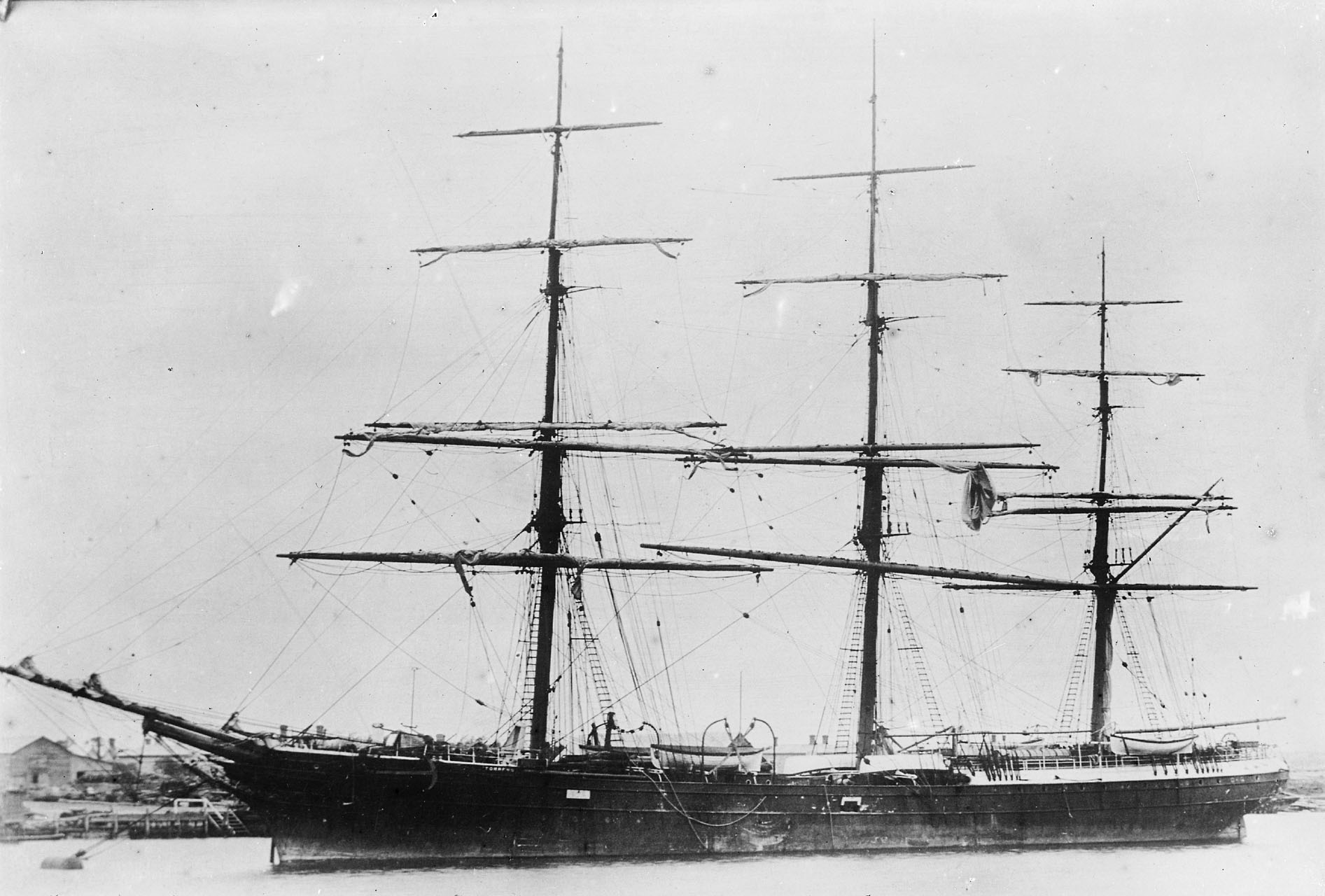 トーレンス コンラッドは一等航海士として、1891年11月から1893年7月にかけてロンドンからアデレードまで2往復した。 コンラッドは1890年12月末にアフリカを離れ、翌年1月下旬までにブリュッセルに到着した。1892年10月25日、客船トーレンス号でロンドンを出 航したとき、乗客のひとりにケンブリッジ大学を卒業したウィリアム・ヘンリー・ジャックがいた。コンラッドの『個人的記録』によれば、ジャックはコンラッ ドの『アルマイヤーの愚行』のまだ未完成の原稿の最初の読者だった。ジャックはコンラッドに小説の執筆を続けるよう勧めた[57]。  コンラッドがトーレンスで出会ったジョン・ガルスワシー 1893年7月26日、トーレンス号がロンドンに停泊し、「J.コンラッド・コルゼモウィン」(除籍証明書による)が下船したとき、コンラッドは船員として最後の長距離航海を終えた。 トーレンス号が1893年3月13日にアデレードを出港したとき、乗客にはオーストラリアとニュージーランドから帰国した2人の若い英国人が含まれてい た。25歳の弁護士で後に小説家となるジョン・ガルスワージーと、父親がエルスツリーで経営する男子予備校を手伝う予定だったエドワード・ランスロット・ サンダーソンである。彼らはおそらく、コンラッドが初めて親交を結んだ英国人であり、船乗りでもなかった。ガルスワージーの最初の文学的試みのひとつであ る『The Doldrums』(1895-96)では、主人公の一等航海士アーマンドがコンラッドをモデルにしている。 トーレンス号が5月17日から19日まで滞在したケープタウンで、ガルスワージーは地元の鉱山を見るために船を離れた。サンダーソンは航海を続け、コン ラッドと親密な関係を築いた最初の人物であったようだ[58]。その年の暮れ、コンラッドはポーランドとウクライナの親戚を再び訪れることになる[48] [59]。 作家  1916年のコンラッド(アルヴィン・ラングドン・コバーン撮影) 1889年の秋、コンラッドは処女作『アルマイヤーの愚行』の執筆を始める[60]。 [母方の)叔父[タデウシュ・ボブロフスキ]からその手紙の文体の美しさを賞賛された作家の息子であり、最初のページから仕事に対する真剣でプロフェッ ショナルなアプローチを示していたコンラッドが、『アルマイヤーの愚行』の執筆を始めたのは、束縛のない気軽な出来事であった...。[彼は書く必要性を 強く感じていたに違いない。しかし、彼は書くことの必要性を強く感じていたに違いない。最初の1ページ目から、書くことが娯楽のためでも暇つぶしでもな かったことを物語っている。それどころか、それは真剣な仕事であり、巨匠たちの入念で勤勉な読書に支えられ、芸術と現実に対する彼自身の態度を形成するこ とを目的としていた......。[彼の芸術的衝動と創造的才能の源はわからない[61]。 コンラッドが後に文学仲間に宛てた手紙には、文体の分析、個々の単語や表現、フレーズの感情的なトーン、言語が作り出す雰囲気の分析に注意を払っていたこ とが示されている。この点で、コンラッドは彼なりにギュスターヴ・フローベールの例に倣った。彼は「問題の本質」を表現するのに適切な言葉、le mot justeを何日も探し続けたことで有名である。ナジダーはこう言う: 「外国語で書くということは、個人的に繊細な問題に取り組む際により大胆になれるということである。原則として、後天的に習得した言語のほうが、悪態をつくのも冷静に分析するのも容易なのである」[62]。 1894年、36歳のとき、コンラッドは不本意ながら海をあきらめたが、その理由のひとつは、健康状態が悪かったこと、船が手に入らなかったこと、そして もうひとつは、書くことに魅了され、文学の道に進むことを決意したからであった。ボルネオ東海岸を舞台にした『アルマイヤーの愚行』は1895年に出版さ れた。もちろん「コンラッド」は彼のポーランド名である「コンラッド」の3番目の名前であったが、彼が「コンラッド」というペンネームを使用したのは、 ポーランドのロマン派詩人アダム・ミキェヴィッチの愛国的な物語詩『コンラッド・ワレンロッド』へのオマージュでもあったのかもしれない[63]。 コンラッドの文学的キャリアにおいて主要な脇役の一人を演じることになる若い出版社の読者であり文芸批評家であったエドワード・ガーネットは、『アルマイ ヤーの愚行』のアンウィンの最初の読者であったウィルフリッド・ヒュー・チェソンと同様に、この原稿に感銘を受けたが、ガーネットは「出版に十分な英語か どうかは不確か」であった。ガーネットは、後にロシア文学の翻訳者となる妻のコンスタンス・ガーネットにこの小説を見せた。彼女はコンラッドが外国人であ ることを肯定的に評価していた[64]。 コンラッドが東南アジアの人々と個人的に面識があったのは限られていたが、この地域は彼の初期の作品に大きく登場する。ナジャーによれば、亡命者であり放 浪者であったコンラッドは、一度ならず告白した困難さを自覚していた。英語圏の読者と共通の文化的背景を持たないコンラッドは、英語圏の世界について書く 英語作家と競争することができなかったのである。英語圏の読者と共通の文化的背景を持たない彼は、英語圏について書く英語圏の作家と競争することはできな かった。同時に、非英語圏の植民地を舞台に選んだことで、彼は気恥ずかしい忠誠心の分裂から解放された: アルマイヤーの愚行』や、後にベルギー国王レオポルド2世に搾取されたコンゴを舞台にした『前進の前哨基地』(1897年)、同じくコンゴを舞台にした 『闇の奥』(1899年)には、植民地主義に対する辛辣な考察が含まれている。マレー諸国は理論的にはオランダ政府の宗主国であり、コンラッドは一度も訪 れたことのないこの地域のイギリス従属国については書かなかった。彼は「どうやら国民の独立を守ろうとする...闘争に興味をそそられたようだ。熱帯の自 然の多産で破壊的な豊かさと、その中での人間生活の悲惨さは、彼の初期の作品の厭世的な気分とよく一致していた」[65][注 13]。 アルマイヤーの愚行』は、その後継作である『島の追放者』(1896年)とともに、コンラッドがエキゾチックな物語のロマンチックな語り手として評価される基礎を築いた。 フォートナイトリー・レビュー』や『ノース・アメリカン・レビュー』のような影響力のある批評誌、『サヴォイ』、『ニュー・レビュー』、『イングリッ シュ・レビュー』のような前衛的な出版物、『サタデー・イブニング・ポスト』や『ハーパーズ・マガジン』のような大衆的な短編小説雑誌、『ピクトリアル・ レビュー』や『ロマンス』のような女性誌、『デイリー・メール』や『ニューヨーク・ヘラルド』のような大衆紙、『イラストレイテッド・ロンドン・ニュー ス』や『イラストレイテッド・バッファロー・エクスプレス』のような挿絵入りの新聞などである。 [また、1898年から1906年にかけて帝国主義的な週刊誌『アウトルック』にも寄稿した[69][注 15]。 1910年8月9日に支給された年額100ポンドの政府補助金(「市民リスト年金」)によって、コンラッドは経済的な心配から解放され[72][注釈 17]、やがてコレクターが彼の原稿を購入するようになった。彼の才能は早くからイギリスの知識人たちに認められていたが、1913年に『チャンス』が出 版されるまで大衆的な成功は得られなかった。 私生活  タイム』1923年4月7日号 気質と健康 コンラッドは控えめな男で、感情を表に出すことを警戒していた。叔父のボブロウスキーの言葉を借りれば、若い頃のコンラッドは「非常に繊細で、うぬぼれが強く、控えめで、おまけに興奮しやすかった。要するに[...]ナウエノーラ家の欠点をすべて備えていた」[75]。 コンラッドは生涯を通じて、肉体的にも精神的にも不健康に苦しんだ。1891年、コンラッドは痛風、右腕の神経痛、マラリアの再発に苦しみ、数ヶ月入院し た。また、手の腫れを訴え、「字を書くのが困難」であった。叔父のタデウシュ・ボブロフスキの勧めもあり、スイスの温泉で療養した[77]。コンラッドは 歯科恐怖症で、抜歯しなければならなくなるまで歯を放置していた。コンラッドの身体的な苦悩は、どちらかといえば、精神的な苦悩よりも少ないものであっ た。その証拠に」、ナジェルダーは「疑うことはほとんど不可能なほど強い」と書いている[79]。 自殺未遂 1878年3月、マルセイユ時代の終わりに、20歳のコンラッドはリボルバーで自分の胸を撃って自殺を図った[80]。友人に呼び出された叔父によると、 コンラッドは借金を抱えていた。ボブロフスキは、自身の思想的な敵対者であり、コンラッドの亡父アポロの友人であったステファン・ブシチンスキに宛てた膨 大な手紙の中で、その後の甥の「研究」について述べている[注 18] 。自殺未遂がどの程度本格的なものであったかは知る由もないが、状況的な鬱病を示唆している[81]。 ロマンスと結婚 1888年、インド洋のモーリシャスに立ち寄った際、コンラッドは2、3の恋愛感情を抱いた。そのうちのひとつが1910年に発表された「幸運の微笑み」 で描かれることになるが、この物語には自伝的要素が含まれている(例えば、登場人物のひとりは『シャドー・ライン』に登場するバーンズ航海長と同じ人物で ある)。語り手である若い船長は、立派なバラ園に囲まれた家に住む地元の商人の娘、アリス・ジャコバスと曖昧に、こっそりと浮気する。調査の結果、当時の ポートルイスには17歳のアリス・ショーがおり、その父親は海運代理店で、町で唯一のバラ園を所有していたことが確認されている[82]。 コンラッドのもう一つの、より公然の浮気についてはもっと知られている。旧友であるフランス商船のガブリエル・ルヌーフ大尉は、コンラッドを義兄の家族に 紹介した。ルヌーフの長姉は植民地の高官ルイ・エドワード・シュミットの妻で、他に2人の姉と2人の兄弟がいた。島は1810年に英国に占領されたが、住 民の多くはフランス人入植者の子孫であり、コンラッドは優れたフランス語と完璧なマナーで、地元のサロンをすべて彼に開放した。コンラッドはシュミット家 に頻繁に通うようになり、そこでルヌーフ夫人にしばしば会った。ポートルイスを去る数日前、コンラッドはルヌーフ兄弟の一人に26歳の妹ユージェニーの求 婚をした。しかし、彼女はすでに薬剤師のいとこと婚約していた。拒絶された後、コンラッドは別れの訪問はしなかったが、ガブリエル・ルヌーフに丁寧な手紙 を送り、モーリシャスには二度と戻らないと言い、結婚式の日には彼らのことを思っていると付け加えた。  ケント州カンタベリーにあるウェストベア・ハウスは、かつてコンラッドが所有していた。イングランドの国民遺産リストにグレードⅡとして登録されている[83]。 1896年3月24日、コンラッドはイギリス人女性のジェシー・ジョージと結婚した[48]。ジェシーはコンラッドより16歳も年下で、素朴な労働者階級 の少女だった[85]。コンラッドの友人たちにとって、彼女は不可解な妻選びであり、かなり軽蔑的で不親切な発言の対象だった[86](『印象』における レディ・オットリン・モレルのジェシーに対する評価を参照)。 しかし、フレデリック・カールなど他の伝記作家によれば、ジェシーはコンラッドが必要としていたもの、すなわち「素直で、献身的で、かなり有能な」伴侶を 提供した[68]。同様に、ジョーンズは、結婚生活がどのような困難に耐えたとしても、「この関係がコンラッドの作家としてのキャリアを支えたことに疑い の余地はない」と述べている。 コンラッド夫妻は、主にイギリスの田舎に、長い間、家を借り続けた。コンラッドはたびたびうつ病を患い、気分を変えるために多大な努力をした。1910年 から1919年の間、コンラッドの住まいはケント州オルストンのカペル・ハウスで、オリヴァー卿夫妻が彼に貸していた。ここで『救出』、『勝利』、『金の 矢』を執筆した[89]。 フランスとイタリアでの数回の休暇、1914年の母国ポーランドでの休暇、1923年のアメリカ訪問を除いて、コンラッドは残りの生涯をイギリスで過ごした。 ポーランド滞在  1914年、コンラッドと家族は、後に同名のポーランド人翻訳者となるアニエラ・ザゴルスカの母である従姉妹が経営するザコパネ・ウィラ・コンスタンティヌフカに滞在した[90]。  コンラッドの姪アニエラ・ザゴルスカ(左)、カロラ・ザゴルスカ;コンラッド 1914年7月28日、オーストリア=ハンガリーとセルビアの間で戦争が勃発した日、コンラッドとレッティンガー夫妻はクラクフ(当時はオーストリア=ハンガリー帝国領)に到着し、コンラッドは幼少時代に過ごした場所を訪れた。 この街はロシアとの国境からわずか数マイルしか離れていなかったため、戦闘地域に取り残される危険性があった。妻ジェシーと次男ジョンが病気だったため、 コンラッドは山岳リゾートの町ザコパネに避難することにした。彼らは8月2日にクラクフを出発した。ザコパネに到着して数日後、彼らはコンラッドのいとこ アニエラ・ザゴルスカが経営するペンション「コンスタンチヌフカ」に移った。このペンションは、政治家ヨゼフ・ピウスツキやコンラッドの知人である若きコ ンサートピアニスト、アルトゥール・ルービンシュタインなどの著名人がよく利用していた[91]。 ザゴルスカは、小説家ステファン・ジェロムスキや人類学者ブロニスワフ・マリノフスキの友人であった作家タデウシュ・ナレピンスキなど、同じくザコパネに 避難していたポーランドの作家、知識人、芸術家にコンラッドを紹介した。コンラッドは有名な作家として、また外国から来た異国の同胞としてポーランド人の 関心を集めた。彼は新しい知り合い、特に女性を魅了した。 しかし、マリー・キュリーの医師の妹で、同じ医師で著名な社会主義活動家カジミエシュ・ドゥウスキの妻であるブロニスワワ・ドゥウスカは、コンラッドが自 分の偉大な才能を祖国の未来をより良くする以外の目的のために使ったことを公然と非難した[92][注 19][注 20]。 しかし、コンラッドの姪で、1923年から39年にかけてコンラッドの作品をポーランド語に翻訳することになる32歳のアニエラ・ザゴルスカ(年金管理人 の娘)は、コンラッドを慕い、付き合い、本を提供した。特に10歳年上で最近亡くなったボレスワフ・プリュス[95][96](彼もまたザコパネを訪れて いた[97])の物語や小説を喜び、1863年のポーランドの蜂起の犠牲者仲間である「私の愛するプリュス」の手に入るものはすべて読み、コンラッドが好 んだイギリスの小説家である「ディケンズよりも優れている」と評した[98][注釈 21]。 コンラッドはポーランドの知人たちから、いまだに母国語が流暢であることを指摘され、彼らの熱のこもった政治的議論に参加した。ポーランドが独立を取り戻 すためには、戦争においてロシアが中央列強(オーストリア=ハンガリー帝国とドイツ帝国)に打ち勝たなければならず、中央列強は今度はフランスとイギリス に打ち勝たなければならない[100][注釈 22]と、1914年にヨゼフ・ピウスツキがパリで先駆けて宣言したように、彼は先見の明があった。 多くの苦難と波乱を経て、1914年11月初め、コンラッドは家族をイギリスに連れて帰ることに成功した。帰国後、彼はポーランドの主権回復を支持するイギリスの世論を動かすことに尽力する決意を固めた[102]。 ジェシー・コンラッドは後に回想録にこう記している: 「ポーランドでの数ヶ月の後、私は夫のことがよくわかった。それまでは奇妙で理解不能だった多くの特徴が、いわば正しい比率を持つようになった。私は彼の気質が彼の同胞の気質であることを理解した」[103]。 政治 伝記作家のズジスワフ・ナイデルはこう書いている: コンラッドは政治に熱心だった。[このことは、『アルマイヤーの愚行』から始まるいくつかの作品によって確認できる。[それはもちろん、政治が日常生活の 問題であるだけでなく、生と死の問題でもあった国(ポーランド)出身の人物にとっては、ごく自然な関心事であった。しかも、コンラッド自身は、国家問題に 対する独占的な責任を主張する社会階級の出身であり、非常に政治活動的な家庭の出身であった。ノーマン・ダグラスはこう総括する: 「コンラッドは何よりもまずポーランド人であり、多くのポーランド人と同様、政治家であり、モラリストであった。これが彼の基本である。[コンラッドに政 治問題を、法と暴力、無政府と秩序、自由と独裁、物質的利益と個人の崇高な理想主義との間の絶え間ない闘争という観点からとらえさせたのは......コ ンラッドの歴史認識であった。彼のポーランドの経験は、当時の西欧文学のなかでも例外的に、これらの闘争の最前線がいかに曲がりくねったものであり、絶え ず変化するものであるかという認識を彼に与えた[104]。 コンラッドがこれまでに書いた中で最も広範で野心的な政治的発言は、1905年のエッセイ『独裁と戦争』であり、その出発点は日露戦争であった(彼はこの 論文を対馬海峡海戦の1ヶ月前に書き上げた)。このエッセイは、ロシアの不治の弱さについての記述で始まり、将来のヨーロッパ戦争における危険な侵略者で あるプロイセンに対する警告で終わっている。ロシアについては、近い将来に暴力的な暴発が起こると予測していたが、ロシアには民主主義の伝統がなく、大衆 も後進的であるため、革命が救済的な効果をもたらすことは不可能であった。コンラッドは、ロシアで代議制政府を樹立することは不可能だと考え、独裁政治か ら独裁政治への移行を予見した。コンラッドは、西ヨーロッパが経済的対立と商業的利己主義によって引き起こされた対立に引き裂かれていると見ていた。ロシ ア革命は、過去の戦争よりもはるかに残忍な戦争に備えて武装した、物質主義的でエゴイスティックな西ヨーロッパに助言や助けを求めても無駄かもしれない [105]。  1924年、ジェイコブ・エプスタインによるコンラッドの胸像。コンラッドはこの胸像を「いささか記念碑的な威厳のある素晴らしい作品であり、しかもその似顔絵が印象的であることは誰もが認めるところである」と評している[106]。 コンラッドの民主主義に対する不信感は、それ自体が目的である民主主義の普及が何らかの問題を解決することができるのかという疑問から生じていた。コン ラッドは、人間の本性の弱さと社会の「犯罪的」性格を考慮すると、民主主義はデマゴーグやチャラタンに無限の機会を提供すると考えた[107]。 コンラッドは、当時の社会民主主義者が「国民感情(国民感情を維持することが彼の関心事であった)」を弱めるような行動をとり、非人間的な坩堝の中で国民 のアイデンティティを溶解させようとしていることを非難した。「私は非常に黒い過去の深みから未来を見つめ、私には失われた大義への忠誠、未来のない思想 への忠誠以外、何も残されていないことに気がついた"。ポーランドの記憶に対するコンラッドの絶望的な忠誠心が、「国際友愛」という考えを信じることを妨 げたのである。彼は、自由と世界の兄弟愛について語る一方で、分割され抑圧された自国のポーランドについては沈黙を守る一部の社会主義者に憤慨していた [107]。 それ以前の1880年代初頭、叔父のタデウシュからコンラッドに宛てた手紙[注釈 23]を見ると、コンラッドはポーランドの状況の改善を解放運動ではなく、近隣のスラヴ諸国との同盟の確立によって望んでいたようである。これには、パン スラヴィック・イデオロギーへの信頼が伴っていた-「後にロシアへの敵意を強調することになる人物としては驚くべきことだが」、ナジデルはこう書いてい る。ポーランドの(優れた)文明と(歴史的な)伝統によって、ポーランドはパンスラヴ共同体の中で(主導的な)役割を果たすことができるという確信、そし てポーランドが完全に主権を持つ国民国家になる可能性についての疑念であった」[109]。 1894年、コンラッドがブリュッセルの親戚で作家仲間のマルグリット・ポラドフスカ(旧姓ガシェ、フィンセント・ファン・ゴッホの主治医ポール・ガシェのいとこ)に宛てた手紙にこう書かれている: 私たちは自分の人格という鎖と玉を最後まで引きずっていかなければならない。この世で囚人となるのは、選ばれた者たちだけである。理解し、うめき声をあげ ながらも、マニアックな身振りとバカげた笑みを浮かべながら、大勢の幻影の中で大地を踏みしめる栄光の一団である。バカと囚人、あなたはどちらになりたい だろうか? コンラッドはH.G.ウェルズに対して、1901年に刊行されたウェルズの著書『予期』は社会の大きな流れを予見しようとする野心的な試みであったが、 「世界の他の部分を埒外に置き去りにして、自分自身だけを対象とする一種の選ばれたサークルを前提にしているようだ。[加えて、狡猾で裏切り者である人間 の愚かさを十分に考慮していない」[111][注 24]。 1922年10月23日、数学者であり哲学者でもあるバートランド・ラッセルに宛てた手紙の中で、ラッセルの著書『中国の問題』(The Problem of China)に対して、社会主義改革と中国社会を再構築する聖賢の寡頭制を提唱したコンラッドは、政治的万能薬に対する自身の不信感を説明している: 私は、この人間の住む世界を支配している宿命に対する私の根深い感覚に立ち向かえるようなものを...どんな人の本や...話の中にも...見いだしたこ とはない...。中国人と私たちにとっての唯一の救済策は、[心の]変化であるが、過去2000年の歴史を見ると、人間が空を飛ぶようになったとしても、 [それを]期待する理由はあまりない-大きな「高揚」は間違いないが、大きな変化はない[112]。 レオ・ロブソンはこう書いている: コンラッドは......より広範な皮肉的スタンス、つまり『西部の瞳の下に』の登場人物によって定義された、あらゆる信仰、献身、行動の否定という、あ る種の包括的な信じられないというスタンスを採用した。口調と物語の細部をコントロールすることによって...。コンラッドは、無政府主義や社会主義と いった運動のナイーブさや、資本主義(宣伝効果のある海賊行為)、合理主義(人間の生来の非合理性に対する精巧な防衛策)、帝国主義(昔ながらの強姦と略 奪のための壮大な隠れ蓑)といった歴史的だが「自然化」された現象の利己的な論理を暴いている。皮肉であるということは、目を覚まし、蔓延する 「傾眠 」を警戒することである。ノストロモ』では...ジャーナリストのマーティン・デクーは...人々が「自分自身が宇宙の運命を左右していると信じている」 という考えを嘲笑している。(H.G.ウェルズは、コンラッドが「私は社会的、政治的問題を真剣に受け止めることができる」と驚いていたことを回想してい る)[113]。 しかしロブソンは、コンラッドは道徳的ニヒリストではないと書いている: 物事には目に映る以上のものがあることを示唆するために皮肉が存在するのだとすれば、コンラッドはさらに、十分に注意を払えば、その「以上のもの」は無限 にありうると主張する。彼は、[『若者たち』に登場する]マーローが「私たちの文明の窶れた功利主義的な嘘」と呼ぶものを、何もないものとして拒絶するの ではなく、「何か」、「救いのある真実」、「疑念の亡霊に対する悪魔祓い」、つまり言葉には容易に還元できない、より深い秩序の暗示として拒絶するのであ る。本物の、自覚的な感情-自らを「理論」とも「知恵」とも呼ばない感情-は、一種の旗手となり、「印象」や「感覚」が最も確かな証拠に近いものとなる [114]。 1901年8月、『ニューヨーク・タイムズ』紙の『サタデイ・ブック・レヴュー』の編集者に宛てた手紙の中で、コンラッドは次のように書いている。「世界 を動かす力であるエゴイズムと、その道徳である利他主義、この二つの矛盾した本能は、一方はとても平明であり、他方はとても神秘的であるが、その両立しが たい拮抗の不可解な同盟の中でなければ、われわれに奉仕することはできない」[115][注 25]。 死  ケント州ハーブルダウン近郊のカンタベリー墓地にあるコンラッドの墓 1924年8月3日、コンラッドはイングランド、ケント州ビショップボーンの自宅オズワルズで、おそらく心臓発作のため死去した。墓碑銘には、エドマンド・スペンサーの『フェアリー・クイーン』の一節が刻まれている: 戯れの後の眠り、嵐の海の後の港、 戦いの後の安らぎ、生の後の死は、大いに喜ばしい[118]。 コンラッドのささやかな葬儀は大群衆の中で行われた。旧友エドワード・ガーネットは苦々しげに回想している: 1924年のクリケット・フェスティバルの最中にカンタベリーで行われたコンラッドの葬儀に参列し、国旗で飾られた混雑した通りを車で通り抜けた人々に とって、イギリスのもてなしと、この偉大な作家の存在すら知らない群衆の姿には、象徴的なものがあった。数人の旧友、知人、報道関係者が彼の墓のそばに 立っていた[117]。 コンラッドのもう一人の旧友カニングヘイム・グラハムはガーネットにこう書いている:「オーブリーは私に......アナトール・フランスが死んでいたら、パリ中が彼の葬儀に参列していただろうと言っていた」[117]。 コンラッドの妻ジェシーは12年後の1936年12月6日に亡くなり、彼とともに埋葬された。 1996年、コンラッドの墓は第二級建造物に指定された[119]。 |
| Writing style Themes and style 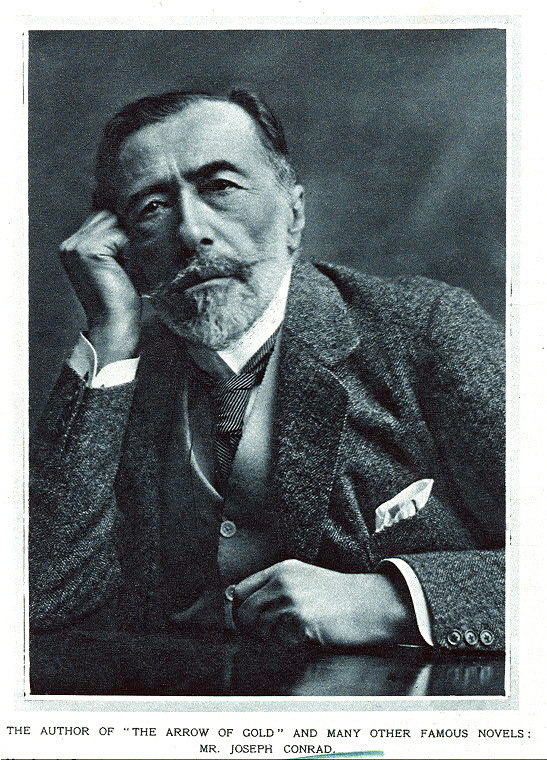 Joseph Conrad, 1919 or after Despite the opinions even of some who knew Conrad personally, such as fellow-novelist Henry James,[120] Conrad—even when only writing elegantly crafted letters to his uncle and acquaintances—was always at heart a writer who sailed, rather than a sailor who wrote. He used his sailing experiences as a backdrop for many of his works, but he also produced works of similar world view, without the nautical motifs. The failure of many critics to appreciate this caused him much frustration.[121] He wrote more often about life at sea and in exotic parts than about life on British land because—unlike, for example, his friend John Galsworthy, author of The Forsyte Saga—he knew little about everyday domestic relations in Britain. When Conrad's The Mirror of the Sea was published in 1906 to critical acclaim, he wrote to his French translator: "The critics have been vigorously swinging the censer to me.... Behind the concert of flattery, I can hear something like a whisper: 'Keep to the open sea! Don't land!' They want to banish me to the middle of the ocean."[67] Writing to his friend Richard Curle, Conrad remarked that "the public mind fastens on externals" such as his "sea life", oblivious to how authors transform their material "from particular to general, and appeal to universal emotions by the temperamental handling of personal experience".[122] Nevertheless, Conrad found much sympathetic readership, especially in the United States. H.L. Mencken was one of the earliest and most influential American readers to recognise how Conrad conjured up "the general out of the particular". F. Scott Fitzgerald, writing to Mencken, complained about having been omitted from a list of Conrad imitators. Since Fitzgerald, dozens of other American writers have acknowledged their debts to Conrad, including William Faulkner, William Burroughs, Saul Bellow, Philip Roth, Joan Didion, and Thomas Pynchon.[123] An October 1923 visitor to Oswalds, Conrad's home at the time—Cyril Clemens, a cousin of Mark Twain—quoted Conrad as saying: "In everything I have written there is always one invariable intention, and that is to capture the reader's attention."[124] Conrad the artist famously aspired, in the words of his preface to The Nigger of the 'Narcissus' (1897), "by the power of the written word to make you hear, to make you feel... before all, to make you see. That—and no more, and it is everything. If I succeed, you shall find there according to your deserts: encouragement, consolation, fear, charm—all you demand—and, perhaps, also that glimpse of truth for which you have forgotten to ask."[125] Writing in what to the visual arts was the age of Impressionism, and what to music was the age of impressionist music, Conrad showed himself in many of his works a prose poet of the highest order: for instance, in the evocative Patna and courtroom scenes of Lord Jim; in the scenes of the "melancholy-mad elephant"[note 26] and the "French gunboat firing into a continent", in Heart of Darkness; in the doubled protagonists of "The Secret Sharer"; and in the verbal and conceptual resonances of Nostromo and The Nigger of the 'Narcissus'. Conrad used his own memories as literary material so often that readers are tempted to treat his life and work as a single whole. His "view of the world", or elements of it, is often described by citing at once both his private and public statements, passages from his letters, and citations from his books. Najder warns that this approach produces an incoherent and misleading picture. "An... uncritical linking of the two spheres, literature and private life, distorts each. Conrad used his own experiences as raw material, but the finished product should not be confused with the experiences themselves."[126] Many of Conrad's characters were inspired by actual persons he had met, including, in his first novel, Almayer's Folly (completed 1894), William Charles Olmeijer, the spelling of whose surname Conrad probably altered to "Almayer" inadvertently.[127] The historic trader Olmeijer, whom Conrad encountered on his four short visits to Berau in Borneo, subsequently haunted Conrad's imagination.[128] Conrad often borrowed the authentic names of actual individuals, e.g., Captain McWhirr[note 27] (Typhoon), Captain Beard and Mr. Mahon ("Youth"), Captain Lingard (Almayer's Folly and elsewhere), and Captain Ellis (The Shadow Line). "Conrad", writes J. I. M. Stewart, "appears to have attached some mysterious significance to such links with actuality."[130] Equally curious is "a great deal of namelessness in Conrad, requiring some minor virtuosity to maintain."[131] Thus we never learn the surname of the protagonist of Lord Jim.[132] Conrad also preserves, in The Nigger of the 'Narcissus', the authentic name of the ship, the Narcissus, in which he sailed in 1884.[133] Apart from Conrad's own experiences, a number of episodes in his fiction were suggested by past or contemporary publicly known events or literary works. The first half of the 1900 novel Lord Jim (the Patna episode) was inspired by the real-life 1880 story of the SS Jeddah;[134] the second part, to some extent by the life of James Brooke, the first White Rajah of Sarawak.[135] The 1901 short story "Amy Foster" was inspired partly by an anecdote in Ford Madox Ford's The Cinque Ports (1900), wherein a shipwrecked sailor from a German merchant ship, unable to communicate in English, and driven away by the local country people, finally found shelter in a pigsty.[136][note 28] In Nostromo (completed 1904), the theft of a massive consignment of silver was suggested to Conrad by a story he had heard in the Gulf of Mexico and later read about in a "volume picked up outside a second-hand bookshop."[138] [note 29] The novel's political strand, according to Maya Jasanoff, is related to the creation of the Panama Canal. "In January 1903", she writes, "just as Conrad started writing Nostromo, the US and Colombian secretaries of state signed a treaty granting the United States a one-hundred-year renewable lease on a six-mile strip flanking the canal... While the [news]papers murmured about revolution in Colombia, Conrad opened a fresh section of Nostromo with hints of dissent in Costaguana", his fictional South American country. He plotted a revolution in the Costaguanan fictional port of Sulaco that mirrored the real-life secessionist movement brewing in Panama. When Conrad finished the novel on 1 September 1904, writes Jasanoff, "he left Sulaco in the condition of Panama. As Panama had gotten its independence instantly recognized by the United States and its economy bolstered by American investment in the canal, so Sulaco had its independence instantly recognized by the United States, and its economy underwritten by investment in the [fictional] San Tomé [silver] mine."[140] The Secret Agent (completed 1906) was inspired by the French anarchist Martial Bourdin's 1894 death while apparently attempting to blow up the Greenwich Observatory.[141] Conrad's story "The Secret Sharer" (completed 1909) was inspired by an 1880 incident when Sydney Smith, first mate of the Cutty Sark, had killed a seaman and fled from justice, aided by the ship's captain.[142] The plot of Under Western Eyes (completed 1910) is kicked off by the assassination of a brutal Russian government minister, modelled after the real-life 1904 assassination of Russian Minister of the Interior Vyacheslav von Plehve.[143] The near-novella "Freya of the Seven Isles" (completed in March 1911) was inspired by a story told to Conrad by a Malaya old hand and fan of Conrad's, Captain Carlos M. Marris.[144] For the natural surroundings of the high seas, the Malay Archipelago and South America, which Conrad described so vividly, he could rely on his own observations. What his brief landfalls could not provide was a thorough understanding of exotic cultures. For this he resorted, like other writers, to literary sources. When writing his Malayan stories, he consulted Alfred Russel Wallace's The Malay Archipelago (1869), James Brooke's journals, and books with titles like Perak and the Malays, My Journal in Malayan Waters, and Life in the Forests of the Far East. When he set about writing his novel Nostromo, set in the fictional South American country of Costaguana, he turned to The War between Peru and Chile; Edward Eastwick, Venezuela: or, Sketches of Life in a South American Republic (1868); and George Frederick Masterman, Seven Eventful Years in Paraguay (1869).[145] [note 30] As a result of relying on literary sources, in Lord Jim, as J. I. M. Stewart writes, Conrad's "need to work to some extent from second-hand" led to "a certain thinness in Jim's relations with the... peoples... of Patusan..."[147] This prompted Conrad at some points to alter the nature of Charles Marlow's narrative to "distanc[e] an uncertain command of the detail of Tuan Jim's empire."[148] In keeping with his scepticism[149][7] and melancholy,[150] Conrad almost invariably gives lethal fates to the characters in his principal novels and stories. Almayer (Almayer's Folly, 1894), abandoned by his beloved daughter, takes to opium, and dies.[151] Peter Willems (An Outcast of the Islands, 1895) is killed by his jealous lover Aïssa.[152] The ineffectual "Nigger", James Wait (The Nigger of the 'Narcissus', 1897), dies aboard ship and is buried at sea.[153] Mr. Kurtz (Heart of Darkness, 1899) expires, uttering the words, "The horror! The horror!"[153] Tuan Jim (Lord Jim, 1900), having inadvertently precipitated a massacre of his adoptive community, deliberately walks to his death at the hands of the community's leader.[154] In Conrad's 1901 short story, "Amy Foster", a Pole transplanted to England, Yanko Goorall (an English transliteration of the Polish Janko Góral, "Johnny Highlander"), falls ill and, suffering from a fever, raves in his native language, frightening his wife Amy, who flees; next morning Yanko dies of heart failure, and it transpires that he had simply been asking in Polish for water.[note 31] Captain Whalley (The End of the Tether, 1902), betrayed by failing eyesight and an unscrupulous partner, drowns himself.[156] Gian' Battista Fidanza,[note 32] the eponymous respected Italian-immigrant Nostromo (Italian: "Our Man") of the novel Nostromo (1904), illicitly obtains a treasure of silver mined in the South American country of "Costaguana" and is shot dead due to mistaken identity.[157] Mr. Verloc, The Secret Agent (1906) of divided loyalties, attempts a bombing, to be blamed on terrorists, that accidentally kills his mentally defective brother-in-law Stevie, and Verloc himself is killed by his distraught wife, who drowns herself by jumping overboard from a channel steamer.[158] In Chance (1913), Roderick Anthony, a sailing-ship captain, and benefactor and husband of Flora de Barral, becomes the target of a poisoning attempt by her jealous disgraced financier father who, when detected, swallows the poison himself and dies (some years later, Captain Anthony drowns at sea).[159] In Victory (1915), Lena is shot dead by Jones, who had meant to kill his accomplice Ricardo and later succeeds in doing so, then himself perishes along with another accomplice, after which Lena's protector Axel Heyst sets fire to his bungalow and dies beside Lena's body.[160] When a principal character of Conrad's does escape with his life, he sometimes does not fare much better. In Under Western Eyes (1911), Razumov betrays a fellow University of St. Petersburg student, the revolutionist Victor Haldin, who has assassinated a savagely repressive Russian government minister. Haldin is tortured and hanged by the authorities. Later Razumov, sent as a government spy to Geneva, a centre of anti-tsarist intrigue, meets the mother and sister of Haldin, who share Haldin's liberal convictions. Razumov falls in love with the sister and confesses his betrayal of her brother; later, he makes the same avowal to assembled revolutionists, and their professional executioner bursts his eardrums, making him deaf for life. Razumov staggers away, is knocked down by a streetcar, and finally returns as a cripple to Russia.[161] Conrad was keenly conscious of tragedy in the world and in his works. In 1898, at the start of his writing career, he had written to his Scottish writer-politician friend Cunninghame Graham: "What makes mankind tragic is not that they are the victims of nature, it is that they are conscious of it. [A]s soon as you know of your slavery the pain, the anger, the strife—the tragedy begins." But in 1922, near the end of his life and career, when another Scottish friend, Richard Curle, sent Conrad proofs of two articles he had written about Conrad, the latter objected to being characterised as a gloomy and tragic writer. "That reputation... has deprived me of innumerable readers... I absolutely object to being called a tragedian."[162] Conrad claimed that he "never kept a diary and never owned a notebook." John Galsworthy, who knew him well, described this as "a statement which surprised no one who knew the resources of his memory and the brooding nature of his creative spirit."[163] Nevertheless, after Conrad's death, Richard Curle published a heavily modified version of Conrad's diaries describing his experiences in the Congo;[164] in 1978 a more complete version was published as The Congo Diary and Other Uncollected Pieces.[165] The first accurate transcription was published in Robert Hampson's Penguin edition of Heart of Darkness in 1995; Hampson's transcription and annotations were reprinted in the Penguin edition of 2007.[166][167] Unlike many authors who make it a point not to discuss work in progress, Conrad often did discuss his current work and even showed it to select friends and fellow authors, such as Edward Garnett, and sometimes modified it in the light of their critiques and suggestions.[168] Edward Said was struck by the sheer quantity of Conrad's correspondence with friends and fellow writers; by 1966, it "amount[ed] to eight published volumes". Said comments: "[I]t seemed to me that if Conrad wrote of himself, of the problem of self-definition, with such sustained urgency, some of what he wrote must have had meaning for his fiction. [I]t [was] difficult to believe that a man would be so uneconomical as to pour himself out in letter after letter and then not use and reformulate his insights and discoveries in his fiction." Said found especially close parallels between Conrad's letters and his shorter fiction. "Conrad... believed... that artistic distinction was more tellingly demonstrated in a shorter rather than a longer work.... He believed that his [own] life was like a series of short episodes... because he was himself so many different people...: he was a Pole[note 33] and an Englishman, a sailor and a writer."[169] Another scholar, Najder, wrote: Throughout almost his entire life Conrad was an outsider and felt himself to be one. An outsider in exile; an outsider during his visits to his family in the Ukraine; an outsider—because of his experiences and bereavement—in [Kraków] and Lwów; an outsider in Marseilles; an outsider, nationally and culturally, on British ships; an outsider as an English writer.... Conrad called himself (to Graham) a "bloody foreigner." At the same time... [h]e regarded "the national spirit" as the only truly permanent and reliable element of communal life.[170] Conrad borrowed from other, Polish- and French-language authors, to an extent sometimes skirting plagiarism. When the Polish translation of his 1915 novel Victory appeared in 1931, readers noted striking similarities to Stefan Żeromski's kitschy novel, The History of a Sin (Dzieje grzechu, 1908), including their endings. Comparative-literature scholar Yves Hervouet has demonstrated in the text of Victory a whole mosaic of influences, borrowings, similarities and allusions. He further lists hundreds of concrete borrowings from other, mostly French authors in nearly all of Conrad's works, from Almayer's Folly (1895) to his unfinished Suspense. Conrad seems to have used eminent writers' texts as raw material of the same kind as the content of his own memory. Materials borrowed from other authors often functioned as allusions. Moreover, he had a phenomenal memory for texts and remembered details, "but [writes Najder] it was not a memory strictly categorized according to sources, marshalled into homogeneous entities; it was, rather, an enormous receptacle of images and pieces from which he would draw."[171] Continues Najder: "[H]e can never be accused of outright plagiarism. Even when lifting sentences and scenes, Conrad changed their character, inserted them within novel structures. He did not imitate, but (as Hervouet says) 'continued' his masters. He was right in saying: 'I don't resemble anybody.' Ian Watt put it succinctly: 'In a sense, Conrad is the least derivative of writers; he wrote very little that could possibly be mistaken for the work of anyone else.'[172] Conrad's acquaintance George Bernard Shaw says it well: "[A] man can no more be completely original [...] than a tree can grow out of air."[173] Conrad, like other artists, faced constraints arising from the need to propitiate his audience and confirm their own favourable self-regard. This may account for his describing the admirable crew of the Judea in his 1898 story "Youth" as "Liverpool hard cases", whereas the crew of the Judea's actual 1882 prototype, the Palestine, had included not a single Liverpudlian, and half the crew had been non-Britons;[174] and for Conrad's transforming the real-life 1880 criminally negligent British captain J. L. Clark, of the SS Jeddah, in his 1900 novel Lord Jim, into the captain of the fictitious Patna—"a sort of renegade New South Wales German" so monstrous in physical appearance as to suggest "a trained baby elephant".[175] Similarly, in his letters Conrad—during most of his literary career, struggling for sheer financial survival—often adjusted his views to the predilections of his correspondents.[176] Historians have also noted that Conrad's works which were set in European colonies and intended to critique the effects of colonialism were set in Dutch and Belgian colonies, instead of the British Empire.[177] The singularity of the universe depicted in Conrad's novels, especially compared to those of near-contemporaries like his friend and frequent benefactor John Galsworthy, is such as to open him to criticism similar to that later applied to Graham Greene.[178] But where "Greeneland" has been characterised as a recurring and recognisable atmosphere independent of setting, Conrad is at pains to create a sense of place, be it aboard ship or in a remote village; often he chose to have his characters play out their destinies in isolated or confined circumstances. In the view of Evelyn Waugh and Kingsley Amis, it was not until the first volumes of Anthony Powell's sequence, A Dance to the Music of Time, were published in the 1950s, that an English novelist achieved the same command of atmosphere and precision of language with consistency, a view supported by later critics like A. N. Wilson; Powell acknowledged his debt to Conrad. Leo Gurko, too, remarks, as "one of Conrad's special qualities, his abnormal awareness of place, an awareness magnified to almost a new dimension in art, an ecological dimension defining the relationship between earth and man."[179] T. E. Lawrence, one of many writers whom Conrad befriended, offered some perceptive observations about Conrad's writing:  T. E. Lawrence, whom Conrad befriended He's absolutely the most haunting thing in prose that ever was: I wish I knew how every paragraph he writes (...they are all paragraphs: he seldom writes a single sentence...) goes on sounding in waves, like the note of a tenor bell, after it stops. It's not built in the rhythm of ordinary prose, but on something existing only in his head, and as he can never say what it is he wants to say, all his things end in a kind of hunger, a suggestion of something he can't say or do or think. So his books always look bigger than they are. He's as much a giant of the subjective as Kipling is of the objective. Do they hate one another?[180] The Irish novelist-poet-critic Colm Tóibín captures something similar: Joseph Conrad's heroes were often alone, and close to hostility and danger. Sometimes, when Conrad's imagination was at its most fertile and his command of English at its most precise, the danger came darkly from within the self. At other times, however, it came from what could not be named. Conrad sought then to evoke rather than delineate, using something close to the language of prayer. While his imagination was content at times with the tiny, vivid, perfectly observed detail, it was also nourished by the need to suggest and symbolize. Like a poet, he often left the space in between strangely, alluringly vacant. His own vague terms—words like "ineffable", "infinite", "mysterious", "unknowable"—were as close as he could come to a sense of our fate in the world or the essence of the universe, a sense that reached beyond the time he described and beyond his characters' circumstances. This idea of "beyond" satisfied something in his imagination. He worked as though between the intricate systems of a ship and the vague horizon of a vast sea. This irreconcilable distance between what was precise and what was shimmering made him much more than a novelist of adventure, a chronicler of the issues that haunted his time, or a writer who dramatized moral questions. This left him open to interpretation—and indeed to attack [by critics such as the novelists V.S. Naipaul and Chinua Achebe].[12] In a letter of 14 December 1897 to his Scottish friend, Robert Bontine Cunninghame Graham, Conrad wrote that science tells us, "Understand that thou art nothing, less than a shadow, more insignificant than a drop of water in the ocean, more fleeting than the illusion of a dream."[181]  Conrad's friend Cunninghame Graham In a letter of 20 December 1897 to Cunninghame Graham, Conrad metaphorically described the universe as a huge machine: It evolved itself (I am severely scientific) out of a chaos of scraps of iron and behold!—it knits. I am horrified at the horrible work and stand appalled. I feel it ought to embroider—but it goes on knitting. You come and say: "this is all right; it's only a question of the right kind of oil. Let us use this—for instance—celestial oil and the machine shall embroider a most beautiful design in purple and gold." Will it? Alas no. You cannot by any special lubrication make embroidery with a knitting machine. And the most withering thought is that the infamous thing has made itself; made itself without thought, without conscience, without foresight, without eyes, without heart. It is a tragic accident—and it has happened. You can't interfere with it. The last drop of bitterness is in the suspicion that you can't even smash it. In virtue of that truth one and immortal which lurks in the force that made it spring into existence it is what it is—and it is indestructible! It knits us in and it knits us out. It has knitted time space, pain, death, corruption, despair and all the illusions—and nothing matters.[181] Conrad wrote Cunninghame Graham on 31 January 1898: Faith is a myth and beliefs shift like mists on the shore; thoughts vanish; words, once pronounced, die; and the memory of yesterday is as shadowy as the hope of to-morrow.... In this world—as I have known it—we are made to suffer without the shadow of a reason, of a cause or of guilt.... There is no morality, no knowledge and no hope; there is only the consciousness of ourselves which drives us about a world that... is always but a vain and fleeting appearance.... A moment, a twinkling of an eye and nothing remains—but a clod of mud, of cold mud, of dead mud cast into black space, rolling around an extinguished sun. Nothing. Neither thought, nor sound, nor soul. Nothing.[7] Leo Robson suggests that What [Conrad] really learned as a sailor was not something empirical—an assembly of "places and events"—but the vindication of a perspective he had developed in childhood, an impartial, unillusioned view of the world as a place of mystery and contingency, horror and splendor, where, as he put it in a letter to the London Times, the only indisputable truth is "our ignorance."[182] According to Robson, [Conrad's] treatment of knowledge as contingent and provisional commands a range of comparisons, from Rashomon to [the views of philosopher] Richard Rorty; reference points for Conrad's fragmentary method [of presenting information about characters and events] include Picasso and T.S. Eliot—who took the epigraph of "The Hollow Men" from Heart of Darkness.... Even Henry James's late period, that other harbinger of the modernist novel, had not yet begun when Conrad invented Marlow, and James's earlier experiments in perspective (The Spoils of Poynton, What Maisie Knew) don't go nearly as far as Lord Jim.[8] Language  Caricature of Conrad by David Low, 1923 Conrad spoke his native Polish and the French language fluently from childhood and only acquired English in his twenties. He would probably have spoken some Ukrainian as a child; he certainly had to have some knowledge of German and Russian.[183][184] His son Borys records that, though Conrad had insisted that he spoke only a few words of German, when they reached the Austrian frontier in the family's attempt to leave Poland in 1914, Conrad spoke German "at considerable length and extreme fluency".[185] Russia, Prussia, and Austria had divided up Poland among them, and he was officially a Russian subject until his naturalization as a British subject.[186] As a result, up to this point, his official documents were in Russian.[183] His knowledge of Russian was good enough that his uncle Tadeusz Bobrowski wrote him (22 May 1893) advising that, when Conrad came to visit, he should "telegraph for horses, but in Russian, for Oratów doesn't receive or accept messages in an 'alien' language."[187] Conrad chose, however, to write his fiction in English. He says in his preface to A Personal Record that writing in English was for him "natural", and that the idea of his having made a deliberate choice between English and French, as some had suggested, was in error. He explained that, though he had been familiar with French from childhood, "I would have been afraid to attempt expression in a language so perfectly 'crystallized'."[188] In 1915, as Jo Davidson sculpted his bust, Conrad answered his question: "Ah… to write French you have to know it. English is so plastic—if you haven't got a word you need you can make it, but to write French you have to be an artist like Anatole France."[189] These statements, as so often in Conrad's "autobiographical" writings, are subtly disingenuous.[190] In 1897 Conrad was visited by a fellow Pole, the philosopher Wincenty Lutosławski, who asked Conrad, "Why don't you write in Polish?" Lutosławski recalled Conrad explaining: "I value our beautiful Polish literature too much to bring into it my clumsy efforts. But for the English my gifts are sufficient and secure my daily bread."[191] Conrad wrote in A Personal Record that English was "the speech of my secret choice, of my future, of long friendships, of the deepest affections, of hours of toil and hours of ease, and of solitary hours, too, of books read, of thoughts pursued, of remembered emotions—of my very dreams!"[192] In 1878 Conrad's four-year experience in the French merchant marine had been cut short when the French discovered he did not have a permit from the Imperial Russian consul to sail with the French.[note 34] This, and some typically disastrous Conradian investments, had left him destitute and had precipitated a suicide attempt. With the concurrence of his mentor-uncle Tadeusz Bobrowski, who had been summoned to Marseilles, Conrad decided to seek employment with the British merchant marine, which did not require Russia's permission.[193] Thus began Conrad's sixteen years' seafarer's acquaintance with the British and with the English language. Had Conrad remained in the Francophone sphere or had he returned to Poland, the son of the Polish poet, playwright, and translator Apollo Korzeniowski—from childhood exposed to Polish and foreign literature, and ambitious to himself become a writer[38]—he might have ended up writing in French or Polish instead of English. Certainly his Uncle Tadeusz thought Conrad might write in Polish; in an 1881 letter he advised his 23-year-old nephew: As, thank God, you do not forget your Polish... and your writing is not bad, I repeat what I have... written and said before—you would do well to write... for Wędrowiec [The Wanderer] in Warsaw. We have few travelers, and even fewer genuine correspondents: the words of an eyewitness would be of great interest and in time would bring you... money. It would be an exercise in your native tongue—that thread which binds you to your country and countrymen—and finally a tribute to the memory of your father who always wanted to and did serve his country by his pen.[194] In the opinion of some biographers, Conrad's third language, English, remained under the influence of his first two languages—Polish and French. This makes his English seem unusual. Najder writes that: [H]e was a man of three cultures: Polish, French, and English. Brought up in a Polish family and cultural environment... he learned French as a child, and at the age of less than seventeen went to France, to serve... four years in the French merchant marine. At school he must have learned German, but French remained the language he spoke with greatest fluency (and no foreign accent) until the end of his life. He was well versed in French history and literature, and French novelists were his artistic models. But he wrote all his books in English—the tongue he started to learn at the age of twenty. He was thus an English writer who grew up in other linguistic and cultural environments. His work can be seen as located in the borderland of auto-translation.[6] Inevitably for a trilingual Polish–French–English-speaker, Conrad's writings occasionally show linguistic spillover: "Franglais" or "Poglish"—the inadvertent use of French or Polish vocabulary, grammar, or syntax in his English writings. In one instance, Najder used "several slips in vocabulary, typical for Conrad (Gallicisms) and grammar (usually Polonisms)" as part of internal evidence against Conrad's sometime literary collaborator Ford Madox Ford's claim to have written a certain instalment of Conrad's novel Nostromo, for publication in T. P.'s Weekly, on behalf of an ill Conrad.[195] The impracticality of working with a language which has long ceased to be one's principal language of daily use is illustrated by Conrad's 1921 attempt at translating into English the Polish physicist, columnist, story-writer, and comedy-writer Bruno Winawer's short play, The Book of Job. Najder writes: [T]he [play's] language is easy, colloquial, slightly individualized. Particularly Herup and a snobbish Jew, "Bolo" Bendziner, have their characteristic ways of speaking. Conrad, who had had little contact with everyday spoken Polish, simplified the dialogue, left out Herup's scientific expressions, and missed many amusing nuances. The action in the original is quite clearly set in contemporary Warsaw, somewhere between elegant society and the demimonde; this specific cultural setting is lost in the translation. Conrad left out many accents of topical satire in the presentation of the dramatis personae and ignored not only the ungrammatical speech (which might have escaped him) of some characters but even the Jewishness of two of them, Bolo and Mosan.[196] As a practical matter, by the time Conrad set about writing fiction, he had little choice but to write in English.[note 35] Poles who accused Conrad of cultural apostasy because he wrote in English instead of Polish[198] missed the point—as do Anglophones who see, in Conrad's default choice of English as his artistic medium, a testimonial to some sort of innate superiority of the English language.[note 36] According to Conrad's close friend and literary assistant Richard Curle, the fact of Conrad writing in English was "obviously misleading" because Conrad "is no more completely English in his art than he is in his nationality".[201] Conrad, according to Curle, "could never have written in any other language save the English language....for he would have been dumb in any other language but the English."[202] Conrad always retained a strong emotional attachment to his native language. He asked his visiting Polish niece Karola Zagórska, "Will you forgive me that my sons don't speak Polish?"[55] In June 1924, shortly before his death, he apparently expressed a desire that his son John marry a Polish girl and learn Polish, and toyed with the idea of returning for good to now independent Poland.[203] Conrad bridled at being referred to as a Russian or "Slavonic" writer. The only Russian writer he admired was Ivan Turgenev.[170] "The critics", he wrote an acquaintance on 31 January 1924, six months before his death, "detected in me a new note and as, just when I began to write, they had discovered the existence of Russian authors, they stuck that label on me under the name of Slavonism. What I venture to say is that it would have been more just to charge me at most with Polonism."[204] However, though Conrad protested that Dostoyevsky was "too Russian for me" and that Russian literature generally was "repugnant to me hereditarily and individually",[205] Under Western Eyes is viewed as Conrad's response to the themes explored in Dostoyevsky's Crime and Punishment.[206] Conrad had an awareness that, in any language, individual expressions – words, phrases, sentences – are fraught with connotations. He once wrote: "No English word has clean edges." All expressions, he thought, carried so many connotations as to be little more than "instruments for exciting blurred emotions."[207] This might help elucidate the impressionistic quality of many passages in his writings. It also explains why he chose to write his literary works not in Polish or French but in English, with which for decades he had had the greatest contact. Controversy In 1975 the Nigerian writer Chinua Achebe published an essay, "An Image of Africa: Racism in Conrad's 'Heart of Darkness'", which provoked controversy by calling Conrad a "thoroughgoing racist". Achebe's view was that Heart of Darkness cannot be considered a great work of art because it is "a novel which celebrates... dehumanisation, which depersonalises a portion of the human race." Referring to Conrad as a "talented, tormented man", Achebe notes that Conrad (via the protagonist, Charles Marlow) reduces and degrades Africans to "limbs", "ankles", "glistening white eyeballs", etc., while simultaneously (and fearfully) suspecting a common kinship between himself and these natives—leading Marlow to sneer the word "ugly."[208] Achebe also cited Conrad's description of an encounter with an African: "A certain enormous buck nigger encountered in Haiti fixed my conception of blind, furious, unreasoning rage, as manifested in the human animal to the end of my days."[209] Achebe's essay, a landmark in postcolonial discourse, provoked debate, and the questions it raised have been addressed in most subsequent literary criticism of Conrad.[210][211][212] Achebe's critics argue that he fails to distinguish Marlow's view from Conrad's, which results in very clumsy interpretations of the novella.[213] In their view, Conrad portrays Africans sympathetically and their plight tragically, and refers sarcastically to, and condemns outright, the supposedly noble aims of European colonists, thereby demonstrating his skepticism about the moral superiority of white men.[214] Ending a passage that describes the condition of chained, emaciated slaves, the novelist remarks: "After all, I also was a part of the great cause of these high and just proceedings." Some observers assert that Conrad, whose native country had been conquered by imperial powers, empathised by default with other subjugated peoples.[215] Jeffrey Meyers notes that Conrad, like his acquaintance Roger Casement, "was one of the first men to question the Western notion of progress, a dominant idea in Europe from the Renaissance to the Great War, to attack the hypocritical justification of colonialism and to reveal... the savage degradation of the white man in Africa."[216] Likewise, E.D. Morel, who led international opposition to King Leopold II's rule in the Congo, saw Conrad's Heart of Darkness as a condemnation of colonial brutality and referred to the novella as "the most powerful thing written on the subject."[217] More recently, Nidesh Lawtoo complicated the race debate by showing that Conrad's images of "frenzy" depict rituals of "possession trance" that are equally central to Achebe's Things Fall Apart.[218] Conrad scholar Peter Firchow writes that "nowhere in the novel does Conrad or any of his narrators, personified or otherwise, claim superiority on the part of Europeans on the grounds of alleged genetic or biological difference." If Conrad or his novel is racist, it is only in a weak sense, since Heart of Darkness acknowledges racial distinctions "but does not suggest an essential superiority" of any group.[219][220] Achebe's reading of Heart of Darkness can be (and has been) challenged by a reading of Conrad's other African story, "An Outpost of Progress", which has an omniscient narrator, rather than the embodied narrator, Marlow. Some younger scholars, such as Masood Ashraf Raja, have also suggested that if we read Conrad beyond Heart of Darkness, especially his Malay novels, racism can be further complicated by foregrounding Conrad's positive representation of Muslims.[221] In 1998 H.S. Zins wrote in Pula: Botswana Journal of African Studies: Conrad made English literature more mature and reflective because he called attention to the sheer horror of political realities overlooked by English citizens and politicians. The case of Poland, his oppressed homeland, was one such issue. The colonial exploitation of Africans was another. His condemnation of imperialism and colonialism, combined with sympathy for its persecuted and suffering victims, was drawn from his Polish background, his own personal sufferings, and the experience of a persecuted people living under foreign occupation. Personal memories created in him a great sensitivity for human degradation and a sense of moral responsibility."[17] Adam Hochschild makes a similar point: What gave [Conrad] such a rare ability to see the arrogance and theft at the heart of imperialism?... Much of it surely had to do with the fact that he himself, as a Pole, knew what it was like to live in conquered territory.... [F]or the first few years of his life, tens of millions of peasants in the Russian empire were the equivalent of slave laborers: serfs. Conrad's poet father, Apollo Korzeniowski, was a Polish nationalist and an opponent of serfdom... [The] boy [Konrad] grew up among exiled prison veterans, talk of serfdom, and the news of relatives killed in uprisings [and he] was ready to distrust imperial conquerors who claimed they had the right to rule other peoples.[222] Conrad's experience in the Belgian-run Congo made him one of the fiercest critics of the "white man's mission." It was also, writes Najder, Conrad's most daring and last "attempt to become a homo socialis, a cog in the mechanism of society. By accepting the job in the trading company, he joined, for once in his life, an organized, large-scale group activity on land. [...] It is not accidental that the Congo expedition remained an isolated event in Conrad's life. Until his death he remained a recluse in the social sense and never became involved with any institution or clearly defined group of people."[223] |
文体 テーマと文体 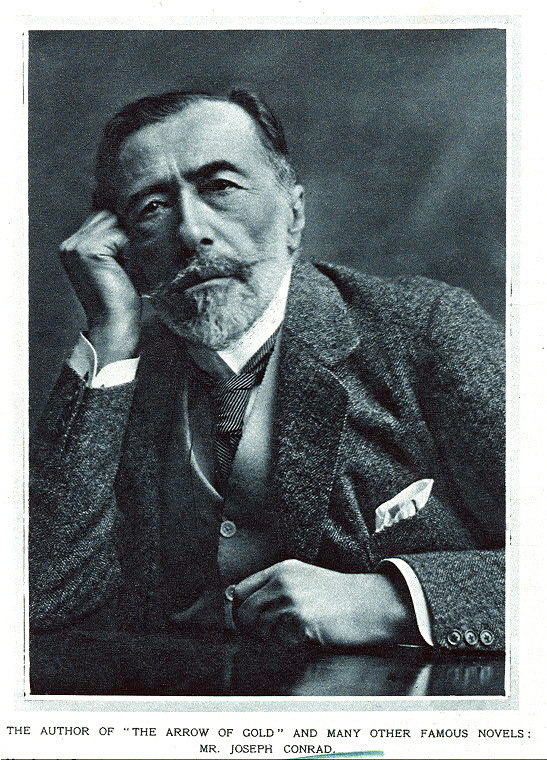 ジョセフ・コンラッド、1919年以降 小説家仲間のヘンリー・ジェイムズ[120]など、コンラッドを個人的に知っていた人々の意見にもかかわらず、コンラッドは、叔父や知人に宛てた優雅な手 紙を書くときでさえも、書く船乗りというよりはむしろ、船乗りの作家であった。彼は多くの作品の背景として航海体験を用いたが、航海をモチーフにしない似 たような世界観の作品も生み出した。このことを多くの批評家が評価しなかったことは、彼に大きな不満を抱かせた[121]。 彼はイギリスの陸地での生活よりも、海や異国の地での生活について書くことが多かったが、それは例えば『フォーサイト・サーガ』の作者である友人ジョン・ ガルスワージーとは異なり、イギリスの日常的な家庭関係についてほとんど知らなかったからである。コンラッドの『海の鏡』が1906年に出版され、批評家 の絶賛を浴びたとき、彼はフランス語の翻訳者にこう書き送っている: 「批評家たちは盛んに私に香炉を振っている......。お世辞のコンサートの背後で、ささやきのようなものが聞こえてくる!大海原にとどまれ!上陸する な!』と。彼らは私を大洋の真ん中に追放しようとしている」[67]。コンラッドは友人リチャード・カールに宛てた手紙の中で、作家がどのように「特殊な ものから一般的なものへと素材を変化させ、個人的な経験の気質的な扱いによって普遍的な感情に訴えかける」のかに気づかず、彼の「海の生活」のような「外 見に大衆の心は固執する」と述べている[122]。 それにもかかわらず、コンラッドは、特にアメリカにおいて、多くの共感的読者を見つけた。H.L.メンケンは、コンラッドがいかに「特殊なものから一般的 なもの」を想起させるかを認識した、最も初期の、そして最も影響力のあるアメリカ人読者の一人であった。F・スコット・フィッツジェラルドはメンケンに宛 てた手紙の中で、コンラッドの模倣者リストから漏れたことに不満を述べている。フィッツジェラルド以降、ウィリアム・フォークナー、ウィリアム・バロウ ズ、ソール・ベロー、フィリップ・ロス、ジョーン・ディディオン、トマス・ピンチョンなど、何十人ものアメリカ人作家がコンラッドへの恩義を認めている [123]。 1923年10月、当時コンラッドの自宅であったオズワルドを訪れた訪問者(マーク・トウェインの従兄弟であるシリル・クレメンス)は、コンラッドの言葉 を引用してこう述べている: 「私が書いたものすべてには、常にひとつの不変の意図があり、それは読者の注意を引くことである」[124]。 芸術家としてのコンラッドは、『ナルキッソスのニガー』(1897年)の序文にあるように、「書かれた言葉の力によって、読者に聞かせ、感じさ せ......何よりもまず、見させる」ことを目指していた。それだけがすべてだ。励まし、慰め、恐れ、魅力、あなたが求めるものすべて、そしておそら く、あなたが求めることを忘れていた真実の片鱗も、」[125]。 視覚芸術にとっては印象派の時代であり、音楽にとっては印象派音楽の時代であったこの時代に執筆したコンラッドは、その作品の多くで最高級の散文詩人であ ることを示している: 例えば、『ロード・ジム』のパトナや法廷の情景、『闇の奥』の「憂鬱な狂気の象」[注 26]や「大陸に向かって発砲するフランスの砲艦」の情景、『秘密の共有者』の二重の主人公たち、『ノストロモ』や『ナルキッソス号のニガー』の言葉と概 念の共鳴などである。 コンラッドは自身の記憶を文学の素材として頻繁に用いているため、読者は彼の人生と作品をひとつの全体として扱いたくなる。彼の「世界観」、あるいはその 要素は、しばしば彼の私的な発言と公的な発言、手紙の一節、著書からの引用を一度に引用することによって説明される。ナジダーは、このようなアプローチは 支離滅裂で誤解を招くと警告している。「文学と私生活という二つの領域を無批判に結びつけると、それぞれが歪んでしまう。コンラッドは彼自身の経験を原料 として使ったが、完成品は経験そのものと混同されるべきではない」[126]。 コンラッドの登場人物の多くは、彼が実際に出会った人物から着想を得たものであり、最初の小説『アルマイヤーの愚行』(1894年完成)では、ウィリア ム・チャールズ・オルメイジャー(William Charles Olmeijer)が登場するが、その姓の綴りはコンラッドがおそらく不注意で「Almayer」に変えてしまったものであった[127]、 例えば、マクウィアー大尉[注釈 27](『タイフーン』)、ベアード大尉とマホン氏(『青春』)、リンガード大尉(『アルマイヤーの愚行』ほか)、エリス大尉(『影の線』)などである。 「コンラッドは」、「このような現実との結びつきに、何か神秘的な意味を持たせているように見える」[130]とJ. I. M. スチュワートは書いている[131]。 コンラッド自身の体験とは別に、彼の小説に登場する多くのエピソードは、過去または現代の公知の出来事や文学作品によって示唆されている。1900年の小 説『ロード・ジム』の前半部(パトナのエピソード)は、1880年に実際に起こったSSジェッダ号の物語に触発されたものであり[134]、後半部は、サ ラワクの初代ホワイト・ラジャであったジェームズ・ブルックの生涯にある程度触発されたものである[135]。 [1901年の短編「エイミー・フォスター」は、フォード・マドックス・フォードの『サンク・ポーツ』(1900年)に出てくる逸話にインスパイアされた もので、ドイツ商船から難破した船員が、英語が通じず、地元の田舎町の人々に追い払われ、最終的に豚小屋に身を寄せたというものである[136][注釈 28]。 ノストロモ』(1904年完成)では、大量の銀貨の窃盗がメキシコ湾で聞いた話によってコンラッドに示唆され、後に「古本屋の外で拾った一冊の本」で読ん だ[138] [注 29] マヤ・ジャサノフによれば、この小説の政治的な筋はパナマ運河の創設に関連している。「1903年1月、コンラッドが『ノストロモ』を書き始めたちょうど そのとき、アメリカとコロンビアの国務長官が、運河を挟む6マイルの土地をアメリカが100年間リースする条約に調印した。新聞がコロンビアの革命につい てつぶやく一方で、コンラッドは南米の架空の国、コスタグアナの反体制を示唆する『ノストロモ』の新しいセクションを開いた。彼はコスタグアナの架空の港 スラコで、パナマで起こっている現実の分離独立運動を反映した革命を企てた。コンラッドが1904年9月1日に小説を書き終えたとき、「彼はスラコをパナ マの状態に置き去りにした」とジャサノフは書いている。パナマがアメリカによって即座に独立を認められ、運河へのアメリカの投資によって経済が強化された ように、スラコもアメリカによって即座に独立を認められ、(架空の)サン・トメ(銀)鉱山への投資によって経済が下支えされた」[140]。 The Secret Agent』(1906年完成)は、フランスのアナキスト、マルシャル・ブルダンがグリニッジ天文台を爆破しようとして1894年に死亡した事件から着想 を得た[141]。コンラッドの物語『The Secret Sharer』(1909年完成)は、1880年にカティ・サーク号の一等航海士シドニー・スミスが船長を助けて船員を殺害し逃亡した事件から着想を得 た。 [142]『Under Western Eyes』(1910年完成)のプロットは、1904年に実際に起きたロシア内務大臣ヴャチェスラフ・フォン・プレヴェの暗殺をモデルにした、残忍なロシ ア政府大臣の暗殺によって幕を開ける[143]。 コンラッドが生き生きと描いた公海、マレー諸島、南米の自然環境については、彼自身の観察に頼ることができた。彼の短い上陸では得られなかったのは、異国 の文化を徹底的に理解することであった。そのために彼は、他の作家と同様、文学的資料に頼った。マレー小説を書く際には、アルフレッド・ラッセル・ウォレ スの『マレー群島』(1869年)、ジェームズ・ブルックの日記、『ペラックとマレー人』、『マレー海域での私の日記』、『極東の森林での生活』といった タイトルの本を参考にした。南米の架空の国コスタグアナを舞台にした小説『ノストロモ』の執筆に取りかかったとき、彼は『ペルーとチリの戦争』、エドワー ド・イーストウィック『ベネズエラ:あるいは南米共和国の生活スケッチ』(1868年)、ジョージ・フレデリック・マスターマン『パラグアイの七年』 (1869年)などを参考にした[145] [注釈 30] 文献に頼った結果、『ロード・ジム』ではJ. コンラッドは、『ロード・ジム』において、J. I. M. Stewartが書いているように、「中古品からある程度仕事をする必要性」によって、「ジムとパトゥーサンの...人々との...関係におけるある種の 薄さ」[147]がもたらされた。 コンラッドはその猜疑心[149][7]と憂鬱さ[150]に沿って、主要な小説や物語の登場人物にほとんど必ずと言っていいほど致命的な運命を与えてい る。アルマイヤー(『アルマイヤーの愚行』1894年)は最愛の娘に捨てられ、アヘンに手を出して死ぬ[151]。 ピーター・ウィレムス(『島の追放者』1895年)は嫉妬深い恋人アイッサに殺される[152]。 [152] 無能な 「ニガー」、ジェイムズ・ウェイト(『ナルシス号のニガー』、1897年)は、船上で死に、海に埋葬される。 153] カーツ氏(『闇の奥』、1899年)は、「恐ろしい!トゥアン・ジム(『ロード・ジム』、1900年)は、うっかりして自分の養子である共同体の大虐殺を 引き起こしてしまったが、共同体のリーダーの手によって意図的に歩いて死ぬ。 [154] コンラッドの1901年の短編『エイミー・フォスター』では、イギリスに移植されたポーランド人のヤンコ・ゴオラル(ポーランド語のヤンコ・ゴオラル、 「ジョニー・ハイランダー」の英語訳)が病に倒れ、熱に苦しみながら母国語でわめき散らし、妻のエイミーを怖がらせて逃げ出す。翌朝、ヤンコは心不全で死 亡し、ポーランド語で水を求めていただけだったことが判明する。 [注31] キャプテン・ウォーリー(『綱渡りの果て』、1902年)は、視力の衰えと不誠実なパートナーに裏切られ、自ら溺死する[156] ジャン・バッティスタ・フィダンツァ[注32]は、小説『ノストロモ』(1904年)の主人公で、尊敬すべきイタリア移民のノストロモ(イタリア語で「我 らの男」)は、南米の「コスタグアナ」という国で採掘された銀の財宝を不正に入手し、人違いで射殺される。 [157] 忠誠心が分裂している『秘密諜報員』(1906)のヴァーロック氏は、テロリストのせいにされる爆弾テロを企て、誤って精神的に欠陥のある義理の弟ス ティービーを殺してしまう。 [158]『チャンス』(1913)では、帆船の船長でフローラ・デ・バラルの夫であり恩人であるロデリック・アンソニーが、嫉妬深い失脚した金融業者の 父親による毒殺未遂の標的になり、発見されたアンソニー船長は自ら毒を飲み込んで死亡する(数年後、アンソニー船長は海で溺死する)。 [159]『勝利』(1915年)では、レナはジョーンズに射殺されるが、ジョーンズは共犯者のリカルドを殺すつもりで、後にそれに成功する。 コンラッドの主要な登場人物が命からがら逃げ延びたとしても、あまりうまくいかないこともある。UnderWesternEyes』(1911)では、ラ ズモフはサンクトペテルブルク大学の学生仲間で、野蛮な弾圧を加えるロシア政府の大臣を暗殺した革命家ヴィクトル・ハルディンを裏切る。ハルディンは拷問 を受け、当局によって絞首刑に処される。その後、政府のスパイとして反ツァーリストの中心地ジュネーブに派遣されたラズモフは、ハルディンの母と妹に出会 う。ラズモフは妹と恋に落ち、彼女の兄への裏切りを告白する。後日、彼は集まった革命家たちに同じ告白をするが、プロの処刑人に鼓膜を破裂させられ、一生 耳が聞こえなくなる。ラズモフはよろめきながら立ち去り、路面電車に倒され、最後は廃人となってロシアに戻る[161]。 コンラッドは、世界と自分の作品における悲劇を強く意識していた。1898年、作家としてのキャリアをスタートさせたとき、彼はスコットランドの作家・政 治家の友人カニングヘイム・グラハムにこう書き送っている。[人間が悲劇的であるのは、彼らが自然の犠牲者であることではなく、それを自覚しているからで ある。しかし1922年、彼の生涯とキャリアの終わりに近づいたとき、もう一人のスコットランド人の友人、リチャード・カールがコンラッドについて書いた 二つの記事の校正刷りをコンラッドに送ったところ、コンラッドは陰鬱で悲劇的な作家と評されることに異議を唱えた。「その評判は...私から無数の読者を 奪った。悲劇作家と呼ばれることには絶対に反対だ」[162]。 コンラッドは「日記をつけたこともなければ、ノートを所有したこともない」と主張した。コンラッドの死後、リチャード・カールはコンラッドのコンゴでの体 験を綴った日記を大幅に修正したものを出版した[164]。 [165]最初の正確な書き起こしは1995年のロバート・ハンプソンのペンギン版『闇の奥』で出版され、ハンプソンの書き起こしと注釈は2007年のペ ンギン版で再版された[166][167]。 進行中の作品について語らないことを旨とする多くの作家とは異なり、コンラッドはしばしば現在の作品について語り、エドワード・ガーネットのような選りすぐりの友人や作家仲間にもそれを見せ、彼らの批評や提案に照らして修正することもあった[168]。 エドワード・サイードは、コンラッドが友人や作家仲間と交わした書簡の膨大な量に驚かされた。サイードはこう語っている: 「コンラッドが自分自身について、自己定義の問題について、これほど持続的な緊急性をもって書いたのであれば、彼が書いたことのいくつかは彼の小説にとっ て意味があったに違いないと私には思えた。[手紙に次ぐ手紙に自分自身を注ぎ込みながら、その洞察や発見を小説に生かしたり再定義したりしないほど不経済 な人間がいるとは考えにくかった」。サイードは、コンラッドの手紙と彼の短編小説との間に、特に密接な類似点を見出した。「コンラッドは......芸術 的な区別は、長い作品よりもむしろ短い作品においてより明確に示されると信じていた......。コンラッドは......芸術的区別は長い作品よりもむ しろ短い作品においてこそ、より雄弁に示されると信じていた......: コンラッドはほとんど全生涯を通じてアウトサイダーであり、自分自身がアウトサイダーであると感じていた。亡命中のアウトサイダー、ウクライナの家族のも とを訪れていたときのアウトサイダー、[クラクフ]とルヴフでの体験と死別によるアウトサイダー、マルセイユでのアウトサイダー、国民的にも文化的にもイ ギリスの船に乗っていたアウトサイダー、イギリス人作家としてのアウトサイダー......。コンラッドは自らを(グラハムに対して)「血まみれの外国人 」と呼んだ。同時に [コンラッドは同時に......「国民精神」を共同生活の唯一の真に永続的で信頼できる要素とみなしていた[170]。 コンラッドはポーランド語やフランス語の他の作家の作品を借用し、時には盗作を免れなかった。1931年に彼の1915年の小説『勝利』のポーランド語訳 が出版されたとき、読者はステファン・ジェロムスキーのキッチュな小説『罪の歴史』(Dzieje grzechu, 1908)との顕著な類似点を指摘した。比較文学者のイヴ・エルヴュエは、『勝利』のテキストに、影響、借用、類似、引用のモザイクがあることを示した。 彼はさらに、『アルマイヤーの愚行』(1895)から未完の『サスペンス』まで、コンラッドのほぼすべての作品において、他の、主にフランスの作家からの 具体的な借用を何百も挙げている。コンラッドは、著名な作家のテクストを、彼自身の記憶の内容と同種の素材として使っていたようだ。他の作家から借用した 資料は、しばしば引用として機能した。さらに、彼はテクストに対して驚異的な記憶力を持っており、細部まで記憶していた。「しかし(ナジャデルは)それは 出典に従って厳密に分類された記憶ではなく、均質な実体に集められる記憶でもなく、むしろ、彼がそこから引き出すイメージや断片の巨大な容れ物であった」 [171]。 ナジダーは続ける: 「彼は決して完全な盗作だと非難されることはない。文章や場面を引用する場合でも、コンラッドはその性格を変え、斬新な構造の中に挿入した。彼は真似をし たのではなく、(エルヴュエが言うように)師匠を『継続』したのだ。私は誰にも似ていない」という彼の言葉は正しかった。イアン・ワットは簡潔にこう言っ た: ある意味で、コンラッドは作家の中で最も派生性の少ない作家であり、他の誰かの作品と間違われるようなものはほとんど書いていない」[172] コンラッドの知人であるジョージ・バーナード・ショーはこう言っている: 「人間は、木が空気から成長するのと同じように、完全に独創的であることはできない」[173]。 コンラッドは、他の芸術家たちと同様に、聴衆をなだめ、彼らの好意的な自己評価を確認する必要性から生じる制約に直面していた。このことは、彼が1898 年の物語『青春』の中で、ジュデア号の立派な乗組員を「リバプールの堅物」と表現しているのに対し、ジュデア号の実際の1882年の原型であるパレスチナ 号の乗組員にはリバプール人は一人も含まれておらず、乗組員の半数は非英国人であったこと[174]や、コンラッドが1880年に実在した犯罪的過失のあ るイギリス人船長J. また、コンラッドが1900年の小説『ロード・ジム』において、SSジェッダ号のJ.L.クラークという実在の犯罪的過失のあるイギリス人船長を、架空の パトナ号の船長-「一種の反逆的なニューサウスウェールズ系ドイツ人」であり、その外見は「訓練された子象」を思わせるほど怪物的であった-に変身させた ことについても言及した[175]。 [また歴史家は、ヨーロッパの植民地を舞台とし、植民地主義の影響を批判することを意図したコンラッドの作品が、大英帝国ではなくオランダやベルギーの植 民地を舞台としていたことを指摘している[177]。 コンラッドの小説に描かれる宇宙の特異性は、特に、彼の友人であり、しばしば彼の恩人であったジョン・ガルスワージーのような同時代の作家の作品と比較す ると、後にグレアム・グリーンに適用される批判と同様の批判をコンラッドに浴びせるようなものである[178]。しかし、「グリーンランド」が設定とは無 関係に繰り返され、認識可能な雰囲気として特徴づけられてきたのに対し、コンラッドは、船上であれ、辺境の村であれ、場所の感覚を作り出すことに苦心して おり、しばしば彼は、登場人物に孤立した、あるいは限定された状況で運命を演じさせることを選んだ。エヴリン・ウォーやキングスレー・エイミスの見解によ れば、アンソニー・パウエルの一連の作品『時の音楽への踊り』の第1巻が1950年代に出版されるまで、イギリスの小説家が一貫性をもって同じような雰囲 気の支配と言葉の正確さを達成することはなかった。レオ・グルコもまた、「コンラッドの特別な資質のひとつは、彼の場所に対する異常な意識であり、その意 識は芸術においてほとんど新しい次元にまで拡大され、地球と人間の関係を定義する生態学的な次元にまで拡大された」と述べている[179]。 T. コンラッドが親しくしていた多くの作家の一人であるT.E.ロレンスは、コンラッドの文章について鋭い見解を述べている:  T. T・E・ロレンスはコンラッドと親交があった。 コンラッドと親交のあったT・E・ロレンスは、コンラッドの文章について次のような鋭い見解を述べている: 彼が書くすべての段落(...すべて段落である:彼は単文を書くことはめったにない...)が、それが止まった後も、テノールの鐘の音のように、波打つよ うに鳴り続けることを私は知りたい。普通の散文のリズムではなく、彼の頭の中にだけ存在する何かによって構築されている。だから彼の本はいつも実際よりも 大きく見える。彼は、キップリングが客観的な巨人であるのと同じくらい、主観的な巨人なのだ。二人は憎み合っているのだろうか[180]。 アイルランドの小説家・詩人・批評家であるコルム・トイビンは、似たようなことを捉えている: ジョセフ・コンラッドの英雄はしばしば孤独であり、敵意や危険と隣り合わせだった。時には、コンラッドの想像力が最も豊かで、彼の英語力が最も正確であっ たとき、危険は自己の内部から暗く迫ってきた。しかし他の時には、それは名づけることのできないものからやってきた。そのときコンラッドは、祈りの言葉に 近いものを使って、描写するよりも喚起することを求めた。彼のイマジネーションは、時には生き生きとした、完璧に観察された小さなディテールに満足するこ ともあったが、示唆し象徴化する必要性によっても養われた。詩人のように、彼はしばしばその間を奇妙に、魅力的に空けた。 彼自身の漠然とした言葉、「言葉にできない」、「無限」、「神秘的」、「不可知」などは、彼が描いた時間を超え、登場人物の境遇を超えた感覚、世界におけ る私たちの運命や宇宙の本質に限りなく近いものだった。この「彼方」という考えは、彼の想像力の中の何かを満足させた。彼はまるで、船の複雑なシステムと 広大な海の漠然とした地平線の間で働いているかのようだった。 正確なものと揺らめくものとの間のこの両立しがたい距離が、彼を冒険小説家、同時代につきまとう問題の記録者、あるいは道徳的な問題を劇化する作家以上の 存在にしていた。そのため、彼は解釈の余地があり、実際に[小説家のV.S.ナイポールやチヌア・アチェベなどの批評家による]攻撃の対象となっていた [12]。 1897年12月14日のスコットランドの友人であるロバート・ボンタイン・カニングヘイム・グラハムへの手紙の中で、コンラッドは科学が「汝は無であ り、影にすぎず、大海の一滴の水よりも取るに足らず、夢の幻影よりもはかない存在であることを理解せよ」と告げていると書いている[181]。  コンラッドの友人カニングヘイム・グラハム 1897年12月20日のカニングヘイム・グラハム宛の手紙の中で、コンラッドは宇宙を巨大な機械に喩えている: コンラッドは宇宙を巨大な機械に喩えた。(私はひどく科学的である)宇宙は鉄の切れ端のカオスから進化したのだ。私はその恐ろしい仕事におののき、呆然と 立ち尽くす。刺繍をすべきなのに、編み続けている。あなたが来て言う: 「油の種類が問題なだけだ。例えば、この天空のオイルを使えば、ミシンは紫と金でとても美しいデザインを刺繍してくれるだろう」。そうだろうか?そうだろ うか?特別な潤滑油を使っても、編み機で刺繍をすることはできない。そして最も痛烈な思いは、この悪名高きものが自ら作り出したということだ。考えもな く、良心もなく、先見の明もなく、目もなく、心もなく、自ら作り出したのだ。それは悲劇的な事故であり、起こってしまったことなのだ。それを妨げることは できない。苦渋の最後の一滴は、それを打ち砕くことさえできないという疑念の中にある。それを誕生させた力の中に潜む、唯一にして不滅の真理によって、そ れはありのままの姿であり、不滅なのだ!それは私たちを編み込み、私たちを編み出す。それは時間、空間、苦痛、死、腐敗、絶望、そしてすべての幻想を結び つけ、そして何も問題にはしない[181]。 コンラッドは1898年1月31日にカニングヘイム・グラハムに手紙を書いている: 信仰は神話であり、信念は岸辺の霧のように移り変わり、思考は消え去り、一度発した言葉は死んでしまう。 私が知っているこの世界では、私たちは理由も原因も罪の意識もなく、苦しみを強いられている......。 道徳も、知識も、希望もない。あるのは自分自身に対する意識だけで、それが私たちをこの世界に駆り立てる。 一瞬、瞬く間に、何も残らない。ただ泥の塊が、冷たい泥が、死んだ泥が、黒い空間に投げ出され、消えた太陽の周りを転がっているだけだ。何もない。思考も、音も、魂もない。何もない。 レオ・ロブソンは次のように述べている。 船乗りとして[コンラッドが]本当に学んだことは、経験的な何か、つまり「場所と出来事」の集合体ではなく、彼が幼少期に培った視点、すなわち、ロンド ン・タイムズ紙への手紙の中で彼が述べたように、唯一の議論の余地のない真実は「我々の無知」であるという、神秘と偶発性、恐怖と素晴らしさの場としての 世界に対する公平で幻惑のない見方の正当性を証明することだった[182]。 ロブソンは言う、 [コンラッドの]偶発的で暫定的なものとしての知識の扱いは、羅生門から[哲学者]リチャード・ローティの見解まで、さまざまな比較対象がある。コンラッ ドの[登場人物や出来事に関する情報を提示する]断片的な手法の参照点としては、ピカソやT.S.エリオット(彼は『闇の奥』のエピグラフから「空洞の男 たち」を引用している)が挙げられる。モダニズム小説のもうひとつの先駆者であるヘンリー・ジェイムズの後期でさえ、コンラッドがマーロウを生み出したと きにはまだ始まっていなかったし、ジェイムズの初期の遠近法の実験(『ポイントンの戦利品』、『メイジーの知っていたこと』)は『ロード・ジム』ほどには 進んでいない[8]。 言語  デイヴィッド・ロウによるコンラッドの風刺画、1923年 コンラッドは子供の頃から母国語であるポーランド語とフランス語を流暢に話し、英語を習得したのは20代になってからだった。息子のボリスは、コンラッド はドイツ語は数語しか話せないと主張していたが、1914年に一家がポーランドを離れようとしてオーストリアの辺境に到達したとき、コンラッドは「かなり 長く、非常に流暢に」ドイツ語を話したと記録している[183][184]。 [185]ロシア、プロイセン、オーストリアはポーランドを分割統治しており、コンラッドはイギリスに帰化するまで公式にはロシアの臣民であった [186]。 しかし、コンラッドは英語で小説を書くことを選んだ。コンラッドは『個人的な記録』の序文で、英語で書くことは彼にとって「自然なこと」であり、ある人々 が示唆したように、英語とフランス語のどちらかを意図的に選択したという考えは誤りであったと述べている。1915年、ジョー・デイヴィッドソンが彼の胸 像を彫ったとき、コンラッドは彼の質問に答えた: 「ああ...フランス語を書くには、それを知らなければならない。英語はとても可塑的で、必要な単語がなければ作ることができるが、フランス語を書くには アナトール・フランスのような芸術家でなければならない」[189]。1897年、コンラッドは同じポーランド人で哲学者のヴィンチェンティ・ルトスワフ スキの訪問を受け、「なぜポーランド語で書かないのですか?」とコンラッドに尋ねた。ルトスワフスキはコンラッドがこう説明したのを覚えている: 「私の不器用な努力をポーランド文学に持ち込むことはできない。しかし、イギリス人にとっては、私の贈り物は十分であり、私の日々の糧を確保してくれる」 [191]。 コンラッドは『個人的な記録』の中で、英語は「私の秘密の選択、私の将来、長い友情、深い愛情、労苦の時間、安楽の時間、孤独な時間、読んだ本、追求した 思考、思い出した感情、まさに私の夢の言葉」であったと書いている[192]! 「1878年、コンラッドのフランス商船での4年間の経験は、彼が帝政ロシア領事からフランス商船と航海する許可を得ていないことがフランス側に発覚し、 打ち切られた[注釈 34]。このことと、いくつかの典型的なコンラッド流の悲惨な投資によって、コンラッドは困窮し、自殺未遂に追い込まれた。コンラッドは、マルセイユに呼 び出された恩師である叔父のタデウシュ・ボブロフスキの同意を得て、ロシアの許可を必要としないイギリス商船に就職することを決めた[193]。こうして コンラッドの16年にわたるイギリス人と英語との船員生活が始まった。 もしコンラッドがフランス語圏にとどまっていたら、あるいはポーランドに帰国していたら、ポーランドの詩人、劇作家、翻訳家であったアポロ・コルツェニウ スキーの息子であったコンラッドは、幼少期からポーランド文学や外国文学に親しみ、自らも作家になるという野心を抱いていた[38]。確かに叔父のタデウ シュは、コンラッドがポーランド語で書くかもしれないと考えていた。1881年の手紙の中で、彼は23歳の甥にこう忠告している: 1881年の手紙の中で、彼は23歳の甥にこうアドバイスしている。旅行者は少ないし、本物の通信員はもっと少ない。目撃者の言葉は大きな関心を呼び、や がてあなたにお金をもたらすだろう。それは、祖国と同胞を結ぶ糸である母国語の訓練にもなるし、最終的には、常にペンをもって祖国のために尽くそうとし、 また尽くしたあなたの父の思い出への賛辞にもなるだろう[194]」。 一部の伝記作家の意見では、コンラッドの第3の言語である英語は、最初の2つの言語(ポーランド語とフランス語)の影響下にあった。そのため、コンラッドの英語は普通ではないように思われる。ナジダーはこう書いている: [彼は3つの文化を持つ人間だった: ポーランド語、フランス語、そして英語である。ポーランド人の家庭と文化的環境の中で育った彼は、幼い頃からフランス語を学び、17歳足らずでフランスに 渡り、フランス商船に4年間勤務した。学校ではドイツ語を学んだに違いないが、フランス語は彼が生涯を終えるまで最も流暢に(そして外国訛りなく)話した 言語であった。彼はフランスの歴史と文学に造詣が深く、フランスの小説家は彼の芸術的モデルであった。しかし、彼はすべての著作を20歳のときに習い始め た英語で書いた。つまり、彼は他の言語的・文化的環境で育ったイギリス人作家だったのである。彼の作品は、自動翻訳のボーダーランドに位置していると見る ことができる[6]。 ポーランド語、フランス語、英語のトリリンガルであるコンラッドの著作には、時折、言語的な波及が見られる: 「フランス語やポーランドの語彙、文法、構文が英語の文章に不用意に使われているのだ。ある例では、ナジダーは「コンラッドに典型的な語彙(ガリシア語) や文法(通常はポーロン語)におけるいくつかの不注意」を、コンラッドの時々の文学的協力者であったフォード・マドックス・フォードが、病気のコンラッド に代わって『T.P.'s Weekly』誌に掲載するためにコンラッドの小説『ノストロモ』のある部分を執筆したという主張に対する内部証拠の一部として用いている[195]。 コンラッドが、ポーランドの物理学者、コラムニスト、ストーリー作家、喜劇作家であるブルーノ・ワイナワーの短編戯曲『ヨブ記』を英訳しようとした 1921年の試みは、日常的に使用される主要言語でなくなって久しい言語を使って仕事をすることの非現実性を物語っている。ナジダーはこう書いている: [戯曲の)言葉は簡単で、口語的で、少し個性的だ。特にヘルプと俗物的なユダヤ人 「ボロ」・ベンジナーには特徴的な話し方がある。ポーランド語の日常会話にほとんど接したことのないコンラッドは、台詞を単純化し、ヘルプの科学的表現を 省き、多くの面白いニュアンスを聞き逃した。原作では、現代のワルシャワ、優雅な社交界とデミモンの中間のような場所が舞台となっている。コンラッドは、 ドラマの人物像の表現において、話題性のある風刺の多くのアクセントを省き、何人かの登場人物の非文法的な話し方(これはコンラッドにはわからなかったか もしれない)だけでなく、そのうちの二人、ボロとモサンのユダヤ人らしささえも無視した[196]。 実際問題として、コンラッドが小説を書こうとした時点では、英語で書く以外に選択肢はほとんどなかった[注釈 35]。コンラッドがポーランド語ではなく英語で書いたために文化的背教だと非難したポーランド人[注釈 198]は的外れであり、コンラッドが芸術的媒体として英語を選択した既定路線に、ある種の英語の生得的優位性の証左を見出す英語圏の人々と同様である [注釈 36]。 コンラッドの親友で文学アシスタントのリチャード・カールによれば、コンラッドが英語で執筆しているという事実は「明らかに誤解を招く」ものであった。 コンラッドは常に母国語に強い感情的な愛着を抱いていた。死の直前の1924年6月には、息子のジョンがポーランド人の娘と結婚してポーランド語を学ぶことを望み、独立したポーランドに永久に帰国することも考えていたようだ[203]。 コンラッドは、ロシアあるいは「スラヴ」の作家と呼ばれることに歯がゆさを感じていた。批評家たち」は、亡くなる半年前の1924年1月31日に知人に宛 てて、「私の中に新しいノートを発見し、ちょうど私が書き始めた頃、彼らはロシア人作家の存在を発見したので、スラヴォニズムという名で私にそのレッテル を貼った。しかし、コンラッドはドストエフスキーは「私にはロシア的すぎる」と抗議し、ロシア文学は一般的に「遺伝的にも個人的にも私には忌み嫌われる」 ものであったが[205]、『Under Western Eyes』は、ドストエフスキーの『罪と罰』で探求されたテーマに対するコンラッドの反応とみなされている[206]。 コンラッドは、どのような言語においても、個々の表現-単語、フレーズ、文章-には含蓄があるという意識を持っていた。彼はかつて、「どんな英単語にもき れいな端はない」と書いた。すべての表現は、「ぼやけた感情を興奮させる道具」に過ぎないほど多くの含蓄を持っていると彼は考えていた[207]。このこ とは、彼の著作の多くの箇所が印象主義的であることを説明するのに役立つかもしれない。また、ポーランド語でもフランス語でもなく、何十年もの間、最も親 しんできた英語で作品を書くことを選んだ理由も説明できる。 論争 1975年、ナイジェリアの作家チヌア・アチェベは「アフリカのイメージ」というエッセイを発表した: コンラッドを「徹底した人種差別主義者」と呼び、論争を引き起こした。アチェベの見解は、『闇の奥』は偉大な芸術作品とは見なされないというもので、それ は「人間性の喪失を賛美する小説であり、人類の一部を非人格化する小説」だからである。アチェベはコンラッドのことを「才能に溢れ、苦悩する男」と称し、 コンラッドが(主人公のチャールズ・マーロウを通して)アフリカ人を「手足」「足首」「輝く白い目玉」などに貶め、堕落させると同時に(そして恐る恐る) 自分自身とこれらの原住民との間に共通の血縁関係があるのではないかと疑い、マーロウに「醜い」という言葉を嘲笑させたことを指摘している[208]: 「ハイチで出会ったある巨大な牡鹿のようなニガーは、盲目で、猛烈で、理不尽な怒りが人間の動物に現れるという私の概念を、私の日々の終わりまで固定化さ せた」[209] アチェベのエッセイはポストコロニアル言説における画期的なものであり、議論を引き起こした。 アチェベの批評家たちは、コンラッドがマーロウの見解とコンラッドの見解を区別しておらず、その結果、この小説を非常に不器用に解釈していると主張してい る[213]。彼らの見解では、コンラッドはアフリカ人を同情的に、彼らの苦境を悲劇的に描いており、ヨーロッパの植民地主義者たちの崇高とされる目的に 皮肉を込めて言及したり、真っ向から非難したりすることで、白人の道徳的優越性に対する懐疑を示している。 [214]鎖につながれ、やせ細った奴隷の状態を描写した一節の最後に、この小説家はこう述べている。「結局のところ、私もまた、こうした高邁で公正な手 続きの大義の一部だったのだ」。ジェフリー・マイヤーズは、コンラッドは知人のロジャー・ケースマンと同様、「ルネサンスから第一次世界大戦までヨーロッ パで支配的だった進歩という西洋の概念に疑問を投げかけ、植民地主義の偽善的な正当化を攻撃し、アフリカにおける白人の野蛮な堕落を明らかにした最初の人 物の一人である」と指摘している[215]。 同様に、コンゴにおけるレオポルド2世の支配に対する国際的な反対運動を率いたE.D.モレルは、コンラッドの『闇の奥』を植民地支配の蛮行を非難するも のと見なし、この小説を「このテーマについて書かれた最も力強いもの」と呼んだ[217]。 最近では、ニデシュ・ロットーが、コンラッドの「狂乱」のイメージが、アチェベの『別離』でも同様に中心的な意味を持つ「憑依トランス」の儀式を描いてい ることを示すことによって、人種論争を複雑にしている[218]。 コンラッドの研究者であるピーター・フィルチョーは、「この小説のどこにも、コンラッドやその語り手は、擬人化されていようがいまいが、遺伝的あるいは生 物学的な差異を理由にヨーロッパ人の側の優位性を主張していない」と書いている。コンラッドや彼の小説が人種差別的であるとすれば、それは弱い意味におい てのみであり、『闇の奥』は人種的区別を認めてはいるが、いかなる集団の「本質的な優越性を示唆しているわけではない」のである[219][220]。ア チェベの『闇の奥』の読解は、コンラッドのもう一つのアフリカの物語である『前進の前哨基地』の読解によって異議を唱えることができる(そして、それはな されてきた)。マスード・アシュラフ・ラジャのような若い研究者の中には、『闇の奥』を超えてコンラッド、特に彼のマレー小説を読めば、コンラッドのムス リムに対する肯定的な表現を前景化することによって人種差別がさらに複雑化する可能性があることを示唆する者もいる[221]。 1998年、H.S.ジンズはPula: Botswana Journal of African Studies)にこう書いている: コンラッドが英文学をより成熟した反省的なものにしたのは、彼がイギリス市民や政治家によって見過ごされてきた政治的現実の恐ろしさに注意を喚起したから である。コンラッドの抑圧された祖国ポーランドの事件もそのような問題の一つであった。アフリカ人に対する植民地的搾取もその一つだった。帝国主義と植民 地主義に対する彼の非難は、迫害され苦しむ犠牲者への同情と結びついて、ポーランド人としての背景、彼自身の個人的な苦しみ、外国の占領下で生きる迫害さ れた人々の経験から引き出された。個人的な記憶は、彼の中に人間の劣化に対する大きな感受性と道徳的責任感を生み出した」[17]。 アダム・ホックチャイルドも同様の指摘をしている: 帝国主義の核心にある傲慢と窃盗を見抜く稀有な能力を[コンラッドに]与えたものは何だったのか。その多くは、彼自身がポーランド人として、征服された領 土に住むことがどのようなものかを知っていたという事実と関係しているに違いない......。[彼の人生の最初の数年間は、ロシア帝国の何千万という農 民が奴隷労働者、つまり農奴に相当するものだった。コンラッドの詩人の父アポロ・コルツェニウスキはポーランドの民族主義者で、農奴制に反対していた。 [少年(コンラッド)は、追放された刑務所の退役軍人、農奴制の話、反乱で殺された親戚のニュースの中で育った。 コンラッドはベルギーが運営するコンゴでの経験から、「白人の使命」に対する最も激しい批判者の一人となった。それはまた、コンラッドにとって最も大胆か つ最後の「社会的ホモ、つまり社会の仕組みの歯車になろうとする試み」でもあった、とナジダーは書いている。商社の仕事を引き受けることで、彼は人生で一 度だけ、陸上で組織化された大規模な集団活動に参加した。[コンゴ探検がコンラッドの人生において孤立した出来事であったのは偶然ではない。彼は死ぬまで 社会的な意味での世捨て人であり続け、いかなる組織や明確に定義された集団とも関わることはなかった」[223]。 |
| Citizenship Conrad was a Russian subject, having been born in the Russian part of what had once been the Polish–Lithuanian Commonwealth. After his father's death, Conrad's uncle Bobrowski had attempted to secure Austrian citizenship for him—to no avail, probably because Conrad had not received permission from Russian authorities to remain abroad permanently and had not been released from being a Russian subject. Conrad could not return to the Russian Empire—he would have been liable to many years of military service and, as the son of political exiles, to harassment.[224] In a letter of 9 August 1877, Conrad's uncle Bobrowski broached two important subjects:[note 37] the desirability of Conrad's naturalisation abroad (tantamount to release from being a Russian subject) and Conrad's plans to join the British merchant marine. "[D]o you speak English?... I never wished you to become naturalized in France, mainly because of the compulsory military service... I thought, however, of your getting naturalized in Switzerland..." In his next letter, Bobrowski supported Conrad's idea of seeking citizenship of the United States or of "one of the more important Southern [American] Republics".[226] Eventually Conrad would make his home in England. On 2 July 1886 he applied for British nationality, which was granted on 19 August 1886. Yet, in spite of having become a subject of Queen Victoria, Conrad had not ceased to be a subject of Tsar Alexander III. To achieve his freedom from that subjection, he had to make many visits to the Russian Embassy in London and politely reiterate his request. He would later recall the Embassy's home at Belgrave Square in his novel The Secret Agent.[227] Finally, on 2 April 1889, the Russian Ministry of Home Affairs released "the son of a Polish man of letters, captain of the British merchant marine" from the status of Russian subject.[228] |
市民権 コンラッドは、かつてのポーランド・リトアニア連邦のロシア領で生まれたロシア臣民だった。父親の死後、叔父のボブロフスキはコンラッドのためにオースト リア国籍を取得しようとしたが、コンラッドがロシア当局から外国に永住する許可を得ておらず、ロシア臣民であることを解いていなかったためであろう、効果 はなかった。コンラッドはロシア帝国に戻ることができず、何年もの兵役と、政治亡命者の息子としての嫌がらせを受けることになっただろう[224]。 1877年8月9日の手紙の中で、コンラッドの叔父ボブロフスキは、コンラッドの外国への帰化(ロシア臣民からの解放に等しい)とコンラッドのイギリス商 船への入港計画という2つの重要な話題を切り出している[注 37]。「英語は話せるか?私は君がフランスに帰化することを決して望まなかった。しかし、スイスに帰化することも考えた......」。次の手紙の中 で、ボブロウスキーは、アメリカか「より重要な南部(アメリカ)共和国のひとつ」の市民権を求めるというコンラッドの考えを支持した[226]。 最終的にコンラッドはイギリスに家を構えることになる。1886年7月2日、彼はイギリスの国民権を申請し、8月19日に許可された。しかし、ヴィクトリ ア女王の臣民となったにもかかわらず、コンラッドはアレクサンドル3世の臣民であることをやめなかった。その臣従から解放されるために、彼は何度もロンド ンのロシア大使館を訪れ、丁寧に要求を繰り返さなければならなかった。1889年4月2日、ついにロシア内務省は「イギリス商船の船長であったポーランド 人の文士の息子」をロシア臣民の身分から解放した[228]。 |
Memorials Anchor-shaped Conrad monument at Gdynia, on Poland's Baltic seacoast An anchor-shaped monument to Conrad at Gdynia, on Poland's Baltic Seacoast, features a quotation from him in Polish: "Nic tak nie nęci, nie rozczarowuje i nie zniewala, jak życie na morzu" ("[T]here is nothing more enticing, disenchanting, and enslaving than the life at sea" – Lord Jim, chapter 2, paragraph 1[user-generated source]). In Circular Quay, Sydney, Australia, a plaque in a "writers walk" commemorates Conrad's visits to Australia between 1879 and 1892. The plaque notes that "Many of his works reflect his 'affection for that young continent.'"[229]  Monument to Conrad in Vologda, Russia, to which Conrad and his parents were exiled in 1862 In San Francisco in 1979, a small triangular square at Columbus Avenue and Beach Street, near Fisherman's Wharf, was dedicated as "Joseph Conrad Square" after Conrad. The square's dedication was timed to coincide with the release of Francis Ford Coppola's Heart of Darkness-inspired film, Apocalypse Now. Conrad does not appear to have ever visited San Francisco. In the latter part of World War II, the Royal Navy cruiser HMS Danae was rechristened ORP Conrad and served as part of the Polish Navy.  Plaque commemorating "Joseph Conrad–Korzeniowski", Singapore Notwithstanding the undoubted sufferings that Conrad endured on many of his voyages, sentimentality and canny marketing place him at the best lodgings in several of his destinations. Hotels across the Far East still lay claim to him as an honoured guest, with, however, no evidence to back their claims: Singapore's Raffles Hotel continues to claim he stayed there though he lodged, in fact, at the Sailors' Home nearby. His visit to Bangkok also remains in that city's collective memory, and is recorded in the official history of The Oriental Hotel (where he never, in fact, stayed, lodging aboard his ship, the Otago) along with that of a less well-behaved guest, Somerset Maugham, who pilloried the hotel in a short story in revenge for attempts to eject him. A plaque commemorating "Joseph Conrad–Korzeniowski" has been installed near Singapore's Fullerton Hotel. Conrad is also reported to have stayed at Hong Kong's Peninsula Hotel—at a port that, in fact, he never visited. Later literary admirers, notably Graham Greene, followed closely in his footsteps, sometimes requesting the same room and perpetuating myths that have no basis in fact. No Caribbean resort is yet known to have claimed Conrad's patronage, although he is believed to have stayed at a Fort-de-France pension upon arrival in Martinique on his first voyage, in 1875, when he travelled as a passenger on the Mont Blanc. In April 2013, a monument to Conrad was unveiled in the Russian town of Vologda, where he and his parents lived in exile in 1862–63. The monument was removed, with unclear explanation, in June 2016.[230] Legacy Conrad is regarded as one of the greatest writers in the English language.[231] After the publication of Chance in 1913, he was the subject of more discussion and praise than any other English writer of the time. He had a genius for companionship, and his circle of friends, which he had begun assembling even prior to his first publications, included authors and other leading lights in the arts, such as Henry James, Robert Bontine Cunninghame Graham, John Galsworthy, Galsworthy's wife Ada Galsworthy (translator of French literature), Edward Garnett, Garnett's wife Constance Garnett (translator of Russian literature), Stephen Crane, Hugh Walpole, George Bernard Shaw, H. G. Wells (whom Conrad dubbed "the historian of the ages to come"[232]), Arnold Bennett, Norman Douglas, Jacob Epstein, T. E. Lawrence, André Gide, Paul Valéry, Maurice Ravel, Valery Larbaud, Saint-John Perse, Edith Wharton, James Huneker, anthropologist Bronisław Malinowski, Józef Retinger (later a founder of the European Movement, which led to the European Union, and author of Conrad and His Contemporaries). In the early 1900s Conrad composed a short series of novels in collaboration with Ford Madox Ford.[233] In 1919 and 1922 Conrad's growing renown and prestige among writers and critics in continental Europe fostered his hopes for a Nobel Prize in Literature. It was apparently the French and Swedes—not the English—who favoured Conrad's candidacy.[234] [note 38]  Conrad's Polish Nałęcz coat-of-arms In April 1924 Conrad, who possessed a hereditary Polish status of nobility and coat-of-arms (Nałęcz), declined a (non-hereditary) British knighthood offered by Labour Party Prime Minister Ramsay MacDonald.[note 39] [note 40] Conrad kept a distance from official structures—he never voted in British national elections—and seems to have been averse to public honours generally; he had already refused honorary degrees from Cambridge, Durham, Edinburgh, Liverpool, and Yale universities.[108] In the Polish People's Republic, translations of Conrad's works were openly published, except for Under Western Eyes, which in the 1980s was published as an underground "bibuła".[236] Conrad's narrative style and anti-heroic characters[10] have influenced many authors, including T. S. Eliot,[8] Maria Dąbrowska,[237] F. Scott Fitzgerald,[238] William Faulkner,[238] Gerald Basil Edwards,[239][page needed] Ernest Hemingway,[240] Antoine de Saint-Exupéry,[237] André Malraux,[237] George Orwell,[241] Graham Greene,[238] William Golding,[238] William Burroughs,[182] Saul Bellow,[182] Gabriel García Márquez,[238] Peter Matthiessen,[note 41] John le Carré,[238] V. S. Naipaul,[238] Philip Roth,[242] Joan Didion,[182] Thomas Pynchon[182] J. M. Coetzee,[238] and Salman Rushdie.[note 42] Many films have been adapted from, or inspired by, Conrad's works. Impressions A portrait of Conrad, aged about 46, was drawn by the historian and poet Henry Newbolt, who met him about 1903: One thing struck me at once—the extraordinary difference between his expression in profile and when looked at full face. [W]hile the profile was aquiline and commanding, in the front view the broad brow, wide-apart eyes and full lips produced the effect of an intellectual calm and even at times of a dreaming philosophy. Then [a]s we sat in our little half-circle round the fire, and talked on anything and everything, I saw a third Conrad emerge—an artistic self, sensitive and restless to the last degree. The more he talked the more quickly he consumed his cigarettes... And presently, when I asked him why he was leaving London after... only two days, he replied that... the crowd in the streets... terrified him. "Terrified? By that dull stream of obliterated faces?" He leaned forward with both hands raised and clenched. "Yes, terrified: I see their personalities all leaping out at me like tigers!" He acted the tiger well enough almost to terrify his hearers: but the moment after he was talking again wisely and soberly as if he were an average Englishman with not an irritable nerve in his body.[243] On 12 October 1912, American music critic James Huneker visited Conrad and later recalled being received by "a man of the world, neither sailor nor novelist, just a simple-mannered gentleman, whose welcome was sincere, whose glance was veiled, at times far-away, whose ways were French, Polish, anything but 'literary,' bluff or English."[244]  Lady Ottoline Morrell After respective separate visits to Conrad in August and September 1913, two British aristocrats, the socialite Lady Ottoline Morrell and the mathematician and philosopher Bertrand Russell—who were lovers at the time—recorded their impressions of the novelist. In her diary, Morrell wrote: I found Conrad himself standing at the door of the house ready to receive me.... [His] appearance was really that of a Polish nobleman. His manner was perfect, almost too elaborate; so nervous and sympathetic that every fibre of him seemed electric... He talked English with a strong accent, as if he tasted his words in his mouth before pronouncing them; but he talked extremely well, though he had always the talk and manner of a foreigner.... He was dressed very carefully in a blue double-breasted jacket. He talked... apparently with great freedom about his life—more ease and freedom indeed than an Englishman would have allowed himself. He spoke of the horrors of the Congo, from the moral and physical shock of which he said he had never recovered... [His wife Jessie] seemed a nice and good-looking fat creature, an excellent cook, ... a good and reposeful mattress for this hypersensitive, nerve-wracked man, who did not ask from his wife high intelligence, only an assuagement of life's vibrations.... He made me feel so natural and very much myself, that I was almost afraid of losing the thrill and wonder of being there, although I was vibrating with intense excitement inside .... His eyes under their pent-house lids revealed the suffering and the intensity of his experiences; when he spoke of his work, there came over them a sort of misty, sensuous, dreamy look, but they seemed to hold deep down the ghosts of old adventures and experiences—once or twice there was something in them one almost suspected of being wicked.... But then I believe whatever strange wickedness would tempt this super-subtle Pole, he would be held in restraint by an equally delicate sense of honour.... In his talk he led me along many paths of his life, but I felt that he did not wish to explore the jungle of emotions that lay dense on either side, and that his apparent frankness had a great reserve.[245] A month later, Bertrand Russell visited Conrad at Capel House in Orlestone, and the same day on the train wrote down his impressions: 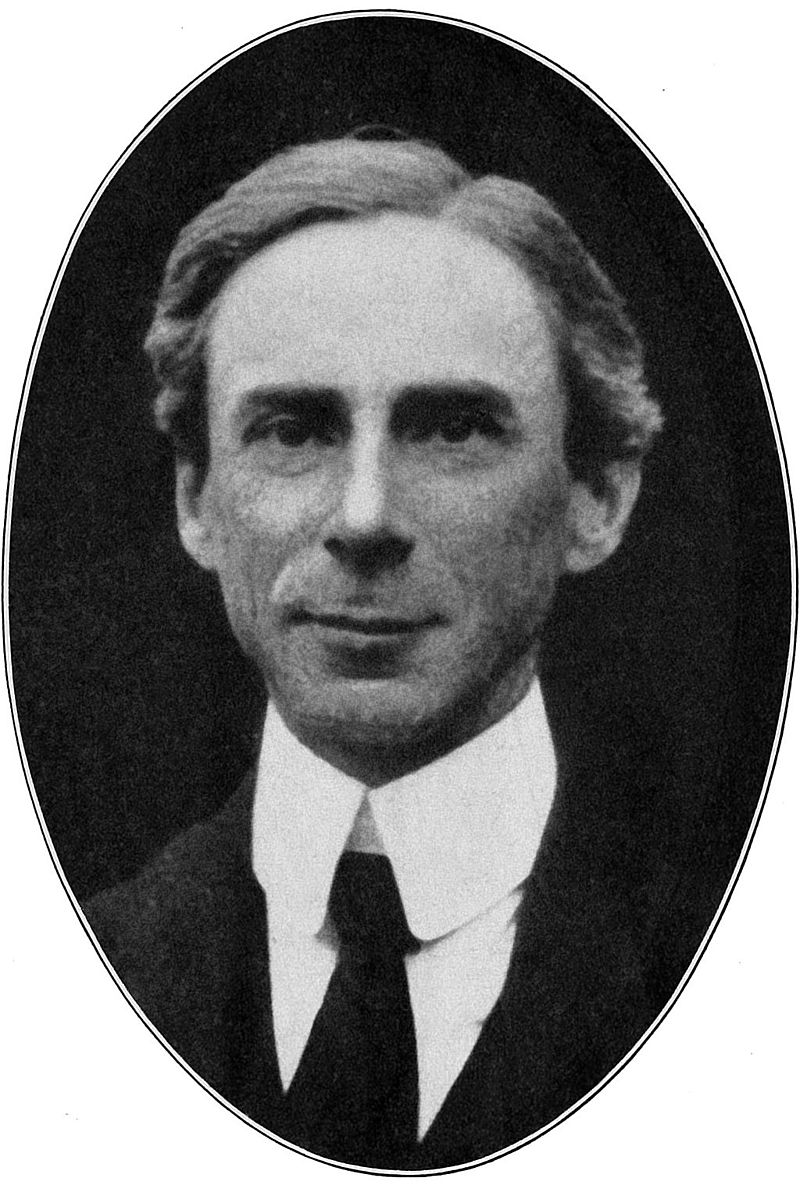 Bertrand Russell It was wonderful—I loved him & I think he liked me. He talked a great deal about his work & life & aims, & about other writers.... Then we went for a little walk, & somehow grew very intimate. I plucked up courage to tell him what I find in his work—the boring down into things to get to the very bottom below the apparent facts. He seemed to feel I had understood him; then I stopped & we just looked into each other's eyes for some time, & then he said he had grown to wish he could live on the surface and write differently, that he had grown frightened. His eyes at the moment expressed the inward pain & terror that one feels him always fighting.... Then he talked a lot about Poland, & showed me an album of family photographs of the [18]60's—spoke about how dream-like all that seems, & how he sometimes feels he ought not to have had any children, because they have no roots or traditions or relations.[246] Russell's Autobiography, published over half a century later in 1968, confirms his original experience: My first impression was one of surprise. He spoke English with a very strong foreign accent, and nothing in his demeanour in any way suggested the sea. He was an aristocratic Polish gentleman to his fingertips.... At our very first meeting, we talked with continually increasing intimacy. We seemed to sink through layer after layer of what was superficial, till gradually both reached the central fire. It was an experience unlike any other... I have known. We looked into each other's eyes, half appalled and half intoxicated to find ourselves together in such a region. The emotion was as intense as passionate love, and at the same time all-embracing. I came away bewildered, and hardly able to find my way among ordinary affairs.[18] It was not only Anglophones who remarked Conrad's strong foreign accent when speaking English. After French poet Paul Valéry and French composer Maurice Ravel made Conrad's acquaintance in December 1922, Valéry wrote in 1924 of having been astonished at Conrad's "horrible" accent in English.[247] The subsequent friendship and correspondence between Conrad and Russell lasted, with long intervals, to the end of Conrad's life. In one letter, Conrad avowed his "deep admiring affection, which, if you were never to see me again and forget my existence tomorrow will be unalterably yours usque ad finem."[248] Conrad in his correspondence often used the Latin expression meaning "to the very end", which he seems to have adopted from his faithful guardian, mentor and benefactor, his maternal uncle Tadeusz Bobrowski.[249] [note 43] Conrad was less optimistic than Russell about the possibilities of scientific and philosophical knowledge.[248] In a 1913 letter to acquaintances who had invited Conrad to join their society, he reiterated his belief that it was impossible to understand the essence of either reality or life: both science and art penetrate no further than the outer shapes.[251] Najder describes Conrad as "[a]n alienated émigré... haunted by a sense of the unreality of other people – a feeling natural to someone living outside the established structures of family, social milieu, and country".[170] Throughout almost his entire life Conrad was an outsider and felt himself to be one. An outsider in exile; an outsider during his visits to his family in... Poland; an outsider—because of his experiences and bereavement—in [Kraków] and Lwów; an outsider in Marseilles; an outsider, nationally and culturally, on British ships; an outsider as an English writer.[170] Conrad's sense of loneliness throughout his life in exile found memorable expression in the 1901 short story "Amy Foster". |
記念碑 ポーランドのバルト海沿岸、グディニアにあるコンラッドの錨型記念碑 ポーランドのバルト海沿岸、グディニアにあるコンラッドの錨の形をした記念碑には、コンラッドの言葉がポーランド語で記されている: 「Nic tak nie nęci, nie rozczarowuje i nie zniewala, jak życie na morzu"(「海での生活ほど魅力的で、魅惑的で、奴隷的なものはない」-ジム卿、第2章、第1段落[ユーザー生成ソース])。 オーストラリア、シドニーのサーキュラー・キーにある「作家の散歩道」には、1879年から1892年にかけてコンラッドがオーストラリアを訪れたことを 記念するプレートがある。このプレートには、「彼の作品の多くは、その若い大陸に対する彼の『愛情』を反映している」と記されている[229]。  1862年にコンラッドと彼の両親が追放されたロシアのヴォログダにあるコンラッドの記念碑。 サンフランシスコでは1979年、フィッシャーマンズワーフ近くのコロンバス通りとビーチ通りにある小さな三角形の広場が、コンラッドにちなんで「ジョセ フ・コンラッド・スクエア」として奉納された。この広場の寄贈は、フランシス・フォード・コッポラ監督の『ハート・オブ・ダークネス』にインスパイアされ た映画『アポカリプス・ナウ』の公開に合わせたものだった。コンラッドはサンフランシスコを訪れたことはないようだ。 第二次世界大戦後期、イギリス海軍の巡洋艦HMSダナエはORPコンラッドと改名され、ポーランド海軍の一員として活躍した。  ジョセフ・コンラッド=コルゼニウスキ」を記念するプレート(シンガポール) コンラッドが多くの航海で耐えた苦難は疑いようもなかったが、感傷的な気持ちと巧みなマーケティングによって、コンラッドはいくつかの寄港地で最高の宿に 泊まることになった。極東各地のホテルは、今でもコンラッドを名誉ある客人だと主張しているが、その主張を裏付ける証拠はない: シンガポールのラッフルズ・ホテルは、彼が宿泊したと主張し続けているが、実際には近くのセーラーズ・ホームに宿泊している。彼のバンコク訪問もまた、バ ンコクの人々の記憶に残っており、オリエンタル・ホテル(実際には彼は宿泊せず、彼の船オタゴ号に乗船していた)の公式な歴史に、お行儀の悪い宿泊客サマ セット・モームの歴史とともに記録されている。 シンガポールのフラートン・ホテルの近くには、「ジョセフ・コンラッド=コルゼニウスキー」を記念するプレートが設置されている。 コンラッドは香港のペニンシュラ・ホテルにも滞在したと伝えられているが、実際には一度も訪れていない。後にコンラッドに憧れた文学者たち、特にグレア ム・グリーンはコンラッドの足跡を追い、時には同じ部屋をリクエストし、事実無根の神話を広めた。カリブ海のリゾートでコンラッドの庇護を受けたとされる 場所はまだ知られていないが、1875年にモンブラン号の乗客として初めて航海した際、マルティニークに到着したコンラッドはフォール・ド・フランスのペ ンションに滞在したと考えられている。 2013年4月、彼と彼の両親が1862年から63年にかけて亡命生活を送ったロシアの町ヴォログダで、コンラッドの記念碑が除幕された。この記念碑は2016年6月に不明確な説明とともに撤去された[230]。 遺産 コンラッドは英語で最も偉大な作家の一人とみなされている[231]。 1913年に『チャンス』が出版された後、彼は当時の他のどのイギリス人作家よりも多くの議論と賞賛の対象となった。彼は交友関係の天才であり、最初の出 版以前から集め始めていた友人の輪には、ヘンリー・ジェームズ、ロバート・ボンタイン・カニングヘイム・グラハム、ジョン・ガルスワージー、ガルスワー ジーの妻エイダ・ガルスワージー(フランス文学の翻訳者)、エドワード・ガーネット、ガーネットの妻コンスタンス・ガーネット(ロシア文学の翻訳者)、ス ティーヴン・クレイン、ヒュー・ウォルポール、ジョージ・バーナード・ショー、H. G.ウェルズ(コンラッドは「来るべき時代の歴史家」と呼んだ[232])、アーノルド・ベネット、ノーマン・ダグラス、ジェイコブ・エプスタイン、 T.E.ローレンス、アンドレ・ジド、ポール・ヴァレリー、モーリス・ラヴェル、ヴァレリー・ラルボー、サン=ジョン・ペルス、エディス・ウォートン、 ジェームズ・ヒューンカー、人類学者ブロニスワフ・マリノフスキ、ヨゼフ・レティンガー(後に欧州連合につながる欧州運動の創設者、『コンラッドとその同 時代人』の著者)。1900年代初頭、コンラッドはフォード・マドックス・フォードと共同で短い連作小説を執筆した[233]。 1919年と1922年、ヨーロッパ大陸の作家や批評家の間でコンラッドの名声と名声が高まり、ノーベル文学賞への期待が高まった。コンラッドの立候補を支持したのは、イギリス人ではなくフランス人とスウェーデン人であったらしい[234] [注釈 38]。  コンラッドのポーランド・ナウエーナの紋章 1924年4月、コンラッドはポーランドの世襲貴族であり紋章(ナウエーナ)を持っていたが、労働党の首相ラムジー・マクドナルドが提示した(世襲ではな い)イギリスの爵位を辞退した[注釈 39] [注釈 40] コンラッドは公的な機構から距離を置いており、イギリスの国民選挙で投票したことはなく、一般的に公的な栄誉を嫌っていたようで、ケンブリッジ大学、ダラ ム大学、エディンバラ大学、リバプール大学、イェール大学からの名誉学位をすでに拒否していた[108]。 ポーランド人民共和国では、1980年代に地下の「ビブワ」として出版された『Under Western Eyes』を除いて、コンラッドの作品の翻訳が公然と出版された[236]。 コンラッドの物語スタイルとアンチヒーロー的なキャラクター[10]は、T・S・エリオット、[8]マリア・ドブロフスカ、[237]F・スコット・ フィッツジェラルド、[238]F. Scott Fitzgerald,[238] William Faulkner,[238] Gerald Basil Edwards,[239][page needed] Ernest Hemingway,[240] Antoine de Saint-Exupéry,[237] André Malraux,[237] George Orwell、 241] グレアム・グリーン,[238] ウィリアム・ゴールディング,[238] ウィリアム・バロウズ,[182] ソール・ベロー,[182] ガブリエル・ガルシア・マルケス,[238] ピーター・マティエッセン,[注釈 41] ジョン・ル・カレ,[238] V. S. ナイポール,[238] V. S.ナイポール、[238] フィリップ・ロス、[242] ジョーン・ディディオン、[182] トマス・ピンチョン[182] J.M.コッツェー、[238] サルマン・ラシュディ[注釈 42] コンラッドの作品から映画化された、あるいはコンラッドの作品にインスパイアされた映画は多い。 印象 1903年頃にコンラッドに会った歴史家で詩人のヘンリー・ニューボルトは、46歳頃のコンラッドの肖像画を描いた: 彼の横顔と全顔を見たときの表情の驚くべき違いだ。[横顔はアクイラインで威厳があったが、正面から見ると、広い眉、大きく見開かれた目、ふっくらとした 唇が、知的な落ち着きと、時には夢見る哲学のような効果さえ生み出していた。そして、私たちが火を囲んで小さな半円を描くように座り、あらゆることについ て話しているうちに、第3のコンラッドが姿を現した。話せば話すほど、コンラッドはすぐにタバコを吸い始めた...。そしてやがて、なぜたった2日でロン ドンを去るのかと私が尋ねると、彼は通りの人ごみが怖かったと答えた。「恐怖?消し去られた顔の、あの鈍い流れに?」 彼は両手を上げ、握りしめたまま身を乗り出した。「そう、怖かった: 彼らの個性が虎のように飛び出してくるのが見えるんだ。しかし、その直後には、まるで全身に過敏な神経を持たない普通のイギリス人であるかのように、また 賢く冷静に話していた[243]。 1912年10月12日、アメリカの音楽批評家ジェイムズ・ヒュネカーはコンラッドを訪れ、後に「船乗りでも小説家でもない、ただ素朴な紳士であり、その 歓迎は誠実で、その視線はベールに包まれ、時に遠くを見つめ、そのやり方はフランス風であり、ポーランド風であり、『文学的』でも、はったりでも、イギリ ス風でもなかった」と述懐している[244]。  レディ・オットリン・モレル 1913年8月と9月にそれぞれ別々にコンラッドを訪れた2人の英国貴族、社交界の貴婦人オットリン・モレルと、当時恋人同士だった数学者で哲学者のバートランド・ラッセルは、コンラッドの印象を日記に記している。モレルは日記にこう書いている: コンラッド自身が家のドアの前に立っていて、私を迎えようとしていた。[彼の風貌は本当にポーランドの貴族のそれだった。彼の態度は完璧で、凝りすぎてい るほどだった。彼は強いアクセントで英語を話し、まるで発音する前に口の中で自分の言葉を味わっているかのようだった。彼は青いダブルブレストのジャケッ トをとても丁寧に着ていた。彼は......どうやら自分の人生についてとても自由に語っていたようだ。彼はコンゴの惨状について語ったが、その精神的、 肉体的ショックから立ち直ることはできなかったという。[妻のジェシーは)太ったいい女で、料理上手で、......この過敏で神経過敏な男にとって、安 らかでいいマットレスだった。彼は私をとても自然で、とても自分らしい存在に感じさせてくれた。私は、内面では激しい興奮で振動していたにもかかわらず、 そこにいることのスリルと驚きを失うことを恐れそうになった......。彼が自分の仕事について話すとき、その目には一種の霧がかかったような、官能的 な、夢見るような表情が浮かんでいた。しかしその目には、昔の冒険や経験の亡霊が心の奥底に宿っているようだった。しかし私は、この超微妙な極道がどんな 奇妙な邪悪な誘惑に駆られようとも、同じように繊細な名誉の感覚によって抑制されると信じている......。彼の話の中で、彼は自分の人生の多くの道を 私に案内してくれたが、私は、彼がどちら側にも鬱蒼と横たわる感情のジャングルを探検したがらず、彼の見かけの率直さには大きな遠慮があると感じた [245]。 その1ヵ月後、バートランド・ラッセルはオーレストーンのカペル・ハウスにコンラッドを訪ね、同じ日の列車の中で彼の印象を書き留めている: 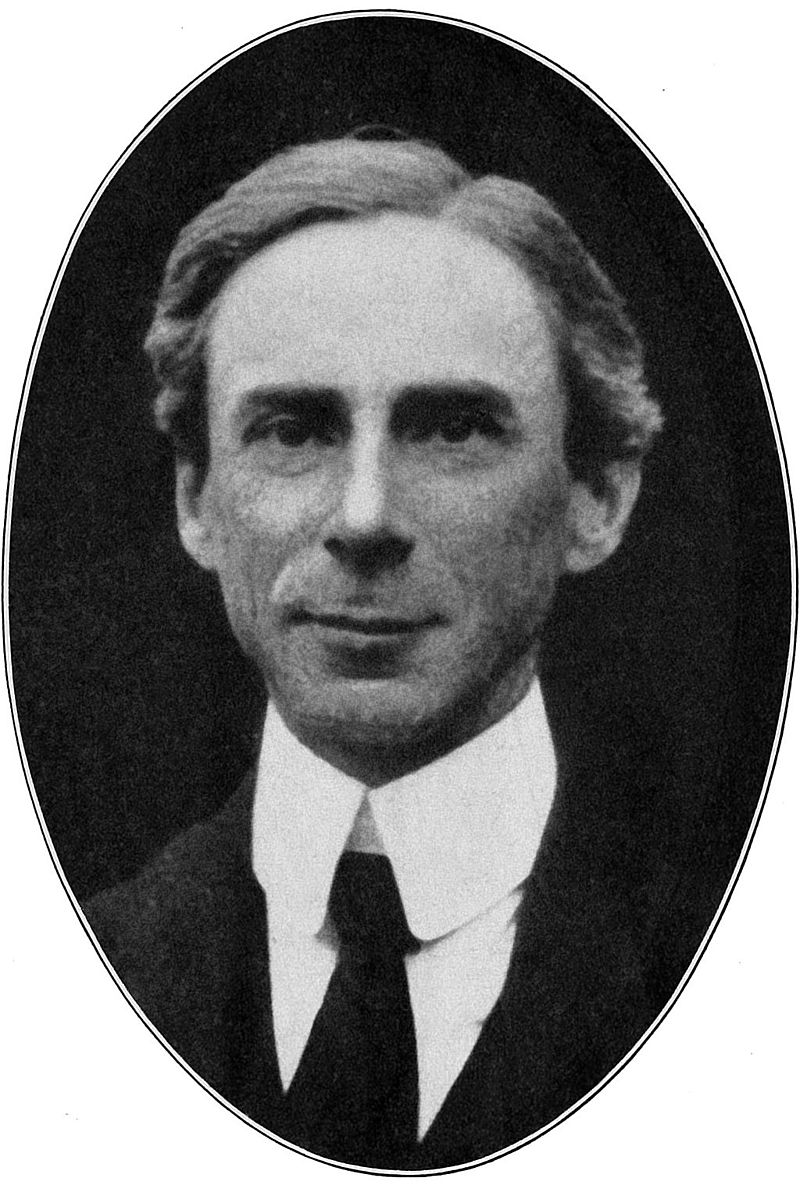 バートランド・ラッセル 私は彼を愛し、彼は私を好きだったと思う。彼は自分の仕事、人生、目標、そして他の作家について大いに語った......。それから少し散歩をして、どう いうわけかとても親密になった。私は勇気を出して、彼の作品に見出したもの、つまり、物事を突き詰めていき、見かけの事実の下にあるどん底に到達すること について話した。彼は私が彼を理解したと感じたようだった。そして私は立ち止まり、しばらくお互いの目を見つめ合った。そのときの彼の目は、彼がいつも 戦っているように感じる内なる痛みと恐怖を表現していた......。それから彼はポーランドのことをたくさん話し、[18]60年代の家族写真のアルバ ムを見せてくれた。 半世紀以上後の1968年に出版されたラッセルの自伝は、彼の原体験を裏付けている: 私の第一印象は驚きだった。彼は非常に強い外国訛りの英語を話し、その態度には海を連想させるものは何もなかった。彼は指先まで貴族的なポーランド紳士 だった......。初めて会ったとき、私たちは親密さを増しながら話をした。私たちは、表面的なものから何層にも重なって沈んでいくようで、次第に中心 的な炎にたどり着いた。それは今までにない経験だった...。私が知っている限りでは。私たちは互いの目を見つめ合い、半ば愕然とし、半ばそのような領域 に一緒にいることに酔いしれた。その感情は情熱的な愛のように激しく、同時にすべてを包み込むものだった。私は戸惑いながら、日常生活の中で自分の進むべ き道を見つけることができなかった[18]。 英語を話すときのコンラッドの強い外国訛りを指摘したのは、英語圏の人々だけではなかった。フランスの詩人ポール・ヴァレリーとフランスの作曲家モーリ ス・ラヴェルが1922年12月にコンラッドと知り合った後、ヴァレリーは1924年にコンラッドの英語の「ひどい」アクセントに驚いたと書いている [247]。 その後、コンラッドとラッセルの間の友情と文通は、長いインターバルを挟みつつ、コンラッドの生涯の終わりまで続いた。ある手紙の中で、コンラッドは「深 い敬愛の念を抱いており、もしあなたが二度と私に会わず、明日私の存在を忘れることがなかったとしても、永遠にあなたのものusque ad finemであろう」[248]と公言している。コンラッドは文通の中でしばしば「最後まで」という意味のラテン語の表現を用いていたが、これは彼の忠実 な後見人であり、指導者であり、恩人であった母方の叔父タデウシュ・ボブロフスキから採用したと思われる[249] [注 43]。 コンラッドは科学的・哲学的知識の可能性についてはラッセルよりも楽観的ではなかった[248]。コンラッドを自分たちの社交界に招いた知人たちに宛てた 1913年の手紙の中で、コンラッドは現実や人生の本質を理解することは不可能であり、科学も芸術も外側の形以上に浸透することはないという信念を繰り返 していた[251]。 ナジダーはコンラッドを「疎外された移住者...他人の非現実性という感覚に悩まされた...家族、社会的環境、国といった既成の構造の外で生きる人間にとって自然な感覚」と表現している[170]。 コンラッドはほぼ全生涯を通じてアウトサイダーであり、自分自身がアウトサイダーであると感じていた。亡命中のアウトサイダー、ポーランドの家族のもとを 訪れているときのアウトサイダー、アウトサイダーであるが故に、アウトサイダーであると感じていた。マルセイユではアウトサイダーであり、国民的にも文化 的にもアウトサイダーであり、イギリス人作家としてもアウトサイダーであった[170]。 コンラッドの亡命生活を通しての孤独感は、1901年の短編小説「エイミー・フォスター」で印象的に表現されている。 |
| Works Main article: Joseph Conrad bibliography Novels Almayer's Folly (1895) An Outcast of the Islands (1896) The Nigger of the 'Narcissus' (1897) Heart of Darkness (1899) Lord Jim (1900) The Inheritors (with Ford Madox Ford) (1901) Typhoon (1902, begun 1899) The End of the Tether (written in 1902; collected in Youth, a Narrative and Two Other Stories, 1902) Romance (with Ford Madox Ford, 1903) Nostromo (1904) The Secret Agent (1907) Under Western Eyes (1911) Chance (1913) Victory (1915) The Shadow Line (1917) The Arrow of Gold (1919) The Rescue (1920) The Nature of a Crime (1923, with Ford Madox Ford) The Rover (1923) Suspense (1925; unfinished, published posthumously)[252] Stories "The Black Mate": written, according to Conrad, in 1886; may be counted as his “opus double zero”?; published 1908; posthumously collected in Tales of Hearsay, 1925. "The Idiots": Conrad's truly first short story, which may be counted as his opus zero, was written during his honeymoon (1896), published in The Savoy periodical, 1896, and collected in Tales of Unrest, 1898. "The Lagoon": composed 1896; published in Cornhill Magazine, 1897; collected in Tales of Unrest, 1898: "It is the first short story I ever wrote." "An Outpost of Progress": written 1896; published in Cosmopolis, 1897, and collected in Tales of Unrest, 1898: "My next [second] effort in short-story writing"; it shows numerous thematic affinities with Heart of Darkness; in 1906, Conrad described it as his "best story". "The Return": completed early 1897, while writing "Karain"; never published in magazine form; collected in Tales of Unrest, 1898: "[A]ny kind word about 'The Return' (and there have been such words said at different times) awakens in me the liveliest gratitude, for I know how much the writing of that fantasy has cost me in sheer toil, in temper, and in disillusion." Conrad, who suffered while writing this psychological chef-d'oeuvre of introspection, once remarked: "I hate it." "Karain: A Memory": written February–April 1897; published November 1897 in Blackwood's Magazine and collected in Tales of Unrest, 1898: "my third short story in... order of time". "Youth": written 1898; collected in Youth, a Narrative, and Two Other Stories, 1902 "Falk": novella / story, written early 1901; collected only in Typhoon and Other Stories, 1903 "Amy Foster": composed 1901; published in the Illustrated London News, December 1901, and collected in Typhoon and Other Stories, 1903. "To-morrow": written early 1902; serialised in The Pall Mall Magazine, 1902, and collected in Typhoon and Other Stories, 1903 "Gaspar Ruiz": written after Nostromo in 1904–5; published in The Strand Magazine, 1906, and collected in A Set of Six, 1908 (UK), 1915 (US). This story was the only piece of Conrad's fiction ever adapted by the author for cinema, as Gaspar the Strong Man, 1920. "An Anarchist": written late 1905; serialised in Harper's Magazine, 1906; collected in A Set of Six, 1908 (UK), 1915 (US) "The Informer": written before January 1906; published, December 1906, in Harper's Magazine, and collected in A Set of Six, 1908 (UK), 1915 (US) "The Brute": written early 1906; published in The Daily Chronicle, December 1906; collected in A Set of Six, 1908 (UK), 1915 (US) "The Duel: A Military Story": serialised in the UK in The Pall Mall Magazine, early 1908, and later that year in the US as "The Point of Honor", in the periodical Forum; collected in A Set of Six in 1908 and published by Garden City Publishing in 1924. Joseph Fouché makes a cameo appearance. "Il Conde" (i.e., "Conte" [The Count]): appeared in Cassell's Magazine (UK), 1908, and Hampton's (US), 1909; collected in A Set of Six, 1908 (UK), 1915 (US) "The Secret Sharer": written December 1909; published in Harper's Magazine, 1910, and collected in Twixt Land and Sea, 1912 "Prince Roman": written 1910, published 1911 in The Oxford and Cambridge Review; posthumously collected in Tales of Hearsay, 1925; based on the story of Prince Roman Sanguszko of Poland (1800–81) "A Smile of Fortune": a long story, almost a novella, written in mid-1910; published in London Magazine, February 1911; collected in 'Twixt Land and Sea, 1912 "Freya of the Seven Isles": a near-novella, written late 1910–early 1911; published in The Metropolitan Magazine and London Magazine, early 1912 and July 1912, respectively; collected in 'Twixt Land and Sea, 1912 "The Partner": written 1911; published in Within the Tides, 1915 "The Inn of the Two Witches": written 1913; published in Within the Tides, 1915 "Because of the Dollars": written 1914; published in Within the Tides, 1915 "The Planter of Malata": written 1914; published in Within the Tides, 1915 "The Warrior's Soul": written late 1915–early 1916; published in Land and Water, March 1917; collected in Tales of Hearsay, 1925 "The Tale": Conrad's only story about World War I; written 1916, first published 1917 in The Strand Magazine; posthumously collected in Tales of Hearsay, 1925 Essays "Autocracy and War" (1905) The Mirror of the Sea (collection of autobiographical essays first published in various magazines 1904–06), 1906 A Personal Record (also published as Some Reminiscences), 1912 The First News, 1918 The Lesson of the Collision: A monograph upon the loss of the "Empress of Ireland", 1919 The Polish Question, 1919 The Shock of War, 1919 Notes on Life and Letters, 1921 Notes on My Books, 1921 Last Essays, edited by Richard Curle, 1926 The Congo Diary and Other Uncollected Pieces, edited by Zdzisław Najder, 1978, ISBN 978-0-385-00771-9 |
作品 主な記事 ジョセフ・コンラッド書誌 小説 アルマイヤーの愚行(1895年) 島の追放者(1896年) 水仙号のニガー(1897年) 闇の奥(1899年) ロード・ジム(1900年) 相続者たち(フォード・マドックス・フォードと共作)(1901年) タイフーン(1902年、1899年執筆開始) The End of the Tether(1902年執筆、『Youth, a Narrative and Two Other Stories』1902年所収) ロマンス(フォード・マドックス・フォードとの共作、1903年) ノストロモ(1904年) 秘密工作員(1907年) 西部の瞳の下で(1911年) チャンス (1913) 勝利(1915年) シャドーライン(1917年) 黄金の矢(1919年) 救出(1920年) 犯罪の本質(1923年、フォード・マドックス・フォードと共作) ローバー(1923年) サスペンス(1925年、未完、死後出版)[252] 小説 「ブラックメイト』:コンラッドによれば1886年に書かれた。1908年に出版され、死後1925年に『伝聞物語』に収録された。 「The Idiots」である: コンラッドの本当に最初の短編小説で、彼の作品ゼロに数えられるかもしれない。新婚旅行中(1896年)に書かれ、定期刊行物『サボイ』(1896年)に掲載され、『不安の物語』(1898年)に収録された。 ラグーン』:1896年作、1897年『コーンヒル・マガジン』誌に発表、1898年『不安の物語』誌に収録: 「私が初めて書いた短編小説である。 「進歩の前哨基地":1896年執筆、1897年『コスモポリス』誌に発表、1898年『不安の物語』誌に収録: 私の次の(2番目の)短編小説執筆の努力」であり、『闇の奥』とのテーマ的親和性を数多く示している。1906年、コンラッドはこの作品を「最高の物語」 と評している。 The Return」:「Karain」を執筆中の1897年初頭に完成、雑誌の形では出版されず、1898年の「Tales of Unrest」に収録された: 「帰還』についてのどんな親切な言葉も(そして、そのような言葉はさまざまな時に言われてきた)、私の中で最も生き生きとした感謝の気持ちを呼び覚ます。 この心理学的内観のシェフ・ド・ヴルを書きながら苦しんだコンラッドは、かつてこう言った: 「大嫌いだ。 「カレイン: 1897年11月にブラックウッド誌に発表され、1898年の『不安の物語』に収録された: 「私の3番目の短編小説である。 青春」:1898年執筆、1902年『青春、物語、他2編』に収録。 「フォーク」:1901年初めに書かれた小説/物語。 エイミー・フォスター」:1901年作、1901年12月『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』紙に発表、1903年『台風とその他の物語』に収録。 「To-morrow":1902年初めに書かれ、1902年のThe Pall Mall Magazineに連載され、1903年のTyphoon and Other Storiesに収録された。 ギャスパー・ルイズ」:1904-5年の『ノストロモ』の後に書かれ、1906年に『ストランド・マガジン』誌に発表され、1908年(英国)、1915 年(米国)の『6つのセット』に収録された。この物語は、コンラッドの小説の中で唯一映画化された作品であり、1920年の『ガスパール強者』として映画 化された。 「An Anarchist(無政府主義者)」:1905年末に書かれ、1906年にハーパース誌に連載された。 「The Informer":1906年1月以前に書かれ、1906年12月にハーパース誌に発表され、1908年(英国)、1915年(米国)のA Set of Sixに収録された。 「The Brute":1906年初めに書かれ、1906年12月にThe Daily Chronicleに発表され、1908年(英国)、1915年(米国)のA Set of Sixに収録された。 「決闘: The Duel: A Military Story「:英国では1908年初頭にThe Pall Mall Magazineに連載され、米国では同年末に定期刊行物Forumに 」The Point of Honor "として掲載された。1908年にA Set of Sixに収録され、1924年にGarden City Publishingから出版された。ジョセフ・フーシェがカメオ出演している。 「イル・コンデ「(すなわち 」コンテ"[伯爵]):1908年カッセル誌(英国)、1909年ハンプトン誌(米国)に掲載、1908年A Set of Six(英国)、1915年A Set of Six(米国)に収録。 「秘密の共有者(The Secret Sharer)」:1909年12月執筆、1910年ハーパーズ誌に発表、1912年Twixt Land and Seaに収録。 「ローマ王子":1910年執筆、1911年『オックスフォード・ケンブリッジ・レビュー』誌に発表、死後1925年『伝聞物語集』に収録、ポーランドのロマン・サングスコ王子(1800~81年)の物語に基づく。 「幸運の微笑み":1910年半ばに書かれた小説に近い長編小説、1911年2月『ロンドン・マガジン』誌に掲載、1912年『陸と海』誌に収録された。 「Freya of the Seven Isles":1910年末から1911年初頭に書かれた小説に近いもの;1912年初頭に『メトロポリタン・マガジン』誌に、1912年7月に『ロンド ン・マガジン』誌にそれぞれ掲載;1912年『Twixt Land and Sea』に収録 パートナー」:1911年執筆、1915年『潮の流れの中で』に発表。 二人の魔女の宿」:1913年執筆、1915年『Within the Tides』誌に発表。 ドルのせい」:1914年執筆、『潮の流れの中で』1915年掲載 マラタの植木職人」:1914年執筆、『潮の流れの中で』1915年掲載 戦士の魂」(The Warrior's Soul):1915年後半から1916年前半にかけて執筆、1917年3月『ランド・アンド・ウォーター』誌に発表、1925年『伝聞の物語』誌に収録。 「物語」: コンラッドの第一次世界大戦に関する唯一の物語で、1916年に書かれ、1917年に『ストランド・マガジン』に発表された。 エッセイ 「独裁政治と戦争」(1905年) 海の鏡』(1904-06年に様々な雑誌に発表された自伝的エッセイ集)1906年 個人的記録』(『回想』としても出版)、1912年 最初のニュース』1918年 衝突の教訓: アイルランドの女帝」号喪失についての単行本、1919年 ポーランド問題(1919年 戦争の衝撃、1919年 人生と手紙についてのノート、1921年 私の本についてのノート、1921年 リチャード・カール編『最後のエッセイ』1926年 ズジスワフ・ナイデル編『コンゴ日記とその他の未収録作品』1978年 ISBN 978-0-385-00771-9 |
| Joseph Conrad's career at sea Bolesław Prus King Leopold's Ghost Alice Sarah Kinkead List of Poles (prose literature) List of covers of Time magazine (1920s) – 7 April 1923 ORP Conrad – a World War II Polish Navy cruiser named after Joseph Conrad Politics in fiction Stefan Bobrowski, one of Conrad's maternal uncles. Like Conrad's father, he was a "Red"-faction political leader. |
ジョセフ・コンラッドの海でのキャリア ボレスワフ・プリュス レオポルド王の亡霊 アリス・サラ・キンキード ポーランド人のリスト(散文文学) タイム誌表紙リスト(1920年代) - 1923年4月7日 ORP Conrad - ジョセフ・コンラッドにちなんで命名された第二次世界大戦ポーランド海軍巡洋艦 小説における政治 コンラッドの母方の叔父の一人、ステファン・ボブロフスキ。コンラッドの父と同様、「赤」派の政治指導者であった。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad |
|
| Nostromo: A Tale of the Seaboard
is a 1904 novel by Joseph Conrad, set in the fictitious South American
republic of "Costaguana". It was originally published serially in
monthly instalments of T.P.'s Weekly. In 1998, the Modern Library ranked Nostromo 47th on its list of the 100 best English-language novels of the 20th century. It is frequently regarded as amongst the best of Conrad's long fiction; F. Scott Fitzgerald once said, "I'd rather have written Nostromo than any other novel."[1] 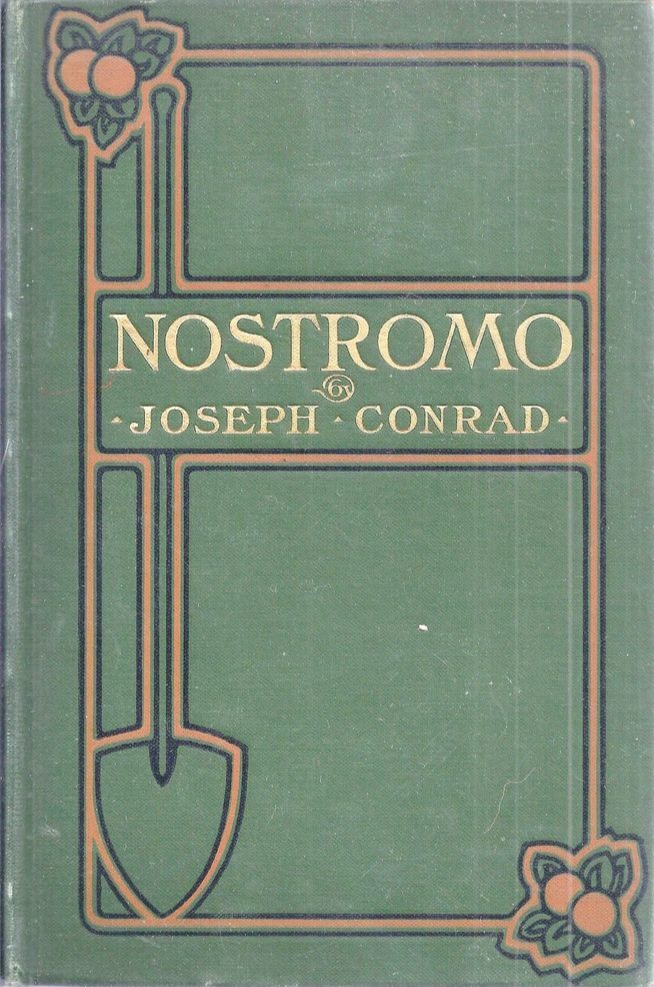 |
『ノストロモ: 海沿いの物語』は、ジョセフ・コンラッドによる1904年の小説で、架空の南米共和国「コスタグアナ」を舞台にしている。もともとはT.P.'s Weeklyに毎月連載された。 1998年、モダン・ライブラリーは20世紀の英語小説ベスト100の47位に『ノストロモ』を選んだ。F・スコット・フィッツジェラルドはかつて、「他のどの小説よりもノストロモを書きたかった」と語っている[1]。 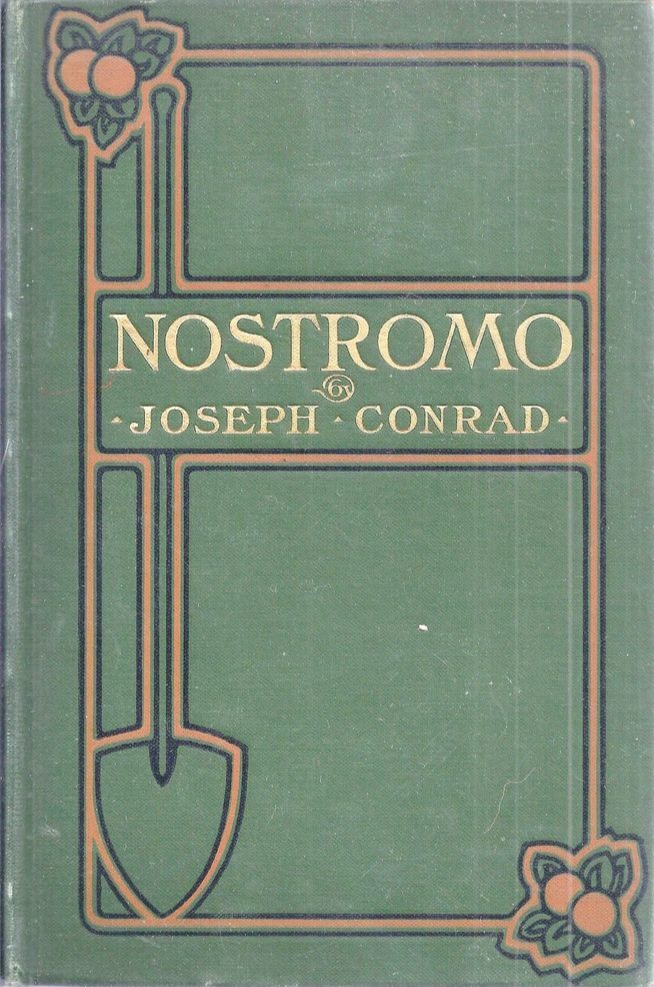 |
| Background Conrad set his novel in the town of Sulaco, a port in the western region of the imaginary country Costaguana. In his "Author's Note" to later editions of Nostromo, Joseph Conrad provides a detailed explanation of the inspirational origins of his novel. There he relates how, as a young man of about seventeen, while serving aboard a ship in the Gulf of Mexico, he heard the story of a man who had stolen, single-handedly, "a whole lighter-full of silver". As Conrad goes on to relate, he forgot about the story until some twenty-five years later when he came across a travelogue in a used-book shop in which the author related how he worked for years aboard a schooner whose master claimed to be that very thief who had stolen the silver.[2] |
背景 コンラッドは、架空の国コスタグアナの西部にある港、スラコの町を小説の舞台とした。 ジョセフ・コンラッドは『ノストロモ』後期版の「著者ノート」で、この小説の着想の起源について詳しく説明している。そこでは、17歳くらいの若者だった コンラッドが、メキシコ湾で船員をしていたときに、「ライター一杯の銀貨」をたった一人で盗んだ男の話を聞いたと述べている。その後、コンラッドはその話 を忘れていたが、25年後に古本屋でその旅行記を見つけ、その中で著者が銀を盗んだ泥棒を船主とするスクーナー船で何年も働いたことを語っている[2]。 |
| Plot summary Nostromo is set in the fictional South American country of Costaguana, and more specifically in that country's Occidental Province and its port city of Sulaco. Though Costaguana is a fictional nation, its geography as described in the book resembles real-life Colombia. Costaguana has a long history of tyranny, revolution and warfare, but has recently experienced a period of stability under the dictator Ribiera. Charles Gould is a native Costaguanero of English descent who owns an important silver-mining concession near the key port of Sulaco. He is tired of the political instability in Costaguana and its concomitant corruption, and uses his wealth to support Ribiera's government, which he believes will finally bring stability to the country after years of misrule and tyranny by self-serving dictators. Instead, Gould's refurbished silver mine and the wealth it has generated inspires a new round of revolutions and self-proclaimed warlords, plunging Costaguana into chaos. Among others, the forces of the revolutionary General Montero invade Sulaco after securing the inland capital. Gould, adamant that his silver mine should not become spoil for his enemies, orders Nostromo, the trusted "Capataz de Cargadores" (Head Longshoreman) of Sulaco, to take the mine's most recent load of silver offshore, and arranges for the mine complex to be destroyed by dynamite if the coup leaders try to take it. Nostromo is an Italian expatriate who has risen to his position through his bravery and daring exploits. ("Nostromo" is Italian for "shipmate" or "boatswain", but the name could also be considered a corruption of the Italian phrase "nostro uomo" or "nostr'uomo", meaning "our man"). Nostromo's real name is Giovanni Battista Fidanza —Fidanza meaning "trust" in archaic Italian. Nostromo is a commanding figure in Sulaco, respected by the wealthy Europeans and seemingly limitless in his abilities to command power among the local population. He is, however, never admitted to become a part of upper-class society, but is instead viewed by the rich as their useful tool. He is believed by Charles Gould and his own employers to be incorruptible, and it is for this reason that Nostromo is entrusted with removing the silver from Sulaco to keep it from the revolutionaries. Accompanied by the young journalist Martin Decoud, Nostromo sets off to smuggle the silver out of Sulaco. However, the lighter on which the silver is being transported is struck at night in the waters off Sulaco by a transport carrying the invading revolutionary forces under the command of Colonel Sotillo. Nostromo and Decoud manage to save the silver by putting the lighter ashore on Great Isabel. Decoud and the silver are deposited on the deserted island of Great Isabel in the expansive bay off Sulaco, while Nostromo scuttles the lighter and manages to swim back to shore undetected. Back in Sulaco, Nostromo's power and fame continues to grow as he daringly rides over the mountains to summon the army which ultimately saves Sulaco's powerful leaders from the revolutionaries and ushers in the independent state of Sulaco. In the meantime, left alone on the deserted island, Decoud eventually loses his mind. He takes the small lifeboat out to sea and there shoots himself, after first weighing his body down with some of the silver ingots so that he would sink into the sea. His exploits during the revolution do not bring Nostromo the fame he had hoped for, and he feels slighted and used. Feeling that he has risked his life for nothing, he is consumed by resentment, which leads to his corruption and ultimate destruction, for he has kept secret the true fate of the silver after all others believed it lost at sea. He finds himself becoming a slave of the silver and its secret, even as he slowly recovers it ingot by ingot during nighttime trips to Great Isabel. The fate of Decoud is a mystery to Nostromo, which combined with the fact of the missing silver ingots only adds to his paranoia. Eventually a lighthouse is constructed on Great Isabel, threatening Nostromo's ability to recover the treasure in secret. The ever resourceful Nostromo manages to have a close acquaintance, the widower Giorgio Viola, named as its keeper. Nostromo is in love with Giorgio's younger daughter, but ultimately becomes engaged to his elder daughter Linda. One night while attempting to recover more of the silver, Nostromo is shot and killed, mistaken for a trespasser by old Giorgio. |
プロットの概要 『ノストロモ』は南米の架空の国コスタグアナ、特に同国のオクシデンタル州とその港湾都市スラコが舞台である。コスタグアナは架空の国民だが、本書で描か れるそのナショナリズムは現実のコロンビアに似ている。コスタグアナには暴政、革命、戦乱の長い歴史があるが、最近は独裁者リビエラの下で安定期を迎えて いる。 チャールズ・グールドは英国系のコスタグアネーロ出身で、重要な港であるスラコ港の近くに重要な銀採掘権を所有している。彼はコスタグアナの政情不安とそ れに伴う腐敗に嫌気がさし、利己的な独裁者たちによる長年の悪政と暴政の末にようやく国に安定をもたらすと信じているリビエラ政権を支援するために自分の 富を使う。その代わり、グールドが改修した銀山とそれが生み出した富は、新たな革命と自称軍閥を刺激し、コスタグアナを混乱に陥れる。中でも革命家モンテ ロ将軍の軍は、内陸部の首都を確保した後、スラコに侵攻する。グールドは、自分の銀山を敵の戦利品にしてはならないと固く決意し、スラコの信頼厚い 「Capataz de Cargadores」(港湾労働者の頭目)であるノストロモに、鉱山の直近の積荷である銀を沖合に運ぶよう命じ、クーデター指導者たちが銀山を奪おうと した場合は、ダイナマイトで鉱山群を破壊するよう手配する。 ノストロモはイタリア人駐在員で、勇敢さと大胆な功績によってその地位に上り詰めた。(ノストロモ」はイタリア語で「船員」または「船頭」を意味するが、 イタリア語で「我々の男」を意味する「nostro uomo」または「nostr'uomo」の転訛とも考えられる)。ノストロモの本名はジョヴァンニ・バッティスタ・フィダンツァで、フィダンツァは古風 なイタリア語で「信頼」を意味する。 ノストロモは、スラコの有力者であり、裕福なヨーロッパ人たちから尊敬され、地元住民の権力を無限に握っているように見える。しかし、彼が上流社会の一員 になることを認められることはなく、富裕層からは便利な道具としてしか見られていない。ノストロモは、チャールズ・グールドと彼の雇い主たちから、彼は腐 敗しない(裏切らない?)と信じられており、そのためノストロモは、革命派から銀を守るため、スラコから銀を持ち出す仕事を任されている。ノストロモは若 いジャーナリスト、マルティン・デクーに連れられて、銀をスラコから密輸する旅に出る。しかし、銀を乗せたライターは夜、ソティロ大佐率いる革命軍を乗せ た輸送船によってスラコ沖で爆破される。ノストロモとドゥクーは、ライターをグレート・イザベルに陸揚げし、銀を救うことに成功する。ドゥクーと銀はスラ コ沖の広大な湾に浮かぶ無人島グレート・イザベルに沈められ、ノストロモはライターを捨て、気づかれないように泳いで岸に戻ることに成功する。スラコに戻 ると、ノストロモの権力と名声はますます高まり、彼は大胆にも山を越えて軍隊を召集し、最終的にスラコの有力指導者たちを革命派から救い、スラコ独立国家 の到来を告げる。一方、無人島にひとり取り残されたドゥクーは、やがて正気を失う。小さな救命艇で海に出て、海に沈むように銀のインゴットで体を重くした 後、そこで拳銃自殺を遂げる。 革命での活躍はノストロモに名声をもたらさず、彼は軽んじられ、利用されたと感じる。銀が海で失われたと誰もが信じた後、彼は銀の本当の運命を秘密にして きたのだ。夜のグレート・イザベルへの旅で銀を少しずつ回収しながらも、彼は銀とその秘密の奴隷と化していく。デクーの運命はノストロモにとって謎であ り、銀のインゴットの行方不明という事実と相まって、彼のパラノイアに拍車をかけている。やがてグレート・イザベルに灯台が建設され、ノストロモが秘密裏 に財宝を回収する能力が脅かされる。機知に富むノストロモは、親しい知人である男やもめのジョルジオ・ヴィオラを灯台守に任命することに成功する。ノスト ロモはジョルジオの若い娘と恋に落ちるが、最終的には彼の長女リンダと婚約する。ある夜、銀を取り戻そうとしていたノストロモは、ジョルジオ老人に不法侵 入者と間違われて射殺される。 |
| Major characters Nostromo (or Giovanni Battista Fidanza) – a charismatic Italian seaman who has settled in Sulaco and established a reputation for leadership and daring; as an employee of the Oceanic Steam Navigation Company, he earns the unofficial title of the "Capataz de Cargadores", or "Head Longshoreman" Charles "don Carlos" Gould, known as the "King of Sulaco" – an Englishman by ancestry and temperament, he is nevertheless a third generation Costaguanero; owner of the San Tomé Silver Mine, a bequest from his late father who was forced into ownership of the then derelict mine as repayment for many forced loans made to the corrupt government of Guzman Bento; the mine becomes his single-minded obsession Mrs. "dona Emilia" Gould – the English-born wife of Charles Gould; an altruistic and refined woman of strong will but who ultimately finds herself second to the mine in her husband's attentions Dr. Monygham – a misanthropic and taciturn English doctor and long-time resident of Costaguana; rumors swirl about him regarding his past involvement in political plots Martin Decoud – a Costaguanero who has spent much of his time in Paris and considers himself a European by temperament if not birth; he returns to Costaguana and becomes an outspoken journalist and editor of the progressive newspaper Porvenir ("The Future"); initially a cynic, he becomes the intellectual force behind the idea of independence for the Occidental Province of Costaguana; he is also in love with Antonia Avellanos Don José Avellanos – the patriarch of one of the most prominent families of Sulaco and a close confidant of Charles Gould; he suffered greatly under the dictatorship of Guzman Bento and now has complete allegiance to Gould Antonia Avellanos – a highly educated and cosmopolitan daughter of Don José; held in awe by the other young women of Sulaco Giorgio Viola – an exiled Italian revolutionary who once fought alongside Garibaldi but who is now an innkeeper in Sulaco and the father of two daughters Teresa Viola – the wife of Giorgio Viola Linda Viola – the eldest daughter of Teresa and Giorgio; she is in love with Nostromo Giselle Viola – the youngest daughter of Teresa and Giorgio Captain Joseph "Fussy Joe" Mitchell – the English Superintendent of the Oceanic Steam Navigation Company's offices in Sulaco and supervisor of Nostromo President don Vincente Ribiera – Costaguana's first civilian head of state, who takes over after the overthrow of the tyrannical Guzman Bento; a member of the landed aristocracy; corpulent to the point of infirmity; highly respected abroad and full of good intentions, and many of the characters, including Charles Gould, place their hopes in his ability to bring democracy and stability to Costaguana Guzman Bento – a former dictator of Costaguana whose death some years before the novel opens had ushered in a renewed period of political and economic instability; the period of his rule was a dark and bloody chapter in the history of Costaguana General Montero – an early supporter of Ribiera; a self-made man from peasant stock; he manages to muster an army of supporters to eventually overthrow Ribiera Pedro Montero – the younger brother of General Montero Senor Hirsch – a Jewish hide merchant who finds himself in Sulaco at the time of the political upheavals that comprise most of the novel Colonel Sotillo – the commander of a military unit in Esmeralda, up the coast from Sulaco; he abandons the Ribiera regime and joins the uprising of General Montero and is the first to arrive in Sulaco after the fall of the Ribiera government; his loyalties, however, are soon consumed by a mad desire to get hold of the silver of the San Tomé Mine Holroyd – wealthy American industrialist and financier of the San Tomé Mine Hernandez – leader of a gang of bandits Father Roman – Catholic Priest, chaplain to miners, former military padre, and Hernandez's "bandit chaplain" Father Corbelán – Catholic Priest, Don José's brother-in-law, and eventually Cardinal Archbishop of Sulaco General Barrios – commander of the military in the Occidental Province Don Pepe – the manager of the San Tomé Silver Mine under Charles Gould; under Gould's orders, he is prepared to blow up the mine rather than let if fall into the hands of the Montero forces |
主な登場人物 ノストロモ(またはジョバンニ・バッティスタ・フィダンツァ)-スラコに定住し、リーダーシップと大胆さで名声を確立したカリスマ的イタリア人船員。オー シャニック・スチーム・ナビゲーション・カンパニーの従業員として、「Capataz de Cargadores」(港湾労働者長)という非公式な称号を得る。 チャールズ・「ドン・カルロス」・グールド、「スラコの王 」として知られる。先祖も気質もイギリス人だが、コスタグアネーロの3世である。 グールド 「ドナ・エミリア 」夫人-チャールズ・グールドのイギリス生まれの妻。利他的で洗練された強い意志を持つ女性だが、夫の関心では結局、鉱山の次であることに気づく。 人間嫌いで寡黙なイギリス人医師で、コスタグアナに長年住んでいる。過去に政治的陰謀に関与したという噂が絶えない。 コスタグアナに戻り、率直なジャーナリストとなり、進歩的な新聞「ポルヴニール」(「未来」)の編集者となる。当初は皮肉屋だったが、コスタグアナ西州の独立のアイデアを支える知的勢力となる。アントニア・アヴェジャーノスと恋仲でもある。 ドン・ホセ・アベリャーノス - スラーコの名家の家長であり、チャールズ・グールドの側近。 アントニア・アヴェラーノス-ドン・ジョゼの娘で、高い教養と国際感覚を持ち、スラコの他の若い女性たちから畏敬の念を持たれている。 ジョルジョ・ヴィオラ:かつてガリバルディとともに戦った亡命イタリア人革命家だが、現在はスラコの宿屋の主人であり、2人の娘の父親でもある。 テレサ・ヴィオラ:ジョルジョ・ヴィオラの妻。 リンダ・ヴィオラ:テレサとジョルジョの長女で、ノストロモに恋している。 テレサとジョルジオの末娘。 ジョセフ・「うるさいジョー」・ミッチェル船長 - スラコにあるオーシャニック蒸気航行会社のイギリス人監督官で、ノストロモの監督でもある。 コスタグアナ初の文民国家元首で、専制的なグスマン・ベントの打倒後に就任する。地主貴族の一員で、病弱なほど太っているが、海外では高く評価されてお り、善意に満ちている。チャールズ・グールドを含む多くの登場人物は、コスタグアナに民主主義と安定をもたらす彼の能力に期待を寄せている。 グスマン・ベント-コスタグアナの元独裁者で、小説が始まる数年前に死去し、政治的・経済的に不安定な時代が再来した。彼の統治時代は、コスタグアナの歴史において暗く血なまぐさい章であった。 モンテロ将軍-リビエラの初期の支持者。農民出身の自営業者で、最終的にリビエラを打倒するために支持者の軍隊を集めることに成功する。 ペドロ・モンテロ-モンテロ将軍の弟。 セニョール・ハーシュ-ユダヤ系の皮商人で、小説の大部分を占める政変の時期にスラコに身を置く。 リビエラ政権を放棄し、モンテロ将軍の蜂起に加わり、リビエラ政権崩壊後、最初にスラコに到着する。 ホロイド-裕福なアメリカ人実業家であり、サン・トメ鉱山の出資者である。 エルナンデス - 盗賊団のリーダー ローマン神父 - カトリック司祭、鉱夫のチャプレン、元軍人神父、エルナンデスの「盗賊のチャプレン」。 コルベラン神父-カトリック司祭、ドン・ホセの義弟、やがてスラコの枢機卿大司教となる。 バリオス将軍-オクシデンタル州軍司令官 ドン・ペペ - チャールズ・グールドのもとでサン・トメ銀山の経営者。グールドの命令により、モンテロ軍の手に落ちるくらいなら鉱山を爆破する覚悟を決める。 |
| Adaptations and translations Fox Film produced a lavish silent film version in 1926 called The Silver Treasure directed by Rowland V. Lee and starring George O'Brien. It is now a lost film. In 1991, British director David Lean was to film the story of Nostromo, with Steven Spielberg producing it for Warner Bros., but Lean died a few weeks before the principal photography was to begin in Almería. Marlon Brando, Paul Scofield, Peter O'Toole, Isabella Rossellini, Christopher Lambert and Dennis Quaid had all been set to star in this adaptation, along with Georges Corraface in the title role.[citation needed] In 1996, a television adaptation Nostromo was produced. It was adapted by John Hale and directed by Alastair Reid for the BBC, Radiotelevisione Italiana, Televisión Española, and WGBH Boston. It starred Claudio Amendola as Nostromo, and Colin Firth as Señor Gould.[3] The novel was translated to Polish for the first time in 1928 by Stanisław Wyrzykowski [pl]. It received several other translations to Polish: in 1972 by Jadwiga Korniłowiczowa [pl], in 1981 by Jan Józef Szczepański and in 2023 by Maciej Świerkocki [pl].[4] |
翻案と翻訳 フォックス・フィルムは1926年、ローランド・V・リー監督、ジョージ・オブライエン主演の『銀の宝玉』という豪華なサイレント映画版を製作した。この作品は現在では失われている。 1991年、イギリスのデヴィッド・リーン監督が『ノストロモ号』の物語を映画化し、スティーブン・スピルバーグがワーナー・ブラザースのためにプロ デュースする予定だったが、リーンはアルメリアでの主要撮影が始まる数週間前に亡くなった。マーロン・ブランド、ポール・スコフィールド、ピーター・オ トゥール、イザベラ・ロッセリーニ、クリストファー・ランバート、デニス・クエイドが、タイトルロールのジョルジュ・コラフェイスとともに、この映画化作 品に出演することが決まっていた[要出典]。 1996年、テレビドラマ化された『Nostromo』が製作された。ジョン・ヘイルが脚色し、アラステア・リードが監督を務め、BBC、イタリア国営放 送、スペイン国営放送、WGBHボストンで放映された。主演はノストロモ役のクラウディオ・アメンドーラとセニョール・グールド役のコリン・ファースだっ た[3]。 この小説は1928年にスタニスワフ・ウィルコフスキによって初めてポーランド語に翻訳された[pl]。1972年にヤドヴィガ・コルニウォヴィツォワ (Jadwiga Korniłowiczowa)[pl]、1981年にヤン・ヨゼフ・シュチェパンスキ(Jan Józef Szczepański)、2023年にマチェイ・シュヴィエルコツキ(Maciej Świerkocki)[pl]によって翻訳された[4]。 |
| Andrew Greeley's novel Virgin
and Martyr (1985) has much of the story set in the fictional country of
Costaguana. Many of the place names are borrowed from Conrad's novel. In Ridley Scott's Alien (1979), the spacecraft is named the Nostromo; the escape vessel is named Narcissus, an allusion to another of Conrad's works, The Nigger of the "Narcissus". In James Cameron's sequel Aliens (1986), the Marine transport vessel is named Sulaco.[5] Furthermore, appearing in the video game Aliens: Colonial Marines, a vessel of the same class as the Sulaco is named the Sephora, a reference to Conrad's The Secret Sharer. In Dean Koontz's novel Fear Nothing (1998), the protagonist Christopher Snow visits a man named Roosevelt Frost, who lives aboard a boat named Nostromo. In the Warhammer 40,000 science fantasy franchise, "Nostramo" ("nostramo" is Catalan for "nostromo", "shipmate" or "boatswain"), is the name of a corruption-ridden city world covered in unending darkness. Nostramo eventually falls under control of a brutal serial killer demigod named Konrad Curze, an allusion to the name of a central character in Conrad's novella Heart of Darkness, later used by Francis Ford Coppola as the base for the film Apocalypse Now. Colombian writer Juan Gabriel Vásquez's novel The Secret History of Costaguana (2007) narrates the secession of Panamá from Colombia as the background story that (in this fictional work) served as Conrad's inspiration for Nostromo. In the USA Network series Colony, the fighters of the Resistance use copies of the book as a decoder key for their encrypted communications.[6] The travel writer John Gimlette suggests in his At the Tomb of the Inflatable Pig: Travels through Paraguay (2003) that there are many similarities to Paraguay and its 19th-century history of despotism, war, and revolution: "Conrad, meanwhile, was absorbing the Paraguayan story. His nightmarish political novel, Nostromo, emerged in 1904. It is Paraguay, seen through the prisms of his great friend's [Robert Bontine Cunninghame Graham] anger – Napoleonic dictators and a Great Conspiracy. There is even 'a barefoot army of scarecrows' and a priest who becomes the state torturer." Graham arrived in Paraguay in 1873 and wrote many books on it. |
アンドリュー・グリーリーの小説『聖母と殉教者』(1985年)は、物語の大部分が架空の国コスタグアナを舞台にしている。地名の多くはコンラッドの小説から借用されている。 リドリー・スコット監督の『エイリアン』(1979年)では、宇宙船は「ノストロモ号」と名付けられ、脱出船はコンラッドの別の作品『ナルシス号のニ ガー』からの連想で「ナルシス号」と名付けられた。ジェームズ・キャメロン監督の続編『エイリアン』(1986年)では、海兵隊の輸送船は「スラコ」と名 付けられている[5]。さらに、ビデオゲーム『エイリアン:コロニアル海兵隊』に登場する「スラコ」と同型の船は「セフォラ」と名付けられ、コンラッドの 『秘密の共有者』への引用となっている。 ディーン・クーンツの小説『Fear Nothing』(1998年)では、主人公クリストファー・スノーがノストロモ号という名の船に乗るルーズベルト・フロストという男を訪ねている。 ウォーハンマー40,000のサイエンス・ファンタジー・フランチャイズでは、「ノストラモ」(「ノストラモ 」はカタロニア語で 「船員 」または 「船頭 」を意味する)は、果てしない闇に覆われた腐敗にまみれた都市世界の名前である。ノストラモは最終的に、コンラート・クルゼという名の残忍な連続殺人鬼の 半神の支配下に入るが、これはコンラートの小説『闇の奥』の中心人物の名前にちなんだもので、後にフランシス・フォード・コッポラが映画『アポカリプス・ ナウ』のベースとして使用した。 コロンビアの作家フアン・ガブリエル・バスケスの小説『コスタグアナの秘史』(2007年)は、(この架空の作品において)コンラッドが『ノストロモ』の着想を得た背景として、パナマのコロンビアからの分離独立を描いている。 USAネットワークのシリーズ『コロニー』では、レジスタンスの戦士たちが暗号化された通信のデコーダーキーとしてこの本のコピーを使用している[6]。 旅行作家のジョン・ジムレットは、『膨張する豚の墓にて:パラグアイ旅行記』(2003年)の中で、パラグアイとその専制政治、戦争、革命の19世紀の歴 史には多くの類似点があると示唆している: 「一方、コンラッドはパラグアイの物語を吸収していた。彼の悪夢のような政治小説『ノストロモ』は1904年に発表された。それは彼の偉大な友人[ロバー ト・ボンタイン・カニンガム・グラハム]の怒りのプリズムを通して見たパラグアイであり、ナポレオンの独裁者と大いなる陰謀である。裸足のかかし軍団」 や、国の拷問官となった司祭まで登場する。グラハムは1873年にパラグアイに到着し、パラグアイについて多くの本を書いた。 |
| Bibliography Thomas L. Jeffers, "The Logic of Material Interests in Conrad's Nostromo", Raritan (Fall 2003), pp. 80–111. |
参考文献 Thomas L. Jeffers, 「The Logic of Material Interests in Conrad's Nostromo」, Raritan (Fall 2003), pp. |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Nostromo |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆