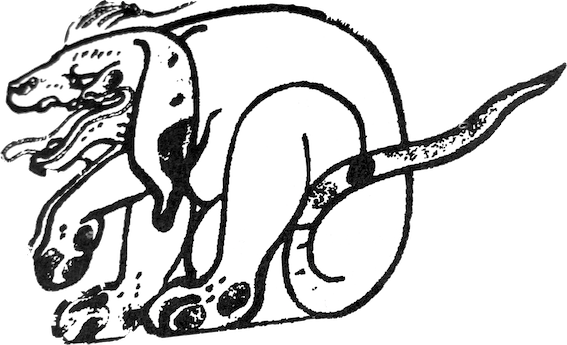
野生の思考
La Pensée sauvage, 1962
☆『野生の思考』は、クロード・レヴィ=ストロースによるエッセイであり、1962年にプロン社から初めて出版された。
| La Pensée sauvage est un essai de Claude Lévi-Strauss publié pour la première fois en 1962 chez Plon. |
『野生の思考』は、クロード・レヴィ=ストロースによるエッセイであり、1962年にプロン社から初めて出版された。 |
| Thématique En utilisant le thème de l'ethnologie traditionnelle, l'auteur cherche à décrire les mécanismes de la pensée en tant qu'attribut universel de l'esprit humain. Pour lui, la pensée sauvage est présente en tout homme tant qu'elle n'a pas été cultivée et domestiquée à « fins de rendement ». Par l'utilisation de l'idée de rendement, il met en opposition l'utilité immédiate de la science et des connaissances dont a besoin la communauté pour se reproduire, avec une forme de pensée adaptée aux besoins sociaux ou de productivité des sociétés modernes. La pensée sauvage, « bricoleuse », associe les événements aux structures ; la pensée moderne, « ingénieuse », part de la structure pour créer l'événement. Partant de ce principe, l'évocation de thèmes tels que la science, la culture, les totems et castes, ou encore les « Catégories, Éléments, Espèces et Nombres », appuyés par de nombreuses références ethnologiques issues de l'étude de peuples primitifs variés, sont autant de moyens d'illustrer le fonctionnement de la pensée chez l'homme primitif. Mais sous ce travail ethnologique minutieux, se dissimule en réalité une tentative de démonstration que peu de chose démarque la pensée du « sauvage » de celle du « civilisé ». Qu'il est erroné d'affirmer que la différence entre la pensée primitive et la pensée moderne résiderait dans la capacité de cette dernière à appréhender la complexité ou des phénomènes complexes. Les deux premiers chapitres intitulés « La Science du Concret » et « La Logique des Classifications Totémiques » cherchent à convaincre le lecteur de cette universalité de la pensée, et surtout de l'uniformité des capacités intellectuelles et conceptuelles des hommes quel que soit leur degré de civilisation. Le livre tente aussi de démontrer la relativité d'une supposée supériorité de la science des civilisés sur celle des archaïques. Ainsi, en nous expliquant dans le premier chapitre qu'il existe une science autre mais non moindre dans les sociétés dites primitives, mais dont la construction est empirique (contrairement à la science moderne, expérimentale mais aussi largement spéculative et théorique), l'auteur nous démontre que la science n'est pas l'apanage du moderne, mais qu'elle fait partie de l'histoire des hommes depuis des temps immémoriaux. À la suite, en nous présentant des systèmes de classification totémique dont l'existence est incontestablement archaïque, il nous prouve que le désir de classification du vivant et plus généralement de tout ce qui constitue l'univers des hommes (jusqu'aux concepts), ne correspond pas à une capacité des civilisations antiques (par exemple les systèmes de mémorisation de Cicéron), ou même modernes (systématique de Carl von Linné, combinatoire de Gottfried Wilhelm Leibniz, ou encore travaux de Francis Bacon), mais qu'il existe sans aucun doute chez les peuples de tous continents des systèmes évolués de classification et de combinaisons. Il s'achève par un chapitre consacré à une discussion d'un livre de Jean-Paul Sartre (Critique de la raison dialectique I), dont il conteste le regard sur certains fondements philosophiques de l'anthropologie. |
テーマ 伝統的な民族学のテーマを用いて、著者は人間の精神の普遍的な属性としての思考のメカニズムを説明しようとしている。彼にとって、野生の思考は、「生産性 の目的」のために培われ、飼いならされるまでは、すべての人間に存在するものである。生産性という概念を用いて、彼は、コミュニティが存続するために必要 な科学や知識の即時の有用性と、現代社会の社会的ニーズや生産性に適応した思考形態とを対比させている。野生の思考、つまり「手先が器用な」思考は、出来 事を構造と結びつける。一方、現代の思考、つまり「創意工夫に富んだ」思考は、構造から出発して出来事を創り出す。 この原則に基づき、科学、文化、トーテムやカースト、あるいは「カテゴリー、要素、種、数」といったテーマが、様々な原始民族の研究から得られた数多くの 民族学的参考資料とともに取り上げられ、原始人の思考のしくみを説明するための手段となっている。しかし、この綿密な民族学的研究の背後には、実際には、 「野蛮人」の思考と「文明人」の思考の間にほとんど違いがないことを証明しようとする試みが隠されている。原始的な思考と現代的な思考の違いは、後者が複 雑さや複雑な現象を理解する能力にあると主張するのは誤りだということだ。 最初の2つの章「具体性の科学」と「トーテム分類の論理」は、思考の普遍性、そして何よりも、文明の程度に関わらず、人間の知的・概念的能力は均一である ことを読者に納得させようとしている。また、この本は、文明化された人々の科学が原始的な人々の科学よりも優れているという仮定の相対性を示すことも試み ている。 したがって、第1章で、いわゆる原始社会にも、現代科学とは異なるとはいえ、その構築が経験的である(実験的であると同時に、大部分が推測的かつ理論的で ある現代科学とは対照的である)別の科学が存在することを説明することで、著者は、科学は現代の専売特許ではなく、太古の昔から人類の歴史の一部であるこ とを示している。 続いて、紛れもなく古代に存在したトーテム分類体系を紹介することで、生物、そしてより一般的には人間の宇宙を構成するあらゆるもの(概念に至るまで)を 分類したいという欲求は、古代文明(例えばキケロの記憶術)や あるいは現代文明(カール・フォン・リンネの分類法、ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツの組み合わせ論、フランシス・ベーコンの研究など)の能 力によるものではないことを証明している。むしろ、あらゆる大陸の人々に、高度な分類と組み合わせの体系が確かに存在していたことを示しているのだ。 この本は、ジャン=ポール・サルトルの著書(『弁証法的理性の批判 I』)に関する議論を扱った章で終わっている。著者は、この本(弁証法的理性の批判 )の人類学の哲学的基礎に関する見解に異議を唱えている。 |
| Influence Publié dans les années 60, La Pensée Sauvage est devenu un classique de l'ethnologie. Par ailleurs son influence sur les sciences humaines et sociales est aujourd'hui considérée comme décisive. L'anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro estime qu'« en forgeant le concept fondamental de “pensée sauvage”, [Lévi-Strauss] a montré que science, philosophie, art, religion, mythologie, magie, etc. se déploient en réalité sur un même axe, celui de la connaissance humaine »[1]. André Comte-Sponville affirme quant à lui que dans son débat avec Sartre, Lévi-Strauss a retrouvé les termes du conflit entre Descartes et Spinoza : « Le sujet est-il ce dont il faut partir (Descartes, Sartre), ou l'illusion dont il faut se déprendre (Spinoza) »[2]. |
影響 1960年代に出版された『野生の思考』は、民族学の古典となった。また、人文社会科学への影響は、今日では決定的なものと見なされている。ブラジル人人 類学者エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロは、「『野生の思考』という基本概念を打ち立てたことで、[レヴィ=ストロース]は、科学、哲学、芸 術、宗教、神話、魔術などが、実際には人間の知識という同じ軸上で展開していることを示した」[1]と評価している。アンドレ・コント=スポンヴィルは、 サルトルとの議論の中で、レヴィ=ストロースがデカルトとスピノザの対立の論点を再発見したと述べている。「主体は出発点となるもの(デカルト、サルト ル)なのか、それとも脱却すべき幻想(スピノザ)なのか」[2]。 |
| Épigraphe « Il n'y a rien au monde que les Sauvages, les paysans et les gens de province pour étudier à fond leurs affaires dans tous les sens ; aussi quand ils arrivent de la Pensée au Fait, trouvez-vous les choses complètes. » (Honoré de Balzac, Le Cabinet des Antiques) |
エピグラフ 「世の中には、野蛮人や農民、田舎者ほど、あらゆる角度から自分のことを徹底的に研究する者たちはいない。だから、彼らが思考から行動に移ったときには、物事はすでに完成しているのだ。」(オノレ・ド・バルザック『骨董品店』より) |
| Notes et références 1. « Il a montré l'universalité de la raison », Books, n°1, décembre 2008 janvier 2009, p. 53. 2. Documentaire Réflexions faites, https://www.youtube.com/watch?v=0hStPQRsW7Y [archive] Vidéo non disponible |
注釈と参考文献 1. 「彼は理性の普遍性を示した」、Books、第1号、2008年12月~2009年1月、53ページ。 2. ドキュメンタリー『Réflexions faites』、https://www.youtube.com/watch?v=0hStPQRsW7Y [アーカイブ] ビデオは利用不可 |
| https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Pens%C3%A9e_sauvage | |
| The
Savage Mind (French: La Pensée sauvage), also translated as Wild
Thought, is a 1962 work of structural anthropology by the
anthropologist Claude Lévi-Strauss. |
『野生の思考』(原題:La Pensée sauvage)は、人類学者クロード・レヴィ=ストロースによる1962年の構造人類学の著作である。 |
| Summary "The Savage Mind" Lévi-Strauss makes clear that "la pensée sauvage" refers not to the discrete mind of any particular type of human, but rather to 'untamed' human thought: "In this book it is neither the mind of savages nor that of primitive or archaic humanity, but rather mind in its untamed state as distinct from mind cultivated or domesticated for the purpose of yielding a return."[1] Savage thought, Lévi-Strauss argues, continually gathers and applies structures wherever they can be used. If scientific thought is represented by the engineer who asks a question and tries to design an optimal or complete solution, savage thought resembles the bricoleur, who constructs things using whatever materials are at hand. One of Lévi-Strauss's many examples is the relationship between two Australian groups, the Aranda and the Arabanna. The Aranda have a complex system for intermarriages that divides all people into two groups and then four stages within each group. The system specifies where the children will live and how they will marry. The Arabanna use a different system for marriages, but somehow use the Aranda's marriage system for determining the sex and affiliation of reincarnated spirits. The structure has been borrowed and transposed, appropriated because of its ability to generate a certain economy independently of its substrate. |
要約 「野生の思考」 レヴィ=ストロースは「ラ・パンセ・ソヴァージュ」が特定の人類の個別の思考を指すのではなく、「飼いならされていない」人間の思考を指すことを明確にし ている。「本書においてそれは野蛮人の思考でも、原始的あるいは古風な人類の思考でもない。むしろ、利益を得る目的で培われたり飼いならされたりする思考 とは異なる、飼いならされていない状態の思考である」[1] レヴィ=ストロースによれば、野蛮的思考は利用可能な構造を絶えず収集し適用する。科学的思考が問題提起し最適解や完全解を設計しようとする技術者に例えられるなら、野蛮的思考は手近な材料で物を作るブリコルールに似ている。 レヴィ=ストロースが挙げる数多くの事例の一つが、オーストラリアの二部族、アランダ族とアラバンナ族の関係である。アランダ族は複雑な婚姻制度を持ち、 全人口を二つの集団に分け、さらに各集団内で四つの段階を設けている。この制度は子供の居住地や結婚相手を規定する。一方アラバンナ族は異なる婚姻制度を 用いるが、なぜか転生した精霊の性別や所属を決定する際にはアランダ族の婚姻制度を利用している。この構造は借用され転用されたのだ。基盤とは独立して特 定の経済性を生み出す能力ゆえに、流用されたのである。 |
| Critique of totemism Lévi-Strauss (continuing the argument from Totemism, his previous work) criticizes the concept of totemism for arbitrarily prioritizing a particular structural relation. He admits the reality of totemism, in which, within a larger group, smaller groups distinguish themselves through identification with a plant or animal. He denies, however, that totemic societies differ fundamentally from societies that divide people on the basis of caste. Totems, he argues, are just another way to create necessary distinctions within a larger group. These distinctions may have greater or lesser practical significance, but ultimately:[2] Totemism, which has been rendered amply formal in 'primitive language', could at the cost of a very simple transformation equally well be expressed in the language of the regime of castes which is quite the reverse of primitive. This is already sufficient to show that we are here dealing not with an autonomous institution, which can be defined by its distinctive properties and is typical of certain regions of the world and certain forms of civilization but with a modus operandi which can be discerned even behind social structures traditionally defined in a way diametrically opposed to totemism. In other words, the operation of identifying with a totem is secondary to the underlying process of re-appropriating structure (for example, observed differences between animals) for the purposes of society. |
トーテミズム批判 レヴィ=ストロース(前著『トーテミズム』の議論を継続して)は、特定の構造的関係を恣意的に優先させるとしてトーテミズムの概念を批判する。彼は、より 大きな集団の中で、より小さな集団が植物や動物との同一化によって自己を区別するトーテミズムの現実を認める。しかし、トーテミックな社会がカーストに基 づいて人々を分ける社会と根本的に異なるという主張は否定する。トーテムとは、より大きな集団内で必要な区別を生み出すための、単なる別の方法に過ぎない と彼は主張する。これらの区別は実用的な重要性が大小あれど、結局のところ:[2] 「原始言語」において十分に形式化されたトーテミズムは、ごく単純な変換を代償に、原始とは正反対のカースト制度の言語で同様に表現しうる。これはすで に、我々がここで扱っているものが、その特徴的な性質によって定義され、世界の特定の地域や文明形態に典型的な自律的な制度ではなく、トーテミズムとは正 反対の方法で伝統的に定義されてきた社会構造の背後にも見出せる作用様式であることを示すのに十分である。 言い換えれば、トーテムとの同一視という操作は、社会のために構造(例えば、動物間の観察された差異)を再利用するという根底にあるプロセスに次ぐ二次的なものである。 |
| English translation The English translation of The Savage Mind appeared in 1966. However, the anthropologist Clifford Geertz called the translation "execrable" and insisted on using his own translations from the French edition.[3] A new translation by Jeffrey Mehlman and John Leavitt was published under the title Wild Thought in 2021.[4] |
『野生の思考』の英語(John
Weightman)訳は1966年に刊行された。しかし人類学者クリフォード・ギアーツはこの訳を「ひどい」と評し、フランス語版からの自身の訳を用い
ることを主張した[3]。ジェフリー・メルマンとジョン・リーヴィットによる新たな訳は2021年、『ワイルド・ソート(Wild
Thought)』のタイトルで出版された[4]。 |
| Reception The Savage Mind was one of the earliest works of structural anthropology and had a large influence on the field of anthropology. The book also played a role within the larger currents of structuralism and post-structuralism. The application of bricolage to social structure provided the inspiration for the philosopher Jacques Derrida's essay "Structure, Sign and Play".[5] The idea that social structures can be transposed and recontextualized also plays a large role in the philosopher Gilles Deleuze and the psychoanalyst Félix Guattari's Capitalism and Schizophrenia.[6] |
受容 『野生の思考』は構造人類学の初期の著作の一つであり、人類学の分野に大きな影響を与えた。 この本は、構造主義とポスト構造主義というより大きな潮流の中でも役割を果たした。社会構造へのブリコラージュの応用は、哲学者ジャック・デリダの論文 『構造、記号、遊び』の着想源となった[5]。社会構造が転置され再文脈化され得るという考え方は、哲学者ジル・ドゥルーズと精神分析学者フェリックス・ ガタリの『資本主義と統合失調症』においても重要な役割を果たしている[6]。 |
| References 1. Lévi-Strauss, Claude (1966). The Savage Mind. Chicago, Illinois: University of Chicago Press. p. 219. ISBN 0-226-47484-4. OCLC 491441. 2. Lévi-Strauss, Claude (1966). The Savage Mind. Chicago, Illinois: University of Chicago Press. p. 129. ISBN 978-0-226-47484-7. OCLC 491441. 3. Geertz, Clifford (1973). The Interpretation of Cultures. Basic Books. p. 351 (note 2). ISBN 9780465097197. 4. Lévi-Strauss, Claude (2021). Wild Thought: A New Translation of "La Pensée sauvage". Translated by Mehlman, Jeffrey; Leavitt, John. Chicago, Illinois: University of Chicago Press. ISBN 9780226413082. OCLC 1232713622. 5. Derrida, Jacques (1980). Writing and Difference. Translated by Bass, Alan. Chicago, Illinois: University of Chicago Press. ISBN 9780226143293. 6. Deleuze, Gilles; Guattari, Félix (1983). Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Translated by Hurley, Robert; Seem, Mark; Lane, Helen R. Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press. ISBN 9780816612253. |
参考文献 1. レヴィ=ストロース, クロード (1966). 『野生の思考』. イリノイ州シカゴ: シカゴ大学出版局. p. 219. ISBN 0-226-47484-4. OCLC 491441. 2. レヴィ=ストロース, クロード (1966). 『野生の思考』. イリノイ州シカゴ: シカゴ大学出版局. p. 129. ISBN 978-0-226-47484-7. OCLC 491441. 3. クリフォード・ギアーツ (1973). 『文化の解釈』. ベーシック・ブックス. p. 351 (注2). ISBN 9780465097197. 4. レヴィ=ストロース、クロード(2021)。『野生の思考:「ラ・パンセ・ソヴァージュ」新訳』。ジェフリー・メルマン、ジョン・リーヴィット訳。イリノイ州シカゴ:シカゴ大学出版局。ISBN 9780226413082。OCLC 1232713622。 5. ジャック・デリダ (1980). 『書かれと差異』. アラン・バス訳. イリノイ州シカゴ: シカゴ大学出版局. ISBN 9780226143293. 6. ドゥルーズ、ジル; ガタリ、フェリックス (1983). 『アンチ・オイディプス:資本主義と分裂症』. ハーリー、ロバート; シーム、マーク; レーン、ヘレン・R 訳. ミネアポリス、ミネソタ州: ミネソタ大学出版局. ISBN 9780816612253. |
| https://en.wikipedia.org/wiki/The_Savage_Mind |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099