Ideas
In his book The Condition of Man, published in 1944, Mumford
characterized his orientation toward the study of humanity as "organic
humanism." The term is important because it sets limits on human
possibilities, limits that are aligned with the nature of the human
body. Mumford never forgot the importance of air quality, of food
availability, of the quality of water, or the comfort of spaces,
because all these elements had to be respected if people were to
thrive. Technology and progress could never become a runaway train in
his reasoning, so long as organic humanism was there to act as a brake.
Indeed, Mumford considered the human brain from this perspective,
characterizing it as hyperactive, a good thing in that it allowed
humanity to conquer many of nature's threats, but potentially a bad
thing if it were not occupied in ways that stimulated it meaningfully.
Mumford's respect for human "nature", that is to say, the natural
characteristics of being human, provided him with a platform from which
to assess technologies, and techniques in general. Thus his criticism
and counsel with respect to the city and with respect to the
implementation of technology was fundamentally organized around the
organic humanism to which he subscribed. It was from the perspective of
organic humanism that Mumford eventually launched a critical assessment
of Marshall McLuhan, who argued that the technology, not the natural
environment, would ultimately shape the nature of humankind, a
possibility that Mumford recognized, but only as a nightmare scenario.
Mumford believed that what defined humanity, what set human beings
apart from other animals, was not primarily our use of tools
(technology) but our use of language (symbols). He was convinced that
the sharing of information and ideas amongst participants of primitive
societies was completely natural to early humanity, and had obviously
been the foundation of society as it became more sophisticated and
complex. He had hopes for a continuation of this process of information
"pooling" in the world as humanity moved into the future.[13]
Mumford's choice of the word "technics" throughout his work was
deliberate. For Mumford, technology is one part of technics. Using the
broader definition of the Greek tekhne, which means not only technology
but also art, skill, and dexterity, technics refers to the interplay of
social milieu and technological innovation—the "wishes, habits, ideas,
goals" as well as "industrial processes" of a society. As Mumford
writes at the beginning of Technics and Civilization, "other
civilizations reached a high degree of technical proficiency without,
apparently, being profoundly influenced by the methods and aims of
technics."
Megatechnics
In The Myth of the Machine Vol II: The Pentagon of Power (Chapter 12)
(1970), Mumford criticizes the modern trend of technology, which
emphasizes constant, unrestricted expansion, production, and
replacement. He contends that these goals work against technical
perfection, durability, social efficiency, and overall human
satisfaction. Modern technology, which he called "megatechnics," fails
to produce lasting, quality products by using devices such as consumer
credit, installment buying, non-functioning and defective designs,
planned obsolescence, and frequent superficial "fashion" changes.
"Without constant enticement by advertising," he writes, "production
would slow down and level off to normal replacement demand. Otherwise
many products could reach a plateau of efficient design which would
call for only minimal changes from year to year."
He uses his own refrigerator as an example, reporting that it "has been
in service for nineteen years, with only a single minor repair: an
admirable job. Both automatic refrigerators for daily use and
deepfreeze preservation are inventions of permanent value. ... [O]ne
can hardly doubt that if biotechnic criteria were heeded, rather than
those of market analysts and fashion experts, an equally good product
might come forth from Detroit, with an equally long prospect of
continued use."
Biotechnics
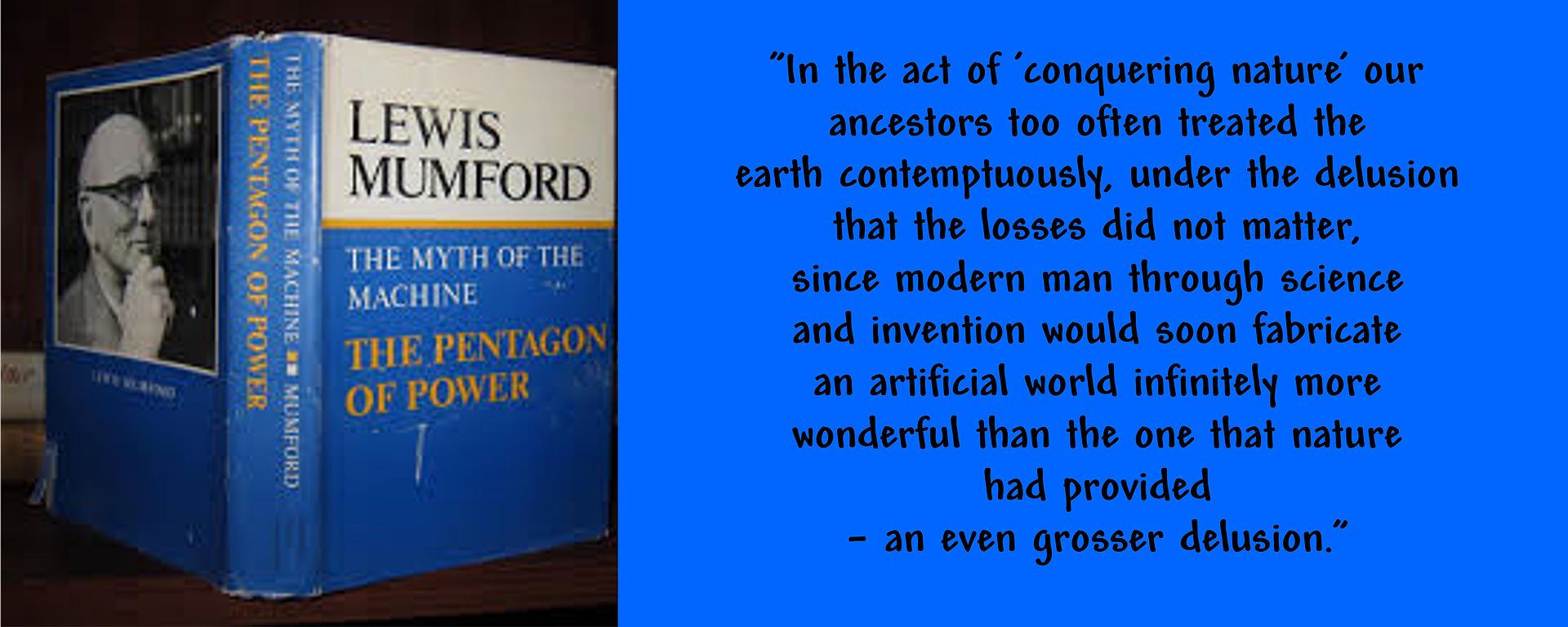
The Pentagon of Power picture and a quote from it.
Mumford was deeply concerned with the relationship between techniques
and bioviability. The latter term, not used by Mumford, characterizes
an area's capability to support life. Before the advent of technology,
most areas of the planet were bioviable at some level or other;
however, where certain forms of technology advance rapidly,
bioviability decreases dramatically. Slag heaps, poisoned waters,
parking lots, and concrete cities, for example, are extremely limited
in terms of their bioviability. Non-bioviable regions are common in
cinema in the form of dystopias (e.g., Blade Runner). Mumford did not
believe it was necessary for bioviability to collapse as technology
advanced, however, because he held it was possible to create
technologies that functioned in an ecologically responsible manner, and
he called that sort of technology biotechnics.[14] Mumford believed
that biotechnic consciousness (and possibly even community) was
emerging as a later stage in the evolution of Darwinian thinking about
the nature of human life. He believed this was the sort of technology
needed to shake off the suicidal drive of "megatechnics." While Mumford
recognized an ecological consciousness that traces back to the earliest
communities, he regarded emerging biotechnics as a product of
neo-Darwinian consciousness, as a post-industrial form of thinking, one
that refuses to look away from the mutually-influencing relationship
between the state of the living organism and the state of its
environment. In Mumford's mind, the society organized around
biotechnics would restrain its technology for the sake of that integral
relationship.
In Mumford's understanding, the various technologies that arose in the
megatechnic context have brought unintended and harmful side effects
along with the obvious benefits they have bequeathed to us. He points
out, for example, that the development of money (as a technology)
created, as a side effect, a context for irrational accumulation of
excess because it eliminated the burdensome aspects of object-wealth by
making wealth abstract. In those eras when wealth was not abstract,
plenitude had functioned as the organizing principle around its
acquisition (i.e., wealth, measured in grains, lands, animals, to the
point that one is satisfied, but not saddled with it). Money, which
allows wealth to be conceived as pure quantity instead of quality, is
an example of megatechnics, one which can spiral out of control. If
Mumford is right in this conceptualization, historians and economists
should be able to trace a relationship between the still-increasing
abstraction of wealth and radical transformations with respect to
wealth's distribution and role. And, indeed, it does appear that,
alongside its many benefits, the movement toward electronic money has
stimulated forms of economic stress and exploitation not yet fully
understood and not yet come to their conclusion. A technology for
distributing resources that was less given to abstract hoarding would
be more suitable to a biotechnic conception of living.
Thus Mumford argued that the biotechnic society would not hold to the
megatechnic delusion that technology must expand unceasingly,
magnifying its own power and would shatter that delusion in order to
create and preserve "livability." Rather than the megatechnic pursuit
of power, the biotechnic society would pursue what Mumford calls
"plenitude"; that is, a homeostatic relationship between resources and
needs. This notion of plenitude becomes clearer if we suggest that the
biotechnic society would relate to its technology in the manner an
animal relates to available food–under circumstances of natural
satisfaction, the pursuit of technological advance would not simply
continue "for its own sake."
Alongside the limiting effect of satisfaction amidst plenitude, the
pursuit of technological advance would also be limited by its
potentially negative effects upon the organism. Thus, in a biotechnic
society, the quality of air, the quality of food, the quality of water,
these would all be significant concerns that could limit any
technological ambitions threatening to them. The anticipated negative
value of noise, radiation, smog, noxious chemicals, and other technical
by-products would significantly constrain the introduction of new
technical innovation. In Mumford's words, a biotechnic society would
direct itself toward "qualitative richness, amplitude, spaciousness,
and freedom from quantitative pressures and crowding. Self-regulation,
self-correction, and self-propulsion are as much an integral property
of organisms as nutrition, reproduction, growth, and repair." The
biotechnic society would pursue balance, wholeness, and completeness;
and this is what those individuals in pursuit of biotechnics would do
as well.
Mumford's critique of the city and his vision of cities that are
organized around the nature of human bodies, so essential to all
Mumford's work on city life and urban design, is rooted in an incipient
notion of biotechnics: "livability," a notion which Mumford got from
his mentor, Patrick Geddes.
Mumford used the term biotechnics in the later sections of The Pentagon
of Power, written in 1970. The term sits well alongside his early
characterization of "organic humanism," in that biotechnics represent
the concrete form of technique that appeals to an organic humanist.
When Mumford described biotechnics, automotive and industrial pollution
had become dominant technological concerns, along with the fear of
nuclear annihilation. Mumford recognized, however, that technology had
even earlier produced a plethora of hazards, and that it would do so
into the future. For Mumford, human hazards are rooted in a
power-oriented technology that does not adequately respect and
accommodate the essential nature of humanity. Mumford is stating
implicitly, as others would later state explicitly, that contemporary
human life understood in its ecological sense is out of balance because
the technical parts of its ecology (guns, bombs, cars, drugs) have
spiraled out of control, driven by forces peculiar to them rather than
constrained by the needs of the species that created them. He believed
that biotechnics was the emerging answer and the only hope that could
be set out against the problem of megatechnics. It was an answer, he
believed, that was already beginning to assert itself in his time.
It is true that Mumford's writing privileges the term "biotechnics"
more than the "biotechnic society." The reason is clear in the last
sentence of The Pentagon of Power where he writes, "for those of us who
have thrown off the myth of the machine, the next move is ours: for the
gates of the technocratic prison will open automatically, despite their
rusty ancient hinges, as soon as we choose to walk out." Mumford
believed that the biotechnic society was a desideratum—one that should
guide his contemporaries as they walked out the doors of their
megatechnic confines (he also calls them "coffins"). Thus he ends his
narrative, as he well understood, at the beginning of another one: the
possible revolution that gives rise to a biotechnic society, a quiet
revolution, for Mumford, one that would arise from the biotechnic
consciousness and actions of individuals. Mumford was an avid reader of
Alfred North Whitehead's philosophy of the organism.[15]
Polytechnics versus monotechnics
A key idea, introduced in Technics and Civilization (1934) was that technology was twofold:
Polytechnic, which enlists many different modes of technology, providing a complex framework to solve human problems.
Monotechnic, which is technology only for its own sake, which oppresses humanity as it moves along its own trajectory.
Mumford commonly criticized modern America's transportation networks as
being "monotechnic" in their reliance on cars. Automobiles become
obstacles for other modes of transportation, such as walking, bicycle
and public transit, because the roads they use consume so much space
and are such a danger to people. Mumford explains that the thousands of
maimed and dead each year as a result of automobile accidents are a
ritual sacrifice the American society makes because of its extreme
reliance on highway transport.
Three epochs of civilization
Also discussed at length in Technics and Civilization is Mumford's
division of human civilization into three distinct epochs (following
concepts originated by Patrick Geddes):
Eotechnic (the Middle Ages)
Paleotechnic (the time of the Industrial Revolution) and
Neotechnic (later, present-day)
Megamachines
Mumford also refers to large hierarchical organizations as
megamachines—a machine using humans as its components. These
organizations characterize Mumford's stage theory of civilization. The
most recent megamachine manifests itself, according to Mumford, in
modern technocratic nuclear powers—Mumford used the examples of the
Soviet and United States power complexes represented by the Kremlin and
the Pentagon, respectively. The builders of the pyramids, the Roman
Empire and the armies of the World Wars are prior examples.
He explains that meticulous attention to accounting and
standardization, and elevation of military leaders to divine status,
are spontaneous features of megamachines throughout history. He cites
such examples as the repetitive nature of Egyptian paintings which
feature enlarged pharaohs and public display of enlarged portraits of
Communist leaders such as Mao Zedong and Joseph Stalin. He also cites
the overwhelming prevalence of quantitative accounting records among
surviving historical fragments, from ancient Egypt to Nazi Germany.
Necessary to the construction of these megamachines is an enormous
bureaucracy of humans which act as "servo-units", working without
ethical involvement. According to Mumford, technological improvements
such as the assembly line, or instant, global, wireless, communication
and remote control, can easily weaken the perennial psychological
barriers to certain types of questionable actions. An example which he
uses is that of Adolf Eichmann, the Nazi official who organized
logistics in support of the Holocaust. Mumford collectively refers to
people willing to carry out placidly the extreme goals of these
megamachines as "Eichmanns".
The clock as herald of the Industrial Revolution
One of the better-known studies of Mumford is of the way the mechanical
clock was developed by monks in the Middle Ages and subsequently
adopted by the rest of society. He viewed this device as the key
invention of the whole Industrial Revolution, contrary to the common
view of the steam engine holding the prime position, writing: "The
clock, not the steam-engine, is the key-machine of the modern
industrial age. ... The clock ... is a piece of power-machinery whose
'product' is seconds and minutes ...."[16]
Urban civilization
The City in History won the 1962 U.S. National Book Award for
Nonfiction.[11] In this influential book Mumford explored the
development of urban civilizations. Harshly critical of urban sprawl,
Mumford argues that the structure of modern cities is partially
responsible for many social problems seen in western society. While
pessimistic in tone, Mumford argues that urban planning should
emphasize an 'organic' relationship between people and their living
spaces.
Mumford uses the example of the medieval city as the basis for the
"ideal city," and claims that the modern city is too close to the Roman
city (the sprawling megalopolis) which ended in collapse; if the modern
city carries on in the same vein, Mumford argues, then it will meet the
same fate as the Roman city.
Mumford wrote critically of urban culture believing the city is "a
product of earth ... a fact of nature ... man's method of
expression."[17] Further, Mumford recognized the crises facing urban
culture, distrustful of the growing finance industry, political
structures, fearful that a local community culture was not being
fostered by these institutions. Mumford feared "metropolitan finance,"
urbanization, politics, and alienation. Mumford wrote: "The physical
design of cities and their economic functions are secondary to their
relationship to the natural environment and to the spiritual values of
human community."[18]
Suburbs
Suburbia did not escape Mumford's criticism either:
In the suburb one might live and die without marring the image of an
innocent world, except when some shadow of evil fell over a column in
the newspaper. Thus the suburb served as an asylum for the preservation
of illusion. Here domesticity could prosper, oblivious of the pervasive
regimentation beyond. This was not merely a child-centered environment;
it was based on a childish view of the world, in which reality was
sacrificed to the pleasure principle.[19]
Religion and spirituality
Mumford is also among the first urban planning scholars who paid
serious attention to religion in the planning field.[20][21] In one of
his least well-known books, Faith for Living (1940), Mumford argues
that:
The segregation of the spiritual life from the practical life is a
curse that falls impartially upon both sides of our existence.[22]: 216
|
思想
1944年に出版された著書『人間の条件』の中で、マンフォードは人間研究に対する自分の方向性を "有機的ヒューマニズム
"としている。この言葉が重要なのは、人間の可能性に制限を設け、その制限を人体の性質と一致させているからである。マンフォードは、空気の質、食料の入
手可能性、水の質、空間の快適さの重要性を決して忘れなかった。彼の推論では、有機的ヒューマニズムがブレーキとして働く限り、テクノロジーと進歩が暴走
列車になることはなかった。実際、マンフォードはこの観点から人間の脳を考察し、それを多動であるとした。多動であることは、人類が自然の脅威の多くを克
服することを可能にするという点では良いことであるが、脳を有意義に刺激するような方法で占有しなければ、悪いことになる可能性がある。マンフォードは人
間の
"本性"、つまり人間であることの自然な特性を尊重し、そこからテクノロジーや技術全般を評価する基盤を提供した。このように、都市とテクノロジーの導入
に関する彼の批判と助言は、基本的に彼が信奉する有機的ヒューマニズムを中心に組織されたものであった。マンフォードが最終的にマーシャル・マクルーハン
を批判的に評価するようになったのは、有機的ヒューマニズムの観点からであった。マクルーハンは、自然環境ではなくテクノロジーが最終的に人類の本質を形
成すると主張したが、マンフォードはその可能性を認めていた。
マンフォードは、人間性を定義するもの、人間を他の動物から引き離すものは、主として道具(テクノロジー)の使用ではなく、言語(シンボル)の使用である
と考えていた。彼は、原始的な社会の参加者同士が情報やアイデアを共有することは、初期の人類にとってはまったく自然なことであり、社会がより洗練され複
雑になっていく過程では、明らかにその基盤となっていたと確信していた。彼は、人類が未来に向かうにつれて、世界におけるこの情報の「プール」のプロセス
の継続に期待していた[13]。
マンフォードが作品を通して「テクニクス」という言葉を選んだのは意図的なものであった。マンフォードにとって、テクノロジーはテクニクスの一部である。
技術だけでなく、芸術、技能、器用さをも意味するギリシア語のtekhneの広義の定義を用いると、テクニクスとは、社会的環境と技術革新の相互作用、す
なわち社会の「願望、習慣、アイデア、目標」だけでなく「産業プロセス」を指す。マンフォードが『テクニクスと文明』の冒頭で書いているように、「他の文
明は、明らかにテクニクスの方法や目的に深く影響されることなく、高度な技術的熟達に達した」のである。
メガテクニクス
機械の神話 第二巻
権力のペンタゴン(第12章)』(1970年)の中で、マンフォードは、絶え間ない無制限の拡大、生産、交換を強調する現代のテクノロジーの傾向を批判し
ている。彼は、こうした目標は、技術的完成度、耐久性、社会的効率、そして人間全体の満足度に反すると主張する。彼が「メガテクニクス」と呼ぶ現代のテク
ノロジーは、消費者信用、割賦購入、機能しない欠陥設計、計画的陳腐化、頻繁な表面的な「ファッション」の変化といった装置を用いることによって、永続的
で質の高い製品を生み出すことに失敗している。「広告による絶え間ない誘惑がなければ、生産は減速し、通常の買い替え需要に落ち着くだろう。そうでなけれ
ば、多くの製品が効率的なデザインのプラトーに達し、年ごとに最小限の変更しか必要としなくなるだろう」。
彼は自分自身の冷蔵庫を例に挙げ、「19年間、たった一度の小さな修理で使い続けている。日常使いの自動冷蔵庫も深冷保存冷蔵庫も、永久に価値のある発明
である。...
[市場アナリストやファッションの専門家の基準ではなく、バイオテクノロジーの基準に従えば、同じように優れた製品がデトロイトから生まれ、同じように長
く使い続けられる可能性があることを疑うことはできない。"
バイオテクノロジー
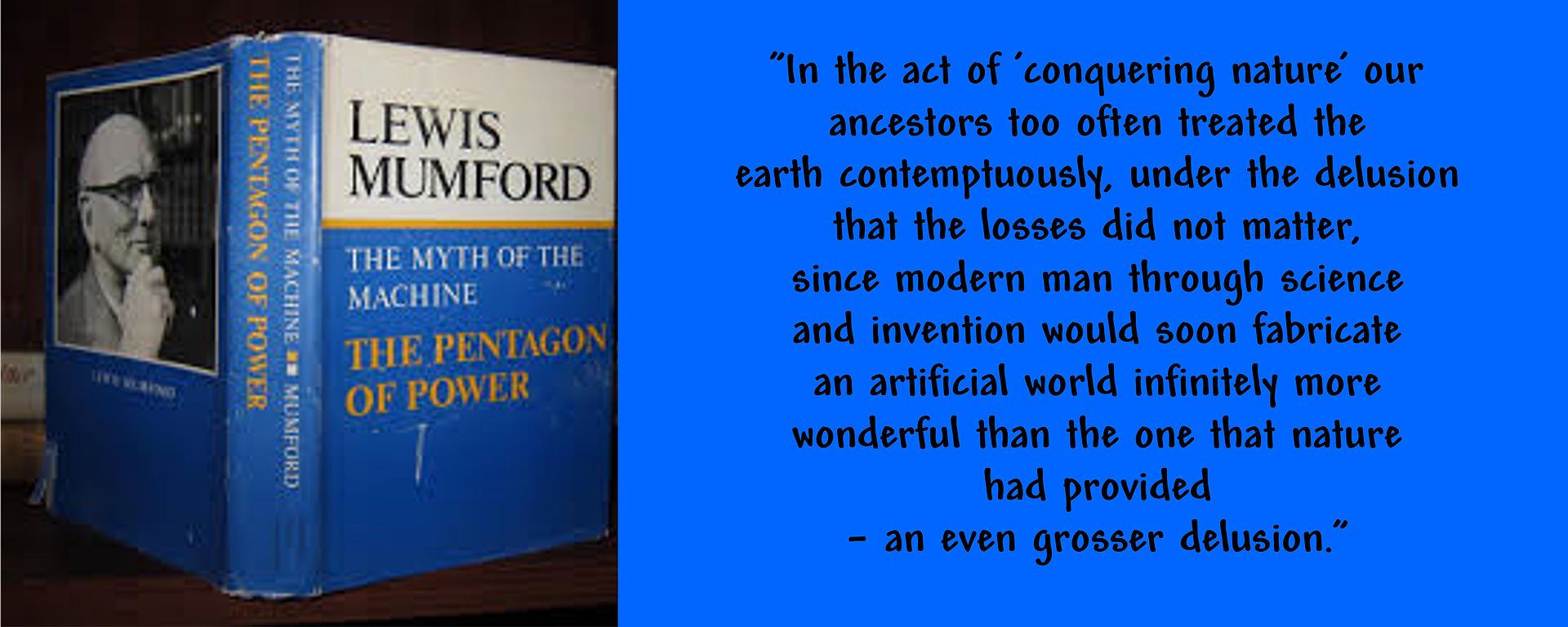
『ペンタゴン・オブ・パワー』の写真と引用。
マンフォードは、技術とバイオビリティーとの関係に深い関心を寄せていた。後者の用語は、マンフォードが使用したものではないが、その地域の生命維持能力
を特徴づけるものである。しかし、ある種の技術が急速に進歩すると、生物の生存可能性は劇的に低下する。例えば、スラグ山、汚染された水、駐車場、コンク
リート都市などは、生物生存可能性が極めて限られている。生物多様性のない地域は、映画ではディストピア(『ブレードランナー』など)という形でよく登場
する。しかしマンフォードは、技術が進歩するにつれて生存可能性が崩壊する必要はないと考えていた。なぜなら彼は、生態学的に責任ある方法で機能する技術
を創造することは可能だと考えており、そのような技術をバイオテクニクスと呼んでいたからである。彼は、これこそが「メガテクニクス」の自殺的な推進力を
振り払うために必要なテクノロジーであると信じていた。マンフォードは、最古の共同体にまでさかのぼるエコロジー意識を認める一方で、新興のバイオテクノ
ロジーをネオ・ダーウィン意識の産物、つまり、生物の状態と環境の状態との相互影響関係から目をそらすことを拒否する、産業革命後の思考形態とみなしてい
た。マンフォードの考えでは、バイオテクノロジーを中心に組織された社会は、その不可欠な関係のためにテクノロジーを抑制する。
マンフォードの理解では、メガテクノロジーの文脈で生まれたさまざまなテクノロジーは、それらが私たちに遺した明らかな利益とともに、意図しない有害な副
作用をもたらしてきた。例えば、(技術としての)貨幣の発達は、富を抽象化することによって、モノとしての富の重荷となる側面を排除したため、副次的な効
果として、不合理な過剰蓄積の状況を生み出したと指摘する。富が抽象的でなかった時代には、富の獲得(穀物、土地、家畜で測られる富、つまり、人は満足す
るが、富に溺れることはない)にまつわる組織原理として、豊かさが機能していた。富を質ではなく純粋な量として考えることを可能にする貨幣は、制御不能に
陥りかねないメガテクニックスの一例である。もしマンフォードのこの概念が正しければ、歴史家や経済学者は、富の抽象化がなおも進むことと、富の分配や役
割に関する根本的な変容との関係をたどることができるはずである。そして実際、電子マネーへの移行は、その多くの利点とともに、まだ十分に理解されておら
ず、その結論も出ていない経済的ストレスと搾取の形態を刺激したように見える。抽象的な貯蓄に走ることの少ない資源分配技術は、バイオテクノロジー的な生
活概念により適しているだろう。
こうしてマンフォードは、バイオテクノロジーの社会は、テクノロジーが絶え間なく拡大し、自らの力を拡大しなければならないというメガテクノロジーの妄想
を抱かず、"住みやすさ
"を創造し維持するために、その妄想を打ち砕くだろうと主張した。バイオテクノロジー社会は、メガテクノロジー的なパワーの追求ではなく、マンフォードが
「プレニチュード」と呼ぶもの、つまり資源とニーズの恒常的な関係を追求する。この "plenitude
"という概念は、動物が利用可能な食料に関係するように、バイオテクノロジー社会がそのテクノロジーに関係することを示唆すれば、より明確になる。
豊かさの中での満足という制限的な効果とともに、技術的進歩の追求は、生物に対する潜在的な悪影響によっても制限されるだろう。したがって、バイオテクノ
ロジー社会では、空気の質、食物の質、水の質、これらはすべて、それらに脅威を与えるあらゆる技術的野心を制限しうる重大な懸念事項であろう。騒音、放射
線、スモッグ、有害化学物質、その他の技術的副産物がもたらす負の価値は、新たな技術革新の導入を著しく制限するだろう。マンフォードの言葉を借りれば、
バイオテクノロジー社会は「質的な豊かさ、振幅、ゆとり、量的な圧力や混雑からの解放」に向かうだろう。自己調整、自己修正、自己推進は、栄養、生殖、成
長、修復と同様に、生物に不可欠な特性である」。バイオテクノロジー社会は、バランス、全体性、完全性を追求する。
マンフォードの都市批判と、都市生活と都市デザインに関するすべてのマンフォードの仕事に不可欠な、人間の身体の性質を中心に組織された都市という彼のビ
ジョンは、バイオテクニクスの初期の概念に根ざしている: 「住みやすさ」とは、マンフォードが師であるパトリック・ゲッデスから得た概念である。
マンフォードは、1970年に書かれた『権力の五角形』の後半部分で、バイオテクニクスという言葉を用いている。この用語は、彼の初期の「有機的ヒューマ
ニズム」の特徴づけと並んで、バイオテクニクスが有機的ヒューマニストにとって魅力的なテクニックの具体的な形を表しているという点で、よく馴染んでい
る。マンフォードがバイオテクニクスについて述べた当時、自動車や産業公害は、核による消滅の恐怖とともに、技術的な主要関心事となっていた。しかしマン
フォードは、テクノロジーはそれ以前から多くの危険を生み出しており、将来もそうであろうと認識していた。マンフォードにとって、人間の危険は、人間の本
質的な性質を十分に尊重し、受け入れていない権力志向のテクノロジーに根ざしている。マンフォードは、後に他の人々が明言するように、生態学的な意味で理
解される現代の人間の生活がバランスを欠いているのは、その生態系の技術的な部分(銃、爆弾、自動車、麻薬)が、それらを生み出した種の必要性によって制
約されるのではなく、それらに特有の力によって駆り立てられ、制御不能に陥っているからだと暗に述べているのである。彼は、バイオテクノロジーこそが、メ
ガテクノロジーの問題に対する新たな答えであり、唯一の希望であると信じていた。それは、彼の時代にはすでに主張し始めていた答えだと彼は信じていた。
マンフォードの著作が、「バイオテクノロジー社会」よりも「バイオテクノロジー」という言葉に特権を与えているのは事実である。その理由は、『権力の五角
形』の最後の一文にある。「機械の神話を捨て去った私たちにとって、次の一手は私たちのものだ。マンフォードは、バイオテクノロジーの社会は、同時代の人
々がメガテクノロジーの牢獄(彼はそれを「棺桶」とも呼んでいる)の扉から出て行く際の指針となるべき、あるべき姿だと考えていた。つまり、バイオテクノ
ロジー社会を生み出す可能性のある革命であり、マンフォードにとっては静かな革命であり、個人のバイオテクノロジーに対する意識と行動から生まれる革命な
のである。マンフォードはアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドの有機体哲学の熱心な読者であった[15]。
ポリテクニック対モノテクニック
テクニクスと文明』(1934年)で紹介された重要な考え方は、技術には2つの側面があるというものだった:
ポリテクニックとは、人間の問題を解決するための複雑な枠組みを提供する、多くの異なる技術様式を集めたものである。
モノテクニックとは、それ自身のための技術であり、それ自身の軌道に沿って進む人類を抑圧するものである。
マンフォードは一般的に、現代アメリカの交通網は自動車に依存した「モノテクニック的」なものだと批判した。自動車は、徒歩や自転車、公共交通機関といっ
た他の交通手段にとって障害となる。なぜなら、自動車が使う道路は非常に多くのスペースを消費し、人々にとって危険だからだ。マンフォードは、自動車事故
によって毎年何千人もの負傷者や死者が出ているのは、アメリカ社会が高速道路交通に極度に依存しているために行っている儀式の犠牲なのだと説明している。
文明の3つの時代
また、『テクニクスと文明』では、マンフォードが人類の文明を(パトリック・ゲッデスが提唱した概念に従って)3つの明確なエポックに分類したことについても詳しく論じている:
エオテクニック(中世)
パレオテクニック(産業革命の時代)と
ネオテクニック(後の現代)
メガマシン
マンフォードはまた、大規模な階層的組織をメガマシン(人間を構成要素として使用する機械)と呼んでいる。これらの組織は、マンフォードの文明段階説を特
徴づけている。マンフォードによれば、最も新しいメガマシンは、現代の技術主義的な核保有国に現れている。マンフォードは、クレムリンとペンタゴンにそれ
ぞれ代表されるソ連とアメリカの権力複合体を例に挙げている。ピラミッドの建設者、ローマ帝国、世界大戦の軍隊などがその例である。
彼は、会計や標準化に対する細心の注意や、軍事指導者を神の地位へと昇格させることは、歴史を通じてメガマシンの自然発生的な特徴であると説明する。彼
は、拡大されたファラオを特徴とするエジプト絵画の反復性や、毛沢東やヨシフ・スターリンのような共産主義指導者の拡大された肖像画の公然陳列などの例を
挙げている。また、古代エジプトからナチス・ドイツに至るまで、現存する歴史的断片の中に量的な会計記録が圧倒的に多いことも挙げている。
こうしたメガマシンの建設に必要なのは、倫理的な関与なしに働く「サーボ・ユニット」として機能する人間の巨大な官僚機構である。マンフォードによれば、
組み立てラインや、インスタント、グローバル、ワイヤレス、コミュニケーション、遠隔操作などの技術改良は、ある種の疑わしい行為に対する長年の心理的障
壁を容易に弱めることができる。その例として、ホロコーストを支援するための兵站を組織したナチスの幹部、アドルフ・アイヒマンを挙げている。マンフォー
ドは、こうしたメガマシンの極端な目標を平然と遂行しようとする人々を総称して「アイヒマン」と呼んでいる。
産業革命の先駆者としての時計
マンフォードの研究でよく知られているのは、機械式時計が中世の修道士によって開発され、その後社会の他の人々によって採用された方法に関するものであ
る。彼はこの装置を、蒸気機関が第一の地位を占めるという一般的な見方とは逆に、産業革命全体の重要な発明とみなし、こう書いている:
「時計は、蒸気機関ではなく、近代工業時代の重要な機械である。時計は......その "製品
"が秒と分である動力機械の一部である......」[16]。
都市文明
歴史の中の都市』は1962年の全米図書賞ノンフィクション部門を受賞した[11]。この影響力のある本でマンフォードは都市文明の発展について探求し
た。都市のスプロールを厳しく批判するマンフォードは、近代都市の構造が西洋社会に見られる多くの社会問題の原因の一部であると主張している。悲観的な論
調ではあるが、マンフォードは、都市計画は人々と生活空間の「有機的な」関係を重視すべきだと主張している。
マンフォードは「理想都市」の基礎として中世都市を例に挙げ、近代都市は崩壊に終わったローマ都市(広大なメガロポリス)に近すぎると主張する。もし近代都市が同じ流れをたどれば、ローマ都市と同じ運命をたどるだろうとマンフォードは主張する。
マンフォードは都市文化を批判的に書き、都市は「地球の産物であり、自然の事実であり、人間の表現方法である」と信じていた[17]。さらにマンフォード
は都市文化が直面している危機を認識し、成長する金融産業や政治構造に不信感を抱き、これらの制度によって地域社会の文化が育まれていないことを恐れてい
た。マンフォードは「メトロポリタン金融」、都市化、政治、疎外を恐れた。マンフォードは、「都市の物理的設計とその経済的機能は、自然環境との関係や人
間共同体の精神的価値との関係にとっては二の次である」と書いている[18]。
郊外
郊外もまた、マンフォードの批判を免れることはできなかった:
郊外では、新聞のコラムに邪悪な影が落ちたときを除いては、無垢な世界のイメージを損なうことなく生き、死ぬことができた。こうして郊外は、幻想を守るた
めの隔離施設として機能した。ここでは、向こう側に蔓延する規制を意識することなく、家庭的な生活が栄えることができた。これは単に子供中心の環境という
だけでなく、子供じみた世界観に基づいており、そこでは現実が快楽原則の犠牲にされていた[19]。
宗教と精神性
マンフォードはまた、都市計画の分野において宗教に真剣に注目した最初の都市計画学者の一人である:
精神生活と実践生活の分離は、私たちの存在の両面に公平に降りかかる呪いである。
|



 ☆
☆