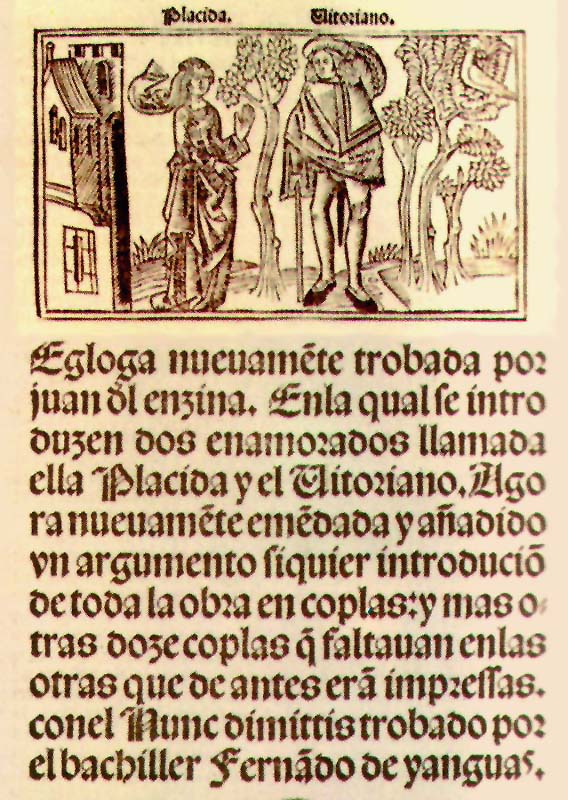
マドリガル
Madrigal (música)
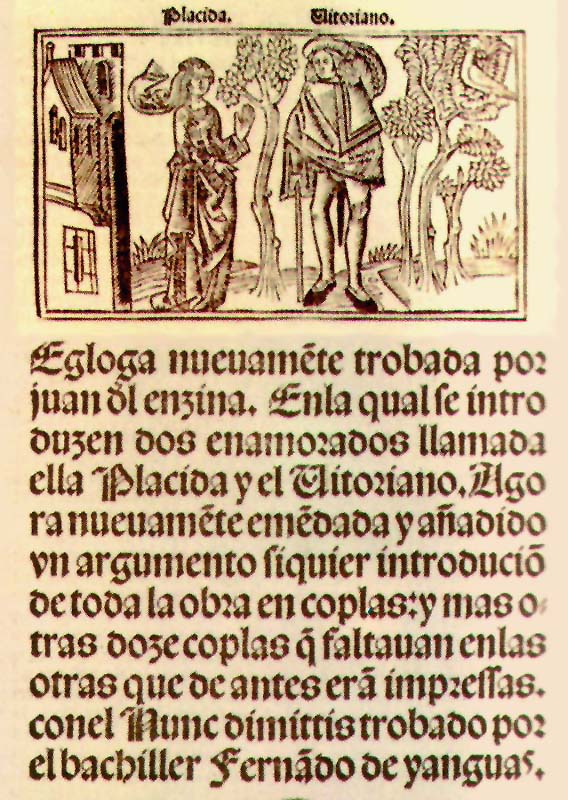
Primera publicación de los madrigales. por Juan del Encina
☆
マドリガル[1]は、世俗的な、しばしばイタリアのテキストに3から6の声部を合わせた楽曲である。マドリガルはルネサンス時代から初期バロック時代にか
けて全盛期を迎えた。音楽的にはフロッタラに起源を持ち、世俗的なテーマのイタリア語の歌詞、対位法的な和声、大衆的な性格を持つ。一般的に、この名称は
12世紀後半から14世紀初頭にかけてのイタリアのマドリガルと関連付けられており、そのほとんどはアカペラの声楽のために作曲され、一部では楽器が声楽
パートを補う場合もあった。
マドリガルは当時最も重要な世俗音楽の形式であった。16世紀後半に特に盛んになり、17世紀の30年代頃には重要性を失い、オペラなどの新しい世俗形式
の成長とともに衰退し、カンタータや対話劇と混ざり合った。
| El madrigal[1] es
una composición de tres a seis voces sobre un texto profano, a menudo
en italiano. Tuvo su máximo auge en el Renacimiento y primer Barroco.
Musicalmente reconoce orígenes en la frottola, posee una letra en
lengua italiana de temática profana, armonía contrapuntística, y
carácter popular. Generalmente el nombre se asocia al Madrigal de fines
del siglo xii y principios del siglo xiv en Italia, compuestos en su
mayoría para voces a capela, y en algunos casos con instrumentos
doblando las partes vocales. El madrigal fue la forma musical profana más importante de su tiempo. Floreció especialmente en la segunda mitad del siglo xvi, perdiendo su importancia alrededor de la tercera década del siglo xvii, cuando se desvanece a través del crecimiento de nuevas formas profanas como la ópera, y se mezcla con la cantata y el diálogo. Su difusión se inició con el "Primer Libro de Madrigales" de Philippe Verdelot, publicado en Venecia en 1533. Esta publicación tuvo un gran éxito y la forma creció rápidamente, primero en Italia, y hacia el fin del siglo, a varios otros países de Europa. El madrigal fue especialmente apreciado en Inglaterra, desde la publicación en 1588 de "Música Transalpina" de Nicholas Yonge -una colección de madrigales italianos con sus textos traducidos al inglés- que inició por sí misma una cultura inglesa del madrigal. Allí tuvo incluso vida mucho más larga que en el resto de Europa; los compositores continuaron produciendo obras de maravillosa calidad aún después de que pasara de moda en el resto del continente. La música secular es el conjunto de composiciones musicales que no tienen un propósito religioso, sino que están destinadas al entretenimiento, la narración de historias, el amor cortesano, las danzas y la vida cotidiana. A diferencia de la música litúrgica, la música secular fue desarrollada principalmente en el ámbito popular y cortesano desde la Edad Media y evolucionó a lo largo de los siglos hasta convertirse en la base de muchos géneros modernos. Orígenes Aunque la música secular ha existido desde tiempos remotos, en la Edad Media (siglos XI-XIV) comenzó a consolidarse como un género separado del repertorio religioso. Se transmitía principalmente de forma oral y estaba relacionada con la poesía y las tradiciones populares. Los trovadores, juglares y minnesänger (en Alemania) fueron los principales intérpretes de esta música. Características principales Textos profanos: Trata temas no religiosos, como el amor, la naturaleza, la guerra, la sátira y la política. Ritmo marcado: A diferencia del ritmo libre del canto gregoriano, la música secular utiliza patrones rítmicos definidos para acompañar bailes o narraciones. Polifonía: Aunque comenzó siendo monódica (una sola voz), con el tiempo adoptó formas polifónicas, especialmente en el Renacimiento. Lenguas vernáculas: Se canta en las lenguas locales (francés, español, italiano, alemán), no en latín. Instrumentos musicales: Se emplean instrumentos como el laúd, la flauta, la zanfona, el tambor, y más adelante, el clavecín y la vihuela. Tipos de música secular Canciones de trovadores y juglares: Narraciones poéticas acompañadas por instrumentos. Música para danza: Con un ritmo más marcado para acompañar las danzas populares y cortesanas. Villancicos y madrigales: Formas vocales polifónicas muy populares durante el Renacimiento. Baladas y romances: Historias contadas en forma de canciones, a menudo transmitidas oralmente. Evolución e influencia La música secular evolucionó rápidamente durante el Renacimiento, ganando en complejidad y difusión. Compositores como Claudio Monteverdi o John Dowland llevaron estas formas a un nuevo nivel artístico. Con el tiempo, la música secular se convirtió en la base para el desarrollo de la ópera, la música clásica y, posteriormente, los géneros populares modernos como el folk, el pop y el rock. Legado Hoy en día, la música secular sigue siendo la forma musical predominante en el mundo, reflejando la diversidad cultural y la riqueza expres |
マドリガル[1]は、世俗的な、しばしばイタリアのテキストに3から6
の声部を合わせた楽曲である。マドリガルはルネサンス時代から初期バロック時代にかけて全盛期を迎えた。音楽的にはフロッタラに起源を持ち、世俗的なテー
マのイタリア語の歌詞、対位法的な和声、大衆的な性格を持つ。一般的に、この名称は12世紀後半から14世紀初頭にかけてのイタリアのマドリガルと関連付
けられており、そのほとんどはアカペラの声楽のために作曲され、一部では楽器が声楽パートを補う場合もあった。 マドリガルは当時最も重要な世俗音楽の形式であった。16世紀後半に特に盛んになり、17世紀の30年代頃には重要性を失い、オペラなどの新しい世俗形式 の成長とともに衰退し、カンタータや対話劇と混ざり合った。 マドリガルの普及は、1533年にヴェネツィアで出版されたフィリップ・ヴェルデロットの『マドリガル第1集』から始まった。この出版は大成功を収め、こ の形式はまずイタリアで、そして世紀末にかけてヨーロッパの他のいくつかの国々へと急速に広まっていった。 マドリガルは特にイギリスで高く評価され、1588年にニコラス・ヨンジが出版した『Transalpine Music』という、イタリアのマドリガルを英語に訳した歌詞付きのコレクションが、イギリスにおけるマドリガル文化の誕生につながった。また、イギリス ではヨーロッパの他の地域よりもはるかに長い期間、マドリガル文化が続いた。作曲家たちは、大陸で流行が廃れた後も、素晴らしい作品を作り続けた。 世俗音楽とは、宗教的な目的を持たず、娯楽、物語、宮廷恋愛、舞踏、日常生活などを目的とした音楽作品の総称である。典礼音楽とは異なり、世俗音楽は中世 以降、主に大衆や宮廷の領域で発展し、何世紀にもわたって進化を遂げ、多くの現代のジャンルの基礎となった。 起源 世俗音楽は古代から存在していたが、宗教的なレパートリーとは別のジャンルとして確立し始めたのは中世(11世紀から14世紀)であった。 主に口頭で伝えられ、詩や民間伝承と関連していた。 トルバドゥール、曲芸師、ミンネゼンガー(ドイツ)が、この音楽の主な演奏者であった。 主な特徴 世俗的なテキスト:愛、自然、戦争、風刺、政治など、宗教以外のテーマを扱う。 強いリズム:グレゴリオ聖歌の自由なリズムとは異なり、世俗音楽では、ダンスや物語の伴奏として、明確なリズムパターンが用いられる。 多声音楽:最初は単旋律(1つの声部)であったが、時代とともに多声音楽の形式が採用されるようになり、特にルネサンス期にその傾向が強まった。現地語: ラテン語ではなく、現地の言語(フランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語)で歌われる。 楽器:リュート、フルート、手回しオルガン、ドラム、そして後にチェンバロやビウエラなどの楽器が使われる。 世俗音楽の種類 トルバドゥールや吟遊詩人の歌:楽器の伴奏にのせて詩が朗読される。舞曲:より際立ったリズムで、民衆の踊りや宮廷の踊りを伴奏する。ヴィリャンシーコと マドリガル:ルネサンス期に非常に人気があった多声音楽の形式。バラードとロマンス:歌の形式で語られる物語で、口頭で伝えられることが多かった。進化と 影響 世俗音楽はルネサンス期に急速に進化し、複雑さと普及度を増した。クラウディオ・モンテヴェルディやジョン・ダウランドなどの作曲家は、世俗音楽を新たな 芸術的レベルへと高めた。やがて世俗音楽は、オペラやクラシック音楽、そして後にフォーク、ポップ、ロックなどの現代のポピュラー音楽のジャンルの発展の 基礎となった。 今日、世俗音楽は依然として世界で最も一般的な音楽形式であり、文化の多様性と表現の豊かさを反映している。 |
| Lista de compositores de madrigales Compositores de madrigales medievales Jacopo da Bologna Johannes Ciconia Compositores de madrigales antiguos Jacques Arcadelt Adrian Willaert Costanzo Festa Cipriano de Rore Philippe Verdelot Bernardo Pisano Compositores de madrigales renacentistas Orlando di Lasso. Andrea Gabrieli. Claudio Monteverdi. Giovanni Pierluigi da Palestrina. Philippe de Monte. Sebastián Raval. Giovanni Gastoldi. Los madrigalistas tardíos Giaches de Wert Luzzasco Luzzaschi Luca Marenzio Carlo Gesualdo Sigismondo d'India Compositores de madrigales con acompañamiento instrumental en el Barroco Orazio Vecchi Adriano Banchieri Giulio Caccini Claudio Monteverdi Heinrich Schütz Hans Leo Hassler Johann Hermann Schein Escuela Inglesa Véase también: Categoría:Madrigalistas ingleses William Byrd John Dowland John Farmer Orlando Gibbons Thomas Morley: escribió tipos ligeros de madrigal, parecidos a los ballets (canciones homofónicas con ritmo de danza, con la melodía en la voz superior y estribillo "fa-la-la") y las canzonets. Thomas Tomkins Thomas Weelkes John Wilbye |
マドリガル作曲家の一覧 中世のマドリガル作曲家 ヤコポ・ダ・ボローニャ ヨハンネス・シコニア 初期のマドリガル作曲家 ジャック・アルカデルト エイドリアン・ウィラールト コンスタンツォ・フェスタ チプリアーノ・デ・ローレ フィリップ・ヴェルデロット ベルナルド・ピサーノ ルネサンスのマドリガル作曲家 オルランド・ディ・ラッソ アンドレア・ガブリエリ クラウディオ・モンテヴェルディ。 ジョヴァンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナ。 フィリッポ・デ・モンテ。 セバスティアン・ラヴァル。 ジョヴァンニ・ガストルディ。 マドリガーリスタ(マドリガーレの歌手)の故人 ジャケス・デ・ヴェルト ルッツァスコ・ルッツァスキ ルカ・マレンツィオ カルロ・ジェズアルド バロック時代の器楽伴奏付きマドリガーレの作曲家 オラツィオ・ヴェッキ アドリアーノ・バンキエリ ジュリオ・カッチーニ クラウディオ・モンテヴェルディ ハインリヒ・シュッツ ハンス・レオ・ハスラー ヨハン・ヘルマン・シャイン イギリス楽派 関連項目: カテゴリー:イギリスのマドリガーナ歌手 ウィリアム・バード ジョン・ダウランド ジョン・ファーマー オーランド・ギボンズ トマス・モアリー:軽快なマドリガーレを書いた。それは、バレエ(ダンスのリズムに合わせて歌われる同声部の歌で、旋律は上声部にあり、「ファ・ラ・ラ」というリフレインがある)やカンツォネに似ている。 トマス・トムキンス トマス・ウィールクス ジョン・ウィルビー |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Madrigal_(m%C3%BAsica) |
|
Madrigalismo español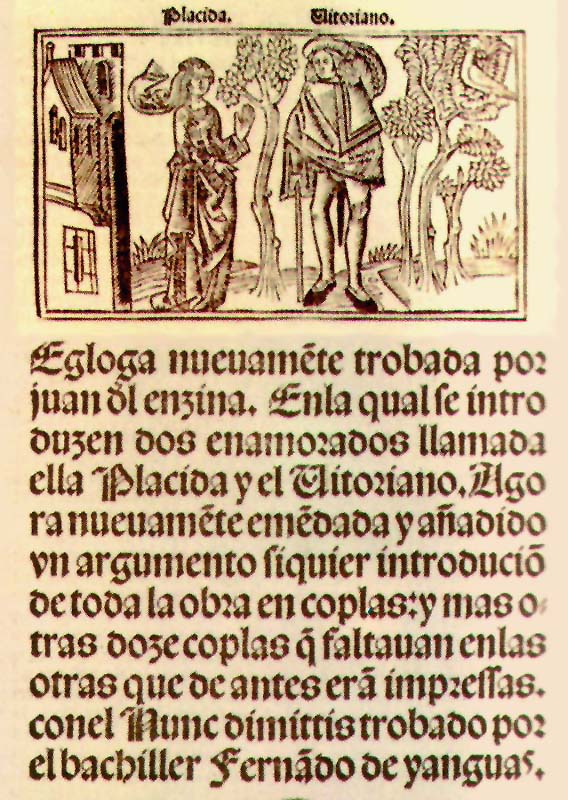 Primera publicación. Juan del Encina En España no hubo las transformaciones humanas ni religiosas que la Reforma ocasionó en muchos países de Europa. Después de la Reforma, la influencia de los reyes católicos siguió siendo muy poderosa, y durante esta hubo mucha producción musical. La mayoría de las producciones estuvieron dedicadas a la música sacra. El origen del madrigal viene de Italia del siglo xiv, se deriva de la frottola, de escritura homófona e isométrico. De todas formas no será este primer madrigal el que influya en los compositores españoles, sino el del siglo xvi, que tiene un estilo contrapuntístico e imitativo, gracias a los músicos como Willaert. Este género sorprende sobre todo a los músicos de Cataluña como Pedro Alberch Vila; los castellanos y andaluces no aceptaron el término, pero si la forma. El madrigal en España puede definirse como una composición musical polifónico – vocal, sobre textos poéticos muy refinados, tanto por su lenguaje como por su contenido, sin estribillo, con música para toda la letra y de estilo imitativo, un poco a semejanza del motete, con el cual por cierto se le suele comparar, salvo por el texto, de carácter profano. La importancia que se le dio a la música en la Iglesia española fue tan grande que produjo un gran movimiento de competencia entre los autores, de tal manera que quien no tuviera una producción considerable y de buena calidad, podría terminar relegado a los últimos puestos de las capillas catedralicias. Bajo el reinado de Isabel y Fernando se habían manifestado los primeros intentos de los músicos españoles para librarse de las influencias francesa e italiana, que predominaban desde el siglo xv. Durante el reinado de Carlos V, él sostuvo la capilla más rica y excelente de toda la cristiandad, y se integraba fundamentalmente por músicos españoles.[2] |
スペインのマドリガル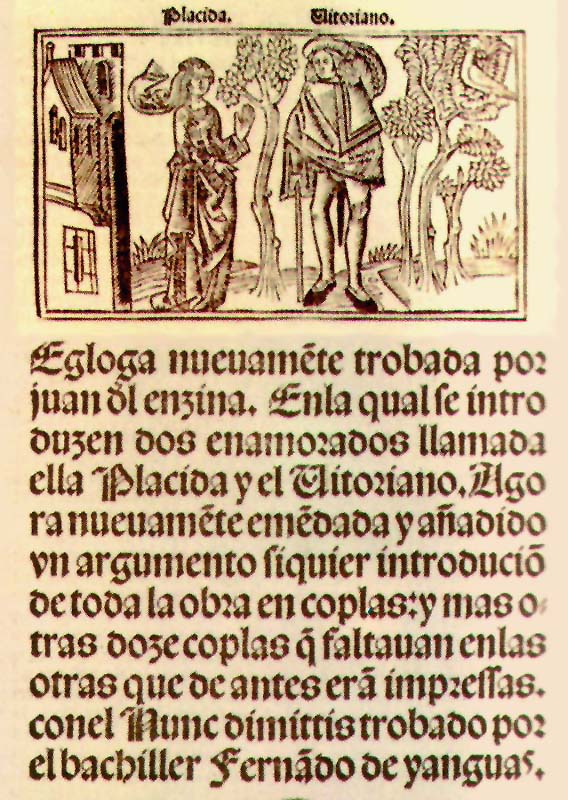 初版。フアン・デル・エンシーナ スペインでは、多くのヨーロッパ諸国で宗教改革が引き起こしたような、人間や宗教の変革は起こらなかった。宗教改革後も、カトリック両王の影響力は非常に強力であり、この時代には多くの音楽作品が生み出された。そのほとんどは宗教音楽であった。 マドリガルの起源は14世紀のイタリアにあり、ホモフォニーで等長記譜法のフロッタラから派生した。しかし、スペインの作曲家に影響を与えたのは、この最 初のマドリガルではなく、むしろヴィラールトなどの音楽家のおかげで対位法的で模倣的なスタイルを持つ16世紀のマドリガルであった。 このジャンルは、とりわけペドロ・アルベルチ・ビラのようなカタルーニャの音楽家に衝撃を与えた。カスティーリャ人とアンダルシア人はこの用語を受け入れ なかったが、形式は受け入れた。スペインのマドリガルは、言語と内容の両面で高度に洗練された詩的なテキストに、リフレインなしで、すべての歌詞に音楽が つけられ、モテットにやや似た模倣スタイルで作曲された多声部の声楽作品と定義することができる。モテットと比較されることも多いが、世俗的なテキストで あるという点を除いては。 スペインの教会における音楽の重要性は非常に大きく、作曲家たちの間で多くの競争が繰り広げられた。質の高い作品を数多く生み出さなければ、大聖堂の聖歌隊の最下層に追いやられることにもなりかねなかった。 カスティーリャのイザベラ1世とアラゴンのフェルディナンド2世の治世下では、15世紀以来支配的であったフランスやイタリアの影響から脱却しようとする スペイン人音楽家たちの最初の試みが明らかになった。カール5世の治世下では、キリスト教世界で最も豊かで優れた聖歌隊が維持され、その聖歌隊は主にスペ イン人音楽家で構成されていた。 |
| Madrigalistas en España Algunos de los compositores españoles de la época, son: Gabriel Gálvez, Andrés Torrentes, Melchor Robledo, Pere Alberch Vila, Juan Navarro, Rodrigo de Ceballos, Ándres de Villalar, Mateo Flecha, Pedro y Francisco Guerrero, Fernando de las Infantas, Juan Esquivel y el gran Tomás Luis de Victoria. La mayoría de ellos estuvieron bajo el patrocinio eclesiástico, y la gran mayoría quiso convertir su producción musical en una forma de facilitar la comunicación entre el hombre y Dios.[3] Juan Cornago (c. 1400 - 1475), destacado compositor español que marca la transición entre los usos del Ars Nova y el Renacimiento dentro de la música española. Es considerado como uno de los pioneros de la Polifonía Española del Sigo XV. Figuró como músico favorito de Fernando I, hijo de Alfonso V El Magnánimo, durante su reinado en Nápoles. Es autor de numerosos salmos, misas y motetes, entre otras obras. Bartolomé Ramos de Pareja (c. 1440 - 1522), natural de Baeza; se destacó como teórico y compositor. Vivió en Salamanca, donde ocupó la cátedra de formación musical en la Universidad; más tarde, se trasladó a Bolonia donde permaneció varios años; allí publicó su tratado de Música Práctica (1472); luego fue a Roma, donde murió. Juan de Anchieta (c. 1450 - 1523), nacido en Azpeitia; compositor y clérigo; primo por vía materna de San Ignacio de Loyola. Vinculado a la casa de Isabel de Castilla; fue músico de la corte en 1489; además, en 1499, se desempeñó como canónigo de la catedral de Granada. Desde 1504 fue rector de la iglesia de su ciudad natal. Es autor de una extensa obra que comprende misas, motetes, canciones y piezas populares profanas. Juan del Encina (1469 - 1534), compositor y dramaturgo, uno de los padres del teatro español; nacido en las proximidades de Salamanca y estudió en la Universidad de dicha ciudad, bajo la tutela del gran humanista español Antonio Martínez de Cala y Jarava, más conocido como Antonio de Nebrija (1441-1522); sirvió al Duque de Alba en Toledo. Fue nombrado archidiácono de Málaga en 1509. Estuvo en Roma en 1514, donde presentó su Farsa de Plácida e Vittoriano; en Tierra Santa en 1519. Llegó a ser Prior de León y es autor de una importante obra teatral y musical conservada en el MS Cancionero del Palacio, tanto profana como religiosa, p.e. O Reyes Magos Benditos. Compuso también numerosos Villancicos, para canto solo con acompañamiento instrumental, a semejanza del Lied borgoñón* y muchas canciones para sus propias églogas* y obras teatrales. Juan de Urrede (1430 - 1482), llamado también Johannes Wrede, autor de 'Nunca fue pena mayor'; JUAN DE TRIANA († 1490) compositor activo durante el período de los reyes católicos; autor de 'Pínguele', 'respinguete', 'Ya de amor era partido', y la 'Ensalada Querer vieja yo'; el sevillano FRANCISCO DE LA TORRE (1483-1504), autor de 'Dime, triste coraçon'. Mateo Flecha el Viejo (1481 - c. 1554), natural de Prados; destacó como clérigo y compositor; se formó bajo la tutela de Juan Castelló en Barcelona; fue maestro de capilla de las Infantas de Castilla. Su sobrino del mismo nombre, Mateo (c.1520-1604), se formó con él; también profesó como monje y se destacó como compositor al servicio del emperador Carlos V hasta 1558 y luego, al servicio de Felipe II. Más tarde, prestó servicios al emperador Maximiliano en Praga. Al igual que su tío, escribió música religiosa, madrigales, ensaladas o madrigales burlescos, y otras obras. Diego Pisador (1508 - 1557), natural de Salamanca; se destacó como ejecutante del Laúd y la Vihuela, compositor y teórico musical; en 1552 publicó su Libro de Música para Vihuela en el cual incluye muchas de sus obras, villanescas a 3 y 4 voces, fantasías, romances y villancicos. Joan Brudieu (c. 1515 - 1591), nacido cerca de Limoges. Se hizo célebre por su presentación como cantor en la Navidad de Urgell (Pirineos) en 1538; prestó servicios en la iglesia de Santa María del Mar en Barcelona, donde publicó un Libro de Madrigales en 1585. Pere Alberc i Vila (llamado en francés Pere Albert Vila, 1517 - 1582), destacado compositor y organista, madrigalista, prelado y canónigo de la Catedral de Barcelona. Es autor de varios madrigales y obras para órgano; Juan Vásquez (c. 1500 - c. 1560), nacido en Badajoz y formado en Sevilla. Se desempeñó como cantor de la Catedral de Plasencia. Fue maestro de capilla en Burgos; autor de una colección de Villancicos y Canciones a tres y cinco voces, por lo general, una de ellas era tomada del folklore, impresa en 1551 por la Universidad de Osuna; luego en 1560 publicó una Recopilación de sonetos y villancicos a 4 y a 5. Antonio de Cabezón (1500 - 1566), natural de Castrillo Mota de Judíos, población cercana a Burgos. Ciego de nacimiento, fue famoso como organista, ejecutante de laúd y compositor de la corte española de Carlos V y Felipe II, quienes le protegieron y le permitieron recorrer importantes ciudades de la Europa de su tiempo. Es autor de importantes obras religiosas y profanas; destacan sus Tientos, forma española del ricercare. Cristóbal de Morales (1500 - 1553), sevillano; uno de los más destacados compositores polifonistas españoles del siglo xvi. Maestro de Capilla en Ávila desde 1526 hasta 1530; luego pasó a Roma, recibió los hábitos y fue canónigo en la Capilla Sixtina en 1535. Luego regresó a España donde estuvo al servicio del Duque de Arcos. Compuso muchas misas, motetes, una Cantata para la Paz de Niza (1538) y otra para Ippolito d’Este; además de numerosos madrigales. Bartolomé de Escobedo (c. 1515 - 1563), nacido en Zamora. Teórico y compositor español. Integrante de la Capilla Pontifical en Roma en 1536, se desempeñó como juez en la disputa (1551) entre Vicentino y Lusitano. Maestro de capilla en Segovia desde 1554; es autor de motetes, magnificats, Miserere, misas, etc. Francisco de Peñalosa (c. 1470 - 1528), músico y compositor natural de Talavera de la Reina. Fue cantor en la corte de Fernando de Aragón El Católico desde 1498 hasta 1516; luego se desempeñó durante un tiempo como cantor de la Capilla Pontificia de León X. Es autor de muchas misas, motetes y otras obras religiosas. Falleció en Sevilla. Francisco Guerrero (1528 - 1599), que fue discípulo de Morales y en 1546, a los 18 años, fue Maestro de Capilla en Jaén (1545), Málaga y Sevilla. Visitó Lisboa, Roma, Venecia y Tierra Santa; es uno de los grandes maestros de este período. Autor de hermosos villancicos, villanelas espirituales y chanzonetas para la Navidad. Es un genuino representante de la llamada escuela sevillana, cuya característica dentro de la escuela española es una especial dedicación a temas Marianos. Murió en Sevilla en noviembre de 1599. Francisco Soto de Langa (c. 1534 - 1619), natural de Langa; fue cantor sopranista masculino y compositor de madrigales y Laudi Spirituali. Ingresó al Coro Papal en 1562; luego integró el coro en la iglesia de los Oratorianos de San Felipe de Neri. Joan Pau Pujol (1573 - 1626), maestro de coros y compositor español nacido en Cataluña, autor de varias misas y otras obras religiosas, canciones profanas y madrigales. Se desempeñó como maestro de capilla en Tarragona (1593-95), luego en la Catedral de Zaragoza (1595-1612) y en Barcelona (1612-26). Y en especial: Tomás Luis de Victoria (c. 1548- 1611), compositor español posiblemente, nacido en Ávila; el más importante de los compositores religiosos de la Polifonía Renacentista Española, cuyas obras brillan con el fervor visionario de los místicos. En su arte sabe superponer melodías gregorianas en una magistral polifonía; así mismo, con el retardo de notas produce hermosas disonancias que logran un intenso dramatismo. Desde muy joven presta sus servicios como músico, al Infante D. Luis, hijo de D. Manuel I de Portugal. En 1565 y con el apoyo de Felipe II, sobrino de D.Luis, es enviado al Colegio Germánico de Roma donde es discípulo de G. P. da Palestrina para luego, en 1573, convertirse en su sucesor en la cátedra. Amigo personal de Felipe de Neri, junto a él se retira durante ocho años al Convento de San Gerolamo della Caritá, donde escribe gran parte de su mejor producción musical y del cual sale en 1585. Es autor de numerosas obras: Magníficat (1581), Motecta libri duo (1583), Missa Quarti Toni y Missarum libri duo (1583) dedicado a D. Felipe II; Officium Hebdomadæ Sanctæ (1583); y otras obras de polifonía vocal. Es muy famoso su Officium Defunctorum (1603), escrito a seis voces y el cual contiene la Missa Pro Deffunctis, un Motete, un Responsorio y una Lección; esta obra publicada en 1605, fue compuesta para las exequias de la Emperatriz María, hermana de D. Felipe II (In Obitv et obsequiis Sacræ I Emperatricis, Matriti Ex Tipographia Regia). Desde 1585 y hasta su muerte en 1611, se desempeñó como organista del Convento de la Carmelitas Descalzas Reales de Madrid. |
スペインのマドリガル歌手 当時のスペインの作曲家には、ガブリエル・ガルベス、アンドレス・トレンテス、メルチョール・ロボレド、ペレ・アルベルク・ビラ、フアン・ナバーロ、ロド リーゴ・デ・セバロス、アンドレス・デ・ビジャラール、マテオ・フレチャ、ペドロ・ゲレロ、フランシスコ・ゲレロ、フェルナンド・デ・ラス・インファンタ ス、フアン・エスキベル、そして偉大なトマス・ルイス・デ・ビクトリアなどがいた。彼らの大半は教会の後援を受けており、その大半は、音楽作品を通じて人 と神とのコミュニケーションを円滑にすることを望んでいた。[3] フアン・コルナゴ(Juan Cornago、1400年頃 - 1475年)は、スペイン音楽におけるアルス・ノヴァとルネサンスの移行期を象徴する優れたスペインの作曲家である。彼は15世紀スペインのポリフォニー の先駆者の一人と考えられている。ナポリ在位中のフェルナンド1世(アルフォンソ5世「大公」の息子)のお気に入りの音楽家であった。彼は数多くの詩篇、 ミサ曲、モテットなどの作品を残している。 バルトロメ・ラモス・デ・パレハ(1440年頃 - 1522年)は、ベアサ生まれ。理論家および作曲家として名を馳せた。サラマンカに住み、同地の大学で音楽教育の教授職に就いた。その後、ボローニャに数 年間滞在し、そこで『実践音楽論』(1472年)を出版した。その後ローマに移り、そこで死去した。 フアン・デ・アンシエタ(1450年頃 - 1523年)アスペイティア生まれ。作曲家、聖職者。聖イグナチオ・デ・ロヨラの母方の従兄弟。カスティーリャのイザベラ家とつながりがあり、1489年 には宮廷音楽家を務めた。さらに1499年にはグラナダ大聖堂の参事会員となった。1504年からは故郷の教会の牧師を務めた。ミサ曲、モテット、歌、世 俗的な民謡など、広範な作品を残している。 フアン・デル・エンシーナ(1469年 - 1534年)は、スペイン演劇の父の一人である作曲家兼劇作家。サラマンカ近郊で生まれ、同市の大学でスペインの偉大なヒューマニスト、アントニオ・マル ティネス・デ・カラ・イ・ハラバ(アントニオ・デ・ネブリハ(1441年 - 1522年)としてよりよく知られている)の指導を受けた。トレドではアルバ公爵に仕えた。1509年にはマラガの首席司祭に任命された。1514年には ローマに滞在し、そこで『プラシダとヴィットリアーノの道化芝居』を発表。1519年には聖地を訪れた。レオンの修道院長となり、宮廷の歌集に保存されて いる世俗および宗教的な重要な演劇および音楽作品の作者となった。例えば、『祝福された東方の三博士』などである。また、声楽と器楽伴奏による多数のヴィ リャンシーコを作曲した。これは、ブルゴーニュの「リート」*に似たもので、自身の牧歌*や劇のための歌も数多く作曲した。 フアン・デ・ウレド(1430年 - 1482年)、ヨハネス・ウレドとしても知られ、『Nunca fue pena mayor』の作者。フアン・デ・トリアナ(1490年没)、カトリック両王の時代に活躍した作曲家。『Pínguele』、 『respinguete』、『Ya de amor era partido』、『エンサラーダ・ケレル・ビエハ・ヨ』の作者。セビリアのフランシスコ・デ・ラ・トーレ(1483-1504)は、「Dime, triste coraçon」の作者である。 マテオ・フレチャ・エル・ビエホ(1481年-1554年頃)はプラドス出身で、聖職者および作曲家として頭角を現した。バルセロナでフアン・カステジョ の指導を受け、カスティーリャ王女たちの礼拝堂楽長を務めた。彼の甥で同じ名前のマテオ(c.1520-1604)も彼のもとで修行し、彼もまた修道士と なり、1558年までは神聖ローマ皇帝カール5世に仕え、その後はフェリペ2世に仕えた。彼は後にプラハで神聖ローマ皇帝マクシミリアンに仕えた。叔父と 同じく、宗教音楽、マドリガル、エンサラーダやマドリガル・バーレスク、その他の作品を書いた。 ディエゴ・ピサドール(1508年 - 1557年)はサラマンカ生まれで、リュートとビウエラの名手であり、作曲家、音楽理論家としても著名であった。1552年には『ビウエラのための音楽 書』を出版し、その中には3声と4声のヴィリャンシーコ、幻想曲、ロマンスなど、自身の作品が数多く含まれていた。 ジョアン・ブルディウ(1515年頃 - 1591年)はリモージュ近郊生まれ。1538年のウルジェル(ピレネー)のクリスマスで聖歌隊員として活躍し、一躍有名になった。バルセロナのサンタ・マリア・デル・マル教会で奉仕し、1585年にマドリガル集を出版した。 ペレ・アルベルク・イ・ビラ(フランス語名ペレ・アルベール・ビラ、1517年 - 1582年)は、優れた作曲家でありオルガニスト、マドリガル歌手、高位聖職者、バルセロナ大聖堂の参事会員であった。彼はマドリガルやオルガン曲の作者である。 フアン・バスケス(1500年頃 - 1560年頃)はバダホス生まれで、セビリアで修業した。プラセンシア大聖堂で歌手として働いた。ブルゴスでは礼拝堂長を務め、3声と5声のヴィリャン シーコとカンシオンのコレクションの作者である。これらの曲は一般的に、そのうちの1曲が民謡から採られており、1551年にオスン大学から出版された。 その後、1560年には4声と5声のソネットとヴィリャンシーコの集成を出版した。 アントニオ・デ・カベソン(1500年 - 1566年)は、ブルゴス近郊の町カストリージョ・モタ・デ・フディオスで生まれた。生まれつき目が見えなかった彼は、カルロス5世とフェリペ2世のスペ イン宮廷でオルガニスト、リュート奏者、作曲家として有名であった。彼は、宗教曲と世俗曲の重要な作品の作者であり、特にスペインのリチェルカーレである ティエントスが有名である。 セビリア出身のクリストバル・デ・モラレス(1500年 - 1553年)は、16世紀スペインのポリフォニー作曲家の中でも最も優れた人物の一人である。1526年から1530年までアビラの礼拝堂長を務め、その 後ローマへ渡り、聖職に就き、1535年にはシスティーナ礼拝堂の参事会員となった。その後スペインに戻り、アルコス公爵に仕えた。ミサ曲、モテット、 ニースの和約のためのカンタータ(1538年)、イッポリト・デステのためのカンタータなど多数の作品を作曲し、マドリガルも数多く作曲した。 バルトロメ・デ・エスコベード(1515年頃 - 1563年)は、サモラ生まれ。スペインの理論家、作曲家。1536年にローマ教皇庁礼拝堂のメンバーとなり、1551年にはビセンテ人とルシタニア人の 間の論争の裁定者となった。1554年よりセゴビアの礼拝堂長となり、モテット、マニフィカト、ミゼレーレ、ミサ曲などを作曲した。 フランシスコ・デ・ペニャロサ(1470年頃 - 1528年)は、タラベラ・デ・ラ・レイナ出身の音楽家、作曲家。1498年から1516年まで、カトリック王として知られるアラゴン王フェルナンド2世 の宮廷で歌手として活躍し、その後、レオ10世のローマ教皇礼拝堂で歌手として働いた時期もあった。彼は数多くのミサ曲、モテット、その他の宗教曲の作者 である。彼はセビリアで死去した。 フランシスコ・ゲレロ(1528年 - 1599年)はモラレスの弟子であり、1546年、18歳の時にハエン(1545年)、マラガ、セビリアの礼拝堂長を務めた。彼はリスボン、ローマ、ヴェ ネツィア、聖地を訪れた。彼はこの時代の偉大な巨匠の一人である。クリスマス向けの美しいヴィリャンシーコ、精神的なビジャネラ、シャンソネタの作者。ス ペイン楽派の中でマリアをテーマにした作品に特に力を入れた、いわゆるセビリア楽派の真の代表者である。1599年11月、セビリアで死去。 ラングア出身のフランシスコ・ソト・デ・ラングア(1534年頃 - 1619年)は、男性ソプラノ歌手であり、マドリガルやラウディ・スピリチュアリス(Laudi Spirituali)の作曲家であった。1562年に教皇聖歌隊に入団し、その後は聖フィリッポ・ネリ・オラトリオ会の教会聖歌隊にも加わった。 ジョアン・パウ・プジョール(1573年 - 1626年)は、カタルーニャ生まれのスペインの合唱指揮者、作曲家。ミサ曲やその他の宗教曲、世俗曲、マドリガルなどの作品がある。彼はタラゴナ (1593年~1595年)で礼拝堂長を務め、その後サラゴサ大聖堂(1595年~1612年)とバルセロナ(1612年~1626年)で同職を務めた。 特に、 トマス・ルイス・デ・ビクトリア(c. 1548-1611)は、おそらくアビラ生まれのスペイン人作曲家であり、スペイン・ルネサンスの宗教音楽作曲家の中で最も重要な人物である。彼の作品 は、神秘主義者の先見的な熱狂に満ちている。彼の芸術では、グレゴリオ聖歌の旋律を巧みなポリフォニーで重ね合わせることを知っている。同様に、音の遅れ によって美しい不協和音を生み出し、劇的な効果を強烈に引き出している。 彼は幼い頃から、ポルトガルのマヌエル1世の息子であるインファンテ・ド・ルイスの音楽家として働いていた。1565年、ルイスの甥であるフェリペ2世の 支援を受け、彼はローマのゲルマン・カレッジに派遣され、G. P. ダ・パレストリーナの弟子となった。そして1573年には、パレストリーナの後継者となった。フィリッポ・ネーリとは個人的な友人であり、8年間、会議 (フンタ)のサン・ジェロニモ・デッラ・カリタ修道院で彼とともに隠遁生活を送った。そこで、彼は最高の音楽の多くを作曲し、1585年にそこを去った。 彼は数多くの作品の作者である。Magníficat(1581年)、Motecta libri duo(1583年)、Missa Quarti ToniとMissarum libri duo(1583年)はフェリペ2世に捧げられた作品である。Officium Hebdomadæ Sanctæ(1583年)、その他声楽のポリフォニー作品などがある。彼の『死者のためのミサ曲』(1603年)は非常に有名であり、6声部で書かれ、 ミサ曲『死者のためのミサ曲』、モテット、応答歌、レッスンが含まれている。この作品は1605年に出版され、フェリペ2世の姉であるマリア皇后の葬儀の ために作曲されたものである(『神聖ローマ皇后マリアの死と葬儀』、王室印刷所より)。(In Obitv et obsequiis Sacræ I Emperatricis, Matriti Ex Tipographia Regia)。1585年から1611年に亡くなるまで、彼はマドリードのカルメル会修道院のオルガニストを務めた。 |
| Curiosidades En su espectáculo Mastropiero que nunca, el grupo argentino de humor Les Luthiers interpreta un madrigal denominado La Bella y Graciosa Moza Marchóse a Lavar la Ropa , la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó, la frotó sobre una piedra, la colgó de un abedul, con el cual comienza el espectáculo. |
珍品 アルゼンチンのコメディグループ、レ・リュティエによる「マストロピエロ・ケ・ヌンカ(決してないマストロピエロ)」というショーでは、マドリガル「ラ・ ベリャ・イ・グラシオサ・モサ・マルチョ・ア・ラヴァール・ラ・ロパ(美しく優雅なメイドは洗濯をしにいった)」が披露される。彼女を小川に浸し、歌いな がら洗濯し、石でこすり洗いし、白樺の木に彼女を吊るす。ショーはこれで始まる。 |
| Figuralismo Glee (pieza musical) Madrigal (poesía) Madrigales de Claudio Monteverdi |
フィギュラリズム グリー(楽曲) マドリガル(詩) クラウディオ・モンテヴェルディのマドリガル |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Madrigal_(m%C3%BAsica) |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099