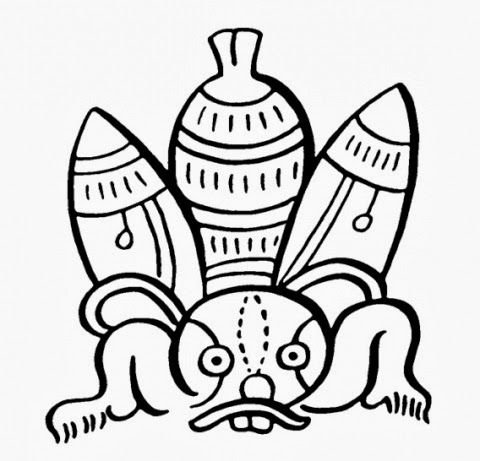人文地理学者のフレデリック・シムーンズは『この肉 を食べてはいけない:先史時代から現在までの食物禁忌』という原著で240ページの本を今から半世紀以上前に出版をした。序論と結論の間には、豚肉、牛 肉、鶏肉と卵、馬肉、ラクダ肉、犬肉、魚肉の7つのカテゴリーの「肉(フレッシュ)」の食慣習と禁忌(タブー)についての言及がある。この本の初版は出版 直後から資料の取り扱い方と結論の誘導をめぐって賛否両論の議論が湧き上がり、彼はその間さらに文献渉猟を積み重ね苦節(かどうかは知らないが)13年後 に、今度は倍以上の分量の550ページの決定版を出版した。そしてその邦訳は670ページにおよぶ。満を持した改訂版の注と文献を除いた内容分量は原書 320ページあまりだが、犬肉への言及は52ページ(16パーセント)で豚肉(27パーセント)の次に多い。豚肉や牛肉への禁忌は誰でも想像できるように 宗教による規制のためだが、犬肉食を推奨したり、あるいは禁忌したりする宗教規制はそれほど明確化されていないところに特徴がある。犬肉食に対する、人類 の関心はいかなるものだろうか。
ペット化されている今日の日本や世界の多くの地域で は、犬肉食はきわめて特殊な好みで、むしろ蛇蝎のように嫌われている。しかし、シームンズは、この視座を人類の長い歴史からみれば、まったく逆に言えると 主張し、犬肉食忌避説に異論を唱えている。本書の執筆者たちがすでに述べているように、犬は人類のもっとも古い付き合いをもつ家畜であり、およそ2万年前 から1万5千年前に始まったという説が一般的であり、シームンズも「遅くとも紀元前」1万2千年前という解説をしている。犬と狼は分類学上同じ種 (Canis lupus)であり、分子遺伝学的手法なども動員すると両者が分岐するとすれば最古なもので13万年以上前まで比定できるとまで述べる研究者もいる。
では、犬がなぜ人間の家畜になったのかについて一般 的な説明は2つあり、それは、
【1】犬(狼)の狩猟能力の高さを人間が認め飼い馴らしたのだという説と、
【2】狩人たち(当時は、農耕はまだなかった)が食べ残した肉や骨などを恐れることなく近づいて来 て、狩人たちに自発的になつくようになったという説、
である。この2つの仮説は、犬と人間がともに狩猟肉 に依存する生活をしていた競争者であったために、お互いに協力しあうことで結果的に ウィン=ウィンの関係になったという点で、ダナ・ハラウェイ(Donna Haraway, 1944- )のコンパニオン仮説 と符合するところがある。だがその際には犬と狼の違いについての考察が必要である。狼が自分よりもより大きな相手を倒せるのは、そのタフな運動の能力によ り相手を疲れさせるまで追いつめる「根性」と、集団で狩りをする知的な「連携能力」を持っているからだと言われる。もし、狼が自分たちのコンパニオンと共 同で狩猟することで自分たちの種族の生存能力——進化学では適応度という——を維持するとすれば、狼たちが犬と分岐する時に、狼たちはコンパニオンを裏切 り異なる種族の人間と同盟関係を結び直したということができる。犬たちは狼たちの親 戚なのだが、狼たちから見れば同胞の裏切り者たちの一族と言うことがで きる。
さて、そのような裏切りには実は代価(コスト)がか かったようである。フレデリック・シームンズは、クライド・マンウェ ルとアン・ベイカーの所論を紹介して、人類が犬類を手なずけた最大の要因は、その肉を食糧として利用 することであると言っている。さらに彼らの研究よりもさらに1世紀前のベルンハルト・アウグスト・ランカベルというドイツ(プロイセン)の 動物学者——こ の人には「犬と野蛮人」という論文もある——は、狩猟採集時代において食物の枯渇は狩人とその家族、ひいては一族(バンドという単位で遊動していた)に とっては危機的な状態であり、犬は非常に便利なタンパク源であったと 主張している。この人類最初の家畜の肉は、ずいぶん後になって食べるようになったどの 家畜の肉よりも脂肪分が少なくてヘルシーだというおまけもついてくる。これらのことをまとめて、「犬は共同で狩猟をするために人間を助けるのみならず時に は食われてタンパク源も提供する」ことを《シームンズのテーゼ》 と言っておこう。
この人類初の家畜は、現在の私たちの隣人=コンパニ オンでもあったが、その豊かな表情をもち——これは科学的進化学の泰斗であるチャールズ・ダーウィンのお墨つきでもある——人類と犬類がつき合い出した草 創期においてもかなり濃厚なコミュニケーションを取ることができたようだ。現在の動物行動学では、このような行動のレパートリーの共有は収斂(しゅうれ ん)と呼んでおり、これは単に犬類が人類によって一方的に馴致(馴化)されたものでなく、人類もまた犬類に合わせて自らも犬用に進化したせいだと言われて いる。
人類学研究の対象であった未開人——かつては野蛮人 と呼ばれた——に関する報告を民族誌というが、それらの報告の中には、西洋からやってきた白人の研究者がより客観的にあろうとしてもさまざまな未開人に対 する偏見が反映されていたということは、つとに指摘されているところである。そのためにこの研究草創期の民族誌記述には、現代の読者はその取り扱い方によ り慎重でなければならないとされる。そのような要注意の「記述」のひとつがカニバリズム(食人)である。かの動植物に対してきわめて客観的かつ中立な観 察態度をとったダーウィンですら、フエゴ島民の未開人の「食人」については、自分が直接観察もしていないのにも関わらず、おそらく西洋人の彼らの対する偏 見を投影して次のように言う。
「飼育動物の子孫の遺伝的形質をかつて考えたことの ないほど野蛮な未開人がいたとしても、特殊な目的のために彼らにとって特に有用な動物は、彼らが受け易い飢餓やその他の災難の間にも注意して保存されるで あろう。そしてこのような選ばれた動物は一般に劣った動物よりも多くの子孫を残すに違いない。従ってこの場合にも一種の無意識的淘汰が進行していることに なる。フエゴ諸島(Tierra del Fuego)の未開人でさえ動物に価値を認め、食料欠乏のときに、犬よりも価値のないものとして彼らの老婦を殺して食うのである」(ダーウィン 2009:28)。
その後の民族誌においてフエゴ諸島の未開人——とい うもののアン・チャップマンの民族誌によるとその末裔は1980年代には数人のレベルまで激減していた——が「食料欠乏のときに、犬よりも価値のないもの として彼らの老婦を殺して食う」事実は発見されたことがない。真実なのは、ダーウィンがビーグル号に乗船してこの地に上陸した時期には、もちろんカニバリ ズムの習慣などなく、またダーウィンも観察などしていないことである。いずれにせよ、この場合は、《シームンズのテーゼ》のうち、犬への有用性評価と愛着 が、タンパク質としての人間的価値よりも尊ばれたということになる。
シームンズは、多くの文献渉猟し、人類の多くの集団 では犬肉を常用してきたことを明らかにした。同時に、犬肉を食べることを忌避する宗教的規制や慣習もあったことも指摘している。彼のアプローチは非常に公 平で、すでに言われていることをそのまま鵜呑みにすることではなく、反証例をもって前者の説を検証し、適切な着地点をめざすというものである。例えば、 「ムスリムは犬を嫌う」というステレオタイプは、「ムスリムもペットとして犬に愛着をもつ人が少なからずいる」という報告によって相対化され、歴史的な検 証がなされる。この場合、人類と犬との共存がもたらした人類進化の感情のベースの上に、犬に対する宗教的な忌避思想が後の時代に普及、被さり、このムスリ ムの犬に対する感情の両義性——愛着と嫌悪の相矛盾する感覚の共存——が後に生まれたのだと推測する。
さて、しかしながら人類と犬類が邂逅した歴史の初期 においては犬食が頻繁におこなわれた考古学資料もたくさんあるが、それは現在の食肉用家畜のような人間と家畜のようなよそよそしい関係ではない。犬は有益 なタンパク源として利用されるのみならず、供犠獣としてよく使われてきた。そのため儀礼用の犬は聖別されて敬われていた可能性が多いにある。ここでも人類 と犬類は、近しいコンパニオンであると同時に、やがてあの世におくるために神に捧げられて、場合によっては人間の胃袋も満たすという役割も果たしてきたと いうのだ。犬と人間の貸借対照表(バランスシート)は明らかに、人間がより多く犬に負債をおっている。
他方、シームンズは犬肉食が嫌われる集団の忌避の理 由と、犬肉を常食する人たちのどのような肉が好まれるのかについては、共通する価値がみられることを指摘している。つまり「なぜ犬肉を食わないのか」とい う調査者の質問に答える集団の多くは「犬肉が汚いからだ」と答える。あるいは犬の食べ方は汚いというものもある。では「なぜ犬肉は汚いのか」という次の質 問には「連中は屍肉(=汚い餌)をたべるからだ」と説明している。たしかに、犬がリードにつながれて人間が与える餌(残飯や専用のドッグフード)を食べる 以前は、多くの犬は放し飼いにされていた。飼い犬ですら放浪化したり、野犬化したりする。それで野犬は行路死した同胞や他の動物の屍肉をたべる状況を人間 は長く目撃してきたであろう。それゆえ「犬の肉は汚い」という推論から犬肉食の忌避へとつながる、と言うのだ。他方、犬肉を常食する人たちの肉の選好性は どうであろうか。それによると、幼犬、成犬、老犬の順になり、幼犬は食べるが老犬は食べないという社会も多くあるらしい。その理由もまた「成犬になればな るほど肉は汚い」というものだ。もちろん、あらゆるほ乳動物の肉は、人間のものも含めて、若い獣のほうが圧倒的に「柔らかくておいしい」(ジョナサン・ス ウィフトの言葉)。
犬肉への忌避は、ペットとして愛しているものをわざ
わざ食糧として食べたくないという多く人の信条と論理的に整合している。それゆえ、シームンズも犬肉を忌避する人や集団が、犬が汚い餌を食べることと、人
間との深い結びつきという二つの理由によるものだと主張している。
つづく......
■資料:Thịt chó(ベトナム語)より

Thịt chó được bán tại một chợ ở Hà Nội, Việt Nam

リンク(外部)
リンク
文献
- 肉食タブーの世界史 /
フレデリック,J.シムーンズ [著] ; 香ノ木隆臣, 山内彰, 西川隆訳,法政大学出版局 , 2001.12 . -
(叢書・ウニベルシタス ; 709)/Eat not this flesh : food avoidances from prehistory
to the present / Frederick J. Simoons, 2nd ed., rev. and enl. - Madison
: University of Wisconsin Press , c1994.
その他の情報