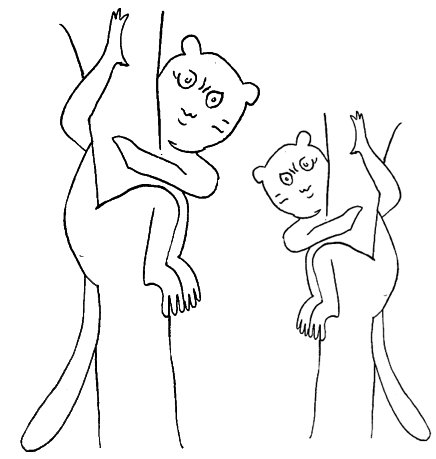
パイドロスと記憶
Phaedrus and his memory
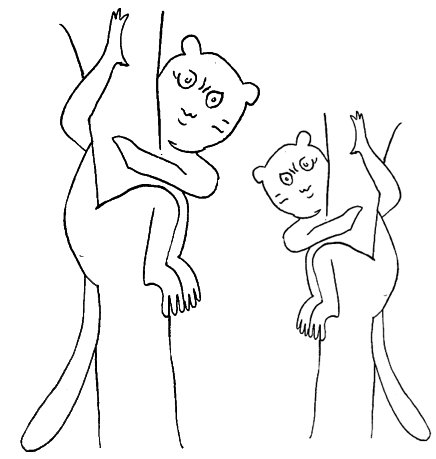
『パイドロス』 (古希: Φαῖδρος、英: Phaedrus)は、プラトンの中期対話篇の1つであり、そこに登場する人物の名称。副題は「恋(エロース)について」[1][2]など。
| 紀元前5世紀末、真夏の日中、アテナイ南郊外にて。ソクラテスがパイド ロスと出くわすところから話は始まる。パイドロスは朝早くから弁論作家リュシアスのところで長い時間を過ごし、今出てきたところで、これから城壁の外へ散 歩に行く所だという。(リュシアス等ケパロスの一家は、アテナイ市民ではなく、アテナイの外港ペイライエウスに住む富裕居留民だが(『国家』参照)、リュ シアスはその時はアテ ナイの町に来て、城壁の南東内側にあるゼウス神殿近くの、民主派政治弁論家エピクラテスの家に滞在しており、そこで一緒に時を過ごしたのだという。)パイ ドロスとリュシアスが何を話していたのか気になるソクラテスは、パイドロスの散歩に付き合いながら聞き出そうとする。なんでも、リュシアスが書いた、 「好きでもない美少年を口説く男」の風変わりな恋(エロース)の話だという。俄然興味が湧いたソクラテスは、パイドロスがその文書を上着の下に隠してるの を見つけ、是非教えてくれるよう頼む。2人はイリソス川に入って川沿いに歩いて行き、プラタナスの木陰に腰を下ろし、恋の話を披露し合いまた語らい合う。 十分に語らい合い、両者がそこを立ち去るまでが描かれる。 |
| ●想起 我々人間の知る働きは、雑多な感覚から出発して単一なる形相(エイドス)に即して行われるが、これは我々の中の「魂」がかつて見ていた真実在(イデア)を 「想起」しているに他ならない。 |
| ●話すことについて ソクラテスは上手に語るためには対象の「真実」をよく知っていなくてはならないと考えるが、説得を目的とする弁論術(レートリケー)を「言論の技術(テク ネー)」の名で広めている教師たち[10]は、内容が正しいかどうかよりも、「群衆の心に正しいと思われるかどうか」が重要であることを説いている。この 双方の考えの対立を背景として、ソクラテスがこの弁論術教師たちの主張を突き崩すべく話を進めていく。 ソクラテスは弁論術が物事の「類似性・混同」を利用して相手の魂を思い 通りに誘導していく術であるならば、対象の「真実」を知っていて、他との「類似点」 や「相違点」を正確に把握していなくては、そのようなことはうまくできないことを指摘する。特に「正しい」「善い」といった異論の多い抽象概念に関して は、そうした把握が大事になってくる。先の3つの話で扱った「恋」も同様で、最初のリュシアスの話はそれができていなかったが、2番目のソクラテスの話は 冒頭で「恋」の定義を行っていた。また2番目の話と3番目の話で「恋」について反対の評価を下す話をしたし、3番目の話の中では「狂気」を4分類して説明 した。 ソクラテスがなにげなく語った話の中でそうしたことができたのは、多様に散らばって いる概念を「綜合・定義」し、また自然本来の分節に従って「分割」する という「2種類の手続き」を行ったからだという。ソクラテスはそれを 「ディアレクティケー」(弁証術・問答法)と呼び、「レートリケー」(弁論術)と対置 させる。 次にソクラテスは、「言論の技術(テクネー)」の名で多様に教科書が書かれ、教えられている弁論術[10]の内容、例えば、 テオドロスの「序論・陳述・証拠・証明・蓋然性・保証(続保証)・反駁(続反駁)」で構成される法廷弁論術 エウエノスの「ほのめかし法」「婉曲賞讃法」「あてこすり法」 テイシアス[11]・ゴルギアス・プロディコス・ヒッピアス等の話術 ゴルギアスの弟子ポロスの「重言法」「格言的話法」「譬喩的話法」 リキュムニオスの美文創作術 プロタゴラスの「正語法」 トラシュマコスの「俳優術」[12] その他に話の最後に「総括」(要約)を持ってくる手法 などを列挙し、こうした「予備的」な内容で以てその分野の技術を修得したと称しても、例えば医者・悲劇詩人・音楽家などであれば相手にされないと指摘す る。 ソクラテスは自分が技術を身につけ、他人にも教授することを望むのなら、まずはその技術の対象が「単一」なのか「多種類」なのかを調べ、「多種類」であれ ばそれを一つ一つ数え上げ、それら一つ一つの「機能・性質」(能動的作用・受動的作用)を調べ把握しなくてはならないと指摘する。そして弁論術であれば 「魂」がその対象となるので、第1に「魂」が「単一」なのか「多種類」なのか、第2に「魂」の「機能・性質」(能動的作用・受動的作用)、第3に「話し 方」の種類と「魂」の種類、それらの反応の分類整理と原因を論じることができてはじめて技術と呼ぶに値するものである(すなわち弁論術は技術と呼ぶに値し ない)ことを指摘する。 ソクラテスは締め括りに架空のテイシアス[11]に語りかける体裁で、「真実らしくみえるもの」は「真実」に似ているからこそ多数の者に真実らしく見える のであり、その「真実」と他の類似を最も把握できるのはいつの場合も「真実」そのものを知っている者であること、そしてその「真実」の把握には対象の詳細 な検討が必要であり並々ならぬ労苦を伴うこと、それを人間相手の説得という「小さな目的」のために行うよりは神々の御心にかなうように語れる・振る舞える ようになるという「大きな目的」のために行うべきであり、そうしていれば自ずと「小さな目的」も達成されるようになることなどを述べる。 |
| ●書くことについて 「話すこと」に関する議論が終わり、続いて「書くこと」についての議論に移る。 ソクラテスはまず古来から伝わる物語という体裁でエジプトにまつわる創作話を披露する。テーバイ(テーベ)に住んでエジプト全体に君臨していた神の王タモス(アモン、アンモーン)の 下に、発明の神であるテウト(トート)がやって来て、様々な技術を披露した。「文字」を披露した時、テウトはそれが知恵を高め、記憶を良くすると説明した が、タモスはむしろ人々は「文字」という外部に彫られた印(しるし)に頼り、記憶の訓練を怠り、自分の内から想起することをしなくなるので、かえって忘 れっぽい性質が植え付けられてしまうこと、また「文字」によって親密な教えを受けなくても「物知り」になれるため、上辺だけのうぬぼれた付き合いにくい自 称知者・博識家を生むだろうと指摘する。 ソクラテスは「書かれた言葉」というものは「絵画」と似ていて、何か尋 ねてみても沈黙して答えず、また内容を理解できない不適当な者の目にも触れてしまう し、誤って扱われたり不当に罵られても身を守ることができないものであり、せいぜい自分が老いた時や自分と同じ道を進む者のために蓄えておく「覚え書き」 「慰み」程度にしかならないものだと指摘する。 そしてそれと対比されるのが、「書かれた言葉」と兄弟関係にあり正嫡の 子とも言うべき「ものを知る者が語る生命を持った言葉」「学ぶ人の魂の中に知識と共 に書き込まれる言葉」であり、それはちょうど農夫が適した土地に種を蒔いて時間をかけて育てていくように、「ディアレクティケー」(弁証術・問答法)の技 術を使ってその内部、魂の中に「正義」「善」「美」の知識と共に植え付けられるものであり、その中の種を育て、継承し、不滅のままに保っていくものである と述べる。 こうして全ての問答が終わり、これまでの内容をおさらいした後、ソクラテスは「長い 時間をかけて文句をひねくり返し組み立て書き、その作品以上のものを自 己の中に持ってないような者」はそれらの書き物からつけられる「詩人」「作文家」「法律起草家」などの名で呼ばれるのがふさわしいが、他方で真実のありよ うを知り自己の魂の中に書き込まれている知識・言葉に基づいて語ることができる者はその真剣な目的から採って「愛知者(哲学者)」などの名で呼ぶのが適切 だと述べる。 最後にソクラテスが当時まだ若かったイソクラテスが偉大になることを予言しつつ、土地の神々に祈りを捧げて2人はその場を去る。 |
| パ イドロス |
★「パイドロス」終わりの部分:https://www.gutenberg.org/files/1636/1636-h/1636-h.htm
「ソクラテス: しかし、書かれた言葉には必然的に多くの不真面目なものが含まれており、詩であれ散文であれ、口頭であれ書面であれ、それらは大した価値を持たないと考え る者は、 批評や教訓を目的とせず、ただ信じさせるために朗誦されるものだと考える者。 また、最良の著作でさえ我々が知るものの記憶に過ぎず、 教訓のために口頭で教え伝えられ、魂に刻まれた正義と善と高貴さの原理のみが、 真の書き方であり、明晰さと完璧さと真摯さを備えていると考える者。 そして、そうした原理は人間自身のもの、正当な子孫であると考える者── まず第一に、彼が自らの内に見出す言葉こそが 真の書き方である。そこには明晰さと完全さと厳粛さがあり、 そうした原理こそが人の真の子であり正当な子孫である—— 第一に、自らの胸中に見出す言葉であり、 第二に、自らの理念の兄弟や子孫や親族であり、 自ら他者の魂に正しく植え付けたものである—— そしてそれらを他の何よりも気にかける者こそが、 真に正しい人間である。そして、フェードロス(=パイドロス)よ、 我々は彼のような者になりたいと願うだろう。 他の言葉など顧みない——これこそ正しい人間である。そして君と私は、 フェードロスよ、彼のような者になれますようにと祈るだろう」
ソクラテス:もし誰かが、文字が理解可能で確実であるという考えのもとで、いかなる技術も文 字に記して残したり受け取ったりするならば、あるいは文字が同じ事柄に関する知識や記憶よりも優れていると考えるならば、その者は非常に単純な人格であ り、タモスやアモンの神託にはまったく無縁な者であろう。
ソクラテス:フェードロスよ、残念ながら書物は絵画に似ていると私は感じずにはいられない。 画家の作品は生命の息吹を宿しているのに、問いを投げかけても厳かな沈黙を守る。演説も同様だ。知性があるかのように思えるが、何かを知りたくなって問い を投げかけても、演説者は常に同じ答えしか返さない。いったん書き記されると、 理解できる者にもできない者にも、無造作に放り出される。 誰に答えるべきか、誰に答えるべきでないか、 見当もつかない。 虐待され、侮辱されても、 守る親はいない。 自らを守り、身を守る術もないのだ。
ソクラテス:つまり、学び手の魂に刻まれた知的な言葉のことだ。 それは自らを守ることができ、いつ語り、いつ沈黙すべきかを知っている。
フェードロス:つまり、魂を持つ生きた知識の言葉であり、 書かれた言葉は本来、その単なる写しに過ぎないというのか?
ソクラテス:では彼は、ペンとインクで自らの考えを「水に」書き記すこと、すなわち自らを語ることすらできず、他者に真実を十分に教えることのできない言葉を蒔くことに、真剣に傾倒することはないだろう?(フェードロス「それはありえない」)
ソクラテス:いや、それはありえない――学問の園で彼は
種を蒔き、植えるだろうが、それはただ娯楽と楽しみのためだ。 老いによる忘却に備え、自らあるいは同じ道を歩む他の老人が
大切に保管する記念として、それらを書き留めるだろう。 彼はその若芽の成長を喜びながら見守る。他の人々が
宴やそれに類するもので魂を潤している間、これが彼の日々を費やす 娯楽となるだろう。
ソクラテス:人が書き記し、あるいは語っている諸々の事柄の真実を知り、
それらをありのままに定義し、定義した上でさらに分割し続け、 もはや分割できなくなるまで分割し、 同様に魂の本質を見極め、
異なる性質に適した様々な話し方の様式を発見し、 それらを整理し配置する方法を身につけるまでは、
分割できなくなるまで分割し、同様に魂の本質を識別し、 異なる性質に適した様々な言説の様式を発見し、
それらを整理・配置して、単純な性質には単純な言葉の形式を、 より複雑な性質には複雑で複合的なものを用いることができるようになるまで―
これら全てを達成するまでは、 これら全てを達成するまでは、 その性質が技術に従属することを許す限りにおいて、
技術的な規則に従って議論を扱うことはできないだろう。 それは、教えるためであれ説得するためであれ、
—これが、前述の議論全体に内在する見解である。
ソクラテス:しかし、書かれた言葉には必然的に多くの不真面目なものが含まれており、詩であ
れ散文であれ、口頭であれ書面であれ、それらは大した価値を持たないと考える者は、
批評や教訓を目的とせず、ただ信じさせるために朗誦されるものだと考える者。 また、最良の著作でさえ我々が知るものの記憶に過ぎず、
教訓のために口頭で教え伝えられ、魂に刻まれた正義と善と高貴さの原理のみが、 真の書き方であり、明晰さと完璧さと真摯さを備えていると考える者。
そして、そうした原理は人間自身のもの、正当な子孫であると考える者── まず第一に、彼が自らの内に見出す言葉こそが
真の書き方である。そこには明晰さと完全さと厳粛さがあり、 そうした原理こそが人の真の子であり正当な子孫である——
第一に、自らの胸中に見出す言葉であり、 第二に、自らの理念の兄弟や子孫や親族であり、 自ら他者の魂に正しく植え付けたものである——
そしてそれらを他の何よりも気にかける者こそが、 真に正しい人間である。そして、フェードロスよ、 我々は彼のような者になりたいと願うだろう。
他の言葉など顧みない——これこそ正しい人間である。そして君と私は、 フェードロスよ、彼のような者になれますようにと祈るだろう。
★紀元前5世紀末、真夏の日中、アテナイ南郊外にて。
★つまり、文字言語は、ファルマコンつまり「毒」であり、かつ「薬」である。
リンク
文献
その他の情報


Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099