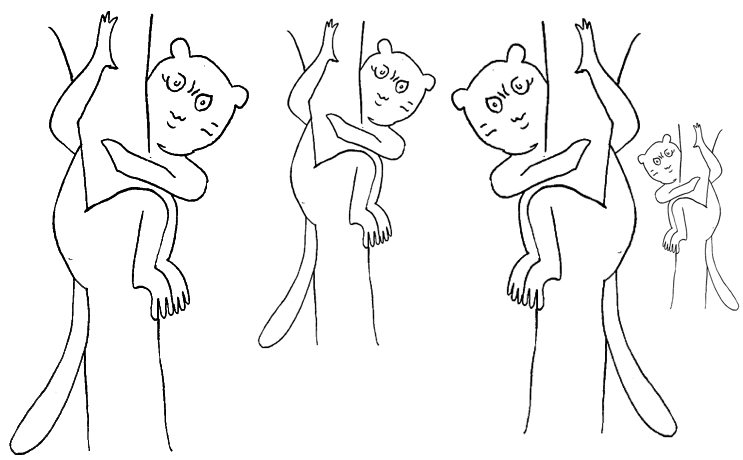
徳の倫理学
Virtue ethics
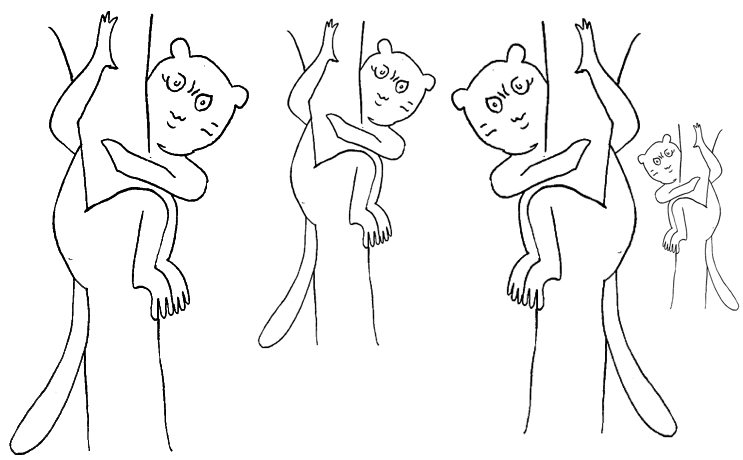
☆ 徳倫理学(アレテー的倫理学とも[a][1]、ギリシャ語のἀρετή [aretḗ]に由来する)とは、自発的な行為の結果、行動の原則や規則、あるいは神の権威への服従を主要な役割とする他の倫理体系とは対照的に、徳と人 格を倫理の主要な主題として扱う哲学的アプローチである[2](→規範倫理学のひとつ)。 徳倫理学は通常、倫理学における他の2つの主要なアプローチである帰結主義と義務論と対比される。帰結主義では行為の結果の善し悪し(帰結主義)、義務論 では道徳的義務の概念(義務論)が中心となる。徳倫理学は、状況の善性や道徳的義務の倫理学にとっての重要性を必ずしも否定するものではないが、他の倫理 学理論にはない程度に徳や、時にはエウダイモニアのような他の概念を強調する[要出典]。徳の倫理学の代表格はアリストテレスの倫理学(とりわけ「ニコマコス倫理学」で論じられたもの)である。
☆下記のものに重複するが、再掲する。
| According to
Rosalind Hursthouse, in Aristotelian virtue ethics, the emotions have
moral significance because "virtues (and vices) are all dispositions
not only to act, but to feel emotions, as reactions as well as impulses
to action... [and] In the person with the virtues, these emotions will
be felt on the right occasions, toward the right people or objects, for
the right reasons, where 'right' means 'correct'..."[8] [8] Hursthouse, Rosalind (1997). "Virtue Ethics and the Emotions". In Statman, Daniel (ed.). Virtue Ethics: A Critical Reader. Edinburgh University Press. p. 108. |
ロザリンド・ハーストハウスによれば、アリストテレスの徳倫理学におい
て感情が道徳的意義を持つのは、「徳(および悪徳)はすべて、行動するだけでなく感情を抱く傾向でもあるからだ。それは反応として、また行動への衝動とし
て現れる...
[そして]徳を備えた人格においては、これらの感情は適切な機会に、適切な対象や人物に対して、正しい理由から感じられる。ここで『正しい』とは『適切で
ある』ことを意味する...」[8] [8] Hursthouse, Rosalind (1997). 「Virtue Ethics and the Emotions」. In Statman, Daniel (ed.). Virtue Ethics: A Critical Reader. Edinburgh University Press. p. 108. |
| Phronesis and eudaimonia Phronesis (φρόνησις; prudence, practical virtue, or practical wisdom) is an acquired trait that enables its possessor to identify the best thing to do in any given situation.[9] Unlike theoretical wisdom, practical reason results in action or decision.[10] As John McDowell puts it, practical wisdom involves a "perceptual sensitivity" to what a situation requires.[11] 9. Pincoffs, Edmund (1971). "Quandary ethics". Mind. 80 (320): 552–571. doi:10.1093/mind/LXXX.320.552. 10. Kraut, Richard (2016-01-01). Zalta, Edward N. (ed.). Aristotle's Ethics (Spring 2016 ed.). Archived from the original on 2019-03-18. Retrieved 2016-05-05. 11. McDowell, John (1979). "Virtue and Reason". The Monist. 62 (3): 331–350. doi:10.5840/monist197962319. |
フロネシスとユーダイモニア フロネシス(φρόνησις、慎重さ、実践的徳、あるいは実践的知恵)とは、その所有者が、あらゆる状況において最善の行動を見極めることを可能にす る、後天的に獲得される特性である[9]。理論的な知恵とは異なり、実践的理性は行動や決断につながる[10]。ジョン・マクダウェルが言うように、実践 的知恵には、状況が要求するものに対する「知覚的感受性」が伴う。[11] 9. Pincoffs, Edmund (1971). "Quandary ethics". Mind. 80 (320): 552–571. doi:10.1093/mind/LXXX.320.552. 10. Kraut, Richard (2016-01-01). Zalta, Edward N. (ed.). Aristotle's Ethics (Spring 2016 ed.). Archived from the original on 2019-03-18. Retrieved 2016-05-05. 11. McDowell, John (1979). "Virtue and Reason". The Monist. 62 (3): 331–350. doi:10.5840/monist197962319. |
| Eudaimonia (εὐδαιμονία) is a state variously translated from Greek as
'well-being', 'happiness', 'blessedness', and in the context of virtue
ethics, 'human flourishing'.[12] Eudaimonia in this sense is not a
subjective, but an objective, state.[citation needed] It characterizes
the well-lived life. 12. Pojman, L.P.; Fieser, J. (2009). "Virtue Theory". Ethics: Discovering Right and Wrong (6th ed.). Belmont, Calif.: Wadsworth. pp. 146–169. |
ユーダイモニア(εὐδαιμονία)は、ギリシャ語から「幸福」、「幸福」、「祝福」、そして徳倫理の文脈では「人間の繁栄」とさまざまな訳語がある
状態だ。[12] この意味でのユーダイモニアは主観的な状態ではなく、客観的な状態だ。[要出典] それは、よく生きた人生の特徴だ。 12. Pojman, L.P.; Fieser, J. (2009). "Virtue Theory". Ethics: Discovering Right and Wrong (6th ed.). Belmont, Calif.: Wadsworth. pp. 146–169. |
| According to Aristotle, the most prominent exponent of eudaimonia in
the Western philosophical tradition, eudaimonia defines the goal of
human life. It consists of exercising the characteristic human
quality—reason—as the soul's most proper and nourishing activity. In
his Nicomachean Ethics, Aristotle, like Plato before him, argued that
the pursuit of eudaimonia is an "activity of the soul in accordance
with perfect virtue",[13]: I which further could only properly be
exercised in the characteristic human community—the polis or
city-state.[14] 13.Dubey, Damayanti (December 31, 2021). "12 Virtues of Aristotle". evolveinc.io. 14. Aristotle. Politics. |
西洋哲学伝統においてユーダイモニアの最も顕著な提唱者であるアリストテレスによれば、ユーダイモニアは人間生活の目標を定義する。それは、魂にとって最
も適切かつ滋養となる活動として、人間特有の資質である理性を行使することから成る。『ニコマコス倫理学』においてアリストテレスは、彼以前のプラトンと
同様に、ユーダイモニアの追求は「完全な徳に従った魂の活動」であると論じた[13]: I 。そしてそれはさらに、人間特有の共同体——ポリス(都市国
家)——においてのみ適切に行使され得るとした。[14] 13.Dubey, Damayanti (December 31, 2021). "12 Virtues of Aristotle". evolveinc.io. 14. Aristotle. Politics. |
| Although eudaimonia was first popularized by Aristotle, it now belongs
to the tradition of virtue theories generally.[15] For the virtue
theorist, eudaimonia describes that state achieved by the person who
lives the proper human life, an outcome that can be reached by
practicing the virtues. A virtue is a habit or quality that allows the
bearer to succeed at his, her, or its purpose. The virtue of a knife,
for example, is sharpness; among the virtues of a racehorse is speed.
Thus, to identify the virtues for human beings, one must have an
account of what is the human purpose. 15. Hursthouse, Rosalind (8 Dec 2016). "Virtue Ethics". Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University. Archived from the original on 23 September 2018. Retrieved 11 May 2020. Although modern virtue ethics does not have to take a 'neo-Aristotelian' or eudaimonist form..., almost any modern version still shows that its roots are in ancient Greek philosophy by the employment of three concepts derived from it. These are arête (excellence or virtue), phronesis (practical or moral wisdom) and eudaimonia (usually translated as happiness or flourishing). |
ユーダイモニアはアリストテレスによって初めて普及したが、現在では一般的に徳理論の伝統に属している[15]。徳理論家にとって、ユーダイモニアとは人
間らしい生活を実践する人格が到達する状態を指し、それは徳を実践することによって達成可能な結果である。徳とは、その保持者が自らの目的を達成すること
を可能にする習慣または資質である。例えば、ナイフの徳は鋭さである。競走馬の徳の一つは速さである。したがって、人間の徳を特定するには、人間の目的が
何であるかを説明しなければならない。 15. ハーストハウス、ロザリンド(2016年12月8日)。「徳倫理学」。スタンフォード哲学百科事典。スタンフォード大学。2018年9月23日にオリジナ ルからアーカイブ。2020年5月11日に閲覧。現代の徳倫理学は必ずしも「新アリストテレス主義」やユーダイモニストの形を取る必要はないが…、ほぼ全 ての現代版は、古代ギリシャ哲学に由来する三つの概念を採用することで、その根源が古代ギリシャ哲学にあることを示している。これらはアレテー(卓越性ま たは徳)、フロネーシス(実践的または道徳的知恵)、ユーダイモニア(通常は幸福または繁栄と訳される)である。 |
| Not all modern virtue ethics theories are eudaimonic; some propose
another end in place of eudaimonia, while others are non-teleological:
that is, they do not account for virtues in terms of the results that
the practice of the virtues produce or tend to produce.[16] 16. Statman, Daniel (1997). "Introduction to Virtue Ethics". Virtue Ethics: A Critical Reader. Edinburgh University Press. p. 11. ISBN 0878402217. [I]t is important to notice (1.) that virtue ethics is not necessarily tied to the notion of wellbeing; and (2.) that according to some philosophers, virtue ethics is necessarily, or at least typically, of a non-teleological nature. |
現代の徳倫理学理論の全てがユーダイモニア的ではない。ユーダイモニアに代わる別の目的を提案するものもあれば、非目的論的なものもある。つまり、徳の実践がもたらす結果や傾向によって徳を説明しないのである。[16] 16. Statman, Daniel (1997). "Introduction to Virtue Ethics". Virtue Ethics: A Critical Reader. Edinburgh University Press. p. 11. ISBN 0878402217. [I]t is important to notice (1.) that virtue ethics is not necessarily tied to the notion of wellbeing; and (2.) that according to some philosophers, virtue ethics is necessarily, or at least typically, of a non-teleological nature. |
★
| Virtue ethics (also
aretaic ethics,[a][1] from Greek ἀρετή [aretḗ]) is a philosophical
approach that treats virtue and character as the primary subjects of
ethics, in contrast to other ethical systems that put consequences of
voluntary acts, principles or rules of conduct, or obedience to divine
authority in the primary role.[2] Virtue ethics is usually contrasted with two other major approaches in ethics, consequentialism and deontology, which make the goodness of outcomes of an action (consequentialism) and the concept of moral duty (deontology) central. While virtue ethics does not necessarily deny the importance to ethics of goodness of states of affairs or of moral duties, it emphasizes virtue, and sometimes other concepts, like eudaimonia, to an extent that other ethics theories do not.[citation needed] |
徳倫理学(アレテー的倫理学とも[a][1]、ギリシャ語のἀρετή
[aretḗ]に由来する)とは、自発的な行為の結果、行動の原則や規則、あるいは神の権威への服従を主要な役割とする他の倫理体系とは対照的に、徳と人
格を倫理の主要な主題として扱う哲学的アプローチである[2]。 徳倫理学は通常、倫理学における他の2つの主要なアプローチである帰結主義と義務論と対比される。帰結主義では行為の結果の善し悪し(帰結主義)、義務論 では道徳的義務の概念(義務論)が中心となる。徳倫理学は、状況の善性や道徳的義務の倫理学にとっての重要性を必ずしも否定するものではないが、他の倫理 学理論にはない程度に徳や、時にはエウダイモニアのような他の概念を強調する[要出典]。 |
| Key concepts Virtue and vice Main articles: Virtue and Moral character In virtue ethics, a virtue is a characteristic disposition to think, feel, and act well in some domain of life.[3] In contrast, a vice is a characteristic disposition to think, feel, and act poorly. Virtues are not everyday habits; they are character traits, in the sense that they are central to someone’s personality and what they are like as a person. In early versions and some modern versions of virtue ethics, a virtue is defined as a character trait that promotes or exhibits human "flourishing and well being" in the person who exhibits it.[4] Some modern versions of virtue ethics do not define virtues in terms of well being or flourishing, and some go so far as to define virtues as traits that tend to promote some other good that is defined independently of the virtues, thereby subsuming virtue ethics under (or somehow merging it with) consequentialist ethics.[5] To Aristotle, a virtue was not a skill that made you better able to achieve eudaimonia but was itself an expression of eudaimonia—eudaimonia in activity.[6] In contrast with consequentialist and deontological ethical systems, in which one may be called upon to do the right thing even though it is not in one's own interests (one is to do it instead for the greater good, or out of duty), in virtue ethics, one does the right thing because it is in one's own interests. Part of training in practical virtue ethics is to come to see the coincidence of one's enlightened self-interest and the practice of the virtues, so that one is virtuous willingly, gladly, and enthusiastically because one knows that being virtuous is the best thing one can do with oneself.[7]: I |
主要概念 美徳と悪徳 主な記事 美徳と道徳的性格 徳倫理学において、徳とは、人生のある領域において、よく考え、感じ、行動する特徴的な気質のことである[3]。対照的に、悪徳とは、悪く考え、感じ、行 動する特徴的な気質のことである。美徳は日常的な習慣ではなく、その人の性格や人としてのあり方の中心をなすという意味で、性格的特徴である。 徳倫理学の初期バージョンやいくつかの現代バージョンでは、徳は、それを発揮する人の人間的な「繁栄と幸福」を促進する、または発揮する性格的特徴として 定義されている[4]。徳倫理学のいくつかの現代バージョンは、幸福や繁栄の観点から徳を定義しておらず、徳とは別に定義される他の善を促進する傾向のあ る特徴として徳を定義することまで行っており、それによって徳倫理学を結果主義倫理学の下に(または何らかの形でそれと融合させて)包含している[5]。 アリストテレスにとって徳とは、エウダイモニアを達成しやすくするスキルではなく、それ自体が活動におけるエウダイモニア=エウダイモニアの表現であった[6]。 結果論的倫理体系や義務論的倫理体系とは対照的に、徳倫理においては、自分の利益にならないことであっても正しいことをするよう求められることがある(よ り大きな善のために、あるいは義務として)。実践的な徳倫理の訓練の一部は、自分の啓発された自己利益と徳の実践が一致することを理解するようになること であり、そうすることで、徳を積むことが自分にできる最善のことだと知っているからこそ、進んで、喜んで、熱心に徳を積むことができるようになる[7]: I |
| Virtue and emotion In ancient Greek and modern eudaimonic virtue ethics, virtues and vices are complex dispositions that involve both affective and intellectual components.[8] That is, they are dispositions that involve both being able to reason well about the right thing to do (see below on phronesis), and also to engage emotions and feelings correctly. For example, a generous person can reason well about when and how to help people, and such a person also helps people with pleasure and without conflict. In this, virtuous people are contrasted not only with vicious people (who reason poorly about what to do and are emotionally attached to the wrong things) and with the incontinent (who are tempted by their feelings into doing the wrong thing even though they know what is right), but also with the merely continent (whose emotions tempt them toward doing the wrong thing but whose strength of will lets them do what they know is right). According to Rosalind Hursthouse, in Aristotelian virtue ethics, the emotions have moral significance because "virtues (and vices) are all dispositions not only to act, but to feel emotions, as reactions as well as impulses to action... [and] In the person with the virtues, these emotions will be felt on the right occasions, toward the right people or objects, for the right reasons, where 'right' means 'correct'..."[9] |
美徳と感情 古代ギリシアや現代のエウダイモニックな美徳倫理学では、美徳と悪徳は情緒的要素と知的要素の両方を含む複雑な気質である[8]。つまり、美徳と悪徳は、 なすべき正しいこと(フロネシスについては後述)についてよく推論できることと、感情や情緒を正しく働かせることの両方を含む気質である。 例えば、寛大な人は、いつ、どのように人々を助けるべきかについてよく推論することができ、そのような人はまた、喜びをもって、争うことなく人々を助ける ことができる。この点で、高潔な人は、悪徳な人(何をすべきかについて理性に乏しく、間違ったことに感情的に執着する)や不節制な人(何が正しいかを知っ ているにもかかわらず、感情に誘惑されて間違ったことをしてしまう)だけでなく、単に大陸的な人(感情に誘惑されて間違ったことをしてしまうが、意志の強 さによって正しいと知っていることを実行できる)とも対比される。 ロザリンド・ハーストハウスによれば、アリストテレスの徳倫理学では、感情は道徳的な意味を持つ。[そして[中略]徳のある人においては、これらの感情は 正しい場面で、正しい人や対象に対して、正しい理由のために感じられるのであり、ここで『正しい』とは『正しい』という意味である」[9]。 |
| Phronesis and eudaimonia Phronesis (φρόνησις; prudence, practical virtue, or practical wisdom) is an acquired trait that enables its possessor to identify the best thing to do in any given situation.[10] Unlike theoretical wisdom, practical reason results in action or decision.[11] As John McDowell puts it, practical wisdom involves a "perceptual sensitivity" to what a situation requires.[12] Eudaimonia (εὐδαιμονία) is a state variously translated from Greek as 'well-being', 'happiness', 'blessedness', and in the context of virtue ethics, 'human flourishing'.[13] Eudaimonia in this sense is not a subjective, but an objective, state.[citation needed] It characterizes the well-lived life. According to Aristotle, the most prominent exponent of eudaimonia in the Western philosophical tradition, eudaimonia defines the goal of human life. It consists of exercising the characteristic human quality—reason—as the soul's most proper and nourishing activity. In his Nicomachean Ethics, Aristotle, like Plato before him, argued that the pursuit of eudaimonia is an "activity of the soul in accordance with perfect virtue",[7]: I which further could only properly be exercised in the characteristic human community—the polis or city-state.[14] Although eudaimonia was first popularized by Aristotle, it now belongs to the tradition of virtue theories generally.[15] For the virtue theorist, eudaimonia describes that state achieved by the person who lives the proper human life, an outcome that can be reached by practicing the virtues. A virtue is a habit or quality that allows the bearer to succeed at his, her, or its purpose. The virtue of a knife, for example, is sharpness; among the virtues of a racehorse is speed. Thus, to identify the virtues for human beings, one must have an account of what is the human purpose. Not all modern virtue ethics theories are eudaimonic; some place another end in place of eudaimonia, while others are non-teleological: that is, they do not account for virtues in terms of the results that the practice of the virtues produce or tend to produce.[16] |
フロネシスとエウダイモニア フロネシス(φρόνησις;慎重さ、実践的な美徳、または実践的な知恵)とは、その所有者がどのような状況においても最善の行動をとることができるよ うにする後天的な特性である[10]。理論的な知恵とは異なり、実践的な理性は行動や決断をもたらす[11]。 ジョン・マクダウェルが言うように、実践的な知恵には、状況が必要とするものに対する「知覚的な感受性」が含まれる[12]。 エウダイモニア(εὐδαιμονία)とは、ギリシャ語で「幸福」、「幸福」、「祝福」、そして徳倫理学の文脈では「人間の繁栄」と様々に訳される状態である[13]。この意味でのエウダイモニアは主観的な状態ではなく、客観的な状態である[要出典]。 西洋哲学の伝統におけるエウダイモニアの最も著名な提唱者であるアリストテレスによれば、エウダイモニアは人間の人生の目標を定義している。エウダイモニ アとは、人間の特徴的な資質である理性を、魂の最も適切で滋養に満ちた活動として発揮することである。アリストテレスは『ニコマコス倫理学』において、そ れ以前のプラトンと同様に、エウダイモニアの追求は「完全な徳に従った魂の活動」であると主張した[7]: さらに、エウダイモニアは、ポリスや都市国家 といった特徴的な人間共同体においてのみ適切に行使されうるものであった[14]。 エウダイモニアはアリストテレスによって最初に一般化されたが、現在では一般的に徳理論の伝統に属している[15]。徳理論家にとって、エウダイモニア は、適切な人間生活を送る人が達成する状態であり、徳を実践することによって到達できる結果である。美徳とは、持ち主がその目的を成功させるための習慣や 資質のことである。例えば、ナイフの美徳は切れ味であり、競走馬の美徳はスピードである。このように、人間にとっての美徳を特定するためには、人間の目的 とは何かについて説明する必要がある。 現代の徳倫理学の理論がすべてエウダイモニックであるわけではなく、エウダイモニアの代わりに別の目的を置くものもあれば、非テレオロジー的なものもある。 |
| Like much of the Western tradition, virtue theory originated in ancient Greek philosophy. Virtue ethics began with Socrates, and was subsequently developed further by Plato, Aristotle, and the Stoics.[17] Virtue ethics concentrates on the character of the individual, rather than the acts (or consequences thereof) of the individual. There is debate among adherents of virtue ethics concerning what specific virtues are praiseworthy. However, most theorists agree that ethics is demonstrated by the practice of virtues. Plato and Aristotle's treatments of virtues are not the same. Plato believes virtue is effectively an end to be sought, for which a friend might be a useful means. Aristotle states that the virtues function more as means to safeguard human relations, particularly authentic friendship, without which one's quest for happiness is frustrated. Discussion of what were known as the four cardinal virtues—wisdom, justice, fortitude, and temperance—can be found in Plato's Republic. The virtues also figure prominently in Aristotle's ethical theory found in Nicomachean Ethics.[7] Virtue theory was inserted into the study of history by moralistic historians such as Livy, Plutarch, and Tacitus. The Greek idea of the virtues was passed on in Roman philosophy through Cicero and later incorporated into Christian moral theology by Ambrose of Milan. During the scholastic period, the most comprehensive consideration of the virtues from a theological perspective was provided by Thomas Aquinas in his Summa Theologiae and his Commentaries on the Nicomachean Ethics.[18] After the Reformation, Aristotle's Nicomachean Ethics continued to be the main authority for the discipline of ethics at Protestant universities until the late seventeenth century, with over fifty Protestant commentaries published on the Nicomachean Ethics before 1682.[19] Though the tradition receded into the background of European philosophical thought in the past few centuries, the term "virtue" remained current during this period, and in fact appears prominently in the tradition of classical republicanism or classical liberalism. This tradition was prominent in the intellectual life of 16th-century Italy, as well as 17th- and 18th-century Britain and America; indeed the term "virtue" appears frequently in the work of Tomás Fernández de Medrano, Niccolò Machiavelli, David Hume, the republicans of the English Civil War period, the 18th-century English Whigs, and the prominent figures among the Scottish Enlightenment and the American Founding Fathers. |
西洋の伝統の多くと同様、徳の理論は古代ギリシャ哲学に端を発する。 徳倫理学はソクラテスに始まり、プラトン、アリストテレス、ストア学派によってさらに発展した[17]。徳倫理学は、個人の行為(またはその結果)よりも むしろ、個人の人格に焦点を当てる。具体的にどのような徳が賞賛に値するかについては、徳倫理学の信奉者の間で議論がある。しかし、ほとんどの理論家は、 倫理は徳の実践によって示されるという点で一致している。 プラトンとアリストテレスの徳の扱いは同じではない。プラトンは、徳は事実上求めるべき目的であり、そのためには友人が有用な手段であると考える。アリス トテレスは、徳はむしろ人間関係、特に真の友情を守るための手段として機能するものであり、それがなければ幸福の探求は挫折すると述べている。 プラトンの『共和国』には、知恵、正義、不屈の精神、節制という4つの枢要な徳について論じられている。また、徳は『ニコマコス倫理学』にあるアリストテレスの倫理理論においても重要な位置を占めている[7]。 徳目論は、リヴィ、プルターク、タキトゥスといった道徳主義的な歴史家によって歴史研究に挿入された。ギリシアの徳の思想はキケロを通じてローマ哲学に受 け継がれ、後にミラノのアンブローズによってキリスト教の道徳神学に取り入れられた。スコラ学時代、神学的観点から徳について最も包括的に考察したのは、 トマス・アクィナスによる『スンマ・テオロギアエ』と『ニコマコス倫理学注解』であった[18]。 宗教改革後、アリストテレスの『ニコマコス倫理学』は17世紀後半までプロテスタントの大学における倫理学の主要な権威であり続け、1682年までに50以上のプロテスタントによる『ニコマコス倫理学』の注釈書が出版された[19]。 この伝統は過去数世紀においてヨーロッパの哲学思想の背景へと退いていったが、「徳」という用語はこの時期にも流行しており、事実、古典的共和主義や古典 的自由主義の伝統の中に顕著に現れていた。この伝統は、16世紀のイタリア、17世紀と18世紀のイギリスとアメリカの知的生活において顕著であった。実 際、「徳」という用語は、トマス・フェルナンデス・デ・メドラーノ、ニッコロ・マキアヴェッリ、デイヴィッド・ヒューム、イギリス内戦期の共和主義者、 18世紀のイギリスのホイッグ、スコットランド啓蒙主義者やアメリカ建国の父たちの著名な人物の著作に頻繁に登場する。 |
| Contemporary "aretaic turn" Although some Enlightenment philosophers (e.g. Hume) continued to emphasise the virtues, with the ascendancy of utilitarianism and deontological ethics, virtue theory moved to the margins of Western philosophy. The contemporary revival of virtue theory is frequently traced to the philosopher Elizabeth Anscombe's 1958 essay "Modern Moral Philosophy".[20] Following this: In the 1976 paper "The Schizophrenia of Modern Ethical Theories", Michael Stocker summarises the main aretaic criticisms of deontological and consequentialist ethics.[21] Philosopher, psychologist, and encyclopedist Mortimer Adler appealed to Aristotelian ethics, and the virtue theory of happiness or eudaimonia throughout his published work. Philippa Foot, published a collection of essays in 1978 entitled Virtues and Vices.[22] Alasdair MacIntyre made an effort to reconstruct a virtue-based theory in dialogue with the problems of modern and postmodern thought; his works include After Virtue and Three Rival Versions of Moral Enquiry.[23] Paul Ricoeur accorded an important place to Aristotelian teleological ethics in his hermeneutical phenomenology of the subject, most notably in his book Oneself as Another.[24] Theologian Stanley Hauerwas found the language of virtue helpful in his own project. Richard Taylor argues for the restoration of classical virtues as the basis for morality in Virtue Ethics An Introduction (1991) [25] Roger Crisp and Michael Slote edited a collection of important essays titled Virtue Ethics.[26] Martha Nussbaum and Amartya Sen employed virtue theory in theorising the capability approach to international development. Julia Annas wrote The Morality of Happiness (1993).[27] Lawrence C. Becker identified current virtue theory with Greek Stoicism in A New Stoicism. (1998).[28] Rosalind Hursthouse published On Virtue Ethics (1999).[29] Psychologist Martin Seligman drew on classical virtue ethics in conceptualizing positive psychology. Psychologist Daniel Goleman opens his book on Emotional Intelligence with a challenge from Aristotle's Nicomachean Ethics.[30] Michael Sandel discusses Aristotelian ethics to support his ethical theory of justice in his book Justice: What's the Right Thing to Do? The aretaic turn in moral philosophy is paralleled by analogous developments in other philosophical disciplines. One of these is epistemology, where a distinctive virtue epistemology was developed by Linda Zagzebski and others. In political theory, there has been discussion of "virtue politics", and in legal theory, there is a small but growing body of literature on virtue jurisprudence. The aretaic turn also exists in American constitutional theory, where proponents argue for an emphasis on virtue and vice of constitutional adjudicators[clarification needed].[citation needed] Aretaic approaches to morality, epistemology, and jurisprudence have been the subject of intense debates. One criticism focuses on the problem of guidance; one opponent, Robert Louden in his article "Some Vices of Virtue Ethics", questions whether the idea of a virtuous moral actor, believer, or judge can provide the guidance necessary for action, belief formation, or the resolution of legal disputes.[31] |
現代の 「アレテー的転回」 一部の啓蒙哲学者(ヒュームなど)は美徳を強調し続けたが、功利主義や義務論的倫理学の台頭により、美徳論は西洋哲学の片隅に追いやられた。現代の徳理論の復活は、哲学者エリザベス・アンスコムの1958年のエッセイ『現代の道徳哲学』[20]に端を発することが多い: 1976年の論文「The Schizophrenia of Modern Ethical Theories」において、マイケル・ストッカーは義務論的倫理学と結果論的倫理学の主なアレテー的批判を要約している[21]。 哲学者であり、心理学者であり、百科事典学者でもあるモーティマー・アドラーは、アリストテレス倫理学や、幸福やエウダイモニアに関する徳の理論に訴えかけていた。 フィリッパ・フットは1978年に『美徳と悪徳』と題するエッセイ集を出版した[22]。 アラスデア・マッキンタイアは、モダンとポストモダンの思想の問題と対話しながら、徳に基づく理論を再構築する努力をした。彼の著作には『徳の後に』や『道徳探究の3つのライバル版』などがある[23]。 ポール・リクールは、彼の解釈学的現象学において、アリストテレス的テレオロギー倫理学を重要な位置づけとしており、特に著書『他者としての自分』において顕著である[24]。 神学者のスタンリー・ハウアーワスは、徳の言語が自身のプロジェクトに役立つと考えた。 リチャード・テイラーは『Virtue Ethics An Introduction』(1991年)の中で、道徳の基礎としての古典的美徳の復権を主張している[25]。 ロジャー・クリスプとマイケル・スロートは『美徳倫理学』と題する重要なエッセイ集を編集した[26]。 マーサ・ヌスバウムとアマルティア・センは、国際開発へのケイパビリティ・アプローチを理論化する際に徳の理論を用いた。 ジュリア・アナスは『幸福の道徳』(1993年)を著した[27]。 ローレンス・C・ベッカーは『A New Stoicism』(1998年)の中で、現在の徳理論をギリシャのストア派と同一視している。(1998).[28] ロザリンド・ハーストハウスは『徳の倫理学』(1999年)を出版した[29]。 心理学者のマーティン・セリグマンは、ポジティブ心理学を概念化する際に古典的な美徳倫理を用いた。 心理学者ダニエル・ゴールマンは『エモーショナル・インテリジェンス』の冒頭で、アリストテレスの『ニコマコス倫理学』からの挑戦を行っている[30]。 マイケル・サンデルは著書『正義』の中で、正義の倫理理論を支えるためにアリストテレス倫理学を論じている: What's the Right Thing to Do? 道徳哲学におけるアレテー的転回は、他の哲学分野においても同様の展開を見せている。そのひとつが認識論であり、リンダ・ザグゼブスキーらによって独特の 徳認識論が展開された。政治理論では「徳の政治」が議論され、法学では徳の法学に関する文献が小さいながらも増えている。アレテー的転回はアメリカの憲法 理論にも存在し、支持者は憲法裁定者の徳と悪を強調することを主張している[要明示][要出典]。 道徳、認識論、法学に対するアレテー的アプローチは、激しい議論の対象となってきた。批判のひとつはガイダンスの問題に焦点を当てたものであり、反対者の ひとりであるロバート・ルーデンはその論文「美徳倫理学のいくつかの悪徳」において、徳のある道徳的行為者、信者、裁判官という考え方が、行動や信念の形 成、法的紛争の解決に必要なガイダンスを提供することができるかどうかを問うている[31]。 |
| Lists of virtues There are several lists of virtues. Socrates argued that virtue is knowledge, which suggests that there is really only one virtue.[32] The Stoics identified four cardinal virtues: wisdom, justice, courage, and temperance. Wisdom is subdivided into good sense, good calculation, quick-wittedness, discretion, and resourcefulness. Justice is subdivided into piety, honesty, equity, and fair dealing. Courage is subdivided into endurance, confidence, high-mindedness, cheerfulness, and industriousness. Temperance or moderation is subdivided into good discipline, seemliness, modesty, and self-control.[33] John McDowell argues that virtue is a "perceptual capacity" to identify how one ought to act, and that all particular virtues are merely "specialized sensitivities" to a range of reasons for acting.[34] Aristotle's list Aristotle identifies approximately 18 virtues that demonstrate a person is performing their human function well.[7] He distinguished virtues pertaining to emotion and desire from those relating to the mind.[7]: II The first he calls moral virtues, and the second intellectual virtues (though both are "moral" in the modern sense of the word). Moral virtues Aristotle suggested that each moral virtue was a mean (see golden mean) between two corresponding vices, one of excess and one of deficiency. Each intellectual virtue is a mental skill or habit by which the mind arrives at truth, affirming what is or denying what is not.[7]: VI In the Nicomachean Ethics he discusses about 11 moral virtues:  Intellectual virtues Nous (intelligence), which apprehends fundamental truths (such as definitions, self-evident principles)[7]: VI.11 Episteme (science), which is skill with inferential reasoning (such as proofs, syllogisms, demonstrations)[7]: VI.6 Sophia (theoretical wisdom), which combines fundamental truths with valid, necessary inferences to reason well about unchanging truths.[7]: VI.5 Aristotle also mentions several other traits: Gnome (good sense) – passing judgment, "sympathetic understanding"[7]: VI.11 Synesis (understanding) – comprehending what others say, does not issue commands Phronesis (practical wisdom) – knowledge of what to do, knowledge of changing truths, issues commands[7]: VI.8 Techne (art, craftsmanship)[7]: VI.4 Aristotle's list is not the only list, however. As Alasdair MacIntyre observed in After Virtue, thinkers as diverse as Homer, the authors of the New Testament, Thomas Aquinas, and Benjamin Franklin have all proposed lists.[35] |
美徳のリスト 徳のリストはいくつかある。ソクラテスは、徳とは知識であると主張し、徳は本当は一つしかないことを示唆した[32]。ストア派は、知恵、正義、勇気、節 制の四つの枢要な徳を挙げた。知恵は、分別、計算、機転、思慮深さ、機知に細分化される。正義は、敬虔、誠実、公平、公正な取引に細分化される。勇気は、 持久力、自信、高邁さ、明るさ、勤勉さに細分化される。節制は、よい規律、見かけのよさ、慎み深さ、自制心に細分化される[33]。 ジョン・マクダウェルは、徳とは人がどのように行動すべきかを識別する「知覚能力」であり、すべての特定の徳は行動する理由の範囲に対する「特殊な感受性」に過ぎないと主張している[34]。 アリストテレスのリスト アリストテレスは、人が人間としての機能を十分に果たしていることを示す約18の美徳を挙げている[7]。彼は感情や欲望に関わる美徳と心に関わる美徳と を区別した[7]: II 前者を道徳的徳、後者を知性的徳と呼ぶ(ただし、どちらも現代的な意味での「道徳的」である)。 道徳的徳 アリストテレスは、それぞれの道徳的徳は、対応する2つの悪徳(1つは過剰、もう1つは不足)の間の平均(黄金平均を参照)であるとした。各知的徳は、心 が真理に到達し、あるものを肯定し、ないものを否定するための精神的な技術や習慣である[7]: VI 『ニコマコス倫理学』では11の徳について論じている:  知性の徳 ヌース(知性)は、基本的真理(定義や自明の原理など)を理解する[7]: VI.11 エピステーメー(科学):推論的推論(証明、対義語、実証など)に長けている[7]: VI.6 ソフィア(理論的な知恵):不変の真理についてよく推論するために、基本的な真理と有効で必要な推論とを結びつける[7]: VI.5 アリストテレスは他にもいくつかの特質に言及している: ノーム(良識)-判断を下すこと、「共感的理解」[7]: VI.11 シネシス(理解)- 他人の言うことを理解し、命令しない。 フロネシス(実践的な知恵)-何をすべきかについての知識、変化する真理についての知識、命令を発する[7]: VI.8 テクネ(芸術、職人技)[7]: VI.4 しかし、アリストテレスのリストだけが唯一のリストではない。アラスデア・マッキンタイアが『徳の後に』で述べているように、ホメロス、新約聖書の著者、トマス・アクィナス、ベンジャミン・フランクリンなど、さまざまな思想家がリストを提案している[35]。 |
| Criticisms Regarding which are the most important virtues, Aristotle proposed the following nine: wisdom; prudence; justice; fortitude; courage; liberality; magnificence; magnanimity; temperance.[citation needed] In contrast, philosopher Walter Kaufmann proposed as the four cardinal virtues ambition/humility, love, courage, and honesty.[36][non sequitur] Proponents of virtue theory[who?] sometimes argue that a central feature of a virtue is its universal applicability. In other words, any character trait defined as a virtue must reasonably be universally regarded as a virtue for all people. According to this view, it is inconsistent to claim, for example, servility as a female virtue, while at the same time not proposing it as a male one.[37] Other proponents of virtue theory, notably Alasdair MacIntyre, respond to this objection by arguing that any account of the virtues must indeed be generated out of the community in which those virtues are to be practiced: the very word ethics implies ethos. That is to say that the virtues are, and necessarily must be, grounded in a particular time and place. What counts as a virtue in 4th-century BCE Athens would be a ludicrous guide to proper behaviour in 21st-century CE Toronto and vice versa. To take this view does not necessarily commit one to the argument that accounts of the virtues must therefore be static: moral activity—that is, attempts to contemplate and practice the virtues—can provide the cultural resources that allow people to change, albeit slowly, the ethos of their own societies. MacIntyre appears to take this position in his seminal work on virtue ethics, After Virtue. Another objection[whose?] to virtue theory is that virtue ethics does not focus on what sorts of actions are morally permitted and which ones are not, but rather on what sort of qualities someone ought to foster in order to become a good person. In other words, while some virtue theorists[who?] may not condemn, for example, murder as an inherently immoral or impermissible sort of action, they may argue that someone who commits a murder is severely lacking in several important virtues, such as compassion and fairness. Still, antagonists of the theory[who?] often object that this particular feature of the theory makes virtue ethics useless as a universal norm of acceptable conduct suitable as a base for legislation[citation needed]. Some virtue theorists[who?] concede this point, but respond by opposing the very notion of legitimate legislative authority instead, effectively advocating some form of anarchism as the political ideal.[citation needed] Other virtue theorists[who?] argue that laws should be made by virtuous legislators, and still another group argue that it is possible to base a judicial system on the moral notion of virtues rather than rules. Aristotle himself saw his Nicomachean Ethics as a prequel for his Politics and felt that the point of politics was to create the fertile soil for a virtuous citizenry to develop in, and that one purpose of virtue was that it helps you to contribute to a healthy polis.[7]: X.9 [14] Some virtue theorists[who?] might respond to this overall objection with the notion of a "bad act" also being an act characteristic of vice.[citation needed] That is to say that those acts that do not aim at virtue, or that stray from virtue, would constitute our conception of "bad behavior". Although not all virtue ethicists agree to this notion, this is one way the virtue ethicist can re-introduce the concept of the "morally impermissible". One could raise an objection that he is committing an argument from ignorance by postulating that what is not virtuous is unvirtuous. In other words, just because an action or person 'lacks of evidence' for virtue does not, all else constant, imply that said action or person is unvirtuous. |
批判 最も重要な徳はどれかについて、アリストテレスは次の9つを提唱した:知恵、賢明さ、正義、不屈の精神、勇気、寛大さ、大らかさ、節制[要出典]。対照的 に、哲学者のウォルター・カウフマンは4つの枢要徳として野心・謙虚さ、愛、勇気、誠実さを提唱した[36][要出典]。 美徳理論の支持者[誰?]は、美徳の中心的な特徴は普遍的な適用可能性であると主張することがある。言い換えれば、美徳として定義された性格特性は、すべ ての人々にとって普遍的に美徳であると合理的に見なされなければならない。この見解によれば、例えば、隷属性を女性の美徳として主張し、同時にそれを男性 の美徳として提案しないことは矛盾している[37]。 徳理論の他の支持者、特にアラスデア・マッキンタイアは、徳に関するいかなる説明も、その徳が実践される共同体から生み出されなければならないと主張する ことによって、この反論に応えている。つまり、徳は特定の時代と場所に根ざしたものであり、必然的にそうでなければならないのだ。紀元前4世紀のアテネで 美徳とされるものが、21世紀のトロントで適切な振る舞いをするためのおかしな指針となるであろうし、その逆もまた然りである。道徳的な活動、つまり徳に ついて考え、実践しようとする試みは、文化的な資源を提供し、人々が自分たちの社会の倫理観を少しずつではあるが変えていくことを可能にする。 マッキンタイアは、徳倫理学の代表作である『徳の後に』でこの立場をとっているようだ。 徳理論に対するもう一つの反論[誰の?]は、徳倫理学は、どのような行為が道徳的に許され、どのような行為が許されないかに焦点を当てるのではなく、善人 になるためにどのような資質を養うべきかに焦点を当てるというものである。言い換えれば、徳の理論家[誰?]の中には、例えば殺人を本質的に不道徳な行 為、あるいは許されない行為として非難はしないかもしれないが、殺人を犯すような人は、思いやりや公平さといったいくつかの重要な徳が著しく欠けていると 主張するかもしれない。それでも、この理論の敵対者[誰?]は、この理論のこの特別な特徴によって、美徳倫理学は、法制化の基盤として適した、許容される 行為の普遍的規範として役に立たなくなるとしばしば異議を唱える[要出典]。徳の理論家[誰?]の中にはこの点を認めながらも、代わりに正当な立法権とい う概念そのものに反対することで反論し、政治的理想としてある種の無政府主義を事実上提唱する者もいる[要出典]。他の徳の理論家[誰?]は、法律は徳の ある立法者によって作られるべきであると主張し、さらに別のグループは、規則ではなく徳という道徳的概念に司法制度を基礎づけることは可能であると主張す る。アリストテレス自身は、『ニコマコス倫理学』を『政治学』の前日譚とみなし、政治の要諦は、徳のある市民が発展するための肥沃な土壌を作ることであ り、徳の目的のひとつは、健全なポリスに貢献することにあると考えた[7]: X.9 [14] 徳の理論家[誰?]の中には、この全体的な反論に対して、「悪い行為」もまた悪徳に特徴的な行為であるという概念で反論する者もいるかもしれない[要出 典]。つまり、徳を目指さない行為、あるいは徳から逸脱した行為は、我々の考える「悪い行為」を構成することになる。すべての徳倫理学者がこの考え方に同 意しているわけではないが、これは徳倫理学者が「道徳的に許されない」という概念を再び導入する一つの方法である。徳のないことは徳のないことであると仮 定することで、無知からの議論を犯しているのではないかという反論を提起することもできる。言い換えれば、ある行為や人物が美徳の「証拠を欠いている」か らといって、他のすべてが一定であっても、その行為や人物が美徳でないということにはならない。 |
| Subsumed in deontology and utilitarianism Martha Nussbaum suggested that while virtue ethics is often considered to be anti-Enlightenment, "suspicious of theory and respectful of the wisdom embodied in local practices",[38] it is actually neither fundamentally distinct from, nor does it qualify as a rival approach to deontology and utilitarianism. She argues that philosophers from these two Enlightenment traditions often include theories of virtue. She pointed out that Kant's "Doctrine of Virtue" (in The Metaphysics of Morals) "covers most of the same topics as do classical Greek theories", "that he offers a general account of virtue, in terms of the strength of the will in overcoming wayward and selfish inclinations; that he offers detailed analyses of standard virtues such as courage and self-control, and of vices, such as avarice, mendacity, servility, and pride; that, although in general, he portrays inclination as inimical to virtue, he also recognizes that sympathetic inclinations offer crucial support to virtue, and urges their deliberate cultivation."[38] Nussbaum also points to considerations of virtue by utilitarians such as Henry Sidgwick (The Methods of Ethics), Jeremy Bentham (The Principles of Morals and Legislation), and John Stuart Mill, who writes of moral development as part of an argument for the moral equality of women (The Subjection of Women). She argues that contemporary virtue ethicists such as Alasdair MacIntyre, Bernard Williams, Philippa Foot, and John McDowell have few points of agreement and that the common core of their work does not represent a break from Kant. |
義務論と功利主義に包摂される マーサ・ヌスバウムは、徳の倫理学はしばしば反啓蒙主義であり、「理論を疑い、ローカルな実践に具現化された知恵を尊重する」と考えられているが[38]、 実際には義務論や功利主義とは根本的に異なるものでもなければ、対立するアプローチでもないと示唆している。彼女は、これら2つの啓蒙主義の伝統の哲学者 たちはしばしば徳の理論を含んでいると論じている。彼女は、カントの「徳の教義」(『道徳の形而上学』所収)が「古典的なギリシアの理論とほとんど同じ テーマを扱っている」こと、「カントは徳の一般的な説明を、行き過ぎた利己的な傾向を克服する意志の強さという観点から提供している」ことを指摘した; 勇気や自制心といった標準的な徳と、貪欲、托鉢、隷属、高慢といった悪徳の詳細な分析を提供している。一般的に、彼は傾倒を徳に不都合なものとして描いて いるが、共感的な傾倒が徳にとって重要な支えとなることも認めており、その意図的な育成を促している。 「[38] ヌスバウムはまた、ヘンリー・シジウィック(『倫理の方法』)、ジェレミー・ベンサム(『道徳と立法の原理』)、ジョン・スチュアート・ミル(『女性の被 支配』)といった功利主義者による徳についての考察も指摘している。彼女は、アラスデア・マッキンタイア、バーナード・ウィリアムズ、フィリッパ・フッ ト、ジョン・マクダウェルといった現代の徳倫理学者には一致する点がほとんどなく、彼らの研究の共通の核心はカントからの脱却を意味するものではないと論 じている。 |
| Kantian critique Immanuel Kant's position on virtue ethics is contested. Those who argue that Kantian deontology conflicts with virtue ethics include Alasdair MacIntyre, Philippa Foot, and Bernard Williams.[39] In the Groundwork of the Metaphysics of Morals and the Critique of Practical Reason, Immanuel Kant offers many different criticisms of ethical frameworks and against moral theories before him.[citation needed] Kant rarely mentioned Aristotle by name but did not exclude his moral philosophy of virtue ethics from his critique. Many Kantian arguments against virtue ethics claim that virtue ethics is inconsistent, or sometimes that it is not a real moral theory at all.[40] In "What Is Virtue Ethics All About?",[41] Gregory Velazco y Trianosky identified the key points of divergence between virtue ethicists and what he called "neo-Kantianism", in the form these nine neo-Kantian moral assertions: The crucial moral question is "what is it right/obligatory to do?" Moral judgments are those that concern the rightness of actions. Such judgments take the form of rules or principles. Such rules or principles are universal, not respecting persons. They are not based on some concept of human good that is independent of moral goodness. They take the form of categorical imperatives that can be justified independently of the desires of the person they apply to. They are motivating; they can compel action in an agent, also independently of that agent's desires. An action, in order to be morally virtuous, must be motivated by this sort of moral judgment (not, for example, merely coincidentally aligned with it). The virtuousness of a character trait, or virtue, derives from the relationship that trait has to moral judgments, rules, and principles. Trianosky says that modern sympathizers with virtue ethics almost all reject neo-Kantian claim #1, and many of them also reject certain of the other claims. |
カント批判 徳倫理に関するイマヌエル・カントの立場には異論がある。カントの義務論が徳倫理学と矛盾すると主張する人々には、アラスデア・マッキンタイア、フィリッ パ・フット、バーナード・ウィリアムズなどがいる[39]。イマヌエル・カントは『道徳形而上学の基礎づけ』と『実践理性批判』において、倫理的枠組みや それ以前の道徳理論に対する様々な批判を展開している[要出典]。徳倫理学に対するカント派の主張の多くは、徳倫理学は矛盾していると主張し、時には、徳 倫理学は真の道徳理論では全くないと主張している[40]。 グレゴリー・ヴェラスコ・イ・トリアノスキーは『徳倫理学とは何か』[41]において、徳倫理学者と彼が「ネオ・カント主義」と呼ぶものとの乖離の主要点を、これら9つのネオ・カント主義的道徳的主張という形で特定している: 重要な道徳的問題は、「何をすることが正しいのか/義務なのか 」である。 道徳的判断とは、行為の正しさに関するものである。 そのような判断は規則や原則の形をとる。 そのような規則や原則は普遍的なものであり、個人を尊重するものではない。 また、道徳的善とは無関係な人間の善の概念に基づくものでもない。 それらは定言命法の形をとり、それが適用される人の欲望とは無関係に正当化されうる。 それは動機づけであり、行為者の欲望とは無関係に、行為者に行動を強制することができる。 ある行為が道徳的に高潔であるためには、この種の道徳的判断によって動機づけられなければならない(例えば、単に偶然に道徳的判断に合致しているのではない)。 ある性格的特質(徳)の徳性は、その特質が道徳的判断、規則、原則とどのような関係にあるかに由来する。 トリアノスキーによれば、現代の徳倫理学のシンパは、ほとんど全員が新カント派の主張1を否定しており、その多くは他の主張も否定しているという。 |
| Utopianism and pluralism Robert B. Louden criticizes virtue ethics on the basis that it promotes a form of unsustainable utopianism. Trying to arrive at a single set of virtues is immensely difficult in contemporary societies as, according to Louden, they contain "more ethnic, religious, and class groups than did the moral community which Aristotle theorized about" with each of these groups having "not only its own interests but its own set of virtues as well". Louden notes in passing that MacIntyre, a supporter of virtue-based ethics, has grappled with this in After Virtue but that ethics cannot dispense with building rules around acts and rely only on discussing the moral character of persons.[42] |
ユートピア主義と多元主義 ロバート・B・ルーデンは、徳倫理が持続不可能なユートピア主義を助長しているとして、徳倫理を批判している。ルーデンによれば、現代社会には「アリスト テレスが理論化した道徳的共同体よりも多くの民族的、宗教的、階級的集団」が存在し、これらの集団はそれぞれ「独自の利益だけでなく、独自の徳の集合も 持っている」ため、単一の徳の集合に到達しようとすることは非常に困難であるという。ルーデンは、徳に基づく倫理学の支持者であるマッキンタイアが『徳の 後に』の中でこのことに取り組んでいるが、倫理学は行為の周りにルールを構築することを省くことはできず、人物の道徳的性格を論じることだけに頼ることは できないと述べている[42]。 |
| Topics in virtue ethics Virtue ethics as a category Virtue contrasts with deontological and consequentialist ethics (the three being together the most predominant contemporary normative ethical theories). Deontological ethics, sometimes referred to as duty ethics, places the emphasis on adhering to ethical principles or duties. How these duties are defined, however, is often a point of contention and debate in deontological ethics. One predominant rule scheme used by deontologists is divine command theory. Deontology also depends upon meta-ethical realism, in that it postulates the existence of moral absolutes that make an action moral, regardless of circumstances. Immanuel Kant is considered one of the foremost theorists of deontological ethics. The next predominant school of thought in normative ethics is consequentialism. While deontology places the emphasis on doing one's duty, consequentialism bases the morality of an action upon its outcome. Instead of saying that one has a moral duty to abstain from murder, a consequentialist would say that we should abstain from murder because it causes undesirable effects. The main contention here is what outcomes should/can be identified as objectively desirable. The greatest happiness principle of John Stuart Mill is a commonly adopted criteria for what is objectively desirable. Mill asserts that the desirability of an action is the net amount of happiness it brings, the number of people it brings it to, and the duration of the happiness. He tries to delineate classes of happiness, some preferable to others, but there is a great deal of difficulty in classifying such concepts. Further information: Utilitarianism, Utilitarianism (book), and On Liberty This section may require copy editing. (July 2023) (Learn how and when to remove this message) A virtue ethicist identifies virtues, desirable characteristics, that an excellent person embodies. Exhibiting these virtues is the aim of ethics, and one's actions are a reflection of one's virtues. To the virtue philosopher, action cannot be used as a demarcation of morality, because a virtue encompasses more than just a simple selection of action. Instead, a virtue is a way of being that leads the person exhibiting the virtue to make certain "virtuous" types of choices consistently in each situation. There is a great deal of disagreement within virtue ethics over what are virtues and what are not. There are also difficulties in identifying what is the "virtuous" action to take in all circumstances, and how to define a virtue. Consequentialist and deontological theories often still employ the term virtue, but in a restricted sense, namely as a tendency or disposition to adhere to the system's principles or rules. In other words, in those theories, virtue is secondary, and the principles or rules are primary. These very different senses of what constitutes virtue, hidden behind the same word, are a potential source of confusion.[43] This disagreement over the meaning of virtue points to a larger conflict between virtue theory and its philosophical rivals. A system of virtue theory is only intelligible if it is teleological: that is, if it includes an account of the purpose (telos) of human life, or in popular language, the meaning of life.[citation needed] Obviously, strong claims about the purpose of human life, or of what the good life for human beings is, will be controversial. Virtue theory's necessary commitment to a teleological account of human life thus puts the tradition in tension with other dominant approaches to normative ethics, which, because they focus on actions, do not bear this burden.[citation needed] |
徳倫理学のトピックス カテゴリーとしての徳倫理学 徳は、義務論的倫理学(deontological ethics)および結果論的倫理学(consequentialist ethics)と対照的である。 義務論的倫理学は、倫理原則や義務を遵守することに重きを置く。しかし、これらの義務がどのように定義されるかは、しばしば非論理的倫理学の争点となり、 議論となる。脱自律主義者が用いる支配的なルールスキームのひとつに、神の命令理論がある。義務論はまた、状況に関係なく行為を道徳的にする道徳的絶対性 の存在を仮定するという点で、メタ倫理的実在論に依存している。イマヌエル・カントは、義務論的倫理学の最も優れた理論家の一人と考えられている。 規範倫理の次の主流派は帰結主義である。義務論が自分の義務を果たすことに重きを置くのに対し、帰結主義は行為の道徳性をその結果に基づいて判断する。殺 人を控える道徳的義務があると言う代わりに、結果主義者は、殺人は望ましくない結果を引き起こすので、殺人を控えるべきだと言うだろう。ここでの主な論点 は、どのような結果を客観的に望ましいものとして特定すべきか/特定できるかである。 ジョン・スチュアート・ミルの最大幸福原則は、何が客観的に望ましいかの基準として一般的に採用されている。ミルは、ある行為の望ましさとは、それがもた らす正味の幸福の量、それをもたらす人々の数、幸福の持続時間であると主張している。彼は幸福のクラスを定義しようとし、あるものは他のものより好ましい が、そのような概念を分類することは非常に困難である。 詳細はこちら: 功利主義、功利主義(著書)、自由について このセクションはコピー編集が必要な場合がある。(2023年7月) (このメッセージを削除する方法とタイミングを学ぶ) 美徳倫理主義者は、優れた人が体現する美徳、望ましい特性を特定する。これらの美徳を発揮することが倫理の目的であり、人の行動はその人の美徳を反映する ものである。徳の哲学者にとっては、徳は単純な行動の選択以上のものを包含しているため、行動を道徳の境界線として用いることはできない。なぜなら、徳は 単なる行動の選択以上のものを包含しているからである。その代わり、徳とは、その徳を発揮する人がそれぞれの状況において一貫して特定の「徳のある」種類 の選択をするように導くあり方なのである。徳倫理学では、何が徳で何が徳でないかをめぐって多くの意見の相違がある。また、あらゆる状況において取るべき 「徳のある」行動とは何かを特定することや、徳をどのように定義するかについても困難がある。 結果論的理論や義務論的理論では、美徳という言葉をしばしば用いるが、それは限定された意味、つまり、システムの原則や規則を遵守する傾向や気質という意 味である。言い換えれば、これらの理論では、徳は二次的なものであり、原理やルールが一次的なものである。美徳を構成するものについてのこのような全く異 なる感覚は、同じ言葉の背後に隠されており、潜在的な混乱の原因となっている[43]。 徳の意味をめぐるこの不一致は、徳理論とその哲学的ライバルとの間のより大きな対立を指し示している。徳理論の体系が理解できるのは、それが目的論的であ る場合、つまり人間生活の目的(テロス)、一般的な言葉で言えば人生の意味についての説明を含んでいる場合だけである。そのため、人間生活の目的論的説明 に対する徳理論の必要なコミットメントは、行為に焦点を当てているため、この重荷を負わない規範倫理学への他の支配的なアプローチと緊張関係にこの伝統を 置く[要出典]。 |
| Virtue and politics Virtue theory emphasises Aristotle's belief in the polis as the acme of political organisation,[citation needed] and the role of the virtues in enabling human beings to flourish in that environment. Classical republicanism in contrast emphasises Tacitus' concern that power and luxury can corrupt individuals and destroy liberty, as Tacitus perceived in the transformation of the Roman Republic into the Roman Empire; virtue for classical republicans is a shield against this sort of corruption and a means to preserve the good life one has, rather than a means by which to achieve the good life one does not yet have. Another way to put the distinction between the two traditions is that virtue ethics relies on Aristotle's fundamental distinction between the human-being-as-he-is from the human-being-as-he-should-be, while classical republicanism relies on the Tacitean distinction of the risk-of-becoming.[44] Virtue ethics has a number of contemporary applications. Social and political philosophy Within the field of social ethics, Deirdre McCloskey argues that virtue ethics can provide a basis for a balanced approach to understanding capitalism and capitalist societies.[45] Education Within the field of philosophy of education, James Page argues that virtue ethics can provide a rationale and foundation for peace education.[46] Health care and medical ethics Thomas Alured Faunce argued that whistleblowing in the healthcare setting would be more respected within clinical governance pathways if it had a firmer academic foundation in virtue ethics.[47] He called for whistleblowing to be expressly supported in the UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights.[48] Barry Schwartz argues that "practical wisdom" is an antidote to much of the inefficient and inhumane bureaucracy of modern health care systems.[49] Technology and the virtues In her book Technology and the Virtues,[50] Shannon Vallor proposed a series of 'technomoral' virtues that people need to cultivate in order to flourish in our socio-technological world: Honesty (Respecting Truth), Self-control (Becoming the Author of Our Desires), Humility (Knowing What We Do Not Know), Justice (Upholding Rightness), Courage (Intelligent Fear and Hope), Empathy (Compassionate Concern for Others), Care (Loving Service to Others), Civility (Making Common Cause), Flexibility (Skillful Adaptation to Change), Perspective (Holding on to the Moral Whole), and Magnanimity (Moral Leadership and Nobility of Spirit). |
徳と政治 美徳論は、政治組織の頂点としてのポリスに対するアリストテレスの信念[要出典]と、その環境の中で人間が繁栄するための美徳の役割を強調する。これとは 対照的に、古典的共和主義では、タキトゥスがローマ共和国からローマ帝国への変貌の中で感じたように、権力と贅沢が個人を堕落させ、自由を破壊することへ の懸念が強調される。古典的共和主義者にとっての徳とは、この種の堕落に対する盾であり、まだ手にしていない良い生活を実現するための手段ではなく、手に している良い生活を維持するための手段である。2つの伝統の違いを別の言い方をすれば、徳倫理学はアリストテレスの「あるべき人間」と「あるべき人間」の 基本的な区別に依拠しており、古典的共和主義はタキテウスの「なるリスク」の区別に依拠しているということである[44]。 美徳倫理学は現代においても多くの応用がなされている。 社会哲学と政治哲学 社会倫理の分野において、ディアドレ・マクロスキーは、徳倫理が資本主義と資本主義社会を理解するためのバランスの取れたアプローチの基礎を提供することができると主張している[45]。 教育 教育哲学の分野において、ジェームズ・ペイジは、徳倫理が平和教育の根拠と基礎を提供することができると主張している[46]。 ヘルスケアと医療倫理 Thomas Alured Faunceは、医療現場における内部告発は、徳倫理におけるより強固な学問的基盤があれば、臨床ガバナンスの経路の中でより尊重されるようになると主張 している[47]。彼は、ユネスコの「生命倫理と人権に関する世界宣言」において内部告発が明示的に支持されるよう求めている[48]。 Barry Schwartzは、「実践的な知恵」は、現代の医療制度における非効率的で非人道的な官僚主義の多くに対する解毒剤であると主張している[49]。 テクノロジーと美徳 シャノン・バローは、著書『テクノロジーと美徳』[50]の中で、社会技術化された世界で繁栄するために人々が培うべき一連の「テクノモラル」的美徳を提 唱している: 誠実さ(真実を尊重する)、自制心(欲望の所有者になる)、謙虚さ(知らないことを知る)、正義感(正しさを支持する)、勇気(知性的な恐怖と希望)、共 感(他者への思いやり)、気遣い(他者への愛ある奉仕)、礼節(共通の原因を作る)、柔軟性(変化への巧みな適応)、展望(道徳的な全体性を保持する)、 寛大さ(道徳的なリーダーシップと精神の高貴さ)である。 |
| Applied ethics – Practical application of moral considerations Arete – Greek philosophical concept Buddhist ethics (discipline) Confucianism – Chinese ethical and philosophical system Cynicism (philosophy) – Ancient school of philosophy Environmental virtue ethics – Way of approaching environmental ethics through the lens of virtue ethics Modern Stoicism – Virtue-focused philosophical system Phronesis – Ancient Greek word for a type of wisdom or intelligence Rule according to higher law – Belief that universal principles of morality override unjust laws Seven virtues – Seven virtues in Christian tradition Stoicism – Virtue-focused philosophical system Tirukkuṟaḷ – Ancient Tamil composition on personal ethics and morality Virtue epistemology – Philosophical approach Virtue jurisprudence – Virtue ethics applied to jurisprudence Virtue signalling – Pejorative term |
応用倫理学 - 道徳的配慮の実践的応用 アレテー - ギリシャ哲学の概念 仏教倫理学 儒教 - 中国の倫理哲学体系 シニシズム(哲学) - 古代の哲学の学派 環境徳倫理学 - 徳倫理学のレンズを通して環境倫理にアプローチする方法 現代ストア派 - 徳に焦点を当てた哲学体系 フロネシス - 古代ギリシャ語で、知恵や知性の一種を意味する。 高次の法則に基づく支配 - 普遍的な道徳原理が不公正な法律に優先すると信じる。 7つの徳 - キリスト教の伝統における7つの徳 ストイシズム - 徳に焦点を当てた哲学体系 Tirukku_1E37 - 個人倫理と道徳に関する古代タミル語の作文。 美徳認識論 - 哲学的アプローチ 徳の法学 - 法学に適用される徳の倫理学 美徳のシグナリング - 蔑称 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Virtue_ethics |
☆Virtue Ethics(スタンフォード哲学百科事典)
| 徳の倫理学は現在、規範倫理学における三つの
主要なアプローチの一つである。 これは当初、義務や規則を重視するアプローチ(義務論)や、
行動の帰結を重視するアプローチ(帰結主義)とは対照的に、 美徳、すなわち道徳的性格を強調するものとして特定されるかもしれない。
困っている人を助けるべきであることは明らかだと仮定しよう。功利主義者は、そうすることで幸福が格律されるという結果を指摘するだろう。義務論者は、
「己が為されたいように他者にせよ」といった道徳的規則に従って行動することになるという事実を指摘するだろう。そして徳倫理学者は、その人格を助けるこ
とが慈善的あるいは慈悲深い行為であるという事実を指摘するだろう。 これは、徳倫理学者だけが徳に注意を払うと言っているわけではなく、 帰結主義者だけが結果に注意を払うと言っているわけでも、 義務論者だけが規則に注意を払うと言っているわけでもない。 上記の各アプローチは、徳、結果、そして規則のすべてに余地を設けることができる。実際、妥当な規範的倫理理論はこれら三つすべてについて何かを述べるだ ろう。徳倫理学が帰結主義や義務論と異なる点は、理論における徳の中心的地位にある(Watson 1990; Kawall 2009)。帰結主義者は美徳を「良い結果をもたらす特性」と定義し、義務論者は「確実に義務を果たす者が持つ特性」と定義する一方で、美徳倫理学者は美 徳を「より根本的とされる他の概念」によって定義しようとする試みに抵抗する。むしろ美徳と悪徳こそが美徳倫理学理論の基盤となり、他の規範的概念はそれ らに根ざすのである。 まず、あらゆる形態の徳倫理学の中心となる二つの概念、すなわち徳と実践的知恵について論じる。次に、異なる徳倫理学理論を互いに区別する特徴のいくつか を指摘した後、徳倫理学に対して提起されてきた異議と、それに対する反論に目を向ける。最後に、将来の研究が発展しうる方向性について考察する。 |
|
| 1. 予備事項 1.1 美徳 1.2 実践的知恵 2. 徳倫理学の形態 2.1 幸福主義的徳倫理学 2.2 エージェントベースと実例主義的徳倫理学 2.3 対象中心の徳倫理学 2.4 プラトン的徳倫理学 3. 徳倫理学への異議 4. 今後の方向性 参考文献 学術ツール その他のインターネットリソース 関連項目 |
|
| 1. 予備事項 西洋における徳倫理学の創始者はプラトンとアリストテレスであり、 東洋では孟子と孔子に遡ることができる。 この思想は少なくとも啓蒙時代まで西洋道徳哲学の主流として存続し、 19世紀に一時的に苦悩したものの、 1950年代後半に英米哲学において再興した。この復活は、当時主流だった義務論や功利主義への不満を結晶化した アンスカムの著名な論文「現代道徳哲学」(Anscombe 1958)によって 告げられた。当時、どちらの学派も、美徳倫理学の伝統において常に重要な位置を占めてきた数々の主題——美徳と悪徳、動機と道徳的性格、道徳教育、道徳的 知恵や識別力、友情と家族関係、幸福の深い概念、道徳的生活における感情の役割、そして私たちがどのような人格であるべきか、どう生きるべきかという根本 的に重要な問い——に注意を払っていなかった。 その再興は他の二つのアプローチに活力を与え、 それらの支持者の多くが自らの好む理論の枠組みで これらの主題に取り組むようになった。(この結果、 「徳倫理学」(第三のアプローチ)と「徳理論」を区別する必要が生じた。 後者は他のアプローチにおける徳の解釈も含む用語である。) カントの徳理論への関心は、 哲学者たちの注意を、長い間軽視されてきたカントの 徳の教義へと再び向けさせ、功利主義者たちは帰結主義的な徳理論を発展させた(Driver 2001; Hurka 2001)。また、プラトンやアリストテレス以外の哲学者たち、例えばマーティノー、ヒューム、ニーチェなどに対する徳倫理学的解釈も生み出し、 マーティノー、ヒューム、ニーチェなど、プラトンやアリストテレス以外の哲学者に対する徳倫理学的解釈を生み出し、 それによって異なる形の徳倫理学が発展してきた(Slote 2001; Swanton 2003, 2011a)。 現代の徳倫理学は必ずしも「新アリストテレス主義」や幸福主義の形を取る必要はない(第2節参照)が、 ほぼ全ての現代版は、古代ギリシャ哲学に由来する三つの概念を採用することで、 その根源が古代ギリシャ哲学にあることを依然として示している。 これらはアレテー(卓越性または徳)、 フロネシス(実践的または道徳的知恵)、そしてエウダイモニア (通常は幸福または繁栄と訳される)である。(これら三つすべてに関する簡潔で明快かつ権威ある説明についてはAnnas 2011を参照のこと。) 本節の残りの部分では最初の二つについて論じる。ユーダイモニアについては、次の節で徳倫理学のユーダイモニスト的解釈と関連付けて論じる。 |
|
| 1.1 美徳 美徳とは人格の優れた特性である。それは持ち主の中に深く根付いた性質——つまり、例えばお茶を飲む習慣とは異なり、根底から備わるもの——であり、特定 の特性的な方法で気づき、期待し、価値を見出し、感じ、望み、選択し、行動し、反応する傾向を指す。美徳を持つとは、特定の複雑な心構えを持つ特定の種類 の人格であることである。この思考様式における重要な側面は、 行動の理由として特定の考慮事項群を 心から受け入れることである。例えば、 正直な人格とは単に「誠実な取引を実践し 騙さない者」と定義できるわけではない。もしそうした行動が、単に「正直が最善策だ」と考えるから、あるいは「見つかるのが怖い」から行われるのであっ て、「そうでなければ不正直になる」という理由を認識して行われるのではないなら、それは正直な人格の行動ではない。例えば、真実が真実だからという理由 で真実を語る人格だけを正直な人格と見なすことはできない。なぜなら、不器用でも無分別でもなく正直であるという美徳はあり得るからだ。正直な人格は「そ れは嘘になる」という事実を、行動しないための強い(ただし絶対的なものではない)理由として認識する。 という理由で真実を語る者とは限らない。誠実であることは、 無神経さや軽率さを伴わずに実現し得る美徳だからだ。誠実な人格は、 「それは嘘になる」という理由を、特定の状況下で特定の言明を避けるための 強い(ただし絶対的なものではない)根拠として認識し、 「それは真実になる」という理由を、それらを述べる根拠として適切に(ただし絶対的なものではない)重みづけする。 正直な人格の行動や選択は、正直さと不正直さに対する彼女の見解を反映している。 もちろん、そうした見解は他の行動や感情的反応にも表れる。 彼女は正直さを重んじるからこそ、可能な限り正直な人と働き、正直な友人を持ち、子供を正直に育てることを選ぶ。 彼女は不誠実さを非難し、嫌悪し、嘆く。 ある種の詐欺話には面白がらず、欺瞞によって成功した者を 賢いとは考えず、軽蔑するか哀れむ。 誠実さが勝利した時には(状況に応じて) 驚きも喜びもしない。 身近な愛する者が不誠実な行為に及んだ時には 衝撃を受け、苦悩する。美徳とはこのように多面的な性質である以上、 観察された単一の行動、あるいは類似した一連の行動のみに基づいて ある主体に美徳を帰属させるのは明らかに軽率である。 特に、その主体がそうした行動をとった理由を知らない場合にはなおさらだ(Sreenivasan 2002)。 徳を備えることは程度の問題である。そのような性質を完全に備えることは、完全あるいは完璧な徳を備えることであり、それは稀である。そしてこの理想に及 ばない状態にはいくつかの形態がある(Athanassoulis 2000)。真に「かなり徳のある」と評され得る人々、 そして確かに「不誠実で自己中心的で貪欲」と評される人々より 明らかに優れた人々でさえ、盲点を持っている—— 期待される理由に基づいて行動しない小さな領域である。したがって、ほとんどの状況で誠実あるいは親切であり、 特に困難な状況では顕著にそうである人物でさえ、 些細な偏見に染まっている可能性があり、 先祖について不誠実になりがちで、 聞き慣れない訛りの見知らぬ者には親切に接しないかもしれない。 さらに、行動の特定の理由に対する理性的な認識と感情を調和させることは容易ではない。私は、誤りを認めないことが不誠実である以上、その過ちを認めるべ きだと正直に認識しているかもしれない。しかし、その認識が心から受け入れられていなければ、内面の葛藤なく容易に認めることはできない。 アリストテレスに従い(そして適応して)、徳倫理学者は完全な徳と「節制」、すなわち意志の強さとの区別を設ける。完全に徳ある者は相反する欲望との葛藤 なくすべきことを行い、節制ある者はそれとは異なる行動への欲望や誘惑を制御しなければならない。 大陸を「完全な徳に及ばない」と描写することは、特に困難な状況下で善行を成し遂げる人々には何か特に称賛すべき点があるという直観に反するように思え る。しかしこの妥当性は、「困難を生む要因」が何かによって決まる(Foot 1978: 11–14)。もし困難の原因が行為者の置かれた状況にあるなら——例えば、誰かが満杯の財布を落としたのを見た時、彼女が極貧状態にあるとか、助けを求 めて誰かが訪ねてきた時、彼女が深い悲嘆に暮れているとか——ならば、確かに、そうした困難な状況下で財布を返したり助けを与えたりする彼女の行動は特に 称賛に値する。しかし、困難の原因が彼女の性格上の欠陥—— 他人の物を横取りしたい誘惑や、他人の苦悩への冷淡な無関心——にあるなら、 それは称賛に値しない。 |
|
| 1.2 実践的知恵(フロネーシス) 完全な徳に容易に及ばないもう一つの方法は、 フロネシス―道徳的あるいは実践的な 知恵―を欠くことである。 美徳の概念とは、その所有者を善たらしめるものの概念である。すなわち、美徳ある人格とは、道徳的に善く、卓越し、称賛に値する人格であり、あるべき姿で 行動し、感じる者である。これらは広く受け入れられた自明の真理である。しかし、特定の(仮定された)美徳の事例に関しては、これらの自明の真理を放棄す ることも同様に一般的である。私たちは誰かについて、彼が「欠点と言えるほど」寛大であるとか正直であるとか言うかもしれない。例えば、他人の傷つく感情 を防ぎたいという思いから、言ってはならない嘘をついてしまうなど、人の思いやりが誤った行動を招くことがあるとよく言われる。また、ならず者における勇 気は、臆病であったならばできなかったであろうはるかに邪悪な行いを可能にするとも言われる。つまり、寛大さ、誠実さ、思いやり、勇気といった美徳が、時 に欠点となり得るのだ。寛大で誠実、思いやりがあり勇気ある人格が、必ずしも道徳的に優れた人格とは限らない——あるいは、彼らが道徳的に優れているとい う通念が依然として正しいとすれば、道徳的に優れた人格は、その優れた性質ゆえに誤った行動を取らされる可能性があるのだ! どうしてこんな奇妙な結論に至ったのだろうか? その答えは、一般的な用法への安易な受容にある。この受容は、多くの徳目用語のかなり広範な適用を許容し、おそらく現代的な傾向と結びついている。すなわ ち、徳ある行為者は理性的な選択ではなく、感情や傾向によって動機づけられていると仮定する傾向である。もし寛大さや誠実さを、 与えたいという欲求や真実を語りたいという衝動といった 寛大な、あるいは誠実な衝動によって行動に移される傾向と考えるならば、 もし 思いやりを他者の苦悩に心を動かされ、 その感情に基づいて行動する性質と考えるなら、 もし 勇気を単なる恐れを知らないこと、 あるいは危険に立ち向かう意思と考えるなら、 これらが全て、その持ち主を誤った行動へと導きうる性質であることは 確かに明白に思えるだろう。しかし同時に、これらは子供にも備わっている性質であることも明白だ。そしてこうした性質(「勇気」の性質を除いて)を備えた 子供たちは確かにとても良い子供たちだろうが、道徳的に高潔で称賛に値する人間だとは決して言えない。通常の用法、すなわち傾向による動機付けへの依存 は、アリストテレスが「自然徳」と呼ぶものを我々に与える——それはphronesis(実践的知恵)による完成を待つ完全な徳の原型である。 アリストテレスはフロネシスについて多くの具体的な言及を行っており、 これらは学界で活発に議論されているが、 (関連する)現代の概念を理解するには、 道徳的に成熟した徳ある成人が持ち、 善良な子供(善良な青年を含む)が欠いているものを 考えるのが最も適切である。徳ある成人も善良な子供も善意を持つが、 子供は意図した行動を遂行するために必要な知識を欠いているため、 事態を台無しにする傾向がはるかに強い。 徳ある成人ももちろん無謬ではなく、知識不足により 意図した行動を遂行できない場合もあるが、 それは知識不足が非難されるべき状況に該当しない場合に限られる。例えば、子供や青年は、利益をもたらそうとした相手に害を及ぼすことが多い。それは、利 益を確保する方法を知らないか、有益と有害の区別が限定的でしばしば誤っているためである。幼い子供のこうした無知は、ほとんど、あるいは全く非難される べきものではない。一方、成人は、 無思慮、無神経、無謀、衝動的、近視眼的であることによって、 あるいはより客観的な視点を持つ代わりに、 自分に都合の良いことが誰にでも都合が良いと仮定することによって、 物事を台無しにした場合、非難される。 また、有益と有害の区別が誤っている場合も非難される。真の利益を効果的に得る方法を知ることは 実践的知恵の一部である。実践的知恵を持つ者は、 「相手のためになる」と信じて、知る必要のある人格から 有害な真実を隠す過ちを犯さない。 概して言えば、善意とは善く行動する、すなわち「正しいことを行う」意図である以上、実践的知恵とは、善良な青少年とは異なり、その所有者があらゆる状況 においてまさにそれを可能にする知識あるいは理解であると言える。そのような知識や理解に何が含まれるかの詳細な規定は文献上まだ現れていないが、そのい くつかの側面は広く知られるようになってきている。多くの義務論者でさえ、自らの行動指針となる規則は、実践的知恵なしには確実に適用できないと強調して いる。なぜなら、正しい適用には状況認識——特定の状況において、その道徳的に重要な特徴を認識する能力——が必要だからである。これにより、実践的知恵 の二つの側面が浮き彫りになる。 一つは、それが本質的に人生経験によってのみ得られる点である。 状況の道徳的に重要な特徴には、特定の行動が関係者に及ぼす可能性のある結果が含まれ、 これはまさに経験不足ゆえに、青少年が著しく無知である領域である。人間と人生について賢明であることは、 実践的知恵の一部である。(言うまでもなく、 徳ある者は可能な行動の結果を心に留めている。 そうでなければ、どうして無謀で、 無思慮で、近視眼的でないことができようか?) 第二に、実践的に賢明な主体が持つ能力とは、ある状況において特定の特徴を他の特徴より重要であると認識する力、あるいはその状況においては唯一関連性の ある要素であると見極める力である。賢者は、未熟な徳を備えた善良な青年たちとは物事を同じように見ない。彼らはまだ、ある行為の個人的不利益という性質 が、その誠実さや慈愛や正義といった性質と同等に重要であると見なす傾向があるのだ。 これらの側面は、実践的に賢明な者を「人生において真に価値あるもの、真に重要なもの、そしてそれゆえ真に有益なものを理解する者、つまり端的に言えば、いかに良く生きるかを心得ている者」と描写する点で一致する。 |
|
| 2. 徳倫理学の形態 あらゆる形態の徳倫理学は、徳が中心であり実践的知恵が必要である点では一致しているが、特定の状況下で何をなすべきか、また人生全体をいかに生きるべき かを明らかにするために、これらの概念やその他の概念をどのように組み合わせるかについては異なる。以下では、現代の徳倫理学が取る四つの異なる形態、す なわちa)幸福主義的徳倫理学、b)行為者基盤的・模範主義的徳倫理学、c)目標中心的徳倫理学、d)プラトン主義的徳倫理学を概説する。 |
|
| 2.1 幸福主義(エウダイモニア)的徳倫理学 幸福論的徳倫理学の特徴は、 徳を幸福(eudaimonia)との関係において定義する点にある。 徳とは幸福(eudaimonia)に寄与する、あるいはその構成要素となる特質であり、 幸福論者は主張する——徳を育むべき理由は、 まさにそれらが幸福(eudaimonia)に寄与するからだと。 古代ギリシャ道徳哲学の重要概念であるユーダイモニアは、通常「幸福」または「繁栄」と訳され、時に「ウェルビーイング」とも訳される。各訳語には欠点が ある。「繁栄」の問題点は、動物や植物でさえ繁栄し得るが、ユーダイモニアは理性ある存在にのみ可能であることだ。「幸福」の問題点は、日常会話では主観 的に決定されるものを暗示することだ。私が幸福かどうかを判断するのは私自身であって、あなたではない。自分が幸福だと考えるなら、それは誤り得ない(高 度な自己欺瞞を除けば)。これに対し「健康である」や「繁栄している」の場合は、たとえ身体的・心理的に健康だと自覚していても、あるいは繁栄していると 思い込んでいても、それが誤り得ることを容易に認められる。この点において、 「幸福」よりも「繁栄」の方が適切な訳語である。 自らを欺くことが容易であるだけでなく、 eudaimon(eudaimoniaの形容詞形)であるか否かについて 誤った認識を抱きやすいからだ。(eudaimoniaの形容詞形)であるか否かについて誤った認識を持つのは、単に自己欺瞞が容易であるからだけでな く、eudaimonia、すなわち人間として良く生きるということの本質について誤った概念を抱きやすいからでもある。例えば、それが主に肉体的快楽や 贅沢から成ると信じ込むような場合がそうだ。 ユーダイモニアは、公言されている通り、道徳的あるいは価値判断を伴う幸福の概念であり、「真の」あるいは「現実の」幸福、あるいは「追求したり持つ価値 のある種類の幸福」のようなものである。したがって、この概念は、人間生活に関する見解が異なる人々の間で、外部基準への訴えによって解決できない重大な 意見の相違が生じうる類のものである。その外部基準とは、意見の相違があるにもかかわらず、対立する当事者が合意する基準を指す(Hursthouse 1999: 188–189)。 美徳倫理学のほとんどの流派は、美徳に従って生きることはユーダイモニアにとって必要不可欠であると認めている。この至高の善は、美徳の実践が促進すると 考えられるような(例えば、美徳的活動を含まない非道徳的善のリストで構成されるような)独立して定義された状態として捉えられてはいない。徳倫理学にお いては、 それはすでに、徳的活動が少なくとも部分的に構成要素となるものとして 捉えられている(クラウト 1989)。したがって、 徳倫理学者は、肉体的快楽や富の獲得に捧げられた人生は ユーダイモニアではなく、 無駄な人生であると主張する。 しかし、あらゆる標準的な徳倫理学が徳とユーダイモニアの概念的連関を主張する一方で、 それ以上の連関は論争の的となり、異なる解釈を生み出す。 アリストテレスにとって、徳は必要条件ではあるが十分条件ではない—— さらに必要なのは、運の問題である外的善である。 プラトンとストア派にとって、徳はユーダイモニアにとって 必要かつ十分な条件である(Annas 1993)。 幸福主義的徳倫理によれば、善き人生とは 幸福な人生であり、徳とは人間が 幸福であることを可能にするものである。なぜなら徳とは、 不運を除けば、そのようにして所有者に利益をもたらす性格的特性そのものだからである。したがって、eudaimonia(幸福)と、ある性格特性に徳と しての地位を与えるものとの間には関連性がある。(幸福主義者間の差異に関する議論についてはBaril 2014を参照。幸福主義の最近の擁護論についてはAnnas 2011; LeBar 2013b; Badhwar 2014; Bloomfield 2014を参照。) |
|
| 2.2 エージェントベースと実例主義的徳倫理学 徳の規範性をユーダイモニアの価値から導出するのではなく、主体に基づく徳倫理学者は、ユーダイモニアの価値を含む他の規範性の形態は、主体のもつ動機付け的・傾向的性質に遡及し、最終的にそれによって説明されると主張する。 理論が主体ベースとみなされるためには、さらにいくつの規範性を主体の性質によって説明しなければならないのかは不明である。最も著名な主体ベース理論家 であるマイケル・スロートとリンダ・ザグゼブスキーは、幅広い規範的性質を主体の性質に遡及している。例えばスロットは正しさ・誤りを行為者の動機で定義 する:「行為者基盤の徳倫理学は…正しい行為を善き動機によって、誤った行為を悪しき(あるいは十分に善くない)動機を持つことによって理解する」 (2001: 14)。同様に彼は、行為の善良さ、ユーダイモニアの価値、 法律や社会制度の正義、実践的合理性の規範性を、 行為者の動機的・傾向的性質によって説明する(2001: 99–100, 154, 2000)。ザグゼブスキもまた、 正しい行為と誤った行為を、 徳ある行為者と悪徳ある行為者の感情、動機、性向を参照して定義する。例えば、 「 不正行為=phronimosが 通常行わない行為であり、行った場合に罪悪感を覚える行為= 彼がそれを行う可能性がない行為= 悪徳を表現する行為= 徳(徳ある自己)の要求に反する行為」(Zagzebski 2004: 160)。義務、善悪の目的、善悪の状態に関する彼女の定義も同様に、模範的行為者の動機付け的・傾向的状態に根差している(1998, 2004, 2010)。 しかしながら、徳倫理学に対するより控えめなエージェントベースのアプローチも存在する(Slote 1997年を参照)。少なくとも、主体に基づくアプローチは、 主体が持つ動機付け状態や傾向性状態を参照することで、 「何をすべきか」を説明することを前提としなければならない。 しかし、これは主体に基づくアプローチと見なされるための 十分条件ではない。なぜなら、この条件はあらゆる美徳倫理学説が 満たすものだからである。ある理論が行為者ベースの徳倫理学とみなされるためには、さらに、動機づけや傾向性の規範的性質が、より根本的と見なされる他の 何か(例えばユーダイモニアや状況状態)の規範的性質によって説明できないことも必要である。 この基本的な前提を超えて、主体に基づく理論は 異なる方向へ発展する余地がある。最も重要な 区別要因は、動機や傾向性が他の規範的性質を説明する際 にどのように重要視されるかに関わる。スロットにとって重要なのはこの特定の行為者の実際の動機と傾向性である。例えば行為Aの善性は、行為者がAを実行 した際の動機から導かれる。それらの動機が善であれば行為は善であり、そうでなければ善ではない。これに対しザグゼブスキの立場では、善悪・正誤の行動は 当該行為者の実際の動機ではなく、徳的に動機づけられた行為者が行うであろう行動の種類によって定義される(Zagzebski 2004: 160)。徳ある行為者の仮説的な動機と傾向性への訴えかけにより、ザグゼブスキは「正しい行為を行うこと」と「正しい理由で行い」を区別できる(この区 別は、ブレイディ(2004)が指摘するように、スロートが明確に描くのに苦労している点である)。 エージェントベースの徳倫理学が異なる可能性のある別の点は、 徳ある動機や傾向をどのように特定するかに関するものである。 ザグゼブスキの模範主義的説明によれば、「善の基準は、善の模範を特定する以前に存在するものではない」(Zagzebski 2004: 41)。周囲の人々を観察する中で、私たちは(少なくとも ある点において)ある人々のようにありたいと願い、 またある人々のようにありたくないと気づく。前者は 私たちに肯定的な模範を、後者は否定的な模範を提供する。 より良い動機とより悪い動機、徳ある性質と悪しき性質への 私たちの理解は、こうした模範に対する原始的な反応に根ざしている (2004: 53)。これは、行動するたびに立ち止まって「この状況で模範となる人物は何をするか」と自問するわけではない。道徳的概念は、より多様な模範例に触れ、 それらを体系的に結びつけながら——共通点や異なる点、そして道徳的に重要な共通点・異なる点を認識する過程で——時間とともに洗練されていく。 認識可能な動機プロファイルが浮かび上がり、美徳や悪徳として名付けられる。これらはさらに、私たちが負う義務や追求すべき目的についての理解を形成す る。しかし、道徳的思考の体系化が起点から遠くまで進んだとしても、模範主義者によれば、模範への参照がより根本的な何かの認識に置き換わる段階には決し て到達しない。結局のところ、模範主義者によれば、 私たちの道徳体系は依然として、模範に対して好意(あるいは嫌悪)を抱く という基本的な傾向に依拠している。とはいえ、善悪・美徳と悪徳の判断の 起源や参照条件について模範主義者の説明を支持しなくとも、 行為主体に基づく理論家であることは可能である。 |
|
| 2.3 対象中心の徳倫理学 幸福主義的徳倫理学者の試金石は、人間が繁栄する人生である。行為者中心の徳倫理学者にとっては、模範的な行為者の動機がそれにあたる。これに対し、クリ スティン・スワントン(2003)が展開した対象中心の視点は、我々が既に持つ徳の概念から出発する。我々はすでに、どの特性が徳であり、それらが何を包 含するのかについて、まずまずの理解を持っている。もちろん、この素朴な理解は 明確化・改善が可能であり、徳倫理学者の任務の一つは まさにその手助けにある。しかし目標中心論は、 模倣すべき動機といった基礎的な要素まで還元したり、 繁栄した人生全体といった複雑な概念まで構築したりする代わりに、 倫理学を学ぶ学生の大半が置かれている地点、すなわち 寛大さ、勇気、自己規律、思いやりなどが 肯定的な評価を得ているという認識から出発する。 そしてこれらの特質が何を包含するのかを検証する。 徳の完全な説明は、1) その領域、2) その応答様式、3) その道徳的承認の基盤、そして4) その対象を明らかにする。異なる美徳は異なる領域に関わる。例えば勇気は我々を傷つける可能性のあるものに関わるが、寛大さは時間、才能、財産の共有に関 わる。ある美徳の基盤とは、 その美徳が反応する対象領域内の特性である。 先ほどの例を続けると、 寛大さは他者が自らの働きかけを通じて享受し得る利益に注意を向け、 勇気は価値や地位、あるいは特定の人々との絆に対する脅威、 そしてそうした脅威が生み出す恐れに反応する。美徳の様式は、その領域内の承認基盤への応答の仕方に関わる。寛大さは促進する、すなわち他者の利益という 善を。一方、勇気は守る、価値、絆、または地位を。最後に、美徳の対象とは、 それが目指すものである。勇気は恐怖を制御し危険に対処することを目指し、 寛大さは時間、才能、所有物を他者と分かち合い、 彼らに利益をもたらす方法を志向する。 標的中心論によれば、徳とは「その領域内にある事象に対して、優れた、あるいは十分に良い方法で応答し、あるいは認識する傾向である」(Swanton 2003: 19)。善行とは、ある徳の標的を捉える行為であり、すなわち、その領域内の事象に対して指定された方法で応答することに成功する行為である(233)。 徳ある行為とは、徳の目標を達成する行為、すなわちその領域内の事象に対して規定された方法で応答することに成功した行為である(233頁)。正しい行為 の目標中心的な定義を提供するには、単一の徳とその派生行為の分析を超えた考察が必要となる。なぜなら、単一の行為状況には複数の異なる、かつ重なり合う 領域が関与し得るからである。決意は、たとえ単一の目的を要するとしても、困難な課題の完遂を試み続けるよう私を駆り立てるかもしれない。しかし家族への 愛は、私の時間と注意を異なる形で用いるかもしれない。正しい行為を定義するためには、目標中心の視点は、異なる美徳が私たちの資源に対して抱く相反する 要求を、私たちがどのように処理するかを説明しなければならない。この課題に対処する方法は少なくとも三通り異なる。 完璧主義的な目標中心論は「行為は全体として徳ある場合にのみ正しく、 それは状況下で可能な最善の行動であることを意味する」と規定する(239–240)。より寛容な目標中心論は「正しい」と「最善」を同一視せず、 「最善(あるいは最善の一つ)でなくとも十分に良い」行為を 正しいと認める(240頁)。最小限主義的な目標中心論では、 行動が正しいとされるためにさえ、善である必要はない。 この見解によれば、「行為は、全体として悪ではない場合に限り正しい」(240)。 (目標中心の徳倫理学に関するさらなる議論については、Van Zyl 2014; Smith 2016を参照のこと)。 |
|
| 2.4 プラトン的徳倫理学 徳倫理学が採用しうる第四の形態は、プラトンにその着想を得ている。プラトンの対話篇に登場するソクラテスは、正義、勇気、敬虔、知恵といった徳の本質を アテネの同胞たちに説明させることに多くの時間を費やしている。したがってプラトンが徳理論家として数えられることは明らかである。しかし彼が徳倫理学者 として解釈されるべきかどうかは議論の余地がある (White 2015)。議論の余地がないのは、プラトンが現代における徳倫理学への関心再燃に重要な影響を与えたかどうかである。この再興に貢献した研究者の多くは プラトン学者として活動してきた(例:Prior 1991; Kamtekar 1998; Annas 1999; Reshotko 2006)。 しかしながら、彼らはしばしば、独自の分類を正当化するような形態ではなく、幸福主義的徳倫理学の形態を擁護する結果となっている(Prior 2001、Annas 2011参照)。とはいえ、別個の扱いが必要とされる二つの変種が存在する。 ティモシー・チャペルは、プラトン的徳倫理学の決定的特徴を「真の意味で完全な善き行為は、善のイデアの観想を前提とする」(2014年)と捉える。 チャペルはアイリス・マードックに倣い、「道徳的生活における敵は 肥大化した執拗な自我である」(Murdoch 1971: 51)と論じる。 自らの欲求、欲望、情熱、思考に絶えず注意を向けることは、 世界の実像に対する視点を歪め、周囲の善を見えなくさせる。遭遇したものの善性を熟考すること―すなわち「それ自体のために、理解するために」注意深く向 き合うこと(チャペル2014:300)―は、この自然な傾向を断ち切る。それは私たちの注意を自己から逸らすからだ。こうした良さを定期的に熟考するこ とは、 自己以外のものに、より容易に、より誠実に焦点を当てる 新たな思考習慣の余地を作る。それは私たちの意識の質を変える。 そして「意識を利他性、客観性、現実主義の方向へ変えるものは、 すべて美徳と結びつく」(マーダック 1971: 82)。したがって美徳は、人が「利己的な意識のベールを突き破り、世界が実際に存在する姿に参与する」(91)のを助ける資質として定義される。そして 善き行為主体性は、そうした美徳の保有と実践によって定義される。チャペルとマーダックの枠組みにおいては、規範的性質のすべてが美徳によって定義される わけではない。特に善性はそう定義されない。しかし我々のような存在に可能な善性は徳によって定義され、人が何をなすべきか、あるいは如何に生きるべきか という問いへのあらゆる答えは、徳に訴えることになる。 美徳倫理学における別のプラトン主義的変種は、ロバート・メリヒュー・アダムズによって示される。マーダックやチャペルとは異なり、彼の出発点は善の意識 に関する一連の主張ではない。むしろ、彼は善の形而上学の説明から始める。マーダックやプラトン主義の影響を受けた他の者たちと同様に、アダムズの善の説 明は、至高の完全なる善という概念を中心に構築されている。そして アウグスティヌスと同様に、アダムズはその完全なる善を神と見なす。神はあらゆる善の 体現であると同時に源泉でもある。他のものは、神に似ている範囲で善であると 彼は示唆する(Adams 1999)。 類似性の要件は善であるための必要条件を特定するが、 それだけでは十分条件とはならない。なぜなら有限の被造物が 神に類似する方法は存在するものの、その被造物の本質に ふさわしくない場合があるからだ。例えば神が全知であるならば、 「私は全知である」という信念は神が持つにふさわしい。 神においては、そのような信念は真実であるゆえに神の完全性の一部となる。しかし、あなたも私も全知ではない以上、私たちの一人が「私は全知である」と信 じることは善ではない。こうした事例を排除するには、別の要素を導入する必要がある。その要素とは、善に対するふさわしい応答であり、アダムズはそれが愛 であると示唆する。アダムズは愛を用いて問題のある類似性を排除する: 「有限なるものが達成しうる卓越性とは、 神がその対象を愛する理由となり得る形で 神に似ることにある」(Adams 1999: 36)。 美徳は、あるもの(すなわち人格)が神に似る方法の一つとして考慮される。「私たちにとって最も重要であり、その価値を最も確信している優れたもののほと んどは、人格、あるいは人格の資質や行動、業績、生涯、物語の優れた点である」(1999: 42)。これがアダムズが、完全性の理想を非人格的な善の形態ではなく個人的な神として構想する理由の一つである。私たちが最も確信する人格の卓越性の多 くは、愛、知恵、正義、忍耐、寛大さといった美徳である。そしてアダムズ自身のキリスト教伝統を含む多くの有神論的伝統において、こうした美徳は一般的に 神聖な存在に帰せられる。 アダムズが『有限と無限の善』で提示するようなプラトン主義的解釈は、明らかに他の規範的性質のすべてを美徳から導出しているわけではない(この見解と彼 が『美徳の理論』(2006年)で提示した見解との関係についての議論については、Pettigrove 2014を参照)。善性が規範的基盤を提供する。徳はその基盤の上に構築されるのではなく、むしろ我々が最も確信を持つ善性の多様性の一つとして、基盤の 一部を成す。義務は対照的に、異なるレベルで理論に組み込まれる。アダムズによれば、道徳的義務は「善または価値ある関係性、あるいは関係性の体系におい て生じる期待や要求」によって決定される(1999: 244)。他の条件が等しい場合、関係性の当事者がより徳を備えているほど、義務はより拘束力を持つ。したがってアダムズの理論では、善(徳を含む)は権 利に先行する。しかし、善なる関係が義務を生み出した後は、それらの義務は独自の生命を帯びる。その拘束力は、善の考慮に直接由来するものではない。むし ろ、関係当事者の期待と関係性自体の要求によって決定されるのである。 |
|
| 3. 徳倫理学への異議——徳の倫理学批判 徳倫理学に対しては数多くの異議が提起されており、その一部は他の形態よりも特定の形態の徳倫理学に直接的に関わるものである。本節では八つの異議、すな わちa)適用、b)妥当性、c)相対主義、d)矛盾、e)自己犠牲、f)正当化、g)利己主義、h)状況主義の問題について考察する。 a) 美徳倫理学が復活した初期の頃、このアプローチは規範理論の支配的な主張に対抗する、倫理に関する「反体系化可能性」の命題と結びついていた。当時、功利 主義者と義務論者は(普遍的ではないが)一般的に、倫理理論の任務は普遍的な規則または原理(行為功利主義の場合のように単一の原理のみである可能性もあ る)から成る規範体系を構築することであり、それは二つの重要な特徴を持つと主張していた:i) その規則(複数可)は、あらゆる個別事例において正しい行動を決定するための判断手順に相当するものであること ii) その規則は、徳を備えていない人格であっても正しく理解し適用できる形で表現されること。 美徳倫理学者たちは、これら 2 つの主張とは対照的に、そのような規範が存在しうることを想像することはまったく非現実的であると主張した(特に、マクダウェル 1979 を参照)。1960年代から1970年代にかけて、医療倫理、そして生命倫理が急成長し、隆盛を極めた時代、 そのような規範を作り出し、適用しようとした試みの結果は、 美徳倫理学者の主張を裏付けるものとなった。 ますます多くの功利主義者や義務論者が、 一般的な規則については合意しているものの、 現代の議論における論争の的となっている道徳的問題については 対立する立場にあることに気づいた。規則や原理を正しく適用するには、道徳的感受性、洞察力、想像力、経験に基づく判断力——要するにフロネシス——が必 要であると認識されるようになった。したがって多くの(ただし決して全てではない)功利主義者と義務論者は明示的に(ii)を放棄し、(i)への重点も大 幅に弱められた。 しかしながら、徳倫理学が体系化可能な原則を生み出さないという批判は、依然としてこのアプローチに対する一般的な批判として表明されており、それは原則的に行動指針を提供できないという異議として表現される。 当初、この反論は誤解に基づいていた。美徳倫理学を「行為よりも存在に関心を置く」「『私はどのような人格であるべきか』には応えるが、『私は何をすべき か』には応えない」「行為中心ではなく主体中心である」と描写するスローガンに目を曇らされた批判者たちは、美徳倫理学が行動指針を提供できないと主張し た。したがって、功利主義や義務論的倫理学に対する規範的対抗馬というより、それらに対する貴重な補完に過ぎないと主張できたのである。奇妙な考えとし て、徳倫理学が提供できるのは「道徳的模範を特定し、その人物が取るであろう行動を取ること」に過ぎないという主張があった。まるで、音楽(自身の希望) と工学(両親の希望)のどちらを学ぶか悩む大学生が「ソクラテスが私の立場なら何を学ぶだろうか?」と自問すべきであるかのように。 しかしこの反論は、アンスコムが示唆した点——すなわち「誠実であること/慈善的であることを行いなさい;不誠実であること/非慈善的であることを行って はならない」といった美徳と悪徳の用語を用いた規則(「v-ルール」)の中に、多くの具体的な行動指針を見出すことができるという点を——見落としていた (Hursthouse 1999)。(私たちの美徳と悪徳の語彙には注目すべき特徴がある。一般的に認められた美徳の用語リストは比較的短いにもかかわらず、悪徳の用語リストは 驚くほど、そして有用なほど長く、標準的な義務論的規則で考える者がこれまでに考案したものをはるかに超えている。無責任、無計画、怠惰、 無配慮、非協力的、苛烈、不寛容、利己的、金銭至上主義、 軽率、無神経、傲慢、冷淡、無関心、冷酷、不注意、 無気力、卑怯、弱腰、尊大、無礼、 偽善的、自己中心、物質主義、強欲、短視、 執念深い、計算高い、恩知らず、けち、残忍、放蕩、 不忠実、などといった行動方針を避けることから得られる。 (b) これと密接に関連する異論は、徳倫理学が正しい行為について十分な説明を提供できるかどうかに関わる。この懸念は二つの形態をとる。(i) 正しい行為に関する徳倫理学的説明は外延的に不十分だと考える者もいる。徳を備えていなくても正しい行為を行うことは可能であり、また徳を備えた人格が時 折誤った行為を行っても、その人格の徳が問われることはない。もし美徳が正しい行為にとって必要でも十分でもないならば、正しさ/誤りと美徳/悪徳の関係 が、前者を後者によって規定できるほど密接であるかどうか疑問に思うかもしれない。(ii) あるいは、たとえ全ての(そして唯一の)正しい行為を網羅する徳倫理学的説明が可能だとしても、少なくとも一部の事例においては、正しさを説明する要因が 徳ではないと考える余地が残る(Adams 2006:6–8)。 ある美徳倫理学者は、美徳倫理学がそもそも正しい行為の説明を提供すべきだという前提そのものを拒否することで、妥当性への異議に対処する。アンスコム (1958)やマッキンタイア(1985)の足跡を辿り、タルボット・ブリュワー(2009)は、正しさ・誤りというカテゴリーを扱うこと自体が既に誤っ た出発点であると主張する。現代の正しさ・誤り行為の概念は、誤りという概念を中心に構築されているため、正しい行為の概念を構築することは誤った方向へ 進むことになる。 (2009)は、正しさ・誤りというカテゴリーを扱うこと自体が誤った出発点であると主張する。現代の正誤行動の概念は、神(あるいは道徳的)法の枠組み を前提とする道徳的義務の概念、あるいは自己利益との対比で定義される義務の概念を中心に構築されており、これらは徳倫理学者が避けるべき負の遺産を伴っ ている。徳倫理学は、いかに生きるべきか、いかなる人格になるべきか、さらには何をなすべきかという問いに向き合うことができる。それは「正しい行為」の 説明を提供することを意味しない。代わりに、アレテー的概念(美徳と悪徳によって定義される)や価値論的概念(善悪、優劣によって定義される)を用いて、 義務論的概念(正しい/間違った行動、義務、責務など)を完全に排除する道を選ぶことも可能である。 他の徳倫理学者は正しい行為の概念を保持したいと望むが、 現在の哲学的議論では、その旗印の下に数多くの異なる性質が混在していると指摘する。 ある文脈では「正しい行為」とは、行為者が状況下で遂行し得る最善の行為を指す。 別の文脈では、称賛に値する行為(最善ではない場合でも)を意味する。さらに別の文脈では、非難に値しない行為(称賛に値しない場合でも)を指す。徳倫理 学者は、例えば最善の行為といった概念を徳と悪徳の観点から定義しつつ、他の「正しい行為」の概念を定義する際には、正当な期待といった他の規範的概念に 訴える選択をするかもしれない。 第2節で考察したように、徳倫理学の立場は、他の規範的概念をすべて徳と悪徳に還元しようとする必要はない。 必要なのは単に、(i) 美徳がより基礎的とされる他の規範的概念に還元されないこと、 (ii) 他の規範的概念が美徳と悪徳によって説明されることである。これにより、徳倫理学の諸形態に対して最も説得力を持つ「適切性」への異議申し立ての刺は抜か れる。それらの形態は「正しい行為」のあらゆる意味を徳によって定義しようと試みるからだ。徳と悪徳に訴えることで、外延的適切性を達成することがはるか に容易になる。徳と悪徳の概念に還元されないと見なされる規範的概念に余地を設けることで、外延的かつ説明的に十分な理論を構築することがさらに容易にな る。他の概念が必要かどうか、また必要ならその数はどれほどかについては、徳倫理学者が正しい行為の説明を提供すべきかどうかという問題と同様、依然とし て議論の的となっている。いずれにせよ、徳倫理学者は 妥当性への異議に対処するための資源を 有している。 美徳倫理学の諸流派がすべて美徳への重点を保持する限り、それらは(c)のよく知られた問題、すなわち文化的相対性への非難に晒される。異なる文化が異な る美徳を体現している(MacIntyre 1985)以上、v-ルールが行動を正誤として選別するのは特定の文化に相対的にのみではないか?この批判に対しては異なる反論がなされてきた。 一つは<tu quoque>、すなわち「共犯者」論法と呼ばれるもので、 これは徳倫理学者の防衛戦略において極めてよく見られるパターンである(Solomon 1988)。彼らは、自分たちにとって文化相対主義が確かに課題であることを認めつつも、他の二つのアプローチにとっても同様に問題であると指摘する。美 徳と見なされる性格特性の(想定される)文化的差異は、行動規範の文化的差異よりも大きくない——むしろ著しく小さい——し、異なる文化は幸福や福祉を構 成する要素について異なる考えを持っている。文化的相対性が三つのアプローチ全てに共通する問題であることは 驚くに当たらない。結局のところ、これは「正当化問題」 (後述) ——道徳的懐疑論者、多元主義者、あるいは異文化の人々といった 意見の相違者に対して自らの道徳的信念を正当化する という極めて一般的なメタ倫理的問題—— に関連しているからである。 より大胆な戦略は、美徳倫理学が他の二つのアプローチよりも文化的相対性に対して困難が少ないと主張することである。多くの文化的意見の相違は、美徳に対 する地域的な理解から生じていると主張できるが、美徳そのものは文化に相対的なものではない(Nussbaum 1993)。 tu quoqueという反論が部分的に適切であるもう一つの異論は(d)「矛盾の問題」である。美徳倫理学は、一見して異なる美徳の要求が相反する方向を指し 示すために衝突するジレンマ——例えば慈善は死んだ方がましな人格を殺すよう促すが、正義はそれを禁じる——について何を述べるのか?誠実さは 傷つける真実を語ることを指し示すが、親切心と慈しみは 沈黙を守る、あるいは嘘をつくことさえも促す。どうすべきか? もちろん、義務論的規範間の対立からも同様のジレンマが生じる。義務論と徳倫理学は「対立問題」を共有し(功利主義者らのような帰結主義的解決策を採るよ り、むしろ喜んでこの問題を引き受ける)、実際に対処戦略も並行している。両者は「対立は単なる見かけ上のものに過ぎない」と論じることで数多くのジレン マを解決しようとする。実践的知恵を持つ者だけが持つ、問題の徳や規範に対する識別的な理解は、この特定の事例において、徳が相反する要求を課すわけでは ないこと、あるいは一つの規範が他より優先されること、あるいは特定の例外条項が組み込まれていることを認識するだろう。これが全てかどうかは、 解決不能なジレンマが存在するか否かにかかっている。もし存在するならば、 いずれの規範的アプローチの支持者も、 仮説上解決不能な事象に対する解決策を提示することは誤りであると 合理的に指摘しうるだろう。 3つのアプローチすべてに共通するもう1つの問題は、おそらく(e)、つまり 自己抑制である。倫理理論は、大まかに言えば、特定の行動を正当化したり、それを正しいとする主張が、その行動を行う行為者の動機であってはならない場合 に、 自己抑制的であるといえる。 マイケル・ストッカー(1976)は、これを義務論と帰結主義の問題として最初に紹介しました。彼は、正しく、病院に入院中の友人を訪問する行為者は、そ の訪問が彼女に与える影響をむしろ弱めるだろうと指摘しました。なぜなら、その訪問が義務であるから、あるいはそれが一般的な幸福を最大化すると考えたか らだと彼女に伝えると、その訪問が彼女に与える影響は弱まるからです。しかし、サイモン・ケラーが指摘するように、彼が「それは高潔な行為者なら行うべき ことだから」と告げたとしても、彼女の喜びはまったく変わらないだろう。したがって、美徳倫理学にも同様の問題があるように見える(Keller 2007)。しかし、徳倫理学の擁護者たちは、 すべての形態の徳倫理学がこの反論の対象となるわけではないと主張している(Pettigrove 2011)。 また、この問題によって深刻な打撃を受けるものもないと主張している(Martinez 2011)。 徳倫理学にとってのもう一つの問題は、功利主義と義務論の双方に共通する(f) 「正当化の問題」である。 抽象的に捉えれば、これは私たちの倫理的信念をいかに正当化・根拠付けるかという問題であり、 メタ倫理学のレベルで激しく議論されている課題である。具体的な形態において、義務論では特定の道徳的規則が正しいという主張をいかに正当化するかという 問題が、功利主義では道徳的に真に重要なのは幸福や福祉の結果のみであるという主張をいかに正当化するかという問題がそれぞれ存在する。徳倫理学における この問題は、どの性格特性が徳であるかという問いに関わる。 メタ倫理学の議論においては、倫理学に対する外部的な基盤——倫理的信念に外部的な意味での「外部」——を提供することの可能性について広範な意見の相違 が存在し、義務論者と功利主義者の間にも同様の相違が見られる。規範倫理学を確固たる基盤に据え、あらゆる懐疑主義に耐えうるもの(例えば、倫理観に関わ らず誰もが合理的に望むもの、あるいは受け入れ合意するもの)と考える者もいれば、それは不可能だと考える者もいる。 徳倫理学者は、徳倫理学を外部的な基盤に据えようとする試みを一切避けてきた一方で、自らの主張が正当化可能であるという立場を堅持し続けている。その中 には、ロールズの一貫主義的アプローチの一形態を採る者もいれば(Slote 2001; Swanton 2003)、新アリストテレス主義者たちは倫理的自然主義の一形態を採っている。 ユーダイモニアを非道徳的概念と誤解する ことから、一部の批評家は新アリストテレス学派が 自らの主張を、人間の本性および人間にとっての 繁栄とは何かについての科学的説明に立脚させようとしていると 推測する。また、 もし彼らがそうしていないのであれば、例えば、正義、慈善、勇気、寛大さは美徳であるという彼らの主張を正当化することはできないと考える批評家もいる。 彼らは、アリストテレスの信用を失った自然目的論を不当に利用している(Williams 1985)か、あるいは、彼ら自身の個人的、あるいは文化的に教え込まれた価値観を単に合理化しているだけである。しかし、マクダウェル、フット、 マッキンタイア、ハーストハウスは、この両極端の間に第三の道となる 考え方を概説している。徳倫理学におけるユーダイモニアは、 確かに道徳化された概念であるが、それだけではない。人間にとって何が繁栄を構成するかという主張は、 人間がどのような存在であるかに関する科学的事実から、 象にとって何が繁栄を構成するかという動物行動学の主張から 同様に、自由に浮遊することはできない。どちらの場合も、 その主張の真偽は、部分的には、彼らがどのような動物であり、 人間や象がどのような能力、欲求、興味を持っているかによって 決まる。 今日入手可能な最良の科学(進化論や心理学を含む)は、 私たちが象や狼のように社会的動物であり、 ホッキョクグマとは異なるという古代ギリシャの仮定を 弱めるどころかむしろ支持している。協力の利点を確保するために自己中心的な欲望を抑え、共に生きることを選ぶ理由を説明するのに、社会契約のような概念 による合理的な説明は不要である。他の社会性動物と同様、我々の自然な衝動は自己の快楽や生存のみに向けられているのではなく、利他的で協力的な衝動も含 んでいる。 この私たちに関する基本的な事実は、美徳が少なくとも部分的に人間の繁栄を構成するものであるという主張をより理解しやすくすると同時に、美徳倫理学がある意味で利己的であるという反論を弱めるものである。 (g) 利己主義の反論にはいくつかの根拠がある。一つは単純な混同である。完全に徳ある行為者が内的な葛藤なく当然の行いを特徴とすることを理解すると、人々は 「彼女は単に望むことをしているだけであり、したがって利己的である」と勝利を宣言するように主張する。したがって、寛大な人格が寛大な者の常として喜ん で与えるとき、結局のところ彼女は寛大でも無私でもない、あるいは少なくとも自分が持つ全てを貪欲に握りしめたいが「すべきだ」と考えて無理やり与える人 ほど寛大ではないという結果になる!関連する解釈では、徳ある行為者に奇妙な動機を帰する。 不当にも、彼女がそう行動するのは この機会にそう行動することが ユーダイモニア(幸福)の達成に役立つと 信じているからだと仮定するのだ。 しかし「徳ある行為者」とは単に 「徳を備えた行為主体」に過ぎず、徳の概念にはそれぞれ固有の行動理由の範囲が伴うことは 我々の日常的理解の一部である。徳ある行為主体がそう行動するのは、 それによって誰かの苦悩が回避されると信じているから、あるいは誰かが利益を得ると信じているから、 真実が確立されると信じているから、負債が返済されると信じているから、 あるいは…そう信じているからに他ならない。 人生における美徳の実践こそが、ユーダイモニアを少なくとも部分的に構成すると考えられており、これは不幸な出来事が美徳ある主体を命を捧げることを要求 される状況に陥らせる可能性があるという認識と一致する。勇気ある者、誠実な者、忠実な者、慈愛に満ちた者が行動の理由として心から認めるような諸般の事 情を考慮すれば、彼らは価値ある目的のために危険に立ち向かうこと、誰かの擁護のために声を上げること、同志の名を明かすことを拒むこと(たとえそれが必 然的に処刑につながると知りつつ)、最後のパンのかけらを分かち合い飢餓に直面することを、自ら進んで選択せざるを得ない状況に陥るかもしれない。美徳の 実践が幸福(ユーダイモニア)にとって必要だが十分ではないとする見解によれば、こうした事例は、美徳ある主体が不幸にも事態がそうなってしまった以上、 自分にとって幸福が不可能であると悟る場合と説明される(Foot 2001, 95)。一方、 ストア派の見解では、徳の実践は必要かつ十分条件であり、 幸福な人生とは成功裏に生き抜かれた人生である (「成功」は当然ながら物質主義的な意味では理解されない)。 そうした人々は、自らの人生を成功させただけでなく、 その人生を顕著な成功をもって完結させたことを自覚して死ぬのである。いずれにせよ、こうした英雄的行為は 利己的とは到底言えない。 いわゆる「自己指向的」と「他者指向的」美徳の誤った区別には、自己中心主義の残響が認められる。古代の伝統から隔絶された人々は、 正義と仁愛を真の徳と見なしがちである。 これらは他者に利益をもたらすが、 その所有者には利益をもたらさない。 一方、慎重さ、勇気、そして先見性(その反対は 「無計画」あるいは浪費家である)は、 所有者だけに利益をもたらすため、 真の徳とは見なされない。これは二つの点で誤りである。第一に、正義と仁愛は概してその保持者にも利益をもたらす。なぜなら、それらがなければ幸福は不可 能だからである。第二に、我々が社会的な動物として共に生きる以上、「自己指向的」美徳は他者にも利益をもたらす。それらが欠如している者は、身近な者に とって大きな負担となり、時に悲しみをもたらす(無計画あるいは無分別な成人した子を持つ親が痛感している通りである)。 美徳倫理に対する最新の反論(h)は、「状況主義」社会心理学の研究が、 性格特性のようなものは存在せず、したがって美徳倫理が扱うべき美徳のようなものも存在しないことを示していると主張している(Doris 1998; ハーマン 1999)。これに対し、 一部の徳倫理学者は、社会心理学者の研究は、 徳が本来備えているとされる多面的な性質(前述)とは無関係であると主張している(Sreenivasan 2002; Kamtekar 2004)。 その多面性を十分に認識した上で、彼らは、慈善のような厳しい徳を、 従来の規範的徳の表現しか見られない人々に帰することは、 極めて無謀であることに同意している。その多面性を 念頭に置き、慈善のような要求の厳しい美徳を、 従来の礼儀正しさを示しているという情報しか持たない人々に 帰することは、極めて無謀であることに同意している。 これはまさに「基本的な帰属の誤り」である。他の研究者たちは、経験的に裏付けられた性格特性の代替概念を構築しようと試みてきた(Snow 2010; Miller 2013 and 2014; ただしMillerへの反論についてはUpton 2016を参照)。他にも様々な反論が存在する(Prinz 2009とMiller 2014に有益にまとめられている)。特に注目すべきはAdams(2006、Merritt 2000を呼応)による応答で、「性格特性は全く存在しない」という立場と、アリストテレス的徳概念の厳格な基準(その強調点であるphronesisゆ えに高い性格統合性を要求する)との間の中道を進むものである。彼の概念によれば、性格特性は「脆弱で断片的」であっても美徳となり得、また珍しいもので はない。しかしアダムズがそうせざるを得なかったように、実践的知恵が全ての美徳の核心であるという考えを放棄することは、ラッセル(2009)やカムテ カル(2010)が論じるように、重大な犠牲を伴う。 「状況主義的挑戦」は伝統的な徳倫理学者たちを動揺させなかったものの、経験的心理学文献との健全な対話を生み出した。この対話は、フットの『自然の善性』に関する文献の増加と、まったく独立した動きとして、品性教育への関心の高まり(後述)によっても促進されてきた。 |
|
| 4. 今後の方向性 過去 35 年間に、美徳倫理の復活に貢献した人々のほとんどは、新アリストテレス主義、 ユーダイモニズムの枠組みの中で活動してきました。 しかし、第 2 節で述べたように、他の形態の美徳倫理も出現し始めています。 理論家たちは、代替案を開発するために利用できる資源を、ハッチェソン、ヒューム、ニーチェ、マーティノー、ハイデガーなどの哲学者に求め始めています (ラッセル 2006、スワントン 2013 および 2015、テイラー 2015、ハーコート 2015 を参照)。また、 東洋に目を向け、儒教、仏教、 ヒンドゥー教の伝統を探求する者もいる(Yu 2007、スリンガーランド 2011、フィニガンとタナカ 2011; マクレー 2012; アングルとスロート 2013; デイヴィス 2014; フラナガン 2015; ペレットとペティグローブ 2015; シム 2015)。これらの探求は、 徳倫理学の発展に新たな道を開くことを約束している。 美徳倫理学は過去35年間で著しく発展したにもかかわらず、特に応用倫理学の分野では依然として少数派である。「道徳的問題」や「応用倫理学」に関する大 規模な教科書シリーズの編集者の多くは、現在では三つの規範的アプローチそれぞれを代表する論文を収録しようと努めているが、特定の問題に取り組む美徳倫 理学の論文を見つけることができない場合が多い。これは時に、その問題が義務論/功利主義の対立構図で設定されているためではあるが、多くの場合、単に美 徳倫理学者がその主題についてまだ執筆していないという単純な理由による。しかし過去10年間で、応用美徳倫理学への注目は確実に高まっている (Walker and Ivanhoe 2007; Hartman 2013; Austin 2014; Van フート 2014; アナス 2015)。この分野は、今後さらに発展することが期待でき、 環境倫理の分野に徳倫理学を適用することは、 特に有益であると思われる(サンドラー 2007; ハーストハウス 2007、2011; ズウォリンスキーとシュミット 2013; カファロ 2015)。 Cafaro 2015)。 徳倫理学が「徳政治学」へと発展する可能性、すなわち道徳哲学から政治哲学へと拡張する可能性は、必ずしも明らかではない。ギゼラ・ストライカー (2006)は、アリストテレスの倫理学は彼の政治学における位置付けを考慮せずに適切に理解できないと論じている。これは少なくともアリストテレスに触 発された徳倫理学者たちが、徳の政治学の発展に資する資源を提供できるはずであることを示唆している。 しかし、プラトンとアリストテレスは徳倫理学に関して大きな啓発源となり得る一方で、 政治哲学の観点では、一見したところ魅力的な知見の源泉とは言い難い。 とはいえ、近年の研究はアリストテレス思想が結局のところ 満足のいく自由主義的政治哲学を生み出し得ることを示唆している(Nussbaum 2006; LeBar 2013a)。さらに前述の通り、徳倫理学は新アリストテレス主義である必要はない。ハッチェソンやヒュームの徳倫理学は、現代の政治哲学へと自然に拡張 できる可能性がある(Hursthouse 1990–91; Slote 1993)。 プラトンとアリストテレスに続き、現代の徳倫理学は常に道徳教育の重要性を強調してきた。それは規則の押し付けではなく、人格の訓練としてである。現在、 学界(Carr 1999; アタナソウリス 2014; カレン 2015)と教室の教師の間で、美徳教育への動きが高まっている。この分野の研究における興味深い点は、心理学、教育理論、神学を含む他の学術分野との関 わりにある(クライン 2015; スノー 2015を参照)。 最後に、徳倫理学におけるより生産的な発展の一つは、特定の徳と悪徳の研究を通じてもたらされた。現在では、主要な徳と重大な悪徳に関する数多くの緻密な 研究が存在する(Pieper 1966; Taylor 2006; Curzer 2012; Timpe and Boyd 2014)。他の研究者たちは、礼儀正しさ、品位、誠実さ、野心、柔和さなど、 あまり議論されていない美徳や悪徳を探求している(Calhoun 2000; Kekes 2002; Williams 2002; Pettigrove 2007 and 2012)。これらの研究が提起する疑問の一つは「美徳はいくつ存在するのか?」である。二つ目は「これらの美徳は互いにどのように関連しているのか?」 である。一部の美徳倫理学者は、美徳の数を制限する原理的な理由はなく、むしろ複数の美徳を想定する十分な理由があると仮定して研究を進めてきた (Swanton 2003; Battaly 2015)。他方、美徳に対するこのような開放的なアプローチは、美徳倫理学者が正しい行動の適切な説明を提示したり、前述の矛盾問題に対処したりするこ とを困難にするのではないかと懸念する者もいる。ダン・ラッセルは、彼が「列挙問題」(美徳が多すぎるという問題)と呼ぶものに対する解決策として、基数 性と統一性命題の一形態を提案している。美徳の明らかな増殖は、主要美徳とそれに従属する拡張美徳にグループ分けすることで大幅に削減できる。残された美 徳間の潜在的衝突は、統一された全体の一部として何らかの形で結びつけることで管理可能となる(ラッセル 2009)。これは今後の研究における二つの重要な方向性を示唆している。一つは個々の美徳を探求するものであり、もう一つはそれらの相互関係性を分析す るものである。 |
|
| 文献はリンク先 |
|
| https://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/ |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆