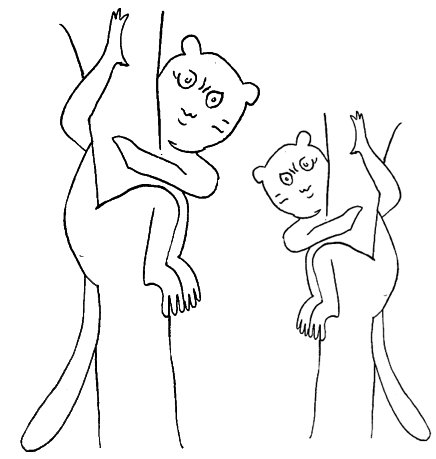
クトゥルセン時代の人類学
Anthro-Cthulhu-logy in Cthulucene
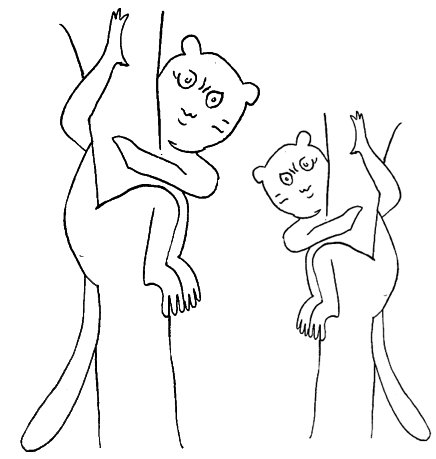
☆ク トゥルセンとは、人新世(Anthropocene)などの造語のように、クトゥルフが地球の地質時代の主人公になる時代区分のことをさす。クトゥルフ は、神話ないしはクトゥルフ教なるもので、示唆された、かつて、人類が誕生する以前に地球を支配していた生物である。しかし、その記憶はクトゥルフ教とい う秘密カルトのなかに生き残り、ある時代に再び復活し、人類に災厄をもたらす危険性のある存在(可能態)でもある。クトゥルセンという用語と地質時代区分 は、ダナ・ハラウェイが2016年の論文「触手の思考:人新世、資本世、クトゥルセン(Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene)」の中で主張した新造語である。
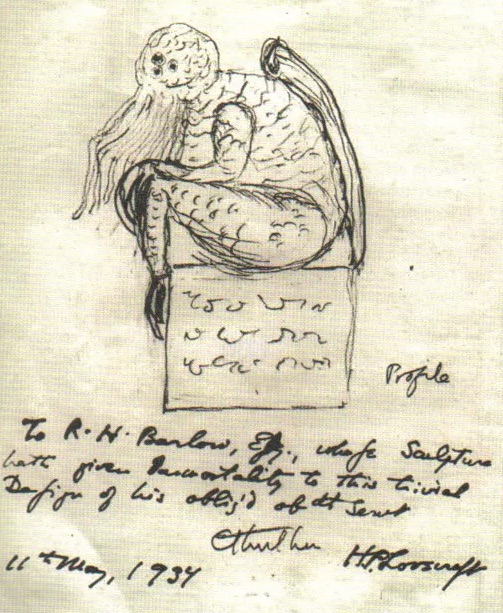 Tentacular
Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene Tentacular
Thinking: Anthropocene, Capitalocene, ChthuluceneDonna Haraway, e-Flux Journal, Issue #75. Dep. 2016. We are all lichens. — Scott Gilbert, “We Are All Lichens Now” Think we must. We must think. —Stengers and Despret, Women Who Make a Fuss What happens when human exceptionalism and bounded individualism, those old saws of Western philosophy and political economics, become unthinkable in the best sciences, whether natural or social? Seriously unthinkable: not available to think with. Biological sciences have been especially potent in fermenting notions about all the mortal inhabitants of the Earth since the imperializing eighteenth century. Homo sapiens — the Human as species, the Anthropos as the human species,Modern Man — was a chief product of these knowledge practices. What happens when the best biologies of the twenty-first century cannot do their job with bounded individuals plus contexts, when organisms plus environments, or genes plus whatever they need, no longer sustain the overflowing richness of biological knowledges, if they ever did? What happens when organisms plus environments can hardly be remembered for the same reasons that even Western-indebted people can no longer figure themselves as individuals and societies of individuals in human-only histories? Surely such a transformative time on Earth must not be named the Anthropocene! With all the unfaithful offspring of the sky gods, with my littermates who find a rich wallow in multispecies muddles, I want to make a critical and joyful fuss about these matters. I want to stay with the trouble, and the only way I know to do that is in generative joy, terror, and collective thinking. My first demon familiar in this task will be a spider, Pimoa cthulhu, who lives under stumps in the redwood forests of Sonoma and Mendocino Counties, near where I live in North Central California. Nobody lives everywhere; everybody lives somewhere. Nothing is connected to everything; everything is connected to something. This spider is in place, has a place, and yet is named for intriguing travels elsewhere. This spider will help me with returns, and with roots and routes. The eight-legged tentacular arachnid that I appeal to gets her generic name from the language of the Goshute people of Utah and her specific name from denizens of the depths, from the abyssal and elemental entities, called chthonic. The chthonic powers of Terra infuse its tissues everywhere, despite the civilizing efforts of the agents of sky gods to astralize them and set up chief Singletons and their tame committees of multiples or subgods, the One and the Many. Making a small change in the biologist’s taxonomic spelling, from cthulhu to chthulu, with renamed Pimoa chthulu I propose a name for an elsewhere and elsewhen that was, still is,and might yet be: the Chthulucene. I remember that tentacle comes from the Latin tentaculum, meaning “feeler,” and tentare, meaning “to feel” and “to try”; and I know that my leggy spider has many-armed allies. Myriad tentacles will be needed to tell the story of the Chthulucene. The tentacular are not disembodied figures; they are cnidarians, spiders, fingery beings like humans and raccoons, squid, jellyfish, neural extravaganzas, fibrous entities, flagellated beings, myofibril braids, matted and felted microbial and fungal tangles, probing creepers, swelling roots, reaching and climbing tendrilled ones. The tentacular are also nets and networks, it critters, in and out of clouds. Tentacularity is about life lived along lines — and such a wealth of lines — not at points, not in spheres. “The inhabitants of the world, creatures of all kinds, human and non-human, are wayfarers”; generations are like “a series of interlaced trails.” All the tentacular stringy ones have made me unhappy with posthumanism, even as I am nourished by much generative work done under that sign. My partner Rusten Hogness suggested compost instead of posthuman(ism), as well as humusities instead of humanities, and I jumped into that wormy pile. Human as humus has potential, if we could chop and shred human as Homo, the detumescing project of a self-making and planet-destroying CEO. Imagine a conference not on the Future of the Humanities in the Capitalist Restructuring University, but instead on the Power of the Humusities for a Habitable Multispecies Muddle! Ecosexual artists Beth Stephens and Annie Sprinkle made a bumper sticker for me, for us, for SF: “Composting is so hot!” https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |
『クトゥルフの呼び声』(クトゥルフのよびごえ、英: The
Call of
Cthulhu)とは、アメリカ合衆国のホラー小説家ハワード・フィリップス・ラヴクラフトが1928年に発表した小説。ラヴクラフト、およびクトゥルフ
神話の代表作の一つとされる。ラヴクラフト自身、この作品によって、のちに「クトゥルフ神話」と呼ばれることになる彼独自の作品世界を大きく飛躍させた
[2]。オーガスト・ダーレスがラヴクラフトの作品世界を体系化したさい、それが「クトゥルフ神話」という名称になったのは、本作の影響力の大きさを示す
ものである。この語を思い付いたのが誰なのか不明だが、この語が現在、ラヴクラフトの作品の代名詞として使用されるようになっている[注
1]。大瀧啓裕は、『クトゥルフの呼び声』『ダンウィッチの怪』『インスマウスの影』の3作品をダーレスによるクトゥルフ神話体系の中核と述べる[3]。
全集の翻訳を手掛けた宇野利泰は「クトゥルフ神話の出発点として、その大綱を知るに欠くべからざる作品」と解説する[4]。クトゥルフ神話内においては
「クトゥルフ物語」の代表作である[5][6]。正式掲載されたのはWT1928年2月号だが、その前に一度不採用になった経緯がある。前任者が売り上げ
減で解任されたこともありWT編集長がファーンズワース・ライトに代わってから、ラヴクラフトの作品はしばしば掲載を拒否されるようになったという。本作
が不採用になった事態を受けて、友人ドナルド・ワンドレイは、別の出版社に送ることを薦めた。このような経緯を経ているが、最終的にはWTに掲載されてい
る。[注
2]ラヴクラフト自身は、この作品を「そこそこの出来、自作のうち最上のものでも最低のものでもない」と評した[7]。同僚作家のロバート・E・ハワード
は、「人類史上に残る文学の金字塔であり、ラヴクラフトの傑作」と激賞している[8]。https://x.gd/UQCTA ++++++++++++++++++++++++ 私たちはみんな地衣類 - スコット・ギルバート、"We Are All Lichens Now" 考えなければならない。私たちは考えなければならない。 -ステンジャーズとデスプリ『騒ぐ女たち 西洋哲学や政治経済学の古くからの常識である、人間の例外主義や束縛された個人主義が、自然科学であれ社会科学であれ、最良の科学で考えられなくなったら どうなるだろうか?本当に考えられないとは、一緒に考えることができないということである。生物科学は、帝国主義化する18世紀以来、地球に住むすべての 人間に関する概念を発酵させるのに特に力を発揮してきた。ホモ・サピエンス(種としてのヒト、人類種としてのアントロポス、現代人)は、こうした知識実践 の主要な産物だった。21世紀の最良の生物学が、個体+コンテクスト、つまり生物+環境、あるいは遺伝子+必要な何であれ、もはや生物学的知の溢れんばか りの豊かさを維持することができなくなったら、どうなるのだろうか。西洋に恩義を感じている人々でさえ、もはや人間だけの歴史の中で自分自身を個人や個人 の社会として描くことができないのと同じ理由で、生物+環境がほとんど記憶されなくなったらどうなるのだろうか?確かに、このような地球上の変容の時を 「人新世」と名付けてはならない! 天空の神々の不実な子孫たちや、多種多様な泥沼の中で豊かな喜びを見出す私の同胞たちとともに、私はこの問題について批評的かつ喜びに満ちた大騒ぎをした い。そしてそのための唯一の方法は、喜びと恐怖と集団的思考を生み出すことだ。 この仕事における私の最初の悪魔は、カリフォルニア州北中央部にある私の住まいの近く、ソノマ郡とメンドシーノ郡のレッドウッド林の切り株の下に生息する クモ、ピモア・クトゥルフである。どこにでも住んでいる人はいない。すべてが何かにつながっている。このクモはその場所にいて、その場所を持っていて、そ れでいて他の場所を旅する興味をそそる名前がつけられている。このクモは私の帰還、そしてルーツとルートを助けてくれるだろう。私が訴える8本足の触手ク モは、ユタ州のゴシュート族の言語から一般的な名前をもらい、深淵の住人、深淵と元素の存在、クトニックと呼ばれるものから具体的な名前をもらっている。 天空の神々の代理人たちが組織を幽体離脱させ、シングルトン族長と、その手なずけられた委員会である多重神や亜神、「一」と「多」を設置しようと文明化し ようと努力しているにもかかわらず、テラのあらゆる場所にクトニックパワーが浸透している。生物学者の分類学的綴りを少し変えて、クトゥルフからクトゥ ルーとし、ピモア・クトゥルーと改名した。触手はラテン語で「感じる」を意味するtentaculumと、「感じる」「試す」を意味するtentareか ら来ていることを私は覚えている。クトゥルーセンの物語を語るには、無数の触手が必要だろう。 刺胞動物、クモ、人間やアライグマのような指先の器官、イカ、クラゲ、神経の贅肉、繊維状の存在、鞭毛状の存在、筋原線維の三つ編み、マット状やフェルト 状の微生物や真菌のもつれ、探検する匍匐茎、膨張する根、到達して登る蔓状のものなどである。触手はまた、網やネットワーク、雲を出入りする生き物でもあ る。触手とは、線に沿って--そして、点ではなく、球体でもなく、このような豊かな線に沿って--生きる生命のことである。「世界の住人、あらゆる種類の 生き物、人間も人間でないものも、旅人である。 その看板の下で行われる多くのジェネレーティブな仕事から栄養をもらっているにもかかわらず、触手的なひものようなものすべてが、私をポストヒューマニズ ムから遠ざけている。私のパートナーであるラステン・ホグネスは、ポストヒューマン(主義)の代わりにコンポスト(堆肥)を、また人文学の代わりに腐植学 を提案してくれた。腐葉土としての人間には可能性がある。ホモとしての人間、つまり自己を創造し、地球を破壊するCEOの解体プロジェクトを切り刻み、細 断することができれば。資本主義再構築大学における人文科学の未来」ではなく、「居住可能な多種多様な泥沼のための腐植の力」をテーマにした会議を想像し てみてほしい!エコセクシュアル・アーティストのベス・スティーブンスとアニー・スプリンクルは、私のために、私たちのために、SFのためにバンパー・ス テッカーを作った。 |
| 「私」フランシス・ウェイランド・サーストンは、1926年に急死した 古文碑文字の権威である大伯父エインジェル教授の遺品、研究文書を整理しているさい、『クトゥルフ教』なるものの研究記録を発見する。そこには怪物めいた 像と都市風景、そして謎の文字が浮き彫りにされた小さな粘土板も含まれており、それは、ウィルコックスなる若い彫刻家が、悪夢の中に見たものを写し取った ものであった。ウイルコックスはそれが太古のものだと信じたがために教授にその文字についての意見を聞きに来たのだったが、教授はそれを見て驚いた。なぜ なら、そこに彫られた怪物は17年前、ある学会の場で、ニューオーリンズの刑事が持ち込んできた謎の怪物像にそっくりだったからだ。それは悪辣な殺人カル トが謎の言葉を口にしながら崇めていた神像であったが、別の教授は48年前にグリーンランドで現地民が「同じ怪物像を同じ呪文で」祀っていたのを見たとい う。刑事が聴取したところによれば、謎の言葉は「死せるクトゥルフがルルイエの館で夢見ながら待っている」という意味で、クトゥルフとは太古に宇宙から来 た怪物であり、人類が生まれたときにはその都ともども海中に没していたが、いつか星座が元の位置に戻ると復活し、人類に災厄をもたらすのだという。のち彫 刻家ウィルコックスは3月23日に高熱を出し、またこの日、多くの狂気の発作めいた事件が世界中で起きていたことが教授の記録には記されていた。 合理主義者の「私」は半信半疑ながらも、大伯父はこれらの秘密を知ったがゆえに『クトゥルフ教』の信者たちに殺されたのではないかと、『クトゥルフ教』の 研究調査に乗り出す。そんなとき「私」はあの怪物像と同じ像がオーストラリアの新聞に載っているのを見る。それは南太平洋を漂流していた難破船アラート号 にあったもので、「私」が内密に入手したノルウェー人水夫ヨハンセンの手記によればこういうことであった。ヨハンセンの乗ったエンマ号は、南太平洋でア ラート号から「この先に進むな」と一方的な命令を受けたが、無視すると相手が砲撃してきたため、舷づけしての格闘後、凶暴な相手乗員を殺すことやむなきに 至り、沈むエンマ号からアラート号に乗り移った。そこで好奇心から「先」に進むと、海から出ている巨大な石造建築物を発見、上陸すると巨大な粘液まみれの 怪物が出現、生きて帰れたのはヨハンセンひとりだった。それは1925年3月23日のことで、のちその海域には何も発見されていない。 ヨハンセンもまた殺された疑いがあった。「私」は知り過ぎたゆえの身の危険を感じ、自分の遺言執行人にこの記録を発見したら処理してほしいと願う。 | 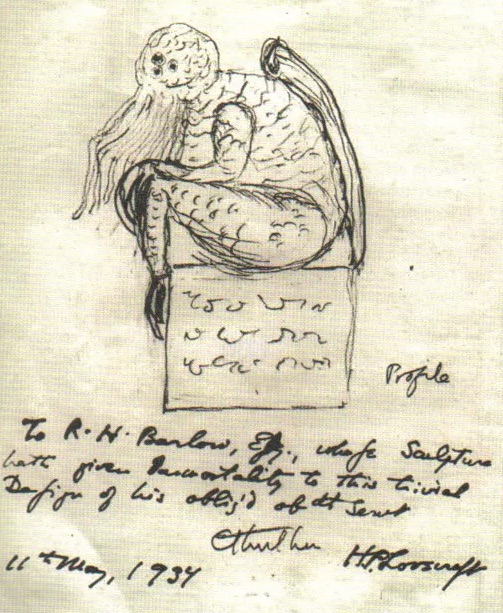 3章から成る。語り手の「私」が、エインジェル教授と船乗りヨハンセン
の記録を入手して謎を探究していく。短い作品であり、描写は梗概的であるが、のちのラヴクラフトにおけるクトゥルフ神話系統作品のパターンである、謎の祭
儀を行う教団、太古の人類外によって造られた古代都市遺跡の探検、そこでの怪物との遭遇、それら秘密を知ったゆえに命を狙われる展開などが、すでに示され
ている。エインジェル教授の残した遺品、全てに共通するのがCthulhuという発音すら定かでない固有名詞がほのめかされる点である。物語の全貌は、読
者が推理し、つなげていくことを求められるような文体になっている。実在する大学名や地名、ジェームズ・フレイザーの「金枝篇」などが登場するが解説がな
く読者自身の知識・教養を前提とする点も特色となっている。また冒頭でアルジャーノン・ブラックウッドの言葉が引用されている。 3章から成る。語り手の「私」が、エインジェル教授と船乗りヨハンセン
の記録を入手して謎を探究していく。短い作品であり、描写は梗概的であるが、のちのラヴクラフトにおけるクトゥルフ神話系統作品のパターンである、謎の祭
儀を行う教団、太古の人類外によって造られた古代都市遺跡の探検、そこでの怪物との遭遇、それら秘密を知ったゆえに命を狙われる展開などが、すでに示され
ている。エインジェル教授の残した遺品、全てに共通するのがCthulhuという発音すら定かでない固有名詞がほのめかされる点である。物語の全貌は、読
者が推理し、つなげていくことを求められるような文体になっている。実在する大学名や地名、ジェームズ・フレイザーの「金枝篇」などが登場するが解説がな
く読者自身の知識・教養を前提とする点も特色となっている。また冒頭でアルジャーノン・ブラックウッドの言葉が引用されている。 |
| 登場人物たち |
登場人物たち |
| フランシス・ウェイランド・サーストン(Francis
Wayland Thurston) |
「わたし」。ボストン在住。
最終的には死亡しており、この小説そのものが死後に発見された彼の手記という形式になっている。結末の時点で自らの命の危機を感じており、書き終えた後に
クトゥルフ教団に暗殺された可能性が高い。
名前は19世紀にブラウン大学の学長をしていたフランシス・ウェイランド(英語版)の名を引用していると考えられている[9]。また語り手である彼の名前
は、本編に登場せず、ウィアードテイルズ掲載時に副題として添えられていたものの、それ以降の発行物からは欠落していた期間がある[1]。後にアーカムハ
ウスの再出版になると再び加えられるようになった。日本語翻訳でも、当事情を見逃された『ラヴクラフト全集2巻』などの初期の翻訳では、この小説そのもの
が故人の手記である点が抜け落ちている。 |
| ジョージ・ギャマル・エインジェル教授(George
Gammell Angell) |
1926年に92歳で死去。ロード・アイランド州プロヴィデンスにある
ブラウン大学セム語族諸言語学科の名誉教授で、クトゥルフ教団について調べていた。
ニューポートで船から降りて帰宅途中、船員らしい風体の黒人がぶつかられたあと、突然倒れ死亡。医師たちは急な坂道を急足で登ったため、心臓に何らかの病
変が起こって死に至ったのだと結論付けた。 |
| ヘンリー・アンソニー・ウィルコックス(Henry Anthony
Wilcox) |
プロヴィデンス在住の青年彫刻家。古代都市の夢を見て、夢に現れた古代
文字を粘土板に再現し、エインジェル教授に解読を依頼する。悪夢を見なくなると、悪夢を見ていた期間の出来事や教授に依頼したという記憶を失う。 |
| ジョン・レイモンド・ルグラース警視正(John Raymond
Legrasse) |
ニューオーリンズの警官。1907年のある事件で、小さな石像を入手す
る。 |
| ウィリアム・チャニング・ウェブ教授(William
Channing Webb) |
プリンストン大学の教授。1860年にグリーンランドで奇怪な儀式と接
触し、1908年の学会でルグラース警部の持ち込んだ石像を見て解説する。 |
| グスタフ・ヨハンセン(Gustaf Johansen) |
ノルウェー人の船乗り。エンマ号11人で唯一の生存者。生還するも衰弱
し、後にオスロで謎の死を遂げる。11人の船員たちは、3人が狂信者の船との海戦で殺され、6人がルルイエで命を落とし、ヨハンセンと共に船で脱出したも
う1人も救出が来る前に力尽きた。 |
| アンゲコク(Angakoq) |
グリーンランドのイヌイットの呪術祭司。悪魔トルナスクに生贄を捧げ
る。 |
| カストロ(Castro) |
1907年の事件の逮捕者。メスティーソの老人。クトゥルフ教団の不死
の指導者と会ったと自称する。1926年時点ではすでに死去している。 |
| クトゥルフ(Cthulhu) |
エインジェル教授の論文に現れる邪神。信者は世界各地におり、グリーン
ランド、ニューオーリンズ、南太平洋で同一の神像が見つかっている。 |
| クトゥル
フの呼び声 (小説)--ウィキペディア日本語 |
|
| Shaping her thinking about the
times called Anthropocene and “multi-faced Gaïa” (Stengers’s term) in
companionable friction with Latour, Isabelle Stengers does not ask that
we recompose ourselves to become able, perhaps, to “face Gaïa.” But
like Latour and even more like Le Guin, one of her most generative SF
writers, Stengers is adamant about changing the story. Focusing on
intrusion rather than composition, Stengers calls Gaia a fearful and
devastating power that intrudes on our categories of thought, that
intrudes on thinking itself. Earth/Gaia is maker and destroyer, not
resource to be exploited or ward to be protected or nursing mother
promising nourishment. Gaia is not a person but complex systemic
phenomena that compose a living planet. Gaia’s intrusion into our
affairs is a radically materialist event that collects up multitudes.
This intrusion threatens not life on Earth itself — microbes will
adapt, to put it mildly — but threatens the livability of Earth for
vast kinds, species, assemblages, and individuals in an “event” already
under way called the Sixth Great Extinction. Stengers, like Bruno Latour, evokes the name of Gaia in the way James Lovelock and Lynn Margulis did, to name complex nonlinear couplings between processes that compose and sustain entwined but nonadditive subsystems as a partially cohering systemic whole. In this hypothesis, Gaia is autopoietic — self-forming, boundary maintaining, contingent, dynamic, and stable under some conditions but not others. Gaia is not reducible to the sum of its parts, but achieves finite systemic coherence in the face of perturbations within parameters that are themselves responsive to dynamic systemic processes. Gaia does not and could not care about human or other biological beings’ intentions or desires or needs, but Gaia puts into question our very existence, we who have provoked its brutal mutation that threatens both human and nonhuman livable presents and futures. Gaia is not about a list of questions waiting for rational policies; Gaia is an intrusive event that undoes thinking as usual. “She is what specifically questions the tales and refrains of modern history. There is only one real mystery at stake, here: it is the answer we, meaning those who belong to this history, may be able to create as we face the consequences of what we have provoked.”14 https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |
人新世と「多面的なガイア」(ステンガーズの用語)と呼ばれる時代につ
いて、ラトゥールとの友好的な摩擦の中で思考を形成しているイザベル・ステンガーズは、おそらく「ガイアと向き合う」ことができるようになるために、私た
ちが自分自身を再構成することを求めてはいない。しかし、ラトゥールのように、そしてSF作家のなかでも最も創造的な作家のひとりであるル=グウィンのよ
うに、ステンガーズは物語を変えることに固執する。構成よりも侵入に焦点を当て、ステンガーズはガイアを、私たちの思考のカテゴリーに侵入し、思考そのも
のに侵入する、恐ろしく破滅的な力と呼んでいる。地球/ガイアは創造者であり破壊者であり、搾取されるべき資源でも、保護されるべき被保護者でも、栄養を
約束する哺育母でもない。ガイアは人ではなく、生きている惑星を構成する複雑なシステム現象なのだ。ガイアが私たちの問題に介入してくるのは、根本的に唯
物論的な出来事であり、多くの人々を集めてしまう。この侵入は、地球上の生命そのものを脅かすものではなく、控えめに言っても微生物は適応するだろうが、
すでに進行中の「第6の大絶滅」と呼ばれる「出来事」において、膨大な種類、種、集合体、個体にとっての地球の住みやすさを脅かしている。 ステンガーズは、ブルーノ・ラトゥールのように、ジェームズ・ラブロックやリン・マーグリスが行ったように、ガイアの名を想起させる。それは、部分的にま とまったシステム全体として、絡み合いながらも非相加的なサブシステムを構成し、維持するプロセス間の複雑な非線形結合に名前をつけるためである。この仮 説では、ガイアはオートポイエティックであり、自己形成的で、境界を維持し、偶発的で、ダイナミックで、ある条件下では安定するが、他の条件下では安定し ない。ガイアは部分の総和には還元できないが、動的なシステム的プロセスに反応するパラメータの中で、摂動に直面して有限のシステム的一貫性を達成する。 ガイアは、人間や他の生物学的存在の意図や欲望やニーズを気にしないし、気にするはずもない。しかしガイアは、人間や人間以外の生物の住みやすい現在と未 来の両方を脅かす残忍な変異を引き起こした私たちの存在そのものに疑問を投げかけている。ガイアは、合理的な政策を待ち望む疑問の羅列ではない。ガイア は、通常の思考を覆す侵入的な出来事なのだ。「ガイアは、現代史の物語や教訓に疑問を投げかける存在なのだ。それは、私たち、つまりこの歴史に属する者た ちが、私たちが引き起こしたことの結果に直面する中で作り出せるかもしれない答えである。"14 |
| Anthropocene So, what have we provoked? Writing in the midst of California’s historic multiyear drought and the explosive fire season of 2015, I need the photograph of a fire set deliberately in June 2009 by Sustainable Resource Alberta near the Saskatchewan River Crossing on the Icefields Parkway in order to stem the spread of mountain pine beetles, to create a fire barrier to future fires, and to enhance biodiversity. The hope is that this fire acts as an ally for resurgence. The devastating spread of the pine beetle across the North American West is a major chapter of climate change in the Anthropocene. So too are the predicted megadroughts and the extreme and extended fire seasons. Fire in the North American West has a complicated multispecies history; fire is an essential element for ongoing, as well as an agent of double death, the killing of ongoingness. The material semiotics of fire in our times are at stake. Thus it is past time to turn directly to the time-space-global thing called Anthropocene. The term seems to have been coined in the early 1980s by University of Michigan ecologist Eugene Stoermer (d. 2012), an expert in freshwater diatoms. He introduced the term to refer to growing evidence for the transformative effects of human activities on the Earth. The name Anthropocene made a dramatic star appearance in globalizing discourses in 2000 when the Dutch Nobel Prize – winning atmospheric chemist Paul Crutzen joined Stoermer to propose that human activities had been of such a kind and magnitude as to merit the use of a new geological term for a new epoch, superseding the Holocene, which dated from the end of the last ice age, or the end of the Pleistocene, about twelve thousand years ago. Anthropogenic changes signaled by the mid-eighteenth-century steam engine and the planet-changing exploding use of coal were evident in the airs, waters, and rocks. Evidence was mounting that the acidification and warming of the oceans are rapidly decomposing coral reef ecosystems, resulting in huge ghostly white skeletons of bleached and dead or dying coral. That a symbiotic system — coral, with its watery world-making associations of cnidarians and zooanthellae with many other critters too — indicated such a global transformation will come back into our story. But for now, notice that the Anthropocene obtained purchase in popular and scientific discourse in the context of ubiquitous urgent efforts to find ways of talking about, theorizing, modeling, and managing a Big Thing called Globalization. Climate-change modeling is a powerful positive feedback loop provoking change-of-state in systems of political and ecological discourses. That Paul Crutzen was both a Nobel laureate and an atmospheric chemist mattered. By 2008, many scientists around the world had adopted the not-yet-official but increasingly indispensable term; and myriad research projects, performances, installations, and conferences in the arts, social sciences, and humanities found the term mandatory in their naming and thinking, not least for facing both accelerating extinctions across all biological taxa and also multispecies, including human, immiseration across the expanse of Terra. Fossil-burning human beings seem intent on making as many new fossils as possible as fast as possible. They will be read in the strata of the rocks on the land and under the waters by the geologists of the very near future, if not already. Perhaps, instead of the fiery forest, the icon for the Anthropocene should be Burning Man! https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |
アントロポセン では、私たちは何を引き起こしたのだろうか?カリフォルニアの歴史的な数年にわたる干ばつと2015年の爆発的な火災の季節の真っ只中に、私は2009年 6月にアイスフィールド・パークウェイのサスカチュワン・リバー・クロッシングの近くで、サステイナブル・リソース・アルバータ社がマウンテン・パイン・ ビートルの蔓延を食い止め、将来の火災に対する防火壁を作り、生物多様性を高めるために意図的に放った火災の写真を必要としている。この火災が復活のため の味方となることを期待している。北米西部におけるマツクイムシの壊滅的な蔓延は、人新世における気候変動の主要な章である。予測される巨大干ばつや極端 で長期化する火災シーズンも同様である。北アメリカ西部における火は、複雑な多種多様の歴史を持っている。火は、現在進行中のものにとって不可欠な要素で あると同時に、二重の死、つまり現在進行中のものを殺す作用がある。現代における火の物質的記号論は危機に瀕している。 こうして、アントロポセン(人新世)と呼ばれる時空間的・地球的なものに直接目を向けるべき時が来た。この言葉は1980年代初頭、ミシガン大学の生態学 者で淡水珪藻の専門家であるユージン・ストーマー(2012年没)によって作られたようだ。彼はこの言葉を、人間活動が地球に与える影響の大きさを示す証 拠の増加を意味する言葉として紹介した。2000年、ノーベル賞を受賞したオランダの大気化学者ポール・クルッツェンがストーマーと共同で、人間の活動 が、約1万2千年前の最後の氷河期の終わり、つまり更新世の終わりを意味する完新世に取って代わる、新しい地質学用語の使用に値するような種類と規模で あったことを提唱したとき、人新世という名称はグローバル化する言説の中で劇的なスターとして登場した。18世紀半ばの蒸気機関や、地球を一変させる石炭 の爆発的な使用によってもたらされた人為的な変化は、大気、水、岩石にはっきりと現れていた。海の酸性化と温暖化がサンゴ礁の生態系を急速に分解し、白化 したサンゴや死滅したサンゴの巨大な亡霊のような白い骸骨を生み出しているという証拠が次々と出てきた。共生システムであるサンゴが、刺胞動物や褐虫藻と 他の多くの生物たちとの水中世界を作る仲間であることが、このような世界的な変化を示していたことは、また後日お話することになるだろう。 しかし今のところ、人新世は、グローバリゼーションという「大きなもの」について語り、理論化し、モデル化し、管理する方法を見出そうとする、どこにでも ある緊急の努力の中で、一般の人々や科学者の言説の中で購入されたことに注目してほしい。気候変動モデリングは、政治的・生態学的言説のシステムにおい て、国家の変化を引き起こす強力な正のフィードバックループである。ポール・クルッツェンがノーベル賞受賞者であり、大気化学者であったことは重要であ る。また、芸術、社会科学、人文科学における無数の研究プロジェクト、パフォーマンス、インスタレーション、会議において、この用語が命名と思考において 必須であることがわかった。化石を燃やす人類は、できるだけ早く、できるだけ多くの新しい化石を作ることに躍起になっているようだ。すでにそうでないとし ても、ごく近い将来、地質学者たちは、陸上や水中の岩石の地層を読み解くだろう。おそらく、燃える森の代わりに、人新世のアイコンはバーニングマンである べきだろう! |
| The scale of burning ambitions
of fossil-making man — of this Anthropos whose hot projects for
accelerating extinctions merits a name for a geological epoch — is hard
to comprehend. Leaving aside all the other accelerating extractions of
minerals, plant and animal flesh, human homelands, and so on, surely,
we want to say, the pace of development of renewable energy
technologies and of political and technical carbon pollution-abatement
measures, in the face of palpable and costly ecosystem collapses and
spreading political disorders, will mitigate, if not eliminate, the
burden of planet-warming excess carbon from burning still more fossil
fuels. Or, maybe the financial troubles of the global coal and oil
industries by 2015 would stop the madness. Not so. Even casual
acquaintance with the daily news erodes such hopes, but the trouble is
worse than what even a close reader of IPCC documents and the press
will find. In “The Third Carbon Age,” Michael Klare, a professor of
Peace and World Security Studies at Hampshire College, lays out strong
evidence against the idea that the old age of coal, replaced by the
recent age of oil, will be replaced by the age of renewables. He
details the large and growing global national and corporate investments
in renewables; clearly, there are big profit and power advantages to be
had in this sector. And at the same time, every imaginable, and many
unimaginable, technologies and strategic measures are being pursued by
all the big global players to extract every last calorie of fossil
carbon, at whatever depth and in whatever formations of sand, mud, or
rock, and with whatever horrors of travel to distribution and use
points, to burn before someone else gets at that calorie and burns it
first in the great prick story of the first and the last beautiful
words and weapons. In what he calls the Age of Unconventional Oil and
Gas, hydrofracking is the tip of the (melting) iceberg. Melting of the
polar seas, terrible for polar bears and for coastal peoples, is very
good for big competitive military, exploration, drilling, and tanker
shipping across the northern passages. Who needs an ice-breaker when
you can count on melting ice? 22 A complex systems engineer named Brad Werner addressed a session at the meetings of the American Geophysical Union in San Francisco in 2012. His point was quite simple: scientifically speaking, global capitalism “has made the depletion of resources so rapid, convenient and barrier-free that ‘earth-human systems’ are becoming dangerously unstable in response.” Therefore, he argued, the only scientific thing to do is revolt! Movements, not just individuals, are critical. What is required is action and thinking that do not fit within the dominant capitalist culture; and, said Werner, this is a matter not of opinion, but of geophysical dynamics. The reporter who covered this session summed up Werner’s address: “He is saying that his research shows that our entire economic paradigm is a threat to ecological stability.” Werner is not the first or the last researcher and maker of matters of concern to argue this point, but his clarity at a scientific meeting is bracing. Revolt! Think we must; we must think. Actually think, not like Eichmann the Thoughtless. Of course, the devil is in the details — how to revolt? How to matter and not just want to matter? https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |
化石を作る人間、つまり絶滅を加速させる人類は、地質学的エポックと呼
ぶにふさわしいホットなプロジェクトを行っているが、その燃える野望の規模は理解しがたい。鉱物、動植物の肉、人間の土地など、加速度的に採掘されている
ものはさておき、再生可能エネルギー技術の開発ペースと、政治的・技術的な炭素汚染削減対策は、目に見えてコストのかかる生態系の崩壊や政治的な混乱の広
がりに直面しても、化石燃料のさらなる燃焼による地球温暖化の余剰炭素の負担は、解消されないまでも、軽減されるに違いない。あるいは、2015年までに
世界の石炭産業と石油産業が財政難に陥れば、狂気の沙汰は収まるかもしれない。そうではない。日々のニュースを何気なく見ているだけでも、そのような希望
は失われるが、IPCCの文書や報道をよく読んでも、問題はもっと深刻だ。ハンプシャー・カレッジの平和・世界安全保障研究教授であるマイケル・クレア
は、『第三の炭素時代』(原題:The Third Carbon
Age)の中で、石炭の時代から石油の時代に変わり、自然エネルギーの時代になるという考えに対する強力な証拠を示している。彼は、自然エネルギーへの大
規模かつ増大する世界的な国や企業の投資を詳述している。明らかに、この分野には大きな利益と電力のメリットがある。そして同時に、想像しうる限りの、そ
して想像もつかないような技術や戦略的手段が、あらゆるグローバルな大企業によって追求されている。彼の言う「非在来型石油・ガスの時代」において、ハイ
ドロフラッシュは氷山の一角である。極地の海が溶けることは、ホッキョクグマや沿岸の人々にとっては恐ろしいことだが、競争の激しい軍事、探査、掘削、北
方海峡を渡るタンカー輸送にとっては非常に良いことなのだ。溶けた氷を当てにできるのなら、誰が砕氷船を必要とするだろうか? 22 ブラッド・ワーナーという複雑系エンジニアが、2012年にサンフランシスコで開催されたアメリカ地球物理学連合の会議で講演した。彼の主張は非常にシン プルで、科学的に言えば、グローバル資本主義は「資源の枯渇を非常に迅速かつ便利で障壁のないものにしたため、"地球と人間のシステム "はそれに応じて危険なほど不安定になりつつある」というものだった。したがって、科学的になすべきことは反乱しかない、と彼は主張した!個人ではなく、 運動が重要である。必要なのは、支配的な資本主義文化に収まらない行動と思考であり、ヴェルナーは、これは意見の問題ではなく、地球物理学的力学の問題で あると述べた。このセッションを取材した記者は、ヴェルナーの演説を要約した: 「彼の研究は、我々の経済パラダイム全体が生態系の安定を脅かしていることを示している。ヴェルナーは、この点を主張する最初でも最後でもない研究者であ り、懸念事項のメーカーである。反乱!我々は考えなければならない。思考停止のアイヒマンのようにではなく、実際に考えよう。もちろん、悪魔は細部に宿 る。どうすれば、ただ重要でありたいと思うのではなく、重要なのだろうか? |
| Capitalocene But at least one thing is crystal clear. No matter how much he might be caught in the generic masculine universal and how much he only looks up, the Anthropos did not do this fracking thing and he should not name this double-death-loving epoch. The Anthropos is not Burning Man after all. But because the word is already well entrenched and seems less controversial to many important players compared to the Capitalocene, I know that we will continue to need the term “Anthropocene.” I will use it too, sparingly; what and whom the Anthropocene collects in its refurbished netbag might prove potent for living in the ruins and even for modest terran recuperation. Still, if we could only have one word for these SF times, surely it must be the Capitalocene. Species Man did not shape the conditions for the Third Carbon Age or the Nuclear Age. The story of Species Man as the agent of the Anthropocene is an almost laughable rerun of the great phallic humanizing and modernizing Adventure, where man, made in the image of a vanished god, takes on superpowers in his secular-sacred ascent, only to end in tragic detumescence, once again. Autopoietic, self-making man came down once again, this time in tragic system failure, turning biodiverse ecosystems into flipped-out deserts of slimy mats and stinging jellyfish. Neither did technological determinism produce the Third Carbon Age. Coal and the steam engine did not determine the story, and besides the dates are all wrong, not because one has to go back to the last ice age, but because one has to at least include the great market and commodity reworldings of the long sixteenth and seventeenth centuries of the current era, even if we think (wrongly) that we can remain Euro-centered in thinking about “globalizing” transformations shaping the Capitalocene. One must surely tell of the networks of sugar, precious metals, plantations, indigenous genocides, and slavery, with their labor innovations and relocations and recompositions of critters and things sweeping up both human and nonhuman workers of all kinds. The infectious industrial revolution of England mattered hugely, but it is only one player in planet-transforming, historically situated, new-enough, worlding relations. The relocation of peoples, plants, and animals; the leveling of vast forests; and the violent mining of metals preceded the steam engine; but that is not a warrant for wringing one’s hands about the perfidy of the Anthropos, or of Species Man, or of Man the Hunter. The systemic stories of the linked metabolisms, articulations, or coproductions (pick your metaphor) of economies and ecologies, of histories and human and nonhuman critters, must be relentlessly opportunistic and contingent. They must also be relentlessly relational, sympoietic, and consequential. They are terran, not cosmic or blissed or cursed into outer space. The Capitalocene is terran; it does not have to be the last biodiverse geological epoch that includes our species too. There are so many good stories yet to tell, so many netbags yet to string, and not just by human beings. As a provocation, let me summarize my objections to the Anthropocene as a tool, story, or epoch to think with: (1) The myth system associated with the Anthropos is a setup, and the stories end badly. More to the point, they end in double death; they are not about ongoingness. It is hard to tell a good story with such a bad actor. Bad actors need a story, but not the whole story. (2) Species Man does not make history. (3) Man plus Tool does not make history. That is the story of History human exceptionalists tell. (4) That History must give way to geostories, to Gaia stories, to symchthonic stories; terrans do webbed, braided, and tentacular living and dying in sympoietic multispecies string figures; they do not do History. (5) The human social apparatus of the Anthropocene tends to be top-heavy and bureaucracy prone. Revolt needs other forms of action and other stories for solace, inspiration, and effectiveness. (6) Despite its reliance on agile computer modeling and autopoietic systems theories, the Anthropocene relies too much on what should be an “unthinkable” theory of relations, namely the old one of bounded utilitarian individualism — preexisting units in competition relations that take up all the air in the atmosphere (except, apparently, carbon dioxide). (7) The sciences of the Anthropocene are too much contained within restrictive systems theories and within evolutionary theories called the Modern Synthesis, which for all their extraordinary importance have proven unable to think well about sympoiesis, symbiosis, symbiogenesis, development, webbed ecologies, and microbes. That’s a lot of trouble for adequate evolutionary theory. (8) Anthropocene is a term most easily meaningful and usable by intellectuals in wealthy classes and regions; it is not an idiomatic term for climate, weather, land, care of country, or much else in great swathes of the world, especially but not only among indigenous peoples. I am aligned with feminist environmentalist Eileen Crist when she writes against the managerial, technocratic, market-and-profit besotted, modernizing, and human-exceptionalist business-as-usual commitments of so much Anthropocene discourse. This discourse is not simply wrong-headed and wrong-hearted in itself; it also saps our capacity for imagining and caring for other worlds, both those that exist precariously now (including those called wilderness, for all the contaminated history of that term in racist settler colonialism) and those we need to bring into being in alliance with other critters, for still possible recuperating pasts, presents, and futures. “Scarcity’s deepening persistence, and the suffering it is auguring for all life, is an artifact of human exceptionalism at every level.” Instead, a humanity with more earthly integrity “invites the priority of our pulling back and scaling down, of welcoming limitationsof our numbers, economies, and habitats for the sake of a higher, more inclusive freedom and quality of life.” If Humans live in History and the Earthbound take up their task within the Anthropocene, too many Posthumans (and posthumanists, another gathering altogether) seem to have emigrated to the Anthropocene for my taste. Perhaps my human and nonhuman people are the dreadful Chthonic ones who snake within the tissues of Terrapolis. Note that insofar as the Capitalocene is told in the idiom of fundamentalist Marxism, with all its trappings of Modernity, Progress, and History, that term is subject to the same or fiercer criticisms. The stories of both the Anthropocene and the Capitalocene teeter constantly on the brink of becoming much Too Big. Marx did better than that, as did Darwin. We can inherit their bravery and capacity to tell big-enough stories without determinism, teleology, and plan. Historically situated relational worldings make a mockery both of the binary division of nature and society and of our enslavement to Progress and its evil twin, Modernization. The Capitalocene was relationally made, and not by a secular godlike anthropos, a law of history, the machine itself, or a demon called Modernity. The Capitalocene must be relationally unmade in order to compose in material-semiotic SF patterns and stories something more livable, something Ursula K. Le Guin could be proud of. Shocked anew by our — billions of Earth habitants’, including your and my — ongoing daily assent in practice to this thing called capitalism, Philippe Pignarre and Isabelle Stengers note that denunciation has been singularly ineffective, or capitalism would have long ago vanished from the Earth. A dark bewitched commitment to the lure of Progress (and its polar opposite) lashes us to endless infernal alternatives, as if we had no other ways to reworld, reimagine, relive, and reconnect with each other, in multispecies well-being. This explication does not excuse us from doing many important things better; quite the opposite. Pignarre and Stengers affirm on-the-ground collectives capable of inventing new practices of imagination, resistance, revolt, repair, and mourning, and of living and dying well. They remind us that the established disorder is not necessary; another world is not only urgently needed, it is possible, but not if we are ensorcelled in despair, cynicism, or optimism, and the belief/disbelief discourse of Progress. Many Marxist critical and cultural theorists, at their best, would agree. So would the tentacular ones. https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |
キャピタロセン しかし、少なくともはっきりしていることがある。どんなに一般的な男性的普遍性に囚われ、上ばかり見ていたとしても、アントロポスはこのフラッキングを やったわけではないし、この二重の死を愛するエポックに名前をつけるべきでもない。アントロポスはバーニングマンではない。しかし、この言葉はすでに定着 しており、キャピタロセン(資本新世)に比べれば、多くの重要人物にとって論争の余地が少ないように思える。人新世が何を、誰を、その改装されたネット バッグに集めるかは、廃墟の中で生きるために、そしてささやかなテランの復興のためにさえ、強力であることが証明されるかもしれない。 それでも、このSF的な時代を表す言葉がひとつだけあるとすれば、それはきっと「キャピタロセン(資本新世)」に違いない。 種人類は、第三次炭素時代や核時代の条件を形作ったわけではない。人間新世の代理人としての「種人間」の物語は、男根を人間化し近代化する大冒険のほとん ど笑い話のような再演であり、そこでは、消え去った神に似せて作られた人間が、世俗的で神聖な上昇の中で超大国を手に入れるが、悲劇的な終焉を迎えるだけ である。オートポイエティックに自己形成する人間は、今度は悲劇的なシステム不全に陥り、生物多様性の生態系をぬるぬるしたマットと刺すようなクラゲの砂 漠に変えてしまった。技術的決定論が第三次炭素時代を生み出したわけでもない。石炭と蒸気機関はこの物語を決定づけたわけではないし、その上、年代はすべ て間違っている。最終氷河期まで遡らなければならないからではなく、資本新世を形成する「グローバル化」の変容について考えるのにヨーロッパ中心のままで いられると(間違って)考えているとしても、少なくとも、現在の時代の長い16世紀と17世紀の大市場と商品の再世界化を含めなければならないからであ る。砂糖、貴金属、プランテーション、先住民の大量虐殺、奴隷制のネットワークは、労働革新と移転、生物と事物の再構成によって、あらゆる種類の人間と人 間以外の労働者を一網打尽にした。イギリスの感染産業革命は非常に重要であったが、それは地球を変革し、歴史的に位置づけられ、新しい十分な、世界化する 関係性のひとつのプレーヤーに過ぎない。蒸気機関に先立って、民族や動植物の移動、広大な森林の平地化、金属の乱暴な採掘が行われたが、だからといって、 人類や種人類、狩猟民族の背信行為に手を焼く理由にはならない。 経済と生態系、歴史と人間、そして人間以外の生き物の、代謝、連関、あるいは共同生産(比喩はお好みで)のシステマティックな物語は、容赦なく日和見的で 偶発的でなければならない。それらはまた、容赦なく関係的で、共感的で、結果的でなければならない。それらはテラン的なものであり、宇宙的なものでもなけ れば、宇宙空間に祝福されたり呪われたりするものでもない。キャピタロセンは地球的なものであり、私たちの種を含む最後の生物多様性のある地質学的エポッ クである必要はない。人類だけでなく、まだ語られていない物語、まだ結ばれていない網袋がたくさんあるのだ。 挑発の意味を込めて、人新世を考えるためのツール、物語、エポックとしての人新世に対する私の反論をまとめてみよう: (1) アントロポスにまつわる神話システムは仕組まれたもので、物語はひどい結末を迎える。もっと言えば、物語は二重の死で終わる。このような悪い役者を使って 良い物語を語るのは難しい。悪い役者にはストーリーは必要だが、物語全体は必要ない。 (2) 種の人間は歴史を作らない。 (3) 人間+道具は歴史を作らない。それは人間の例外主義者が語る歴史の物語である。 (4) その歴史は、地質学的な物語、ガイアの物語、シンキトニックな物語に道を譲らなければならない。テラ人は、網状、編組状、触手状の生と死をシンポイエ ティックな多種のひも状図形で行うが、彼らは歴史を行わない。 (5) 人新世の人間の社会機構は、頭でっかちで官僚主義になりがちである。反乱は、慰め、インスピレーション、有効性のために、他の行動形態や他の物語を必要と する。 (6) 俊敏なコンピュータ・モデリングとオートポイエティック・システム理論に依存しているにもかかわらず、人新世は「考えられない」はずの関係論、すなわち境 界功利主義的個人主義の古い理論に頼りすぎている。 (7) 人新世の科学は、制限的なシステム理論や現代総合と呼ばれる進化理論に収められすぎており、その並外れた重要性にもかかわらず、シンポイエーシス、共生、 共生発生、発生、網の目のような生態系、微生物についてうまく考えることができないことが証明されている。これは、適切な進化論にとっては非常に厄介なこ とである。 (8) 人新世という言葉は、裕福な階層や地域の知識人にとって最も意味がわかりやすく、使いやすい言葉であり、気候、天候、土地、国土、その他多くのことを表す 慣用的な言葉ではない。 フェミニスト環境保護主義者のアイリーン・クリストが、人新世の言説の多くに見られる、経営的、技術主義的、市場主義的、利益主義的、近代化主義的、そし て人間排他主義的なビジネス・アズ・ユージューアルへのコミットメントに反対しているとき、私は彼女に賛同する。このような言説は、単にそれ自体が誤った 考えや心得違いであるというだけでなく、現在不安定に存在する世界(人種差別的な入植者植民地主義において原生地域と呼ばれるこの言葉が汚染された歴史が あるにせよ、そのような世界も含む)や、他の生物と連携して、過去、現在、未来を回復する可能性のある世界を実現させる必要がある世界など、他の世界を想 像し、思いやる私たちの能力を奪っている。「欠乏が深まる一方であること、そして欠乏がすべての生命にもたらす苦しみは、あらゆるレベルにおける人間の例 外主義の産物である。その代わりに、より地球的な誠実さを持つ人類は、「より高い、より包括的な自由と生活の質のために、私たちの数、経済、生息地の制限 を歓迎し、後退し、縮小することの優先順位を誘う」。 人類が歴史の中に生き、地球人が人新世の中でその使命を果たすとすれば、ポスト・ヒューマン(そしてポスト・ヒューマニスト、これはまた別の集まりだが) は、私の好みからすると、人新世に移住した人が多すぎるように思える。おそらく、私の人間や非人間は、テラポリスの組織の中で蛇行する恐ろしいクト族のよ うなものなのだろう。 資本新世が原理主義的マルクス主義のイディオムで語られる限りにおいて、近代性、進歩、歴史といったあらゆる装いを持つこの用語は、同じかそれ以上に激し い批判にさらされることに注意されたい。人新世と資本新世の両方の物語は、あまりにも大きくなりすぎるという瀬戸際で常に揺れている。マルクスもダーウィ ンも、それよりはましだった。私たちは、決定論や目的論や計画なしに、十分に大きな物語を語る彼らの勇気と能力を受け継ぐことができる。 歴史的に位置づけられた関係的世界観は、自然と社会の二元的な区分と、進歩とその邪悪な双子である近代化への私たちの隷属の両方を嘲笑する。資本新世は関 係的に作られたのであり、世俗的な神のような人間や、歴史の法則や、機械そのものや、近代という悪魔によって作られたのではない。アーシュラ・K・ル=グ ウィンが誇りに思うような、より住みやすいものを物質記号論的なSFのパターンと物語で構成するためには、資本新世は関係的に解かれなければならない。 フィリップ・ピニャールとイザベル・ステンガーズは、資本主義と呼ばれるものに対して、私たち(あなたや私を含む何十億もの地球居住者)が日常的に同意し 続けていることにあらためて衝撃を受けた。進歩の誘惑(そしてその対極にあるもの)への暗い呪術的なコミットメントが、私たちを果てしない地獄のような選 択肢に縛り付ける。あたかも私たちには、多種多様な幸福の中で、再世界化し、再想像し、追体験し、互いにつながり直す方法が他にないかのように。この説明 は、私たちが多くの重要なことをよりよく行うことを免罪するものではない。ピニャーレとステンガーズは、想像力、抵抗、反乱、修復、弔い、そしてよく生 き、よく死ぬという新たな実践を発明することのできる、現場の集団性を肯定する。もうひとつの世界は緊急に必要なだけでなく、可能なのだ。しかし、絶望や 冷笑、楽観主義、進歩の信念/不信仰の言説に取り憑かれていては、そうはならない。多くのマルクス主義的な批評理論家、文化理論家も、その最良の点では同 意するだろう。触らぬ神に祟りなしである。 |
| Chthulucene Reaching back to generative complex systems approaches by Lovelock and Margulis, Gaia figures the Anthropocene for many contemporary Western thinkers. But an unfurling Gaia is better situated in the Chthulucene, an ongoing temporality that resists figuration and dating and demands myriad names. Arising from Chaos, Gaia was and is a powerful intrusive force, in no one’s pocket, no one’s hope for salvation, capable of provoking the late twentieth century’s best autopoietic complex systems thinking that led to recognizing the devastation caused by anthropogenic processes of the last few centuries, a necessary counter to the Euclidean figures and stories of Man. Brazilian anthropologists and philosophers Eduardo Viveiros de Castro and Déborah Danowski exorcise lingering notions that Gaia is confined to the ancient Greeks and subsequent Eurocultures in their refiguring the urgencies of our times in the post-Eurocentric conference “The Thousand Names of Gaia.” Names, not faces, not morphs of the same, something else, a thousand somethings else, still telling of linked ongoing generative and destructive worlding and reworlding in this age of the Earth. We need another figure, a thousand names of something else, to erupt out of the Anthropocene into another, big-enough story. Bitten in a California redwood forest by spidery Pimoa chthulhu, I want to propose snaky Medusa and the many unfinished worldings of her antecedents, affiliates, and descendants. Perhaps Medusa, the only mortal Gorgon, can bring us into the holobiomes of Terrapolis and heighten our chances for dashing the twenty-first-century ships of the Heroes on a living coral reef instead of allowing them to suck the last drop of fossil flesh out of dead rock. The terra-cotta figure of Potnia Theron, the Mistress of the Animals, depicts a winged goddess wearing a split skirt and touching a bird with each hand. She is a vivid reminder of the breadth, width, and temporal reach into pasts and futures of chthonic powers in Mediterranean and Near Eastern worlds and beyond. Potnia Theron is rooted in Minoan and then Mycenean cultures and infuses Greek stories of the Gorgons (especially the only mortal Gorgon, Medusa) and of Artemis. A kind of far-traveling Ur-Medusa, the Lady of the Beasts is a potent link between Crete and India. The winged figure is also called Potnia Melissa, Mistress of the Bees, draped with all their buzzing-stinging-honeyed gifts. Note the acoustic, tactile, and gustatory senses elicited by the Mistress and her sympoietic, more-than-human flesh. The snakes and bees are more like stinging tentacular feelers than like binocular eyes, although these critters see too, in compound-eyed insectile and many-armed optics. In many incarnations around the world, the winged bee goddesses are very old, and they are much needed now. Potnia Theron/Melissa’s snaky locks and Gorgon face tangle her with a diverse kinship of chthonic earthly forces that travel richly in space and time. The Greek word Gorgon translates as dreadful, but perhaps that is an astralized, patriarchal hearing of much more aweful stories and enactments of generation, destruction, and tenacious, ongoing terran finitude. Potnia Theron/Melissa/Medusa give faciality a profound makeover, and that is a blow to modern humanist (including technohumanist) figurations of the forward-looking, sky-gazing Anthropos. Recall that the Greek chthonios means “of, in, or under the Earth and the seas” — a rich terran muddle for SF, science fact, science fiction, speculative feminism, and speculative fabulation. The chthonic ones are precisely not sky gods, not a foundation for the Olympiad, not friends to the Anthropocene or Capitalocene, and definitely not finished. The Earthbound can take heart — as well as action. The Gorgons are powerful winged chthonic entities without a proper genealogy; their reach is lateral and tentacular; they have no settled lineage and no reliable kind (genre, gender), although they are figured and storied as female. In old versions, the Gorgons twine with the Erinyes (Furies), chthonic underworld powers who avenge crimes against the natural order. In the winged domains, the bird-bodied Harpies carry out these vital functions. Now, look again at the birds of Potnia Theron and ask what they do. Are the Harpies their cousins? Around 700 BCE Hesiod imagined the Gorgons as sea demons and gave them sea deities for parents. I read Hesiod’s Theogony as laboring to stabilize a very bumptious queer family. The Gorgons erupt more than emerge; they are intrusive in a sense akin to what Stengers understands by Gaia. The Gorgons turned men who looked into their living, venomous, snake-encrusted faces into stone. I wonder what might have happened if those men had known how to politely greet the dreadful chthonic ones. I wonder if such manners can still be learned, if there is time to learn now, or if the stratigraphy of the rocks will only register the ends and end of a stony Anthropos. Because the deities of the Olympiad identified her as a particularly dangerous enemy to the sky gods’ succession and authority, mortal Medusa is especially interesting for my efforts to propose the Chthulucene as one of the big-enough stories in the netbag for staying with the trouble of our ongoing epoch. I resignify and twist the stories, but no more than the Greeks themselves constantly did. The hero Perseus was dispatched to kill Medusa; and with the help of Athena, head-born favorite daughter of Zeus, he cut off the Gorgon’s head and gave it to his accomplice, this virgin goddess of wisdom and war. Putting Medusa’s severed head face-forward on her shield, the Aegis, Athena, as usual, played traitor to the Earthbound; we expect no better from motherless mind children. But great good came of this murder-for-hire, for from Medusa’s dead body came the winged horse Pegasus. Feminists have a special friendship with horses. Who says these stories do not still move us materially? And from the blood dripping from Medusa’s severed head came the rocky corals of the western seas, remembered today in the taxonomic names of the Gorgonians, the coral-like sea fans and sea whips, composed in symbioses of tentacular animal cnidarians and photosynthetic algal-like beings called zooanthellae. With the corals, we turn definitively away from heady facial representations, no matter how snaky. Even Potnia Theron, Potnia Melissa, and Medusa cannot alone spin out the needed tentacularities. In the tasks of thinking, figuring, and storytelling, the spider of my first pages, Pimoa chthulhu, allies with the decidedly nonvertebrate critters of the seas. Corals align with octopuses, squids, and cuttlefish. Octopuses are called spiders of the seas, not only for their tentacularity, but also for their predatory habits. The tentacular chthonic ones have to eat; they are at table, cum panis, companion species of terra. They are good figures for the luring, beckoning, gorgeous, finite, dangerous precarities of the Chthulucene. This Chthulucene is neither sacred nor secular; this earthly worlding is thoroughly terran, muddled, and mortal — and at stake now. Mobile, many-armed predators, pulsating through and over the coral reefs, octopuses are called spiders of the sea. And so Pimoa chthulhu and Octopus cyanea meet in the webbed tales of the Chthulucene. All of these stories are a lure to proposing the Chthulucene as a needed third story, a third netbag for collecting up what is crucial for ongoing, for staying with the trouble. The chthonic ones are not confined to a vanished past. They are a buzzing, stinging, sucking swarm now, and human beings are not in a separate compost pile. We are humus, not Homo, not anthropos; we are compost, not posthuman. As a suffix, the word kainos, “-cene,” signals new, recently made, fresh epochs of the thick present. To renew the biodiverse powers of terra is the sympoietic work and play of the Chthulucene. Specifically, unlike either the Anthropocene or the Capitalocene, the Chthulucene is made up of ongoing multispecies stories and practices of becoming-with in times that remain at stake, in precarious times, in which the world is not finished and the sky has not fallen — yet. We are at stake to each other. Unlike the dominant dramas of Anthropocene and Capitalocene discourse, human beings are not the only important actors in the Chthulucene, with all other beings able simply to react. The order is reknitted: human beings are with and of the Earth, and the biotic and abiotic powers of this Earth are the main story. However, the doings of situated, actual human beings matter. It matters with which ways of living and dying we cast our lot rather than others. It matters not just to human beings, but also to those many critters across taxa which and whom we have subjected to exterminations, extinctions, genocides, and prospects of futurelessness. Like it or not, we are in the string figure game of caring for and with precarious worldings made terribly more precarious by fossil-burning man making new fossils as rapidly as possible in orgies of the Anthropocene and Capitalocene. Diverse human and nonhuman players are necessary in every fiber of the tissues of the urgently needed Chthulucene story. The chief actors are not restricted to the too-big players in the too-big stories of Capitalism and the Anthropos, both of which invite odd apocalyptic panics and even odder disengaged denunciations rather than attentive practices of thought, love, rage, and care. Both the Anthropocene and the Capitalocene lend themselves too readily to cynicism, defeatism, and self-certain and self-fulfilling predictions, like the “game over, too late” discourse I hear all around me these days, in both expert and popular discourses, in which both technotheocratic geoengineering fixes and wallowing in despair seem to coinfect any possible common imagination. Encountering the sheer not-us, more-than-human worlding of the coral reefs, with their requirements for ongoing living and dying of their myriad critters, is also to encounter the knowledge that at least 250 million human beings today depend directly on the ongoing integrity of these holobiomes for their own ongoing living and dying well. Diverse corals and diverse people and peoples are at stake to and with each other. Flourishing will be cultivated as a multispecies response-ability without the arrogance of the sky gods and their minions, or else biodiverse terra will flip out into something very slimy, like any overstressed complex adaptive system at the end of its abilities to absorb insult after insult. Corals helped bring the Earthbound into consciousness of the Anthropocene in the first place. From the start, uses of the term Anthropocene emphasized human-induced warming and acidification of the oceans from fossil-fuel-generated CO2 emissions. Warming and acidification are known stressors that sicken and bleach coral reefs, killing the photosynthesizing zooanthellae and so ultimately their cnidarian symbionts and all of the other critters belonging to myriad taxa whose worlding depends on intact reef systems. Corals of the seas and lichens of the land also bring us into consciousness of the Capitalocene, in which deep-sea mining and drilling in oceans and fracking and pipeline construction across delicate lichen-covered northern landscapes are fundamental to accelerating nationalist, transnationalist, and corporate unworlding. But coral and lichen symbionts also bring us richly into the storied tissues of the thickly present Chthulucene, where it remains possible — just barely — to play a much better SF game, in nonarrogant collaboration with all those in the muddle. We are all lichens; so we can be scraped off the rocks by the Furies, who still erupt to avenge crimes against the Earth. Alternatively, we can join in the metabolic transformations between and among rocks and critters for living and dying well. “ ‘Do you realize,’ the phytolinguist will say to the aesthetic critic, ‘that [once upon a time] they couldn’t even read Eggplant?’ And they will smile at our ignorance, as they pick up their rucksacks and hike on up to read the newly deciphered lyrics of the lichen on the north face of Pike’s Peak.’ ” Attending to these ongoing matters returns me to the question that began this text. What happens when human exceptionalism and the utilitarian individualism of classical political economics become unthinkable in the best sciences across the disciplines and interdisciplines? Seriously unthinkable: not available to think with. Why is it that the epochal name of the Anthropos imposed itself at just the time when understandings and knowledge practices about and within symbiogenesis and sympoietics are wildly and wonderfully available and generative in all the humusities, including noncolonizing arts, sciences, and politics? What if the doleful doings of the Anthropocene and the unworldings of the Capitalocene are the last gasps of the sky gods, not guarantors of the finished future, game over? It matters which thoughts think thoughts. We must think! The unfinished Chthulucene must collect up the trash of the Anthropocene, the exterminism of the Capitalocene, and chipping and shredding and layering like a mad gardener, make a much hotter compost pile for still possible pasts, presents, and futures. https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |
クトゥルセン(クトゥルフ世) ラブロックやマーギュリスによる生成的複雑系アプローチにさかのぼると、ガイアは多くの現代西洋思想家にとって人新世の姿をしている。しかし、展開するガ イアは、形象化や年代測定に抵抗し、無数の名称を要求する現在進行形の時間性であるクトゥルーセンの中に、よりよく位置づけられる。カオスから発生したガ イアは、誰の懐にも入らず、誰の救済の望みもない、強力な侵入力であり、20世紀後半の最高のオートポイエティックな複雑系思考を刺激することができた。 それは、ここ数世紀の人為的プロセスによって引き起こされた荒廃を認識することにつながり、人間のユークリッド的な図形や物語に必要なカウンターとなっ た。ブラジルの人類学者であり哲学者でもあるエドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロとデボラ・ダノウスキーは、ポスト・ヨーロッパ中心主義会議 "The Thousand Names of Gaia "において、現代の緊急性を再認識する中で、ガイアは古代ギリシャ人やその後のヨーロッパ文化圏に限定されたものであるという長引く概念を払拭した。名 前、顔ではなく、同じものの変容でもなく、別の何か、別の千の何かが、地球のこの時代において進行中の生成と破壊の世界化と再世界化を物語っている。人新 世からもうひとつの大きな物語を紡ぎ出すために、私たちにはもうひとりの人物、千の別の何かの名前が必要なのだ。カリフォルニアのレッドウッドの森で、蜘 蛛のようなピモア・クトゥルフに噛まれた私は、蛇のようなメドゥーサと、彼女の先祖、関連会社、子孫の未完成の世界観を提案したい。おそらくメドゥーサ は、唯一の死すべきゴルゴンであり、我々をテラポリスのホロビオームに導き、21世紀の英雄たちの船を、死んだ岩から化石の肉を最後の一滴まで吸い取らせ る代わりに、生きたサンゴ礁に墜落させるチャンスを高めてくれるだろう。 テラコッタ製の「動物の女王」ポトニア・セロンのフィギュアは、スカートを分け、両手で鳥に触れる有翼の女神を描いている。彼女は、地中海と近東の世界、 そしてそれ以外の世界における、クトニック・パワーの過去と未来への広がり、幅、そして時間的な広がりを鮮やかに思い起こさせる存在である。ポトニア・セ ロンはミノア、そしてミケーネ文化に根ざし、ギリシャ神話のゴルゴン(特に唯一の死すべきゴルゴン、メドゥーサ)とアルテミスの物語を吹き込んでいる。遠 くを旅するウル・メドゥーサのようなもので、獣の女性はクレタとインドを結ぶ強力な存在である。この翼のある人物はまた、蜂の愛人ポトニア・メリッサとも 呼ばれ、蜂がブンブンと刺す蜂蜜のような贈り物をまとっている。愛人と彼女の共感的で人間以上の肉体によって引き出される音響、触覚、味覚に注目してほし い。蛇や蜂は双眼鏡の目というよりは、刺すような触覚のようだが、これらの生物も複眼の昆虫や多腕の光学系で見ている。 世界中の多くの化身において、翼を持つ蜂の女神は非常に古い存在であり、今大いに必要とされている。ポトニア・セロン/メリッサのいびつな髪とゴルゴンの 顔は、時空を豊かに旅するクトニックな大地の力の多様な親族と彼女を絡め取る。ギリシア語のゴルゴンは恐ろしいと訳されるが、おそらくそれは、生成、破 壊、そして粘り強い、現在進行形のテランの有限性についての、もっと恐ろしい物語や演出の、幽体離脱した家父長的な聞き取りなのだろう。ポトニア・セロン /メリッサ/メドゥーサは顔立ちに深遠な変身を与えるが、それは前向きで空を見つめるアントロポスという近代ヒューマニズム(テクノヒューマニズムを含 む)の造形に対する打撃である。ギリシャ語のchthoniosが「大地と海の、大地と海の中、大地と海の下」という意味であり、SF、サイエンス・ファ クト、サイエンス・フィクション、スペキュラティヴ・フェミニズム、スペキュラティヴ・ファブレーションにとって、豊かなテランの泥沼であることを思い出 してほしい。SF、サイエンス・ファクト、サイエンス・フィクション、スペキュラティヴ・フェミニズム、そしてスペキュラティヴ・ファブにとって、テラン は豊かな泥沼のような存在なのだ。地球人類は、行動と同様に、心も受け止めることができる。 ゴルゴンは、適切な系譜を持たない強力な翼を持つクトニックな存在であり、その到達範囲は横方向で触手状であり、定まった系譜もなく、信頼できる種類 (ジャンル、性別)もない。古いバージョンでは、ゴルゴンはエリニュス(フューリー)と結びついており、自然の摂理に反する犯罪を討つ神話的な冥界の力で ある。翼のある領域では、鳥の体をしたハーピーがこれらの重要な機能を担っている。さて、ポトニア・セロンの鳥をもう一度見て、彼らが何をしているのか尋 ねてみよう。ハーピーは彼らのいとこなのだろうか?前700年頃、ヘシオドスはゴルゴンを海の悪魔として想像し、海の神々を両親に与えた。私は、ヘシオド スの『神統記』を、非常に凸凹なクィア一族を安定させるための労作として読んでいる。ゴルゴンは出現するというより噴出する。ステンガーズがガイアを理解 するのと同じような意味で、彼らは侵入的だ。 ゴルゴンは、その生きた、毒蛇に包まれた顔を覗き込んだ男たちを石に変えた。もしその男たちが、恐ろしいチトニックに礼儀正しく挨拶する方法を知っていた らどうなっていただろう。そのような礼儀作法はまだ学べるのだろうか、今学ぶ時間があるのだろうか、それとも岩石の層序が石だらけのアントロポスの端と端 を記録するだけなのだろうか。 オリンピアードの神々は、彼女を天空の神々の継承と権威に対する特に危険な敵と見なしたので、死すべきメドゥーサは、現在進行中のエポックの問題に対処す るために、ネットバッグの中の大きな物語の一つとしてクトゥルーセンを提案する私の努力にとって、特に興味深い。私は、ギリシャ人自身が常に行っていた以 上に、物語を諦め、捻じ曲げてはいない。英雄ペルセウスはメドゥーサを殺すために派遣され、ゼウスの愛娘アテナの助けを借りてゴルゴンの首を切り落とし、 共犯者であるこの知恵と戦争の処女女神に与えた。メドゥーサの切断された頭を自分の盾であるイージスの上に前向きに置くと、アテナはいつものように地球人 に対する裏切り者を演じた。しかし、メデューサの死体からは翼のある馬ペガサスが生まれた。フェミニストは馬と特別な友情を持っている。このような物語が いまだに私たちを物質的に動かしていないと誰が言えるだろうか?そして、メデューサの切断された頭から滴り落ちる血から、西の海の岩サンゴが生まれた。今 日、ゴルゴニアンという分類名で記憶されている、サンゴに似たウミウチワやウミウチワは、触手を持つ動物の刺胞動物と、褐虫藻と呼ばれる光合成をする藻の ような生物との共生体である。 サンゴでは、どんなにいびつであっても、頭でっかちな顔の表現から決定的に遠ざかっている。ポトニア・セロン、ポトニア・メリッサ、メデューサでさえ、単 独では必要な触角を紡ぎ出すことはできない。考え、把握し、物語るという作業において、私の最初のページのクモ、ピモア・チュルフは、明らかに無脊椎動物 ではない海の生き物と同盟を組む。サンゴはタコ、イカ、コウイカと手を組む。タコはその触角だけでなく、捕食の習性から海のクモと呼ばれている。触角のあ るチトニックなものは食べなければならない。彼らは食卓につき、パニスと呼ばれ、テラの仲間である。彼らは、クトゥルーセンの誘い、手招き、華やかさ、有 限性、危険な不安定さを表現するのに適した存在なのだ。このChthuluceneは神聖でも世俗的でもない。この地上の世界観は、徹底的にテラ的であ り、混濁しており、死すべきものであり、今まさに危機に瀕している。 珊瑚礁の上を脈動しながら移動する多腕の捕食者であるタコは、海のクモと呼ばれている。ピモア・チュルフとオクトパス・シアネアは、クトゥルーセンの蜘蛛 の巣のような物語の中で出会う。 これらの物語はすべて、必要な第3の物語として、継続するために重要なものを収集するための第3の網袋として、トラブルと一緒にいるための第3の網袋とし て、クトゥルーシンを提案するための誘い水である。クトゥルーシンは消え去った過去に閉じこもるものではない。人類は別の堆肥の山ではない。私たちは腐植 であり、ホモではなく、アントロポスでもない。接尾辞として、カイノス(「-シーン」)という言葉は、新しい、最近作られた、厚い現在の新鮮なエポックを 示す。テラの生物多様性の力を更新することは、クトゥルーセンのシンポイエティックな仕事であり、遊びである。具体的には、人新世とも資本新世とも異な り、クトゥルーシーンは、世界はまだ完成しておらず、空もまだ落ちていない不安定な時代、危機に瀕したままの時代における、進行中の多種多様な物語と「共 になること」の実践から成り立っている。私たちは互いに危機に瀕している。人新世や資本新世の言説の支配的なドラマとは異なり、チュルチュルセンでは人間 だけが重要なアクターではなく、他のすべての存在は単に反応することしかできない。人間は地球とともにあり、地球のものであり、この地球の生物学的・生物 学的パワーが主な物語なのである。 しかし、実際に存在する人間の行動は重要である。どのような生き方や死に方をするのかが重要なのだ。それは人間だけでなく、私たちが絶滅、絶滅、大量殺 戮、そして未来なき未来へと追いやった、分類学上の多くの生物たちにとっても重要なことなのだ。好むと好まざるとにかかわらず、私たちは、化石を燃やす人 間が人新世と資本新世の乱痴気騒ぎで可能な限り急速に新たな化石を作り出したことで、不安定な世界観が恐ろしく不安定になり、それを気遣うという糸数ゲー ムの中にいるのだ。緊急に必要とされるチュルチュルーセンの物語を構成する組織のあらゆる部分に、人間と人間以外の多様なプレーヤーが必要である。その主 役は、「資本主義」と「人間新世」という大きすぎる物語の、大きすぎる主役に限定されるものではない。両者とも、思考、愛、怒り、気遣いの行き届いた実践 よりも、奇妙な終末的パニックや、さらに奇妙な無関心な非難を招いている。 人新世も資本新世も、シニシズムや敗北主義、そして自己確信的で自己成就的な予言に、あまりにも安易に身を貸している。最近、私の周りでよく耳にする 「ゲームオーバー、手遅れ」という言説のように、専門家も大衆の言説も、テクノテオクラテス的な地球工学的修正と絶望に打ちひしがれることの両方が、可能 な限りの共通の想像力を独占しているようだ。サンゴ礁の、私たちではない、人間以上の世界観に出会うことは、サンゴ礁に生息する無数の生物たちの継続的な 生と死への要求に出会うことであり、また、少なくとも2億5千万人の人類が今日、自らの継続的な生と死のために、これらのホロバイオームの継続的な完全性 に直接依存しているという知識に出会うことでもある。多様なサンゴと多様な人々や民族は、互いに、そして互いに危機に瀕している。繁栄は、天空の神々やそ の手先の傲慢さを排して、多種多様な対応能力として培われなければならない。さもなければ、生物多様性のあるテラは、侮辱に次ぐ侮辱を吸収する能力の限界 に達した、過度のストレスを受けた複雑な適応システムのように、非常にぬるぬるしたものに反転してしまうだろう。 そもそもサンゴは、地球人が人新世を意識するきっかけを作った。当初から、人新世という言葉は、化石燃料が生み出すCO2排出による人為的な海洋の温暖化 と酸性化を強調して使われてきた。温暖化と酸性化は、サンゴ礁を病気にし、白化させ、光合成を行う褐虫藻を死滅させ、その結果、刺胞動物の共生生物や、無 傷のサンゴ礁系に依存する無数の分類群に属する他のすべての生物を死滅させる、既知のストレス要因である。海のサンゴと陸の地衣類はまた、深海での採掘や 海洋掘削、繊細な地衣類に覆われた北部の景観での水圧破砕やパイプライン建設が、ナショナリスト、トランスナショナリスト、そして企業による非世界化を加 速させる基盤となっている資本新世を意識させる。 しかし、サンゴと地衣類の共生によって、私たちは厚く存在するクトゥルーセンの物語組織にも豊かに入り込むことができる。私たちは皆、地衣類なのだ。だか ら、地球に対する罪を討つために噴出するフューリーに岩から削り取られることもできる。あるいは、私たちは岩や生き物の間で、うまく生きたり死んだりする ための代謝変換に参加することもできる。植物言語学者が美学批評家に言うだろう、「(昔は)ナスの字も読めなかったのですよ」。そして彼らはリュックサッ クを背負い、パイクスピークの北壁の地衣類が新たに解読した歌詞を読むためにハイキングに出かける。 「このような現在進行形の問題に目を向けることで、 私はこの文章を始めたときの問いに立ち戻る。古典的な政治経済学の人間的例外主義や功利主義的個人主義が、学問分野や学際領域を超えて、最良の科学では考 えられなくなったらどうなるのだろうか?本気で考えられない:一緒に考えることができない。非植民地化的な芸術、科学、政治を含むすべての腐植質におい て、共生とシンポイエティックスに関する理解と知識実践が、荒々しくも素晴らしく利用可能であり、生成的であるときに、なぜアントロポスという画期的な名 前が自らに課されたのだろうか。もし、人新世の悲惨な行いや資本新世の不世出の行いが、空の神々の最後のあがきであって、完成された未来の保証人ではな く、ゲームオーバーだとしたら?どの思考が思考するかが重要なのだ。 私たちは考えなければならない! 未完成のクトゥルーセンは、人新世のゴミ、資本新世の絶滅主義を集め、狂った庭師のように切り刻み、細断し、重ね合わせ、まだ可能性のある過去、現在、未 来のために、もっと熱い堆肥の山を作らなければならない。 |
| Notes Scott Gilbert, “We Are All Lichens Now” →. See also Gilbert, Jan Sapp, and Alfred I. Tauber, “A Symbiotic View of Life: We Have Never Been Individuals,” Quarterly Review of Biology, vol. 87, no. 4 (December 2012): 325–41. Gilbert has erased the “now” from his rallying cry; we have always been symbionts—genetically, developmentally, anatomically, physiologically, neurologically, ecologically. These sentences are on the rear cover of Isabelle Stengers and Vincinae Despret, Women Who Make a Fuss:The Unfaithful Daughters of Virginia Woolf, trans. April Knutson (Minneapolis: Univocal, 2014). From Virginia Woolf’s Three Guineas, “think we must” is the urgency relayed to feminist collective thinking-with in Women Who Make a Fuss through María Puig de la Bellacasa, Penser nous devons: Politiques féminists et construction des saviors (Paris: Harmattan, 2013). Gustavo Hormiga, “A Revision and Cladistic Analysis of the Spider Family Pimoidae (Aranae: Araneae),” Smithsonian Contributions to Zoology 549 (1994): 1–104. See “Pimoa cthulhu,” Wikipedia; “Hormiga Laboratory” →. The brand of holist ecological philosophy that emphasizes that ‘everything is connected to everything,’ will not help us here. Rather, everything is connected to something, which is connected to something else. While we may all ultimately be connected to one another, the specificity and proximity of connections matters—who we are bound up with and in what ways. Life and death happen inside these relationships. And so, we need to understand how particular human communities, as well as those of other living beings, are entangled, and how these entanglements are implicated in the production of both extinctions and their accompanying patterns of amplified death.” Thom Van Dooren, Flight Ways: Life at the Edge of Extinction (New York: Columbia University Press, 2014), 60. Two indispensable books by my colleague-sibling from thirty-plus years in the History of Consciousness Department at the University of California, Santa Cruz, guide my writing: James Clifford, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997); and Clifford, Returns: Becoming Indigenous in the Twenty-First Century (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013). Chthonic” derives from ancient Greek khthonios, “of the earth,” and from khthōn, “earth.” Greek mythology depicts the chthonic as the underworld, beneath the Earth; but the chthonic ones are much older (and younger) than those Greeks. Sumeria is a riverine civilizational scene of emergence of great chthonic tales, including possibly the great circular snake eating its own tail, the polysemous Ouroboros (figure of the continuity of life, an Egyptian figure as early as 1600 BCE; Sumerian SF worlding dates to 3500 BCE or before). The chthonic will accrue many resonances throughout my text. See Thorkild Jacobsen, The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion (New Haven, CT: Yale University Press, 1976). In lectures, conversations, and e-mails, the scholar of ancient Middle Eastern worlds at UC Santa Cruz, Gildas Hamel, gave me “the abyssal and elemental forces before they were astralized by chief gods and their tame committees” (personal communication, June 12, 2014). Cthulu (note spelling), luxuriating in the science fiction of H. P. Lovecraft, plays no role for me, although it/he did play a role for Gustavo Hormiga, the scientist who named my spider demon familiar. For the monstrous male elder god (Cthulu), see Lovecraft, The Call of Cthulu. Eva Hayward proposes the term “tentacularity”; her trans-thinking and -doing in spidery and coralline worlds entwine with my writing in SF patterns. See Hayward, “FingeryEyes: Impressions of Cup Corals,” Cultural Anthropology, vol. 24, no. 4 (2010): 577–99; Hayward, “SpiderCitySex,” Women and Performance: A Journal of Feminist Theory, vol. 20, no. 3 (2010): 225–51; and Hayward, “Sensational Jellyfish: Aquarium Affects and the Matter of Immersion,” differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, vol. 23, no. 1 (2012): 161–96. See Eleanor Morgan, “Sticky Tales: Spiders, Silk, and Human Attachments,” Dandelion, vol. 2, no. 2 (2011) →. UK experimental artist Eleanor Morgan’s spider silk art spins many threads resonating with this chapter, tuned to the interactions of animals (especially arachnids and sponges) and humans. See Morgan’s website →. Tim Ingold, Lines, a Brief History (New York: Routledge, 2007), 116–19. The pile was made irresistible by María Puig de la Bellacasa, “Encountering Bioinfrastructure: Ecological Movements and the Sciences of Soil,” Social Epistemology vol. 28, no. 1 (2014): 26–40. Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes: Résister à la barbarie qui vient (Paris: Découverte), 2009. Gaia intrudes in this text from p. 48 on. Stengers discusses the “intrusion of Gaïa” in numerous interviews, essays, and lectures. Discomfort with the ever more inescapable label of the Anthropocene, in and out of sciences, politics, and culture, pervades Stengers’s thinking, as well as that of many other engaged writers, including Latour, even as we struggle for another word. See Stengers in conversation with Heather Davis and Etienne Turpin, “Matters of Cosmopolitics: On the Provocations of Gaïa,” in Architecture in the Anthropocene: Encounters among Design, Deep Time, Science and Philosophy, ed. Etienne Turpin (London: Open Humanities, 2013), 171–82. Scientists estimate that this extinction “event,” the first to occur during the time of our species, could, as previous great extinction events have, but much more rapidly, eliminate 50 to 95 percent of existing biodiversity. Sober estimates anticipate half of existing species of birds could disappear by 2100. By any measure, that is a lot of double death. For a popular exposition, see Voices for Biodiversity, “The Sixth Great Extinction” →. For a report by an award-winning science writer, see Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction: An Unnatural History (New York: Henry Holt, 2014). Reports from the Convention on Biological Diversity are more cautious about predictions and discuss the practical and theoretical difficulties of obtaining reliable knowledge, but they are not less sobering. For a disturbing report from summer 2015, see Geraldo Ceballos, Paul Ehrlich, Anthony Barnosky, Andres Garcia, Robert Pringle, and Todd Palmer, “Accelerated Modern Human-Induced Species Losses: Entering the Sixth Mass Extinction,” Science Advances vol. 1, no. 5 (June 19, 2015). Lovelock, “Gaia as Seen through the Atmosphere,” Atmospheric Environment, vol. 6, no. 8 (1967): 579–80; Lovelock and Margulis, “Atmospheric Homeostasis by and for the Biosphere: The Gaia Hypothesis,” Tellus, Series A (Stockholm: International Meteorological Institute) vol. 26, nos. 1–2 (February 1, 1974): 2–10 →. For a video of a lecture to employees at the National Aeronautic and Space Agency in 1984, go to →. Autopoiesis was crucial to Margulis’s transformative theory of symbiogenesis, but I think if she were alive to take up the question, Margulis would often prefer the terminology and figural-conceptual powers of sympoiesis. I suggest that Gaia is a system mistaken for autopoietic that is really sympoietic. Gaia’s story needs an intrusive makeover to knot with a host of other promising sympoietic tentacular ones for making rich compost, for going on. Gaia or Ge is much older and wilder than Hesiod (Greek poet around the time of Homer, circa 750 to 650 BCE), but Hesiod cleaned her/it up in the Theogony in his story-setting way: after Chaos, “wide-bosomed” Gaia (Earth) arose to be the everlasting seat of the immortals who possess Olympus above (Theogony, 116–18, trans. Glenn W. Most, Loeb Classical Library), and the depths of Tartarus below (Theogony, 119). The chthonic ones reply, Nonsense! Gaia is one of theirs, an ongoing tentacular threat to the astralized ones of the Olympiad, not their ground and foundation, with their ensuing generations of gods all arrayed in proper genealogies. Hesiod’s is the old prick tale, already setting up canons in the eighth century BCE. Although I cannot help but think more rational environmental and socialnatural policies of all sorts would help! Isabelle Stengers, from English compilation on Gaia sent by e-mail January 14, 2014. I use “thing” in two senses that rub against each other: (1) the collection of entities brought together in the Parliament of Things that Bruno Latour called our attention to, and (2) something hard to classify, unsortable, and probably with a bad smell. Latour, We Have Never Been Modern (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993). Paul Crutzen and Eugene Stoermer, “The ‘Anthropocene,’” Global Change Newsletter, International Geosphere-Biosphere Program Newsletter, no. 41 (May 2000): 17–18 →; Crutzen, “Geology of Mankind,” Nature 415 (2002): 23; Jan Zalasiewicz et al., “Are We Now Living in the Anthropocene?” GSA (Geophysical Society of America) Today vol. 18, no. 2 (2008): 4–8. Much earlier dates for the emergence of the Anthropocene are sometimes proposed, but most scientists and environmentalists tend to emphasize global anthropogenic effects from the late eighteenth century on. A more profound human exceptionalism (the deepest divide of nature and culture) accompanies proposals of the earliest dates, coextensive with Homo sapiens on the planet hunting big now-extinct prey and then inventing agriculture and domestication of animals. A compelling case for dating the Anthropocene from the multiple “great accelerations,” in Earth system indicators and in social change indicators, from about 1950 on, first marked by atmospheric nuclear bomb explosions, is made by Will Steffen, Wendy Broadgate, Lisa Deutsch, Owen Gaffney, and Cornelia Ludwig, “The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration,” The Anthropocene Review, January 16, 2015. Zalasiewicz et al. argue that adoption of the term “Anthropocene” as a geological epoch by the relevant national and international scientific bodies will turn on stratigraphic signatures. Perhaps, but the resonances of the Anthropocene are much more disseminated than that. One of my favorite art investigations of the stigmata of the Anthropocene is Ryan Dewey’s “Virtual Places: Core Logging the Anthropocene in Real-Time,” in which he composes “core samples of the ad hoc geology of retail shelves.” For a powerful ethnographic encounter in the 1990s with climate-change modeling, see Anna Lowenhaupt Tsing, “Natural Universals and the Global Scale,” ch. 3 in Friction: An Ethnography of Global Connection (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), 88–112, especially “Global Climate as a Model,” 101–6. Tsing asks, “What makes global knowledge possible?” She replies, “Erasing collaborations.” But Tsing does not stop with this historically situated critique. Instead she, like Latour and Stengers, takes us to the really important question: “Might it be possible to attend to nature’s collaborative origins without losing the advantages of its global reach?” (95). “How might scholars take on the challenge of freeing critical imaginations from the specter of neoliberal conquest—singular, universal, global? Attention to the frictions of contingent articulation can help us describe the effectiveness, and the fragility, of emergent capitalist—and globalist—forms. In this shifting heterogeneity there are new sources of hope, and, of course, new nightmares” (77). At her first climate-modeling conference in 1995, Tsing had an epiphany: “The global scale takes precedence—because it is the scale of the model” (103, italics in original). But this and related properties have a particular effect: they bring negotiators to an international, heterogeneous table, maybe not heterogeneous enough, but far from full of identical units and players. “The embedding of smaller scales into the global; the enlargement of models to include everything; the policy-driven construction of the models: Together these features make it possible for the models to bring diplomats to the negotiating table” (105). That is not to be despised. The Anthropocene Working Group, which was established in 2008 to report to the International Union of Geological Sciences and the International Commission on Stratigraphy on whether to name a new epoch in the geological timeline, aimed to issue its final report in 2016. See Newsletter of the Anthropocene Working Group, volume 4 (June 2013): 1–17 →; and volume 5 (September 2014): 1–19 →. For a photogallery of fiery images of the Man burning at the end of the festival, see “Burning Man Festival 2012: A Celebration of Art, Music, and Fire,” New York Daily News, September 3, 2012 →. Attended by tens of thousands of human people (and an unknown number of dogs), Burning Man is an annual week-long festival of art and (commercial) anarchism held in the Black Rock Desert of Nevada since 1990 and on San Francisco’s Baker Beach from 1986 to 1990. The event’s origins tie to San Francisco artists’ celebrations of the summer solstice. “The event is described as an experiment in community, art, radical self-expression, and radical self-reliance” (“Burning Man,” Wikipedia). The globalizing extravaganzas of the Anthropocene are not the drug- and art-laced worlding of Burning Man, but the iconography of the immense fiery “Man” ignited during the festival is irresistible. The first burning effigies on the beach in San Francisco were of a nine-foot-tall wooden Man and a smaller wooden dog. By 1988 the Man was forty feet tall and dogless. Relocated to a dry lakebed in Nevada, the Man topped out in 2011 at 104 feet. This is America; supersized is the name of the game, a fitting habitat for the Anthropos. See Klare, “The Third Carbon Age,” Huffington Post, August 8, 2013 →, in which he writes, “According to the International Energy Agency (IEA), an inter-governmental research organization based in Paris, cumulative worldwide investment in new fossil-fuel extraction and processing will total an estimated $22.87 trillion between 2012 and 2035, while investment in renewables, hydropower, and nuclear energy will amount to only $7.32 trillion.” Nuclear, after Fukushima! Not to mention that none of these calculations prioritize a much lighter, smaller, more modest human presence on Earth, with all its critters. Even in its “sustainability” discourses, the Capitalocene cannot tolerate a multispecies world of the Earthbound. For the switch in Big Energy’s growth strategies to nations with the weakest environmental controls, see Klare, “What’s Big Energy Smoking?” Common Dreams, May 27, 2014 →. See also Klare, The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources (New York: Picador, 2012). Heavy tar sand pollution must break the hearts and shatter the gills of every Terran, Gaian, and Earthbound critter. The toxic lakes of wastewater from tar sand oil extraction in northern Alberta, Canada, shape a kind of new Great Lakes region, with more giant “ponds” added daily. Current area covered by these lakes is about 50 percent greater than the area covered by the world city of Vancouver. Tar sands operations return almost none of the vast quantities of water they use to natural cycles. Earthbound peoples trying to establish growing things at the edges of these alarmingly colored waters filled with extraction tailings say that successional processes for reestablishing sympoietic biodiverse ecosystems, if they prove possible at all, will be an affair of decades and centuries. See Pembina Institute, “Alberta’s Oil Sands” →; and Bob Weber, “Rebuilding Land Destroyed by Oil Sands May Not Restore It,” Globe and Mail, March 11, 2012 →. Only Venezuela and Saudi Arabia have more oil reserves than Alberta. All that said, the Earthbound, the Terrans, do not cede either the present or the future; the sky is lowering, but has not yet fallen, yet. Pembina Institute, “Oil Sands Solutions” →. First Nation, Métis, and Aboriginal peoples are crucial players in every aspect of this unfinished story. Photograph from NASA Earth Observatory, 2015 (public domain). If flame is the icon for the Anthropocene, I use the missing ice and the unblocked Northwest Passage to figure the Capitalocene. The Soufan Group provides strategic security intelligence services to governments and multinational organizations. Its report “TSG IntelBrief: Geostrategic Competition in the Arctic” includes the following quotes: “The Guardian estimates that the Arctic contains 30 percent of the world’s undiscovered natural gas and 15 percent of its oil.” “In late February, Russia announced it would form a strategic military command to protect its Arctic interests.” “Russia, Canada, Norway, Denmark, and the US all make some claim to international waters and the continental shelf in the Arctic Ocean.” “(A Northwest Passage) route could provide the Russians with a great deal of leverage on the international stage over China or any other nation dependent on sea commerce between Asia and Europe.” Naomi Klein, “How Science Is Telling Us All to Revolt,” New Statesman, October 29, 2013 →; Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (New York: Macmillan/Picador, 2008). “Capitalocene”is one of those words like“sympoiesis”; if you think you invented it, justlook around and notice how many other people are inventing the term at the same time. That certainly happened to me, and after I got over a small fit of individualist pique at being asked whom I got the term “Capitalocene” from—hadn’t I coined the word? (“Coin”!) And why do other scholars almost always ask women which male writers their ideas are indebted to?—I recognized that not only was I part of a cat’s cradle game of invention, as always, but that Jason Moore had already written compelling arguments to think with, and my interlocutor both knew Moore’s work and was relaying it to me. Moore himself first heard the term “Capitalocene” in 2009 in a seminar in Lund, Sweden, when then graduate student Andreas Malm proposed it. In an urgent historical conjuncture, words-to-think-with pop out all at once from many bubbling cauldrons because we all feel the need for better netbags to collect up the stuff crying out for attention. Despite its problems, the term “Anthropocene” was and is embraced because it collects up many matters of fact, concern, and care; and I hope “Capitalocene” will roll off myriad tongues soon. To get over Eurocentrism while thinking about the history of pathways and centers of globalization over the last few centuries, see Dennis O. Flynn and Arturo Giráldez, China and the Birth of Globalisation in the 16th Century (Farnum, UK: Ashgate Variorium, 2012). For analysis attentive to the differencesand frictions among colonialisms, imperialisms, globalizing trade formations, and capitalism, see Engseng Ho, “Empire through Diasporic Eyes: A View from the Other Boat,” Society for Comparative Study of Society and History (April 2004): 210–46; and Ho, The Graves of Tarem: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean (Berkeley: University of California Press, 2006). In “Anthropocene or Capitalocene, Part III,” May 19, 2013 →, Jason Moore puts it this way: “This means that capital and power—and countless other strategic relations—do not act upon nature but develop through the web of life. ‘Nature’ is here offered as the relation of the whole. Humans live as a specifically endowed (but not special) environment-making species within Nature. Second, capitalism in 1800 was no Athena, bursting forth, fully grown and armed, from the head of a carboniferous Zeus. Civilizations do not form through Big Bang events. They emerge through cascading transformations and bifurcations of human activity in the web of life … the long seventeenth century forest clearances of the Vistula Basin and Brazil’s Atlantic Rainforest occurred on a scale, and at a speed, between five and ten times greater than anything seen in medieval Europe.” Crist, “On the Poverty of Our Nomenclature,” Environmental Humanities 3 (2013): 129–47; 144. Crist does superb critique of the traps of Anthropocene discourse, as well as gives us propositions for more imaginative worlding and ways to stay with the trouble. For entangled, dissenting papers that both refuse and take up the name Anthropocene, see videos from the conference “Anthropocene Feminism,” University of Wisconsin–Milwaukee, April 10–12, 2014 →. For rich interdisciplinary research, organized by Anna Tsing and Nils Ole Bubandt, that brings together anthropologists, biologists, and artists under the sign of the Anthropocene, see AURA: Aarhus University Research on the Anthropocene →. I owe the insistence on “big-enough stories” to Clifford, Returns: “I think of these as ‘big enough’ histories, able to account for a lot, but not for everything—and without guarantees of political virtue” (201). Rejecting one big synthetic account or theory, Clifford works to craft a realism that “works with open-ended (because their linear historical time is ontologically unfinished) ‘big-enough stories,’ sites of contact, struggle, and dialogue” (85–86). Philippe Pignarre and Isabelle Stengers, La sorcellerie capitaliste: Pratiques de désenvoûtement (Paris: Découverte, 2005). Latour and Stengers are deeply allied in their fierce rejection of discourses of denunciation. They have both patiently taught me to understand and relearn in this matter. I love a good denunciation! It is a hard habit to unlearn. It is possible to read Max Horkheimer and Theodor Adorno’s Dialectic of Enlightenment as an allied critique of Progress and Modernization, even though theirresolute secularism gets in their own way. It is very hard for a secularist to really listen to the squid, bacteria, and angry old women of Terra/Gaia. The most likely Western Marxist allies, besides Marx, for nurturing the Chthulucene in the belly of the Capitalocene are Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, and Stuart Hall. Hall’s immensely generative essays extend from the 1960s through the 1990s. See, for example, Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies, eds. David Morley and Kuan-Hsing Chen (London: Routledge, 1996). See Dave Gilson, “Octopi Wall Street!” Mother Jones, October 6, 2011 →, for the fascinating history of cephalopods figuring the depredations of Big Capital in the United States (for example, the early twentieth-century John D. Rockefeller/Standard Oil octopus strangling workers, farmers, and citizens in general with its many huge tentacles). Resignification of octopuses and squids as chthonic allies is excellent news. May they squirt inky night into the visualizing apparatuses of the technoid sky gods. Hesiod’s Theogony in achingly beautiful language tells of Gaia/Earth arising out of Chaos to be the seat of the Olympian immortals above and of Tartarus in the depths below. She/it is very old and polymorphic and exceeds Greek tellings, but just how remains controversial and speculative. At the very least, Gaia is not restricted to the job of holding up the Olympians! The important and unorthodox scholar-archaeologist Marija Gimbutis claims that Gaia as Mother Earth is a later form of a pre–Indo-European, Neolithic Great Mother. In 2004, filmmaker Donna Reed and neopagan author and activist Starhawk released a collaborative documentary film about the life and work of Gimbutas, Signs out of Time. See Belili Productions, “About Signs out of Time” →; Gimbutas, The Living Goddesses,ed. Miriam Robbins Dexter (Berkeley: University of California Press, 1999). To understand what is at stake in “non-Euclidean” storytelling, go to Le Guin, Always Coming Home (Berkeley: University of California Press, 1985);and Le Guin, “A Non-Euclidean View of California as a Cold Placeto Be,” in Dancing at the Edge of the World: Thoughts on Words, Women, Places (New York: Grove, 1989), 80–100. “The Thousand Names of Gaia: From the Anthropocene to the Age of the Earth,” International Colloquium, Rio de Janeiro, September 15–19, 2014. The bee was one of Potnia Theron’s emblems, and she is also called Potnia Melissa, Mistress of the Bees. Modern Wiccans remember these chthonic beings in ritual and poetry. If fire figured the Anthropocene, and ice marked the Capitalocene, it pleases me to use red clay pottery for the Chthulucene, a time of fire, water, and Earth, tuned to the touch of its critters, including its people. With her PhD writing on the riverine goddess Ratu Kidul and her dances now performed on Bali, Raissa DeSmet (Trumbull) introduced me to the web of far-traveling chthonic tentacular ones emerging from the Hindu serpentine Nagas and moving through the waters of Southeast Asia. DeSmet, “A Liquid World: Figuring Coloniality in the Indies,” PhD diss., History of Consciousness Department, University of California at Santa Cruz, 2013. Links between Potnia Theron and the Gorgon/Medusa continued in temple architecture and building adornment well after 600 BCE, giving evidence of the tenacious hold of the chthonic powers in practice, imagination, and ritual, for example, from the fifth through the third centuries BCE on the Italian peninsula. The dread-full Gorgon figure faces outward, defending against exterior dangers, and the no less awe-full Potnia Theron faces inward, nurturing the webs of living. See Kimberly Sue Busby, “The Temple Terracottas of Etruscan Orvieto: A Vision of the Underworld in the Art and Cult of Ancient Volsinii,” PhD diss., University of Illinois, 2007. The Christian Mary, Virgin Mother of God, who herself erupted in the Near East and Mediterranean worlds, took on attributes of these and other chthonic powers in her travels around the world. Unfortunately, Mary’s iconography shows her ringed by stars and crushing the head of the snake (for example, in the Miraculous Medal dating from an early nineteenth-century apparition of the Virgin), more than allying herself with Earth powers. The “lady surrounded by stars” is a Christian scriptural apocalyptic figure for the end of time. That is a bad idea. Throughout my childhood, I wore a gold chain with the Miraculous Medal. Finally and luckily, it was her residual chthonic infections that took hold in me, turning me from both the secular and also the sacred, and toward humus and compost. The Hebrew word Deborah means “bee,” and she was the only female judge mentioned in the Bible. She was a warrior and counselor in premonarchic Israel. The Song of Deborah may date to the twelfth centuryBCE. Deborah was a military heroand ally of Jael, one of the 4Js in Joanna Russ’s formative feminist science fiction novel The Female Man. “Erinyes 1,” Theoi Greek Mythology → Martha Kenney pointed out to me that the story of the Ood, in the long-running British science fiction TV series Doctor Who, shows how the squid-faced ones became deadly to humanity only after they were mutilated, cut off from their symchthonic hive mind, and enslaved. The humanoid empathic Ood have sinuous tentacles over the lower portion of their multifolded alien faces; and in their proper bodies they carry their hindbrains in their hands, communicating with each other telepathically through these vulnerable, living, exterior organs (organons). Humans (definitely not the Earthbound) cut off the hindbrains and replaced them with a technological communication-translator sphere, so that the isolated Ood could only communicate through their enslavers, who forced them into hostilities. I resist thinking the Ood techno-communicators are a future release of the iPhone, but it is tempting when I watch the faces of twenty-first-century humans on the streets, or even at the dinner table, apparently connected only to their devices. I am saved from this ungenerous fantasy by the SF fact that in the episode “Planet of the Ood,” the tentacular ones were freed by the actions of Ood Sigma and restored to their nonsingular selves. Doctor Who is a much better story cycle for going-on-with than Star Trek. “Medousa and Gorgones,” Theoi Greek Mythology → Suzy McKee Charnas’s Holdfast Chronicles, beginning in 1974 with Walk to the End of the World, is greatSFfor thinking about feminists and their horses. The sex isexciting if very incorrect, and the politics are bracing. Eva Hayward first drew my attention to the emergence of Pegasus from Medusa’s body and of coral from drops of her blood. In her “The Crochet Coral Reef Project Heightens Our Sense of Responsibility to the Oceans,” Independent Weekly, August 1, 2012,” she writes: “If coral teaches us about the reciprocal nature of life, then how do we stay obligated to environments—many of which we made unlivable—that now sicken us? … Perhaps Earth will follow Venus, becoming uninhabitable due to rampaging greenhouse effect. Or, maybe, we will rebuild reefs or construct alternate homes for the oceans’ refugees. Whatever the conditions of our future, we remain obligate partners with oceans.” See Margaret Wertheim and Christine Wertheim, Crochet Coral Reef: A Project by the Institute for Figuring (Los Angeles: IFF, 2015). I am inspired by the 2014–15 Monterey Bay Aquarium exhibition Tentacles: The Astounding Lives of Octopuses, Squids, and Cuttlefish. See Marcel Detienne and Jean-Pierre Vernant, Cunning Intelligence in Greek Culture and Society, trans. Janet Lloyd (Brighton, UK: Harvester Press, 1978), with thanks to Chris Connery for this reference in which cuttlefish, octopuses, and squid play a large role. Polymorphy, the capacity to make a net or mesh of bonds, and cunning intelligence are the traits the Greek writers foregrounded. “Cuttlefish and octopuses are pure áporai and the impenetrable pathless night they secrete is the most perfect image of their metis” (38). Chapter 5, “The Orphic Metis and the Cuttle-Fish of Thetis,” is the most interesting for the Chthulucene’s own themes of ongoing looping, becoming-with, and polymorphism. “The suppleness of molluscs, which appear as a mass of tentacles (polúplokoi), makes their bodies an interlaced network, a living knot of mobile animated bonds” (159). For Detienne and Vernant’s Greeks, the polymorphic and supple cuttlefish are close to the primordial multisexual deities of the sea—ambiguous, mobile, and ever changing, sinuous and undulating, presiding over coming-to-be, pulsating with waves of intense color, cryptic, secreting clouds of darkness, adept at getting out of difficulties, and having tentacles where proper men would have beards. See Donna Haraway and Martha Kenney, “Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene,” interview for Art in the Anthropocene: Encounters among Aesthetics, Politics, Environment, and Epistemology, ed. Heather Davis and Etienne Turpin (Open Humanities Press, Critical Climate Change series, 2015) → Le Guin, “‘The Author of Acacia Seeds’ and Other Extracts from the Journal of the Association of Theolinguistics,” in Buffalo Gals and Other Animal Presences (New York: New American Library, 1988), 175. |
ノート=注記(番号をまだ振っていない) Scott Gilbert, "We Are All Lichens Now" →. Gilbert, Jan Sapp, and Alfred I. Tauber, "A Symbiotic View of Life: 私たちは決して個体ではなかった」Quarterly Review of Biology, vol. 87, no. 4 (December 2012): 325-41. ギルバートは彼の叫びから "今 "を消し去った。我々は常に共生者であった-遺伝学的に、発生学的に、解剖学的に、生理学的に、神経学的に、生態学的に。 これらの文章は、イザベル・ステンジャーズとヴィンシーネ・デスプレ『騒ぐ女たち:ヴァージニア・ウルフの不実な娘たち』(訳、ミネアポリス)の裏表紙に 書かれている。April Knutson (Minneapolis: Univocal, 2014)。ヴァージニア・ウルフの『スリー・ギニー』から、"think we must "はフェミニストの集団的思考に伝えられた緊急性である: Politiques féminists et construction des saviors (Paris: Harmattan, 2013). Gustavo Hormiga, "A Revision and Cladistic Analysis of the Spider Family Pimoidae (Aranae: Araneae)," Smithsonian Contributions to Zoology 549 (1994): 1-104. Wikipedia "Pimoa cthulhu"; "Hormiga Laboratory" →参照。 すべてのものはすべてのものとつながっている」と強調するホリスト・エコロジーの哲学は、ここでは役に立たない。むしろ、すべては何かとつながっており、 それはまた何かとつながっている。私たちは皆、最終的には互いにつながっているのかもしれないが、そのつながりの具体性と近さが重要なのである。生と死は これらの関係の中で起こる。そして、他の生き物と同様に、特定の人間のコミュニティがどのように絡み合っているのか、また、このような絡み合いが、絶滅と それに伴う死の増幅パターンの両方の生成にどのように関与しているのかを理解する必要がある」。Thom Van Dooren, Flight Ways: Life at the Edge of Extinction (New York: Columbia University Press, 2014), 60. カリフォルニア大学サンタクルーズ校の意識史学科に30年以上在籍していた頃の同僚である兄弟による、私の執筆に欠かせない2冊の本は、私の執筆の指針と なっている: ジェイムズ・クリフォード『Routes』: James Clifford, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997); and Clifford, Returns: 20世紀における先住民になること』(マサチューセッツ州ケンブリッジ:ハーバード大学出版、2013年)。 Chthonic」とは、古代ギリシャ語のkhthonios「大地の」とkhthōn「大地」に由来する。ギリシャ神話では、クトニックは地球の下にあ る冥界として描かれているが、クトニックはそのギリシャ人よりずっと古い(そして若い)。シュメリアは、おそらく自分の尾を食べる円形の大蛇、多義的なウ ロボロス(生命の連続性の象徴、紀元前1600年頃のエジプトの人物、シュメールのSF的世界観は紀元前3500年かそれ以前のもの)を含む、偉大な神話 が出現した河川文明の舞台である。シュメールSFの世界観は紀元前3500年以前のものである。Thorkild Jacobsen, The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion (New Haven, CT: Yale University Press, 1976)を参照。カリフォルニア大学サンタクルーズ校の古代中東世界の研究者、ギルダス・ハメルは、講義、会話、電子メールの中で、私に「主神とその飼 いならされた委員会によって幽体化される前の深淵と元素の力」を与えてくれた(私信、2014年6月12日)。H.P.ラヴクラフトのSFに登場するク トゥルー(スペルに注意)は、私にとっては何の役にも立たない。怪物のような男性の長老神(クトゥルー)については、ラヴクラフトの『クトゥルーの呼び 声』を参照のこと。 エヴァ・ヘイワードは "tentacularity"(触手性)という言葉を提唱している。蜘蛛や珊瑚のような世界での彼女のトランス思考と行動は、SFのパターンで私の文章 と絡み合っている。ヘイワード、"FingeryEyes: Impressions of Cup Corals," Cultural Anthropology, vol. 24, no. 4 (2010): 577-99; Hayward, "SpiderCitySex," Women and Performance: A Journal of Feminist Theory, vol. 20, no. 3 (2010): 225-51; and Hayward, "Sensational Jellyfish: 水族館の情緒と没入の問題」(Hayward, "Sensational Jellyfish: Aquarium Affects and the Matter of Immersion," differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, vol. 23, no. 1 (2012): 161-96. Eleanor Morgan, "Sticky Tales: Spiders, Silk, and Human Attachments," Dandelion, vol. 2, no. 2 (2011) →を参照。英国の実験的アーティスト、エレノア・モーガンのクモの糸アートは、動物(特にクモ類と海綿動物)と人間の相互作用に同調し、本章と共鳴する多 くの糸を紡いでいる。モーガンのウェブサイトはこちら→。 Tim Ingold, Lines, a Brief History (New York: Routledge, 2007), 116-19. María Puig de la Bellacasa, "Encountering Bioinfrastructure: Ecological Movements and the Sciences of Soil," Social Epistemology vol. 28, no. 1 (2014): 26-40. Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes: Résister à la barbarie qui vient (Paris: Découverte), 2009. この文章では48頁からガイアが侵入してくる。ステンジェスは数々のインタビュー、エッセイ、講演で「ガイアの侵入」について論じている。科学、政治、文 化の内外を問わず、アントロポセン(人新世)というレッテルがますます避けられなくなることへの不快感は、ラトゥールをはじめとする他の多くの作家と同 様、ステンガーズの思考を貫いている。Stengers in conversation with Heather Davis and Etienne Turpin, "Matters of Cosmopolitics: アーキテクチャー・イン・ザ・アンソロポセン(人新世の建築)』所収: エティエンヌ・ターピン編『人新世の建築:デザイン、深い時間、科学、哲学の出会い』(ロンドン:東京大学出版会)所収。Etienne Turpin (London: Open Humanities, 2013), 171-82. 科学者たちは、この絶滅 "現象 "は、私たちの種が誕生して以来初めて起こるものであり、これまでの大絶滅現象がそうであったように、現存する生物多様性の50%から95%が、より急速 に消滅する可能性があると見積もっている。冷静に見積もってみると、2100年までに現存する鳥類の半数が姿を消す可能性がある。どのように考えても、こ れは多くの二重の死である。一般的な解説は、Voices for Biodiversity, "The Sixth Great Extinction" を参照されたい。受賞歴のあるサイエンスライターによる報告は、Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction: An Unnatural History』(New York: Henry Holt, 2014)を参照。生物多様性条約からの報告書は、予測についてより慎重であり、信頼できる知識を得ることの実際的・理論的な難しさについて論じている が、悲痛な思いを抱かせないわけではない。2015年夏の不穏な報告書については、ジェラルド・セバロス、ポール・エーリック、アンソニー・バーノス キー、アンドレス・ガルシア、ロバート・プリングル、トッド・パーマー「加速する現代の人類による種の損失: 第6次大量絶滅に突入」Science Advances vol. 1, no. 5 (June 19, 2015). Lovelock, "Gaia as Seen Through the Atmosphere," Atmospheric Environment, vol. 6, no. 8 (1967): 579-80; Lovelock and Margulis, "Atmospheric Homeostasis by and for the Biosphere: The Gaia Hypothesis," Tellus, Series A (Stockholm: International Meteorological Institute) vol. 26, nos. 1-2 (February 1, 1974): 2-10 →. 1984年にアメリカ航空宇宙局で職員に行った講義のビデオは→。オートポイエーシスは、マルグリスの変容的な共生理論にとって極めて重要であったが、も し彼女が生きていてこの問題を取り上げていたとしたら、マルグリスはしばしばシンポイエーシスの用語と形象概念的な力を好むだろうと思う。私は、ガイアは オートポイエティックと勘違いされたシステムであり、本当はシンポイエティックなのだと提案する。ガイアのストーリーは、豊かな堆肥を作るため、あるいは 先に進むために、他の多くの有望なシンポイエティックな触手と結びつけられるよう、押しつけがましく変身する必要がある。ヘシオドス(前750年から前 650年頃のホメロスの頃のギリシャの詩人)よりも、ガイアやゲはずっと古く、荒々しいものだが、ヘシオドスは『神統記』の中で、彼女/それの物語を設定 するやり方で、彼女/それについてきれいにしている:カオスの後、"広々とした "ガイア(大地)が生じて、上はオリンポスを所有する不死の者たちの永遠の座となり(『神統記』116-18、グレン・W・モスト訳、Loeb Classical Library)、下はタルタロスの深淵となった(『神統記』119)。クトニックな者たちはこう答える!ガイアは彼らの仲間であり、オリンピアードの幽 体離脱者たちに対する現在進行形の触手的脅威であって、彼らの地盤や基盤ではなく、その後に続く神々の世代はすべて適切な系図に配列されている。ヘシオド スのそれは、紀元前8世紀にはすでに定説を定めていた、古くからのゲスな物語である。 もっと合理的な環境政策や社会自然政策があればいいのだが......! イザベル・ステンガーズ、2014年1月14日、電子メールで送られたガイアに関する英文編集より。 (1)ブルーノ・ラトゥールが私たちに注意を喚起した「モノの議会」に集められた実体の集合体、(2)分類が難しく、分類不可能で、おそらく悪臭を放つも の。Latour, We Have Never Been Modern (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993). Paul Crutzen and Eugene Stoermer, "The 'Anthropocene'," Global Change Newsletter, International Geosphere-Biosphere Program Newsletter, no. 41 (May 2000): 17-18 →; Crutzen, "Geology of Mankind", Nature 415 (2002): 23; Jan Zalasiewicz et al., "Are We Now Living in the Anthropocene?". GSA(Geophysical Society of America)Today 18巻2号(2008年): 4-8. 人新世が出現した時期については、もっと早い時期が提唱されることもあるが、ほとんどの科学者や環境保護主義者は、18世紀後半以降の地球規模の人為的影 響を強調する傾向がある。ホモ・サピエンスが地球上に出現し、今では絶滅してしまった大きな獲物を狩猟し、その後、農耕と家畜化を発明したという、最も古 い時期の提案には、より深遠な人間の例外主義(自然と文化の最も深い分裂)が伴っている。人類新世の年代を、大気圏内核爆弾の爆発によって最初に示された 1950年頃からの、地球システム指標と社会変化指標における複数の「大加速」から推定する説得力のあるケースは、Will Steffen, Wendy Broadgate, Lisa Deutsch, Owen Gaffney, and Cornelia Ludwig, "The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration," The Anthropocene Review, January 16, 2015. Zalasiewiczらは、地質学的エポックとしての "人新世 "という用語が、国内および国際的な関連科学団体によって採用されるかどうかは、層序的な特徴によって決まると主張している。そうかもしれないが、人新世 の共鳴はそれよりもはるかに広範囲に広がっている。人新世の痕跡を調査した私のお気に入りのアート作品のひとつが、ライアン・デューイの「Virtual Places」だ: この作品では、「小売店の棚にあるその場限りの地質学のコア・サンプル」を構成している。 1990年代における気候変動モデリングとの強力な民族誌的出会いについては、Anna Lowenhaupt Tsing, "Natural Universals and the Global Scale", ch. 3 in Friction: Friction: An Ethnography of Global Connection (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), 88-112, ch.3、特に「モデルとしての地球気候」101-6を参照。何がグローバルな知識を可能にするのか?彼女は "共同作業の消去 "と答える。しかし、ツィンはこの歴史的に位置づけられた批判にとどまらない。その代わりに彼女は、ラトゥールやステンガーズのように、本当に重要な問い を私たちに投げかける: 「自然のグローバルな広がりの利点を失うことなく、自然の共同的な起源に注目することは可能だろうか?(95). 「新自由主義的な征服、普遍的な征服、世界的な征服という呪縛から批判的な想像力を解き放つという課題に、学者たちはどのように挑むことができるだろう か?偶発的な連結の摩擦に注目することは、資本主義やグローバリズムの新たな形態の有効性や脆弱性を説明するのに役立つ。この移り変わる異質性の中に、新 たな希望の源泉があり、もちろん新たな悪夢もある」(77)。1995年、彼女が初めて気候モデル会議を開いたとき、ツィンはある啓示を受けた。なぜな ら、それがモデルのスケールだからである」(103)(原文ママ)。しかし、この性質と関連する性質には特別な効果があり、交渉者を国際的で異質なテーブ ルに着かせる。「より小さなスケールをグローバルに埋め込むこと、あらゆるものを含むようにモデルを拡大すること、政策主導でモデルを構築すること: これらの特徴が相まって、モデルが外交官を交渉のテーブルに着かせることを可能にしている」(105)。それは軽蔑されるべきことではない。 2008年に設置された人新世作業部会は、国際地質科学連合と国際層序委員会に対し、地質学年表に新たなエポックを命名するかどうかを報告することを目的 としており、2016年に最終報告書を発表することを目指していた。人新世作業部会ニュースレター第4巻(2013年6月)参照: 1-17 →;および第5巻(2014年9月): 1-19 →. フェスティバルの終わりに燃えるマンの燃えるようなイメージのフォトギャラリーは、"Burning Man Festival 2012 "を参照: アート、音楽、炎の祭典」ニューヨーク・デイリー・ニュース、2012年9月3日 →。何万人もの人間(と未知数の犬)が参加するバーニングマンは、1990年からネバダ州のブラックロック砂漠で、1986年から1990年まではサンフ ランシスコのベイカー・ビーチで開催された、アートと(商業的な)アナーキズムの1週間にわたる年次フェスティバルである。このイベントの起源は、サンフ ランシスコのアーティストたちが夏至を祝うことにある。「このイベントは、コミュニティ、アート、急進的な自己表現、急進的な自立の実験として説明されて いる」(『バーニングマン』ウィキペディア)。人新世のグローバリゼーションの喧騒は、バーニングマンのようなドラッグとアートに彩られた世界観ではない が、祭りの最中に点火される巨大な炎のような「マン」の図像は抗いがたい。サンフランシスコの浜辺で最初に燃やされたのは、高さ9フィートの木製の「男」 と小さな木製の「犬」だった。1988年までには、「男」は高さ40フィート(約1.5メートル)になり、犬もいなくなっていた。ネバダ州の乾燥した湖底 に移された「男」は、2011年に高さ104フィートに達した。ここはアメリカだ。超大型はゲームの名前であり、人類にふさわしい生息地なのだ。 パリに本部を置く政府間研究機関である国際エネルギー機関(IEA)によれば、2012年から2035年までの間に、化石燃料の採掘と加工に投じられる世 界の累積投資額は22兆8,700億ドルに上ると推定され、再生可能エネルギー、水力発電、原子力への投資は7兆3,200億ドルに過ぎないという。福島 原発事故後の原子力発電 言うまでもなく、これらの計算のどれもが、地球上に存在するすべての生物とともに、より軽く、より小さく、より控えめな人間の存在を優先していない。その 「持続可能性」の言説においてさえ、資本新世は地球上の多種多様な生物の世界を容認することはできない。ビッグ・エネルギーの成長戦略が環境規制の最も緩 やかな国々に切り替わっていることについては、Klare, "What's Big Energy Smoking?" を参照。Common Dreams, May 27, 2014 →。Klare, The Race for What's Left: The Global Scramble for the World's Last Resources (New York: Picador, 2012)も参照。 タール砂の重汚染は、地球人、ガイア人、そして地球上のあらゆる生物の心を打ち砕き、エラを砕くに違いない。カナダ、アルバータ州北部のタールサンド石油 採掘による有害な廃水湖は、日々巨大な「池」を増やしながら、新たな五大湖地域を形成している。現在、これらの湖に覆われている面積は、世界都市バンクー バーの面積を約50%上回っている。タールサンド事業は、使用した大量の水をほとんど自然のサイクルに戻さない。採掘滓で埋め尽くされ、驚くほど色づいた 水域の端に生育可能なものを植えようとしている地球人たちによれば、共生的な生物多様性生態系を再確立するための後継プロセスは、それが可能であると証明 されたとしても、何十年、何百年もかかるものだという。Pembina Institute, "Alberta's Oil Sands" →、Bob Weber, "Rebuilding Land Destroyed by Oil Sands May Not Restore It," Globe and Mail, March 11, 2012 →参照。アルバータ州よりも石油埋蔵量が多いのは、ベネズエラとサウジアラビアだけである。とはいえ、地球人である地球人は、現在も未来も譲るつもりはな い。ペンビナ・インスティテュート『オイルサンドの解決策』→。先住民、メティス、アボリジニの人々は、この未完の物語のあらゆる局面で重要な役割を担っ ている。 写真はNASA Earth Observatory, 2015より(パブリックドメイン)。炎が人新世のアイコンであるならば、私は欠けた氷と塞がれていない北西航路を資本新世のアイコンとしている。ソウ ファン・グループは、政府や多国籍組織に戦略的安全保障情報サービスを提供している。その報告書「TSG IntelBrief: 北極圏における地政学的競争」には次のような記述がある: 「ガーディアン紙は、北極圏には世界の未発見の天然ガスの30%、石油の15%が存在すると推定している。"2月下旬、ロシアは北極圏の権益を守るための 戦略的軍事司令部を設立すると発表した。" 「ロシア、カナダ、ノルウェー、デンマーク、アメリカは北極海の国際水域と大陸棚の領有権を主張している。「北西航路は)中国やアジアとヨーロッパ間の海 上貿易に依存する国に対して、国際舞台でロシアに大きな影響力を与えることができる」。 Naomi Klein, "How Science Is Telling Us All to Revolt," New Statesman, October 29, 2013 →; Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (New York: Macmillan/Picador, 2008)。 「キャピタロセン」は「シンポイエーシス」のような言葉のひとつで、自分が発明したと思っているのなら、周囲を見回して、他の多くの人々が同時にこの言葉 を発明していることに気づいてほしい。そして、「キャピタロセン」という言葉を誰からもらったのかと聞かれて、個人主義的な憤りを感じたのを乗り越えた。 -私は、いつものように自分が発明という猫の揺りかごゲームの一部であるだけでなく、ジェイソン・ムーアがすでに説得力のある議論を書いていて、私の対談 相手はムーアの仕事を知っていて、それを私に伝えているのだと気づいた。ムーア自身は、2009年にスウェーデンのルンドで開かれたセミナーで、当時大学 院生だったアンドレアス・マームが提唱した「キャピタロセン」という言葉を初めて耳にした。切迫した歴史的状況において、多くの湧き上がる釜から「考える ための言葉」が一斉に飛び出してくる。そのような問題にもかかわらず、「人新世」という言葉は、多くの事実、懸念、関心を集めるために受け入れられ、また 受け入れられている。 過去数世紀にわたるグローバリゼーションの経路と中心地の歴史について考えながら、ヨーロッパ中心主義を乗り越えるためには、Dennis O. Flynn and Arturo Giráldez, China and the Birth of Globalisation in the 16th Century (Farnum, UK: Ashgate Variorium, 2012)を参照されたい。植民地主義、帝国主義、グローバル化する貿易形態、資本主義の差異と摩擦に配慮した分析については、Engseng Ho, "Empire through Diasporic Eyes: A View from the Other Boat," Society for Comparative Study of Society and History (April 2004): 210-46;Ho, The Graves of Tarem: The Graves of Tarem: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean (Berkeley: University of California Press, 2006). 2013年5月19日付の「人新世か資本新世か、パートIII」で、ジェイソン・ムーアはこう述べている: 「つまり、資本と権力、そしてその他無数の戦略的関係は、自然の上に作用するのではなく、生命の網を通じて発展するということだ。自然』はここで、全体の 関係として提示されている。人間は自然の中で、特別に恵まれた(しかし特別ではない)環境をつくる種として生きている。第二に、1800年当時の資本主義 は、炭化石時代のゼウスの頭から、完全に成長し武装して飛び出してきたアテナではなかった。文明はビッグバンによって形成されるのではない。文明は、生命 の網の目における人間活動の、連鎖的な変化と分岐を通して出現するのである......ヴィスワ盆地とブラジルの大西洋熱帯雨林における17世紀の長い森 林伐採は、中世ヨーロッパで見られたものの5倍から10倍の規模と速度で起こった。 Crist, "On the Poverty of Our Nomenclature," Environmental Humanities 3 (2013): 129-47; 144. Cristは、人新世言説の罠を見事に批評し、より想像力豊かな世界観や、この問題に対処する方法を提示している。アントロポセン(人新世)という名称を 拒否し、また取り上げる、もつれ合った異論のある論文については、2014年4月10~12日にウィスコンシン大学ミルウォーキー校で開催された会議「人 新世フェミニズム」のビデオを参照のこと→。アンナ・ツィンとニルス・オーレ・ブバントが主催し、人類学者、生物学者、アーティストが「人新世」の名のも とに結集した豊かな学際的研究については、AURA: Aarhus University Research on the Anthropoceneを参照されたい。 十分に大きな物語」という主張は、クリフォードに負うところが大きい: 私はこれらを、多くのことを説明することはできるが、すべてを説明することはできない、政治的美徳の保証のない、"十分に大きな "歴史だと考えている」(201)。一つの大きな総合的な説明や理論を否定するクリフォードは、「(直線的な歴史的時間が存在論的に未完成であるため) オープンエンドな『十分に大きな物語』、接触、闘争、対話の場と連動する」リアリズムを構築しようと努めている(85-86)。 Philippe Pignarre and Isabelle Stengers, La sorcellerie capitaliste: Pratiques de désenvoûtement (Paris: Découverte, 2005). ラトゥールとスタンジュールは、糾弾の言説を激しく拒絶するという点で深く結びついている。二人は、この問題について理解し、学び直すことを辛抱強く教え てくれた。私は良い糾弾が大好きだ!糾弾は、学ぶのが難しい習慣である。 マックス・ホルクハイマーとテオドール・アドルノの『啓蒙の弁証法』を、進歩や近代化に対する批判として読むことは可能である。世俗主義者がテラ/ガイア のイカ、バクテリア、怒れる老婆の話に耳を傾けるのは非常に難しい。マルクス以外で、資本新世の腹の中でクトゥルーセンを育む最も有力な西洋マルクス主義 の盟友は、アントニオ・グラムシ『獄中ノートからの選択』とスチュアート・ホールである。1960年代から1990年代まで、ホールのエッセイは膨大な示 唆に富んでいる。例えば、Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies, eds. David Morley and Kuan-Hsing Chen (London: Routledge, 1996)を参照。 Dave Gilson, "Octopi Wall Street!" 参照。例えば、20世紀初頭のジョン・D・ロックフェラー/スタンダード・オイルのタコは、多くの巨大な触手で労働者、農民、一般市民を絞め殺した)。タ コとイカが神話の盟友となることは、素晴らしいニュースだ。テクノイドの天空神々の視覚化装置に、漆黒の夜が吹き込まれますように。 ヘシオドスの『神統記』は痛々しいほど美しい言葉で、ガイア/大地がカオスから生じて、上はオリンポスの仙人たちの座となり、下は深淵のタルタロスとなる ことを語っている。彼女/地球は非常に古く、多形的で、ギリシアの説話を凌駕している。少なくとも、ガイアはオリンポスの神々を支えるだけの存在ではな い!重要かつ異端的な学者であり考古学者であるマリヤ・ギンブティスは、母なる大地としてのガイアは、インド・ヨーロッパ以前の新石器時代の偉大なる母の 後世の姿であると主張している。2004年、映画監督のドナ・リードとネオペイガン作家で活動家のスターホークは、ギンブタスの人生と仕事についての共同 ドキュメンタリー映画『サインズ・アウト・オブ・タイム』を発表した。Belili Productions, "About Signs out of Time" →; Gimbutas, The Living Goddesses, ed. Miriam Robbins Dexter (Berkeley: University of California Press, 1999)を参照。 非ユークリッド的な」物語りにおいて何が問題になっているかを理解するには、ル=グウィン『Always Coming Home』(Berkeley: University of California Press, 1985)、およびル=グウィン『A Non-Euclidean View of California as a Cold Placeto Be』(Dancing at the Edge of the World: Dancing at the Edge of the World: Thoughts on Words, Women, Places (New York: Grove, 1989), 80-100. "The Thousand Names of Gaia: From the Anthropocene to the Age of the Earth," International Colloquium, Rio de Janeiro, September 15-19, 2014. 蜂はポトニア・セロンの紋章のひとつであり、彼女はポトニア・メリッサ、蜂の女王とも呼ばれている。現代のウィッカンは、儀式や詩の中でこれらの神話的存 在を記憶している。火は人新世を表し、氷は資本新世を表すとすれば、火と水と大地の時代であるクトゥルーセンのために赤土の陶器を使うことは、私を喜ばせ てくれる。ライサ・デスメット(トランブル)は、河の女神ラトゥ・キドゥルと現在バリ島で上演されている彼女の舞踊に関する博士論文を執筆し、ヒンドゥー 教の蛇のようなナーガから出現し、東南アジアの水域を移動する、はるかな旅をするチュトニックな触手の網を私に紹介した。デスメット『A Liquid World: Figuring Coloniality in the Indies," PhD diss., History of Consciousness Department, University of California at Santa Cruz, 2013. ポトニア・セロンとゴルゴン/メドゥーサとの結びつきは、紀元前600年以降も神殿建築や建物の装飾の中で続いており、例えばイタリア半島では紀元前5世 紀から3世紀にかけて、実践、想像、儀式において神々の力が粘り強く保持されていたことを示す証拠となっている。恐ろしいゴルゴンの姿は外側を向き、外界 の危険から身を守り、畏怖に満ちたポトニア・セロンの姿は内側を向き、生きる網を育む。Kimberly Sue Busby, "The Temple Terracottas of Etruscan Orvieto: The Temple Terracottas of Etruscan Orvieto: A Vision of the Underworld in the Art and Cult of Ancient Volsinii," PhD diss. キリスト教の聖母マリアは、近東と地中海の世界で生まれ、世界中を旅する中で、これらや他の神々の力を身につけた。残念なことに、マリアの図像は、星に囲 まれ、蛇の頭を砕く姿(例えば、19世紀初頭の聖母出現に由来する奇跡のメダル)を示しており、地上のパワーと手を結ぶというよりも、その姿を表してい る。星に囲まれた女性」は、キリスト教の聖典に登場する終末の象徴である。それは悪い考えだ。子供の頃、私は奇跡のメダルのついた金の鎖をつけていた。最 終的に、そして幸運にも、彼女の残留したクトニック感染症が私の中に定着し、私を世俗的なものから聖なるものへと、そして腐葉土と堆肥へと向かわせたの だ。 ヘブライ語のデボラとは「蜂」を意味し、聖書に登場する唯一の女性裁判官である。彼女は先君主制イスラエルの戦士であり、助言者でもあった。デボラの歌は 紀元前12世紀のものと思われる。デボラは、ジョアンナ・ラスのフェミニズムSF小説『女の男』に登場する4Jの一人、ヤエルの軍事的英雄であり盟友で あった。 エリニュス1」『テオイ ギリシア神話』→こちら マーサ・ケニーに指摘されたのだが、イギリスの長寿SFテレビシリーズ『ドクター・フー』に登場するウードの物語では、イカの顔をした者たちが人類にとっ て致命的な存在となったのは、彼らが切り刻まれ、シムヒトの集合意識から切り離され、奴隷となった後のことなのだ。ヒューマノイドであるエンパス・ウード は、多面的なエイリアンの顔の下部にしなやかな触手を持ち、本来の身体では後頭部の脳を両手に持ち、この傷つきやすく、生きている外側の器官(オルガノ ン)を通してテレパシーで互いにコミュニケーションをとる。人間(間違いなく地球人ではない)は後脳を切り離し、技術的なコミュニケーション・トランス レーターの球体に置き換えた。そのため、孤立したウードは、敵対行為を強要した奴隷商人を通してしかコミュニケーションをとることができなかった。私は ウードのテクノコミュニケーターが将来発売されるiPhoneのようなものだと思うことに抵抗があるが、街で、あるいは食卓で、明らかにデバイスにしか接 続されていない21世紀の人間たちの顔を見ると、そう思いたくなる。エピソード "Planet of the Ood "では、触手たちはウード・シグマの行動によって解放され、非人間的な自分に戻ったというSF的事実に、私はこの不謹慎な空想から救われている。ドク ター・フーは、スタートレックよりもはるかに優れた物語サイクルなのだ。 メドゥーサとゴルゴネス」、テオイギリシャ神話→「メドゥーサとゴルゴネス」。 1974年の『Walk to the End of the World』から始まるスージー・マッキー・チャーナスの『ホールドファスト・クロニクルズ』は、フェミニストとその馬についての素晴らしい考察である。 セックスは非常に正しくないが刺激的であり、政治は勇気づけられる。 エヴァ・ヘイワードは、メデューサの体からペガサスが、そしてメデューサの血のしずくからサンゴが出現することに、最初に私の目を向けさせた。彼女の「か ぎ針編みのサンゴ礁プロジェクトが海に対する責任感を高める」(Independent Weekly、2012年8月1日号)の中で、彼女はこう書いている。「もしサンゴが生命の互恵的な性質について教えてくれるのであれば、私たちはどのよ うにして、今私たちを苦しめている環境(その多くは私たちが住めなくしたもの)に対して義務を負い続けるのだろうか?...おそらく地球は金星の後を追う ように、温室効果の暴走によって人が住めなくなるだろう。あるいは、私たちはサンゴ礁を再建し、海洋難民のために別の住居を建設するかもしれない。未来が どのような状況であろうと、私たちは海洋との義務的なパートナーであり続ける。Margaret Wertheim and Christine Wertheim, Crochet Coral Reef: A Project by the Institute for Figuring』(ロサンゼルス:IFF、2015年)参照。 私は2014-15年のモントレー湾水族館の展覧会「Tentacles」に触発された: The Astounding Lives of Octopuses, Squids, and Cuttlefish. Marcel Detienne and Jean-Pierre Vernant, Cunning Intelligence in Greek Culture and Society, trans. Janet Lloyd (Brighton, UK: Harvester Press, 1978)を参照。イカ、タコ、イカが大きな役割を果たしているこの文献を紹介してくれたクリス・コネリーに感謝する。多形性、網や網の目を作る能力、狡 猾な知性は、ギリシアの作家が強調した特徴である。「イカとタコは純粋なアポライであり、彼らが分泌する不可解な道なき夜は、彼らのメティスの最も完璧な イメージである」(38)。第5章「オルフィックスのメティスとテティスのイカ」は、クトゥルセーヌ独自のテーマである、進行中のループ、「共になるこ と」、多形性にとって最も興味深い。「触手の塊(polúplokoi)のように見える軟体動物のしなやかさは、その体を絡み合ったネットワーク、つまり 可動性のある生気に満ちた結び目にしている」(159)。デティエンヌとヴェルナンのギリシア人にとって、多形でしなやかなイカは、海の原初的な両性具有 の神々に近い存在である。 ドナ・ハラウェイとマーサ・ケニー「人新世、資本新世、チュルセン」『人新世の芸術』インタビュー参照: Heather Davis and Etienne Turpin編『Art in Anthropocene: Encounters among Aesthetics, Politics, Environment, and Epistemology』(Open Humanities Press, Critical Climate Change series, 2015)→参照。 ル=グウィン「『アカシアの種の作者』とその他の言語学会誌からの抜粋」『バッファロー・ギャルズ・アンド・アザー・アニマル・プレゼンス』(ニューヨー ク:ニュー・アメリカン・ライブラリー、1988年)、175。 |
| https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099