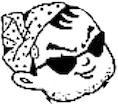
道徳的運
Moral Luck
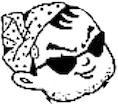
☆ このページはトーマス・ネーゲルの論文「道徳的運(moral luck)」について考察するページである。
| パラ |
頁 | ||
| 1 |
40 | カントは幸運や運を、あらゆる道徳的判断から排除した。 |
|
| 2 |
40 | 「道徳形而上学原論」からの引用(第一部第三パラグラフ) 善い意志は、それが何を行うか、何をもたらすか、あるいは、提案された目的の達成に適しているかによって善いわけではない。単に意志の力によって善いので ある。つまり、それ自体が善いのであり、それ自体で評価されるべきであり、いかなる傾向、いや、あらゆる傾向の総体さえも、それによってもたらされるもの よりもはるかに高く評価されるべきである。たとえ、運命の特別な不運や、継母的な性質のけちな配慮によって、この意志が目的を達成する力をまったく欠いて いたとしても、最大限の努力をしても何も達成できず、善い意志だけが残った場合(もちろん、単なる願望ではなく、自分たちの力でできる限りのことをした結 果としての意志)、それは宝石のように、それ自体の光で輝くだろう。それ自体に価値があるものとして、その価値を保ち続けるだろう。その有用性や無益性 は、この価値を損なうことも高めることもできない。それは、いわば、それをより便利に一般商業で取り扱うための設定、あるいは、まだ鑑定家ではない人々の 注目を集めるための設定であり、真の鑑定家に推奨したり、その価値を決定したりするためのものではない。 |
A good will is good not because of what it performs or effects, not by its aptness for the attainment of some proposed end, but simply by virtue of the volition; that is, it is good in itself, and considered by itself is to be esteemed much higher than all that can be brought about by it in favour of any inclination, nay even of the sum total of all inclinations. Even if it should happen that, owing to special disfavour of fortune, or the niggardly provision of a step-motherly nature, this will should wholly lack power to accomplish its purpose, if with its greatest efforts it should yet achieve nothing, and there should remain only the good will (not, to be sure, a mere wish, but the summoning of all means in our power), then, like a jewel, it would still shine by its own light, as a thing which has its whole value in itself. Its usefulness or fruitlessness can neither add nor take away anything from this value. It would be, as it were, only the setting to enable us to handle it the more conveniently in common commerce, or to attract to it the attention of those who are not yet connoisseurs, but not to recommend it to true connoisseurs, or to determine its value. |
| 3 |
・カントの議論だと、悪い意志についても言える。悪い意志と運は無関係だと。 ・カントによると運の良し悪しは、その道徳の実践の結果の評価に影響をうけない。 |
||
| 4 |
・運の問題は、現実の道徳的判断に影響を与えていることは確かだ(過失傷害と意図的な傷害では罪の重さが違う経験的事実) ・しかし、行われたことに対する責任をとることは当然とも考えられるので、運を考慮に入れることも正当でないともいえる |
||
| 5 |
42 | ・何がなされたかは、部分的には外的要因——つまり行為者のコントロールの範囲外——により決定される |
|
| 6 |
43 | ・それを道徳的運(moral luck)と呼ぼう——訳本では「道徳上の運」 |
|
| 7 |
44 | ・運を要素に入れると、道徳的判断を無効とするような主張につながる危険性があるから、運を排除しようとする考えが生じるのだ。 |
|
| 8 |
44 | ・道徳的判断を直観的に受け入れるためには、運はノイズのような働きをする |
|
| 9 |
45 | ・運を外的要因とすると、内的要因(=実行責任)と外的要因から、私たちの信念は形成されているように思われる。 ・運はままならない、外的要因だからである。 |
|
| 10 |
|||
| 11 |
46 | ・運に作用されるやり方には4つある ・1)構成的な運、あなたがどういう人間かということも含まれる ・2)あなたの置かれた環境に関する運 ・3)先行する事情によって構成される運 ・4)行為や計画が何らかの結果をもたらす運 |
|
| 12 |
47 | ・行為のもたらす運:身に覚えのある悪運の招来。まったく落ち度のない(みつからない)悪運、は後悔の心証がことなるはずだ |
|
| 13 |
|||
| 14 |
48 |
・結果の重大さにおいて、運の評価がおおきくぶれることがある。重大な帰結が生じたとしたら、運だけでなく、行為責任の重さが大きくなる |
|
| 15 |
|||
| 16 |
|||
| 17 |
50 |
・どんなことでも、道徳的判断に全部の責任を負わせてしまうのは、法的責任からみて、致し方ないが、道徳的立場からは「不合理」なように見えることもある。法的責任と道徳的責任を分ける思考がそこにはある。 |
|
| 18 |
アダム・スミス「道徳感情論」 |
||
| 19 |
・引用文:ある行為がたまたま生じる現実の結果がその行為の功罪に関する我々の感情に大きな影響を与える |
||
| 20 |
・ジョエル・ファインバーグの警告:道徳的責任を内的世界に限定することは、道徳的責任の、運に対する免疫性を与えてしまう。 |
||
| 21 |
52-53 |
・カントは、意志の統制できない、気質や性格は、道徳とは無関係であることを強調した。 ・嫉妬深い人は、他人が自分よりも成功することを嫌悪する ・嫉妬深さはその人の徳の評判に影響を与える。 |
|
| 22 |
53 |
・徳が、統制されないようなもので影響をうけるのは、カントにとっては理不尽なことだ。 ・しかしながら、「意志の統制できない性質に関して、自分や他人を非難することはできない」(=運という項目で行為責任に対して偶然の要素を考慮することが現実にはありえる) |
|
| 23 |
54 |
・行為責任のみ負えというカントの結論は、直観的には受け入れがたい。 |
|
| 24 |
54 |
・環境における運を考えたまえ。 |
|
| 25 |
・ナチスにおけるドイツの一般市民の責任(→責罪論) |
||
| 26 |
|||
| 27 |
|||
| 28 |
|||
| 29 |
|||
| 30 |
|||
| 31 |
|||
| 32 |
|||
| 33 |
・行為主体という概念は、脆弱な基盤に立っている。 |
||
| 34 |
|||
| 35 |
|||
| 36 |
・われわれは道徳的判断において、内的な視点を、他人にまで拡張している(60) |
||
| 37 |
60 |
・われわれが為したことという概念のなかに結果を含めることは、われわれの世界の一部分であることを認めることである。しかし、このように認めることから生じてくる道徳的運の逆説的な性格は、そのような見解がわれわれに存在する余地を残さない以上、われわれはそれを受け入れることができないことを示している(p.60) |
|
| 38 |
61 |
・道徳的運の問題は、行為主体を内的にとらえることと、そのことが他の型の価値に対立するものとして道徳的態度に対して特別な関係をもっていることとが説明されなければ、理解されえない(61) ・自分と他人に対する基本的な道徳的態度は現実に起こることによって決定される、と言うだけでは十分ではない(61) |
★モラリストの系譜
| Un moraliste est un
écrivain qui propose des réflexions sur les mœurs, les usages et les
coutumes humaines, les caractères et les façons de vivre. Il s'agit en
somme des actions et des comportements humains. Il vit le plus souvent
à la cour du Roi, comme le duc de Saint-Simon, mais certains moralistes
préfèrent la solitude, comme Blaise Pascal. |
道徳家(モラリスト)とは、人間の道徳、習慣、性格、生き方について考察する作家である。つまり、人間の行動や振る舞いを扱う。彼らは、サン=シモン侯爵のように王宮に住むことが多いが、ブレーズ・パスカルのように孤独を好む道徳家もいる。 |
| Poétique des moralistes L'écriture moraliste se caractérise par le choix d'une forme discontinue : l'essai montaignien qui va « à sauts et à gambades » (Montaigne, Essais, III, 9) sans obéir à une organisation préétablie, la collection de maximes chez La Rochefoucauld, le choix de recueil par La Bruyère, ou de fables chez La Fontaine. C'est précisément le signe de cette attitude descriptive propre au moraliste : il refuse par là le discours construit, démonstratif et prescriptif, et conteste ainsi la posture d'autorité et de savoir qui y sont attachées et qui sont précisément celles du « moralisateur », c'est-à-dire du théologien ou de l'apologète. Le choix de la forme discontinue, soit en privilégiant le désordre (Montaigne), soit en valorisant la brièveté de la notation (La Rochefoucauld, La Bruyère), rend compte et atteste l'infinie diversité des comportements humains et de la complexité d'un réel désormais sans cohérence ni signification assurée. |
道徳家たちの詩学 道徳家の著作は、不連続な形式の選択によって特徴づけられる。すなわち、モンテーニュの『エセー』のように、あらかじめ定められた構成に従うことなく「飛 躍と飛翔」(モンテーニュ著『エセー』第3巻第9章)を試みるもの、ラ・ロシュフコーの格言集、ラ・ブリュイエールによるコレクションの選択、あるいは ラ・フォンテーヌの寓話集などである。これはまさに、道徳家特有のこの記述的な態度の表れである。彼は、構築された、説明的で規範的な言説を拒絶し、それ によって、それに付随する権威や知識の姿勢に異議を唱える。そして、それらはまさに「道徳家」、すなわち神学者や擁護論者のものである。不連続な形式の選 択は、無秩序を好む(モンテーニュ)か、記号の簡潔さを強調する(ラ・ロシュフコー、ラ・ブリュイエール)か、いずれにしても、人間の行動の無限の多様性 と、今や一貫性も確かな意味もない現実の複雑さを説明し、証明するものである。 |
| Les moralistes dans l'Histoire La critique du xixe siècle et ses continuateurs ont considéré que le courant moraliste était le caractère le plus distinctif de l'esprit français du xviie siècle, d'abord par réaction contre le matérialisme ou l'indifférence morale et religieuse que les scandales des guerres et anarchies civiles et religieuses avaient amenés, ensuite par le développement de la société polie contre la grossièreté du siècle précédent1. Néanmoins, une telle approche fait se superposer dangereusement les notions de moraliste et de moralisateur, ce que ne sont jamais exactement ces écrivains ; de surcroît, la seule considération de la forme des écrits des moralistes montre une ambiguïté quant à leur signification : en l'absence d'énonciateur à qui rapporter exactement les morceaux détachés, qui fonctionnent comme des quasi-citations, un texte comme les Maximes de La Rochefoucauld est susceptible d'interprétations augustiniennes comme libertines. L'hypothèse d'une réaction « spirituelle » ne tient guère, et s'il faut s'en tenir aux thèmes, des moralistes comme La Fontaine ou comme Montaigne sont bien plus proches de l'épicurisme que d'un souci apologétique. On a même prétendu que cette mode trouva des encouragements dans les fameuses Relazioni vénitiennes, où les ambassadeurs s'appliquaient à décrire les traits des personnages les plus importants de la cour du royaume de France2. C'est la fameuse hypothèse des « clés », appliquées notamment aux Caractères de La Bruyère : il y aurait un personnage réel contemporain caché sous chaque portrait moral. La Bruyère a lui-même refusé une telle lecture dans son ouvrage, lecture qui réduit le texte à un amusant document historique. Si l'on veut donc être précis et ne pas spéculer sur une hypothétique « origine » des moralistes, il importe de circonscrire historiquement la catégorie des moralistes, stricto sensu, à la seconde moitié du xviie siècle, qui succède à la période héroïque et romanesque de la Fronde : les moralistes rendent compte et participent simultanément d'une « destruction du héros » (Paul Bénichou) et de sa mythologie qu'opère le règne de Louis XIV. C'est dans une causalité de ce type qu'on trouvera des éléments permettant d'expliquer l'apparition de ce type d'écriture, marquée par une forme de pessimisme ou de mise en question des valeurs et du sens. Le meilleur moyen de rendre compte de la spécificité de l'écriture moraliste consiste à la comparer à ce qu'elle n'est pas. On compte de nombreux écrivains apparemment très proches de cette littérature moraliste, amateurs ou de profession, et de valeur inégale : Nicolas Coeffeteau, Marin Cureau de La Chambre, Jean-François Senault ou Mlle de Scudéry, de même que les traductions de moralistes étrangers, tels Pétrarque, plus ancien, ou l'Espagnol Baltasar Gracián. À strictement parler, ces écrivains ne sont moralistes que par des thématiques comparables ; leur mode d'exposition et de pensée est radicalement différent, et détermine un mode de lecture tout autre. En effet, ces auteurs, en choisissant le genre du traité continu et démonstratif, exposent de façon assertive et définitive une vérité qu'ils donnent pour certaine ; tandis que, comme l'a montré Marc Escola3, la forme discontinue, définitoire d'une écriture moraliste, oblige quant à elle le lecteur à intervenir et reconstruire des liens multiples de continuité entre les fragments, et le laisse largement responsable du parcours du sens. C'est là une manière pour les moralistes de rendre compte précisément d'une vérité désormais mouvante, ondoyante et labile, d'une ambiguïté nouvelle des signes et des comportements ; l'économie textuelle est l'équivalent d'un réel dont l'assiette, pour reprendre une expression de Montaigne (Essais, III, 2) , n'est plus stable, et fait éprouver au lecteur cette instabilité. Si l'on rattache justement Montaigne à ce corpus, c'est d'une part que la posture moraliste y est pour la première fois inventée, d'autre part que les Essais constituent le livre de chevet du xviie siècle, et spécialement des auteurs ici considérés. Si l'on joint également les Pensées de Blaise Pascal à l'écriture moraliste, c'est le fait d'un accident de l'Histoire : les Pensées sont ce qui reste sous forme fragmentaire d'un projet d'apologie du christianisme ; elles ne se rattachent au genre que du fait de leur inachèvement à la mort de Pascal, et le projet initial, apologétique, et donc doté d'une forme organisée et démonstrative, aurait procédé d'une posture rien moins que moraliste [réf. souhaitée]. Au xviie siècle, les différents genres inventés, ou plutôt dotés d'une dignité littéraire, par La Rochefoucauld, La Bruyère et La Fontaine, sont abondamment repris par une série d'imitateurs ou de continuateurs, parmi lesquels on ne peut guère retenir, pour la qualité de leurs productions, que Vauvenargues, Chamfort et Rivarol. C'est par une double extension de la définition que l'on a pu procéder à un élargissement du corpus des moralistes, non sans mettre à mal la pertinence de la notion : Les contemporains de La Rochefoucauld et de La Bruyère qui écrivent au sujet des mœurs, mais dans une forme cette fois-ci organisée et parfaitement convenue. Ainsi Pierre Nicole et ses Essais de Morale, Jacques Esprit et son traité La Fausseté des vertus humaines, Saint-Evremond et ses Dissertations, ou le Descartes du traité sur Les Passions de l'âme. Certains d'entre eux, notamment Esprit, adoptent de surcroît des vues fort proches d'un La Rochefoucauld et ces deux derniers ont même collaboré à la conception de leurs œuvres respectives. Néanmoins, il demeure une différence essentielle entre ces auteurs et les moralistes au sens strict, différence formelle qui détermine, on l'a vu, un mode de lecture et de pensée irréductible à des points communs thématiques. En ne saisissant pas le rapport polémique qu'entretient le moraliste au discours philosophique, la critique du xixe siècle a souvent assimilé les moralistes à une branche de la philosophie ou de la physiognomonie : c'est rendre inutilisable la notion, et être particulièrement inattentif à la spécificité formelle de ces textes, pour une large part responsable de leur succès comme de la permanence de leur lisibilité aujourd'hui et de leur annexion à la notion de littérature telle qu'elle s'élabore à la charnière du xviiie siècle et du xixe siècle. A contrario, il n'y a guère de philosophes qui rangeraient ces moralistes dans sa discipline, et cela, à raison. Tout individu qui écrit au sujet des mœurs et de l'homme sans pour autant adopter la forme du traité philosophique, sans souci de système ni de démonstration peut être défini comme moraliste. Le point commun avec les moralistes classiques réside dans l'utilisation d'une forme brève, maxime, fragment, apophtegme ou aphorisme. On a pu ainsi annexer aux moralistes des écrivains aussi divers que Joubert, Lichtenberg, Schopenhauer, Nietzsche4 (à partir de Humain, trop humain), Cioran, Maurois, Camus ou Quignard : le recours à une forme discontinue pour rendre compte des comportements humains procède chez eux d'une toute autre configuration intellectuelle et historique qu'au xviie siècle et l'on peut considérer cette annexion comme abusive. |
歴史上の道徳家 19世紀の批評家とその後継者たちは、道徳主義の潮流を17世紀のフランス精神の最も特徴的な特徴であると考えた。戦争や市民的・宗教的無秩序の不祥事に よってもたらされた唯物論や道徳的・宗教的無関心に対する反応として、そして、前世紀の粗野さに対する礼儀正しい社会の発展としてである。しかし、このよ うなアプローチは、道徳家と道徳主義者の概念を混同する危険性をはらんでいる。これらの作家は決して道徳家や道徳主義者ではない。さらに、道徳家の著作の 形式そのものが、その意味について曖昧さを示している。断片的な引用文を正確に関連付けることができる話し手が不在であるため、ラ・ロシュフコーの『箴 言』のような文章は、アウグスティヌスから自由主義者まで、さまざまな解釈を受けやすい。「精神的な」反応という仮説は説得力に欠ける。テーマに固執する ならば、ラ・フォンテーヌやモンテーニュのような道徳家は弁明的な関心よりも快楽主義に近い。 この流行は、ヴェネツィアの有名な『レラーツィオーニ』によって奨励されたと主張する者さえいる。この書物では、大使たちがフランス王国の宮廷における最 も重要な人物の特徴を描写しようと試みていたのである。2 これは、特にラ・ブリュイエールの『性格論』に適用された有名な「鍵」となる仮説である。各々の道徳的肖像の下には、現実の現代的な人物像が隠されてい る。ラ・ブリュイエール自身は、その著作の中で、テキストを面白おかしい歴史的文書に還元するような解釈を拒否している。 仮説上の「道徳家」の起源について推測するのではなく、正確に述べたいのであれば、道徳家というカテゴリーを歴史的に厳密に規定し、17世紀後半、フロン ドの乱の英雄的でロマンチックな時代に続く時代に限定することが重要である。道徳家たちは同時に、「英雄の破壊」を説明し、それに参加した (ポール・ベニシュー)と、ルイ14世の治世がもたらしたその神話についてである。このような因果関係において、価値や意味を悲観的に見つめたり、問いか けたりする特徴を持つこの種の文章の登場を説明する要素を見出すことができる。 道徳的な文章の特異性を説明するには、そうではないものとの比較が最もわかりやすい。この道徳文学に非常に近いと思われる作家は、アマチュアやプロフェッ ショナルなど様々であり、価値もまちまちである。ニコラ・コエフェトー、マラン・キュロー・ド・ラ・シャンブル、ジャン=フランソワ・セノー、あるいは ド・スクデリィ嬢、そしてペトラルカやスペイン人のバルタサル・グラシアンといった外国の道徳主義者の翻訳などである。厳密に言えば、これらの作家はテー マが似ているという点で道徳家であるに過ぎず、その説明の仕方や思想は根本的に異なっており、それによって読解の仕方も全く異なってくる。実際、連続的か つ説明的論文というジャンルを選択することで、これらの著者は当然のこととして受け止めている真理を断定的かつ決定的に説明している。一方、マーク・エス コラ(Marc Escola)が示しているように、道徳的な文章の特徴である非連続的な形式は、読者に介入を強いるものであり、断片間の連続性を再構築するよう促す。そ して、読者は意味の展開をほぼ完全に担うことになる。これは、道徳家たちが、今や揺れ動き、うねり、不安定な、新たな記号と行動のあいまいさについて、真 実を正確に説明する方法である。テキストの経済性は、モンテーニュ(『エセー』第3巻第2章)の表現を借りれば、もはや安定していない現実の等価物であ り、読者にこの不安定さを感じさせる。 モンテーニュがこのコーパスに正しく関連付けられているとすれば、それは道徳的な立場がそこで初めて考案されたからであり、また『エセー』が17世紀の、特にここで取り上げた作家たちの枕元の本であったからでもある。 ブレーズ・パスカルの『パンセ』が道徳的な文章と関連付けられているとすれば、それは歴史の偶然によるものである。『パンセ』はキリスト教を擁護するプロ ジェクトの断片的な形として残ったものであり、このジャンルに関連付けられているのは、パスカルの死の時点で未完成であったためである。当初のプロジェク トは擁護的なものであり、したがって組織化され、説得力のある形を備えていたはずであり、それは道徳的なものではなかったというスタンスから進められてい たはずである[参照先:希望]。 17世紀には、ラ・ロシュフコー、ラ・ブリュイエール、ラ・フォンテーヌが創案した、あるいは文学的な威厳を与えたさまざまなジャンルが、模倣者や継承者 たちによって広く取り入れられた。その中では、ヴォーヴナルグ、シャンフォール、リヴァロルの作品の質を除いては、彼らの作品を記憶にとどめておくことは 難しい。 定義を2つの方向に拡大することで、道徳家たちの体系を広げることは可能となったが、その概念の妥当性を損なうことなく、というわけではない。 ラ・ロシュフコーやラ・ブリュイエールの同時代人たちは、マナーをテーマに執筆したが、今回は組織化され、完全に合意された形式で執筆した。例えば、ピ エール・ニコルと彼の著書『道徳試論』、ジャック・エスプリと彼の論文『人間の美徳の偽善性』、セント・エヴリモンドと彼の論文『論考』、あるいはデカル トと彼の論文『情念論』などである。 彼らのうち、特にエスプリは、ラ・ロシュフコーの考え方に非常に近い見解を採用しており、後者の2人はそれぞれの作品の構想において協力関係にあった。し かし、これらの作家と厳密な意味での道徳家との間には本質的な違いが残っている。それは形式的な違いであり、それは、すでに見てきたように、主題の共通性 では還元できない読み方や考え方を決定づけるものである。19世紀の批評は、道徳家と哲学的言説の間の論争的な関係を理解できなかったため、しばしば道徳 家を哲学の一分野や人相学と同一視した。これはその概念を無用なものとし、これらのテキストの形式的な特異性に対する特別な配慮の欠如を示している。この 特異性は、これらの作品の成功、今日における継続的な読みやすさ、そして18世紀から19世紀の変わり目に発展した文学の概念に含まれることの主な要因と なっている。一方で、これらの道徳家たちを学問分野で分類する哲学者はほとんどいないが、それは当然のことである。 哲学論文の形式を採用せず、体系や論証を気にすることなく、道徳や人間について書く人物は、道徳主義者と定義できる。古典的な道徳主義者たちとの共通点 は、簡潔な形式、格言、断片、ことわざ、警句を用いることである。ジュベール、リヒテンベルク、ショーペンハウアー、ニーチェ(『人間的、あまりに人間的 な』)、シオラン、モーロワ、カミュ、キニャールなど、多様な作家たちが道徳主義者として分類されてきた。人間の行動を説明するために不連続な形式を用い るという点において、彼らの場合は17世紀とは全く異なる知的・歴史的構成から出発しており、この分類は誤用であると考えることもできる。 |
| Bibliographie Paul Bénichou, Morales du grand siècle, Gallimard, 1948 Louis Van Delft, « Qu'est-ce qu'un moraliste ? », Cahiers de l'AIEF, vol. 30, no 1, 1978, p. 105–120 (DOI 10.3406/caief.1978.1165, lire en ligne [archive], consulté le 12 février 2024) Louis Van Delft, Le Moraliste classique. Essai de définition et de typologie, Droz, 1982 Louis Van Delft, Les Spectateurs de la vie. Généalogie du regard moraliste, Les Presses de l’Université Laval, 2005 Louis Van Delft, Les Moralistes. Une apologie, Gallimard, coll. « Folio essais », 2008 Collectif sous la direction de Jean Lafond (Philippe Sellier, Patrice Soler, Jacques Chupeau, André-Alain Morello), Moralistes du XVIIe siècle, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1994 Bérengère Parmentier, Le Siècle des moralistes. De Montaigne à La Bruyère, Seuil, 2000 Marc Escola, La Bruyère, Champion, 2 vol. (1. Brèves questions d'herméneutique ; 2. Rhétorique du discontinu), 2000 Cyril Le Meur, Les moralistes français et la politique à la fin du XVIIIe siècle, Honoré Champion, 2002 Cyril Le Meur, Trésor des moralistes du XVIIIe siècle, Le Temps des Cerises, 2005 |
参考文献 ポール・ベニシュー著『大世紀の道徳』ガリマール社、1948年 ルイ・ヴァン・デルフト、「道徳家とは何か?」、AIEF研究年報第30巻第1号、1978年、105-120ページ(DOI 10.3406/caief.1978.1165、オンラインで閲覧[アーカイブ]、2024年2月12日アクセス) ルイ・ヴァン・デルフト、『古典的モラリスト。定義と類型論の試み』、ドロ、1982年 ルイ・ヴァン・デルフト、『人生の傍観者たち。モラリストの視線の系譜』、ラヴァル大学出版、2005年 ルイ・ヴァン・デルフト、『モラリストたち。弁明』、ガリマール、「Folio essais」叢書、2008年 ジャン・ラフォン(フィリップ・セリエ、パトリス・ソレル、ジャック・シュポー、アンドレ=アラン・モレロ)編『17世紀の道徳家たち』ロベール・ラフォン社「ブキニ」叢書、1994年 ベレンジェール・パルマンティエ著『道徳家たちの時代。モンテーニュからラ・ブリュイエールまで』Seuil社、2000年 マーク・エスコラ著『ブリュイエール』、チャンピオン社、全2巻(1. 解釈学に関する簡潔な質問、2. 不連続の修辞学)、2000年 シリル・ル・ムール著『18世紀末のフランスの道徳家と政治』、オノレ・チャンピオン社、2002年 シリル・ル・ムール著『18世紀の道徳家たちの宝庫』、ル・タン・デ・セリーズ、2005年 |
| La Rochefoucauld La Bruyère Montaigne Vauvenargues Chamfort Antoine Rivarol Emil Cioran Nicolás Gómez Dávila Joseph Joubert Scepticisme |
ラ・ロシュフコー ラ・ブリュイエール モンテーニュ ヴォーヴォナール シャンフォール アントワーヌ・リヴァロル エミール・シオラン ニコラス・ゴメス・ダビラ ジョゼフ・ジュベール 懐疑主義 |
| https://fr.wikipedia.org/wiki/Moraliste |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆