My web-page on Ludwig Josef Johann
Wittgenstein,
1889-1951 is now moved to Ludwig_Wittgenstein.html
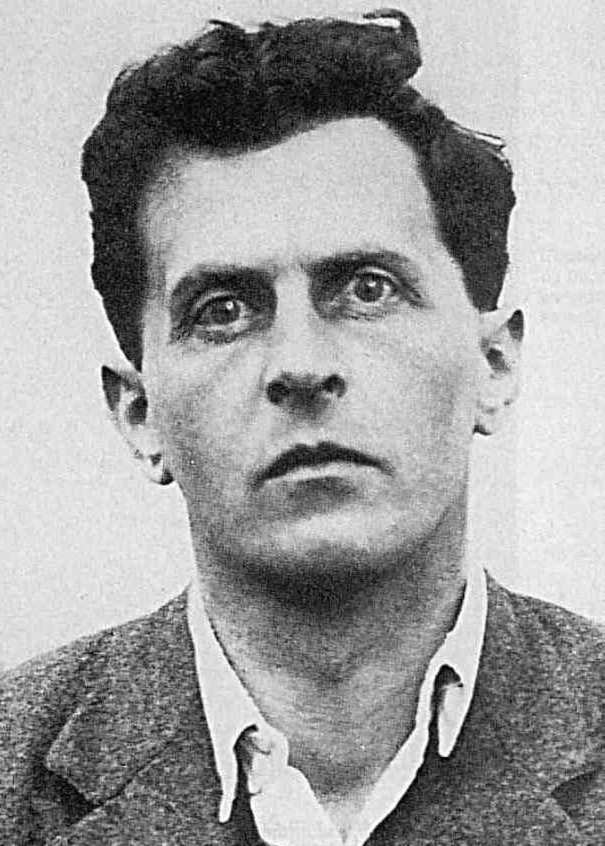
1929年にトリニティカレッジから奨学金
を受賞した時に撮影されたもの(部分)
My web-page on Ludwig Josef Johann
Wittgenstein,
1889-1951 is now moved to Ludwig_Wittgenstein.html
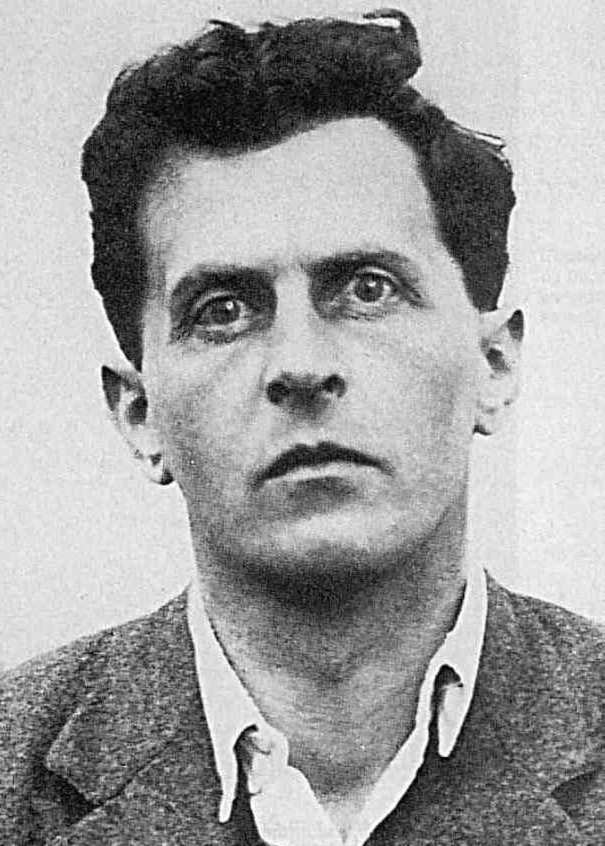
1929年にトリニティカレッジから奨学金
を受賞した時に撮影されたもの(部分)