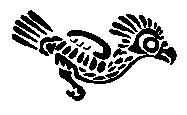
臨床コミュニケーション教育:PBL から対話論理へ、対話論理から実践へ
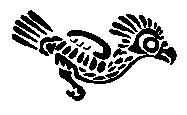
池田光穂・西村ユミ
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター
臨床コミュニケーション教育:PBLから対話論理
へ、対話論理から実践へ
池田光穂・西村ユミ
[要旨]
2006(平成18)年度から今日にいたるまで、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター(CSCD)では、全研究科の大学院生を対象とする全学 共通科目である「コミュニケーションデザイン科目」を現在では40種類以上提供してきた。私たちは臨床コミュニケーション関連科目群とよばれる5種類の授 業(臨床コミュニケーション I と II、ディスコミュニケーションの理論と実践、現場力と実践知、医療対人関係論)を担当している。
本稿では、(1)この経験にもとづく「臨床コミュニケーション授業」の概要の紹介、(2)医学教育における対話型教育といえる「問題にもとづく学習」
(Problem-Based Learning, PBL)についての簡潔な紹介とPBL教育に関する技術的な問題点などについて検討をくわえる。
1.はじめに:臨床コミュニケーション教育
臨床コミュニケーションとは、人間が社会生活をおこなうかぎり続いていく、ある具体的な結果を引き出すためにおこなう対人コミュニケーションであると私
たちは定義している。ここでの臨床は、狭い専門領域としての臨床(clinic)のことではなく、臨床は対人コミュニケーションにおいてあまねくみられ
る、その現場における実践状況(human care in practice)そのもののことをさす。
臨床コミュニケーションを人間的コミュニケーションの基盤としてみようとする私たちのアイディアのルーツは、1990年代から浮上する「臨床」という言 葉に対するリビジョニズムの隆盛にある。1990年代、哲学者である中村雄二郎が〈科学の知〉に対抗し、それに置き換わる〈臨床の知〉を提唱した。人間ど うしが相互作用のうちに読み取る、諸感覚(五感)を協働させる共通感覚と実践状況が不可分になった状態を〈臨床の知〉と呼んだ。1990年代、看護研究の 現象学派の人たちが、アリストテレスの〈実践知〉概念などを手掛かりにして科学的認識からは捉えきれない、感性や現場の知恵の重要性に着目した〈アートと しての看護〉実践論が生まれた。
このように私たちにとって、臨床コミュニケーションは世の中のおよそ社会的とよばれる領域に遍在するものとみてよい。医療者と患者でみられる相互作用、 学校教育、心理カウンセリング、法律相談、友人間の悩み事の解決など、臨床コミュニケーションとよばれる社会活動の範囲は広大である。
その現場は人間活動のほとんどあらゆる面で見られ、解決が求められている課題も多様で、広範囲である。人間コミュニケーションに関するさまざまな諸分野 の成果を活かしつつ、対話にもとづく現場の臨場感を反映させるような実践教育が不可欠。文理融合、学際、領域横断型の協働研究を通して、リアルタイムでそ の成果を伝える必要がある。ここでの問題は、臨床コミュニケーションは、はたして「教える」ことができるかということである。
現在、大阪大学大学院に所属する高度教養教育としてのコミュニケーションデザイン科目の下位科目群としての臨床コミュニケーションの授業は次のような形 式でおこなわれている。20から60名の受講生に対して3から4名の教員が参加する。教員とTA(ティーチングアシスタント)と大学院生が水平的な関係を 維持し、対話を遂行する。授業の進行はつぎのような段取りですすむ。課題の提示からグループ討論に入る。そして討論結果の報告を経て、質疑応答、や教員の コメントをおこなった後、さらに、全体討論でまとめる。授業終了後は、Reaction-Paperの作成をおこなう。その間に質問やコメントがある場合 は随時教員が応答する。授業が終わった後は、教員によるReaction-Paperの分析をおこなう。教員集団は定期的に反省会を兼ねた小カンファレン スをおこない、それらの結果を教員の授業改善に反映させる。
取り上げられたテーマを列挙してみると次のようになる:臨床コミュニケーションの広がり、語らぬコミュニケーション、騙るコミュニケーション、参加する ことの意味、自己との対話。 病むことの意味、 対話・対峙における即興、未知なるものとの対話、臨床的対話とはなにか、コミュニケーションとしての身体、言語を媒介とするコミュニケーション、身体を媒 介とするコミュニケーション、病める身体「について/を通して」語ること、医療現場のコミュニケーション、医学教育おけるPBLとNBM、よい臨床コミュ ニケーションとは、偽りのコミュニケーション・デザイン、紛争におけるコミュニケーション、紛争とナラティヴ、What is community?(英語による授業)、臨床コミュニケーションの未来像、などである。
授業をおこなう過程で浮上してきた問題がある。それは、実践教育としての臨床コミュニケーション教育に携わる教員は、自分たちの狭い理論の枠組みに囚わ
れており、その十全たる教育効果の可能性については未だ信じていないということだった。他方、社会に羽ばたこうとしている学生は最初から私たち教員に十全
な教育効果など期待せず、必修科目ではないことも手伝って、新しい形式の授業そのものを純粋に楽しんでいる。だから変わらなければならないのは、学生では
なく他ならぬ大学の体制と旧態依然としている大学教員そのものだ、というわけだ。
2.教育改革における「問題にもとづく学習」の意味
ここで1960年代から今日に至るまでの米国医学教育についておさらいしてみよう。
1960年代は、行動科学・コミュニケーション教育を中心とした全人教育、包括医療教育としての臓器別統合型カリキュラム、プライマリ・ケア医養成のた
めの地域志向型教育などで特徴づけられる時代である。それが1970年代に入ると、後述するPBLチュートリアル教育の構想と先行実施という重要な時代に
突入する。1980年代では、1984年の米国医科大学協会による『GPEPレポート』があり、ニューパスウェイ=詰め込みではない学習主体教育(ハー
バード大学医学校)。そして、コミュニケーション技能評価を含むOSCE(Objective Structured Clinical
Examination: 「客観的構造化された臨床での試験」)の開発は忘れてはいけない。
1990年以降の米国医学教育ではさらにこれらの伝統が次のように展開する。1990年代は、まさにOSCEの本格化がはじまり、PBLの世界中の先進 国の医学校に普及する。日本でも、折衷型のPBL教育が導入される。ニューミレニアム以降は、Outcome Based Education、プロフェッショナル教育、多職種間コミュニケーション、ポートフォリオ評価などが盛んになって今日にいたる。
学習者じしんが中心となり、反省的反復の作業をともないながら、実践される少人数グループの教育手法ことを「問題にもとづく学習」とよぶ。PBL とは, Problem Based Learningのアクロニム(頭文字による略記法)である。問題にもとづく学習は、一種のブランドあるいは確立された手法として理解されることが多いの で、英語によるアクロニムにより、PBLと簡略ないしは、ジャーゴンでふつう呼ばれている。医学領域におけるPBLによる教育の牙城であったカナダ・オン タリオ州ハミルトンにあるマックマスター大学ではPBLを意味深に以下のように定義している。
「PBLは、学習を引き起こす問題の中にある、あらゆる学習環境のことをさす。すなわち、学習者たちがいくつかの知識を学ぶ前には、すでに彼/彼女らに ひとつの問題が与えられている。学生は、自分たちが問題を解くことができる前に、いくつかの新しい知識をまなぶ必要があるということを学生自身が先に発見 できるように問題が仕向けられているのである」。
私の理解にもとづいてPBLを4項目にまとめて言い直してみよう。つまり、(i)問題にもとづく学習(PBL)は、学生が問題をとりくんでいる学習行為 の全体のことであり、それには学習環境なども含まれる。(ii)PBLの文脈の中では、我々は知識を習得しようと思う前にすでに何か解き明かすべき問題認 識がある。(iii)人は「〜とは何であるか」という命題化された問題に到達すれば、それを解くために新しく具体的な知識を仕入れなければならない。学習 者がそのように自覚化している環境(=「知的な文脈」)それ自体がPBLに他ならない。(iv)PBLの学習観では、〈解かれるべき具体的問題〉の自覚と 〈問題解決にむけた行為実践〉を切り離して考えることできないという立場をとる。
また、このマックマスター大学による定義を引用をしたウェブページでは、PBLによる教育実践の理念的特徴を次の3つにまとめる。すなわち小グループ・
自発性・自己評価による問題にもとづいた学習(Small group, self-directed, self-assessed
PBL)である。わずか3つの標語だが、そのことが学習者の行動理念を見事に表現している。すなわち、(1)学習の単位は少人数のグループである。なお実
際には、これにチューターという積極的な介入をしないと命じられている教員格の監督者が加わる。(2)チュートリアルという資料以外には資源が与えられな
いために、学習者はチーム内で分業し収集した知識や情報を発表し、協働で考え、さらなる情報収集のために自発的に討論に参加しなければならない。(3)
チームという学習環境の中で自己の立場を明確に打ち出すことが期待されているので、学習の成果は適確な結論に到達したかという観点よりも、自分が協働作業
にどのように関わりチームによる知識探究にどれだけ貢献したのか、つまりリーダーシップだけでも縁の下の力持ちだけでもダメという、そのような共同学習主
体の存在証明を自分で表明しなければならない、ということにある。
3.実践知習得手法としてのPBL
マックマスター大学で編纂された教科書には、PBLと系統的学習の対比の例が面白おかしく描かれている。すなわちPBLの問題とはこうである:「ここに
故障したトースターがあります、これを直してください。でなければ、少しばかり要求を譲歩して、ちょっとでも使えるようにしてください」。ハワイ大学にあ
る医学校――米国の医学教育は学部ではなく専門大学院でおこなわれる――では、PBLの第1回目の授業では、たとえば次のような問題が出される。「高校生
の女性シンディは、下腹部の痛みが数日続いていた。彼女はいつもはファミレスでバイトしているが痛みがひどく、大学病院の外来を訪れた」(原文を大幅に改
変している)。ただ、それだけである。またネバダ大学医学校PBLのチュートリアル・ケース『ゲロ吐き少年!のケース』では、11項目の情報が盛り込まれ
ているが、最初の解説は「1.ランディ・ミルバーンは10歳の男性で、母親に連れられて君のオフィスにやってきたが、彼は虚弱、喉の渇き、そして継続する
嘔吐発作を訴えている」という一文のみである。
ここでチューターならびにチュートリアルの用語法についてさまざまな留意が必要である。チュートリアルには複数の意味があるからだ。すなわち、(a) チューターを利用する少人数教育の形式そのものを指すことがある。そして(b)文書や画像、データなどから構成されるチュートリアルという資料体を使うよ うなケーススタディを指す場合。そして、(c)チュートリアルを用いてかつチューターが授業に参加するPBLのスタイルからの連想されるPBL の同義語としての用法である。
学習者は5,6名からなる小グループ班を作り、このチュートリアルにもとづく学習課題がつづく限りチームで問題解決に取り組む。この患者にまず何をすべ きか? 患者が病院に訪れる前はどのような状態だったのか? 病院ではどのような観察やデータが必要なのか? どのようなインタビューによって患者のこと を適確に知ることができるのか? チュートリアルには、これらに関する状況説明、生物医学的データ、その後の医学的処置、さらに処置後の状況説明や、生物 医学的データの変化などが、臨床の現場で手に入るような形で提供されている。チュートリアルの多くは事実に基づいた資料をベースにしているが事実そのもの ではない。
学習者は次にどのような資料を集めるのかを相談する。また、その授業の集まりで必要とされるような学問上の理論などを次回にまでにどれだけ学んでくるの か課題を設定する。そしていつごろ、どの程度の集まりをもつのか、チューターの都合はどうかなど、スケジュールを調整する。チューターの助言は必要かつ最 低限なものであり、具体的な学習内容を指示することは控えている。
PBLの教科書やマニュアルを読むと、いかにも良いことずくめの記載が多い。そしてPBLと聞いたり、そのことについて多少なりとも理解すると流行りも のの最先端のようなブランドを身につけるような幻想に囚われる。
しかし、医学校の例で理解できるように、ごく普通の専門家がその社会の中で専門性を発揮した仕事をはじめる際のごくごく当たり前の事例が用いられる
PBLは、具体的な問題解決に日々取り組んでいる専門家の現場での知識習得そのものである。そして専門家の育成教育において、このようなプロの感覚がいっ
たいどのように身につけることができるのか。マニュアルによるインストラクションや、最初から答え(=診断名)が提示されてあるレントゲン写真をみて病巣
を確認するような従来の教育に限界があることは明白である。日常の診療のように教科書に載っていないようなあいまいな病像や、未経験のケースに直面しなが
ら、専門家として対話論理の実践を通して鍛えられてゆくからである。
4.総括
以上の検討により私たちによる総括は次の2点にまとめられる。
1.授業を動態的(dynamic)にするためには、受講学生が抱くこれまでの授業観を変更(deconstruction)する必要がある。授業参加者 (=学生と教員集団)全員がその手順に馴染むことにより対話型の授業が円滑に進む大きく2つの促進要因がある;ひとつは学習者の授業参加への自発性の強化 であり、他のひとつは教員がもつ旧い教育に対する固定観念の解体である。これは予習・本習・復習を含めた学習の時空間のみならず、学習がおかれているより 大きな社会文化的文脈への介入(=挑戦)が持続的におこなわれる必要性を示唆している。
2.コミュニケーション教育では授業参加者が対話論理を経由して、その成果を日常的実践に結実させることが求められている。臨床コミュニケーションの授業
における言表(utterance)が、説明責任と応答責任(accountability and
responsibility)を発話行為のなかで発生させない限り、実践はうまれないだろう。したがって現時点における臨床コミュニケーション教育の目
標(=理想的状況)は、授業という場が社会空間であることを対話的他者である学生と共に認識し、あらゆる対話が私たちにしむける説明責任と応答責任を、授
業のなかに具体的なかたちで呼び起こすことにある。
文献
■ 授業風景など

■ リンク
2009年7月10日 第1回ヘルスコミュニケーション研究会予稿集 於:東京大学医学部附属病院内、中央診療棟2 B1会議室
ウェブページ:http://healthcommunication.jp/
Copyright Mitzub'ixi Quq Chi'j, 2009-2015