
第2章 先行研究:「実験室における社会実践の民族誌学的研究」
Chapter 2: Review: “Ethnographic Studies of Social Practices in the Laboratory.”

2.1 トマス・クーン『科学革命の構 造』(1962)以降
トマス・クーンの著作に始まる論争以前の科学研究は、大きく分けて(a)科学哲学・思想史という内在的アプローチ(internal approach)と、(b)科学史に着想を借りた形式論的な科学社会学という外在的アプローチ(external approach)に分けられていた。それらは、科学研究がどのようなプロセスを経て科学理論として確立するのかという認識論においては、理論の客観的真 理という尺度を措定したうえで、歴史的事実を論理形式のパターンとして推論するということが主たるものであった。またその科学観においても科学者集団は社 会との関係をもちながらも、独立した集団を形成しその集団の成員がもつエートスによって維持されていると考えていた(Merton 1970[1938]; 有本1987:16)。
クーンのパラダイム論は、カール・ポパーのいう反証主義(falsificationism)が科学史上のおおきな刷新について説明でき ないことを示したものである。成熟した科学には、研究上の行動をかたちづくる理論とそれを支える技術の体系(規範化されたコスモロジー)というものがあ り、それがパラダイムである。パラダイムの中で行動する科学者は、その規範にもとづいたパズル解きをおこなっているのである。パラダイムの中で、しばしば 観測される変則事例つまりポパーのいう反証の可能性をもった事例が出てきても、それは観測のやり方に誤りがあるとされてしまう。このような変則がパラダイ ムの維持ができなくなるほど拡大したときに科学革命すなわちパラダイムの転換がおこる。相互のパラダイムの間での翻訳や理解は不能であり、これを共約不可 能性(incommensurability)と呼ぶ。
クーンの主張に対する、ポパー派の科学 哲学の論争がもたらした理論的課題には次のようなものがあげられる(高田 1999:441)。
(1)観測/観察の理論負荷性
(2)競合理論の間での理論選択の不確実性
(3)共約不可能性(incommensurability)
(4)発見の文脈/正当化の文脈の関係
(チャルマーズ 1985; ブラウン 1985)
ポパーとクーンの立場の違いは、その間で大きな論争がおこったために対比的に描かれることが多いが、ともに理論の進化(変化)や革命があ るという点では、科学を相対主義的に捉えており、反実証主義の系譜に属するものである(Galison 1997)。クーンは、パラダイムという科学者集団における固有の認識(コスモロジー)の共有というアイディアの維持と再生産について重要な貢献をおこ なった。しかし、その相対論的な見方は1950年代の社会哲学に大きな影響を与えたエヴァンズ=プリチャードやウィンチなどの動きとともに、科学という社 会的営為を把握する際に過度の相対主義的な見方を植え付けることになった。
2.2 科学知識の社会学
このような流れは、科学研究者の著作や論文のみならず、実験ノートや私信などへと資料が拡大し、科学者自身がどのように実験データから知 識を構成していったのかという知識社会学の具体的な諸相への関心を生むにいたった。その結果、科学者じしんが生きた社会との関係、すなわち科学の社会史と いう研究下位領域を形成することにつながった(マルケイ 1985; 松本 1998)。
そのなかでもっとも有力なものがエジンバラ大学の科学研究グループ(ブルア、バーンズ、シェイピンら)のストロング・プログラムである。 ストロング・プログラムでは、科学知識の信念や知識に関する社会的条件(因果性)、その時代におこった真偽、正否、合理/非合理の説明を価値判断ぬきにお こ なう(不偏性)、それらの対立する要素の説明が同じ論理のなかで対称的に説明できる(対称性)、および説明がみずからの正しさを証明できる(自己反射性) という原則において科学の説明を試みようとした(ブルア 1986; バーンズ 1989)。
ストロング・プログラムに代表される——科学論ではこれにバース学派が加わる——科学知識の社会学(Sociology of Scientific Knowledge, SSK)は、科学の社会現象を認識論的相対化によって理解しようとした立場である。さらにその認識論的な相対化ゆえに、あらゆる知識表象がその現場の知識 生産のプロセスと無媒介的に認識論的に自由に操作されるという危険性を孕んでいた。それゆえ科学の実在論の立場からはさまざまな角度から批判されることに なる(そのもっとも極端な例は Gross and Levitt [1994]に始まるサイエンス・ウォーズである)。
ストロング・プログラムの最大の問題は、その相対論的な議論を引き出すためのデータを既存のもの、ないしは発見される歴史的資料に依存し ており、研究スタイルとしての実証データを自ら収集したり、また収集の過程における事実の構築性(自己反射性)に対する学派としての補強するプログラムを もたないというジレンマにつきあたったことにある。このジレンマを解消するためには、より具体的で詳細な社会史的な資料が不可欠であった。この学問的必要 性から実験室における民族誌的な資料への関心が高まることになった。
2.3 科学実践としての実験室研究 (laboratory studies)
科学研究への関心は歴史的発見から科学者 自身が実験室でおこなう日常的実践へとシフトした。それは科学の発見のような歴史的事実の再構成 では得られないような、より詳細で正確な情報が手に入るからであった。また会話分析やエスノメソドロジー、エスノサイエンスなど隣接経験科学(社会学や人 類学)の研究分析手法の発達があったこともその流行の要因にあげられる(ブラニガン 1984; ギルバートとマルケイ 1990)。
科学の民族誌学研究の代表にあげられるの は、ラトゥールとウールガー『実験室の生活』(Latour and Woolgar 1979, 1986)、クノール=セティナ『知識の製作』(Knorr-Cetina 1981)、リンチ『実験室における技と人工物』(Lynch 1985)、ラビノウ『PCRの誕生』(1998[1996])などである。
ラトゥールとウールガー『実験室の生活』 は、共著者のラトゥールが1975年カリフォルニアのソーク研究所で、ロジェ・ギルマンの研究室 で甲状腺刺激放出ホルモン(TRH)——当時は放出因子(TRF)と呼ばれていた——の構造決定に関する研究のプロセスを調査したものである。この著作の 重要な指摘は2点ある。まず、実験科学者の活動の多くは文献を集め、それを読み、論文を書くという文書作業に多くの時間を割く点である。そのために彼らは 測定装置を維持し、そこから得られるデータをもって図表や方程式などの表現方法に熟達しているということであった。このような作業を通してカオスとも思え る複雑な現象に秩序を与えて、理解可能な堅固な構造を作っているとしたのである。
ラトゥールらのもうひとつの貢献は、科学 者たちの科学的言明を5つのタイプ(〜と示唆した、〜の証拠はある/ない、〜と証明した、[客観 的事実として]〜である、言う必要のない〜であるという前提)を分類して、実験室の現場が「科学的事実」をめぐる言明が繰り広げられる競争的場 (agonistic field)として位置づけたことである(Latour and Woolger 1986:75-88)。
ラトゥールらの著作の改訂版の公刊の10 年がたってポール・ラビノウ(1996)の民族誌が公刊された。この著作は、著者がフランスの近 代思想に造詣の深い文化人類学であり、その間に公刊されてきた科学論の民族誌とは一線を画していることを意識した著作である。これはバイオテクノロジー産 業の一企業体シータス社における遺伝子の化学反応系の発明をめぐる民族誌である。書名のPCRとは、この発明の中核をなすポリメラーゼという酵素の連鎖反 応(Polymerase Chain Reaction)のことであり、今日のDNA鑑定など微量の遺伝子資料の検出や遺伝子の「量産」などに幅広く使われている。この技術的応用を思いついた 生化学者キャリー・マリスは1993年のノーベル化学賞を受賞している。
科学技術の誕生を描く古典的な手法は、ま ず主人公である科学者を中心に据えて、それが発見した内発的な経緯や技術の応用や、社会的波及効 果について広げてゆく。しかしそれとは逆に、本書では発明された科学技術がアカデミズムや企業という環境を生みだし、その環境の中で活動する主体として科 学者たち振る舞わせる様を描く手法がとられる。遺伝子を増幅する技術であるクローニングまずバイオテクノロジーという民族誌領域が誕生する技術が発明され た頃から、アメリカの製薬企業がその技術開発に投資したり、直接投資家から資本を集めベンチャー企業を起こす科学者たちが現れたりする。科学的営為と経済 的収益の両立が、官僚的な大学制度の縛りから自由になりたい研究者をベンチャーへと誘う。起業に成功者した科学者は、大学のスタッフをより有意な研究条件 でヘッドハントする。他方でより安定した収益を求めるようになる企業はやがて自由で柔軟な職場から営利性を優先した功利的システムへと運営方針を変えてゆ く。その中で働く技術者は企業の中でより統合された機能をになう適合的なエートスを構築してゆく。
ラトゥールらの『実験室の生活』が、研究 者が営む生活の論理や認識の構築のやり方にあるとすれば、ラビノウのアプローチは対象にしてる関 係者に会いに行きインタビューし、関連文献をよみ、知識の実践の現場に社会や文化というものがどのように影響しているのかについて具体的に記述するという 手順を踏んでいる——ラビノウは古典ともいえる『実験室の生活』については先行研究に挙げないどころか文献にリストにすら挙げていない。
研究室の出来事に関する質的研究としては エスノメソドロジーや解釈学(e.g. Knorr-Cetina 1981, 1999)やラトゥールらのアクターネットワーク理論など先行する成果があるのだが、ラビノウはそれらを意図的に無視しているふしがある。それは本書の中 でシータス社においてPCRの開発に関わった重要な人物——マリス[2000]はフォーマルなインタビューからは外され中心人物として背景化されている ——に対してラビノウがインタビュー発言を多用しているように、行為者の感情を含む主義主張という偶発的でかつ主体としての人間の複雑な動きに着目した かったからであろう。従ってこの書物は現代の生物学の研究室におけるディープ・プレイ(彼はC・ギアツに薫育される)に関する人類学的考察ともいえる。
他方、日本におけるバイオ研究室の文化論 ともいえる民族誌がサミュエル・コールマン『検証・なぜ日本の科学者は報われないのか(原題: Japanese Science: From the inside)』[2002[1999]]である。この民族誌は原題と翻訳題のねじれにみられるように、海外の読者からみれば、科学研究体制に関する日本 研究であり、また、日本の読者からみれば、円滑な科学研究を阻んでいる科学政治における官僚制や組織論上の問題について論じているものである。コールマン はラトゥールらの研究を引用するが、その核心部分の検討を日本の文脈でおこなうのではなく、後者の研究にみられる「クレジット(信用)のサイクル」という 研究と社会的信用の相互依存関係についての説明原理を適用するのみに留まり、彼らの実験室における行動を理念の構築という議論には全く踏み込んでいない。
コールマンと対照的なのはソーヤーりえこ [2006; Sawyer 2003]による日本のおそらく大学院の物理学実験室における日本人学生とヨーロッパ系留学生——composite characterと呼ばれる複合的な人格データを一つの個性に統合したもの——のあいだの社会的駆け引きに関する研究である。ここでは、実験室に登場す るさまざまな大学院生が実験室という生活空間を共にし、実験装置の管理や機械の性質から日常の彼らとは特異な行動パターンや社会意識(エートス)が生まれ ることを指摘している。しかし、社会行動の分析には中範囲とも言える実践共同体やゴッフマンの理論などが援用されこぢんまりとした分析がなされるだけで、 なぜ大学の実験室なのか、そしてなぜ文化的背景を異にする大学院生たちの行為の振る舞いの微妙な力学を研究するのかという彼女の強い動機をそれらの論文か ら読み取ることは難しい。
2.4 アクターネットワークという袋 小路を抜けて
観念論的な科学知識の社会学派の人たち が、サイエンス・ウォーズによってもその命脈を絶たれなかったのは、実験室研究という実証的な学問 によりカウンターバランスが保たれていたからである。また実験室研究の大物であったラトゥールがカロンと連携をとりつつアクターネットワーク理論という流 れをつくり、科学知識の社会学の考え方を包摂することに成功したからである(eg. Pickering 1995)。
アクターネットワーク理論は、社会と自然 のなかで科学技術がダイナミックに動く様子をさまざまなアクター(=人・組織・装置・機械・自然 物などを区別しないエージェントの要素)の連関で説明する、きわめて中範囲(middle range)でわかりやすい議論である。しかしながら、アクターネットワーク理論による具体的な事例検討は、その現場によるフィールドワークにもとづく詳 細なデータに裏付けられていないと、観念論的なアクター像とその記号的操作により簡単に現実とは遊離した、ないしは極めてパターン化された議論に陥ってし まう危険性がある。アクターネットワーク理論は、その人類学的方法について深く考えないかぎり、お手軽な説明の原理になってしまうために、これ(というか むしろラトゥールの議論)を有利なものと考えるかそれとも害悪と考えるで、毀誉褒貶がはげしい。彼の理論は、ラトゥール自身が科学の認識論と社会がおこな う技術的制御の「対称性」に拘っており、その都度彼に与えられる「誤解」と戦っていることからみれば、たいへん皮肉な出来事である[ラトゥール 1999:2-3]。
科学論を安易な観念論から離礁させるもの こそが実験室の人類学的研究なのである。中島[2002]は、「実験室の人類学」による研究成果 を以下のように的確にまとめている。
「実験室の人類学などで分かったことは、 実験装置を使用した個々の観察それだけでは確実な知識は得られないということだ。研究結果は実験室 内外の科学者集団で吟味され、重みづけされ、広められなければならない。否、それだけではない、実験が遂行され、科学者がこれに関与するには、確固とした 研究資金の裏付けがなければならないのだ。すなわち、科学知識の創出には、自然からの作用だけでは不十分で、社会との相互作用が必然的に含まなければなら ないということ、すなわちそれが共生成(coproduction——引用者)の産物であることが示されたのである」[中島 2002:iv]。
科学は、それを規範とする西洋近代科学 ——ラトゥールの用語では近代性(modernity)——に起源をもっているが、きわめて普遍的 統合性を志向するという意味でコスモポリタン的な性格をもつ。しかし他方で、時代・社会・文化の影響をうけて、とくにその実践の現場では多様な展開を遂げ る。実験室の民族誌が書かれる必要性があるのは、実験室おける行為者と行為者が構成する社会的現実を、その文脈から離れた研究者が観想することの無根拠性 をあらわにし、科学現象(scientific phenomena)を研究するアームチェアの科学理論家たちに社会的現実の多様な解釈と実践的理解に開くことにある。
リンク
文献
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
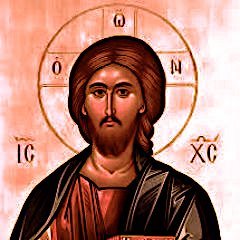
「論理の法則は、結局は知的世界を支配する
もの
なの
だが、その本性によって、本質的に不変易なものであり、すべての時代、すべての揚を通じて共通であるのみならず、また、われわれが現実の主体、架空の主体
と呼び分けているものの間でさえもすこしの差別もなく、すべてのいかなる主体にも共通である。実は、論理の法則は、夢の中においてまで守られている」——オーギュスト・コント『実証哲学講
座(Cours de philosophie positive)』
第52章。
「実証主義は実際には物神化した市民意識の表出なので
ある」——アグネス・ヘラー(1978)
「閃光が眼にとびこんでくれば光源は見えな
いも
の
だ。啓発的受容も、理解とか誤解とは呼びえないのである。だれかがスピノザの倫理学の最初の本を読んで、神はいないと叫んだとする——その場合、彼がスピ
ノザを誤解したのだと主張することは、彼がスピノザを理解したと主張するのと同様に無意味なことである」(ヘラー 1992:55)。