Against their own death
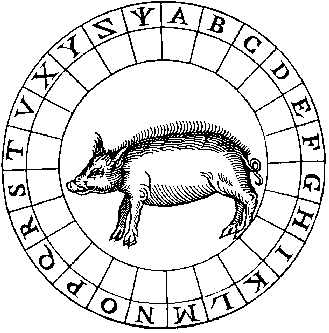
死の恐ろしさに抗して
Against their own death
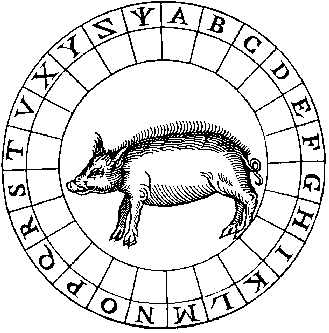
殺人とは、人間の同種内の殺傷行為 (killing)のことである。死に至らない場合は、殺人未遂(さつじん・みすい)という。
OEDの語源は、直接にはフランス古語、そして古く
はラテン語からきており、人間を殺すことである。[a. F. homicide (12th c.), ad. L. homicīda, f.
shortened stem of homo, homini-s man + cædĕre, -cīdĕre to kill: see
-cide 1.]
●アチェのケースから、進化心理学的な前提に疑問符 を振ること(ある草稿から)
これまで「彼らは親や子を殺し、われわれも同じこ とをしている」という命題に対して〈なぜ〉殺すのか?という疑問ではなく〈どのように〉殺しているのか?という問いかけから叙述することを筆者は試みよう としてきた。ヒトである私たちは、さまざまな方法をもって、親や子を殺している。彼らは、ある種の情動のもとで、あるいは情愛の念にほだされて(あるいは 情愛の念を押し殺して)、そして直接的暴力やネグレクトにより殺害や遺棄を実行している。私たちも、また親や子を「殺して」はいるが、それは限りなく直接 的ではなく、間接的な行為を通してである。つまりこういうことだ。私たちもアチェも、ある者を殺害するとは、その殺害の前に、その者を、同胞としての人間 や正常人というカテゴリーから除外し、正常から逸脱した状態であると再定義することが必要になる。人間の延長上にあるが限りなく異なった他者化した準=人 間(quasi-human)として老人や子供を処遇することにより、ようやく「殺す」ことが可能になるのだ。私たちがおこなっている再定義とはつぎのよ うなものである。出生前の胚、重篤な症状をもつ障害者、脳死者、認知症者、QOL(生命の質)が低下した人、成年後見人が必要とされる人(「精神上の障害 により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」民法第七条)などというカテゴリーが設けられる。そして、治療や保護や監視を通して、彼らの法的権利——生 存権あるいは生きることにまつわる良いQOLを維持する権利——が剥奪するというふうに。
「親が子供に与えるものを親は失い、親は子供のう ちで死ぬ。親が子供に与えるものは、彼ら自身の意識である」——私たちが、奪ったり与えたりいるものは、それは「意識」である。進化行動学的帰結としての 子殺しや親殺しにおいては、それは「生殖にかかるコスト」や「遺伝子」である。ここで言う「意識」とは、多くの人類学者なら(遺伝により伝わらない後天的 に獲得される)「文化」であるというだろうし、進化学者のリチャード・ドーキンス(二〇〇六)に言わせれば「ミーム(meme)」と彼が表現しているもの がそれに相当するだろう。〈どのように?〉ということが枚挙にいとまがないほどの多様性の産出——私たちの身体の内部で日々おこなわれている自然の免疫応 答のメカニズムに似て——という性質をもつことは、この意識の組み合わせもまた無限に近いものであるという可能性を示している。
もちろん〈なぜ?〉という疑問に答えようとするこ とに、私たちは禁欲的である必要はない。ヘーゲルもまた一八〇五年頃に講義ノートの欄外に書いた「北アメリカの未開人は親を殺し、私たちも同じことをして いる」というヘーゲルの予感は、実は他ならぬ彼がその二年後に公刊した『精神現象学』という著作のなかでより抽象化されたかたちで彼なりの説明を与えられ ることになる。すなわち人間の「悟性(Verstandes)」——現在では知性や理解力とも訳される——がもつ「分離の活動」(分けるというはたらき; Tätigkeit des Scheidens, activity of parting/distinguishing)がそれをなしとげるというのである。「分けるというはたらきは悟性、最も不思議で偉大で、あるいはむしろ 絶対的な威力である悟性の力であり仕事である」(ヘーゲル 一九九七:四八)。コージェブ(一九八七)によると、私たちの悟性が実践している分離(わけるということ)は「自然に反して」ことであり、それは人間に与 えられた自然の延長にある「意識」がそれをなさしめる。このような悟性のなかにある矛盾は、弁証法によって解消されるわけだが、この自然とそれ以外のもの ——後者は私たちが「文化」と呼んでいるものであることは言うまでもない(レヴィ=ストロース 二〇〇〇)——をある意味で暴力的に切り分ける。それは死をもたらす殺害がまさに実践する暴力である。
屠畜や殺人が、私たちにとって恐怖の対象になるの は、単純に生と死の暴力的な分離の出来事だからではない。むしろ、そのことを「悟性」がもつ分離という働きを通して私たちが意識を通した時に、死んだ者以 外は誰も経験することのない「死」の情動——死の想像力——を私たち自身にもたらす。だが、私たちの死への感情には驚くべき多様性がある。エルツ(二〇〇 一:一二〇)は、それは「同じ社会にあっても、死のもたらす感情は、死者の社会的性格により強度が」異なってくるからであり「こうした感情をまったく欠い てくることさえもある」とまで述べている。屠畜や殺人をめぐる私たちの理解のパラドクスは、自己の死を嫌いかつ不死を望む人間が、なぜ他者が死を迎えるこ とにかんしては〈時間を前倒しにして〉も率先しておこなうのかということにある。それを「自己の死の否定/他者の死の容認」のテーゼと名づけてもよいだろ う。民族誌学的意味における理論的抽象度や説明の洗練度においていかに二世紀後の私たちがヘーゲルの言及の少なさについて身勝手な不満 を持とうとも、彼が指摘した「分離(わけるということ)」の意味のほうに幾度も私たちは回帰していかざるを得ない。
人間とそれ以外の動物の峻別を、前者を〈政治的動
物〉として特徴づけておこなったのは言うまでもない、アリストテレスその人であった。(女性と奴隷を人間のカテゴリーに含めないために現在では留保が必要
だが)、共同体=ポリスをつくる人間と、共同体そのものは「無駄なものはなにも造らない」自然がなせる産物である。人間は、群棲的動物であるが、そのなか
でも最も〈ポリス的=国家的動物
〉である。その人間の共同体の構築を支えるのは言語使用だという(「動物のなかで人間だけが言葉をもつ」からである)(アリストテレス
二〇〇一:九—一〇)。もし仮に「人間はなぜ動物殺しを宿命づけられているのですか?」と、アリストテレスに問うたならば、「それは、人間とそれ以外の動
物は類似の存在ではあるが、言葉をもち、共同体に生き、自然に従い善をなすから、動物の命を奪うことが正当化される。それゆえ、言語を弄せず、共同性を否
定し、善をなさないならば、それ(動物の生殺与奪)は正当化できないだろう」という答が得られるだろう。この点において、古代ギリシャと(クラストルの調
査した)アチェの社会(=共同体)における〈人間と動物の間の倫理〉の共通項を見出すことが可能になる。クラストルは言う。「もし獣を殺すことを続けたい
のなら、それを食べてはならない。土着の理論は、消費のレベルでの狩人とほふられた獣の結合は、「生産」のレベルでの狩人と生きた獣の分離をまねく、とい
う観念のみに支えられている」(クラストル 一九八七:一三九)(Clastres
1974:99)。殺害(=分離)と「生産」の隠喩ともいえる性交と摂食(=結合)のコントロールとは、私たち〈ポリス的=国家的動物〉が日々おこなって
いる活動にほかならないからである。
リンク
文献(→「殺人に関する考察」の文献を参照)