Descartes' sixth MEDITATIONES

第六省察
Descartes' sixth MEDITATIONES

池田光穂
解説
註:日本語の翻訳は三木清(青空文庫)訳を、ラ テン語テキストは下記のサイトから抽出した。なおページ記号や註釈記号は場合によっては削除しているために、オリジナルサイトの情報を正確に反映している のではない。文章のパラグラフ番号は、原文にないもので、6.n は第六省察のn番目のパラグラフを指している。
Full text of "Meditationes de prima philosophia" https://archive.org/stream/meditationesdepr23306gut/23306-8.txt
省察VI(デカルト)
De rerum materialium existentia, et reali mentis a corpore distinctione.
物質的なものの存在並びに精神と身体との実在的な区 別について。
| 以下の六省察の概要 |
|
| しかしそのほかに、我々が明晰に判明に理解する一切は、我々がそれを理
解する通りに、眞であるといふことを知ることがまた要求せられるのである。これは第四省察以前には證明せられることができなかつた。更に、物體的本性の判
明な概念を有しなければならないのであつて、かかる概念は一部分この第二省察において、また一部分は第五及び第六省察において作られてゐる。なほまたこれ
ら一切のことから、精神と身體とがまさにそのやうに把握せられる如く、別個の實體として明晰に判明に把握せられるものは、全く實在的に互に區別せられた實
體であることが結論せられねばならないのである。そしてこれは第六省察においてその通り結論せられてゐる。これはしかも、同じ第六省察において、我々はい
かなる物體も可分的としてでなければ理解せず、反對にいかなる精神も不可分的としてでなければ理解しないといふことによつて、確かめられてゐる。すなはち
我々はどのやうに小さい物體でもその半分を考へることはできるが、いかなる精神についてもその半分を考へることはできぬ。かやうにして兩者の本性は單に別
であるのみでなく、また或る點で相反することが認められる。 |
|
| 最後に、第六省察においては、悟性が想像力から分たれる。その區別の徴
表が記述せられる。精神が實在的に身體から區別せられることが證明せられる。にも拘らず精神が身體に、これと或る統一を成すほど密接に結合せられてゐるこ
とが示される。感覺から起るのを慣はしとするすべての誤謬が調査せられる。これを避け得る手段が開陳せられる。そして最後に、物質的なものの存在を結論し
得る一切の根據が提示せられる。それは、この根據がまさに證明することがら、すなはち、世界は實際にあるといふこと、また人間は身體を有するといふこと、
その他この類のことがらを證明するために、この根據が極めて有益であると考へるからではない、かかることがらについては健全な精神を有する何人も決して本
氣に疑はなかつたのである。さうではなくて、この根據を考察することによつて、これがかの我々を我々の精神及び神の認識に達せしめる根據ほど堅固でも分明
でもないことが認められる故である。從つてかの根據は人間の智能によつて知られ得る一切のうち最も確實で最も明證的である。ただこの一事を證明することを
私はこの省察において目的としたのである。かるが故に私はその中でまたたまたま取扱はれた他の種々の問題をここで枚擧しないことにする。 |
★
| 6.1
Reliquum est ut examinem an res materiales existant: et quidem jam ad
minimum scio illas, quatenus sunt purae Matheseos objectum, posse
existere, quandoquidem ipsas clare et distincte percipio. Non enim
dubium | est quin Deus sit capax ea omnia efficiendi quae ego sic
percipiendi sum capax; nihilque unquam ab illo fieri non posse
judicavi, nisi propter hoc quod illud a me distincte percipi
repugnaret. Praeterea ex imaginandi facultate, qua me uti experior, dum
circa res istas materiales versor, sequi videtur illas existere: nam
attentius consideranti quidnam sit imaginatio, nihil aliud esse apparet
quam quaedam applicatio facultatis cognoscitivae ad corpus ipsi intime
praesens ac proinde existens. |
なお残っているのは、物質的なものが存在 するかどうかを検討することである。そしてたしかに私は既に少くとも、それが、純粋数学の対象である限りにおい ては、存在し得ることを知っている、たしかに私はそれをかかるものとしては明晰かつ判明に知覚するのであるから。なぜなら、神が私のこのように知覚し能う すべてのものを作り出す力を有することは疑われないことであり、また私は、どのようなものでも神によって、それを私が判明に知覚することは矛盾であるとい う理由によるほかは、決して作られ得ぬことはない、と判断したからである。さらに、私が物質的なものにかかずらう場合にそれを用いるのを私が経験するとこ ろの想像の能力からして、かかる物質的なものは存在するということが帰結するように思われる。というのは、想像力とはいったい何であるかをいっそう注意深 く考察するとき、それは認識能力にまざまざと現前するところの、従って存在するところの物体に対する認識能力の或る適用以外のなにものでもないことがわか るから。 |
| Quod ut planum fiat, primo examino differentiam quae est inter imaginationem(51) et puram intellectionem. Nempe, exempli causa, cum triangulum imaginor, non tantum intelligo illud esse figuram tribus lineis comprehensam, sed simul etiam istas tres lineas tanquam praesentes acie mentis intueor, atque hoc est quod imaginari appello. Si vero de chiliogono velim cogitare, equidem aeque bene intelligo illud esse figuram constantem mille lateribus, ac intelligo triangulum esse figuram constantem tribus, | sed non eodem modo illa mille latera [89] imaginor, sive tanquam praesentia intueor: et quamvis tunc, propter consuetudinem aliquid semper imaginandi, quoties de re corporea cogito, figuram forte aliquam confuse mihi repraesentem, patet tamen illam non esse chiliogonum, quia nulla in re est diversa ab ea quam mihi etiam repraesentarem, si de myriogono, aliave quavis figura plurimorum laterum cogitarem; nec quicquam juvat ad eas proprietates, quibus chiliogonum ab aliis polygonis differt, agnoscendas. Si vero de pentagono quaestio sit, possum quidem ejus figuram intelligere, sicut figuram chiliogoni, absque ope imaginationis; sed possum etiam eandem imaginari(52), applicando scilicet aciem mentis ad ejus quinque latera, simulque ad aream iis contentam; et manifeste hic animadverto mihi peculiari quadam animi contentione opus esse ad imaginandum; qua non utor ad intelligendum: quae nova animi contentio differentiam inter imaginationem, et itellectionem puram | clare ostendit.[90] | 6.2 このことが明瞭になるように、私 はまず想像力と純粋な悟性作用との間に存する差異を検討する。言うまでもなく、例えば、私が三角形を想像するとき、私は 単にそれが三つの線によって囲まれた図形であることを理解するのみでなく、同時にまたこれらの三つの線をあたかも精神の眼に現前するもののごとくに直観す るのであって、そしてこれが想像すると私の称するところのものなのである。しかるにもし私が千角形について思惟しようと欲するならば、もちろん私は、三角 形が三辺から成る図形であることを理解するのと同様に、それが千辺から成る図形であることをよく理解するが、しかし私はこの千辺を三辺におけると同様に想 像すること、すなわち、あたかも精神の眼に現前するもののごとくに直観することはできないのである。また、たといそのとき、私が物体的なものについて思惟 するたびごとに、つねに何ものかを想像する習慣によって、おそらく何らかの図形を不分明に自分のうちに表現するにしても、それがしかし千角形でないことは 明かである。なぜならそれは、もし私が万角形について、あるいは他のどのようなはなはだ多くの辺を有する図形についてでも、思惟するならば、そのときにま た私が自分のうちに表現する図形と何ら異なるところがないし、またそれは、千角形を他の多角形から異ならせるところの固有性を認知するに何らの助けともな らないからである。しかるにもし問題が五角形についてであるならば、私はたしかにこの図形をば、千角の図形と同じように、想像力の助けなしに理解し得る が、しかしまたこれをば、言うまでもなく精神の眼をその五つの辺に、同時にまたこの辺によって囲まれた面積に向けることによって、想像し得るのである。そ してここに私は、想像するためには心の或る特殊の緊張が、すなわち理解するためには私の使わないような緊張が、私に必要であることを明かに認めるのであっ て、この心の新しい緊張は、想像力と純粋な悟性作用との間の差異を明晰に示している。 |
| Ad haec considero istam vim imaginandi quae in me est, prout differt a vi intelligendi, ad mei ipsius, hoc est, ad mentis meae essentiam non requiri; nam quamvis illa a me abesset, procul dubio manerem nihilominus ille idem, qui nunc sum; unde sequi videtur illam ab aliqua re a me diversa pendere; atque facile intelligo: si corpus aliquod existat cui mens sit ita conjuncta ut ad illud veluti inspiciendum pro arbitrio se applicet, fieri posse, ut per hoc ipsum res corporeas imaginer; adeo ut hic modus cogitandi in eo tantum a pura intellectione differat, quod mens, dum intelligit, se ad seipsam quodammodo convertat, respiciatque aliquam ex ideis, quae illi ipsi insunt; dum autem imaginatur, se convertat ad corpus, et aliquid in eo ideae vel a se intellectae, vel sensu perceptae conforme intueatur. Facile, inquam, intelligo imaginationem ita perfici posse, siquidem corpus existat; et quia nullus alius modus aeque conveniens occurrit ad illam explicandam, probabiliter inde conjicio corpus existere; | sed probabiliter tantum, et [91] quamvis accurate omnia investigem, nondum tamen video ex ea naturae corporeae idea distincta, quam in imaginatione mea invenio, ullum sumi posse argumentum, quod necessario concludat aliquod corpus existere. | 6.3 これに加えるに、私のうちにある ところのこの想像の力は、それが理解の力と異なるに応じて、私自身の本質にとって、言い換えると私の精神の本質にとって 必要とせられぬ、と私は考える。なぜなら、たといそれが私に存しなくても、疑いもなく私はそれにもかかわらず私が現在あるのと同一のものにとどまるであろ うから。そしてそこから、それが私とは別の或るものに懸っているということが帰結するように思われる。しかも、もし何らかの物体が存在していて、精神がこ れをいわば観察するために随意に自己をこれに向け得るというように、これに精神が結合せられているならば、まさにこのことによって私が物体的なものを想像 するということは生じ得ること、従って、この思惟の仕方が純粋な悟性作用と異なるのはただ、精神は、理解するときには、或る仕方で自己を自己自身に向わ せ、そして精神そのものに内在する観念の或るものを顧るが、しかるに想像するときには、自己を物体に向わせ、そしてそのうちに、自己によって思惟せられ た、あるいは感覚によって知覚せられた観念に一致する或るものを直観する、ということに存すること、を私は容易に理解する。私は言う、もしたしかに物体が 存在するならば、想像力がこのようにして成立し得ることを私は容易に理解する、と。そして想像力を説明するにいかなる他の同等に好都合な仕方も心に浮ばな いゆえに、私は蓋然的にそこから、物体は存在する、と推測する。しかしそれは単に蓋然的である。そして、たとい私が厳密にすべてのものを調べても、私の想 像力のうちに私が発見するところの物体的本性の判明な観念からしては、何らかの物体が存在することをば必然的に結論するいかなる論拠も取り出され得ないと いうことを私は見るのである。 |
| Soleo vero alia multa imaginari praeter illam naturam corpoream, quae est purae Matheseos objectum, ut colores, sonos, sapores, dolorem, et similia, sed nulla tam distincte; et quia haec percipio melius sensu, a quo videntur ope memoriae ad imaginationem pervenisse; ut commodius de ipsis agam, eadem opera etiam de sensu est agendum, videndumque an ex iis quae isto cogitandi modo, quem sensum appello, percipiuntur, certum aliquod argumentum pro(53) rerum corporearum existentia habere possim. | 6.4 しかるに私は、純粋数学の対象で あるところのこの物体的本性のほかに、どれもこれほど判明にではないが、他の多くのものを、例えば、色、音、味、苦痛、 及びこれに類するものを、想像するのを慣わしとしている。そして私はこれらのものをいっそうよく感覚によって知覚し、これらのものは感覚から記憶の助けを 藉りて想像力に達したと思われるゆえに、これらのものについていっそう適切に論じるためには、同時にまた感覚についても論じなければならず、そして私が感 覚と称するこの思惟の仕方によって知覚せられるところのものからして、物体的なものの存在を証すべき何らかの確実な論拠を得ることができるかどうかを見な ければならぬ。 |
| Et primo quidem apud me hic repetam quaenam illa sint quae antehac ut sensu percepta vera esse putavi, et quas ob causas id putavi; deinde etiam causas expendam, propter quas eadem postea in dubium revocavi; ac denique considerabo | quid mihi nunc de iisdem sit credendum. [92] | 6.5 そしてもちろんまず第一に、私は ここで、以前に、感覚によって知覚せられたものとして、真であると私の思ったものはいったい何であるか、またいかなる理 由で私はそれをそう思ったのか、を自分に想い起してみよう。次にまた、どういうわけで私はその同じものに後になって疑いをいれるに至ったかの理由を検討し てみよう。そして最後に、現在そのものについて私は何を信ずべきであるかを考察してみよう。 |
| Primo itaque sensi me habere caput, manus, pedes, et membra caetera, ex quibus constat illud corpus quod tanquam mei partem, vel forte etiam anquam me totum spectabam; sensique hoc corpus inter alia multa corpora versari, a quibus variis commodis, vel incommodis affici potest, et commoda ista sensu quodam voluptatis, et incommoda sensu doloris metiebar. Atque praeter dolorem et voluptatem sentiebam etiam in me famem, sitim, aliosque ejusmodi appetitus; itemque corporeas quasdam propensiones ad hilaritatem, ad tristitiam, ad iram, similesque alios affectus; foris vero, praeter corporum extensionem, et figuras, et motus, sentiebam etiam in illis duritiem, et calorem, aliasque tactiles qualitates; ac praeterea lumen, et colores, et odores, et sapores, et sonos, ex quorum varietate caelum, terram, maria, et reliqua corpora ab invicem distinguebam. Nec sane absque ratione ob ideas istarum omnium qualitatum quae cogitationi meae se offerebant, et | quas solas [93] proprie et immediate sentiebam, putabam me sentire res quasdam a mea cogitatione plane diversas, nempe corpora a quibus ideae istae procederent; experiebar enim illas absque ullo meo consensu mihi advenire, adeo ut neque possem objectum ullum sentire, quamvis vellem, nisi illud sensus organo esset praesens; nec possem non sentire cum erat praesens; cumque ideae sensu perceptae essent multo magis vividae et expressae, et suo etiam modo magis distinctae, quam ullae ex iis quas ipse prudens et sciens meditando effingebam, vel memoriae meae impressas advertebam, fieri non posse videbatur ut a meipso procederent; ideoque supererat ut ab aliis quibusdam rebus advenirent. Quarum rerum cum nullam aliunde notitiam haberem quam ex istis ipsis ideis, non poterat aliud mihi venire in mentem quam illas iis similes esse. Atque etiam quia recordabar me prius usum fuisse sensibus quam ratione, videbamque ideas quas ipse effingebam non tam expressas esse, quam | illae [94] erant quas sensu percipiebam, et plerumque ex earum partibus componi, facile mihi persuadebam nullam plane me habere in intellectu, quam non prius habuissem in sensu. Non etiam sine ratione corpus illud, quod speciali quodam jure meum appellabam, magis ad me pertinere quam alia ulla arbitrabar; neque enim ab illo poteram unquam sejungi, ut a reliquis; omnes appetitus et affectus in illo, et pro illo sentiebam; ac denique dolorem et titillationem voluptatis in ejus partibus, non autem in aliis extra illud(54) positis advertebam. Cur vero ex isto nescio quo doloris sensu quaedam animi tristitia, et ex sensu titillationis laetitia quaedam consequatur, curve illa nescio quae vellicatio ventriculi, quam famem voco, me de cibo sumendo admoneat, gutturis vero ariditas de potu, et ita de caeteris, non aliam sane habebam rationem, nisi quia ita doctus sum a natura; neque enim ulla plane est affinitas (saltem quam ego intelligam) inter istam vellicationem, et cibi sumendi volun|tatem, sive inter sensum rei dolorem inferentis, et [95] cogitationem tristitiae ab isto sensu exortae. Sed et reliqua omnia quae de sensuum objectis judicabam, videbar a natura didicisse: prius enim illa ita se habere mihi persuaseram, quam rationes ullas, quibus hoc ipsum probaretur, expendissem. | 6.6 かようにしてまず第一に私は、私 がいわば私の部分あるいはおそらくいわば私の全体とさえ看做したこの身体を構成するところの、頭、手、足、及びその他の 器官を有することを感覚した。また私は、この身体が他の多くの物体の間に介在し、これらの物体から、あるいは都合好く、あるいは都合悪く、種々の仕方で影 響せられ得ることを感覚した、そして私はこの都合好いものを或る快楽の感覚によって、また都合悪いものを苦痛の感覚によって量ったのである。なおまた、苦 痛と快楽とのほか、私はまた私のうちに飢、渇、及びこの種の欲望を、同じくまた歓びへの、悲しみへの、怒りへの、或る身体的傾向性及び他のこれに類する情 念を感覚した。そして外においては、物体の延長、及び形体、及び運動のほか、私はまた物体において堅さ、熱、及び他の触覚的性質を感覚した。さらにまた私 は光、及び色、及び香、及び味、及び音を感覚し、これらのものの様々の変化によって私は天、地、海、及びその他の物体を相互に区別したのである。そして実 に、私の思惟に現われたところのこれらすべての性質の観念——そしてただこれらの観念のみを私は本来かつ直接に感覚したのであるが——によって見れば、私 が私の思惟とはまったく別の或るものを、すなわちこれらの観念のそこから出てきたところの物体を感覚すると考えたのは、理由のないことではなかった。とい うのは、私はこれらの観念が何ら私の同意なしに私にやってくることを経験した、従って、もし対象が感覚器官に現前していなかったならば、私はこれを感覚し ようと欲しても感覚し得なかったし、また現前していたときには、感覚すまいと欲しても感覚せざるを得なかったからである。また、感覚によって知覚せられた 観念は、自分であらかじめ知って意識的に省察することにおいて私が作り出した観念のどれよりも、あるいは私の記憶に刻印せられたものとして私が認めた観念 のどれよりも、遥かに多くの生気があって明瞭であり、またそれ自身の仕方でいっそう判明でさえあったから、これらの観念が私自身から出てくるということは あり得ないように思われた。かようにして、これらの観念は、或る他のものから私にやってきたと考えるほかなかったのである。そして私はかかるものについ て、まさにこれらの観念からのほか、他のどこからも知識を得なかったゆえに、かかるものがこれらの観念に類似しているというよりほかの考えは私の心に浮か び得なかったのである。なおまた私は、私が以前に理性よりもむしろ感覚を使用したことを想い起したし、また自分で作り出した観念が感覚によって知覚した観 念ほど明瞭なものでなく、そして前者の多くが後者の部分から構成せられていることを見たゆえに、私は、私がまず感覚のうちに有しなかったところのいかなる 観念も私はまったく悟性のうちに有しないということをば、容易に自分に説得したのである。さらにまた、私が或る特殊の権利をもって私のものと称したところ のこの身体は他のいずれの物体よりもいっそう多く私に属すると私が信じたのは理由のないことではなかった。なぜというに、私は身体からは、その他の物体か らのように、決して切り離され得なかったし、また私はすべての欲望や情念を身体のうちにかつ身体のために感覚したし、そして最後に私は苦痛及び快楽のくす ぐりを身体の部分において、身体の外に横たわる他の物体においてではなく、認めたからである。しかし何故に、この何か知らない苦痛の感覚から心の或る悲し みが生じてくるのか、また快いくすぐりの感覚から或る悦びが生じてくるのか、あるいは何故に、私が飢えと呼ぶこの何か知らない腹部のいらだちは私に食物を 取ることについて忠告し、咽喉の乾きはしかし飲むことについて忠告するのか、その他これに類することが生じるのは何故であるかについては、私は自然によっ てこのように教えられたからという以外、実に私は他の説明を有しなかった。なぜなら、腹部のいらだちと食物を取ろうとする意志との間には、あるいは苦痛を もたらすものの感覚と、この感覚から出てきた悲しみの意識との間には、いかなる類同も(少くとも私の理解し得たような類同は)まったく存しないからであ る。むしろ、私が感覚の対象について判断したその他の一切のこともまた、自然によって教えられたように思われたのである。というのは、私は、それら一切の ことが私の判断したごとくであるということをば、まさにこのことを証明する何らかの根拠を考量するよりも前に、自分に説得したのであるから。 |
| Postea vero multa
paulatim experimenta fidem omnem quam sensibus
habueram labefactarunt, nam et interdum turres quae rotundae visae
fuerant e longinquo, quadratae apparebant e propinquo, et statuae
permagnae in earum fastigiis stantes, non magnae e terra spectanti
videbantur; et talibus aliis innumeris in rebus sensuum externorum
judicia falli deprehendebam; nec externorum duntaxat, sed etiam
internorum, nam quid dolore intimius esse potest? atqui audiveram
aliquando ab iis quibus crus aut brachium fuerat abscissum, se sibi
videri adhuc interdum dolorem sentire in ea parte corporis qua
carebant;
ideoque etiam in me non plane certum esse videbatur membrum aliquod
mihi
dolere, quamvis | sentirem in eo dolorem. Quibus etiam duas maxime [96]
generales dubitandi causas nuper adjeci: prima erat, quod nulla unquam
dum vigilo me sentire crediderim, quae non etiam inter dormiendum
possim
aliquando putare me sentire; cumque illa quae sentire mihi videor in
somnis, non credam a rebus extra me positis mihi advenire, non
advertebam, quare id potius crederem de iis quae sentire mihi videor
vigilando. Altera erat, quod cum authorem meae originis adhuc
ignorarem,
vel saltem ignorare me fingerem, nihil videbam obstare quo minus essem
natura ita constitutus ut fallerer, etiam in iis quae mihi verissima
apparebant. Et quantum ad rationes quibus antea rerum sensibilium
veritatem mihi persuaseram, non difficulter ad illas respondebam. Cum
enim viderer ad multa impelli a natura quae ratio dissuadebat, non
multum fidendum esse putabam iis quae a natura docentur. Et quamvis
sensuum perceptiones a voluntate mea non penderent, non ideo
concludendum esse pu|tabam illas a rebus a me diversis procedere, [97]
quia forte aliqua esse potest in meipso facultas, etsi mihi nondum
cognita, illarum effectrix. |
6.7 しかるにその後多くの経験が、次 第次第に、感覚に対して私の有したすべての信頼を毀していった。なぜなら、時々、遠くからは円いものと思われた塔が、近 くでは四角なものであることが明かになったことがあったし、またこれらの塔の頂に据えられた非常に大きな彫像が、地上から眺めるときには大きなものと思わ れなかったことがあった、そして私はかくのごとき他の無数のものにおいて外的感覚の判断が過つことを見つけたから。単に外的感覚の判断のみではない、また 内的感覚の判断もそうであった。なぜなら、何が苦痛よりもいっそう内部的であり得るだろうか、しかも私はかつて、脚あるいは腕を切断した人々から、自分で はまだ時々この失くした身体の部分において苦痛を感じるように思われるということを聞いた、従ってまた、私においても、私が身体の或る部分において苦痛を 感じるとしても、その部分が私に苦痛を与えるということは、まったく確実ではないように思われたから。これらの上にまた私は最近二つの極めて一般的な疑い の原因を加えたのである。その第一のものは、私の醒めているときに私が感覚すると信じたもので、眠っている間にまたいつか私が感覚すると考え得ないものは 決してなく、そして私が睡眠中に感覚すると思われるものは、私の外に横たわるものから私にやってくると私は信じないゆえに、どうしてこのことをむしろ私の 醒めているときに感覚すると思われるものについて私が信じるのであるか、私にはわからなかったということであった。もう一つの疑いの原因は、私は私の起原 の作者をこれまで知らなかったゆえに、あるいは少くとも知らないと仮定したゆえに、私に極めて真なるものと見えたものにおいてさえ過つというように私が本 性上作られているということをば、いかなるものも妨げるものを私は見なかったということであった。そして以前に私が感覚的なものの真理を説得させられたと ころの理由についていえば、これに対して答えることは困難でなかった。というのは、理性が制止した多くのものに私は自然によって駆り立てられるように思わ れたので、自然によって教えられるものに多く信頼すべきではないと私は考えたから。またたとい感覚の知覚は私の意志に懸っていないとしても、だからといっ てそれが私とは別のものから出てくると結論すべきではないと私は考えたから。なぜならおそらく、私にはまだ認識せられていないとはいえ、私自身のうちには かかる知覚を作り出すものとして何らかの能力があるかもしれないからである。 |
| Nunc autem postquam incipio meipsum, meaeque authorem originis melius nosse, non quidem omnia quae habere videor a sensibus, puto esse temere admittenda; sed neque etiam omnia in dubium revocanda. | 6.8 しかしながら今、私は私自身並び に私の起原の作者をいっそうよく知り始めるに至って、感覚によって得ると思われるすべてのものは、もちろん軽々しく容認 せらるべきではないが、しかしまたそのすべてのものに疑いをいれるべきでもない、と私は考えるのである。 |
| Et primo quoniam
scio omnia quae clare et distincte intelligo, talia a
Deo fieri posse qualia illa intelligo, satis est quod possim unam rem
absque altera clare et distincte intelligere, ut certus sim unam ab
altera esse diversam, quia potest saltem a Deo seorsim poni; et non
refert a qua potentia id fiat, ut diversa existimetur; ac proinde, ex
hoc ipso quod sciam me existere, quodque interim nihil plane aliud ad
naturam, sive essentiam meam pertinere animadvertam, praeter hoc solum
quod sim res cogitans, recte concludo, meam essentiam in hoc uno
consistere, quod sim res cogitans. Et quamvis fortasse (vel potius ut
postmodum dicam, pro | certo) habeam corpus, quod mihi valde arcte [98]
conjunctum est, quia tamen ex una parte claram et distinctam habeo
ideam
mei ipsius quatenus sum tantum res cogitans, non extensa; et ex alia
parte distinctam ideam corporis, quatenus est tantum res extensa, non
cogitans, certum est me a corpore meo revera esse distinctum, et absque
illo posse existere. |
6.9 そしてまず第一に、私が明晰かつ 判明に理解するすべてのものは、私が理解する通りのものとして神によって作られ得ることを私は知っているからして、或る 一つのものが他のものと異なることが私に確実であるためには、私がその一つのものをば他のものを離れて明晰かつ判明に理解し得るということで十分である。 なぜならそのものは少くとも神によって分離して措定せられることができるから。それに、そのものが異なるものと思量せられるためには、いかなる力によって かく分離して措定せられるということが生ずるかは、問題にならない。かようにして、まさにこのこと、すなわち、私は存在することを私が知っているというこ と、しかも、私は思惟するものであるということのみのほか他の何ものもまったく私の本性すなわち私の本質に属しないことに私が気づいているということか ら、私の本質はこの一つのこと、すなわち私は思惟するものであるということに存することを、私は正当に結論するのである。そしてたとい私はたぶん(あるい はむしろ、すぐ後に言う通り、確かに)私と極めて密接に結合せられているところの身体を有するにしても、しかし一方では、私が延長を有するものではなくて ただ思惟するものである限りにおいて、私は私自身の明晰で判明な観念を有し、そして他方では、物体が思惟するものではなくてただ延長を有するものである限 りにおいて、私は物体の判明な観念を有するゆえに、私が私の身体から実際に区別せられたものであるということ、そして私がこの身体なしに存在し得るという ことは、確かである。 |
| Praeterea invenio
in me facultates specialibus quibusdam modis
cogitandi(55), puta facultates imaginandi, et sentiendi, sine quibus
totum me possum clare et distincte intelligere, sed non vice versa
illas
sine me, hoc est sine substantia intelligente cui insint:
intellectionem
enim nonnullam in suo formali conceptu includunt(56) unde percipio
illas
a me, ut modos a re distingui. Agnosco etiam quasdam alias facultates,
ut locum mutandi, varias figuras induendi, et similes, quae quidem, non
magis quam praecedentes, absque aliqua substantia cui insint, possunt
intelligi, nec proinde etiam absque illa existere, | sed manifestum
[99]
est has, siquidem existant inesse debere substantiae corporeae sive
extensae, non autem intelligenti, quia nempe aliqua extensio, non autem
ulla plane intellectio, in earum claro et distincto conceptu
continetur.
Jam vero est quidem in me passiva quaedam facultas sentiendi, sive
ideas
rerum sensibilium recipiendi et cognoscendi, sed ejus nullum usum
habere
possem, nisi quaedam activa etiam existeret, sive in me, sive in alio,
facultas istas ideas producendi, vel efficiendi. Atque haec sane in me
ipso esse non potest, quia nullam plane intellectionem praesupponit, et
me non cooperante, sed saepe etiam invito ideae istae producuntur: ergo
superest ut sit in aliqua substantia a me diversa, in qua quoniam omnis
realitas vel formaliter vel eminenter inesse debet, quae est objective
in ideis ab ista facultate productis, (ut jam supra animadverti) vel
haec substantia est corpus, sive natura corporea, in qua nempe omnia
formaliter continentur quae in ideis objective; vel certe Deus est, vel
aliqua crea|tura corpore nobilior in qua continentur eminenter. [100]
Atqui, cum Deus non sit fallax, omnino manifestum est illum nec per se
immediate istas ideas mihi immittere, nec etiam mediante aliqua
creatura, in qua earum realitas objectiva non formaliter, sed eminenter
tantum contineatur. Cum enim nullam plane facultatem mihi dederit ad
hoc
agnoscendum, sed contra, magnam propensionem ad credendum illas a rebus
corporeis emitti, non video qua ratione posset intelligi ipsum non esse
fallacem, si aliunde quam a rebus corporeis emitterentur: Ac proinde
res
corporeae existunt. Non tamen forte omnes tales omnino existunt, quales
illas sensu comprehendo; quoniam ista sensuum comprehensio in multis
valde obscura est et confusa; sed saltem illa omnia in iis sunt, quae
clare et distincte intelligo, id est omnia generaliter spectata quae in
purae Matheseos objecto comprehenduntur. |
6.10 なおまた私は私のうちに思惟の 仕方における或る特殊な能力、すなわち想像の能力や感覚の能力を発見するが、私はこれらの能力なしに全体としての私を明晰 かつ判明に理解することができるに反し、逆にこれらの能力は私なしには、言い換えるとこれらの能力がそのうちに内在する思惟的実体なしには理解せられるこ とができない。なぜなら、これらの能力は自己の形相的概念のうちに或る悟性作用を含み、そこから私は、あたかも様態が物から区別せられているごとく、これ らの能力が私から区別せられていることを知覚するからである。さらにまた私は或る他の能力、例えば場所を変じる能力、種々の形体をとる能力、その他これに 類するものを認知するが、これらの能力もたしかに、前のものと同じく、これらの能力がそのうちに内在する或る実体を離れては理解せられることができず、 従ってまたこの実体を離れては存在することができない。むしろこれらの能力が、もしたしかに存在するならば、物体的実体すなわち延長を有する実体に、しか し思惟的実体にではなく、内在しなくてはならぬということは明瞭である。なぜなら、これらの能力の明晰で判明な概念のうちには、もちろん或る延長が含まれ るが、しかしいかなる悟性作用もまったく含まれないからである。しかるに今たしかに私のうちには感覚する或る受動的な能力、すなわち感覚的なものの観念を 受取り認識する能力があるが、しかし私はこれをば、もし私のうちに、あるいは他のもののうちに、或る能動的な、かかる観念を生産するあるいは実現する能力 がまた存在しなかったならば、何ら用い得なかったであろう。しかもこの能動的な能力は実に私自身のうちに存することができない。なぜなら、それはいかなる 悟性作用をもまったく予想しないし、またかかる観念は私が協力することなしに、かえってしばしば私の意志に反してさえ生産せられるから。ゆえにそれは私と は別の或る実体のうちに存すると考えるほかはない。そしてこの実体のうちには(既に上に注意したごとく)この能力によって生産せられた観念のうちに客観的 に有る一切の実在性が形相的にか優越的にか内在しなくてはならないからして、この実体は物体、すなわちもちろんかかる観念が客観的に含む一切のものを形相 的に含むところの物体的本性であるか、それとも神そのものであるか、それともかかる一切のものを優越的に含むところの、物体よりも高貴な或る被造物である かである。しかるに、神は欺瞞者でないゆえに、神がかかる観念を、直接に自己自身によって私に伝えるのではないこと、またかかる観念の客観的実在性をば形 相的にではなく単に優越的に含むところの或る被造物の媒介によって私に伝えるのでもないことは、まったく明白である。なぜなら、神はこれがそのような被造 物の媒介によるのであると認知するいかなる能力をもまったく私に与えなかったし、かえって反対にかかる観念が物体的なものから発すると信じる大きな傾向性 を私に与えたのであるから、もしかかる観念が物体的なものからよりほかの他のところから発したとしたならば、どういうわけで神が欺瞞者でないことが理解せ られ得るのか私にはわからないからである。従って、物体的なものは存在する。しかしおそらくそのすべてはまったく私がそれを感覚によって把捉するがごとき ものとして存在するのではなかろう、この感覚の把捉は多くの場合極めて不明瞭であり不分明であるから。しかしながら少くともそのうちにおいて私が明晰かつ 判明に理解する一切のもの、言い換えると、一般的に見るならば、純粋数学の対象のうちに包括せられる一切のものは、実際に有るのである。 |
| Quantum autem
attinet ad reliqua quae vel tantum particularia sunt, ut
quod sol sit talis magnitudinis, aut figurae etc. vel minus clare
intellecta, ut lumen, sonus, dolor, et similia, quamvis valde dubia et
incerta sint, hoc tamen ipsum, quod Deus non sit fallax, quodque
idcirco
fieri non possit ut ulla falsitas in meis opinionibus reperiatur, nisi
aliqua etiam sit in me facultas a Deo tributa ad illam emendandam,
certam mihi spem ostendit veritatis etiam in iis assequendae. Et sane
non dubium est quin ea omnia quae doceor a natura aliquid habeant
veritatis: Per naturam enim generaliter spectatam nihil nunc aliud quam
vel Deum ipsum, vel rerum creatarum coordinationem a Deo institutam
intelligo; nec aliud per naturam meam in particulari, quam complexionem
eorum omnium quae mihi a Deo sunt tributa. |
6.11 しかるにその余のものについて いえば、それらのものは、例えば、太陽はかくかくの大きさまたは形体のものである、等々のごとく、単に特殊的なものである か、それとも、例えば、光、音、苦痛、及びこれに類するものののごとく、より少く明晰に理解せられたものであるかであるが、たといそれらのものは極めて疑 わしい不確実なものであるにしても、しかもまさにこのこと、すなわち、神は欺瞞者ではないということ、従ってまた私の意見のうちにはいかなる虚偽も、これ を訂正する或る能力がまた私のうちに神によって賦与せられている場合のほかは、見出されることがあり得ないということは、それらのものにおいてもまた真理 に達し得る確実な希望を私に示すのである。そして実に自然によって教えられるすべてのものが何らかの真理を有するはずであるということは疑い得ないことで ある。なぜなら、私がいま一般的に見られた自然というのは、神そのもの、それとも神によって制定せられたところの被造物の整序以外の何物でもなく、また特 殊的に私の自然というのは、神によって私に賦与せられたすべてのものの集合体以外のものではないからである。 |
| Nihil autem est quod me ista natura magis expresse doceat quam quod habeam corpus, cui male est cum dolorem sentio: quod cibo, vel potu indiget, cum famem, aut sitim patior, et similia; nec proinde dubitare debeo, quin aliquid in eo sit veritatis. | 6.12 ところで、私が身体を有するこ と、すなわち、私が苦痛を感覚するときにはその具合が悪く、そして私が飢えまたは渇きに悩むときには食物あるいは飲料を必 要とし、等々といった、身体を有することよりもいっそう明白にこの自然が私に教えることは何もない。従ってまたこのことのうちに或る真理が存することを私 は疑うべきではないのである |
| Docet etiam natura
per istos sensus | doloris, famis, sitis, etc. [102]
me non tantum adesse meo corpori ut nauta adest navigio, sed illi
arctissime esse conjunctum, et quasi permixtum, adeo ut unum quid cum
illo componam; alioqui enim cum corpus laeditur, ego, qui nihil aliud
sum quam res cogitans, non sentirem idcirco dolorem, sed puro
intellectu
laesionem istam perciperem, ut nauta visu percipit, si quid in nave
frangatur; et cum corpus cibo, vel potu indiget, hoc ipsum expresse
intelligerem, non confusos famis et sitis sensus haberem. Nam certe
isti
sensus sitis, famis, doloris, etc. nihil aliud sunt quam confusi quidam
cogitandi modi ab unione et quasi permixtione mentis cum corpore exorti. |
6.13 また自然はこれら苦痛、飢え、 渇き、等々の感覚によって、あたかも水夫が船のなかにいるごとく私が単に私の身体のなかにいるのみでなく、かえって私がこ の身体と極めて密接に結合せられ、そしていわば混合せられていて、かくてこれと或る一体を成していることを教えるのである。というのは、もしそうでないと すれば、身体が傷つけられるとき、私すなわち思惟するもの以外の何物でもない私は、そのために苦痛を感じないはずであり、かえってあたかも水夫が船のなか で何かが毀れるならば視覚によってこれを知覚するごとく、私はこの負傷を純粋な悟性によって知覚するはずであり、また身体が食物あるいは飲料を必要とする とき、私は単純にこのことを明白に理解し、飢えや渇きの不分明な感覚を有しないはずであるからである。なぜなら確かに、これら渇き、飢え、苦痛、等々の感 覚は、精神と身体との結合と、いわば混合とから生じた或る不分明な思惟の仕方にほかならないから。 |
| Praeterea etiam
doceor a natura varia circa meum corpus alia corpora
existere, ex quibus nonnulla mihi prosequenda sunt, alia fugienda. Et
certe ex eo quod valde diversos sentiam colores, sonos, odores,
sapores,
calorem, duritiem, et similia, recte concludo, aliquas esse in
corporibus, a quibus variae istae sensuum perceptiones | [103]
adveniunt, varietates iis respondentes, etiamsi forte iis non similes;
atque ex eo quod quaedam ex illis perceptionibus, mihi gratae sint,
aliae ingratae, plane certum est meum corpus, sive potius me totum,
quatenus ex corpore et mente sum compositus, variis commodis et
incommodis a circumjacentibus corporibus affici posse. |
6.14 さらにまた私は自然によって、 私の身体のまわりに、その或るものは私にとって追い求むべきものであり、或るものは避け逃るべきものであるところの、他の 種々異なる物体が存在することを教えられる。そして確かに、私が極めて異なる色、音、香、味、熱、堅さ、及びこれに類するものを感覚するということから、 私は、これら種々に異なる感覚の知覚がそこからやってくる物体のうちに、これらの知覚にたといおそらく類似していないにしても対応している或る異種性が存 する、と正当に結論するのである。なおまた、かかる知覚のうち或るものは私にとって快適であり、或るものは不快であるということから、私の身体が、あるい はむしろ、私が身体と精神とから成っている限りにおいて、全体としての私が、そのまわりを取り繞っている物体によって、あるいは都合好く、あるいは都合悪 く、種々異なる仕方で影響せられ得るということは、まったく確かである。 |
| Multa vero alia
sunt quae, etsi videar a natura doctus esse, non tamen
revera ab ipsa, sed a consuetudine quadam inconsiderate judicandi
accepi, atque ideo(57) falsa esse facile contingit; ut quod omne
spatium, in quo nihil plane occurrit quod meos sensus moveat, sit
vacuum; quod in corpore, exempli gratia, calido aliquid sit plane
simile
ideae caloris quae in me est: in albo aut viridi sit eadem albedo aut
viriditas quam sentio; in amaro aut dulci idem sapor et sic de
caeteris;
quod et astra et turres, et quaevis alia remota corpora ejus sint
tantum
magnitudinis et figurae, quam sensibus meis exhibent, et alia ejusmodi.
Sed ne quid in hac re non satis distincte percipiam, accura|tius [104]
debeo definire quid proprie intelligam, cum dico me aliquid doceri a
natura; nempe hic naturam strictius sumo, quam pro complexione eorum
omnium quae mihi a Deo tributa sunt; in hac enim complexione multa
continentur quae ad mentem solam pertinent, ut quod percipiam id quod
factum est infectum esse non posse, et reliqua omnia quae lumine
naturali sunt nota, de quibus hic non est sermo; multa etiam quae ad
solum corpus spectant, ut quod deorsum tendat, et similia de quibus
etiam non ago, sed de iis tantum quae mihi ut composito ex mente et
corpore a Deo tributa sunt. Ideoque haec natura docet quidem ea
refugere
quae sensum doloris inferunt et ea prosequi quae sensum voluptatis, et
talia; sed non apparet illam praeterea nos docere ut quicquam ex istis
sensuum perceptionibus sine praevio intellectus examine de rebus extra
nos positis concludamus, quia de iis verum scire ad mentem solam, non
autem ad compositum videtur pertinere. Ita quamvis stella non magis
oculum | meum quam ignis exiguae facis afficiat, nulla tamen in eo
[105]
realis, sive positiva propensio est ad credendum illam non esse
majorem,
sed hoc sine ratione ab ineunte aetate judicavi; et quamvis ad ignem
accedens sentio calorem, ut etiam ad eundem nimis prope accedens sentio
dolorem, nulla profecto ratio est quae suadeat in igne aliquid esse
simile isti calori; ut neque etiam isti dolori, sed tantummodo in eo
aliquid esse, quodcunque demum sit, quod istos in nobis sensus caloris
vel doloris efficiat: et quamvis etiam in aliquo spatio nihil sit quod
moveat sensum, non ideo sequitur in eo nullum esse corpus, sed video me
in his aliisque permultis ordinem naturae pervertere esse assuetum,
quia
nempe sensuum perceptionibus, quae proprie tantum a natura datae sunt
ad
menti significandum quaenam composito, cujus pars est, commoda sint vel
incommoda, et eatenus sunt satis clarae et distinctae, utor tanquam
regulis certis ad immediate dignoscendum quaenam sit corporum extra nos
positorum essentia, de qua tamen | nihil nisi valde obscure et confuse
significant. |
6.15 しかしながら、自然が私に教え たもののように見えても、実際は自然からではなく、かえって無思慮に判断する或る習慣から私が受取った他の多くのものがあ る、従って容易にこれらのものは偽であることが生じ得る。すなわち、その中には私の感覚に影響を与える何ものもまったく現われない一切の空間は真空である とすること、また、例えば、熱い物体のうちには私のうちにある熱の観念にまったく類似する或るものがあり、白い物体または緑の物体のうちには私の感覚する のと同じ白または緑があり、苦い物体または甘い物体のうちにはこれと同じ味があり、その他の場合にも同様のことがあるとすること、また、星や塔、その他何 でも遠く離れた物体は単に私の感覚に現われるのと同じ大きさや形体のものであるとすること、その他この種のことが、それである。しかるに、これらのことが らにおいて私が十分に判明に知覚しない何ものもないようにするためには、私が或ることを自然によって教えられると言うとき、何を本来意味するかをいっそう 厳密に定義しなくてはならぬ。すなわち私はここに自然をば、神によって私に賦与せられたすべてのものの集合体という意味よりもいっそう狭い意味に解する。 というのは、この集合体のうちにはただ精神のみに属する多くのもの、例えば、為されたことは為されなかったことであることができぬと私が知覚すること、及 びその他、自然的な光によって知られているすべてのものが、含まれるが、これらについてはここでは言及しないし、またそのうちにはさらに、ただ物体のみに 関する多くのもの、例えば、物体は下に向うということ、及びこれに類すること、が含まれるが、これらについてもまたここでは問題でなく、かえってただ、精 神と身体とからの合成体としての私に、神によって賦与せられたもののみが問題なのであるからである。従ってまた、この自然はたしかに、苦痛の感覚をもたら すものを避け逃れ、そして快楽の感覚をもたらすものを追い求むること、及びかかる性質のことを教えるが、しかしこの自然がその上になお、これらの感覚の知 覚から、悟性のあらかじめの考査なしに、我々の外に横たわるものについて何かを結論することを我々に教えるということは明かではないのである、なぜなら、 かかるものについて真を知るということはただ精神のみに属し、合成体には属しないように思われるから。かようにして、たとい星は私の眼を小さい松明の火よ りもいっそう多くは刺戟しないにしても、かかる合成体としての私のうちにはしかし星がこの火よりも大きくないと信ぜしめる何らの実在的なあるいは積極的な 傾向性も存せず、かえって私は根拠なしに若い時分からこのように判断したのである。また、たとい火に近づくと私は熱を感覚し、そして余りに近くそれに近づ くと私は苦痛を感覚しさえするにしても、実際、火のうちにはこの熱に類似する或るものがあると、またこの苦痛に類似する或るものがあると、私に説得する何 らの根拠も存せず、かえってただ、火のうちには我々においてこれらの熱あるいは苦痛の感覚を喚び起す或るもの——それが結局どのようなものであろうとも ——があるということを私に説得する根拠が存するに過ぎないのである。さらに、たといまた或る空間のうちに感覚に影響を与える何物も存しないにしても、だ からといってこの空間のうちには何らの物体も存しないということは帰結せず、かえって私は、私がこの場合に、また他の非常に多くの場合に、自然の秩序を歪 曲するのを慣わしとすることを見るのである。なぜなら実に、感覚の知覚は本来ただ精神に、精神がその部分であるところの合成体にとっていったい何が都合好 いものあるいは都合悪いものであるかを指示するために、自然によって与えられており、そしてその限りにおいて十分に明晰で判明であるが、私はこの知覚をあ たかも我々の外に横たわる物体の本質がいったい何であるかを直接に弁知するための確実な規則であるかのように使用するのであって、かかる本質についてはし かるにこの知覚は極めて不明瞭にそして不分明にでなければ何物も指示しないからである。 |
| Atqui jam ante
satis perspexi qua ratione, non obstante Dei bonitate,
judicia mea falsa esse contingat. Sed nova hic occurrit difficultas
circa illa ipsa quae tanquam persequenda vel fugienda mihi a natura
exhibentur; atque etiam circa internos sensus in quibus errores videor
deprehendisse: Ut cum quis grato cibi alicujus sapore delusus venenum
intus latens assumit. Sed nempe tunc tantum a natura impellitur ad
illud
appetendum in quo gratus sapor consistit; non autem ad venenum quod
plane ignorat; nihilque hinc aliud concludi potest quam naturam istam
non esse omnisciam: quod non mirum, quia, cum homo sit res limitata,
non
alia illi competit quam limitatae perfectionis. |
6.16 ところで既に前に私は、どうい うわけで、神の善意にもかかわらず、私の判断の偽であることが生ずるのかという理由を十分に洞見した。しかしながらここ に、あたかも追い求むべきものあるいは避け逃るべきもののように自然によって私に示されるものそのものに関して、さらにまた私がそのうちにおいて誤謬を発 見したと思われる内部感覚に関して、新しい困難が現われる。例えば、ひとが或る食物の快い味に欺かれて、中に隠されている毒をも一緒に取る場合のごときが それである。しかしもちろん、この場合、彼はただそのうちに快い味が存するものを欲求するように自然によって駆り立てられるのであって、彼がまったく知ら ない毒を欲求するように駆り立てられるのではない。かくてここから結論せられ得ることは、この自然は全智ではないということ以外の何物でもないのである。 そしてこれは驚くべきことではない、なぜなら、人間は制限せられたものであるゆえに、彼には制限せられた完全性しかふさわしくないから。 |
| At vero non raro
etiam in iis erramus ad quae a natura impellimur; ut
cum ii qui aegrotant, potum vel cibum appetunt sibi paulo post
nociturum. Dici forsan hic poterit illos ob id errare quod natura eorum
sit corrupta: sed | hoc difficultatem non tollit, quia non minus [107]
vere homo aegrotus creatura Dei est quam sanus; nec proinde minus
videtur repugnare illum a Deo fallacem naturam habere. Atque ut
horologium ex rotis, et ponderibus confectum non minus accurate leges
omnes naturae observat, cum male fabricatum est, et horas non recte
indicat, quam cum omni ex parte artificis voto satisfacit: ita, si
considerem hominis corpus quatenus machinamentum quoddam est ex
ossibus,
nervis, musculis, venis, sanguine, et pellibus ita aptum et compositum,
ut, etiamsi nulla in eo mens existeret, eosdem tamen haberet omnes
motus
qui nunc in eo non ab imperio voluntatis, nec proinde a mente
procedunt(58), facile agnosco illi aeque naturale fore, si, exempli
causa, hydrope laboret, eam faucium ariditatem pati quae sitis sensum
menti inferre solet, atque etiam ab illa ejus nervos, et reliquas
partes
ita disponi ut potum sumat ex quo morbus augeatur; quam, cum nullum
tale
in eo vitium est, a | simili faucium siccitate moveri ad potum [108]
sibi utilem assumendum. Et quamvis respiciens ad praeconceptum
horologii
usum dicere possim illud, cum horas non recte indicat, a natura sua
deflectere; atque eodem modo considerans machinamentum humani corporis
tanquam comparatum ad motus qui in eo fieri solent, putem illud etiam a
natura sua aberrare, si ejus fauces sint aridae, cum potus ad ipsius
conservationem non prodest; satis tamen animadverto hanc ultimam
naturae
acceptionem ab altera multum differre; haec enim nihil aliud est quam
denominatio a cogitatione mea hominem aegrotum, et horologium male
fabricatum, cum idea hominis sani, et horologii recte facti comparante
dependens, rebusque de quibus dicitur extrinseca; per illam vero
aliquid
intelligo quod revera in rebus reperitur, ac proinde nonnihil habet
veritatis. |
6.17 しかし実に我々が自然によって 駆り立てられるものにおいてさえも我々が過つことは稀ではない。例えば、病気である人々がすぐ後に自分に害をなすべき飲料 あるいは食物を欲求する場合のごときがそれである。この場合たぶん、彼等は彼等の自然が頽廃しているために過つのである、と言われることができるであろ う。しかしながらこれは困難を除くものではない。なぜなら、病気の人間は健康な人間に劣らず真実に神の被造物であり、従ってまた前者が神から欺くところの 自然を授けられているということは後者がそうであるということに劣らず矛盾であると思われるから。そして歯車と錘とから出来ている時計が、悪く作られてい て時刻を正しく示さないときにも、あらゆる点で製作者の願いを満足させるときに劣らず正確に、自然のすべての法則を遵守するように、そのようにまた、もし 私が人間の身体をば、骨、神経、筋肉、脈官、血液及び皮膚から、たといそのうちに何ら精神が存在しなくともなお、現在そのうちに、意志の命令によってでは なく、従って精神によってではなく、行われているのと同じすべての運動を有するように、調整せられ合成せられているところの或る種の機械として見るなら ば、この身体にとって、もし、例えば、水腫病を患っているならば、かの精神に渇きの感覚をもたらすのをつねとするのと同じ咽喉の乾きに悩み、そしてまたこ の乾きによってその精神及びその他の部分が、病気を重くすることになる飲料をとるように、配置せられるということは、この身体のうちに何らかかる欠陥が存 しないときに、咽喉の同様の乾きによって自分に有益な飲料をとるように動かされるということと等しく、おそらく自然的であるのを、私は容易に認めるのであ る。そしてたとい、時計のあらかじめ意図せられた用途を顧るならば、時刻を正しく示さないときには、それは自己の自然からそれていると言うことができるに しても、また同じように、人間の身体の機械をあたかもそのうちにおいて生ずるのをつねとする運動のために調整せられたもののごとくに見るならば、もし、飲 料が身体そのものの保存に役立たないときに、その咽喉が乾いているとすれば、それはまた自己の自然からはずれていると考えるにしても、しかし私は自然のこ の後の意味が前の意味とははなはだ異なることに十分に気づくのである。なぜなら、後の意味での自然は、病気の人間や悪く作られた時計を健康な人間の観念や 正しく作られた時計の観念と比較する私の思惟に依存するところの規定以外の何物でもなく、そしてそれは、それについて語られるものに対して外面的な規定で あり、しかるに前の意味においては、自然というものは、実際にもののうちに見出される或るもの、従って或る真理を有するあるものであるからである。 |
| At certe, etiamsi
respiciendo ad corpus hydrope laborans, sit tantum
denominatio extrinseca, cum dicitur ejus | natura esse corrupta, [109]
ex eo quod aridas habeat fauces, nec tamen egeat potu; respiciendo
tamen
ad compositum, sive ad mentem tali corpori unitam, non est pura
denominatio, sed verus error naturae quod sitiat cum potus est ipsi
nociturus; ideoque hic remanet inquirendum quo pacto bonitas Dei non
impediat, quo minus natura sic sumpta sit fallax. |
6.18 しかしながら確かに、水腫病を患っている身体について見るならば、飲料を必要としないのに渇いた咽喉を有するということから、その自然は頽廃していると 言われるとき、それは単に外面的な規定であるにしても、しかし合成体、すなわちかかる身体と合一せる精神について見るならば、飲料が自分に害をするであろ うときに渇くということは、単なる規定ではなく、かえって自然の真の誤謬である。従ってここに追求すべく残っているのは、いかにして神の善意はかように解 せられた自然が欺くものであることを妨げないのであるか、ということである。 |
| Nempe imprimis hic
adverto magnam esse differentiam inter mentem et
corpus, in eo quod corpus ex natura sua sit semper divisibile, mens
autem plane indivisibilis; nam sane cum hanc considero, sive meipsum
quatenus sum tantum res cogitans, nullas in me partes possum
distinguere, sed rem plane unam et integram me esse intelligo: et
quamvis toti corpori tota mens unita esse videatur, abscisso tamen
pede,
vel brachio, vel quavis alia corporis parte, nihil ideo de mente
subductum esse cognosco; neque etiam facultates volendi, sentiendi,
intelligendi, etc. ejus partes dici possunt, quia una et eadem mens est
quae vult, quae sentit, quae intel|ligit. Contra vero nulla res [110]
corporea, sive extensa potest a me cogitari(60) quam non facile in
partes cogitatione dividam, atque hoc ipso illam divisibilem esse
intelligam: quod unum sufficeret ad me docendum, mentem a corpore
omnino
esse diversam, si nondum(61) illud aliunde satis scirem. |
6.19 ところで私はここにまず第一 に、精神と身体との間には、身体は自己の本性上つねに可分的であり、しかるに精神はまったく不可分的であるという点におい て、大きな差異が存することを認めるのである。というのは実に、私が後者、すなわち単に思惟するものである限りにおける私自身を考察するとき、私は私のう ちに何らの部分をも区別することができず、かえって私は私がまったく一にして全体的なものであることを理解するからである。そしてたとい全体の精神が全体 の身体に結合せられているかのように思われるにせよ、しかし足、あるいは腕、あるいはどのような他の身体の部分を切り離しても、私はそのために何物も精神 から取り去られていないことを認識する。なおまた意欲の能力、感覚の能力、理解の能力、等々は、精神の部分と言われることができない、なぜなら、意欲し、 感覚し、理解するのは一にして同じ精神であるから。しかるにこれに反して、私が思惟によって容易に部分に分割し、そしてまさにこれによってそれが可分的で あることを私の理解しないような物体的ないかなるものも、すなわち延長を有するものも私によって思惟せられることができないのである。この一事は、精神が 身体とはまったく異なっていることをば、もしまだ私がこのことを他のところから十分に知らないならば、私に教えるに足りるであろう。 |
| Deinde adverto
mentem non ab omnibus corporis partibus immediate affici,
sed tantummodo a cerebro, vel forte etiam ab una tantum exigua ejus
parte, nempe ab ea in qua dicitur esse sensus communis; quae
quotiescunque eodem modo est disposita, menti idem exhibet, etiamsi
reliquae corporis partes diversis interim modis possint se habere, ut
probant innumera experimenta quae hic recensere non est opus. |
6.20 次に私は、精神が身体のすべて の部分からではなく、ただ脳髄から、あるいはおそらくそれのみでなく単に一つの極めて小さい部分、すなわちそこに共通感覚 が存すると言われる部分から、直接に影響せられるということを、認めるのである。この部分は、ここで数え上げることを要しない無数の経験の証明するごと く、それが同じ仕方で配置せられるときはつねに、たといその間に身体のその他の部分は種々異なる状態にあることができるにしても、精神に同一のものを示す のである。 |
| Adverto praeterea
eam esse corporis naturam, ut nulla ejus pars possit
ab alia parte aliquantum remota moveri, quin possit etiam moveri eodem
modo a qualibet ex iis, quae interjacent, quamvis illa remotior nihil
agat. Ut, exempli causa, in fune A, B, C, D, si trahatur ejus ultima
pars D, non alio pacto mo|vebitur prima A, quam moveri etiam [111]
posset, si traheretur una ex intermediis B, vel C, et ultima D maneret
immota. Nec dissimili ratione, cum sentio dolorem pedis, docuit me
Physica, sensum illum fieri ope nervorum per pedem sparsorum, qui inde
ad cerebrum usque funium instar extensi, dum trahuntur in pede, trahunt
etiam intimas cerebri partes ad quas pertingunt, quemdamque motum in
iis
excitant, qui institutus est a natura, ut mentem afficiat sensu doloris
tanquam in pede existentis. Sed quia illi nervi per tibiam, crus,
lumbos, dorsum, et collum transire debent, ut a pede ad cerebrum
perveniant, potest contingere, ut etiamsi eorum pars quae est in pede
non attingatur, sed aliqua tantum ex intermediis, idem plane ille motus
fiat in cerebro qui fit pede male affecto, ex quo necesse erit ut mens
sentiat eundem dolorem, et idem de quolibet alio sensu est putandum. |
6.21 さらに私は、物体のいかなる部 分も他のなにほどか遠く隔っている部分によって、たといこのいっそう遠く隔っている部分が何ら動かないにしても、 その間に 横たわっている部分のうちの何らかのものによってまた同じ仕方で動かされ得るのでないと、動かされ得ないということが、物体の本性であるのを認めるのであ る。すなわち、例えば、A・B・C・Dなる綱において、その最後の部分Dが引かれる場合、最初の部分Aは、最後の部分Dが動かないままに止まっていて中間 の部分のうちの一つBあるいはCが引かれた場合にまたそれが動かされ得るのと別の仕方で動かされないであろう。これと同様の理由によって、私が足の苦痛を 感覚する場合、自然学は私に、この感覚は足を通じて拡がっている神経の助けによって生ずるのであって、この神経は、そこから脳髄へ連続的に綱のごとくに延 びていて、足のところで引かれるときには、その延びている先の脳髄の内部の部分をまた引き、このうちにおいて、精神をして苦痛をばあたかもそれが足に存在 するものであるかのごとくに感覚せしめるように自然によって定められているところの或る一定の運動を惹き起すのである、ということを教えるのである。しか るにこれらの神経は、足から脳髄に達するためには、脛、腿、腰、脊及び頸を経由しなくてはならぬゆえに、たといこれらの神経の足のうちにある部分が触れら れなくて、ただ中間の部分の或るものが触れられても、脳髄においては足が傷を受けたときに生ずるのとまったく同じ運動が生じ、そこから必然的に精神は足に おいてそれが傷を受けたときのと同じ苦痛を感覚するということが起り得るのである。そして同じことが他のどのような感覚についても考えられねばならない。 |
| Adverto denique
quandoquidem unusquisque ex motibus qui fiunt in ea
| parte cerebri quae immediate mentem afficit, non nisi unum [112]
aliquem sensum illi infert, nihil hac in re melius posse excogitari,
quam si eum inferat qui ex omnibus quos inferre potest ad hominis sani
conservationem quam maxime, et quam frequentissime conducit.
Experientiam autem testari tales esse omnes sensus nobis a natura
inditos; ac proinde nihil plane in iis reperiri, quod non(62) Dei
potentiam, bonitatemque testetur. Ita, exempli causa, cum nervi qui
sunt
in pede, vehementer, et praeter consuetudinem moventur, ille eorum
motus
per spinae dorsi medullam ad intima cerebri pertingens ibi menti signum
dat ad aliquid sentiendum, nempe dolorem tanquam in pede existentem, a
quo illa excitatur ad ejus causam ut pedi infestam, quantum in se est,
amovendam. Potuisset vero natura hominis a Deo sic constitui, ut ille
idem motus in cerebro quidvis aliud menti exhiberet; nempe vel seipsum,
quatenus est in cerebro; vel quatenus est in pede; vel in aliquo ex
locis intermediis, | vel denique aliud quidlibet; sed nihil aliud [113]
ad corporis conservationem aeque conduxisset. Eodem modo, cum potu
indigemus, quaedam inde oritur siccitas in gutture nervos ejus movens,
et illorum ope cerebri interiora; hicque motus mentem afficit sensu
sitis, quia nihil in toto hoc negotio nobis utilius est scire, quam
quod
potu ad conservationem valetudinis egeamus, et sic de caeteris. |
6.22 最後に私は、直接に精神に影響 を与えるところの脳髄の部分において生ずる運動のおのおのは、精神に或る一定の感覚しかもたらさないのであるから して、こ の場合、この運動が、それのもたらし得るあらゆる感覚のうち、健康な人間の保存に最も多くかつ最もしばしば役立つところのものをもたらすということよりも いっそう善いいかなることも考え出され得ないということを認めるのである。しかるに経験は自然によって我々に賦与せられたすべての感覚がかくのごとき性質 のものであることを証している。従ってそのうちには神の力並びに善意を証しない何物もまったく見出されないのである。かようにして、例えば、足のうちにあ る神経が激しくそして通例に反して動かされるとき、その運動は、脊髄を経て脳髄の内部の部分に達し、そこにおいて精神に或るものを、すなわち苦痛を、あた かも足に存在するもののごとくに、感覚せしめるところの合図を与え、これによって精神は苦痛の原因をば足に害をするものとして自分にできるだけ取り除くよ うに刺戟せられるのである。もっとも、人間の本性は、この脳髄における同じ運動が精神に何か他のものを示すように、すなわちあるいはこの運動そのものを、 脳髄にある限りにおいて、あるいは足にある限りにおいて、あるいは両者の中間の場所のうちのどこかにある限りにおいて、示すように、あるいは最後に何か もっと他のものを示すように、神によって仕組まれることができたであろう。しかしながらこれらの他のいずれのものも身体の保存に右にいったものと同等に役 立たなかったであろう。同じように、我々が飲料を必要とするとき、これによって或る種の乾きが咽喉に起り、その神経を動かし、そしてこの神経を介して脳髄 の内部を動かし、そしてこの運動は精神に渇きの感覚を生ぜしめる。なぜなら、この全体のことがらにおいて、健康状態の維持のためには我々は飲料を必要とす ることを知るということよりも、我々にとっていっそう有用なことは何もないのであるから。そしてその他の場合についても同様である。 |
| Ex quibus omnino
manifestum est, non obstante immensa Dei bonitate,
naturam hominis ut ex mente et corpore compositi non posse non
aliquando
esse fallacem. Nam si quae causa, non in pede, sed in alia quavis ex
partibus per quas nervi a pede ad cerebrum porriguntur, vel etiam in
ipso cerebro eundem plane motum excitet, qui solet excitari pede male
affecto, sentietur dolor tanquam in pede, sensusque naturaliter
falletur, quia cum ille idem motus in cerebro non possit nisi eundem
semper sensum menti inferre, multoque frequentius oriri soleat a causa
quae laedit pedem, quam ab alia alibi existente, rationi consentaneum
est, ut | pedis potius, quam alterius partis dolorem menti semper [114]
exhibeat. Et si quando faucium ariditas non ut solet ex eo quod ad
corporis valetudinem potus conducat, sed ex contraria aliqua causa
oriatur, ut in hydropico contingit, longe melius est illam tunc
fallere,
quam si contra semper falleret, cum corpus est bene constitutum, et sic
de reliquis. |
6.23 これらのことから、神の広大無辺なる善意にもかかわらず、精神と身体とから合成せられたものとしての人間の本性が、時には欺くものであらざるを 得ないこ とは、まったく明白である。というのは、もし或る原因が、足においてではなく、神経が足からそこを経て脳髄へ拡がっている部分のうちのどこかにおいて、あ るいは脳髄そのものにおいてさえも、足が傷を受けたときに惹き起されるのを常とするのとまったく同じ運動を惹き起すならば、苦痛はあたかも足にあるものの ごとくに感覚せられ、かくして感覚は自然的に欺かれるから。なぜなら、この脳髄における同じ運動はつねに同じ感覚をしか精神にもたらすことができず、そし てこの運動は他のところに存在する他の原因によってよりも足を傷つける原因によって遥かにしばしば惹き起されるのをつねとするゆえに、この運動が他の部分 の苦痛よりもむしろ足の苦痛を精神につねに示すということは、理に適ったことであるからである。またもし時に咽喉の乾きが、通例のごとく身体の健康に飲料 が役立つということからではなく、かえって水腫病において起るごとく、或る反対の原因から惹き起されるならば、それがこの場合に欺くということは、反対に 身体が健全な状態にあるときにつねに欺くということよりも、遥かにいっそう善いことである。そしてその他の場合についても同様である。 |
| Atque haec
consideratio plurimum juvat, non modo ut errores omnes quibus
natura mea obnoxia est animadvertam, sed etiam ut illos aut emendare,
aut vitare facile possim. Nam sane cum sciam omnes sensus circa ea quae
ad corporis commodum spectant multo frequentius verum indicare quam
falsum, possimque uti fere semper pluribus ex iis ad eandem rem
examinandam; et insuper memoria; quae praesentia cum praecedentibus
connectit; et intellectu, qui jam omnes errandi causas perspexit, non
amplius vereri debeo ne illa, quae mihi quotidie a sensibus exhibentur
sint falsa, sed hyperbolicae superiorum dierum dubitationes ut risu
dignae, sunt explodendae. Praesertim summa illa de somno, quem a
vigilia
non distinguebam; nunc enim adverto permagnum inter utrumque esse
discrimen in eo quod nunquam insomnia cum reliquis omnibus actionibus
vitae a memoria conjungantur, ut ea quae vigilanti occurrunt; nam sane
si quis dum vigilo mihi derepente appareret, statimque postea
dispareret, ut fit in somnis, ita scilicet, ut nec unde venisset, nec
quo abiret viderem, non immerito spectrum potius, aut phantasma in
cerebro meo effictum(63) quam verum hominem esse judicarem. Cum vero
eae
res occurrunt, quas distincte unde, ubi, et quando mihi adveniant
adverto, earumque perceptionem absque ulla interruptione cum tota
reliqua vita connecto, plane certus sum, non in somnis, sed vigilanti
occurrere. Nec de ipsarum veritate debeo vel minimum dubitare, si,
postquam omnes sensus, memoriam et intellectum ad illas examinandas
convocavi, nihil mihi quod cum caeteris pugnet ab ullo ex his
nuntietur.
Ex eo enim quod Deus non sit fallax, sequitur omnino in talibus me non
| falli. Sed quia rerum agendarum necessitas non semper tam [116]
accurati examinis moram concedit, fatendum est humanam vitam circa res
particulares saepe erroribus esse obnoxiam, et naturae nostrae
infirmitas est agnoscenda. |
6.24 ところでこの考察は、単に私の 本性が陥り易いすべての誤謬に気づくためにのみでなく、またこれらの誤謬を容易に匡《ただ》しあるいは避け得るた めに、は なはだ多くの貢献をするのである。なぜなら実に、私はすべての感覚が身体の利益に関することがらについて偽よりも真を遥かにしばしば指示することを知って いるし、また私は或る同じものを検査するためにほとんどつねにこれらの感覚の多くを使用することができるし、そしてその上に、現在のものを先行のものと結 合するところの記憶や、すでに誤謬のすべての原因を洞見したところの悟性をも使用することができるからして、もはや私は毎日感覚によって私に示されるもの が偽でありはしないかと恐れることを要せず、かえって過ぐる日の数々の誇張的な懐疑は、笑に値するものとして、追い払わるべきものであるからである。これ はとりわけ私が覚醒から区別しなかったところの夢についての極めて一般的な懐疑がそうである。というのは、私は今、両者の間には、夢に現われるものは決し て、醒めているときに起るもののように、生涯の余のすべての活動と記憶によって結び附けられないという点において、非常に大きな差別があることを認めるか らである。なぜなら実に、もし何者かが、私の醒めているときに、夢において起るごとく突然に私に現われ、そしてすぐ後に消え失せ、かくしてもちろんこの者 がどこから来たのかもどこへ去ったのかもわからなかったならば、私がこの者を真実の人間であると判断するよりもむしろ幽霊、または私の脳裡で作られた幻想 であると判断するのは、不当ではないであろうから。しかしながら、それがどこから来たか、どこにあるかという場所、またそれがいつ私にやってきたかという 時間を私が判明に認めるところの、そしてそれについての知覚を何らの中断もなしに全生涯の他の時期と私が結び附けるところのものが起るときには、それが夢 においてではなく、醒めているときに起っていることは、私にまったく確実である。またかかるものの真理について私は、もし、それを検査するためにすべての 感覚、記憶及び悟性を召喚した後に、そのうちのいずれによってもその他のものと矛盾するいかなることも私に知らされないならば、わずかなりとも疑うことを 要しないのである。なぜなら、神は欺くものではないということから、かかるものにおいて私は過たないということが一般に帰結するからである。しかしながら 行動の必要はつねにかように厳密な検査の余裕を与えないゆえに、人間の生活は特殊的なものに関してしばしば誤謬に陥り易いことを告白しなければならず、そ して我々の本性の弱さを承認しなければならないのである。 |
| https://archive.org/stream/meditationesdepr23306gut/23306-8.txt | https://www.aozora.gr.jp/cards/001029/files/4730_58083.html |
余滴
三木清の最期:「1945年6月に豊多摩刑務所に (移送)、三木はそこで疥癬をやみ、それに起因する腎臓病の悪化により、敗戦後の9月26日に独房の寝台から転がり落ちて死亡しているのを発見された48 歳没。遺体を収めた棺は死後2日後、布川角左衛門が借りた荷車を用い、東畑精一宅に引き取られた」
出典
青空文庫「ルネ・デカルト 省察(せいさつ)」(三 木 清・訳) https://www.aozora.gr.jp/cards/001029/files/4730_58083.html
文献
Do not paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!
このページは三木清の霊前に捧げられる
Maria Magdalena
三木清の最期:「1945年6月に豊多摩刑務所に(移送)、
三木はそこで疥癬をやみ、
それに起因する腎臓病の悪化により、
敗戦後の9月26日に独房の寝台 から転がり落ちて死亡しているのを発見された。
享年48歳没。
遺体を収めた棺は死後2日後、
布川角左衛門が借りた荷車を用い、
東畑精一宅に引き取られた」
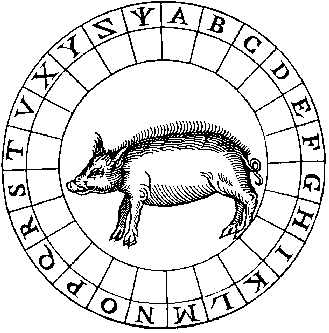
++
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099