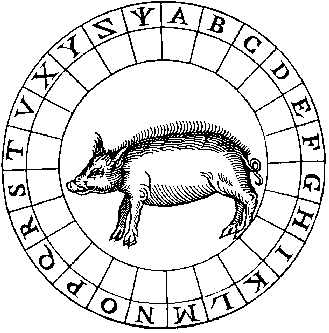Descartes' Second MEDITATIONES
René Descartes (1648), by Frans Hals (1581?-1666)
第二省察
Descartes' Second MEDITATIONES
René Descartes (1648), by Frans Hals (1581?-1666)
池田光穂
解説
デカルトの『省察』は、アリストテレスの霊魂、ある いは「魂」概念の概念を完全に葬り去ったと言われる。その根拠となると言われるのが、『省察』のうち、第二省察と呼ばれる部分である。アルキメデスの不動 のポイントを彼は、私は考える(cogito)の中に発見したと宣言する。考える私は、身体をもち、栄養を摂取し、動き、そして感覚することができる。し かし、それらの要素や動態は、私から切り離すことができる——確実な根拠をもって本質がそこにあるとは信じられない。しかしながら、私と考えることは、私 が考えているかぎり、この2つは不可分で切り離すことはできない。私は、考えるもの(res cogitance)であり、これが精神(mens) だ。身体は、延長するもの(es extensa)として、精神と切り離 すことができる。これが有名な、デカルトの心身二元論である。この2つの実体か ら構成される、自我観、身体観、さらには宇宙観には、アリストテレス的な魂の概念が入る余地がない。
さらに、状況を複雑にするのは、アリストテレスによ る魂と身体に関する「理論」(らしきもの)の曖昧さと、それを正典とみて、夥しい解釈が齎されてきたことにもある。古代ギリシャによって、魂の崇高さと不 滅性は、ソクラテスにおいて最初に力づよく指摘された。それを受け継いだプラトンは魂に欲求・気概・理知に3つの部分を与えた。しかしながらアリストテレ スの考察は、観察に基づいた考察や、独特の目的論や運動論的解釈がもとになったより総合的な観点で、魂と肉 体の区分をおこなう二元論的な解釈というよりも一元論的なものだった。さらに複雑化するのは、中世におけるキリスト教解釈との「共存」の問題だった。アリ ストテレスの霊魂観では、どう考えても、個々の魂は身体=肉体が終わる以上、死後は消滅してしまうことが明白だったからだ。1513年ラテラノ公会議は哲 学者に対して「魂の不死性を自然理性に基づいて証明せよ」と命じるものだったという[中畑 2006:216]。
デカルトの『省察』も、このラテラノ公会議の要請に
応え
るものであり、第二
省察に関する記述でも魂の不死は、私は考える(cogito)の確実性とは対照的に、ほとんど無条件に当たり前のものとしてされている。この設問というか
課題は、我々の常識からみて全く馬鹿馬鹿しいものであるが、逆に、下記にみるような理性の(再)出発を「私は考える=私は在る・有る」というラディカリズ
ムを今更ながら感じる。林達夫(1896-1984)は「デカルトのポリティーク」で、デカルトの
著述が彼がおかれていた歴史的背景を考慮する彼自身の修辞戦略の意味について考
えることを強調している(ということは、応用問題としてジョルダーノ・ブルーノ(Giordano Bruno, 1548-1600)やガリレオ・ガリレイの著述と彼らの命運にも思いを馳せる必
要があるという
ことだ)。

***
序文の部分で……
「第二省察においては、自己の有する自由を使用する 精神は、その存在について極めて少しでも疑い得る一切は存在しないと仮定するが、自身はしかし存在せざるを得ないことに気づくのである。そのことはまた、 このようにして、自己に、すなわち思惟する本性に属するものと、身体に属するものとを容易に区別するからして、極めて大きな効用を有している。しかしおそ らく或る者は、その箇所において霊魂の不死についての根拠を期待するであろうから、ここで彼等に告げておかねばならぬと思う、私は厳密に論証しない何物も 書かないことに努めたので、幾何学者たちの間で慣用せられている順序、すなわち何かを結論する前に、求められた命題が依繁する一切を前もって提論するとい う順序よりほかの順序に従うことができなかった、と。しかるに霊 魂の不死をよく認識するために前もって要求せられる第一の何より重要なことがらは、霊魂に ついてできるだけ分明な、そして身体のあらゆる概念からまったく区別せられた概念を作るということである。これはそこでなされている。しか しそのほかに、 我々が明晰に判明に理解する一切は、我々がそれを理解する通りに、真であるということを知ることがまた要求せられるのである。これは第四省察以前には証明 せられることができなかった。さらに、物体的本性の判明な概念を有しなければならないのであって、かかる概念は一部分この第二省察において、また一部分は 第五及び第六省察において作られている。なおまたこれら一切のことから、精神と身体とがまさにそのように把握せられるごとく、別個の実体として明晰 に判明 に把握せられるものは、全く実在的に互に区別せられた実体であることが結論せられねばならないのである。そしてこれは第六省察においてその 通り結論せられ ている。これはしかも、同じ第六省察において、我々はいかなる物体も可分的としてでなければ理解せず、反対にいかなる精神も不可分的としてでなければ理解 しないということによって、確かめられている。すなわち我々はどのように小さい物体でもその半分を考えることはできるが、いかなる精神についてもその半分 を考えることはできぬ。かようにして両者の本性は単に別であるのみでなく、また或る点で相反することが認められる。しかしながらこのことについてはこの書 物の中ではそれ以上立ち入って論じなかった。というのは、一方それだけで、身体の消滅から精神の死が帰結しないことを示し、そしてかようにして人間に来世 の生の希望を与えるには、十分であるからであり、他方またこの精神の不死を結論し得るもろもろの前提はあらゆる自然学からの説明に依繁しているからであ る。すなわちまず、およそあらゆる実体、詳しく言うと、存在する ためには神によって創造せられねばならぬものは、自己の本性上不滅であり、その同じ神に よって、そのものに神の協力が拒まれることによって、無に帰せしめられるのでなければ、決してあることをやめ得ないということが知られねばならぬ。 そして 次に、一般的に見られた物体は実体であり、それがために決してま た滅びないということ、しかし人間の身体は、余の 物体と異なる限り、ただ単にもろもろの器 官の或る一定の布置、及びこの種の他の偶有性から組立てられたものであり、しかるに人間の精神はかように何らかの偶有性から成るのではなく、純粋な実体で あるということ、に着目せられねばならぬ。というのは、たといその一切の偶有性が変化せられ、その結果、別のものを思惟し、別のものを意欲 し、別のものを 感覚し、など、するにしても、そのために同じ精神が別のものにならないが、人間の身体はしかし、ただ単にその何らかの部分の形体が変化せられることによっ て、別のものになる。そのことから身体はきわめて容易に滅亡し、精神はしかし自己の 本性上不死であるということが帰結せられるのである。」
本文で……
「人間の精神の本性について。精神は身体よりも容易
に知られるということ。
昨日の省察によって私は懐疑のうちに投げ込まれた。それは私のもはや忘れ得ないほど大きなものであり、しかも私はそれがいかなる仕方で解決すべきもので
あるかを知らないのである。かえって、あたかも渦巻く深淵の中へ不意に落ち込んだように、私は狼狽して、足を底に着けることもできなければ、泳いで水面へ
脱出することもできないというさまであった。しかしなおも私は努力し、昨日進んだと同じ道を、もちろん、極めてわずかであれ疑いを容れるものはすべて、あ
たかもそれが全く偽であることを私がはっきり知っているのと同じように、払い除けつつ、改めて辿ろう。そして何か確実なものに、あるいは、余のことが何も
できねば、少くともまさにこのこと、すなわち、確実なものは何もないということを確実なこととして認識するに至るまで、さらに先へ歩み続けよう。アルキメ
デスは、全地球をその場所から移動させるために、一つの確固不動の点のほか何も求めなかった。もし私が極めてわずかなものであれ何か確実で揺るがし得ない
ものを見出すならば、私はまた大きなものを希望することができるのである。
そこで私は、私が見るすべてのものは偽であると仮 定する。また、私はひとを欺く記憶が表現するものはいかなるものにせよかつて存在しなかったと信じるこ とにする。私はまったく何らの感官も有しないとする。物体、形体、延長、運動及び場所は幻想であるとする。しからば真であるのは何であろうか。たぶんこの 一つのこと、すなわち、確実なものは何もないということであろう。
しかしながらどこから私は、いましがた数え上げたすべてのもの とは別で、少しの疑うべき余地もない或るものが存しないことを、知っているのであるか。何 か神というもの、あるいはそれをどのような名前で呼ぶにせよ、何か、まさにこのような思想を私に注ぎ込むものが存するのではあるまいか。しかし何故に私は このようなことを考えるのであるか、たぶん私自身がかの思想の作者であり得るのであるのに。それゆえに少くとも私は或るものであるのではあるまいか。しか しながら既に私は、私が何らかの感官、または何らかの身体を有することを否定したのであった。とはいえ私は立ち止まらされる、というのは、このことから何 が帰結するのであるか。いったい私は身体や感官に、これなしには存し得ないほど、結いつけられているのであろうか。しかしながら私は、世界のうちに全く何 物も、何らの天も、何らの地も、何らの精神も、何らの身体も、存しないと私を説得したのであった。従ってまた私は存しないと説得したのではなかろうか。 否、実に、私が或ることについて私を説得したのならば、確かに私 は存したのである。しかしながら何か知らぬが或る、計画的に私をつねに欺く、この上なく有 力な、この上なく老獪な欺瞞者が存している。しからば、彼が私を 欺くのならば、疑いなく私はまた存するのである。そして、できる限り多く彼は私を欺くがよ い、しかし、私は或るものであると私の考えるであろう間は、彼は決して私が何ものでもないようにすることはできないであろう。かようにして、一切のことを 十分に考量した結果、最後にこの命題、すなわち、私は有る、私は存在する、という命 題は、私がこれ を言表するたびごとに、あるいはこれを精神によって把握するたびごとに、必然的に真である、として立てられねばならぬ。
しかし、いま必然的に有る私、その私がいったい何 であるかは、私は未だ十分に理解しないのである。そこで次に、おそらく何か他のものを不用意に私と思い 違いしないように、かくてまたこのすべてのうち最も確実で最も明証的であると私の主張する認識においてさえ踏み迷うことがないように、注意しなければなら ない。かるがゆえにいま、この思索に入った以前、かつて私はいったい何ものであると私が信じたのか、改めて省察しよう。このものから次に何であれ右に示し た根拠によって極めてわずかなりとも薄弱にせられ得るものは引き去り、かくて遂にまさしく確実で揺がし得ないもののみが残るようにしよう。
そこで以前、私はいったい何であると考えたのか。 言うまでもなく、人間と考えたのであった。しかしながら人間とは何か。理性的動物と私は言うでもあろう か。否。何故というに、さすれば後に、動物とはいったい何か、また理性的とは何か、と問わねばならないであろうし、そしてかようにして私は一個の 問題から 多数の、しかもいっそう困難な問題へ落ち込むであろうから。またいま私はこのような煩瑣な問題で空費しようと欲するほど多くの閑暇を有しないのである。む しろ私はここで、私は何であるかと私が考察したたびごとに、何が以前私の思想に、おのずと、私の本性に導かれて、現われたか、に注意しよう。そこに現われ たのは、もちろん、まず第一に、私が顔、手、腕、そしてこのもろ もろの部分の全体の機械を有するということであって、かようなものは死骸においても認めら れ、そしてこれを私は身体と名づけたのである。なおまた、そこに現われたのは、私が栄養をとり、歩行し、感覚し、思惟するということであって、これらの活 動を私は霊魂に関係づけたのである。しかしながらこの霊魂が何であるかに、私は注意を向けなかったか、それともこれを風とか火とか空気とか に似た、私の いっそう粗大な部分に注ぎ込まれた、何か知らぬが或る微細なものと想像した。物体については私は決して疑わず、判明にその本性を知っていると思っていた。 これをもしおそらく、私が精神によって把握したごとくに、記述することを試みたならば、私は次のように説明したであろう。曰く、物体とはすべて、何らかの 形体によって限られ、場所によって囲まれ、他のあらゆる物体を排するごとくに空間を充たすところの性質を有するもの、すべて、触覚、視覚、聴覚、味覚、あ るいは嗅覚によって知覚せられ、そして実に多くの仕方で、決して自己自身によってではなく、他のものによって、そのどこかに触れられて、動かされるところ の性質を有するものである、と。すなわち、自己自身を動かす力、 同じように、感覚する、あるいは思惟する力を有することは、決して物体の本性に属し ないと 私は判断したのであり、のみならずかような能力が或る物体のうちに見出されることに私はむしろ驚いたのである[引用者註→アリストテレスの「魂」批判、あるいはその存在の否定?]。
しかし現在、或る極めて有力な、そして、もしそう いうことが許されるならば、悪意のある、欺瞞者が、あらゆる点において、できる限り、私を欺くことに、 骨を折っていると仮定する場合、どうであろうか。私は、物体の本性に属するとさきほど言ったすべてのものうち極めてわずかなものであれ私が有することを確 認し得るものがあろうか。私は注意し、考え、また考える。私が有すると言い得るものには何も出会わない。私は同じことを空しく繰り返すことに疲れる。しか らば霊魂に属するとしたものは、どうであろうか。栄養をとるとか歩行するとかいうことは? 実にいま私は身体を有しないのであるから、これもまた作りごと 以外の何ものでもない。感覚することは? もちろんこれも身体がなければ存しないものであり、また私は夢において、後になって実際に感覚したのではないと 気づいた非常に多くのことを感覚すると思ったのである。思惟することは? ここに私は発見する、思惟がそれだ、と。これのみは私から切り離し得ないの であ る。私は有る、私は存在する、これは確実だ。しかしいかなる間か。もちろん、私が思惟する間である。なぜというに、もし私が一切の思惟をや めるならば、私 は直ちに有ることを全くやめるということがおそらくまた生じ得るであろうから。いま私は必然的に真であるもののほか何も許容しない、そこで私はまさしくた だ思惟するもの、言い換えれば、精神、すなわち霊魂、すなわち悟性、すなわち理性である、これらは私には以前その意味が知られていなかった言葉である。 し かし私は真のもの、そして真に存在するものである。だがいかなるものなのか。私は言った、思惟するもの、と。
そのほかに何か。想像を働かせてみよう。私は人体 と称せられるかのもろもろの部分の集合ではない。私はまたこれらの部分に注ぎ込まれた或る微妙な空気で もなく、風でも、火でも、蒸気でも、気息でも、その他私の構像するような何ものでもない。というのは、このようなものは無であると私は仮定したのであるか ら。けれどそれにもかかわらず、私は或るものである、という立言は動かないのである。しかし、たぶん、私に知られていないとのゆえをもって、無であると仮 定するこれらのものそのものが、ものの真理においては私が知っている私、その私と別のものでないということが生じないであろうか。これについて私は何も知 らない。このことについては私はいま争わない。ただ私に知られていることについてのみ、私は判断を下し得るのである。私は私が存在することを知っている。 そして、私の知っている私、その私は何であるか、と問うている。この、かように厳密な意味における知識が、その存在を私が未だ知っていないものに依繋しな いということ、従って私が想像力によって構像する何ものにも依繋しないということは、極めて確かである。そしてこの構像するとい う語が私の誤謬を私に告げるのである。なぜなら、もし私が何かであると私が想像したならば、私は実際に構像するであろうから。というのは、想像するとは物 体的なものの形体、あるいは像を見ることにほかならないのであるから。しかるに既に私は、私は有るということ、同時にまた一切このような像、そして一般に 物体の本性に関係づけられるあらゆるものは、夢幻以外の何ものでもないことがあり得るということ、を確かに知っている。このことに気づいた場合、私はいっ たい何であるかをさらに判明に知るために想像力を働かそうと言うのは、いまたしかに私は目覚めており、そして真なるものをいくらか見るが、しかし未だ十分 に明証的に見ないからして、夢がこのものをさらに真にさらに明証的に表現するように、努力して眠りに入ろうと言うのに劣らず、道理に反すると思われるので ある。かようにして私は、想像力の助けを藉りて捉え得るいかなるものも、この、私が私について有する知識に属しないこと、精神が自己の本性をまったく判明 に知覚するためには、極力注意して精神をそのようなものから遠ざけねばならぬこと、を認識するのである。
しからば私は何であるか。思惟するもの、である。これは何をいうのか。言うまでもなく、疑い、理解し、肯定し、否定し、欲 し、欲せぬ、なおまた想像し、 感覚するものである。
まことにこれは、もし全部が私に属するならば、僅 少ではない、しかしなぜ属してはならないであろうか。いまほとんど一切のものについて疑い、しかしいく らかのものは理解し、この一つのことは真であると肯定し、余のことを否定し、いっそう多くのことを知ろうと欲求し、欺かれることを欲せず、多くのことを意 に反してであれ想像し、なおまたいわば感覚からきた多くのものを認めるものは、私そのものではないのか。たとい私がつねに眠るにしても、たといまた私を創 造したものが、できる限り、私を欺くにしても、私は有るということと同等に真でないものは、これらのうち何であるか。私の思惟から区別せられるものは、何 であるか。私自身から分離せられていると言われ得るものは、何であるか。というのは、疑い、理解し、欲するものが私であることは、これをさらに明証的に説 明する何物も現われないほど、明白である。しかし実にまた私は想像する私と同じ私である。なぜなら、たといおそらく、私が仮定したように、想像せられたも のがまったく何一つ真でないにしても、想像する力そのものは実際に存在し、そして私の思惟の部分をなしているからである。最後に、私は、感覚する、すなわ ち物体的なものをいわば感覚を介して認める私と同じ私である。いま私は明かに、光を見、噪音を聴き、熱を感じる。これらは偽である、私は眠っているのだか ら、といわれるでもあろう。しかし私は見、聴き、暖くなると私には思われるということは確実である。これは偽であり得ない。これが本来、私において感覚す ると称せられることなのである。そしてこれは、かように厳密な意味において、思惟すること以外の何物でもないのである。
これらのことによってともかく私は、私はいったい 何であるかを、いくらかよく知り始める。しかしながらこれまでのところ、その像が思惟によって形作ら れ、そして感覚そのものが検証する物体的なものは、この何か知らぬが、想像力の支配下に入り来らぬ、私に属するものよりも、遥かに判明に認知せられると私 には思われ、また私はそう考えざるを得ないのである。とはいえ、実際、疑わしくて、知られていないで、私に関係がないと私の認めるものが、真であるもの、 認識せられているもの、要するに私自身よりも、いっそう判明に、私によって理解せられるということは、奇異なことであろう。しかし私はこれがどういうこと であるかを看取する、すなわち、私の精神はさ迷い歩くことを好み、そして未だ真理の限界内に引き留められることを甘受しないのである。それならそれで宜し い。我々はさらにひとたびこの精神に手綱を極度に弛めてやり、かくして、やがて適当な時に再び引き締める場合、それがいっそう容易に統御せられ得るように しよう。
そこで我々はかの普通にすべてのもののうち最も判 明に理解せられると思われているもの、すなわち、言うまでもなく、我々が触れ、我々が見る物体を考察し よう。しかし物体一般ではない。というのは、この一般的な知覚はむしろいっそう不分明であるのがつねであるから。かえって我々は特殊的な一つのものを考察 する。我々は、例えば、この蜜蝋をとろう。それは今しがた蜜蜂の 巣から取り出されたばかりで、未だ自己の有する蜜のあらゆる味を失わず、それが集められた 花の香りのいくらかを保っている。その色、形体、大きさは明白である。すなわち、それは堅くて冷たく、容易に掴まれ、そして指で打てば音を 発する。要する に或る物体をできるだけ判明に認識し得るために要求せられ得ると思われる一切が、この蜜蝋に具わっている。しかしながら、見よ、私がこう言っている間に、 それを火に近づけると、残っていた味は除き去られ、香は散り失せ、色は移り変わり、形体は毀され、大きさは増し、流動的となり、熱くなり、ほとんど掴まれ ることができず、またいまは、打っても音を発しない。それでもなお同じ蜜蝋は存続しているのか。存続していると告白しなければならぬ。誰もこれを否定しな い。誰もこれと違って考えない。しからばこの蜜蝋においてあのように判明に理解せられたものは、何であったのか。それは確かに私が感官によって捉えたとこ ろのいかなるものでもない。なぜなら味覚、あるいは嗅覚、あるいは視覚、あるいは触覚、あるいは聴覚によって感知したあらゆるものは、いまは変化している からである。しかもなお蜜蝋は存続している。
たぶんそれは私が現在思惟するものであったのであ ろう、すなわち、疑いもなく、蜜蝋そのものは、かの蜜の甘さで も、花の香りでも、かの白さでも、形体で も、音でも、あったのではなく、かえって少し前にはかの仕方で分明なものとして私に現われ、現在は別の仕方で現われるところの物体であったの である。しか しかように私が想像するこのものは、厳密に言えば、何であるか。我々は注意しよう、そして、蜜蝋に属しないものを遠ざけることによって、何が残るかを見よ う。疑いもなく、延長を有する、屈曲し易い、変化し易い或るもの以外は何も残らない。しからばこの屈曲し易い、変化し易いとは、どういうこ とであるか。そ れは、この蜜蝋が円い形体から四角な形体に、あるいはこの四角な形体から三角の形体に転じられ得ると私が想像することであろうか。決してそうではない。な ぜなら、私は蜜蝋がこの種の無数の変化を受け得ることを理解するが、しかし私はこの無数のものを、想像することによってはことごとく辿り得ず、従ってこの 理解は想像する能力によっては仕遂げられないからである。さらに延長を有するとは、どういうことであるか。蜜蝋の延長そのものもまた知られていないのでは あるまいか。なぜならそれは、溶解しつつある蜜蝋においていっそう大きくなり、煮沸せられるときにはさらにいっそう大きくなり、そして熱が増されるなら 従ってまたいっそう大きくなるからである。そして蜜蝋が何であるかは、このものがまた延長において私がかつて想像することによって把握するよりも多くの多 様性を容れると考えるのでなければ、正しく判断せられないであろう。従って私は、この蜜蝋が何であるかを実に想像するのではなく、ただ単に精神によって知 覚する、ということを認めるのほかはないのである。私はこの特殊的な蜜蝋を言っている、なぜなら蜜蝋一般については、そのことはさらに明瞭であるから。し からば精神によってのほか知覚せられないこの蜜蝋は、いったいどういうものであるのか。疑いもなく、私が見、私が触れ、私が想像するものと同じもの、要す るに私が始めからこういうものであると思っていたのと同じものである。しかしながら、注意すべきことは、この蜜蝋の知覚は、視覚の作用でも、触覚の作用で も、想像の作用でもあるのではなく、また、たとい以前にはかように思われたにしても、かつてかようなものであったのではなく、かえってただ単に精神の洞観 である、そしてこれは、これを構成しているものに私が向ける注意の多少に応じて、あるいは以前そうであったように不完全で不分明であることも、あるいは現 在そうあるように明晰で判明であることもできるのである。
しかるに一方私はいかに私の精神が誤謬に陥り易いものであるかに驚く。 というのは、たとい私がこのことどもを自分において黙って、声を上げないで考察す るにしても、私は言葉そのものに執着し、そしてほとんど日常の話し方そのものによって欺かれるからである。すなわち我々は、蜜蝋がそこにあるならば、我々 は蜜蝋そのものを見る、と言い、我々は色あるいは形体を基として蜜蝋がそこにあると判断する、と我々は言わないのである。そこから私は直ちに、蜜蝋はそれ ゆえに眼の視る作用によって、ただ単に精神の洞観によってではなく、認識せられると結論するであろう。ところで、もしいま私がたまたま窓から、街道を通っ ている人間を眺めたならば、私は彼等についても蜜蝋についてと同じく習慣に従って、私は人間そのものを見る、と言う。けれども私は帽子と着物とのほか何を 見るのか、その下には自動機械が隠されていることもあり得るではないか。しかしながら私は、それは人間である、と判断する。そしてかように私は、私が眼で 見ると思ったものでも、これをもっぱら私の精神のうちにある判断の能力によって把捉するのである。
しかしながら自己の知識を一般人を超えて高めよう と欲する者は、一般人が発明した話の形式から懐疑を探し出したことを恥じるであろう。我々は絶えず先へ 進もう。いったい私が蜜蝋の何であるかをいっそう完全にいっそう明証的に知覚したのは、最初私が蜜蝋を眺め、そしてこれを外的感覚そのものによって、ある いは少くとも人々のいわゆる共通感覚によって、言い換えると想像的な力によって、認識すると信じた時であるか、それとも実にむしろ現在、すなわち一方蜜蝋 が何であるかを、他方いかなる仕方で認識せられるかを、いっそう注意深く探究した後であるか、に注目しよう。このことについて疑うのは確かに愚かなことで あろう。最初の知覚において何が判明であったか。どんな動物でも有し得ると思われないものは何であったのか。しかるにいま私が蜜蝋をその外的形式から区別 し、そしていわば着物を脱がせてその赤裸のままを考察する場合、た とい未だ私の判断のうちに誤謬が存し得るにしても、私は実際、人間の精神なしには、かよ うに蜜蝋を知覚することはできないのである。
しかしこの精神そのものについて、すなわち私自身 について、私は何と言うべきであろうか。というのは、私は精神のほか未だ他の何物も私のうちに存すると 認めないのである。しからば、この蜜蝋をかくも判明に知覚すると思われる私、その私について、私は何と言うべきであろうか。私は私自身を単に遥かにいっそ う真に、遥かにいっそう確実に認識するのみでなく、また遥かにいっそう判明にいっそう明証的に認識するのではあるまいか。なぜというに、もし私が蜜蝋を見 るということから、蜜蝋が存在すると判断するならば、確かに遥かにいっそう明証的に、私がそれを見るということそのことから、私自身がまた存在するという ことが、結果するからである。すなわち、この私の見るものが実は蜜蝋ではないということはあり得る、私が何らかのものを見る眼を決して有しないということ はあり得る、しかし、私が見るとき、あるいは(いま私はこれを区別しないが)私は見ると私が思惟するとき、思惟する私自身が或るものでないということは、 まったくあり得ないのである。同様の理由で、もし私が蜜蝋に触れ るということから、蜜蝋が有ると判断するならば、同じことがまた、すなわち私は有るという ことが結果する。もし私が想像するということから、あるいは他のどんな原因からであっても、蜜蝋が有ると判断するならば、やはり同じことが、すなわち私は 有るということが結果するのである。しかも蜜蝋について私が気づくまさにこのことは、私の外に横たわっている余のすべてのものに適用するこ とができる。そ してさらに、もし蜜蝋の知覚が、単に視覚あるいは触覚によってのみでなく、いっそう多くの原因によって私に明瞭になった後、いっそう多く判明なものと思わ れたならば、今やいかに多くいっそう判明に私自身は私によって認識せられることか、と言わなければならぬ。というのは、蜜蝋の知覚に、あるいは何か他の物 体の知覚に寄与するいかなる理由も、すべて同時に私の精神の本性をいっそうよく証明するはずであるからである。しかしながらまた精神そのもののうちにはそ の本性の知識をいっそう判明になし得るものがこれ以上他に極めて多く存するのであり、かくてこれらの物体から精神の本性に推し及ぶものは、ほとんど数える にあたらぬと思われる。
かくて、見よ、遂に私はおのずと私の欲したところに帰って来たので
ある。すなわち、今や、物体そのものも本来は感覚によって、あるいは想像する能力に
よってではなく、もっぱら悟性によって知覚せられるということ、触れられることあるいは見られることによってではなく、ただ理解せられることによって知覚
せられるということ、が私に知られたのであるから、私は何物も私の精神よりもいっそう容易に、またいっそう明証的に私によって知覚せられ得ないということ
を明瞭に認識するのである。しかしながら古い意見の習慣はそんなに速かに除き去られ得ないからして、私の省察の時間の長さによってこの新し
い認識がいっそ
う深く私の記憶に刻まれるように、ここで立ち停まることが適当であろう。」
出典
青空文庫「ルネ・デカルト 省察(せいさつ)」(三 木 清・訳) http://www.aozora.gr.jp/cards/001029/card43291.html
文献
おまけ
当時(1973年)新訳のデカルト著作集(4巻)が 白水社から出版さ れる時に初回配本の時に挟まれていたチラシがある。格安古書で手に入ったがこれまで30数年間誰にも読まれた経緯がないようだ。そのチラシに天文対話の邦 訳者の故・青木靖三さんがエッセーを書いている。真贋不明なデカルトと称される頭骨の望まざる土地=フランスへの帰郷と、当時鬼の首をとったように学者ど ころか「女子供や猿まで」(←当時はまだこの蔑称が赦されたが、これは青木の言葉ではなく私の言葉)がデカルト批判の唱和をしていた社会状況を絡みあわせ て『デカルトの責任を(時代と事由を事後的に好き勝手に操作できる)俺達は追求できるのか?』という、あまり論理的にはシャープではないけど、批判という か皮 肉を書いている。僕は生前会ったことのない、ガリレオヲタの青木靖三先生だが、この教授の生涯がどんなものだったのかについて興味をもった(→descartes130213.pdf)。
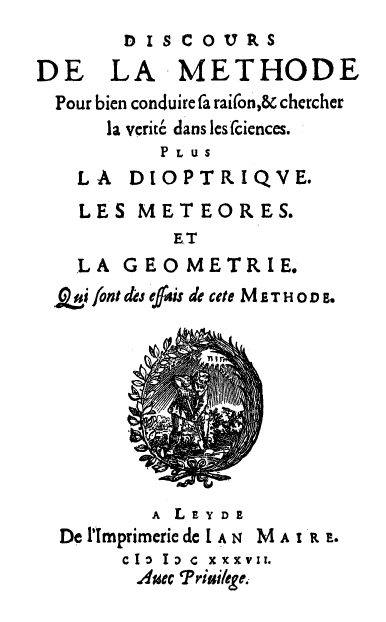
Do not paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!