フロネーシスの救出
Salvation
of Phronesis from Descates
はじめによんでください
フロネーシスの救出
Salvation
of Phronesis from Descates
報告:池田光穂
第2章 アリストテレス的図式の崩壊と近代、塚本明子『動く知フロネーシス:経験にひらかれた実践知』ゆみる出版、2008
第81回 現場力研究会発表、2009年3月18日、大阪大学・大学教育実践センター中会議室[→現場力研究会のあゆみ]
==引用(西村ハンドアウトMarch 4, 2009)==
■本書のテーマ
「テクネーとフロネーシスを対立するものとして捉えるのではなく、フロネーシスがテクネーの働くところに、「テクネー的でないもの」として 初めて登場し認識されてくるのみならず、やがて自らテクネー化することで知としての足場を定め、新たなフロネーシスを生み出していくというプロセスを探る ことである。つまり、テクネーと絡み合って動く知としてのフロネーシスである。」(p.10)
■アリストテレスの図式の崩壊(17世紀の自然科学の台頭によるキリスト教の世俗化のプロセス)[pp.36-]
「ロゴス(理性)」→「合理性(rationality)」
「テオーリア(観想知)」→「セオリー(理論知)」
(変化=ホワイトヘッド:非合理で「頑固な事実」を受け入れた。=神の姿が薄れて人間の住む洞窟の中が世界となり、外にある知(テオーリ ア)に代わって蓋然的で経験的な人間の知の他に頼れるものがなくなり、合理的かつ思弁的に思考を進めるためには、自分の考えを実際にこの世界(自然)に 合っているかどうかを確かめながら一歩ずつ進むしかなくなってしまった)
==章内の構成==
第2章 アリストテレス的図式の崩壊と近代
1. 新しい知 64
1.1 「新しい方法」と精神指導の原理 64
1.2 単純化という方法 71
1.3 目的論の排除と因果律のパラドクス 77
2. テクネー、アルス、アート 87
2.1 神の知の世俗化 90
2.2 アルス・リベラーレスとアルス・メカニカ 95
2.3 作法というアルス 103
3. 芸と術の間ーーコリン[グ]ウッドの美学 107
====
1. 新しい知 64
1.1 「新しい方法」と精神指導の原理 64
【フランシス・ベーコン】
・フランシス・ベーコン(Francis Bacon, 1561-1626)『新しい方法』(→ノヴム・オルガヌム 新機関との翻訳も)「知は力」=知は目的を完遂する手段であり、計画(プラン)そのものであ る。何かを対象とし、それを支配する。知の拡大は、支配の拡大。
■人工的な自然
「この「制作によって自然を征服する人」というのは、まず人工的な知的構築物を制作し、理念的な設計図によって自然を変形ないし再編成する ことで、いわば「人工的な自然」を制作してゆくことになる。制作にあたって人間は「自然物を結びつけたり切り離したりする」だけであって、それ以外のこと は「自然がその内部で成し遂げる」からである。そしてそれが近代科学であった」(p.65)。
・プロメテウス:pro(先に、前に)+metheus(考える者):先見の明、熟慮。人間に火をもたらす。エピメテウスの兄(epi(後 で)+ metheus (考える):後悔、愚鈍)
・変わるものについての知(=科学的方法?)/変わらないものについての観想や直感
【デカルト】
・ルネ・デカルト(1596-1650)『方法序説』にみる、スコラ的教育への失望(アリストテレス[崇拝]憎悪)pp.66-67.
・「中世のスコラ哲学でなされる議論のやり方は、まず命題が出されそれを偽とする主張が述べられ、次にそれに反対する議論が挙げられ、さら にその反論に対する反論をあげて、結局はそれは真であるという議論になってゆく」(p.67)。
・ドクサの排除(→〈分け方2〉)[現状における実践政治家/真の政治家との対立、洞窟/外の世界を含んだ世界全体との対比:p.28]
・デカルトの知は、プラトンのテオーリア(観る知)に類似(p.68)
■理論知と実践知の対比[に塚本は呪縛される?]
「どうしてうまくいったのかを理論的に理解しなければ納得できない。いうなれば実践知の解決が、理論知にとっての問題と化す、ということで ある。理論知は得た利益を享受するより、いわば好きこのんで、どこまでも批判と考察を進めようとするのである。……実践知は成功するかどうかが主たる関心 事であるから、もし成功すればそれで満足して、うまくいったことに対する満足がさらなる探求を抑えるという面はあるだろう……。理論知の成功は、その道の りの質が問題であり、理論上危ういようなショートカットやごまかしは許されない。つまりは理論知にはそれ自身の中に自らを測る規準が含まれているのであ る。/……ギリシャ的な世界観がすでに失われ、ヨーロッパ中世のキリスト教社会や世界観が崩れ始めていた時期に、実践知と理論知という対立は、実験と理論 という近代科学の方法へと編成し直されている」(p.68)。(→ホイジンガ『中世の秋』)
■デカルトの回心=精神のデザイン
「一人の人間がデザインした建物のほうが大勢でやるよりも秩序だっており、より美しい。よく知られているように、そうした認識の建物を建て るのに、彼は基本的には幾何学の解析と証明の方法を用いたのである。……/デカルトの「精神を鍛える方法」は、頭の中でどう考えるかを考えることであり、 少し別の角度から見ると「機械技術の内部」で、他の技術を借りずにいかにその道具を作るべきかをそれ自らが教えるような技術」すなわち機械をつくるデザイ ンの技術に近く、今日の「技術的な理性」に似ている」(p.70)。(→パノフスキー、エーコ『カントとカモノハシ』)
■機械は(近寄りがたく)純粋だが、同時に蝕知できる
「機械は身体(物体、corpus)ではなくむしろ精神(esprit)に近い、いわば思考が具体化した地図であるといえるのではないか。 この考えをさらに進めれば、デザインは身体(物体)をもたないゆえにより純粋で精神的であり、一方で形を得た具体化されたデザインとしての機械は、われわ れ自身(身体)よりも純粋に精神的・論理的であるが、われわれにとっては純粋なデザインよりも具体的かつ身体的であり、tangible(さわれる)で近 づきやすいという一見奇妙なことになる」(p.71)。
この時の塚本の「機械」の具体的イメージは明確であるが、同時に彼女は機械という属性の一部しか表現していない(=想像できない)。
1.2 単純化という方法 71
・還元という方法への探求
(私にとっては相当理解不明な議論がつづく)
例えばメタファーの誤用
・「イギリスのモラル・フィロソフィーは、いわば単位をなす自己利益(elf interest)をもとに構成されたホッブスの社会モデルとその批判から始まったといえるし、またこれに関連して個人が結ぶ社会契約という発想も、物質 の分子式による再構成とパラレルな近代的発想による理論構築であった」(p.73)[註41→ヒューム(1711-1776)『人性論』世界の名著409 -410頁/元素記号の嚆矢はドルトン(1766-1844)ただし現在の原子記号は1828年頃ベルセリウス(1779-1848)が考案]
・同様に「計算合理性」を媒介に、人工知能(AI)とホッブスを直結するような表現などには、私は違和感を憶える。
■個人の誕生
「個人が社会の部分ないし単位とみなされることによって、科学者や政治家が社会全体に果たす機能と、一人の人間としての生き方とが分裂する ようになる。すなわち公私の区別ができ、主観性と客観性が分裂し、思考と現実が次第にずれてゆくことになる」(p.75)(→ヘーゲル、トリリング)
「しかし科学実験は次第に[ママ]日常生活の中ではなく、実験室で条件を整えて行われ、証明は科学者同士のサークルや学会でなされるように なっていった」(p.76)。(→ローヤル・ソサイエティ)
1.3 目的論の排除と因果律のパラドクス 77
・目的論=個物に内在するテロスが原因となり結果を生む、実体に内在するエイドス(形相)――マテリアルな質料(ヒューレ)と不可分――が 運動の原因になる。
・「原因となる事象やものに、外からの力(force)すなわち作用因を及ぼすことで望む結果を生み出すという方法が成功するためには、自 然が能動的な「始まり」をもたず、「形相」(内在的な目的)をもたないという前提が必要であった。一般にギリシア的自然観にあり、特殊的にはアリストテレ スにあった、個物に内在する目的(テロス)が原因となって結果を規定するという目的論は、中世のスコラ哲学において、実体に内在する形相が運動(変化)の 原因となるという目的論として完成されていた」(pp.77-78)。
・「ギリシア人の思弁的理性にとってはロゴスが内在的な繋がりをもつことはむしろ自明であったが、近代のいわゆる科学的態度にとってはこの ような非共役なものを内側に入れた存在論はパラドックスであり、分けた世界の間の繋がりは断ち切らねばならなかった。このことは、無時間的であった存在論 が時間化したためであると説明されるかもしれない。そしてルールが一定であることの意味が、時間的な変化の中でのルールとして考え直されてきたということ であるかもしれない。現代科学の図式には、無時間な永遠の真の場所が入り込めないようである」(p.79)。(→ドッズ「ギリシァ人と非理性」)。
・「人間の普通の生活の中では、目的と手段という因果の繋がりで考える「思考の習慣」はほとんど自明である。目的とは行為の目標であり、そ こに集中して向かう方向づけをなすものであって、さまざまな行為がその目的のための手段と化して方向づけられるとともに、そうした手段相互を関係づけるこ とをめざすものである」(p.79)。(→ホント?_塚本はヒュームの懐疑論を継承している)
・「カントが述べたように目的が現実的な形で意味をもつのは結局、実践的な場面で「あの人に三時に会おう」といった目的を設定する能力をも つということであって、あとはほとんど自動的に原因ー結果の系列ができあがり、その中で最も効率的なものを選べばよいのである。……そこには一つの因果の 結びつきのモデルないしテンプレートがあって、それに合わせてさまざまな系列がつくられるということである。そして、そのモデルが科学的方法なのである」 (p.80)。(→行動の説明=解釈であるが、たとえば再現性などを保証するものではない)
・行動の説明=解釈と塚本が考えている証左として、その後に、科学的説明はモデルが有用であり、規範となりうるということを説明している (p.80)。
■ヒュームの役割(カントに対する?)
「ヒュームは、因果律を否定したのではなく、繋がりがあるはずなのにその根拠が見出せないこと、すなわちわれわれが「結果」を見ているのに 原理的に原因を特定できず、因果の繋がりを観察できない、ということにショックを受けたのであった」(p.81)。(→本当にショックなのか?_ヒューム の理性的判断なのか?)
■テレオロジーは現在に生き残る?
「われわれの経験から出発するのであれば、むしろ船の運行から材料である木や鉄を説明するのが当然ではないだろうか。こう考えてくると科学 の「還元」という方法は、実は出発点で、それ以後に出てくる登場人物の名がすでに書き込まれてようなシナリオをつくりたいからに相違ない、と思われてく る。……すなわち物語が始まるときには、すでに結末がわかっているのである。このような考え方は構造的にみると、目的論的な発想と全く異質なものではない という奇妙な現象が見えてくる」(p.82)。
■現場実践における境界領域画定作業
「通常の日常生活では、思いがけない問題が出てきたときにどのような解決の方法があるかを、われわれはその場で模索せざるをえない。しか し、必ずしも個々の問題を予想できなくても、もし問題の立て方をそれを処理するための対策にあらかじめ合わせておけば、解決の方法は見つけやすい。そこで 特定の方法が設定したルールの中で処理される種類の問題だけを問題と認め、そのルールを合理的とか科学的とよんで、問題解決のモデルとしたのであった」 (p.83)。(→シャドーボクシングにしては空振りしすぎでは?)
・科学的合理性の勝利について、事後的(post hoc)に説明をする「以外」の説明ができない(p.85)
■疎外論(生産からの疎外)
「われわれの生活がいつ技術社会になったかを特定するのは難しいが、どこかの時点で生産のプロセスが人間の手から一段と離れたものとなっ て、もっと多く生産するために、道具が自動的に生産を繰り返す機械に変容したのであった。そこにいわゆる疎外がはじまる」(p.86)。 ・この後、[評者=私にとって]わけのわからない説明が続く……
2. テクネー、アルス、アート 87
・彼女の説明によると、近代ではアリストテレス流の「エピステーメ、テクネー、フロネーシスの三分法が崩壊し、制作知としてテクネーを基礎 とした「近代の知の図式」が新たな変貌をとげたことを[我々は]見てきた」らしい(p.87)。
【図1】(p.13)より
[リンク]アリストテレスの実践知入門(池田光穂)
■テクネーの変貌(テクネーの専横?)
「かつてテクネーはエピステーメではない「有限で変化する人間の知」にかかわるものとして分類されたが、今や「有限で変化する人間の知」こ そが中心になって世界はつくり直され、テクネーは科学的方法に基づいて一つの共役な世界、いわば「科学の共同体(The Republic of Scinece)」(M. Polanyi)をつくり始めたのであった」(p.87)。
・テクネーのテクノロジーへの変貌(pp.88-)
・この後、彼女のテクネー論がつづく(p.88)
・「芸術的なアートがテクネーから生まれ、さらにテクネーではないアートという観念が生まれてくる」(p.89)
・「今日の技術の観念が、古代ギリシャのテクネーと重なりながらも、かつその分け方のレベルが1つではないということである」 (p.90)。
・テクネーの概念に、芸術(ファイン・アート)という概念が「割り込んできた」。(p.90付近の説明を参照)
2.1 神の知の世俗化 90
・アリストテレス派の機械学の引用をおこなった後で、「人間のテクネーは必ずしも自然が望むそのままには働かないという認識でもある。人間 にとって自然は必ずしも自分たちの利益に沿うものではなく、むしろ脅威だったり不都合と思われることが多いが、それは自然が基本的に同じ仕方で単純に働く のに対し、われわれの利益のほうは多様で絶えず変化するから、しばしば思いのままにならないことが起こるのであろう」(p.91)。 ・「メカネーが自然的であるよりも人工的・人為的で、わざとやることであり、その場その場で変化する人間的な利益を実現するための、さまざまな結果をつく り出す工夫であることは明らかであろう。……テクネーがその本来的な、いわば自然の仕上げとして善にむかうべきロゴスから区別され、人間の困難の当座の解 決のための制作(ポイエーシス)にかかわるものとして捉えられている」(p.92)。
・メカニカ(ラテン語)ーメカネー(ギリシャ語):テクネー(=ロゴス)……ポイエシス
・「うまい工夫といった意味で「メカニカ」はこうした個別的な工夫の集合体」であり「「梃子のさまざま」ではあったが「梃子の原理」ではな かったらしい。このことは自然の内在的な目的ではない目的が外から課されるという点では、近代の目的論の排除に繋がっているのかもしれない。……ラテン語 の ars mechanica は、当初は具体的なものではなく、ものをつくる(ポイエーシス)と言う意味で一般的であるが、さまざまな制作に関して複合的な知識が集められ包括的に表さ れたものであったらしく、必ずしも統一的なものではない」(p.92)。
・メカニケ・テクネーをめぐる議論がつづく(pp.93-)
2.2 アルス・リベラーレスとアルス・メカニカ 95
・7自由学芸(アルス・リベラーレス)に関する説明
・神の知の世俗化としてのアルス・リベラーレス(p.97の冒頭の6行)
・デ・アルキテクトゥーラ(ウィトルウィウス Vitruvius Pollo Marco)(p.98)。
・「アルス・リベラーレスとアルス・メカニカとの分類と統合の過程で、次第に今日のアートの意味につながる意味合いを備えるようになる」 (p.100)。→p.102で詳述。
2.3 作法というアルス 103
・アートという概念をめぐる変遷の解説
・「アリストテレス的な制作(ポイエーシス)と行為(プラクーシス)という分け方をのせてみると、アルスは行為の外に所産を生み出すテク ネー(ポイエーシスの知)ではなく、プロセスそのものである身の処し方に専念しているのが特徴といえよう。この場面では、テクネーとアルスの相違はテク ネーとフロネーシスの相違に重なってくる」(p.106)。
・ポイエシス/プラクシス
・テクネー/アルス::テクネー/フロネーシスの関係?
(再掲)【図1】(p.13)より
==【作図の再掲】===
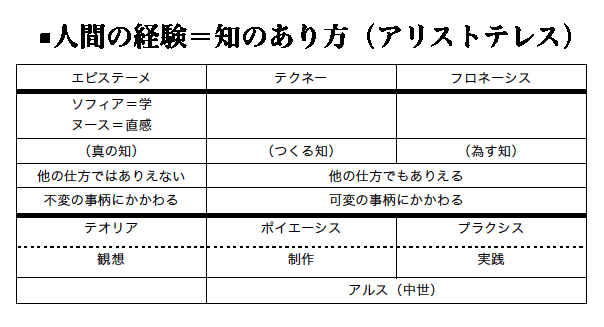
■アルスのもつ3つの意味(p.106)
(1)ポイエーシスに重なるアルス、すなわちものを加工したり有用なものを制作するアルス
(2)作法としてのアルス。行為過程の外にではなく為す自分自身のうちに自らの身体を秩序づけ、感情を制御し表現し、そして儀礼として神秘 的内容形式を与えるという意味で、アリストテレスが初めに区分したフロネーシスに近い知アルス
(3)間接化、メタ化、様式化としてのアルス。すなわちもっとも審美的で芸術的な意味に近いアルス。
・アートに関するフーコーの議論を使って塚本の解説を相対化できないか?
3. 芸と術の間ーーコリン[グ]ウッドの美学 107
■コリングウッド『芸術の原理』に倣いて
「今日のテクノロジーは、近代の技術とはさらに異なった様相を呈している。ハイデガーも述べるように、テクノロジーの問題は技術的(テクニ カル)な問題ではなく、われわれがテクノロジーをどう捉えるかという本質的な問題なのであり、かつてアリストテレスが直面したようなテクネーの危うさや捉 えにくさが、近代を超えてあらためて姿を現してきているようである」(p.109)。
・「楽しみ(amusement)は、感情の高揚と解放そのものを目的としており本来のアートではなく、また魔術(magic)も、人々の 感情を刺激して呪縛し、政治や戦争や教育などの実践的な活動に駆り立てるための手段となるという意味で、本来のアートではないという。どちらも感情を喚起 するもので、前者はカタルシスを与え、後者は実際的な行為へのエネルギーの源となるが、ともにアートの本質ではないという理論である。彼(=コリングウッ ド)によれば魔術はひとつの技術(道具)であり、求める結果を生み出すための手段となっている。それに比べると娯楽(遊技)は「それを享受するため」で あって芸術に近いとも見えるかもしれないが、しかし楽しみとは感覚的刺激であり、これもまた感情喚起のための道具であり手段であって、楽しみを芸術とよぶ ことのほうが、魔術を芸術とよぶことよりもむしろ危険であり、批判すべきであるという」(p.112)。
【まとめ】
・アリストテレスの図式(=エピステーメ/テクネー/フロネーシス)がどのように崩壊したのか?
・近代は、それに代わり、どのような図式になったのか?_また、それをおこなったのは誰なのか、どのようにして、そのことについての人びと もその図式の変動を共有していたのか?
==雑多なメモ==
【ソクラテス以前】
「プシュケはまさに生者を生者たらしめるものであるにもかかわらず、ホメロスにおいては、いかなる特定の活動とも結びつけられていない。 「思い描くこと」あるいは「計画すること」を叙述するときに彼が好んで使う語はヌースであり、これはしばしば「精神」と翻訳できる」(Anthony Long, 『西洋思想大事典』2巻、p.626)。
「エンペドクレスと異なり、アナクサゴラスは知覚を対立するものの相互作用と見なした。われわれは外的な熱をわれわれ自身の中の冷たさに よって認識する。彼はまた極端な実在論者であって、あらゆる質的な差異を物質そのものの根本的差異と解した。彼の同時代人の原子論者デモクリトスは、この 理論に反対した。彼はわれわれが知覚するすべての性質を、物体の状態の変化、およびさまざまな形態の原子との相互作用に帰着させた。デモクリトスは魂(身 体中に分布した球状の原子)と宇宙の原理が同じ実質をもつと考えた点で、ソクラテス以前の哲学者たちの一般的見解と一致している」(同書、p.628)。
【プラトン】
・プラトンにおける魂と神体の極端な二元論(『パイドン』)。ただし「この極端な二元論はプラトンの究極的な言葉ではなかった。『国家』 (IV巻)における魂はもはや統一ではなく、ヌース(「知性」)とテュモス(「情念」)とエピテュミア(「欲望」)に分かれる。その欲望的部分には身体的 欲望が結びつけられる。テュモスは情動的な部分であり、このおかげでわれわれは怒りや恐怖を感じる。ヌースは、テュモスに助けられて欲望を従属させる支配 原理である(あるいはそうなるべきである)」(同書, p.628)。
「プラトンの心理学は、固定した教義のような体系的な教説ではない。彼の魂についての見解は『パイドン』の非妥協的な二元論から出発し、理 性と情動と身体的欲求の間で調和を確立すれば統一的自己に到達できるという説へと発展していったのだ。身体と精神は快楽と感覚を通じて互いに関係づけられ ている。だがプラトンは理性の優位についての信念をけっして捨てなかった。理性は真に実在的で、不変の世界に親和的であり、その本質的な機能はこの世界を 理解することなのである」(同書、p.629)。
【アリストテレス】
「後期の著作『霊魂論』においてアリストテレスは、身体と魂を単一の実体たる「生命をもつ身体」の2つの様相、概念的にしか分けられない2 つの様相と見なす(II, 1)。これらの2つの様相をアリストテレスは「質料」と「形相」とよぶ。
「アリストテレスは魂を「可能的に生命を有する自然的身体の第1の現実態」(『霊魂論』412a 27-28)と定義する。「第1の現実態」とは、生命に必要な諸能力の現実的所有を意味している、眼が眼であるためにはそれが視力をもたねばならないと いったぐあいである。この概念からすれば、身体と魂が必然的に関係づけられるのは明らかだ」(同書, p.630)。
「とりわけ重要なのは魂と思考と感覚と知覚(アリストテレスの用いるアイステシスという語は感覚と知覚の両方を含む)を司る原理だとする考 えである」(同書, p.630)。
【ベイコン主義】
「彼(フランシス・ベーコン)の思想が近代的なのは、その当時の文化の最も進歩的な運動を彼が支持したというよりはむしろ、ベイコンが学問 にこれまでとは異なった役割を割り当てたためである。彼は知識を所与の現実の観照や認識としてではなく、狩猟(venatio)、見知らぬ土地の発見とし て理解している。……彼は革命的な科学上の仮説をつくり出さなかったし、近代科学の地平を大きく変えることになる発明にも貢献しなかった。」(パオロ・ ロッシ「ベイコン主義」『西洋思想大事典』4巻, p.253)。
・ベイコン[主義]の意義「科学は、たとえ内的にみれば没価値的であるとしても、実際は倫理的価値や政治的社会的生活の射程と無縁ではな い。科学は友愛や進歩などの価値を実現するために人間が構築した手段である。こうした価値は、協同、自然に対する謙虚さ、明晰であろうとする意志などを規 則とする科学そのものによって、強化され、増強されなければならない。説得のために構築された人文主義者の論理学は、学者の論争のためよりは、作品の制作 に役立つ発明と発見の論理学にとって代わられるべきである。自然に対する人間の能力の拡張は自らの成果を秘密にする唯ひとりの探求者の仕事ではなく、国家 や公的団体の資金で組織された科学者の集団の賜物である。歴史の領域では、科学は常に明確な実践的役割を有志、学問の改革はいかなるものであれ常に文化的 制度と大学の改革でもある」(パオロ・ロッシ「ベイコン主義」『西洋思想大事典』4巻, p.253)。
「ベイコンが構想していたように、科学(学問)は偶然や気まぐれ、そして性急な総合などを放棄し、人間の類似(analogia hominis)によってではなく、宇宙の類似(analogia universi)によって構築された実験主義を基礎として前進しなければならない」(パオロ・ロッシ「ベイコン主義」『西洋思想大事典』4巻, p.254)。
【虚偽意識】
・「マルクスとエンゲルスは、イデオロギーに軽蔑的な意味合いを付与した。なぜなら、彼らは、すべてのイデオロギー的思考を論理の不誠実な 使用、支配階級の立場を正当化するために行われる意識的ないしは無意識的な事実の歪曲であると見なしたからである。イデオロギーとはエンゲルスの特筆すべ き言葉によれば「虚偽意識」を意味する。虚偽意識は行動に根拠を与えるという主張は、……観念とイデオロギーある程度の自律を享受するという認識、すなわ ち、観念の経済的システムへの依存に関するマルクスの初期の所説とは両立しない認識を提起する」(Mustafa Rejai, イデオロギー, 『西洋思想大事典』1巻, p.133)。
・「[カール・]マンハイムのアプローチは、重要な点でマルクスのアプロー チとは違っている。(マンハイムは)イデオロギーを全体的な社会構造、とくに政治党派の上に基礎づけた。……さらにマンハイムは、マルクスのアプローチは 不当にも2つの異なったタイプのイデオロギーを混同している、と主張する」。つまり部分的イデオロギー概念と全体的イデオロギー的概念である。「部分的イ デオロギー概念とは、「イデオロギーという言葉によって、たんに敵対者の特定の〈理念〉や特定の〈考え〉が信じられないという程度のことを意味する場合で ある」『イデオロギーとユートピア』pp.55-56, 邦訳166頁)。これが部分的なのは、この批判が全体への批判に展開しないからだとマンハイムは主張する。他方「人は、ある時代のイデオロギー、ないし時 代や社会によって具体的に規定されたある集団――例えば階級――のイデオロギーについて語ることができる。この場合には、イデオロギーという言葉によっ て、その時代なり集団なりの、全体としての意味構造の特徴や性格が考えられている」『イデオロギーとユートピア』p.56, 邦訳166頁)(Mustafa Rejai, イデオロギー, 『西洋思想大事典』1巻, p.134)。
【ヒュームの『人間本性論』1739-1740】
・彼によれば「因果性の観念の内容は、因果関係をなすものとして見られる対象が近接し、原因が結果に時間的に先行し、原因と結果の間に必然 的関係がある」と思えることである。この関係は「原因の必然性を観念間の関係に知覚できない、しかもその必然性は論理的に証明もできない」。ヒュームは、 この「観念を生み出す印象」を心のなかに見出す。「心は、繰り返して生ずる類似の事実が頻繁にもしくは恒常的に連接するのを十分な数だけ観察すれば、この 規則性が繰り返されるのを期待する習慣を獲得し、ひとつの事実が与えられると、通常それに随伴するものの存在を期待し信」じるようになる、という。「因果 性についてのこの分析は、因果関係という観念に根拠を与えるが、同時に因果推論にその制限を課す。つまり事実推論は、過去の経験にのみ基礎を持つのであ り、それを未来について確実性をもって適用できるという保証はない。これはいわゆる「帰納の問題」である。ギリシア以来の西欧の知的伝統において、原因に 基づく知識は真なる知識の典型とされてきた」ので、これは当時の西洋の推論の伝統からみれば、ヒュームの議論は大きな挑戦(=懐疑論)になった。(神野彗 一郎「『人間本性論』」『岩波哲学・思想事典』1998:1238-9)。
本章(塚本明子)への批判
1)アリストテレスのエピステーメー、フロネーシス、テクネーの説明における、文化相対主義的配慮が欠けているために、啓蒙主義の哲学史観 ――とくに知が発展し、それが批判され、さらに乗り越えられて現在のようになった――に引きずられているのではないか?
2)それぞれの時代における、エピステーメー、フロネーシス、テクネーに相当するものの間のダイナミズムを過少評価している。そのため、3 つの知と技の静態的な通史概観の記述スタイルが否めない。
3)著者には、フロネーシスの救済(それに対してテクネー=罪悪説をとる)という強い動機があり、それらが論点先取の議論や、論証における 詰めの甘さになっているのではないか?
Copyright Mitzub'ixi Quq Chi'j, 2009-2017