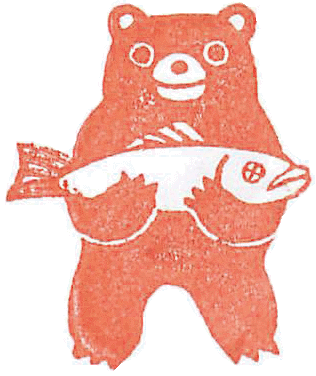


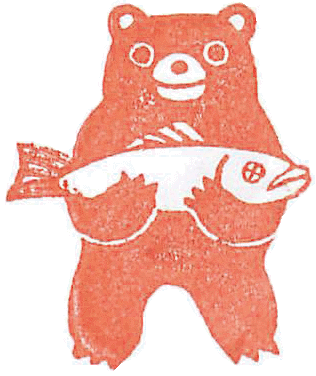


身体の社会的決定論への批判
A Critique for the Social Determination of Human Body
解説:池田光穂
人類学者は、長い間、象徴システムあるいは集合表象 が上空から降り注ぐように個体に浸透して内面化されるという身体観に魅了されてきた。
身体と身体が織りなす“技法”へのM・モース (1976[1935])の関心は、身体の知覚と行動に関する社会的な強制力を明らかにしたM・ ダグラスの研究(1983[1970])に結実すると一般には考えられている。
しかし、これは過度に単純化した議論である。ダグラ スの関心は、社会言語学者B・バーンスティン(1981[1971])に影響を受け、グ リッドとグループという個人に対する社会強度と境界という指標が当該の社会の身体観とどのような関係にあるのかということにある。
ダグラスのモースに対す る言及は驚くほど少なく、彼女が批判しているモースの議論についての内容は論理的に説得力を欠くものである。なぜなら、彼女は、モースが否定していた自然 発生的行動の存在を一方では指摘しておきながら、その行動は最終的には文化=社会によって規定されると言う。身体構築の最終審級を彼女は、文化=社会に求 めるわけだ。ところが、彼女の言うところの、自然発生的行動あるいは無意識は、文化において一般的共通性のあるもののことを指すという。これは、文化概念 を境界のあるものだとして捉えた場合──彼女の主張はそれ以外に何を考えることができるだろうか、この行動や無意識とは、文化を共有する成員にのみ通用す る通貨のようなものであり、後天的に学習されなれければならない。ところが、その通貨を流通させる市場──ここではメディアとしての身体──についてダグ ラスは多くを語らない。それはモースが言う、身体の3つの階層のひとつである、生理学の次元だからである。
このようにして、身体構築の最終審級として文化
=社会的なるものを究極的に証明しようとすると、どこかで身体の生理学的基礎、すなわち身体のメディア性という普遍的事実を密輸入せざるを得ないのであ
る。
身体の社会的あるいは文化的決定論は、それを成り立たせる認識論上の議論からも限界がある。つまり、象徴システムあるいは集合表象が上空から
降り注ぐように個体に浸透して内面化される身体という見方を取ることができる認識論的位置を保証するものは何か、またそれを見ている当の身体とは誰なの
か、という疑問が生じる。
Copyright Mitzub'ixi Quq Chi'j, 2014