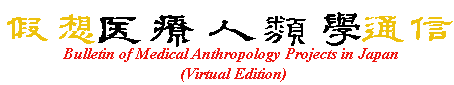
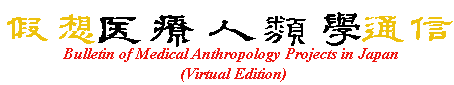
第2号 (1998年10月/1999年2月増補改訂)
身体を鋳込みなおす
―身体構築に関する社会倫理の探究―
池田光穂
本論文は、サイバースペースで提起している拙論における社会意識の産出についての 考察【リンク】の続編である。私は前回の論文の冒頭部分において次のように問いかけた。「我々が 経験のレベルで異質の倫理の時空間に踏み込むことは、人類にとって新しい倫理の時空間に踏み込んだことになるのだろうか」と(池田 1998:20)。ここでの私の関心は、経験のレベルで異質な時空間に踏み込む、ということの身体的根拠について問うことである。
この問いかけの背景には、メディアと社会意識の関係を、身体と個人の意識との関係として捉えることで、メディアと社会意識の間に横たわる自 律・包摂・庇護・従属・影響などの諸々の関係について、身体と個人の意識との関係から問い直すという問題意識を私がもつからである。このアナロジー的思考 は、経験的には十分容認されうるべきものであるが、それらの間には、方法論的「個人」主義と方法論的「社会」主義との間の裂け目、あるいは後者の伝統に位 置づけられてきたE・デュルケームが晩年に到達した二重の人間Homo duplex という命題に遡れる、深い渓谷が横たわっている。個人的存在と社会的存在(=社会)を強制力をもって結びつけるものとして、デュルケームは道徳的事実── 我々はそれを社会倫理と呼ぶ──に着目することに注意を促したが、その橋の上から見おろす水面は遥か谷底に見え、川底に何があるのか、深いのか浅いのか、 現在に至るまで何も解らずじまいである。
身体と社会に関する議論は、大きく2つの流れに収斂させることができる。つまり、象徴システムあるいは集合表象としての社会あるいは社会性が 上空から降り注ぐように個々の身体に浸透して内面化されるという図式と、外部からの不自然な力に抗う主体の器としての身体を考えるという図式の二種類の思 考法がある。
本論文のねらいは、身体と社会に関する諸理論におけるこのような相反する2つのパラダイムを指摘し、この対立図式から逃れる複数の身体の可能 性をさぐり、高度メディアのインターフェースたる身体の位置を今一度確認することにある。私が身体論という古典的なテーマに回帰するのは、次のような理由 からである。
社会が身体を構築するというデュルケーム的あるいは社会人類学な身体観に馴染んだ研究者は、現代医療における生物医学の身体観の図式を過度に 単純化したり──生物医学を要素還元という性格に押し込めておくのはあまりにも要素還元である!──その影響関係の政治的局面のみを誇張しがちである(佐 藤 印刷中)。そのため人々の“伝統的”身体観をア・プリオリに措定したり、近代医学の対抗言説として過度に単純化する傾向が強い。このような医療「人類学的 執着」(田辺 1997b)から逃れることが、まず第一点。そして、我々にとっての未知という単純な理由から、身体を媒介とした相互交流の中で人々がどのような行為実践 をおこなっているのかについて理解可能となるような新しい研究方法を開発しなければならないということが、その第二点である。
「身体を鋳込みなおす」という表題を付けているのは、他者の身体の可能性を問うことが、自己の身体の可能性を問うことに繋がるということを私 が確信しており、高度メディア社会における社会倫理についての議論の基礎づけとしたいからである。
まず、我々の常識となっている生物医学的身体についての議論から始めよう。というのは、この常識にある、いくつかの思想史的前提を明らかにす ることで、その常識を相対化することに目標を置きたいからである。
西洋の生物医学の伝統においては、身体は複雑ではあるが、要素還元的理解が可能となる自動機械(automaton)として想定する。要素還 元的であり分析可能な自動機械としての身体は、普遍的なモデルに還元できるのみならず、身体を操作する“主体”が身体の中に宿ることを可能にする。そのよ うな可能性を開いたのは、身体を操作する“主体”が身体の中に宿ることを要求してきた啓蒙主義的伝統の産物だと言える。主体が住みつくことが可能になる身 体と、そこに主体が宿ることは、その際、区別して考えねばならないが、この種の多くの議論は、主体が身体に住みつくのみならず、主体が身体の主人であるこ とを要求することが、あたかも当然であるかのように考える。つまり個(individual)の確立というものを目標にして身体をどのように制御すること ができるのか、あるいはできないのかを議論の核心に据えてきた。
生物医学的身体観は、理論的ならびに実践的課題として、デュルケーム的な個人の身体を統制する外部性(=社会の集合表象)に自律的であること を、要求する。社会性に目覚めた精神分析学者や人間主義的心理学者は、社会の文化的強制力が個人をねじ曲げてきたことを指摘し、身体とその主たる個人を解 放する必要を主張する(ライヒ 1977[1974];マスロー 1998[1982])。そこでは、外部の強制力から自由になった“自然な身体”があることが理想とされている。人間身体の自然のあり方、自然の発達、自 然の経過、自然の成熟という、医療の道徳家が説く、我々になじみの深い言説は、ここから来ているのである。
生物医学的身体は、その意味では我々の主体のあり方についての極めて自然な身体観としてあるかのような印象を受ける。だが、これは肉体を嫌悪 する西洋近代思想という大伝統のもとでは、比較的新しい部類に属する。
というのは、西洋近代思想の中では、身体は主体の住処としては、不十分であるということが出発当初から認められられてきたからである。そのた め、肉としての身体を憎悪し、真理としての意識を特権化する。唯物論的伝統は、肉なき主体を批判するのであるが、そこで前提としてされているのは、歴史的 条件からは逃れることのできない身体の固有性についてである。真理の担い手としての主体をアルチュセールはブルジョアのイデオロギー的実践のメカニズムで あるとして批判する。
──すべては──役割を転倒されて──私に呼びかけ、私にみずからの真理の再認識を要求する観念の外部で、「かのように」生じるのです。そのよ うにあるイデオロギーを構成する諸観念が、人間の「自由な意識」を強要して、そうした観念が真であると自由に再認識させるかたちで、個々人に呼びかけるの です。したがって個々人は、現前しているところで「真理」を再認識できるような、つまり、イデオロギーを構成する諸観念における「真理」を再認識できるよ うな、自由な主体としてみずからを構成するように義務づけられることになります(アルチュセール 1993:105)。
──私としては、「具体的人間」(複数形での)こそが必然的に歴史における主体であると主張します。‥‥しかし、担い手として考察される個々人 は、哲学的な意味での「自由で構成的」な主体などではありません。‥‥彼らは社会的生産関係の歴史的な実在諸形態の諸決定のなかで、それら諸決定のもとで 行動するのです。イデオロギー的諸関係は、あらゆる個人=担い手に主体という形態を押しつけます。だが、あれこれの主体である人間は、歴史の主体には(社 会的・歴史的な実践の担い手を)変えません。主体は、歴史のなかで行動するのです(アルチュセール 1993:139)。
アルチュセールの預言者的な指摘を、唯物論者のそれとするのではなく、西洋近代思想における特異で新しい身体観の基礎づけとしたい。つまり、 生物医学的な身体の成り立ちの普遍性とは、それに宿る主体の自由を保証するものではなく、身体の社会的拘束ということが逃れられないという事実にある。
人類学者は、長い間、象徴システムあるいは集合表象が上空から降り注ぐように個体に浸透して内面化されるという身体観に魅了されてきた。
身体と身体が織りなす“技法”へのM・モース(1976[1935])の関心は、身体の知覚と行動に関する社会的な強制力を明らかにしたM・ ダグラスの研究(1983[1970])に結実すると一般には考えられている。
しかし、これは過度に単純化した議論である。ダグラスの関心は、社会言語学者B・バーンスティン(1981[1971])に影響を受け、グ リッドとグループという個人に対する社会強度と境界という指標が当該の社会の身体観とどのような関係にあるのかということにある。ダグラスのモースに対す る言及は驚くほど少なく、彼女が批判しているモースの議論についての内容は論理的に説得力を欠くものである。なぜなら、彼女は、モースが否定していた自然 発生的行動の存在を一方では指摘しておきながら、その行動は最終的には文化=社会によって規定されると言う。身体構築の最終審級を彼女は、文化=社会に求 めるわけだ。ところが、彼女の言うところの、自然発生的行動あるいは無意識は、文化において一般的共通性のあるもののことを指すという。これは、文化概念 を境界のあるものだとして捉えた場合──彼女の主張はそれ以外に何を考えることができるだろうか、この行動や無意識とは、文化を共有する成員にのみ通用す る通貨のようなものであり、後天的に学習されなれければならない。ところが、その通貨を流通させる市場──ここではメディアとしての身体──についてダグ ラスは多くを語らない。それはモースが言う、身体の3つの階層のひとつである、生理学の次元だからである。このようにして、身体構築の最終審級として文化 =社会的なるものを究極的に証明しようとすると、どこかで身体の生理学的基礎、すなわち身体のメディア性という普遍的事実を密輸入せざるを得ないのであ る。
身体の社会的あるいは文化的決定論は、それを成り立たせる認識論上の議論からも限界がある。つまり、象徴システムあるいは集合表象が上空から 降り注ぐように個体に浸透して内面化される身体という見方を取ることができる認識論的位置を保証するものは何か、またそれを見ている当の身体とは誰なの か、という疑問が生じる。
この身体をセクシュアリティとの関連で考えると、かのM・フーコー(1986[1976])の逆説めいた命題がすぐに思い起こされる。主体の 在処を、セックスという強迫的な二元論の構造に統合し、近代人のアイデンティティ形成にセクシュアリティが大きな意味を果たしてきたという指摘である。西 洋近代世界におけるセクシュアリティの言説の極限に近い拡散を通して、逆にセクシュアリティのあり方が規定されてきたというのである。これは言い得て妙で ある。それはフーコーの晩年の言説実践という観点からという意味である。フーコー自身は、この逆説を自己を構成する“技術”──それはモースの“技法”を 思い起こさせる──という観点から迂回しようとした。
──主体はある象徴システムのなかで構成されるというだけでは十分ではありません。主体が構成されるのは、実際のところ、象徴のはたらきによる のではないのです。それは実際のさまざまな実践なかで構成されます。さまざまな象徴システムを用いながらそれらを横断するような自己構成のテクノロジーと いったものがあるわけです。[フーコーの発話、引用はドレイファスとラビノウ( 1996:337)]
もちろん、その分析と研究は容易ならざるものがある。
──自己の技術の分析を困難にしているものが二つあります。一つは、自己の技術は、物質の生産と同じような物質的装置を必要とせず、したがって それはしばしば目に見えない技術となっていること。もう一つは、自己の技術はしばしば他者を指導するための技術と結びついているということです。たとえ ば、教育制度を取り上げてみますと、そこには他者を管理すると同時に、自己を統制する術を他者に教示していることがわかります[フーコーの発話、引用はド レイファスとラビノウ( 1996:339-340)。
身体を介した他者との相互浸透の現場を見るということを通して、自己の身体の構成を変えていこうという戦略をとるのだが、それ自体がやりにく いものであり、さらに、その行為実践が他者の身体の変容を余儀なくするものであるということだ。この時期のフーコーが、サンフランシスコの同性愛者の“友 愛”の共同性や、SMプレイにおける“合意”の問題に深く関心をもっており、自らそれを実践していたことは、それ自体で示唆的である(ミラー 1998[1993])。
以上のように西洋の生物医学の伝統においては、身体は複雑ではあるが、要素還元的理解が可能となる自動機械として想定する。他方、身体構築の 文化=社会決定論では、身体はいかようにでもなりうる──これは文化的拘束命題の逆説である──完全なメディアとなる。
現在までの多くの人類学者が自らのフィールドワークの結果を分析する際に愛して止まない身体観は、この相反する2つの身体観──つまり生物医 学的身体観と社会文化的身体観──のうち後者の伝統に属するものである。
社会文化的身体観における、“身体”とは、分析者が暗黙の前提としてもっている──事前には証明されることのない──身体の構造のことであ り、個々の人々が共有しているモデルとして想定されているものである。
このモデルを理解するためには、個人は何らかの心的表象をもっていなければならず、身体観の共有は、成長や生活の過程の中で、客観的構造であ る身体に心的操作を加えることから形成されると仮定する。 したがって、身体のあり方を解明するためには、身体所作への類別的な関心のみならず、その“技法”が幼児期にどのようにたたき込まれるのかを観察し、身 体そのものが社会のメタファーとして語られる言説を分析しなければならない。
このような身体観の大きな2つの流れを概観すれば、世に数多ある医療人類学の諸研究が、どちらかの伝統に属することを見てとれることができ る。つまり、それらは、(i)象徴システムあるいは集合表象が上空から降り注ぐように個体に浸透して内面化される身体パラダイムと、(ii)外部からの不 自然な力に抗う主体の器としての身体パラダイム、という2つの流れに収斂する。さらに、病気に関する一連の民族誌研究もまた、(i)その経験を文化的にパ ターン化されたものとして描く傾向と、(ii)その固有の経験を社会に対するメッセージとして人類学者が解釈する傾向に二分されていることがわかる。
医療人類学における解釈学的な研究方法は、苦悩の語りの意味を分析することによって、この2つの傾向を調停・緩和する試みを続けてきた。しか しながら、これらの研究は、ともすれば語りの意味論に傾斜しがちであり、病んだり・悩んだり・本復したりする人の相互作用への十分な注意がなされていない という指摘がある(Kleinman 1986, 1988; 田辺 1997b)。
さて、身体の技法から、先にあげた生物医学的身体の形成とは異なり、社会的な制限を受けながらも身体が自発性をもちながら構築されるものであ ることを理論化した功績はP・ブルデュに与えられるであろう(Bourdieu 1977)。モースが身体技法に関する議論の中で使ったハビトゥス=アビティス(habitus)の用語と概念をブルデュは自己の理論の中に独自の変工を 加えながら横滑りさせる。彼によると、ハビトゥスとは、身体に刻まれた一連の傾向のことであり、実践の母体となるものである──habitusがまさに “体質”として実体化しており、唯物論的根拠をもつかのように感じるのは私だけであろうか。実践を構成するものとしてハビトゥスに関して、彼が過剰と思え るほど詳細に論じるのは、主観主義と客観主義等の一連の対立を調整しようとする彼の意図である。ハビトゥスに関する彼の議論においては、文化的に獲得され た身体性であるところのハビトゥスが、社会的に刻印されたものでありながら、移調可能な形で再生産し、それが実践を生成すると同時に限界づけると主張して いる。ブルデュー派の社会学者のジャーゴンである「構造化する構造」、「構造化された構造」は、ハビトゥスを通して、身体と社会が結びつくまさに境界面( interface )についての様態を表象しているのである。福島真人(1995, 1997)は、モースからブルデュに至る身体構築論に加え、ロシアの発達心理学者ヴィゴツキーの北米での再評価や、レイヴとウェンガーの正統的周辺参加の 理論に関する広闊で精緻な議論をすでにおこなっているので、ここでは先の2つの身体論にとって、この身体構築学派たちがもたらす意義について以下に指摘す るにとどめておく。
それは、まず第一に、身体構築論の理論的な融通性である。象徴システムが個体に浸透して内面化される過程を過度に単純化せずに、個体の実践的 な学習過程に着目したことである。第二に、主体の器としてみる身体観が要求する無根拠な普遍原則も拒否したことである。ここで重要なことは、個人や個体 (individual)と社会の間を、カテゴリー間の対立やせめぎ合いとしてみる身体観から、歴史と社会に規定されざるを得ない具体的な個人が、どのよ うにして社会が要請する枠組みの中で自分に適合する身体を作り上げてゆくのか、という両者を切り結ぶ観点を提示したことにある。
認知科学の発展に伴って、フィールドに活動の現場に身をおく人類学者にとって身体構築のモデルとして有望視されてきたのがレイヴとウェンガー (1995[1991])の正統的周辺参加(Legitimate Peripheral Participation, LPP)の理論である。LPPの提唱の背景には、彼らが、命題的知識の獲得を目標とする従来の教育に対する批判的スタンスが見える。言い替えれば、学習を 認知過程と概念構造の変化を通してみる知識偏重の見方から、学習を社会的過程として捉えなおした時に見えてくる社会的文脈の問題を彼らは重視するのであ る。
LPPには、その概念に関連する2つの重要な別の概念がある。実践共同体(community of practice)と十全的参加(partial participation)である。実践共同体とは、LPPを可能にする社会的文脈を提供する環境のことであり、彼らがとり上げた事例には、徒弟制や共 同体の成員が実践を通して緩やかに結びつく職種集団──具体的には、伝統的出産介助者(産婆)、仕立屋、繰舵手、肉屋、断酒中のアルコール依存症者などが 挙げている。また、十全的参加とは、新参者が実践共同体に周辺的参加を通して知識や技能を習得する実践あるいは実践の様態をさす。ここで重要なことは、十 全的参加と正統的周辺参加とは、相互に排除するものではなく、緩やかな移行を想定したものであり、実践共同体の成り立ちを保証する共に不可欠な実践の形態 ということである。
──正統的周辺性というのは、権力関係を含んだ社会構造に関係している複雑な概念である。人がより一層強く参加するように動いてゆく場として、 周辺性は権力を行使する位置にある。また、より一層の十全的参加からは距離をおかれている──これは社会全体をより広い観点から見ればしばしば正統的なこ とだが──という点で、権力を行使できない位置でもある。それ以上に、正統的周辺性は、関連する共同体の結節点だとも言える(レイヴとウェンガー 1995:11)。
──十全的な参加は……周辺性の概念のある一側面を浮き彫りにしたに過ぎない。これは部分的参加(partial participation)とは異なること、あるいは部分的参加では尽くせないことに強調点をおく。私たちの用語では、周辺性は積極的なことばでもあ り、これに対するもっとも明確な概念上の反意語は進行中の活動への無関係性(unrelatedness)あるいは非関与性(irrelevance)で ある(レイヴとウェンガー 1995:12)。
──実践共同体では、「周辺」だと指し示せるようなところはないし、もっと強調していうならば、単一の核とか中心があるわけではない。中心的参 加(central participation)といってしまうと、共同体に個人の「居場所」に関しての中心(物理的にせよ、政治的にせよ、比喩的にせよ)が一つあることに なってしまう。完全参加(complete participation)といってしまうと、何か知識や集約的実践の閉じた領域があって、新参者の「習得」についての測定可能なレベルがあるかのよう になってしまう。そこで私たちは周辺的参加が向かって行くところを、十全的参加(full participation)と呼ぶことにした。十全的参加というのは共同体の成員性の多様に異なる形態に含まれる多様な関係を正当に扱おうと意図したも のである(レイヴとウェンガー 1995:11-12)。
LPP理論や実践共同体の考え方の骨子は、(1)知識の二元論批判──知識の全体論と名づけておく、(2)知識の実体論批判──“知識は真空 の場において獲得されるものではない”という命題を掲げるゆえに、これを知識の関係論的理解と呼ぼう、(3)認識の際の実践の重要性あるいは不可避性、 (4)身体の歴史性──“身体は普遍的で超時間的存在として把握できない”──である。
LPPを民族誌事例として検討する際に感じる隔靴掻痒という感覚の原因は、たぶんLPP理論が批判して止まない、学習の二元論的還元に、人類 学者そのものが未だに固執している傾向が少なからずあるからなのだろう。つまり、具体的な実践に接して、そこからLPP理論に沿った形で、学問的教訓を引 き出すようなあり方を、じつは当のLPP理論が否定しているにもかかわらず、人類学者がそれを流用しようとしている事実がある。もし、外在する理論として LPPをとらえ、それを人類学理論として取り込むという図式があるのなら、それはLPPの考え方によって批判されなければならない──これは私による自己 批判でもある。
他方、LPPが指摘するようなことは、人類学者には周知の事実であって、なんら新しいものをつけ加えてはいないのだ、という批判は容易であ る。「現地人の視点から見る」という習練の目標を掲げてきた人類学は、フィールドワークそのものが現地人社会という集団に正統的周辺参加することを通して 民族誌的資料を収集してきたからだ。
しかし、だとすれば、LPP理論が古典的学習論に対して挑んだ意味を重要な教訓として、人類学者は何も学んでいないことになる。なぜなら、 LPPを通して学んだ民族誌学的知識を、人類学者は社会やそこに属する当事者から切断された、あたかも外部に存在するものとして表象し、その知識を書物の 形式の中に配列することを通して、いわゆる民族誌というものを描いてきたからである。人類学者の裏切りとは、LPPを通して学んだ民族誌的知識を、古典的 学習論による非LPP的知識として表象するということなのである。
例えば文化人類学者の現地語の学習について考えてみよう。
トロブリアンド諸島のマリノフスキー(1980[1922])の民族誌の冒頭の部分には、言語を学ぶということがいかに現地人の世界を知るう えで重要なことであるのかが力説されている。
エヴァンズ=プリチャード(1978,1982)のヌアーの民族誌には、アザンデにおける言語習得に比べて、ヌアーの言語の習得がいかに困難 であったのか、そして、ヌアーの連中の振る舞いが、いかに人類学者の調査の妨げになったのかについて苦言が述べてある。
高地ビルマのカチンの民族誌には、リーチ(1987)がいかに現地語に通じていたかが、誇らしげに書かれてある。
フィールドワークの教科書的知識では、言語を学ぶことがフィールドワークの前提条件になっており、言語を習得してから、現地調査が可能になる という表現をしばしば見つけることができる。あたかも、言語を学ぶ以前の調査が充分でない状態と、言語を流ちょうに話すことができるようになった以後に、 切断があるかのように書かれてある。
言語の習得は、フィールドにおけるコミュニケーションの根幹であり、ここからフィールドワークが、あるいは民族誌的記述が始まるというのであ る。
しかし、これは嘘である。なぜなら、言語の習得というのは、連続的なプロセスであり、いつまでたっても終わりがないからである。ことばの意味 が飛躍的にわかるようになる瞬間とは、言語の運用能力がある一線を越える瞬間ではなく、ことばを含めた理解の構図の配置が変わった時なのではないだろう か。ある人なら「明示的=推論的コミュニケーション」が可能になったからだと言うかも知れない。
だから、外在化された知識としての民族誌的記述は、言語的=記号的コミュニケーションという回路を通して採集されたものとして書かれてあり、 またそのような知識を特権化するように機能してきたのである。
言語的=記号的コミュニケーションという回路を通してのフィールドワークと、そこから得られた──正確には“構成された”──外在化された知 識は、ある種の隠喩を通してある種の解釈が可能になる。それは真理としての知識である。フィールドには、どこかに真理が隠されており、会話をはぐらかした り、嘘をいう現地人から、上手に話を聞き出して、その真理が埋められた場所を探し出し、最終的に発掘することに成功するという話である。真理とは、クラで あり、分節的リネージ体系であり、グムラオ・グムサの振幅に他ならない。
真理とは誤りがないということだ。だから、マリノフスキーの日記はスキャンダルになった。真理の発見の背景に、汚れた意図や操作──という読 者の期待──があったからである。この種のフレーミングは、自然科学者の実験データの捏造というスキャンダルとよく似ている。
では、言語的コミュニケーションを通して得られた真理問題という構図を人類学者は拒絶したのだろうか? それは、放棄されなかった。いやむし ろ、真理問題について直接対決することなく、真理の追求という問題を棚上げにしたまま、我々の先達は延命策を講じてきたのだ。それが、真理の書である民族 誌とは別に、その背景的描写である「民族誌的出会い ethnographic encounter」を、補足的に、まさに「補遺」として出版することだった。例えば、Paul Rabinow,Reflections on Fieldwork in Moricco(1977)、Jean-Paul Dumont, Headman and I(1978)、そしてVincent Clapanzano, Tuhami (1980)などである。
記号化されないコミュニケーションが、言語的=記号的コミュニケーションの収集にとって重要であることを指摘したのはギアツの「ディープ・プ レイ」(1987[1973])である。ところが、現地の警察による闘鶏の手入れにギアーツ夫妻があたふたと逃げ帰ったエピソードは、それ自体の知識とい う習得についての洞察にいたることなく、厚い記述と相俟って、言語的コミュニケーションの特権化と、それを得ることができる以前と以後のフィールドワーク の時間の切断としてしか取り扱われることとなった。これは、現地語がわかるということを特権化した、民族誌の先達の体験を、隠喩的に読み変えただけのエピ ソードにしか、私には思えない。つまり、真理の発見的発掘という物語は一向に変更されなかった、ということになる。
LPPにもどって、これを人類学的考察として読むときに、私が一番気になったことは、果たして言語的=記号的コミュニケーションによる真理の 発掘という物語を、克服することに寄与することに成功しているのだろうか?、ということである。LPPが、古典的な民族誌が繰り返しおこなってきた真理の 発掘の別のヴァージョンであるならば、私にとって、この著作はまったく魅力のないものだ。実際、LPPをめぐるこの著作において、彼女たちは民族誌記述の ことについてなんら批判的考察はおこなっていない。真理の書としての民族誌的記述を自明のものとして、LPPの素材を引き出すことが重要なのだから、批判 的考察がないのは当然と言えよう。
私にとって、LPPを取り扱う意義は、我々の身体構築に変更を加え、人間存在の可能性──人間の多用な可能態──を探究するという倫理的行為 に対して、LPP理論どれだけ潜在力を持ちうるかということなのである。
生まれながらの同性愛者(ゲイ)は存在しない、人はゲイになるのだという指摘はおそらく妥当であろう。ゲイに対するインタビュー記録やゲイ・ アクティビストの文献を読めばそれが確かめられる。ゲイになることは、さまざまな不安を克服し、喜びに向かってゆく過程そのものだからだ。私がゲイの問題 をとり上げることの意味は、ゲイの身体経験とLPPが接点を持ちうるからである。ここでは、日本の男性のゲイに関する限られた文献的知識にもとづく分析の 素描を紹介し、身体構築に関する私の目標と見通しについて述べてみよう。
その前に、ここで、ゲイを人類学の対象とする際の“必然性”について、多少なりとも正当化しておかなければならない。それは、次のようなこと である。私が尊敬するある人類学者に「池田さんが、なぜゲイを普通の人と区分して特権化して論じる必要性があるのか、私は了解できない。ここに足袋をみて 興奮する人たちがいる。池田さんは“足袋をみて興奮する人”よりも“ゲイ”が研究対象として優先する理由が説明できるのか?」という指摘を受けた。まった くその通りだと思う。ゲイを人類学者として特権化する理由の背景には、ゲイを“我々と異質の人”として表象しようとする暗黙の前提があり、このことがゲイ の研究が、ゲイの差別的言説(例えば同性愛嫌悪 homophobia)と知らない間に「同盟関係」を結ぶこともあり得るだろう。しかしながら、それでもここでゲイをとりあげることを研究者として自己弁 明したい。それは、ゲイが“足袋をみて興奮する人”たちに比べて現在の社会体制のもとでは──女性と同様──有徴な存在であり、それ以外のカテゴリーの人 たちにくらべて劣位の意味づけがなされていることだ。このことは、劣位の徴を私が除去したいという欲望をもつということに他ならないが、他方で、そのよう な社会的認知の差は、研究対象のカテゴリー間の違いに還元できない、歴史的社会的な独自な存在であるということを認めることでもある。だから、私はゲイの 認知上の特異性について論じるつもりはなく、ゲイの社会上の特異性について関心があるのだ。もちろん、ゲイを考察の対象にし、ゲイの身体のあり方が、ゲイ ではない人との相違点と類似点を明らかにすることが、結果的にある種の社会的効果を持ちうるという前提をにおいて、そのように私は発話している。
さて、ゲイであることに関する図式的理解を示せば次のようになる。
ゲイには、同性愛者であることを隠したり、将来の生活にたいする漠然とした不安がある。つまり、その悩みの程度はさまざまだが、異性愛制度か ら排除されることによってこうむる同性愛者の苦悩がみられる。他方、ゲイには、日常生活において隠された喜び(joy in closet)を満たす同性愛を示唆する“記号”を、自ら発見しつつ主体的に解釈するという行為がみられる(Russo 1987)。多くのゲイは、同性愛者のアイデンティティを秘匿する一方で、同性愛の喜びを最大限に引き出そうとする実践を、洗練させるようになる。つま り、同性愛者であることを日常生活として違和感のないものにし、自己の認識と身体感覚を生活の中でバランスのとりながら構築してゆくのである。
また、アイデンティティを秘匿しながら、日常生活をおくるゲイたちがいる一方で、カミング・アウトを通して、より高くて新しい自己実現をもと めたり、同性愛者の不当な処遇の改善を異性愛制度にむけて発言する人たちがいる。
このような同性愛者たちが共有する価値観や世界観の体系というものを「文化」と名付け、彼らには独自の文化があると言うこと、それ自体には深 い意義はない。ゲイ社会の価値観は、全体社会から孤立し自律したものではないからである。ゲイ文化は、異性愛者が作り上げている「優位の」文化と密接な関 係を持ち、半ば強制的に半ば自発的に、作り上げられてきたものであることが明白だからだ。しかしながら、そのことを通して、同性愛と異性愛の性的傾向は、 相互排除するものではなく、両立しうるものだ、あるいは、同性愛者と異性愛者の区分は、あくまでも恣意的にすぎず、人間の性愛の多様な様態──例えば Freudによるpolymorphously perverse(多型倒錯)という概念──の変種にすぎないという主張に到達すれば、それで議論は終わりになるだろうか。それらは、異性愛者のセクシュ アリティを相対化するのには役立つであろうが、さまざなセクシュアリティをもつ同じ世界に住む隣人どうしの関係にとって、納得できる合意には至らないであ ろう。
ここで直面するのは、やはり医療人類学研究における、内蔵感覚としての「共感」と知識的認知としての「理解」という問題である。文化相対主義 を奉ずる異性愛者の研究者にとって、同性愛者について理解することは二重の難しさがある。まず同じ社会に属するこの「異質な隣人」である同性愛者について の語りや生活についての記録(動くゲイとレスビアンの会(アカー)編 1992; 矢島 1996, 1997a, 1997b)を読めば、それは決して理解したり共感したりすることが、とくに困難なものではないという「印象」をすぐに抱いてしまうという誘惑にはまるこ とである。ところが身体の次元における同性愛嫌悪(homophobia)は、観念のレベルでの理解を簡単に払拭してしまう。これが第一点。そして、ゲイ が、同性愛者として我々の社会の中で普通に振る舞うということがいかに苦悩に満ちたものであるのか、そしてカミング・アウトを通して同性愛者が正常なもの として自らを肯定することがどれほど驚くべきことなのか、ということを異性愛者は理解しにくいという事実がある(アカー編1992:3)。これが第2点で ある。
それでは、ゲイにしかゲイの世界は分からないのか。異性愛者の人類学者は、ゲイになってみずから「ゲイである」ことの意味を体験しないと理解 に到達することができないのか。そして、ゲイを研究することの意味は、いったい誰に対して、どのような意味をもつのであろうか。結局のところ、文化人類学 がくり返し問いかけてきた、他者への理解と自己との関係という重要なテーマが頭をもたげてくる。しかし、それは同じ社会の隣人のことを理解するという観点 からは多少傲慢な考えだと言えないだろうか。同じ社会に属する隣人という発想は、R・マーフィー(1992:217)から着想を得た。したがって、障害者 (病人)もまた、“異質な文化をもつ異民族”ではなく、“同じ社会の隣人”という観点から、理解される必要があるということである。
カミングアウトするゲイ・アクティビストたちが突いてくるポイントは、ゲイ文化に理解のある異性愛者がゲイにむける「まなざし」が、ゲイであ るというリアリティを、認識論的に相対化するだけでなく、異性愛者に対して理解可能な形で提示することを通して、その中にある権力関係を中和化してしまっ たということにある(Asad 1986)。
また、ゲイ・アクティビストたちが依拠する一つの理論としてクイアー理論がある。これは、従来のゲイとレスビアン研究からテイクオフした独自 の研究領域であり、ジェンダー間の差異という理論上の拘束を避けるためにセックスを特定することを廃棄するという、ある種の宣言的な内容をもつものであ る。異性愛者に対するゲイの理論の批判的独創性は、クイアーの存在がフェミニスト理論に提起することと同様、研究対象のカテゴリー間の差異を政治化するこ との限界を指し示すことにある。女性の身体へのフェミニスト人類学者のアプローチは、男性偏重主義的傾向を持ち続けてきた現代医療の問題点を浮き上がらせ ることに成功してきたのみならず、それまで閑却視されてきた「女性」の身体の社会的歴史的構築に関する諸研究に新しい知識をつけ加えた。しかし、女性の身 体という、現代社会の中では本質的属性をもつと考えられている研究対象を中心に据えることにより、女性の身体への医学による抑圧と解放への言説の行使とい う研究の枠組みそのものが、女性の身体の本質性という神話をより強固にする道を切り開き、女性でもない男性でもないクイアー的存在──主体を持とうとして いる我々はすべて「部分的アイデンティティ」の持ち主でしかない──である我々の身体への理解の可能性を閉ざすことに繋がらないだろうか、という問いかけ を発生させるのである。
いかなるものでもカテゴリー間の認識論的固定化は、結局、権力構造におけるヘゲモニーを掌握する連中に利益をもたらす。したがって、それを避 けるためには、権力構造が要請するカテゴリー間に風穴を空けることが、逆方向の観点から要請される。ゲイ・アクティビストの中には、異性愛者と同性愛者の 間の緩やかな連帯を求める声がある。そこで目標とされているのは、ゲイが我々の社会の中に権利をもった「一種のサブカルチャーとして」取り込まれるかどう かということではなく、それまでの社会になかった新しい“文化の形式”を作り上げることができるのかということである。ゲイの新しい文化とは、身体構築を とおして、ゲイ自らを作り治すことに他ならない。身体を鋳込み治している彼らの実践は、人間の新しい可能態について提起していることであり、我々の社会に おける実践であることは言うまでもない。
この論文は、国立民族学博物館共同研究会「認知と実践」(代表者:田辺繁治教 授)における発表「医療人類学 における共感と理解」(同館、1998年2月7日)および、第32回民族学会研究大会分科会「現代医療の文化人類学」(西南学院大学、1998年5月24 日)での、私の発表「身体を鋳込み治すこと─現代生活における実践─」【リンク】での発表 内容が基礎になっています。生産的な批判とコメントをおよせくださった以下の方(敬称略・順不同)の名前を記して謝意を表します。田辺繁治、慶田勝彦、村 上隆則、飯嶋秀治。