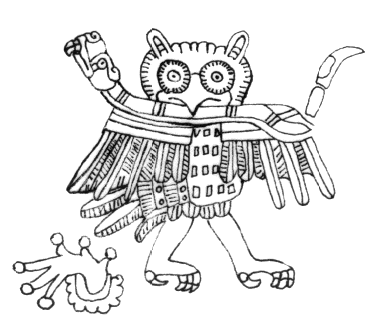
太田好信編『政治的アイデンティティの人類学:21世紀の権力変容と民主化にむけて』昭和堂書評
(『文化人類学』寄稿前・ロング・ヴァージョン)
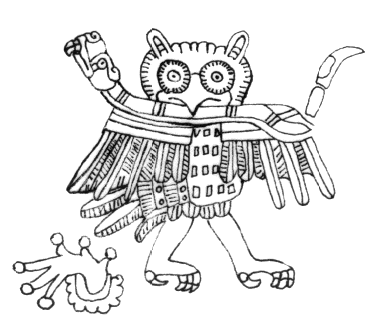
太田好信編『政治的アイデンティティの人類学:21世紀の権力変容と民主化にむけて』昭和堂、2012年。340, +10pp.,
4,800円+税
現代社会における「文化の政治化」や「アイデンティティの政治」についての論集だろうという予見をもって本書を紐解く人は、編者である太田好信による序
論を読み進めるあいだに奇妙な気持ちに苛まれることになるだろう。現代を生きる我々の時間性についての議論、ヘイドン・ホワイトを中心とした時間と歴史認
識論が今日の文化理論にもたらす影響、すでに解決済みだと言われてしまう国家の先住民に対する責務の見直しなどの種々の議論が、本書のタイトルにもなって
いる「政治的アイデンティティ」という新たな理論的枠組の提唱と明確な交差点を持たないように思えるからである。しかし推理小説を読むように冒頭から謎掛
けを浴びせられることは、我々にとってはすでに経験済みかも知れない。つまりこうである。放り込まれたフィールドの現場が渾沌であればあるほど逆に、人類
学者は嫌々ながら再訪を余儀なくされるものであり、もはやその探求を途中で止めることができなくなる。フィールドの魅力とは、謎掛けと謎解きのコール&レ
スポンスがその人の心に響くことだ——人類学者という天職は大いなる辛酸となけなしの快楽の繰り返しかもしれない。評者は、本書を知識や理論の源泉として
ではなく、現場からの問いかけに耳を傾けること、端的に言えば、フィールドワークの実践の仮想的な代替としてこの本を読んだ。
さて本書は、2007年から09年度まで続いた国立民族学博物館共同研究会の報告書として公刊され、その内容は4部構成で1本の総説(序論) と10の論文(各論)からなっている。その4部構成の細目は、第1部「政治的アイデンティティの系譜」、第2部「文化的アイデンティティと政治的アイデン ティティの差異」、第3部「先住民という政治的アイデンティティの行方」、第4部「政治的アイデンティティの外縁」となっている。総説をふくむ11本の論 考をその(章の序数)「題目:副題」(執筆者)について以下に列挙し、その後に各章の要約を付してみよう。
第1部「政治的アイデンティティの系譜」では、太田好信・慶田・内藤の3論文が含まれる。太田論文は、副題の「パワーの視点」にみられるよう に権力から当事者アイデンティティを構成する議論すなわち「政治的アイデンティティ」の理論構築に力が注がれている。これは、アイデンティティをベースに した当事者集団がその社会的承認を得ようとする運動の他称である「アイデンティティの政治」とは趣旨を異にすることが明確に述べられている(pp.42- 48)。政治的アイデンティティの理論的彫琢のために取り上げられる主たる2つの事例は、ルワンダの虐殺事件とメキシコのチアパス州におけるサパティスタ の軍事的蜂起であるが、そこから派生する議論の範囲は1848年のマルクスの著作「ユダヤ人問題」から、クリフォード・ギアツの1960年代の新興国家 論、オバマ大統領就任以降のポスト人種社会論まで多岐にわたっている。
慶田論文と内藤論文は、2007年のケニア総選挙の前後をめぐるそれぞれ異なった社会状況に焦点が当てられている。まず慶田論文では、ケニ ア・ナイロビ郊外の世界有数のスラムであるキベラで2007年の総選挙後の不正抗議に端を発する暴動での「線路引き剥がし」事件を扱う。この暴動は、アカ デミズムが複数政党による国内の統治の脆弱性に着目することに注意喚起しながら、最終的にはニュースメディアでは部族的・民族対立にすぎないという「単一 の物語」に回収された。しかし慶田は、メディア情報と歴史資料の詳細な分析から、キベラの「主」であるキベラ・ヌビ(スーダン人退役兵士が語源)のアイデ ンティティが(a)軍事的、(b)脱部族化した、(c)再部族化した、という3つの特性からなることを指摘する。そこからキベラ・ヌビが、自らの植民地支 配とケニアへのディアスポラ経験を通して「線路」がケニアとウガンダの領土問題とケニア政府の統治能力を問う象徴的シンボルとなりえ、「線路引き剥がし」 が粗暴な暴力の発露ではなく政治的諸権利の主張の隠喩的表現となりえるとしている。内藤論文は、ケニア北部のサンブルとレンディーレの混成牧畜集団である アリアールが、彼らのライサミス選挙区において、財政配分制度などを社会資源として、レンディーレとサンブルという2つの出自や文化的来歴のエピソードを 使いながら「マサゲラ」というアイデンティティを主張し政治的言説を構成(しかつ選挙後に消滅)していったかが、事例を通して検討されている。
第2部「文化的アイデンティティと政治的アイデンティティの差異」では出利葉・黒木の2論文が含まれる。出利葉論文では、アイヌの人びとをア イデンティティの観点から捉えるのではなく、道立の北海道開拓記念館という博物館が、アイデンティティをどのように理解し、それをさまざな民族表象をとお して政治的に構成しているのかという議論がなされる。具体的には、アイヌの工芸家が、自己の創作活動のために博物館展示物の借覧を求めたケースと、展覧会 に先だって内見会に招待された工芸家グループが、借用を受けた海外の資料館からの要望をそのまま受けて(彼らの制作活動に不可欠な)手で触れる許可が認め られなかったケースが扱われる。文化を担う当事者が、自らの文化の展示物にアクセスできないことの政治的含意が議論される。ここではアイデンティティの帰 属の問題よりも、文化資源としての展示物の管理を通して、実際のところ誰がその管理権限をもつのかということが焦点化され、博物館やそれを運営している行 政自治体の「所轄」にあることが事件を契機に暴露されてしまう。
黒木論文は、筆者の日系アメリカ人女性への調査を中心とし、北米アジア系女性のジェンダー、エスニシティ・宗教をめぐる種々の文献を広く渉猟 した広闊な議論が展開されている。そこでは、アジア系アメリカ人、汎エスニシティなどの分類範疇が疑問に付され、筆者のいう「はざま」の存在としての彼女 らのアイデンティティのゆらぎが指摘されている。ただしさまざまな理論や先行研究が広範囲に引用されており議論の幅もフェミニスト神学などにも言及されて いるため、門外漢の評者はここでは十分な論評と判断をすることができない。
第3部「先住民という政治的アイデンティティの行方」は、清水・池谷・小林の3論文が含まれる。
先住民の国際法と条約について研究を積んでこられた清水氏による該博なこの論文は、先住民の概念を規定する(先住民当事者のみならずそれ以外の 様々な)エージェントやそれらの国際的な関係構造、部族(tribe)、先住民ないしは先住の民(indigenous peoples)、民(peoples)やそれを支える自己決定権などが、とりわけ2007年の国連総会で決議採択された「先住民権利宣言」をめぐってダ イナミックに議論され、国際政治力学の中で固有の概念の場所をみつけたことが詳細に分析されている。先住民の概念には自己決定に訴えるイデオロギー性がみ られ、何人の介入をも退ける政治的機能をもつと主張されている。だが、それはもうひとつの「政治的な介入」である学術の関与をも退ける概念だと筆者は締め くくっている。評者もその通りだと思うが、それは我々が切歯扼腕するようなルサンチマンではなく、それ自体が研究対象になり、我々の前に呈示されている点 で学術からの「再関与」の可能性が完全に閉ざされているわけではないとも考えられる。
池谷論文は、1990年代後半からはじまるボツワナ政府による中央カラハリ動物保護区をめぐる立ち退き政策に直面した先住民サンの訴訟運動、 それを支援する(先住民概念の意識を異にし、それに従い支援の方針も異にする)ヨーロッパの2つのNGOとの絡まりと、さらには国連人権委員会をも介入し た、事件の顛末を活写する。そこでは、外部からの介入による先住民の政府に対する抵抗の様式も分化、多様化し、また時系列においても動態的に変化する。先 の清水論文で指摘された「先住民受け口(tribal slot)」が1990年代以降に状況を複雑化することを教えてくれる貴重な報告になっている。
小林論文は、メキシコ中部の先住民プレペチャ(かつてタラスコと呼ばれた)で試みられた自治をめざすナシオン・プレペチャというNGOの組織 の立ち上げと頓挫について、国際援助組織との関係、先住民集団を尊重するのではなくむしろ「多様なものを管理」する傾向を強めてゆくメキシコ合衆国中央政 府との複雑な関係の顛末について書かれている。プレペチャの中心地であるミチョアカン州は中南米の初期インディヘニスモ運動の基盤となった1940年第1 回インディヘニスタ・インターアメリカン会議の開催地であった。1975年には「参加型インディヘニスモ」を謳う第1回メキシコ先住民会議が開催されてい る。そのため先住民自治組織の政治化は早くから進み、国会政党の各派組織と密接な関係をもって発展してきた。この自律した動きは、1994年1月のメキシ コ最南端のチアパス州におけるサパティスタ国民解放軍(EZLN)の蜂起以降もゆるやかな連帯をもっていた。小林はその内部崩壊の理由を、司法権の確立が サパティスタに比べて不十分で、また行政執行職者の輪番制が十分機能せず固定化したことに求めている。
第4部「政治的アイデンティティの外縁」では、武内論文と太田心平論文が取り上げられている。
武内論文は、人口少数派であったトゥチが主に50万人(当時の国内人口の3/4に相当)も犠牲になったルアンダにおける、内戦後にトゥチを中 核にする政府の反ジェノサイド政策の分析である。政府は内戦後の反対派勢力を「ジェノサイド・イデオロギー」の体現派とみなし、特定の民族が殺されるジェ ノサイド概念を使って、多数派フトゥにも生じた犠牲者の存在を認めない政策をとってきた。論文の大部では虐殺の経緯に加えて、国際刑事裁判所の設置や国際 社会からのジェノサイド認定と、そのイデオロギー化の過程が詳細に描かれている。武内によるとこれらの政治的アイデンティティの形成は、ジェノサイドを生 むに到ったエスニシティの政治化が、トゥチとフトゥともにステレオタイプを伴って再編制されている。このことが「ジェノサイドを繰り返さない」という国際 社会に是認された標語を通して、このステレオタイプに該当しない、反体制勢力やフトゥの内戦犠牲者、あるいは二分化されない民族アイデンティティをもつ人 たち——例えば第1章で解説されている「クウィフトゥラ」——への社会的排除の原因になる可能性を示唆する。
太田心平論文は、ニューミレニアム以降に、貧困からの脱出やよりよい生活を求めて海外移住する人以外に、「韓国にいたくない」という理由によ り海外に移民する「絶望移民(チョルマン・イミン)」と呼ばれる人びとの語りとその動機を分析したものである。筆者は、韓国内における文化の均質性と社会 的分節の多様性の歴史的動態について説明した後に、絶望移民に多い三八六世代(1990年代に30代で、1980年代に大学生でかつ学生運動に参加し、 1960年代生まれの世代)の語りについて分析している。とりわけ三八六世代が同時代に体験したユートピアとその挫折が、このような移民を生んだことを示 唆している。
編者の太田好信は、序論において政治的アイデンティティの理論と、これらの各論文がもつ位相について4つのポイントを指摘しているが、それら すべては民族誌事例を分析する際に、各研究地域やその研究ジャンルの中ですでに決定済みで定番とされてきた先行する理論的枠組が、現地の人びとの政治的ア イデンティティに注目することで、疑問に曝されたり、場合によっては解体されたりする可能性を強く示唆している(pp.22-26)。本書は、各論文の民 族誌事例が詳細で豊かで、それぞれの論者が編者の提唱による独自な(sui generis)な政治的アイデンティティの理論を受けて、各論者が非常に中味の濃い議論をおこなっている論文集である。それらを評者が過不足なく紹介し たとは決して言えないが、最後に評者のコメントとして一点のみを指摘する。
それは、政治的アイデンティティという理論的枠組みの可能性についてである。編者は、政治的アイデンティティを含めて、権力(パワー)により 構築される範疇とみなす発想が、人びとが直面している歴史認識、国家とそれに帰属する少数民との権力関係、多様性を認めつつもそれが国民国家の統合を揺る がすのではないかという多数派への危惧などの難問に回答を与えるのではないかと示唆する(p.26)。そして範疇による本質化が否定され、政治権力が担保 され、社会から排除がなくなれば、財産・人種・宗教・ジェンダー・文化的実践などの「構造化の土台となった特徴は……集団化の原則として無意味になるだろ う」(ibid.)と述べる。だが、寄稿された諸論文には、権力により構築される範疇が、様々な政治過程の中で解体されると同時に、別の権力過程により再 構築、再々構築されてゆく様を、読者は見る(=読む)ことになる。範疇による本質化が否定されることが(ヘーゲル的な意味で)止揚され社会から排除がなく なるのは、それだけでは自明な過程ではありえない。再範疇化による本質主義の再生産を明らかにすることと、それに抗する別の次元の社会的状態への移行の処 方箋の間には、更なる付加的議論が必要であるように、評者には思われる。だが、始まりとしての議論の使命は十分に果たしている。本書評が契機になり、近い 将来それぞれの問題関心に引きつけてより深い読解と議論ができるよう会員諸氏への便宜としたい。
リンク
文献
その他の情報

Copyright Mitzub'ixi Quq Chi'j, 2014-2018
Do not paste, but [re]think this message for all undergraduate
students!!!