Dios ya habia muerto, así que lo humano ha sido salvado
神は死んだ、をめぐる人間の誕生
Dios ya habia muerto, así que lo humano ha sido salvado
池田光穂
★神は死んだという命題について
1.基督(キリスト)は我々の罪のために一度死んだ のだから、死から 甦った以上、もはや死ぬことはない(アウグスチヌス『神の国』12-14)、という言挙げの前半の理由をのべた節は、ニーチェのそれ(=神は死んだ)と同 じだということに、今 気づく。
2.本田正昭というひとが1967年に「時熟論一考 --ニーチェとアウグスチヌスに於ける時間意識の構造に関する一比論」という論文を書いているがこれは時間論だ。
3.ふつう、アウグスチヌスとニーチェが交点を結ぶ のは「自由意志」論であると言われる。
4.アウグスチヌスをパラフレイズすれば、神は自ら の死によって人間を救う、それゆえに、人間は救われた状態にあるという、人間の存在論が導けるのである。
5.「人間は救われている」。そうするとニーチェ は、ニヒリズムや実存主義の始祖というよりも、居直りにも近くトコトン楽観的に逝こうという(神様はとりあえず脇においてもよいのだという)人間肯定主義 の始祖のようにも思われる。
6.ニスベットのSocial change and history(邦訳:歴史とメタファー)を読んでいて、気づく。
7.post hoc propter hoc (その後それゆえに)というアウグスチヌスの時間・宿命論と、アラリック1世(Alaric I, 370-410)のロー マ侵攻による基督教徒の恐怖と、神を自分の身体性の延長(res extensa) に位置づける——死体だから横たえるのほうがいいか——という何の関係もないものが、むすびつくわけです。ここにいわゆる今日常識化・定式化したキリスト 教(ローマカトリック)がようやく誕生するわけですね。儀礼のイデオロギーと儀礼行為と、それに伴う情動の三位一体が成立するわけだ。
8.Dios ja habia muerto, así que lo humano ha sido salvado. - Q.E.D.
☆父の機能を基礎付けるのは父親殺しだとフロイトが父なるものを守るように無神論の公式は「神は死んだ」ではなく「神は無意識的である」なのです——ジャック・ラカン「精神分析の四基本概念」(78-79ページ)
★「神は死んだ」(ドイツ語: Gott ist tot [ɡɔt ɪst toːt] ⓘ;神の死とも呼ばれる)は、ドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェによる主張である。ニーチェの著作におけるこの主張の最初の例は、1882年の著書 『愉快な科学』に見られ、そこでは3回登場している。[注1] このフレーズは、ニーチェの『ツァラトゥストラはこう語った』の冒頭にも登場している。 この文の意味するところは、ニーチェが言うように「キリスト教の神への信仰が信じられなくなった」以上、「この信仰の上に築かれ、支えられ、成長してき た」ものすべて、すなわち「ヨーロッパ全体の道徳」も「崩壊」せざるを得ない、というものである。[1] 啓蒙の時代は、多くの人々が自らの信念に疑問を抱くほどに、人類の集合的知識を変化させた。この概念の枠組みは、無神論の観点から、神は現実ではなく人間 の心の中に存在しうることを示唆している。そのため、神への信仰の喪失は神の死を意味することになる。 この概念については、フィリップ・マインレンダーやゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルなど、他の哲学者たちも以前から議論していた。このフ レーズは、『神の死』神学でも議論されている。
| "God is dead"
(German: Gott ist tot [ɡɔt ɪst toːt] ⓘ; also known as the death of God)
is a statement made by the German philosopher Friedrich Nietzsche. The
first instance of this statement in Nietzsche's writings is in his 1882
The Gay Science, where it appears three times.[note 1] The phrase also
appears at the beginning of Nietzsche's Thus Spoke Zarathustra. The meaning of this statement is that since, as Nietzsche says, "the belief in the Christian God has become unbelievable", everything that was "built upon this faith, propped up by it, grown into it", including "the whole [...] European morality", is bound to "collapse".[1] The time of the Enlightenment had transformed collective human knowledge to the point where many would question their beliefs. The framing of the construct suggests that God could exist, from an atheistic perspective, in the minds of men rather than in reality, and so widespread disbelief would equate to God's death. Other philosophers had previously discussed the concept, including Philipp Mainländer and Georg Wilhelm Friedrich Hegel. The phrase is also discussed in the Death of God theology. |
「神は死んだ」(ドイツ語: Gott ist tot [ɡɔt
ɪst toːt]
ⓘ;神の死とも呼ばれる)は、ドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェによる主張である。ニーチェの著作におけるこの主張の最初の例は、1882年の著書
『愉快な科学』に見られ、そこでは3回登場している。[注1] このフレーズは、ニーチェの『ツァラトゥストラはこう語った』の冒頭にも登場している。 この文の意味するところは、ニーチェが言うように「キリスト教の神への信仰が信じられなくなった」以上、「この信仰の上に築かれ、支えられ、成長してき た」ものすべて、すなわち「ヨーロッパ全体の道徳」も「崩壊」せざるを得ない、というものである。[1] 啓蒙の時代は、多くの人々が自らの信念に疑問を抱くほどに、人類の集合的知識を変化させた。この概念の枠組みは、無神論の観点から、神は現実ではなく人間 の心の中に存在しうることを示唆している。そのため、神への信仰の喪失は神の死を意味することになる。 この概念については、フィリップ・マインレンダーやゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルなど、他の哲学者たちも以前から議論していた。このフ レーズは、『神の死』神学でも議論されている。 |
| Early usage Discourses of a "death of God" in German culture appear as early as the 17th century and originally referred to Lutheran theories of atonement. The phrase "God is dead" appears in the hymn "Ein Trauriger Grabgesang" ("A mournful dirge") by Johann von Rist.[2] Before Nietzsche, the phrase 'Dieu est mort!' ('God is dead') was written in Gérard de Nerval's 1854 poem "Le Christ aux oliviers" ("Christ at the olive trees").[3] The poem is an adaptation into a verse of a dream-vision that appears in Jean Paul's 1797 novel Siebenkäs under the chapter title of 'The Dead Christ Proclaims That There Is No God'.[4] In an address he gave in 1987 to the American Academy of Arts and Sciences, the literary scholar George Steiner claims that Nietzsche's formulation 'God is dead' is indebted to the aforementioned 'Dead Christ' dream-vision of Jean Paul, but he offers no concrete evidence that Nietzsche ever read Jean Paul.[5] The phrase is also found in a passage expressed by a narrator in Victor Hugo's 1862 novel Les Misérables:[6][7] "God is dead, perhaps," said Gerard de Nerval one day to the writer of these lines, confounding progress with God, and taking the interruption of movement for the death of Being. Buddhist philosopher K. Satchidananda Murty wrote in 1973 that, coming across in a hymn of Martin Luther what Hegel described as "the cruel words", "the harsh utterance", namely, "God is dead", developed the theme of God's death according to whom, to one form of experience, God is dead. Murty continued that commenting on Kant's first Critique, Heinrich Heine who had purportedly influenced Nietzsche spoke of a dying God. Since Heine and Nietzsche the phrase Death of God became popular.[8] |
初期の使用例 ドイツ文化における「神の死」という概念は、17世紀にはすでに登場しており、当初はルター派の贖罪理論を指していた。「神は死んだ」という表現は、ヨハ ン・フォン・リストの賛美歌「悲しみの墓碑銘」(Ein Trauriger Grabgesang)にも登場している。 ニーチェ以前に、「神は死んだ」というフレーズは、1854年にジェラール・ド・ネルヴァルが書いた詩「オリーブの木々のキリスト」に書かれていた。 [3] この詩は、ジャン・パウルの1797年の小説『ジーベンケーゼン』の「死せるキリストは神はいないと宣言する」という章のタイトルで登場する夢幻を詩に脚 色したものである。 [4] 1987年にアメリカ芸術科学アカデミーで行った講演で、文学者のジョージ・スタイナーは、ニーチェの「神は死んだ」という表現はジャン・パウルの前述の 「死せるキリスト」の夢幻に負っていると主張しているが、ニーチェがジャン・パウルを読んだという具体的な証拠は提示していない。[5] このフレーズは、ヴィクトル・ユゴーの1862年の小説『レ・ミゼラブル』の語り手による表現にも見られる。[6][7] 「神は死んだのかもしれない」と、ある日ジェラール・ド・ネルヴァルはこれらの行を書いた作家に言った。彼は進歩を神と混同し、運動の停止を存在の死と捉 えていた。 仏教哲学者のK. Satchidananda Murtyは1973年に、ヘーゲルが「残酷な言葉」、「辛辣な発言」、すなわち「神は死んだ」と表現したものをマルティン・ルターの賛美歌の中で見つけ たと記している。誰が、どのような経験から、神は死んだというテーマを展開したのか。ムルティはさらに、カントの『批判哲学序説』について、ニーチェに影 響を与えたと言われるハインリヒ・ハイネが「死にかけている神」について語ったと述べた。ハイネとニーチェ以来、「神の死」という表現が一般的になった。 [8] |
| German philosophy Hegel Contemporary historians believe that 19th-century German idealist philosophers, especially those associated with Georg Wilhelm Friedrich Hegel, are responsible for removing the specifically Christian resonance of the phrase relating to the death of Jesus Christ and associating it with secular philosophical and sociological theories.[2] Although the statement and its meaning are attributed to Nietzsche, Hegel had discussed the concept of the death of God in his Phenomenology of Spirit, where he considers the death of God to "Not be seen as anything but an easily recognized part of the usual Christian cycle of redemption".[9] Later on Hegel writes about the great pain of knowing that God is dead: The pure concept, however, or infinity, as the abyss of nothingness in which all being sinks, must characterize the infinite pain, which previously was only in culture historically and as the feeling on which rests modern religion, the feeling that God Himself is dead, (the feeling which was uttered by Pascal, though only empirically, in his saying: Nature is such that it marks everywhere, both in and outside of man, a lost God), purely as a phase, but also as no more than just a phase, of the highest idea."[10] Hegel's student Richard Rothe, in his 1837 theological text Die Anfänge der christlichen Kirche und ihrer Verfassung, appears to be one of the first philosophers to associate the idea of a death of God with the sociological theory of secularization.[11] |
ドイツ哲学 ヘーゲル 現代の歴史家は、19世紀のドイツ観念論哲学者、特にゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルに関連する哲学者たちが、キリストの死に関する表現 からキリスト教的な響きを排除し、世俗的な哲学や社会学の理論と結びつけたと考えている。[2] この言葉とその意味はニーチェのものとされているが、ヘーゲルは著書『精神現象学』の中で「神の死」という概念について論じており、神の死を「通常のキリ スト教の救済サイクルの一部として容易に認識できるもの以外の何者でもない」とみなしている。[9] その後、ヘーゲルは神が死んだことを知るという大きな苦痛について次のように書いている。 しかし、純粋概念、すなわち無限は、あらゆる存在が沈み込む無の深淵として、無限の苦痛を特徴づけなければならない。この苦痛は、それまでは文化史上にお いてのみ存在し、現代の宗教の基盤となっている感情、すなわち神自身が死んだという感情(この感情は、パスカルが経験則としてのみ述べた言葉であるが、 自然は、人間の内側にも外側にも、神の不在を至る所で示すようなものである。)純粋に、最高の理念のひとつの局面として、また、それ以上のものではない局 面として。」[10] ヘーゲルの弟子であるリヒャルト・ロテは、1837年に発表した神学書『キリスト教教会の起源と組織』において、神の死という概念を世俗化という社会学的 理論と関連づけた最初の哲学者の一人であるようだ。[11] |
| Stirner German philosopher Max Stirner, whose influence on Nietzsche is debated, writes in his 1844 book The Ego and its Own that "the work of the Enlightenment, the vanquishing of God: they did not notice that man has killed God in order to become now – 'sole God on high'".[12] |
シュティルナー ドイツの哲学者マックス・シュティルナーは、ニーチェに与えた影響について議論があるが、1844年の著書『自我とそのもの』の中で、「啓蒙主義の功績、 神の敗北:彼らは、人間が今あるようになるために神を殺したことに気づいていなかった。『高みにいる唯一神』」と書いている。[12] |
| Mainländer Before Nietzsche, the concept was popularized in philosophy by the German philosopher Philipp Mainländer.[13] It was while reading Mainländer that Nietzsche explicitly writes to have parted ways with Schopenhauer.[14] In Mainländer's more than 200 pages long criticism of Schopenhauer's metaphysics, he argues against one cosmic unity behind the world, and champions a real multiplicity of wills struggling with each other for existence. Yet, the interconnection and the unitary movement of the world, which are the reasons that lead philosophers to pantheism, are undeniable.[15] They do indeed lead to a unity, but this may not be at the expense of a unity in the world that undermines the empirical reality of the world. It is therefore declared to be dead. Now we have the right to give this being the well-known name that always designates what no power of imagination, no flight of the boldest fantasy, no intently devout heart, no abstract thinking however profound, no enraptured and transported spirit has ever attained: God. But this basic unity is of the past; it no longer is. It has, by changing its being, totally and completely shattered itself. God has died and his death was the life of the world.[note 2] — Mainländer, Die Philosophie der Erlösung |
マインランダー ニーチェ以前に、この概念はドイツの哲学者フィリップ・マインランダーによって哲学の世界に広められた。 ニーチェがショペンハウアーと決別したことを明確に書き記したのは、マインランダーを読んでいるときだった。[14] マインランダーの200ページ以上にわたるショペンハウアーの形而上学批判の中で、彼は世界を支える宇宙の統一性に反対し、存在を求めて互いに争う意志の 真の多様性を擁護している。しかし、哲学者たちが汎神論に導かれる理由である世界の相互関連性と統一的な動きは否定できない。[15] それらは確かに統一へと導くが、それは世界の経験的現実を損なうような世界の統一を犠牲にしてではないかもしれない。したがって、それは死んでいると宣言 される。 今、我々には、この存在に、想像力の及ぶ範囲、大胆な空想の飛翔、熱心な信仰心、いかに深遠な抽象的思考、陶酔し、夢中になった精神をもってしても、これ まで到達できなかったものを常に指し示す、よく知られた名前を与える権利がある。しかし、この基本的な統一は過去のものであり、もはや存在しない。それ は、その存在を変えることによって、完全に、完全に自らを打ち砕いた。神は死に、その死は世界の生命となった。[注2] — マインレンダー、『救済の哲学』 |
| Nietzsche In The Gay Science, "God is dead" is first mentioned in "New Struggles": After Buddha was dead, his shadow was still shown for centuries in a cave––a tremendous, gruesome shadow. God is dead; but given the way of men, there may still be caves for thousands of years in which his shadow will be shown. ––And we––we still have to vanquish his shadow, too.[17] Still in The Gay Science, the expression is stated through the voice of the "madman", in "The Madman", as follows: God is dead. God remains dead. And we have killed him. How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our knives: who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we ourselves not become gods simply to appear worthy of it? — Nietzsche, The Gay Science, Book III, Section 125, tr. Walter Kaufmann In the madman passage, the madman is described as running through a marketplace shouting, "I seek God! I seek God!" He arouses some amusement; no one takes him seriously. "Maybe he took an ocean voyage? Lost his way like a little child? Maybe he's afraid of us (non-believers) and is hiding?" – much laughter. Frustrated, the madman smashes his lantern on the ground, crying out that "God is dead, and we have killed him, you and I!". "But I have come too soon", he immediately realizes, as his detractors of a minute before stare in astonishment: people cannot yet see that they have killed God. He goes on to say: This tremendous event is still on its way, still wandering; it has not yet reached the ears of men. Lightning and thunder require time, the light of the stars requires time, deeds, though done, still require time to be seen and heard. This deed is still more distant from them than the most distant stars – and yet they have done it themselves. — Nietzsche, The Gay Science, Section 125, tr. Walter Kaufmann Lastly, "The Meaning of our Cheerfulness" section of The Gay Science discusses what "God is dead" means ("that the belief in the Christian God has become unworthy of belief"), and the consequences of this fact.[18] In Thus Spoke Zarathustra, at the end of section 2 of Zarathustra's prologue, after beginning his allegorical journey, Zarathustra encounters an aged ascetic who expresses misanthropy and love of God (a "saint"). Nietzsche writes: [Zarathustra] saluted the saint and said "What should I have to give you! But let me go quickly that I take nothing from you!" And thus they parted from one another, the old man and Zarathustra, laughing as two boys laugh. But when Zarathustra was alone, he spoke thus to his heart: "Could it be possible! This old saint has not heard in his forest that God is dead!" — Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, tr. R.J. Hollingdale[19][20] What is more, Zarathustra later not only refers to the death of God but states: "Dead are all the Gods." It is not just one morality that has died, but all of them, to be replaced by the life of the Übermensch, the overman: 'DEAD ARE ALL THE GODS: NOW DO WE DESIRE THE OVERMAN TO LIVE.' — Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, Part I, Section XXII, 3, tr. Thomas Common |
ニーチェ 『悦ばしき科学』の「神は死んだ」という表現は、まず「新しい闘争」で言及されている。 ブッダが死んだ後も、その恐ろしい影は何世紀にもわたって洞窟に映し出されていた。神は死んだ。しかし、人間のあり方を考えると、何千年もの間、神の影が 映し出される洞窟がまだ存在するかもしれない。そして我々も、神の影を克服しなければならないのだ。 『快楽論』では、この表現は「狂人」の声を通して、「狂人」の章で次のように述べられている。 神は死んだ。神は死んだままである。そして我々は神を殺した。我々はいかにして自らを慰めるべきか。殺人者の殺人者である我々はいかにして自らを慰めるべ きか。世界が所有してきたものの中で最も神聖で最も強大なものは、我々のナイフによって失血死した。この血を我々から拭い去るのは誰か?我々を清めるため の水はどこにあるのか? どのような償いの祭り、どのような神聖なゲームを我々は考案しなければならないのか? この偉業の偉大さは我々には大きすぎるのではないか? それにふさわしいと思われるためには、我々自身が神にならなければならないのではないか? — ニーチェ、『悦ばしき科学』第3巻、第125節、訳:ウォルター・カウフマン 狂人のくだりでは、狂人が「神を求める!神を求める!」と叫びながら市場を走り回っている様子が描写されている。彼は人々の笑いを誘い、誰も真剣に受け止 めない。「もしかしたら彼は海を航海したのか?子供のように道に迷ったのか?もしかしたら彼は我々(信者ではない者)を恐れて隠れているのか?」と、大い に笑いが起こる。苛立ちを募らせた狂人は、ランタンを地面に叩きつけ、「神は死んだ!我々がお前とおれで神を殺したんだ!」と叫んだ。しかし、彼はすぐに 気づいた。「私は早すぎたのだ」と。先ほどまで彼を否定していた人々が驚きの表情で彼を見つめている。人々はまだ、自分たちが神を殺したことに気づいてい ないのだ。彼はさらに続けた。 この途方もない出来事は、まだ進行中であり、まださまよっている。まだ人々の耳には届いていない。稲妻や雷には時間が必要であり、星の光にも時間が必要で あり、行いには、それがなされたとしても、まだ見られ、聞かれるには時間が必要である。この行いは、最も遠い星々よりも、まだ彼らから遠い場所にある。し かし、彼ら自身がそれを成し遂げたのだ。 — ニーチェ、『悦ばしき科学』第125節、ウォルター・カウフマン訳 最後に、『ツァラトゥストラはこう語った』の「陽気さの意味」の章では、「神は死んだ」という言葉の意味(「キリスト教の神への信仰はもはや信じるに値し ないものになった」という意味)と、この事実がもたらす結果について論じている。[18] 『ツァラトゥストラはこう語った』では、ツァラトゥストラのプロローグの第2節の終わりで、寓話的な旅を始めた後、ツァラトゥストラは人間嫌いと神への愛 を表明する老いた禁欲主義者(「聖人」)と出会う。ニーチェは次のように書いている。 ザラスツラは聖者に挨拶し、「あなたに何を差し上げればよいのか。しかし、あなたから何も奪わないように、すぐに立ち去ろう」と言った。そして、老人とザ ラスツラは別れた。2人の少年のように笑いながら。 しかし、ザラスツラが1人になったとき、彼は心の中でこう言った。「あり得るだろうか!この年老いた聖者は、神が死んだという話を森の中で聞いたことがな いのだ!」 — ニーチェ、『ツァラトゥストラはかく語りき』、R.J. ホリングデール訳[19][20] さらに、ツァラトゥストラは後に神の死について言及するだけでなく、「神々はみな死んだ」と述べている。死んだのは一つの道徳だけではなく、すべてであ り、超人、オーバーマンの生命に置き換えられるのだ。 「神々はみな死んだ。今こそ超人(オーバーマン)に生き続けてもらいたい」 — ニーチェ、『ツァラトゥストラはこう語った』第1部、第22章第3節、トーマス・コモン訳 |
| Explanations Nietzsche recognized the crisis that this "Death of God" represented for existing moral assumptions in Europe as they existed within the context of traditional Christian belief. "When one gives up the Christian faith, one pulls the right to Christian morality out from under one's feet. This morality is by no means self-evident [...] By breaking one main concept out of Christianity, the faith in God, one breaks the whole: nothing necessary remains in one's hands."[21] |
説明 ニーチェは、伝統的なキリスト教信仰の文脈の中で存在するヨーロッパの既存の道徳的仮定にとって、この「神の死」が意味する危機を認識していた。「キリス ト教の信仰を放棄すると、キリスト教道徳の権利を足元から奪うことになる。この道徳は決して自明ではない。キリスト教の主要な概念である神への信仰を打ち 壊すことで、信仰全体が打ち壊される。手元には何も残らない。」[21] |
| Interpretation Martin Heidegger Martin Heidegger understood Nietzsche’s declaration "God is dead" as a commentary on the end of metaphysics. For Heidegger, Nietzsche’s statement signifies not merely a theological or cultural shift but marks the culmination—and, consequently, the demise—of philosophy as metaphysics. Heidegger argued that metaphysics, which had structured Western thought from its inception, had now reached its maximum potential and, in doing so, had exhausted its relevance. The "death of God," then, is emblematic of this end, signaling the dissolution of any metaphysical worldview. According to Heidegger, metaphysics had been bound to end in this way since its origin.[22] Heidegger viewed the death of God as a pivotal moment in the history of thought, representing a transformation in humanity’s relationship to "Being." This shift, he argued, invites a new mode of engagement with existence, one that transcends human-imposed structures of meaning and value. Unlike Nietzsche, who proposes the "will to power" as a means for individuals to assert their own values, Heidegger critiques this as a lingering form of human-centered valuation, one that still attempts to impose meaning onto existence.[23] Instead, Heidegger advocates a contemplative approach, suggesting that we "let Being be"—appreciating existence without the constraints of human valuation or the demand for purpose. This approach marks a philosophical divergence: while Nietzsche encourages the active creation of values in a world absent of divine authority, Heidegger calls for a more fundamental openness to Being itself, free from valuation. In this sense, the "death" of God is not only a loss but also an opportunity for a new, radically different understanding of existence.[23] |
解釈 マルティン・ハイデガー マルティン・ハイデガーは、ニーチェの「神は死んだ」という宣言を、形而上学の終焉についての論評として理解した。ハイデガーにとって、ニーチェのこの宣 言は、単に神学的あるいは文化的な変化を意味するだけでなく、形而上学としての哲学の絶頂期、そして結果的にその終焉を意味するものであった。ハイデガー は、西洋思想の始まりから形而上学が西洋思想を構築してきたが、今やその可能性の限界に達し、それによって関連性も尽きたと論じた。「神の死」は、この終 焉の象徴であり、形而上学的世界観の崩壊を意味する。ハイデガーによれば、形而上学は、その起源からこのような結末を迎える運命にあったという。 ハイデガーは、神の死を思想史上の重要な転換点と捉え、それは人間と「存在」との関係の変化を意味すると考えた。この変化は、人間が作り出した意味や価値 の体系を超越する、存在に対する新たな関わり方を招く、と彼は主張した。ニーチェが「力への意志」を個人が自らの価値を主張するための手段として提唱した のとは対照的に、ハイデガーはこれを人間中心の価値評価の残滓であり、依然として存在に意味を押し付けようとするものだと批判した。 代わりにハイデガーは観照的なアプローチを提唱し、「存在を存在させる」ことを提案した。すなわち、人間の価値評価や目的の要求といった制約なしに存在を 鑑賞するということである。このアプローチは哲学的相違を意味する。ニーチェは神の権威のない世界において価値の積極的な創造を奨励したが、ハイデガーは 価値判断から自由な存在そのものへのより根本的な開放を呼びかけた。この意味において、神の「死」は喪失であるだけでなく、存在に対するまったく新しい、 根本的に異なる理解の機会でもある。[23] |
| Death of God theology Main article: Death of God theology Although theologians since Nietzsche had occasionally used the phrase "God is dead" to reflect increasing unbelief in God, the concept rose to prominence in theology in the late 1950s and 1960s, subsiding in the early 1970s, as the Death of God theology.[24] The German-born theologian Paul Tillich, for instance, was influenced by the writings of Nietzsche, especially his phrase "God is dead".[25] |
神の死の神学 詳細は「神の死の神学」を参照 ニーチェ以降の神学者たちは、神への信仰が薄れていくことを反映して「神は死んだ」という表現を時折用いていたが、この概念は1950年代後半から 1960年代にかけて神学において注目されるようになり、1970年代初頭には「神の死の神学」として落ち着いた。 [24] 例えば、ドイツ生まれの神学者パウル・ティリッヒは、ニーチェの著作、特に「神は死んだ」というフレーズに影響を受けた。[25] |
| Philosophy of Friedrich Nietzsche Apollonian and Dionysian Zarathustra's roundelay Christian atheism Postmodern Christianity Nontheism Postmodernity Post-theism Post-monotheism Faith and rationality Theories about religions Jungian interpretation of religion |
フリードリヒ・ニーチェの哲学 アポロ的とディオニュソス的 ツァラトゥストラの輪唱 キリスト教の無神論 ポストモダン的キリスト教 非有神論 ポストモダン ポスト有神論 ポスト一神教 信仰と合理性 宗教に関する理論 ユングの宗教解釈 |
| Nietzsche's philosophy Heidegger, Martin. "Nietzsches Wort 'Gott ist tot'" (1943) translated as "The Word of Nietzsche: 'God Is Dead,'" in Holzwege, ed. and trans. Julian Young and Kenneth Haynes. Cambridge University Press, 2002. Kaufmann, Walter. Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist. Princeton: Princeton University Press, 1974. Roberts, Tyler T. Contesting Spirit: Nietzsche, Affirmation, Religion. Princeton: Princeton University Press, 1998. Benson, Bruce E. Pious Nietzsche: Decadence and Dionysian Faith. Bloomington: Indiana University Press, 2008. Holub, Robert C. Friedrich Nietzsche. New York: Twayne, 1995. Magnus, Bernd, and Kathleen Higgins. The Cambridge Companion to Nietzsche. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Pfeffer, Rose. Nietzsche: Disciple of Dionysus. Canbury: Associated University Presses, 1972. Welshon, Rex. The Philosophy of Nietzsche. Montreal: McGill-Queen's UP, 2004. Death of God theology Thinking through the Death of God: A Critical Companion to Thomas J. J. Altizer, ed. Lissa McCullough and Brian Schroeder. Albany: State University of New York Press, 2004. John D. Caputo and Gianni Vattimo, After the Death of God, ed. Jeffrey W. Robbins. New York: Columbia University Press, 2007. Resurrecting the Death of God: The Origins, Influence, and Return of Radical Theology, ed. Daniel J. Peterson and G. Michael Zbaraschuk. Albany: State University of New York Press, 2014. John M. Frame, "Death of God Theology" |
ニーチェの哲学 ハイデガー、マーティン。「ニーチェの言葉『神は死んだ』」(1943年)は、『神は死んだ』と訳され、ジュリアン・ヤングとケネス・ヘインズ編、同訳、 ケンブリッジ大学出版局、2002年。 カウフマン、ウォルター。『ニーチェ:哲学者、心理学者、反キリスト』。プリンストン:プリンストン大学出版、1974年。 ロバーツ、タイラー T. 『精神の対立:ニーチェ、肯定、宗教』プリンストン:プリンストン大学出版、1998年。 ベンソン、ブルース E. 『敬虔なニーチェ:退廃とディオニュソス信仰』ブルーミントン:インディアナ大学出版、2008年。 ホルブ、ロバート C. 『フリードリヒ・ニーチェ』ニューヨーク:トウェイン、1995年。 マグヌス、ベルント、キャスリーン・ヒギンズ著。『ケンブリッジ・ニーチェ入門』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、1996年。 ローゼ・フェファー著。『ニーチェ:ディオニュソスの弟子』キャンベリー:アソシエイテッド大学出版、1972年。 レックス・ウェルション著。『ニーチェの哲学』モントリオール:マギル・クイーンズ大学出版、2004年。 神の死の神学 『神の死』を考える:トマス・J・J・アルタイザー編、リサ・マッカローとブライアン・シュローダー共著。オルバニー:ニューヨーク州立大学出版、 2004年。 ジョン・D・カピュートとジャンニ・ヴァッティモ著、ジェフリー・W・ロビンス編『神の死の後に』。ニューヨーク:コロンビア大学出版、2007年。 『死の復活:ラディカル神学の起源、影響、回帰』編:ダニエル・J・ピーターソン、G・マイケル・ズバラシュク。オルバニー:ニューヨーク州立大学出版、 2014年。 ジョン・M・フレーム、「死の神学」 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/God_is_dead |
リンク
文献
その他の情報
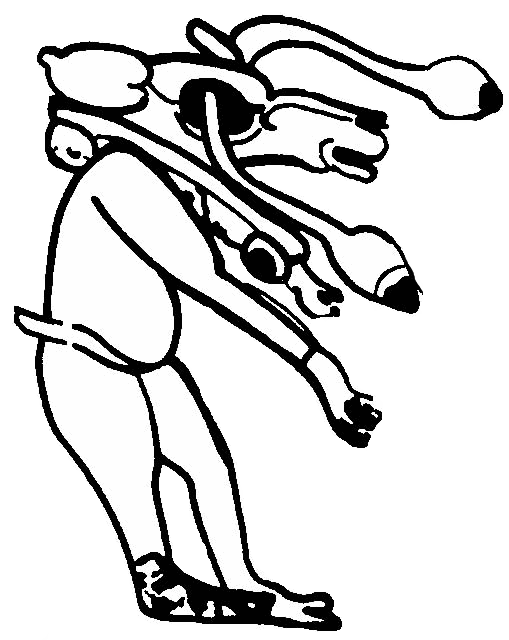
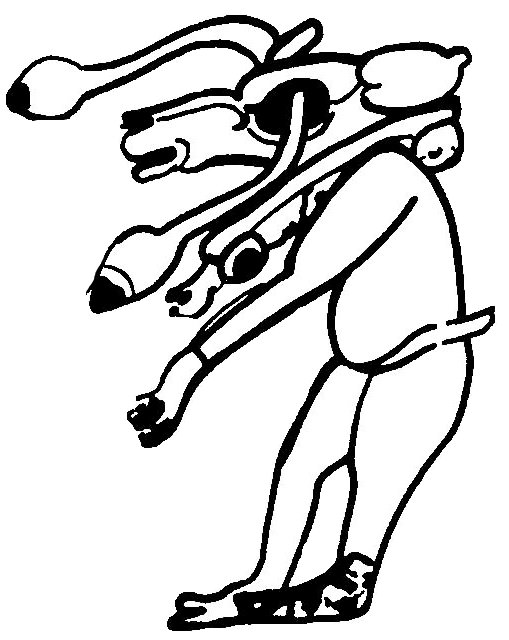
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
Do not paste, but [re]think this message for all undergraduate students!!!
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆