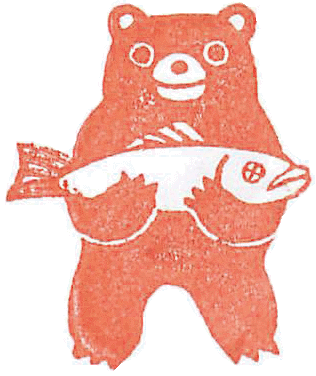O-157,オーイチゴウナナ,病原性大腸菌
On Escherichia coli O157:H7
画面をクリックすると出典サイトにリンクします
解説:池田光穂
O-157,オーイチゴウナナ,病原性大腸菌
On Escherichia coli O157:H7
病原性大腸菌は、O157以外にも、O111(オー イチイチイチ)などいくつかの種類が同定されている。
大腸菌(Escherichia coli)は、常在菌とよばれ、腸内のほかに、我々 の身の回りにたくさんいて、ふつうは病原性をもたない菌だといわれている。
しかしながら、1940年代にイギリスで、小児の下 痢症で、大腸菌との関連性について研究されている際に、病原性をもつ大腸菌が発見、分離された。
大腸菌の抗原のタイプは、細菌の表面にある抗原(O 抗原とH抗原)で細く種類がわかっている。
まず、1960年代後半に、エンテロトキシン(腸内 の細菌から出た毒素)を出す大腸菌の存在がわかった。病原性大腸菌の毒素には、高温で殺菌できるものと、耐熱性のある毒素の2種類があることが1970年 ごろまでにわかってきた。その後、1982年になって、アメリカ合衆国で、ハンバーガーによる食中毒が病原性大腸菌であることがわかり、一連の病原性大腸 菌の検索(=O抗原とH抗原よるタイプ分類のこと)が始まった。
日本では、1996年に岡山でおこった学校給食によ る集団食中毒事件により、O157の存在が有名なった。
さて、大腸菌はすでに述べたように、我々の身の回り にたくさんいて、ふつうは病原性をもたない菌である。それがなぜ、20世紀になって急速に問題になったのだろうか?
そのことについては、いろいろな仮説が考えられてい る。
とりわけ、現在では、飼育牛には、O157をはじめ とした病原性大腸菌が多くみつかることが多い。しかし、病原性大腸菌に感染している牛には、無症状(つまり病気の徴候がみられない)のため、病原性大腸菌 は、20世紀になんらかの形で先進国で肥育している牛の腸内のなかに住み着くようになったと考えられている。
その原因として考えられるのは、牛の肉を効率良く太 らせるために、高たんぱく質の飼料を与えることが当たり前になったことと関係していると言われる。かつては、(捨てられていた)牛の骨や筋から作られた材 料を、高温高圧の圧力鍋で分解した肉骨粉(にくこっぷん)を与えることがよくおこなわれていた。骨の髄や脳などの部位に存在する高温高圧に耐える異常たん ぱく質であるプリオンが、狂牛病を引き起こし、プリオンに汚染された食肉の摂取により、人間の狂牛病、すなわちクロイツェルト=ヤコブ病を発症、流行する ようになったことは良く知られている。
O157やO111のような病原性大腸菌は、高温高 圧の圧力鍋には耐えられないが、屠畜場などで、処理された動物の腸管にいたものが、何らかのかたちで、食肉などに汚染するようなった可能性がある。つま り、かつては草食だけの牛が、肉の生産のために、人工的飼料に依存する割合が高くなり、その際に、牛にとって無害な病原性大腸菌が繁殖することが、全世界 中で当たり前になった可能性がある。問題は、病原性大腸菌と牛の関係は、病気という被害をもたらさず「共存」していることにあり、それに触れる人間のみが 害を生ずるという問題である。ただし、病原性大腸菌は、よく加熱すれば殺菌され、無毒化されるために、生肉を扱うところでの汚染がなく、かつ加熱を十分に おこなえば、リスクを少なくできることを理解することが重要である。
そのために、かつては、ユッケ食のように生の牛肉を
食することができていた社会も、牛と病原性大腸菌の共存のために、もはや高いリスクをもたらすことになったことである。調理が安全であれば、牛肉の生食は
安全であるということは、21世紀では、もはやなりたたないことを理解することが、正しい「細菌病理学」の常識になったのである。
リンク先
文献
Copyright Mitzub'ixi Quq Chi'j, 2017-2018