序論
第1節 健康言説の構築分析とは何か
健康言説とは、文字どおり健康に関する言説のことである。
では、健康とは何であろうか。健康は、人間の心身(=身体)における良好な状態のことと一般には理解されている。ところが、このような身体の状態のあり方について思いを馳せれば、個々人の内部から経験されているところの身体感覚(“私の身体のここが痛い”“私の身体の全体が何かおかしい”)と外部からの観察評価(“君は風邪を引いている”“あなたの胃には癌の病巣があります”)の擦り合わせによる一種の統合の結果であることがわかる。しかし、そのような統合は、徹頭徹尾社会的なものである。社会的に構築されていることが決定的な条件であると言明するのは、外部からの観察評価は社会によって客観的に承認される必要があるのと同時に、それが身体感覚と照応されながら最終的に学習されなければならないからである。つまり個々人における健康の感覚とは、外部から注入される価値基準と照応されるから、後天的に構成されていると言えるのである。良好な状態に関する観念は、つねに社会の外部表象との関連の中で初めて理解されるから、健康は価値や規範概念の一つとして考察することが可能になる。これを身体の社会的構築と呼んでおこう。
次に、言説とは何であろうか。言説の原語である discourse, Diskurs は、一般には談話のことをさすが、ここでいう言説は社会科学の分析概念としての言説のことである。一般の談話は、会話や講演における発話の総体として考えられているが、社会科学では、発話のもつ歴史的条件や社会的な場による拘束性に着目して、その概念を進展させ、“社会における発言行為とその権力性の総体”として言説を捉え直すのである。そのため社会科学における「言説」とは、人間の言語活動における意味の構造化に関する重要な概念の一つとなった。言説の研究とは、発話者の立場や見解、ならびにそのような発話を仕向け、その発言の内容を蓄積し、さらに流通させる制度が、どのようなものであるかを研究することに他ならない。
このような認識論的前提に立てば、健康言説の研究は、新たな課題を我々に要請することになる。我々は言説を介して健康に関する身体感覚を社会的に構築するが、身体の内部観察は、外部にある言説と完全に照応する訳ではない。完全に照応するユートピアが存在しないのは経験的真理である。このような差異(=ズレ)があるために、健康に関する言説は無限増殖をはじめる。このような言説の再生産が、どのような理由において可能になっているのだろうか。健康言説と身体の内部観察の差異の存在だけでは、言説増殖を説明することができない。健康言説の論理構造の特異性が再生産を加速する要因も否定でないが、健康言説を増殖させる社会的要因もまた考える必要がありそうだ。医療化あるいはヘルシズムに求めたり、資本主義的生産様式やイデオロギーについて考察する議論にいたるまで多様な試みがなされてきたが、それは未だ明確にはされていない。我々の挑戦はこれを解明することにある。
健康は社会によって想像され個人の経験を通して共有される社会的構築物である。健康は、人間の言説行為によって構成されているにも関わらず、我々は日常生活の中で、それを実体化(=物象化)し、身体の本質的状態として無反省的に了解している。人間の身体感覚に関するこの錯視とも言えるべき現象は、病気の原因を外部表象に還元して、それに対する象徴的操作を好む社会よりも、病気の原因を身体の内部から由来するものと考える傾向の強い社会に広く見られる【注:1】。後者の社会のもっとも身近な例は、近代医療的概念が広く受容された社会、我々が通常“近代的”と形容する我々の社会のことである。
構築分析とは、正確には構築主義的分析を指している。構築主義とは社会問題研究、社会心理学、科学社会学、心理学、精神医学、人工知能研究などで広く用いられるようになった研究の立場であり、「実在物とみなされている現象は、実は、人々による、文化に媒介された合同の活動 joint activities の産物(構築物)である」とする社会認識論である【注:2】。心身の良好な状態として健康は、それが仮に実在しようと構築されるものであろうと、あるいはその混成体であろうと、少なくとも我々の身の前には言説をとおして構築されるものしか手に入らない以上、「健康は言説のことである」という認識論が正当性をもつのである。
以上のことによって、健康言説の構築分析が可能になる理論的根拠を提示した。
第2節 広告研究の政治学─構築主義以前─
広告が我々を写す鏡であることを否定する者はいない。しかしながら、一般的には、広告は我々の社会経験を形づくる一領域として、また自律性の高い領域として理解されることのほうが多い。そのため広告研究もまた様々な社会理論の影響を受けながらも、独自の研究領域として社会から認知され、パラダイムを形成するほどの発展してきたように思われる【注:3】。パラダイムとしての広告研究と理論生産の基盤の確立、それ自体が問題にされることもあろうが、ここでは広告研究が担わされてきたイデオロギー性について明らかにしたい。広告にみられる現象を、より大きな社会現象の反映としてみる素朴な反映論が後を絶たない一方で、広告研究を特殊な研究領域として分離する研究領域上の隔離主義が蔓延っている理由を明らかにし、現代社会を分析する視点を提供すると同時に生活の指針を生み出すような広告研究の可能性を追求したいからである。
広告研究のこれまでの発展をみるに、これまでの研究には、広告の生産と批判という2つの大きな社会的役割を担わされてきたようだ。この2つの役割は、個々の実践を可能にする認識論(=理論)に大きく依存してきた。我々は、それらを(1)広告生産を前提とする実務や現場の思考にもとづく広告の実体論的分析、(2)現代社会批判へと射程をもつ広告の関係論的分析、という2つの系譜に分けて考えてみたい。実体論の代表は広告の機能や効果を実証主義的に測定検証するもので、それを機能論と総称しよう。関係論の代表は、広告批判研究でめざましい成果を収めた記号学的分析やイデオロギー批判と呼ばれる一連の研究で、ここでは記号論と総称しておく。
これらの研究領域は、広告研究の伝統の中でそれぞれ相互に批判しながら発展してきたが、それぞれ理論上の有利な点および不利な点がある。このような対比を明示するには、実体論と関係論が相互にどのような批判を応酬してきたかについて整理すればよい。
実体論解釈が成功するのは、その理論自体の正しさというよりも、理論が常識の延長上にあり、消費社会のイデオロギーを共有するからである。単純に言うと、常識の理論化がおこなわれ、そのような理論が出す答えに、人びとは誰も異議を唱えることができないからである。これは関係論的立場からは、イデオロギーによる“隠蔽”と説明されている。この理論が、常に批判的な対象になるのは、理論が精緻ではないということが問題になるのではなく、現実に合わせた解釈の範囲しか提示することができないからである。つまり、現状肯定か、現象の事後的説明に終わり、創発性の欠如という点で限界がある。認識論的情熱が明証性の確認へと収斂するからである。
他方、関係論的な主張は、実体論のもつイデオロギー的欺瞞を暴くことに専念する。その社会的効果は、我々の無反省的な生き方に省察を与えることを通して、創発的な作用をもたらすことにあった。他方、批判が自己目的化する傾向の強い関係論的分析には、生産的な代案を提出できないという批判が、つねに実体論からもたらされてきたし、事実その通りである。記号論的批判は、理論生産性が高く、また学問がもつ批判の伝統に合致するため、大学などの研究者や評論家のみならず、リベラルな信条をモットーとする若い研究者を魅了してきた。
このように実体論と関係論は、水と油のように相互に敵対するもののように思われてきたし、また実際にそうであった。だが、それはパラダイム上の反発以上に、それぞれの理論が依拠する政治的あるいはイデオロギー的なスタンスとの親和性によるものであろう。
その典型例を山崎カヲルのADSEC(広告記号論研究会)編『牛タコさっちゃん』への反発にみることができよう。欧米における広告の記号論研究の金字塔J・ウィリアムスン『広告を解読する─広告におけるイデオロギーと意味─』(邦題『広告の記号論 I ・II』)の翻訳者の一人である山崎は、ADSECの研究を「面白い」と評価しながらも、記号論研究における意味の「生成や生産は、具体的な商品開発だの広告の産出だのとはなんの関係もない。それは解読の過程における意味生成の問題を扱うのであって、広告を生産することではない」と、ADSECのイデオロギー的立場を批判している【注:4】。
ところが山崎もウィリアムスンもまた、広告業界が記号論的批判を逆手にとって、より高度に洗練された広告を産出する事態を憂慮している。記号論における認識論立場と道徳的立場のズレに苦慮しているのである。山崎は、この難問を「広告は権力の言説なのである」という言明を再提示することで、自らのイデオロギー的立場を確認する。だが、これは記号のもつ意味生産において意図的な操作が、必ずしも成功するわけでないという記号論上におけるもう一つの大きな理論的教訓を過小評価することに他ならない。そのために、山崎の権力論は極めて硬直したものになっている。また、記号論のイデオロギーに関する議論を徹底的に脱色すれば、記号の意味生産の恣意性の過度の強調に陥り、意図的に政治的無知を装うことでしか状況に直面することができなくなる【注:5】。
他方、機能論研究の多くは、目的意識を明確にもっており、実証的な仮説検証を学問的俎上に載せること主眼にする。このような学問的中立性を装うことが、記号論的なイデオロギー批判の対象になってきたわけだが、機能論は、その実証主義の検証装置の中立性ゆえに、理論を道具化した方向を逆方向に転換させれば、いわゆる“広告という権力”への批判へと奉仕させることもできる。リベラル派を標榜する実証主義者は、理論の道具化についての無反省が理論生産性の根拠になっていることを知らないか、それを意図的に無視する。
広告研究において機能論を取るにせよ記号論を採用するにせよ、我々は学問の政治的な利用という事態からは逃れることができないのである。
第3節 広告研究における健康言説の構築分析
前節で広告研究を、実体論と関係論の2つに大別し、その典型として機能論と記号論をそれぞれ挙げて、その学問と権力行使の問題──第1節の用語法に従えば“広告研究の言説”──について解説した。そこで、本節では、第1節で提示した健康言説の構築の研究を、広告研究全体の中で位置づけることにしたい。
まず、機能論では、古典的広告におけるアプリオリな目標、つまり広告を通しての「商品の認知」と「購買行動の誘発」があり、それらの因果関係を明らかにすることに力点が置かれている。それに対して、記号論では多少なりとも理論装置が複雑である。広告の記号論では、広告と商品の関連づけの問題を、ソシュール派言語学にもとづいて、意味するもの=記号表現=シニフィアン(signifiant)と意味されるもの=記号内容=シニフィエ(signifie^)の関連の中に位置づける。そして、アルチュセールのイデオロギー論に基づいて、広告が生産する意味や広告を消費する<主体>の構築に関する議論を、個々の事例に即しながら分析するというスタイルをとる【注:6】。つまり記号論は、その分析によって商品が何であるかを明らかにすると同時に、商品を購入する者が何者であるかを示す。広告は、このようにして商品を購入する<主体>に対する呼びかけを通して、資本主義における主体そのものを産出してゆくとするのである。
このように要約すれば、広告研究における機能論と記号論は相当異なっているかの印象を抱くはずである。ところが、記号論的分析の内容の外に出て、記号論が提示するメッセージの機能について解読すれば、記号論が明らかにしようとする目的は、機能論が目標にする分析対象と驚くほど類似していることに気づく【図1】。このような相同性の理由は明らかである。広告研究が要請する分析の目標は、機能論によれば(販売者の立場から)商品をいかに売るために自覚することであり、記号論によれば(消費者の立場から)商品をいかに買わないかを自覚することであるからだ。つまり、商品の販売と消費という同じ現象を、逆方向の角度から見ているのである。機能論と記号論のイデオロギー的な含みと、その機能論=販売者、記号論=消費者という政治的記号的棲み分けの法則がすでに論理的に破綻していることについては前節で解説したとおりである。
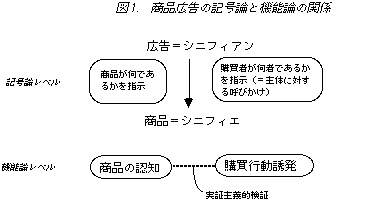
健康言説の構築分析は、立論のタイプから関係論的伝統のうちとくに記号論の立場に属するものである。そのなかで、記号論のシニフィアンとシニフィエの関係は、それぞれ健康言説と身体感覚(=身体の内部観察)に相当する。ただし、言語や、記号としての広告とは異なり、健康言説が一義的に身体感覚を形成するだけでなく、身体そのものを介して健康言説の生産に組することになる【図2】。身体そのものが即<主体>になるか否かは、我々の議論においては意見の相違があろうから、これ以上の言明は避けるが、健康言説と身体感覚が、相互に循環したり、あるいは弁証法的な関係にあることは、数多くの論者によって指摘されている【注:7】。
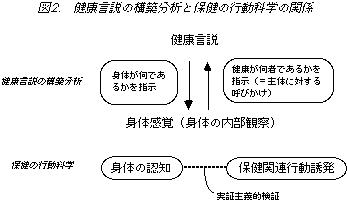
他方、身体の認知と健康関連行動誘発の間に、実証主義的検証を求める研究領域は、保健の行動科学研究と呼ばれてきたものがそれに相当する。後者の研究は、社会の中で人々の身体について定義し、決定を下すことができる、つまり医療のヘゲモニーをもつ側からおこなわれてきた研究である。しかしながら、その理論が政治的に常にヘゲモニーを有する側に独占される保証はどこにもない。それは、広告研究における記号論と機能論における不毛な対立の歴史から教訓として得られていることは、すでに述べたとおりである。
本報告書は、健康言説についてのさまざまな諸相――言説の構築、類型、構造、作用形態、流通、さらには、言説そのものを存立させる社会形態――に関する議論を集成したものである。これに関する先行研究が存在しないために、我々は健康言説についてのオリジナルな考えを多面的に提示することになった。第2章を執筆した野村が、社会に流布している健康言説をクリーシェ(決まり文句)にもとづく類型論でまとめたように、健康言説は極めて多様である。つまり、今回はじめて世に問うことになる健康言説に関する理論も、それぞれの論者が主張する健康言説の範型に少なからず影響を与えている。このような多様性は、我々が提唱する理論的分析にとっては障碍ではなく僥倖であると考えている。なぜなら、健康言説の多様性の範囲を、それぞれの理論的範型にもとづいて考量することが可能になるからである。そのため、編者である研究代表者(池田)は、字句の修正以外は、禁欲的にならざるを得なかった。当面は、多声的な意見の集約こそが、健康言説の構築分析の現在に求められているからである。