1 健康言説の探究
健康言説とは、健康に関する言説のことである。
健康とは何であろうか。健康は、人間の心身(=身体)における良好な状態のことと理解されている。ところが、このような身体の状態とは、個々人の内部から経験されているところの身体感覚と外部からの観察評価の擦り合わせによる一種の統合の結果に他ならない。そのような統合は、徹頭徹尾社会的なものである。なぜなら、外部からの観察評価は社会によって客観的に承認される必要があるのと同時に、それが身体感覚と照応されながら最終的に学習されなければならないからである。
言説とは何であろうか。言説とは一般的には会話や講演における発話の総体として考えられているが、人文科学・社会科学では、発話のもつ歴史的条件や社会的な場による拘束性に着目して、その概念を進展させる。言説の研究とは、発話者の立場や見解、ならびにそのような発話を仕向け、その発言の内容を蓄積し、さらに流通させる制度が、どのようなものであるかを研究することに他ならない。
このような認識論に立てば、健康言説の研究は、新たな課題を我々に要請することになる。我々は言説を介して健康に関する身体感覚を社会的に構築するが、身体の内部観察は、外部にある言説と完全に照応する訳ではない。完全に照応するユートピアが存在しないのは経験的真理である。このような差異(=ズレ)があるために、健康に関する言説は無限増殖をはじめる。このような言説の再生産が、どのような理由において可能になっているのだろうか。健康言説と身体の内部観察の差異の存在だけでは、言説増殖を説明することができない。健康言説の論理構造の特異性はその再生産を加速する要因ではあるが、健康言説を増殖させる社会的主要因について考える必要がありそうだ。医療化あるいはヘルシズムに求めたり、資本主義的生産様式やイデオロギーについて考察する議論にいたるまで多様な試みがなされてきたが、我々の前にはそれは未だ明瞭な姿を現していない。我々の挑戦はこれを解明することにある。
健康言説は、およそ人間の身体を媒介とした我々の認識している世界についての議論つまりコスモロジーの総体を表象する。それは我々の日常生活の中に氾濫しており広大で一見無秩序な言説の束のように見える。第3章の実証的研究に対する貢献とは、健康関連広告における健康言説の諸類型を確立するのみならず、その発生論的根拠を明らかにしたことにある。
医薬品広告の中で健康言説が直接指し示すものを探究することには、大きな限界がある。これは第4章で検討したが、微に入り犀を穿つ医療広告に関する極めて厳しい規制が、広告の内部の言説の自由度を極限にまで制限しているからである。これを、医療広告における「健康(=言説)の不在」と呼んでおこう。このような権限を行使する権力の具体的な顕現の様態については第2章で考察した。しかし、医療広告への法的な規制の厳しさとは裏腹に、健康の想像力は、医療品ならびに関連の広告の範囲をはるかに超えて、種々の商品宣伝、あるいは一般啓蒙活動(パブリシティ)といった、いわばメタ広告とも言えるメディアの中に氾濫している。この事態をどのように解釈すべきだろうか。医療広告のポルノグラフィー的性格の分析や、医療広告のメタコンテクストの解読に関する研究が求められている。健康言説とは、そのような医療広告の範囲の外部にある領域のことについて指し示す用語法なのである。微に入り犀を穿つ医療広告に関する極めて厳しい規制とは裏腹に、薬局の店頭やカウンターには“医薬品広告で禁止されているコード”が横溢している。また毎朝の朝刊の中に折り込まれた広告が、雄弁にそのポルノグラフィックな想像力をかき立てる。第3章における健康関連広告におけるクリーシェの分析や、第4章における陀羅尼助の消費と流通というテーマは、テレビ広告における大衆医薬品の学問的分析との極端な対比をなしながら、健康言説についての極めて重要な貢献をするとはこのような意味においてである。
健康関連広告におけるクリーシェとは決まり文句のことである。クリーシェは機能的に見ると、言語の直接的な意味の指示作用を失ってはいるが、言語のもつ感情喚起作用つまり話者と聞き手に社会性の確認を喚起させるため、クリーシェは我々の日常世界を理解するための重要な言説作用の一つとなっている。クリーシェを操作したり受容する<主体>すなわち人間は、クリーシェのもつ自己推進能力──その原動力は未だ解明されてはいないが──を創出したり、それに翻弄されていることもよく知られた事実である。従来の実証的広告研究は、この自己推進能力(=培養型ナヴィゲート構造)の働きを解明し、それを道具化しようと格闘してきたのである。
この視点から特定の社会現象を研究するさいに戦略的に重要になるのは、人びとが日常世界においてものごとを理解する仕方であり、そのさいに重要な役割を果たす「ことば」である。社会構築主義をとる我々は、この種のことばを言説とみなし、その調査研究を言説分析と呼ぶ。
多彩な広告表現の中で、とくにクリーシェに着目したのは我々の研究の目的がヘルシズムの論理構成に向けられているからである。ヘルシズムとは健康志向主義と一般には理解されているが、我々はそれを健康への過度の傾斜という社会的性向とその集合的現象と定義する。しかしながらヘルシズムという言説空間は平坦な空間ではない。むしろ異質なファクターが複雑にからみあう複合体である。健康関連広告は、ヘルシズムを社会的に構築する言説、つまり健康言説の重要な一部をなしており、ある種の傾向をもっている。にもかかわらず、広告のみならず、ひろく人間の発話の中で個別の健康が語られる際には、多様な語り口をもつ。健康を語る<主体>はひとつではないからだ。専門家、メディア、素人たちがそれぞれの集団的社会的規定性のもとで健康を語る。さらに、しばしば「~といわれている」と受動態表現で引用される、語る主体の不明確な言説もある。広告は、それらの語る主体の姿を様々に取り込んだ「メディア言説」である。異質な言説を取り込むということは、全体像としては論理主張に一貫性がないということであり、メッセージの中身が限定されにくいということである。マスメディアが、世論という中空のイデオロギーを振り回したり、浪費を止めろというパブリシティ・メッセージを掲載する一方で、大型消費財の広告を掲載するというのは、収益という資本の論理に従順であることに他ならないが、メディアがどのようなものでも取り込めるという汎用性に根ざしたものである。メディアは言説に公共性を付与することができ、個々の出来事を公の場で議論できる出来事一般に変換する機能をもっていると社会的に承認されているからである。生活世界イデオロギーは、メディアを不可欠なエンジンとして常識を産出する。メディアは広告によって支えられている。つまり、生活世界イデオロギーは、広告という自己像を通して、自らの背理について知るのである。
健康関連の折込広告を通して健康言説を精読するという作業の結果、我々が到達した基本的合意とは、広告という共同言説空間で自生的に構築されている健康言説のコスモロジーがすでに民衆宗教のそれと同型性を有していることである。そこには中心といったものがなく、メディアのように、多種多様な健康言説が内包されているだけである。中空だからこそ、自己の健康について誰もが語り所有する権利がアプリオリに与えられていると人々は錯視する。人びとは健康を語ることによってヘルシズムの言説宇宙の構築に関与し、同時に「予言の自己成就」のメカニズムによって自己言及的に拘束される。健康言説によって自己(そして他者)の身体アイデンティティについてのモニタリングとリアクションが生じる。こうした再帰的な循環構造がさまざまな言説主体によって強化されており、その中でも広告をはじめとする各種メディア言説が重要な培養的役割を果たしている。 あらゆる民衆宗教の教義と説教がそうであるように、そこでは言説がもつ状況定義作用が極限まで伸張されている。これは言葉の遊びであり、人間の文化の創出作用の中核のエンジンたるべき活動に他ならない。健康言説の増殖性は、言説の汎用性であり、それを裏返せば、何ものも指示しないという中空性という特性に理由が求められる[図1.参照]。
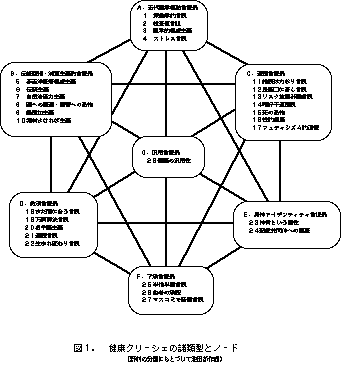
現代社会は、健康が実体化する社会である。ところが、我々が第2章で議論したように、近代医療が定義する健康の概念は、定義のできないマジックワードで、権力を持った者がいかようにも操作することができるということだ。近代医療体制のもとで、健康はそのような操作的実体としてみなされており、それは権力の作用の結果であることが第2章で検証された。
この主張の論拠として、(1)健康の医学的概念構築上から出てくる論理的必然性と、(2)健康を定義することで有効に機能すると思われる外部権力による結果、という2つがあげられる。まず、最初の論理構成上の必然性とは次のようなことである。健康の定義は、臨床医学的には病気の「不在」によって証明されなければならないが、臨床医学的に病気のない身体の状態はあり得ないので、健康は現実には存立できない。この理由には近代医学の論理構成が、病気の実在仮説にもとづく、個別事象の検討にあるので、その病気の不在を積極的に推進する理由が、社会医学領域以外にあり得なかったという「社会学的事由」も絡んでくる。健康の実体化を促進させるより強力な理由は、健康を定義する外部権力が存在することである。そのことを生活習慣病の概念の誕生と定着を積極的に推進する<主体>がとった行動という観点から分析した。
生活習慣病という名称と概念を定着させようとする政治的言説の論理構築とは、病気の因果関係論とは異なったものである。「ブレスローの7つの健康習慣」の因果法則がある。これは、未来の健康な人たちの集団、つまり病気がないという集団を時系列にさかのぼって再構成した統計的虚構を前提とするものである。そのような未来の(=実際には過去における大過去の時制において存在した)仮想的健康集団の人々には、現在(=過去)の時点で、ライフタイルの中に7つほどの共通した行動的傾向が共有されていたというのが、この健康習慣である。ところが、生活習慣病の検討においては、それが社会医学的教訓として倒立して利用される。ライフスタイルの7つの共通した項目を遵守したなら、将来健康になるだろうという<予言>を行うからである。この統計的虚構は、科学の操作的定義にもとづく知識生産性と(完全な因果関係が証明された後で、という限定句が付くが)社会的効果というメリットはあるが、それが常識的――生活世界イデオロギー的――に利用されれば、そのような仮想集団が、快復できない事故外傷、自殺、精神疾患、食品や環境汚染による障害などなった者は、あらかじめその予言の適応法則から外されている点で、上の主張には注意が必要である。我々の得た結論は、それが政治的に流用されて構築されたものが生活習慣病であるということであった。
成人病から生活習慣病への関心のシフトは、成人病対策から得られた「早期発見早期治療」の予防面をよりさらに強化するものである。成人病の早期発見早期治療の医療政策が失敗したので、さらにその前の段階へと管理の方針を前倒しにしたものが予防言説の骨子である。成人病概念が横滑りした生活習慣病という用語の誕生と定着の背景にある疾病概念を社会的に統制しようとするイデオロギーは、最終的に病人の自己責任論に還元される。 ただ次のような問題がまだ十分に解決されていないために、我々が暫定的に得られたこのような権力像はいまだ解釈作業の途上にある。
まず、そのような論理的に中空の意味のないものがなぜ大規模に流通し、それに対して大きな疑義が与えられることがなかったのか。中空なものが実定性をもつことを証明するには、隠れた論理を逆転するだけでなく、逆転した論理が成立するための社会像を提示しなければならない。臨床・社会医学ならびに国家の権力性を発動すると想定されている<主体>は、中空であるという認識をもっているのか、いないのかが解明されていない。現時点での我々の権力認識論の要衝は、このような健康=中空の無意味な実体化(=構築化)を理解すべきであるということに止まっている。もし、健康概念が近代社会において中空で、何でも意味の込める器(メディア)のようなものであるとすれば、健康の社会学や人類学もまた、そのような中空現象を相手に無益な格闘をする学問ということになりはしないだろうか。第2章の論考においては、権力政治を解剖するような認識論上のアルキメデスの支点を持ちうるという想定から未だ脱却できていない。それに対して、そのような立場の代表格である生活世界イデオロギー中心主義を放棄すべきだというのが第6章の主張である。
「陀羅尼助」という薬がある。古くから飲まれてきた家庭用胃腸薬である。しかし、薬局以外の場でもときおり目にする陀羅尼助は、たんなる「医薬品」というイメージには収まりきらない。陀羅尼助を言説と見立てて、その流通と消費について考察したのが第5章である。医薬品はその実用的な価値だけで所有されたり取引されるものではない。持ち主の地位を示すものとなったり、何かの記憶のアイテムとなったりする。つまり様々な「意味」をもつ事物として持たれたり、売り買いされる。ある事物がなぜ売れるか/買われるかは、事物の中身だけではわからない。事物が私たちの前に現われる場面、その文脈、そしてその場面で事物が表す意味。それらの検討が必要となる。健康は言説に他ならないが、陀羅尼助のように事物の形態をとる「商品」の場合、言説的性格とその効果は、不可視である。この不可視の構造を解明するためには、健康言説である陀羅尼助を構築分析にかけなければならない。構築分析に必要な資料はフィールドワークで収集された。
陀羅尼助が売り買いされる場面とその文脈について整理することは、その資料の分析の際に重要な課題となる。その結果、実際は一つの場面に複数の文脈や意味が混在している。つまり要素のいくつかが常に陀羅尼助上でブレンドされて売られているということが明らかになった。意味のブレンドという作用が、陀羅尼助の購買意欲を多様にかきたてる魅力を作り出す。豊富な意味のストックと、それらのブレンドによる自己呈示の柔軟性が、陀羅尼助という事物の魅力をつくり、消費社会を生き抜くしたたかさの証となっている。
「意味のブレンド」とともに陀羅尼助の購買と普及をサポートする要素として、「口コミ」作用もまた重要な機能だ。「ブレンドされた意味」が、口コミのパーソナルネットワークに乗って広まっていく。同時に、パーソナルなネットワークから「保証」を得て、購買への動機を一層高めさせていく。陀羅尼助は広告代理店などに頼った大規模な宣伝は行なわれていない。しかしそれは事物の側から見ると、事物自らが多様に自己呈示できる意味領域がそれだけ開かれていることを意味する。マスコミを使った宣伝は、しばしばその事物を単一のフレームの中に強力に閉じこめてしまうだろう。広告に規制の多い医薬品ではなおさらのことである。事物のしたたかさ強さの一端は「口コミ」の喚起力から供給されている。
陀羅尼助は、長い歴史のなかで、その用いられてきた文脈を失うことなく、むしろ新たな意味を重層的に身にまとうようなかたちで、サバイバルしてきた。現在においても、多様な文脈のなかで、その場に応じた意味をブレンドして身にまとう。製造業者によると陀羅尼助は堅調な売れゆきをみせているという。もはや<薬>という枠を超えたこの事物の、現代消費社会における「足腰の強さ」に目を見張らざるをえない。これらの現象は第2章で紹介したクリーシェ言説の増殖性の下部構造の考察に示唆を与える。
現代社会における健康言説の氾濫は、従来はヘルシズム批判の文脈の中で否定的な意味として評価されてきた。その意味理解の根本的誤認の原因を探究したのが第6章である。
その研究方法論の基本構想は、まず多種多様にあると捉えられている健康広告における言説のタイプを社会学的に分類し、それを基に、通常考えられている健康と健康広告の関係性、健康をめぐるパブリシティと広告の布置状況などを示すことにある。
まず最初に、規範と価値の通常想定されている因果関係が解体される。問題を次のように立てる。健康という本質的価値がアプリオリに実在し、それ(=価値言説)にもとづいて、規範が構成されるということは、果たして本当なのだろうか。
ここでは、価値言説のパラドキシカル特性つまり、価値言説が、それによって言及される価値を先取りして表象している実態について検討される。価値が規範および規範言説を生むという単純な事柄も、健康言説の実態を論理的な要素に還元して、モデル化した際にはさまざまな矛盾を生む。価値言説が価値を事後的に構成するにも関わらず、それ自体によって前提とされ先取りされなければならないという逆説について解説される。このような逆説に対する無根拠性を拒否することで、従来捉えられていた関係性や布置状況の問題点を指摘することができる。
その考えに従えば、健康言説の無限増殖の論理的仕組みは、次のように説明される。価値言説の語りを、<語る主体>が理解し、規範言説によって指示された所作を身体を媒介として行う。所作を行う<行為する主体>は、健康という価値を前提としている<語る主体>自身を客観的に見いだすことになる。このようなあり方を自ら知る主体の観点からみれば、価値言説と規範言説の境界は消失し、これらは一体となって価値を構築することに気づくはずだ。主体は、このような価値言説と規範言説の差異を揺れ動きながら生きることになるのである。
つまり、価値言説を内包するパブリシティと、規範言説を内包する広告の区別は、身体を有する主体形成の観点からみると有効な弁別的特性を持たない。だが、我々はそのような論理的判断だけを下すことに満足してはならない。通常の健康広告のみならず広告一般とパブリシティの境界が維持されたり、それらの相互侵犯について一般市民の間から道徳的危惧が主張されるが、それがどのような動機に基づいているのかについて次に批判的に検討しなければならない。第3章では、健康言説が生活世界イデオロギーを代弁(=表象)するものであり、このイデオロギーの歴史的ルーツが養生論に遡れるものであることを明らかにした。養生論は都市生活の発生によって、生活世界イデオロギーを外部から教育的手段――広告とパブリシティが合わせ持つ特性――を介して人々に注入される必要が生じたからだ。養生論はコスモロジーに根拠をもつ道徳論なのである。
そのような道徳=規範言説がもつ社会的効果に関するこの論理に基づくと健康言説にはひとつの構造から2つの効果が発生していることに気づく。その効果のひとつの側面は、病因論を説明する論理として、病因を「健康の欠如」として作用するものである。その際に、過去に遡る現在の主体の様態を欠如態として構築する現象である。これは健康言説がもつ規範言説的特性である。もうひとつの側面は、健康言説が、つねに未来の「健康」状態――これもまた病気の欠如態に他ならないが――を想定して、時間的に先行する状況から、現在に対して、「未来における欠如」に備えるようなかたちで「現在における過剰」を要求するという現象である。これは健康=健康言説として、言説増殖を説明するためのヒントを我々に与えてくれる。
このような生活世界イデオロギーが要求する言説増殖の仕組みの背景に存在するのが、交換価値に還元された健康=健康言説の資本主義における「商品」の生産という普遍的な現象に他ならない。健康言説の無限増殖は、商品の生産と流通の法則性に合致する。
資本主義世界観において、商品に付託される主体の所有欲望が消失する時、それは交換価値をもった商品の死に他ならない。同様に商品である健康言説もまた、無限の所有欲望に曝されなくなった時、健康もまた死に至るのである。そこから導き出される結論は、主体は身体を持ち生命活動を続ける限り未完の健康=健康言説を必要とすることになるということだ。生活世界イデオロギーが、日常世界の中のどこかに係留点をもち、そこからの発想が重要だという道徳論を弄するかぎり、健康言説は不滅であると言えよう。
6 健康言説を検案する
結論である。
1.健康言説は、現代社会におけるもっとも強力な言説活動である。
健康言説は、狭い意味での医療品や自然食品を超えて一見無関係な事物の中にも、あまねく存在する。健康広告がパブリシティと区別されなければならないという生活世界イデオロギーからの批判は、その論理構成が根本的に誤ってはいるが、広告が人間の感情を喚起させる作用の象徴的大きさの証であり、広告が身体レベルですでに様々な局面で実際に介入しているという証である。これほど強力な言語活動が我々の前に存在したことがあるだろうか?
2.健康言説は資本主義世界においてはオートマトン的増殖を遂げる。
健康言説は、人間をして未来に投企した活動を励起すると同時にその活動を拘束するような作用効果を発生する。商品経済の流通と消費を前提とする社会においては、このような活動と活動の結果の差異は決して埋まることはない。健康言説が、その言説の増殖を止める時とは、商品経済が終焉する時である。
3.健康言説は、現代社会における人間主体のあり方についての基本構造を提供する。
商品が社会活動の結節点になるという意味で、健康言説は現代社会の構成要素となる。構成要素間の繋がりこそが、この現代社会の成り立ちの基本構造と言えるだろう。この場合の基本構造とは、家屋の構造のような静態的な構築物全体の構造をさすのではなく、例えば梁と柱のつなぎ目(ジョイント)における節合のようなものをさす。健康言説の基本構造は、「病気の欠如」と「健康の過剰」の節合様式であり、この節合様式が歴史的社会的文脈の中で変化する。
(文責:池田光穂)