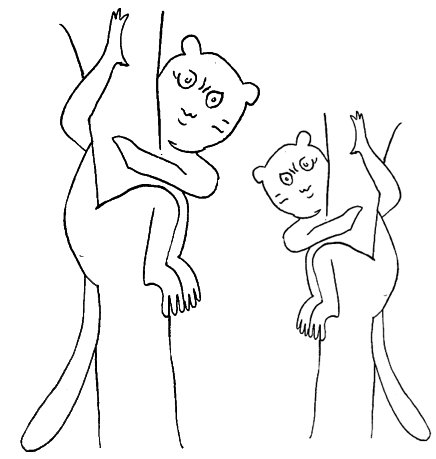
人類学と帝国主義
Anthropology and imperialism
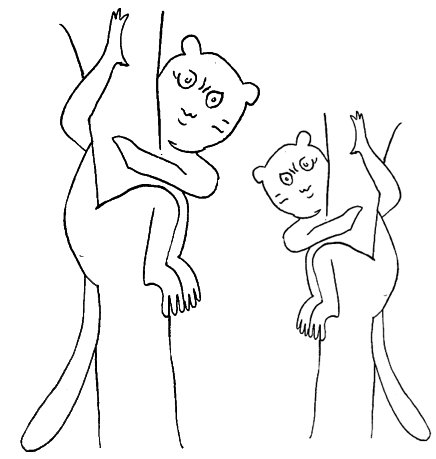
★K GOUGH — Anthropology is a child of Western imperialismのレビュー(→こちら「人類学と植民地主義」も参照のこと)
| Anthropology and imperialism have a deep, complex, and often problematic history, as the discipline emerged from European colonialism, producing knowledge that often served imperial interests by categorizing and governing colonized peoples, while simultaneously developing critical perspectives, especially from American schools (like Boasian anthropology), to challenge ethnocentrism and racism, leading to modern self-reflexivity and efforts to decolonize the field today. Key aspects involve anthropology's reliance on colonial structures for funding/access, the use of its findings for colonial administration, the ongoing debate about its complicity, and contemporary movements aiming for an anti-imperialist anthropology focused on dismantling power imbalances. |
人類学と帝国主義 この学問はヨーロッパの植民地主義から生まれ、植民地化された人々を分類し統治することで帝国主義の利益に奉仕する知識を生み出す一方で、特にアメリカ学 派(ボアズ派人類学など)から批判的視点を発展させ、民族中心主義や人種主義への挑戦を促した。その結果、現代的な反省性と、今日の分野の脱植民地化への 取り組みが生まれた。主な側面には、資金調達やアクセスにおける植民地構造への依存、研究成果の植民地行政への利用、その共犯性に関する継続的な議論、そ して権力の不均衡を解体することに焦点を当てた反帝国主義人類学を目指す現代の運動が含まれる。 |
| Historical Entanglement Child of Empire: Anthropology developed as a modern science alongside European imperial expansion, using colonial structures for fieldwork and subjects. Knowledge Production: Anthropologists generated data and theories (e.g., cultural evolution, racial hierarchies) that often supported colonial ideologies, even if unintentionally. Mutual Constitution: The imperial context shaped anthropological methods and concepts, while the knowledge produced fueled governance, creating a mutually beneficial (for empire) relationship. |
歴史的絡み合い 帝国の子:人類学はヨーロッパの帝国的拡大と並行して近代科学として発展し、フィールドワークや研究対象に植民地構造を利用した。 知識の生産:人類学者はデータと理論(例:文化進化論、人種的階層)を生み出したが、意図せずとも植民地イデオロギーを支えるものとなった。 相互構成:帝国主義的文脈が人類学的方法論と概念を形成し、生み出された知識が統治を促進した。これにより(帝国にとって)相互に有益な関係が生まれた。 |
| The American Counter-Narrative (Boasian Anthropology) Challenging Racism: The Franz Boas-influenced American school emphasized cultural relativism and challenged racial determinism, spreading appreciation for diverse cultures. Less Direct Complicity: American anthropologists were generally less directly involved with colonial governments than their European counterparts, though some worked in development post-independence. |
アメリカの対抗ナラティブ(ボアズ派人類学) 人種主義への挑戦:フランツ・ボアズの影響を受けたアメリカ学派は文化相対主義を強調し、人種決定論に異議を唱え、多様な文化への理解を広めた。 より間接的な関与:アメリカ人類学者は一般的に、植民地政府との直接的な関与がヨーロッパの同業者より少なかった。ただし独立後の開発事業に携わった者もいた。 |
| Modern Critiques & Reflexivity Self-Critique: Anthropology has become highly self-reflexive, critically examining its colonial past and the inherent power dynamics in studying other cultures. Colonial Categories: The discipline grapples with how to move beyond the categories and frameworks developed under colonialism, which can inherently colonize the subjects of study. Cultural Imperialism: The concept describes dominant cultures imposing norms via media/economy, which anthropologists study as a form of power imbalance. |
現代の批判と反省性 自己批判:人類学は高度に反省性となり、植民地時代の過去や他文化研究に内在する権力構造を批判的に検証している。 植民地的カテゴリー:この学問は、研究対象を本質的に植民地化する可能性のある植民地主義下で構築されたカテゴリーや枠組みをどう超越するかに取り組んでいる。 文化的帝国主義:支配的文化がメディアや経済を通じて規範を押し付ける概念であり、人類学者はこれを権力の不均衡の一形態として研究する。 |
| Contemporary Approaches (Anthropology Against Empire) Anti-Imperialist Stance: Some anthropologists aim to interpret and actively oppose imperialism, focusing on issues like corporate extraction and technocratic constraints on Indigenous communities. Ethical Challenges: Events like the Human Terrain System project highlight ongoing ethical debates about anthropologists' roles in military or development contexts. Decolonizing Ethnography: Modern efforts focus on indigenous methodologies, participatory research, and challenging Eurocentric perspectives to create more equitable anthropology. |
現代的アプローチ(人類学対帝国) 反帝国主義的立場:一部の人類学者は帝国主義を解釈し積極的に反対することを目指し、企業による資源搾取や先住民族コミュニティへの技術官僚的制約といった問題に焦点を当てる。 倫理的課題:ヒューマン・テリトリー・システム計画のような事例は、軍事や開発の文脈における人類学者の役割に関する継続的な倫理的議論を浮き彫りにしている。 脱植民地化の民族誌:現代の取り組みは、より公平な民族誌を構築するため、先住民の方法論、参加型研究、そしてヨーロッパ中心主義的視点への挑戦に焦点を当てている。 |
☆一般論
| Anthropology
and imperialism have a deep, complex, and often problematic history, as
the discipline emerged from European colonialism, producing knowledge
that often served imperial interests by categorizing and governing
colonized peoples, while simultaneously developing critical
perspectives, especially from American schools (like Boasian
anthropology), to challenge ethnocentrism and racism, leading to modern
self-reflexivity and efforts to decolonize the field today. Key aspects
involve anthropology's reliance on colonial structures for
funding/access, the use of its findings for colonial administration,
the ongoing debate about its complicity, and contemporary movements
aiming for an anti-imperialist anthropology focused on dismantling
power imbalances. The relationship between anthropology and imperialism is historically foundational, characterized by both complicity in colonial administration and subsequent critical self-reflection. Traditionally called the "child of imperialism," the discipline was established during the 19th-century expansion of Western power, which provided the practical conditions—such as safety and funding—for fieldwork in colonized societies. |
人
類学と帝国主義は深い、複雑で、しばしば問題のある歴史を持つ。この学問はヨーロッパの植民地主義から生まれ、植民地化された人々を分類し統治することで
帝国主義の利益に奉仕する知識を生み出した。同時に、特にアメリカの学派(ボアズ派人類学など)から批判的視点が発展し、民族中心主義や人種主義への挑戦
につながった。これが現代の反省性と、今日におけるこの分野の脱植民地化への取り組みへと至っている。主な側面には、人類学が資金調達やアクセスにおいて
植民地体制に依存したこと、その知見が植民地行政に利用されたこと、その共犯関係についての継続的な議論、そして権力の不均衡を解体することに焦点を当て
た反帝国主義的人類学を目指す現代の運動が含まれる。 人類学と帝国主義の関係は歴史的に基盤を成しており、植民地行政への共犯と、その後の批判的自己反省の両面が特徴だ。伝統的に「帝国主義の子」と呼ばれた この学問は、19世紀の西洋勢力の拡大期に確立された。この拡大が、植民地社会におけるフィールドワークの実践的条件——安全や資金など——を提供したの である。 |
| Historical Entanglement + Child of Empire: Anthropology developed as a modern science alongside European imperial expansion, using colonial structures for fieldwork and subjects. + Knowledge Production: Anthropologists generated data and theories (e.g., cultural evolution, racial hierarchies) that often supported colonial ideologies, even if unintentionally. + Mutual Constitution: The imperial context shaped anthropological methods and concepts, while the knowledge produced fueled governance, creating a mutually beneficial (for empire) relationship. Administrative Utility: In the early 20th century, anthropological knowledge was often viewed as a tool for governance. Imperial powers utilized ethnographic data to manage "subject peoples" more effectively. Scientific Justification: Some early anthropological theories, such as social evolutionism, categorized non-Western societies in ways that justified imperial rule as a "civilizing mission". Structural Power: Anthropologists often held higher social status than their subjects and were protected by imperial law, even when they sympathized with local populations. |
歴史的絡み合い + 帝国の子:人類学はヨーロッパの帝国的拡張と並行して近代科学として発展し、フィールドワークや研究対象を得るために植民地体制を利用した。 + 知識の生産:人類学者はデータと理論(例:文化進化論、人種的階層)を生み出したが、意図せずとも植民地イデオロギーを支えるものとなった。 + 相互構成:帝国主義的文脈が人類学的方法論と概念を形成し、生み出された知識が統治を促進した。これにより(帝国にとって)相互に有益な関係が生まれた。 行政的有用性:20世紀初頭、人類学的知見は統治の道具と見なされることが多かった。帝国主義勢力は「被支配民」をより効果的に管理するため、民族誌的データを利用した。 科学的正当化:社会進化論などの初期人類学理論は、非西洋社会を分類し、帝国支配を「文明化使命」として正当化する根拠を提供した。 構造的権力:人類学者は対象者より高い社会的地位を持ち、現地住民に同情する場合でも帝国法によって保護されていた。 |
| Modern Critiques & Reflexivity + Self-Critique: Anthropology has become highly self-reflexive, critically examining its colonial past and the inherent power dynamics in studying other cultures. + Colonial Categories: The discipline grapples with how to move beyond the categories and frameworks developed under colonialism, which can inherently colonize the subjects of study. + Cultural Imperialism: The concept describes dominant cultures imposing norms via media/economy, which anthropologists study as a form of power imbalance. |
現代の批判と反省性 + 自己批判:人類学は高度に反省性となり、植民地時代の過去や他文化研究に内在する権力構造を批判的に検証している。 + 植民地的カテゴリー:この学問は、研究対象を本質的に植民地化する恐れのある植民地主義下で構築されたカテゴリーや枠組みをどう超越するかを模索している。 + 文化的帝国主義:支配的文化がメディアや経済を通じて規範を押し付ける概念であり、人類学者はこれを権力の不均衡の一形態として研究する。 |
| Contemporary Approaches (Anthropology Against Empire) + Anti-Imperialist Stance: Some anthropologists aim to interpret and actively oppose imperialism, focusing on issues like corporate extraction and technocratic constraints on Indigenous communities. + Ethical Challenges: Events like the Human Terrain System project highlight ongoing ethical debates about anthropologists' roles in military or development contexts. + Decolonizing Ethnography: Modern efforts focus on indigenous methodologies, participatory research, and challenging Eurocentric perspectives to create more equitable anthropology. |
現代的アプローチ(人類学対帝国) + 反帝国主義的立場:一部の人類学者は帝国主義を解釈し積極的に反対することを目指し、企業による資源搾取や先住民族コミュニティへの技術官僚的制約といった問題に焦点を当てる。 + 倫理的課題:ヒューマン・テリトリー・システム計画のような事例は、軍事や開発の文脈における人類学者の役割に関する継続的な倫理的議論を浮き彫りにしている。 + 脱植民地化の民族誌:現代の取り組みは、より公平な民族誌を構築するため、先住民族の方法論、参加型研究、そしてヨーロッパ中心主義的視点への挑戦に焦点を当てている。 |
| Key Concepts in the Relationship Handmaiden of Colonialism: A term popularized in the 1960s (notably by Kathleen Gough) to describe how the discipline served as an instrument for colonial administration. Cultural Imperialism: This refers to the imposition of a dominant community's culture onto another, often through media, education, or economic pressure. The "Savage Slot": Theorists argue anthropology traditionally created an "Other"—the "savage"—which mirrored colonial fantasies and served to define the Western "self". |
関係性における主要概念 植民地主義の従僕:1960年代(特にキャスリーン・ゴーフによって)普及した用語で、この学問が植民地行政の道具として機能した様相を説明する。 文化的帝国主義:これは支配的な共同体の文化を、メディアや教育、経済的圧力を通じて他者に押し付けることを指す。 「野蛮人枠」:理論家たちは、人類学が伝統的に「他者」―「野蛮人」―を創造し、それが植民地主義的幻想を反映し、西洋の「自己」を定義する役割を果たしたと論じる。 |
| Contemporary Shifts and Decolonization Self-Reflexivity: Since the 1960s and 70s, anthropology has become one of the most self-reflexive disciplines, actively working to deconstruct colonial categories and ethical failures. Anthropology Against Empire: Modern scholarship focuses on the decolonization of knowledge production, emphasizing perspectives from the "periphery" and challenging the economic and political structures of neocolonialism. Ethical Codes: Modern ethical guidelines, such as the principle of "do no harm," emerged directly from 1960s struggles over military collusion in counterinsurgency work. For further reading on the discipline's evolution, the American Anthropological Association provides resources on professional ethics and the history of anthropological research. These articles explore how anthropology served as a "handmaiden of colonialism" and discuss the ongoing efforts to decolonize the discipline. |
現代における転換と脱植民地化 自己反省性:1960~70年代以降、人類学は最も自己反省的な学問分野の一つとなり、植民地的カテゴリーや倫理的失敗の解体を積極的に進めている。 帝国に対する人類学:現代の研究は知識生産の脱植民地化に焦点を当て、「周辺」の視点を重視し、新植民地主義の経済的・政治的構造に異議を唱えている。 倫理規範:「害をなさない」という原則など現代の倫理指針は、1960年代の反乱鎮圧活動における軍との共謀をめぐる闘争から直接生まれた。 この学問の変遷に関する追加文献(さらに読む)として、アメリカ人類学協会は専門的倫理と人類学研究の歴史に関する資料を提供している。 これらの論文は、人類学が「植民地主義の従僕」として機能した経緯を探り、学問の脱植民地化に向けた継続的な取り組みを論じている。 |
| Kathleen Gough, Anthropology and Imperialism. Monthly Review Vol. 19, No. 11: April 1968. https://doi.org/10.14452/MR-019-11-1968-04_2 | |
| This
paper was first prepared for an audience of anthropologists in the
United States of America, where I have taught and researched for the
past twelve years. Some of the questions that it raises apply, although
perhaps less acutely, to social and cultural anthropologists from the
other industrial nations of Western Europe, North America, Australia,
and New Zealand. The international circumstances to which I refer no
doubt also create problems for anthropologists born and resident in a
number of the Latin American, Asian, and African countries where much
anthropological research is carried out. I should be especially glad if
this paper stimulates some among the latter anthropologists to comment
on how these circumstances are viewed by them and how they affect their
work. |
本稿は、過去12年間に
わたり私が教鞭を執り研究を行ってきたアメリカ合衆国の人類学者向けに最初に作成されたものである。ここで提起される問題のいくつかは、西ヨーロッパ、北
米、オーストラリア、ニュージーランドといった他の工業国出身の人類学者にも、おそらくそれほど深刻ではないにせよ、同様に当てはまる。私が言及する国際
的な状況は、間違いなく、多くの人類学研究が行われているラテンアメリカ、アジア、アフリカの諸国で生まれ、居住する人類学者たちにも問題を引き起こして
いる。本論文が、後者の人類学者たちのうち何人かに、こうした状況を彼らがどのように捉え、それが彼らの研究にどのような影響を与えているかについて論評
するきっかけとなれば、特に喜ばしい。 |
★キャサリーン・ガフ(1925-1990)
| Eleanor Kathleen Gough Aberle
(16 August 1925 – 8 September 1990) was a British anthropologist and
feminist who was known for her work in South Asia and South-East Asia.
As a part of her doctorate work, she did field research in Malabar district
from 1947 to 1949. She did further research in Tanjore district from
1950 to 1953 and again in 1976, and in Vietnam in 1976 and 1982. In
addition, some of her work included campaigning for: nuclear
disarmament, the civil rights movement, women's rights, the third world
and the end of the Vietnam War. She was known for her Marxist leanings
and was on an FBI watchlist. |
エレノア・キャスリーン・ゴーフ・アバーレ(1925年8月16日
-
1990年9月8日)は、南アジアと東南アジアにおける研究で知られる英国の人類学者でありフェミニストであった。博士課程の研究の一環として、1947
年から1949年にかけてマラバル地区で現地調査を行った。さらに1950年から1953年、そして1976年にタンジョール地区で調査を継続し、
1976年と1982年にはベトナムでも調査を実施した。さらに、彼女の活動には核軍縮、公民権運動、女性の権利、第三世界支援、ベトナム戦争終結を求め
る運動も含まれていた。マルクス主義的傾向で知られ、FBIの監視リストに載っていた。 |
| Early life and education Kathleen Gough was born on 16 August 1925 in Hunsingore, a village near Wetherby in Yorkshire, England, that then had a population of 100, no electricity and no piped water. She had a brother and a half-sister. Her father, Albert, was a blacksmith who became involved in the introduction of agricultural machinery to the area and has been described by David Price as being a "working-class radical".[1][2] She was educated at the church school in Hunsingore, from where she obtained a scholarship to King James's Grammar School, Knaresborough and then, in 1943, to Girton College, Cambridge. She excelled in anthropology at Girton and pursued postgraduate research there, receiving her degree in 1950.[3] In July 1947, while undertaking that research, she married Eric John Miller, who was also a student. The couple undertook anthropological fieldwork in Kerala. Gough initially was supervised by J. H. Hutton, whose work on caste in India was informed by early twentieth-century anthropological concerns about the origins of social institutions.[4] After Hutton's retirement, British social anthropologist, Meyer Fortes, whose theoretical interests emphasized social structure, oversaw her work. Gough and Miller found the strain of fieldwork impacted on their marriage and they divorced amicably in 1950.[1] She completed her doctorate in anthropology from Cambridge University in the same year and returned to India alone to pursue further fieldwork.[5] She later, married fellow anthropologist David Aberle in 1955.[1] |
幼少期と教育 キャスリーン・ゴーフは1925年8月16日、イングランド・ヨークシャー州ウェザービー近郊の村ハンシングアで生まれた。当時の人口は100人で、電気 も水道も通っていなかった。彼女には兄と異母妹がいた。父アルバートは鍛冶屋で、この地域への農業機械導入に関わり、デイヴィッド・プライスからは「労働 者階級の急進派」と評されている。[1][2] 彼女はハンシングアールの教会学校で教育を受け、そこからナレスボローのキング・ジェームズ・グラマースクールへの奨学金を獲得し、さらに1943年には ケンブリッジ大学ガートン・カレッジへ進学した。ガートンでは人類学で優秀な成績を収め、同校で大学院研究を続け、1950年に学位を取得した[3]。 1947年7月、研究中に同じく学生だったエリック・ジョン・ミラーと結婚した。夫妻はケララ州で人類学のフィールドワークを行った。当初ゴーフはJ・ H・ハットンの指導を受けた。ハットンのインドにおけるカースト研究は、20世紀初頭の人類学が社会制度の起源に抱いた関心に基づいていた[4]。ハット ンの引退後、社会構造を理論的関心とする英国人社会人類学者マイヤー・フォーテスが彼女の研究を監督した。ゴーフとミラーは、フィールドワークの負担が結 婚生活に影響を与えたため、1950年に円満に離婚した[1]。同年、ケンブリッジ大学で人類学の博士号を取得し、さらなるフィールドワークを追求するた め単独でインドに戻った[5]。その後、1955年に人類学者のデイヴィッド・アバーレと再婚した[1]。 |
| Career Gough's research in India were primarily in the Malabar district from 1947 to 1949 and in the Tanjore district from 1950 to 1953.[5] Her efforts were groundbreaking and she published five papers in the 1950s. She contributed over half of the content published as Matrilineal Kinship in 1961, of which Heike Moser and Paul Younger say that "Her analysis is a brilliant example of the structural-functionalist anthropology associated with Britain in her day, and everyone since has begun from her explanations or matriliny of marumukatayam as descent through the female line.... The debates that raged about matriliny, marriage ceremonies, hypergamy, and polyandry after these definitive studies were complex."[6] She returned to India in 1976 and it was after this visit that most of her research work on India was published. She visited Vietnam in the same year and again in 1982.[5] Gough was employed in teaching positions at Brandeis University from 1961 to 1963, the University of Oregon from 1963 to 1967 and Simon Fraser University from 1967 to 1970. She was an Honorary Research Associate at the University of British Columbia from 1974 until her death. Gough also taught and conducted research at Harvard, Manchester, Berkeley, University of Michigan, Wayne State, Toronto, and British Columbia.[5][7] |
経歴 ゴーフのインドにおける研究は、主に1947年から1949年までマラバル地区で、1950年から1953年までタンジョール地区で行われた。[5] 彼女の取り組みは画期的であり、1950年代に5本の論文を発表した。1961年に刊行された『母系親族』に掲載された内容の半分以上を彼女が執筆した。 ハイケ・モーザーとポール・ヤンガーはこれについて「彼女の分析は当時の英国に代表される構造機能主義人類学の見事な例であり、その後誰もが彼女の説明、 すなわち母系(マルムカターヤム)を女性系統による血統と解釈する出発点とした」と評している。これらの決定的研究の後、母系制、婚姻儀式、ハイパーガ ミー、ポリアンダリーを巡る論争は複雑なものとなった。」[6] 彼女は1976年にインドへ再訪し、この訪問後にインドに関する研究成果の大半が発表された。同年及び1982年にはベトナムも訪問している。[5] ゴフは1961年から1963年までブランダイス大学、1963年から1967年までオレゴン大学、1967年から1970年までサイモンフレイザー大学 で教職に就いた。1974年から死去するまでブリティッシュコロンビア大学の名誉研究員を務めた。ゴーフはまた、ハーバード大学、マンチェスター大学、カ リフォルニア大学バークレー校、ミシガン大学、ウェイン州立大学、トロント大学、ブリティッシュコロンビア大学でも教鞭を執り研究を行った。[5][7] |
| Politics Gough was a Marxist and the responses of some university administrations to her leftist leanings sometimes landed her in trouble. She supported Cuba during the Cuban Missile Crisis and was outspoken in her condemnation of police brutalities. As a result, most of the stipulated pay hikes during her teaching career were cancelled.[8] Moreover, Gough's membership in the Johnson-Forest Tendency and her work for civil rights and against the war in Vietnam triggered the interest of the FBI, who placed her and her husband on their watchlist.[2] In addition, Gough was active in peace movements within Brandeis campus, specifically from 1961 to 1963.[7] Gough promoted the welfare of lower castes in India, hoping to bring them closer to the principles of Communism. Gough also strongly opposed upper castes who generally supported right-wing politics and anti-Marxism.[2] |
政治 ゴーフはマルクス主義者であり、彼女の左派的傾向に対する大学当局の対応が時折トラブルを招いた。キューバ危機ではキューバを支持し、警察の暴行を公然と 非難した。その結果、彼女の教職生活における規定の昇給の大半は取り消された[8]。さらに、ゴフがジョンソン・フォレスト・テンデンシーのメンバーで あったこと、公民権運動やベトナム反戦運動への関与がFBIの関心を呼び、彼女と夫は監視リストに載せられた[2]。加えて、ゴフはブランダイス大学キャ ンパス内の平和運動、特に1961年から1963年にかけて活発に活動した。[7] ゴーフはインドの低カースト層の福祉を推進し、彼らを共産主義の理念に近づけようとした。また、右派政治や反マルクス主義を支持する傾向のある高カースト層に対しては強く反対した。[2] |
| Works Some of Gough's more important works include Ten More Beautiful: The Rebuilding of Vietnam (1978), Rural Society in Southeast India (1981), Rural Change in Southeast India, 1950s–1980s (1989) and Political Economy in Vietnam (1990).[5] The Traditional Kinship System of the Nayars of Malabar. Harvard University. 1954. "The Social Structure of a Tanjore Village," In Village India: Studies in the Little Community, ed. by McKim Marriott. American Anthropological Association Memoir No. 843, pp. 36–52. "Brahman Kinship in a Tamil Village," American Anthropologist vol. 58: 826-53. Cult of the dead among the Nayars. 1958. Anthropology and Imperialism. Radical Education Project. 1960. Nayar: Central Kerala. University of California Press. 1961. David Murray Schneider; Kathleen Gough (1961). Matrilineal Kinship. University of California. The Decline of the State and the Coming of World Society: An Optimist's View of the Future. Correspondence Publishing Company. 1962. "Caste in a Tanjore Village." In Aspects of Caste in South India, Ceylon and North-West Pakistan. ed. by E. R. Leach. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 11–60. Female Initiation Rites on the Malabar Coast. 1965. John Rankin Goody, ed. (1968). Literacy in Traditional Societies. University Press. "Anthropology and Imperialism." Monthly Review 12:12-27. Caste in a Tanjore Village. Department of Archaeology and Anthropology at the University Press. 1969. The Struggle at Simon Fraser University. Thurston Taylor. 1970. Kathleen Gough; Hari P. Sharma, eds. (1973). Imperialism and Revolution in South Asia. Monthly Review Press. ISBN 978-0-85345-273-7. The Origin of the Family. New Hogtown Press. 1973. Class developments in South India. Centre for Developing-Area Studies, McGill University. 1975. Ten times more beautiful:The Rebuilding of Vietnam. Monthly Review Press. 1978. ISBN 978-0-85345-464-9. Dravidian Kinship and Modes of Production. Indian Council of Social Science Research. 1978. Rural Society in Southeast India. Cambridge University Press. 1981. ISBN 978-0-521-04019-8. Southeast Asia: Facing the Challenge of Socialist Construction. Synthesis Publications. 1986. Rural Change in Southeast India: 1950s to 1980s. Oxford University Press. 1989. ISBN 978-0-19-562276-8. Political Economy in Vietnam. Folklore Institute. 1990. Saghir Ahmed (1977). Class and Power in a Punjabi Village (Introduction). Monthly Review Press. ISBN 978-0-85345-385-7. |
著作 ゴーフの主な著作には、『さらに美しい十ヶ所:ベトナム再建』(1978年)、『南東インドの農村社会』(1981年)、『南東インドの農村変化、1950年代~1980年代』(1989年)、『ベトナムの政治経済』(1990年)などがある。[5] マラバル地方ナヤール族の伝統的親族制度。ハーバード大学。1954年。 「タンジョール村落の社会構造」、『村落インド:小共同体研究』所収、マッキム・マリオット編。アメリカ人類学会紀要第843号、36-52頁。 「タミル村におけるバラモンの親族関係」『アメリカ人類学雑誌』第58巻:826-53頁。 『ナヤール族における死者崇拝』1958年。 人類学と帝国主義。急進的教育プロジェクト。1960年。 ナヤール:中央ケララ。カリフォルニア大学出版局。1961年。 デイヴィッド・マレー・シュナイダー;キャスリーン・ゴーフ(1961年)。母系血縁。カリフォルニア大学。 国家の衰退と世界社会の到来:未来に対する楽観主義者の見解。通信出版会社。1962年。 「タンジョール村におけるカースト」『南インド、セイロン、北西パキスタンにおけるカーストの諸相』E. R. リーチ編。ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、pp. 11–60。 マラバル海岸における女性の通過儀礼。1965年。 ジョン・ランキン・グッディ編(1968)。『伝統社会における識字』大学出版局。 「人類学と帝国主義」。『月刊レビュー』12号:12-27頁。 『タンジョール村におけるカースト』。考古学・人類学部大学出版局。1969年。 『サイモン・フレイザー大学での闘争』。サーストン・テイラー。1970年。 キャスリーン・ゴーフ、ハリ・P・シャルマ編(1973)。『南アジアにおける帝国主義と革命』。月刊レビュー出版。ISBN 978-0-85345-273-7。 『家族の起源』。ニュー・ホッグタウン出版。1973年。 『南インドにおける階級の発展』。マギル大学発展途上地域研究センター。1975年。 十倍美しい:ベトナム再建。マンスリー・レビュー・プレス。1978年。ISBN 978-0-85345-464-9。 ドラヴィダ親族関係と生産様式。インド社会科学研究評議会。1978年。 『南東インドの農村社会』ケンブリッジ大学出版局、1981年。ISBN 978-0-521-04019-8。 『東南アジア:社会主義建設の課題に直面して』シンセシス出版、1986年。 『南東インドの農村変遷:1950年代から1980年代』オックスフォード大学出版局、1989年。ISBN 978-0-19-562276-8。 ベトナムの政治経済。民俗学研究所。1990年。 サギール・アフマド(1977)。パンジャーブ村における階級と権力(序文)。月刊レビュー出版社。ISBN 978-0-85345-385-7。 |
| Death She died from cancer in Vancouver on 8 September 1990 after a four-month illness. She was buried on 13 September 1990 at Capilano View cemetery.[1] |
死 彼女は癌により、バンクーバーで1990年9月8日に死去した。病期は4ヶ月であった。1990年9月13日、キャピラノ・ビュー墓地に埋葬された。[1] |
| Further reading Jorgensen, Joseph G. (1993). "Kathleen Gough's Fight against the Consequences of Class and Imperialism on Campus". Anthropologica, 35 (2): 227-234. Mencher, Joan (1993). "Kathleen Gough and Research in Kerala". Anthropologica. 35 (2). Canadian Anthropology Society: 195–201. doi:10.2307/25605731. JSTOR 25605731. (subscription required) |
追加文献(さらに読む) ヨルゲンセン、ジョセフ・G. (1993). 「キャンパスにおける階級と帝国主義の結果に対するキャスリーン・ゴフの闘い」. Anthropologica, 35 (2): 227-234. メンチャー、ジョーン(1993)。「キャスリーン・ゴーフとケララ州における研究」。『人類学』35巻2号。カナダ人類学会:195–201頁。doi:10.2307/25605731。JSTOR 25605731。(購読が必要) |
| References 1. Frankenberg, Ronald (2004). "Gough, (Eleanor) Kathleen (1925–1990)". Oxford Dictionary of National Biography. Oxford Dictionary of National Biography (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/60257. Retrieved 8 November 2013. (Subscription, Wikipedia Library access or UK public library membership required.) 2. Price, David H. (2004). Threatening anthropology: McCarthyism and the FBI's surveillance of activist anthropologists. Duke University Press. pp. 307–325. ISBN 978-0-8223-3338-8. 3. Lee, Richard; Sacks, Karen. "Anthropology, Imperialism, and Resistance: The Work of Kathleen Gough". ProQuest. {{cite web}}: Missing or empty |url= (help) 4. Klass, Morton (1980). Caste: the emergence of the South Asian social system. Institute for the Study of Human Issues. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues. ISBN 978-0-915980-97-0. 5. "Biography of Kathleen Gough at the University of British Columbia Archives". University of British Columbia. Archived from the original on 21 March 2008. 6. Moser, Heike; Younger, Paul (2013). "Kerala: Plurality and Consensus". In Berger, Peter; Heidemann, Frank (eds.). The Modern Anthropology of India: Ethnography, Themes and Theory. Routledge. p. 141. ISBN 978-1-134-06111-2. 7. Lee, Richard; Sacks, Karen. "Anthropology, Imperialism and Resistance: The Work of Kathleen Gough". ProQuest. {{cite web}}: Missing or empty |url= (help) 8. "Biography of Kathleen Aberle". Minnesota State University. Archived from the original on 3 June 2010. |
参考文献 1. フランケンバーグ、ロナルド (2004). 「ゴーフ、(エレノア) キャスリーン (1925–1990)」. 『オックスフォード国家人物事典』. オックスフォード国家人物事典 (オンライン版). オックスフォード大学出版局. doi:10.1093/ref:odnb/60257. 2013年11月8日取得。(購読、Wikipediaライブラリアクセス、または英国公共図書館会員資格が必要) 2. Price, David H. (2004). Threatening anthropology: McCarthyism and the FBI's surveillance of activist anthropologists. Duke University Press. pp. 307–325. ISBN 978-0-8223-3338-8. 3. Lee, Richard; Sacks, Karen. 「人類学、帝国主義、そして抵抗:キャスリーン・ゴフの業績」. ProQuest. {{cite web}}: 欠落または空欄の |url= (ヘルプ) 4. Klass, Morton (1980). Caste: the emergence of the South Asian social system. Institute for the Study of Human Issues. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues. ISBN 978-0-915980-97-0。 5. 「ブリティッシュコロンビア大学アーカイブズ所蔵のキャスリーン・ゴフの伝記」。ブリティッシュコロンビア大学。2008年3月21日にオリジナルからアーカイブ。 6. モザー、ハイケ、ヤング、ポール(2013)。「ケララ州:多元性と合意」。ピーター・バーガー、フランク・ハイデマン(編)。『インドの現代人類学:民族誌、テーマ、理論』。ラウトレッジ。141 ページ。ISBN 978-1-134-06111-2。 7. リー、リチャード; サックス、カレン。「人類学、帝国主義、そして抵抗:キャスリーン・ゴーフの業績」。プロクエスト。{{cite web}}: |url= が欠落しているか空である (ヘルプ) 8. 「キャスリーン・アバーレの伝記」。ミネソタ州立大学。2010年6月3日にオリジナルからアーカイブされた。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Kathleen_Gough |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099