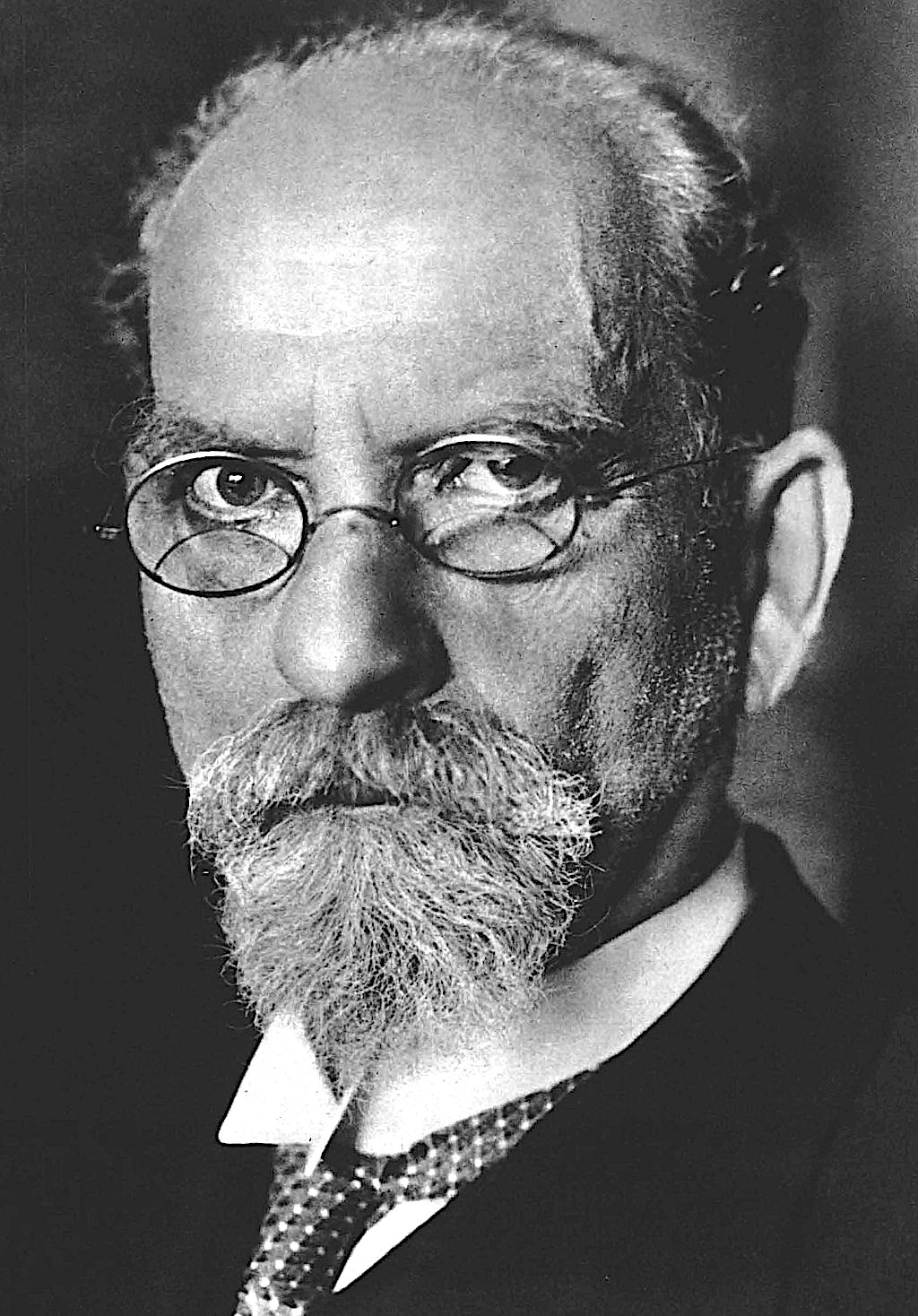
エドムント・フッサール
Edmund Gustav Albrecht Husserl, 1859-1938
☆ エドムント・グスタフ・アルベルト・フッサール(/ˈhʊsɜːrl/ HUUSS-url;[14] 米国では /ˈhʊsərəl/ HUUSS-ər-əl,[15] ドイツ語: [ˈɛtm 1859年4月8日 - 1938年4月27日[17])は、現象学派を創始したオーストリア系ドイツ人の哲学者、数学者である。 初期の著作では、志向性の分析を基盤として、歴史主義と心理主義の論理に対する批判を詳細に論じている。円熟した作品では、いわゆる現象学的還元に基づく 体系的な基礎科学の構築を目指した。超越論的意識がすべての可能な知識の限界を定めるという主張に基づき、フッサールは現象学を超越論的観念論哲学として 再定義した。フッサールの思想は20世紀の哲学に多大な影響を与え、現代哲学を超えて、今なお著名な人物である。 フッサールは、カール・ワイエルシュトラスとレオ・ケーニヒスベルガーから数学を、フランツ・ブレンターノとカール・シュトゥンプから哲学を学んだ。 [18] 1887年からハレで、その後1901年からゲッティンゲンで、さらに1916年からフライブルクで教授として哲学を教え、1928年に引退するまで教鞭 をとり、その後も非常に生産的な活動を続けた。1933年、ナチス党の人種法により、ユダヤ人としての家系を理由にフッサールはフライブルク大学の図書館 から追放され、数か月後にはドイツ学術アカデミーも退会した。病気療養の後、1938年にフライブルクで死去した。[19]
| Edmund Gustav Albrecht Husserl
[ˈhʊsɐl] (* 8. April 1859 in Proßnitz in Mähren, Kaisertum Österreich;
† 27. April 1938 in Freiburg im Breisgau, Deutsches Reich)[1] war ein
österreichisch-deutscher Philosoph und Mathematiker und Begründer der
philosophischen Strömung der Phänomenologie. Er gilt als einer der
einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Husserl studierte an der Universität Leipzig Mathematik bei Karl Weierstraß und Leo Koenigsberger sowie Philosophie bei Franz Brentano und Carl Stumpf.[2] Ab 1887 unterrichtete er an der Universität Halle Philosophie als Privatdozent. Von 1901 an lehrte er zunächst an der Georg-August-Universität Göttingen, später als Professor an der Universität Freiburg. 1928 wurde er emeritiert, was seinem philosophischen Schaffen jedoch keinen Abbruch tat. 1938 erkrankte er und starb im selben Jahr in Freiburg. Während seine frühen Schriften eine psychologische Grundlegung der Mathematik anstrebten, legte Husserl mit seinen 1900 und 1901 erschienenen Logischen Untersuchungen eine umfassende Kritik des zu dieser Zeit vorherrschenden Psychologismus vor, der die Gesetze der Logik als Ausdruck bloßer psychischer Gegebenheiten sah. Er stellte darüber hinaus weitreichende Betrachtungen zur reinen Logik vor. Um 1907 stellte Husserl die von ihm entwickelte Methode der „phänomenologischen Reduktion“ vor. Diese würde fortan nicht nur sein weiteres Schaffen maßgeblich beeinflussen, sondern in seinen folgenden Werken zum philosophischen Ansatz eines transzendentalen Idealismus führen. Husserls Denken prägte die Philosophie des 20. Jahrhunderts besonders in Deutschland und Frankreich und ist bis in die Gegenwart von großer Wirkung. Zu Husserls Schülern zählen Martin Heidegger, Oskar Becker, Ludwig Ferdinand Clauß, Eugen Fink, Edith Stein und Günther Anders. Max Scheler, Alfred Schütz, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas und viele mehr wurden von seinem Denken maßgeblich beeinflusst. |
エドムント・グスタフ・アルベルト・フッサール(ドイツ語発音:
[ˈhuːsɐl]、1859年4月8日 -
1938年4月27日)は、現象学の分野における業績で最もよく知られるオーストリア=ドイツの哲学者、数学者である。20世紀で最も影響力のある思想家
の一人とみなされている。 フッサールはライプツィヒ大学でカール・ワイエルシュトラスとレオ・ケーニヒスベルガーのもとで数学を、フランツ・ブレンターノとカール・シュトゥンプの もとで哲学を学んだ。1887年よりハレ大学で哲学の非常勤講師を務めた。1901年からはゲッティンゲン大学のゲオルク・アウグスト大学で教鞭をとり、 その後フライブルク大学の教授に就任した。1928年に退職したが、哲学的な研究には影響を与えなかった。1938年に病気になり、同年にフライブルクで 死去した。 初期の著作では数学の心理学的基礎を確立しようとしていたが、1900年と1901年に発表された『論理的研究』では、当時主流であった心理学的アプロー チを包括的に批判し、論理法則を単なる精神現象の表現とみなす考え方を否定した。また、純粋論理に関する広範囲にわたる考察も提示した。1907年頃、 フッサールは彼が開発した「現象学的還元」の方法を提示した。それ以降、この方法は彼のその後の研究に決定的な影響を与えただけでなく、その後の研究では 超越論的観念論の哲学的アプローチにつながった。 フッサールの思想は、特にドイツとフランスにおいて20世紀の哲学に大きな影響を与え、今日に至るまで多大な影響を与え続けている。フッサールの弟子に は、マルティン・ハイデッガー、オスカー・ベッカー、ルートヴィヒ・フェルディナント・クラウス、オイゲン・フィンク、エディト・シュタイン、ギュン ター・アンダースなどがいる。また、マックス・シェーラー、アルフレッド・シュッツ、ジャン=ポール・サルトル、モーリス・メルロ=ポンティ、エマニュエ ル・レヴィナスなど、多くの人々がフッサールの思想に大きな影響を受けた。 |
| Inhaltsverzeichnis 1 Leben 1.1 Jugend und Bildung 1.2 Akademische Forschung und Lehre 1.3 Letzte Jahre 2 Grundlagen der Philosophie Husserls 2.1 Frühe Philosophie 2.2 Psychologismuskritik 2.3 Intentionalität 2.4 Phänomenologische Reduktion und Epoché 3 Philosophie als strenge Wissenschaft 4 Das Spätwerk: Krisis der Wissenschaften 5 Ontologie und Metaphysik 6 Intersubjektivität 6.1 Hua XIII 6.2 Hua XIV 6.3 Hua XV 7 Phänomenologie des Raumes und der Bewegung (Hua XVI) 8 Ethik 9 Psychologie und Psychiatrie 10 Husserls Nachlass 11 Schriften Husserls 11.1 Husserliana 11.2 Zu Husserls Lebzeiten erschienene Schriften 11.3 Weitere Ausgaben 12 Literatur 12.1 Zu Husserl 12.2 Weiterführendes 12.3 Rezeption 13 Weblinks |
目次 1 生涯 1.1 青年期と教育 1.2 学術研究と教育 1.3 晩年 2 フッサール哲学の基礎 2.1 初期の哲学 2.2 心理主義への批判 2.3 志向性 2.4 現象学的還元とエポケー 3 厳密科学としての哲学 4 晩年の仕事:科学の危機 5 存在論と形而上学 6 間主観性 6.1 13 Hua 6.2 14 Hua 6.3 15 Hua 7 空間と運動の現象学(16 Hua) 8 倫理学 9 心理学と精神医学 10 フッサールの遺産 11 フッサールの著作 11.1 フッサール関連 11.2 フッサール存命中に出版された著作 11.3 その他の版 12 文献 12.1 フッサールについて 12.2 その他の参考文献 12.3 反響 13 外部リンク |
| Leben Jugend und Bildung 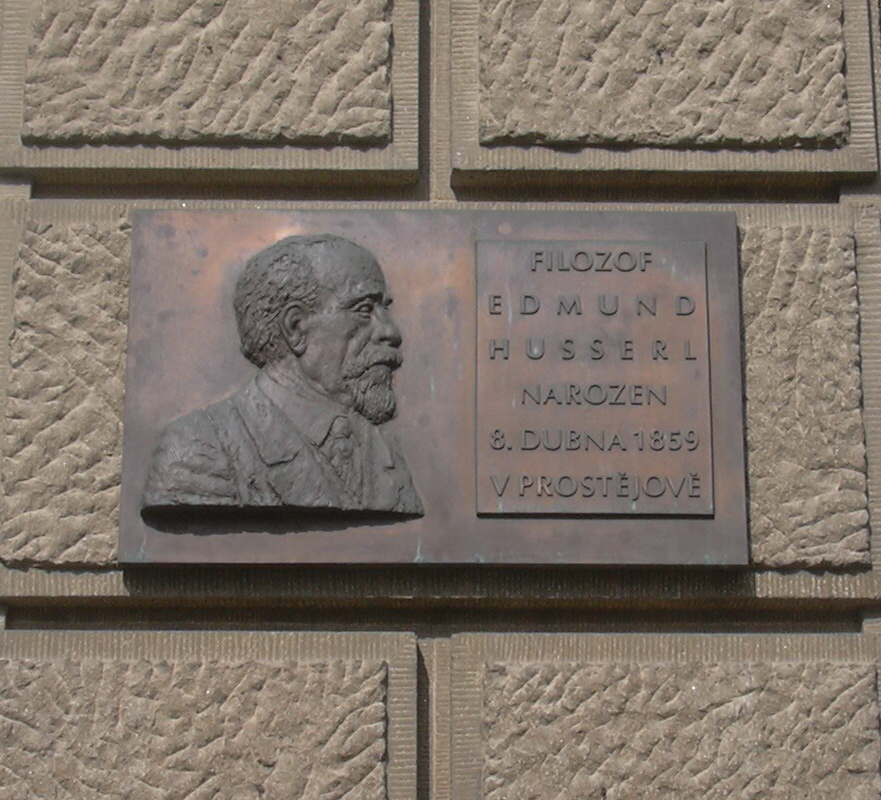 Gedenktafel in Prostějov Als zweiter Sohn einer der deutschsprachigen Mittelschicht angehörigen jüdischen Tuchhändler-Familie wurde Husserl 1859 in Prostějov (deutsch Proßnitz) in Mähren im Kaisertum Österreich geboren. Er besuchte das Gymnasium in Olmütz, an dem er 1876 die Hochschulreife erlangte. An der Universität Leipzig (1876–1878) studierte er Mathematik und Physik sowie Astronomie und besuchte die Vorlesungen des Philosophen Wilhelm Wundt, eines der Begründer der modernen, naturwissenschaftlich orientierten Psychologie. Wundt vertrat einen holistischen Wissenschaftsansatz, in dem natur- und geisteswissenschaftliche Perspektiven verbunden waren. Die Philosophie blieb jedoch zunächst nur eine Nebenbeschäftigung Husserls. An der Universität Leipzig lernte er Tomáš G. Masaryk kennen, der ebenfalls aus Mähren kam und als Privatlehrer seinen Lebensunterhalt verdiente. Masaryk wurde später Abgeordneter im österreichischen Reichsrat, setzte sich während des Ersten Weltkrieges an die Spitze der tschechischen Unabhängigkeitsbewegung und wurde im Jahr 1918 (nach dem Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie) erster Präsident der Tschechoslowakei. Auch wenn sich beide nach drei Semestern in Leipzig aus den Augen verloren, hatte die Begegnung Folgen für Husserls weitere Entwicklung. Masaryk unterstützte nicht nur die Konvertierung Husserls zum evangelisch-lutherischen Glauben, er empfahl ihm auch seinen Doktorvater, den Philosophen Franz Brentano, als philosophischen Lehrer und Mentor. Zunächst zog Husserl 1878 nach Berlin, um an der Friedrich-Wilhelms-Universität (heute: Humboldt-Universität) sein Mathematikstudium unter Leopold Kronecker und Karl Weierstraß fortzusetzen. Dort besuchte er die Philosophie-Vorlesungen von Friedrich Paulsen. Im Jahr 1881 wechselte er an die Universität Wien, um sein Mathematikstudium unter der Leitung eines ehemaligen Schülers von Karl Weierstraß, Leo Königsberger, abzuschließen. Bei diesem wurde er 1883 mit seiner mathematischen Arbeit Beiträge zur Theorie der Variationsrechnung promoviert.[3] Promoviert kehrte er nach Berlin zurück, um dort als Assistent von Karl Weierstraß zu arbeiten. Als dieser erkrankte, zog Husserl abermals nach Wien und leistete dort seinen Militärdienst. 1884 besuchte er an der Universität Wien die Vorlesung Franz Brentanos über Philosophie und philosophische Psychologie. Brentano gilt als Begründer der Aktpsychologie und lehrte Psychologie vom empirischen Standpunkt (1874), wie der Titel seines Hauptwerkes lautet. Er führte Husserl in die Werke von Bernard Bolzano, Hermann Lotze, John Stuart Mill und David Hume ein. Husserl war so beeindruckt von Brentanos Schaffen, dass er entschied, sein Leben der Philosophie zu widmen. Somit wird Franz Brentano oft als wichtigster Einflussgeber Husserls angesehen. Da Brentano als Privatdozent Husserl nicht habilitieren konnte, folgte dieser 1886 Carl Stumpf, einem ehemaligen Studenten Brentanos, der – wie Wundt – ein Vorreiter der modernen Psychologie war, an die Universität Halle/Saale, wo er sich unter seiner Leitung 1887 mit der Arbeit Über den Begriff der Zahl[4] habilitierte. Diese zwischen Psychologie und Mathematik angesiedelte Abhandlung sollte später als Grundlage für seine erste einflussreiche Schrift Philosophie der Arithmetik (1891) dienen. Im Jahr 1887 heiratete Husserl Malvine Steinschneider und ließ sich aus diesem Anlass evangelisch taufen und trauen. 1892 wurde ihre Tochter Elizabeth geboren, 1893 ihr Sohn Gerhart, 1894 ihr Sohn Wolfgang, der im Ersten Weltkrieg fiel. Gerhart Husserl wurde Rechtsphilosoph, der zum Thema vergleichendes Recht forschte und zuerst in den USA und nach dem Krieg in Deutschland lehrte. |
人生 若さと教育 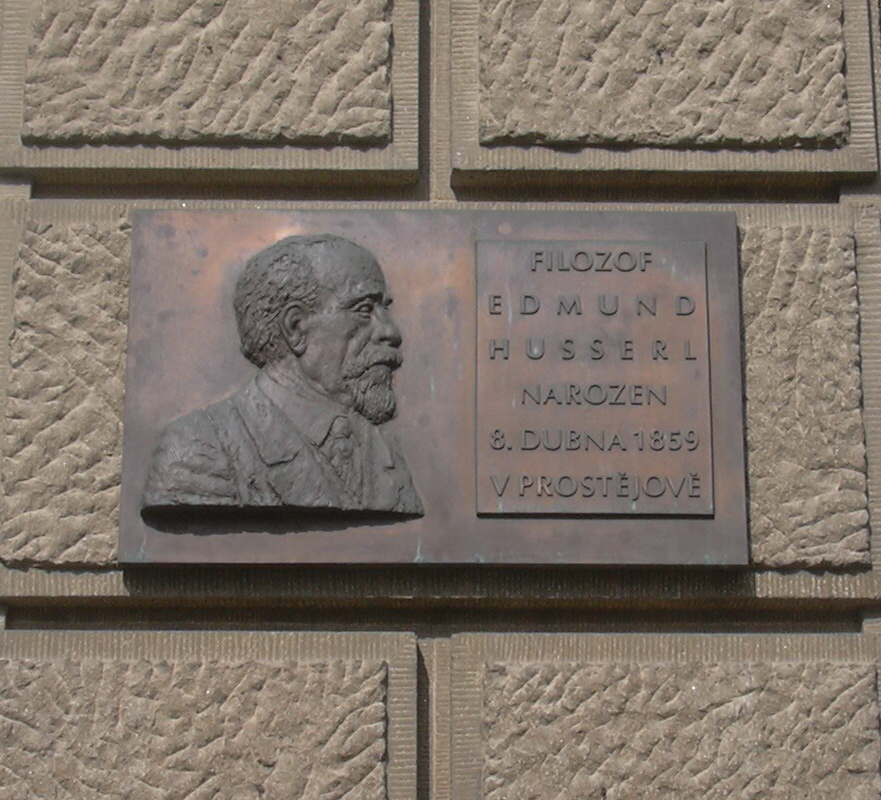 プロスチェヨフの記念プレート ユダヤ人の布商人一家の次男として、ドイツ語話者の中流階級に属する家庭に生まれたフッサールは、1859年にオーストリア帝国領モラヴィアのプロスチェ ヨフ(ドイツ語名:プロスニッツ)で生まれた。彼はオロモウツのグラマースクールに通い、1876年に大学入学資格を取得した。彼はライプツィヒ大学で数 学と物理学、天文学を学び(1876年~1878年)、近代科学心理学の創始者の一人である哲学者ヴィルヘルム・ヴントの講義を受講した。ヴントは自然科 学と人文科学の視点を組み合わせた科学への全体論的アプローチを提唱した。しかし、当初は哲学はフッサールにとってあくまで副業にすぎなかった。ライプ ツィヒ大学で、同じくモラヴィア出身で家庭教師として生計を立てていたトマーシュ・マサリクと出会った。マサリクは後にオーストリア帝国の帝国議会である オーストリア帝国議会の議員となり、第一次世界大戦中はチェコ独立運動の指導的役割を担った。オーストリア=ハンガリー帝国の崩壊後、1918年にチェコ スロバキアの初代大統領に就任した。ライプツィヒでの3学期を終えた後、2人は互いの消息を失ったが、この出会いはフッサールにとってさらなる発展につな がるものとなった。マサリクはフッサールの福音ルーテル派への改宗を支援しただけでなく、フッサールに哲学の師として指導者となるよう、博士課程の指導教 官であった哲学者フランツ・ブレンターノを推薦した。 当初、フッサールは1878年にベルリンに移り、フリードリヒ・ウィルヘルム大学(現フンボルト大学)でレオポルト・クロネッカーとカール・ワイエルシュ トラスのもとで数学の研究を続けた。そこでフリードリヒ・パウルゼンの哲学講義を受講した。1881年、ウィーン大学に移り、カール・ワイエルシュトラス の元学生であるレオ・ケーニヒスベルガーの指導の下で数学の研究を続けた。1883年、数学論文「変分学の理論への貢献」により、彼とともに博士号を取得 した。 卒業後、ベルリンに戻り、カール・ワイエルシュトラスの助手として働く。ワイエルシュトラスが病に倒れると、フッサールは再びウィーンに移り、そこで兵役 についた。1884年、ウィーン大学でフランツ・ブレンターノの哲学と哲学心理学の講義を受講した。ブレンターノは行為心理学の創始者とみなされており、 経験的観点からの心理学(1874年)という主著のタイトルにもなっている。彼はフッサールにベルンハルト・ボルツァーノ、ヘルマン・ロッツェ、ジョン・ スチュアート・ミル、デイヴィッド・ヒュームの著作を紹介した。フッサールはブレンターノの著作に感銘を受け、哲学に生涯を捧げることを決意した。そのた め、フランツ・ブレンターノはしばしばフッサールに最も大きな影響を与えた人物とみなされている。ブレンターノは個人講師としてフッサールをハビリテー ション(大学教授資格)させることができなかったため、フッサールは1886年にヴントと同様に近代心理学のパイオニアであったブレンターノの元教え子 カール・シュムンプトに師事し、1887年にシュムンプトの指導の下、ハレ大学で「数の概念について」という論文でハビリテーションした。心理学と数学の 中間に位置するこの論文は、後に彼の最初の影響力のある著作『算術哲学』(1891年)の基礎となった。 1887年、フッサールはマルバイン・シュタインシュナイダーと結婚し、この機会に自らプロテスタントの洗礼を受け、結婚した。1892年には娘のエリザ ベスが、1893年には息子のゲルハルトが、そして1894年には息子のヴォルフガングが誕生したが、ヴォルフガングは第一次世界大戦で命を落とした。ゲ ルハルト・フッサールは比較法学を研究する法哲学者となり、まずアメリカで、そして戦後はドイツで教鞭をとった。 |
| Akademische Forschung und Lehre Im Anschluss an seine Habilitation begann Husserl im Jahr 1887 seine Universitätskarriere als unbesoldeter Privatdozent an der Universität Halle/Saale. Mit seiner Schrift Philosophie der Arithmetik (1891),[5] die sich auf seine früheren Arbeiten über die Mathematik und die Philosophie beruft und einen psychologischen Rahmen als Basis der Mathematik vorschlägt, erregte Husserl die kritische Aufmerksamkeit des Logikers Gottlob Frege. Mit Rücksicht auf dessen Psychologismuskritik stellte er bis zur Jahrhundertwende umfangreiche Logische Untersuchungen an, die zu seinem ersten Hauptwerk heranwuchsen und dem Zweiundvierzigjährigen 1901 einen Ruf nach Göttingen einbrachten, wo er vierzehn Jahre lang, zunächst als außerordentlicher, ab 1906 ordentlicher Professor, lehrte. Der erste Band der Logischen Untersuchungen enthält Reflexionen über eine „reine Logik“, die eine Zurückweisung des „Psychologismus“[6] darstellen. Das Werk wurde positiv aufgenommen und unter anderem Thema eines Seminars von Wilhelm Dilthey. Persönlich bekannt wurde er in der Göttinger Zeit unter anderen mit David Hilbert, Leonard Nelson, Wilhelm Dilthey, Max Scheler, Alexandre Koyré und Karl Jaspers sowie dem Dichter Hugo von Hofmannsthal.  Das Wohnhaus Husserls in Göttingen bis 1916 (Hermann-Föge-Weg 7, mit Göttinger Gedenktafel[7]) Husserl besuchte 1908 seinen ehemaligen Lehrer Franz Brentano in Italien. 1910 wurde er Mitherausgeber der Zeitschrift Logos. Während dieser Zeit hielt er Vorlesungen über das innere Zeitbewusstsein, die mehr als zehn Jahre später von seinem ehemaligen Studenten Martin Heidegger für die Veröffentlichung bearbeitet wurden.[8] 1912 gründete Husserl mit den Anhängern seiner Philosophie das Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung, das von 1913 bis 1930 Artikel der neuen philosophischen Richtung veröffentlichte – so etwa in der ersten Ausgabe des Jahrbuchs Husserls einflussreiche Arbeit Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie.[9] Im Oktober 1914 wurden beide Söhne Husserls eingezogen und mussten an der Westfront des Ersten Weltkriegs kämpfen. Im darauffolgenden Jahr wurde Wolfgang Husserl schwer verwundet. Am 8. März 1916 starb er auf dem Schlachtfeld von Verdun. Im nächsten Jahr wurde auch sein anderer Sohn Gerhart Husserl im Gefecht verletzt, überlebte jedoch. Husserls Mutter Julia starb im selben Jahr. Im November 1917 fiel Adolf Reinach, einer von Husserls bemerkenswertesten Studenten und selbst Rechtsphilosoph, in Flandern.  Das Wohnhaus Husserls in Freiburg von 1916 bis 1937 Husserl folgte 1916 einem Ruf an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (im Breisgau), wo er als ordentlicher Professor den Lehrstuhl des Neukantianers Heinrich Rickert übernahm und seine philosophischen Forschungen vorantrieb. Zu dieser Zeit hatte sich Husserl – trotz der prekären Lage Deutschlands nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg – zu einem der führenden deutschsprachigen Philosophen entwickelt, der einen großen Schülerkreis um sich hatte und sowohl im Inland wie im Ausland Anerkennung erfuhr. Als seine persönliche Assistentin arbeitete in diesen ersten Jahren Edith Stein; von 1920 bis 1923 übernahm Martin Heidegger diese Stelle. Im Jahr 1922 hielt Husserl vier Vorlesungen über die phänomenologische Methode am University College London. Die Universität von Berlin bot ihm im Jahr 1923 eine Stelle an, die er allerdings ablehnte. Er erhielt Ehrendoktorwürden der Universitäten London, Paris, Prag und Boston und wurde zum Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, der American Academy of Arts and Sciences und der British Academy[10] gewählt. Im Jahr 1927 widmete Heidegger Husserl sein Buch Sein und Zeit „in dankbarer Verehrung und Freundschaft“.[11] Husserl blieb Professor in Freiburg, bis er darum bat, in den Ruhestand gehen zu dürfen; seine letzte Vorlesung hielt er am 25. Juli 1928. Eine Festschrift als Geschenk zu seinem siebzigsten Geburtstag wurde ihm am 8. April 1929 überreicht. Zu seinen Schülern gehörten neben Edith Stein und Martin Heidegger, der die Nachfolge des Freiburger Lehrstuhls übernahm, der Technikphilosoph Günther Stern (Anders), der Rassen- und Völkerpsychologe Ludwig Ferdinand Clauß sowie unter anderem die Philosophen Eugen Fink, Dietrich von Hildebrand und Ludwig Landgrebe. Letzte Jahre  Grab Husserls auf dem Friedhof in Freiburg Günterstal Trotz seiner Emeritierung hielt Husserl noch weitere bedeutende Vorlesungen: Die Pariser Vorlesungen aus dem Jahr 1929 führten zu den Cartesianischen Meditationen (Paris 1931).[12] Seine Vorlesungen in Prag 1935[13][14] und in Wien im Jahr 1936 (nach anderen Quellen 1935[15][16]) mündeten in Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie (Belgrad 1936).[17] Die letzten Schriften tragen die Früchte seines akademischen Lebens. Nach seinem Rücktritt aus dem universitären Betrieb arbeitete Husserl mit großer Intensität und vollendete mehrere größere Arbeiten. Im April 1933 wurde Husserl – obwohl bereits emeritiert – durch einen Sondererlass des Landes Baden zum Reichsgesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das es erlaubte, sowohl politische Gegner der Nationalsozialisten wie auch jüdische Beamte zu entlassen, beurlaubt, womit ihm jegliche Lehrtätigkeit untersagt wurde. Aufgrund der Widersinnigkeit dieses Beschlusses und der Tatsache, dass Husserl, da sein Sohn an der Front gefallen war, unter das Frontkämpferprivileg fiel, wurde der Beschluss im Juli 1933 revidiert. Allerdings wurde ihm 1936, nach Verschärfung der rassischen Verfolgung mit der Einführung der Nürnberger Rassengesetze, endgültig die Lehrbefugnis entzogen. Sein Kollege Heidegger übernahm am 21. April 1933 den Posten des Rektors an der Universität Freiburg und wurde am 1. Mai 1933 Mitglied der NSDAP. Husserl dagegen trat aus der Deutschen Akademie aus. Nach einem Sturz im Herbst 1937 erkrankte Husserl an einer Brustfellentzündung. Er starb am 27. April 1938 in Freiburg, kurz nach seinem 79. Geburtstag. Seine Frau Malvine überlebte ihn. Eugen Fink, sein wissenschaftlicher Mitarbeiter, hielt seine Grabrede. Als einziger Vertreter der Universität Freiburg besuchte Gerhard Ritter das Begräbnis. Husserl wechselte zu Lebzeiten nicht nur zwischen verschiedenen Studienorten und wissenschaftlichen Disziplinen, sondern auch seine Staatsangehörigkeit und Konfession. Letztere hatte er 1887, kurz vor seiner Eheschließung in Wien, gewechselt. Er ließ sich evangelisch-lutherisch taufen, schloss sich also nicht dem vor Ort dominierenden Katholizismus an, sondern dem als fortschrittlicher geltenden Protestantismus. Damit gehört er zu einer Minderheit der jüdischen Staatsbürger, die zum Christentum übertraten. Wenn ihm auch der Übertritt die wissenschaftliche Karriere erleichterte, konvertierte er doch nicht aus Opportunismus, sondern aus Überzeugung. Vor weiterer Verfolgung durch die Nationalsozialisten bewahrte ihn schließlich sein Tod. Husserl nahm 1896, nachdem er bereits sechzehn Jahre im Deutschen Reich gelebt hatte, die preußische Staatsbürgerschaft an. |
学術研究と教育 1887年、ハビリタチオン(大学での研究・教育能力認定)を経て、フッサールはハレ大学の無給の非常勤講師として大学でのキャリアをスタートさせた。数 学と哲学に関するそれ以前の著作を基に、数学の基礎として心理学的な枠組みを提案した著書『算術の哲学』(1891年)[5]により、フッサールは論理学 者ゴットロープ・フレーゲの批判的な注目を集めた。フロゲの心理主義批判に応える形で、彼は広範な論理的な調査に着手し、それは彼の最初の主要な研究へと 発展し、1901年、42歳のときにゲッティンゲン大学の教授職を得ることとなった。『論理的研究』の第1巻には、「心理主義」を否定する「純粋論理」に 関する考察が含まれている。[6] この著作は好評を博し、とりわけヴィルヘルム・ディルタイのセミナーのテーマとなった。ゲッティンゲン在住中、彼はデイヴィッド・ヒルベルト、レオナル ド・ネルソン、ヴィルヘルム・ディルタイ、マックス・シェーラー、アレクサンドル・コイレ、カール・ヤスパース、そして詩人のフーゴ・フォン・ホフマンス タールなどと個人的に親交を深めた。  ゲッティンゲンのフッサール邸宅(1916年まで) (ヘルマン・フェーゲ通り7番地、ゲッティンゲン記念プレート付き[7]) 1908年、フッサールはかつての師フランツ・ブレンターノをイタリアに訪ねた。1910年には学術誌『ロゴス』の共同編集者となった。この時期、彼は内 的時間意識に関する講義を行い、その講義は10年以上経ってから、かつての教え子であったマルティン・ハイデッガーによって編集され出版された。 1912年、フッサールとその哲学の信奉者たちは『哲学・現象学的研究年報』を創刊し、1913年から1930年にかけて、新しい哲学の方向性を示す論文 を掲載した。例えば、年報の創刊号には、フッサールの影響力のある著作『純粋現象学のためのアイデア』と『現象学的哲学』が掲載されている。 1914年10月、フッサールの息子2人とも徴兵され、第一次世界大戦の西部戦線で戦うことになった。翌年、ヴォルフガング・フッサールは重傷を負った。 1916年3月8日、彼はベルダンの戦場で死亡した。翌年、もう一人の息子ゲルハルト・フッサールも戦場で負傷したが、一命を取り留めた。フッサールの母 ユリアは、その同じ年に死亡した。1917年11月、フッサールの最も優れた学生の一人であり、法哲学者でもあったアドルフ・ライナッハがフランダースで 戦死した。  1916年から1937年までフライブルクにあったフッサール邸宅 1916年、フッサールはフライブルク(ブライスガウ)のアルバート・ルートヴィヒ大学の教授職を引き受け、新カント派のハインリヒ・リッケルトの教授職 を引き継ぎ、哲学研究を続けた。この頃には、ドイツが第一次世界大戦に敗れて不安定な状況にあったにもかかわらず、フッサールはドイツ語圏を代表する哲学 者の一人となり、国内外で多くの学生たちに師事され、その名を知られるようになっていた。エディト・シュタインは、この初期の時期にフッサールの個人秘書 を務めていた。1920年から1923年までは、マルティン・ハイデッガーがその役職を引き継いだ。1922年、フッサールはロンドン大学で現象学的方法 に関する4回の講義を行った。1923年、ベルリン大学から教授職のオファーを受けたが、辞退した。ロンドン、パリ、プラハ、ボストンの大学から名誉博士 号を授与され、ハイデルベルク科学アカデミー、アメリカ芸術科学アカデミー、英国学士院の会員に選出された。1927年、ハイデッガーは著書『存在と時 間』を「感謝と尊敬の念を込めて」フッサールに捧げた。[11] フッサールは定年退職を許されるまでフライブルク大学の教授職にとどまり、1928年7月25日に最後の講義を行った。70歳の誕生日に贈られた記念論文 集は1929年4月8日に手渡された。彼の教え子には、エディト・シュタインや、フライブルクの教授職を引き継いだマルティン・ハイデッガー、技術哲学の ギュンター・シュテルン(アンダース)、人種学・民族学心理学者のルートヴィヒ・フェルディナント・クラウス、そして、哲学者のオイゲン・フィンク、 ディートリヒ・フォン・ヒルデブラント、ルートヴィヒ・ランドグレーベなどがいた。 晩年  フライブルク・ギュンターシュタールの墓地にあるフッサールの墓 引退後も、フッサールは重要な講義をいくつか行った。1929年からのパリ講義は、『デカルト的省察』(パリ、1931年)につながった。 1935年のプラハでの講義[13][14]、および1936年のウィーンでの講義(他の情報源によると1935年[15][16])は、『ヨーロッパ科 学の危機と超越論的現象学』(1936年、ベオグラード)へとつながった。[17] 彼の学術的な人生の成果が最後の著作に結実した。大学での職務から退いた後、フッサールは非常に熱心に研究に取り組み、いくつかの主要な著作を完成させ た。 1933年4月、フッサールはバーデン州の特別法令により、ナチス政権の専門公務員復権法により休職処分となった。この法令は、ナチス政権の政治的反対者 とユダヤ人公務員の解雇を認めるもので、フッサールは教職を禁じられた。この決定の不合理性と、フッサールが前線で息子を亡くしていたため前線で戦う兵士 の特権の対象となったという事実により、1933年7月にこの決定は撤回された。しかし、1936年、ニュルンベルク法の導入による人種迫害の激化によ り、ついに教授資格を剥奪された。同僚のハイデッガーは1933年4月21日にフライブルク大学の学長に就任し、1933年5月1日にはナチス党員となっ た。一方、フッサールはドイツ学士院を辞職した。 1937年秋に転倒したフッサールは、胸膜炎を患った。1938年4月27日、79回目の誕生日を迎えて間もなく、フライブルクで死去した。妻のマル ヴィーネが遺された。研究助手のオイゲン・フィンクが弔辞を述べた。フライブルク大学を代表して葬儀に参列したのはゲルハルト・リッターのみであった。 生涯において、フッサールは研究の場や科学分野を転々としただけでなく、国籍や信仰も変えている。1887年、ウィーンで結婚する直前に、彼は信仰を変え た。プロテスタントのルーテル派に洗礼を受け、地元で主流であったカトリックではなく、より進歩的と考えられていたプロテスタントに改宗した。ユダヤ人市 民の中でキリスト教に改宗した少数派の一人であった。改宗は彼の学術的なキャリアを後押ししたが、日和見主義からではなく、信念から改宗した。結局、ナチ スによるさらなる迫害から彼を救ったのは彼の死であった。1896年、ドイツ帝国に16年間住んだ後、フッサールはプロイセンの市民権を取得した。 |
| Grundlagen der Philosophie Husserls Frühe Philosophie In seinen frühen Arbeiten versucht Husserl, Mathematik, Psychologie und Philosophie zu verbinden mit dem Ziel, eine Grundlegung der Mathematik auszuarbeiten. Er analysiert den psychischen Prozess, der nötig ist, um den Begriff der Zahl zu bilden; daran anknüpfend versucht er, eine systematische Theorie zu entwerfen. Auf diesem Weg greift er auf unterschiedliche Methoden und Konzepte seiner Lehrer zurück. So übernimmt er beispielsweise von Weierstraß die Idee, dass wir den Begriff der Zahl erwerben, indem wir eine bestimmte Sammlung von Objekten zählen. Von Brentano und Stumpf übernimmt er die Unterscheidung zwischen „konkreten“ und „unkonkreten“ Vorstellungen. Husserls Beispiel dafür ist: wenn man vor einem Haus steht, dann hat man eine „konkrete“, „direkte“ Vorstellung dieses Hauses, sucht man es jedoch und fragt nach einer Wegbeschreibung, dann stellt die Wegbeschreibung (z. B. das Haus an der Ecke dieser und jener Straße) eine „unkonkrete“, „indirekte“ Vorstellung dar. Anders gesagt, hat man eine „konkrete“ Vorstellung eines Objektes, wenn es unmittelbar präsent ist, und eine „unkonkrete“ (oder „symbolische“, wie Husserl es auch nennt) Vorstellung, wenn man das Objekt durch Zeichen, Symbole etc. darstellt. Logik ist eine formale Theorie des Urteilens, die die formalen a priori Relationen von Urteilen mit Hilfe von Bedeutungskategorien untersucht. Mathematik ist ihrerseits formale Ontologie. Somit sind die Untersuchungsgegenstände einer Philosophie der Logik und der Mathematik nicht sinnliche Gegenstände, sondern die unterschiedlichen formalen Kategorien der Logik und der Mathematik. Das Problem der psychologischen Herangehensweise an Mathematik und Logik ist, dass sie der Tatsache, dass es um formale Kategorien und nicht einfach um Abstraktionen des Empfindungsvermögens geht, nicht Rechnung trägt. Der Grund, warum wir nicht einfach mit sinnlichen Dingen in der Mathematik arbeiten, ist die „kategoriale Abstraktion“, eine andere Ebene des Verstehens. Auf dieser Ebene können wir sinnliche Komponenten des Urteilens beiseitelassen und uns auf die formalen Kategorien selbst konzentrieren. Husserl kritisiert die Logiker seiner Zeit dafür, diesen Zusammenhang in ihren psychologischen Grundlegungen außer Acht zu lassen. |
フッサール哲学の基礎 初期の哲学 初期の著作において、フッサールは数学の基礎を築くことを目的として、数学、心理学、哲学を統合しようとした。彼は数の概念が形成される精神過程を分析 し、それを基盤として体系的な理論を展開しようとした。その際、彼は師から学んださまざまな方法や概念を活用した。例えば、ワイエルシュトラスの「私たち は特定の物体の集合を数えることで数の概念を習得する」という考え方を採用した。 また、ブレンターノとシュトゥンプからは、「具体的」な観念と「非具体的」な観念の区別を取り入れた。フッサールの例を挙げると、ある家を前にして立って いるときには、その家について「具体的」で「直接的な」考えを持つが、その家を探していて道を尋ねているときには、道順(例えば、○○通りの角にある家) は「非具体的」で「間接的な」考えを表す。言い換えれば、対象が即座に存在している場合には「具体的な」考え方であり、対象を記号やシンボルなどを通して 表現する場合には「非具体的な」(あるいはフッサールが「象徴的」とも呼ぶ)考え方である。 論理学は、意味のカテゴリーを援用して判断の形式的な先験的関係を調査する形式的な判断理論である。数学は形式存在論である。したがって、論理学と数学の 哲学の研究対象は、感覚的な対象ではなく、論理学と数学の異なる形式カテゴリーである。数学と論理学に対する心理学的なアプローチの問題点は、形式カテゴ リーを扱っているのであって、感覚の抽象化を扱っているのではないという事実を考慮に入れていないことである。数学において感覚物自体を扱わない理由は、 「範疇的抽象」という異なるレベルの理解にある。このレベルでは、判断の感覚的要素を脇に置いて、形式的なカテゴリー自体に焦点を当てる。フッサールは、 当時の論理学者たちが心理学的な基礎においてこれを無視していると批判している。 |
| Psychologismuskritik Nachdem Husserl in Mathematik promoviert worden war, analysierte er die Grundlagen der Mathematik von einem psychologischen Standpunkt aus. In seiner Habilitationsschrift Über den Begriff der Zahl (1886) und in seiner Philosophie der Arithmetik (1891) versucht er in Anwendung von Brentanos deskriptiver Psychologie, die natürlichen Zahlen auf eine Art und Weise zu definieren, die die Methoden und Techniken von Karl Weierstraß, Richard Dedekind, Georg Cantor, Gottlob Frege und anderen fortschreibt. Im ersten Teil seiner Logischen Untersuchungen, den Prolegomena der reinen Logik, attackiert Husserl dann jedoch den psychologischen Standpunkt in der Logik und der Mathematik. Folgt man dem Psychologismus, so wäre laut Husserl Logik keine autonome Disziplin, sondern ein Zweig der Psychologie: entweder eine präskriptive und praktische „Art und Weise“ des richtigen Urteilens (eine Position, die Brentano und einige seiner orthodoxeren Studierenden vertraten) oder eine Beschreibung der faktischen Prozesse des menschlichen Denkens. Den Grund dafür, dass die Gegner des Psychologismus den Psychologismus nicht überwinden konnten, sieht Husserl in deren Versäumnis, zwischen der theoretischen, fundamentalen Seite der Logik und der angewandten, praktischen Seite derselben zu unterscheiden. Reine Logik befasse sich überhaupt nicht mit „Gedanken“ oder „Urteilen“ als geistigen Episoden, vielmehr gehe es ihr um Gesetze und Bedingungen a priori jeglicher Theorie und jeglichen Urteils. Anhänger des Psychologismus scheiterten daran, zu zeigen, wie wir die Gewissheit logischer Prinzipien, etwa des Prinzips der Identität und des ausgeschlossenen Widerspruchs, von einem psychologischen Standpunkt aus gewährleisten können. Es sei deshalb sinnlos, logische Gesetze und Grundsätze auf unsichere Prozesse des empirischen Bewusstseins zu stützen. Diese Kritik am Psychologismus, die Unterscheidung zwischen psychischen Akten und intentionalen Objekten und die Differenz zwischen der normativen Seite der Logik und ihrer theoretischen, wird von einer idealen Konzeption der Logik abgeleitet. Das bedeutet, dass logische und mathematische Gesetze unabhängig vom empirischen menschlichen Bewusstsein gelten. |
心理主義への批判 数学の博士号を取得した後、フッサールは心理学的な観点から数学の基礎を分析した。ハビリテーション論文『数の概念について』(1886年)および『算術 哲学』(1891年)において、彼はカール・ワイエルシュトラス、リヒャルト・デデキント、ゲオルク・カントール、ゴットロープ・フレーゲなどの方法と技 術を継承し、ブレンターノの記述心理学を適用して自然数を定義しようと試みた。 『論理的研究』の第一部『純粋論理学のプロレゴメナ』において、フッサールは次に、論理学と数学における心理学的観点に攻撃を仕掛ける。フッサールによれ ば、心理主義に従うのであれば、論理学は自律的な学問ではなく、心理学の一分野となる。すなわち、正しく判断するための規範的かつ実践的な「方法」である (ブレンターノや彼の正統派の弟子たちもこの立場をとっていた)か、あるいは人間の思考の事実上のプロセスを記述するものとなる。フッサールは、心理主義 の反対派が心理主義を克服できなかった理由を、論理の理論的・基礎的な側面と、同じく応用的・実践的な側面とを区別できなかったことにあると見ている。純 粋な論理は、精神のエピソードとしての「思考」や「判断」とはまったく関係がない。むしろ、あらゆる理論や判断に先験的に備わる法則や条件に関係してい る。心理主義の信奉者は、同一律や非矛盾律といった論理原則の確実性を、心理学的観点からどのように保証できるかを示せなかった。したがって、論理法則や 原理を不確かな経験的意識のプロセスに基づいて論じるのは無意味である。 この心理主義批判、心的作用と対象の区別、論理の規範的側面と理論的側面の相違は、論理の理想的な概念から導かれる。つまり、論理的・数学的法則は、経験的な人間の意識とは無関係に成り立つ。 |
| Intentionalität Von Brentano übernimmt Husserl das Konzept der Intentionalität. Intentionalität bedeutet, dass das Bewusstsein sich dadurch auszeichnet, dass es immer auf etwas bezogen ist. Häufig vereinfacht als „Bewusstsein von etwas“ zusammengefasst oder die Beziehung zwischen einem Bewusstseinsakt und der äußeren Welt, definiert Brentano es als Hauptcharakteristikum von geistigen Phänomenen, wodurch er diese von physikalischen Phänomenen unterscheidet. Jeder psychische Akt besitzt einen Inhalt, bezieht sich auf ein Objekt (das intentionale Objekt). Jeder Glaube, Wunsch etc. besitzt ein Objekt, auf das er sich bezieht: das Geglaubte, das Gewünschte. Husserl selbst arbeitet den Begriff erstmals in seiner fünften Logischen Untersuchung in systematischer Art und Weise aus. „Erkenntnis“ ist zwar an psychische und physiologische Prozesse gebunden, sie ist aber nicht mit diesen identisch. Aus einem empirisch psychologischen Satz kann niemals eine logische Norm abgeleitet werden. Empirische Sätze sind bloß wahrscheinlich und können falsifiziert werden. Logik hingegen unterliegt nicht wie die Empirie der Kausalität. Philosophie als Wissenschaft kann sich daher nicht an den Naturalismus binden. Philosophie, Erkenntnistheorie, Logik und reine Mathematik sind Idealwissenschaften, deren Gesetze ideale Wahrheiten a priori ausdrücken. Phänomenologie als „Wesensschau des Gegebenen“ soll die voraussetzungslose Grundlage allen Wissens sein. |
志向性 フッサールはブレンターノから志向性の概念を採用した。志向性とは、意識が常に何かに関連しているという特徴を持つことを意味する。しばしば「何かの意 識」または意識の作用と外部世界との関係として単純化されるが、ブレンターノはそれを精神現象の主な特徴として定義し、それによって精神現象を物理現象と 区別した。あらゆる精神作用には内容があり、対象(志向対象)を指し示す。信念、欲望など、あらゆるものは、それらが指し示す対象、すなわち、信念の対 象、欲望の対象を持っている。フッサール自身がこの概念を初めて体系的に展開したのは、彼の『第五の論理的研究』においてである。 「認識」は心理学的および生理学的プロセスと結びついているが、それらと同一ではない。論理的な規範は、経験的な心理学的命題から導かれることは決してな い。経験的な命題は単に可能性があるだけであり、誤りである可能性もある。一方、論理は経験論のような因果関係の影響を受けない。科学としての哲学は、自 然主義に縛られることはできない。哲学、認識論、論理学、純粋数学は、その法則が理想的な真理を先験的に表現する理想科学である。「与えられたものの本質 の見方」としての現象学は、あらゆる知識の無条件の基礎となるべきものである。 |
| Phänomenologische Reduktion und Epoché Einige Jahre nach der Publikation der Logischen Untersuchungen im Jahr 1900–1901 entwickelte Husserl einige entscheidende begriffliche Differenzierungen. Er war zu der Auffassung gelangt, dass zur Untersuchung der Struktur des Bewusstseins zwischen einem „Akt des Bewusstseins“ und einem „Phänomen, auf welches es sich richtet“ (das Objekt, auf das man sich intentional bezieht) zu unterscheiden sei. Das Wissen um das Wesen wäre durch die „Einklammerung“ aller Vorurteile über die Existenz einer Außenwelt möglich. Das entsprechende methodische Verfahren nennt Husserl Epoché (ἐποχή). Diese neue Auffassung führte zur Publikation der Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie im Jahr 1913 sowie den Plänen für eine zweite Auflage der Logischen Untersuchungen. Seit der Veröffentlichung seiner Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie konzentrierte sich Husserl auf die idealen, wesentlichen Strukturen des Bewusstseins. Dabei war das metaphysische Problem der vom wahrnehmenden Subjekt unabhängigen Wirklichkeit der Gegenstände für ihn von keinem besonderen Interesse, obwohl er einen transzendentalen Idealismus vertrat. Er bezeichnete die Weise, mit der wir als „Menschen des natürlichen Lebens“[18] die natürliche Welt und die uns umgebenden Dinge wahrnehmen, als natürliche Einstellung. Diese sei durch die Annahme gekennzeichnet, dass Objekte außerhalb des wahrnehmenden Subjekts existierten und Eigenschaften besäßen, die wir wahrnehmen: „Ich finde beständig vorhanden als meine Gegenüber die eine räumlich-zeitliche Wirklichkeit, der ich selbst zugehöre, wie alle anderen in ihr vorfindlichen und auf sie in gleicher Weise bezogenen Menschen. Die ‚Wirklichkeit‘, das sagt schon das Wort, finde ich als daseiende vor und nehme sie, wie sie sich mir gibt, auch als daseiende hin. Alle Bezweiflung und Verwerfung von Gegebenheiten der natürlichen Welt ändert nichts an der Generalthesis der natürlichen Einstellung.“[19] Gegenüber der natürlichen Einstellung vollzieht die Phänomenologie nun eine Änderung: Sie schaltet die natürliche Einstellung aus, indem sie „eine gewisse Urteilsenthaltung“[20] übt und die natürliche Welt einklammert. Der Blick richtet sich so auf das transzendentale Ich – und auf seine Bewusstseinsinhalte –, das in vielerlei Hinsicht intentional auf die Objekte gerichtet ist und sie dadurch „konstituiert“.[21] Vom phänomenologischen Standpunkt aus existiert dabei das Objekt nicht einfach „außerhalb“ und gibt auch nicht selbst Hinweise dafür, was es ist, sondern wird zu einem Bündel von wahrnehmbaren und funktionalen Aspekten, die sich gegenseitig unter der Idee eines bestimmten Objekts oder „Typs“ implizieren. Die Realität der Objekte wird von der Phänomenologie nicht abgelehnt, sondern „eingeklammert“ – als eine Weise, wie wir Objekte betrachten, anstelle einer Eigenschaft, die dem Wesen des Objekts innewohnt. Um die Welt der Erscheinungen und der Dinge besser zu verstehen, zielt die Phänomenologie darauf, die invarianten Strukturen unserer Wahrnehmungsweisen zu identifizieren und liefert so Erkenntnis über das leistende Bewusstsein und die Strukturen dieser Leistungen. |
現象学的還元とエポケー 『論理的研究』の出版から数年後の1900年から1901年にかけて、フッサールはいくつかの重要な概念上の区別を展開した。彼は、意識の構造を調査する ためには、「意識の行為」と「それが向けられる現象」(意図的に参照する対象)を区別しなければならないという結論に達した。外部世界の存在に関するあら ゆる偏見を「括弧に入れる」ことで、本質に関する知識が可能になる。フッサールは、この対応する方法論的プロセスをエポケー(ἐποχή)と呼ぶ。この新 しい概念は、1913年の『イデーン:純粋現象学への一般序説』の出版、および『論理的研究』の第2版の計画につながった。 『イデーン:純粋現象学への一般序説』の出版以来、フッサールは意識の理想的な本質的構造に集中した。超越論的観念論を唱えてはいたが、知覚する主体から 独立した対象の実在という形而上学的な問題には、彼は特に興味を示さなかった。彼は、我々「自然生活者」[18]が自然界や身の回りの物自体を自然な態度 で知覚する方法を説明した。これは、対象が知覚する主体の外側に存在し、知覚される性質を持つという前提によって特徴づけられる。 「私は常に、私自身もそこに属し、他の人々と同じようにそこに存在し、それと関連しているひとつの時空の現実を、私の対極として存在しているのを見出す。 私は「現実」という言葉をその意味の通り、存在するものとして見出し、また、存在するものとして私に示されるままにそれを受け入れる。自然界の事実に対す る疑いや拒絶は、自然態の一般的な命題を変えることはない。」[19] 自然態とは対照的に、現象学は今、変化をもたらす。それは「ある種の判断からの棄却」[20]を実践し、自然界を括弧で囲むことによって自然態を排除す る。 焦点は超越論的自我、そしてその意識の内容に置かれる。それは意図的にさまざまな方法で対象に向けられ、それによって「構成」される。 現象学的な観点から見ると、対象は「外側」に単に存在しているわけではなく、それ自体が何であるかについてのヒントを与えるわけでもないが、特定の対象ま たは「タイプ」という概念の下で、相互に暗示し合う知覚可能な機能的側面の束となる。現象学は、物自体の現実性を否定するのではなく、それを「括弧」に入 れる。つまり、物自体の本質に内在する性質ではなく、物を見る方法として捉えるのである。現象学は、現象や物自体の世界をよりよく理解するために、私たち の知覚の不変の構造を特定することを目的としている。それにより、心やその成果の構造に対する洞察が得られる。 |
| Philosophie als strenge Wissenschaft Husserl antwortete auf Diltheys 1911 erschienene Weltanschauungsphilosophie noch im selben Jahr mit dem Aufsatz Philosophie als strenge Wissenschaft.[22] Husserl weist dort zunächst den Naturalismus zurück, da dieser sich nicht selbst über seine erkenntnistheoretischen Voraussetzungen Klarheit verschaffen kann.[23] Dies kann nur eine „wissenschaftliche Wesenserkenntnis des Bewußtseins“ leisten[24] und diese ist die Phänomenologie. Sie ermittelt das, was allen individuellen Bewusstseinsakten gemeinsam ist, nämlich Bewusstsein von… zu sein, d. h., sie meinen ein Gegenständliches.[25] Im Absehen von dem im von… gemeinten ergibt sich das Wesen der Bewusstseinsakte, es lässt sich als „objektive Einheit fixieren“.[26] Die Feststellung objektiv gültiger Tatsachen ist möglich, weil, auch wenn diese historisch Gewordene sind, sie trotzdem absolut gültig sein können – die Genesis beeinträchtigt nicht die Geltung.[27] Als Beispiel eines Systems notwendiger Sätze nennt Husserl die Mathematik, welche für die Beurteilung der Wahrheit ihrer Theorien sich überhaupt nicht an der Historie orientieren kann.[28] „Die ‚Idee‘ der Wissenschaft […] ist eine überzeitliche, […] durch keine Relation auf den Geist einer Zeit begrenzt.“[29] Husserl proklamiert daher gegen die Weltanschauungsphilosophie den „Wille[n] zu strenger Wissenschaft“.[30] |
厳密な科学としての哲学 フッサールは、1911年に発表されたディルタイの世界観の哲学に、同年発表の論文『厳密な科学としての哲学』で応えた。22] その中で、フッサールはまず、自然主義が自身の認識論的前提条件について明確な説明を提供できないとして、それを否定した。 [23] これは「意識の本質に関する科学的知識」によってのみ達成可能であり[24]、これが現象学である。それは、個々の意識の作用に共通するものを決定する。 すなわち、意識の...、すなわち、それらは対象を意味する。[25] ...において意味されるものが存在しない場合、意識の作用の本質が生じ、「客観的な単位として固定」される。[26] 客観的に妥当な事実の決定は可能である。なぜなら、それらが歴史的なものになったとしても、それらは依然として絶対的に妥当であり得るからである。起源は 妥当性に影響を与えない。 必要命題の体系の例として、フッサールは数学を挙げている。数学は、その理論の真偽を評価する上で、歴史をまったく基盤とすることができない。 [28] 「科学の『理念』は[...]超時間的なものであり、[...]時代の精神との関係によって制限されるものではない」[29] したがって、フッサールは世界観の哲学に対して「厳格な科学への意志」を宣言する。[30] |
Das Spätwerk: Krisis der Wissenschaften Das Wohnhaus Husserls in Freiburg von Juli 1937 bis zu seinem Tod am 27. April 1938 In seinem Spätwerk kritisierte Husserl, dass die modernen Wissenschaften mit ihrem Anspruch, die Welt objektivistisch zu erfassen, die Fragen der Menschen nach dem Sinn des Lebens nicht mehr beantworten. Er forderte daher die Wissenschaften auf, sich darauf zu besinnen, dass sie selbst ihre Entstehung der menschlichen Lebenswelt verdanken. Die Lebenswelt, als zentraler Begriff, ist für Husserl die vortheoretische und noch unhinterfragte Welt der natürlichen Einstellung: die Welt, in der wir leben, denken, wirken und schaffen.[31] Husserls transzendentale Phänomenologie versucht, die entstandene Entfremdung zwischen den Menschen und der Welt zu vermindern. |
晩年の作品:科学の危機 1937年7月から1938年4月27日の死まで過ごしたフライブルクのフッサール邸 彼の晩年の著作において、フッサールは、客観的に世界を把握するという主張によって、もはや人々の人生の意味に関する問いに答えられなくなったと近代科学 を批判した。 それゆえ、科学が人間的生活世界にその起源を負っていることを忘れないよう、彼は科学に呼びかけた。フッサールにとって、生活世界 (Lebenswelt)は中心概念であり、自然な態度という理論以前の、未だ疑われることのない世界である。すなわち、私たちが生活し、考え、働き、創 造する世界である。31] フッサールの超越論的現象学は、人と世界との間に生じた疎外を解消しようとするものである。 |
| Ontologie und Metaphysik Husserls Phänomenologie versteht sich zwar als eine Zurückweisung „metaphysische[r] Abenteuer“,[32] keineswegs jedoch als Zurückweisung jeglicher Metaphysik überhaupt.[33] Husserls Auseinandersetzung mit Ontologie und Metaphysik kann in drei Phasen unterteilt werden. In den Logischen Untersuchungen findet sich zunächst eine Neutralität in Hinblick auf die metaphysische Frage, die Husserl hier als „[d]ie Frage nach der Existenz und Natur der ‚Außenwelt‘“.[34] versteht. Er konzentriert sich in diesem Werk allein auf die „Erkenntnistheorie, als allgemeine Aufklärung über das ideale Wesen und über den gültigen Sinn des erkennenden Denkens“.[34] Jene Erkenntnistheorie, die er auch als apriorische Theorie der Gegenstände als solcher begreift, bezeichnet Husserl später rückblickend mit dem „alten Ausdruck Ontologie“.[35] Die zweite Phase findet sich in den Ideen I. Im Ausgang von der Epoché strebt Husserl nun eine Phänomenologie als eidetische und transzendentale Wissenschaft an. Sie umfasst eine universale formale Ontologie sowie regionale, materiale Ontologien. Diese liegen als Wesenswissenschaften sämtlichen Erfahrungs- bzw. Tatsachenwissenschaften zugrunde[36] und stellen eine „unabläßliche Vorbedingung […] für jede Metaphysik und sonstige Philosophie – ‚die als Wissenschaft wird auftreten können‘“,[37] dar. Husserl vertieft dieses neue Verständnis von Ontologie und Metaphysik vor allem in der Vorlesung Erste Philosophie: Als „Erste Philosophie“ gehe voran „eine Wissenschaft von der Totalität der reinen (apriorischen) Prinzipien aller möglichen Erkenntnisse und der Gesamtheit der in diesen systematisch beschlossenen, also rein aus ihnen deduktibeln apriorischen Wahrheiten“[38] deren „Anwendung“ auf „die Gesamtheit der ‚echten‘, d. i. der in rationaler Methode ‚erklärenden‘ Tatsachenwissenschaften“[39] zu einer „‚Zweiten Philosophie‘“[39] hinführe, die Husserl auch als „‚metaphysische‘ Interpretation des ‚Weltall[s]‘“ (letzteres als „das universale Thema der positiven Wissenschaften“) versteht.[40] Die dritte Phase enthält eine Umkehrung des Verhältnisses von ontologischer Möglichkeit und metaphysischer Wirklichkeit: „Aber das Eidos transzendentales Ich ist undenkbar ohne transzendentales Ich als faktisches“.[41] „Alle Wesensnotwendigkeiten sind Momente seines Faktums“.[42] Und allgemeiner: „Wir kommen auf letzte ‚Tatsachen‘ – Urtatsachen, auf letzte Notwendigkeiten, die Urnotwendigkeiten“.[41] Eine Metaphysik der Urtatsachen liegt jetzt einer phänomenologischen Wesenswissenschaft und Ontologie zugrunde, die wiederum die Bestimmungen a priori für die Tatsachenwissenschaften liefert. Im Zuge der Rückbesinnung auf Aristoteles seit Trendelenburg, Brentano und Meinong sowie im Umkreis derjenigen frühen Schüler Husserls, die seiner Hinwendung zum Idealismus kritisch gegenüberstanden, entwickelten sich schon früh Ansätze zu Ontologie und Metaphysik, die realistische, in jedem Falle anti-idealistische Züge tragen. Dies gilt etwa für Adolf Reinach, Hedwig Conrad-Martius, Moritz Geiger, Roman Ingarden, aber auch für Nicolai Hartmann. Husserls Assistenten Ludwig Landgrebe und Eugen Fink arbeiteten wiederum auf je eigene Weise an einer Behandlung metaphysischer Fragen im Ausgang von der Husserl’schen Phänomenologie. In der zeitgenössischen Phänomenologie können Weiterführungen bei László Tengelyi, Alexander Schnell, Jocelyn Benoist, Jean-François Lavigne und Dominique Pradelle gefunden werden. |
存在論と形而上学 フッサールの現象学は「形而上学的冒険」の拒絶として理解されているが[32]、決して形而上学のすべてを完全に拒絶するものではない[33]。フッサールの存在論と形而上学への取り組みは3つの段階に分けられる。 『論理的研究』では、まず第一に、形而上学的な問いに関しての中立性が示されている。ここでフッサールは「『外界』の存在と本質に関する問い」としてこれ を理解している。[34] この著作では、彼は「認識論、すなわち、認識思考の理想的な本質と妥当な意味の一般的な解明」にのみ集中している。[34] フッサールは後に、この認識論について言及し、それを「古い用語の存在論」を振り返りながら、物自体のアプリオリな理論として理解している。[35] 第二段階は『アイデア I』に見られる。エポケーから出発したフッサールは、今や現象学をイデア的かつ超越論的科学として目指している。それは普遍的な形式存在論と地域的、物質 的な存在論を包含している。「本質の科学」として、これらはすべての経験的または事実に基づく科学[36]の基礎となり、「いかなる形而上学やその他の哲 学にも不可欠な前提条件」[37]となる。フッサールは、この存在論と形而上学に関する新たな理解を、主に講義『第一哲学』の中で深めていく。「第一哲 学」は「あらゆる知識の純粋な(先験的)原理の全体性と、それらに体系的に帰結される先験的真理の全体性、つまり、それらから純粋に演繹可能なもの」 [38]に先行するものであるため、この「第一哲学」の「応用」は、「『真正な』全体性、つまり、合理的メソッドにおける『説明』」に 事実科学」[39]を「第二哲学」[39]に適用する。フッサールは、この「第二哲学」を「『世界』の『形而上学的』解釈(後者は『実証科学』の普遍的 テーマ)」と理解している。[40] 第三段階では、存在論的可能性と形而上学的現実の関係が逆転する。「しかし、形而上学的超越的自我は、事実としての超越的自我なしには考えられない」 [41] 「すべての本質的な必要条件は、その事実の瞬間である」[42] さらに一般的に言えば、「究極の『事実』、すなわち究極の必要条件、原初の必要条件に到達する」[41] 本質と存在論の現象学的な科学の根底には、今や、原初的な事実の形而上学が存在し、それが事実の科学に対して先験的な決定を提供する。 トレンデルブルク、ブレンターノ、マイノンの時代以降のアリストテレスへの回帰の過程において、また、フッサールの初期の学生たちで、彼の観念論への転向 に批判的だった人々の間でも、現実的で、いずれにしても反観念論的な特徴を持つ存在論や形而上学へのアプローチが早くから発展していた。これは例えばアド ルフ・ラインハック、ヘドウィグ・コンラート=マルティウス、モーリッツ・ガイガー、ロマン・インガルデン、そしてニコライ・ハルトマンにも当てはまる。 一方、フッサールの助手であったルートヴィヒ・ランドグレーベとオイゲン・フィンクは、それぞれ独自の方法でフッサールの現象学に基づく形而上学的な問題 の考察に取り組んだ。現代現象学においては、ラースロー・テンゲリー、アレクサンダー・シュネル、ジョスリン・ベノワ、ジャン=フランソワ・ラヴィニュ、 ドミニク・プラデルらの研究にさらなる発展が見られる。 |
| Intersubjektivität Den besten Aufschluss über Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität geben die Bände 13–15 der Husserliana (Hua).[43] Diese Editionen zeichnen sich formal dadurch aus, dass sie mit wenigen Ausnahmen auf den sogenannten „Forschungsmanuskripten“ beruhen, die Husserl monologisch nur für sich selbst schrieb, und in denen er nicht Problemlösungen einem Publikum vorlegt, sondern nach solchen sucht. Der erste Band[44] umfasst Haupttexte zur Phänomenologie der Intersubjektivität von 1905 bis 1920, der zweite[45] solche von 1921 bis 1928, und der dritte[46] solche von 1929 bis 1935. Die Aufteilung in drei verschiedene Bände entspricht drei verschiedenen großen Arbeitsphasen von Husserls Ringen um die Konzeption und Darstellung seiner phänomenologischen Philosophie. Hua XIII Der früheste Text,[47] der zum Problem der Intersubjektivität im Nachlass gefunden werden konnte, stammt aus dem Sommer 1905, trägt den von Husserl stammenden Titel „Individualität von Ich und Erlebnissen“ und ist dem Unterschied der erlebenden Individuen gewidmet. Er stammt aus dem Beginn der Zeit, in der Husserl die Idee der phänomenologischen Reduktion als „prinzipiellste aller Methoden“ erarbeitete, und die 1910/11 mit den Vorlesungen „Grundprobleme der Phänomenologie“[48] einen Höhepunkt erreichte. Der Hauptpunkt dieser Vorlesungen bestand in der Überwindung des phänomenologischen Solipsismus, in dem Husserl mit seiner Konzeption der phänomenologischen Reduktion in seinen Vorlesungen „Einführung in die Erkenntnistheorie“ von 1906/07[49] und in der Einleitung seiner Vorlesung „Hauptstücke aus der Phänomenologie und Kritik der Vernunft“ von 1907[50] noch befangen war, durch die Ausdehnung der phänomenologischen Reduktion auf die Intersubjektivität. Konkreter gesprochen bestand er darin, dass er die in der Einfühlung (Fremderfahrung) vergegenwärtigten anderen (fremden) intentionalen Bewusstseinssubjekte mit in das phänomenologische Forschungsfeld einbezog. Begreiflicherweise begann Husserl in den Jahren zwischen 1905 und 1910/11, sich auch mit den damals bekanntesten Theorien der Erkenntnis von fremden Ich auseinanderzusetzen: mit Benno Erdmanns Theorie des Analogieschlusses auf das fremde Ich sowie Theodor Lipps’ Kritik derselben und dessen eigener Theorie der in seiner Ästhetik wurzelnden Lehre der unmittelbaren Einfühlung von Erlebnissen in wahrgenommene äußere Leiber. Beide Theorien hielt Husserl für falsch.[51] Von Lipps übernahm Husserl für die Fremderfahrung das Wort Einfühlung, obschon er dessen Theorie der Einfühlung immer ablehnte und der Auffassung war, dass für die Erfahrung fremder Erlebnisse „Einfühlung ein falscher Ausdruck ist“, da diese Erfahrung durch Vergegenwärtigung sich fremder Erlebnisse bewusst ist und in ihr daher nicht aktuelle eigene eingefühlt (introjiziert) sein können.[52] Doch erst in den Jahren 1914/15 hat Husserl sich mit der Analyse der Einfühlung intensiv beschäftigt und diese Problematik in einer Weise gestaltet, die auch für seine spätere Auseinandersetzung mit ihr während der zwanziger und dreißiger Jahre grundlegend war. Die entsprechende Textgruppe[53] handelt zwar nicht ausschließlich von der Einfühlung (Fremderfahrung), sondern auch von verschiedenen anderen Arten (Weisen) von Vergegenwärtigungen; die Einfühlung ist aber ein durchgängiges Problem. Der dritte dieses sechs Texte trägt den Titel: „Studien über anschauliche Vergegenwärtigungen, [d. h. über] Erinnerungen, Phantasien, Bildvergegenwärtigungen mit besonderer Rücksicht auf die Frage des darin vergegenwärtigten Ich und die Möglichkeit, sich Ich’s vorstellig zu machen“, und Husserl bemerkt in einer späteren Fußnote dazu: „Der Zweck dieser Studien war, für die besondere Weise der Vergegenwärtigung, die Einfühlung heisst, etwas zu lernen.“[54] Dieser Kontext zeigt, dass Husserl das Problem der Erfahrung (Einfühlung) des Anderen (d. h. eines anderen Ich und seiner Erlebnisse) als eine Art von Vergegenwärtigung wie etwa die Erinnerung an eigene Erlebnisse anging, die als eine andere Art von Vergegenwärtigung auch ein Ich und seine Erlebnisse vergegenwärtigt, die nicht unmittelbar gegenwärtig sind. Während aber die in der Erinnerung erinnerten eigenen Erlebnisse vergangene sind und das erinnerte Ich dasselbe ist wie das sich erinnernde, können die in der Einfühlung vergegenwärtigten Erlebnisse zeitlich gegenwärtig sein, und es besteht keine Identität zwischen einfühlendem und eingefühltem Ich. Im ersten Text dieser Gruppe[55] stellt Husserl die Frage: „Wie findet diese Interpretation [eines Körpers außer mir als fremder Mensch] statt?“[56] und antwortet schließlich, nachdem er den, aber ab 1920/21 nicht mehr befriedigenden Ansatz versucht hat, die Möglichkeit eines fremden Ich vor seiner wirklichen Erfahrung zu denken, mit dem für ihn nun immer geltenden Satz: „Hätte ich keinen Leib, wäre mir nicht mein Leib, mein empirisches Ich […] gegeben, so könnte ich also keinen anderen Leib, keinen anderen Menschen ‚sehen’ […] Fremden Leib kann ich nur erfassen in der Interpretation eines dem meinen ähnlichen Leibkörpers als Leibes und damit als Trägers eines Ich (eines dem meinen ähnlichen).“[57] Dieser Satz ist die Grundlage der „Paarung [zwischen fremden Leibkörper und eigenem Leib] als assoziativ konstituierende Komponente der Fremderfahrung“ im § 51 in der fünften der Cartesianischen Meditationen von 1931. Husserl denkt in der Textgruppe von 1914/15 das andere Ich als Analogon des eigenen Ich im Dort, d. h. als Gesichtspunkt auf die Welt, die ich hätte, wenn ich nicht hier, sondern dort wäre.[58] Im Text Nr. 14 aus der Zeit zwischen 1914 und 1917 geht Husserl dem durch die psychophysische Konditionalität bedingten Relativismus der Normalität der Erfahrung nach und erörtert Bedingungen der Möglichkeit der intersubjektiven Objektivität der Natur bis hin zur logisch-mathematischen Objektivität. Er äußert in diesem Zusammenhang wohl zum ersten Mal den Gedanken der Intersubjektivität der Erscheinungen („Aspekte“, Anblicke),[59] die er in der ersten Fassung der Ideen II noch als dem einzelnen Subjekt – der einzelnen Monade – zugehörig betrachtete. Im Text Nr. 15 aus dem September 1918 entwickelt er die Unterscheidung zwischen „gerader Einfühlung“, in welcher der Einfühlende auf die dem eingefühlten Ich erscheinende Umwelt gerichtet ist, und „obliquer Einfühlung“, in welcher der Einfühlende auf die intentionalen Erlebnisse des eingefühlten Ich reflektiert. Im Zentrum des letzten, im Sommer 1920 entstandenen Textes[60] von Hua XIII steht der Unterschied zwischen „uneigentlicher (unanschaulicher) Einfühlung“, die der naturwissenschaftlichen Psychologie, und der „eigentlichen (anschaulichen Einfühlung)“ als „absolut einfühlender Kenntnisnahme“, die den Geisteswissenschaften zugrunde liegt.[61] |
相互主観性 フッサールにおけるintersubjectivity(間主観性)の現象学に関する最も優れた洞察は、HuaのHusserliana(フッサリアナ) 第13巻から第15巻によって提供されている。[43] これらの版は、いくつかの例外を除いて、いわゆる「研究原稿」に基づいており、フッサールが自分自身に対してのみモノローグ形式で書いたものであり、聴衆 に対する問題の解決策を提示するのではなく、その問題を探索しているという点で、形式的に区別されている。第1巻[44]には1905年から1920年ま での間における主観性の現象学に関する主要なテキストが、第2巻[45]には1921年から1928年までの間における主観性の現象学に関する主要なテキ ストが、第3巻[46]には1929年から1935年までの間における主観性の現象学に関する主要なテキストがそれぞれ収録されている。3つの異なる巻に 分かれているのは、フッサールが自身の 現象学哲学の構想と提示に関する彼の研究における3つの主要な段階に対応している。 Hua XIII(フッサリアーナ 13巻) 主観性の問題に関する最も初期のテキスト[47]は、1905年の夏に書かれたもので、タイトルは「私と経験の個別性」(ドイツ語では 「Individualität von Ich und Erlebnissen」)であり、フッサールが選んだもので、経験する個人の間の差異に捧げられている。この論文は、フッサールが「あらゆる方法のなか でも最も根本的なもの」として現象学的還元の考え方を発展させた時期の初期のものであり、1910年から1911年にかけて行われた「現象学の根本問題」 [48]と題された講義で頂点に達した。これらの講義の主な目的は、現象学的還元の概念に依然として囚われていたフッサールが、1906年から1907年 の講義「知識論序説」[49]や、1907年の講義「理性の現象学と批判の主要部分」の序説で 現象学的還元を相互主観性へと拡張することで、1907年の『理性の現象学と批判の主要部分』[50]の序文でも同様の現象学的還元を行った。より具体的 には、共感(他者の経験)によって想起される他者(他者)の意図的意識の主題を、現象学的研究の分野に含めた。当然のことながら、フッサールは1905年 から1910年/11年の間、当時最もよく知られていた他者自我の知識に関する理論の研究を始めた。ベノ・エルドマンの他者自我に関する類推的結論の理 論、そしてテオドール・リップスの それに対する批判、そして自身の美学に根ざした、知覚された他者の身体における直接的な経験の共感の教義に関する自身の理論を探究し始めた。 フッサールによると、両理論とも誤りであった。 [51] リップスから、フッサールは他者の経験を表す「Einfühlung」という語を採用したが、彼は常に「Einfühlung」の理論を否定しており、 「Einfühlung」は他者の経験を表す「不正確な表現」であるという意見を持っていた。なぜなら、この経験は視覚化を通じて他者の経験を認識するも のであり、したがって、現在存在していない自身の経験が「Einfühlt」(内面化)される可能性があるからだ。 しかし、フッサールが共感の分析に集中的に取り組んだのは1914年から1915年にかけてであり、この問題を1920年代と1930年代に彼がそれにつ いて後に行なった調査にも根本的な形で定式化した。対応するテキスト群[53]は、共感(他者の経験)のみに焦点を当てているのではなく、さまざまな他の タイプ(方法)の視覚化についても論じている。しかし、共感は一貫した問題である。これら6つのテキストのうち3つ目のタイトルは、 「絵画的表象についての研究、すなわち、記憶、空想、そこに表現されている自我の問題と自我の存在の可能性を特に考慮した絵画的表象」と題されており、 フッサールは後の脚注で次のように述べている。「これらの研究の目的は、共感と呼ばれる特別な表象の方法について何かを学ぶことだった。」 [54] この文脈から、フッサールが他者(すなわち、もう一つの自我とその経験)を経験(感情移入)するという問題を、自身の経験の記憶のような一種の心的表象と して捉えていたことがわかる。記憶もまた、別の種類の心的表象として、現在に即してはいない自我とその経験を表象する。しかし、記憶の中で想起される経験 は過去の経験であり、想起される自己は想起する自己と同じであるが、共感の中で視覚化される経験は一時的に存在する可能性があり、共感する自己と共感され る自己の間には同一性はない。 このグループの最初の文章[55]で、フッサールは「この解釈(私以外の身体を他者としての人間として解釈すること)はどのようにして行われるのか?」 [56]という問いを投げかけ、最終的に、1920/21年以降はもはや満足のいくものではなくなった、他者としての自己の現実的な経験の前にその可能性 について考えるというアプローチを試みた後、次のような文章で答えを出した。「もし私が身体を持たなければ、私の身体、私の経験的自我は私に与えられない だろうから、私は他の身体、他の人間を『見る』ことはできないだろう。私は、私と似た身体を身体として、そして自我の担い手として(私と似たものとして) 解釈することによってのみ、異物をつかむことができるのだ。」 [57] この文章は、1931年の『デカルト的省察』第5部の§51における「異物に対する経験の連想的に構成的な要素としての結合」の基礎となっている。 1914/15年の文章群において、フッサールは他者の自我を、そこにいる自分の自我の類似体として考えている。つまり、 つまり、私がここにいなくてあそこにいるとしたら持つであろう世界の見方としてである。 1914年から1917年の間に書かれたテキスト第14号において、フッサールは心理物理的条件性によって条件付けられる経験の正常性の相対主義を調査 し、論理数学的客観性までの自然の相互主観的客観性の可能性の条件について論じている。この文脈において、おそらく彼は現象(「側面」、「見解」)の相互 主観性という考えを初めて表現した。この考えは、彼が『イデーン』第2巻の最初のバージョンでは依然として個々の主題、すなわち個々のモナドに属するもの として考えていたものである。1918年9月のテキスト第15号では、共感する人物が共感される自我に見える環境に向かう「ストレートな共感」と、共感す る人物が共感される自我の意図的な経験を振り返る「斜めの共感」の区別を展開している。1920年の夏に書かれた最後の文章の焦点は、科学心理学の基礎で ある「非現実的(非例示的)共感」と、人文科学の基礎である「絶対的共感的知識」としての「現実的(例示的共感)」との違いである。 |
| Hua XIV Aus den zahlreichen Texten, die in Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, Zweiter Teil: 1921–1928 veröffentlicht wurden, seien hier nur vier Themen aus Texten oder Textgruppen hervorgehoben. Im ersten der Texte aus dem Zusammenhang der Vorbereitungen eines „grossen systematischen Werkes“ (1921/22) bringen ihn seine phänomenologischen Analysen zum ersten Mal zur Anerkennung des eingefühlten Ich als radikale Transzendenz gegenüber dem eigenen Ich, obschon es zum transzendental-phänomenologischen Bereich gehört: „Die Einfühlung schafft die erste wahre Transzendenz […] Hier ist ein zweiter Bewusstseinsstrom mitgesetzt, nicht [wie die physischen Dinge] als Sinnbildung meines Stromes, sondern als durch seine Sinnbildung [Konstitution] und Rechtgebung nur indiziert […].“[62] Besondere Beachtung verdienen innerhalb der Textgruppe von 1921/22 die Texte Nr. 9 und 10 und ihre Beilagen, die Husserl unter den Titel „Gemeingeist“ stellte. Diesen Begriff übernimmt Husserl vom Begründer der deutschen Soziologie, Ferdinand Tönnies (1855–1936). Mit ihm wird im Deutschen seit Herder der gemeinsame Geist einer Gemeinschaft bezeichnet. Husserl hat diesen Begriff in dem von ihm mit „Personale Einheiten höherer Ordnung und ihre Wirkungskorrelate“ überschriebenen Text Nr. 10 übernommen; in Text Nr. 9 bezieht er sich namentlich auf Tönnies und sein Werk Gemeinschaft und Gesellschaft.[63] In Text Nr. 10 heißt es: „Es ist also keine blosse Analogie, kein blosses Bild, wenn wir von einem Gemeingeist […] sprechen, ebenso wenig als wenn wir korrelativ von einem Gebilde wie der Sprache sprechen oder der Sitte usw. Eine Fakultät hat Überzeugungen, Wünsche, Willensentschlüsse, sie vollzieht Handlungen, ebenso ein Verein, ein Volk, ein Staat. Und auch von Vermögen, von Charakter, von Gesinnung usw. können wir im strengen, aber entsprechend höherstufigen Sinn reden.“[64] Ebenso wichtig und für Text Nr. 10 grundlegend ist Text Nr. 9, dem Husserl auch den Titel „Gemeingeist“ gab. Hier geht es um die „sozialen Akte“, die Husserl vom bloßen Einfühlen und Verstehen unterscheidet und die er in diesem Text, nur andeutungsweise gesprochen, in Akte des sich an Andere Wendens, ihnen etwas Zeigens, des in der Ich-Du-Beziehung miteinander Sprechens, des miteinander gemeinsam etwas Wollens, etwas Verrichtens, einander Liebens in dessen verschiedenen Weisen (von der sexuellen Liebe bis zur Nächstenliebe) differenziert. In keinen anderen Texten hat Husserl so differenziert von solchen sozialen Akten und entsprechenden Gemeinschaften gesprochen wie in diesen beiden und ihren Beilagen. Im Text Nr. 19 (zwischen 1925 und 1928) wird der Begriff der „Originalität“, der schon in Text Nr. 11 (um 1921) zur Sprache kam, genauer analysiert. Husserl versucht zuerst, auch die Erfahrung von Anderen als originale Erfahrung zu bestimmen, verwirft dann aber diesen Ansatz und unterscheidet schließlich drei verschiedene Begriffe der originalen Erfahrung: 1. die Sphäre der „primordinalen Originalität (Uroriginalität)“,[65] „die originale Erfahrung, die keine Einfühlungsbestände, keine Bestände des fremden Subjekts […] gelten lässt“,[66] 2. die Sphäre der „sekundären Originalität [erste Originarität]“, „die eines jeden Anderen originale Erfahrungssphäre in sich schliesst“,[67] 3. meine „tertiäre originale Erfahrung [= zweite Originarität]“, die mir „Kulturobjekte gibt, die ihrerseits ihre Sinngebung ursprünglich den kultivierenden [fremden] Subjekten verdanken“.[68] In dieser Differenzierung tritt zum ersten Mal der Begriff der „primordinalen Originalität (Uroriginalität)“ auf, den Husserl in seinem Begriff der Primordinalspähre oder Eigenheitsspäre in der fünften Cartesianischen Meditation (Hua I) übernimmt und der grundlegend ist für seinen Begriff der Monade: Die Monade ist nach Husserl identisch mit der Sphäre der primordinalen Originalität oder der Eigenheit. Die Texte (Nr. 20–37) aus dem Zusammenhang des zweiten Teils der Vorlesungen „Einführung in die Phänomenologie“ des WS 1926/27 enthalten die genauesten Reflexionen und phänomenologischen Analysen zum Problem der Fremderfahrung, der „Wahrnehmung eines Menschen“, seit der Textgruppe von 1914/15 in Hua XIII. Die größte Leistung dieser Reflexionen ist ihr Erweis, dass das für die Einfühlung grundlegende unmittelbare Wahrnehmen der Entsprechung zwischen dem mir im äußeren Raum erscheinenden sich bewegenden (sich verhaltenden) fremden und dem mir erscheinenden eigenen Leib, trotz der prinzipiellen Verschiedenheit ihrer visuellen Erscheinungsweisen, durch die konstitutive Rückbeziehung jeder räumlichen Bewegung und Ortsveränderung auf das eigene subjektive „kinästhetische“ Bewegen und Bewegenkönnen ohne Analogisierung „ohne weiteres“[69] verständlich wird.[70] Dieses bloß sinnliche, gegenwärtigende Sehen ist zwar noch kein vergegenwärtigendes „in der Phantasie“ sich Versetzen auf den Gesichtspunkt dieses sich zu seiner räumlichen Umgebung verhaltenden lebendigen Wesens und damit noch kein Verstehen eines anderen Ich, aber dessen notwendige Grundlage. Hua XV Der dritte Teil von Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, Dritter Teil: 1929–1935.[71] umfasst 670 Seiten. Der Text Nr. 35 und seine Beilage XLVIII aus dem September 1933 widmen sich gegenüber den beiden vorangehenden Bänden einem ganz neuen, durch die Problematik der Lebenswelt bedingten sehr reichhaltigen Thema: dem Verhältnis von Heimwelt und fremder Welt, der Zueignung von fremden Welten („Verheimatlichen von Fremde“[72]), dem einander Verstehen als Menschen mit einem Sinneskern von Welt als einem verstandenen „Kern der Unverstandenheiten, die Menschentum und Welt erst konkret machen in ihrer natürlichen Relativität“.[72] Die Beilage endet mit den Sätzen „Wir leben normalerweise […] in einer Umwelt, die für uns […] wirklich vertraute Welt ist […]. Im mittelbaren Horizont sind die fremdartigen Menschheiten und Kulturen; die gehören dazu als fremde und fremdartige, aber Fremdheit besagt Zugänglichkeit in der eigentlichen Unzugänglichkeit im Modus der Unverständlichkeit.“[73] |
Hua XIV(フッサリアーナ 14巻) 『相互主観性の現象学』第2部(1921年~1928年)で発表された多数のテクストの中から、ここでは4つのトピックに絞って取り上げる。 最初のテキストは、「大規模な体系的な作品」の準備(1921/22年)の文脈から抜粋されたもので、彼の現象学的分析は、超越論的現象学の領域に属する ものであるが、共感する自己を初めて根本的な自己超越として認識するに至った。「共感は最初の真の超越を生み出す。[...] ここで、第二の意識の流れが仮定される。それは、[物理的な物自体のように] 私の流れの意味の形成としてではなく、意味の形成[構成]と立法によって示されるものとしてである。[...]」[62] 1921/22年のテクスト群の中で、番号9と10のテクストとそれらの封入物については、フッサールが「ゲマインゲイスト」(共通精神)というタイトル を付けているため、特に注目に値する。フッサールは、この用語をドイツ社会学の創始者であるフェルディナント・トニース(1855-1936)から借用し ている。ドイツ語では、ヘルダー以来、この用語は共同体に共通する精神を表現するために使われてきた。フッサールは「高次個人単位とその相関効果」(テキ スト第10号)と題したテキストでこの用語を採用し、テキスト第9号では、トニースと彼の著書『共同体と社会』(Gemeinschaft und Gesellschaft)に言及している。[63] テキスト第10号には次のように書かれている。「したがって、共通の精神について語る場合、それは単なる類推でも単なるイメージでもない。言語や習慣など の現象について相関的に語る場合と同様である。能力には信念、欲望、意志の決定があり、団体や国民、国家が行うように行動を行う。そして、能力、性格、態 度などについても、厳密ではあるが、より高度な意味で語ることができる。」[64] テキスト第10番にとって同様に重要かつ基本的なテキスト第9番は、フッサールも「共通精神」というタイトルを付けた。 ここでフッサールは、単なる共感や理解から「社会的行為」を区別し、このテキストでは、 ほのめかしているにすぎず、他者に向かう行為、何かを見せる行為、I-Thou関係において互いに語り合う行為、共に何かを望む行為、共に何かを行う行 為、様々な方法で互いに愛し合う行為(性的な愛から隣人愛まで)に区別している。フッサールが、この2つのテクストとその補遺において、これほどまでに多 様な社会的行為やそれに対応する共同体について、これほどまでに詳細に語ったことはない。 テクスト第19号(1925年から1928年の間に執筆)では、テクスト第11号(1921年頃)ですでに登場していた「オリジナリティ」の概念 がさらに 詳しく分析されている。フッサールはまず他者の経験を「原初的オリジナル体験」として定義しようとするが、このアプローチを拒否し、最終的に3つの異なる 「オリジナル体験」の概念を区別する。1.「原初的オリジナル体験(原初的オリジナル体験)」の領域[65]、「共感の蓄え、他者の主題の蓄えを一切許さ ないオリジナル体験」[ [66] 2. 「二次的独創性(第一のオリジナリティ)」の領域。「あらゆる他者の原体験を内包する」[67] 3. 私の「三次的独創性(第二のオリジナリティ)」。「私に文化的対象を与える。それらの文化的対象は、元来、育成する(他者)の主題にその意味を負う」 [68] [68] この区別において、「原初的独創性(原初的独創)」という概念が初めて登場する。これは、フッサールが第五のデカルト的省察( Hua I )における原初的領域または特異性の領域の概念で採用したものであり、彼のモナドの概念の基礎となっている。フッサールによれば、モナドは原初的独創また は特異性の領域と同一である。 1926/27年冬学期の講義「現象学入門」の第二部の文脈におけるテキスト(第20-37番)は、1914/15年のテキスト群(『Hua XIII』)以来、「他者の経験」の問題、すなわち「人間の知覚」に関する最も正確な考察と現象学的分析を含んでいる。これらの考察の最大の功績は、外部 空間において私に見える動く(振る舞う)他者と、私に見える私自身の身体との間の対応関係を直接知覚することが、共感の基礎となるものであり、視覚的な外 見に根本的な違いがあるにもかかわらず、「さらなる説明なしに」理解できることを証明したことである[69]。あらゆる空間的な動きと位置の変化を、自身 の主観的な「 類推の必要もなく、さらなる説明もなしに、自分の主観的な「運動感覚」の動きと移動能力へと帰着する。」[69] この感覚的な表象的な視覚は、空間環境と関わるこの生き物の視点に「想像上」に自分を置く視覚化ではなく、したがって、他者の自我の理解ではなく、しか し、その理解の必要条件である。 Hua XV(フッサリアーナ 15巻) 『相互主観性の現象学』第3部:1929年~1935年[71]の第3部は670ページからなる。これまでの2巻と比較すると、1933年9月のテキスト 第35号とその補遺第48号は、生活世界の諸問題に条件づけられた、まったく新しい広範なテーマに捧げられている。すなわち、内界と外界の関係、他界の獲 得(「他界を内界とする」[72])、 「人間性と世界を自然な相対性の中で具体化する不可解さの核心」として理解される世界観を核として、人間としてお互いを理解することである。[72] 補遺は「私たちは通常、[...]私たちにとって本当に馴染みのある世界である[...]環境の中で暮らしている」という文章で締めくくられている。間接 的な地平線上には、異質な人文科学や文化がある。それらは、異質で異質なものとしてそこに属しているが、異質性は、理解不能という様式において、まさにア クセス不能性の中にアクセス可能性を暗示している。」[73] |
| Phänomenologie des Raumes und der Bewegung (Hua XVI) Husserl hat sich zeitlebens mit der Analyse der Wahrnehmung von räumlichen Gegenständen beschäftigt. Von besonderer Bedeutung ist dabei eine im Sommersemester 1907 gehaltene Vorlesung, die 1973 unter dem Titel Ding und Raum als Band XVI der Husserliana publiziert wurde. Dem Grundgedanken der phänomenologischen Intentionalanalyse entsprechend, steht in Husserls Wahrnehmungsanalysen die „Korrelation von Wahrnehmung und wahrgenommener Dinglichkeit“[74] im Zentrum. Dabei zeigt sich, dass im Bewusstsein des Wahrnehmenden das wahrgenommene Ding immer nur einseitig gegeben ist. Diese „wesentliche Inadäquation jeder vereinzelten äußeren Wahrnehmung“ zeichnet die „Wahrnehmung räumlicher Dinge“ aus.[75] Ihr entspricht die notwendige Verwiesenheit auf weitere mit- und untereinander verbundene Wahrnehmungsmöglichkeiten von demselben Ding. Wahrnehmungsdinge können daher nicht in isolierten Akten des Wahrnehmens erfasst werden, sondern nur in Wahrnehmungsprozessen, die in „Synthesen der Identifikation übergehen“.[76] Husserl vertieft seine Wahrnehmungsanalysen, indem er die Abhängigkeit der Konstitution des Wahrnehmungsgegenstandes von leiblichen Bewegungsphänomenen thematisiert und den Zusammenhang zwischen den Bewegungsempfindungen, den sog. Kinästhesen, und den mit ihnen jeweils verbundenen Erscheinungsabwandlungen untersucht. Die besondere Leistung der Kinästhesen besteht zum einen in der Konstitution identischer, körperlich-voluminöser Gegenstände. Zum anderen konstituiert sich gemäß Husserl (anders als für Kant) in und durch die Erscheinungen der wahrgenommenen Dinge zugleich der Raum unserer Wahrnehmungserfahrung. Auch der Raum wird daher letztlich in den kinästhetischen Wahrnehmungssystemen konstituiert.[77] Im Einzelnen arbeitet Husserl die verschiedenen, für die Konstitution des Dinges und des Raumes notwendigen kinästhetischen Leistungen und Erfahrungen heraus, indem er vom einäugigen zum zweiäugigen Sehen, vom starren Blick zur Augen-, Kopf- und Oberkörperbewegung und schließlich zur freien leiblichen Bewegung des Wahrnehmenden übergeht. Dabei äußert er sich hinsichtlich der Frage, welche Kinästhesen letztlich die Erfahrung der dreidimensionalen körperlich-räumlichen Welt zu Stande bringen, schwankend. Während er im Rahmen von Ding und Raum erwogen hat, dass der Übergang vom einäugigen zum zweiäugigen Sehen bereits mit der Erfahrung räumlicher Tiefe verbunden ist,[78] hat er in späteren Arbeiten die Konstitution räumlicher Tiefe als Leistung des taktuellen Feldes verstanden.[79] In sachlicher Hinsicht dürfte es allerdings wenig sinnvoll sein, die konstitutiven Leistungen der visuellen oder taktuellen Wahrnehmung und der ihnen entsprechenden Kinästhesen gegeneinander auszuspielen. Vielmehr sind das visuelle und das taktuelle Feld nach Husserl eng miteinander verflochten.[80] |
空間と運動の現象学(Hua XVI) フッサールは生涯を通じて、空間的な物体の知覚の分析に懸命に取り組んでいた。この点において特に重要なのは、1907年の夏学期に開かれた講義で、 1973年に『Ding und Raum(物自体と空間)』というタイトルで『フッサリアナ』第16巻として出版された。現象学的志向分析の基本的な考え方に沿って、フッサールの知覚分 析の焦点は「知覚と知覚された物自体の相関関係」にある。[74] それによれば、知覚者の意識において、知覚された物は常に一方的にしか与えられない。この「孤立した外部知覚のすべての本質的な不十分さ」は、「空間的な 物自体の知覚」の特徴である。[75] これは、同じ物自体をさらに相互に連結し、相互に関連する可能性として知覚する際に必要な参照に対応する。したがって知覚されるものは、孤立した知覚行為 では把握できず、「同一化の総合へと融合する」知覚のプロセスにおいてのみ把握できるのである。[76] フッサールは、知覚の対象の構成が身体の運動現象に依存していることを指摘し、運動感覚、いわゆる運動感覚知覚と、それに関連する外観のそれぞれの変化と の関係を検証することで、知覚の分析を深めている。一方、運動感覚知覚の特別な功績は、同一の物理的な容積を持つ物体の構成にある。一方、フッサールによ れば(カントとは異なり)、知覚経験の空間は知覚された物自体の様相によって構成される。したがって、空間も最終的には運動感覚知覚システムによって構成 される。 具体的には、フッサールは、物自体と空間自体の構成に必要なさまざまな運動感覚の達成と経験を、単眼視から両眼視へ、固定した視線から目、頭、上半身の運 動へと移行し、最終的には知覚者の自由な身体運動へと移行することで明らかにする。そうすることで、最終的にどの運動感覚が三次元の物理的空間世界の経験 をもたらすのかという問題に対する不確実性を表現している。彼は『物自体と空間』の文脈において、単眼視から両眼視への移行がすでに空間的奥行きの経験と 結びついているとみなしていたが[78]、後の著作では空間的奥行きの構成を触覚領域の達成として理解していた。 しかし、事実に基づいた観点から見ると、視覚や触覚の知覚の構成上の成果と、それに対応する運動感覚を互いに相殺し合うことはほとんど意味がない。むし ろ、フッサールによれば、視覚と触覚の領域は密接に絡み合っている。 |
| Ethik Husserls ethische Überlegungen lassen sich in drei Phasen einteilen: die frühe Phase einer kognitivistisch orientierten Wertethik, die mittlere Phase einer rationalistischen Willensethik und die Spätphase einer affektiven Liebesethik. Alle diese Phasen sind von den phänomenologischen Begriffen des Wertes und der Person durchzogen. Husserls Ziel in der Ethik ist es, mithilfe seiner phänomenologischen Methode einen Mittelweg zwischen Gefühlsmoral und Verstandesmoral zu ebnen. Dabei soll die Herausarbeitung einer formalen und materialen Rationalität der Gemütsakte des Wertens und Wollens den Subjektivismus und Relativismus der Gefühlsmoral zurückweisen. Gleichzeitig hält Husserl gegen die rationalistische Ignoranz der Rolle der Gefühle an der These fest, dass uns Ethisches letztlich nur in Gemütsakten, d. h. in Akten des Wertens und Wollens zugänglich ist und auch nur darin gründen kann. In den Vorlesungen über Ethik und Wertlehre[81] von 1914 vertritt Husserl einen strengen Parallelismus zwischen Logik und Ethik und spricht gemäß seiner antipsychologistischen Auffassung ethischen Sachverhalten eine Eigenrealität zu. Obwohl er in seinem an Brentano angelehnten kategorischen Imperativ „Tue das Beste unter dem Erreichbaren!“ die Situation des handelnden Subjekts mitberücksichtigt, tut er dies unter der Prämisse, dass es in jeder Situation ein formales und materiales Apriori gibt, das eidetisch zu ermitteln wäre. Diese Haltung, dass jedes beliebige Subjekt „nachrechnen“[82] könnte, was für es zu tun eidetisch richtig wäre, gibt Husserl in seiner späten Ethik auf. Dabei ist es aber nicht so, dass er seine axiologische Theorie und seine Überlegungen zu Vorzugsgesetzen des Wollens als falsch verwerfen würde. Er hält sie bloß nicht mehr für eine Zugangsweise, die der ethischen Erfahrung angemessen wäre. Entscheidend hierfür ist Moritz Geigers Einwand, dass „es lächerlich wäre, an eine Mutter die Forderung zu stellen, sie solle erst erwägen, ob die Förderung ihres Kindes das Beste in ihrem praktischen Bereich sei“.[83] Das Bemühen, die Objektivität von Werten und die Rationalität des Gefühls phänomenologisch auszuweisen, weicht damit der Einsicht, dass eine rein theoretische bzw. metaethische Betrachtung der ethischen Getroffenheit durch einen Ruf nicht gerecht wird und führt zu einer Fokussierung auf das personale und individualisierende Angerufen-Sein durch „Liebeswerte“. Dies prägt die zweite und dritte Phase von Husserls Ethik ab 1918, wobei diese Phasen teilweise ineinandergreifen. Einerseits weisen die „Fünf Aufsätze über Erneuerung“[84] aus 1922–1924 deutliche rationalistische und perfektionistische Züge auf: Die Antwort auf den Anruf ist hier ein sich über das ganze Leben erstreckender Willensentschluss, in ständiger Erneuerung auf das Ziel ethischer Vervollkommnung und „wahrer Menschwerdung“ hinzustreben. Andererseits finden sich in Husserls Nachlass[85] die Motive einer Betonung der Affektivität und Passivität des Gerufen-Seins im „absoluten Sollen“ und die Antwort darauf in der aktiven Liebe („Liebeswert“ und „Liebesgemeinschaft“), sowie neben theologisch-teleologischen auch dunklere Motive wie Schicksal, Tod, Opfer und Entscheidung.[86] |
倫理 フッサールの倫理的考察は、3つの段階に分けることができる。すなわち、認識論的価値倫理の初期段階、合理主義的意志倫理の中間段階、情動的愛の倫理の後 期段階である。これらのすべての段階は、価値と人格に関する現象学の概念によって貫かれている。フッサールの倫理学の目的は、現象学的方法を用いて感情的 な道徳と理性的な道徳の間の中道を切り開くことである。 その際、価値づけと意志づけの感情的な行為の形式的かつ物質的な合理性の精緻化は、感情的な道徳の主観主義と相対主義を拒絶することを目的としている。同 時に、感情の役割に対する合理主義者の無知を前にして、フッサールは、倫理的な問題は最終的には感情の行為、すなわち価値づけと意志づけの行為においての み私たちにアクセス可能であり、それらにのみ根拠づけることができるという命題に固執している。 1914年の倫理学と価値論に関する講義において、フッサールは論理と倫理の厳密な平行性を主張し、反心理主義的な見解に沿って、倫理的諸事実に本質的な 現実性を帰属させた。彼は、ブレンターノによる[カント]「定言命法」の解釈において、行為主体の状況を考慮しているが、それはあらゆる状況において、エ イドス的に決定できる形式的な先験的要素と物質的な先験的要素が存在するという前提に基づいている。彼の倫理に関する後年の著作では、フッサールは、あら ゆる主体が「再計算」[82] できるというこの態度を放棄している。すなわち、主体にとってエイドティックに正しいとされる行為を「再計算」できるというものである。しかし、彼は価値 論的理論や、意志の選択の法則に関する考察を誤りであるとして捨て去ることはしなかった。彼は単に、それらを倫理的経験にふさわしいアプローチとは考えな くなっただけである。この点で重要なのは、モーリッツ・ガイガーが「母親に対して、自分の子どもを育てるのが自分の現実的な領域で最善の行動かどうかをま ず考えるように要求するのは馬鹿げている」と異議を唱えていることである。 83] 価値の客観性と現象学的な感情の合理性を示す努力は、呼びかけの倫理的影響を純粋に理論的または形而上学的考察によって正当に評価することはできないとい う洞察に道を譲り、「愛の価値」によって呼びかけられるという個人的かつ個別化された側面に焦点を当てることになる。これは、1918年以降のフッサール の倫理学の第二段階と第三段階の特徴であるが、これらの段階は部分的に重複している。一方、1922年から1924年にかけて書かれた『刷新についての5 つのエッセイ』[84]には、明確な合理主義的・完璧主義的な特徴が表れている。呼びかけに対する答えは、人生全体にわたる意志の決定であり、倫理的な完 璧さや「真の人間化」という目標に向かって絶え間なく刷新を続ける努力である。一方、フッサールの立場では、「絶対的べき」と呼ばれた存在の情動性と受動 性を強調する動機があり、それに対する積極的な愛(「愛の価値」と「愛の共同体」)による応答、そして神学的・目的論的なものに加えて、運命、死、犠牲、 決断といったより暗い動機がある。 |
| Psychologie und Psychiatrie Die Schnittfelder der Phänomenologie mit der Psychologie und Psychiatrie stellen wohl eines der fruchtbarsten Anwendungsgebiete des von Husserl begründeten Ansatzes dar. Dies gilt insbesondere für die Psychopathologie, die, in der modernen Form von Karl Jaspers begründet, der Phänomenologie bis heute nachhaltige Impulse verdankt. Im deutschen und französischen Sprachraum übten phänomenologisch-anthropologische Konzeptionen im letzten Jahrhundert einen maßgeblichen, zeitweise sogar dominierenden Einfluss auf die Psychiatrie aus, der sich insbesondere mit den auf Heideggers Fundamentalontologie basierenden Ansätzen der „Daseinsanalyse“ verknüpfte. Nach der letzten umfassenden Synopse von Spiegelberg[87] traten phänomenologische Forschungsrichtungen jedoch in den folgenden zwei Jahrzehnten gegenüber den bis heute dominierenden experimentell-biologischen Paradigmen in den Hintergrund. Während sich die akademische Psychologie seither nur noch vereinzelt für phänomenologische Ansätze offen zeigt, ist in der Psychopathologie und Psychiatrie inzwischen wieder eine lebhafte, auch internationale Renaissance der Phänomenologie zu beobachten, die in erster Linie auf die Konzeptionen Husserls und Merleau-Pontys zurückgreift. Husserl selbst hat trotz seiner Ablehnung des Psychologismus in den Logischen Untersuchungen[88] durchaus Ansätze zu einer phänomenologischen Psychologie entwickelt, insbesondere in den gleichnamigen Vorlesungen von 1925, in denen die Konzeption einer solchen Psychologie als „apriorische[r] Wissenschaft vom Seelischen“[89] skizziert und als eine Form „regionaler Ontologie“ von der transzendentalen Phänomenologie unterschieden wird. Während die phänomenologische Psychologie sich auf dem Feld der unmittelbaren Selbst- und Fremderfahrung bewegt, deren Aufbau und Wesenstypik sie mittels der phänomenologischen Reduktion und eidetischen Variation erschließen soll, untersucht die transzendentale Phänomenologie die Konstitution alles in der subjektiven Erfahrung Gegebenen auf dem Boden der transzendentalen (absoluten) Subjektivität[90] – eine Unterscheidung, die später auch für die Psychopathologie bedeutsam wurde, da in bestimmten Formen psychotischer Erfahrung gerade diese basalen Konstitutionsleistungen gestört sind. Allerdings blieb das Projekt unausgeführt und der Beitrag der Phänomenologie zur akademischen Psychologie infolgedessen begrenzt. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich eine lebendige phänomenologische Bewegung in den Niederlanden, vertreten insbesondere durch Frederik Buytendijk, Johannes Linschoten und Jan van den Berg. Reichhaltige Forschungen galten dabei insbesondere der Phänomenologie der menschlichen Situation,[91] etwa in alltäglichen Erfahrungen wie der Begrüßung, dem Autofahren, der sexuellen Begegnung oder dem Einschlafen.[92] Abschließend sei noch auf die für die Zukunft der Forschungsrichtung bedeutsame Frage der phänomenologischen Methode hingewiesen, die sich gerade in der Psychologie gegenüber der dominanten empirisch-experimentellen Orientierung zu behaupten hat. Eine elaborierte Methodik deskriptiver Phänomenologie wurde unter anderem von Giorgi seit den 1960er Jahren an der Duquesne University entwickelt.[93] Basierend auf der phänomenologischen Epoché und eidetischen Variation, soll die subjektive Erfahrung in empathischer Intuition erfasst und so als Basis für weitere qualitative Analysen genutzt werden. Ähnliche Ansätze zur Praxis phänomenologischer Introspektion und Erfahrungsanalyse finden sich heute in der französischen Phänomenologie.[94] Als systematisches Projekt der Untersuchung der Strukturen subjektiver Erfahrung eignete sich die Phänomenologie naturgemäß auch als Grundlagenwissenschaft für die Psychopathologie. Karl Jaspers und Ludwig Binswanger, der über diesen hinausgehend eine phänomenologisch-anthropologische Richtung der Psychiatrie entwickelte, sind hier zu erwähnen. Zu den Hauptvertretern der von Binswanger ausgehenden phänomenologisch-anthropologischen Psychiatrie gehören Erwin Straus, Emil von Gebsattel, Eugen Minkowski, Jürg Zutt, Roland Kuhn, Hubertus Tellenbach, Wolfgang Blankenburg, Bin Kimura und Arthur Tatossian. Phänomenologische Ansätze in Psychologie und Psychiatrie untersuchen die Phänomene, Strukturen und Aufbauelemente der bewussten Erfahrung, insbesondere hinsichtlich Leiblichkeit, Zeitlichkeit, Intentionalität und Intersubjektivität, um so auch ihre Abwandlungen in psychischer Krankheit zu erfassen. Für die Erforschung dieser Erfahrungsschichten stellt die Phänomenologie ein reichhaltiges Instrumentarium zur Verfügung, das von der phänomenologischen Deskription über die Erfassung von eidetischen Typologien bis zur transzendentalen Phänomenologie, zur Konstitutions- und Lebensweltanalyse reicht. Die damit sich bietenden Forschungsmöglichkeiten sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Gerade in den letzten zwei Jahrzehnten ist vielmehr eine internationale Renaissance der besonders an Husserl und Merleau-Ponty orientierten phänomenologischen Psychiatrie zu beobachten, die die Bedeutung der präreflexiven und affektiven Erfahrung, der „passiven Synthesen“ in der Erfahrungskonstitution und nicht zuletzt der transzendentalen Intersubjektivität für das Verständnis psychischer Erkrankungen aufweisen kann.[95] Obgleich sie methodisch nach wie vor jegliche Annahmen zu kausalen Erklärungen einklammert, liefert die Phänomenologie damit einen Rahmen für die Analyse der Subjektivität und ihrer Störungen, die auch zu empirisch testbaren Hypothesen über zugrundeliegende ätiologische Prozesse führen. Die phänomenologisch-anthropologische Psychiatrie versteht sich dabei nicht als eine unbeteiligte Beobachtung von außen. Ihre Analysen der Intersubjektivität schließen auch die Beziehung zwischen Patient und Therapeut ein, und ihre besondere Aufmerksamkeit gilt der Phänomenologie des diagnostischen und therapeutischen Prozesses selbst: etwa den Phänomenen der Intuition, der Zwischenleiblichkeit, des empathischen Verstehens und der existenziellen Begegnung:[96] Damit trägt sie nicht zuletzt auch zur philosophischen Grundlegung der Psychotherapie bei.[97] Vor allem in den Konzepten humanistischer und existenzieller Orientierung wie Gestalttherapie, Gesprächstherapie, Daseins- und Existenzanalyse steht sie vielfach als methodisches Werkzeug im Vordergrund. Nicht zuletzt kann die Phänomenologie heute als die maßgebliche Richtung in den Wissenschaften von der Psyche gelten, die die Wirklichkeit und Bedeutsamkeit von Subjektivität und Intersubjektivität gegenüber reduktionistisch-naturalistischen Ansätzen verteidigt. |
心理学と精神医学 現象学と心理学および精神医学の交差は、おそらくフッサールが創始したアプローチの最も実りある応用分野のひとつである。これは特に精神病理学に当てはま り、カール・ヤスパースによって現代的な形に確立された精神病理学は、今日に至るまで現象学から持続的な刺激を受けている。ドイツ語圏やフランス語圏で は、現象学的人間学の概念は、前世紀の精神医学に決定的な影響を与え、時には支配的な影響力さえも及ぼした。特に、ハイデガーの基本的な存在論に基づく 「存在分析」のアプローチと関連していた。しかし、シュピーゲルバーグによる最新の包括的な概説[87]によると、今日まで支配的な立場を維持している実 験生物学のパラダイムに直面し、現象学的研究の方向性は、その後の20年間で後景へと退いた。それ以来、学術心理学は現象学的なアプローチに対して散発的 にしか門戸を開いてこなかったが、現在では、フッサールやメルロ=ポンティの概念を主に参照する現象学の活気のある国際的なルネサンスが精神病理学や精神 医学の分野で観察されるようになっている。 『論理的研究』において心理主義を否定したにもかかわらず[88]、フッサール自身は現象学心理学へのアプローチを展開し、特に1925年の同名の講義で は、そのような心理学の概念が「魂のアプリオリな科学」[89]として概説され、「局所存在論」の一形態として、 。現象学心理学は自己と他者の直接経験の領域に関わるものであるが、現象学的還元とエイドス的変異によってその構造と本質を明らかにしようとするものであ る。一方、 超越論的現象学は、超越論的(絶対的)主観性に基づいて主観的経験において与えられるあらゆるものの構成を調査する。この区別は、後に精神病理学において も重要となった。なぜなら、精神病的な経験の特定の形式において混乱しているのは、まさにこれらの基本的構成プロセスだからである。しかし、この計画は実 現されることはなく、結果として、学術心理学における現象学の貢献は限定的なものにとどまった。 第二次世界大戦後の時期には、オランダで活発な現象学運動が展開され、特にフレデリック・ブイトェンダイク、ヨハネス・リンショテン、ヤン・ファン・デ ン・ベルクらが代表的な存在であった。特に、人間の状況の現象学に関する広範な研究が行われた。[91] 例えば、挨拶、車の運転、セックス、入眠などの日常的な経験である。 最後に、研究分野の将来にとって重要な現象学的方法の問題について言及しておくべきである。特に心理学では、支配的な経験的・実験的志向に対して、自らを 主張しなければならない。記述的現象学の精巧な方法論は、とりわけジョルジによって、1960年代以降、デュケイン大学で開発されてきた。93] 現象学的エポケーとエイドス的変異に基づいて、主観的経験は共感的直観によって把握され、それによってさらなる質的分析の基礎として用いられる。現象学的 内省と経験分析の実践に対する同様のアプローチは、今日のフランス現象学にも見られる。 主観的経験の構造の調査という体系的なプロジェクトとして、現象学は当然、精神病理学の基礎科学としても適していた。カール・ヤスパースとルートヴィヒ・ ビンスワンガーは、ヤスパースよりもさらに踏み込んで、精神医学における現象学的・人類学的方向性を発展させた。ビンズワンガーに端を発する現象学的・人 類学的精神医学の主な代表者には、エルヴィン・ストラウス、エミール・フォン・ゲプサッテル、オイゲン・ミンコフスキー、ユルク・ズット、ローランド・ クーン、フーベルトゥス・テレンバッハ、ヴォルフガング・ブランケンブルク、ビン・キムラ、アーサー・タトシアンなどがいる。 心理学や精神医学における現象学的アプローチでは、意識経験の現象、構造、要素を、特に身体性、時間性、志向性、相互主観性との関連で調査し、精神疾患に おけるそれらの変化も把握しようとする。これらの経験の層を研究するために、現象学は現象学的記述から、エイドス的類型の記録、超越論的現象学から、構成 と生活世界の分析に至るまで、豊富なツールセットを提供している。これらのツールによって提供される研究の可能性は、まだまだ尽きることはない。それどこ ろか、特にフッサールとメルロ=ポンティに重点を置く現象学的精神医学の国際的なルネサンスが、この20年間で観察されている。それは、精神疾患の理解に とって、前反射的および情動的な経験、経験の構成における「受動的統合」、そしてとりわけ超越論的間主観性の重要性を示すことができる。 因果関係の説明に関する仮定を排除し続けているが、現象学は主観性とその障害を分析する枠組みを提供しており、その枠組みは、根本的な病因プロセスに関す る経験的に検証可能な仮説にもつながっている。現象学的・人類学的精神医学は、外部から関与しない観察者として自分自身を捉えてはいない。その相互主観性 の分析には、患者とセラピストの関係も含まれ、診断および治療プロセス自体の現象学、例えば直観、中間的身体性、共感的理解、実存的遭遇などの現象に特に 注意が払われる。 [97] 現象学は、ゲシュタルト療法、クライエント中心療法、実存分析などの人間中心主義的および実存主義的な志向の概念において、特に方法論的なツールとして顕 著である。 現象学は、還元論的・自然主義的なアプローチに対して主観性および間主観性の現実性と重要性を擁護するものであり、今日の精神科学において最も影響力のあ るアプローチであると考えられる。 |
| Husserls Nachlass Husserl hat zeit seines Lebens im Vergleich mit dem, was er tatsächlich zu Papier brachte, nur wenig veröffentlicht. Seine Buchpublikationen lassen sich an einer Hand abzählen, und darüber hinaus hat er nur wenige kleinere Texte und Aufsätze bzw. Rezensionen veröffentlicht. Husserl schrieb fast jeden Tag eine Art philosophisches Denktagebuch, in Stenographie verfasste Manuskripte, in denen er Ideen ausprobierte oder Gedankengänge verfolgte, die er teilweise später wieder verwarf. Zum Teil ähneln diese Texte einem reinen Gedankenstrom ohne erkennbare Linie oder Argumentationsrichtung. Dennoch gibt es Aussagen von Husserl, vor allem im vorgerückten Alter, dass seine Manuskripte das Wesentliche seiner Philosophie enthalten, insbesondere deshalb, weil seine veröffentlichten Schriften größtenteils einführenden Charakter haben, die Manuskripte hingegen viele Einzelanalysen sowie Entwürfe und Ansätze zu einem systematischen Werk enthalten, das er ab etwa 1922 verfassen wollte, aber nie vollendete. Da Husserl vor allem seit Beginn der Zeit des Nationalsozialismus 1933 einsah, dass er zu einem systematischen Abschluss eines solchen Systems der Phänomenologie nicht mehr kommen würde (ganz abgesehen vom durch die Nationalsozialisten erlassenen Publikationsverbot für Juden), traf er Vorkehrungen, seinen Nachlass systematisch zu ordnen, um ihn als Arbeitsmittel für spätere Generationen von Phänomenologen zu archivieren. Unmittelbarer Anlass, die Ordnung vorzunehmen, war der Wunsch, sie dem Brentano-Archiv in Prag anzubieten; in Verbindung damit hätte er auch für sich und seine Familie Asyl beantragen können. Nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten in Prag wurde auch diese letzte Hoffnung zerstört. Husserl nahm diese Ordnung zusammen mit seinen Assistenten Eugen Fink und Ludwig Landgrebe vor. Die verschiedenen Manuskripte wurden zu Konvoluten geordnet und erhielten eine Archiv-Nummer. Hierbei gab es die Hauptgruppen mit den Buchstaben A bis F, die wiederum teilweise in Untergruppen mit römischen Buchstaben geordnet wurden. Die einzelnen Konvolute in diesen Untergruppen wurden wiederum (v. a. in den Gruppen A, B und E) in arabischen Zahlen gruppiert; z. B. ist Konvolut B I 21 das Konvolut 21 in der Untergruppe B I. Jedes Blatt ist nummeriert als a (recto) und b (verso). Die Konvolute reichen von Manuskripten, die nur wenige Seiten umfassen, bis hin zu mehreren hundert Manuskriptblättern, die zum größten Teil auf Blättern im DIN-A-5-Format abgefasst sind. Natürlich schrieb Husserl auch nachdem er diese Nachlassordnung vorgenommen hatte weiter – die Texte, die nach seinem Tod gesichtet und archiviert wurden, wurden von den nachkommenden Archivaren in die Gruppe K eingeteilt. Die systematische Archivierung wurde später noch weitergeführt, unter Einbezug von Husserls Vorlesungsmitschriften aus seiner Studienzeit sowie seiner Korrespondenz, seiner Bibliothek (sowohl Bücher und Sonderdrucke mit und ohne Annotationen), weiterhin Einlageblättern in Büchern oder Sonderdrucken, sowie schließlich Druckproben, Reinschriften für Publikationen und Arbeiten seiner Assistenten (schriftliche beziehungsweise typographische Abschriften), in denen er zum Teil umfangreiche Anmerkungen anbrachte. Zur Geschichte von Husserls Nachlass (ca. 40.000 Seiten in Gabelsberger Stenographie) gehört schließlich auch dessen Rettung durch den belgischen Franziskanerpater Herman Leo Van Breda. Husserl starb, bevor er seinen Nachlass in Sicherheit bringen konnte. Van Breda, der 1938 in der Hoffnung, Husserl über seine künftige Dissertation zur Phänomenologie befragen und in seinen unveröffentlichten Texten lesen zu können, nach Freiburg kam, fand Husserls verzweifelte Witwe und die archivierten Manuskripte vor. In einer aufregenden Aktion gelang es Van Breda, den Nachlass per Diplomatenpost über Berlin nach Belgien zu bringen, wo er 1939 das Husserl-Archiv gründete.[98] Dort – im Hoger Instituut voor Wijsbegeerte der Katholieke Universiteit Leuven – liegt heute der Nachlass in der Ordnung, wie sie von Husserl und seinen Assistenten vorgenommen wurde. |
フッサールの遺産 彼が実際に紙に書き留めたものに比べると、フッサールは生涯に出版した書籍はごくわずかである。書籍の出版数は片手で数えられるほどであり、それ以外に は、いくつかの短いテキストやエッセイ、あるいは書評を出版しただけである。フッサールはほぼ毎日、速記の原稿に一種の哲学的な日記を書いており、その中 で彼はアイデアを試したり、思考の方向性を追求したりしていたが、そのうちのいくつかは後に却下された。これらの文章は、論証の方向性や流れが明確でない 純粋な意識の流れに似ている部分もある。しかし、フッサールは晩年、特に、自らの哲学のエッセンスは自筆原稿に含まれていると述べた。これは特に、彼の出 版された著作の多くが概論的性格であるのに対し、原稿には多くの個別分析や、1922年頃から書こうとしていたが完成させることのできなかった体系的な著 作の草稿やアプローチが含まれているためである。 フッサールは、特に1933年の国家社会主義の台頭以降、もはや体系的な現象学体系を完成させることはできないと悟った(国家社会主義によるユダヤ人への 出版禁止令は言うまでもない)。そのため、後世の現象学者たちのためのツールとしてアーカイブ化するために、自身の遺産を体系的に整理する対策を講じた。 再編成の直接の理由は、プラハのブレンターノ・アーカイブに提供したいという希望であった。これに関連して、彼自身と家族の亡命を申請することも可能で あった。ナチスによるプラハ侵攻後、この最後の望みも潰えた。 フッサールは、助手のオイゲン・フィンクとルートヴィヒ・ランドグレーベとともに、この作業を組織した。さまざまな原稿は束にまとめられ、アーカイブ番号 が付けられた。主要なグループにはAからFまでのアルファベットが付けられ、さらにその一部はローマ数字でサブグループにまとめられた。これらのサブグ ループ内の個々の束は、さらにアラビア数字でグループ分けされた(主にグループA、B、E)。例えば、束B I 21はサブグループB Iの21番目の束である。各シートには、a(表)とb(裏)の番号が振られている。束は、数ページの原稿から数百ページに及ぶ原稿まであり、そのほとんど はA5サイズの用紙に書かれている。 もちろん、フッサールは自身の財産をこのように整理した後も書き続けた。彼の死後に閲覧され、保存されたテキストは、その後の記録係によってグループKに 分類された。体系的なアーカイブ作業はその後も継続され、学生時代のヒュッセルの講義ノート、書簡、蔵書(注釈付き・なしの両方の書籍および抜き刷り)、 書籍や抜き刷りへの挿入物、そして最終的に校正刷り、出版用原稿、助手による論文(手書きまたはタイプライター打ち)などが含まれた そこには広範な注釈が加えられていた。 フッサールが残した遺産(ガベルスベルガー式速記で書かれた約4万ページ)の歴史には、ベルギーのフランシスコ会士ハーマン・レオ・ファン・ブレダ神父に よる救済も含まれている。フッサールは、自身の遺産を安全な場所に移す前に亡くなった。現象学に関する将来の博士論文についてフッサールに相談し、未発表 の原稿を読みたいと考えて1938年にフライブルクを訪れたヴァン・ブレダは、絶望した未亡人と保管されていた原稿を発見した。大胆な行動に出たヴァン・ ブレダは、遺品を外交郵便としてベルリン経由でベルギーに持ち出すことに成功し、1939年にフッサール文書館を設立した。98] 現在、その遺品はルーヴェン・カトリック大学の高等哲学研究所で、フッサールと彼の助手たちが整理した順番通りに保管されている。 |
| Schriften Husserls Husserliana Husserls Schriften werden für gewöhnlich nach der Husserliana zitiert. Husserliana: Edmund Husserl – Gesammelte Werke (Kritische Edition). Auf Grund des Nachlasses veröffentlicht vom Husserl-Archiv Leuven. Nijhoff, Den Haag, bzw. Dordrecht / Boston / Lancaster, 1950 ff., jetzt: Springer, Berlin 2008: 42 Bände. Hua I: Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. Hrsg. und eingeleitet von Stephan Strasser. Nachdruck der 2., verbesserte Auflage. 1991, ISBN 90-247-0214-3. Hua II: Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen. Hrsg. und eingeleitet von Walter Biemel. Nachdruck der 2., erg. Auflage. 1973, ISBN 90-247-5139-X. Hua III/1 und III/2: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. In: zwei Bänden; 1. Halbband: Text der 1. – 3. Auflage. 2. Halbband: Ergänzende Texte (1912–1929). (Neu hrsg. von Karl Schuhmann. Nachdruck 1976. 1. Halbband: ISBN 90-247-1913-5; 2. Halbband: ISBN 90-247-1914-3) Hua IV: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution. Hrsg. von Marly Biemel. Nachdruck. 1991, ISBN 90-247-0218-6. Hua V: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Drittes Buch: Die Phänomenologie und die Fundamente der Wissenschaften. Hrsg. von Marly Biemel. Nachdruck, ISBN 90-247-0219-4. Hua VI: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Hrsg. von Walter Biemel. Nachdruck der 2., verbesserte Auflage, ISBN 90-247-0221-6. Hua VII: Erste Philosophie (1923/24). Erster Teil: Kritische Ideengeschichte. Hrsg. von Rudolf Boehm. 1956, ISBN 90-247-0223-2. Hua VIII: Erste Philosophie (1923/24). Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Reduktion. Hrsg. von Rudolf Boehm. 1959, ISBN 90-247-0225-9. Hua IX: Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925. Hrsg. von Walter Biemel. 2., verbesserte Auflage. 1968, ISBN 90-247-0226-7. Hua X: Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893–1917). Hrsg. von Rudolf Boehm. Nachdruck der 2., verbesserte Auflage. 1969, ISBN 90-247-0227-5. Hua XI: Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungs- und Forschungsmanuskripten (1918–1926). Hrsg. von Margot Fleischer. 1966, ISBN 90-247-0229-1. Hua XII: Philosophie der Arithmetik. Mit ergänzenden Texten (1890–1901). Hrsg. von Lothar Eley, ISBN 90-247-0230-5. Hua XIII: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil: 1905–1920. Hrsg. von Iso Kern. 1973. ISBN 90-247-5028-8. Hua XIV: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil: 1921–1928. Hrsg. von Iso Kern. 1973, ISBN 90-247-5029-6. Hua XV: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Dritter Teil: 1929–1935. Hrsg. von Iso Kern, ISBN 90-247-5030-X. Hua XVI: Ding und Raum. Vorlesungen 1907. Hrsg. von Ulrich Claesges. 1973, ISBN 90-247-5049-0. Hua XVII: Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft. Mit ergänzenden Texten. Hrsg. von Paul Janssen. 1974, ISBN 90-247-5115-2. Hua XVIII: Logische Untersuchungen. Erster Band: Prolegomena zur reinen Logik. Text der 1. und 2. Auflage. Hrsg. von Elmar Holenstein. 1975, ISBN 90-247-1722-1. Hua XIX/1 und Hua XIX/2: Logische Untersuchungen. Zweiter Band: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. Hrsg. von Ursula Panzer. 1984, ISBN 90-247-2517-8. Hua XX/1: Logische Untersuchungen. Ergänzungsband. Erster Teil. Entwürfe zur Umarbeitung der VI. Untersuchung und zur Vorrede für die Neuauflage der Logischen Untersuchungen (Sommer 1913). Hrsg. von Ullrich Melle. 2002, ISBN 1-4020-0084-7. Hua XX/2: Logische Untersuchungen. Ergänzungsband. Zweiter Teil. Texte für die Neufassung der VI. Untersuchung: Zur Phänomenologie des Ausdrucks und der Erkenntnis (1893/94 – 1921). Hrsg. von Ullrich Melle, 2005, ISBN 1-4020-3573-X. Hua XXI: Studien zur Arithmetik und Geometrie. Texte aus dem Nachlass (1886–1901). Hrsg. von Ingeborg Strohmeyer. 1983, ISBN 90-247-2497-X. Hua XXII: Aufsätze und Rezensionen (1890–1910). Hrsg. von Bernhard Rang. 1979, ISBN 90-247-2035-4. Hua XXIII: Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der anschaulichen Vergegenwärtigungen. Texte aus dem Nachlass (1898–1925). Hrsg. von Eduard Marbach. 1980, ISBN 90-247-2119-9. Hua XXIV: Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie. Vorlesungen 1906/07. Hrsg. von Ullrich Melle. 1984, ISBN 90-247-2947-5. Hua XXV: Aufsätze und Vorträge (1911–1921). Hrsg. von Thomas Nenon und Hans Rainer Sepp. 1987, ISBN 90-247-3216-6. Hua XXVI: Vorlesungen über Bedeutungslehre. Sommersemester 1908. Hrsg. von Ursula Panzer. 1987, ISBN 90-247-3383-9. Hua XXVII: Aufsätze und Vorträge (1922–1937). Hrsg. von Thomas Nenon und Hans Rainer Sepp.1989, ISBN 90-247-3620-X. Hua XXVIII: Vorlesungen über Ethik und Wertlehre (1908–1914). Hrsg. von Ullrich Melle. 1988, ISBN 90-247-3708-7. Hua XXIX: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Ergänzungsband. Texte aus dem Nachlass 1934–1937. Hrsg. von R.N. Smid. 1993, ISBN 0-7923-1307-0. Hua XXX: Logik und allgemeine Wissenschaftstheorie. Vorlesungen Wintersemester 1917/18. Mit ergänzenden Texten aus der ersten Fassung von 1910/11. Hrsg. von Ursula Panzer. 1996, ISBN 0-7923-3731-X. Hua XXXI: Aktive Synthesen. Aus der Vorlesung „Transzendentale Logik“ 1920/21. Ergänzungsband zu „Analysen zur passiven Synthesis“. Hrsg. von Roland Breeur. 2000, ISBN 0-7923-6342-6. Hua XXXII: Natur und Geist. Vorlesungen Sommersemester 1927. Hrsg. von Michael Weiler, 2001, ISBN 0-7923-6714-6. Hua XXXIII: Die Bernauer Manuskripte über das Zeitbewusstsein (1917/18). Hrsg. von Rudolf Bernet und Dieter Lohmar. 2001, ISBN 0-7923-6956-4. Hua XXXIV: Zur phänomenologischen Reduktion. Texte aus dem Nachlass (1926–1935). Hrsg. von Sebastian Luft, 2002, ISBN 1-4020-0744-2. Hua XXXV: Einleitung in die Philosophie. Vorlesungen 1922/23. Hrsg. von Berndt Goossens, 2002, ISBN 1-4020-0080-4. Hua XXXVI: Transzendentaler Idealismus. Texte aus dem Nachlass (1908–1921). Hrsg. von Robin D. Rollinger in Verbindung mit Rochus Sowa, 2003, ISBN 1-4020-1816-9. Hua XXXVII: Einleitung in die Ethik. Vorlesungen Sommersemester 1920 und 1924. Hrsg. von Henning Peucker. 2004, ISBN 1-4020-1994-7. Hua XXXVIII: Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Texte aus dem Nachlass (1893–1912). Hrsg. von Thomas Vongehr und Regula Giuliani. 2004, ISBN 1-4020-3117-3. Hua XXXIX: Die Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution. Texte aus dem Nachlass (1916–1937). Hrsg. von Rochus Sowa. 2008, ISBN 978-1-4020-6476-0. Hua XL: Untersuchungen zur Urteilstheorie. Texte aus dem Nachlass (1893–1918). Hrsg. von Robin D. Rollinger. 2009, ISBN 978-1-4020-6896-6. Hua XLI: Zur Lehre vom Wesen und zur Methode der eidetischen Variation. Texte aus dem Nachlass (1891–1935). Hrsg. von Dirk Fonfara. 2012, xlv + 499 pp. HB, ISBN 978-94-007-2624-6. Hua XLII: Grenzprobleme der Phänomenologie. Analysen des Unbewusstseins und der Instinkte. Metaphysik. Späte Ethik. Texte aus dem Nachlass (1908–1937). Hrsg. von Rochus Sowa und Thomas Vongehr. 2014, ISBN 978-94-007-5813-1. Husserliana: Materialien. Hrsg. von Elisabeth Schuhmann, Michael Weiler und Dieter Lohmar, Dordrecht 2001 ff. Hua Mat I: Logik. Vorlesung 1896. Hrsg. von Elisabeth Schuhmann. 2001, ISBN 0-7923-6911-4. Hua Mat II: Logik. Vorlesung 1902/03. Hrsg. von Elisabeth Schuhmann. 2001, ISBN 0-7923-6912-2. Hua Mat III: Allgemeine Erkenntnistheorie. Vorlesung 1902/03. Hrsg. von Elisabeth Schuhmann. 2001, ISBN 0-7923-6913-0. Hua Mat IV: Natur und Geist. Vorlesungen Sommersemester 1919. Hrsg. von Michael Weiler. 2002, ISBN 1-4020-0404-4. Hua Mat V: Urteilstheorie. Vorlesung 1905. Hrsg. von Elisabeth Schuhmann. 2002, ISBN 1-4020-0928-3. Hua Mat VI: Alte und neue Logik. Vorlesung 1908/09. Hrsg. von Elisabeth Schuhmann. 2003, ISBN 1-4020-1397-3. Hua Mat VII: Einführung in die Phänomenologie der Erkenntnis. Vorlesung 1909. Hrsg. von Elisabeth Schuhmann. 2005, ISBN 1-4020-3306-0. Hua Mat VIII: Späte Texte über Zeitkonstitution (1929–1934): Die C-Manuskripte. Hrsg. von Dieter Lohmar. 2006, ISBN 1-4020-4121-7. Hua Mat IX: Einleitung in die Philosophie. Vorlesungen 1916–1920. Hrsg. von Hanne Jacobs. 2012, ISBN 978-94-007-4657-2. Husserliana: Dokumente. Den Haag/Dordrecht 1977 ff. Hua Dok I: Karl Schuhmann: Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg Edmund Husserls, 1977. Eugen Fink: VI. Cartesianische Meditation. Set ISBN 90-247-3436-3. Hua Dok II/1: Teil I. Die Idee einer transzendentalen Methodenlehre. Texte aus dem Nachlass Eugen Finks (1932) mit Anmerkungen und Beilagen aus dem Nachlass Edmund Husserls (1933/34). Hrsg. von H. Ebeling, J. Holl und G. van Kerckhoven, 1988. Hua Dok II/2: Eugen Fink: Teil II. Ergänzungsband. Hrsg. von G. van Kerckhoven, 1988. Edmund Husserl: Briefwechsel. Hrsg. von Elisabeth Schuhmann in Verbindung mit Karl Schuhmann, Dordrecht 1994 (in zehn Sektionen): Hua Dok III/1: Die Brentanoschule. ISBN 0-7923-2173-1. Hua Dok III/2: Die Münchener Phänomenologen. ISBN 0-7923-2174-X. Hua Dok III/3: Die Göttinger Schule. ISBN 0-7923-2175-8. Hua Dok III/4: Die Freiburger Schüler. ISBN 0-7923-2176-6. Hua Dok III/5: Die Neukantianer. ISBN 0-7923-2177-4. Hua Dok III/6: Philosophenbriefe. ISBN 0-7923-2178-2. Hua Dok III/7: Wissenschaftlerkorrespondenz. ISBN 0-7923-2179-0. Hua Dok III/8: Institutionelle Schreiben. ISBN 0-7923-2180-4. Hua Dok III/9: Familienbriefe. ISBN 0-7923-2181-2. Hua Dok III/10: Einführung und Register. ISBN 0-7923-2182-0. Hua Dok IV: Edmund Husserl: Bibliography. Compiled by Steven Spileers. 1999, ISBN 0-7923-5181-9. Zu Husserls Lebzeiten erschienene Schriften Über den Begriff der Zahl. Psychologische Analysen. (Memento vom 9. April 2014 im Internet Archive) Heynemann, Halle 1887. Philosophie der Arithmetik. Psychologische und logische Untersuchungen. Pfeffer, Halle 1891. Logische Untersuchungen : Band 1, Prolegomena zur reinen Logik. 2., umgearb. Auflage. Niemeyer, Halle 1913. (1. Auflage. 1900) Logische Untersuchungen. Zweiter Teil: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. Niemeyer, Halle 1901. Philosophie als strenge Wissenschaft. 1911. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. Max Niemeyer Verlag, Halle (Saale) 1913. Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Hrsg. von Martin Heidegger, Niemeyer, Halle 1928. Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft, Niemeyer, Halle 1929. Nachwort zu meinen „Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie“. Niemeyer, Halle 1930. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. 1936. Weitere Ausgaben Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie. Hamburg 1992 (= Edmund Husserl, Gesammelte Schriften, hrsg. von Elisabeth Ströker. Band 5). Beiträge zur Theorie der Variationsrechnung. Wien, Univ., Diss.,1882, E-Book der Universitätsbibliothek Wien (eBooks on Demand). Erfahrung und Urteil. Hrsg. v. Ludwig Landgrebe. 7. Auflage. Meiner, Hamburg 1999, ISBN 3-7873-1352-4. Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. Ausgearbeitet und hrsg. von Ludwig Landgrebe, Academia, Prag 1939. V. Logische Untersuchung. Hrsg. v. Elisabeth Ströker. 2. Auflage. Meiner, Hamburg 1988, ISBN 3-7873-0786-9. Cartesianische Meditationen. Hrsg. v. Elisabeth Ströker. 3. Auflage. Meiner, Hamburg 1995, ISBN 3-7873-1241-2 (online) Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. (= Edmund Husserl, Gesammelte Schriften, hrsg. von Elisabeth Ströker. Band 8). 3. Auflage. Meiner, Hamburg 1996, ISBN 3-7873-1297-8. (bzw. Meiner, Hamburg 2012, ISBN 978-3-7873-2259-6) Grundprobleme der Phänomenologie. Hrsg. v. Iso Kern. 2. Auflage. Meiner, Hamburg 1992, ISBN 3-7873-1102-5. Texte zur Phänomenologie des Inneren Zeitbewußtseins (1893–1917). Hrsg. v. Rudolf Bernet. Meiner, Hamburg 1985, ISBN 3-7873-0597-1. Die Konstitution der geistigen Welt. Hrsg. v. Manfred Sommer. Meiner, Hamburg 1984, ISBN 3-7873-0618-8. Die Idee der Phänomenologie. Hrsg. v. Paul Janssen. Meiner, Hamburg 1986, ISBN 3-7873-0685-4. Die Phänomenologie und die Fundamente der Wissenschaften. Hrsg. v. Karl-Heinz Lembeck. Meiner, Hamburg 1986, ISBN 3-7873-0686-2. Ding und Raum. Hrsg. v. Karl-Heinz Hahnengreß und Smail Rapic. Meiner, Hamburg 1991, ISBN 3-7873-1013-4. Phänomenologische Psychologie. Hrsg. v. Dieter Lohmar. Meiner, Hamburg 2003, ISBN 3-7873-1603-5. Philosophie als strenge Wissenschaft. hrsg. von Wilhelm Szilasi. 5. Auflage. Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-465-02888-0. |
フッサールの著作 フッサリアナ フッサールの著作は通常、フッサリアナとして引用される。 フッサリアナ:エドムント・フッサール - 著作集(批判版)。遺産管理団体であるフッサール・アーカイブ(ルーヴェン)より刊行。Nijhoff(ハーグ)、またはDordrecht / Boston / Lancaster(1950年以降)、現在:Springer(ベルリン)2008年:全42巻。 Hua I: Cartesian Meditations and Paris Lectures. 編集および序文:Stephan Strasser。第2版の増補改訂版。1991年、ISBN 90-247-0214-3。 Hua II: 現象学の理念。5つの講義。編者および序文:ウォルター・ビーメル。第2版の増補改訂版。1973年、ISBN 90-247-5139-X。 Hua III/1 and III/2: Ideas of a Pure Phenomenology and Phenomenological Philosophy. First Book: General Introduction to Pure Phenomenology. In two volumes; 1st half-volume: Text of the 1st – 3rd editions. 2nd half-volume: Supplementary texts (1912–1929). (Newly edited by Karl Schuhmann. 1976年再版。前半分:ISBN 90-247-1913-5;後半分:ISBN 90-247-1914-3 Hua IV: Ideas for a Pure Phenomenology and Phenomenological Philosophy. Second Book: Phenomenological Investigations on the Constitution. Ed. by Marly Biemel. 再版。1991年、ISBN 90-247-0218-6。 Hua V: 純粋現象学と現象学的哲学のためのアイデア。第3巻:現象学と科学の基礎。Marly Biemel編。再版、ISBN 90-247-0219-4。 第6巻:ヨーロッパ科学の危機と超越論的現象学。現象学的哲学入門。ウォルター・ビーメル編。第2版改訂版、ISBN 90-247-0221-6の再版。 第7巻:第一哲学(1923/24年)。第1部:思想の批判的歴史。ルドルフ・ベーム編。1956年、ISBN 90-247-0223-2。 Hua VIII: First Philosophy (1923/24)。第2部:現象学的還元論。ルドルフ・ベーム編。1959年、ISBN 90-247-0225-9。 Hua IX: 現象学心理学。1925年夏学期講義。ウォルター・ビーメル編。第2版。1968年、ISBN 90-247-0226-7。 華X:内的時間意識の現象学(1893年~1917年)について。ルドルフ・ベーム編。第2版改訂版の再版。1969年、ISBN 90-247-0227-5。 Hua XI: 受動態の総合分析。講義および研究原稿(1918年~1926年)より。Margot Fleischer編集。1966年、ISBN 90-247-0229-1。 Hua XII: 算術哲学。補足テキスト(1890年~1901年)付き。編集:ローター・エリー、ISBN 90-247-0230-5。 Hua XIII: 間主観性の現象学について。遺稿からのテキスト。第1部:1905年~1920年。編集:イソ・カーン。1973年。ISBN 90-247-5028-8。 Hua XIV: 相互主観性の現象学について。遺稿からのテキスト。第2部:1921年~1928年。編集:Iso Kern。1973年、ISBN 90-247-5029-6。 Hua XV: 相互主観性の現象学について。遺稿からのテキスト。第3部:1929年~1935年。イソ・カーン編、ISBN 90-247-5030-X。 Hua XVI:物自体と空間。1907年の講義。ウルリッヒ・クラーエスゲス編。1973年、ISBN 90-247-5049-0。 Hua XVII: Formal and Transcendental Logic. An Attempt at a Critique of Logical Reason. With supplementary texts. Edited by Paul Janssen. 1974, ISBN 90-247-5115-2. Hua XVIII: Logical Investigations. First volume: Prolegomena to Pure Logic. Text of the 1st and 2nd edition. エルマール・ホーレンシュタイン編。1975年、ISBN 90-247-1722-1。 Hua XIX/1およびHua XIX/2:論理的研究。第2巻:現象学と認識論の研究。ウルスラ・パンザー編。1984年、ISBN 90-247-2517-8。 Hua XX/1: 論理的研究。補遺。第1部。第6研究の改訂と『論理的研究』新装版序文のための草稿(1913年夏)。ウルリッヒ・メレ編。2002年、ISBN 1-4020-0084-7。 Hua XX/2: Logical Investigations. Supplementary volume. Part Two. Texts for the new version of the VI. Investigation: On the Phenomenology of Expression and Cognition (1893/94–1921). Ed. by Ullrich Melle, 2005, ISBN 1-4020-3573-X. Hua XXI: Studies in Arithmetic and Geometry. Texts from the estate (1886–1901). Edited by Ingeborg Strohmeyer. 1983, ISBN 90-247-2497-X. Hua XXII: Essays and Reviews (1890–1910). Edited by Bernhard Rang. 1979, ISBN 90-247-2035-4. Hua XXIII: Imagination, Image Consciousness, Memory. On the Phenomenology of the Visualisations. Texts from the Estate (1898–1925). エドゥアルト・マルバッハ編。1980年、ISBN 90-247-2119-9。 Hua XXIV: 論理学と認識論序説。1906/07年の講義。ウルリッヒ・メレ編。1984年、ISBN 90-247-2947-5。 Hua XXV: Essays and lectures (1911–1921). Edited by Thomas Nenon and Hans Rainer Sepp. 1987, ISBN 90-247-3216-6. Hua XXVI: Lectures on the Theory of Meaning. Summer Semester 1908. Edited by Ursula Panzer. 1987, ISBN 90-247-3383-9. Hua XXVII: Essays and lectures (1922–1937). トーマス・ネノンとハンス・ライナー・ゼップ編。1989年、ISBN 90-247-3620-X。 Hua XXVIII: Lectures on Ethics and the Theory of Values (1908–1914)。ウルリッヒ・メレ編。1988年、ISBN 90-247-3708-7。 Hua XXIX: The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Supplementary volume. Texts from the estate 1934–1937. Edited by R.N. Smid. 1993, ISBN 0-7923-1307-0. Hua XXX: Logik und allgemeine Wissenschaftstheorie. Vorlesungen Wintersemester 1917/18. Mit ergänzenden Texten aus der ersten Fassung von 1910/11. Ed. by Ursula Panzer. 1996, ISBN 0-7923-3731-X. Hua XXXI: Active Syntheses. 1920/21年の講義「超越論的論理学」より。「受動的総合のための分析」の補遺。ローランド・ブルール編。2000年、ISBN 0-7923-6342-6。 Hua XXXII: Nature and Spirit. Lectures summer semester 1927. Edited by Michael Weiler, 2001, ISBN 0-7923-6714-6. Hua XXXIII: The Bernau Manuscripts on Time Consciousness (1917/18). ルドルフ・ベルネットとディーター・ローマー編。2001年、ISBN 0-7923-6956-4。 Hua XXXIV: 現象学的還元について。遺稿からのテキスト(1926年~1935年)。セバスチャン・ルフト編。2002年、ISBN 1-4020-0744-2。 Hua XXXV: 哲学入門。1922/23年の講義。Berndt Goossens編、2002年、ISBN 1-4020-0080-4。 Hua XXXVI: 超越論的観念論。遺稿(1908年~1921年)からのテキスト。Robin D. ロビン・D・ローリンガーとロヒュス・ソワ共編、2003年、ISBN 1-4020-1816-9。 Hua XXXVII: 倫理学序説。1920年および1924年夏学期講義。ヘニング・ペッカー編、2004年、ISBN 1-4020-1994-7。 Hua XXXVIII: Perception and Attention. Texts from the Estate (1893–1912). Edited by Thomas Vongehr and Regula Giuliani. 2004, ISBN 1-4020-3117-3. Hua XXXIX: The Life World. Interpretations of the Given World and its Constitution. Texts from the Estate (1916–1937). ロホス・ソワ編。2008年、ISBN 978-1-4020-6476-0。 Hua XL: 判断理論の研究。遺稿からのテキスト(1893年~1918年)。ロビン・D・ロリンジャー編。2009年、ISBN 978-1-4020-6896-6。 Hua XLI: 本質論および直観的変容の方法について。 未発表テキスト(1891年~1935年)。 ディルク・フォンファラ編。 2012年、xlv + 499ページ。ハードカバー、ISBN 978-94-007-2625-3。 Hua XLII: 現象学の問題。無意識と本能の分析。形而上学。後期倫理学。遺稿からのテキスト(1908年~1937年)。編集:Rochus SowaとThomas Vongehr。2014年、ISBN 978-94-007-5814-8。 Husserliana: Materials. Edited by Elisabeth Schuhmann, Michael Weiler and Dieter Lohmar, Dordrecht 2001 ff. Hua Mat I: Logic. Lecture 1896. Edited by Elisabeth Schuhmann. 2001, ISBN 0-7923-6911-4. Hua Mat II: Logic. 講義1902/03。エリザベス・シュマン編。2001年、ISBN 0-7923-6912-2。 Hua Mat III: 一般知識論。講義1902/03。エリザベス・シュマン編。2001年、ISBN 0-7923-6913-0。 Hua Mat IV: Nature and Spirit. Lectures summer semester 1919. Edited by Michael Weiler. 2002, ISBN 1-4020-0404-4. Hua Mat V: Judgement Theory. 1905年の講義。エリザベート・シュマン編。2002年、ISBN 1-4020-0928-3。 Hua Mat VI: 旧論理学と新論理学。1908/09年の講義。エリザベート・シュマン編。2003年、ISBN 1-4020-1397-3。 Hua Mat VII: 認識現象学序説。講義1909。エリザベート・シュマン編。2005年、ISBN 1-4020-3306-0。 Hua Mat VIII: 晩年の時間論テキスト(1929年~1934年):C-Manuscripts。ディーター・ローマー編。2006年、ISBN 1-4020-4121-7。 Hua Mat IX: 哲学入門。1916年から1920年の講義。ハンネ・ジェイコブス編。2012年、ISBN 978-94-007-4657-2。 Husserliana: Documents. The Hague/Dordrecht 1977 ff. Hua Dok I: Karl Schuhmann: Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg Edmund Husserls, 1977. Eugen Fink: VI. Cartesianische Meditation. Set ISBN 90-247-3436-3. Hua Dok II/1: 第1部。超越論的方法の理念。オイゲン・フィンクの遺産からのテキスト(1932年)に、エドムント・フッサールの遺産からの注釈および添付書類 (1933/34年)を添えて。H. Ebeling、J. Holl、G. van Kerckhoven編、1988年。 Hua Dok II/2: Eugen Fink: Part II. Supplementary volume. Ed. by G. van Kerckhoven, 1988. Edmund Husserl: Correspondence. Ed. by Elisabeth Schuhmann in conjunction with Karl Schuhmann, Dordrecht 1994 (in ten sections): Hua Dok III/1: ブレンターノ学派。ISBN 0-7923-2173-1。 Hua Dok III/2: ミュンヘンの現象学者たち。ISBN 0-7923-2174-X。 Hua Dok III/3: ゲッティンゲン学派。ISBN 0-7923-2175-8。 Hua Dok III/4: フライブルク学派。ISBN 0-7923-2176-6. Hua Dok III/5: 新カント派。ISBN 0-7923-2177-4. Hua Dok III/6: 哲学者の手紙。ISBN 0-7923-2178-2. Hua Dok III/7: 科学者の書簡。ISBN 0-7923-2179-0。 Hua Dok III/8: 組織の文書。ISBN 0-7923-2180-4。 Hua Dok III/9: 家族書簡。ISBN 0-7923-2181-2。 Hua Dok III/10: 序文と登録。ISBN 0-7923-2182-0。 Hua Dok IV: エドムンド・フッサール:書誌。スティーブン・スパイラー編。1999年、ISBN 0-7923-5181-9。 フッサール存命中に出版された著作 『数概念について』。心理学的分析。(2014年4月9日のインターネットアーカイブにおけるメモ)Heynemann、ハレ1887年。 『算術の哲学』。心理学的および論理的研究。Pfeffer、ハレ1891年。 論理的研究:第1巻、純粋論理学へのプロレゴメナ。第2版。ニーメイヤー、ハレ 1913年。(初版。1900年) 論理的研究。第2部:現象学と知識論の研究。ニーメイヤー、ハレ 1901年。 厳格な科学としての哲学。1911年。 純粋現象学と現象学的哲学に関する諸概念。第1部:純粋現象学への一般序説。マックス・ニーメイヤー出版、ハレ(ザーレ)1913年。 内なる時間意識の現象学に関する講義。編集:マルティン・ハイデッガー、ニーメイヤー、ハレ1928年。 形式と超越論的論理学。論理的推論の批判的考察の試み、ニーメイヤー、ハレ、1929年。 私の「純粋現象学と現象学的哲学のためのアイデア」への追記。ニーメイヤー、ハレ、1930年。 ヨーロッパの科学の危機と超越論的現象学。現象学的哲学への序説。1936年。 その他の版 『イデーン:純粋現象学と現象学的哲学への一般序説』ハンブルク、1992年(エドムント・フッサール全集、エリザベート・シュトローカー編、第5巻)。 『変分学の理論への貢献』ウィーン大学、1882年、ウィーン大学図書館電子書籍(オンデマンド電子書籍)。 経験と判断。編者:ルートヴィヒ・ラントグレーベ。第7版。マイネル、ハンブルク1999年、ISBN 3-7873-1352-4。 経験と判断。論理学の系譜学的研究。編者:ルートヴィヒ・ラントグレーベ、アカデミア、プラハ1939年。 V. 論理的な調査。ドナルド・A・クレス訳。第2版。マイネル、ハンブルク、1988年、ISBN 3-7873-0786-9。 デカルト的省察。ドナルド・A・クレス訳。第3版。マイネル、ハンブルク、1995年、ISBN 3-7873-1241-2(オンライン) 『ヨーロッパ科学の危機と超越論的現象学』。(エドムント・フッサール著、エリザベート・シュトレーカー編。第8巻)。第3版。Meiner、ハンブルク 1996年、ISBN 3-7873-1297-8。(またはMeiner、ハンブルク2012年、ISBN 978-3-7873-2259-6) 現象学の根本問題。Iso Kern編。第2版。マイネル、ハンブルク 1992年、ISBN 3-7873-1102-5。 内面的時間意識の現象学に関するテキスト(1893年~1917年)。 ルドルフ・ベルネット編。マイネル、ハンブルク 1985年、ISBN 3-7873-0597-1。 精神世界の憲法。マンフレッド・ゾマー編。マイネル、ハンブルク、1984年、ISBN 3-7873-0618-8。 現象学の理念。ポール・ヤンセン編。マイネル、ハンブルク、1986年、ISBN 3-7873-0685-4。 現象学と科学の基礎。編集:カール・ハインツ・レンベック。マイネル、ハンブルク、1986年、ISBN 3-7873-0686-2。 物自体と空間。編集:カール・ハインツ・ハーネングレスとスメール・ラピック。マイネル、ハンブルク、1991年、ISBN 3-7873-1013-4。 現象学心理学。ディーター・ローマー編。マイネル、ハンブルク、2003年、ISBN 3-7873-1603-5。 厳格な科学としての哲学。ヴィルヘルム・シラシ編。第5版。フランクフルト・アム・マイン、1996年、ISBN 3-465-02888-0。 |
| Literatur Zu Husserl Javier Yusef Álvarez-Vázquez: Frühentwicklungsgeschichte der phänomenologischen Reduktion: Untersuchungen zur erkenntnistheoretischen Phänomenologie Edmund Husserls. FreiDok, Freiburg 2010, urn:nbn:de:bsz:25-opus-74421, 250 pp. (e-Book: PDF). Edmund Husserl und die phänomenologische Bewegung. Zeugnisse in Text und Bild. Im Auftrag des Husserl-Archivs Freiburg im Breisgau herausgegeben von Hans Rainer Sepp. Alber, Freiburg / München 1988, ISBN 3-495-47636-9. David Bell: Husserl. Routledge, London 1990, ISBN 0-415-03300-4. Rudolf Bernet, Iso Kern, Eduard Marbach: Edmund Husserl. Darstellung seines Denkens. Felix Meiner, Hamburg 1989, ISBN 3-7873-1284-6. Christian Beyer u. a. (Hrsg.): Husserl’s Phenomenology of Intersubjectivity. Routledge, London 2020, ISBN 978-0-367-73216-5. Alwin Diemer: Edmund Husserl. Versuch einer systematischen Darstellung seiner Philosophie. 2., verbesserte Auflage. Hain, Meisenheim am Glan 1965. Eugen Fink: VI. Cartesianische Meditation. Teil 1: Die Idee einer transzendentalen Methodenlehre. Texte aus dem Nachlass Eugen Finks (1932) mit Anmerkungen und Beilagen aus dem Nachlass Edmund Husserls (1933/34). In: Hans Ebeling, Jann Holl und Guy van Kerckhoven (Hrsg.): Husserliana, Dokumente Band II/1 (Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1988). Christel Fricke u. a. (Hrsg.): Intersubjectivity and Objectivity in Adam Smith and Edmund Husserl. Frankfurt / Paris / Lancaster / New Brunswick 2012. Thomas Fuchs: Phenomenology and Psychopathology. In: S. Gallagher, D. Schmicking (Hrsg.): Handbook of phenomenology and the cognitive sciences. Springer, Dordrecht 2010, S. 547–573. Hans-Helmuth Gander (Hrsg.): Husserl-Lexikon. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2009, ISBN 978-3-534-16493-6. Klaus Held (Hrsg.): Edmund Husserl. Ausgewählte Texte. 1. Die phänomenologische Methode. ISBN 3-15-008084-3. 2. Phänomenologie der Lebenswelt. ISBN 3-15-008085-1. Gisbert Hoffmann: Bewusstsein, Reflexion und Ich bei Husserl. Karl Alber Verlag, Freiburg/München 2001, ISBN 3-495-48050-1. Husserl. (= Philosophie Jetzt!). Ausgewählt und vorgestellt von Uwe C. Steiner. Hrsg.: Peter Sloterdijk. Diederichs, München 1997, ISBN 3-424-01290-4. Julia V. Iribarne: Husserls Theorie der Intersubjektivität. Alber, Freiburg / München 1994. Paul Janssen: Edmund Husserl. Einführung in seine Phänomenologie. Koleg Philosophie. Karl Alber, Freiburg / München 1976, ISBN 3-495-47247-9. Edda Kapsch: Verstehen des Anderen. Fremdverstehen im Anschluss an Husserl, Gadamer und Derrida. Parodos, Berlin 2007, ISBN 978-3-938880-11-1. Iso Kern: Fremderfahrung. In: Bernet, Kern, Marbach (Hrsg.): Edmund Husserl. Darstellung seines Denkens. 2. Auflage. Meiner, Hamburg, 1996, S. 143–153. Matis Kronschläger: Die Einigung der Lebenswelt(en) nach Husserl. Universität Wien, Diplomarbeit, 2012. (Digitalisat) Sebastian Luft: Die Archivierung des Husserlschen Nachlasses 1933–1935. In: Husserl Studies. Band 20, S. 1–23. Utz Maas: Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger Sprachforscher 1933–1945. Eintrag zu Edmund Husserl (abgerufen: 13. April 2018) Verena Mayer: Edmund Husserl: Logische Untersuchungen. Akademie Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-05-004391-3. Verena Mayer: Edmund Husserl. C. H. Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-58688-0. Karl Mertens: Zwischen Letztbegründung und Skepsis. Kritische Untersuchungen zum Selbstverständnis der transzendentalen Phänomenologie Edmund Husserls. (= Orbis Phaenomenologicus. VI. 1). Alber, Freiburg / München 1996, ISBN 3-495-47818-3. Wolfgang Hermann Müller: Die Philosophie Edmund Husserls nach den Grundzügen ihrer Entstehung und ihrem systematischen Gehalt. Bouvier, Bonn 1956. Dominique Pradelle: Généalogie de la raison. Essai sur l’historicité du sujet transcendantal de Kant à Heidegger. Paris 2013. Dominique Pradelle: Par-delà la révolution copernicienne. Sujet transcendantal et facultés chez Kant et Husserl. Paris 2012. Peter Prechtl: Edmund Husserl zur Einführung. 5. Auflage. Junius, Hamburg 2012, ISBN 978-3-88506-369-8. Bernhard Rang: Husserls Phänomenologie der materiellen Natur. Klostermann, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-465-02217-3. Adolf Reinach: Was ist Phänomenologie? München 1951. R. D. Rollinger: Husserl's Position in the School of Brentano (Phaenomenologica 150). Kluwer, Dordrecht 1999, ISBN 0-7923-5684-5. Christian Rother: Der Ort der Bedeutung. Zur Metaphorizität des Verhältnisses von Bewußtsein und Gegenständlichkeit in der Phänomenologie Edmund Husserls. Dr. Kovac, Hamburg 2005, ISBN 3-8300-1801-0. Leonardo Scarfò: Philosophie als Wissenschaft reiner Idealitäten. Zur Spätphilosophie Husserls in besonderer Berücksichtigung der Beilage III zur Krisis-Schrift. Herbert Utz, München 2006, ISBN 3-8316-0649-8. Alexander Schnell: Temps et phénomène. La phénoménologie husserlienne du temps. Olms, Braunschweig 2004. Alexander Schnell: Husserl et les fondements de la phénoménologie constructive. Millon, 2007. Karl Schuhmann: Husserl – Chronik (Denk- und Lebensweg Edmund Husserls) Number I in Husserliana Dokumente. Nijhoff, Den Haag 1977, ISBN 90-247-1972-0. Karl Schuhmann: Husserl and Masaryk. In: Josef Novak (Hrsg.): On Masaryk. Texts in English and German. Amsterdam 1988, S. 129–156. Josef Seifert: Die Bedeutung von Husserls Logischen Untersuchungen für die Realistische Phänomenologie – Und die Kritik Realistischer Phänomenologen an einigen Husserl’schen Thesen. In: AEMAET. 4, 2015, S. 28–119. ISSN 2195-173X Barry Smith, David Woodruff Smith (Hrsg.): The Cambridge Companion to Husserl. Cambridge University Press, Cambridge 1995, ISBN 0-521-43616-8. Thorsten Streubel: Das Wesen der Zeit. Zeit und Bewußtsein bei Augustinus, Kant und Husserl. Würzburg 2006. Elisabeth Ströker: Husserls transzendentale Phänomenologie. Klostermann, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-465-01773-0. Herman Leo van Breda: Die Rettung von Husserls Nachlass und die Gründung des Husserl-Archivs. In: Husserl-Archiv Leuven (Hrsg.): History of the Husserl-Archives Leuven. Springer, Heidelberg 2007, ISBN 978-1-4020-5726-7, S. 1–37. Dan Zahavi: Husserl und die transzendentale Intersubjektivität. Kluwer, 1996. Dan Zahavi: Husserls Phänomenologie. UTB, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8252-3239-9. Philosophisches Denken in Halle. Abt. 3, Philosophen des 20. Jahrhunderts, Band 2., Beförderer der Logik / Georg Cantor, Heinrich Behmann und Edmund Husserl bearb. von Günter Schenk, 1. Auflage. 2002 Weiterführendes Jocelyn Benoist: Elemente einer realistischen Philosophie: Reflexion über das, was man hat. Aus dem Franz. v. David Espinet. Suhrkamp, Berlin 2014, ISBN 978-3-518-29700-1. Ludwig Binswanger: Über Ideenflucht. Orell Füssli, Zürich 1933. Ludwig Binswanger: Daseinsanalytik und Psychiatrie. In: Ausgewählte Vorträge und Aufsätze. (Band II). Francke, Bern 1955, S. 279–302. Ludwig Binswanger: Drei Formen missglückten Daseins: Verstiegenheit, Verschrobenheit, Manieriertheit. de Gruyter, Berlin 1956. Ludwig Binswanger: Schizophrenie. Neske, Pfullingen 1957. Ludwig Binswanger: Melancholie und Manie. Neske, Pfullingen 1960. Ludwig Binswanger: Wahn: Beiträge zu seiner phaenomenologischen und daseinsanalytischen Erforschung. Neske, Pfullingen 1965. Wolfgang Blankenburg: Ansätze zu einer Psychopathologie des „common sense“. In: Con-finia Psychiatrica. 12, 1969, S. 144–163. Wolfgang Blankenburg: Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit. Ein Beitrag zur Psychopathologie symptomarmer Schizophrenien. Enke, Stuttgart 1971. Frederik J.J. Buytendijk: Über den Schmerz. Huber, Bern 1948. Frederik J.J. Buytendijk: Phänomenologie der Begegnung. In: Eranos Jahrbuch. 19, 1951, S. 431–486. Frederik J.J. Buytendijk: Die Frau: Natur, Erscheinung, Dasein. Bachem, Köln 1953. Frederik J.J. Buytendijk: Allgemeine Theorie der menschlichen Haltung und Bewegung. Springer, Berlin 1956. Gary B. Cohen: Education and Middle-Class Society in Imperial Austria, 1848–1918. West Lafayette IN 1996. Hedwig Conrad-Martius: Vorwort. In: Adolf Reinach (Hrsg.): Was ist Phänomenologie? München 1951, S. 5–17. Gerhard Dammann (Hrsg.): Phänomenologie und psychotherapeutische Psychiatrie. Kohlhammer, Stuttgart 2014. Ulrich Dopatka: Phänomenologie der absoluten Subjektivität. Eine Untersuchung zur präreflexiven Bewusstseinsstruktur im Ausgang von Edmund Husserl, Jean-Paul Sartre, Michel Henry und Jean-Luc Marion. Fink Verlag, 2019. Thomas Fuchs: Pathologies of intersubjectivity in autism and schizophrenia. In: Journal of Consciousness Studies. 22, 2015, S. 191–214. Thomas Fuchs u. a. (Hrsg.): Karl Jaspers: Phenomenology and Psychopathology. Springer, Berlin / Heidelberg / New York 2013. Moritz Geiger: Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik. Bonn 1930. Amedeo Giorgi: Psychology as a Human Science. Harper & Row, New York 1970. Amedeo Giorgi: The Descriptive Phenomenological Method in Psychology. Duquesne University Press, Pittsburgh PA 2009. Carl Friedrich Graumann: Phänomenologische Psychologie. In: R. Asanger, G. Wenninger (Hrsg.): Handwörterbuch der Psychologie. 5. Auflage. Psychologie Verlags Union, Weinheim 1994. Carl Friedrich Graumann: Grundlagen einer Phänomenologie und Psychologie der Per-spektivität. de Gruyter, Berlin 1960. Nicolai Hartmann: Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis. Berlin / Leipzig 1921. Nicolai Hartmann: Neue Wege der Ontologie. 3. Auflage. Stuttgart 1949. Alice Holzhey-Kunz: Daseinsanalyse. In: A. Längle, A. Holzhey-Kunz (Hrsg.): Existenzanalyse und Daseinsanalyse. Facultas, Wien 2008, S. 181–348. Roman Ingarden: Der Streit um die Existenz der Welt. I: Existentialontologie. Tübingen 1964. Karl Jaspers: Allgemeine Psychopathologie. 9. Auflage. Springer, Berlin / Heidelberg / New York 1913/1973. David Katz: Der Aufbau der Farbwelt. Barth, Leipzig 1930. David Katz: Gestaltpsychologie. Schwabe, Basel 1944. Joseph J. Kockelmans (Hrsg.): Phenomenological Psychology: The Dutch school. Kluwer, Dordrecht 1987. Kurt Koffka: The Principles of Gestalt Psychology. Harcourt, New York 1935. Wolfgang Köhler: Gestalt Psychology. Bell, London 1929. Hans Köchler: Die Subjekt-Objekt-Dialektik in der transzendentalen Phänomenologie: Das Seinsproblem zwischen Idealismus und Realismus. Anton Hain, Meisenheim a. G., 1974. Hans Köchler: Phenomenological Realism. Peter Lang, Frankfurt am Main / Bern / New York 1986. Alfred Kraus: Sozialverhalten und Psychose Manisch-Depressiver. Enke, Stuttgart 1977. Lenelis Kruse u. a. (Hrsg.): Ökologische Psychologie. Psychologie Verlagsunion, München 1990. Roland Kuhn: Daseinsanalyse und Psychiatrie. In: H. W. Gruhle u. a. (Hrsg.): Psychiatrie der Gegenwart. (I/2), Springer, Berlin / Göttingen / Heidelberg 1963, S. 833–902. Ludwig Landgrebe: Faktizität als Grenze der Reflexion und die Frage des Glaubens. In: Ders. (Hrsg.): Faktizität und Individuation. Studien zu den Grundfragen der Phänomenologie. Hamburg 1976, S. 117–136. Ludwig Landgrebe: Phänomenologie und Metaphysik. Hamburg 1949. Jan Huygen van Linschoten: Über das Einschlafen. In: Psychologische Beiträge. 2, 1955, S. 70–97 sowie Einschlafen und Tun. vgl. Linschoten 1955, S. 266–298. Jan Huygen van Linschoten: Auf dem Wege zu einer phänomenologischen Psychologie. Die Psychologie von William James. de Gruyter, Berlin 1961. Sebastian Luft: Zur phänomenologische Methode in Karl Jaspers‘ „Allgemeiner Psychopathologie“. In: S. Rinofner-Kreidl, H. A. Wiltsche (Hrsg.) Karl Jaspers‘ Allgemeine Psychopathologie zwischen Wissenschaft, Philosophie und Praxis. Königshausen & Neumann, Würzburg 2008, S. 31–51. Eric Matthews: Body-Subjects and Disordered Minds: Treating the 'whole' person in psychiatry. Oxford University Press, Oxford 2007. Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung. de Gruyter, Berlin 1966. Maurice Merleau-Ponty: Die Struktur des Verhaltens. de Gruyter, Berlin 1967. Maurice Merleau-Ponty: Keime der Vernunft: Vorlesungen an der Sorbonne, 1949–1952. Fink, München 1994. Daniel Nischk u. a.: From theory to clinical practice: A phenomenologically inspired intervention for patients with schizophrenia. In: Psychopathology. 48, 2015, S. 127–136. Josef Parnas u. a.: EASE: Examination of Anomalous Self-Experience. In: Psychopathology. 38, 2005, S. 236–258. Josef Parnas u. a.: Rediscovering psychopathology: the epistemology and phenomenology of the psychiatric object. In: Schizophrenia Bulletin. 39, 2012, S. 270–277. Claire Petitmengin-Peugeot: The intuitive experience. In: Journal of Consciousness Studies. 6, 1999, S. 43–77. Claire Petitmengin: Describing one’s subjective experience in the second person: An interview method for the science of consciousness. In: Phenomenology and the Cognitive sciences. 5, 2006, S. 229–269. Matthew Ratcliffe: Feelings of being. Phenomenology, psychiatry and the sense of reality. Oxford University Press, Oxford / New York 2008. Louis A. Sass, Josef Parnas: Schizophrenia, consciousness, and the self. In: Schizophrenia Bulletin. 29, 2003, S. 427–444. Louis A. Sass, E. Pienkos, B. Skodlar, G. Stanghellini, T. Fuchs, J. Parnas, N. Jones: Examination of Anomalous World Experience. (= Psychopathology. 50). Karger, Basel / Freiburg 2017, ISBN 978-3-318-06020-1. Alexander Schnell: Hinaus. Entwürfe zu einer phänomenologischen Metaphysik und Anthropologie. Würzburg 2011. Alexander Schnell: Wirklichkeitsbilder. Tübingen 2015. Herbert Spiegelberg: Phenomenology in Psychology and Psychiatry. A Historical Introduction. Northwestern University Press, Evanston 1972. Giovanni Stanghellini: Disembodied spirits and deanimatied bodies: The psychopathology of common sense. Oxford University Press, Oxford 2004. Giovanni Stanghellini, Thomas Fuchs (Hrsg.): One Century of Karl Jaspers’ General Psychopathology. Oxford University Press, Oxford 2013. Erwin W. Straus: Vom Sinn der Sinne. 2. Auflage. Springer, Berlin 1956. Erwin Straus: Psychologie der menschlichen Welt. Springer, Berlin / Göttingen / Heidelberg 1960. Hubertus Tellenbach: Melancholie. Problemgeschichte, Endogenität, Typologie, Pathogenese, Klinik. 4. Auflage. Springer, Berlin 1983. László Tengelyi: Welt und Unendlichkeit. Zum Problem phänomenologischer Metaphysik. Freiburg / München 2014. Jan Hendrik van den Berg u. a.: Situation. Beiträge zur phänomenologischen Psychologie und Psychopathologie. Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1954. Kai Vogeley, Christian Kupke: Disturbances of time consciousness from a phenomenological and a neuroscientific perspective. In: Schizophrenia Bulletin. 33, 2007, S. 157–165. Dan Zahavi (Hrsg.): Exploring the self: Philosophical and psychopathological perspectives on self-experience. John Benjamins, Amsterdam 2000. Rezeption Toon Horsten: Der Pater und der Philosoph. Die abenteuerliche Rettung von Husserls Vermächtnis. Dokumentarischer Roman. Galiani, Berlin 2021, ISBN 978-3-86971-211-6. |
文献 フッサール ハビエル・ユセフ・アルバレス=バスケス著『現象学的還元の初期の歴史:エドムント・フッサールの認識論的現象学に関する研究』。FreiDok, Freiburg 2010, urn:nbn:de:bsz:25-opus-74421, 250 pp. (e-Book: PDF). エドムント・フッサールと現象学運動。テキストと画像による証言。フライブルク・イム・ブライスガウのフッサール・アーカイブを代表してハンス・ライナー・ゼップが出版。アルベル、フライブルク/ミュンヘン1988年、ISBN 3-495-47636-9。 デビッド・ベル:フッサール。ルートレッジ、ロンドン1990年、ISBN 0-415-03300-4。 ルドルフ・ベルネ、イソ・カーン、エドゥアルト・マルバッハ:エドムント・フッサール。その思想の展開。フェリックス・マイナー、ハンブルク 1989年、ISBN 3-7873-1284-6。 クリスチャン・バイヤー他(編):フッサールの主観性に関する現象学。Routledge, London 2020, ISBN 978-0-367-73216-5. アルウィン・ディーマー:エドムント・フッサール。体系的な彼の哲学の提示の試み。第2版、改訂版。ハイン、マイゼンハイム・アム・グラン1965年。 オイゲン・フィンク:第6章。デカルト的瞑想。第1部:超越論的方法論のアイデア。エーゴン・フィンクの遺品(1932年)のテキストに、エドムント・ フッサールの遺品(1933/34年)の注釈と添付書類を添付。 出典:ハンス・エーベリング、ヤン・ホー、ガイ・ヴァン・ケルコフ(編):『フッサリアナ、ドキュメント第2巻/1』(ドルドレヒト/ボストン/ロンド ン:クルーワー・アカデミック・パブリッシャーズ、1988年)。 クリステル・フリッケ他(編):『アダム・スミスとエドムンド・フッサールにおける主観性と客観性』。フランクフルト/パリ/ランカスター/ニューブランズウィック 2012年。 トーマス・フックス:『現象学と精神病理学』。S. ギャラガー、D. シュミッキング(編):『現象学と認知科学ハンドブック』。シュプリンガー、ドルドレヒト 2010年、547-573ページ。 ハンス=ヘルムート・ガンダー(編):『フッサール事典』。科学書協会、ダルムシュタット 2009年、ISBN 978-3-534-16493-6。 クラウス・ヘルド(編):『エドムンド・フッサール。 選集。1.現象学的方法。ISBN 3-15-008084-3。 2. 生活世界の現象学。ISBN 3-15-008085-1。 ギスベルト・ホフマン著『フッサールにおける意識、反映、そして「私」』。カール・アルベル出版、フライブルク/ミュンヘン 2001年、ISBN 3-495-48050-1。 フッサール。(『Philosophy Now!』) ウーヴェ・C・シュタイナー選・編。 編集:ペーター・スローターダイク。 ディードリヒス、ミュンヘン 1997年、ISBN 3-424-01290-4。 ジュリア・V・イリバルネ:フッサールの相互主観性理論。 アルベル、フライブルク/ミュンヘン 1994年。 ポール・ヤンセン:エドムント・フッサール。 彼の現象学入門。カール・アルベル、フライブルク/ミュンヘン 1976年、ISBN 3-495-47247-9。 エッダ・カプシュ:他者の理解。フッサール、ガダマー、デリダに続く他者理解。パロドス、ベルリン 2007年、ISBN 978-3-938880-11-1。 Iso Kern: Fremderfahrung. In: Bernet, Kern, Marbach (eds.): Edmund Husserl. Darstellung seines Denkens. 2nd edition. Meiner, Hamburg, 1996, pp. 143–153. Matis Kronschläger: Die Einigung der Lebenswelt(en) nach Husserl. University of Vienna, diploma thesis, 2012. (digitised version) セバスチャン・ルフト著『フッサール遺産のアーカイブ化 1933年~1935年』『フッサール研究』第20巻、1~23ページ。 ウッツ・マース著『ドイツ語話者言語学者に対する迫害と亡命 1933年~1945年』エドムント・フッサールに関する項目(アクセス日:2018年4月13日) ヴェレーナ・マイヤー著『エドムント・フッサール:論理的研究』アカデミー出版、ベルリン、2008年、ISBN 978-3-05-004391-3。 ヴェレーナ・マイヤー著『エドムント・フッサール』C. H. ベック、ミュンヘン、2009年、ISBN 978-3-406-58688-0。 カール・メルテンズ著『最終根拠付けと懐疑の間:超越論的現象学の自己理解に関する批判的考察』(『現象学的展望』第6巻第1号)。アルベル、フライブルク/ミュンヘン1996年、ISBN 3-495-47818-3。 ヴォルフガング・ヘルマン・ミュラー著『エドムント・フッサールの哲学:その出現の主な特徴と体系的内容』。ブヴィエ社、ボン、1956年。 ドミニク・プラデル著『理性の系譜:カントからハイデガーまでの超越論的主体の歴史性に関する試論』。パリ、2013年。 ドミニク・プラデル著『コペルニクス的転回を超えて』。カントとフッサールにおける超越論的対象と能力。パリ、2012年。 ペーター・プレヒトル著『エドムント・フッサール入門』第5版。ユニアス社、ハンブルク、2012年、ISBN 978-3-88506-369-8。 ベルンハルト・ラング著『フッサールの物質的本質の現象学』Klostermann, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-465-02217-3. アドルフ・ライナッハ著『現象学とは何か?』ミュンヘン 1951. R. D. ローリンガー著『フッサールにおけるブレンターノ学派の位置づけ(Phaenomenologica 150)』 Kluwer, Dordrecht 1999, ISBN 0-7923-5684-5. クリスチャン・ローター著『意味の場所』。エドムント・フッサールの現象学における意識と客観性の関係の隠喩性について。Dr. Kovac, Hamburg 2005, ISBN 3-8300-1801-0. レオナルド・スカルフォ著『哲学は純粋観念の科学である。危機』草稿の補遺IIIを特に考慮した上で、フッサールの晩年の哲学について』。ヘルベルト・ウッツ社、ミュンヘン、2006年、ISBN 3-8316-0649-8。 アレクサンダー・シュネル著『時間と現象。フッサールにおける時間現象学』。オルムス社、ブラウンシュヴァイク、2004年。 アレクサンダー・シュネル著『フッサールと構成現象学の基礎』ミロン社、2007年。 カール・シューマン著『フッサール年譜(エドムント・フッサールの思想と生涯)』フッサリアナ・ドキュメント第1号。ニホフ社、ハーグ、1977年、ISBN 90-247-1972-0。 カール・シューマン著『フッサールとマサリク』。ヨゼフ・ノヴァク編『マサリクについて』。英語とドイツ語のテキスト。アムステルダム、1988年、129-156ページ。 ヨゼフ・ザイフェルト著『現実的現象学にとってのフッサール『論理的研究』の意義――そして、フッサールのテーゼに対する現実的現象学者たちの批判』。In: AEMAET. 4, 2015, pp. 28–119. ISSN 2195-173X バリー・スミス、デヴィッド・ウッドラフ・スミス(編):『フッサール入門』ケンブリッジ大学出版局、ケンブリッジ 1995年、ISBN 0-521-43616-8。 トルステン・シュトルーベル著『時間の本質。アウグスティヌス、カント、フッサールにおける時間と意識』ヴュルツブルク 2006年。 エリザベス・シュトロイカー著『フッサールの超越論的現象学』クロスターマン、フランクフルト・アム・マイン 1987年、ISBN 3-465-01773-0。 ハーマン・レオ・ファン・ブレダ著『フッサール遺産の救済とフッサール・アーカイブの創設』。フッサール・アーカイブ・ルーヴェン編『フッサール・アーカ イブ・ルーヴェンの歴史』。シュプリンガー、ハイデルベルク、2007年、ISBN 978-1-4020-5726-7、1~37ページ。 ダン・ザハヴィ著『フッサールと超越論的間主観性』。クルーワー、1996年。 ダン・ザハヴィ著『フッサールの現象学』。シュトゥットガルト、UTB、2009年、ISBN 978-3-8252-3239-9。 ハレにおける哲学的思考。第3章、20世紀の哲学者たち、第2巻、論理学の推進者たち/ゲオルク・カントール、ハインリヒ・ベーハマン、エドムント・フッサール、ギュンター・シェンク編、初版。2002年 参考文献 ジョスリン・ベノワ:『現実的哲学の要素:人が持つものについての考察』。フランス語からの翻訳:デヴィッド・エスピネ。シュルカンプ、ベルリン2014年、ISBN 978-3-518-29700-1。 ルートヴィヒ・ビンスワンガー:『観念の飛翔について』。オレル・フースリ、チューリッヒ1933年。 ルートヴィヒ・ビンズワンガー著『存在分析学と精神医学』。『厳選講演および論文集』(第2巻)フランケ、ベルン、1955年、279-302ページ。 ルートヴィヒ・ビンズワンガー著『3つの不適切な存在形態:偏狭、偏屈、わざとらしさ』。デ・グルイター、ベルリン、1956年。 ルートヴィヒ・ビンスワンガー著『統合失調症』ネスケ出版、プフルリンゲン、1957年。 ルートヴィヒ・ビンスワンガー著『憂鬱と躁病』ネスケ出版、プフルリンゲン、1960年。 ルートヴィヒ・ビンスワンガー著『妄想:現象学的および実存的分析への貢献』ネスケ出版、プフルリンゲン、1965年。 ヴォルフガング・ブランケンブルク著『「常識」の精神病理学へのアプローチ』。『精神医学ジャーナル』第12号、1969年、144-163ページ。 ヴォルフガング・ブランケンブルク著『自然な自明性の喪失。症状のない統合失調症の精神病理学への貢献』。エンケ社、シュトゥットガルト、1971年。 フレデリック・J.J.・ブイトェンダイク著『苦悩について』フーバー、ベルン、1948年。 フレデリック・J.J.・ブイトェンダイク著『出会い現象学』『エラノス年鑑』第19号、1951年、431~486ページ。 フレデリック・J・J・ブイトエンダイク著『人間と動物』M. J. モーリー訳、ロンドン、1957年。 フレデリック・J・J・ブイトエンダイク著『人間姿勢と運動の一般理論』M. J. モーリー訳、ロンドン、1959年。 ゲイリー・B・コーエン著『帝国オーストリアにおける教育と中流社会、1848年~1918年』インディアナ州ウェスト・ラファイエット、1996年。 ヘドヴィヒ・コンラート=マルティウス著『序文』アドルフ・ライナッハ編『現象学とは何か?』ミュンヘン、1951年、5~17ページ。 ゲルハルト・ダマン(編):現象学と心理療法精神医学。コルハマー、シュトゥットガルト2014年。 ウルリッヒ・ドパトカ:絶対主観性の現象学。エドムント・フッサール、ジャン=ポール・サルトル、ミシェル・アンリ、ジャン=リュック・マリオンの著作における意識の反射以前の構造の調査。フィンク・フェアラーク、2019年。 トーマス・フックス:自閉症と統合失調症における相互主観性の病理。『意識研究ジャーナル』22、2015年、191-214ページ。 トーマス・フックス他(編):カール・ヤスパース:現象学と精神病理学。シュプリンガー、ベルリン/ハイデルベルク/ニューヨーク2013年。 モーリッツ・ガイガー著『科学と形而上学の現実』ボン、1930年。 アメデオ・ジョルジ著『人間科学としての心理学』ニューヨーク、ハーパー・アンド・ロー、1970年。 アメデオ・ジョルジ著『心理学における記述的現象学的方法』ペンシルベニア州ピッツバーグ、デュケイン大学出版、2009年。 カール・フリードリヒ・グラウマン著『現象学的心理学』。R. アサンガー、G. ヴェニンガー編『心理学ハンドブック』第5版。心理学出版社連合、ヴァインハイム、1994年。 カール・フリードリヒ・グラウマン著『現象学の基礎と視点心理学』。デ・グルイター、ベルリン、1960年。 ニコライ・ハルトマン著『認識の形而上学の基本原理』。ベルリン / ライプツィヒ 1921年。 ニコライ・ハルトマン著『存在論の新展開』第3版。シュトゥットガルト 1949年。 アリス・ホルツハイ=クンツ著『存在分析』。A. レングル、A. ホルツハイ=クンツ編『存在分析と存在分析』ファカルタス、ウィーン 2008年、181-348ページ。 ローマン・インガルデン:世界の存在に関する論争。第1巻:存在論。テュービンゲン、1964年。 カール・ヤスパース:一般精神病理学。第9版。シュプリンガー、ベルリン/ハイデルベルク/ニューヨーク、1913/1973年。 デビッド・カッツ:色彩世界の構造。バルト、ライプツィヒ、1930年。 デビッド・カッツ:ゲシュタルト心理学。シュヴァーベ、バーゼル、1944年。 Joseph J. Kockelmans (編): 現象学心理学:オランダ学派。 Kluwer, Dordrecht 1987. クルト・コフカ: ゲシュタルト心理学の原理。 Harcourt, New York 1935. ヴォルフガング・ケーラー: ゲシュタルト心理学。 Bell, London 1929. ハンス・ケーヒラー著『超越論的現象学における主観と客観の弁証法:観念論と現実論の間の存在論的問題』アントン・ハイン出版、1974年、メーゼンハイム・アム・ライン ハンス・ケーヒラー著『現象学的実在論』ピーター・ラング出版、フランクフルト・アム・マイン/ベルン/ニューヨーク、1986年 アルフレッド・クラウス著『躁うつ病者の社会行動と精神病』エンケ、シュトゥットガルト、1977年 レネリス・クルーゼ他編著『生態心理学』プシコロギー・フェアラークスユニオン、ミュンヘン、1990年 ローランド・クーン著『実存分析と精神医学』H. W. グルーレ他編著『現代の精神医学』 (I/2)、Springer、ベルリン/ゲッティンゲン/ハイデルベルク1963年、833~902ページ。 ルートヴィヒ・ランドグレーベ著『反省の限界としての事実性と信念の問題』。同著『事実性と個別化。現象学の根本問題に関する研究』。ハンブルク1976年、117~136ページ。 ルートヴィヒ・ラントグレーベ著『現象学と形而上学』ハンブルク、1949年。 ヤン・ホイゲン・ファン・リンショテン著『入眠について』『心理学的貢献』第2巻、1955年、70~97ページ。また、『入眠と行動について』も参照。リンショテン著『1955年、266~298ページ』。 ヤン・ホイゲン・ファン・リンスコテン著『現象学心理学への道』ウィリアム・ジェームズの心理学』de Gruyter, ベルリン 1961年 セバスチャン・ルフト著『カール・ヤスパースの「一般精神病理学」における現象学的方法について』 S. Rinofner-Kreidl, H. A. Wiltsche (eds.) Karl Jaspers' General Psychopathology between Science, Philosophy and Practice. Königshausen & Neumann, Würzburg 2008, pp. 31–51. Eric Matthews: Body-Subjects and Disordered Minds: Treating the 'whole' person in psychiatry. Oxford University Press, Oxford 2007. モーリス・メルロ=ポンティ著:知覚の現象学。Harper & Row、ニューヨーク、1968年。 モーリス・メルロ=ポンティ著:行動の構造。Harper & Row、ニューヨーク、1968年。 モーリス・メルロ=ポンティ著:精神の生成:論文集。Harper & Row、ニューヨーク、1969年。 ダニエル・ニッシュク他:理論から臨床実践へ:現象学に着想を得た統合失調症患者への介入。『精神病理学』第48号、2015年、127-136ページ。 ヨゼフ・パーナス他:EASE:異常な自己体験の検証。『精神病理学』第38号、2005年、236-258ページ。 ヨゼフ・パルナス他:精神病理学の再発見:精神医学的対象の認識論と現象学。『統合失調症速報』第39号、2012年、270-277ページ。 クレア・プティマンジャン=プジョー:直観的経験。『意識研究ジャーナル』第6号、1999年、43-77ページ。 クレア・プティマンジャン:主観的体験を二人称で描写する:意識の科学のためのインタビュー方法。『現象学と認知科学』第5号、2006年、229-269ページ。 マシュー・ラトクリフ:存在の感覚。現象学、精神医学、現実感。オックスフォード大学出版局、オックスフォード/ニューヨーク、2008年。 ルイス・A・サス、ジョゼフ・パーナス:統合失調症、意識、自己。『Schizophrenia Bulletin』29、2003年、427-444ページ。 ルイス・A・サス、E. ピエンコス、B. スコドラー、G. スタンゲリーニ、T. フックス、J. パーナス、N. ジョーンズ:『異常な世界体験の検証』。(『精神病理学』第50号)。Karger, Basel / Freiburg 2017, ISBN 978-3-318-06020-1. アレクサンダー・シュネル:『超克』。現象学的形而上学と人間学の構想。ヴュルツブルク2011年。 アレクサンダー・シュネル:『現実のイメージ』。テュービンゲン2015年。 ハーバート・シュピーゲルバーグ:心理学と精神医学における現象学。歴史的概説。ノースウェスタン大学出版、エバンストン1972年。 ジョヴァンニ・スタンゲリーニ:魂の脱肉体化と生命のない身体:常識の精神病理学。オックスフォード大学出版、オックスフォード2004年。 ジョヴァンニ・スタンゲリーニ、トーマス・フックス(編):『カール・ヤスパース『一般精神病理学』100年』。オックスフォード大学出版局、オックスフォード 2013年。 エルヴィン・W・シュトラウス:『感覚の意味』第2版。シュプリンガー、ベルリン 1956年。 エルヴィン・シュトラウス:『人間世界の心理学』。シュプリンガー、ベルリン/ゲッティンゲン/ハイデルベルク 1960年。 フーベルトゥス・テレンバッハ著『メランコリー。問題史、内因性、類型論、病態生理学、臨床。第4版。シュプリンガー、ベルリン、1983年。 ラースロー・テンゲリ著『世界と無限。現象学的な形而上学の問題について。フライブルク/ミュンヘン、2014年。 ヤン・ヘンドリック・ファン・デン・ベルク他、『状況。現象学的心理学と精神病理学への貢献』、スペクトラム、ユトレヒト/アントワープ、1954年。 カイ・フォーゲルイ、クリスチャン・クプケ、「時間意識の障害:現象学的および神経科学的観点から」、『統合失調症速報』第33巻第2号(2007年)、157-65ページ。 Dan Zahavi (ed.): Exploring the self: Philosophical and psychopathological perspectives on self-experience. John Benjamins, Amsterdam 2000. レセプション Toon Horsten: The Father and the Philosopher. The Adventurous Rescue of Husserl's Legacy. A documentary novel. Galiani, Berlin 2021, ISBN 978-3-86971-211-6. |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl |
|
★
★ウィキペディア(英語版)
| Edmund Gustav
Albrecht Husserl (/ˈhʊsɜːrl/ HUUSS-url;[14] US also /ˈhʊsərəl/
HUUSS-ər-əl,[15] German: [ˈɛtmʊnt ˈhʊsɐl];[16] 8 April 1859 – 27 April
1938[17]) was an Austrian-German philosopher and mathematician who
established the school of phenomenology. In his early work, he elaborated critiques of historicism and of psychologism in logic based on analyses of intentionality. In his mature work, he sought to develop a systematic foundational science based on the so-called phenomenological reduction. Arguing that transcendental consciousness sets the limits of all possible knowledge, Husserl redefined phenomenology as a transcendental-idealist philosophy. Husserl's thought profoundly influenced 20th-century philosophy, and he remains a notable figure in contemporary philosophy and beyond. Husserl studied mathematics, taught by Karl Weierstrass and Leo Königsberger, and philosophy taught by Franz Brentano and Carl Stumpf.[18] He taught philosophy as a Privatdozent at Halle from 1887, then as professor, first at Göttingen from 1901, then at Freiburg from 1916 until he retired in 1928, after which he remained highly productive. In 1933, under racial laws of the Nazi Party, Husserl was expelled from the library of the University of Freiburg due to his Jewish family background and months later resigned from the Deutsche Akademie. Following an illness, he died in Freiburg in 1938.[19] |
エドムント・グスタフ・アルベルト・フッサール(/ˈhʊsɜːrl/
HUUSS-url;[14] 米国では /ˈhʊsərəl/ HUUSS-ər-əl,[15] ドイツ語: [ˈɛtm 1859年4月8日 -
1938年4月27日[17])は、現象学派を創始したオーストリア系ドイツ人の哲学者、数学者である。 初期の著作では、志向性の分析を基盤として、歴史主義と心理主義の論理に対する批判を詳細に論じている。円熟した作品では、いわゆる現象学的還元に基づく 体系的な基礎科学の構築を目指した。超越論的意識がすべての可能な知識の限界を定めるという主張に基づき、フッサールは現象学を超越論的観念論哲学として 再定義した。フッサールの思想は20世紀の哲学に多大な影響を与え、現代哲学を超えて、今なお著名な人物である。 フッサールは、カール・ワイエルシュトラスとレオ・ケーニヒスベルガーから数学を、フランツ・ブレンターノとカール・シュトゥンプから哲学を学んだ。 [18] 1887年からハレで、その後1901年からゲッティンゲンで、さらに1916年からフライブルクで教授として哲学を教え、1928年に引退するまで教鞭 をとり、その後も非常に生産的な活動を続けた。1933年、ナチス党の人種法により、ユダヤ人としての家系を理由にフッサールはフライブルク大学の図書館 から追放され、数か月後にはドイツ学術アカデミーも退会した。病気療養の後、1938年にフライブルクで死去した。[19] |
| Life and career Youth and education Husserl was born in 1859 in Proßnitz in the Margraviate of Moravia in the Austrian Empire (today Prostějov in the Czech Republic). He was born into a Jewish family, the second of four children. His father was a milliner. His childhood was spent in Prostějov, where he attended the secular primary school. Then Husserl traveled to Vienna to study at the Realgymnasium there, followed next by the Staatsgymnasium in Olmütz.[20][21] At the University of Leipzig from 1876 to 1878, Husserl studied mathematics, physics, and astronomy. At Leipzig, he was inspired by philosophy lectures given by Wilhelm Wundt, one of the founders of modern psychology. Then he moved to the Frederick William University of Berlin (the present-day Humboldt University of Berlin) in 1878 where he continued his study of mathematics under Leopold Kronecker and the renowned Karl Weierstrass. In Berlin he found a mentor in Tomáš Garrigue Masaryk, then a former philosophy student of Franz Brentano and later the first president of Czechoslovakia. There Husserl also attended Friedrich Paulsen's philosophy lectures. In 1881 he left for the University of Vienna to complete his mathematics studies under the supervision of Leo Königsberger (a former student of Weierstrass). At Vienna in 1883 he obtained his PhD with the work Beiträge zur Variationsrechnung (Contributions to the Calculus of variations).[20] Evidently as a result of his becoming familiar with the New Testament during his twenties, Husserl asked to be baptized into the Lutheran Church in 1886. Husserl's father Adolf had died in 1884. Herbert Spiegelberg writes, "While outward religious practice never entered his life any more than it did that of most academic scholars of the time, his mind remained open for the religious phenomenon as for any other genuine experience." At times Husserl saw his goal as one of moral "renewal". Although a steadfast proponent of a radical and rational autonomy in all things, Husserl could also speak "about his vocation and even about his mission under God's will to find new ways for philosophy and science," observes Spiegelberg.[22] Following his PhD in mathematics, Husserl returned to Berlin to work as the assistant to Karl Weierstrass. Yet already Husserl had felt the desire to pursue philosophy. Then professor Weierstrass became very ill. Husserl became free to return to Vienna where, after serving a short military duty, he devoted his attention to philosophy. In 1884 at the University of Vienna he attended the lectures of Franz Brentano on philosophy and philosophical psychology. Brentano introduced him to the writings of Bernard Bolzano, Hermann Lotze, J. Stuart Mill, and David Hume. Husserl was so impressed by Brentano that he decided to dedicate his life to philosophy; indeed, Franz Brentano is often credited as being his most important influence, e.g., with regard to intentionality.[23] Following academic advice, two years later in 1886 Husserl followed Carl Stumpf, a former student of Brentano, to the University of Halle, seeking to obtain his habilitation which would qualify him to teach at the university level. There, under Stumpf's supervision, he wrote Über den Begriff der Zahl (On the Concept of Number) in 1887, which would serve later as the basis for his first important work, Philosophie der Arithmetik (1891).[24] In 1887 Husserl married Malvine Steinschneider, a union that would last over fifty years. In 1892 their daughter Elizabeth was born, in 1893 their son Gerhart, and in 1894 their son Wolfgang. Elizabeth would marry in 1922, and Gerhart in 1923; Wolfgang, however, became a casualty of the First World War.[21] Gerhart would become a philosopher of law, contributing to the subject of comparative law, teaching in the United States and after the war in Austria.[25] Professor of philosophy  Edmund Husserl c. 1900 Following his marriage Husserl began his long teaching career in philosophy. He started in 1887 as a Privatdozent at the University of Halle. In 1891 he published his Philosophie der Arithmetik. Psychologische und logische Untersuchungen which, drawing on his prior studies in mathematics and philosophy, proposed a psychological context as the basis of mathematics. It drew the adverse notice of Gottlob Frege, who criticized its psychologism.[26][27] In 1901 Husserl with his family moved to the University of Göttingen, where he taught as extraordinarius professor. Just prior to this a major work of his, Logische Untersuchungen (Halle, 1900–1901), was published. Volume One contains seasoned reflections on "pure logic" in which he carefully refutes "psychologism".[28][29] This work was well received and became the subject of a seminar given by Wilhelm Dilthey; Husserl in 1905 traveled to Berlin to visit Dilthey. Two years later in Italy he paid a visit to Franz Brentano his inspiring old teacher and to Constantin Carathéodory the mathematician. Kant and Descartes were also now influencing his thought. In 1910 he became joint editor of the journal Logos. During this period Husserl had delivered lectures on internal time consciousness, which several decades later his former students Edith Stein and Martin Heidegger edited for publication.[30] In 1912 at Freiburg the journal Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung ("Yearbook for Philosophy and Phenomenological Research") was founded by Husserl and his school, and which published articles of their phenomenological movement from 1913 to 1930. His important work Ideen[31] was published in its first issue (Vol. 1, Issue 1, 1913). Before beginning Ideen, Husserl's thought had reached the stage where "each subject is 'presented' to itself, and to each all others are 'presentiated' (Vergegenwärtigung), not as parts of nature but as pure consciousness".[32] Ideen advanced his transition to a "transcendental interpretation" of phenomenology, a view later criticized by, among others, Jean-Paul Sartre.[33] In Ideen Paul Ricœur sees the development of Husserl's thought as leading "from the psychological cogito to the transcendental cogito". As phenomenology further evolves, it leads (when viewed from another vantage point in Husserl's 'labyrinth') to "transcendental subjectivity".[34] Also in Ideen Husserl explicitly elaborates the phenomenological and eidetic reductions.[35][36] Ivan Ilyin and Karl Jaspers visited Husserl at Göttingen. In October 1914 both his sons were sent to fight on the Western Front of World War I, and the following year one of them, Wolfgang Husserl, was badly injured. On 8 March 1916, on the battlefield of Verdun, Wolfgang was killed in action. The next year his other son Gerhart Husserl was wounded in the war but survived. His own mother Julia died. In November 1917 one of his outstanding students and later a noted philosophy professor in his own right, Adolf Reinach, was killed in the war while serving in Flanders.[21] Husserl had transferred in 1916 to the University of Freiburg (in Freiburg im Breisgau) where he continued bringing his work in philosophy to fruition, now as a full professor.[37] Edith Stein served as his personal assistant during his first few years in Freiburg, followed later by Martin Heidegger from 1920 to 1923. The mathematician Hermann Weyl began corresponding with him in 1918. Husserl gave four lectures on Phenomenological method at University College London in 1922. The University of Berlin in 1923 called on him to relocate there, but he declined the offer. In 1926 Heidegger dedicated his book Sein und Zeit (Being and Time) to him "in grateful respect and friendship."[38] Husserl remained in his professorship at Freiburg until he requested retirement, teaching his last class on 25 July 1928. A Festschrift to celebrate his seventieth birthday was presented to him on 8 April 1929. Despite retirement, Husserl gave several notable lectures. The first, at Paris in 1929,[39] led to Méditations cartésiennes (Paris 1931).[40] Husserl here reviews the phenomenological epoché (or phenomenological reduction), presented earlier in his pivotal Ideen (1913), in terms of a further reduction of experience to what he calls a 'sphere of ownness.' From within this sphere, which Husserl enacts to show the impossibility of solipsism, the transcendental ego finds itself always already paired with the lived body of another ego, another monad. This 'a priori' interconnection of bodies, given in perception, is what founds the interconnection of consciousnesses known as transcendental intersubjectivity, which Husserl would go on to describe at length in volumes of unpublished writings. There has been a debate over whether or not Husserl's description of ownness and its movement into intersubjectivity is sufficient to reject the charge of solipsism, to which Descartes, for example, was subject. One argument against Husserl's description works this way: instead of infinity and the Deity being the ego's gateway to the Other, as in Descartes, Husserl's ego in the Cartesian Meditations itself becomes transcendent. It remains, however, alone (unconnected). Only the ego's grasp "by analogy" of the Other (e.g., by conjectural reciprocity) allows the possibility for an 'objective' intersubjectivity, and hence for community.[41] In 1933, the racial laws of the new National Socialist German Workers Party were enacted. On 6 April Husserl was banned from using the library at the University of Freiburg, or any other academic library; the following week, after a public outcry, he was reinstated.[42] Yet his colleague Heidegger was elected Rector of the university on 21–22 April, and joined the Nazi Party. By contrast, in July Husserl resigned from the Deutsche Akademie.[21]  The Kiepenheuer Institute for Solar Physics in Freiburg, Husserl's home 1937–1938 Later Husserl lectured at Prague in 1935 and Vienna in 1936, which resulted in a very differently styled work that, while innovative, is no less problematic: Die Krisis (Belgrade 1936).[43][44] Husserl describes here the cultural crisis gripping Europe, then approaches a philosophy of history, discussing Galileo, Descartes, several British philosophers, and Kant. The apolitical Husserl before had specifically avoided such historical discussions, pointedly preferring to go directly to an investigation of consciousness. Merleau-Ponty and others question whether Husserl here does not undercut his own position, in that Husserl had attacked in principle historicism, while specifically designing his phenomenology to be rigorous enough to transcend the limits of history. On the contrary, Husserl may be indicating here that historical traditions are merely features given to the pure ego's intuition, like any other.[45][46] A longer section follows on the "lifeworld" [Lebenswelt], one not observed by the objective logic of science, but a world seen through subjective experience.[47] Yet a problem arises similar to that dealing with 'history' above, a chicken-and-egg problem. Does the lifeworld contextualize and thus compromise the gaze of the pure ego, or does the phenomenological method nonetheless raise the ego up transcendent?[48] These last writings presented the fruits of his professional life. Since his university retirement Husserl had "worked at a tremendous pace, producing several major works."[20] After suffering a fall in the autumn of 1937, the philosopher became ill with pleurisy. Edmund Husserl died in Freiburg on 27 April 1938, having just turned 79. His wife Malvine survived him. Eugen Fink, his research assistant, delivered his eulogy.[49] Gerhard Ritter was the only Freiburg faculty member to attend the funeral, as an anti-Nazi protest. Heidegger and the Nazi era Husserl was rumoured to have been denied the use of the library at Freiburg as a result of the anti-Jewish legislation of April 1933.[50] However, among other disabilities Husserl was unable to publish his works in Nazi Germany [see above footnote to Die Krisis (1936)]. It was also rumoured that his former pupil Martin Heidegger informed Husserl that he was discharged, but it was actually the previous rector.[51] Apparently Husserl and Heidegger had moved apart during the 1920s, which became clearer after 1928 when Husserl retired and Heidegger succeeded to his university chair. In the summer of 1929 Husserl had studied carefully selected writings of Heidegger, coming to the conclusion that on several of their key positions they differed: e.g., Heidegger substituted Dasein ["Being-there"] for the pure ego, thus transforming phenomenology into an anthropology, a type of psychologism strongly disfavored by Husserl. Such observations of Heidegger, along with a critique of Max Scheler, were put into a lecture Husserl gave to various Kant Societies in Frankfurt, Berlin, and Halle during 1931 entitled Phänomenologie und Anthropologie.[52][53] In the war-time 1941 edition of Heidegger's primary work, Being and Time (Sein und Zeit, first published in 1927), the original dedication to Husserl was removed. This was not due to a negation of the relationship between the two philosophers, however, but rather was the result of a suggested censorship by Heidegger's publisher who feared that the book might otherwise be banned by the Nazi regime.[54] The dedication can still be found in a footnote on page 38, thanking Husserl for his guidance and generosity. Husserl had died three years earlier. In post-war editions of Sein und Zeit the dedication to Husserl is restored. The complex, troubled, and sundered philosophical relationship between Husserl and Heidegger has been widely discussed.[53][55] On 4 May 1933, Professor Edmund Husserl addressed the recent regime change in Germany and its consequences: The future alone will judge which was the true Germany in 1933, and who were the true Germans—those who subscribe to the more or less materialistic-mythical racial prejudices of the day, or those Germans pure in heart and mind, heirs to the great Germans of the past whose tradition they revere and perpetuate.[56] After his death, Husserl's manuscripts, amounting to approximately 40,000 pages of "Gabelsberger" stenography and his complete research library, were in 1939 smuggled to the Catholic University of Leuven in Belgium by the Franciscan priest Herman Van Breda. There they were deposited at Leuven to form the Husserl-Archives of the Higher Institute of Philosophy.[57] Much of the material in his research manuscripts has since been published in the Husserliana critical edition series.[58] |
生涯とキャリア 青年期と教育 フッサールは1859年、オーストリア帝国のモラヴィア辺境伯領プロスニッツ(現在のチェコ共和国プロスチエヨフ)で生まれた。ユダヤ人の家庭に4人兄弟 の2番目として生まれた。父親は帽子屋であった。幼少期はプロスチエヨフで過ごし、世俗的な小学校に通った。その後、フッサールはウィーンのギムナジウム で学び、次いでオルミュツのギムナジウムに進学した。 1876年から1878年にかけて、フッサールはライプツィヒ大学で数学、物理学、天文学を学んだ。ライプツィヒでは、近代心理学の創始者の一人である ヴィルヘルム・ヴントの哲学講義に感銘を受けた。その後、1878年にベルリンのフリードリヒ・ウィリアム大学(現在のベルリン・フンボルト大学)に移 り、レオポルト・クロネッカーや著名なカール・ワイエルシュトラスのもとで数学の研究を続けた。ベルリンでは、当時フランツ・ブレンターノの哲学の学生で あり、後にチェコスロバキアの初代大統領となるトマーシュ・マサリクを師と仰いだ。また、フッサールはフリードリヒ・パウルゼンの哲学講義にも出席した。 1881年、彼はウィーン大学でレオ・ケーニヒスベルガー(ワイエルシュトラスの元学生)の指導の下、数学の研究を続けるためにウィーン大学へ向かった。 1883年、ウィーンで博士号を取得。博士論文のタイトルは「Beiträge zur Variationsrechnung(変分学への貢献)」であった。 20代に新約聖書に親しんだ結果、1886年にフッサールはルター派教会で洗礼を受けることを希望した。フッサールの父アドルフは1884年に死去してい た。ハーバート・シュピーゲルバーグは、「当時のほとんどの学者と同様に、彼の生活には宗教的な実践は一切なかったが、彼の心は、他の真の経験と同様に、 宗教的な現象に対して開かれていた」と記している。フッサールは、自身の目標を道徳的な「刷新」のひとつとして捉えていた時期もあった。あらゆる物事にお ける急進的かつ合理的な自律性の揺るぎない提唱者であったフッサールは、「自身の天職、さらには哲学と科学の新たな道を見出すという神の意志に基づく使命 について」語ることもできた、とシュピーゲルバーグは指摘している。 数学の博士号取得後、フッサールはベルリンに戻り、カール・ワイエルシュトラスの助手として働くことになった。しかし、すでにフッサールは哲学を追求した いという願望を感じていた。その後、ワイエルシュトラス教授が重病にかかった。フッサールはウィーンに戻る自由を手に入れ、短い兵役を終えた後、哲学に専 念した。1884年、ウィーン大学でフランツ・ブレンターノの哲学と哲学心理学の講義を受講した。ブレンターノは、フッサールにベルンハルト・ボルツァー ノ、ヘルマン・ロッツェ、J.スチュアート・ミル、デイヴィッド・ヒュームの著作を紹介した。フッサールはブレンターノに感銘を受け、哲学に生涯を捧げる ことを決意した。実際、フランツ・ブレンターノは、志向性に関してなど、彼の最も重要な影響力となった人物としてしばしば挙げられている。学術的な助言に 従い、2年後の1886年、フッサールはブレンターノの元学生であったカール・シュトゥンプフに続いてハレ大学へ赴き、大学レベルでの教職に就くための資 格であるハビリテーションの取得を目指した。そこでシュトゥンプフの指導の下、1887年に『数の概念について』を執筆し、これが後に彼の最初の重要な著 作『算術の哲学』(1891年)の基礎となった。 1887年、フッサールはマルバイン・シュタインシュナイダーと結婚し、その結婚生活は50年以上続いた。1892年に娘のエリザベスが、1893年に息 子のゲルハルトが、そして1894年に息子のヴォルフガングが生まれた。エリザベスは1922年に、ゲルハルトは1923年に結婚した。しかし、ヴォルフ ガングは第一次世界大戦の犠牲となった。[21] ゲルハルトは法哲学の研究者となり、比較法学の分野に貢献し、アメリカ合衆国で教鞭をとり、戦後はオーストリアで教鞭をとった。[25] 哲学教授  エドムント・フッサール c. 1900 結婚後、フッサールは哲学の教師としての長いキャリアをスタートさせた。1887年にハレ大学の非常勤講師として教鞭をとり始め、1891年には『算術の 哲学:心理学的および論理的研究』を出版した。この著書では、それまでの数学と哲学の研究を基に、数学の基礎として心理学的な文脈を提案した。この著書 は、心理主義を批判したゴットロープ・フレーゲの反感を買った。 1901年、フッサールは家族とともにゲッティンゲン大学に移り、非常勤教授として教鞭をとった。この主要な著作『論理的研究』(1900年から1901 年、ハレ)が出版されたのは、その直前であった。第1巻には「純粋論理学」に関する熟考が含まれており、その中で彼は「心理主義」を慎重に論駁している。 [28][29] この著作は好評を博し、ヴィルヘルム・ディルタイによるゼミナールのテーマとなった。1905年、フッサールはディルタイを訪問するためにベルリンを訪れ た。2年後、イタリアで彼は、かつての恩師であるフランツ・ブレンターノと数学者のコンスタンティン・カラテオドリーを訪問した。カントやデカルトも、こ の頃には彼の思想に影響を与えていた。1910年には、雑誌『ロゴス』の共同編集者となった。この時期、フッサールは内的時間意識に関する講義を行ってい たが、その講義は数十年後に、かつての教え子であるエディト・シュタインとマルティン・ハイデガーによって編集され、出版された。 1912年、フライブルクで、フッサールとその学派によって『Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung』(「哲学と現象学的研究年鑑」)が創刊され、1913年から1930年にかけて、彼らの現象学運動に関する論文が掲載された。彼の重 要な著作『イデーエン』[31]は、その創刊号(第1巻第1号、1913年)に掲載された。『イデーエン』の執筆に着手する以前に、フッサールの思想は 「各主題はそれ自体に『提示』され、各主題は他のすべてを『提示する』(Vergegenwärtigung)という段階に達していた。自然の一部として ではなく、純粋な意識として」[32] 『イデーエン』は、彼の現象学の「超越論的解釈」への転換を推進した 現象学の「超越論的解釈」への移行を提唱したが、この見解は後にジャン=ポール・サルトルなどから批判された。[33] 『イデー』において、ポール・リクールはフッサールの思想の発展が「心理学的コギトから超越論的コギト」へと導くものであると見ている。現象学がさらに発 展すると、「超越論的自己意識」へとつながる(フッサールの「迷宮」における別の視点から見た場合)。[34] 『アイデア』において、フッサールは現象学的還元とエイドス的還元を明確に説明している。[35][36] イワン・イリインとカール・ヤスパースはゲッティンゲンを訪れ、フッサールと面会した。 1914年10月、彼の2人の息子が第一次世界大戦の西部戦線に送られ、翌年、そのうちの1人であるヴォルフガング・フッサールが重傷を負った。1916 年3月8日、ヴォルフガングはヴェルダンの戦場で戦死した。翌年、もう1人の息子ゲルハルト・フッサールは負傷したが、生き延びた。実母のユリアは死亡し た。1917年11月、彼の優秀な学生の一人であり、後に著名な哲学教授となるアドルフ・ライナッハが、フランダースで従軍中に戦死した。 フッサールは1916年にフライブルク大学(フライブルク・イム・ブライスガウ)に移り、そこで哲学の研究を続け、最終的には正教授となった。[37] エディト・シュタインは、フッサールがフライブルクにいた最初の数年間、個人的なアシスタントを務め、その後1920年から1923年まではマルティン・ ハイデガーが務めた。数学者のヘルマン・ワイエルは1918年から彼と文通を始めた。フッサールは1922年にロンドン大学で現象学的方法に関する4つの 講義を行った。1923年にはベルリン大学から移籍の誘いを受けたが、申し出を断った。1926年、ハイデガーは著書『存在と時間』を「感謝と友情の念を 込めて」フッサールに捧げた。[38] フッサールはフライブルク大学の教授職を退くまで在職し、1928年7月25日に最後の授業を行った。1929年4月8日には、彼の70歳の誕生日を祝う 記念論文集が贈られた。 退職後も、フッサールはいくつかの著名な講義を行った。最初の講義は1929年にパリで行われ、[39] 『カードによる省察』(1931年、パリ)[40]につながった。フッサールはここで、現象学におけるエポケー(現象学的還元)を、彼の重要な著作『イ デーン』(1913年)で以前に提示した内容を、さらに経験を「自己性」の領域に還元する観点から再検討した。この「自己性」の領域内から、フッサールは 自己同一説の不可能を明らかにしようとするが、超越論的自我は、常にすでに別の自我、別のモナドの生きた身体と結びついていることに気づく。知覚によって 与えられる身体のこの「先験的」相互関係こそが、フッサールが後に未発表の論文の数々で詳細に説明することになる、超越論的相互主観性として知られる意識 の相互関係の基盤となるものである。フッサールによる自己性と相互主観性へのその動きの記述は、例えばデカルトがそうであったような自己本位主義の非難を 退けるのに十分であるかどうかについては、議論がある。フッサールの記述に対する反対意見のひとつは次のようなものである。無限と神が自我の他者への入り 口であるというデカルトの考え方ではなく、フッサールの『Cartesian Meditations』における自我そのものが超越的になる。しかし、それは単独のまま(つながりを持たない)である。自我が「類推によって」他者(例 えば、推測上の相互性によって)を把握することによってのみ、「客観的な」相互主観性、ひいては共同体の可能性が生まれるのである。 1933年、新たに結成された国家社会主義ドイツ労働者党の民族法が制定された。4月6日、フッサールはフライブルク大学図書館やその他の学術図書館の利 用を禁止された。翌週、世論の反発を受けて、彼は復職した。[42] しかし、彼の同僚であるハイデガーは4月21日~22日に学長に選出され、ナチス党に入党した。対照的に、7月にはフッサールはドイツ学術アカデミーを辞 任した。[21]  フライブルクのキープヘーア太陽物理学研究所、1937年から1938年のフッサールの自宅 その後、フッサールは1935年にプラハ、1936年にウィーンで講義を行ったが、その結果、革新的ではあるが、同様に問題の多い、まったく異なるスタイ ルの著作『危機』(1936年、ベオグラード)が生まれた。[43][44] フッサールはここで、ヨーロッパを襲った文化の危機について述べ、ガリレオ、デカルト、イギリスの哲学者数名、カントについて論じながら、歴史哲学に接近 している。政治に関心がなかったフッサールは、それまではこのような歴史論の議論を特に避けており、意識の研究に直接取り組むことを好んでいた。メルロ= ポンティや他の人々は、フッサールが歴史主義を原理的に攻撃していた一方で、自身の現象学を歴史の限界を超越するほど厳密なものとして具体的に設計してい たという点で、フッサールがここで自身の立場を損なっているのではないかと疑問を呈している。それどころか、フッサールはここで、歴史的伝統は純粋自我の 直観に与えられた特徴にすぎず、他のものと同様のものであると示唆しているのかもしれない。[45][46] 「生活世界」(Lebenswelt)については、より長い節が続く。これは、科学の客観的論理によって観察されるものではなく、主観的な経験を通して見 られる世界である。[47] しかし、ここで「歴史」を扱う際に生じたのと同様の問題、つまり鶏が先か卵が先かという問題が生じる。生活世界は純粋なエゴの視線を文脈化し、妥協させる のか、それとも現象学的方法はそれでもなおエゴを超越的に高めるのか?[48] これらの最後の著作は、彼の職業人生の成果を示している。大学を退職して以来、フッサールは「驚異的なペースで働き、いくつかの主要な著作を生み出した」 [20]。 1937年秋に転倒して負傷した哲学者は、胸膜炎を患った。エドムント・フッサールは1938年4月27日、79歳になったばかりでフライブルクで死去し た。彼の妻マルヴィーネは彼より長生きした。研究助手のオイゲン・フィンクが弔辞を述べた。[49] ゲルハルト・リッターは反ナチス抗議として、フライブルクの教職員の中で唯一葬儀に参列した。 ハイデガーとナチス時代 フッサールは、1933年4月の反ユダヤ法の結果、フライブルク大学の図書館の利用を拒否されたという噂があった。[50] しかし、他の障害に加えて、フッサールはナチス・ドイツで作品を出版することができなかった。[『危機』(1936年)の脚注を参照] また、かつての教え子であったマルティン・ハイデガーがフッサールに解雇されたと伝えたという噂もあったが、実際には前学長であった。[51] どうやら、1920年代にフッサールとハイデガーは疎遠になっていたようで、1928年にフッサールが引退し、ハイデガーが後任の教授職に就いたことで、 そのことがより明確になった。1929年の夏、フッサールは厳選したハイデガーの著作を注意深く研究し、いくつかの重要な立場において両者の見解が異なっ ているという結論に達した。例えば、ハイデガーは純粋自我に代えて「存在-そこにあること(Dasein)」を置き、現象学を人間学へと変容させた。人間 学は、フッサールが強く嫌悪していた心理主義の一種である。このようなハイデガーに関する観察とマックス・シェーラーに対する批判は、フッサールが 1931年にフランクフルト、ベルリン、ハレのカント協会で行った講演『現象学と人間学』に盛り込まれた。 ハイデガーの主要著作『存在と時間』(1927年初版)の戦時中の1941年版では、フッサールへの献辞は削除された。これは2人の哲学者の関係を否定し たためではなく、むしろ、ナチス政権によって本が発禁になることを恐れたハイデガーの出版社が検閲を勧めた結果であった。献辞は、38ページの脚注に、 フッサールへの感謝の意とともに今でも見ることができる。フッサールは3年前に亡くなっていた。戦後の『存在と時間』では、フッサールへの献辞が復活して いる。フッサールとハイデガーの複雑で、問題の多い、断絶した哲学上の関係は広く議論されてきた。[53][55] 1933年5月4日、エドムント・フッサール教授は、ドイツにおける最近の政権交代とその結果について次のように述べた。 1933年の真のドイツ、真のドイツ人とは誰であったのかは、未来だけが判断するだろう。当時の多かれ少なかれ唯物論的・神話的な人種的偏見に賛同する者なのか、それとも、過去の偉大なドイツ人の伝統を敬い、受け継ぐ心身ともに純粋なドイツ人なのか、と。[56] 彼の死後、ガベルスベルガー速記による約4万ページに及ぶ原稿と、彼の研究図書館のすべてが、フランシスコ会の神父ヘルマン・ファン・ブレダによって、 1939年にベルギーのルーヴェン・カトリック大学に密輸された。そこでは、高等哲学研究所のフッサール文書館に保管された。[57] 彼の研究原稿の資料の多くは、それ以来、フッサリアナ批判版シリーズで出版されている。[58] |
| Development of his thought Several early themes In his first works, Husserl combined mathematics, psychology, and philosophy with the goal of providing a sound foundation for mathematics. He analyzed the psychological process needed to obtain the concept of number and then built up a theory on this analysis. He used methods and concepts taken from his teachers. From Weierstrass he derived the idea of generating the concept of number by counting a certain collection of objects. From Brentano and Stumpf he took the distinction between proper and improper presenting.[59]: 159 In an example, Husserl explained this in the following way: if someone is standing in front of a house, they have a proper, direct presentation of that house, but if they are looking for it and ask for directions, then these directions (e.g. the house on the corner of this and that street) are an indirect, improper presentation. In other words, the person can have a proper presentation of an object if it is actually present, and an improper (or symbolic, as Husserl also calls it) one if they only can indicate that object through signs, symbols, etc. Husserl's Logical Investigations (1900–1901) is considered the starting point for the formal theory of wholes and their parts known as mereology.[60] Another important element that Husserl took over from Brentano was intentionality, the notion that the main characteristic of consciousness is that it is always intentional. While often simplistically summarised as "aboutness" or the relationship between mental acts and the external world, Brentano defined it as the main characteristic of mental phenomena, by which they could be distinguished from physical phenomena. Every mental phenomenon, every psychological act, has a content, is directed at an object (the intentional object). Every belief, desire, etc. has an object that it is about: the believed, the wanted. Brentano used the expression "intentional inexistence" to indicate the status of the objects of thought in the mind. The property of being intentional, of having an intentional object, was the key feature to distinguish mental phenomena and physical phenomena, because physical phenomena lack intentionality altogether.[61] The elaboration of phenomenology Some years after the 1900–1901 publication of his main work, the Logische Untersuchungen (Logical Investigations), Husserl made some key conceptual elaborations which led him to assert that to study the structure of consciousness, one would have to distinguish between the act of consciousness[62] and the phenomena at which it is directed (the objects as intended). Knowledge of essences would only be possible by "bracketing" all assumptions about the existence of an external world. This procedure he called "epoché". These new concepts prompted the publication of the Ideen (Ideas) in 1913, in which they were at first incorporated, and a plan for a second edition of the Logische Untersuchungen. From the Ideen onward, Husserl concentrated on the ideal, essential structures of consciousness. The metaphysical problem of establishing the reality of what people perceive, as distinct from the perceiving subject, was of little interest to Husserl in spite of his being a transcendental idealist. Husserl proposed that the world of objects—and of ways in which people direct themselves toward and perceive those objects—is normally conceived of in what he called the "natural attitude", which is characterized by a belief that objects exist distinct from the perceiving subject and exhibit properties that people see as emanating from them (this attitude is also called physicalist objectivism). Husserl proposed a radical new phenomenological way of looking at objects by examining how people, in their many ways of being intentionally directed toward them, actually "constitute" them (to be distinguished from materially creating objects or objects merely being figments of the imagination); in the Phenomenological standpoint, the object ceases to be something simply "external" and ceases to be seen as providing indicators about what it is, and becomes a grouping of perceptual and functional aspects that imply one another under the idea of a particular object or "type". The notion of objects as real is not expelled by phenomenology, but "bracketed" as a way in which people regard objects—instead of a feature that inheres in an object's essence founded in the relation between the object and the perceiver. To better understand the world of appearances and objects, phenomenology attempts to identify the invariant features of how objects are perceived and pushes attributions of reality into their role as an attribution about the things people perceive (or an assumption underlying how people perceive objects). The major dividing line in Husserl's thought is the turn to transcendental idealism.[63] In a later period, Husserl began to wrestle with the complicated issues of intersubjectivity, specifically, how communication about an object can be assumed to refer to the same ideal entity (Cartesian Meditations, Meditation V). Husserl tries new methods of bringing his readers to understand the importance of phenomenology to scientific inquiry (and specifically to psychology) and what it means to "bracket" the natural attitude. The Crisis of the European Sciences is Husserl's unfinished work that deals most directly with these issues. In it, Husserl for the first time attempts a historical overview of the development of Western philosophy and science, emphasizing the challenges presented by their increasingly one-sidedly empirical and naturalistic orientation. Husserl declares that mental and spiritual reality possess their own reality independent of any physical basis,[64] and that a science of the mind ('Geisteswissenschaft') must be established on as scientific a foundation as the natural sciences have managed: "It is my conviction that intentional phenomenology has for the first time made spirit as spirit the field of systematic scientific experience, thus effecting a total transformation of the task of knowledge."[65] |
彼の思想の発展 初期のテーマのいくつか 彼の初期の作品において、フッサールは数学、心理学、哲学を融合させ、数学の確固たる基礎を提供することを目標としていた。彼は数の概念を得るために必要 な心理的過程を分析し、その分析に基づいて理論を構築した。彼は師から学んだ方法や概念を用いた。ワイエルシュトラスからは、ある物体の集合を数えること で数の概念を生み出すという考え方を導き出した。ブレンターノとシュトゥンプフから、適切な提示と不適切な提示の区別を取り入れた。[59]:159 例として、フッサールは次のように説明している。誰かが家の前に立っている場合、その家を適切に直接的に提示していることになるが、その家を探していて道 を尋ねている場合、その道順(例えば、この通りとあの通りの角にある家)は間接的で不適切な提示である。言い換えれば、対象が実際に存在している場合は、 その対象を適切に提示することができ、対象が記号やシンボルなどを通して示される場合のみでは、不適切な(あるいは、フッサールが「象徴」とも呼ぶ)提示 となる。フッサールの『論理的研究』(1900年-1901年)は、ミレオロジーとして知られる全体とその部分の形式理論の出発点とみなされている。 フッサールがブレンターノから引き継いだもう一つの重要な要素は、意識の主な特徴は常に意図的であるという考え方である「志向性」である。 しばしば単純に「aboutness」または心的作用と外部世界との関係として要約されるが、ブレンターノはそれを心的現象の主な特徴として定義し、それ によって心的現象は物理現象と区別されるとした。 あらゆる心的現象、あらゆる心理的行為には内容があり、対象(志向対象)に向けられている。信念、欲望など、あらゆるものは対象を持っている。すなわち、 信念の対象、欲望の対象である。ブレターノは、心の思考の対象の状態を示すために「意図的な非存在」という表現を用いた。意図的であること、意図的な対象 を持つことは、心的現象と物理現象を区別する重要な特徴であった。なぜなら、物理現象には意図性がまったく欠けているからである。 現象学の精緻化 1900年から1901年にかけて発表された主要著作『論理的研究』の数年後、フッサールは意識の構造を研究するには、意識の作用と、意識が向けられる現 象(意図された対象)とを区別しなければならないと主張するに至る、いくつかの重要な概念的精緻化を行った。本質に関する知識は、外部世界の存在に関する あらゆる想定を「括弧で囲む」ことによってのみ可能となる。この手順を彼は「エポケー」と呼んだ。これらの新しい概念は、1913年に『イデーン (Ideen)』として出版され、当初はそこに組み込まれた。また、『論理的研究』の第2版の計画も立てられた。 『イデーン』以降、フッサールは意識の理想的な本質的構造に集中した。 人々が知覚するものの現実性を確立するという形而上学的な問題は、知覚する主体とは区別されるものとして、超越論的観念論者であったにもかかわらず、フッ サールにとってはほとんど関心が持たれなかった。フッサールは、物体の世界、そして人々がそれらの物体に向かい、それらを知覚する方法は、通常、彼が「自 然態」と呼ぶものとして考えられていると提案した。この態度は、物体が知覚する主体とは別個に存在し、そこから発せられていると人々が認識する性質を示す という信念によって特徴づけられる(この態度は、物理主義的客観主義とも呼ばれる)。フッサールは、人々がさまざまな方法で意図的に対象に向かう際に、実 際にそれらを「構成」する方法を検証することで、対象を観察する根本的に新しい現象学的な方法を提案した(物質的に対象を創造することや、対象が単に想像 の産物であることとは区別される)。現象学的観点では、対象は単なる「外部」のものではなくなり、それが何であるかを示す指標として見られることもなくな る。そして、特定の対象または「タイプ」という概念の下で、互いを暗示する知覚的および機能的な側面の集合体となる。現象学によって物体の実在という概念 が排除されるわけではなく、物体と知覚者の関係に根ざす物体の本質に内在する特徴ではなく、人々が物体をどう見るかという方法として「括弧で囲む」のであ る。現象学は、物や外見の世界をよりよく理解するために、物に対する知覚の不変の特徴を特定しようとし、現実性の帰属を、人々が知覚する物に関する帰属 (または、人々が物を知覚する方法の基礎となる仮定)として位置づけようとする。フッサールの思想における主な分岐点は、超越論的観念論への転換である。 後年、フッサールは、特に、対象物に関するコミュニケーションがどのようにして同一の理想的な実体(『デカルト的省察』第5省察)を参照していると想定で きるかという、主観性の複雑な問題に取り組むようになった。フッサールは、読者に科学的な探究(特に心理学)における現象学の重要性を理解させ、自然な態 度を「括弧に入れる」とは何を意味するのかを理解させるための新しい方法を試みている。『ヨーロッパ科学の危機』は、これらの問題に最も直接的に取り組ん だフッサールの未完の作品である。この中で、フッサールは初めて西洋哲学と科学の発展の歴史的概観を試み、その一方的な経験主義的・自然主義的傾向がもた らした課題を強調している。フッサールは、精神と霊魂の現実には、物理的な基盤とは無関係に独自の現実があるとし[64]、自然科学が成し遂げたのと同様 に科学的基盤の上に心の科学(「精神科学」)を確立しなければならないと主張した。「意図的現象学は、精神を精神として初めて体系的な科学的経験の分野と し、それによって知識の課題を完全に変革したと、私は確信している」[65] |
| Husserl's thought Further information: Phenomenology (philosophy) Husserl's thought is revolutionary in several ways, most notably in the distinction between "natural" and "phenomenological" modes of understanding. In the former, sense-perception in correspondence with the material realm constitutes the known reality, and understanding is premised on the accuracy of the perception and the objective knowability of what is called the "real world".[66] Phenomenological understanding strives to be rigorously "presuppositionless" by means of what Husserl calls "phenomenological reduction".[67] This reduction is not conditioned but rather transcendental: in Husserl's terms, pure consciousness of absolute Being.[68] In Husserl's work, consciousness of any given thing calls for discerning its meaning as an "intentional object".[69] Such an object does not simply strike the senses, to be interpreted or misinterpreted by mental reason; it has already been selected and grasped, grasping being an etymological connotation, of percipere, the root of "perceive".[70] Meaning and object From Logical Investigations (1900/1901) to Experience and Judgment (published in 1939), Husserl expressed clearly the difference between meaning and object. He identified several different kinds of names. For example, there are names that have the role of properties that uniquely identify an object. Each of these names expresses a meaning and designates the same object.[71] Examples of this are "the victor in Jena" and "the loser in Waterloo", or "the equilateral triangle" and "the equiangular triangle"; in both cases, both names express different meanings, but designate the same object. There are names which have no meaning, but have the role of designating an object: "Aristotle", "Socrates", and so on. Finally, there are names which designate a variety of objects. These are called "universal names"; their meaning is a "concept" and refers to a series of objects (the extension of the concept). The way people know sensible objects is called "sensible intuition". Husserl also identifies a series of "formal words" which are necessary to form sentences and have no sensible correlates. Examples of formal words are "a", "the", "more than", "over", "under", "two", "group", and so on. Every sentence must contain formal words to designate what Husserl calls "formal categories". There are two kinds of categories: meaning categories and formal-ontological categories. Meaning categories relate judgments; they include forms of conjunction, disjunction, forms of plural, among others. Formal-ontological categories relate objects and include notions such as set, cardinal number, ordinal number, part and whole, relation, and so on. The way people know these categories is through a faculty of understanding called "categorial intuition". Through sensible intuition, consciousness constitutes what Husserl calls a "situation of affairs" (Sachlage). It is a passive constitution where objects themselves are presented. To this situation of affairs, through categorial intuition, people are able to constitute a "state of affairs" (Sachverhalt). One situation of affairs through objective acts of consciousness (acts of constituting categorially) can serve as the basis for constituting multiple states of affairs. For example, suppose a and b are two sensible objects in a certain situation of affairs. It can be used as the basis to say, "a<b" and "b>a", two judgments which designate the same state of affairs. For Husserl a sentence has a proposition or judgment as its meaning, and refers to a state of affairs which has a situation of affairs as a reference base.[72]: 35 Formal and regional ontology Husserl sees ontology as a science of essences.[73] Sciences of essences are contrasted with factual sciences: the former are knowable a priori and provide the foundation for the later, which are knowable a posteriori.[74][75] Ontology as a science of essences is not interested in actual facts, but in the essences themselves, whether they have instances or not.[76] Husserl distinguishes between formal ontology, which investigates the essence of objectivity in general,[77] and regional ontologies, which study regional essences that are shared by all entities belonging to the region.[73] Regions correspond to the highest genera of concrete entities: material nature, personal consciousness and interpersonal spirit.[78][79] Husserl's method for studying ontology and sciences of essence in general is called eidetic variation.[75] It involves imagining an object of the kind under investigation and varying its features.[80] The changed feature is inessential to this kind if the object can survive its change, otherwise it belongs to the kind's essence. For example, a triangle remains a triangle if one of its sides is extended but it ceases to be a triangle if a fourth side is added. Regional ontology involves applying this method to the essences corresponding to the highest genera.[81] Philosophy of logic and mathematics Husserl believed that truth-in-itself has as ontological correlate being-in-itself, just as meaning categories have formal-ontological categories as correlates. Logic is a formal theory of judgment, that studies the formal a priori relations among judgments using meaning categories. Mathematics, on the other hand, is formal ontology; it studies all the possible forms of being (of objects). Hence for both logic and mathematics, the different formal categories are the objects of study, not the sensible objects themselves. The problem with the psychological approach to mathematics and logic is that it fails to account for the fact that this approach is about formal categories, and not simply about abstractions from sensibility alone. The reason why sensible objects are not dealt with in mathematics is because of another faculty of understanding called "categorial abstraction." Through this faculty people are able to get rid of sensible components of judgments, and just focus on formal categories themselves. Thanks to "eidetic reduction" (or "essential intuition"), people are able to grasp the possibility, impossibility, necessity and contingency among concepts and among formal categories. Categorial intuition, along with categorial abstraction and eidetic reduction, are the basis for logical and mathematical knowledge. Husserl criticized the logicians of his day for not focusing on the relation between subjective processes that offer objective knowledge of pure logic. All subjective activities of consciousness need an ideal correlate, and objective logic (constituted noematically) as it is constituted by consciousness needs a noetic correlate (the subjective activities of consciousness). Husserl stated that logic has three strata, each further away from consciousness and psychology than those that precede it. The first stratum is what Husserl called a "morphology of meanings" concerning a priori ways to relate judgments to make them meaningful. In this stratum people elaborate a "pure grammar" or a logical syntax, and he would call its rules "laws to prevent non-sense", which would be similar to what logic calls today "formation rules". Mathematics, as logic's ontological correlate, also has a similar stratum, a "morphology of formal-ontological categories". The second stratum would be called by Husserl "logic of consequence" or the "logic of non-contradiction" which explores all possible forms of true judgments. He includes here syllogistic classic logic, propositional logic and that of predicates. This is a semantic stratum, and the rules of this stratum would be the "laws to avoid counter-sense" or "laws to prevent contradiction". They are very similar to today's logic "transformation rules". Mathematics also has a similar stratum which is based among others on pure theory of pluralities, and a pure theory of numbers. They provide a science of the conditions of possibility of any theory whatsoever. Husserl also talked about what he called "logic of truth" which consists of the formal laws of possible truth and its modalities, and precedes the third logical third stratum. The third stratum is metalogical, what he called a "theory of all possible forms of theories." It explores all possible theories in an a priori fashion, rather than the possibility of theory in general. Theories of possible relations between pure forms of theories could be established; these logical relations could in turn be investigated using deduction. The logician is free to see the extension of this deductive, theoretical sphere of pure logic. The ontological correlate to the third stratum is the "theory of manifolds". In formal ontology, it is a free investigation where a mathematician can assign several meanings to several symbols, and all their possible valid deductions in a general and indeterminate manner. It is, properly speaking, the most universal mathematics of all. Through the posit of certain indeterminate objects (formal-ontological categories) as well as any combination of mathematical axioms, mathematicians can explore the apodeictic connections between them, as long as consistency is preserved. According to Husserl, this view of logic and mathematics accounted for the objectivity of a series of mathematical developments of his time, such as n-dimensional manifolds (both Euclidean and non-Euclidean), Hermann Grassmann's theory of extensions, William Rowan Hamilton's Hamiltonians, Sophus Lie's theory of transformation groups, and Cantor's set theory. Jacob Klein was one student of Husserl who pursued this line of inquiry, seeking to "desedimentize" mathematics and the mathematical sciences.[82] |
フッサールの思想 詳細情報:現象学(哲学). フッサールの思想は、いくつかの点で革新的であるが、とりわけ「自然」と「現象学的」な理解の方法の区別において顕著である。前者の場合、物質界に対応す る感覚知覚が既知の現実を構成し、理解は知覚の正確性と「現実世界」と呼ばれるものの客観的な知覚可能性を前提としている。[66] 現象学的理解は、フッサールが「現象学的還元」と呼ぶ手段によって厳密に「前提のない」ものとなるよう努める。[67] この還元は条件付けられたものではなく、むしろ超越的なものである。フッサール流に言えば、 絶対的な存在の純粋意識である。[68] フッサールの研究では、意識は与えられたものについて、それが「志向対象」として持つ意味を識別することを求める。[69] このような対象は、感覚に単純に訴えかけるものではなく、精神的な理性によって解釈されたり誤解釈されたりするものでもない。それはすでに選択され、把握 されているものであり、把握するということは、perceiveの語源であるpercipereの語源的な含意である。[70] 意味と対象 『論理的研究』(1900/1901年)から『経験と判断』(1939年)まで、フッサールは意味と対象の違いを明確に表現した。彼はいくつかの異なる種 類の名称を特定した。例えば、ある対象を唯一に特定する性質としての役割を持つ名称がある。これらの名称はそれぞれ意味を表現し、同一の対象を指し示す。 [71] その例としては、「イエナの勝利者」と「ワーテルローの敗者」、あるいは「正三角形」と「等角三角形」などがある。いずれの場合も、両方の名称は異なる意 味を表現しているが、同一の対象を指し示している。意味を持たないが、対象を指し示す役割を持つ名称もある。例えば、「アリストテレス」、「ソクラテス」 などである。最後に、さまざまな対象を指し示す名称もある。これらは「普遍名称」と呼ばれ、その意味は「概念」であり、一連の対象(概念の拡張)を指し示 す。人々が感覚的な対象を知覚する方法は「感覚的直観」と呼ばれる。 また、フッサールは、文章を構成するために必要であり、感覚的な相関関係を持たない「形式語」の系列も特定している。形式語の例としては、「a」、 「the」、「more than」、「over」、「under」、「two」、「group」などがある。すべての文章は、フッサールが「形式範疇」と呼ぶものを指定するため に、形式語を含まなければならない。カテゴリーには2種類あり、意味カテゴリーと形式存在論カテゴリーである。意味カテゴリーは判断に関連し、接続、選 択、複数形などの形式を含む。形式存在論カテゴリーは対象に関連し、集合、基数、序数、部分と全体、関係などの概念を含む。人々がこれらのカテゴリーを知 覚する方法は、「範疇直観」と呼ばれる理解力による。 感覚的直観を通じて、意識はフッサールが「状況(Sachlage)」と呼ぶものを構成する。これは、対象そのものが提示される受動的な構成である。この 状況に対して、範疇的直観を通じて、人は「状態(Sachverhalt)」を構成することができる。意識の客観的行為(範疇的構成行為)を通じて得られ る一つの状況は、複数の状態を構成するための基礎として役立つ。例えば、aとbが、ある状況における2つの感覚可能な対象であると仮定する。これは、 「a<b」と「b>a」という2つの判断、つまり同じ状況を指し示す2つの判断の基礎として使用できる。フッサールにとって、文は命題または 判断を意味として持ち、状況を参照ベースとして持つ状況の状態を参照する。[72]: 35 形式および地域的実在論 フッサールは、実在論を本質の科学と見なしている。[73] 本質の科学は事実科学と対比される。前者は先験的に認識可能であり、後者の基礎を提供する。後者は後天的に認識可能である。[74][75] 本質の科学としての実在論は、実際の事実ではなく、本質そのものに関心がある。それらが実例を持つかどうかに関わらず、本質そのものに興味を持っている。 [76] フッサールは、客観性の本質を一般的に調査する形式存在論と、ある領域に属するすべての実体によって共有される地域的な本質を調査する地域存在論を区別し ている。[73] 地域は、具体的な実体の最高範疇である物質的自然、個人的意識、対人精神に対応する。[ 78][79] 存在学や本質科学一般を研究するためのフッサールの方法は、エイドス的変化と呼ばれる。[75] それは、調査対象の種類の対象を想像し、その特徴を変化させることを含む。[80] 対象がその変化を生き延びることができる場合、変化した特徴はこの種類にとって本質的ではない。そうでなければ、それはその種類のエッセンスに属する。例 えば、三角形は、その辺の1つが延長されても三角形のままであるが、4番目の辺が追加されると三角形ではなくなる。 地域存在論では、この方法を最高範疇に対応する本質に適用する。 論理学と数学の哲学 フッサールは、真実そのものには存在論的な相関関係として存在そのものがあると考えた。意味カテゴリーには形式存在論的なカテゴリーが相関関係として存在 するのと同様である。論理学は判断の形式理論であり、意味カテゴリーを使用して判断間の形式的な先験的関係を研究する。一方、数学は形式存在論であり、存 在(対象)のあり得るすべての形式を研究する。したがって、論理学と数学の両方において、研究対象となるのは異なる形式カテゴリーであり、感覚的な対象そ のものではない。数学と論理学に対する心理学的なアプローチの問題点は、このアプローチが形式カテゴリーに関するものであり、感覚からの単純な抽象化では ないという事実を説明できないことである。感覚的な対象が数学で扱われない理由は、「範疇的抽象」と呼ばれる別の理解能力によるものである。この能力に よって、人は判断の感覚的な要素を取り除き、形式的なカテゴリーそのものにのみ集中することができる。 「エイドス(直観)」による還元(または「本質的直観」)により、人は概念や形式的なカテゴリーにおける可能性、不可能性、必然性、偶然性を把握することができる。カテゴリー直観は、カテゴリー抽象やエイドス還元とともに、論理的および数学的知識の基礎となる。 フッサールは、純粋論理の客観的知識を提供する主観的プロセス間の関係に焦点を当てていないとして、当時の論理学者たちを批判した。意識のすべての主観的 活動には理想的な相関関係が必要であり、意識によって構成される客観的論理には、ノエマティックな相関関係(意識の主観的活動)が必要である。 フッサールは、論理には3つの層があり、その層は意識や心理学から離れるほど、前の層から離れていると述べた。 最初の層は、判断に意味を持たせるための先験的な関連付け方法に関する、フッサールが「意味の形而上学」と呼んだものである。この層において、人々は「純 粋文法」または論理構文を構築し、その規則を「無意味を防ぐ法則」と呼ぶ。これは、今日論理学で「形成規則」と呼ばれるものに類似している。数学は論理学 の存在論的相関物として、同様の層、「形式存在論的カテゴリーの形態論」も有している。 第二の層は、フッサールによって「帰結の論理」または「非矛盾の論理」と呼ばれ、真の判断のあり得るすべての形式を探究する。 彼は、三段論法、命題論理、述語論理をここに含めている。 これは意味論的な層であり、この層の規則は「非意味を回避する法則」または「矛盾を回避する法則」である。 これらは今日の論理における「変換規則」と非常に類似している。数学にも同様の層があり、それは純粋多数理論や純粋数理論などに基づいている。これらは、 あらゆる理論の可能性の条件に関する科学を提供する。フッサールはまた、可能的な真理の形式法則とその様態から成る「真理の論理」について語っており、そ れは3番目の論理層よりも上位にある。 3番目の層はメタ論理的なものであり、彼が「理論のあらゆる可能性の形の理論」と呼ぶものである。それは、理論一般の可能性というよりも、先験的な方法 で、あり得るすべての理論を探求する。理論の純粋な形式間のあり得る関係についての理論を確立することができ、これらの論理関係は、演繹法を用いて調査す ることができる。論理学者は、純粋論理の演繹的かつ理論的なこの領域の拡張を自由に考えることができる。 存在論における第3層相の相関は、「多様体の理論」である。形式存在論では、数学者はいくつかの記号にいくつかの意味を割り当てることができ、それらの記 号のすべての可能な妥当な推論を一般的な不確定な方法で導くことができる。 厳密に言えば、これは最も普遍的な数学である。 数学者は、ある不確定な対象(形式存在論のカテゴリー)と数学的公理のあらゆる組み合わせを仮定することで、一貫性が保たれる限り、それらの間の無前提の 関係を探究することができる。 フッサールによれば、この論理と数学の考え方は、彼が当時研究していた一連の数学的発展、例えばn次元多様体(ユークリッドおよび非ユークリッド)、ヘル マン・グラスマンの拡張理論、ウィリアム・ローワン・ハミルトンのハミルトニアン、ソフス・リー群の変換理論、カントールの集合論などの客観性を説明でき る。 ヤコブ・クラインは、数学と数理科学の「脱堆積」を求め、この研究を追求したフッサールの教え子の一人であった。[82] |
| Husserl and psychologism Philosophy of arithmetic and Frege After obtaining his PhD in mathematics, Husserl began analyzing the foundations of mathematics from a psychological point of view. In his habilitation thesis, On the Concept of Number (1886) and in his Philosophy of Arithmetic (1891), Husserl sought, by employing Brentano's descriptive psychology, to define the natural numbers in a way that advanced the methods and techniques of Karl Weierstrass, Richard Dedekind, Georg Cantor, Gottlob Frege, and other contemporary mathematicians. Later, in the first volume of his Logical Investigations, the Prolegomena of Pure Logic, Husserl, while attacking the psychologistic point of view in logic and mathematics, also appears to reject much of his early work, although the forms of psychologism analysed and refuted in the Prolegomena did not apply directly to his Philosophy of Arithmetic. Some scholars question whether Frege's negative review of the Philosophy of Arithmetic helped turn Husserl towards modern Platonism, but he had already discovered the work of Bernard Bolzano independently around 1890/91.[83] In his Logical Investigations, Husserl explicitly mentioned Bolzano, G. W. Leibniz and Hermann Lotze as inspirations for his newer position. Husserl's review of Ernst Schröder, published before Frege's landmark 1892 article, clearly distinguishes sense from reference; thus Husserl's notions of noema and object also arose independently.[29] Likewise, in his criticism of Frege in the Philosophy of Arithmetic, Husserl remarks on the distinction between the content and the extension of a concept. Moreover, the distinction between the subjective mental act, namely the content of a concept, and the (external) object, was developed independently by Brentano and his school, and may have surfaced as early as Brentano's 1870s lectures on logic. Scholars such as J. N. Mohanty, Claire Ortiz Hill, and Guillermo E. Rosado Haddock, among others, have argued that Husserl's so-called change from psychologism to Platonism came about independently of Frege's review.[84][85]: 253–262 For example, the review falsely accuses Husserl of subjectivizing everything, so that no objectivity is possible, and falsely attributes to him a notion of abstraction whereby objects disappear until all that remains are numbers as mere ghosts.[citation needed] Contrary to what Frege states, in Husserl's Philosophy of Arithmetic there are already two different kinds of representations: subjective and objective. Moreover, objectivity is clearly defined in that work. Frege's attack seems to be directed at certain foundational doctrines then current in Weierstrass's Berlin School, of which Husserl and Cantor cannot be said to be orthodox representatives. Furthermore, various sources indicate that Husserl changed his mind about psychologism as early as 1890, a year before he published the Philosophy of Arithmetic. Husserl stated that by the time he published that book, he had already changed his mind—that he had doubts about psychologism from the very outset. He attributed this change of mind to his reading of Leibniz, Bolzano, Lotze, and David Hume.[86] Husserl makes no mention of Frege as a decisive factor in this change. In his Logical Investigations, Husserl mentions Frege only twice, once in a footnote to point out that he had retracted three pages of his criticism of Frege's The Foundations of Arithmetic, and again to question Frege's use of the word Bedeutung to designate "reference" rather than "meaning" (sense). In a letter dated 24 May 1891, Frege thanked Husserl for sending him a copy of the Philosophy of Arithmetic and Husserl's review of Ernst Schröder's Vorlesungen über die Algebra der Logik. In the same letter, Frege used the review of Schröder's book to analyze Husserl's notion of the sense of reference of concept words. Hence Frege recognized, as early as 1891, that Husserl distinguished between sense and reference. Consequently, Frege and Husserl independently elaborated a theory of sense and reference before 1891. Commentators argue that Husserl's notion of noema has nothing to do with Frege's notion of sense, because noemata are necessarily fused with noeses which are the conscious activities of consciousness. Noemata have three different levels: The substratum, which is never presented to the consciousness, and is the support of all the properties of the object; The noematic senses, which are the different ways the objects are presented to us; The modalities of being (possible, doubtful, existent, non-existent, absurd, and so on). Consequently, in intentional activities, even non-existent objects can be constituted, and form part of the whole noema. Frege, however, did not conceive of objects as forming parts of senses: If a proper name denotes a non-existent object, it does not have a reference, hence concepts with no objects have no truth value in arguments. Moreover, Husserl did not maintain that predicates of sentences designate concepts. According to Frege the reference of a sentence is a truth value; for Husserl it is a "state of affairs." Frege's notion of "sense" is unrelated to Husserl's noema, while the latter's notions of "meaning" and "object" differ from those of Frege. In detail, Husserl's conception of logic and mathematics differs from that of Frege, who held that arithmetic could be derived from logic. For Husserl this is not the case: mathematics (with the exception of geometry) is the ontological correlate of logic, and while both fields are related, neither one is strictly reducible to the other. Husserl's criticism of psychologism Reacting against authors such as John Stuart Mill, Christoph von Sigwart and his own former teacher Brentano, Husserl criticised their psychologism in mathematics and logic, i.e. their conception of these abstract and a priori sciences as having an essentially empirical foundation and a prescriptive or descriptive nature.[87] According to psychologism, logic would not be an autonomous discipline, but a branch of psychology, either proposing a prescriptive and practical "art" of correct judgement (as Brentano and some of his more orthodox students did)[88] or a description of the factual processes of human thought. Husserl pointed out that the failure of anti-psychologists to defeat psychologism was a result of being unable to distinguish between the foundational, theoretical side of logic, and the applied, practical side. Pure logic does not deal at all with "thoughts" or "judgings" as mental episodes but about a priori laws and conditions for any theory and any judgments whatsoever, conceived as propositions in themselves. "Here 'Judgement' has the same meaning as 'proposition', understood, not as a grammatical, but as an ideal unity of meaning. This is the case with all the distinctions of acts or forms of judgement, which provide the foundations for the laws of pure logic. Categorial, hypothetical, disjunctive, existential judgements, and however else we may call them, in pure logic are not names for classes of judgements, but for ideal forms of propositions."[89] Since "truth-in-itself" has "being-in-itself" as ontological correlate, and since psychologists reduce truth (and hence logic) to empirical psychology, the inevitable consequence is scepticism. Psychologists have not been successful either in showing how induction or psychological processes can justify the absolute certainty of logical principles, such as the principles of identity and non-contradiction. It is therefore futile to base certain logical laws and principles on uncertain processes of the mind. This confusion made by psychologism (and related disciplines such as biologism and anthropologism) can be due to three specific prejudices: 1. The first prejudice is the supposition that logic is somehow normative in nature. Husserl argues that logic is theoretical, i.e., that logic itself proposes a priori laws which are themselves the basis of the normative side of logic. Since mathematics is related to logic, he cites an example from mathematics: a formula like "(a + b)(a – b) = a² – b²" does not offer any insight into how to think mathematically. It just expresses a truth. A proposition that says: "The product of the sum and the difference of a and b should give the difference of the squares of a and b" does express a normative proposition, but this normative statement is based on the theoretical statement "(a + b)(a – b) = a² – b²". 2. For psychologists, the acts of judging, reasoning, deriving, and so on, are all psychological processes. Therefore, it is the role of psychology to provide the foundation of these processes. Husserl states that this effort made by psychologists is a "metábasis eis állo génos" (Gr. μετάβασις εἰς ἄλλο γένος, "a transgression to another field").[90]: 344 It is a metábasis because psychology cannot provide any foundations for a priori laws which themselves are the basis for all correct thought. Psychologists have the problem of confusing intentional activities with the object of these activities. It is important to distinguish between the act of judging and the judgment itself, the act of counting and the number itself, and so on. Counting five objects is undeniably a psychological process, but the number 5 is not. 3. Judgments can be true or not true. Psychologists argue that judgments are true because they become "evidently" true to us.[91]: 261 This evidence, a psychological process that "guarantees" truth, is indeed a psychological process. Husserl responds by saying that truth itself, as well as logical laws, always remain valid regardless of psychological "evidence" that they are true. No psychological process can explain the a priori objectivity of these logical truths. From this criticism to psychologism, the distinction between psychological acts and their intentional objects, and the difference between the normative side of logic and the theoretical side, derives from a Platonist conception of logic. This means that logical and mathematical laws should be regarded as being independent of the human mind, and also as an autonomy of meanings. It is essentially the difference between the real (everything subject to time) and the ideal or irreal (everything that is atemporal), such as logical truths, mathematical entities, mathematical truths and meanings in general. |
フッサールと心理主義 算術哲学とフレーゲ 数学の博士号を取得した後、フッサールは心理学的な観点から数学の基礎を分析し始めた。ハビトゥーラント論文『数概念について』(1886年)および『算 術哲学』(1891年)において、フッサールはブレンターノの記述心理学を採用し、カール・ワイエルシュトラス、リヒャルト・デデキント、ゲオルク・カン トール、ゴットロープ・フレーゲ、およびその他の同時代の数学者の方法と技術を前進させるような形で自然数を定義しようとした。その後、著書『論理的研 究』の第1巻『純粋論理学のプロレゲメーナ』において、フッサールは論理学と数学における心理主義的な観点に異議を唱える一方で、自身の初期の研究の多く を否定しているように見える。ただし、『プロレゲメーナ』で分析され、反駁された心理主義の形態は、フッサールの『算術哲学』には直接当てはまらない。フ レーゲによる『算術の哲学』の否定的な書評が、フッサールを近代プラトン主義へと向かわせたのではないかという疑問を呈する学者もいるが、フッサールは 1890年から1891年頃にすでにベルンハルト・ボルツァーノの研究を独自に行っていた。[83] フッサールは『論理的研究』の中で、ボルツァーノ、G.W.ライプニッツ、ヘルマン・ロッツェを、自身の新しい立場へのインスピレーションとして明確に挙 げている。 フレーゲの画期的な1892年の論文が発表される前に発表された、フッサールのエルンスト・シュレーダーの批評では、感覚と参照を明確に区別している。し たがって、フッサールのノエマと対象の概念も独自に生じたものである。[29] 同様に、『算術の哲学』におけるフレーゲの批判において、フッサールは概念の内容と拡張の区別について言及している。さらに、主観的な精神作用、すなわち 概念の内容と、(外部の)対象との区別は、ブレンターノとその一派によって独自に発展し、ブレンターノが1870年代に行った論理学の講義で早くも表面化 していた可能性がある。 J. N. モハンティ、クレア・オルティス・ヒル、ギジェルモ・E・ロサド・ハドックなどの学者は、フッサールのいわゆる心理主義からプラトン主義への転換は、フ リーゲのレビューとは無関係に起こったと主張している。[84][85]:253–262 例えば、このレビューは フッサールがすべてを主観化し、客観性が不可能であると誤って非難し、また、対象が消え去り、残るのは単なる幽霊のような数字だけになるような抽象概念を 彼に帰属させている。[要出典] フレーゲの主張とは逆に、フッサールの『算術の哲学』にはすでに主観的および客観的という2つの異なる種類の表現が存在している。さらに、客観性は同著の 中で明確に定義されている。フレーゲの攻撃は、ワイエルシュトラスのベルリン学派で当時主流であった特定の基礎的教義に向けられたものであり、フッサール やカントールは正統派の代表者とは言えない。 さらに、さまざまな資料によると、フッサールは心理主義に対する考えを1890年にはすでに変えており、これは『算術の哲学』を出版する1年前のことであ る。フッサールは、その本を出版した時点ではすでに考えを変えており、当初から心理主義に疑問を抱いていたと述べている。彼は、この考えの変化はライプ ニッツ、ボルツァーノ、ロッツェ、デイヴィッド・ヒュームの研究によるものだと述べている。[86] フッサールは、この変化の決定的な要因としてフリーゲについて言及していない。フッサールは『論理的研究』の中で、フレーゲについて2度言及している。1 度目は、フレーゲの著書『算術の基礎』に対する批判の3ページを撤回したことを指摘する脚注の中で、もう1度目は、フレーゲが「意味」ではなく「参照」を 意味する言葉として「Bedeutung」を使用したことを疑問視する中でである。 1891年5月24日付の手紙で、フレーゲはヒュルセルに『算術の哲学』とエルンスト・シュレーダーの『論理学の代数学』のヒュルセルによる書評を送って くれたことに感謝した。同じ手紙の中で、フレーゲはシュレーダーの本の書評を用いて、ヒュルセルの概念語の参照の意味の概念を分析した。したがって、フ レーゲは1891年にはすでに、フッサールが意味と参照を区別していることを認識していた。その結果、フレーゲとフッサールは1891年以前に、それぞれ 独自に意味と参照の理論を練り上げていた。 解説者たちは、ノエマの概念は意識の意識的活動であるノエシスと必然的に融合されるため、フッサールのノエマの概念はフレゲの感覚の概念とは何の関係もないと論じている。ノエマには3つの異なるレベルがある。 意識に提示されることは決してなく、対象のすべての特性の基盤となる基盤、 対象が私たちに提示されるさまざまな方法であるノエマ的感覚、 存在様相(可能、疑わしい、存在、非存在、不合理など)。 したがって、意図的な活動においては、たとえ存在しない対象であっても、ノエマの一部として構成される可能性がある。しかし、フレーゲは、対象が感覚の一 部を形成するという考えを持っていなかった。固有名詞が存在しない対象を指し示す場合、それは参照を持たないため、対象を持たない概念は議論において真偽 値を持たない。さらに、フッサールは、文の述語が概念を指し示すとは考えなかった。フレーゲによれば、文の参照先は真理値であるが、フッサールにとっては 「状況」である。フレーゲの「意味」の概念はフッサールのノエマとは無関係であるが、フッサールの「意味」と「対象」の概念はフレーゲのそれとは異なる。 詳細に述べると、フッサールの論理学と数学の概念は、算術は論理から導き出されると主張したフリーゲのそれとは異なる。フッサールにとっては、これは当て はまらない。数学(幾何学を除く)は論理の存在論的な相関であり、両者は関連しているが、どちらも厳密に他方に還元できるものではない。 フッサールの心理主義批判 ジョン・スチュアート・ミル、クリストフ・フォン・ジークワルト、そして自身の元師であるブレンターノなどの著者たちに反発し、フッサールは彼らの数学と 論理学における心理主義、すなわち、これらの抽象的かつ先験的な科学を本質的に経験的な基盤と規定的または記述的な性質を持つものとして捉える考え方を批 判した。 7] 心理主義によれば、論理学は自律した学問ではなく、心理学の一分野であり、正しい判断の処方的かつ実践的な「芸術」を提唱するもの(ブレターノや、より正 統派の学生の一部がそうであったように)[88]、あるいは人間の思考の事実上のプロセスを記述するものとなる。フッサールは、反心理主義者が心理主義を 打ち負かすことができなかったのは、論理学の基礎的・理論的な側面と応用・実践的な側面を区別できなかったためであると指摘した。純粋な論理学は、心的エ ピソードとしての「思考」や「判断」を一切扱うことはなく、あらゆる理論やあらゆる判断の前提条件となる先験的な法則や条件について、それ自体命題として 考えられるものについてのみ扱う。 「ここで『判断』は『命題』と同じ意味であり、文法的なものではなく、意味の理想的な統一体として理解される。これは、純粋論理学の法則の基礎となる判断 の行為や形式のすべての区別にも当てはまる。範疇的判断、仮言的判断、選言的判断、存在判断、そして純粋論理学では、それらをどのように呼ぶにしても、判 断の分類の名称ではなく、命題の理想的な形式の名称である。」[89] 「真理それ自体」には存在論的な相関関係として「存在それ自体」がある。また、心理学者は真理(そして論理)を経験心理学に還元しているため、必然的な帰 結として懐疑論が生まれる。心理学者は、帰納法や心理的プロセスが、同一性や非矛盾性といった論理原則の絶対的な確実性をどのように正当化できるかを示そ うとして成功していない。したがって、不確かな心のプロセスを基に、特定の論理法則や原則を確立することは無意味である。 心理主義(および生物学主義や人間中心主義などの関連分野)によるこの混乱は、3つの特定の偏見に起因する可能性がある。 1. 最初の偏見は、論理が本質的に規範的であるという仮定である。フッサールは、論理は理論的であると主張する。すなわち、論理自体が先験的な法則を提案し、 それ自体が論理の規範的な側面の基礎となるというのである。数学は論理に関連しているため、彼は数学の例を挙げる。「(a + b)(a – b) = a² – b²」のような公式は、数学的に考える方法について何ら洞察を与えてはくれない。それはただ真理を表現しているだけである。「aとbの和と差の積は、aと bの平方の差を与えるべきである」という命題は規範命題を表現しているが、この規範命題は「(a + b)(a – b) = a² – b²」という理論命題に基づいている。 2. 心理学者にとって、判断、推論、導出などの行為はすべて心理的なプロセスである。したがって、これらのプロセスの基礎を提供することは心理学の役割であ る。フッサールは、心理学者によるこの取り組みを「メタバシス・アイ・アッロ・ゲノス」(Gr. μετάβασις εἰς ἄλλο γένος、「他分野への侵犯」)であると述べている。[90]: 344 心理学は、正しい思考のすべてが基盤としている先験的法則の基盤を提供することができないため、メタバシスである。心理学者は、意図的な活動とそれらの活 動の対象を混同するという問題を抱えている。判断する行為と判断そのもの、数える行為と数そのもの、などを区別することが重要である。5つの物体を数える ことは紛れもなく心理的なプロセスであるが、5という数はそうではない。 3. 判断には真実と真実でないものがある。心理学者は、判断が真実であるのは、それが「明白に」真実となるからだと主張している。[91]: 261 この証拠、つまり真実を「保証する」心理的プロセスは、確かに心理的プロセスである。フッサールは、真理そのものや論理法則は、それが真実であるという心 理的な「証拠」に関わらず、常に有効であると応答している。心理的なプロセスでは、これらの論理的真理のアプリオリな客観性を説明することはできない。 この心理主義への批判から、心理的な行為とその意図的な対象との区別、そして論理の規範的な側面と理論的な側面の違いが、プラトン主義的な論理観から派生 している。つまり、論理法則や数学法則は人間の精神から独立したものであり、また意味の自律性でもあるとみなされるべきである。これは本質的には、現実 (時間に従属するものすべて)と理想または非現実(時間に従属しないものすべて)との違いであり、例えば論理的真理、数学的実体、数学的真理、そして一般 的な意味などである。 |
Influence Husserl's gravestone at Günterstal David Carr commented on Husserl's following in his 1970 dissertation at Yale: "It is well known that Husserl was always disappointed at the tendency of his students to go their own way, to embark upon fundamental revisions of phenomenology rather than engage in the communal task" as originally intended by the radical new science.[92] Notwithstanding, he did attract philosophers to phenomenology. Martin Heidegger is the best known of Husserl's students, the one whom Husserl chose as his successor at Freiburg. Heidegger's magnum opus Being and Time was dedicated to Husserl. They shared their thoughts and worked alongside each other for over a decade at the University of Freiburg, Heidegger being Husserl's assistant during 1920–1923.[93][94][95] Heidegger's early work followed his teacher, but with time he began to develop new insights distinctively variant. Husserl became increasingly critical of Heidegger's work, especially in 1929, and included pointed criticism of Heidegger in lectures he gave during 1931.[96] Heidegger, while acknowledging his debt to Husserl, followed a political position offensive and harmful to Husserl after the Nazis came to power in 1933, Husserl being of Jewish origin and Heidegger infamously being then a Nazi proponent.[97] Academic discussion of Husserl and Heidegger is extensive. At Göttingen in 1913 Adolf Reinach (1884–1917) "was now Husserl's right hand. He was above all the mediator between Husserl and the students, for he understood extremely well how to deal with other persons, whereas Husserl was pretty much helpless in this respect."[98] He was an original editor of Husserl's new journal, Jahrbuch; one of his works (giving a phenomenological analysis of the law of obligations) appeared in its first issue.[99] Reinach was widely admired and a remarkable teacher. Husserl, in his 1917 obituary, wrote, "He wanted to draw only from the deepest sources, he wanted to produce only work of enduring value. And through his wise restraint he succeeded in this."[100] Edith Stein was Husserl's student at Göttingen and Freiburg while she wrote her doctoral thesis The Empathy Problem as it Developed Historically and Considered Phenomenologically (1916). She then became his assistant at Freiburg in 1916–18. She later adapted her phenomenology to the modern school of modern Thomism.[101] Ludwig Landgrebe became assistant to Husserl in 1923. From 1939 he collaborated with Eugen Fink at the Husserl-Archives in Leuven. In 1954 he became leader of the Husserl-Archives. Landgrebe is known as one of Husserl's closest associates, but also for his independent views relating to history, religion and politics as seen from the viewpoints of existentialist philosophy and metaphysics. Eugen Fink was a close associate of Husserl during the 1920s and 1930s. He wrote the Sixth Cartesian Meditation which Husserl said was the truest expression and continuation of his own work. Fink delivered the eulogy for Husserl in 1938.[21] Roman Ingarden, an early student of Husserl at Freiburg, corresponded with Husserl into the mid-1930s. Ingarden did not accept, however, the later transcendental idealism of Husserl which he thought would lead to relativism. Ingarden has written his work in German and Polish. In his Spór o istnienie świata (Ger.: "Der Streit um die Existenz der Welt", Eng.: "Dispute about existence of the world") he created his own realistic position, which also helped to spread phenomenology in Poland. Max Scheler met Husserl in Halle in 1901 and found in his phenomenology a methodological breakthrough for his own philosophy. Scheler, who was at Göttingen when Husserl taught there, was one of the original few editors of the journal Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung (1913). Scheler's work Formalism in Ethics and Nonformal Ethics of Value appeared in the new journal (1913 and 1916) and drew acclaim. The personal relationship between the two men, however, became strained, due to Scheler's legal troubles, and Scheler returned to Munich.[102] Although Scheler later criticised Husserl's idealistic logical approach and proposed instead a "phenomenology of love", he states that he remained "deeply indebted" to Husserl throughout his work. Nicolai Hartmann was once thought to be at the center of phenomenology, but perhaps no longer. In 1921 the prestige of Hartmann the Neo-Kantian, who was Professor of Philosophy at Marburg, was added to the Movement; he "publicly declared his solidarity with the actual work of die Phänomenologie." Yet Hartmann's connections were with Max Scheler and the Munich circle; Husserl himself evidently did not consider him as a phenomenologist. His philosophy, however, is said to include an innovative use of the method.[103] Emmanuel Levinas in 1929 gave a presentation at one of Husserl's last seminars in Freiburg. Also that year he wrote on Husserl's Ideen (1913) a long review published by a French journal. With Gabrielle Peiffer, Levinas translated into French Husserl's Méditations cartésiennes (1931). He was at first impressed with Heidegger and began a book on him, but broke off the project when Heidegger became involved with the Nazis. After the war he wrote on Jewish spirituality; most of his family had been murdered by the Nazis in Lithuania. Levinas then began to write works that would become widely known and admired.[104] Alfred Schutz's Phenomenology of the Social World seeks to rigorously ground Max Weber's interpretive sociology in Husserl's phenomenology. Husserl was impressed by this work and asked Schutz to be his assistant.[105] Jean-Paul Sartre was also largely influenced by Husserl, although he later came to disagree with key points in his analyses. Sartre rejected Husserl's transcendental interpretations begun in his Ideen (1913) and instead followed Heidegger's ontology.[106] Maurice Merleau-Ponty's Phenomenology of Perception is influenced by Edmund Husserl's work on perception, intersubjectivity, intentionality, space,[107] and temporality, including Husserl's theory of retention and protention. Merleau-Ponty's description of 'motor intentionality' and sexuality, for example, retain the important structure of the noetic/noematic correlation of Ideen I, yet further concretize what it means for Husserl when consciousness particularizes itself into modes of intuition. Merleau-Ponty's most clearly Husserlian work is, perhaps, "the Philosopher and His Shadow." Depending on the interpretation of Husserl's accounts of eidetic intuition, given in Husserl's Phenomenological Psychology[108] and Experience and Judgment, it may be that Merleau-Ponty did not accept the "eidetic reduction" nor the "pure essence" said to result.[109] Merleau-Ponty was the first student to study at the Husserl-archives in Leuven. Gabriel Marcel explicitly rejected existentialism, due to Sartre, but not phenomenology, which has enjoyed a wide following among French Catholics. He appreciated Husserl, Scheler, and (but with apprehension) Heidegger.[110] His expressions like "ontology of sensability" when referring to the body, indicate influence by phenomenological thought.[111] Kurt Gödel is known to have read Cartesian Meditations. He expressed very strong appreciation for Husserl's work, especially with regard to "bracketing" or "epoché". Hermann Weyl's interest in intuitionistic logic and impredicativity appears to have resulted from his reading of Husserl. He was introduced to Husserl's work through his wife, Helene Joseph, herself a student of Husserl at Göttingen. Colin Wilson has used Husserl's ideas extensively in developing his "New Existentialism," particularly in regards to his "intentionality of consciousness," which he mentions in a number of his books.[112] Rudolf Carnap was also influenced by Husserl,[113] not only concerning Husserl's notion of essential insight that Carnap used in his Der Raum, but also his notion of "formation rules" and "transformation rules" is founded on Husserl's philosophy of logic. Karol Wojtyla, who would later become Pope John Paul II, was influenced by Husserl. Phenomenology appears in his major work, The Acting Person (1969). Originally published in Polish, it was translated by Andrzej Potocki and edited by Anna-Teresa Tymieniecka in the Analecta Husserliana. The Acting Person combines phenomenological work with Thomistic ethics.[114] 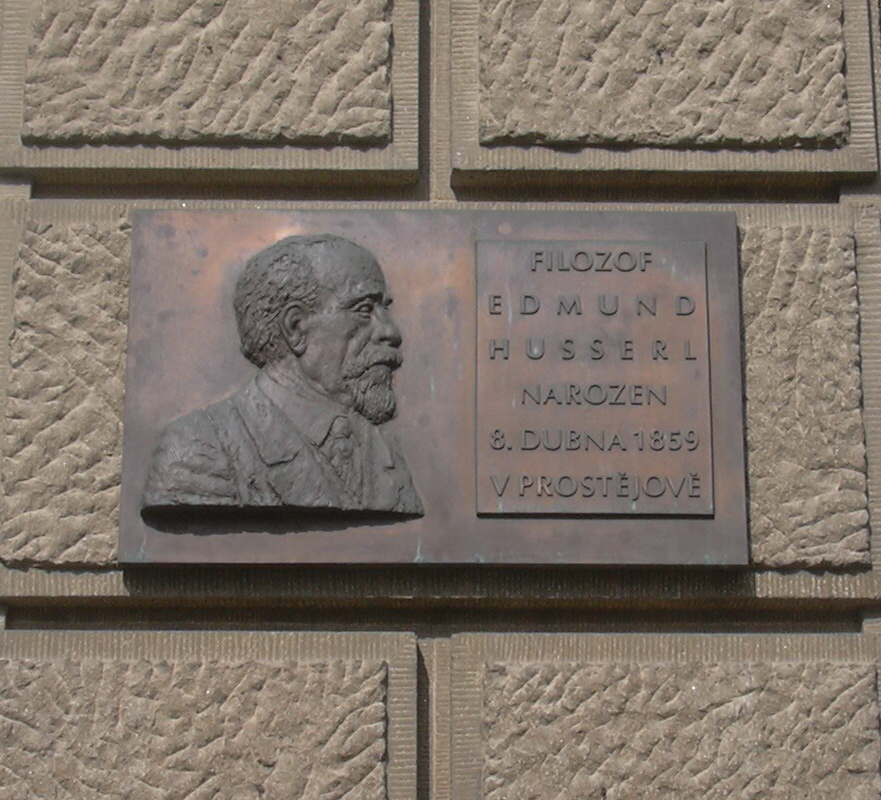 Plaque commemorating Husserl in his home town of Prostějov, Czech Republic Paul Ricœur has translated many works of Husserl into French and has also written many of his own studies of the philosopher.[115] Among other works, Ricœur employed phenomenology in his Freud and Philosophy (1965).[116] Jacques Derrida wrote several critical studies of Husserl early in his academic career. These included his dissertation, The Problem of Genesis in Husserl's Philosophy, and also his introduction to The Origin of Geometry. Derrida continued to make reference to Husserl in works such as Of Grammatology. Stanisław Leśniewski and Kazimierz Ajdukiewicz were inspired by Husserl's formal analysis of language. Accordingly, they employed phenomenology in the development of categorial grammar.[117] José Ortega y Gasset visited Husserl at Freiburg in 1934. He credited phenomenology for having 'liberated him' from a narrow neo-Kantian thought. While perhaps not a phenomenologist himself, he introduced the philosophy to Iberia and Latin America.[118] Wilfrid Sellars, an influential figure in the so-called "Pittsburgh School" (Robert Brandom, John McDowell) had been a student of Marvin Farber, a pupil of Husserl, and was influenced by phenomenology through him: Marvin Farber led me through my first careful reading of the Critique of Pure Reason and introduced me to Husserl. His combination of utter respect for the structure of Husserl's thought with the equally firm conviction that this structure could be given a naturalistic interpretation was undoubtedly a key influence on my own subsequent philosophical strategy.[119] In his 1942 essay The Myth of Sisyphus, absurdist philosopher Albert Camus acknowledges Husserl as a previous philosopher who described and attempted to deal with the feeling of the absurd, but claims he committed "philosophical suicide" by elevating reason and ultimately arriving at ubiquitous Platonic forms and an abstract god. Hans Blumenberg received his habilitation in 1950, with a dissertation on ontological distance, an inquiry into the crisis of Husserl's phenomenology. Roger Scruton, despite some disagreements with Husserl, drew upon his work in Sexual Desire (1986).[120]: 3–4 The influence of the Husserlian phenomenological tradition in the 21st century extends beyond the confines of the European and North American legacies. It has already started to impact (indirectly) scholarship in Eastern and Oriental thought, including research on the impetus of philosophical thinking in the history of ideas in Islam.[121][122] |
影響 ギュンターシュタールのフッサール墓碑 デビッド・カーは、1970年にイェール大学で行った論文で、フッサールの信奉者について次のように述べている。「フッサールは、自分の学生たちが独自の 道を歩み、共同作業ではなく現象学の根本的な見直しに着手する傾向にあることに常に失望していたことはよく知られている。」[92] しかし、フッサールは現象学に哲学者たちを引きつけた。 フッサールのもっとも著名な弟子であるマルティン・ハイデガーは、フッサールがフライブルクの後継者に選んだ人物である。ハイデガーの代表作『存在と時 間』はフッサールに捧げられた。彼らは思想を共有し、フライブルク大学で10年以上にわたって共に働き、1920年から1923年にかけてはハイデガーが フッサールの助手を務めた。[93][94][95] ハイデガーの初期の作品は師の作品を踏襲していたが、時が経つにつれ、彼は独自に変化した新たな洞察を展開し始めた。フッサールはハイデガーの研究に対し て次第に批判的になり、特に1929年には、1931年の講義でハイデガーに対する痛烈な批判を展開した。[96] ハイデガーはフッサールへの負い目を認めながらも、 1933年にナチスが政権を握った後、ユダヤ系であったフッサールに対して政治的に攻撃的で有害な立場を取った。ハイデガーは当時悪名高いナチスの支持者 であった。[97] フッサールとハイデガーに関する学術的な議論は広範囲にわたる。 ゲッティンゲンでは1913年にアドルフ・ライナッハ(1884年 - 1917年)が「今やフッサールの右腕となった。彼は何よりもまず、フッサールと学生たちの間の仲介者であった。なぜなら、彼は他人と接する方法を極めて よく理解していたが、フッサールはこの点に関してはほとんど無力であったからだ」[98] 彼はフッサールの新しい学術誌『Jahrbuch』の編集者の一人であった。彼の作品(義務の法則の現象学的分析)は、その創刊号に掲載された。[99] ラインハハは広く尊敬を集め、優れた教師であった。フッサールは1917年の追悼文で、「彼は最も深い源泉からだけを引き出そうとし、永続的な価値を持つ 作品だけを生み出そうとした。そして、その賢明な自制心によって、彼はこの目標を達成した」と記している。 エーディト・シュタインはゲッティンゲンとフライブルクでフッサールの学生であり、博士論文『歴史的に展開し、現象学的に考察された共感の問題』 (1916年)を執筆した。その後、彼女は1916年から1918年にかけてフライブルクでフッサールの助手を務めた。その後、彼女は自身の現象学を近代 トミズムの学派に適応させた。 ルートヴィヒ・ランドグレーベは1923年にフッサールの助手となった。1939年からはルーヴェンのフッサール・アーカイブでオイゲン・フィンクと協力 した。1954年にはフッサール・アーカイブのリーダーとなった。ランドグレーベはフッサールのもっとも親しい協力者の一人として知られているが、実存主 義哲学や形而上学の観点から見た歴史、宗教、政治に関する独自の視点でも知られている。 オイゲン・フィンクは1920年代から1930年代にかけてフッサールと親交のあった人物である。彼は『第六のデカルト的省察』を著し、フッサールは、こ の著作が自身の研究の最も真実な表現であり、継続であると述べた。フィンクは1938年にフッサールを称える追悼演説を行った。 ローマン・イングアルデンはフライブルクにおけるフッサールの初期の学生であり、1930年代半ばまでフッサールと文通していた。しかし、イングアルデン は、相対主義につながるとして、フッサールの後の超越論的観念論を受け入れなかった。イングアルデンはドイツ語とポーランド語で著作を残している。著書 『世界の存在をめぐる論争』(独語: 「世界存在の論争」)の中で、彼は独自の現実的な立場を打ち出し、ポーランドにおける現象学の普及にも貢献した。 マックス・シェーラーは1901年にハレでフッサールと出会い、彼の現象学に自身の哲学の方法論的飛躍を見出した。ゲッティンゲンでフッサールが教鞭を とっていたとき、シェーラーは同地に滞在しており、雑誌『Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung』(1913年)の編集者の一人となった。シェーラーの著作『Formalism in Ethics』と『Nonformal Ethics of Value』は、この新しい雑誌(1913年と1916年)に掲載され、高い評価を得た。しかし、シェーラーの法的なトラブルにより、2人の個人的な関係 はぎくしゃくし、シェーラーはミュンヘンに戻った。[102] シェーラーは後にフッサールの観念論的論理アプローチを批判し、代わりに「愛の現象学」を提唱したが、自身の研究全体を通じてフッサールに「深く負うとこ ろがある」と述べている。 ニコライ・ハルトマンはかつて現象学の中心人物と考えられていたが、もはやそうではないかもしれない。1921年、マールブルクの哲学教授であり新カント 派のハルトマンの名声がこの運動に加えられた。彼は「現象学の実際の活動との連帯を公に宣言した」 しかし、ハルトマンのつながりはマックス・シェーラーやミュンヘンのサークルとのものであり、フッサール自身はハルトマンを現象学者とはみなしていなかっ た。しかし、彼の哲学は、その方法の革新的な使用を含んでいると言われている。 1929年、エマニュエル・レヴィナスはフライブルクで行われたフッサールの最後のゼミナールの一つで発表を行った。また、同年に彼はフッサールの『イ デーン』(1913年)について、フランスの雑誌に長い書評を書いた。ガブリエル・ペイファーとともに、レヴィナスはフッサールの『カードスにおける省 察』(1931年)をフランス語に翻訳した。当初はハイデガーに感銘を受け、彼に関する著述を始めたが、ハイデガーがナチスと関わりを持つようになったた め、そのプロジェクトを中止した。戦後、レヴィナスはユダヤ教の精神性に関する著作を執筆した。彼の家族のほとんどはリトアニアでナチスに殺害されてい た。その後、レヴィナスは広く知られ、賞賛されることになる著作を書き始めた。 アルフレッド・シュッツの『社会世界の現象学』は、マックス・ヴェーバーの解釈社会学をフッサールの現象学に厳密に根拠づけようとするものである。フッサールはこの著作に感銘を受け、シュッツに自分の助手になるよう依頼した。 ジャン=ポール・サルトルもフッサールから大きな影響を受けたが、後に彼の分析の主要な点に反対するようになった。サルトルは『イデーン』(1913年)で始まったフッサールの超越論的解釈を拒絶し、代わりにハイデガーの存在論に従った。 モーリス・メルロ=ポンティの『知覚の現象学』は、知覚、相互主観性、志向性、空間、時間性に関するエドムンド・フッサールの研究に影響を受けている。例 えば、メルロ=ポンティの「運動の志向性」と「性」に関する記述は、『イデーンI』におけるノエティック/ノエマティック相関の重要な構造を保持している が、さらに、意識が直観の様式へと自己を特化させることの意味を具体的に示している。メルロ=ポンティの著作の中で最もハッセルリアンなのは、おそらく 『哲学者とその影』であろう。現象学的心理学』と『経験と判断』で示されたイデア的直観に関するフッサールの説明の解釈によっては、メルロ=ポンティは 「イデア的還元」も、その結果として生じるという「純粋本質」も受け入れなかった可能性がある。メルロ=ポンティは、ルーヴェンのフッサール文書館で研究 した最初の学生であった。 ガブリエル・マルセルは、実存主義はサルトルの影響で明確に拒絶したが、現象学は拒絶せず、フランス・カトリックの間で広く支持された。彼はフッサール、 シェーラー、そして(不安を抱きつつも)ハイデガーを高く評価した。[110] 身体について「感覚性の存在論」といった表現を用いるなど、現象学的思考の影響が見られる。[111] クルト・ゲーデルは『デカルト的省察』を読んだことが知られている。彼はフッサールの仕事に対して、特に「括弧付け」や「エポケー」に関して、非常に強い評価を表明した。 ヘルマン・ワイルの直観主義論理学や非述語性への関心は、フッサールの著作を読んだことがきっかけとなったようだ。ワイルは妻のヘレーネ・ヨゼフを通じてフッサールの著作を知ったが、彼女自身もゲッティンゲンでフッサールの学生であった。 コリン・ウィルソンは、彼の「新実存主義」を展開するにあたり、特に「意識の志向性」に関して、フッサールの考えを広範に利用しており、この考えは彼の著書の多くで言及されている。[112] ルドルフ・カルナップもフッサールから影響を受けている。[113] カルナップが『空間』で用いた本質的洞察に関するフッサールの概念だけでなく、「形成規則」と「変換規則」の概念も、フッサールの論理学の哲学に基づいている。 後にヨハネ・パウロ2世となるカロル・ヴォイティワはフッサールから影響を受けた。現象学は彼の主要な著作『行為する人間』(1969年)に現れている。 ポーランド語で最初に出版されたこの著作は、アンジェイ・ポトツキによって翻訳され、アナレクタ・フッサリアナでアンナ・テレサ・ティミエニェツカによっ て編集された。『行為する人間』は現象学的研究とトミスト倫理学を組み合わせたものである。 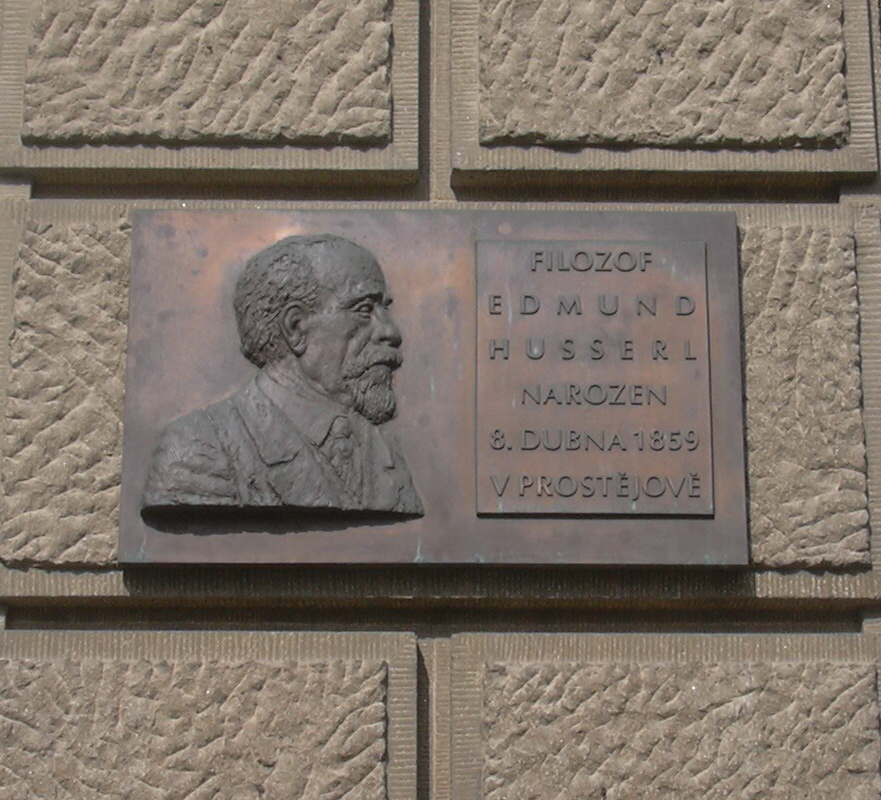 チェコ共和国の故郷プロスチェヨフにあるフッサールを記念する銘板 ポール・リクールはフッサールの多くの著作をフランス語に翻訳し、また哲学者に関する自身の研究も数多く著している。[115] リクールは『フロイトと哲学』(1965年)の中で現象学を用いた。[116] ジャック・デリダは、学術的なキャリアの初期にフッサールに関するいくつかの批判的研究を書いた。これには、彼の学位論文『フッサール哲学における生成の 問題』や、『幾何学原論』の序文も含まれている。デリダは、『グラマトロジーについて』などの著作でもフッサールに言及し続けている。 スタニスワフ・レシニェフスキとカジミェシュ・アイドゥキェヴィチは、フッサールの言語の形式分析に触発された。それゆえ、彼らは現象学を範疇文法の展開に採用した。 ホセ・オルテガ・イ・ガセットは1934年にフライブルクを訪れ、フッサールに会った。彼は現象学が狭い新カント主義思想から彼を「解放」したと評価した。おそらく自身は現象学者ではなかったが、彼はイベリア半島とラテンアメリカに現象学を紹介した。 ウィルフリッド・セラーズは、いわゆる「ピッツバーグ学派」(ロバート・ブランドン、ジョン・マクダウェル)の有力な人物であったが、彼はフッサールの弟子であったマーヴィン・ファーバーの教え子であり、彼を通じて現象学の影響を受けていた。 マーヴィン・ファーバーは、私に『純粋理性批判』を初めて注意深く読ませ、フッサールを紹介してくれた。 フッサールの思想構造に対する絶対的な敬意と、この構造は自然主義的な解釈が可能だという同様に確固とした信念を併せ持つ彼の姿勢は、間違いなく、その後 の私の哲学戦略に大きな影響を与えた。[119] 1942年のエッセイ『シジフォスの神話』において、不条理哲学の哲学者アルベール・カミュは、不条理感について記述し、その対処を試みた過去の哲学者と してフッサールを認めているが、理性を重視し、最終的に遍在するプラトン的な形や抽象的な神に到達したことは「哲学的自殺」であると主張している。 ハンス・ブルーメンベルクは1950年に存在論的距離に関する論文で博士号を取得したが、これはフッサール現象学の危機に関する研究であった。 ロジャー・スクルートンはフッサールとの意見の相違はあるものの、著書『性的欲望』(1986年)でフッサールの研究を引用している。[120]:3-4 21世紀におけるフッサール現象学の伝統の影響は、ヨーロッパや北米の遺産の枠を超えて広がっている。それはすでに、イスラム思想史における哲学思考の推進力に関する研究を含め、東洋思想や東洋哲学の研究に(間接的に)影響を与え始めている。[121][122] |
| Bibliography In German 1887. Über den Begriff der Zahl. Psychologische Analysen (On the Concept of Number; habilitation thesis) 1891. Philosophie der Arithmetik. Psychologische und logische Untersuchungen (Philosophy of Arithmetic) 1900. Logische Untersuchungen. Erster Teil: Prolegomena zur reinen Logik (Logical Investigations, Vol. 1: Prolegomena to Pure Logic) 1901. Logische Untersuchungen. Zweiter Teil: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis (Logical Investigations, Vol. 2) 1911. Philosophie als strenge Wissenschaft (included in Phenomenology and the Crisis of Philosophy: Philosophy as Rigorous Science and Philosophy and the Crisis of European Man) 1913. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie (Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology) 1923–24. Erste Philosophie. Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Reduktion (First Philosophy, Vol. 2: Phenomenological Reductions) 1925. Erste Philosophie. Erster Teil: Kritische Ideengeschichte (First Philosophy, Vol. 1: Critical History of Ideas) 1928. Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (Lectures on the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time) 1929. Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft (Formal and Transcendental Logic) 1930. Nachwort zu meinen "Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie" (Postscript to my "Ideas") 1936. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie (The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy) 1939. Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. (Experience and Judgment) 1950. Cartesianische Meditationen (translation of Méditations cartésiennes (Cartesian Meditations, 1931)) 1952. Ideen II: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution (Ideas II: Studies in the Phenomenology of Constitution) 1952. Ideen III: Die Phänomenologie und die Fundamente der Wissenschaften (Ideas III: Phenomenology and the Foundations of the Sciences) 1973. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität (On the Phenomenology of Intersubjectivity) In English Philosophy of Arithmetic, Willard, Dallas, trans., 2003 [1891]. Dordrecht: Kluwer. Logical Investigations, 1973 [1900, 2nd revised edition 1913], Findlay, J. N., trans. London: Routledge. "Philosophy as Rigorous Science", translated in Quentin Lauer, S.J., editor, 1965 [1910] Phenomenology and the Crisis of Philosophy. New York: Harper & Row. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy – First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology, 1982 [1913]. Kersten, F., trans. The Hague: Nijhoff. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy – Second Book: Studies in the Phenomenology of Constitution, 1989. R. Rojcewicz and A. Schuwer, translators. Dordrecht: Kluwer. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy – Third Book: Phenomenology and the Foundations of the Sciences, 1980, Klein, T. E., and Pohl, W. E., translators. Dordrecht: Kluwer. On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time (1893–1917), 1990 [1928]. Brough, J.B., trans. Dordrecht: Kluwer. Cartesian Meditations, 1960 [1931]. Cairns, D., trans. Dordrecht: Kluwer. Formal and Transcendental Logic, 1969 [1929], Cairns, D., trans. The Hague: Nijhoff. Experience and Judgement, 1973 [1939], Churchill, J. S., and Ameriks, K., translators. London: Routledge. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, 1970 [1936/54], Carr, D., trans. Evanston: Northwestern University Press. "Universal Teleology". Telos 4 (Fall 1969). New York: Telos Press. Anthologies Willard, Dallas, trans., 1994. Early Writings in the Philosophy of Logic and Mathematics. Dordrecht: Kluwer. Welton, Donn, ed., 1999. The Essential Husserl. Bloomington: Indiana University Press. |
参考文献 ドイツ語で 1887年。数の概念について。心理学分析(ハビリテーション論文) 1891年。算術哲学。心理学および論理的研究(算術哲学) 1900年。論理的研究。第1部:純粋論理学への序説(論理的研究、第1巻:純粋論理学への序説) 1901年。論理的研究。第2部:現象学と知識論の研究(『論理的研究』第2巻) 1911年。厳格な科学としての哲学(『現象学と哲学の危機:厳格な科学としての哲学とヨーロッパ人の危機としての哲学』に収録) 1913年。『アイデア:純粋現象学への一般序説』(Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie) 1923年~1924年。『第一哲学。第二部:現象学的還元論』(First Philosophy, Vol. 2: Phenomenological Reductions) 1925年。『第一哲学』第1部:『観念の批判史』(『第一哲学』第1巻:『観念の批判史』) 1928年。『内的時間の意識の現象学講義』(『内的時間の意識の現象学講義』) 1929年。『形式論理学・超越論理学』。論理的理由の批判的考察の試み(『形式論理学・超越論理学』) 1930年。『イデーン』への補遺 1936年。『ヨーロッパ科学の危機と超越論的現象学:現象学的哲学への序説 1939年。『経験と判断。論理学の系譜における研究』。(『経験と判断』) 1950年。『デカルト的省察』(『デカルト的省察』(1931年)の翻訳) 1952年。『アイデアII:憲法に関する現象学的研究』(『アイデアII:憲法の現象学的研究』) 1952年 『アイデアIII:現象学と科学の基礎』 1973年 『相互主観性の現象学について 英語 算術哲学』、Willard、ダラス、訳、2003年 [1891年]。ドルドレヒト:クルーワー。 論理の探究、1973年[1900年、第2改訂版1913年]、J. N. ファインレイ訳。ロンドン:ルートレッジ。 「哲学としての厳密な科学」、クエンティン・ラウアー(S.J.)編、1965年[1910年]『現象学と哲学の危機』所収。ニューヨーク:Harper & Row。 純粋現象学および現象学的哲学に関する諸観念 - 第1巻:純粋現象学への一般序説、1982年 [1913年]。 ケルステン、F. 訳。ハーグ:ニホフ。 純粋現象学および現象学的哲学に関する諸観念 - 第2巻:構成の現象学的研究、1989年。R. RojcewiczとA. Schuwer、翻訳者。ドルドレヒト:クルーワー。 純粋現象学および現象学的哲学に関する諸概念 - 第3巻:現象学と科学の基礎、1980年、クライン、T. E.、およびポール、W. E.、翻訳者。ドルドレヒト:クルーワー。 内的時間の意識の現象学(1893年~1917年)について、1990年[1928年]。Brough, J.B., 訳。Dordrecht: Kluwer。 デカルト的省察、1960年[1931年]。Cairns, D., 訳。Dordrecht: Kluwer。 『形式論理学と超越論理学』1969年[1929年]、ケアンズ訳、ハーグ:ニーホフ。 『経験と判断』1973年[1939年]、チャーチル、J. S. およびアメリクス、K. 訳、ロンドン:ルートレッジ。 『ヨーロッパ科学の危機と超越論的現象学』、1970年[1936/54年]、カー、D. 訳、エバンストン:ノースウェスタン大学出版。 「普遍的テレオロジー」。『テロス』4(1969年秋)。ニューヨーク:テロス出版。 アンソロジー Willard, Dallas, trans., 1994. Early Writings in the Philosophy of Logic and Mathematics. Dordrecht: Kluwer. Welton, Donn, ed., 1999. The Essential Husserl. Bloomington: Indiana University Press. |
| Early phenomenology Experimental phenomenology List of phenomenologists |
初期現象学 実験現象学 現象学者の一覧 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl |
|
★
★
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆