
現 象 学
Phenomenology
★現象学(ギ リシャ語の φαινόμενον / phainómenon、「現れるもの」、および λόγος / lógos、「研究」から)は、哲学を経験的な学問とすることを目指してエドムント・フッサールによって創設された20世紀の思想潮流である。その名称 は、現象を通して現実をありのままに把握するというその手法に由来している。現象学は、哲学を、経験と意識[1]そのものを、自らを思考し、世界を思考す る思考の現象として体系的に研究・分析する学問としている。 この哲学の学派は、現象はそれを知覚する意識がある場合にのみ存在することを証明しようと努めている。したがって、あらゆる意識は何かに対する意識であ り、それは意識の意図性という考え方である。現象学的方法は、意識と世界との間に本質的な関係が存在することを証明しようとするものである。現象学は、本 質という概念に関する哲学的疑問を取り上げ、それを考察するアプローチとして、生きた経験、つまり現象そのものを研究する。このように、現象学は、観念論 (観念を通じて現実を捉える)と経験論(現実を通じて観念を捉える)の橋渡しをしようとしているとみなされることもある。 フッサールは、最初の主要著作『論理学研究』(1900-1901)の中で、心理主義と決別し、形而上学に対抗して、自然科学に基礎を与える科学として現 象学を確立した。彼は、自然科学は「人間と世界との関係を解明する」には不十分だと考えていた[3]。
☆善の公案に似てエポケーはなかなか[分かりそうで]分かりにくい実践である.実践と書いたのは[形而上学的実践[撞着語法]]概念を自分のものにするから実践でなのであるがカントの[これまた通俗形而上学を嫌った用語としての]超越論的観念論ならぬ美学的実践だからだ.
| La phénoménologie
(du grec φαινόμενον / phainómenon, « ce qui apparaît », et λόγος /
lógos, « étude ») est un courant de pensée du xxe siècle fondé par
Edmund Husserl dans l'optique de faire de la philosophie une discipline
empirique. Elle tire son nom de sa démarche, qui est d'appréhender la
réalité telle qu'elle se donne, à travers les phénomènes. Elle fait de
la philosophie l'étude systématique et l'analyse de l’expérience vécue
et de la conscience[1] comme étant eux-mêmes des phénomènes de la
pensée qui se pense elle-même et pense le monde. Cette école de philosophie s'attache à démontrer que le phénomène n'existe que s'il y a une conscience pour le percevoir. Toute conscience serait donc conscience de quelque chose, c'est l'idée d'intentionnalité de la conscience. La méthode phénoménologique veut démontrer qu'il existe une relation essentielle entre la conscience et le monde. La phénoménologie reprend les interrogations philosophiques sur le concept d'essence, et son approche pour les aborder est d'étudier l'expérience vécue, c'est-à-dire le phénomène en tant que tel. Il est parfois considéré qu'ainsi, la phénoménologie cherche à faire le lien entre l'idéalisme (passer par l'idée pour accéder au réel) et l'empirisme (passer par le réel pour accéder à l'idée)[2]. C'est dans sa première oeuvre majeure, Recherches logiques (1900-1901), que Husserl, en rupture avec le psychologisme et en opposition à la métaphysique, fonde la phénoménologie comme science destinée à donner un fondement aux sciences de la nature, qu'il juge insuffisantes à « élucider le rapport de l'homme au monde »[3]. La phénoménologie telle qu'on la connaît aujourd'hui s'étend au sein d'un cercle de disciples dans les universités de Göttingen et de Munich en Allemagne (Edith Stein, Roman Ingarden, Martin Heidegger, Eugen Fink, Max Scheler, Nicolai Hartmann), et se propage rapidement à l'étranger, en particulier en France (grâce aux traductions et aux travaux de Paul Ricœur, d'Emmanuel Levinas, de Jean-Paul Sartre, de Maurice Merleau-Ponty) et aux États-Unis (Alfred Schütz et Eric Voegelin), souvent avec une très large prise de distance critique par rapport aux premiers travaux de Husserl, mais sans jamais que soit abandonnée sa volonté fondamentale de s'en tenir à l'expérience vécue. Il n'y a pas lieu de s'étonner de la grande variété de formulations de ce courant de pensée, qui ressortit à sa nature même, cherchant à exprimer les aspects spécifiques de chacun de ses domaines d'étude[1]. La phénoménologie constitue l'une des traditions principales de la philosophie européenne du xxe siècle. Elle a en outre inspiré de nombreux travaux hors de son champ philosophique propre, telles la philosophie des sciences, la psychiatrie, l'esthétique, la morale, la théorie de l'histoire[1], l'anthropologie existentiale[4]. |
現象学(ギリシャ語の φαινόμενον /
phainómenon、「現れるもの」、および λόγος /
lógos、「研究」から)は、哲学を経験的な学問とすることを目指してエドムント・フッサールによって創設された20世紀の思想潮流である。その名称
は、現象を通して現実をありのままに把握するというその手法に由来している。現象学は、哲学を、経験と意識[1]そのものを、自らを思考し、世界を思考す
る思考の現象として体系的に研究・分析する学問としている。 この哲学の学派は、現象はそれを知覚する意識がある場合にのみ存在することを証明しようと努めている。したがって、あらゆる意識は何かに対する意識であ り、それは意識の意図性という考え方である。現象学的方法は、意識と世界との間に本質的な関係が存在することを証明しようとするものである。現象学は、本 質という概念に関する哲学的疑問を取り上げ、それを考察するアプローチとして、生きた経験、つまり現象そのものを研究する。このように、現象学は、観念論 (観念を通じて現実を捉える)と経験論(現実を通じて観念を捉える)の橋渡しをしようとしているとみなされることもある。 フッサールは、最初の主要著作『論理学研究』(1900-1901)の中で、心理主義と決別し、形而上学に対抗して、自然科学に基礎を与える科学として現 象学を確立した。彼は、自然科学は「人間と世界との関係を解明する」には不十分だと考えていた[3]。 今日知られている現象学は、ドイツのゲッティンゲン大学とミュンヘン大学の弟子たち(エディット・シュタイン、ロマン・インガルデン、マルティン・ハイデ ガー、オイゲン・フィンク、マックス・シェラー、ニコライ・ハルトマン)の間で広まり、特にフランス (ポール・リクール、エマニュエル・レヴィナス、ジャン=ポール・サルトル、モーリス・メルロ=ポンティによる翻訳や研究のおかげで)、そしてアメリカ (アルフレッド・シュッツとエリック・ヴォーゲリン)に急速に広まった。多くの場合、フッサールの初期の研究からはかなり批判的に距離を置いていたが、経 験に忠実であり続けようという基本的な意志は決して放棄されなかった。 この思想潮流の表現が極めて多様であることは、その本質からして当然のことであり、それぞれの研究分野における特定の側面を表現しようとしている[1]。 現象学は、20世紀のヨーロッパ哲学の主要な伝統の一つだ。さらに、科学哲学、精神医学、美学、道徳、歴史理論[1]、実存的人類学[4]など、哲学の分 野以外の多くの研究にも影響を与えている。 |
| La phénoménologie avant Husserl On attribue généralement l'invention du terme « phénoménologie » à Jean-Henri Lambert (1728-1777), qui dénomme ainsi dans la quatrième partie de son Nouvel Organon (1764) la « doctrine de l'apparence »[5],[N 1]. Kant (1724-1804) Une section de la Critique de la raison pure de Kant devait s'appeler Phénoménologie ; mais Kant remplaça finalement ce nom par celui d'Esthétique transcendantale. Kant y opère la séparation entre la « chose en soi » et le phénomène (ce qui se montre), ce dernier étant donné dans le cadre transcendantal de l'espace, du temps et de la causalité[N 2]. La thèse de Kant est qu'il existe seulement un cadre a priori dans lequel les objets peuvent nous « faire encontre » et qui permet leur représentation. Ce cadre qui n'est autre que la structure de notre connaissance va ouvrir la possibilité d'une connaissance universelle[6]. Fichte (1762-1814) Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2024). La phénoménologie est un concept central de la philosophie de Johann Gottlieb Fichte. Elle désigne la partie de la doctrine de la science qui développe la phénoménalisation (apparition, extériorisation) du fondement et du principe du savoir. Il ne peut y avoir de savoir absolu (qui n'est pas un savoir d'un objet mais de ce qui fait qu'un savoir est effectivement un savoir) que phénoménalisé. Aussi, dès La Doctrine de la Science de 1804, oppose-t-il la doctrine du phénomène ou phénoménologie à la doctrine de l'être et de la vérité. À la fin de sa vie, Fichte identifie même la phénoménologie à la doctrine de la science, parce que, sans elle, le « savoir absolu » n'aurait pas d'existence. Hegel (1770-1831) Article détaillé : Phénoménologie de l'esprit. Des thèses kantiennes, Hegel déduit qu'avec le phénomène, la conscience découvre la structure de sa propre connaissance, s'élevant ainsi à la conscience de soi. Dans la Phénoménologie de l'esprit, « Hegel trace le parcours de cette conscience dans l'histoire de ses manifestations, de ses figures, qui sont autant d'expériences de soi dans son élan vers la science »[6],[N 3]. Schopenhauer (1788-1860) Si pour Arthur Schopenhauer, le monde est notre représentation (c'est-à-dire qu'être et être une représentation, pour le sujet, c'est tout un), il s'agit toujours pour lui de chercher plus profond que cette évidence première : comment connaître ce que le monde peut être dans son être en soi ? Il s'agit pour lui de rechercher l’essence du phénomène à partir d'une étude descriptive préalable du donné phénoménal et en particulier, de la manière dont se donne à moi mon propre corps comme « volonté »[N 4]. |
フッサール以前の現象学 「現象学」という用語の発明は、一般的にジャン=アンリ・ランベール(1728-1777)によるものとされている。彼は『新オルガノン』(1764)の第4部で、「外観の教義」[5]、[N 1]をそう呼んだ。 カント(1724-1804) カントの『純粋理性批判』の一部は、本来「現象学」という名称になる予定だったが、カントは最終的にこの名称を「超越論的美学(→邦訳では超越論的観念 論)」に変更した。カントは、この部分で「物自体」と現象(見えるもの)を区別しており、現象は空間、時間、因果関係の超越論的枠組みの中で与えられるも のであるとしている[N 2]。カントの主張は、物体が私たちに「出会う」ことができる、そしてそれらの物体を表現することを可能にする、先験的な枠組みだけが存在するというもの である。この枠組みは、私たちの知識の構造そのものであり、普遍的な知識の可能性を開くものである[6]。 フィヒテ(1762-1814) このセクションは、出典を十分に引用していない(2024年9月)。 現象学は、ヨハン・ゴットリーブ・フィヒテの哲学の中心的な概念である。それは、知識の基礎と原理の現象化(出現、外部化)を展開する科学の教義の一部を 指す。現象化されたもの以外には、絶対的な知識(対象に関する知識ではなく、知識が実際に知識である理由に関する知識)は存在しえない。そのため、 1804年の『科学の教義』以降、彼は現象の教義、すなわち現象学を、存在と真実の教義に対立させるようになった。フィヒテは、その生涯の終わりに、現象 学を科学の教義と同一視した。なぜなら、現象学がなければ、「絶対的な知識」は存在しえないからである。 ヘーゲル(1770-1831) 詳細記事:精神の現象学。 カントの説から、ヘーゲルは、現象によって意識は自らの認識の構造を発見し、それによって自己意識に到達すると結論づけた。『精神の現象学』の中で、 「ヘーゲルは、その顕現の歴史、その姿、すなわち科学への衝動における自己の経験の軌跡を、この意識の軌跡として描いている」[6]、[N 3]。 ショーペンハウアー(1788-1860) アーサー・ショーペンハウアーにとって、世界は我々の表象である(つまり、存在することと表象であることは、主体にとっては同じことである)。しかし、彼 にとっては、この第一義的な自明性よりもさらに深いところを探求することが常に重要であった。つまり、世界がそれ自体としてどのような存在であるかを、ど のように知ることができるのか?彼にとっては、現象の本質を、現象的に与えられたものを事前に記述的に研究すること、特に、自分の体が「意志」として自分 に与えられている方法を研究することである[N 4]。 |
Vue d'ensemble de la phénoménologie Photographie en noir et blanc. Buste d'homme en costume. Il porte une barbe blanche fournie, des moustaches en croc et observe au-delà du spectateur. Edmund Husserl en 1900. Avec Edmund Husserl, la phénoménologie a l'ambition de se constituer en science[N 5], et elle se dote d'une problématique, d'un objet ou domaine, et d'une méthode[N 6]. Hegel encore, dans sa Phénoménologie de l'esprit donne au terme de phénoménologie le sens de méthode, qui finit avec Husserl par désigner la philosophie tout entière elle-même avec pour mot d'ordre : « revenir aux choses elles-mêmes ». La problématique L'histoire du concept de phénoménologie montre que, depuis Jean-Henri Lambert, la phénoménologie n’a cessé d’évoluer. C'est donc le contexte qui va déterminer si l'on parle de la phénoménologie au sens fichtéen, hégélien ou husserlien, même si en général, le terme de phénoménologie, pris isolément, désigne la philosophie et la méthode de Husserl ou de ses héritiers. Comprise jusqu'à lui comme science de l’« apparaître », la phénoménologie devient, chez Heidegger, la science de ce qui n’apparaît justement pas à première vue[7] ou, comme l'écrit Françoise Dastur citant Heidegger, une « phénoménologie de l'inapparent »[8]. Dans le phénomène de l'apparaître, la phénoménologie « post husserlienne », problématise la « constitution du sens » de ce qui se présente à la conscience, cela requiert une attitude qui ne se satisfait jamais de solutions définitives. Ainsi, Jean-François Courtine[9] précise que « la phénoménologie ne caractérise pas le « Was » (ce que c'est), mais le « Wie » des objets, le comment de la recherche, la modalité de leur « être-donné », la manière dont ils viennent à la rencontre »[N 7]. De telles recherches exigent de chacun qu'il refasse pour son compte l'expérience phénoménologique de celui qui l'a précédemment faite, note Alexander Schnell[10]. La phénoménologie se constitue en opposition au « néokantisme »[N 8] ; elle « consiste à décrire les phénomènes sans parti pris, en renonçant de façon méthodique à leur origine physiologico-psychologique ou à leur réduction à des principes préconçus », résume Hans-Georg Gadamer[11]. Le mot « phénomène » signifie étymologiquement « ce qui se montre », et il conserve, depuis son origine grecque un sens ambigu provenant de ce qu'il tient à la fois de l'objet et du sujet. Il est délicat de distinguer ce qui appartient à l'objet de ce qui appartient à l'interprétation propre au sujet[12] (connaissance, illusion, erreur). Cette dépendance, vis-à-vis du sujet pourrait rendre difficile, voire impossible, la constitution d'une science, à partir d'une expérience, d'où le souci grec, notamment chez Platon et Aristote, de « sauver les phénomènes »[6]. |
現象学の概要 白黒写真。スーツを着た男性の胸像。彼は豊かな白ひげと鉤鼻を生やし、観客の背後を見つめている。 1900年のエドムント・フッサール。 エドムント・フッサールにとって、現象学は科学として確立することを目指しており[N 5]、問題意識、対象または領域、そして方法論を備えている[N 6]。ヘーゲルは、その『精神の現象学』の中で、現象学という用語に方法論の意味を与え、フッサールによって、それは「物事そのものに立ち返る」というス ローガンを掲げた哲学全体そのものを指すようになった。 問題意識 現象学という概念の歴史は、ジャン=アンリ・ランベール以来、現象学が絶えず進化してきたことを示している。したがって、フィヒテ、ヘーゲル、フッサー ル、どの意味での現象論を論じるかは、文脈によって決まる。ただし、一般的に現象学という用語は、単独で使用される場合、フッサールやその継承者たちの哲 学および方法を指す。 それまでは「現れ」の科学として理解されていた現象学は、ハイデガーによって、一見しただけでは現れないものの科学[7]、あるいはフランソワーズ・ダストゥールがハイデガーを引用して書いているように、「現れないものの現象学」[8]となった。 出現という現象において、「ポストフッサール的」現象学は、意識に現れるものの「意味の構成」を問題視する。そのためには、決定的な解決に決して満足しな い姿勢が必要だ。したがって、ジャン=フランソワ・クルティーンは、「現象学は、物事の「Was」(何であるか)ではなく、物事の「Wie」(どのよう に)、つまり、研究の方法、物事の「与えられ方」、物事がどのように出会うかを特徴づける」と述べている。このような研究は、各人が、以前にそれを経験し た人の現象学的経験を、自分なりに再現することを要求する、とアレクサンダー・シュネル[10]は述べている。現象学は「新カント主義」[N 8] に対抗して成立したものであり、ハンス・ゲオルク・ガダマー[11] は「現象を偏見なく記述し、その生理学的・心理学的起源や、先入観に基づく原理への還元を体系的に放棄すること」と要約している。 「現象」という言葉は、語源的には「現れるもの」を意味し、そのギリシャ語起源以来、対象と主体の両方に由来する曖昧な意味合いを保っている。対象に属す るものと、主体固有の解釈(認識、錯覚、誤謬)に属するものを区別することは難しい。この主体への依存は、経験に基づいて科学を構築することを困難、ある いは不可能にする可能性がある。そのため、特にプラトンやアリストテレスなどのギリシャ人は、「現象を救う」[6]ことを重視した。 |
| L'objet La phénoménologie moderne, dominée par les pensées d'Edmund Husserl et de Martin Heidegger, ambitionne d'aller « droit à la chose même ». Le phénomène Husserl le répète expressément, la phénoménologie vise à se débarrasser de toute théorie préalable, de toute préconception et se soucie exclusivement de « faire droit à la chose même, [car], le voir ne se laisse pas démontrer ni déduire »[13], en s'en tenant scrupuleusement à la façon dont la chose se donne selon le principe « Zu den Sachen selbst »[N 9]. En ce sens précis, l'écoute du phénomène exige la réduction phénoménologique. « Ce n'est que par une réduction […] que j'obtiens une donnée absolue, qui n'offre plus rien d'une transcendance. Si je mets en question le moi, et le monde, et le vécu en tant que vécu du moi, alors, de la vue réflexive dirigée simplement sur ce qui est donné dans l'aperception du vécu en question, sur mon moi, résulte le phénomène de cette aperception : par exemple le phénomène perception appréhendé comme ma perception […] Mais je peux pendant que je perçois porter sur la perception le regard d'une pure vue […] laisser le rapport au moi de côté ou en faire abstraction : alors la perception saisie et délimitée dans une telle vue est une perception absolue, dépourvue de toute transcendance, donnée comme phénomène pur au sens de la phénoménologie » écrit Husserl dans L'idée de la phénoménologie[14]. En reprenant le terme de « phénoménologie », Heidegger pourrait paraître d'emblée s'inscrire dans le prolongement de la pensée de son maître Husserl, sauf qu'il en élimine une partie essentielle, en rejetant tout ce qui a succédé à ce qu'il a qualifié de « tournant non phénoménologique » de Husserl, c'est-à-dire, son penchant pour une méthodologie scientifique, qu'il discerne à partir des Ideen, et notamment l'institution du « sujet transcendantal »[15]. De plus, Martin Heidegger a pu paradoxalement avancer que l'impératif Zu den Sachen selbst (aller droit à la chose même) ne soit justement pas la chose mais « ce qui est en cause » chaque fois que nous sommes en rapport avec quoi que ce soit[16]. Pour Heidegger, ce que la phénoménologie doit finalement montrer ce n'est justement pas l'étant mais bien son « être », « or celui-ci, de prime abord, ne se montre pas, même s'il est toujours pré-compris d'une certaine manière », remarque Christian Dubois[17]. Si l'être est le phénomène par excellence […] alors la phénoménologie devrait le faire voir […] tel qu'il se montre à partir de lui-même, c'est-à-dire ne pas chercher à l'extraire de sa dissimulation, mais le montrer dans cette dissimulation même écrit Sylvaine Gourdin[18] Heidegger ambitionne ainsi, à l'encontre des évolutions contestées de son prédécesseur, de ressaisir la « phénoménologie » en sa pure possibilité d'avant ce tournant. Comme l'écrit Jean-François Courtine[19], Heidegger ne veut pas dépasser mais créer une nouvelle tendance, l'ontologie phénoménologique mise en œuvre dans Sein und Zeit, « se propose de penser plus originellement ce qu'est la phénoménologie, c'est-à-dire de prendre l'entière mesure de son importance ou de sa signification, fallût-il pour cela aller jusqu'à renoncer au titre de phénoménologie ». Cependant, les deux penseurs conviennent que le « phénomène » possède un sens phénoménologique différent de son sens dit « vulgaire », « n'étant pas immédiatement donné, ne se montre de lui-même que dans une thématisation expresse qui est l'œuvre de la phénoménologie elle-même » écrit Françoise Dastur[20]. Heidegger prend conscience que le « phénomène » a besoin pour se montrer du Logos, qu'il comprend, en revenant à la source grecque, moins comme un discours sur la chose, que d'un « faire voir » écrit Marlène Zarader[21]. Heidegger en déduit sa propre position théorique à savoir que l'ajointement des deux mots, phénomène et logos, dans celui de « phénoménologie » doit signifier « ce qui se montre à partir de lui-même »[22]. En gros, Heidegger se différencie de son maître Husserl, en ce qu'il s'intéresse moins à la relation de l'homme au monde qu'à la « pré-ouverture », autrement dit à la « dimension » qui rend possible la rencontre de ce qu'il appelle « l'étant sous la main » ; en résumé au poids ontologique du « auprès de.. » de « l'être-au-monde », préoccupé dira Paul Ricœur[23]. |
対象 エドムント・フッサールとマルティン・ハイデガーの思想に支配された現代現象学は、「物そのもの」に直行することを目指している。 現象 フッサールが繰り返し強調しているように、現象学はあらゆる先入観や先入観を排除し、「物事そのものを正しく捉えること」に専心する。なぜなら、物事を見 ることは、証明も演繹もできないからだ 」[13]、つまり「物事そのものへ」[N 9]という原則に従って、物事が与えられるありのままの姿を厳密に守ることにある。この厳密な意味において、現象に耳を傾けることは現象学的還元を必要と する。「還元によってのみ、私は超越性を一切持たない絶対的なデータを得る。私が自我と世界、そして自我の経験としての経験を疑問視すると、その経験の知 覚において与えられているもの、つまり私の自我に単に反射的に向けられた視線から、その知覚の現象、例えば私の知覚として把握される知覚という現象が生ま れる。しかし、知覚している間、私は純粋な視線によって知覚を観察することができる […] 自己との関係を脇に置いたり、それを抽象化したりすることができる。そうすることで、そのような視線によって捉えられ、限定された知覚は、あらゆる超越性 を欠いた、現象学の意味での純粋な現象として与えられる絶対的な知覚となる」とフッサールは『現象学の理念』[14] で述べている。 「現象学」という用語を再び取り上げたハイデガーは、一見、師である フッサールの思想の延長線上にあるように見えるかもしれない。しかし、彼はその本質的な部分を排除し、フッサールの「非現象学的転換」と彼が呼んだもの、 つまり、ハイデガーは、フッサールの『アイデア』から読み取った、科学的方法論への傾倒、特に「超越的主体」の確立を、フッサールの「非現象学的転換」と みなして、これを完全に否定したのである。さらに、マルティン・ハイデガーは、逆説的に、「物事そのものへ(Zu den Sachen selbst)」という要求は、まさに物事そのものではなく、私たちが何かと関わるときに「問題となるもの」であると主張した[16]。ハイデガーにとって、現象学が最終的に示すべきものは、まさに存在そのものではなく、その「存在」である。しかし、「それは、ある意味で常に事前に理解されているにもかかわらず、一見しただけでは見せない」とクリスチャン・デュボワは指摘している。 存在がまさに現象であるならば、現象学はそれを、それ自体から現れている姿、つまり、その隠蔽から引き出そうとするのではなく、その隠蔽そのものの中で示すべきである、とシルヴァイン・グルダンは書いている。 ハイデガーは、前任者の物議を醸した変化に反して、この転換以前の純粋な可能性としての「現象学」を取り戻そうとしている。ジャン=フランソワ・クルティ ン[19]が書いているように、 ハイデガーは、それを超えるのではなく、新しい傾向、つまり『存在と時間』で展開された現象学的オントロジーを創り出そうとしている。それは「現象学とは 何かをより独創的に考えること、つまり、たとえ現象学という名称を放棄することになっても、その重要性や意味を完全に理解すること」を提案している。 しかし、二人の思想家は、「現象」は、いわゆる「俗的な」意味とは別の現象学的な意味を持つという点で意見が一致している。フランソワーズ・ダストゥール [20]は、「現象は、すぐに与えられるものではなく、現象学そのものの仕事である、明確な主題化によってのみ自らを現す」と書いている。 ハイデガーは、「現象」が自らを現すためにはロゴスが必要であることを認識し、ギリシャ語の源流に立ち返って、それを物事に関する言説というよりも、「見 せること」と理解したと、マルレーヌ・ザラデルは述べている[21]。ハイデガーはそこから、現象学という用語における「現象」と「ロゴス」という二つの 言葉の結合は、「それ自体から現れるもの」を意味するとする、自身の理論的立場を導き出している[22]。 大まかに言えば、ハイデガーは師であるフッサールとは、人間と世界との関係よりも、「事前開放」、つまり、彼が「手元にある存在」と呼ぶものとの出会いを 可能にする「次元」に関心がある点で異なっている。つまり、ポール・リクールが言うところの、「世界における存在」の「そばにある」という存在論的重み、 つまり「傍にある」という存在論的重みに注目しているのだ。 |
| Une expérience phénoménologique : l'œuvre d'art Article détaillé : L'Origine de l'œuvre d'art.  Temple grec de Ségeste Dans l'esprit du « retour aux choses mêmes », prendre pour objets d'étude l'art et l'expérience que nous en avons montrera ce qui en fait la particularité. Le Dictionnaire des Concepts[24], distingue deux courants principaux : Pour Heidegger, l'œuvre d'art est une puissance qui ouvre et « installe un monde ». L'artiste n'a pas une claire conscience de ce qu'il veut faire, seul le « tout fera l'œuvre ». L'œuvre d'art n'est pas un outil, elle n'est pas une simple représentation mais la manifestation de la vérité profonde d'une chose : « ainsi du temple grec qui met en place un monde et révèle une terre, le matériau qui la constitue, un lieu où elle s'impose (la colline pour le temple), et le fondement secret, voilé et oublié de toute chose »[24]. . La poésie aussi va apparaître comme le dire du décèlement de l'étant à partir de l'être. Le poème, est conçu comme un « appel », appel à ce qui est éloigné à venir dans la proximité. En les nommant[N 10], la « Parole poétique » fait venir les choses en la présence, comme dans ces deux simples vers qui introduisent le poème « soir d'hiver » de Georg Trakl : « Quand il neige à la fenêtre, Que longuement sonne la cloche du soir »[25]. Le deuxième courant, représenté par Maurice Merleau-Ponty s'éloigne tout autant de la représentation idéalisée des choses pour appuyer « sur le vécu et le ressenti avant d'être nommé »[26]. « En peignant, le peintre manifeste et montre comment le monde devient sous et par ses yeux, car le peintre peint à la fois le monde et son monde. Tout en se mettant totalement dans ce qu'il peint, le peintre est le serviteur de ce qui est en face à lui »[26]. |
現象学的体験:芸術作品 詳細記事:芸術作品の起源。  ギリシャのセゲスト神殿 「物事そのものへの回帰」の精神に基づき、芸術とそれに対する我々の体験を研究対象とすることで、その特異性が明らかになる。概念辞典[24]は、主に2つの潮流を区別している。 ハイデガーにとって、芸術作品は「世界を開き、世界を構築する」力である。芸術家は自分が何をしたいのか明確に意識しているわけではない。ただ「全体が作 品を作る」だけである。芸術作品は道具でも、単なる表現でもなく、物事の深層にある真実の現れである。「ギリシャの神殿が世界を構築し、大地、それを構成 する物質、それが存在する場所(神殿にとっては丘)、そしてあらゆるものの隠された、覆い隠され、忘れられた基礎を明らかにするように」[24]。詩もま た、存在から存在を明らかにする言葉として現れる。詩は「呼びかけ」、つまり遠くにあるものを近くに呼び寄せる呼びかけとして考えられている。それらに名 前を付けることで、「詩的な言葉」は物事を現実に呼び寄せる。ゲオルク・トラクルの詩「冬の夜」の冒頭の2行は、その例だ。「窓に雪が降るとき、夕べの鐘 が長く鳴り響く」[25]。 モーリス・メルロー=ポンティに代表される第二の流れは、物事の理想化された表現から同様に距離を置き、「名付けられる前に経験し、感じる」ことを重視す る[26]。「絵を描くことで、画家は、自分の目を通して、また自分の目によって、世界がどのように変化していくかを表現し、示す。なぜなら、画家は世界 と自分の世界の両方を描くからだ。自分が描くものに完全に没頭しながら、画家は自分の目の前にあるものの僕である」[26]。 |
| La méthode Si l'on suit Levinas[27], il n'y aurait pas de méthode proprement phénoménologique, mais seulement des gestes qui révèlent un air de famille de méthodes d'approche entre tous les phénoménologues[N 11]. La « phénoménologie » n'a aucun contenu doctrinal à proposer, souligne de son côté François Doyon[28], il s'agit d'« une science qui n’en finit pas de naître et de renaître sous différentes formes », de quelque chose qui n'est même pas une méthode au sens scientifique, uniquement un « cheminement », un mode d'accès à la « chose »; c'est ce mode d'accès que Martin Heidegger va être amené à justifier dans un long paragraphe (§7) de Être et Temps en prenant appui sur le sens grec initial de ce mot, une fois celui-ci décomposé en ses deux éléments originaires, à savoir, « phénomène » et « logos » (§ 7 Être et Temps). Le philosophe Gérard Wormser[1] écrit que « la méthode distinctive (de la phénoménologie) est la « description eidétique », qui vise à rendre raison de l'essence d'un phénomène à partir de la série des variations dont est susceptible son appréhension ». Par la « réduction » le phénoménologue va chercher à isoler un noyau invariant qui permet « de rendre compte des phénomènes tels qu'ils se présentent dans leur nécessité d'essence »[1]. Levinas recense ainsi, quelques caractéristiques de la geste phénoménologique : 1. la place primordiale accordée à la sensibilité et à l'intuition. « La phénoménologie décrit les modes d'accès de la conscience à la signification, ainsi que le précise Husserl, en explorant les structures de l'intuition objectivante (noèse) et de son corrélat (noématique) en tant qu'il est inclus réellement dans l'intuition au sein de laquelle il se rapporte »[29]. 2. la disparition du concept[30], de l'objet théorique, de l'évidence, du phénomène idéalement parfait, au profit d'une attention portée à l'imperfection du vécu, de l'excédent et du surplus que le théorique laisse échapper, qui vont devenir constitutifs de la vérité du phénomène (ainsi du souvenir, toujours modifié par le présent où il revient, donc absence de souvenir absolu auquel se référer, la préférence accordée avec Kierkegaard, au dieu qui se cache, qui est le vrai dieu de la révélation). Ce qui semblait jusqu'ici un échec, une imperfection de la chose (la brumosité du souvenir), par un retournement radical du regard, devient un mode de son achèvement, sa vérité intrinsèque. 3. la réduction phénoménologique qui autorise la suspension de l'approche naturelle et la lutte contre l'abstraction[N 12]. Dans ses Problèmes fondamentaux de la phénoménologie[31], Heidegger, complète cette approche en distinguant trois éléments constitutifs de la « méthode » phénoménologique : la réduction, la construction et la « destruction », ce dernier élément constituant à la fois le socle et l’apogée de sa méthode phénoménologique selon François Doyon. |
方法 レヴィナス[27]に従えば、現象学的な方法というものは存在せず、すべての現象学者たちのアプローチ方法に共通点を見出すことができる行動があるだけだ [N 11]。フランソワ・ドヨン[28]は、「現象学」は教義的な内容を提供することはなく、「さまざまな形で生まれ、生まれ変わることを繰り返す科学」であ り、科学的な意味での方法ではなく、単に「道筋」、つまり「もの」にアクセスする方法にすぎない、と強調している。この到達方法を、マルティン・ハイデ ガーは『存在と時間』の長い段落(§7)で、この言葉のギリシャ語の本来の意味、すなわち「現象」と「ロゴス」という二つの要素に分解して、その根拠を説 明している(§ 7 『存在と時間』)。 哲学者ジェラール・ウォームサー[1]は、「(現象学の特徴的な)方法は「イデティックな記述」であり、それは、現象の理解が影響を受けうる一連の変動か ら、現象の本質を説明することを目的としている」と書いている。現象学者は「還元」によって、現象を「その本質的な必然性において表現する」[1] ことを可能にする不変の核心を分離しようとする。レヴィナスは、現象学的手法のいくつかの特徴を次のように挙げている。 1. 感受性と直感に最優先の地位を与えること。「現象学は、フッサールが指摘するように、客観化直観(ノエシス)とその相関物(ノエマティクス)の構造を探求 することにより、意識が意味にアクセスする方法を記述する。それは、直観が関連付ける直観に実際に含まれているものとしてである」[29]。 2. 概念[30]、理論上の対象、自明性、理想的に完璧な現象が消滅し、その代わりに、経験の不完全性、理論が逃してしまう過剰や余剰、つまり現象の真実を構 成する要素(したがって、現在に回帰するたびに常に変化する記憶、 つまり、参照すべき絶対的な記憶は存在せず、キルケゴールが、隠れている神、つまり啓示の真の神を優先した)。これまで失敗、つまり物事の不完全性(記憶 の曖昧さ)と思われていたものが、見方を根本的に転換することで、その完成の様式、つまりその本質的な真実となる。 3. 現象学的還元は、自然なアプローチの停止と抽象化との闘いを可能にする[N 12]。 ハイデガーは『現象学の基本問題』[31]の中で、このアプローチを補完し、現象学的「方法」を構成する3つの要素、すなわち還元、構築、そして「破壊」を区別している。フランソワ・ドヨンによれば、この最後の要素は、現象学的方法の基盤であると同時にその頂点でもある。 |
| La réduction phénoménologique Article détaillé : Réduction phénoménologique. La réduction phénoménologique ou épochè en grec (ἐποχή / epokhế) consiste pour Husserl « à suspendre radicalement l'approche naturelle du monde », posé comme objet, réduction à laquelle s'ajoute une lutte sans concession contre toutes les abstractions que la perception naturelle de l'objet présuppose[32],[N 13]. La découverte de la « réduction phénoménologique » a donc le sens d'un dépassement du cartésianisme qui se limite à combattre le doute et requiert pour sa cohésion globale, la garantie divine, note Françoise Dastur[33]. Mais si pour Husserl l'« époché », ἐποχή, ou mise entre parenthèses du monde objectif, constituait l'essentiel de la réduction phénoménologique, il n'en allait pas de même pour Heidegger selon qui le « Monde » n'ayant, par construction, aucun caractère objectif, ce type de réduction s'avérait inutile[34],[N 14]. De plus, pour Heidegger, la phénoménologie ne vaut en tant qu'instrument que pour autant que ses propres présupposés sont pris en compte dans la description elle-même. Par rapport à son maître Husserl, on note un certain nombre d'évolutions décisives telles que la recherche du domaine dit « originaire »[N 15], sis dans l'expérience concrète de la vie, par un processus de « destruction » et d'explicitation, qui vont permettre à une herméneutique de la facticité de se développer[35]. Par contre, selon Alexander Schnell[36], on peut considérer qu'on a avec la définition heideggerienne de la phénoménologie, comme reconduction du regard de l'étant à la compréhension de son être, quelque chose qui est en soi un acte de « réduction phénoménologique ». Avec Heidegger, l'« enquête phénoménologique » ne doit pas tant porter sur les vécus de conscience, comme le croyait Husserl que sur l'être pour qui on peut parler de tels vécus, et qui est par là capable de phénoménalisation, à savoir le Dasein, c'est-à-dire, l'existant. Christoph Jamme[37] écrit : « la phénoménologie doit être élaborée comme une auto-interprétation de la vie factive […]. Heidegger définit ici la phénoménologie comme science originaire de la vie en soi ». En fait, la « réduction phénoménologique » va jouer, dans Être et Temps, un rôle essentiel dans l’analytique du Dasein, notamment dans l'analyse de la quotidienneté et la mise à jour des structures existentiales du Dasein, en exigeant un regard résolument plus « authentique »[38]. La réduction dans Être et Temps, conclut François Doyon, « apparaît comme un parcours de détachement progressif à l’aveuglement de la quotidienneté du monde ambiant afin de s’exposer résolument à la finitude radicale de son être ». |
現象学的還元 詳細記事:現象学的還元。 現象学的還元、あるいはギリシャ語でエポケー(ἐποχή / epokhế)とは、フッサールによれば「世界に対する自然なアプローチを根本的に停止すること」であり、対象として設定されたものに対する還元である。 この還元には、対象に対する自然な知覚が前提とするあらゆる抽象概念に対する妥協のない闘争が加わる[32]。[N 13]。したがって、「現象学的還元」の発見は、疑念と闘うことに限定され、その全体的な結束のために神の保証を必要とするデカルト主義を超越する意味を 持つと、フランソワーズ・ダストゥールは述べている[33]。 しかし、フッサールにとって「エポケー」、ἐποχή、つまり客観的世界を括弧で囲むことが現象学的還元の本質であったのに対し、ハイデガーにとってはそ うではなかった。ハイデガーによれば、「世界」は構造上、客観的性格をまったく持たないため、この種の還元は役に立たないものだった[34]、[N 14]。 さらに、ハイデガーにとって、現象学は、その前提自体が記述の中で考慮されている場合にのみ、手段としての価値がある。師であるフッサールと比較すると、 具体的な生活経験にある「原初的」領域[N 15]を「破壊」と明示のプロセスによって探求し、事実性の解釈学を発展させるという、いくつかの決定的な進化が見られる[35]。 一方、アレクサンダー・シュネルによれば、ハイデガーの現象学の定義は、存在の理解からその存在の理解へと視線を戻すものであり、それ自体が「現象学的還 元」の行為であると考えられる。ハイデガーによれば、「現象学的調査」は、フッサールが考えていたような意識の体験よりも、そのような体験について語るこ とができ、それによって現象化が可能である存在、すなわちダセイン、つまり存在者について行うべきである。クリストフ・ジャム[37]は、「現象学は、事 実上の生活に対する自己解釈として構築されなければならない[…]。ハイデガーはここで、現象学を、生活そのものに由来する科学として定義している」と書 いている。 実際、『存在と時間』において「現象学的還元」は、ダセインの分析、特に日常性の分析とダセインの実存的構造の解明において、より「真正」な視点[38] を求めることで、重要な役割を果たす。『存在と時間』における還元は、フランソワ・ドヨンが結論づけるように、「周囲の世界の日常性による盲目性から徐々 に脱却し、自らの存在の根本的な有限性に断固として直面するための道筋として現れる」のだ。 |
| La construction phénoménologique C'est à l'opération d'induction de l'« être », qui n'apparaît jamais spontanément, à partir de l'étant que Heidegger a donné le nom de « construction phénoménologique »[39], c'est une tâche, un projet, qu'il revient au Dasein de réaliser sachant « qu'il n'y a d'être que s'il y a compréhension de l'être, c'est-à-dire si le Dasein existe »[40]. Pour Heidegger, « l’interprétation existentiale du Dasein, comme souci, dans Être et Temps, est une construction ontologique qui possède un sol et une pré-esquisse élémentaire »[41]. |
現象学的構築 ハイデガーは、存在から「存在」を誘導する操作を「現象学的構築」と呼んだ。この操作は決して自発的には現れない。」と呼んだ。これは、ダセインが「存在 は、存在の理解、すなわちダセインの存在があって初めて存在する」[40]ことを認識した上で、達成すべき課題、計画である。ハイデガーにとって、「『存 在と時間』における、関心としてのダセインの実存的解釈は、基盤と基本的な下書きを持つ存在論的構築物である」[41]。 |
| La destruction phénoménologique Articles détaillés : Déconstruction (Heidegger) et Heidegger et Aristote. La « construction réductrice de l’être », en tant qu’interprétation conceptuelle de l’être et de ses structures, implique donc nécessairement une « destruction phénoménologique », c’est-à-dire une « dé-construction » ou démontage critique préalable des concepts légués par la tradition philosophique. Sophie-Jan Arrien[42] note que Heidegger délaisse très rapidement la réduction phénoménologique husserlienne pour lui préférer une méthodologie de la « déconstruction» « qui loin d'être une mise entre parenthèses du caractère facticiel des phénomènes en jeu (le soi, l'histoire, la foi), consiste plutôt à partir d'une explicitation[N 16] critique de ces concepts, en une traversée de la vie telle qu'elle se phénoménalise et se donne facticiellement »[42]. La « destruction phénoménologique » se donne pour tâche de démanteler les constructions théoriques, philosophiques ou théologiques qui recouvrent notre expérience de la vie facticielle et que nous devons faire apparaître. La tâche essentielle consistera à se rapprocher, par exemple, de l’Aristote originel, en se détournant de la scolastique médiévale qui le recouvre. De même, la destruction des présupposés de la science esthétique, qui va « permettre d'accéder à l'œuvre d'art pour la considérer en elle-même »[43], est solidaire de la destruction de l'histoire de l'ontologie. C'est surtout dans son travail sur Aristote que Heidegger a pu préciser sa propre conception de la phénoménologie. Philippe Arjakovsky[44] parle de « travail d'« anabase » que Heidegger a effectué pour dégager les soubassements tant ontologiques qu'existentiels de la Logique aristotélicienne[…] » ainsi est apparu en pleine lumière, le concept originaire de « phénomène » tel qu'il était compris par les grecs, c'est-à-dire, comme « ce qui se montre de soi-même ». Mais comme pour Heidegger les « choses mêmes » ne se donne justement pas dans une intuition immédiate, il se sépare à cette occasion définitivement de Husserl, pour s'engager résolument dans le « cercle herméneutique »[45]. Autre exercice de déconstruction, le démantèlement de la tradition théologique avec laquelle il tentera, en s'inspirant de Luther et de Paul, de retrouver la vérité première du message évangélique, qu'il considère obscurcie et voilée dans la « Scolastique » inspirée d'Aristote[46]. |
現象学的破壊 詳細記事:脱構築(ハイデガー)およびハイデガーとアリストテレス。 存在とその構造に関する概念的な解釈としての「存在の還元的な構築」は、必然的に「現象学的破壊」、すなわち哲学の伝統によって受け継がれてきた概念の 「脱構築」や事前の批判的分解を意味する。ソフィー=ジャン・アリエン[42]は、ハイデガーがフッサールの現象学的還元を非常に早く放棄し、代わりに 「脱構築」という方法論を好んだと指摘している。「これは、問題となっている現象(自己、歴史、信仰)の虚構的な性格を括弧で囲むこととは程遠く、むしろ これらの概念を批判的に明示すること[N 16] から出発し、現象として現れ、虚構的に与えられる人生を横断することである」[42] と指摘している。 「現象学的破壊」は、私たちの虚構的な人生の経験に覆い被さっている、理論的、哲学的、神学的構築物を解体し、それを明らかにすることをその任務としてい る。その本質的な任務は、例えば、中世のスコラ哲学から距離を置き、それを覆い隠しているものから離れて、原初のアリストテレスに近づくことにある。同様 に、美的科学の前提を破壊することは、「芸術作品にアクセスし、それをそれ自体として考察することを可能にする」[43]ものであり、存在論の歴史の破壊 と連帯している。ハイデガーは、とりわけアリストテレスに関する研究を通じて、現象学に関する自身の考えを明確にした。フィリップ・アルジャコフスキー [44]は、アリストテレスの論理学の「存在論的かつ実存的な基礎を明らかにするためにハイデガーが行った「アナバシス」の作業」について述べている。こ うして、ギリシャ人が理解していた「現象」という本来の概念、すなわち「自ら現れるもの」という概念が、はっきりと明らかになった。 しかし、ハイデガーにとって「物自体」は即座の直感では理解できないため、彼はこの点でフッサールと完全に決別し、「解釈学の輪」[45]に断固として取り組むことになる。 もうひとつの脱構築の試みとして、彼は、ルターやパウロに触発され、アリストテレスに触発された「スコラ哲学」によって覆い隠され、不明瞭になったと彼が考える福音のメッセージの本来の真実を見出そうとして、神学の伝統の解体に取り組んだ[46]。 |
| Le statut de la phénoménologie Dans sa volonté de saisir le sens du monde en écartant tous les préjugés comme en renonçant à se situer dans un monde prédonné ou préformé, « la phénoménologie ne rejoint pas une rationalité déjà donnée, elle l'établit par une initiative qui n'a pas de garantie dans l'être et dont le droit repose entièrement sur le pouvoir effectif qu'elle nous donne d'assumer notre histoire […] la phénoménologie comme révélation du monde repose sur elle-même se fonde sur elle-même. Car elle ne peut s'appuyer comme les autres connaissances sur un sol de présuppositions acquises. Il en résulte un redoublement infini d'elle-même. […] Elle se redoublera donc indéfiniment, elle sera comme le dit Husserl un dialogue ou une méditation infinie et dans la mesure où elle reste fidèle à son intention, elle ne saura jamais où elle va » écrit Bernhard Waldenfels dans sa contribution[47]. |
現象学の地位 あらゆる偏見を排除し、あらかじめ与えられた、あるいはあらかじめ形成された世界の中に自分の立場を置くことを放棄することで、世界の意味を理解しようと するその意志において、 「現象学は、すでに与えられた合理性に合致するものではなく、存在において保証のない、その権利が完全に、私たちの歴史を引き受ける力を私たちに与えると いう事実に基づく、独自の取り組みによってそれを確立するものである。[…] 世界を明らかにする現象学は、それ自体に基づいており、それ自体に立脚している。なぜなら、他の知識のように、既得の前提という土台に立脚することはでき ないからだ。その結果、現象学は無限に自己を倍増させることになる。[…] したがって、現象学は際限なく二重化され、フッサールが言うように、無限の対話あるいは瞑想となり、その意図に忠実であり続ける限り、その行き先を決して 知ることができない」と、ベルンハルト・ヴァルデンフェルスは自身の論文で述べている[47]。 |
| Les grandes avancées husserliennes Principaux ouvrages : Ideen, Krisis.., Méditations cartésiennes, Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. |
フッサールの大きな進歩 主な著作:『観念』『危機』『デカルト的省察』『時間の本質に関する現象学のための講義』 |
| L'idée de phénoménologie chez Husserl La phénoménologie de Edmund Husserl se définit d'abord comme une science transcendantale qui veut mettre au jour les structures universelles de l'objectivité. Le premier objectif poursuivi fut d'assurer un fondement indubitable aux sciences et pour cela d'éclairer les conditions théoriques de toute connaissance possible[N 17]. Le projet de la phénoménologie fut d'abord de refonder la science en remontant au fondement de ce qu'elle considère comme acquis et en mettant au jour le processus de sédimentation des vérités qui peuvent être considérées comme éternelles. La phénoménologie propose une appréhension nouvelle du monde, complètement dépouillée des conceptions naturalistes. D'où ce leitmotiv des phénoménologues qu'est le retour aux choses mêmes. Les phénoménologues illustrent ainsi leur désir d'appréhender les phénomènes dans leur plus simple expression et de remonter au fondement de la relation intentionnelle[N 18]. Husserl espère ainsi échapper à la crise des sciences qui caractérise le xxe siècle. C'est avec la reprise détournée du concept d'intentionnalité, empruntée à son maître Franz Brentano, que Husserl consacre ses premiers pas en phénoménologie. Son principe est simple : toute conscience doit être conçue comme « conscience de quelque chose ». En conséquence, la phénoménologie va prendre pour point de départ la description des vécus de conscience afin d'étudier la constitution essentielle des expériences ainsi que l'essence de ce vécu[N 19]. L'intuition fondamentale de Husserl, de ce point de vue, a consisté à dégager ce qu'il appelle l’« a priori universel de corrélation », qui désigne le fait que le phénomène tel qu'il se manifeste est constitué par le sujet, que dont chaque chose a, à chaque fois, pour chaque homme une apparence différente. Husserl ne verse pas pour autant dans le relativisme bien au contraire puisqu'il affirme que cette corrélation subjective est une nécessité d'essence. Ce qui veut dire que l'étant n'est pas autrement qu'il nous apparaît, il n'y a plus de chose en soi[48],[N 20]. En ce sens, on peut donc bien dire que la phénoménologie est une science des phénomènes, mais à condition d'y entendre qu'elle a une vocation descriptive des vécus (de l'expérience subjective). Pour autant, l'activité constitutive du sujet de la corrélation ne doit pas faire croire que la phénoménologie serait un pur subjectivisme. Comme le dit Merleau-Ponty, « le réel est un tissu solide, il n'attend pas nos jugements pour s'annexer les phénomènes », et en conséquence, « la perception n'est pas une science du monde, ce n'est même pas un acte, une prise de position délibérée, elle est le fond sur lequel tous les actes se détachent et elle est présupposée par eux »[49]. La phénoménologie husserlienne se veut également une science philosophique, c'est-à-dire universelle. De ce point de vue, elle est une science apriorique, ou éidétique, à savoir une science qui énonce des lois dont les objets sont des « essences immanentes »[N 21]. Le caractère apriorique de la phénoménologie oppose la phénoménologie transcendantale de Husserl à la psychologie descriptive de son maître Franz Brentano, qui en fut néanmoins, à d'autres égards, un précurseur. La phénoménologie doit en ce sens se distinguer de l'ousiologie, laquelle, comme science philosophique, a pour but l'étude des essences indépendamment de toute subjectivité exclusivement constituante. Échappant à ces déterminations traditionnelles, on signale pour mémoire la dimension radicale de l'interprétation de cette pensée par son secrétaire particulier Eugen Fink[50] dans son ouvrage De la phénoménologie. |
フッサールの現象学における考え方 エドムント・フッサールの現象学は、まず第一に、客観性の普遍的な構造を明らかにしようとする超越論的科学として定義される。その第一の目的は、科学に疑 いの余地のない基礎を確立し、そのためにはあらゆる知識の理論的条件を明らかにすることだった。現象学のプロジェクトは、まず、科学が当然のことと考えて いるものの基礎に立ち返り、永遠とみなせる真理の堆積過程を明らかにすることで、科学を再構築することだった。 現象学は、自然主義的な概念を完全に排除した、世界に対する新しい理解を提案している。そこから、現象学者たちのレトモティフである「物事そのものへの回 帰」が生まれた。現象学者たちは、現象を最も単純な表現で理解し、意図的な関係の基礎に立ち返りたいという願望を、このように表現している。 フッサールは、20世紀を特徴づける科学の危機から逃れることを望んでいる。フッサールは、師であるフランツ・ブレンターノから借りた意図性の概念を間接 的に採用することで、現象学への第一歩を踏み出した。その原理は単純だ。あらゆる意識は「何かに対する意識」として理解されなければならない。その結果、 現象学は、経験の本質と、その経験の本質を研究するために、意識の体験の記述を出発点とする。 この観点から、フッサールの基本的な直感は、彼が「普遍的相関の先験的原理」と呼ぶものを明らかにすることだった。これは、現象はそれが現れる形で主体に よって構成されており、あらゆるものは、あらゆる人にとって、その都度、異なる外観を持つという事実を指している。しかし、フッサールは相対主義に陥って いるわけではない。むしろ、この主観的な相関は本質的に必要なものであると主張している。つまり、存在は私たちに現れる姿以外の姿はなく、物自体というも のはもはや存在しないということだ[48]、[N 20]。この意味で、現象学は現象の科学であると言えるが、それは、現象学が(主観的な経験という)体験を記述する役割を担っていることを理解することを 条件とする。とはいえ、相関の主体の構成的活動は、現象学が純粋な主観主義であると思わせるべきではない。メルロ=ポンティが言うように、「現実とは堅固 な織物であり、現象を併合するために我々の判断を待つことはない」ため、「知覚は世界に関する科学ではなく、行為でも、意図的な立場表明でもなく、あらゆ る行為が浮かび上がる背景であり、それらによって前提とされている」 」[49]。 フッサールの現象学は、哲学的、つまり普遍的な科学でもある。この観点から、それは先験的、つまりイデティックな科学であり、その対象が「内在的な本質」 [N 21]である法則を述べる科学である。現象学の先験的性格は、フッサールの超越論的現象学を、その師であるフランツ・ブレンターノの記述心理学と対比させ る。しかし、他の点では、ブレンターノは先駆者であった。この意味で、現象学は、哲学的科学として、あらゆる主観性を排除した本質の研究を目的とする実体 論とは区別されなければならない。 こうした伝統的な決定から逃れる形で、彼の秘書オイゲン・フィンク[50] が著書『現象学について』で示した、この思想の解釈の急進的な側面が注目される。 |
| Le concept d'Intentionnalité Article détaillé : Intentionnalité.  Franz Brentano « La phénoménologie c'est l'Intentionnalité » affirme ni plus ni moins, Levinas[51]. Heidegger donnerait son accord à cette parole, encore faut-il préciser les contours qu'il donne au concept d'« Intentionnalité », concept qu'il puise principalement dans les cinquième et sixième « Recherches logiques » de Edmund Husserl, que lui-même avait hérité de Brentano note Jean Greisch[52],[N 22]. Traits généraux du concept d'intentionnalité L'« Intentionnalité » qui est depuis Franz Brentano, un « se diriger sur », n'est plus une mise en rapport externe, mais une « structure interne à la conscience » souligne Jean Greisch[53]. Avec Husserl cette conscience ne va plus être considérée comme un simple contenant, réceptacle des images et des choses, ce qu'elle était depuis Descartes ; l'acte de conscience devient une intentionnalité visant un objet nécessairement transcendant précise Françoise Dastur[54],[N 23]. Le même raisonnement est à appliquer aux actes de représentation quels qu'ils soient, chacun tire son sens de la spécificité de l'acte intentionnel. « Tout savoir d'objet est toujours simultanément un savoir que le « Moi » a de lui-même, et ceci n'est point simplement un fait psychique, c'est bien plus une structure d'essence de la conscience » comprend de son côté Eugen Fink[55]. Le fait que l'« Intentionnalité » soit un « a priori » appartenant à « la structure du vécu et non une relation construite après coup » entraîne un sens spécifiquement phénoménologique à la notion d'acte et notamment pour ce qui concerne l'acte de représentation qui peut emprunter selon Heidegger deux directions différentes, la voie naïve qui nous dit par exemple que ce fauteuil est confortable et lourd ou l'autre qui va s'inquiéter de son poids et de ses dimensions[53]. Structure du concept C'est à Husserl que l'on doit la découverte que la connaissance implique au moins deux moments intentionnels successifs (que Heidegger portera à trois), un premier acte correspondant à une visée de sens qui se trouve ultérieurement comblé par un acte intentionnel de remplissement[56]. Heidegger saura s'en souvenir dans sa théorie du Vollzugsinn ou sens de « l'effectuation » qui domine sa compréhension de la vie facticielle et qui fait suite à deux autres moments intentionnels, le Gehaltsinn (teneur de sens), et le Bezugsinn (sens référentiel). C'est la structure intentionnelle de la vie facticielle qui nous livre ce ternaire. Pour une analyse approfondie de ces concepts voir Jean Greisch[57]. L'intuition catégoriale Dans la VIe de ses « Recherches logiques », Husserl, grâce au concept d'« intuition catégoriale »[58], « parvient à penser le catégorial comme donné, s'opposant ainsi à Kant et aux néo-kantiens qui considéraient les catégories comme des fonctions de l'entendement »[59]. Il faut comprendre cette expression d'« intuition catégoriale » comme « la simple saisie de ce qui est là en chair et en os tel que cela se montre » nous dit Jean Greisch. Appliquée jusqu'au bout cette définition autorise le dépassement de la simple intuition sensible soit par les actes de synthèse[N 24], soit par des actes d'idéation. Un exemple de l'extraordinaire fécondité de cette découverte nous est donnée dans les avancées qu'elle a permises pour délivrer Heidegger du carcan du sens attributif de la copule. Dans la proposition « le tableau est mal placé », « l'entrelacement du nom et du verbe fait que la proposition ajoute aux termes isolés, une composition qui relie et sépare donnant à voir un rapport irréductible à une relation formelle, rapport sur lequel elle se fonde plutôt qu'elle ne la fonde »[60],[N 25]. |
意図性の概念 詳細な記事:意図性。  フランツ・ブレンターノ 「現象学とは意図性である」とレヴィナスは断言している[51]。ハイデガーもこの言葉に同意するだろう。しかし、彼が「意図性」という概念に与えた輪郭 を明確にする必要がある。この概念は、エドムント・フッサールの『論理学研究』第5巻および第6巻から主に引き出されたものであり、フッサール自身がブレ ンターノから受け継いだものであると、ジャン・グレイシュは指摘している[52]、[N 22]。 意図性の概念の一般的な特徴 フランツ・ブレンターノ以来、「意図性」は「向かっていくこと」であり、もはや外的な関連付けではなく、「意識の内部構造」であるとジャン・グレイシュは 強調している[53]。フッサールによれば、この意識は、デカルト以来の、単なるイメージや事象の容器、受け皿とは見なされなくなった。意識の行為は、必 然的に超越的な対象を目指す意図性となる、とフランソワーズ・ダストゥールは述べている[54]、[N 23]。 同じ考え方は、あらゆる表現行為にも当てはまる。それぞれの行為は、意図的な行為の特殊性からその意味を引き出すのだ。「対象に関するあらゆる知識は、常 に同時に『自我』がそれ自体について持つ知識でもあり、これは単なる精神的な事実ではなく、むしろ意識の本質的な構造である」と、オイゲン・フィンクは理 解している[55]。 「意図性」が「経験の構造に属する先験的なものであり、後付けで構築された関係ではない」という事実は、行為の概念、特に表象行為に、現象学的に特有の意 味をもたらす。ハイデガーによれば、表象行為は二つの異なる方向、 例えば、この椅子は快適で重いという素朴な道と、その重さや大きさを気にする道だ。 概念の構造 知識には少なくとも2つの連続した意図的瞬間(ハイデガーはこれを3つとする)が含まれるという発見は、フッサールによるものである。最初の行為は意味の 指向に対応し、それは後に意図的な充足行為によって満たされる[56]。ハイデガーは、事実的な生活に対する理解を支配する「実行の意味」である Vollzugsinn の理論において、このことを思い出すことになる。この理論は、他の 2 つの意図的瞬間、すなわち Gehaltsinn(意味内容)と Bezugsinn(参照意味)に続くものである。事実的な生活の意図的構造が、この 3 つを私たちに提供しているのだ。これらの概念の詳細な分析については、ジャン・グレイシュを参照のこと。 カテゴリー的直観 『論理学研究』第6巻において、フッサールは「カテゴリー的直観」の概念によって [58]という概念によって、「カテゴリーを、与えられたものとして考えることに成功し、カテゴリーを理性の機能とみなしたカントや新カント派に対抗した」[59]。 この「カテゴリー的直観」という表現は、「そこにあるものを、それが現れているままの、ありのままの姿で単純に把握すること」と理解すべきだと、ジャン・ グレイシュは述べている。この定義を徹底的に適用すると、統合[N 24]の行為、あるいは観念形成の行為によって、単純な感覚的直観を超越することが可能になる。 この発見の驚くべき実り多さを示す一例は、ハイデガーを、述語の帰属的意味という束縛から解放する上で、この発見がもたらした進歩に見ることができる。 「その絵は不適切な場所に置かれている」という文では、「名詞と動詞が絡み合うことで、この文は個別の用語に加えて、結びつけ、分離する構成要素を加え、 形式的な関係に還元できない関係、つまり、その関係に基づいて成立するよりも、むしろその関係そのものを示すものとなっている」[60]、[N 25]。 |
| La postérité d'Husserl Article connexe : Heidegger et la phénoménologie. Les héritiers immédiats  Centre de Recherches Phénoménologiques et Herméneutiques du CNRS, dirigé par Paul Ricœur, avenue Parmentier à Paris. 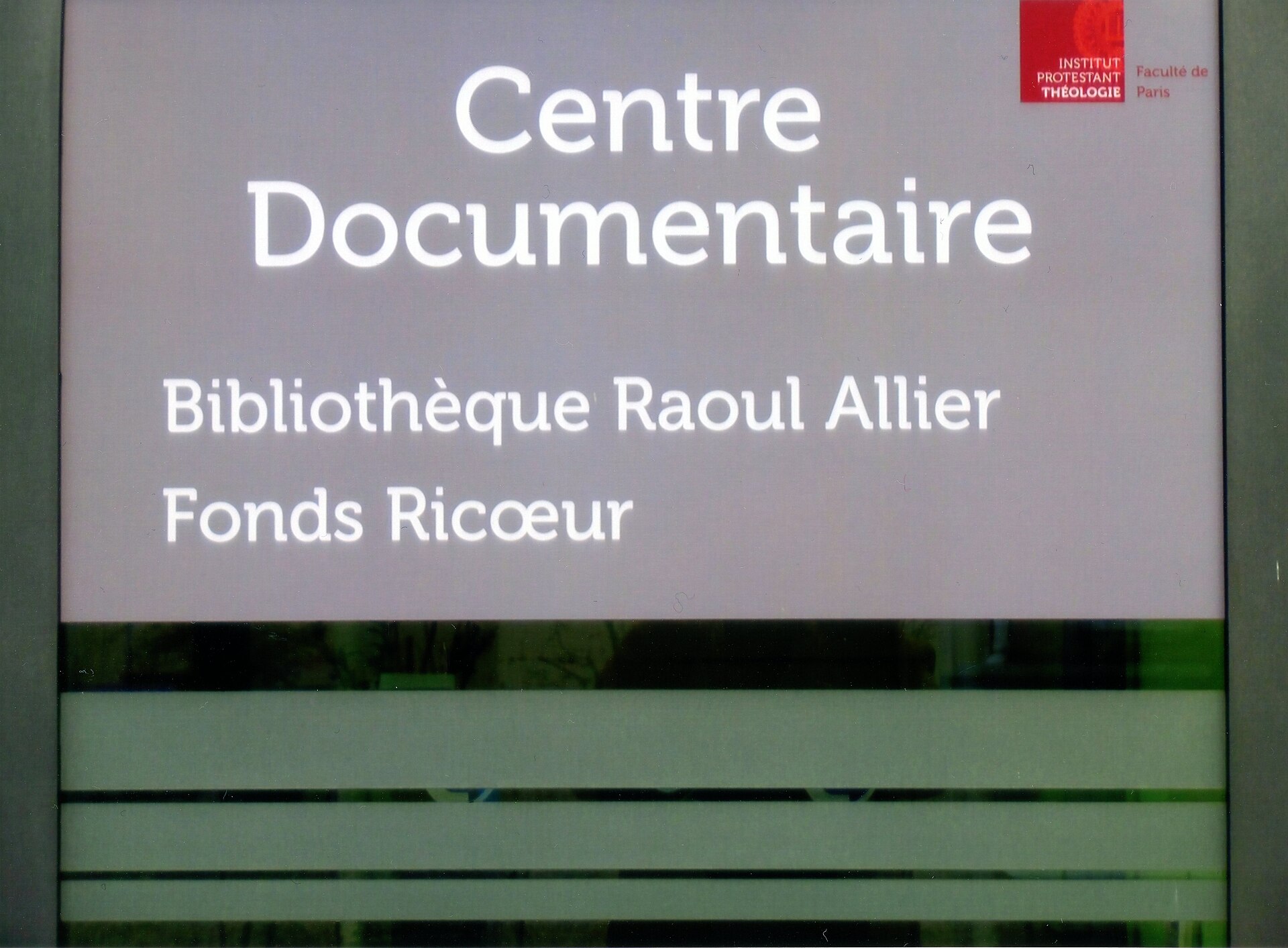 Le Fonds Ricœur à Paris. En 1933, le philosophe Eugen Fink, abandonne la carrière universitaire, pour devenir son secrétaire privé jusqu'à la mort de son maître en 1938. Il est l'auteur de trois ouvrages remarquables de commentaires et de développement à partir de l'œuvre de son mentor, traduits en français : De la phénoménologie[61], la Sixième Méditation cartésienne[62] et Autres rédactions des Méditations cartésiennes[63]. Comme élève et proche compagnon il y eut aussi, un temps, Martin Heidegger, à qui fut confié la publication de son ouvrage Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps. Hans-Georg Gadamer, un autre de ses élèves, rapporte que Husserl disait que, au moins dans la période de l'entre-deux-guerres, « la phénoménologie, c'est Heidegger et moi-même »[64]. Dans une « lettre à Husserl » d'octobre 1927, Heidegger a bien mis en évidence la question qui le séparait de son maître : « Nous sommes d'accord sur le point suivant que l'étant, au sens de ce que vous nommez "monde" ne saurait être éclairé dans sa constitution transcendantale par retour à un étant du même mode d'être. Mais cela ne signifie pas que ce qui constitue le lieu du transcendantal n'est absolument rien d'étant - au contraire le problème qui se pose immédiatement est de savoir quel est le mode d'être de l'étant dans lequel le "monde" se constitue. Tel est le problème central de Sein und Zeit - à savoir une ontologie fondamentale du Dasein »[65]. Autrement dit, l'enquête phénoménologique, pour Heidegger, ne doit pas tant porter sur les vécus de conscience, que sur l'être pour qui on peut parler de tels vécus, et qui est par là capable de phénoménalisation, à savoir le Dasein, c'est-à-dire, l'existant. Le conflit phénoménologique entre Husserl et Heidegger a influencé le développement d'une phénoménologie existentielle et de l'existentialisme : en France, avec les travaux de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir ; en Allemagne avec la phénoménologie de Munich (Johannes Daubert, Adolf Reinach) et Alfred Schütz ; en Allemagne et aux États-Unis avec la phénoménologie herméneutique de Hans-Georg Gadamer et de Paul Ricœur[66]. La philosophie husserlienne fut ensuite développée, et en des sens souvent infléchis, par des penseurs aussi divers que Maurice Merleau-Ponty, Max Scheler, Hannah Arendt, Gaston Bachelard, Dietrich von Hildebrand, Jan Patočka, Jean-Toussaint Desanti, Guido Küng[réf. nécessaire] et Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas[67], se penche sur l'évolution du concept d'« intentionnalité ». En tant que compréhension d'être, c'est toute l'existence du Dasein qui se trouve concernée par l'intentionnalité. Il en est ainsi du sentiment qui lui aussi vise quelque chose, ce quelque chose qui n'est accessible que par lui. « L'intentionnalité du sentiment n'est qu'un noyau de chaleur auquel s'ajoute une intention sur un objet senti ; cette chaleur effective qui est ouverte sur quelque chose à laquelle on accède en vertu d'une nécessité essentielle que par cette chaleur effective, comme on accède par la vision seule à la couleur ». Jean Greisch[68] a cette formule étonnante « le vrai visage -vu de l'intérieur-de l'intentionnalité n'est pas le « se-diriger-vers » mais le devancement de soi du souci ». |
フッサールの後継者たち 関連項目:ハイデガーと現象学。 直接の後継者たち  CNRS(フランス国立科学研究センター)の現象学・解釈学研究センター。ポール・リクールが所長を務め、パリのパルマンティエ通りに所在。 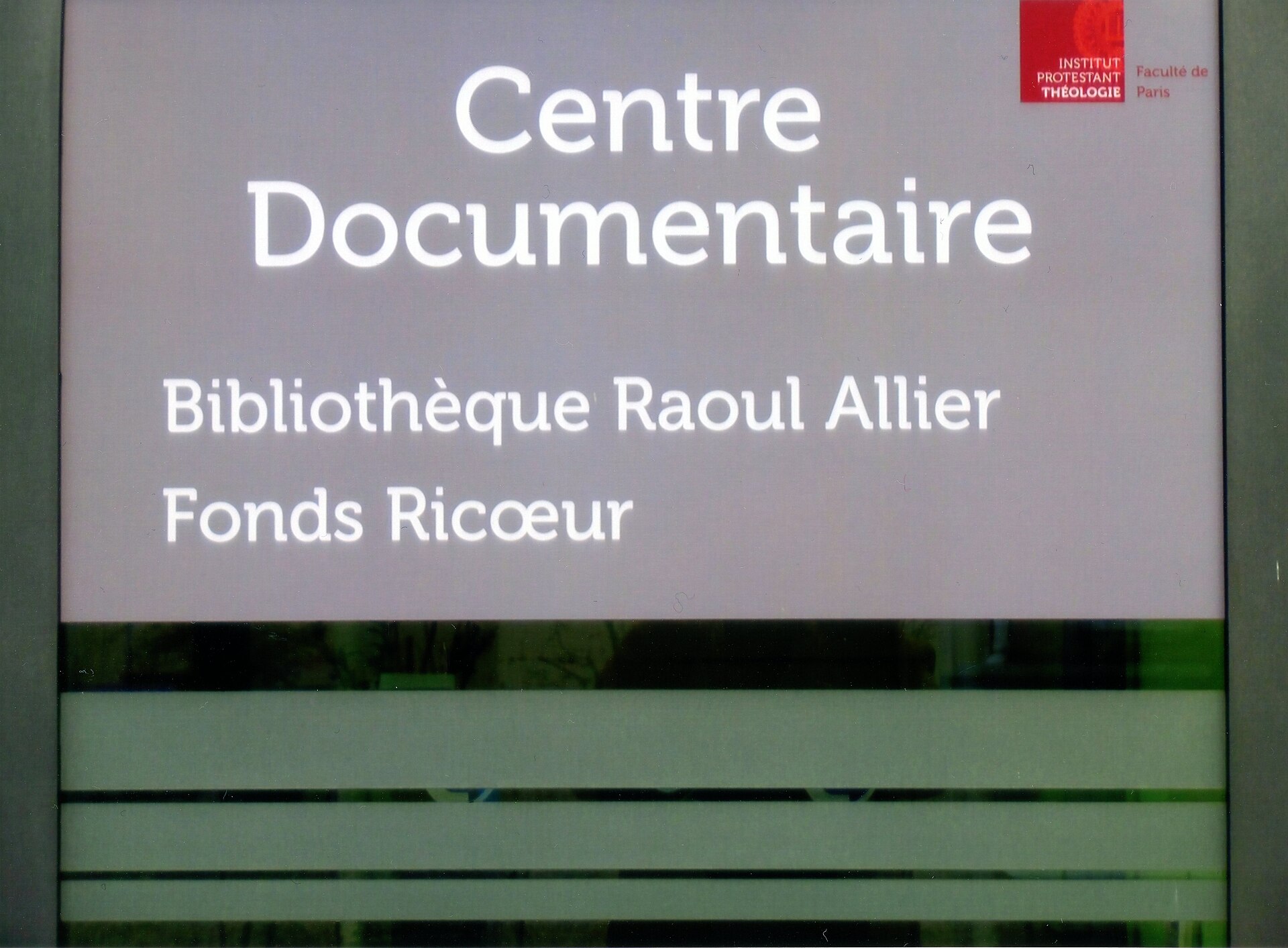 パリのリクール基金。 1933年、哲学者オイゲン・フィンクは学界を離れ、1938年に師が亡くなるまでその私設秘書を務めた。彼は、師匠の著作に基づいて、3冊の注目すべき 解説書および発展書を執筆し、それらはフランス語に翻訳されている。それらは、『現象学について』[61]、『デカルトの第六瞑想』[62]、『デカルト の瞑想に関するその他の論文』[63]である。 弟子であり親しい仲間として、一時期、マルティン・ハイデガーもいた。彼は、フッサールの著作『時間の本質に関する現象学講義』の出版を任されていた。別 の弟子であるハンス=ゲオルク・ガダマーは、少なくとも戦間期には、フッサールが「現象学とはハイデガーと私である」[64] と語っていたと伝えている。1927年10月の「フッサールへの手紙」の中で、ハイデガーは師と自分を隔てる問題を明確に指摘している。「私たちは、あな たが『世界』と呼ぶ意味での存在は、同じ存在様式を持つ存在に立ち返ってその超越的な構成を明らかにすることはできないという点で意見が一致している。し かし、それは、超越的な場所を構成するものが、まったく存在ではないことを意味するわけではない。それどころか、すぐに生じる問題は、「世界」が構成され る存在のあり方は何か、ということだ。これが『存在と時間』の中心的な問題、すなわち、ダセインの基本的な存在論である」[65]。つまり、ハイデガーに とって、現象学的調査は、意識の体験そのものよりも、そのような体験について語ることができ、それによって現象化が可能である存在、すなわちダセイン、つ まり存在するものについて行うべきだということだ。 フッサールとハイデガーの現象学的対立は、実存的現象学と実存主義の発展に影響を与えた。フランスではジャン=ポール・サルトルとシモーヌ・ド・ボーヴォ ワールの研究、ドイツではミュンヘン現象学(ヨハネス・ダウベルト、アドルフ・ライナッハ)とアルフレート・シュッツ ドイツとアメリカでは、ハンス=ゲオルク・ガダマーとポール・リクールによる解釈学的現象学がそれにあたる[66]。 フッサールの哲学はその後、モーリス・メルロー=ポンティ、マックス・シェラー、ハンナ・アーレント、ガストン・バシュラール、ディートリッヒ・フォン・ ヒルデブランド、ヤン・パトチカ、ジャン=トゥーサン・デサンティ、グイド・キュング[要出典]、エマニュエル・レヴィナスなど、さまざまな思想家たちに よって、しばしば異なる方向へと発展していった。 エマニュエル・レヴィナス[67]は、「意図性」の概念の変遷について考察している。存在の理解として、意図性はダゼインの存在全体に関わるものである。 感情もまた、それによってのみ到達可能な何かを指し示すものであり、その点でも同様である。「感情の意図性は、感じられた対象に対する意図が加わった、熱 の核にすぎない。この実効的な熱は、本質的な必要性によってのみアクセスできる何かに開かれている。それは、視覚だけで色にアクセスするのと同じであ る」。ジャン・グレイシュ[68]は、「意図性の真の姿は、内部から見た場合、『向かっていく』ことではなく、自己の懸念を先取りすることである」という 驚くべき表現をしている。 |
| Élargissement heideggérien Délaissant l'ontologie spéculative et la phénoménologie descriptive, Heidegger considère dans Être et Temps (SZ p. 38)[N 26], « que l'ontologie et la phénoménologie devaient bel et bien partir de l'« herméneutique » du Dasein » écrit Jean Grondin[69]. S'il a été beaucoup dit que la phénoménologie de Heidegger était une herméneutique Jean Grondin[70] souligne que l'herméneutique est elle-même une phénoménologie au sens où « il s'agit de reconquérir le phénomène du Dasein contre sa propre dissimulation ». Parce qu'une chose peut se montrer en soi-même, remarque Heidegger, elle peut se montrer autre qu'elle n'est (apparence) ou indiquer autre chose (indice), note Marlène Zarader[71]. Chez Heidegger il n'y a pas d'inconnaissable en arrière-plan comme chez Kant (la chose en soi), ce qui est « phénomène » de façon privilégié selon François Vezin[72] « c'est quelque chose qui le plus souvent ne se montre justement pas, qui à la différence de ce qui se montre d'abord et le plus souvent est en retrait mais qui est quelque chose qui fait corps avec ce qui se montre de telle sorte qu'il en constitue le sens le plus profond ». Dans une opposition frontale à Husserl, Heidegger avance (SZ p. 35) que la phénoménologie a pour but de mettre en lumière ce qui justement ne se montre pas spontanément de lui-même et se trouve le plus souvent dissimulé confirme Jean Grondin[73], d'où la nécessité d'une herméneutique comme le remarque Marlène Zarader.« Si le phénomène est ce qui se montre, il sera l'objet d'une description […] ; si le phénomène est ce qui se retire dans ce qui se montre, alors il faut se livrer à un travail d'interprétation ou d'explicitation de ce qui se montre, afin de mettre en lumière ce qui ne s'y montre pas de prime abord et le plus souvent »[74]. Après Être et temps, Heidegger ne s'intéressera plus à la description du sens de l'Être à partir du Dasein « mais il tente de le faire voir tel qu'il se déploie dans et par la pensée » écrit Sylvaine Gourdain[18], qui fait par ailleurs en note la remarque suivante : « Sans doute faudrait-il préciser et dire qu'il s'agit (avec Heidegger) d'une phénoméno-logie, c'est-à-dire non d'une science descriptive et épistémologique des phénomènes tels qu'ils apparaissent à la conscience mais d'une pensée ou d'un dire du seul « phénomène », qui en réalité intéresse Heidegger, à savoir l'« Être » ». |
ハイデガーの拡張 思索的な存在論と記述的な現象学を捨て、ハイデガーは『存在と時間』(SZ p. 38)[N 26]の中で、「存在論と現象学は、まさにダセインの「解釈学」から出発すべきである」と述べている、とジャン・グロンダン[69]は記している。ハイデ ガーの現象学は解釈学であるとの見方が多くあるが、ジャン・グロンダン[70]は、解釈学自体が「実存の現象を、それ自身の隠蔽から取り戻すこと」という 意味で現象学である、と強調している。 物事はそれ自体で現れることができるため、ハイデガーは、それがそれ自体とは異なるもの(外観)として現れたり、別のものを示したり(兆候)することがで きる、と述べている[71]。ハイデガーには、カントのように(物自体という)背景にある知ることのできないものは存在しない。フランソワ・ヴェザンによ れば、それは「現象」という特権的なものである[72]。「それは、ほとんどの場合、まさに現れないものであり、最初に、そしてほとんどの場合、現れるも のとは違って、控えめであるが、現れるものと一体となって、その最も深い意味を構成するものである」。 フッサールとは正反対の立場から、ハイデガーは(SZ p. 35)、現象学の目的は、自発的には現れず、ほとんどの場合隠されているものを明らかにすることだと主張している、とジャン・グロダン[73]は述べてい る。そのため、マルレーヌ・ザラデルが指摘するように、解釈学が必要となる。現象が表れるものであるならば、それは記述の対象となるだろう […]。現象が表れるものの中に隠れているものであるならば、表れるものを解釈し、説明し、そこに表れないもの、そしてほとんどの場合、表れないものを明 らかにする作業に取り組まなければならない」[74]。 『存在と時間』以降、ハイデガーは、ダセインに基づく存在の意味の記述にはもはや関心を示さず、「思考の中で、そして思考によって展開される存在を、その まま見ようとした」とシルヴァイン・グルダンは記している[18]。また、彼女は注釈で次のように述べている。「おそらく(ハイデガーにとって)それは現 象学、つまり意識に現れる現象を記述し認識論的に研究する科学ではなく、ハイデガーが実際に興味を持っている「現象」、すなわち「存在」そのものを思考し 表現する学問である、と明確に述べるべきだろう」 」 |
| La phénoménologie sectorielle contemporaine Cette section peut contenir un travail inédit ou des déclarations non vérifiées (octobre 2021). Vous pouvez aider en ajoutant des références ou en supprimant le contenu inédit. Sergiu Celibidache : phénoménologie de la musique Gaston Bachelard : phénoménologie de l'imagination Maurice Merleau-Ponty : phénoménologie de la perception et du corps propre Jan Patočka : phénoménologie dynamique ou phénoménologie du monde naturel Hans-Georg Gadamer : phénoménologie du dialogue Michel Henry : phénoménologie de la vie (comme auto-affection) Paul Ricœur : phénoménologie de la volonté Jean-Luc Marion : phénoménologie de la donation Renaud Barbaras : phénoménologie de la vie (comme mouvement) Natalie Depraz : phénoménologie de l'attention et de la surprise Claude Romano : phénoménologie de l'événement Bruce Bégout : phénoménologie de la quotidienneté Alexander Schnell : phénoménologie constructive/générative Jean-Louis Chrétien : phénoménologie de la parole Erazim Kohák : écophénoménologie Marc Richir : phénoménologie refondue ou hyperbolique Henri Maldiney : phénoménologie de l'existence Emmanuel Falque: phénoménologie du hors-phénoménalité[75 |
現代の分野別現象学 このセクションには、未発表の著作や未確認の記述が含まれている可能性がある(2021年10月)。参考文献を追加したり、未発表のコンテンツを削除したりすることで、このセクションの改善に協力できる。 セルジュ・チェリビダッケ:音楽の現象学 ガストン・バシュラール:想像力の現象学 モーリス・メルロー=ポンティ:知覚と自己の身体の現象学 ヤン・パトチェカ:動的現象学または自然界の現象学 ハンス=ゲオルク・ガダマー:対話の現象学 ミシェル・アンリ:生命(自己愛着としての)の現象学 ポール・リクール:意志の現象学 ジャン=リュック・マリオン:贈与の現象学 ルノー・バルバラ:生命(運動としての)の現象学 ナタリー・デプラズ:注意と驚きの現象学 クロード・ロマーノ:出来事の現象学 ブルース・ベグー:日常性の現象学 アレクサンダー・シュネル:建設的/生成的現象学 ジャン=ルイ・クレティアン:言葉の現象学 エラジム・コハーク:エコ現象学 マルク・リシール:再構築された、あるいは双曲的な現象学 アンリ・マルディネイ:存在の現象学 エマニュエル・ファルク:現象外性の現象学[75 |
| Le tournant théologique de la phénoménologie française Dominique Janicaud[76], rappelle que dans la vision de Husserl, l'intentionnalité ne concerne que les phénomènes du monde et en aucun cas l'au-delà du monde. Renaud Barbaras[77] rappelle l'impératif explicite de Husserl : « toute intuition donatrice originaire est une source de droit pour la connaissance mais tout ce qui s'offre à nous dans cette intuition doit être simplement reçu pour ce qu'il se donne, sans outrepasser les limites dans lesquelles il se donne ». À l'occasion d'un véritable pamphlet, publié en 1990, intitulé Le tournant théologique de la phénoménologie française, Dominique Janicaud dénonce le fait qu'à « partir des années 1970, s'opère une singulière ouverture au transcendant, à l'absolu et à l'originaire qui […] scellent une alliance avec des préoccupations de type théologique ou religieux »[78]. Il situe en 1961 avec la publication de Totalité et Infini d'Emmanuel Levinas la première œuvre majeure de philosophie qui assume ce tournant de la phénoménologie vers la théologie, tendance confirmée depuis lors par toute une série d'autres philosophes (Paul Ricœur, Michel Henry, Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien). Pour Dominique Janicaud, face à ces multiples démarches, qui réintroduisent « l'absolument Autre » (Levinas), « l'Archi-Révélation de la vie »(Michel Henry), la donation pure (Jean-Luc Marion), la question devient : qu'est-ce qui reste de phénoménologique dans ces œuvres[79] ? Toutes ces tentatives restent éloignées de la neutralité scientifique dont Edmund Husserl désirait doter la phénoménologie. |
フランス現象学の神学的転換 ドミニク・ジャニコ[76]は、フッサールの見解では、意図性は世界の現象のみに関係し、決して世界の彼方に関係するものではないと指摘している。ル ノー・バルバラス[77]は、フッサールの明確な要求を次のように述べている。「あらゆる原初的な直観は、認識の権利の源泉であるが、その直観の中で我々 に提示されるものはすべて、それが与えるものとして、それが与える限界を超えずに、単に受け取られるべきである」。 1990年に出版された『フランス現象学の神学的転換』と題された、まさにパンフレットのような本の中で、 ドミニク・ジャニコーは、「1970年代以降、超越的、絶対的、原初的なものに対する特異な開放が起こり、それが神学的あるいは宗教的な関心と結びつい た」[78] ことを非難している。彼は、1961年にエマニュエル・レヴィナスが『全体性と無限』を出版したことを、現象学が神学へと転換した最初の主要な哲学作品と 位置づけており、この傾向はその後、他の多くの哲学者(ポール・リクール、ミシェル・アンリ、ジャン=リュック・マリオン、ジャン=ルイ・クレティエン) によって確認されている。ドミニク・ジャニコーは、こうした「絶対的に他者」(レヴィナス)、「生命の究極的啓示」(ミシェル・アンリ)、純粋な贈与 (ジャン=リュック・マリオン)を再導入する多様なアプローチに直面して、これらの著作に現象学的な要素は残されているのかという疑問を投げかけている [79]。これらの試みはすべて、エドムント・フッサールが現象学に与えたかった科学的客観性からは程遠いものだ。 |
| Applications pratiques La phénoménologie connaît aussi des applications pratiques. Natalie Depraz - recherches sur l'adaptation de l'attitude phénoménologique lors de pratiques d'entretiens Emmanuel Galacteros - fondateur de l'entretien phénoménologique de la vie radicale (inspiration Michel Henry) Alfonso Caycedo - pratiques de la réduction phénoménologique (Edmund Husserl, Martin Heidegger, Ludwig Binswanger) psychiatrie et prophylaxie sociale. Phénoménologie appliquée axiologos. Pierre Vermersch, technique de l'entretien d'explicitation et la psycho-phénoménologie Henri Maldiney - étude des pathologies psychiques comme fléchissement des modalités d'existence. Le Cercle herméneutique : cette revue de phénoménologie anthropologique aborde des sujets appliqués au quotidien, avec des sujets autour de l'hystérie, la paranoïa, le sentiment d'étrangeté à soi, le besoin d'événements, l'homme intérieur et le discours intérieur. Recherches qualitatives au Canada La phénoménologie a aussi eu une grande influence sur la psychologie telle qu'elle se pratique encore de nos jours et plus généralement sur l'épistémologie. Elle a donné naissance à une clinique psychiatrique particulièrement riche, à partir des travaux du psychanalyste Ludwig Binswanger. En France, elle influença le courant de la psychothérapie institutionnelle. |
実用的な応用 現象学は実用的な応用もされている。 ナタリー・デプラズ - 面接の実践における現象学的姿勢の適応に関する研究 エマニュエル・ガラクトロス - 急進的な生活に関する現象学的面接の創始者(ミシェル・アンリに触発された) アルフォンソ・カイセド - 現象学的還元の実践(エドムント・フッサール、マルティン・ハイデガー、ルートヴィヒ・ビンズワンガー)精神医学および社会予防医学。 応用現象学アクシオロゴス。 ピエール・ヴェルメルシュ、説明的面接技法および精神現象学 アンリ・マルディーネ - 存在様態の弱体化としての精神病理の研究。 解釈学サークル:この人類学的現象学の雑誌は、ヒステリー、パラノイア、自己に対する異質感、出来事への欲求、内なる人間、内なる言説など、日常生活に適用される主題を取り上げている。 カナダにおける質的調査 現象学は、今日でも実践されている心理学、そしてより一般的には認識論にも大きな影響を与えている。精神分析医ルートヴィヒ・ビンズワンガーの研究から、特に豊かな精神医学の臨床が生まれた。フランスでは、制度精神療法の流れに影響を与えた。 |
| Notes n1. « D’une façon générale, la phénoménologie s’occupe de déterminer ce qui dans chaque espèce d’apparence est réel et vrai ; à cette fin, elle fait ressortir les causes et les circonstances particulières qui produisent et modifient une apparence, afin que l’on puisse à partir de l’apparence inférer le réel et le vrai. […] La phénoménologie dans son acception la plus générale peut être qualifiée d’optique transcendante, dans la mesure où elle détermine en partant du vrai l’apparence, et inversement, en partant de l’apparence le vrai »-Lambert-Neues Organon, (§266)-« Sixième section : de la représentation sémiotique de l'apparence », dans Johann-Heinrich Lambert, Nouvel Organon : Phénoménologie (trad. Gilbert Fanfalone), Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 2002 (lire en ligne [archive]), p. 193 n2. « Kant remarque que la connaissance débute avec l'expérience sensible, sans pour autant en provenir, et que l'interrogation sur le phénomène doit être menée dans le cadre d'une philosophie transcendantale. Pour cela il ne faut pas confondre la présentation des choses elles-mêmes, qui nous demeure inaccessible, et le phénomène, qui n'est autre que l'objet possible de l'intuition d'un sujet »-article Phénomène Dictionnaire des concepts philosophiques, 2013, p. 613 n3. « Dans ma Phénoménologie de l'Esprit, qui forme la première partie du système de la connaissance, j'ai pris l'Esprit à sa plus simple apparition ; je suis parti de la conscience immédiate afin de développer son mouvement dialectique jusqu'au point où commence la connaissance philosophique, dont la nécessité se trouve démontrée par ce mouvement même »-G. W. F. Hegel, Logik, §25 ; trad. fr. A. Vera : Science de la logique, Paris, Ladrange, 1859, t. 1, p. 257. n4. « La Volonté, seule, lui [sc. à l'homme] donne la clef de sa propre existence phénoménale, lui en découvre la signification, lui montre la force intérieure qui fait son être, ses actions, son mouvement. Le sujet de la connaissance, par son identité avec le corps, devient un individu ; dès lors, ce corps lui est donné de deux façons toutes différentes : d'une part comme représentation dans la connaissance phénoménale, comme objet parmi d'autres objets et comme soumis à leur loi ; et d'autre part, en même temps, comme ce principe immédiatement connu de chacun, que désigne le mot Volonté »-A. Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, trad. fr. A Burdeau, Paris, PUF, 1966, vol. 1, §18. n5. voir sur cette ambition la première méditation des Méditations cartésiennes, 1986, p. 6 n6. « Phénoménologie : cela désigne une science, un ensemble de disciplines scientifiques ; mais phénoménologie désigne en même temps et avant tout, une méthode et une attitude de pensée : l'attitude de pensée spécifiquement philosophique et la méthode spécifiquement philosophique »-Edmund Husserl 2010, p. 45 n7. « Heidegger ne demande jamais Was ist das Sein ?. Il met en garde au contraire contre l'absurdité d'une question ainsi formulée […] Il demande plutôt. Comment est-il signifié ? Quel est son sens ? » n8. Si pour Kant, la connaissance débute avec l'expérience sensible « ce sont les objets qui doivent se régler sur notre connaissance et non l'inverse, et les objets ne nous livrent pas la nature des choses, leur être nouménal mais les formes sous lesquelles notre connaissance les appréhende »-article Phénomène Dictionnaire des concepts philosophiques, 2013, p. 613 n9. Ce « droit aux choses mêmes », s'oppose à toutes les constructions échafaudées dans le vide, à la reprise de concepts qui n'ont rien de bien fondé que l'apparence et l'ancienneté-Martin Heidegger 1986, p. 54 n10. Nommer n'est pas simplement faire voir mais faire apparaître au sens strict insiste Jean Beaufret-Jean Beaufret 1973, p. 125 n11. par exemple c'est autour du « phénomène de la vie », que Heidegger aurait construit sa propre approche de la phénoménologie-Emmanuel Levinas 1988, p. 112 n12. voir pour l'approfondissement de tous ces points les pages lumineuses que Lévinas y consacre-Emmanuel Levinas 1988, p. 111-123 n13. À dire vrai « l'Épochè vise à faire apparaître, l'apparaître lui-même et non pas seulement telle ou telle apparition essentielle »-Dominique Janicaud 2009, p. 67 n14. « N'entre pas plus dans le débat les questions distinctes mais étroitement interdépendantes : celles de la frontière entre donné et construit, objet et sujet […] qui s'interrogent jusqu'à quel point les hommes sont prisonniers de cadres « linguistico-pragmatiques » […] à travers lesquels, ils voient le monde […] »-Dictionnaire des Concepts philosophiques, 2012, p. 614 n15. L'origine, si elle doit être autre chose qu'un flatus voci, doit correspondre au lieu d'émergence du matériau philosophique qu'est le concept et rendre compte de sa formation et de son déploiement concret-Sophie-Jan Arrien 2014, p. 38 n16. la (Auslegung ) ou explicitation est le nom que donne Heidegger à l'éclaircissement des présupposés de la compréhensionJean Grondin 1996, p. 191 n17. « L'obscurité qui enveloppe la connaissance quant à son sens ou à son essence appelle une science de la connaissance, une science qui ne veut rien d'autre qu'amener la connaissance à une clarté véritable »-Edmund Husserl 2010, p. 69 n18. Mais comme le note Jean-François Lyotard : « pour accomplir cette opération, il faut sortir de la science même et plonger dans ce dans quoi elle plonge innocemment. C'est par volonté rationaliste que Husserl s'engage dans l'anté-rationnel »-Jean-François Lyotard 2011, p. 9 n19. « Un trait distinctif des vécus qu'on peut tenir véritablement pour le thème central de la phénoménologie orientée « objectivement » : l'intentionnalité ». Cette caractéristique éidétique concerne la sphère des vécus en général, dans la mesure où tous les vécus participent en quelque manière à l'intentionnalité, quoique nous ne puissions dire de tout vécu qu'il a une intentionnalité. « C'est l'intentionnalité qui caractérise la conscience au sens fort et qui autorise en même temps de traiter tout le flux du vécu comme un flux de conscience et comme l'unité d'une conscience »-E. Husserl, Ideen I, § 84 ; trad. fr., op. cit., p. 283. n20. « L'alternative idéalisme/réalisme est dépassée (et tout aussi bien la dualité subjectif/objectif) par une corrélation préalable, ce fait irréductible qu'aucune image physique ne peut rendre : l'éclatement de la conscience dans le monde, d'emblée conscience d'« autre chose que soi ». Il n'y a pas de conscience pure. « Toute conscience est conscience de quelque chose » proclame que la pseudo pureté du cogito est toujours prélevée sur une corrélation intentionnelle préalable »-Dominique Janicaud 2009, p. 44 n21. « La phénoménologie pure ou transcendantale ne sera pas érigée en science portant sur des faits, mais portant sur des essences (en science « éidétique ») ; une telle science vise à établir uniquement des « connaissances d'essence » et nullement des faits »-E. Husserl, Ideen I, Préface ; trad. fr., op. cit., p. 7. n22. « On ne trouve dans la donnée immédiate [de la conscience] rien de ce qui, dans la psychologie traditionnelle, entre en jeu, comme si cela allait de soi, à savoir : des data-de-couleur, des data-de-son et autres data de sensation ; des data-de-sentiment, des data-de-volonté, etc. Mais on trouve ce que trouvait déjà René Descartes, le cogito, l'intentionalité, dans les formes familières qui ont reçu, comme tout le réel du monde ambiant, l'empreinte de la langue : le « je vois un arbre, qui est vert ; j'entends le bruissement de ses feuilles, je sens le parfum de ses fleurs, etc. » ; ou bien « je me souviens de l'époque où j'allais à l'école », « je suis inquiet de la maladie de mon ami », etc. Nous ne trouvons là, en fait de conscience, qu'une conscience de… »E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die tanszendentale Phänomenologie, La Haye, Martinus Nijhoff, 1954, § 68 ; trad. fr. G. Granel : La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Paris, Gallimard, Tel, 1976, p. 262. n23. Il en découle deux conséquences : premièrement « que la perception est d'abord un commerce concret et pratique avec les choses, je ne perçois pas pour seulement percevoir mais pour m'orienter, percevoir n'est plus une simple observation neutre » et deuxièmement « que l'objet n'est plus totalement étranger au sujet, qu'il ne lui est plus absolument extérieur »Françoise Dastur 2011, p. 13 n24. L'exemple de Jean Greisch (du chat qui est sur le paillasson) et qui est autre chose qu'un paillasson plus un chat ou les exemples du troupeau de moutons ou de la foule qui manifeste, enfin encore plus simple et plus évident la forêt et pas seulement une série d'arbres, soit par des actes d' idéationJean Greisch op cité 1994 pages 56-57 n25. En effet pouvoir énoncer que « le tableau est mal placé » dans un coin de la salle suppose au préalable que soit manifeste la salle de cours en son entier, visée en tant que salle cours exigeant un emplacement déterminé du tableau et non une salle de danse exigeant un autre emplacement; le sens du « est », est plus ample que dans le simple énoncé, il opère de manière préverbale et prélogique avant tout énoncé une synthèse unifiante qui permet de rassembler les choses et de les distinguer sans les séparer (article Logique Le Dictionnaire Martin Heidegger, p. 778). n26. « La philosophie est l'ontologie phénoménologique universelle issue de l'« herméneutique » du Dasein, qui en tant qu'analytique de l'existence (l'existentialité), a fixé comme terme à la démarche de tout questionnement philosophique le point d'où il jaillit et celui auquel il remonte » |
注 n1. 「一般的に、現象学は、あらゆる種類の現象において、何が現実であり、真実であるかを決定することに取り組んでいる。その目的のために、現象を生み出し、 変化させる特定の要因や状況を明らかにし、現象から現実と真実を推測できるようにする。[…] 現象学は、その最も一般的な意味において、超越的な視点と表現することができる。なぜなら、それは真実から外観を決定し、逆に、外観から真実を決定するか らだ」-ランバート『新オルガノン』 (§266)-「 第六節:外観の記号的表現について」ヨハン・ハインリッヒ・ランベルト著『新オルガノン:現象学』(ギルバート・ファンファローン訳)、ヴリン社、「哲学 テキスト文庫」シリーズ、2002年(オンラインで読む [アーカイブ])、193ページ n2. 「カントは、認識は感覚的経験から始まるが、そこから生じるわけではないこと、そして現象に関する探求は超越論的哲学の枠組みの中で行わなければならない ことを指摘している。そのためには、私たちには理解できない物事そのものの提示と、主体の直観の対象となりうる現象とを混同してはならない」-「現象」の 項目、哲学概念辞典、2013年、613ページ n3. 「私の『精神の現象学』では、認識体系の第一部を構成する部分において、精神をその最も単純な出現形態で捉えた。私は、即座の意識から出発し、その弁証法 的運動を、哲学的認識が始まる地点まで発展させた。その必要性は、この運動そのものによって実証されている」―G. W. F. ヘーゲル、『論理学』§25 仏訳 A. ベラ:『論理学』パリ、ラドランジュ、1859年、第1巻、257ページ。 n4. 「意志だけが、彼(人間)に、彼自身の現象的存在の鍵を与え、その意味を明らかにし、彼の存在、行動、運動を構成する内なる力を示す。認識の主体は、身体 との同一性によって、個人となる。それゆえ、この身体は二つのまったく異なる形で与えられる。一方では、現象的認識における表象として、他の物体の一つと して、そしてそれらの法則に従属するものとして。他方では、同時に、各人が直ちに認識する原理として、それは「意志」という言葉で表されるものである。」 -A. ショーペンハウアー、『意志として、また表象としての世界』、仏訳 A Burdeau、パリ、PUF、 1966年、第1巻、§18。 n5. この野望については、『デカルトの瞑想』の最初の瞑想、1986年、6ページを参照のこと。 n6. 「現象学:それは科学、一連の科学分野を指す。しかし現象学は同時に、そして何よりもまず、方法と思考の姿勢、すなわち、特に哲学的な思考の姿勢と特に哲学的な方法を指す」―エドムント・フッサール 2010年、p. 45 n7. 「ハイデガーは決して Was ist das Sein ? と問うことはない。それどころか、そのような形で問うことの不条理さを警告している […] むしろ彼はこう問う。それはどのように意味づけられているのか?その意味は何か?」 n8. カントにとって、認識は感覚的な経験から始まる。「私たちの認識に合わせて調整すべきは対象であり、その逆ではない。そして対象は、物事の性質、つまりそ の nouménal(実体)を私たちに伝えるのではなく、私たちの認識がそれを理解する形を伝えるのだ」-記事「現象」哲学概念辞典、2013年、613 ページ n9. この「物そのものに対する権利」は、空虚に構築されたあらゆる概念、外見と歴史性以外に根拠のない概念の流用とは対立する。- マルティン・ハイデガー 1986年、54ページ n10. 名付けることは、単に「見せる」ことではなく、厳密な意味で「現す」ことだとジャン・ボーフレは主張している。ジャン・ボーフレ 1973年、125ページ n11. 例えば、ハイデガーは「生命の現象」を中心に、独自の現象学のアプローチを構築したとされる。エマニュエル・レヴィナス 1988年、112ページ n12. これらの点についてさらに詳しく知りたい場合は、レヴィナスがこれについて書いた素晴らしいページを参照のこと。エマニュエル・レヴィナス 1988、111-123 ページ n13。実を言えば、「エポケーは、ある特定の重要な出現だけでなく、出現そのものを現出させることを目指している」とドミニク・ジャニコーは述べている。ドミニク・ジャニコー 2009、 p. 67 n14. 「与えられたものと構築されたもの、対象と主体の境界といった、別個でありながら密接に相互依存する問題も、この議論には含まれない。これらの問題は、人 間が「言語的・実用的な」枠組みにどの程度囚われているか、そして人間がその枠組みを通して世界を見ているのかどうかを問うものである。」-哲学概念辞 典、2012年、p. 614 n15. 起源は、単なる空虚な言葉(flatus voci)ではないならば、哲学的素材である概念が出現した場所に対応し、その形成と具体的な展開を説明しなければならない。-ソフィー・ジャン・アリエン 2014年、p. 38 n16. 解釈(Auslegung)とは、ハイデガーが理解の前提を明らかにすることを指す言葉だ。ジャン・グロンダン 1996年、191ページ n17. 「知識の意味や本質を覆い隠す曖昧さは、知識の科学、つまり知識を真に明確なものにすることを唯一の目的とする科学を必要とする」―エドムント・フッサール 2010年、69ページ n18。しかし、ジャン=フランソワ・リオタールが指摘しているように、「この作業を達成するには、科学そのものを離れ、科学が無邪気に飛び込むものに飛 び込む必要がある。フッサールは、合理主義的な意志によって、前合理的領域に取り組んでいる」―ジャン=フランソワ・リオタール 2011年、9ページ n19。「客観的に」指向された現象学の中心的なテーマと真に考えうる、経験の特徴的な側面:意図性」。このイデイティックな特徴は、すべての経験が何ら かの形で意図性に関与している限り、一般的な経験の領域に関わるものである。ただし、すべての経験が意図性を持っているとは言い切れない。「意識を強い意 味で特徴づけ、同時に経験の流れ全体を意識の流れとして、また意識の統一性として扱うことを可能にするのは、意図性である」―E. フッサール、Ideen I、§ 84、仏訳、前掲書、283 ページ。 n20. 「理想主義/現実主義という二分法(そして主観/客観という二分法も同様)は、それ以前の相関関係、すなわち、いかなる物理的イメージも表現できないとい う還元不可能な事実、すなわち、世界における意識の分裂、つまり、最初から「自分以外の何か」に対する意識によって、すでに克服されている。純粋な意識な ど存在しない。「あらゆる意識は何かに対する意識である」ということは、コギトの偽りの純粋性は、常に先行する意図的な相関関係から引き出されていること を示している」-ドミニク・ジャニコー 2009年、44ページ n21. 「純粋あるいは超越的な現象学は、事実に関する科学ではなく、本質に関する科学(「イデイティック」科学)として確立される。そのような科学は、「本質に 関する知識」のみを確立することを目的とし、事実を確立することを目的とはしない」―E. フッサール、Ideen I、序文、仏訳、前掲書、p. 7。 n22. 「(意識の)直接的なデータには、伝統的な心理学で当然のこととして扱われてきたもの、すなわち、色彩データ、音データ、その他の感覚データ、感情デー タ、意志データなどは一切見られない。しかし、ルネ・デカルトがすでに発見したもの、すなわちコギト、意図性が、周囲の世界の現実のすべてと同様に、言語 の痕跡を受けた身近な形で発見される。すなわち、「私は緑色の木を見る。その葉のざわめきを聞く、その花の香りを感じる」といったもの、あるいは「学校に 通っていた頃を覚えている」、「友人の病気のことが心配だ」といったものなどである。ここで意識として見出されるのは、実際には…の意識にすぎない。E. フッサール、Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die tanszendentale Phänomenologie、ハーグ、Martinus Nijhoff、1954年、§ 68、フランス語訳 G. Granel:La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale、パリ、Gallimard、Tel、1976年、262ページ。 n23。そこから二つの結論が導かれる。第一に、「知覚とはまず第一に、物事との具体的かつ実践的な関わりである。私は知覚するだけでは知覚しない。方向 を見定めるために知覚する。知覚はもはや単なる中立的な観察ではない」ということ。第二に、「対象はもはや主体にとって完全に異質なものではなく、主体に とって完全に外部のものでもない」ということである。Françoise Dastur 2011, p. 13 n24。ジャン・グレイシュの例(玄関マットの上にいる猫)は、玄関マットと猫を足した以上のもの、あるいは羊の群れやデモを行う群衆の例、さらに単純で 明白な例としては、単なる一連の樹木ではなく、森そのものである。つまり、観念化という行為によってジャン・グレイシュ、前掲書 1994年、56-57ページ n25. 実際、「黒板が部屋の隅に置かれている」と言うには、まず教室全体が教室として認識されていることが前提となる。つまり、黒板は教室として特定の場所に置 かれるべきであり、別の場所に置かれるべきダンススタジオではないということだ。「ある」の意味は、単純な発言よりも広範であり、あらゆる発言に先立っ て、言語的・論理的以前の段階で、物事をまとめ、分離することなく区別することを可能にする統一的な統合を行う(記事「論理」『マルティン・ハイデガー辞 典』778ページ)。 n26. 「哲学とは、ダーザイン(存在)の「解釈学」から生まれた普遍的な現象学的存在論であり、存在(実存性)の分析として、あらゆる哲学的探求の出発点と帰着点をその終着点として定めている」 |
| Références | Références(省略) |
| Articles connexes Edmund Husserl Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pures La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale Méditations cartésiennes Maurice Merleau-Ponty Hector de Saint-Denys Garneau Glossaire de phénoménologie Réduction phénoménologique La Voix et le Phénomène Intentionnalité Intersubjectivité (phénoménologie) Perception (phénoménologie) Phénoménologie de la perception Ontologie Dasein Martin Heidegger et la phénoménologie Maine de Biran De la phénoménologie Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps Sixième Méditation cartésienne . Catégories Concepts phénoménologiques Œuvres de phénoménologie Phénoménologues |
関連項目 エドムント・フッサール 純粋現象学および現象学的哲学のための指導的観念 ヨーロッパ科学の危機と超越論的現象学 デカルト的瞑想 モーリス・メルロー=ポンティ エクトール・ド・サン=ドニ・ガルノー 現象学用語集 現象学的還元 声と現象 意図性 相互主観性(現象学) 知覚(現象学) 知覚の現象学 存在論 ダセイン マルティン・ハイデガーと現象学 メイン・ド・ビラン 現象学について 時間の内的な意識の現象学のための教訓 第六のデカルト的瞑想 。 カテゴリー 現象学的概念 現象学の著作 現象学者 |
| Bibliographie dédiée Edmund Husserl (trad. Henri Dussort, préf. Gérard Granel), Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, PUF, coll. « Épiméthée », 1994, 4e éd. (1re éd. 1964), 202 p. (ISBN 2-13-044002-9). Edmund Husserl (trad. Alexandre Lowit), L'idée de la phénoménologie : Cinq Leçons, PUF, coll. « Épiméthée », 2010, 4e éd., 136 p. (ISBN 978-2-13-044860-0). Edmund Husserl (trad. de l'allemand par Paul Ricœur), Idées directrices pour une phénoménologie, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Tel », 1985, 567 p. (ISBN 2-07-070347-9). Edmund Husserl (trad. Mlle Gabrielle Peiffer, Emmanuel Levinas), Méditations cartésiennes : Introduction à la phénoménologie, J.VRIN, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 1986, 136 p. (ISBN 2-7116-0388-1). Eugen Fink (trad. Didier Franck), De la phénoménologie : Avec un avant-propos d'Edmund Husserl, Les Éditions de Minuit, coll. « Arguments », 1974, 242 p. (ISBN 2-7073-0039-X). Eugen Fink (trad. Natalie Depraz), Sixième méditation cartésienne : L'idée d'une théorie transcendantale de la méthode, Jérôme Millon, 1994, 265 p. (ISBN 2-905614-98-6, lire en ligne [archive]). Eugen Fink (trad. de l'allemand par Françoise Dastur et Anne Montavont), Autres rédactions des Méditations cartésiennes : textes issus du fonds posthume d'Eugen Fink (1932) avec des annotations et des appendices issus du fonds posthume d'Edmund Husserl (1933-1934), Grenoble, Jérôme Millon, 1998, 350 p. (ISBN 2-84137-075-5). Dominique Janicaud, La phénoménologie dans tous ses états, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio essais », 2009, 323 p. (ISBN 978-2-07-036317-9). Philippe Arjakovsky, François Fédier et Hadrien France-Lanord (dir.), Le Dictionnaire Martin Heidegger : Vocabulaire polyphonique de sa pensée, Paris, Éditions du Cerf, 2013, 1450 p. (ISBN 978-2-204-10077-9). Michel Blay, Dictionnaire des concepts philosophiques, Paris, Larousse, 2013, 880 p. (ISBN 978-2-03-585007-2). Martin Heidegger (trad. de l'allemand par Jean-François Courtine), Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, Paris, Éditions Gallimard, 1989, 410 p. (ISBN 2-07-070187-5). Martin Heidegger (trad. Jean Beaufret,Wolfgang Brokmeier,François Fédier), Acheminement vers la parole, Éditions Gallimard, coll. « Tel », 1988, 260 p. (ISBN 2-07-023955-1). Martin Heidegger (trad. François Vezin), Être et Temps, Paris, Gallimard, 1986, 589 p. (ISBN 2-07-070739-3). Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Tel », 2005, 537 p. (ISBN 2-07-029337-8). Alain Boutot, Heidegger, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? » (no 2480), 1989, 127 p. (ISBN 2-13-042605-0) Jean Greisch, Ontologie et temporalité : Esquisse systématique d'une interprétation intégrale de Sein und Zeit, Paris, PUF, 1994, 1re éd., 522 p. (ISBN 2-13-046427-0). Jean Beaufret, Dialogue avec Heidegger : tome 1- Philosophie grecque, Éditions de Minuit, 1973, 145 p.. Jean Grondin, « L'herméneutique dans Sein und Zeit », dans Jean-François Courtine (dir.), Heidegger 1919-1929: De l'herméneutique de la facticité à la métaphysique du Dasein (ISBN 978-2-7116-1273-4, lire en ligne [archive]), p. 179-192. Françoise Dastur, Heidegger et la pensée à venir, Paris, J. Vrin, coll. « Problèmes et controverses », 2011, 252 p. (ISBN 978-2-7116-2390-7, BNF 42567422). Françoise Dastur, HEIDEGGER, Paris, J. Vrin, coll. « Bibliothèque des Philosophies », 2007, 252 p. (ISBN 978-2-7116-1912-2, lire en ligne [archive]). Jean-François Courtine, Heidegger et la phénoménologie, Paris, J. Vrin, coll. « Bibliothèque d'histoire de la philosophie », 1990, 405 p. (ISBN 2-7116-1028-4, lire en ligne [archive]). Hans-Georg Gadamer, Les Chemins de Heidegger, Paris, Vrin, coll. « Textes Philosophiques », 2002, 289 p. (ISBN 2-7116-1575-8). Christian Dubois, Heidegger : Introduction à une lecture, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 2000 (ISBN 2-02-033810-6). Emmanuel Levinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, J. Vrin, coll. « Bibliothèque d'histoire de la philosophie », 1988, 236 p. (ISBN 2-7116-0488-8). Marlène Zarader, Lire Être et Temps de Heidegger, Paris, J. Vrin, coll. « Histoire de la philosophie », 2012, 428 p. (ISBN 978-2-7116-2451-5). Émile Bréhier et Paul Ricœur, Histoire de la philosophie allemande troisième édition mise à jour P.Ricœur, VRIN, coll. « Bibliothèque d'histoire de la philosophie », 1954, 262 p. Alexander Schnell, De l'existence ouverte au monde fini : Introduction à la philosophie de Martin Heidegger, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque d'histoire de la philosophie », 2005, 255 p. (ISBN 978-2-7116-1792-0, présentation en ligne [archive]). Servanne Jollivet, Heidegger, Sens et histoire (1912-1927), PUF, coll. « Philosophies », 2009, 160 p. (ISBN 978-2-13-056259-7). Christoph Jamme, « Être et Temps de Heidegger dans le contexte de l'histoire de sa genèse », dans Jean-François Courtine (dir.), Heidegger 1919-1929: De l'herméneutique de la facticité à la métaphysique du Dasein, 1996 (ISBN 978-2-7116-1273-4), p. 221-236. Jean-François Lyotard, La phénoménologie, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2011, 133 p. (ISBN 978-2-13-058815-3). Sophie-Jan Arrien, L'inquiétude de la pensée : L'herméneutique de la vie du jeune Heidegger (1919-1923), Paris, PUF, coll. « Épiméthée », 2014, 385 p. (ISBN 978-2-13-062453-0). Fink, Legros, Loraux, Pierobo, Richir, Van Kerkhoven, Le statut du phénoménologique Revue Époké, Millon, 1990 (ISBN 2-905614-45-5). Renaud Barbaras, Introduction à la philosophie de Husserl, Chatou, Les éditions de la transparence, 2008, 160 p. (ISBN 978-2-35051-002-6 et 2-35051-002-6). Cahier de l'Herne : Heidegger, Éditions de l'Herne, coll. « Biblio essais.Livre de poche », 1986, 604 p. (ISBN 2-253-03990-X). collectif, Eugen Fink Actes du colloque de Cerisy-la Salle 23-30 juillet 1994, Amsterdam, Rodopi, 1994, 367 p. (ISBN 90-420-0243-3). collectif (dir.), Lire les Beitrage zur Philosophie de Heidegger, Paris, Hermann, coll. « Rue de la Sorbonne », 2017, 356 p. (ISBN 978-2-7056-9346-6). |
関連文献 エドムント・フッサール(翻訳:アンリ・デュソルト、序文:ジェラール・グラネル)、『時間の内面的意識の現象学のための講義』、PUF、シリーズ「エピメテウス」、1994年、第4版(初版1964年)、202ページ。(ISBN 2-13-044002-9)。 エドムント・フッサール(アレクサンドル・ロウィット訳)、『現象学の思想:五つの講義』、PUF、コレクション「エピメテウス」、2010年、第4版、136ページ。(ISBN 978-2-13-044860-0)。 エドムント・フッサール(ドイツ語からポール・リクールが翻訳)、『現象学のための指導的観念』、パリ、エディシオン・ガリマール、コレクション「テル」、1985年、567ページ。(ISBN 2-07-070347-9)。 エドムント・フッサール(ガブリエル・ペイファー、エマニュエル・レヴィナス訳)、『デカルト的瞑想:現象学入門』、J.VRIN、シリーズ「哲学テキスト文庫」、1986年、136ページ。(ISBN 2-7116-0388-1)。 オイゲン・フィンク(ディディエ・フランク訳)、『現象学について:エドムント・フッサールの序文付き』、レ・エディシオン・ド・ミニュイ、コレクション「アルギュマン」、1974年、242ページ。(ISBN 2-7073-0039-X)。 オイゲン・フィンク(ナタリー・デプラズ訳)、『デカルトの第六瞑想:方法論の超越論的理論の構想』、ジェローム・ミヨン、1994年、265ページ(ISBN 2-905614-98-6、オンラインで読む [アーカイブ])。 オイゲン・フィンク(フランソワーズ・ダストゥール、アンヌ・モンタヴォンによるドイツ語からの翻訳)、『デカルトの瞑想のその他の草稿:オイゲン・フィ ンクの遺作(1932年)からのテキスト、エドムント・フッサールの遺作(1933-1934年)からの注釈と付録付き』、グルノーブル、ジェローム・ミ ヨン、 1998年、350ページ(ISBN 2-84137-075-5)。 ドミニク・ジャニコー、『あらゆる側面における現象学』、パリ、エディシオン・ガリマール、コレクション「フォリオ・エッセイ」、2009年、323ページ(ISBN 978-2-07-036317-9)。 フィリップ・アルジャコフスキー、フランソワ・フェディエ、アドリアン・フランス=ラノード(編)、『マルティン・ハイデガー辞典:彼の思想の多声的な語 彙』、パリ、エディション・デュ・セルフ、2013年、1450ページ(ISBN 978-2-204-10077-9)。 ミシェル・ブレ、『哲学概念辞典』、パリ、ラルース社、2013年、880ページ(ISBN 978-2-03-585007-2)。 マルティン・ハイデガー(ジャン=フランソワ・クルティンによるドイツ語からの翻訳)、『現象学の基本問題』、パリ、 Éditions Gallimard、1989年、410ページ(ISBN 2-07-070187-5)。 Martinハイデガー (Jean Beaufret、Wolfgang Brokmeier、François Fédier 訳)、『言葉への道程』、Éditions Gallimard、coll. 「Tel」、1988年、260ページ (ISBN 2-07-023955-1)。 マルティン・ハイデガー(フランソワ・ヴェザン訳)、『存在と時間』、パリ、ガリマール社、1986年、589ページ。(ISBN 2-07-070739-3)。 モーリス・メルロー=ポンティ、『知覚の現象学』、パリ、ガリマール社、「テル」シリーズ、2005年、537ページ(ISBN 2-07-029337-8)。 アラン・ブート、『ハイデガー』、パリ、PUF社、「ケ・セ・ジュ?」シリーズ(No. 2480)、 1989年、127ページ(ISBN 2-13-042605-0) ジャン・グレイシュ『存在論と時間性:存在と時間』の総合的解釈の体系的概説、パリ、PUF、1994年、初版、522ページ(ISBN 2-13-046427-0)。 ジャン・ボーフレ、『ハイデガーとの対話:第1巻 ギリシャ哲学』、エディション・ドゥ・ミニュイ、1973年、145ページ。 ジャン・グロンダン、「『存在と時間』における解釈学」、ジャン=フランソワ・クルティン編、『 ハイデガー 1919-1929:事実性の解釈学から実存の形而上学へ(ISBN 978-2-7116-1273-4、オンラインで読む [アーカイブ])、179-192 ページ。 フランソワーズ・ダスター、『ハイデガーと未来の思想』、パリ、J. Vrin、シリーズ「問題と論争」、2011年、252ページ(ISBN 978-2-7116-2390-7、BNF 42567422)。 フランソワーズ・ダスター、『ハイデガー』、パリ、J. Vrin、シリーズ「哲学図書館」、2007年、252ページ(ISBN 978-2-7116-1912-2、オンラインで読む[アーカイブ])。 ジャン=フランソワ・クルティン、『ハイデガーと現象学』、パリ、J. Vrin、シリーズ「哲学史図書館」、1990年、405ページ(ISBN 2-7116-1028-4、オンラインで読む [アーカイブ])。 ハンス=ゲオルク・ガダマー、『ハイデガーの道』、パリ、Vrin、 coll. 「Textes Philosophiques」、2002年、289ページ(ISBN 2-7116-1575-8)。 クリスチャン・デュボワ、『ハイデガー:読解入門』、パリ、Seuil、coll. 「Points Essais」、2000年(ISBN 2-02-033810-6)。 エマニュエル・レヴィナス、『フッサールとハイデガーとともに存在を発見する』、J. Vrin、coll. 「哲学史図書館」、1988年、236ページ。(ISBN 2-7116-0488-8)。 マルレーヌ・ザラデル、『ハイデガーの「存在と時間」を読む』、パリ、J. Vrin、 「哲学史」シリーズ、2012年、428ページ(ISBN 978-2-7116-2451-5)。 エミール・ブレイエとポール・リクール、『ドイツ哲学史』第3版(P.リクールによる更新)、VRIN、シリーズ「哲学史図書館」、 1954年、262ページ。 アレクサンダー・シュネル著、『開かれた存在から有限の世界へ:マルティン・ハイデガー哲学入門』、パリ、ヴラン社、「哲学史ライブラリー」シリーズ、2005年、255ページ(ISBN 978-2-7116-1792-0、オンライン紹介 [アーカイブ])。 セルヴァンヌ・ジョリヴェ、『ハイデガー、意味と歴史(1912-1927)』、PUF、シリーズ「哲学」、2009年、160ページ(ISBN 978-2-13-056259-7)。 クリストフ・ジャム、『ハイデガーの「存在と時間」の誕生の経緯』ジャン=フランソワ・クルティン編、『ハイデガー 1919-1929:事実性の解釈学からダセインの形而上学へ』1996年 (ISBN 978-2-7116-1273-4)、221-236 ページ。 ジャン=フランソワ・リオタール、『現象学』、パリ、PUF、シリーズ「Quadrige」、2011年、133 ページ。(ISBN 978-2-13-058815-3)。 ソフィー=ジャン・アリエン、『思考の不安:若いハイデガーの生活解釈学(1919-1923)』、パリ、PUF、コレクション「エピメテウス」、2014年、385ページ(ISBN 978-2-13-062453-0)。 Fink、Legros、Loraux、Pierobo、Richir、Van Kerkhoven、『現象学者の地位』 Revue Époké、Millon、1990年(ISBN 2-905614-45-5)。 Renaud Barbaras、『フッサール哲学入門』 Chatou、Les éditions de la transparence、2008年、160ページ。(ISBN 978-2-35051-002-6 および 2-35051-002-6)。 Cahier de l『Herne : ハイデガー, Éditions de l』Herne, coll. 「Biblio essais.Livre de poche」、1986年、604ページ。(ISBN 2-253-03990-X)。 共同執筆、Eugen Fink Actes du colloque de Cerisy-la Salle 23-30 juillet 1994、アムステルダム、Rodopi、1994年、367ページ。(ISBN 90-420-0243-3)。 共同編集、リール・レ・ベイトラージュ・ズール・フィロソフィー・ド・ハイデガー、パリ、エルマン、コレクション「リュ・ド・ラ・ソルボンヌ」、2017年、356ページ。(ISBN 978-2-7056-9346-6)。 |
| https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A9nologie_(philosophie) |
☆ 現象学、とりわけ哲学的現象学(philosophical phenomenology)は、主観的に生き、経験される客観性と現実(より一般的な)についての哲学的研究である。外界についての仮定を避けながら、意識の普遍的な特徴を調査しようとするものであり、対象者に 現れる現象を記述し、生きた経験の意味と意義を探求することを目的としている。 このアプローチは、様々な科学分野、特に社会科学、人文科学、心理学、認知科学における質的研究において多くの応用を見出しているが、健康科学、建築学、 ヒューマンコンピュータインタラクションなどの多様な分野においても応用されている。これらの分野における現象学の応用は、行動に焦点を当てるのではな く、主観的経験をより深く理解することを目的としている。 現象学は、精神状態や物理的対象を感覚の複合体に還元する現象主義や、論理的真理や認識論的原理を人間の心理学の産物として扱う心理主義と対比される。 特に、エドムント・フッサールによって概説された超越論的現象学は、人間の主観的経験における普遍的な論理構造の発見を通じて、世界の客観的理解に到達す ることを目指している。 現象学の異なる枝が主観性にアプローチする方法には重要な違いがある。例えば、マルティン・ハイデガーによれば、真理は文脈的に位置づけられ、それらが出 現する歴史的、文化的、社会的文脈に依存している。他にも解釈学的現象学、遺伝学的現象学、身体化現象学などがある。これらの現象学の異なる枝はすべて、 現象学的探究という共通の基礎的アプローチを共有しているにもかかわらず、異なる哲学を代表していると見なすことができる。
| Phenomenology
is the
philosophical study of objectivity and reality (more generally) as
subjectively lived and experienced. It seeks to investigate the
universal features of consciousness while avoiding assumptions about
the external world, aiming to describe phenomena as they appear to the
subject, and to explore the meaning and significance of the lived
experiences.[1] This approach has found many applications in qualitative research across different scientific disciplines, especially in the social sciences, humanities, psychology, and cognitive science, but also in fields as diverse as health sciences,[2] architecture,[3] and human-computer interaction,[4] among many others. The application of phenomenology in these fields aims to gain a deeper understanding of subjective experience, rather than focusing on behavior. Phenomenology is contrasted with phenomenalism, which reduces mental states and physical objects to complexes of sensations,[5] and with psychologism, which treats logical truths or epistemological principles as the products of human psychology.[6] In particular, transcendental phenomenology, as outlined by Edmund Husserl, aims to arrive at an objective understanding of the world via the discovery of universal logical structures in human subjective experience.[1] There are important differences in the ways that different branches of phenomenology approach subjectivity. For example, according to Martin Heidegger, truths are contextually situated and dependent on the historical, cultural, and social context in which they emerge. Other types include hermeneutic, genetic, and embodied phenomenology. All these different branches of phenomenology may be seen as representing different philosophies despite sharing the common foundational approach of phenomenological inquiry; that is, investigating things just as they appear, independent of any particular theoretical framework.[7] |
現象学は、主観的に生き、経験される客観性と現実(より一般的な)につ
いての哲学的研究である。外界についての仮定を避けながら、意識の普遍的な特徴を調査しようとするものであり、対象者に現れる現象を記述し、生きた経験の
意味と意義を探求することを目的としている[1]。 このアプローチは、様々な科学分野、特に社会科学、人文科学、心理学、認知科学における質的研究において多くの応用を見出しているが、健康科学、[2]建 築学、[3]ヒューマンコンピュータインタラクション[4]などの多様な分野においても応用されている。これらの分野における現象学の応用は、行動に焦点 を当てるのではなく、主観的経験をより深く理解することを目的としている。 現象学は、精神状態や物理的対象を感覚の複合体に還元する現象主義[5]や、論理的真理や認識論的原理を人間の心理学の産物として扱う心理主義[6]と対 比される。 特に、エドムント・フッサールによって概説された超越論的現象学は、人間の主観的経験における普遍的な論理構造の発見を通じて、世界の客観的理解に到達す ることを目指している[1]。 現象学の異なる枝が主観性にアプローチする方法には重要な違いがある。例えば、マルティン・ハイデガーによれば、真理は文脈的に位置づけられ、それらが出 現する歴史的、文化的、社会的文脈に依存している。他にも解釈学的現象学、遺伝学的現象学、身体化現象学などがある。これらの現象学の異なる枝はすべて、 現象学的探究という共通の基礎的アプローチを共有しているにもかかわらず、異なる哲学を代表していると見なすことができる。 |
| Etymology The term phenomenology derives from the Greek φαινόμενον, phainómenon ("that which appears") and λόγος, lógos ("study"). It entered the English language around the turn of the 18th century and first appeared in direct connection to Husserl's philosophy in a 1907 article in The Philosophical Review.[8] In philosophy, "phenomenology" (or transcendental phenomenology) refers to the tradition inaugurated by Edmund Husserl at the beginning of the 20th century.[9] The term, however, had been used in different senses in other philosophy texts since the 18th century. These include those by Johann Heinrich Lambert (1728–1777), Immanuel Kant (1724–1804), G. W. F. Hegel (1770–1831; Hegel's approach to philosophy is sometimes referred to as dialectical phenomenology), and Carl Stumpf (1848–1936), among others.[10][11][12] It was, however, the usage of Franz Brentano (and, as he later acknowledged, Ernst Mach[5]) that would prove definitive for Husserl.[13] From Brentano, Husserl took the conviction that philosophy must commit itself to description of what is "given in direct 'self-evidence'."[14] Central to Brentano's phenomenological project was his theory of intentionality, which he developed from his reading of Aristotle's On the Soul.[15] According to the phenomenological tradition, "the central structure of an experience is its intentionality, it being directed towards something, as it is an experience of or about some object."[16] Also, on this theory, every intentional act is implicitly accompanied by a secondary, pre-reflective awareness of the act as one's own.[17] |
語源 現象学という言葉は、ギリシャ語のφαινόμενον、phainómenon(「現れるもの」)とλόγος、lógos(「研究」)に由来する。こ の言葉は18世紀の終わり頃に英語になり、1907年に『The Philosophical Review』に掲載された論文でフッサールの哲学に直接関連して初めて登場した[8]。 哲学では、「現象学」(または超越論的現象学)は20世紀初頭にエドムント・フッサールによって創始された伝統を指す[9]。これにはヨハン・ハインリッ ヒ・ランベルト(1728-1777)、イマヌエル・カント(1724-1804)、G・W・F・ヘーゲル(1770-1831;ヘーゲルの哲学へのアプ ローチは弁証法的現象学と呼ばれることもある)、カール・シュトゥンプ(1848-1936)などによるものが含まれる[10][11][12]。 しかし、フッサールにとって決定的なものとなったのはフランツ・ブレンターノ(そして後に彼が認めたようにエルンスト・マッハ[5])の用法であった [13]。フッサールはブレンターノから、哲学は「直接的な『自明性』において与えられるもの」の記述にコミットしなければならないという確信を得た [14]。 現象学の伝統によれば、「経験の中心的な構造はその意図性であり、それはある対象についての経験であるように、あるいはある対象についての経験であるよう に、何かに向けられている」[16]。 |
| Overview Phenomenology proceeds systematically, but it does not attempt to study consciousness from the perspective of clinical psychology or neurology. Instead, it seeks to determine the essential properties and structures of experience.[18] Phenomenology is not a matter of individual introspection: a subjective account of experience, which is the topic of psychology, must be distinguished from an account of subjective experience, which is the topic of phenomenology.[19] Its topic is not "mental states", but "worldly things considered in a certain way".[20] Phenomenology is a direct reaction to the psychologism and physicalism of Husserl's time.[21] It takes as its point of departure the question of how objectivity is possible at all when the experience of the world and its objects is thoroughly subjective.[22] So far from being a form of subjectivism, phenomenologists argue that the scientific ideal of a purely objective third-person is a fantasy. The perspective and presuppositions of the scientist must be articulated and taken into account in the design of the experiment and the interpretation of its results. Inasmuch as phenomenology is able to accomplish this, it can help to improve the quality of empirical scientific research.[23] In spite of the field's internal diversity, Shaun Gallagher and Dan Zahavi argue that the phenomenological method is composed of four basic steps: the époche, the phenomenological reduction, the eidetic variation, and intersubjective corroboration.[24] The époche is Husserl's term for the procedure by which the phenomenologist endeavors to suspend commonsense and theoretical assumptions about reality (what he terms the natural attitude) in order to attend only to what is directly given in experience. This is not a skeptical move; reality is never in doubt. The purpose is to see it more closely as it truly is.[25] The underlying insight is that objects are "experienced and disclosed in the ways they are, thanks to the way consciousness is structured."[26] The phenomenological reduction is closely linked to the époche. The aim of the reduction is to analyze the correlations between what is given in experience and specific structures of subjectivity shaping and enabling this givenness. This "leads back" (Latin: re-ducere) to the world.[27] Eidetic variation is the process of imaginatively stripping away the properties of things to determine what is essential to them, that is, what are the characteristics without which a thing would not be the thing that it is (Eidos is Plato's Greek word for the essence of a thing). Significantly for the phenomenological researcher, eidetic variation can be practiced on acts of consciousness themselves to help clarify, for instance, the structure of perception or memory. Husserl openly acknowledges that the essences uncovered by this method include various degrees of vagueness and also that such analyses are defeasible. He contends, however, that this does not undermine the value of the method.[28] Intersubjective corroboration is simply the sharing of one's results with the larger research community. This allows for comparisons that help to sort out what is idiosyncratic to the individual from what might be essential to the structure of experience as such.[29] According to Maurice Natanson, "The radicality of the phenomenological method is both continuous and discontinuous with philosophy's general effort to subject experience to fundamental, critical scrutiny: to take nothing for granted and to show the warranty for what we claim to know."[30] According to Husserl the suspension of belief in what is ordinarily taken for granted or inferred by conjecture diminishes the power of what is customarily embraced as objective reality. In the words of Rüdiger Safranski, "[Husserl's and his followers'] great ambition was to disregard anything that had until then been thought or said about consciousness or the world [while] on the lookout for a new way of letting the things [they investigated] approach them, without covering them up with what they already knew."[31] |
概要 現象学は体系的に進行するが、臨床心理学や神経学の観点から意識を研究しようとはしない。現象学は個人の内省の問題ではない。心理学の主題である主観的な 経験の説明は、現象学の主題である主観的な経験の説明とは区別されなければならない[19]。 現象学はフッサールの時代の心理主義や身体主義に対する直接的な反動であり[21]、世界やその対象の経験が徹底的に主観的であるときに客観性がどのよう に可能なのかという問題を出発点としている[22]。 主観主義の一形態であるどころか、現象学者は純粋に客観的な第三者という科学的理想は幻想であると主張している。科学者の視点と前提は、実験の設計とその 結果の解釈において明確にされ、考慮されなければならない。現象学がこれを達成できる限りにおいて、経験的科学研究の質を向上させるのに役立つことができ る[23]。 この分野の内部的な多様性にもかかわらず、ショーン・ギャラガーとダン・ザハヴィは、現象学的方法は4つの基本的なステップから構成されていると主張して いる:エポシュ、現象学的還元、エイデティック・バリエーション、そして間主観的裏付け[24]。 エポシュとはフッサールの用語で、現象学者が経験において直接的に与えられているものだけに注意を向けるために、現実についての常識的で理論的な仮定(彼 が自然的態度と呼ぶもの)を一時停止しようとする手順のことである。これは懐疑的な動きではない。その根底にある洞察は、対象は「意識が構造化されている おかげで、そのあり方において経験され、開示される」というものである[25]。 現象学的還元はエポシュと密接に結びついている。還元の目的は、経験において与えられるものと、この与えられるものを形成し可能にする主観性の特定の構造 との間の相関関係を分析することである。これは世界へと「戻る」(ラテン語でre-ducere)ことにつながる[27]。 エイドス的変奏とは、事物の特性を想像的に剥ぎ取って、その事物の本質的なものは何か、つまり、それがなければその事物はその事物たりえないという特性は 何かを決定するプロセスのことである(エイドスとはプラトンのギリシャ語で事物の本質を意味する)。現象学的研究者にとって重要なのは、例えば知覚や記憶 の構造を明らかにするために、意識行為そのものに対してエイドス的変奏を実践できることである。フッサールは、この方法によって明らかにされる本質がさま ざまな程度の曖昧さを含むこと、またそのような分析が敗北可能であることを率直に認めている。しかしながら彼は、このことはこの方法の価値を損なうもので はないと主張している[28]。 主観的相互確証とは、単に自分の結果をより大きな研究コミュニティと共有することである。これによって、個人にとって特有なものと、経験の構造にとって本 質的なものを選別するのに役立つ比較が可能になる。 モーリス・ナタンソンによれば、「現象学的方法の急進性は、経験を根本的で批判的な精査にかける哲学の一般的な努力と連続的であると同時に非連続的であ る。リュディガー・サフランスキーの言葉を借りれば、「[フッサールとその追随者たちの]大きな野心は、[彼らが調査した]事物を、彼らがすでに知ってい るもので覆い隠すことなく、それらに接近させる新しい方法を探し求めながら]、それまで意識や世界について考えられたり語られたりしてきたものをすべて無 視することであった」[31]。 |
| History Edmund Husserl "set the phenomenological agenda" for even those who did not strictly adhere to his teachings, such as Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, and Maurice Merleau-Ponty, to name just the foremost.[32][33] Each thinker has "different conceptions of phenomenology, different methods, and different results."[34] Husserl's conceptions Main article: Edmund Husserl  Edmund Husserl in 1900. Husserl derived many important concepts central to phenomenology from the works and lectures of his teachers, the philosophers and psychologists Franz Brentano and Carl Stumpf.[35] An important element of phenomenology that Husserl borrowed from Brentano is intentionality (often described as "aboutness" or "directedness"[36]), the notion that consciousness is always consciousness of something. The object of consciousness is called the intentional object, and this object is constituted for consciousness in many different ways, through, for instance, perception, memory, signification, and so forth. Throughout these different intentionalities, though they have different structures and different ways of being "about" the object, an object is still constituted as the identical object; consciousness is directed at the same intentional object in direct perception as it is in the immediately-following retention of this object and the eventual remembering of it. As envisioned by Husserl, phenomenology is a method of philosophical inquiry that rejects the rationalist bias that has dominated Western thought since Plato in favor of a method of reflective attentiveness that discloses the individual's "lived experience."[37] Loosely rooted in an epistemological device called epoché, Husserl's method entails the suspension of judgment while relying on the intuitive grasp of knowledge, free of presuppositions and intellectualizing. Sometimes depicted as the "science of experience," the phenomenological method, rooted in intentionality, represents an alternative to the representational theory of consciousness. That theory holds that reality cannot be grasped directly because it is available only through perceptions of reality that are representations in the mind. In Husserl's own words: experience is not an opening through which a world, existing prior to all experience, shines into a room of consciousness; it is not a mere taking of something alien to consciousness into consciousness... Experience is the performance in which for me, the experiencer, experienced being "is there", and is there as what it is, with the whole content and the mode of being that experience itself, by the performance going on in its intentionality, attributes to it.[38] In effect, he counters that consciousness is not "in" the mind; rather, consciousness is conscious of something other than itself (the intentional object), regardless of whether the object is a physical thing or just a figment of the imagination. ----- Logical Investigations (1900/1901) In the first edition of the Logical Investigations, under the influence of Brentano, Husserl describes his position as "descriptive psychology." Husserl analyzes the intentional structures of mental acts and how they are directed at both real and ideal objects. The first volume of the Logical Investigations, the Prolegomena to Pure Logic, begins with a critique of psychologism, that is, the attempt to subsume the a priori validity of the laws of logic under psychology. Husserl establishes a separate field for research in logic, philosophy, and phenomenology, independently from the empirical sciences.[39][40][32] "Pre-reflective self-consciousness" is Shaun Gallagher and Dan Zahavi's term for Husserl's (1900/1901) idea that self-consciousness always involves a self-appearance or self-manifestation prior to self-reflection.[41] This is one point of nearly unanimous agreement among phenomenologists: "a minimal form of self-consciousness is a constant structural feature of conscious experience. Experience happens for the experiencing subject in an immediate way and as part of this immediacy, it is implicitly marked as my experience."[42] ---Ideas (1913) In 1913, Husserl published Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology. In this work, he presents phenomenology as a form of "transcendental idealism". Although Husserl claimed to have always been a transcendental idealist, this was not how many of his admirers had interpreted the Logical Investigations, and some were alienated as a result.[32] This work introduced distinctions between the act of consciousness (noesis) and the phenomena at which it is directed (the noemata). Noetic refers to the intentional act of consciousness (believing, willing, etc.). Noematic refers to the object or content (noema), which appears in the noetic acts (the believed, wanted, hated, loved, etc.).[43] What is observed is not the object as it is in itself, but how and inasmuch it is given in the intentional acts. Knowledge of essences would only be possible by "bracketing" all assumptions about the existence of an external world and the inessential (subjective) aspects of how the object is concretely given to us. This phenomenological reduction is the second stage of Husserl's procedure of epoché. That which is essential is then determined by the imaginative work of eidetic variation, which is a method for clarifying the features of a thing without which it would not be what it is.[44] Husserl concentrated more on the ideal, essential structures of consciousness. As he wanted to exclude any hypothesis on the existence of external objects, he introduced the method of phenomenological reduction to eliminate them. What was left over was the pure transcendental ego, as opposed to the concrete empirical ego. Transcendental phenomenology is the study of the essential structures that are left in pure consciousness: this amounts in practice to the study of the noemata and the relations among them. Munich phenomenology Main article: Munich phenomenology Some phenomenologists were critical of the new theories espoused in Ideas. Members of the Munich group, such as Max Scheler and Roman Ingarden, distanced themselves from Husserl's new transcendental phenomenology. Their theoretical allegiance was to the earlier, realist phenomenology of the first edition of Logical Investigations. Heidegger's conception Main article: Martin Heidegger 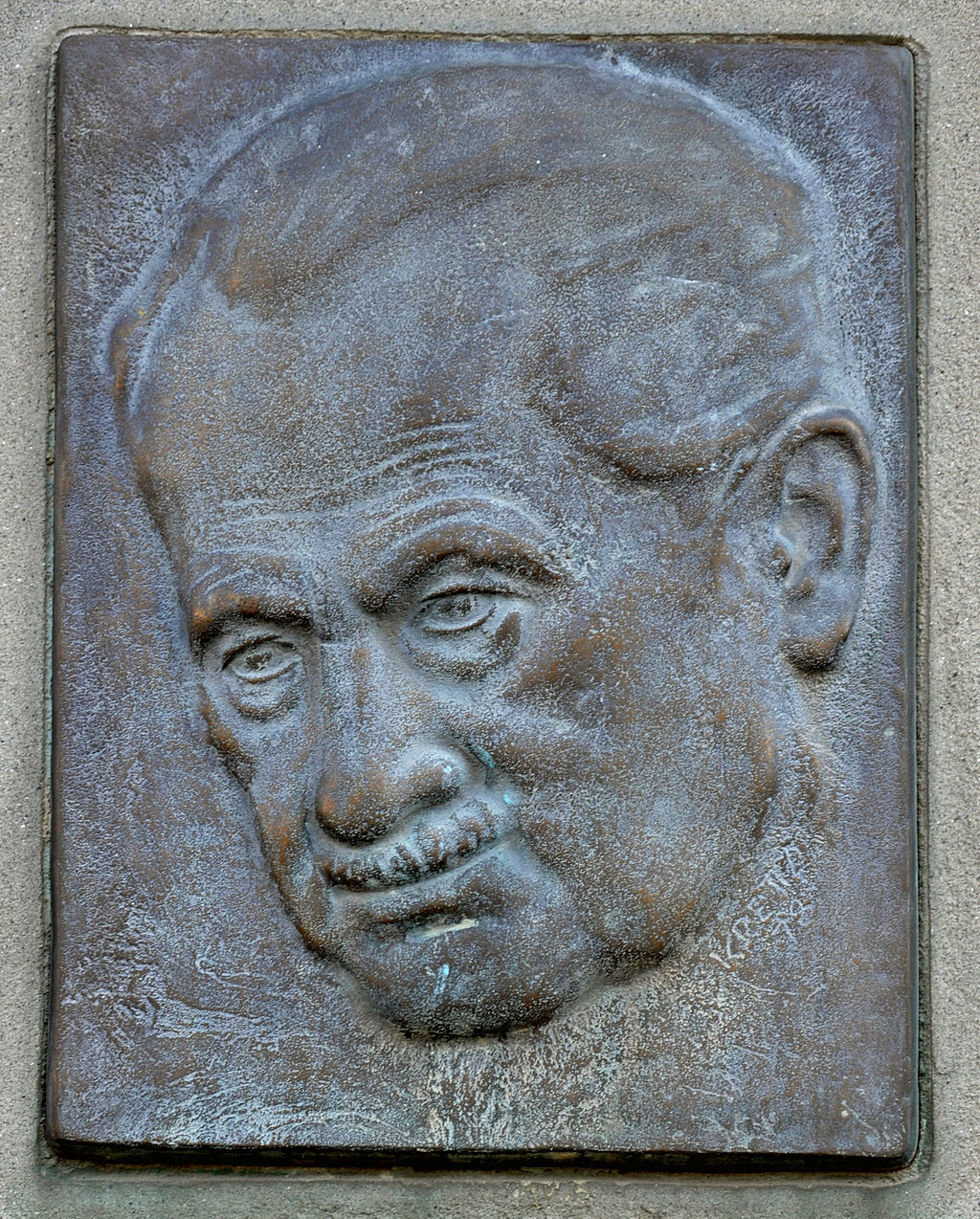 Memorial plaque of Martin Heidegger in Messkirch. Martin Heidegger modified Husserl's conception of phenomenology because of what Heidegger perceived as Husserl's subjectivist tendencies. Whereas Husserl conceived humans as having been constituted by states of consciousness, Heidegger countered that consciousness is peripheral to the primacy of one's existence, for which he introduces Dasein as a technical term, which cannot be reduced to a mode of consciousness. From this angle, one's state of mind is an "effect" rather than a determinant of existence, including those aspects of existence of which one is not conscious. By shifting the center of gravity to existence in what he calls fundamental ontology, Heidegger altered the subsequent direction of phenomenology. According to Heidegger, philosophy was more fundamental than science itself. According to him, science is only one way of knowing the world with no special access to truth. Furthermore, the scientific mindset itself is built on a much more "primordial" foundation of practical, everyday knowledge. This emphasis on the fundamental status of a person's pre-cognitive, practical orientation in the world, sometimes called "know-how", would be adopted by both Sartre and Merleau-Ponty.[45] While for Husserl, in the epoché, being appeared only as a correlate of consciousness, for Heidegger the pre-conscious grasp of being is the starting point. For this reason, he replaces Husserl's concept of intentionality with the notion of comportment, which is presented as "more primitive" than the "conceptually structured" acts analyzed by Husserl. Paradigmatic examples of comportment can be found in the unreflective dealing with equipment that presents itself as simply "ready-to-hand" in what Heidegger calls the normally circumspect mode of engagement within the world.[46] For Husserl, all concrete determinations of the empirical ego would have to be abstracted in order to attain pure consciousness. By contrast, Heidegger claims that "the possibilities and destinies of philosophy are bound up with man's existence, and thus with temporality and with historicality."[47] For this reason, all experience must be seen as shaped by social context, which for Heidegger joins phenomenology with philosophical hermeneutics.[48] Husserl charged Heidegger with raising the question of ontology but failing to answer it, instead switching the topic to Dasein. That is neither ontology nor phenomenology, according to Husserl, but merely abstract anthropology. While Being and Time and other early works are clearly engaged with Husserlian issues, Heidegger's later philosophy has little relation to the problems and methods of classical phenomenology.[32] |
歴史 エドムント・フッサールは、マルティン・ハイデガー、ジャン=ポール・サルトル、モーリス・メルロ=ポンティなど、彼の教えを厳格に守らなかった人々に対 しても「現象学の課題を設定した」[32][33]。各思想家は「現象学の異なる概念、異なる方法、異なる結果」を持っている[34]。 フッサールの概念 主な記事 エドムント・フッサール  1900年のフッサール。 フッサールがブレンターノから借用した現象学の重要な要素は意図性(しばしば「aboutness」や「directedness」と表現される [36])であり、意識は常に何かを意識しているという概念である。意識の対象は意図的な対象と呼ばれ、この対象は、たとえば知覚、記憶、意味化などを通 じて、さまざまな方法で意識に構成される。これらの異なる意図性において、それらは異なる構造を持ち、対象「について」の在り方が異なっているにもかかわ らず、対象は依然として同一の対象として構成されている。意識は、直接的な知覚においても、その直後の対象の保持や最終的な記憶においても、同一の意図的 対象に向けられている。 フッサールが思い描いたように、現象学は哲学的探究の方法であり、プラトン以来の西洋思想を支配してきた合理主義的偏向を否定し、個人の「生きた経験」を 開示する反省的注意の方法を支持するものである[37]。エポケーと呼ばれる認識論的装置にゆるやかに根ざしたフッサールの方法は、前提や知識化から解放 された知識の直観的把握に依拠しながら、判断の停止を伴う。時に「経験の科学」として描かれる現象学的方法は、意図性に根ざし、意識の表象理論に代わるも のである。この理論では、現実は心の表象である現実の知覚を通してのみ利用可能であるため、現実を直接把握することはできないとする。フッサール自身の言 葉を借りれば 経験とは、すべての経験に先立って存在する世界が、意識の部屋に差し込む開口部ではない。経験とは、経験者である私にとって、経験された存在が「そこにあ る」パフォーマンスであり、経験それ自体が、その意図性の中で進行しているパフォーマンスによって、それに帰属させる全内容と存在の様式をもって、それが 何であるかとしてそこにあるパフォーマンスなのである[38]。 事実上、意識は心の「中に」あるのではなく、むしろ意識は、その対象が物理的なものであろうと単なる想像の産物であろうと関係なく、自分自身以外の何か (意図的な対象)を意識しているのだと彼は反論している。 ——『論理探究』(1900年/1901年) ブレンターノの影響を受けたフッサールは、『論理学的考察』の初版で、自らの立場を "記述心理学 "と表現している。フッサールは、心的行為の意図的構造と、それが現実の対象と理想の対象の両方にどのように向けられるかを分析している。論理学的考察』 の第1巻『純粋論理学へのプロレゴメナ』は、心理学主義、すなわち論理法則のアプリオリな妥当性を心理学の下に包摂しようとする試みへの批判から始まる。 フッサールは論理学、哲学、現象学の研究のために、経験科学とは独立した領域を確立している[39][40][32]。 前反省的自己意識」とはショーン・ギャラガーとダン・ザハヴィの用語で、フッサール(1900/1901年)の「自己意識は常に自己反省に先立つ自己出現 や自己顕示を含む」という考えを指す[41]。これは現象学者の間でほぼ一致している点の一つである: 「自己意識の最小形態は意識的経験の不変の構造的特徴である。経験は経験する主体にとって即時的な仕方で起こり、この即時性の一部として、それは暗黙のう ちに私の経験としてマークされる」[42]。 ——イデア[イーデン] (1913) 1913年、フッサールは『イデア』を出版した: 1913年、フッサールは『純粋現象学入門』を出版した。この著作の中で、彼は現象学を「超越論的観念論」の一形態として提示している。フッサールは常に 超越論的観念論者であったと主張していたが、これは彼の崇拝者の多くが『論理学的考察』をどのように解釈していたかではなく、結果として疎外された者もい た[32]。 この著作は意識の行為(ノエシス)とそれが向けられる現象(ノエマタ)の間の区別を導入した。ノエシスとは意識の意図的行為(信じること、意志することな ど)を指す。ノエマティックとは、ノエティックな行為(信じたもの、望んだもの、憎んだもの、愛したものなど)に現れる対象や内容(ノエマ)のことである [43]。 観察されるのは、それ自体である対象ではなく、それが意図的行為の中でどのように、どのように与えられるかである。本質の知識は、外界の存在や、対象が具 体的にどのように私たちに与えられるかという本質的でない(主観的な)側面についてのすべての仮定を「括弧で囲む」ことによってのみ可能となる。この現象 学的還元が、フッサールのエポケー手順の第二段階である。そして本質的なものは、それなしにはそれが何であるかはありえないような事物の特徴を明確にする ための方法である、イデア的変奏の想像的作業によって決定される[44]。 フッサールは意識の理想的で本質的な構造により集中していた。彼は外的対象の存在に関するいかなる仮説も排除したかったので、それらを排除するために現象 学的還元という方法を導入した。残されたのは、具体的な経験的自我とは対照的な、純粋な超越論的自我であった。 超越論的現象学とは、純粋意識に残された本質的な構造の研究であり、これは実際にはノエマータとそれらの間の関係の研究に相当する。 ミュンヘン現象学 主な記事 ミュンヘン現象学 現象学者の中には、『イデア』で唱えられた新しい理論に批判的な者もいた。マックス・シェーラーやローマン・インガルデンといったミュンヘン・グループの メンバーは、フッサールの新しい超越論的現象学から距離を置いていた。彼らの理論的忠誠心は、『論理学的考察』第1版の、それ以前の現実主義的現象学に あった。 ハイデガーの概念 主な記事 マルティン・ハイデガー 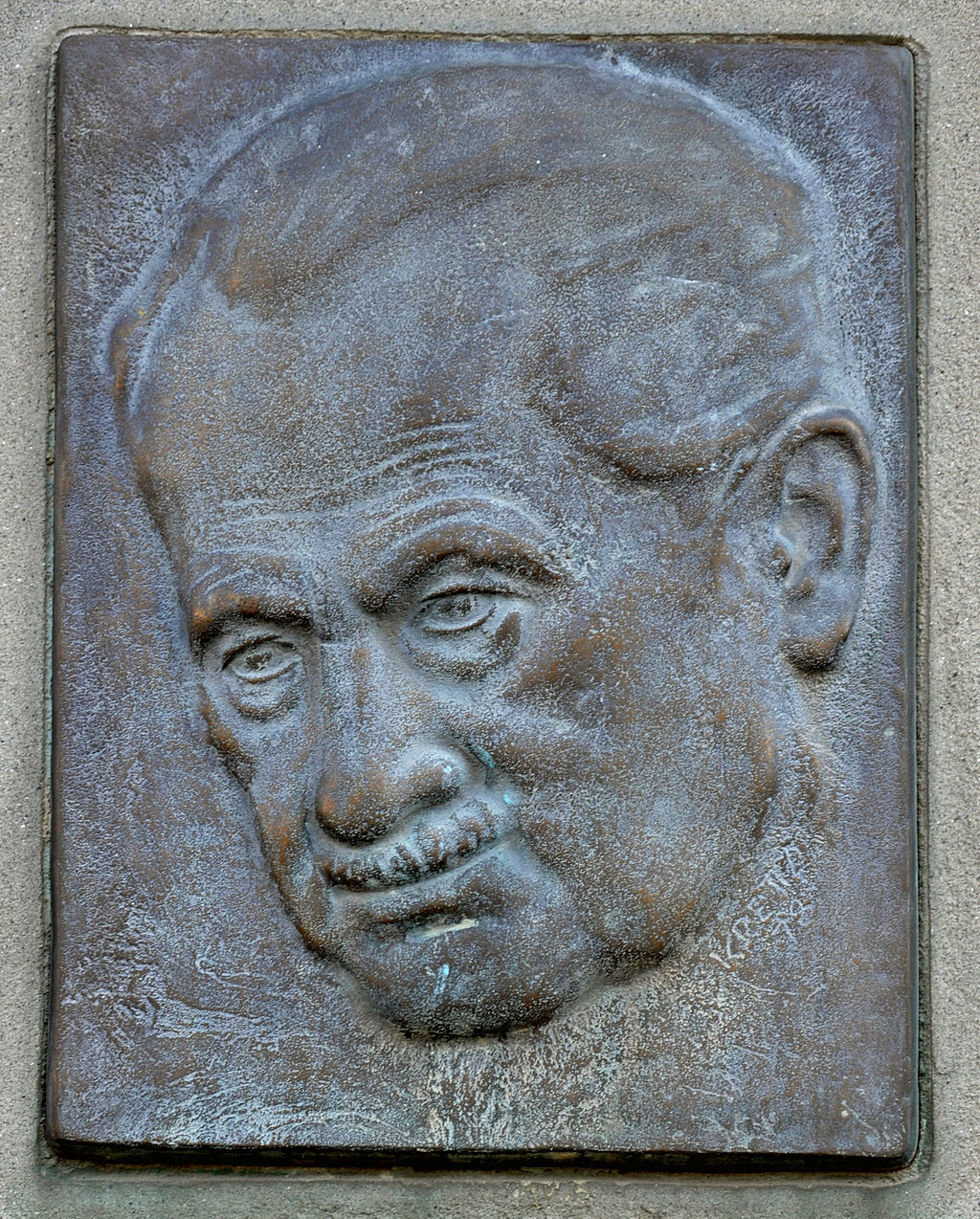 メスキルヒにあるマルティン・ハイデガーの記念プレート。 マルティン・ハイデガーは、フッサールの主観主義的傾向をハイデガーが認識したため、フッサールの現象学の概念を修正した。フッサールが人間を意識状態に よって構成されていると考えたのに対し、ハイデガーは、意識は自分の存在の優位性にとって周辺的なものであり、意識の様式に還元することはできないとし、 専門用語としてダーザインを導入した。この角度から見れば、自分の心の状態は、自分が意識していない存在の側面も含めて、存在の決定要因ではなく「結果」 なのである。彼が基本的存在論と呼ぶところの存在に重心を移すことによって、ハイデガーは現象学のその後の方向性を変えた。 ハイデガーによれば、哲学は科学そのものよりも根源的なものであった。彼によれば、科学は世界を知るための一つの方法に過ぎず、真理への特別なアクセスは ない。さらに、科学的な考え方そのものは、実践的で日常的な知識という、より「根源的」な基盤の上に成り立っている。ノウハウ」と呼ばれることもある、世 界における人の前認知的で実践的な志向性の基本的な地位に対するこの強調は、サルトルとメルロ=ポンティの両者によって採用されることになる[45]。 フッサールにとっては、エポケーにおいて、存在は意識の相関物としてのみ現れたが、ハイデガーにとっては、存在の前意識的な把握が出発点である。この理由 から、ハイデガーはフッサールの意図性の概念を、フッサールが分析した「概念的に構造化された」行為よりも「より原始的な」行為として提示されるコンポー トメントの概念に置き換えた。コンポートメントのパラダイム的な例は、ハイデガーが世界内における通常周到な関与の様式と呼ぶものにおいて、単に「すぐに 使える」ものとしてそれ自体を提示する装備品への無反省な対処に見出すことができる[46]。 フッサールにとって、経験的自我のすべての具体的な決定は、純粋意識を達成するために抽象化されなければならない。対照的に、ハイデガーは「哲学の可能性 と運命は人間の存在と結びついており、したがって時間性と歴史性と結びついている」と主張している[47]。この理由から、ハイデガーにとって現象学は哲 学的解釈学と結びついており、すべての経験は社会的文脈によって形成されていると見なされなければならない[48]。 フッサールはハイデガーが存在論の問題を提起しながらもそれに答えることができず、代わりに話題をダーザインにすり替えたことを非難した。フッサールによ れば、それは存在論でも現象学でもなく、抽象的人間学に過ぎない。 存在と時間』や他の初期の著作は明らかにフッサールの問題と関わっているが、ハイデガーの後期の哲学は古典的現象学の問題や方法とはほとんど関係がない [32]。 |
| Varieties Some scholars have differentiated phenomenology into these seven types:[34] 1.Transcendental constitutive phenomenology studies how objects are constituted in transcendental consciousness, setting aside questions of any relation to the natural world. 2.Naturalistic constitutive phenomenology studies how consciousness constitutes things in the world of nature, assuming with the natural attitude that consciousness is part of nature. 3. Existential phenomenology studies concrete human existence, including human experience of free choice and/or action in concrete situations. 4. Generative historicist phenomenology studies how meaning—as found in human experience—is generated in historical processes of collective experience over time. 5. Genetic phenomenology studies the emergence (or genesis) of meanings of things within the stream of experience. 6. Hermeneutical phenomenology (sometimes hermeneutic phenomenology or post-phenomenology/postphenomenology)[49][50] studies interpretive structures of experience. This approach was introduced in Martin Heidegger's early work.[51] 7. Realistic phenomenology (sometimes realist phenomenology) studies the structure of consciousness and intentionality as "it occurs in a real world that is largely external to consciousness and not somehow brought into being by consciousness."[52] The contrast between "constitutive phenomenology" (sometimes static phenomenology or descriptive phenomenology) and "genetic phenomenology" (sometimes phenomenology of genesis) is due to Husserl.[53] Modern scholarship also recognizes the existence of the following varieties: late Heidegger's transcendental hermeneutic phenomenology,[54] Maurice Merleau-Ponty's embodied phenomenology,[55][56][57] Michel Henry's material phenomenology,[58] Alva Noë's analytic phenomenology,[59][60] and J. L. Austin's linguistic phenomenology.[61][62] |
種類 一部の学者は現象学を以下の7つのタイプに区別している[34]。 1. 超越論的構成的現象学は、対象が超越論的意識においてどのように構成されるかを研究するものであり、自然界との関係性の問題は脇に置いておく。 2. 自然主義的構成的現象学は、意識が自然の一部であるという自然的態度を前提として、意識が自然の世界においてどのように物事を構成するかを研究する。 3. 実存的現象学は、具体的な状況における人間の自由な選択や行動の経験を含む、具体的な人間存在を研究する。 4. 生成史観現象学は、人間の経験に見られるような意味が、時間をかけて集団的経験の歴史的プロセスの中でどのように生成されるかを研究する。 5. 遺伝的現象学は、経験の流れの中での物事の意味の出現(または発生)を研究する。 6. 解釈学的現象学(解釈学的現象学またはポスト現象学/ポスト現象学と呼ばれることもある)[49][50]は経験の解釈構造を研究する。このアプローチは マルティン・ハイデガーの初期の著作で紹介された[51]。 7. 現実主義的現象学(時にリアリスト的現象学)は、「意識にとって大部分は外部にあり、意識によって何らかの形でもたらされたわけではない現実の世界におい て生じている」[52]意識と意図性の構造を研究している。 「構成的現象学」(時に静的現象学や記述的現象学)と「遺伝的現象学」(時に発生の現象学)の対比はフッサールによるものである[53]。 現代の学問は以下のような種類の存在も認めている:後期ハイデガーの超越論的解釈学的現象学[54]、モーリス・メルロ=ポンティの身体化された現象学 [55][56][57]、ミシェル・アンリの物質的現象学[58]、アルヴァ・ノエの分析的現象学[59][60]、J・L・オースティンの言語学的現 象学[61][62]。 |
| Concepts Intentionality Main article: Intentionality Intentionality refers to the notion that consciousness is always the consciousness of something. The word itself should not be confused with the "ordinary" use of the word intentional, but should rather be taken as playing on the etymological roots of the word. Originally, intention referred to a "stretching out" ("in tension," from Latin intendere), and in this context it refers to consciousness "stretching out" towards its object. However, one should be careful with this image: there is not some consciousness first that, subsequently, stretches out to its object; rather, consciousness occurs as the simultaneity of a conscious act and its object. Intentionality is often summed up as "aboutness." Whether this something that consciousness is about is in direct perception or in fantasy is inconsequential to the concept of intentionality itself; whatever consciousness is directed at, that is what consciousness is conscious of. This means that the object of consciousness does not have to be a physical object apprehended in perception: it can just as well be a fantasy or a memory. Consequently, these "structures" of consciousness, such as perception, memory, fantasy, and so forth, are called intentionalities. The term "intentionality" originated with the Scholastics in the medieval period and was resurrected by Brentano who in turn influenced Husserl's conception of phenomenology, who refined the term and made it the cornerstone of his theory of consciousness. The meaning of the term is complex and depends entirely on how it is conceived by a given philosopher. The term should not be confused with "intention" or the psychoanalytic conception of unconscious "motive" or "gain". Significantly, "intentionality is not a relation, but rather an intrinsic feature of intentional acts." This is because there are no independent relata. It is (at least in the first place) a matter of indifference to the phenomenologist whether the intentional object has any existence independent of the act.[63] Intuition Main article: Intuition Intuition in phenomenology refers to cases where the intentional object is directly present to the intentionality at play; if the intention is "filled" by the direct apprehension of the object, one has an intuited object. Having a cup of coffee in front of oneself, for instance, seeing it, feeling it, or even imagining it – these are all filled intentions, and the object is then intuited. The same goes for the apprehension of mathematical formulae or a number. If one does not have the object as referred to directly, the object is not intuited, but still intended, but then emptily. Examples of empty intentions can be signitive intentions – intentions that only imply or refer to their objects.[64] Evidence In everyday language, the word evidence is used to signify a special sort of relation between a state of affairs and a proposition: State A is evidence for the proposition "A is true." In phenomenology, however, the concept of evidence is meant to signify the "subjective achievement of truth."[65] This is not an attempt to reduce the objective sort of evidence to subjective "opinion," but rather an attempt to describe the structure of having something present in intuition with the addition of having it present as intelligible: "Evidence is the successful presentation of an intelligible object, the successful presentation of something whose truth becomes manifest in the evidencing itself."[66] In Ideas, Husserl presents as the "Principle of All Principles" that, "every originary presentive intuition is a legitimizing source of cognition, that everything originally (so to speak, in its 'personal' actuality) offered to us in 'intuition' is to be accepted simply as what it is presented as being, but also only within the limits in which it is presented there." [67] It is in this realm of phenomenological givenness, Husserl claims, that the search begins for "indubitable evidence that will ultimately serve as the foundation for every scientific discipline."[68] Noesis and noema Main article: Noema Franz Brentano introduced a distinction between sensory and noetic consciousness: the former describes presentations of sensory objects or intuitions, while the latter describes the thinking of concepts.[69][70] In Husserl's phenomenology, this pair of terms, derived from the Greek nous (mind) designate respectively the real content, noesis, and the ideal content, noema, of an intentional act (an act of consciousness). The noesis is the part of the act that gives it a particular sense or character (as in judging or perceiving something, loving or hating it, accepting or rejecting it, etc.). This is real in the sense that it is actually part of what takes place in the consciousness of the subject of the act. The noesis is always correlated with a noema. For Husserl, the full noema is a complex ideal structure comprising at least a noematic sense and a noematic core. The correct interpretation of what Husserl meant by the noema has long been controversial, but the noematic sense is generally understood as the ideal meaning of the act. For instance, if A loves B, loving is a real part of A's conscious activity – noesis – but gets its sense from the general concept of loving, which has an abstract or ideal meaning, as "loving" has a meaning in the English language independently of what an individual means by the word when they use it. The noematic core as the act's referent or object as it is meant in the act. One element of controversy is whether this noematic object is the same as the actual object of the act (assuming it exists) or is some kind of ideal object.[71] Empathy and intersubjectivity See also: Empathy and Intersubjectivity In phenomenology, empathy refers to the experience of one's own body as another. While people often identify others with their physical bodies, this type of phenomenology requires that they focus on the subjectivity of the other, as well as the intersubjective engagement with them. In Husserl's original account, this was done by a sort of apperception built on the experiences of one's own lived body. The lived body is one's own body as experienced by oneself, as oneself. One's own body manifests itself mainly as one's possibilities of acting in the world. It is what lets oneself reach out and grab something, for instance, but it also, and more importantly, allows for the possibility of changing one's point of view. This helps to differentiate one thing from another by the experience of moving around it, seeing new aspects of it (often referred to as making the absent present and the present absent), and still retaining the notion that this is the same thing that one saw other aspects of just a moment ago (it is identical). One's body is also experienced as a duality, both as object (one's ability to touch one's own hand) and as one's own subjectivity (one's experience of being touched). The experience of one's own body as one's own subjectivity is then applied to the experience of another's body, which, through apperception, is constituted as another subjectivity. One can thus recognise the Other's intentions, emotions, etc. This experience of empathy is important in the phenomenological account of intersubjectivity. In phenomenology, intersubjectivity constitutes objectivity (i.e., what one experiences as objective is experienced as being intersubjectively available – available to all other subjects. This does not imply that objectivity is reduced to subjectivity nor does it imply a relativist position, cf. for instance intersubjective verifiability). In the experience of intersubjectivity, one also experiences oneself as being a subject among other subjects, and one experiences oneself as existing objectively for these Others; one experiences oneself as the noema of Others' noeses, or as a subject in another's empathic experience. As such, one experiences oneself as objectively existing subjectivity. Intersubjectivity is also a part in the constitution of one's lifeworld, especially as "homeworld." Lifeworld Main article: Lifeworld The lifeworld (German: Lebenswelt) is the "world" each one of us lives in. One could call it the "background" or "horizon" of all experience, and it is that on which each object stands out as itself (as different) and with the meaning it can only hold for us. The lifeworld is both personal and intersubjective (it is then called a "homeworld"), and, as such, it does not enclose each one of us in a solus ipse. Phenomenology and empirical science The phenomenological analysis of objects is notably different from traditional science. However, several frameworks do phenomenology with an empirical orientation or aim to unite it with the natural sciences or with cognitive science. For a classical critical point of view, Daniel Dennett argues for the wholesale uselessness of phenomenology considering phenomena as qualia, which cannot be the object of scientific research or do not exist in the first place. Liliana Albertazzi counters such arguments by pointing out that empirical research on phenomena has been successfully carried out employing modern methodology. Human experience can be investigated by surveying, and with brain scanning techniques. For example, ample research on color perception suggests that people with normal color vision see colors similarly and not each in their own way. Thus, it is possible to universalize phenomena of subjective experience on an empirical scientific basis.[72] In the early twenty-first century, phenomenology has increasingly engaged with cognitive science and philosophy of mind. Some approaches to the naturalization of phenomenology reduce consciousness to the physical-neuronal level and are therefore not widely acknowledged as representing phenomenology. These include the frameworks of neurophenomenology, embodied constructivism, and the cognitive neuroscience of phenomenology. Other likewise controversial approaches aim to explain life-world experience on a sociological or anthropological basis despite phenomenology being mostly considered descriptive rather than explanatory.[73] |
コンセプト 意図性 主な記事 意図性 意図性とは、意識は常に何かを意識しているという考え方のことである。この言葉自体は、意図的という言葉の「普通の」用法と混同されるべきではなく、むし ろ語源的な根源を利用したものととらえるべきである。元来、intentionは「伸ばす」こと(ラテン語のintendereに由来する「緊張状態」) を指し、この文脈では意識が対象に向かって「伸びる」ことを指す。しかし、このイメージには注意が必要である。最初に意識があり、その後に対象に向かって 伸びるのではなく、意識は意識的行為とその対象の同時性として生じるのである。 意図性はしばしば "aboutness "として要約される。意識が対象としているものが、直接的な知覚の中にあるのか、空想の中にあるのかは、意図性という概念そのものにとって重要ではない。 つまり、意識の対象は、知覚によって理解される物理的な物体である必要はない。その結果、知覚、記憶、空想などの意識の「構造」を意図性と呼ぶ。 意図性」という用語は、中世のスコラ学者に端を発し、ブレンターノによって復活した。ブレンターノはフッサールの現象学の概念に影響を与え、フッサールは この用語を洗練させ、彼の意識論の基礎とした。この用語の意味は複雑で、ある哲学者がどのように捉えるかによって全く異なる。この用語は、「意図」や、無 意識の「動機」や「利得」という精神分析学的概念と混同されるべきではない。 重要なのは、「意図性は関係性ではなく、むしろ意図的行為の本質的特徴である」ということである。なぜなら、独立した関係性は存在しないからである。意図 的な対象が行為から独立した何らかの存在を持っているかどうかは、現象学者にとっては(少なくとも第一義的には)無関心な問題である[63]。 直観 主な記事 直観 現象学における直観とは、意図的対象が行為中の意図性に直接存在する場合を指す。もし意図が対象の直接的な理解によって「満たされる」なら、直観された対 象が存在することになる。例えば、目の前にコーヒーカップがあること、それを見ること、感じること、あるいは想像すること--これらはすべて満たされた意 図であり、対象は直観される。数式や数字を理解するのも同じである。直接的に参照される対象がない場合、その対象は直観されるのではなく、意図されたもの ではあるが、空虚なものとなる。空虚な意図の例としては、意味的意図、つまり対象を暗示したり参照したりするだけの意図がある[64]。 証拠 日常言語では、証拠という言葉は、ある状態と命題との間の特別な種類の関係を意味するために使われる: 状態Aは「Aは真である」という命題の証拠である。しかし現象学では、証拠という概念は「真理の主観的達成」[65]を意味するものである。これは証拠の 客観的な種類を主観的な「意見」に還元しようとする試みではなく、むしろ直観において何かが存在し、それが理解可能なものとして存在するという構造を追加 して記述しようとする試みである: 「証拠とは、理解可能な対象がうまく提示されることであり、その真理が証明されること自体において明らかになる何かがうまく提示されることである」 [66]。 『イデア』においてフッサールは「すべての原理の原理」として、「すべての起源的な提示的直観は認識の正当化の源泉であり、『直観』においてわれわれに提 示されたすべてのものは、もともと(いわばその『個人的な』実在性において)、それがあるものとして提示されたものとして単純に受容されるべきであり、ま たそれがそこで提示された限界の範囲内においてのみ受容されるべきものである」と提示している[67]。[フッサールは、この現象学的所与性の領域におい てこそ、「あらゆる科学的学問分野の基礎として最終的に機能する確実な証拠」の探求が始まると主張している[68]。 ノエシスとノエマ 主な記事 ノエマ フランツ・ブレンターノは感覚的意識とノエティックな意識の区別を導入した:前者は感覚的対象または直観の提示を記述し、後者は概念の思考を記述する [69][70]。 フッサールの現象学では、ギリシャ語のヌース(心)に由来するこの一対の用語はそれぞれ、意図的行為(意識行為)の現実的内容であるノエシスと理想的内容 であるノエマを指定する。ノエシスとは、行為に特定の感覚や性格を与える部分である(何かを判断したり知覚したり、愛したり憎んだり、受け入れたり拒絶し たりするときのように)。これは、行為の主体の意識の中で実際に起こっていることの一部であるという意味で実在する。ノエシスは常にノエマと関連してい る。フッサールにとって、完全なノエマとは、少なくともノエマ的意味とノエマ的核心からなる複雑な理想構造である。フッサールの言うノエマの正しい解釈に ついては長い間議論があったが、ノエマ的意味とは一般に行為の理想的意味として理解されている。例えば、AがBを愛している場合、愛することはAの意識活 動の現実的な部分-ノエシス-ではあるが、「愛する」という一般的な概念からその意味を得ているのであり、それは抽象的な、あるいは理想的な意味を持って いる。ノエマティック・コアは、その行為において意味される、その行為の参照者または対象として。論争の一つの要素は、このノエマティックな対象が行為の 実際の対象(それが存在すると仮定して)と同じなのか、それともある種の理想的な対象なのかということである[71]。 共感と間主観性 こちらも参照: 共感と間主観性 現象学において共感とは、自分の身体を他者として経験することを指す。人はしばしば他者を自分の身体と同一視するが、このタイプの現象学では、他者との間 主観的な関わりだけでなく、他者の主観性に注目する必要がある。フッサールの当初の説明では、これは自分自身の生かされている身体の経験に基づいて構築さ れた一種の知覚によって行われた。生きている身体とは、自分自身によって、自分自身として経験される自分自身の身体のことである。自分の身体は、主に世界 における自分の行動の可能性として現れる。例えば、手を伸ばして何かをつかむことができるのは身体であるが、それだけではなく、より重要なこととして、視 点を変えることができるのも身体である。これは、あるものを別のものから区別するのに役立ち、その周囲を動き回り、そのものの新たな側面を見る(しばしば 不在を現在に、現在を不在にすると言われる)経験によって、これはついさっき別の側面を見たのと同じものである(同一である)という観念を保持したままで ある。自分の身体もまた、対象として(自分の手に触れることができる)、また自分自身の主観として(触れられるという経験)、二重性として経験される。 自分の主観としての自分の身体の経験は、次に他者の身体の経験に適用され、それは知覚を通して、もうひとつの主観として構成される。こうして人は、他者の 意図や感情などを認識することができる。この共感の経験は、間主観性の現象学的説明において重要である。現象学では、間主観性は客観性を構成する(つま り、ある人が客観的なものとして経験することは、間主観的に利用可能なもの、つまり他のすべての主体が利用可能なものとして経験される)。これは客観性が 主観性に還元されることを意味するものではなく、また相対主義的な立場を意味するものでもない。) 間主観性の経験において、人はまた、自分が他の主体の中の主体であることを経験し、自分がこれらの他者のために客観的に存在することを経験する。このよう に、人は自分自身を客観的に存在する主観として経験する。相互主観性はまた、自分のライフワールド、特に "ホームワールド "を構成する一部でもある。 ライフワールド(生活世界) 主な記事 ライフワールド ライフワールド(ドイツ語:Lebenswelt)とは、私たち一人ひとりが生きている「世界」のことである。あらゆる経験の「背景」あるいは「地平」と 呼べるものであり、それぞれの対象がそれ自体として(異なるものとして)、また私たちにとってのみ意味を持つものとして際立つものである。生命世界は、個 人的であると同時に間主観的であり(そのような世界は「同郷世界」と呼ばれる)、そのような世界として、私たち一人ひとりをソルス・イプセで囲むことはな い。 現象学と経験科学 対象の現象学的分析は、伝統的な科学とは明らかに異なる。しかし、いくつかの枠組みでは、現象学を経験的な方向づけで行ったり、自然科学や認知科学との統 合を目指したりしている。 古典的な批判的視点として、ダニエル・デネットは、現象をクオリアとみなす現象学は、科学的研究の対象にはなり得ないか、そもそも存在しないとして、全く 無意味であると主張している。リリアナ・アルベルタッツィは、このような議論に対して、現象に関する実証的研究は近代的な方法論によって成功裏に行われて きたと指摘する。人間の経験は、調査や脳スキャン技術によって調べることができる。例えば、色の知覚に関する十分な研究は、正常な色覚の持ち主であれば、 色の見え方は人それぞれではなく、似たようなものであることを示唆している。このように、主観的経験の現象を経験科学的根拠に基づいて普遍化することは可 能である[72]。 21世紀初頭、現象学は認知科学や心の哲学との関わりを強めている。現象学の自然化へのアプローチの中には、意識を物理的な神経細胞レベルに還元するもの もあり、そのため現象学を代表するものとして広く認められていない。これには、神経現象学、身体化構成主義、現象学の認知神経科学の枠組みが含まれる。他 の同様に論争の的となるアプローチは、現象学が説明的というよりはむしろ記述的であると考えられているにもかかわらず、社会学的または人類学的な基礎の上 に生命世界の経験を説明することを目指している[73]。 |
| Binding problem Existentialism Geneva School Hard problem of consciousness Heterophenomenology Phenomenography Phenomenology of religion Vertiginous question |
バインディング問題 実存主義 ジュネーブ学派 意識の難問 異次元の現象学 現象学 宗教現象学 垂直的問題 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenology_(philosophy) |
|
| The
consciousness and binding problem is the problem of how objects,
background and abstract or emotional features are combined into a
single experience.[1] The binding problem refers to the overall encoding of our brain circuits for the combination of decisions, actions, and perception. It is considered a "problem" due to the fact that no complete model exists. The binding problem can be subdivided into four problems of perception, used in neuroscience, cognitive science, and the philosophy of mind. It includes general considerations on coordination, the subjective unity of perception, and variable binding.[2] |
意識と結合の問題とは、対象、背景、抽象的または感情的な特徴が、どの
ように一つの経験に組み合わされるかという問題である[1]。 結合問題とは、意思決定、行動、知覚の組み合わせに関する脳回路の全体的な符号化のことである。完全なモデルが存在しないことから、「問題」と考えられて いる。 結合問題は、神経科学、認知科学、心の哲学において用いられる知覚の4つの問題に細分化することができる。これには、協調、知覚の主観的統一性、変数束縛 に関する一般的な考察が含まれる[2]。 |
| General considerations on
coordination Summary of problem Attention is crucial in determining which phenomena appear to be bound together, noticed, and remembered.[3] This specific binding problem is generally referred to as temporal synchrony. At the most basic level, all neural firing and its adaptation depends on specific consideration to timing (Feldman, 2010). At a much larger level, frequent patterns in large scale neural activity are a major diagnostic and scientific tool.[4] Synchronization theory and research A popular hypothesis mentioned by Peter Milner, in his 1974 article A Model for Visual Shape Recognition, has been that features of individual objects are bound/segregated via synchronization of the activity of different neurons in the cortex.[5][6] The theory, called binding-by-synchrony (BBS), is hypothesized to occur through the transient mutual synchronization of neurons located in different regions of the brain when the stimulus is presented.[7] Empirical testing of the idea was brought to light when von der Malsburg proposed that feature binding posed a special problem that could not be covered simply by cellular firing rates.[8] However, it has been shown this theory may not be a problem since it was revealed that the modules code jointly for multiple features, countering the feature-binding issue.[9] Temporal synchrony has been shown to be the most prevalent when regarding the first problem, "General Considerations on Coordination," because it is an effective method to take in surroundings and is good for grouping and segmentation. A number of studies suggested that there is indeed a relationship between rhythmic synchronous firing and feature binding. This rhythmic firing appears to be linked to intrinsic oscillations in neuronal somatic potentials, typically in the gamma range around 40 – 60 hertz.[10] The positive arguments for a role for rhythmic synchrony in resolving the segregational object-feature binding problem have been summarized by Singer.[11] There is certainly extensive evidence for synchronization of neural firing as part of responses to visual stimuli. However, there is inconsistency between findings from different laboratories. Moreover, a number of recent reviewers, including Shadlen and Movshon[6] and Merker[12] have raised concerns about the theory being potentially untenable. Thiele and Stoner found that perceptual binding of two moving patterns had no effect on synchronization of the neurons responding to two patterns: coherent and noncoherent plaids.[13] In the primary visual cortex, Dong et al. found that whether two neurons were responding to contours of the same shape or different shapes had no effect on neural synchrony since synchrony is independent of binding condition. Shadlen and Movshon[6] raise a series of doubts about both the theoretical and the empirical basis for the idea of segregational binding by temporal synchrony. There is no biophysical evidence that cortical neurons are selective to synchronous input at this point of precision and cortical activity with synchrony this precise is rare. Synchronization is also connected to endorphin activity. It has been shown that precise spike timing may not be necessary to illustrate a mechanism for visual binding and is only prevalent in modeling certain neuronal interactions. In contrast, Seth[14] describes an artificial brain-based robot that demonstrates multiple, separate, widely distributed neural circuits, firing at different phases,showing that regular brain oscillations at specific frequencies are essential to the neural mechanisms of binding. Goldfarb and Treisman[15] point out that a logical problem appears to arise for binding solely via synchrony if there are several objects that share some of their features and not others. At best synchrony can facilitate segregation supported by other means (as von der Malsburg acknowledges).[16] A number of neuropsychological studies suggest that the association of color, shape and movement as "features of an object" is not simply a matter of linking or "binding", but shown to be inefficient to not bind elements into groups when considering association[17] and give extensive evidence for top-down feedback signals that ensure that sensory data are handled as features of (sometimes wrongly) postulated objects early in processing. Pylyshyn[18] has also emphasized the way the brain seems to pre-conceive objects from which features are to be allocated to which are attributed continuing existence even if features such as color change. This is because visual integration increases over time and indexing visual objects helps to ground visual concepts. |
調整に関する一般的な考察 問題の概要 注意は、どのような現象が一緒に束縛され、注目され、記憶され ているように見えるかを決定する上で極めて重要である[3]。この特 定の束縛の問題は一般に時間的同期性と呼ばれる。最も基本的なレベルでは、すべての神経発火とその適応は、タイミン グに対する特定の配慮に依存している(Feldman, 2010)。もっと大きなレベルでは、大規模な神経活動における頻度の高いパターンは、主要な診断および科学的ツールである[4]。 同期の理論と研究 ピーター・ミルナー(Peter Milner)により1974年に発表された論文「視覚的形状認 識モデル(A Model for Visual Shape Recognition)」において言及された一般的な仮説は、個々の物体の特徴が大脳皮質の異なるニューロンの活動の同期を介して結合/分離されるとい うものである[5][6]。Binding-by-Synchrony(BBS)と呼ばれるこの理論は、刺激が提示されたときに脳の異なる領域に位置する ニューロンの一時的な相互同期によって起こると仮定されている[7]。 [しかし、モジュールが複数の特徴について共同でコーディングしていることが明らかになり、特徴結合の問題に対抗しているため、この理論が問題ではない可 能性があることが示されている[8]。 [最初の問題である「協調に関する一般的考察」に関しては、時間的同期が最も優勢であることが示されている。多くの研究が、リズミカルな同期発火と特徴的 な結合との間に確かに関係があることを示唆した。このリズミカルな発火は、神経細胞の体電位の固有振動と関連しているようであり、典型的には約40~60 ヘルツのガンマ範囲にある[10]。分離物体-特徴結合問題の解決におけるリズミカルな同期の役割に対する肯定的な議論は、Singerによってまとめら れている[11]。確かに、視覚刺激に対する反応の一部として神経発火が同期していることについては、広範な証拠がある。 しかし、異なる研究室から得られた知見には一貫性がない。さらに、ShadlenとMovshon[6]やMerker[12]を含む多くの最近のレビュ アーが、この理論が潜在的に成り立たないという懸念を提起している。ThieleとStonerは、2つの動くパターンを知覚的に結合しても、2つのパ ターン(コヒーレントな格子縞と非コヒーレントな格子縞)に反応するニューロンの同期に影響を与えないことを発見した[13]。Dongらは、一次視覚野 において、2つのニューロンが同じ形状の輪郭に反応するか、異なる形状の輪郭に反応するかは、同期が結合条件に依存しないため、神経同期に影響を与えない ことを発見した。 ShadlenとMovshon[6]は、時間的同期による分離結合という考え方の理論的根拠と経験的根拠の両方について、一連の疑念を呈している。皮質 ニューロンがこの精度の同期入力に対して選択的であるという生物物理学的証拠はなく、この精度の同期を持つ皮質活動はまれである。同期化はエンドルフィン 活動にも関係している。正確なスパイク・タイミングは視覚的結合のメカニズムを説明するのに必要ではなく、特定のニューロン相互作用をモデル化するのに普 及しているだけかもしれないことが示されている。対照的に、Seth[14]は、異なる位相で発火する、複数の、分離した、広範囲に分散した神経回路を示 す人工脳ベースのロボットについて記述しており、特定の周波数における規則的な脳の振動が、結合の神経メカニズムに不可欠であることを示している。 GoldfarbとTreisman[15]は、いくつかの特徴を共有し、他の特徴を共有しない対象が複数存在する場合、同期のみを介した結合には論理的 な問題が生じるようだと指摘している。せいぜい同期が他の手段によってサポートされる分離を促進することができる程度である(フォン・デア・マルスブルク も認めている)[16]。 多くの神経心理学的研究は、「物体の特徴」としての色、形、動きの関連付けが単純にリンクや「結合」の問題ではなく、関連付けを考える際に要素をグループ に結合しないことが非効率的であることを示していることを示唆しており[17]、感覚データが処理の初期段階で(時には間違って)仮定された物体の特徴と して扱われることを保証するトップダウンのフィードバック信号に関する広範な証拠を与えている。Pylyshyn[18]はまた、色などの特徴が変化して も、脳がどの特徴からどの特徴に割り当てられ、継続的に存在すると仮定される対象物をあらかじめ想定しているようであることを強調している。これは、視覚 的統合が時間の経過とともに増加し、視覚的対象をインデックス化することで、視覚的概念を根拠づけることができるためである。 |
| Feature integration theory Summary of problem The visual feature binding problem refers to the question of why we do not confuse a red circle and a blue square with a blue circle and a red square. The understanding of the circuits in the brain stimulated for visual feature binding is increasing. A binding process is required for us to accurately encode various visual features in separate cortical areas. In her feature integration theory, Treisman suggested that one of the first stages of binding between features is mediated by the features' links to a common location. The second stage is combining individual features of an object that requires attention, and selecting that object occurs within a "master map" of locations. Psychophysical demonstrations of binding failures under conditions of full attention provide support for the idea that binding is accomplished through common location tags.[19] An implication of these approaches is that sensory data such as color or motion may not normally exist in "unallocated" form. For Merker:[20] "The 'red' of a red ball does not float disembodied in an abstract color space in V4." If color information allocated to a point in the visual field is converted directly, via the instantiation of some form of propositional logic (analogous to that used in computer design) into color information allocated to an "object identity" postulated by a top-down signal as suggested by Purves and Lotto (e.g. There is blue here + Object 1 is here = Object 1 is blue) no special computational task of "binding together" by means such as synchrony may exist. (Although Von der Malsburg[21] poses the problem in terms of binding "propositions" such as "triangle" and "top", these, in isolation, are not propositional.) How signals in the brain come to have propositional content, or meaning, is a much larger issue. However, both Marr[22] and Barlow[23] suggested, on the basis of what was known about neural connectivity in the 1970s that the final integration of features into a percept would be expected to resemble the way words operate in sentences. The role of synchrony in segregational binding remains controversial. Merker[20] has recently suggested that synchrony may be a feature of areas of activation in the brain that relates to an "infrastructural" feature of the computational system analogous to increased oxygen demand indicated via BOLD signal contrast imaging. Apparent specific correlations with segregational tasks may be explainable on the basis of interconnectivity of the areas involved. As a possible manifestation of a need to balance excitation and inhibition over time it might be expected to be associated with reciprocal re-entrant circuits as in the model of Seth et al.[14] (Merker gives the analogy of the whistle from an audio amplifier receiving its own output.) Experimental work Visual feature binding is suggested to have a selective attention to the locations of the objects. If indeed spatial attention does play a role in binding integration it will do so primarily when object location acts as a binding cue. A study's findings has shown that functional MRI images indicate regions of the parietal cortex involved in spatial attention, engaged in feature conjunction tasks in single feature tasks. The task involved multiple objects being shown simultaneously at different locations which activated the parietal cortex. Whereas when multiple objects are shown sequentially at the same location the parietal cortex was less engaged.[24] Behavioral experiments Defoulzi et al. Investigated feature binding through two feature dimensions, to disambiguate whether a specific combination of color and motion direction is perceived as bound or unbound. Two behaviorally relevant features, including color and motion belonging to the same object, are defined as the "bound" condition. Whereas the "unbound" condition has features that belong to different objects. Local field potentials were recorded from the lateral prefrontal cortex(lPFC) in monkeys and were monitored during different stimulus configurations. The findings suggest a neural representation of visual feature binding in 4 to 12 Hertz frequency bands. It is also suggested that transmission of binding information is relayed through different lPFC neural subpopulations. The data shows a behavioral relevance of binding information that is linked to the animal's reaction time. This includes the involvement of the prefrontal cortex targeted by the dorsal and ventral visual streams in binding visual features from different dimensions (color and motion).[25] It is suggested that the visual feature binding consists of two different mechanisms in visual perception. One mechanism consists of agonistic familiarity of possible combinations of features integrating several temporal integration windows. It is speculated that this process is mediated by neural synchronization processes and temporal synchronization in the visual cortex. The second mechanism is mediated by familiarity with the stimulus and is provided by attentional top-down support from familiar objects. [26] |
特徴統合理論 問題の概要 視覚的特徴結合問題とは、赤い丸と青い四角、青い丸と赤い四角をなぜ混同しないのかという問題である。視覚的特徴結合のために刺激される脳内回路の解明が 進んでいる。私たちが様々な視覚的特徴を別々の皮質領域で正確に符号化するためには、結合過程が必要である。 トレイスマンは、特徴統合理論において、特徴間の結合の第一段階の一つは、共通の場所への特徴のリンクによって媒介されることを示唆した。第二段階は、注 意を必要とする対象物の個々の特徴を組み合わせ、その対象物を場所の「マスターマップ」内で選択することである。完全な注意の条件下での結合の失敗の心理 物理学的実証は、結合が共通の場所タグを通じて達成されるという考えを支持している[19]。 これらのアプローチの意味するところは、色や動きのような感覚データは通常「未割り当て」の形では存在しないかもしれないということである。マーカーは次 のように述べている[20]。「赤いボールの "赤 "は、V4の抽象的な色空間に実体のない形で浮かんでいるわけではない」。もし視覚野のある点に割り当てられた色情報が、何らかの命題論理(コンピュータ 設計で使用されるものと類似)のインスタンス化を介して、PurvesとLottoによって提案されたようなトップダウン信号によって仮定された「物体同 一性」に割り当てられた色情報に直接変換されるのであれば(例えば、ここに青がある+物体1がここにある=物体1は青である)、同期のような手段によって 「結合する」という特別な計算タスクは存在しないかもしれない。(フォン・デア・マルスブルグ[21]は、「三角形」や「頂上」といった「命題」の束縛と いう観点から問題を提起しているが、これらは単独では命題ではない。) 脳内の信号がどのようにして命題的な内容、つまり意味を持つようになるかは、もっと大きな問題である。しかし、Marr[22]とBarlow[23]の 両氏は、1970年代に神経結合について知られていたことに基づいて、知覚への特徴の最終的な統合は、文の中で単語が作用する方法に似ていると予想される と示唆した。 分離結合における同期の役割については依然として議論がある。Merker[20]は最近、同期性は脳内の活性化領域の特徴であり、BOLD信号コントラ ストイメージングによって示される酸素需要の増加に類似した、計算システムの「基盤的」特徴に関連している可能性を示唆している。分離課題との明らかな特 異的相関は、関係する領域の相互連結性に基づいて説明できるかもしれない。時間の経過とともに興奮と抑制のバランスをとる必要性の現れとして、Sethら [14]のモデルのような相互リエントラント回路との関連が期待されるかもしれない(Merkerは、オーディオアンプのホイッスルがそれ自身の出力を受 け取るというアナロジーを示している)。 実験的研究 視覚的特徴結合には、対象物の位置に対する選択的注意があることが示唆されている。もし空間的注意が束縛の統合に役割を果たすのであれば、それは主に物体 の位置が束縛の手がかりとして作用するときに行われるであろう。ある研究の結果、MRIの機能的画像から、空間的注意に関与する頭頂皮質の領域が、単一特 徴課題における特徴連結課題に関与していることが示された。この課題では、複数の物体が異なる場所に同時に表示され、頭頂皮質を活性化させた。一方、複数 の物体が同じ場所に順次示される場合、頭頂皮質の関与は少なかった[24]。 行動実験 Defoulziらは、色と運動方向の特定の組み合わせが、束縛されたものとして知覚されるか、束縛されていないものとして知覚されるかを曖昧にするため に、2つの特徴次元を通して特徴束縛を調査した。同じ物体に属する色と動きを含む2つの行動学的に関連する特徴を「束縛」条件と定義。一方、「束縛されて いない」条件には、異なる物体に属する特徴がある。局所電位はサルの外側前頭前皮質(lPFC)から記録され、異なる刺激構成中にモニターされた。その結 果、4ヘルツから12ヘルツの周波数帯域で視覚的特徴の束縛が神経表現されていることが示唆された。また、束縛情報の伝達は、lPFCの異なる神経部分集 団を通じて行われていることが示唆された。データは、動物の反応時間と結びついた結合情報の行動的関連性を示している。これには、異なる次元(色と運動) からの視覚的特徴の束縛における、背側および腹側視覚ストリームが標的とする前頭前野の関与が含まれる[25]。 視覚的特徴の結合は、視覚知覚における2つの異なるメカニズムから構成されていることが示唆されている。1つのメカニズムは、いくつかの時間的統合窓を統 合する特徴の可能な組み合わせの共役的親和性からなる。このプロセスは、視覚野における神経同期プロセスと時間的同期によって媒介されると推測されてい る。2つ目のメカニズムは、刺激に対する慣れによって媒介され、慣れ親しんだ対象からの注意のトップダウン支援によって提供される。[26] |
| Consciousness and binding Summary of problem Smythies[27] defines the combination problem, also known as the subjective unity of perception, as "How do the brain mechanisms actually construct the phenomenal object?". Revonsuo[1] equates this to "consciousness-related binding", emphasizing the entailment of a phenomenal aspect. As Revonsuo explores in 2006,[28] there are nuances of difference beyond the basic BP1:BP2 division. Smythies speaks of constructing a phenomenal object ("local unity" for Revonsuo) but philosophers such as Descartes, Leibniz, Kant and James (see Brook and Raymont)[29] have typically been concerned with the broader unity of a phenomenal experience ("global unity" for Revonsuo) – which, as Bayne[30] illustrates may involve features as diverse as seeing a book, hearing a tune and feeling an emotion. Further discussion will focus on this more general problem of how sensory data that may have been segregated into, for instance, "blue square" and "yellow circle" are to be re-combined into a single phenomenal experience of a blue square next to a yellow circle, plus all other features of their context. There is a wide range of views on just how real this "unity" is, but the existence of medical conditions in which it appears to be subjectively impaired, or at least restricted, suggests that it is not entirely illusory.[31] There are many neurobiological theories about the subjective unity of perception. Different visual features such as color, size, shape, and motion are computed by largely distinct neural circuits but we experience an integrated whole. The different visual features interact with each other in various ways. For example, shape discrimination of objects is strongly affected by orientation but only slightly affected by object size.[32] Some theories suggest that global perception of the integrated whole involves higher order visual areas.[33] There is also evidence that the posterior parietal cortex is responsible for perceptual scene segmentation and organization.[34] Bodies facing each other are processed as a single unit and there is increased coupling of the extrastriate body area (EBA) and the posterior superior temporal sulcus (pSTS) when bodies are facing each other.[35] This suggests that the brain is biased towards grouping humans in twos or dyads.[36] History Early philosophers Descartes and Leibniz[37] noted that the apparent unity of our experience is an all-or-none qualitative characteristic that does not appear to have an equivalent in the known quantitative features, like proximity or cohesion, of composite matter. William James[38] in the nineteenth century, considered the ways the unity of consciousness might be explained by known physics and found no satisfactory answer. He coined the term "combination problem", in the specific context of a "mind-dust theory" in which it is proposed that a full human conscious experience is built up from proto- or micro-experiences in the way that matter is built up from atoms. James claimed that such a theory was incoherent, since no causal physical account could be given of how distributed proto-experiences would "combine". He favoured instead a concept of "co-consciousness" in which there is one "experience of A, B and C" rather than combined experiences. A detailed discussion of subsequent philosophical positions is given by Brook and Raymont (see 26). However, these do not generally include physical interpretations. Whitehead[39] proposed a fundamental ontological basis for a relation consistent with James's idea of co-consciousness, in which many causal elements are co-available or "compresent" in a single event or "occasion" that constitutes a unified experience. Whitehead did not give physical specifics but the idea of compresence is framed in terms of causal convergence in a local interaction consistent with physics. Where Whitehead goes beyond anything formally recognized in physics is in the "chunking" of causal relations into complex but discrete "occasions". Even if such occasions can be defined, Whitehead's approach still leaves James's difficulty with finding a site, or sites, of causal convergence that would make neurobiological sense for "co-consciousness". Sites of signal convergence do clearly exist throughout the brain but there is a concern to avoid re-inventing what Daniel Dennett[40] calls a Cartesian Theater or single central site of convergence of the form that Descartes proposed. Descartes's central "soul" is now rejected because neural activity closely correlated with conscious perception is widely distributed throughout the cortex. The remaining choices appear to be either separate involvement of multiple distributed causally convergent events or a model that does not tie a phenomenal experience to any specific local physical event but rather to some overall "functional" capacity. Whichever interpretation is taken, as Revonsuo[1] indicates, there is no consensus on what structural level we are dealing with – whether the cellular level, that of cellular groups as "nodes", "complexes" or "assemblies" or that of widely distributed networks. There is probably only general agreement that it is not the level of the whole brain, since there is evidence that signals in certain primary sensory areas, such as the V1 region of the visual cortex (in addition to motor areas and cerebellum), do not contribute directly to phenomenal experience. Experimental work on the biological basis of binding fMRI work Stoll and colleagues conducted an fMRI experiment to see whether participants would view a dynamic bistable stimulus globally or locally.[33] Responses in lower visual cortical regions were suppressed when participants viewed the stimulus globally. However, if global perception was without shape grouping, higher cortical regions were suppressed. This experiment shows that higher order cortex is important in perceptual grouping. Grassi and colleagues used three different motion stimuli to investigate scene segmentation or how meaningful entities are grouped together and separated from other entities in a scene.[34] Across all stimuli, scene segmentation was associated with increased activity in the posterior parietal cortex and decreased activity in lower visual areas. This suggests that the posterior parietal cortex is important for viewing an integrated whole. EEG work Mersad and colleagues used an EEG frequency tagging technique to differentiate between brain activity for the integrated whole object and brain activity for parts of the object.[41] The results showed that the visual system binds two humans in close proximity as part of an integrated whole. These results are consistent with evolutionary theories that face-to-face bodies are one of the earliest representations of social interaction.[36] It also supports other experimental work showing that body-selective visual areas respond more strongly to facing bodies.[42] Electron tunneling Experiments have shown that ferritin and neuromelanin in fixed human substantia nigra pars compacta (SNc) tissue are able to support widespread electron tunneling.[43] Further experiments have shown that ferritin structures similar to ones found in SNc tissue are able to conduct electrons over distances as great as 80 microns, and that they behave in accordance with Coulomb blockade theory to perform a switching or routing function.[44][45] Both of these observations are consistent with earlier predictions that are part of a hypothesis that ferritin and neuromelanin can provide a binding mechanism associated with an action selection mechanism,[46] although the hypothesis itself has not yet been directly investigated. The hypothesis and these observations have been applied to Integrated Information Theory.[47] Modern theories Daniel Dennett[40] has proposed that our sense that our experiences are single events is illusory and that, instead, at any one time there are "multiple drafts" of sensory patterns at multiple sites. Each would only cover a fragment of what we think we experience. Arguably, Dennett is claiming that consciousness is not unified and there is no phenomenal binding problem. Most philosophers have difficulty with this position (see Bayne)[30] but some physiologists agree with it. In particular, the demonstration of perceptual asynchrony in psychophysical experiments by Moutoussis and Zeki,[48][49] when color is perceived before orientation of lines and before motion by 40 and 80 ms, respectively, constitutes an argument that, over these very short time periods, different attributes are consciously perceived at different times, leading to the view that at least over these brief periods of time after visual stimulation, different events are not bound to each other, leading to the view of a disunity of consciousness,[50] at least over these brief time intervals. Dennett's view might be in keeping with evidence from recall experiments and change blindness purporting to show that our experiences are much less rich than we sense them to be – what has been called the Grand Illusion.[51] However, few, if any, other authors suggest the existence of multiple partial "drafts". Moreover, also on the basis of recall experiments, Lamme[52] has challenged the idea that richness is illusory, emphasizing that phenomenal content cannot be equated with content to which there is cognitive access. Dennett does not tie drafts to biophysical events. Multiple sites of causal convergence are invoked in specific biophysical terms by Edwards[53] and Sevush.[54] In this view the sensory signals to be combined in phenomenal experience are available, in full, at each of multiple sites. To avoid non-causal combination each site/event is placed within an individual neuronal dendritic tree. The advantage is that "compresence" is invoked just where convergence occurs neuro-anatomically. The disadvantage, as for Dennett, is the counter-intuitive concept of multiple "copies" of experience. The precise nature of an experiential event or "occasion", even if local, also remains uncertain. The majority of theoretical frameworks for the unified richness of phenomenal experience adhere to the intuitive idea that experience exists as a single copy, and draw on "functional" descriptions of distributed networks of cells. Baars[55] has suggested that certain signals, encoding what we experience, enter a "Global Workspace" within which they are "broadcast" to many sites in the cortex for parallel processing. Dehaene, Changeux and colleagues[56] have developed a detailed neuro-anatomical version of such a workspace. Tononi and colleagues[57] have suggested that the level of richness of an experience is determined by the narrowest information interface "bottleneck" in the largest sub-network or "complex" that acts as an integrated functional unit. Lamme[52] has suggested that networks supporting reciprocal signaling rather than those merely involved in feed-forward signaling support experience. Edelman and colleagues have also emphasized the importance of re-entrant signaling.[58] Cleeremans[59] emphasizes meta-representation as the functional signature of signals contributing to consciousness. In general, such network-based theories are not explicitly theories of how consciousness is unified, or "bound" but rather theories of functional domains within which signals contribute to unified conscious experience. A concern about functional domains is what Rosenberg[60] has called the boundary problem; it is hard to find a unique account of what is to be included and what excluded. Nevertheless, this is, if anything is, the consensus approach. Within the network context, a role for synchrony has been invoked as a solution to the phenomenal binding problem as well as the computational one. In his book, The Astonishing Hypothesis,[61] Crick appears to be offering a solution to BP2 as much as BP1. Even von der Malsburg,[62] introduces detailed computational arguments about object feature binding with remarks about a "psychological moment". The Singer group[63] also appear to be interested as much in the role of synchrony in phenomenal awareness as in computational segregation. The apparent incompatibility of using synchrony to both segregate and unify might be explained by sequential roles. However, Merker[20] points out what appears to be a contradiction in attempts to solve the subjective unity of perception in terms of a functional (effectively meaning computational) rather than a local biophysical, domain, in the context of synchrony. Functional arguments for a role for synchrony are in fact underpinned by analysis of local biophysical events. However, Merker[20] points out that the explanatory work is done by the downstream integration of synchronized signals in post-synaptic neurons: "It is, however, by no means clear what is to be understood by 'binding by synchrony' other than the threshold advantage conferred by synchrony at, and only at, sites of axonal convergence onto single dendritic trees..." In other words, although synchrony is proposed as a way of explaining binding on a distributed, rather than a convergent, basis the justification rests on what happens at convergence. Signals for two features are proposed as bound by synchrony because synchrony effects downstream convergent interaction. Any theory of phenomenal binding based on this sort of computational function would seem to follow the same principle. The phenomenality would entail convergence, if the computational function does. The assumption in many of the quoted models suggest that computational and phenomenal events, at least at some point in the sequence of events, parallel each other in some way. The difficulty remains in identifying what that way might be. Merker's[20] analysis suggests that either (1) both computational and phenomenal aspects of binding are determined by convergence of signals on neuronal dendritic trees, or (2) that our intuitive ideas about the need for "binding" in a "holding together" sense in both computational and phenomenal contexts are misconceived. We may be looking for something extra that is not needed. Merker, for instance, argues that the homotopic connectivity of sensory pathways does the necessary work. |
意識と束縛 問題の概要 Smythies[27]は、知覚の主観的統一としても知られる結合問題を、「脳のメカニズムが実際にどのように現象的対象を構築しているのか」と定義し ている。Revonsuo[1]はこれを「意識に関連した束縛」と同一視し、現象的側面の内包を強調している。Revonsuoが2006年に探求してい るように[28]、基本的なBP1:BP2という分け方を超えたニュアンスの違いがある。Smythiesは現象的対象(Revonsuoにとっての「局 所的統一性」)を構築することについて述べているが、デカルト、ライプニッツ、カント、ジェイムズ(Brook and Raymontを参照)[29]といった哲学者たちは一般的に現象的経験のより広範な統一性(Revonsuoにとっての「大域的統一性」)に関心を抱い てきた。さらに議論を進めると、例えば「青い四角」と「黄色い円」に分離された感覚データが、どのようにして黄色い円の隣に青い四角があり、さらにそれら の文脈の他のすべての特徴があるという単一の現象的経験に再び組み合わされるのかという、より一般的な問題に焦点を当てることになる。この「単一性」がど の程度実在するかについては様々な見解があるが、主観的に損なわれているか、少なくとも制限されているように見える医学的状態の存在は、それが完全に幻想 的なものではないことを示唆している[31]。 知覚の主観的統一性については多くの神経生物学的理論がある。色、大きさ、形、動きなどの異なる視覚的特徴は、大きく異なる神経回路によって計算される が、私たちは統合された全体を経験している。異なる視覚的特徴は、さまざまな方法で相互に作用し合う。例えば、物体の形状の識別は、方位に強く影響される が、物体の大きさにはわずかに影響される[32]。 [このことは、脳が人間を2人または2組でグループ化することに偏っていることを示唆している[36]。 歴史 初期の哲学者であるデカルトとライプニッツ[37]は、私たちの経験の見かけの単一性は、複合物質の近接性や凝集性のような既知の量的特徴に相当するもの を持たない、オール・オア・ナンの質的特徴であると指摘した。19世紀のウィリアム・ジェームズ[38]は、意識の統一性が既知の物理学によって説明され るかもしれない方法を検討し、満足のいく答えを見いださなかった。彼は「組み合わせ問題」という言葉を、物質が原子から作り上げられるように、人間の完全 な意識的経験は原始的経験や微小経験から作り上げられるという「心の塵理論」という特定の文脈の中で作り出した。ジェームズは、分散した原体験がどのよう に「結合」するのかについて因果的な物理的説明ができないため、このような理論は支離滅裂であると主張した。彼はその代わりに、「A、B、Cの経験」を組 み合わせるのではなく、「A、B、Cの経験」が1つであるという「共同意識」の概念を支持した。その後の哲学的立場については、ブルックとレイモントが詳 しく論じている(26を参照)。しかし、これらには一般的に物理学的な解釈は含まれていない。 ホワイトヘッド[39]は、統一された経験を構成する一つの出来事や「機会」において、多くの因果的要素が共同で利用可能である、あるいは「存在する」と いう、ジェイムズの共同意識の考え方に一致する関係の基本的な存在論的基礎を提唱した。ホワイトヘッドは物理学的な具体的な説明はしなかったが、物理学と 一致する局所的な相互作用における因果的な収束という観点から、共在の考えが組み立てられている。ホワイトヘッドが物理学で正式に認識されているものを超 えているのは、因果関係を複雑だが離散的な「機会」に「チャンク」している点である。たとえそのような機会が定義できたとしても、ホワイトヘッドのアプ ローチは、「共同意識」にとって神経生物学的に理にかなった因果関係の収束部位を見つけるというジェイムズの難題を残したままである。しかし、ダニエル・ デネット[40]が「デカルト劇場」と呼ぶような、デカルトが提唱したような単一の中心的な収束部位を再発明することは避けなければならないという懸念が ある。 意識的知覚と密接に関連する神経活動が大脳皮質全体に広く分布しているため、デカルトの中心的な「魂」は現在では否定されている。残された選択肢は、因果 的に収束した複数の分散した事象が別々に関与するか、現象的経験を特定の局所的な物理的事象に結びつけず、むしろ何らかの全体的な「機能的」能力に結びつ けるモデルのどちらかになるようだ。どちらの解釈をとるにせよ、Revonsuo[1]が示すように、私たちが扱っ ているのがどのような構造レベルなのか、つまり細胞レベルなのか、 「ノード」、「複合体」、「集合体」としての細胞群なのか、あるいは広く 分布したネットワークなのかについて、コンセンサスは得られてい ない。運動野や小脳に加えて)視覚野のV1領域など、特定の一次感覚野の信号が現象体験に直接寄与していないという証拠があるため、脳全体のレベルではな いということだけは、おそらく一般的な合意となっている。 結合の生物学的基盤に関する実験的研究 fMRI実験 Stollたちは、動的双安定刺激を全体的に見るか局所的に見るかを調べるためにfMRI実験を行った[33]。しかし、グローバルな知覚が形状のグルー プ化を伴わない場合、高次皮質領域の反応は抑制された。この実験は、高次皮質が知覚のグループ化において重要であることを示している。 Grassiたちは、3つの異なる運動刺激を用いて、シーンのセグメンテーション、すなわち、意味のある実体がどのようにグループ化され、シーン内の他の 実体から分離されるかを調べた[34]。すべての刺激において、シーンのセグメンテーションは、後頭頂皮質における活動の増加と、低次視覚野における活動 の減少と関連していた。このことは、後頭頂皮質が統合された全体を見るために重要であることを示唆している。 脳波研究 Mersadたちは、脳波の周波数タグ付け技術を用いて、統合された全体に対する脳活動と対象物の部分に対する脳活動とを区別した[41]。その結果、視 覚系は近接する2人の人間を統合された全体の一部として結合することが示された。これらの結果は、対面する身体は社会的相互作用の最も初期の表象の1つで あるという進化論[36]と一致する。また、身体選択的視覚野が対面する身体により強く反応するという他の実験結果[42]も支持する。 電子トンネリング 実験は、固定されたヒトの黒質(SNc)組織中のフェリチンとニューロメラニンが、広範な電子トンネリングをサポートできることを示している[43]。さ らなる実験は、SNc組織で見られるものと同様のフェリチン構造が、80ミクロンもの距離にわたって電子を伝導できること、またクーロンブロッケード理論 に従ってスイッチングまたはルーティング機能を果たすように振る舞うことを示している[44][45]。 [44] [45] これらの観察はいずれも、フェリチンとニューロメラニンが作用選択機構に関連した結合機構を提供できるという仮説の一部である、以前の予測と一致している [46]。この仮説とこれらの観察は、統合情報理論に応用されている[47]。 現代の理論 ダニエル・デネット[40]は、私たちの経験が単一の事象であるという感覚は幻想であり、その代わりに、いつでも複数の部位に感覚パターンの「複数の草 稿」が存在すると提唱している。それぞれが、私たちが経験していると思っていることの断片をカバーしているにすぎない。おそらくデネットは、意識は統一さ れておらず、現象的束縛の問題は存在しないと主張しているのだろう。ほとんどの哲学者はこの立場に難色を示している(Bayneを参照)が[30]、一部 の生理学者はこれに同意している。特に、MoutoussisとZekiによる心理物理学的実験[48][49]において、色が線の方向よりも、運動より も、それぞれ40ミリ秒と80ミリ秒先に知覚される場合に知覚の非同期性が実証されたことは、これらの非常に短い時間間隔において、異なる属性が異なる時 間に意識的に知覚されるという議論を構成し、少なくとも視覚刺激後のこれらの短い時間間隔においては、異なる事象は互いに束縛されず、意識の不統一性とい う見解につながる[50]。デネットの見解は、想起実験や変化盲から得られた証拠と一致するかもしれず、私たちの経験は、私たちが感じているよりもはるか に豊かではないことを示すものであり、グランド・イリュージョン(大いなる錯覚)と呼ばれているものである。さらに、同じく想起実験に基づいて、 Lamme[52]は、豊かさが幻想であるという考え方に異議を唱え、現象的な内容は認知的なアクセスがある内容と同一視することはできないと強調してい る。 デネットは下書きを生物物理学的事象と結びつけてはいない。因果的収束の複数の部位は、Edwards[53]やSevush[54]によって具体的な生 物物理学的用語で呼び出されている。この見解では、現象的経験において組み合わされるべき感覚信号は、複数の部位のそれぞれで完全に利用可能である。非因 果的な結合を避けるために、各部位/事象は個々のニューロン樹状突起ツリー内に配置される。この利点は、神経解剖学的に収束が起こる場所だけで、「コンプ レゼンス」が発動されることである。デメリットは、デネットと同様、経験の複数の「コピー」という直感に反する概念である。また、たとえ局所的であって も、経験的な出来事や「機会」の正確な性質は不確かなままである。 現象的経験の統一された豊かさに関する理論的枠組みの大部分は、経験が単一 のコピーとして存在するという直観的な考えに固執し、細胞の分散したネットワークの「機 能的」記述を利用している。Baars[55]は、われわれが経験することを符号化するある種の信号が「グ ローバル・ワークスペース」に入り、その中で大脳皮質の多くの部位に「ブ ロード」されて並列処理されることを示唆している。Dehaene、Changeuxら[56]は、このようなワークスペースの詳細な神経解剖学的バー ジョンを開発した。Tononiら[57]は、経験の豊かさのレベルは、統合された機能単位として機能する最大のサブネットワークまたは「複合体」におけ る最も狭い情報インターフェースの「ボトルネック」によって決定されることを示唆している。Lamme[52]は、単にフィードフォワードシグナリングに 関与するネットワークではなく、相互シグナル伝達をサポートするネットワークが経験をサポートすることを示唆している。Cleeremans[59]は、 意識に寄与する信号の機能的特徴としてメタ表象を強調している。 一般的に、このようなネットワークに基づく理論は、意識がどのように統一されるか、あるいは「束縛」されるかについての明確な理論ではなく、むしろ信号が 統一された意識体験に寄与する機能領域についての理論である。機能領域に関する懸念は、ローゼンバーグ[60]が境界問題と呼んでいるもので、何が含ま れ、何が除外されるのかについて独自の説明を見つけるのは難しい。とはいえ、これはどちらかといえば、コンセンサス・アプローチである。 ネットワークの文脈では、計算上の問題と同様に、現象的な束縛の問題に対する解決策として、同期の役割が提唱されてきた。彼の著書『驚異の仮説』[61] の中で、クリックはBP1と同様にBP2に対しても解決策を提示しているように見える。フォン・デア・マルスブルグ[62]も、「心理的瞬間」についての 発言とともに、対象特徴の束縛に関する詳細な計算論的議論を紹介している。Singerグループ[63]もまた、計算論的分離と同様に、現象認識における 同期の役割に興味を持っているように見える。 分離と統一の両方に同期を使用することの明らかな非互換性は、連続的な役割によって説明されるかもしれない。しかしながら、Merker[20]は、知覚 の主観的な統一性を、局所的な生物物理学的領域ではなく、機能的(事実上、計算論的という意味)領域の観点から解決しようとする試みの矛盾と思われる点 を、同期の文脈で指摘している。 実際、同期の役割に関する機能的な議論は、局所的な生物物理学的事象の分析に支えられている。しかしMerker[20]は、説明的な仕事はシナプス後 ニューロンにおける同期信号の下流での統合によって行われると指摘している: しかし、"同期による束縛 "によって理解されることは、軸索が単一の樹状突起に収束する部位で、そしてその部位でのみ、同期によってもたらされる閾値の優位性以外には、決して明確 ではない。言い換えれば、同期性は収束性ではなく分散性の結合を説明する方法として提案されているが、その正当性は収束時に何が起こるかにかかっている。 同期が下流の収束的相互作用に影響を与えるため、2つの特徴のシグナルは同期によって束縛されると提案されている。この種の計算機能に基づく現象的束縛の 理論も、同じ原理に従うと思われる。計算機能がそうであれば、現象性は収束を伴うだろう。 引用したモデルの多くに見られる仮定は、少なくとも一連の出来事のある時点では、計算上の出来事と現象上の出来事が何らかの形で並行していることを示唆し ている。その方法が何であるかを特定することに困難が残る。Merker[20]の分析によると、(1)結合の計算的側面と現象的側面の両方が、ニューロ ン樹状突起ツリー上の信号の収束によって決定されるか、あるいは(2)計算的文脈と現象的文脈の両方において「つなぎ止める」という意味での「結合」が必 要であるという私たちの直感的な考えが誤っていることが示唆される。私たちは、必要のない余計なものを探しているのかもしれない。例えばマーカーは、感覚 経路のホモトピック結合が必要な働きをすると主張している。 |
| Cognitive science and binding In modern connectionism cognitive neuroarchitectures are developed (e.g. "Oscillatory Networks",[64] "Integrated Connectionist/Symbolic (ICS) Cognitive Architecture",[65] "Holographic Reduced Representations (HRRs)",[66] "Neural Engineering Framework (NEF)"[67]) that solve the binding problem by means of integrative synchronization mechanisms (e.g. the (phase-)synchronized "Binding-by-synchrony (BBS)" mechanism) (1) in perceptual cognition ("low-level cognition"): This is the neurocognitive performance of how an object or event that is perceived (e.g., a visual object) is dynamically "bound together" from its properties (e.g., shape, contour, texture, color, direction of motion) as a mental representation, i.e., can be experienced in the mind as a unified "Gestalt" in terms of Gestalt psychology ("feature binding", feature linking"), (2) and in language cognition ("high-level cognition"): This is the neurocognitive performance of how a linguistic unit (e.g. a sentence) is generated by relating semantic concepts and syntactic roles to each other in a dynamic way so that one can generate systematic and compositional symbol structures and propositions that are experienced as complex mental representations in the mind ("variable binding").[68][69][70][71] |
認知科学と結合 現代のコネクショニズム認知ニューロアーキテクチャ(「オシ ラトリーネットワーク」[64]、「統合コネクショニスト/シンボリック(ICS)認知アーキテ クチャ」[65]、「ホログラフィック縮小表現(HRR)」[66]、「ニューラル・エ ンジニアリング・フレームワーク(NEF)」[67]など)は、統合的同期メカニズ ム(例えば(位相)同期化された「バインディング・バイ・シンクロニー(BBS)」 メカニズム)によって結合問題を解決するように開発されている。 (1)知覚認知(「低次認知」)における(位相)同期化された「同期による束縛(Binding-by-synchrony:BBS)」メカニズムなど) (67]: これは、知覚される物体や事象(例えば、視覚的物体)が、その特性(例えば、形状、輪郭、質感、色彩、運動方向)から心的表象としてどのように動的に「結 合」されるのか、すなわち、ゲシュタルト心理学でいう統一的な「ゲシュタルト」として心の中で体験されうるのか(「特徴結合」、「特徴連結」)についての 神経認知的パフォーマンスであり、(2)言語認知(「高次認知」)におけるものである: これは、言語単位(例えば文)が、意味概念と統語的役割を互いにダイナミックに関連づけることによって、どのように生成され、心の中で複雑な心的表象とし て経験される体系的で構成的な記号構造や命題を生成することができるかという神経認知的パフォーマンスである(「変数結合」)[68][69][70] [71]。 |
| Shared intentionality and binding According to Igor Val Danilov,[72] knowledge about neurophysiological processes during Shared intentionality can reveal insights into the binding problem and even the perception of object development since intentionality succeeds before organisms confront the binding problem. Indeed, at the beginning of life, the environment is the cacophony of stimuli: electromagnetic waves, chemical interactions, and pressure fluctuations. Because the environment is uncategorised for the organisms at this beginning stage of development, the sensation is too limited by the noise to solve the cue problem–relevant stimulus cannot overcome the noise magnitude if it passes through the senses. While very young organisms need to combine objects, background and abstract or emotional features into a single experience for building the representation of the surrounded reality, they cannot distinguish relevant sensory stimuli independently to integrate them into object representations. Even the embodied dynamical system approach cannot get around the cue to noise problem. The application of embodied information requires an already categorised environment onto objects–holistic representation of reality–which occurs through (and only after the emergence of) perception and intentionality.[73][74] |
共有された意図性と束縛 イゴール・ヴァル・ダニロフによれば[72]、共有された意図性の間の神経生理学的プロセスに関する知識は、生物が束縛の問題に直面する前に意図性が成功 することから、束縛の問題、さらには対象発生の知覚に関する洞察を明らかにすることができる。実際、生命の初期には、環境は電磁波、化学的相互作用、圧力 変動といった刺激の不協和音である。この初期段階の生物にとって環境は未分類であるため、感覚はノイズによって制限され、手がかりの問題を解決することが できない。つまり、関連する刺激が感覚を通過すると、ノイズの大きさに打ち勝つことができないのである。幼少期の生物は、物体、背景、抽象的または感情的 な特徴を組み合わせて、周囲にある現実の表現を構築する必要があるが、関連する感覚刺激を単独で区別して物体表現に統合することはできない。具現化された 力学的システムによるアプローチでさえ、ノイズに対する手がかりの問題を回避することはできない。具現化された情報の適用には、知覚と意図性によって(そ して、知覚と意図性の出現の後にのみ)生じる、すでに対象へと分類された環境-現実の全体論的表現-が必要である[73][74]。 |
| Artificial Intelligence Frame problem Hard problem of consciousness Neural coding Philosophy of perception Symbol grounding Vertiginous question |
人工知能 フレーム問題 意識のハードプロブレム 神経コーディング 知覚の哲学 シンボルグラウンディング 垂直問題 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Binding_problem |
|
| In artificial intelligence, with
implications for cognitive science, the frame problem describes an
issue with using first-order logic to express facts about a robot in
the world. Representing the state of a robot with traditional
first-order logic requires the use of many axioms that simply imply
that things in the environment do not change arbitrarily. For example,
Hayes describes a "block world" with rules about stacking blocks
together. In a first-order logic system, additional axioms are required
to make inferences about the environment (for example, that a block
cannot change position unless it is physically moved). The frame
problem is the problem of finding adequate collections of axioms for a
viable description of a robot environment.[1] John McCarthy and Patrick J. Hayes defined this problem in their 1969 article, Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence. In this paper, and many that came after, the formal mathematical problem was a starting point for more general discussions of the difficulty of knowledge representation for artificial intelligence. Issues such as how to provide rational default assumptions and what humans consider common sense in a virtual environment.[2] In philosophy, the frame problem became more broadly construed in connection with the problem of limiting the beliefs that have to be updated in response to actions. In the logical context, actions are typically specified by what they change, with the implicit assumption that everything else (the frame) remains unchanged. https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_problem |
フレーム問題とは、認知科学にも影響を与える人工知能において、世界に
おけるロボットに関する事実を表現するために一階論理を使用する際の問題を表す。伝統的な一階論理でロボットの状態を表現するには、単に環境内の物事が任
意に変化しないことを意味する多くの公理を使用する必要がある。例えば、Hayesはブロックを積み重ねるルールで「ブロックの世界」を表現している。一
階論理システムでは、環境に関する推論を行うために、さらなる公理が必要となる(例えば、ブロックは物理的に動かさない限り位置を変えることはできないな
ど)。フレーム問題とは、ロボット環境の実行可能な記述のための適切な公理のコレクションを見つける問題である[1]。 ジョン・マッカーシーとパトリック・J・ヘイズは、1969年の論文「人工知能の立場から見たいくつかの哲学的問題」でこの問題を定義した。この論文や、 それ以降に発表された多くの論文において、形式数学的問題は、人工知能の知識表現の難しさについてのより一般的な議論の出発点となった。仮想環境におい て、いかに合理的なデフォルトの仮定を提供するか、人間が常識と考えるものを提供するかといった問題である[2]。 哲学では、フレーム問題は、行動に応じて更新されなければならない信念を制限する問題に関連して、より広く解釈されるようになった。論理的な文脈では、行 動は通常、何を変化させるかによって特定され、それ以外のすべて(フレーム)は変化しないという暗黙の前提がある。 |
| ★意識のハード・プロブレムとは、人間がなぜ、そしてどのようにクオリ
ア、すなわち現象体験を持つのかを説明する問題であるが、人間や他の動物に識別能力や情報統合能力などを与えている物理システムを説明するという
「イージーな問題=イージー・プロブレム」とは対照的である。哲学者のデービッド・チャルマーズは、脳や経験に関するこのような問題をすべて解決しても、
なお「難しい問題=ハード・プロブレム」が残 ると書いている。【右の図】The hard problem is often
illustrated by appealing to the logical possibility of inverted visible
spectra. Since there is no logical contradiction in supposing that
one's colour vision could be inverted, it seems that mechanistic
explanations of visual processing do not determine facts about what it
is like to see colours.
このハード・プロブレムは、可視スペクトルの反転の論理的可能性に訴えることでしばしば説明される。色覚が反転していると仮定することに論理的矛盾はない
ので、視覚処理の機械論的説明は、色の見え方に関する事実を決定しないように思われる。(→赤をみ
る:意識のハード・プロブレム) |
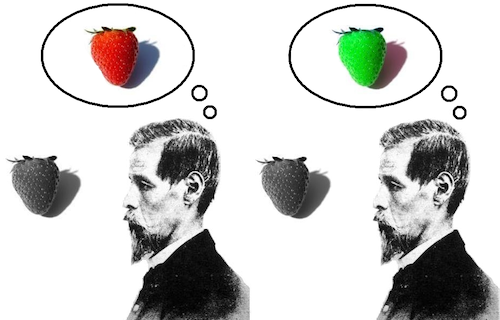 |
★
| 現象学の根本問題 /
M.ミュラー [ほか著] ; 新田義弘, 小川侃編, 晃洋書房 , 1978 . - (現代哲学の根本問題, 8) "Einige Reflexionen über den geschichtlichen Ort der Phänomenologie"ほか各論文の翻訳 |
|
| 現象学の歴史的位置 / マックス・ミュラー [著] ;
池上哲司, 宮原勇訳 フッサールの現象学における操作的概念 / オイゲン・フィンク [著] ; 新田義弘訳 世界関係と存在理解 / オイゲン・フィンク [著] ; 新田義弘訳 フッサールの構成論についての反省 / ルートヴィッヒ・ラントグレーベ [著] ; 小川侃訳 フッサールの〈生活世界〉概念に含まれる二義性 / ウルリッヒ・クレスゲス [著] ; 鷲田清一, 魚住洋一訳 〈生き生きとした現在〉の謎 / クラウス・ヘルト [著] ; 小川侃訳 超越論的現象学的理性主義 / アントニオ・アグィーレ [著] ; 新田義弘訳 事実性と個体化 / ルートヴィッヒ・ラントグレーベ [著] ; 瀬島豊, 常俊宗三郎, 魚住洋一訳 地平・世界・歴史 : コミュニケーションの下部構造 / ゲルト・ブラント [著] ; 小川侃訳 他者 : フッサールの相互主観性理論のめざすもの / ミヒャエル・トイニッセン [著] ; 鷲田清一訳 閉じられた本質認識と開かれた経験 / ベルンハルト・ワルデンフェルス [著] ; 鷲田清一訳 今日の現象学 / ハインリッヒ・ロムバッハ [著] ; 魚住洋一, 渡部菊郎訳 現象学と解釈学 / ポール・リクール [著] ; 水野和久訳 身体の状態感と感情 / ヘルマン・シュミッツ [著] ; 竹市明弘, 小川侃訳 |
|
| https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN00452008 |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆