
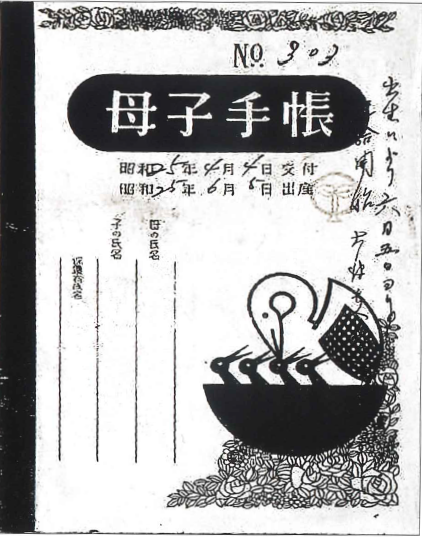
瀬木三雄と母子健康手帳
Mitsuo SEGI (1908-1982)
and Maternal and Child Health Handbook

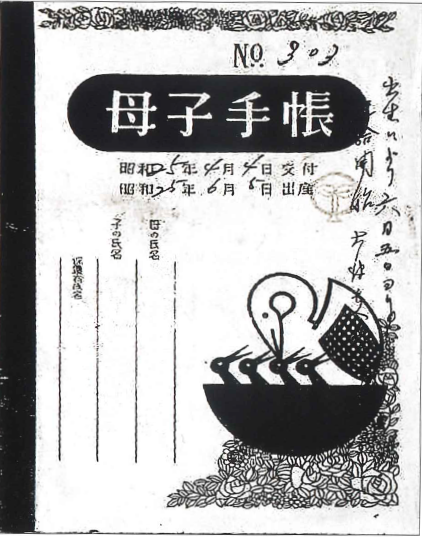
瀬木三雄は1942年妊産婦手帳(現在の母子健康手帳)を創案する(愛知みずほ短期大学HPより)
☆瀬木 三雄(せぎ みつお、1908年3月3日 - 1982年5月8日)は、日本の医学博士。愛知県名古屋市生まれ。旧制愛知県立第五中学校(現・愛知県立瑞陵高等学校)第14回生。東京帝国大学医学部卒業。旧厚生省の初代母子衛生課長として母子 健康手帳を創設し[1]、東北大学医学部にて公衆衛生学教室を主宰[2]。癌統計学の第一人者として知られ、いわゆる「瀬木の帽子」(胎児の基底顆粒細胞 集団)の発見者でもある。1971年に退官。瀬木学園(現 愛知みずほ大学等)理事長、学長、高校長を歴任。
年譜
1960年頃の母子手帳交付
太
平洋戦争直前の日本では、1937年(昭和12年)に保健所法(現在の地域保健法)が施行され、妊産婦と乳幼児の保健指導が保健所の職務とされた。これは
1941年(昭和16年)の人口政策確立要綱[7]で見られる「1夫妻5児」「産めよ殖やせよ」のような、戦時体制下に日本軍の徴兵制度による、極端な人
口増加施策の一環であった。こうした結果、目的や結果はともかく、出産〜保育の環境が著しく急速に整備された。ジョイセフはこの政策を「歴史的に見て、個
人の権利を侵害する決定」と評価している[8]。
1942年(昭和17年)、妊産婦の健康管理を目的とし、国による妊産婦手帳制度が発足。戦時下においても、物資の優先配給が保証されるとともに、定期的
な医師の診察を促すことを目的とした。また国民体力法に基づき、子どもの健康管理を目的とする乳幼児体力手帳が発行された。
1948年(昭和23年) - 児童福祉法施行。妊産婦手帳と乳幼児体力手帳を統合し母子手帳と改められた。5月12日から厚生省が配布開始[9]。
1961年(昭和36年) - 琉球政府によりアメリカ合衆国統治下の沖縄において母子手帳の交付が開始される[10]。
1966年(昭和41年)1月 - 母子保健法施行。児童福祉法等の諸法令に基づく母子保健規定を統合し、名称も母子健康手帳と改められた。
1981年(昭和56年) - 母子保健法の改正に伴い、母親が成長記録が書き込める方式へ変更された。
1992年(平成4年)4月 - 母子保健法の改正によって、都道府県交付から市町村交付へと変更された[11]。
+++
| 瀬木 三雄(せぎ みつお、1908年3月3日 - 1982年5月8日)は、日本の医学博士。 愛知県名古屋市生まれ。旧制愛知県立第五中学校(現・愛知県立瑞陵高等学校)第14回生。東京帝国大学医学部卒業。旧厚生省の初代母子衛生課長として母子 健康手帳を創設し[1]、東北大学医学部にて公衆衛生学教室を主宰[2]。癌統計学の第一人者として知られ、いわゆる「瀬木の帽子」(胎児の基底顆粒細胞 集団)の発見者でもある。1971年に退官。瀬木学園(現 愛知みずほ大学等)理事長、学長、高校長を歴任。 |
・三雄は、1939年9月の第二次大戦の直前(1938年-1939)に、文部省在外研究員としてドイツに赴任している(瀬木 1944:11) ・1939年8月「ヒトラーは医師と助産婦に対する内務省令を発し、「障害者と障害新生児」を保健局 に届けることを義務化し、身体障害児の安楽死計画が開始する」(出典:ローゼ=ヴェヒトラーとT4計画) |
| 1.^
巷野悟郎、福島正美 (1999年). “母子健康手帳の変遷に対する歴史的レビュー” (PDF).
平成11年度厚生科学研究(子ども家庭総合研究事業)「母子健康手帳の評価とさらなる活用に関する研究」. 厚生労働省. pp. 1,11.
2011年10月23日閲覧。 2.^ 東北大学医学部公衆衛生学講座. “東北大学医学部公衆衛生学教室の歴史”. 東北大学. 2011年10月23日閲覧。 |
|
| https://x.gd/S1YOa |
|
| A Maternal and Child Health Handbook
(母子健康手帳, boshi kenkō techō) is a handbook issued by Japanese
municipalities as stipulated by the Maternal and Child Health
Act[1][circular reference] to record the health conditions of mothers
and children throughout pregnancy, childbirth, and childcare. It also
serves as a primary resource book of health guidance for expectant and
nursing mothers[2] and infants, as well as a child-rearing textbook for
parents of infants and toddlers. The first half of the handbook
includes a section for recording pregnancy and childbirth, and for a
newborn baby, there is a section for periodic health examinations,
immunizations (diphtheria, pertussis, tetanus, polio, measles, etc.),
and dental examinations until the child enters elementary school. The
latter half is designed by each municipality, taking advantage of the
regional characteristics.[3] |
母
子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)は、母子保健法[1][回覧参照]の規定に基づき、市町村が発行する手帳で、妊娠、出産、育児における母子(母子)の
健康状態を記録するためのもの。また、妊婦や授乳中の母親[2]、乳幼児のための保健指導の主要な参考書、および乳幼児の親のための育児の教科書としても
機能している。手帳の前半には、妊娠・出産に関する記録欄があり、新生児については、定期健康診断、予防接種(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、麻疹
など)、歯科検診の欄があり、子供が小学校に入学するまで記入する。後半は、各自治体が地域の特性に応じて作成している[3]。 |
| Overview Those who become pregnant must promptly notify the head of the municipality of their pregnancy (Maternal and Child Health Act, Article 15), and upon receipt of the notification, the municipality shall issue them a Maternal and Child Health Handbook (Maternal and Child Health Act, Article 16, Clause 1).[4] The handbook can be issued regardless of nationality or age. The following information must be included in the notification of pregnancy (Enforcement Regulations of the Maternal and Child Health Act, Article 3). Notification date Name, age, My Number (the Japanese social security number), and occupation Place of residence Months of pregnancy Name of physician or midwife, if any, who has provided diagnosis or health guidance Whether or not the applicant has undergone medical examinations for sexually transmitted diseases and tuberculosis The Maternal and Child Health Handbook shall have a page indicating the following (Maternal and Child Health Act, Article 16, Clause 3 and Enforcement Regulations of the Maternal and Child Health Act, Article 7). Guidelines for the health management of expectant and nursing mothers, such as everyday precautions, recommendations for physical examinations, nutritional intake methods, and dental hygiene. Information necessary for the care of infants and toddlers, such as childcare precautions, disease prevention, nutritional intake methods, and dental hygiene. Details on vaccinations, including types of vaccinations, dates and precautions for inoculation. Information that contributes to the improvement of maternal and child health care, including an overview of the maternal and child health care system and the Children’s Charter. Matters to note when using the Maternal and Child Health Handbook, such as procedures for its re-issuance. In addition, each municipality may include its unique content,[5] and there is also a section for the mothers to record the growth of their children. Moreover, municipalities with particularly large foreign resident populations — such as Kawasaki City and Yokohama City in Kanagawa Prefecture and Hamamatsu City in Shizuoka Prefecture — have created their own Maternal and Child Health Handbooks written in languages other than Japanese.[6][7][8] Pregnant women and nursing mothers must have the necessary information written in the Maternal and Child Health Handbook each time they receive medical examinations or health guidance from a doctor, dentist, midwife, or public health nurse. The same shall apply to guardians of infants or young children who have received health examinations or health guidance (Maternal and Child Health Act, Article 16, Clause 2 ). When the child enters or enrolls in a kindergarten, nursery school, or elementary school, confirmation for the recorded information may be requested. Some organizations have published booklets accompanying the Maternal and Child Health Handbook, which are also employed by local governments.[9] Known examples include Little Baby Handbook for children born weighing less than 1500 grams (3.3 pounds),[10] Twins Handbook for children born of multiple births,[11] and +Happy Seeds of Happiness for children with Down syndrome.[12] Even if it is no longer needed, it is advised to keep the Maternal and Child Health Handbook, because it will be useful in confirming vaccination history and underlying health conditions as an adult.[13] |
概要 妊娠した者は、速やかにその旨を市町村の長に届け出なければならず(母子保健法第15条)、届出を受理した市町村は、母子健康手帳を交付しなければならない(母子保健法第16条第1項)[4] 。 妊娠の届出には、次の事項を記載しなければならない(母子保健法施行規則第3条)。 届出年月日 氏名、年齢、マイナンバー(日本の社会保障番号)、職業 居住地 妊娠月数 診断または保健指導を行った医師または助産師がいる場合はその氏名 性感染症、結核の健康診断の有無 母子健康手帳には、次の事項を記載するページを設ける(母子保健法第16条第3項、母子保健法施行規則第7条)。 妊産婦の保健管理に関する指針(日常の注意事項、健康診断の推奨、栄養摂取方法、歯科衛生など)。 乳幼児の保育上の注意、疾病予防、栄養摂取方法、歯科衛生など、乳幼児の保育に必要な情報。 予防接種の種類、接種日、接種の注意点など、予防接種に関する内容。 母子保健制度の概要や児童憲章など、母子保健の向上に資する情報。 母子健康手帳の再発行手続きなど、母子健康手帳を利用する際の留意事項。 また、各自治体独自の内容を盛り込むことができ[5]、母親が子どもの成長を記録する欄もある。さらに、神奈川県川崎市や横浜市、静岡県浜松市など、特に外国人住民の多い自治体では、日本語以外の言語で書かれた独自の母子健康手帳が作成されている[6][7][8]。 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師、保健師等から診察や保健指導を受ける都度、母子健康手帳に必要事項を記載しなければならない。保健指導を受けた乳幼児 の保護者も同様である(母子保健法第16条第2項)。幼稚園、保育所、小学校に入園・入学する際には、記録内容の確認を求められることがある。 母子健康手帳に付属する冊子を発行している団体もあり、自治体でも採用されている[9]。 よく知られている例としては、1500グラム未満で生まれた子どものための「小さな赤ちゃん手帳」[10]、多胎児のための「双子手帳」[11]、ダウン 症児のための「+しあわせのたね」[12]などがある。 母子健康手帳は、たとえ不要になったとしても、大人になってからの予防接種歴や基礎疾患の確認に役立つので、保管しておくことを勧められる[13]。 |
| Spread to the world The Maternal and Child Health Handbook was originally developed in Japan. However, in the 1980s, an Indonesian doctor who was visiting Japan through a training program of the semi-governmental corporation of Japan International Cooperation Agency (JICA) noticed its effectiveness in contributing to the health of mothers and children and decided to promote it in his own country.[14] With the help of the JICA, Indonesia began distributing the handbooks on a trial basis in 1989.[15] Recognizing its effectiveness, the Japanese government also began to support the project, and since 1998, it has been promoted as the “Mother and Child Health Handbook Project.”[16] The Indonesian version of the Maternal and Child Health Handbook is larger (A5 notebook size, about 5-7/8 x 8-1/4 in) than the Japanese handbook. It is designed to be understandable to even illiterate mothers by using abundant illustrations.[13] It is also expected to be used as a simplified childcare book. Since 2007, Indonesia has been helping to spread the project in Palestine and Afghanistan.[14] The success in Indonesia has led the Japan International Cooperation Agency to provide training guidance to promote awareness of the handbook in South America and Africa.[17] |
世界に広がる 母子健康手帳はもともと日本で開発された。しかし1980年代、国際協力機構(JICA)の研修プログラムで来日したインドネシア人医師が、母子の健康に 貢献するその有効性に着目し、自国で普及させることを決意した[14]。[その有効性を認めた日本政府も支援を開始し、1998年からは「母子健康手帳プ ロジェクト」として推進されている[16]。イラストを多用することで、読み書きのできない母親でも理解できるように工夫されている[13]。簡易育児書 としての活用も期待されている。 2007年からは、インドネシアがパレスチナやアフガニスタンでの普及に協力している[14]。インドネシアでの成功を受けて、国際協力機構が南米やアフリカでのハンドブックの普及のための研修指導を行っている[17]。 |
| 1. "母子保健法" [Maternal Health Act]. Retrieved October 30, 2022. 2. “Pregnant and nursing mothers” refers to women who are pregnant or are within one year after giving birth. "Maternal and Child Health Act, Article 6, Clause 1". Retrieved October 30, 2022. 3. Yatagai, Masaaki; Hayashi, Kunio (2006). Dictionary of Childcare Terms. Tokyo: Ichigeisha. p. 350. 4. Nakamura, Yasuhide (January–February 2014). "Maternal and Child Health". Japan Medical Association Journal. 57 (1): 19–23. PMC 4130095. PMID 25237272. 5. Nakamura, Yasuhide (July–August 2010). "Maternal and Child Health Handbook in Japan" (PDF). Japan Medical Association Journal. 53 (4): 261 – via Japan Medical Association. 6. "How can I receive the Mother and Child Health Handbook ("boshi kenko techo")?". Kawasaki City. March 13, 2020. Retrieved November 1, 2022. 7 "Issuance of the Maternal and Child Health Handbook". City of Yokohama. October 24, 2022. Retrieved November 1, 2022. 8. "Maternal and Child Health Handbook". Canal Hamamatsu. July 19, 2022. Retrieved November 1, 2022. 9. "戦時中に誕生の母子手帳、妊娠や出産・子どもの成長支え健やかに進化". Yomiuri Shimbun Online. 2022-05-15. 10. "リトルベビーハンドブック" [Little Baby Handbook]. Specified Nonprofit Corporation HANDS. 6 January 2022. Retrieved October 30, 2022. 11. "ふたご手帖プロジェクト" [Twins Handbook Project]. Japanese Society of Child Health. 12. "子育て手帳 +Happy しあわせのたね" [Childcare Handbook +Happy Seeds of Happiness]. Japan Down Syndrome Association. 9 December 2020. 13. Takeuchi, Jiro; Sakagami, Yu; Perez, Romana C. (May 18, 2016). "The Mother and Child Health Handbook in Japan as a Health Promotional Tool: An Overview of Its History, Contents, Use, Benefits, and Global Influence". Global Pediatric Health. 3: 2333794X1664988. doi:10.1177/2333794X16649884. PMC 4905145. PMID 27336022. 14. "「母子手帳」世界の動き−第10回母子手帳国際会議に寄せて(2016年11月23日〜25日:東京)" [Maternal and Child Health Handbook. The 10th international Conference on Maternal and Child Health Handbook (November 23–25, 2016 : Tokyo, Japan).]. Japan International Cooperation Agency. Retrieved October 30, 2022. 15. "Chapter 2: Details about Japan's ODA". Japan's ODA White Paper 2003. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2003. Retrieved November 1, 2022. 16. "インドネシアにおける母子健康手帳の展開と日本の協力実績". Japan International Cooperation Agency. Retrieved October 30, 2022. 17. "Knowledge Sharing Program on Maternal and Child Health Handbook 2022 7-9 September 2022 in Bogor, Indonesia". Japan International Cooperation Agency. September 9, 2022. Retrieved November 1, 2022. |
|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Maternal_and_Child_Health_Handbook |
|
| 母子健康手帳(ぼ
しけんこうてちょう)とは、母子保健法第16条に基づき市町村が妊娠の届出を行った妊婦に交付する手帳のことで、妊娠中の母体や出生後の子どもの健康管理
について記録する。一般に母子手帳の名でも知られる。自治体によっては親子手帳、親子健康手帳の名称を用いるところもある[1]。 妊産婦[注 1]や乳幼児の保健指導の基礎資料となると同時に、乳幼児の保護者に対する育児書の役割も果たしている。手帳の様式の前半部分は妊娠、出産までの記録、出 生した子どもについては小学校入学までの定期健康審査、予防接種(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、麻疹など)、歯の検査などの記録欄がある。後半部 分は、各市町村の地域特性を生かした内容で作られている[2]。 |
|
| 概要 妊娠した者は速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならず(母子保健法第15条)、市町村は届出を受けて母子健康手帳をその者に交付する (母子保健法第16条1項)[注 2]。国籍や年齢に関わらず交付を受けることができる。妊娠の届出には以下の事項を記載しなければならない(母子保健法施行規則第3条)。 届出年月日 氏名、年齢、個人番号及び職業 居住地 妊娠月数 医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名 性病及び結核に関する健康診断の有無 母子健康手帳の様式は、以下の事項を示した面を設けるものとする(母子保健法第16条3項、母子保健法施行規則第7条)。このほかに、市町村ごとに独自の 面を設けることもでき[注 3][注 4]、母親自身が子供の成長記録を記載する欄もある。また、特に外国人の居住人口が多い市区町村、例えば神奈川県川崎市や横浜市、静岡県浜松市など、独自 に日本語以外の言語で書かれた母子健康手帳が作成されている。 様式第三号に定める面[3] 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨、栄養の摂取方法、歯科衛生等妊産婦の健康管理に当たり必要な情報 育児上の注意、疾病予防、栄養の摂取方法、歯科衛生等乳幼児の養育に当たり必要な情報 予防接種の種類、接種時期、接種に当たっての注意等、ワクチン予防接種に関する情報 母子保健に関する制度の概要、児童憲章等母子保健の向上に資する情報 母子健康手帳の再交付に関する手続等母子健康手帳を使用するに当たっての留意事項 妊産婦は、医師・歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければな らない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする(母子保健法第16条2項)。幼稚園や保育園、小学 校等に入園・入学する際に記載事項の確認を求められることがある。 当事者活動の成果として、母子手帳と一緒に使える小冊子を発行する団体もあり、各自治体でも運用されている[1]。体重1500グラム未満で生まれた子ど ものための「リトルベビーハンドブック」[4]、多胎児のための「ふたご手帖」[5]、ダウン症の子どものための「+Happyしあわせのたね」[6]な どが知られている。 また、不要になったとしても捨てることなく、成人になったときにワクチン接種歴や基礎疾患などの確認を求められた際、その確認に役立つので、母子手帳を保管しておくのが望ましい。 |
|
| 歴史(再掲) 1960年頃の母子手帳交付 太平洋戦争直前の日本では、1937年(昭和12年)に保健所法(現在の地域保健法)が施行され、妊産婦と乳幼児の保健指導が保健所の職務とされた。これ は1941年(昭和16年)の人口政策確立要綱[7]で見られる「1夫妻5児」「産めよ殖やせよ」のような、戦時体制下に日本軍の徴兵制度による、極端な 人口増加施策の一環であった。こうした結果、目的や結果はともかく、出産〜保育の環境が著しく急速に整備された。ジョイセフはこの政策を「歴史的に見て、 個人の権利を侵害する決定」と評価している[8]。 1942年(昭和17年)、妊産婦の健康管理を目的とし、国による妊産婦手帳制度が発足。戦時下においても、物資の優先配給が保証されるとともに、定期的 な医師の診察を促すことを目的とした。また国民体力法に基づき、子どもの健康管理を目的とする乳幼児体力手帳が発行された。 1948年(昭和23年) - 児童福祉法施行。妊産婦手帳と乳幼児体力手帳を統合し母子手帳と改められた。5月12日から厚生省が配布開始[9]。 1961年(昭和36年) - 琉球政府によりアメリカ合衆国統治下の沖縄において母子手帳の交付が開始される[10]。 1966年(昭和41年)1月 - 母子保健法施行。児童福祉法等の諸法令に基づく母子保健規定を統合し、名称も母子健康手帳と改められた。 1981年(昭和56年) - 母子保健法の改正に伴い、母親が成長記録が書き込める方式へ変更された。 1992年(平成4年)4月 - 母子保健法の改正によって、都道府県交付から市町村交付へと変更された[11]。 |
|
| 世界への普及 日本独自に発展した母子健康手帳であったが、1980年代に特殊法人国際協力事業団の研修で、日本を訪れていたインドネシア人の医師が、母子の健康に貢献する有効性に着目し、母国での普及を思い立つ[12]。 インドネシアでは国際協力事業団の働きかけにより、1989年から試験的に手帳の配布を開始。有効性を認識した日本国政府も支援に乗り出し、1998年か らは「母と子の健康手帳プロジェクト」として普及が進められた[12]。インドネシア版の母子健康手帳は、日本の手帳と比べて大型(A5ノートサイズ) で、イラストを多用するなど[12]、文盲の母親が存在したとしても理解できるように工夫されており、簡易な育児書としても活用できるよう工夫されてい る。2007年からは、インドネシアがパレスチナやアフガニスタンでの普及に協力することとなった[12]。 インドネシアでの成功により、独立行政法人国際協力機構では母子健康手帳を意識した研修指導を行うようになり、南アメリカやアフリカでの普及を進めている[12]。 |
|
| https://x.gd/UOSa2 |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099