
優生学に反対するG.K.チェスタトン
Opposition
to eugenics by G.K. Chesterton

チェ
スタトンが描く(?)優生学のイメージ
☆チェスタトンとはどんな人?→ギルバート・キース・チェスタートン
KC*SG(1874年5月29日 -
1936年6月14日)は、イギリスの作家、哲学者、キリスト教の弁証家、ジャーナリスト、雑誌編集者、文学評論家、美術評論家だった。[2]
チェスタートンは、架空の司祭探偵、ブラウン神父を創作し[3]、『正統性』や『永遠の人』などの弁証学に関する著作を残した。[4][5]
チェスタートンは自身を正統派キリスト教徒と称し、この立場を次第にカトリック教徒と同一視するようになった。最終的に、高教会派のアングリカンから改宗
した。伝記作家たちは、彼をマシュー・アーノルド、トマス・カーライル、ジョン・ヘンリー・ニューマン、ジョン・ラスキンといったヴィクトリア朝時代の作
家たちの後継者と位置付けている。[6]
彼は「パラドックスの王子」とも呼ばれている。[7]
彼の文章スタイルについて、『タイム』誌は「チェスタートンは、可能な限り、ことわざ、格言、寓話を使って自分の主張を表現し、まずそれらを注意深く裏返
しにした」と評している。[4] 彼の著作は、エドガー・アラン・ポーの作品と比較したホルヘ・ルイス・ボルヘスにも影響を与えた。[8]
★『部族の真実』の中でチェスタートンはドイツの人種論を非難し、こう書いている。「ナ チスのナショナリズムの本質は、すべての人種が不純である大陸において、ある人種の純粋性を維持することである」と書いている。
| Advocacy of
Catholicism Chesterton's The Everlasting Man contributed to C. S. Lewis's conversion to Christianity. In a letter to Sheldon Vanauken (14 December 1950),[50] Lewis called the book "the best popular apologetic I know",[51] and to Rhonda Bodle he wrote (31 December 1947)[52] "the [very] best popular defence of the full Christian position I know is G. K. Chesterton's The Everlasting Man". The book was also cited in a list of 10 books that "most shaped his vocational attitude and philosophy of life".[53] Chesterton's hymn "O God of Earth and Altar" was printed in The Commonwealth and then included in the English Hymnal in 1906.[54] Several lines of the hymn appear in the beginning of the song "Revelations" by the British heavy metal band Iron Maiden on their 1983 album Piece of Mind.[55] Lead singer Bruce Dickinson in an interview stated "I have a fondness for hymns. I love some of the ritual, the beautiful words, Jerusalem and there was another one, with words by G.K. Chesterton O God of Earth and Altar – very fire and brimstone: 'Bow down and hear our cry'. I used that for an Iron Maiden song, "Revelations". In my strange and clumsy way I was trying to say look it's all the same stuff."[56] Étienne Gilson praised Chesterton's book on St Thomas Aquinas: "I consider it as being, without possible comparison, the best book ever written on Saint Thomas ... the few readers who have spent twenty or thirty years in studying St. Thomas Aquinas, and who, perhaps, have themselves published two or three volumes on the subject, cannot fail to perceive that the so-called 'wit' of Chesterton has put their scholarship to shame."[57] Archbishop Fulton J. Sheen, the author of 70 books, identified Chesterton as the stylist who had the greatest impact on his own writing, stating in his autobiography Treasure in Clay, "the greatest influence in writing was G. K. Chesterton who never used a useless word, who saw the value of a paradox, and avoided what was trite."[58] Chesterton wrote the introduction to Sheen's book God and Intelligence in Modern Philosophy; A Critical Study in the Light of the Philosophy of Saint Thomas.[59] |
カトリシズムの擁護 チェスタトンの『永遠の人』は、C.S.ルイスのキリスト教への改宗に貢献した。1950年12月14日、シェルドン・ヴァノーケンへの手紙の中で、ルイ スはこの本を「私の知る限り最高の一般向け弁明書」と呼び[51]、ロンダ・ボドルには「私の知る限り最高のキリスト教的立場の一般向け弁明書は、G・ K・チェスタトンのThe Everlasting Man(永遠の人)」(52)だと書いている(1947年12月31日)。また、この本は「彼の職業的態度や人生哲学を最も形成した」10冊のリストにも 挙げられている[53]。 チェスタートンの賛美歌「地と祭壇の神よ」は『コモンウェルス』に掲載され、1906年には『イングリッシュ・ハイムーン』に収録された[54]。リード ボーカルのブルース・ディキンソンはインタビューの中で「私は賛美歌が好きだ」と述べた。私はいくつかの儀式、美しい言葉、エルサレムが好きで、もう一 つ、G.K.チェスタートンの言葉、O God of Earth and Altar - very fire and brimstone: 'Bow down and hear our cry'がありました。私はそれをアイアン・メイデンの曲、「Revelations」に使いました。私の奇妙で不器用なやり方で、私はそれがすべて同じ ものであるように見えると言おうとしていたのです」[56]。 エティエンヌ・ギルソンはチェスタートンの聖トマス・アクィナスに関する著書を賞賛している。私はこの本を、比較の余地なく、聖トマスについて書かれた最 高の本だと考えている...聖トマス・アクィナスの研究に20年か30年を費やし、おそらくこのテーマについて自ら2、3冊の本を出版した少数の読者は、 チェスタートンのいわゆる「機知」が、彼らの学識を恥じさせることを認識せずにはいられない」[57]。 70冊の著書を持つ大司教フルトン・J・シーンは、チェスタートンを自身の執筆に最も影響を与えた文筆家とし、自伝『クレイの宝物』の中で「執筆における 最大の影響はG・K・チェスタートンだった。彼は決して無駄口を叩かず、逆説に価値を見出し、陳腐なものを避けた」[58] チェスタートンはシーンの著書『近代哲学における神と知性;聖トマスの哲学の光の中での批判研究』に序文を執筆している[59]。 |
| Charges of antisemitism Chesterton faced accusations of antisemitism during his lifetime, saying in his 1920 book The New Jerusalem that it was something "for which my friends and I were for a long period rebuked and even reviled".[60] Despite his protestations to the contrary, the accusation continues to be repeated.[61] An early supporter of Captain Dreyfus, by 1906 he had turned into an anti-dreyfusard.[62] From the early 20th century, his fictional work included caricatures of Jews, stereotyping them as greedy, cowardly, disloyal and communists.[63] Martin Gardner suggests that Four Faultless Felons was allowed to go out of print in the United States because of the "anti-Semitism which mars so many pages."[64] The Marconi scandal of 1912–13 brought issues of anti-Semitism into the political mainstream. Senior ministers in the Liberal government had secretly profited from advance knowledge of deals regarding wireless telegraphy, and critics regarded it as relevant that some of the key players were Jewish.[65] According to historian Todd Endelman, who identified Chesterton as among the most vocal critics, "The Jew-baiting at the time of the Boer War and the Marconi scandal was linked to a broader protest, mounted in the main by the Radical wing of the Liberal Party, against the growing visibility of successful businessmen in national life and their challenge to what were seen as traditional English values."[66] In a work of 1917, titled A Short History of England, Chesterton considers the royal decree of 1290 by which Edward I expelled Jews from England, a policy that remained in place until 1655. Chesterton writes that popular perception of Jewish moneylenders could well have led Edward I's subjects to regard him as a "tender father of his people" for "breaking the rule by which the rulers had hitherto fostered their bankers' wealth". He felt that Jews, "a sensitive and highly civilized people" who "were the capitalists of the age, the men with wealth banked ready for use", might legitimately complain that "Christian kings and nobles, and even Christian popes and bishops, used for Christian purposes (such as the Crusades and the cathedrals) the money that could only be accumulated in such mountains by a usury they inconsistently denounced as unchristian; and then, when worse times came, gave up the Jew to the fury of the poor".[67][68] In The New Jerusalem Chesterton dedicated a chapter to his views on the Jewish question: the sense that Jews were a distinct people without a homeland of their own, living as foreigners in countries where they were always a minority.[69] He wrote that in the past, his position [his position] was always called Anti-Semitism; but it was always much more true to call it Zionism. ... my friends and I had in some general sense a policy in the matter; and it was in substance the desire to give Jews the dignity and status of a separate nation. We desired that in some fashion, and so far as possible, Jews should be represented by Jews, should live in a society of Jews, should be judged by Jews and ruled by Jews. I am an Anti-Semite if that is Anti-Semitism. It would seem more rational to call it Semitism.[70] |
反ユダヤ主義への非難 チェスタートンは生前、反ユダヤ主義の非難にさらされ、1920年に出版した『新しいエルサレム』で、それは「私の友人と私が長い間、叱られ、非難されさ えした」ことだと述べた[60]。 これに反する彼の抗議にもかかわらず、この非難は繰り返され続けている[61]...ドレフュス大尉を当初は支持していた彼は、1906年までにアンチ・ ドレフュスに転じている...。 [20世紀初頭から、彼のフィクション作品にはユダヤ人の風刺画が含まれ、彼らを強欲、臆病、不誠実、共産主義者とステレオタイプしていた[63]。 マーティン・ガードナーは、「多くのページを飾る反ユダヤ主義」のために、アメリカで「4人の無犯罪者」が絶版になることを許されたと示唆した[64]。 1912年から13年にかけてのマルコーニのスキャンダルは、反ユダヤ主義の問題を政治の本流に引き込んだ。自由党政権の上級大臣が無線電信に関する取引 の事前知識から密かに利益を得ており、批評家たちは主要人物がユダヤ人であったことを関係あるとみなしていた[65]。 [歴史家のトッド・エンデルマンは、チェスタートンを最も声高な批判者の一人として挙げており、「ボーア戦争とマルコーニのスキャンダルの時のユダヤ人排 斥は、国民生活における成功したビジネスマンの知名度の向上と、彼らがイギリスの伝統的価値とみなされたものに対する挑戦に対して、主に自由党の急進派が 行ったより大きな抗議と結びついていた」[66]と述べている。] 1917年の『A Short History of England』という著作の中で、チェスタートンはエドワード1世が1290年に出した勅令によってユダヤ人をイングランドから追放し、その政策が 1655年まで続いたことを考察している。チェスタートンは、ユダヤ人金貸しに対する大衆の認識が、「支配者たちがこれまで銀行家の富を育ててきたルール を破った」エドワード一世を「民衆の優しい父」と見なすことにつながった可能性があると書いている。彼は「繊細で高度に文明化した人々」であるユダヤ人は 「時代の資本家であり、富をすぐに使えるように銀行に預けている人々」であり、「キリスト教の王や貴族、さらにはキリスト教の教皇や司教が、キリスト教的 でないとして矛盾して非難した利潤によってのみそのような山に蓄えられる金を(十字軍や大聖堂のような)キリスト教の目的のために使い、さらに悪い時代が 来ると貧しい人々の怒りにユダヤ人を見放す」ことを正当化するのではないかと考えているのである[67][68]。 新エルサレム』の中でチェスタートンはユダヤ人問題に対する彼の見解に一章を捧げている。ユダヤ人は自分たちの祖国を持たず、常に少数派である国で外国人 として暮らしているという感覚である[69]。 彼は過去において、彼の立場は (彼の立場は)常に反ユダヤ主義と呼ばれていたが、シオニズムと呼ぶ方 がずっと真実だったと書いている。しかし、シオニズムと呼ぶ方がずっと正しい。...私の友人と私はこの問題に関してある一般的な意味での方針を持ってお り、それは実質的に、ユダヤ人に独立国家の尊厳と地位を与えたいという願いであった。私たちは、何らかの形で、可能な限り、ユダヤ人はユダヤ人によって代 表され、ユダヤ人の社会に住み、ユダヤ人によって裁かれ、ユダヤ人によって支配されるべきだと考えていました。それが反ユダヤ主義であるならば、私は反ユ ダヤ主義者である。セムティズムと呼ぶ方が合理的だと思われる[70]。 |
| In the same place he proposed
the thought experiment (describing it as "a parable" and "a flippant
fancy") that Jews should be admitted to any role in English public life
on condition that they must wear distinctively Middle Eastern garb,
explaining that "The point is that we should know where we are; and he
would know where he is, which is in a foreign land."[70] Chesterton, like Belloc, openly expressed his abhorrence of Hitler's rule almost as soon as it started.[71] As Rabbi Stephen Wise wrote in a posthumous tribute to Chesterton in 1937: When Hitlerism came, he was one of the first to speak out with all the directness and frankness of a great and unabashed spirit. Blessing to his memory![72] In The Truth about the Tribes Chesterton blasted German race theories, writing: "the essence of Nazi Nationalism is to preserve the purity of a race in a continent where all races are impure."[73] The historian Simon Mayers points out that Chesterton wrote in works such as The Crank, The Heresy of Race, and The Barbarian as Bore against the concept of racial superiority and critiqued pseudo-scientific race theories, saying they were akin to a new religion.[63] In The Truth About the Tribes Chesterton wrote, "the curse of race religion is that it makes each separate man the sacred image which he worships. His own bones are the sacred relics; his own blood is the blood of St. Januarius."[63] Mayers records that despite "his hostility towards Nazi antisemitism … [it is unfortunate that he made] claims that 'Hitlerism' was a form of Judaism, and that the Jews were partly responsible for race theory."[63] In The Judaism of Hitler, as well as in A Queer Choice and The Crank, Chesterton made much of the fact that the very notion of "a Chosen Race" was of Jewish origin, saying in The Crank: "If there is one outstanding quality in Hitlerism it is its Hebraism" and "the new Nordic Man has all the worst faults of the worst Jews: jealousy, greed, the mania of conspiracy, and above all, the belief in a Chosen Race."[63] |
同じ場所で彼は、ユダヤ人は中東特有の衣服を身につけることを条件にイ
ギリスの公的生活のあらゆる役割を認められるべきであるという思考実験(それを「たとえ話」と「軽薄な空想」と表現)を提案し、「ポイントは我々がどこに
いるのかを知ることであり、彼は異国の地にいることを知るだろう」と説明している[70]。 チェスタートンはベロックと同様に、ヒトラーの支配が始まるとほぼ同時にその嫌悪を公然と表明した[71]。ラビであるスティーブン・ワイズが1937年 にチェスタートンへの死後の賛辞で書いているように。 ヒトラー主義が現れたとき、彼は偉大で臆面もない精神のすべての率直さと率直さをもって最初に発言した一人であった。彼の思い出に祝福を![72]。 『部族の真実』の中でチェスタートンはドイツの人種論を非難し、こう書いている。「ナ チスのナショナリズムの本質は、すべての人種が不純である大陸において、ある人種の純粋性を維持することである」[73]と書いている。 歴史家のサイモン・メイヤーズは、チェスタートンが『クランク』、『人種の異端』、『退屈としての野蛮人』などの著作で、人種的優越性の概念に反対し、疑 似科学的人種理論を批判し、それらは新しい宗教に似ていると指摘している[63]。 『部族の真実』でチェスタートンは、「人種宗教の呪いは、それぞれが崇拝する聖像として個別の人間を作ることである」と書いている。彼自身の骨は神聖な遺 物であり、彼自身の血は聖ヤヌアリウスの血である」[63] メイヤーズは、「ナチの反ユダヤ主義に対する彼の敵意にもかかわらず...(彼が)「ヒトラー主義」はユダヤ教の一形態であり、ユダヤ人は人種論に部分的 に責任があると主張したことは不幸なことだ」と記録している[63]。 ヒトラーのユダヤ教』や『クランク』において、チェスタートンは「選ばれし民族」という概念そのものがユダヤ人由来であることを強調し、『クランク』では 「ヒトラー主義に一つの際立った性質があるとすれば、それはそのヘブラニズム」「新しい北欧人は最悪のユダヤ人の最悪の欠点をすべて持っている:嫉妬、 欲、陰謀狂、とりわけ、選ばれた民族の信仰」[63] と述べている。 |
| Mayers also shows that
Chesterton portrayed Jews not only as culturally and religiously
distinct, but racially as well. In The Feud of the Foreigner (1920) he
said that the Jew "is a foreigner far more remote from us than is a
Bavarian from a Frenchman; he is divided by the same type of division
as that between us and a Chinaman or a Hindoo. He not only is not, but
never was, of the same race."[63] In The Everlasting Man, while writing about human sacrifice, Chesterton suggested that medieval stories about Jews killing children might have resulted from a distortion of genuine cases of devil-worship. Chesterton wrote: the Hebrew prophets were perpetually protesting against the Hebrew race relapsing into an idolatry that involved such a war upon children; and it is probable enough that this abominable apostasy from the God of Israel has occasionally appeared in Israel since, in the form of what is called ritual murder; not of course by any representative of the religion of Judaism, but by individual and irresponsible diabolists who did happen to be Jews.[63][74] The American Chesterton Society has devoted a whole issue of its magazine, Gilbert, to defending Chesterton against charges of antisemitism.[75] Likewise, Ann Farmer, author of Chesterton and the Jews: Friend, Critic, Defender,[76][77] writes, "Public figures from Winston Churchill to Wells proposed remedies for the 'Jewish problem' – the seemingly endless cycle of anti-Jewish persecution – all shaped by their worldviews. As patriots, Churchill and Chesterton embraced Zionism; both were among the first to defend the Jews from Nazism," concluding that "A defender of Jews in his youth – a conciliator as well as a defender – GKC returned to the defence when the Jewish people needed it most."[78] |
またメイヤーズは、チェスタートンがユダヤ人を文化的、宗教的にだけで
なく、人種的にも区別して描いていることを明らかにしている。外国人の確執』(1920年)で彼は、ユダヤ人は「バイエルンとフランス人の間よりもはるか
に我々から遠い外国人であり、彼は我々と中国人やヒンドゥー教徒の間と同じ種類の区分によって分けられている」と述べている。彼は同じ人種でないだけでな
く、決してそうではなかった」[63]。 永遠の人』の中で、人間の生贄について書いているとき、チェスタートンは、ユダヤ人が子供を殺すという中世の話は、悪魔崇拝の本物の事例を歪曲した結果か もしれないと示唆している。チェスタートンはこう書いている。 そして、イスラエルの神からのこの忌まわしい背教が、儀式的殺人と呼ばれる形で、それ以来イスラエルに時々現れていることは十分にあり得ることである。 アメリカのチェスタートン協会は、雑誌『ギルバート』の全号を割いて、反ユダヤ主義の告発からチェスタートンを擁護している[75] 同様に、『チェスタートンとユダヤ人』の著者アン・ファーマーも、『チェスタートンとユダヤ人』の中で、チェスタートンとユダヤ人の関係について述べてい る[68]。ウィンストン・チャーチルからウェルズまでの公人は、反ユダヤ人迫害の無限とも思えるサイクルである「ユダヤ人問題」に対する解決策を提案し たが、それらはすべて彼らの世界観によって形成されたものであった。愛国者として、チャーチルとチェスタートンはシオニズムを受け入れ、両者ともナチズム からユダヤ人を最初に擁護した」と結論づけ、「若い頃はユダヤ人の擁護者-擁護者であると同時に融和者-だったGKCは、ユダヤ人が最も必要とするときに 擁護者に戻った」[78]と述べている。 |
| Opposition to eugenics In Eugenics and Other Evils, Chesterton attacked eugenics as Parliament was moving towards passage of the Mental Deficiency Act 1913. Some backing the ideas of eugenics called for the government to sterilise people deemed "mentally defective"; this view did not gain popularity but the idea of segregating them from the rest of society and thereby preventing them from reproducing did gain traction. These ideas disgusted Chesterton who wrote, "It is not only openly said, it is eagerly urged that the aim of the measure is to prevent any person whom these propagandists do not happen to think intelligent from having any wife or children."[79] He blasted the proposed wording for such measures as being so vague as to apply to anyone, including "Every tramp who is sulk, every labourer who is shy, every rustic who is eccentric, can quite easily be brought under such conditions as were designed for homicidal maniacs. That is the situation; and that is the point ... we are already under the Eugenist State; and nothing remains to us but rebellion."[79] He derided such ideas as founded on nonsense, "as if one had a right to dragoon and enslave one's fellow citizens as a kind of chemical experiment".[79] Chesterton mocked the idea that poverty was a result of bad breeding: "[it is a] strange new disposition to regard the poor as a race; as if they were a colony of Japs or Chinese coolies ... The poor are not a race or even a type. It is senseless to talk about breeding them; for they are not a breed. They are, in cold fact, what Dickens describes: 'a dustbin of individual accidents,' of damaged dignity, and often of damaged gentility."[79][80] |
優生学への反対 チェスタートンは、『優生学とその他の悪』の中で、議会が1913年の精神障害者法の成立に向けて動いているときに優生学を攻撃している。優生学に賛同す る人々の中には、政府が「精神障害者」とみなされる人々を不妊化することを求める者もいた。この考えは支持を得られなかったが、彼らを社会の他の人々から 隔離し、それによって繁殖を防ぐという考えは支持された。これらの考えはチェスタートンをうんざりさせ、「この措置の目的は、これらの宣伝家がたまたま知 的であると考えないいかなる人物も、妻や子供を持つことを防ぐことであると公然と言われているだけでなく、熱心に促されている」と書いている[79]。 「不機嫌な浮浪者も、内気な労働者も、風変わりな田舎者も、殺人狂のために作られたような条件の下に置くことは極めて容易である。それが状況であり、それ がポイントである......我々はすでに優生主義国家の下にあり、我々には反乱以外何も残っていない」[79]。「貧乏人を人種と見なすのは奇妙な新し い傾向であり、まるでジャップや中国のクーリーの植民地であるかのようだ。貧困層は人種でもなければ、タイプですらない。彼らを品種改良しようなどという のは無意味なことだ。彼らは、冷静に考えれば、ディケンズが描いたような存在なのだ。個々の事故のごみ箱」であり、傷ついた尊厳であり、しばしば傷ついた 品位なのである。 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/G._K._Chesterton#Opposition_to_eugenics |
https://www.deepl.com/ja/translator |
★
Gilbert Keith Chesterton KC*SG (29 May 1874 – 14 June 1936)
| Gilbert Keith
Chesterton KC*SG (29 May 1874 – 14 June 1936) was an English
author,
philosopher, Christian apologist, journalist and magazine editor, and
literary and art critic.[2] Chesterton created the fictional priest-detective Father Brown,[3] and wrote on apologetics, such as his works Orthodoxy and The Everlasting Man.[4][5] Chesterton routinely referred to himself as an orthodox Christian, and came to identify this position more and more with Catholicism, eventually converting from high church Anglicanism. Biographers have identified him as a successor to such Victorian authors as Matthew Arnold, Thomas Carlyle, John Henry Newman and John Ruskin.[6] He has been referred to as the "prince of paradox".[7] Of his writing style, Time observed: "Whenever possible, Chesterton made his points with popular sayings, proverbs, allegories—first carefully turning them inside out."[4] His writings were an influence on Jorge Luis Borges, who compared his work with that of Edgar Allan Poe.[8] |
ギルバート・キース・チェスタートン
KC*SG(1874年5月29日 -
1936年6月14日)は、イギリスの作家、哲学者、キリスト教の弁証家、ジャーナリスト、雑誌編集者、文学評論家、美術評論家だった。[2] チェスタートンは、架空の司祭探偵、ブラウン神父を創作し[3]、『正統性』や『永遠の人』などの弁証学に関する著作を残した。[4][5] チェスタートンは自身を正統派キリスト教徒と称し、この立場を次第にカトリック教徒と同一視するようになった。最終的に、高教会派のアングリカンから改宗 した。伝記作家たちは、彼をマシュー・アーノルド、トマス・カーライル、ジョン・ヘンリー・ニューマン、ジョン・ラスキンといったヴィクトリア朝時代の作 家たちの後継者と位置付けている。[6] 彼は「パラドックスの王子」とも呼ばれている。[7] 彼の文章スタイルについて、『タイム』誌は「チェスタートンは、可能な限り、ことわざ、格言、寓話を使って自分の主張を表現し、まずそれらを注意深く裏返 しにした」と評している。[4] 彼の著作は、エドガー・アラン・ポーの作品と比較したホルヘ・ルイス・ボルヘスにも影響を与えた。[8] |
| Biography Early life Chesterton at the age of 17 Chesterton was born in Campden Hill in Kensington, London, on 29 May 1874. His father was Edward Chesterton, an estate agent, and his mother was Marie Louise, née Grosjean, of Swiss-French origin.[9][10][11] Chesterton was baptised at the age of one month into the Church of England,[12] though his family themselves were irregularly practising Unitarians.[13] According to his autobiography, as a young man he became fascinated with the occult and, along with his brother Cecil, experimented with Ouija boards.[14] He was educated at St Paul's School, then attended the Slade School of Art to become an illustrator. The Slade is a department of University College London, where Chesterton also took classes in literature, but he did not complete a degree in either subject. He married Frances Blogg in 1901; the marriage lasted the rest of his life. Chesterton credited Frances with leading him back to Anglicanism, though he later considered Anglicanism to be a "pale imitation". He entered in full communion with the Catholic Church in 1922.[15] The couple were unable to have children.[16][17] A friend from schooldays was Edmund Clerihew Bentley, inventor of the clerihew, a whimsical four-line biographical poem. Chesterton himself wrote clerihews and illustrated his friend's first published collection of poetry, Biography for Beginners (1905), which popularised the clerihew form. He became godfather to Bentley's son, Nicolas, and opened his novel The Man Who Was Thursday with a poem written to Bentley.[citation needed] Career In September 1895, Chesterton began working for the London publisher George Redway, where he remained for just over a year.[18] In October 1896, he moved to the publishing house T. Fisher Unwin,[18] where he remained until 1902. During this period he also undertook his first journalistic work, as a freelance art and literary critic. In 1902, The Daily News gave him a weekly opinion column, followed in 1905 by a weekly column in The Illustrated London News, for which he continued to write for the next thirty years. Early on Chesterton showed a great interest in and talent for art. He had planned to become an artist, and his writing shows a vision that clothed abstract ideas in concrete and memorable images. Father Brown is perpetually correcting the incorrect vision of the bewildered folks at the scene of the crime and wandering off at the end with the criminal to exercise his priestly role of recognition, repentance and reconciliation. For example, in the story "The Flying Stars", Father Brown entreats the character Flambeau to give up his life of crime: "There is still youth and honour and humour in you; don't fancy they will last in that trade. Men may keep a sort of level of good, but no man has ever been able to keep on one level of evil. That road goes down and down. The kind man drinks and turns cruel; the frank man kills and lies about it. Many a man I've known started like you to be an honest outlaw, a merry robber of the rich, and ended stamped into slime."[19] Caricature by Max Beerbohm Chesterton loved to debate, often engaging in friendly public disputes with such men as George Bernard Shaw,[20] H. G. Wells, Bertrand Russell and Clarence Darrow.[21][22] According to his autobiography, he and Shaw played cowboys in a silent film that was never released.[23] On 7 January 1914 Chesterton (along with his brother Cecil and future sister-in-law Ada) took part in the mock-trial of John Jasper for the murder of Edwin Drood. Chesterton was Judge and George Bernard Shaw played the role of foreman of the jury.[24] During the First World War, Chesterton was editing New Witness writing editorials, and publishing letters from writers and thinkers, such as Thomas Maynard,[25] English poet and historian of the Catholic Church whose thinking was influenced by Chesterton's (1908) Orthodoxy; and Hilaire Belloc. In 1917, issues of New Witness[26] shed light on these writers' moral concerns about the way the war was being fought on the home front, by commentary on "the 'Gordon Scandal'", the undercover agent alias "Alex Gordon". This scandal was the refusal of the Attorney-General F.E. Smith to produce 'Gordon', the 'vanishing spy', for examination in court but on whose 'evidence' three defendants to conspiracy to murder (David Lloyd George and Arthur Henderson) were convicted and imprisoned (R v Alice Wheeldon & Ors, 1917). Chesterton was a large man, standing 6 feet 4 inches (1.93 m) tall and weighing around 20 stone 6 pounds (130 kg; 286 lb). His girth gave rise to an anecdote during the First World War, when a lady in London asked why he was not "out at the Front"; he replied, "If you go round to the side, you will see that I am."[27] On another occasion he remarked to his friend George Bernard Shaw, "To look at you, anyone would think a famine had struck England." Shaw retorted, "To look at you, anyone would think you had caused it."[28] P. G. Wodehouse once described a very loud crash as "a sound like G. K. Chesterton falling onto a sheet of tin".[29] Chesterton usually wore a cape and a crumpled hat, with a swordstick in hand, and a cigar hanging out of his mouth. He had a tendency to forget where he was supposed to be going and miss the train that was supposed to take him there. It is reported that on several occasions he sent a telegram to his wife Frances from an incorrect location, writing such things as "Am in Market Harborough. Where ought I to be?" to which she would reply, "Home".[30] Chesterton himself told this story, omitting, however, his wife's alleged reply, in his autobiography.[31] In 1931, the BBC invited Chesterton to give a series of radio talks. He accepted, tentatively at first. He was allowed (and encouraged) to improvise on the scripts. This allowed his talks to maintain an intimate character, as did the decision to allow his wife and secretary to sit with him during his broadcasts.[32] The talks were very popular. A BBC official remarked, after Chesterton's death, that "in another year or so, he would have become the dominating voice from Broadcasting House."[33] Chesterton was nominated for the Nobel Prize in Literature in 1935.[34] Chesterton was part of the Detection Club, a society of British mystery authors founded by Anthony Berkeley in 1928. He was elected as the first president and served from 1930 to 1936 until he was succeeded by E. C. Bentley.[35] Chesterton was one of the dominating figures of the London literary scene in the early 20th century. Death Telegram sent by Cardinal Eugenio Pacelli (the future Pius XII) on behalf of Pope Pius XI to the people of England following the death of Chesterton Chesterton died of congestive heart failure on 14 June 1936, aged 62, at his home in Beaconsfield, Buckinghamshire. His last words were a greeting of good morning spoken to his wife Frances. The sermon at Chesterton's Requiem Mass in Westminster Cathedral, London, was delivered by Ronald Knox on 27 June 1936. Knox said, "All of this generation has grown up under Chesterton's influence so completely that we do not even know when we are thinking Chesterton."[36] He is buried in Beaconsfield in the Catholic Cemetery. Chesterton's estate was probated at £28,389, equivalent to £2,436,459 in 2023.[37] Near the end of Chesterton's life, Pope Pius XI invested him as Knight Commander with Star of the Papal Order of St. Gregory the Great (KC*SG).[33] The Chesterton Society has proposed that he be beatified.[38] |
略歴 幼少期 17歳のチェスタートン チェスタートンは、1874年5月29日にロンドンのケンジントン、キャンプデン・ヒルで生まれた。父親は不動産業者であるエドワード・チェスタートン、 母親はスイスとフランスの血を引くマリー・ルイーズ(旧姓グロジャン)だった。[9][10][11] チェスタートンは生後1ヶ月でイギリス国教会で洗礼を受けたが、家族は不定期にユニテリアン教徒として信仰していた。[12][13] 自伝によると、若き日にオカルトに魅了され、兄のセシルと共にオウジャボードの実験を行った。[14] 彼はセント・ポールズ・スクールで教育を受け、その後スレイド美術学校でイラストレーターを志した。スレイドはロンドン大学ユニバーシティ・カレッジの学 部で、チェスタートンはここで文学の授業も受けたが、どちらの学科も卒業はしなかった。1901年にフランシス・ブログと結婚し、その結婚は生涯続いた。 チェスタートンは、フランシスが彼を英国国教会に戻した功績を称えたが、後に英国国教会を「淡い模倣」だと考えるようになった。1922年にカトリック教 会に完全入信した。[15] 夫婦には子供はいなかった。[16][17] 学生時代の友人には、4行の風変わりな伝記詩「クレリヒュー」の作者であるエドマンド・クレリヒュー・ベントレーがいた。チェスタートン自身もクレリ ヒューを執筆し、友人の最初の詩集『Biography for Beginners』(1905年)をイラストレーションで飾った。この詩集はクレリヒューの形式を普及させた。彼はベントリーの息子ニコラスのかけがえ の父となり、小説『The Man Who Was Thursday』の冒頭にベントリーに捧げた詩を掲載した。[出典必要] キャリア 1895年9月、チェスタートンはロンドン出版社ジョージ・レッドウェイ社で働き始め、1年余り在籍した。[18] 1896年10月、出版社T.フィッシャー・アンウィン社に移り、1902年まで在籍した。この期間、彼はフリーランスの美術・文学批評家として、最初の ジャーナリズム活動も始めた。1902年、『デイリー・ニュース』紙から週刊の論説欄を任され、1905年には『イラストレイテッド・ロンドン・ニュー ス』紙にも週刊のコラムを執筆し、その後30年間にわたって執筆を続けた。 チェスタートンは、幼少の頃から芸術に深い関心を持ち、その才能を発揮していた。彼は芸術家になることを目指しており、その著作には、抽象的な考えを具体 的で印象的なイメージで表現するビジョンが表れている。ブラウン神父は、犯罪現場で混乱する人々の誤った認識を常に訂正し、最後に犯人と共に去って、認 識、悔悛、和解という神父の役割を果たす。例えば、『飛ぶ星』という物語で、ブラウン神父はフラムボーという人物に犯罪の生活を諦めるよう懇願する:「あ なたにはまだ若さ、名誉、ユーモアがある。その職業でそれらが続くとは思わないでくれ。人間は善の一定のレベルを維持することはできるが、悪の同じレベル を維持し続けることは誰にもできない。その道は下り坂だ。優しい男は酒を飲み残酷になり、正直な男は殺して嘘をつく。私が見た多くの男は、あなたのように 正直なアウトロー、金持ちから盗む愉快な強盗として始まり、泥に埋もれて終わった。」[19] マックス・ビアボームの風刺画 チェスタートンは議論を愛し、ジョージ・バーナード・ショー[20]、H・G・ウェルズ、バーナード・ラッセル、クラレンス・ダロウ[21][22] などの人物と、親しい公の論争を繰り広げた。自伝によると、彼とショーは、公開されなかったサイレント映画でカウボーイを演じたことがある。[23] 1914年1月7日、チェスタートン(弟のセシルと将来の義妹アダと共に)は、エドウィン・ドードの殺人事件の模擬裁判に参加した。チェスタートンは判事 役を、ジョージ・バーナード・ショーは陪審員長の役を演じた。[24] 第一次世界大戦中、チェスタートンは『ニュー・ウィットネス』の編集者として社説を執筆し、トーマス・メイナード[25](チェスタートンの『正統性』 (1908年)の影響を受けた英国の詩人であり、カトリック教会の歴史家)やヒレア・ベロックなどの作家や思想家の手紙を掲載した。1917年、 『ニュー・ウィットネス』[26]は、国内戦線の戦争の戦い方に対するこれらの作家の道徳的懸念を、秘密工作員「アレックス・ゴードン」の「ゴードン・ス キャンダル」に関する論評を通じて浮き彫りにした。このスキャンダルは、検事総長F.E.スミスが「消えたスパイ」ゴードンを法廷での尋問に提出すること を拒否した事件で、その「証言」に基づいて、殺人陰謀罪で起訴された3被告(デイビッド・ロイド・ジョージとアーサー・ヘンダーソン)が有罪判決を受け、 収監された(R v Alice Wheeldon & Ors, 1917)。 チェスタートンは、身長6フィート4インチ(1.93メートル)、体重約20ストーン6ポンド(130キログラム;286ポンド)の大男だった。彼の体格 は第一次世界大戦中にエピソードを生んだ。ロンドンで一人の女性が「なぜ前線に行かないのか」と尋ねたところ、彼は次のように答えた。「横から見てみれ ば、私がいるのがわかるだろう」と答えた[27]。別の機会には、友人のジョージ・バーナード・ショーに「あなたを見ると、イギリスに飢饉が襲ったと思う だろう」と述べた。ショーは「あなたを見ると、あなたが原因だと思われそうだ」と返した。[28] P. G. ウッドハウスは、ある大きな衝突音を「G. K. チェスタートンがブリキの板の上に倒れたような音」と表現したことがある[29]。チェスタートンは通常、マントとしわくちゃの帽子、手には剣の柄付き 杖、口には葉巻を咥えていた。彼は、自分がどこに行くべきかを忘れてしまい、その目的地に向かう電車に乗り遅れる傾向があった。彼は何度か、妻フランシス に間違った場所から電報を送ったと伝えられている。例えば「マーケット・ハーボローにいる。どこにいるべきか?」と書き、彼女は「家」と返事した。 [30] チェスタートン自身はこの話を自伝で語ったが、妻の返事は省略していた。[31] 1931年、BBC はチェスタートンに一連のラジオ講演を依頼した。彼は最初はためらったものの、この依頼を受け入れた。彼は台本から即興で話すことを許可され(そして奨励 された)。これにより、彼の講演は親しみやすい雰囲気で進められた。また、講演中は妻と秘書も一緒に座ることを許可されたことも、その雰囲気を醸成した。 [32] この講演は大変好評だった。チェスタートンの死後、BBCの幹部は「あと1、2年あれば、彼は放送局の支配的な声になっていただろう」と述べた。[33] チェスタートンは1935年にノーベル文学賞にノミネートされた。[34] チェスタートンは、1928年にアンソニー・バークレーによって設立された英国のミステリー作家協会「ディテクション・クラブ」のメンバーだった。彼は初 代会長に選出され、1930年から1936年までその職を務め、E. C. ベントレーが後任となった。[35] チェスタートンは、20世紀初頭のロンドン文学界を支配した人物の一人だった。 死 チェスタートンの死後、教皇ピオ十一世に代わって、エウジェニオ・パチェッリ枢機卿(後のピオ十二世)が英国国民に送った電報 チェスタートンは、1936年6月14日、62歳で、バッキンガムシャーのビーコンズフィールドにある自宅で、うっ血性心不全により亡くなった。彼の最後 の言葉は、妻フランシスに向けた「おはよう」という挨拶だった。チェスタートンの追悼ミサがロンドン・ウェストミンスター大聖堂で執り行われた際、説教は ロナルド・ノックスが1936年6月27日に述べた。ノックスは「この世代の私たちは、チェスタートンの影響下で完全に育ったため、自分がチェスタートン の考えを思っていることにすら気づかない」と語った。[36] 彼はビーコンズフィールドのカトリック墓地に埋葬されている。チェスタートンの遺産は£28,389(2023年換算で約£2,436,459)と評価さ れた。[37] チェスタートンの生涯の終わりに、教皇ピオ十一世は彼に聖グレゴリオ大教皇勲章(KC*SG)の騎士司令官の称号を授与した。[33] チェスタートン協会は、彼の列福を提案している。[38] |
| Writing Chesterton wrote around 80 books, several hundred poems, some 200 short stories, 4,000 essays (mostly newspaper columns), and several plays. He was a literary and social critic, historian, playwright, novelist, and Catholic theologian[39][40] and apologist, debater, and mystery writer. He was a columnist for the Daily News, The Illustrated London News, and his own paper, G. K.'s Weekly; he also wrote articles for the Encyclopædia Britannica, including the entry on Charles Dickens and part of the entry on Humour in the 14th edition (1929). His best-known character is the priest-detective Father Brown,[3] who appeared only in short stories, while The Man Who Was Thursday is arguably his best-known novel. He was a convinced Christian long before he was received into the Catholic Church, and Christian themes and symbolism appear in much of his writing. In the United States, his writings on distributism were popularised through The American Review, published by Seward Collins in New York. [citation needed] Of his nonfiction, Charles Dickens: A Critical Study (1906) has received some of the broadest-based praise. According to Ian Ker (The Catholic Revival in English Literature, 1845–1961, 2003), "In Chesterton's eyes Dickens belongs to Merry, not Puritan, England"; Ker treats Chesterton's thought in chapter 4 of that book as largely growing out of his true appreciation of Dickens, a somewhat shop-soiled property in the view of other literary opinions of the time. The biography was largely responsible for creating a popular revival for Dickens's work as well as a serious reconsideration of Dickens by scholars.[41] Chesterton's writings consistently displayed wit and a sense of humour. He employed paradox, while making serious comments on the world, government, politics, economics, philosophy, theology and many other topics.[42][43] T. S. Eliot summed up his work as follows: He was importantly and consistently on the side of the angels. Behind the Johnsonian fancy dress, so reassuring to the British public, he concealed the most serious and revolutionary designs—concealing them by exposure ... Chesterton's social and economic ideas ... were fundamentally Christian and Catholic. He did more, I think, than any man of his time—and was able to do more than anyone else, because of his particular background, development and abilities as a public performer—to maintain the existence of the important minority in the modern world. He leaves behind a permanent claim upon our loyalty, to see that the work that he did in his time is continued in ours.[44] Eliot commented further that "His poetry was first-rate journalistic balladry, and I do not suppose that he took it more seriously than it deserved. He reached a high imaginative level with The Napoleon of Notting Hill, and higher with The Man Who Was Thursday, romances in which he turned the Stevensonian fantasy to more serious purpose. His book on Dickens seems to me the best essay on that author that has ever been written. Some of his essays can be read again and again; though of his essay-writing as a whole, one can only say that it is remarkable to have maintained such a high average with so large an output."[44] In 2022, a three-volume bibliography of Chesterton was published, listing 9,000 contributions he made to newspapers, magazines, and journals, as well as 200 books and 3,000 articles about him.[45] |
執筆 チェスタートンは、約 80 冊の著書、数百編の詩、約 200 編の短編小説、4,000 編のエッセイ(その大半は新聞のコラム)、そしていくつかの戯曲を残した。彼は文学評論家、社会評論家、歴史家、劇作家、小説家、カトリック神学者 [39][40]、そして弁証家、討論家、ミステリー作家でもあった。彼は『デイリー・ニュース』『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』および自身 の新聞『G. K.'s Weekly』のコラムニストを務め、また『ブリタニカ百科事典』のチャールズ・ディケンズに関する記事や、第14版(1929年)の「ユーモア」の項の 一部を執筆した。彼の最も有名なキャラクターは、短編小説のみに登場する司祭探偵のブラウン神父[3] で、『木曜日の男』は、おそらく彼の最も有名な小説だ。彼はカトリック教会に入信するずっと前から、確信を持ったキリスト教徒であり、彼の作品の多くには キリスト教のテーマや象徴が登場する。米国では、彼の分配主義に関する著作は、ニューヨークの Seward Collins 社が発行した『The American Review』を通じて普及した。[要出典] 彼のノンフィクション作品のうち、『チャールズ・ディケンズ:批判的研究』(1906年)は、最も幅広い評価を受けている。イアン・カー(『英国文学にお けるカトリックの復活、1845年~1961年、2003年』)によると、「チェスタートンの目には、ディケンズはピューリタンではなく、陽気なイギリス 人に属している」とのことです。カーは、その著書の第 4 章で、チェスタートンの考えは、当時の他の文学者たちからは多少評価の低いディケンズに対する彼の真の評価から大きく発展したものだと論じている。この伝 記は、ディケンズの作品の人気の復活と、学者たちによるディケンズの再評価に大きく貢献した。 チェスタートンの著作は、一貫して機知とユーモアに富んでいる。彼は、世界、政府、政治、経済、哲学、神学、その他多くのトピックについて真剣なコメント をしながら、パラドックスを用いた。[42][43] T. S. エリオットは、彼の作品を次のように要約している。 彼は、重要かつ一貫して天使たちの側に立っていた。英国国民を安心させるジョンソンの仮装の背後には、最も真剣で革命的な構想が隠されていた。彼はそれを 暴露することで隠していた... チェスタートンの社会・経済思想は... 基本的にキリスト教とカトリックのものであった。彼は、同時代の誰よりも多くのことを成し遂げ、また、彼の特別な経歴、成長、そしてパフォーマーとしての 能力により、現代社会における重要な少数派の存在を維持するために、誰よりも多くのことを成し遂げることができたと思う。彼は、彼の時代に行った仕事が私 たちの時代にも継続されるよう、私たちに忠誠を誓う永続的な義務を残した。[44] エリオットはさらに次のようにコメントしている。「彼の詩は一流のジャーナリスティックなバラッドであり、彼はそれをそれ以上に真剣に考えていなかっただ ろう。彼は『ノッティングヒルのナポレオン』で高い想像力のレベルに達し、『木曜日の男』ではさらに高いレベルに達した。これらのロマンス小説では、彼は スティーブンソンのファンタジーをより真剣な目的に転用した。彼のディケンズに関する本は、その作家について書かれた最も優れたエッセイの一つだと思う。 彼のエッセイの一部は繰り返し読む価値がある。ただし、エッセイ全体としては、膨大な量にもかかわらず高い水準を維持したことは驚くべきことだと言え る。」[44] 2022年には、チェスタートンの3巻からなる書誌目録が刊行され、彼が新聞、雑誌、ジャーナルに寄稿した9,000件の著作、および彼に関する200冊 の書籍と3,000件の記事が掲載されている。[45] |
| Contemporaries "Chesterbelloc" See also: G. K.'s Weekly George Bernard Shaw, Hilaire Belloc, and G. K. Chesterton Chesterton is often associated with his close friend, the poet and essayist Hilaire Belloc.[46][47] George Bernard Shaw coined the name "Chesterbelloc"[48] for their partnership,[49] and this stuck. Though they were very different men, they shared many beliefs;[50] in 1922, Chesterton joined Belloc in the Catholic faith, and both voiced criticisms of capitalism and socialism.[51] They instead espoused a third way: distributism.[52] G. K.'s Weekly, which occupied much of Chesterton's energy in the last 15 years of his life, was the successor to Belloc's New Witness, taken over from Cecil Chesterton, Gilbert's brother, who died in World War I. In his book On the Place of Gilbert Chesterton in English Letters, Belloc wrote that "Everything he wrote upon any one of the great English literary names was of the first quality. He summed up any one pen (that of Jane Austen, for instance) in exact sentences; sometimes in a single sentence, after a fashion which no one else has approached. He stood quite by himself in this department. He understood the very minds (to take the two most famous names) of Thackeray and of Dickens. He understood and presented Meredith. He understood the supremacy in Milton. He understood Pope. He understood the great Dryden. He was not swamped as nearly all his contemporaries were by Shakespeare, wherein they drown as in a vast sea – for that is what Shakespeare is. Gilbert Chesterton continued to understand the youngest and latest comers as he understood the forefathers in our great corpus of English verse and prose."[53] Wilde In his book Heretics, Chesterton said this of Oscar Wilde: "The same lesson [of the pessimistic pleasure-seeker] was taught by the very powerful and very desolate philosophy of Oscar Wilde. It is the carpe diem religion; but the carpe diem religion is not the religion of happy people, but of very unhappy people. Great joy does not gather the rosebuds while it may; its eyes are fixed on the immortal rose which Dante saw."[54] More briefly, and with a closer approximation to Wilde's own style, he wrote in his 1908 book Orthodoxy concerning the necessity of making symbolic sacrifices for the gift of creation: "Oscar Wilde said that sunsets were not valued because we could not pay for sunsets. But Oscar Wilde was wrong; we can pay for sunsets. We can pay for them by not being Oscar Wilde." Shaw Chesterton and George Bernard Shaw were famous friends and enjoyed their arguments and discussions. Although rarely in agreement, they each maintained good will toward, and respect for, the other.[55] In his writing, Chesterton expressed himself very plainly on where they differed and why. In Heretics he writes of Shaw: After belabouring a great many people for a great many years for being unprogressive, Mr Shaw has discovered, with characteristic sense, that it is very doubtful whether any existing human being with two legs can be progressive at all. Having come to doubt whether humanity can be combined with progress, most people, easily pleased, would have elected to abandon progress and remain with humanity. Mr Shaw, not being easily pleased, decides to throw over humanity with all its limitations and go in for progress for its own sake. If man, as we know him, is incapable of the philosophy of progress, Mr Shaw asks, not for a new kind of philosophy, but for a new kind of man. It is rather as if a nurse had tried a rather bitter food for some years on a baby, and on discovering that it was not suitable, should not throw away the food and ask for a new food, but throw the baby out of window, and ask for a new baby.[56] |
同時代人 「チェスターベロック」 参照:G. K. の週刊誌 ジョージ・バーナード・ショー、ヒレア・ベロック、G. K. チェスタートン チェスタートンは、親しい友人である詩人・エッセイストのヒレア・ベロックとよく関連付けられる。[46][47] ジョージ・バーナード・ショーは、彼らのパートナーシップを「チェスターベロック」[48] と名付け[49]、この名前は定着した。彼らは非常に異なる人物だったが、多くの信念を共有していた[50]。1922年、チェスタートンはベロックとと もにカトリックに改宗し、2人は資本主義と社会主義に対する批判を表明した。[51] 彼らは代わりに第三の道である「ディストリビューショニズム」を提唱した。[52] チェスタートンの生涯の最後の15年間の大部分を占めた『G. K.'s Weekly』は、ベルロクの『New Witness』の後継誌で、第一次世界大戦で戦死したギルバートの兄セシル・チェスタートンから引き継がれた。 ベロックは『ギルバート・チェスタートンのイギリス文学における地位』という本の中で、「彼がイギリスの文学の偉大な名前について書いたものはすべて最高 品質だった。彼は、ジェーン・オースティンのような一人の作家の作品を、正確な文で要約した。時には、他の人には真似できない方法で、一つの文で要約し た。この分野では彼は完全に独り立ちしていた。彼は、最も有名な二人の名前を例に取れば、サー・ウォルター・スコットとチャールズ・ディケンズの心を理解 していた。彼はメリディアンを理解し、提示した。彼はミルトンの優越性を理解していた。彼はポープを理解していた。彼は偉大なドライデンを理解していた。 彼は、シェイクスピアに溺れるように沈没したほぼすべての同時代人とは異なり、シェイクスピアに溺れることはなかった——なぜなら、シェイクスピアとはま さにそのような存在だからだ。ギルバート・チェスタートンは、英国の偉大な詩と散文の先人たちを理解したように、最新かつ最年少の作家たちも理解し続け た。[53] ワイルド チェスタートンは、著書『異端者たち』の中で、オスカー・ワイルドについて次のように述べている。「同じ教訓(悲観的な快楽追求者)は、非常に強力で、非 常に荒涼としたオスカー・ワイルドの哲学によっても教えられている。それはカルペ・ディエム(今を生きよう)の宗教だ。しかし、カルペ・ディエムは幸せな 人々の宗教ではなく、非常に不幸な人々の宗教だ。大きな喜びは、その機会があるうちにバラのつぼみを摘むものではない。その目は、ダンテが見た不滅のバラ に釘付けになっているのだ」[54]。より簡潔に、そしてワイルド自身のスタイルにより近い形で、彼は 1908 年の著書『正統性』の中で、創造の賜物に対して象徴的な犠牲を払う必要性について次のように書いている。「オスカー・ワイルドは、夕日はその代償を支払う ことができないから価値がない、と述べた。しかし、オスカー・ワイルドは間違っている。夕日の代償は支払うことができる。オスカー・ワイルドにならないこ とで、その代償を支払うことができるのだ。」 ショー チェスタートンとジョージ・バーナード・ショーは有名な友人であり、議論や討論を楽しんだ。2人はほとんど意見が一致することはなかったが、お互いに善い 意志と敬意を保っていた。[55] チェスタートンは、彼らの相違点とその理由について、自分の著作の中で非常に率直に述べている。『異端者たち』の中で、彼はショーについて次のように書い ている。 長年にわたり、進歩的ではないと多くの人々を厳しく非難してきたショー氏は、その特徴的な感覚から、2 本の足を持つ人間が進歩的であるかどうかは非常に疑わしいことを発見した。人類が進歩と両立できるかどうかを疑うようになったほとんどの人は、満足しやす い性質から、進歩を放棄して人類のままでいることを選ぶだろう。しかし、満足しにくいショー氏は、その限界のある人類をすべて捨てて、進歩そのものを追求 することを決めた。もし、私たちが知る人間が進歩の哲学に無能力であるなら、ショー氏は新しい種類の哲学ではなく、新しい種類の人間を求める。これは、あ る看護師が赤ん坊に数年、やや苦い食べ物を与えてみて、それが適していないと気づいた時、その食べ物を捨てて新しい食べ物を求めるのではなく、赤ん坊を窓 から投げ捨てて新しい赤ん坊を求めるようなものだ。[56] |
| Views Advocacy of Catholicism Chesterton's views, in contrast to Shaw and others, became increasingly focused towards the Church. In Orthodoxy he wrote: "The worship of will is the negation of will ... If Mr Bernard Shaw comes up to me and says, 'Will something', that is tantamount to saying, 'I do not mind what you will', and that is tantamount to saying, 'I have no will in the matter.' You cannot admire will in general, because the essence of will is that it is particular."[57] Chesterton's The Everlasting Man contributed to C. S. Lewis's conversion to Christianity. In a letter to Sheldon Vanauken (14 December 1950),[58] Lewis called the book "the best popular apologetic I know",[59] and to Rhonda Bodle he wrote (31 December 1947)[60] "the [very] best popular defence of the full Christian position I know is G. K. Chesterton's The Everlasting Man". The book was also cited in a list of 10 books that "most shaped his vocational attitude and philosophy of life".[61] Chesterton's hymn "O God of Earth and Altar" was printed in The Commonwealth and then included in The English Hymnal in 1906.[62] Several lines of the hymn appear in the beginning of the song "Revelations" by the British heavy metal band Iron Maiden on their 1983 album Piece of Mind.[63] Lead singer Bruce Dickinson in an interview stated "I have a fondness for hymns. I love some of the ritual, the beautiful words, Jerusalem and there was another one, with words by G. K. Chesterton O God of Earth and Altar – very fire and brimstone: 'Bow down and hear our cry'. I used that for an Iron Maiden song, "Revelations". In my strange and clumsy way I was trying to say look it's all the same stuff."[64] Étienne Gilson praised Chesterton's book on Thomas Aquinas: "I consider it as being, without possible comparison, the best book ever written on Saint Thomas ... the few readers who have spent twenty or thirty years in studying St. Thomas Aquinas, and who, perhaps, have themselves published two or three volumes on the subject, cannot fail to perceive that the so-called 'wit' of Chesterton has put their scholarship to shame."[65] Archbishop Fulton J. Sheen, the author of 70 books, identified Chesterton as the stylist who had the greatest impact on his own writing, stating in his autobiography Treasure in Clay, "the greatest influence in writing was G. K. Chesterton who never used a useless word, who saw the value of a paradox, and avoided what was trite."[66] Chesterton wrote the introduction to Sheen's book God and Intelligence in Modern Philosophy; A Critical Study in the Light of the Philosophy of Saint Thomas.[67] Common sense Chesterton has been called "The Apostle of Common Sense".[68] He was critical of the thinkers and popular philosophers of the day, who though very clever, were saying things that he considered nonsensical. This is illustrated again in Orthodoxy: "Thus when Mr H. G. Wells says (as he did somewhere), 'All chairs are quite different', he utters not merely a misstatement, but a contradiction in terms. If all chairs were quite different, you could not call them 'all chairs'."[69] Conservatism Although Chesterton was an early member of the Fabian Society, he resigned at the time of the Second Boer War.[70] He is often identified as a traditionalist conservative[71][72][73]: 39 due to his staunch support of tradition, expressed in Orthodoxy and other works with Burkean quotes such as the following: Tradition means giving votes to the most obscure of all classes, our ancestors. It is the democracy of the dead. Tradition refuses to submit to the small and arrogant oligarchy of those who merely happen to be walking about. All democrats object to men being disqualified by the accident of birth; tradition objects to their being disqualified by the accident of death. Democracy tells us not to neglect a good man's opinion, even if he is our groom; tradition asks us not to neglect a good man's opinion, even if he is our father.[74] Chesterton has been considered among the United Kingdom's anti-imperialist conservative wing, contrasted with his intellectual rivals in Shaw and Wells.[75]: 158 Chesterton's association with conservatism has expanded beyond British politics; Japanese conservative intellectuals, such as Hidetsugu Yagi [ja], have often referred to Chesterton's appeal to tradition as the "democracy of the dead".[76]: 89 However, Chesterton did not equate conservatism with complacency, arguing that cultural conservatives had to be politically radical.[77] |
見解 カトリックの擁護 チェスタートンの見解は、ショーや他の人々と対照的に、ますます教会に焦点を当てるようになった。『正統性』の中で、彼は次のように書いている。「意志の 崇拝は意志の否定である... もしバーナード・ショー氏が私のところにやってきて、『何かをしてください』と言った場合、それは『あなたが何をしてもかまいません』と言うのと同じであ り、それは『私はそのことについて意志はない」と言っているのと同じだ。意志の本質は個別性にあるので、意志そのものを賞賛することはできない」 [57]。 チェスタートンの『永遠の人』は、C. S. ルイスがキリスト教に改宗するきっかけとなった。1950年12月14日にシェルドン・ヴァナウケン宛ての手紙の中で、[58] ルイスは、この本を「私が知る限り最高の一般向け弁証書」[59]と呼び、ロンダ・ボドルへの手紙(1947年12月31日)[60]では、「私が知る限 り、キリスト教の立場を最もよく擁護した一般向け著作は、G. K. チェスタートンの『永遠の人』だ」と書いている。この本は、彼の職業観と人生観に最も影響を与えた10冊の本のリストにも挙げられている。[61] チェスタートンの賛美歌「O God of Earth and Altar」は、『ザ・コモンウェルス』に掲載され、1906年に『ザ・イングリッシュ・ハイマナル』に収録された。[62] この賛美歌のいくつかの行は、イギリスのヘヴィメタルバンド、アイアン・メイデンの1983年のアルバム『Piece of Mind』収録の曲「Revelations」の冒頭にも登場している。[63] リードボーカル、ブルース・ディッキンソンはインタビューで「私は賛美歌が好きだ。私は、その儀礼や美しい言葉、エルサレムが大好きだ。G. K. チェスタートンの言葉による別の賛美歌「O God of Earth and Altar」も大好きだ。それは、非常に激しい言葉であり、「ひざまずいて、私たちの叫びを聞きなさい」と歌っている。私はそれをアイアン・メイデンの曲 「Revelations」に使った。私の奇妙で不器用な方法で、それはすべて同じことだと伝えようとしたのだ」[64] エティエンヌ・ジルソンは、チェスタートンのトマス・アクィナスに関する著書を「聖トマスについて書かれた本の中で、他に類を見ない最高の作品だ」と評価 している。「20年、30年かけて聖トマス・アクィナスを研究し、おそらくこのテーマについて2、3冊の本を出版した少数の読者でさえ、チェスタートンの いわゆる「機知」が、自分たちの学識を恥じさせるものであることを認識せざるを得ないだろう」。[65] 70冊の著書があるフルトン・J・シーン大司教は、チェスタートンを自分の文章に最も影響を与えた文筆家として挙げ、自伝『Treasure in Clay』の中で、「文章に最も影響を与えたのは、無駄な言葉を使わず、パラドックスの価値を見出し、陳腐な表現を避けたG. K. チェスタートンだった」と述べている。[66] チェスタートンは、シーンの著書『現代哲学における神と知性:聖トマス哲学の観点から見た批判的研究』の序文を執筆している。[67] 常識 チェスタートンは「常識の使徒」と呼ばれている。[68] 彼は、非常に賢いものの、彼がナンセンスだと考えることを口にする当時の思想家や人気のある哲学者たちを批判していた。これは『正統性』でも再び説明され ている。「したがって、H. G. ウェルズ氏が(ある場所で)『すべての椅子はまったく異なる』と述べた場合、彼は単に誤った発言をしただけでなく、用語上の矛盾も犯している。すべての椅 子がまったく異なるのであれば、それらを『すべての椅子』と呼ぶことはできないからだ」[69]。 保守主義 チェスタートンはファビアン協会の初期メンバーだったが、第二次ボーア戦争の際に脱退した。[70] 彼は、伝統主義的な保守派としてよく知られている[71][72][73]: 39 。これは、『正統派』や他の著作で、バークの名言を引用して伝統への 強い支持を表明していることから来ている。 伝統とは、最も不明瞭な階級、すなわち私たちの先祖に投票権を与えることだ。それは死者の民主主義だ。伝統は、たまたま歩き回っているだけの小さな傲慢な 寡頭政治に服従することを拒否する。すべての民主主義者は、出生の偶然によって人間が資格を剥奪されることに反対する。伝統は、死の偶然によって資格を剥 奪されることに反対する。民主主義は、たとえ彼が私たちの婿であっても、良い人間の意見を無視してはならないと教えてくれる。伝統は、たとえ彼が私たちの 父親であっても、良い人間の意見を無視してはならないと教えてくれる。[74] チェスタートンは、ショーやウェルズといった知的なライバルたちとは対照的に、英国の反帝国主義的な保守派の一員と見なされてきた。[75]: 158 チェスタートンの保守主義との関連は、英国の政治だけにとどまらず、 八木秀次 [ja] などの日本の保守派知識人は、チェスタートンの伝統への訴えを「死者の民主主義」と表現してきた。[76]: 89 しかし、チェスタートンは保守主義を安逸と同一視せず、文化的な保守派は政治的に急進的でなければならないと主張した。[77] |
| Liberalism In spite of his association with tradition and conservatism, Chesterton called himself "the last liberal".[78] He was a supporter of the Liberal Party until he severed ties in 1928 following the death of former Liberal Prime Minister H. H. Asquith, although his attachment had already gradually weakened over the decades.[79] In addition the Daily News, for which Chesterton had been a columnist between 1903 and 1913, was aligned with the Liberals.[80] Chesterton's increasing coolness towards the Liberal Party was a response to the rise of New Liberalism in the early 20th century, which differed from his own vision of liberalism in several respects: it was secular, rather than being rooted in Christianity like the party's previously predominant creed of Gladstonian liberalism, and advocated a collectivist approach to social reform at odds with Chesterton's concern about what he saw as an increasingly interventionist and technocratic state challenging both the primacy of the family in social organisation and democracy as a political ideal.[80][81][79] Despite this critique of the development of left-liberalism in this period, Chesterton also criticised the laissez-faire approach of Manchester Liberalism which had been influential among Liberals in the late 19th century, arguing that this had led to the development of monopolies and plutocracy rather than the competition classical theorists had predicted, as well as the exploitation of workers for profit.[79] In addition to Chesterton, other distributists including Belloc were also involved with the Liberals before the First World War. They shared much common ground in terms of their policy agenda with the broader party during this time, including devolution of power to local government, franchise reform, replication of the Irish Wyndham Land Act in Britain, supporting trade unions and a degree of social reform by central government, whilst opposing socialism.[79] Chesterton opposed the Conservative Education Act 1902, which provided for public funding of Church schools, on the grounds that religious freedom was best served by keeping religion out of education. However, he disassociated himself from the campaign against it led by John Clifford, whose invoking of the Act's provisions as resulting in "Rome on the rates" was judged by Chesterton to be bigotry appealing to straw man arguments.[80] The Chestertons and Belloc supported the Liberal leadership on the passage of David Lloyd George's People's Budget and the weakening of the power of the House of Lords through the Parliament Act 1911 in response to its resistance to the budget, but were critical of their timidity in pushing for Irish Home Rule.[79] Following the war, the position of the New Liberals had strengthened, and the distributists came to believe that the party's positions were closer to social democracy than liberalism. They also differed from most Liberals by advocating for home rule for all of Ireland, rather than partition. More generally they developed a policy agenda distinct from any of the main three parties during this time, including promoting guilds and the nuclear family, introducing primary elections and referendums, antitrust action, tax reform to favour small businesses, and transparency regarding party funding and the Honours Lists.[79] On war Chesterton first emerged as a journalist just after the turn of the 20th century. His great, and very lonely, opposition to the Second Boer War, set him very much apart from most of the rest of the British press. Chesterton was a Little Englander, opposed to imperialism, British or otherwise. Chesterton thought that Great Britain betrayed her own principles in the Boer Wars. In vivid contrast to his opposition to the Boer Wars, Chesterton vigorously defended and encouraged the Allies in World War I. "The war was in Chesterton's eyes a crusade, and he was certain that England was right to fight as she had been wrong in fighting the Boers."[82] Chesterton saw the roots of the war in Prussian militarism. He was deeply disturbed by Prussia's unprovoked invasion and occupation of neutral Belgium and by reports of shocking atrocities the Imperial German Army was allegedly committing in Belgium. Over the course of the War, Chesterton wrote hundreds of essays defending it, attacking pacifism, and exhorting the public to persevere until victory. Some of these essays were collected in the 1916 work, The Barbarism of Berlin.[83] One of Chesterton's most successful works in support of the War was his 1915 tongue-in-cheek The Crimes of England.[84] The work is ironic, supposedly apologizing and trying to help a fictitious Prussian professor named Whirlwind make the case for Prussia in WWI, while actually attacking Prussia throughout. Part of the book's humorous impact is the conceit that Professor Whirlwind never realizes how his supposed benefactor is undermining Prussia at every turn. Chesterton "blames" England for historically building up Prussia against Austria, and for its pacifism, especially among wealthy British Quaker political donors, who prevented Britain from standing up to past Prussian aggression. Accusations of antisemitism Chesterton in his office Chesterton faced accusations of antisemitism during his lifetime, saying in his 1920 book The New Jerusalem that it was something "for which my friends and I were for a long period rebuked and even reviled".[85] Despite his protestations to the contrary, the accusation continues to be repeated.[86] An early supporter of Captain Dreyfus, by 1906 he had turned into an anti-Dreyfusard.[87] From the early 20th century, his fictional work included caricatures of Jews, stereotyping them as greedy, cowardly, disloyal and communists.[88] Martin Gardner suggests that Four Faultless Felons was allowed to go out of print in the United States because of the "anti-Semitism which mars so many pages."[89] The Marconi scandal of 1912–1913 brought issues of anti-Semitism into the political mainstream. Senior ministers in the Liberal government had secretly profited from advance knowledge of deals regarding wireless telegraphy, and critics regarded it as relevant that some of the key players were Jewish.[90] According to historian Todd Endelman, who identified Chesterton as among the most vocal critics, "The Jew-baiting at the time of the Boer War and the Marconi scandal was linked to a broader protest, mounted in the main by the Radical wing of the Liberal Party, against the growing visibility of successful businessmen in national life and their challenge to what were seen as traditional English values."[91] In a 1917 work, titled A Short History of England, Chesterton considers the royal decree of 1290 by which Edward I expelled Jews from England, a policy that remained in place until 1655. Chesterton writes that popular perception of Jewish moneylenders could well have led Edward I's subjects to regard him as a "tender father of his people" for "breaking the rule by which the rulers had hitherto fostered their bankers' wealth". He felt that Jews, "a sensitive and highly civilized people" who "were the capitalists of the age, the men with wealth banked ready for use", might legitimately complain that "Christian kings and nobles, and even Christian popes and bishops, used for Christian purposes (such as the Crusades and the cathedrals) the money that could only be accumulated in such mountains by a usury they inconsistently denounced as unchristian; and then, when worse times came, gave up the Jew to the fury of the poor".[92][93] In The New Jerusalem, Chesterton dedicated a chapter to his views on the Jewish question: the sense that Jews were a distinct people without a homeland of their own, living as foreigners in countries where they were always a minority.[94] He wrote that in the past, his position: was always called Anti-Semitism; but it was always much more true to call it Zionism. ... my friends and I had in some general sense a policy in the matter; and it was in substance the desire to give Jews the dignity and status of a separate nation. We desired that in some fashion, and so far as possible, Jews should be represented by Jews, should live in a society of Jews, should be judged by Jews and ruled by Jews. I am an Anti-Semite if that is Anti-Semitism. It would seem more rational to call it Semitism.[95] In the same place he proposed the thought experiment (describing it as "a parable" and "a flippant fancy") that Jews should be admitted to any role in English public life on condition that they must wear distinctively Middle Eastern garb, explaining that "The point is that we should know where we are; and he would know where he is, which is in a foreign land."[95] Chesterton, like Belloc, openly expressed his abhorrence of Adolf Hitler's rule almost as soon as it started.[96] As Rabbi Stephen Samuel Wise wrote in a posthumous tribute to Chesterton in 1937: When Hitlerism came, he was one of the first to speak out with all the directness and frankness of a great and unabashed spirit. Blessing to his memory![97] In The Truth About the Tribes, Chesterton attacked Nazi racial theories, writing: "the essence of Nazi Nationalism is to preserve the purity of a race in a continent where all races are impure".[98] The historian Simon Mayers points out that Chesterton wrote in works such as The Crank, The Heresy of Race, and The Barbarian as Bore against the concept of racial superiority and critiqued pseudo-scientific race theories, saying they were akin to a new religion.[88] In The Truth About the Tribes Chesterton wrote, "the curse of race religion is that it makes each separate man the sacred image which he worships. His own bones are the sacred relics; his own blood is the blood of St. Januarius".[88] Mayers records that despite "his hostility towards Nazi antisemitism … [it is unfortunate that he made] claims that 'Hitlerism' was a form of Judaism, and that the Jews were partly responsible for race theory".[88] In The Judaism of Hitler, as well as in A Queer Choice and The Crank, Chesterton made much of the fact that the very notion of "a Chosen Race" was of Jewish origin, saying in The Crank: "If there is one outstanding quality in Hitlerism it is its Hebraism" and "the new Nordic Man has all the worst faults of the worst Jews: jealousy, greed, the mania of conspiracy, and above all, the belief in a Chosen Race".[88] Mayers also shows that Chesterton portrayed Jews not only as culturally and religiously distinct, but racially as well. In The Feud of the Foreigner (1920) he said that the Jew "is a foreigner far more remote from us than is a Bavarian from a Frenchman; he is divided by the same type of division as that between us and a Chinaman or a Hindoo. He not only is not, but never was, of the same race".[88] In The Everlasting Man, while writing about human sacrifice, Chesterton suggested that medieval stories about Jews killing children might have resulted from a distortion of genuine cases of devil worship. Chesterton wrote: [T]he Hebrew prophets were perpetually protesting against the Hebrew race relapsing into an idolatry that involved such a war upon children; and it is probable enough that this abominable apostasy from the God of Israel has occasionally appeared in Israel since, in the form of what is called ritual murder; not of course by any representative of the religion of Judaism, but by individual and irresponsible diabolists who did happen to be Jews.[88][99] The American Chesterton Society has devoted a whole issue of its magazine, Gilbert, to defending Chesterton against charges of antisemitism.[100] Likewise, Ann Farmer, author of Chesterton and the Jews: Friend, Critic, Defender,[101][102] writes, "Public figures from Winston Churchill to Wells proposed remedies for the 'Jewish problem' – the seemingly endless cycle of anti-Jewish persecution – all shaped by their worldviews. As patriots, Churchill and Chesterton embraced Zionism; both were among the first to defend the Jews from Nazism", concluding that "A defender of Jews in his youth – a conciliator as well as a defender – GKC returned to the defence when the Jewish people needed it most."[103] |
自由主義 伝統と保守主義との関連にもかかわらず、チェスタートンは自分自身を「最後の自由主義者」と呼んでいました[78]。彼は、1928年に元自由党首相 H. H. アスキス(H. H. Asquith)が死去した後、自由党との関係を断ち切るまで、自由党の支持者でした。しかし、その支持は、数十年にわたって徐々に弱まっていました。 [79] さらに、チェスタートンが 1903 年から 1913 年までコラムニストを務めていたデイリー・ニュースも、自由党と提携していた。 チェスタートンが自由党に対して冷淡になったのは、20 世紀初頭に台頭した新自由主義に対する反応だった。新自由主義は、いくつかの点でチェスタートンの自由主義観とは異なっていた。それは、党の以前の主流思 想であったグラッドストン派の自由主義のようにキリスト教に根ざしたものではなく、世俗的なものであった。また、チェスタートンが懸念していた、家族を社 会組織の基盤とする原則と民主主義という政治的理想を脅かす、ますます介入主義的で技術官僚的な国家に対抗する、集団主義的な社会改革を主張していた。 [80][81][79] この時代の左派自由主義の発展に対する批判にもかかわらず、チェスタートンは、19世紀後半に自由党員の間で影響力があったマンチェスター自由主義の自由 放任主義も批判し、これは古典派理論家が予測した競争ではなく、独占と金権政治の発展、そして利益のための労働者の搾取につながったと主張した。[79] チェスタートンに加えて、ベロックを含む他の分配主義者も、第一次世界大戦前に自由党に関わっていた。彼らは、この期間、地方自治体への権限委譲、選挙権 改革、英国におけるアイルランドのウィンダム土地法の複製、労働組合の支援、中央政府による一定の社会改革など、政策の課題において、より広範な政党と多 くの共通点を持っていた。[79] チェスタートンは、宗教の自由は教育から宗教を排除することによって最もよく実現されるという理由で、教会学校への公的資金援助を規定した1902年の保 守党の教育法に反対した。しかし、彼は、この法律の規定を「ローマが税金を徴収する」と主張したジョン・クリフォードが主導した反対運動から距離を置い た。チェスタートンは、クリフォードの主張は、詭弁的な議論に訴える偏見にすぎないとした。[80] チェスタートン夫妻とベロックは、デビッド・ロイド・ジョージの人民予算案の可決と、予算案に反対した貴族院の権力を弱める 1911 年議会法について、自由党の指導部を支持したが、アイルランド自治の推進における彼らの臆病さを批判した。[79] 戦争後、新自由主義者の立場は強化され、分配主義者たちは、党の立場は自由主義よりも社会民主主義に近いと信じるようになった。また、彼らは、分割ではな く、アイルランド全土の自治を主張した点でも、ほとんどの自由主義者とは異なっていた。より一般的に、彼らはこの時代、主要3党のいずれとも異なる政策ア ジェンダを確立した。これには、ギルドと核家族制度の促進、予備選挙と国民投票の導入、独占禁止措置、中小企業を優遇する税制改革、政党資金と栄典名簿の 透明化などが含まれた。[79] 戦争について チェスタートンは20世紀初頭にジャーナリストとして頭角を現した。彼は第二次ボーア戦争に対する激しい反対姿勢で、当時のイギリスメディアの大多数から 大きく異なっていた。チェスタートンは「リトル・イングランド主義者」であり、イギリスを含む帝国主義に反対していた。彼はボーア戦争でイギリスが自らの 原則を裏切ったと考えた。 ボーア戦争への反対とは対照的に、チェスタートンは第一次世界大戦において連合国を熱烈に支持し、鼓舞した。「チェスタートンの目には戦争は十字軍であ り、イギリスがボーア戦争で間違っていたのに対し、この戦争で戦うことは正しいと確信していた。」[82] チェスタートンは戦争の根源をプロイセンの軍国主義に見ていた。彼は、プロイセンの中立国ベルギーに対する無挑発的な侵攻と占領、およびドイツ帝国軍がベ ルギーで犯したとされる残虐行為の報告に深く動揺した。戦争中、チェスタートンは戦争を擁護し、平和主義を批判し、勝利まで粘り強く戦うよう国民を鼓舞す る数百編のエッセイを書いた。これらのエッセイの一部は、1916年の著作『ベルリンの野蛮』に収められている。[83] チェスタートンが戦争を支持して書いた作品の中で最も成功したのは、1915年の皮肉に満ちた『イングランドの犯罪』だ。[84] この作品は皮肉に満ちており、架空のプロイセン人教授、ワールウィンドが第一次世界大戦におけるプロイセンの立場を弁明し、支援しようとしているように見 せながら、実際にはプロイセンを徹底的に攻撃している。この本のユーモアのインパクトの一部は、教授が自分の恩人がプロイセンを裏切っていることに気づか ないという設定にある。チェスタートンは、イギリスが歴史的にオーストリアに対してプロイセンを強化したこと、特に裕福なイギリス人クエーカー教徒の政治 献金者がイギリスのプロイセンの過去の侵略に対抗するのを妨げたことを「非難」している。 反ユダヤ主義の非難 チェスタートン、オフィスにて チェスタートンは生涯、反ユダヤ主義の非難に直面し、1920年の著書『新しいエルサレム』の中で、それは「私の友人たちと私が長い間非難され、甚至いは 罵倒されたこと」であると述べている。[85] 彼の反論にもかかわらず、この非難は繰り返し続けられている。[86] 1906年までに、ドレフュス大尉の初期の支持者であった彼は、反ドレフュス派に転向した。[87] 20 世紀初頭から、彼の小説には、ユダヤ人を貪欲で臆病、不誠実、共産主義者という固定観念で描いた風刺漫画が登場するようになった。[88] マーティン・ガードナーは、『Four Faultless Felons』が米国で絶版となったのは、「多くのページに反ユダヤ主義が散見される」ためだと指摘している。[89] 1912年から1913年にかけてのマルコーニ事件は、反ユダヤ主義の問題を政治の主流に持ち込んだ。自由党政府の高官たちは、無線電信に関する取引の事 前情報を密かに利用して利益を得ていたが、批評家たちは、その主要人物の一部がユダヤ人であったことを関連付け、この事件を問題視した。[90] チェスタートンを最も声高な批判者の一人と特定した歴史家トッド・エンデルマンは、「ボーア戦争とマルコーニ事件当時のユダヤ人嫌悪は、国民生活の中で成 功を収める実業家の存在感の高まりと、彼らが伝統的な英国の価値観に挑む姿勢に対する、主に自由党の急進派によって巻き起こった広範な抗議運動と関連して いた」と述べています。[91] 1917年の著作『イングランドの短い歴史』で、チェスタートンは、エドワード1世がユダヤ人をイングランドから追放した1290年の王令について考察し ている。この政策は1655年まで継続された。チェスタートンは、ユダヤ人の金貸しに対する大衆の認識が、エドワード 1 世の臣民たちに、彼を「これまで支配者たちが銀行家の富を育んできた規則を破った、人民の優しい父」とみなすよう導いた可能性があると述べている。彼は、 ユダヤ人は「敏感で高度に文明化された民族」であり、「その時代の資本家であり、すぐに使える富を蓄えた人々」であったため、「キリスト教の王や貴族、さ らにはキリスト教の教皇や司教たちが、キリスト教の目的(十字軍や大聖堂の建設など)のために、彼ら自身が非キリスト教的だと非難しながら、高利貸しに よってのみ蓄積できる巨額の富を利用し、 そして、より厳しい時代が到来すると、ユダヤ人を貧しい人々の怒りにさらした」と正当に不満を述べる権利があると考えていた。[92][93] 『新エルサレム』の中で、チェスタートンは、ユダヤ人問題に関する自分の見解に 1 章を割いて、ユダヤ人は、自国の故郷を持たない、常に少数派として外国で暮らす、独特の人々であるとの見解を述べている[94]。彼は、過去、自分の立場 は 常に反ユダヤ主義と呼ばれていたが、それをシオニズムと呼ぶほうがはるかに的を射ていた。... 私の友人たちと私は、この問題についてある一般的な方針を持っていた。それは、本質的には、ユダヤ人に別の国民としての尊厳と地位を与えるという願望だっ た。私たちは、何らかの形で、そして可能な限り、ユダヤ人はユダヤ人によって代表され、ユダヤ人の社会で暮らし、ユダヤ人によって裁かれ、ユダヤ人によっ て統治されるべきだと望んでいた。それが反ユダヤ主義であるならば、私は反ユダヤ主義者だ。それを「セミズム」と呼ぶほうがより合理的だと思われる。 [95] 同じ場所で、彼は、ユダヤ人は、中東特有の服装を着用することを条件として、英国の公的生活のあらゆる役割に就くことを認めるべきだという思考実験(彼は それを「寓話」および「軽薄な空想」と表現している)を提案し、「重要なのは、私たちが自分がどこにいるかを認識することだ。そうすれば、彼も自分が外国 にいることを認識できるだろう」と説明している。[95] チェスタートンはベルロク同様、アドルフ・ヒトラーの支配が始まって間もなく、その支配への嫌悪を公然と表明した。[96] 1937年にチェスタートンの追悼文で、ラビのスティーブン・サミュエル・ワイズは次のように書いている: ヒトラー主義が現れた時、彼は偉大で恥知らずな精神の持ち主として、率直かつ率直に声を上げた最初の人物のひとりだった。彼の記憶に祝福を![97] 『部族の真実』の中で、チェスタートンはナチスの人種理論を攻撃し、「ナチスのナショナリズムの本質は、すべての人種が混血している大陸において、ある人 種の純血性を維持することにある」と書いている。[98] 歴史家のサイモン・メイヤーズは、チェスタートンは『クランク』、『人種異端』、『野蛮人としての野蛮人』などの作品で、人種的優越性の概念に反対し、疑 似科学的な人種理論を、新しい宗教に似ているとして批判したと指摘している[88]。『部族の真実』の中で、チェスタートンは「人種宗教の呪いは、それぞ れの個人を、その人が崇拝する神聖な像にしてしまうことだ。彼自身の骨は神聖な遺物であり、彼自身の血は聖ヤヌアリオの血である」と述べています。 [88] メイヤーズは、「ナチスの反ユダヤ主義に対する彼の敵意にもかかわらず…『ヒトラー主義はユダヤ教の一形態であり、ユダヤ人は人種理論に一部責任がある』 と主張したのは残念だ」と記しています。[88] 『ヒトラーのユダヤ教』や『奇妙な選択』、『クランク』の中で、チェスタートンは「選民」という概念そのものがユダヤ教に由来するものであることを大きく 取り上げ、『クランク』の中で次のように述べている。「ヒトラー主義に傑出した特徴があるとしたら、それはそのヘブライ主義だ」と述べ、「新しい北欧人 は、嫉妬、貪欲、陰謀狂、そして何よりも、選民思想という、最悪のユダヤ人の最悪の欠点をすべて備えている」と述べています。[88] メイヤーズはまた、チェスタートンがユダヤ人を文化や宗教的に異なるだけでなく、人種的にも異なる存在として描いていたことを示しています。『The Feud of the Foreigner』(1920 年)では、ユダヤ人は「バイエルン人とフランス人よりもはるかに私たちから遠い外国人であり、私たちと中国人やヒンズー教徒との間の分裂と同じ種類の分裂 によって分断されている。彼らは同じ人種ではないだけでなく、かつてもそうではなかった」と述べています。[88] 『永遠の人』の中で、チェスタートンは、人間を犠牲にする習慣について書きながら、中世のユダヤ人が子供たちを殺すという物語は、悪魔崇拝の実際の事例が 歪曲された結果である可能性があると示唆している。チェスタートンは次のように書いている。 ヘブライ人の預言者たちは、子供たちに対するそのような戦争を伴う偶像崇拝に陥るヘブライ人種に対して絶えず抗議していた。そして、イスラエル神からのこ の忌まわしい背教は、儀式殺人と呼ばれる形で、それ以来イスラエルで時折出現してきた可能性が高い。もちろん、それはユダヤ教の代表者たちによるものでは なく、たまたまユダヤ人であった、無責任な悪魔崇拝者たちによるものだった。[99] アメリカ・チェスタートン協会は、その雑誌『ギルバート』の1号全体を、チェスタートンに対する反ユダヤ主義の非難を擁護するために割いている。 [100] 同様に、チェスタートンとユダヤ人:友人、批評家、擁護者[101][102]の著者アン・ファーマーは、「ウィンストン・チャーチルからウェルズに至る 公人たちは、『ユダヤ人問題』——反ユダヤ迫害の終わりのないサイクル——への解決策を提案した。そのすべては彼らの世界観によって形作られていた」と書 いている。愛国者として、チャーチルとチェスタートンはシオニズムを受け入れ、どちらもナチズムからユダヤ人を擁護した最初の人物の 1 人だった」と述べており、「青年期にユダヤ人を擁護し、調停者であり擁護者でもあった GKC は、ユダヤ人が最も必要としたときに再び擁護者となった」と結論付けている[103]。 |
| Opposition to eugenics |
Opposition to eugenics はこのページの上 |
| Chesterton's fence "Chesterton's fence" is the principle that reforms should not be made until the reasoning behind the existing state of affairs is understood. The quotation is from Chesterton's 1929 book, The Thing: Why I Am a Catholic, in the chapter, "The Drift from Domesticity": In the matter of reforming things, as distinct from deforming them, there is one plain and simple principle; a principle which will probably be called a paradox. There exists in such a case a certain institution or law; let us say, for the sake of simplicity, a fence or gate erected across a road. The more modern type of reformer goes gaily up to it and says, "I don't see the use of this; let us clear it away." To which the more intelligent type of reformer will do well to answer: "If you don't see the use of it, I certainly won't let you clear it away. Go away and think. Then, when you can come back and tell me that you do see the use of it, I may allow you to destroy it."[106] |
チェスタートンの柵 「チェスタートンの柵」とは、現状を維持する理由を理解するまで改革を行ってはならないという原則のことです。この引用は、チェスタートンの1929年の 著書『The Thing: Why I Am a Catholic』の「The Drift from Domesticity」という章から引用したものです。 改革と変形を区別した場合、改革に関する原則は一つだけあり、それはおそらくパラドックスと呼ばれるだろう。そのような場合、ある制度や法律が存在すると しよう。単純化のために、道路に建てられた柵や門だと仮定しよう。現代的なタイプの改革者は、その柵や門に近づき、こう言う。「これの用途が分からない。 撤去しよう」 これに対し、より賢明な改革者は次のように答えるべきだ。「その用途が分からないなら、私は絶対に撤去させない。行って考えなさい。そして、その用途が分 かったら、戻ってきて私に伝えなさい。その時は、撤去を許可するかもしれない。」[106] |
| Distributism This section does not cite any sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (April 2025) (Learn how and when to remove this message)  Self-portrait based on the distributist slogan "Three acres and a cow" Inspired by Leo XIII's encyclical Rerum novarum, Chesterton's brother Cecil and his friend, Hilaire Belloc were instrumental in developing the economic philosophy of distributism, a word Belloc coined. Gilbert embraced their views and, particularly after Cecil's death in World War I, became one of the foremost distributists and the newspaper whose care he inherited from Cecil, which ultimately came to be named G. K.'s Weekly, became its most consistent advocate. Distributism stands as a third way, against both unrestrained capitalism, and socialism, advocating a wide distribution of both property and political power. Scottish and Irish nationalism Despite his opposition to Nazism, Chesterton was not an opponent of nationalism in general and gave a degree of support to Scottish and Irish nationalism. He endorsed Cunninghame Graham and Compton Mackenzie for the post of Lord Rector of Glasgow University in 1928 and 1931 respectively and praised Scottish Catholics as "patriots" in contrast to Anglophile Protestants such as John Knox.[107] Chesterton was also a supporter of the Irish Home Rule movement and maintained friendships with members of the Irish Parliamentary Party. This was in part due to his belief that Irish Catholics had a naturally distributist outlook on property ownership.[108] |
分配主義 このセクションには出典が記載されていません。信頼できる出典を追加して、このセクションを改善してください。出典が記載されていない情報は、削除される 可能性があります。(2025年4月) (このメッセージの削除方法についてはこちらをご覧ください)  ディストリビューショニズムのスローガン「3エーカーの土地と1頭の牛」を基にした自画像 レオ13世の回勅『レルム・ノヴァルム』に触発されたチェスタートンの兄セシルと彼の友人、ヒラール・ベロックは、ベロックが造語した経済哲学「ディスト リビューショニズム」の発展に重要な役割を果たした。ギルバートは彼らの見解を受け入れ、特にセシルが第一次世界大戦で亡くなった後は、分配主義の第一人 者となり、セシルから引き継いだ新聞(最終的には「G. K.'s Weekly」と改名)は、分配主義の最も一貫した支持者となった。分配主義は、無制限の資本主義と社会主義の両方に反対する第三の道として、財産と政治 権力の幅広い分配を提唱している。 スコットランドとアイルランドのナショナリズム チェスタートンは、ナチズムに反対していたにもかかわらず、ナショナリズム全般に反対していたわけではなく、スコットランドとアイルランドのナショナリズ ムをある程度支持していました。彼は、1928年と1931年に、それぞれカニンガム・グラハムとコンプトン・マッケンジーをグラスゴー大学学長候補とし て支持し、ジョン・ノックスなどの英国愛好のプロテスタントとは対照的に、スコットランドのカトリック教徒を「愛国者」と賞賛しました。[107] チェスタートンはアイルランド自治運動の支持者でもあり、アイルランド議会党のメンバーと親交があった。これは、アイルランドのカトリック教徒が財産所有 に関して自然に分配主義的な見方をしていると考えていたためでもある。[108] |
| Legacy James Parker, in The Atlantic, gave a modern appraisal: In his vastness and mobility, Chesterton continues to elude definition: He was a Catholic convert and an oracular man of letters, a pneumatic cultural presence, an aphorist with the production rate of a pulp novelist. Poetry, criticism, fiction, biography, columns, public debate...Chesterton was a journalist; he was a metaphysician. He was a reactionary; he was a radical. He was a modernist, acutely alive to the rupture in consciousness that produced Eliot's "The Hollow Men"; he was an anti-modernist...a parochial Englishman and a post-Victorian gasbag; he was a mystic wedded to eternity. All of these cheerfully contradictory things are true...for the final, resolving fact that he was a genius. Touched once by the live wire of his thought, you don't forget it ... His prose ... [is] supremely entertaining, the stately outlines of an older, heavier rhetoric punctually convulsed by what he once called (in reference to the Book of Job) "earthquake irony". He fulminates wittily; he cracks jokes like thunder. His message, a steady illumination beaming and clanging through every lens and facet of his creativity, was really very straightforward: get on your knees, modern man, and praise God.[109] Possible sainthood The Bishop Emeritus of Northampton, Peter Doyle, in 2012 had opened a preliminary investigation into possibly launching a cause for beatification and then canonization (for possible sainthood), but eventually decided not to open the cause. The current Bishop of Northampton, David Oakley, has agreed to preach at a Mass during a Chesterton pilgrimage in England (the route goes through London and Beaconsfield, which are both connected to his life), and some have speculated he may be more favourable to the idea. If the cause is actually opened at the diocesan level (the Vatican must also give approval, that nothing stands in the way – the "nihil obstat"), then he could be given the title "Servant of God". It is not known if his alleged anti-Semitism (which would be considered a serious matter by the Church if it is true) may have played a role. His life and writings and views and what he did for others would be closely examined, in any case.[110] Literary Chesterton's socio-economic system of Distributism affected the sculptor Eric Gill, who established a commune of Catholic artists at Ditchling in Sussex. The Ditchling group developed a journal called The Game, in which they expressed many Chestertonian principles, particularly anti-industrialism and an advocacy of religious family life.[citation needed] His novel The Man Who Was Thursday inspired the Irish Republican leader Michael Collins with the idea that "If you didn't seem to be hiding nobody hunted you out."[111] Collins's favourite work of Chesterton was The Napoleon of Notting Hill, and he was "almost fanatically attached to it", according to his friend Sir William Darling.[112] His column in The Illustrated London News on 18 September 1909 had a profound effect on Mahatma Gandhi.[113] P. N. Furbank asserts that Gandhi was "thunderstruck" when he read it,[114] while Martin Green notes that "Gandhi was so delighted with this that he told Indian Opinion to reprint it".[115] Another convert was Canadian media theorist Marshall McLuhan, who said that the book What's Wrong with the World (1910) changed his life in terms of ideas and religion.[116] The author Neil Gaiman stated that he grew up reading Chesterton in his school's library, and that The Napoleon of Notting Hill influenced his own book Neverwhere. Gaiman based the character Gilbert from the comic book The Sandman on Chesterton,[117] and Good Omens, the novel Gaiman co-wrote with Terry Pratchett, is dedicated to Chesterton. The Argentine author and essayist Jorge Luis Borges cited Chesterton as influential on his fiction, telling interviewer Richard Burgin that "Chesterton knew how to make the most of a detective story".[118] Education Chesterton's many references to education and human formation have inspired a variety of educators including the 69 schools of the Chesterton Schools Network,[119] which includes the Chesterton Academy founded by Dale Ahlquist.[120] and the Italian Scuola Libera G. K. Chesterton in San Benedetto del Tronto, Marche.[121] The publisher and educator Christopher Perrin (who completed his doctoral work on Chesterton) makes frequent reference to Chesterton in his work with classical schools.[122] Namesakes In 1974, Ian Boyd, founded The Chesterton Review, a scholarly journal devoted to Chesterton and his circle. The journal is published by the G. K. Chesterton Institute for Faith and Culture based in Seton Hall University, South Orange, New Jersey.[123] In 1996, Dale Ahlquist founded the American Chesterton Society to explore and promote Chesterton's writings.[124] In 2008, a Catholic high school, Chesterton Academy, opened in the Minneapolis area. In the same year Scuola Libera Chesterton opened in San Benedetto del Tronto, Italy.[125] In 2012, a crater on the planet Mercury was named Chesterton after the author.[126] In 2014, G. K. Chesterton Academy of Chicago, a Catholic high school, opened in Highland Park, Illinois.[127] A fictionalised G. K. Chesterton is the central character in the Young Chesterton Chronicles, a series of young adult adventure novels by John McNichol,[128][129] and in the G K Chesterton Mystery series, a series of detective novels by the Australian author Kel Richards.[130] Another fictional character named Gil Chesterton is a food and wine critic who works for KACL, the Seattle radio station featured in the American television series Frasier. |
遺産 ジェームズ・パーカーは『アトランティック』誌で、次のような現代的な評価をしている。 その広大さと機動性により、チェスタートンは依然として定義を免れている。彼はカトリックに改宗した、予言的な文筆家であり、文化界に大きな影響力を持っ た人物であり、パルプ小説家のような生産性の高い格言家だった。詩、批評、小説、伝記、コラム、公開討論...チェスタートンはジャーナリストであり、形 而上学者だった。彼は反動的であり、急進的だった。彼はモダニストであり、エリオットの『空虚な人々』を生み出した意識の断絶に鋭敏に反応した。彼は反モ ダニストであり、地方的なイギリス人であり、ヴィクトリア朝後の空論家だった。彼は永遠に結びついた神秘主義者だった。これらの矛盾した特徴はすべて真実 だ……彼が天才だったという最終的な事実によって。彼の思想の活線に触れた者は、それを忘れることはない……彼の散文は……極めて面白く、古い重厚な修辞 の堂々とした輪郭が、彼が『ヨブ記』に言及して「地震の皮肉」と呼んだもので、定期的に痙攣的に揺さぶられる。彼は機知に富んだ怒りを爆発させ、雷のよう なジョークを飛ばす。彼のメッセージは、創造性のあらゆるレンズと面を通して輝き、響き渡る安定した光であり、実は非常に単純だった:現代人よ、膝をつ き、神を賛美せよ。[109] 聖人化の可能性 ノースハムプトン大司教のピーター・ドイルは、2012年に、列福(聖人への第一段階)そして列聖(聖人化)の手続きを開始する可能性について予備調査を 開始したが、最終的には手続きを開始しないことを決定した。現在のノースハムプトン司教デイビッド・オークリーは、イングランドでのチェスタートン巡礼 (ルートはロンドンとベイクンフィールドを通る、どちらも彼の生涯と関連する場所)中のミサで説教することを承諾しており、一部では彼がこのアイデアに好 意的である可能性が指摘されている。もし手続きが教区レベルで正式に開始され(バチカンも承認し、障害がないことを確認する「ニヒル・オブスタット」が必 要)、その後教皇庁が承認すれば、彼は「神の僕」の称号を授与される可能性がある。彼のとされる反ユダヤ主義(もし真実であれば教会にとって重大な問題と なる)が影響したかどうかは不明だ。いずれにせよ、彼の生涯、著作、思想、他者への貢献は詳細に調査されるだろう。[110] 文学 チェスタートンの社会経済システムである分配主義は、サセックスのディッチリングにカトリック芸術家のコミューンを設立した彫刻家エリック・ギルに影響を 与えた。ディッチリング・グループは、チェスタートンの多くの原則、特に反工業主義と宗教的な家庭生活の擁護を表明した雑誌『The Game』を創刊した。[要出典] 彼の小説『木曜日の男』は、アイルランド共和国指導者のマイケル・コリンズに「隠れていなければ、誰もあなたを追いかけることはない」という発想を与え た。コリンズがチェスタートンの中で最も愛した作品は『ノッティング・ヒルのナポレオン』で、彼の友人であるウィリアム・ダーリング卿によると、彼は「ほ とんど狂信的にこの作品に執着していた」という。[112] 1909年9月18日の『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』に掲載された彼のコラムは、マハトマ・ガンディーに深い影響を与えた。[113] P. N. ファーバンクは、ガンディーはそれを読んだときに「雷に打たれた」と主張している[114]、一方、マーティン・グリーンは、「ガンディーはこれに非常に 喜び、インディアン・オピニオンに再掲載するよう依頼した」と記している。[115] もう一人の改宗者は、カナダのメディア理論家マーシャル・マクルーハンで、彼は『世界は何が間違っているのか』(1910年)という本によって、思想と宗 教の面で人生が変わったと述べている。[116]作家ニール・ゲイマンは、学校の図書館でチェスタートンの本を読んで育ち、『ノッティングヒルのナポレオ ン』が自分の著書『ネバーウェア』に影響を与えたと述べている。ゲイマンは、コミック『ザ・サンドマン』のキャラクター・ギルバートをチェスタートンをモ デルに創作した[117]。また、テリー・プラチェットと共著した小説『グッド・オメンズ』はチェスタートンに捧げられている。アルゼンチンの作家でエッ セイストのホルヘ・ルイス・ボルヘスは、チェスタートンが自身の小説に大きな影響を与えたと述べ、インタビューアーのリチャード・バーグインに対し、 「チェスタートンは探偵物語の魅力を最大限に引き出す方法を知っていた」と語っている。[118] 教育 チェスタートンの教育と人間形成に関する多くの言及は、デール・アルクイストが設立したチェスタートン・アカデミー[119] や、マルケ州サン・ベネデット・デル・トロントにあるイタリアのスクオーラ・リベラ・G・K・チェスタートンなど、69 の学校からなるチェスタートン・スクール・ネットワーク[120] を含む、さまざまな教育者に影響を与えている。[121] 出版者であり教育者でもあるクリストファー・ペリン(チェスタートンに関する博士論文を完成)は、古典学校での活動においてチェスタートンを頻繁に引用し ている。[122] 同名の人物 1974年、イアン・ボイドは、チェスタートンとその仲間たちに捧げられた学術誌『チェスタートン・レビュー』を創刊した。この雑誌は、ニュージャージー 州サウスオレンジのセトンホール大学にある G. K. チェスタートン信仰文化研究所によって発行されている。[123] 1996年、デール・アルクイストは、チェスタートンの著作の研究と普及を目的としたアメリカン・チェスタートン協会を設立した。[124] 2008年、ミネアポリス近郊にカトリック系高校チェスタートン・アカデミーが開校した。同年に、イタリアのサン・ベネデット・デル・トロントにスクオー ラ・リベラ・チェスタートンが開校した。[125] 2012年、水星のクレーターにチェスタートンの名前が付けられた。[126] 2014年、カトリック系高校「G. K. チェスタートン・アカデミー・オブ・シカゴ」がイリノイ州ハイランドパークに開校した。[127] ジョン・マクニコルによるヤングアダルト向け冒険小説シリーズ『ヤング・チェスタートン・クロニクルズ』では、架空の人物である G. K. チェスタートンが主人公として登場する。[128][129]、オーストラリアの作家ケル・リチャーズによる探偵小説シリーズ『G K チェスタートン・ミステリー』にも登場している。[130] 別の架空の人物、ギル・チェスタートンは、アメリカのテレビシリーズ『フレイジャー』に登場するシアトルのラジオ局 KACL で働く食とワインの評論家だ。 |
| Major works Main article: G. K. Chesterton bibliography Library resources about G. K. Chesterton Online books Resources in your library Resources in other libraries By G. K. Chesterton Online books Resources in your library Resources in other libraries Books Chesterton, Gilbert Keith (1904), Ward, M. (ed.), The Napoleon of Notting Hill ——— (1903), Robert Browning, Macmillan[131] ——— (1905), Heretics, John Lane ——— (1906), Charles Dickens: A Critical Study, Dodd, Mead & Co., p. 299 ——— (1908a), The Man Who Was Thursday ——— (1908b), Orthodoxy ——— (1911a), The Innocence of Father Brown ——— (1911b), The Ballad of the White Horse ——— (1912), Manalive The Flying Inn (1914) ——— (1916), The Crimes of England ———, Father Brown (short stories) (detective fiction) ——— (1920), Ward, M. (ed.), The New Jerusalem, archived from the original on 15 January 2017 ——— (2018) [1922]. The Man Who Knew Too Much. Simon & Brown. ISBN 978-1731700568. ——— (1922), Eugenics and Other Evils ——— (1923), Saint Francis of Assisi ——— (1925), The Everlasting Man ——— (1925), William Cobbett ——— (1933), Saint Thomas Aquinas ——— (1935), The Well and the Shallows ——— (1936), The Autobiography ——— (1950), Ward, M. (ed.), The Common Man, archived from the original on 15 January 2017 Short stories "The Trees of Pride", 1922 "The Crime of the Communist", Collier's Weekly, July 1934. "The Three Horsemen", Collier's Weekly, April 1935. "The Ring of the Lovers", Collier's Weekly, April 1935. "A Tall Story", Collier's Weekly, April 1935. "The Angry Street – A Bad Dream", Famous Fantastic Mysteries, February 1947. Plays Magic, 1913. |
主な作品 主な記事:G. K. チェスタートン書誌 図書館の資料 G. K. チェスタートン オンライン書籍 お近くの図書館の資料 他の図書館の資料 G. K. チェスタートンによる オンライン書籍 お近くの図書館の資料 他の図書館の資料 書籍 チェスタートン、ギルバート・キース (1904)、ウォード、M. (編)、『ノッティング・ヒルのナポレオン ——— (1903)、ロバート・ブラウニング、マクミラン[131] ——— (1905)、『異端者たち』、ジョン・レーン ——— (1906)、『チャールズ・ディケンズ:批判的研究』、ドッド・ミード社、299 ページ ——— (1908a)、『木曜日の男 ——— (1908b)、『正統 ——— (1911a)、『ブラウン神父の無実 ——— (1911b)、『白い馬のバラード ——— (1912)、『生きた人間 The Flying Inn (1914) ——— (1916)、『イングランドの犯罪 ———、ブラウン神父(短編小説)(探偵小説 ——— (1920)、ウォード、M. (編)、『新しいエルサレム』、2017年1月15日にオリジナルからアーカイブ ——— (2018) [1922]。『知りすぎた男』。サイモン&ブラウン。ISBN 978-1731700568。 ——— (1922)、『優生学とその他の悪 ——— (1923)、『アッシジの聖フランチェスコ ——— (1925)、『永遠の人 ——— (1925)、『ウィリアム・コベット ——— (1933)、『聖トマス・アクィナス ——— (1935)、『井戸と浅瀬 ——— (1936)、『自伝 ——— (1950)、ウォード、M. (編)、『普通の人々』、2017年1月15日にオリジナルからアーカイブ 短編 「誇りの木々」、1922年 「共産主義者の罪」、コリアーズ・ウィークリー、1934年7月。 「三人の騎手」、コリアーズ・ウィークリー、1935年4月。 「恋人の指輪」、コリアーズ・ウィークリー、1935年4月。 「大げさな話」、コリアーズ・ウィークリー、1935年4月。 「怒りの街 - 悪い夢」、Famous Fantastic Mysteries、1947年2月。 戯曲 呪術、1913年。 |
| Sources Cited biographies Barker, Dudley (1973), G. K. Chesterton: A Biography, London, England: Constable, ISBN 978-0-09-457830-2 Ker, Ian (2011), G. K. Chesterton: A Biography, Oxford, England: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-960128-8 Pearce, Joseph (1996), Wisdom and Innocence: A Life of G. K. Chesterton, London, England: Hodder and Stoughton, ISBN 978-0-34-067132-0 Ward, Maisie (1944), Gilbert Keith Chesterton, Sheed & Ward |
出典 引用した伝記 バーカー、ダドリー(1973)、G. K. チェスタートン:伝記、ロンドン、イギリス:コンスタブル、ISBN 978-0-09-457830-2 カー、イアン(2011)、『G. K. チェスタートン:伝記』、イギリス、オックスフォード:オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-960128-8 ピアース、ジョセフ(1996)、『知恵と無垢:G. K. チェスタートンの生涯』、イギリス、ロンドン:ホッダー・アンド・ストウトン、ISBN 978-0-34-067132-0 ウォード、メイジー(1944)、『ギルバート・キース・チェスタートン』、シード&ウォード |
| Further reading Ahlquist, Dale (2012), The Complete Thinker: The Marvelous Mind of G. K. Chesterton, Ignatius Press, ISBN 978-1-58617-675-4 ——— (2003), G. K. Chesterton: Apostle of Common Sense, Ignatius Press, ISBN 978-0-89870-857-8 Belmonte, Kevin (2011). Defiant Joy: The Remarkable Life and Impact of G. K. Chesterton. Nashville, Tenn.: Thomas Nelson. Blackstock, Alan R. (2012). The Rhetoric of Redemption: Chesterton, Ethical Criticism, and the Common Man. New York. Peter Lang Publishing. Braybrooke, Patrick (1922). Gilbert Keith Chesterton. London: Chelsea Publishing Company. Cammaerts, Émile (1937). The Laughing Prophet: The Seven Virtues nd G. K. Chesterton. London: Methuen & Co., Ltd. Campbell, W. E. (1908). "G. K. Chesterton: Inquisitor and Democrat", Archived 6 November 2018 at the Wayback Machine The Catholic World, Vol. LXXXVIII, pp. 769–782. Campbell, W. E. (1909). "G. K. Chesterton: Catholic Apologist" The Catholic World, Vol. LXXXIX, No. 529, pp. 1–12. Chesterton, Cecil (1908). G. K. Chesterton: A Criticism. London: Alston Rivers (Rep. by John Lane Company, 1909). Clipper, Lawrence J. (1974). G. K. Chesterton. New York: Twayne Publishers. Coates, John (1984). Chesterton and the Edwardian Cultural Crisis. Hull University Press. Coates, John (2002). G. K. Chesterton as Controversialist, Essayist, Novelist, and Critic. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press. Conlon, D. J. (1987). G. K. Chesterton: A Half Century of Views. Oxford University Press. Cooney, A (1999), G. K. Chesterton, One Sword at Least, London: Third Way, ISBN 978-0-9535077-1-9 Coren, Michael (2001) [1989], Gilbert: The Man who was G. K. Chesterton, Vancouver: Regent College Publishing, ISBN 9781573831956, OCLC 45190713 Corrin, Jay P. (1981). G. K. Chesterton & Hilaire Belloc: The Battle Against Modernity. Ohio University Press. Ervine, St. John G. (1922). "G. K. Chesterton". In: Some Impressions of my Elders. New York: The Macmillan Company, pp. 90–112. Ffinch, Michael (1986), G. K. Chesterton, Harper & Row Gilbert Magazine (November/December 2008). Vol. 12, No. 2-3, Special Issue: Chesterton & The Jews. Haldane, John. 'Chesterton's Philosophy of Education', philosophy, Vol. 65, No. 251 (Jan. 1990), pp. 65–80. Hitchens, Christopher (2012). "The Reactionary", Archived 10 December 2016 at the Wayback Machine The Atlantic. Herts, B. Russell (1914). "Gilbert K. Chesterton: Defender of the Discarded". In: Depreciations. New York: Albert & Charles Boni, pp. 65–86. Hollis, Christopher (1970). The Mind of Chesterton. London: Hollis & Carter. Hunter, Lynette (1979). G. K. Chesterton: Explorations in Allegory. London: Macmillan Press. Jaki, Stanley (1986). Chesterton: A Seer of Science. University of Illinois Press. Jaki, Stanley (1986). "Chesterton's Landmark Year". In: Chance or Reality and Other Essays. University Press of America. Kenner, Hugh (1947). Paradox in Chesterton. New York: Sheed & Ward. Kimball, Roger (2011). "G. K. Chesterton: Master of Rejuvenation", Archived 27 September 2012 at the Wayback Machine The New Criterion, Vol. XXX, p. 26. Kirk, Russell (1971). "Chesterton, Madmen, and Madhouses", Modern Age, Vol. XV, No. 1, pp. 6–16. Knight, Mark (2004). Chesterton and Evil. Fordham University Press. Lea, F. A. (1947). "G. K. Chesterton". In: Donald Attwater (ed.) Modern Christian Revolutionaries. New York: Devin-Adair Co. McCleary, Joseph R. (2009). The Historical Imagination of G. K. Chesterton: Locality, Patriotism, and Nationalism. Taylor & Francis. McLuhan, Marshall (January 1936), "G. K. Chesterton: A Practical Mystic", Archived 29 May 2021 at the Wayback Machine Dalhousie Review, 15 (4): 455–464. McNichol, J. (2008), The Young Chesterton Chronicles, vol. Book One: The Tripods Attack!, Manchester, NH: Sophia Institute, ISBN 978-1-933184-26-5 Oddie, William (2010). Chesterton and the Romance of Orthodoxy: The Making of GKC, 1874–1908. Oxford University Press. Orage, Alfred Richard. (1922). "G. K. Chesterton on Rome and Germany". In: Readers and Writers (1917–1921). London: George Allen & Unwin, pp. 155–161. Oser, Lee (2007). The Return of Christian Humanism: Chesterton, Eliot, Tolkien, and the Romance of History. University of Missouri Press. Paine, Randall (1999), The Universe and Mr. Chesterton, Sherwood Sugden, ISBN 978-0-89385-511-6 Pearce, Joseph (1997), Wisdom and Innocence – A Life of G. K. Chesterton, Ignatius Press, ISBN 978-0-89870-700-7 Peck, William George (1920). "Mr. G. K. Chesterton and the Return to Sanity". In: From Chaos to Catholicism. London: George Allen & Unwin, pp. 52–92. Raymond, E. T. (1919). "Mr. G. K. Chesterton". In: All & Sundry. London: T. Fisher Unwin, pp. 68–76. Schall, James V. (2000). Schall on Chesterton: Timely Essays on Timeless Paradoxes. Catholic University of America Press. Scott, William T. (1912). Chesterton and Other Essays. Cincinnati: Jennings & Graham. Seaber, Luke (2011). G. K. Chesterton's Literary Influence on George Orwell: A Surprising Irony. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press. Sheed, Wilfrid (1971). "Chesterbelloc and the Jews", The New York Review of Books, Vol. XVII, No. 3. Shuster, Norman (1922). "The Adventures of a Journalist: G. K. Chesterton". In: The Catholic Spirit in Modern English Literature. New York: The Macmillan Company, pp. 229–248. Slosson, Edwin E. (1917). "G. K. Chesterton: Knight Errant of Orthodoxy". In: Six Major Prophets. Boston: Little, Brown and Company, pp. 129–189. Smith, Marion Couthouy (1921). "The Rightness of G. K. Chesterton", The Catholic World, Vol. CXIII, No. 678, pp. 163–168. Stapleton, Julia (2009). Christianity, Patriotism, and Nationhood: The England of G. K. Chesterton. Lanham, MD: Lexington Books. Sullivan, John (1974), G. K. Chesterton: A Centenary Appraisal, London: Paul Elek, ISBN 978-0-236-17628-1 Tonquédec, Joseph de (1920). G. K. Chesterton, ses Idées et son Caractère, Nouvelle Librairie National. Ward, Maisie (1952). Return to Chesterton, London: Sheed & Ward. West, Julius (1915). G. K. Chesterton: A Critical Study. London: Martin Secker. Williams, Donald T (2006), Mere Humanity: G. K. Chesterton, C. S. Lewis, and J. R. R. Tolkien on the Human Condition |
さらに詳しく読む Ahlquist, Dale (2012), The Complete Thinker: The Marvelous Mind of G. K. Chesterton, Ignatius Press, ISBN 978-1-58617-675-4 ——— (2003), G. K. Chesterton: Apostle of Common Sense, Ignatius Press, ISBN 978-0-89870-857-8 エスクリバ、ケビン(2011)。Defiant Joy: The Remarkable Life and Impact of G. K. Chesterton. テネシー州ナッシュビル:トーマス・ネルソン。 ブラックストック、アラン R. (2012). The Rhetoric of Redemption: Chesterton, Ethical Criticism, and the Common Man. ニューヨーク。ピーター・ラング出版。 ブレイブルック、パトリック (1922)。ギルバート・キース・チェスタートン。ロンドン:チェルシー出版。 カマールツ、エミール (1937)。笑う預言者:7つの美徳とG. K. チェスタートン。ロンドン:メトゥエン&カンパニー。 キャンベル、W. E. (1908)。「G. K. チェスタートン:審問官と民主主義者」、2018年11月6日、ウェイバックマシンにアーカイブ。The Catholic World、第 LXXXVIII 巻、769-782 ページ。 キャンベル、W. E. (1909). 「G. K. チェスタートン:カトリックの弁証家」 The Catholic World、第 LXXXIX 巻、第 529 号、 1-12 ページ。 チェスタートン、セシル (1908)。G. K. チェスタートン:批評。ロンドン:アルストン・リバーズ (1909 年、ジョン・レーン社により再版)。 クリッパー、ローレンス J. (1974)。G. K. チェスタートン。ニューヨーク:トウェイン出版社。 コーツ、ジョン(1984)。チェスタートンとエドワード朝文化の危機。ハル大学出版局。 コーツ、ジョン(2002)。G. K. チェスタートン:論争家、エッセイスト、小説家、批評家。ニューヨーク州ルイストン:エドウィン・メレン出版。 コンロン、D. J. (1987)。G. K. チェスタートン:半世紀の見解。オックスフォード大学出版局。 クーニー、A (1999)、G. K. チェスタートン、少なくとも一振りの剣、ロンドン:サード・ウェイ、ISBN 978-0-9535077-1-9 コーレン、マイケル (2001) [1989], ギルバート:G. K. チェスタートンだった男, バンクーバー:リージェント・カレッジ出版, ISBN 9781573831956, OCLC 45190713 コリン, ジェイ・P. (1981). G. K. チェスタートン & ヒルエール・ベロック:現代性との戦い. オハイオ大学出版局. アーヴィン、セント・ジョン・G. (1922). 「G. K. チェスタートン」. In: 私の先人たちからの印象. ニューヨーク: マクミラン社, pp. 90–112. フィンチ、マイケル (1986), G. K. チェスタートン, ハーパー&ロウ ギルバート・マガジン (2008年11月/12月). 第 12 巻、第 2-3 号、特別号:チェスタートンとユダヤ人。 ハルデーン、ジョン。「チェスタートンの教育哲学」、哲学、第 65 巻、第 251 号(1990 年 1 月)、65-80 ページ。 ヒッチェンズ、クリストファー(2012)。「反動的」, 2016年12月10日ウェイバックマシンにアーカイブ。アトランティック。 ハーツ、B. ラッセル(1914)。「ギルバート・K・チェスタートン:見捨てられた者の擁護者」。『軽蔑』所収。ニューヨーク:アルバート&チャールズ・ボニ、 65–86頁。 ホリス、クリストファー(1970)。『チェスタートンの精神』。ロンドン:ホリス&カーター。 ハンター、リネット(1979)。『G. K. チェスタートン:寓話の探求』。ロンドン:マクミラン・プレス。 ジャキ、スタンリー(1986)。『チェスタートン:科学の予見者』。イリノイ大学出版局。 ジャキ、スタンリー (1986). 「チェスタートンの画期的な年」. 『チャンスか現実か、その他のエッセイ』所収. アメリカ大学出版局. ケナー、ヒュー (1947). 『チェスタートンのパラドックス』. ニューヨーク: シード&ウォード. キンボール、ロジャー (2011). 「G. K. チェスタートン:若返りの達人」、2012年9月27日にウェイバックマシンにアーカイブ 『The New Criterion』第30巻、26ページ。 カーク、ラッセル(1971)。「チェスタートン、狂人、そして精神病院」、『Modern Age』第15巻第1号、6-16ページ。 ナイト、マーク(2004)。チェスタートンと悪。フォードハム大学出版局。 リー、F. A.(1947)。「G. K. チェスタートン」。ドナルド・アットウォーター(編)『現代キリスト教革命家たち』。ニューヨーク:デヴィン・アデア社。 マクレアリー、ジョセフ・R.(2009)。G. K. チェスタートンの歴史的想像力:地域性、愛国心、ナショナリズム。テイラー&フランシス。 マクルーハン、マーシャル(1936年1月)、「G. K. チェスタートン:実践的な神秘主義者」、2021年5月29日ウェイバックマシンにアーカイブ ダルハウジー・レビュー、15 (4): 455–464。 マクニコル、J.(2008)、『若いチェスタートン・クロニクルズ』第1巻:三脚の攻撃!、ニューハンプシャー州マンチェスター:ソフィア・インスティ テュート、ISBN 978-1-933184-26-5 オディ、ウィリアム(2010)。チェスタートンと正統派のロマンス:GKCの形成、1874–1908。オックスフォード大学出版局。 オラージュ、アルフレッド・リチャード。(1922). 「G. K. チェスタートン、ローマとドイツについて」。『読者たちと作家たち (1917–1921)』所収。ロンドン:ジョージ・アレン&アンウィン、155–161頁。 オザー、リー(2007)。『キリスト教ヒューマニズムの復活:チェスタートン、エリオット、トールキン、そして歴史のロマンス』。ミズーリ大学出版局。 ペイン、ランドール(1999)、『宇宙とチェスタートン氏』、シャーウッド・サグデン、ISBN 978-0-89385-511-6 ピアース、ジョセフ(1997)、『知恵と無垢 – G. K. チェスタートンの生涯』、イグナティウス・プレス、ISBN 978-0-89870-700-7 ペック、ウィリアム・ジョージ(1920)。「G. K. チェスタートン氏と正気の復活」。『カオスからカトリックへ』所収。ロンドン:ジョージ・アレン&アンウィン、52–92 ページ。 レイモンド、E. T. (1919). 「G. K. チェスタートン氏」 『オール&サンダリー』所収。ロンドン:T. フィッシャー・アンウィン、68–76 ページ。 シャル、ジェームズ・V.(2000)。『シャル・オン・チェスタートン:時宜を得た永遠のパラドックスに関するエッセイ』。カトリック大学アメリカプレ ス。 スコット、ウィリアム・T.(1912)。『チェスタートンとその他のエッセイ』。シンシナティ:ジェニングス&グラハム。 シーバー、ルーク (2011)。G. K. チェスタートンのジョージ・オーウェルへの文学的影響:驚くべき皮肉。ニューヨーク州ルイストン:エドウィン・メレン・プレス。 シード、ウィルフリッド (1971)。「チェスターベロックとユダヤ人」、『ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス』第 XVII 巻、第 3 号。 シュスター、ノーマン (1922)。「ジャーナリストの冒険:G. K. チェスタートン」。『現代英国文学におけるカトリック精神』所収。ニューヨーク:マクミラン社、229-248 ページ。 スロッソン、エドウィン E. (1917)。「G. K. チェスタートン:正統派の騎士道騎士」。『6人の大預言者』所収。ボストン:リトル・ブラウン・アンド・カンパニー、129-189 ページ。 スミス、マリオン・カウトーイ(1921)。「G. K. チェスタートンの正しさ」、『カトリック・ワールド』第 CXIII 巻、第 678 号、163-168 ページ。 Stapleton, Julia (2009). Christianity, Patriotism, and Nationhood: The England of G. K. Chesterton. Lanham, MD: Lexington Books. Sullivan, John (1974), G. K. Chesterton: A Centenary Appraisal, London: Paul Elek, ISBN 978-0-236-17628-1 トンケデック、ジョセフ・ド(1920)。G. K. チェスタートン、その思想と性格、ヌーヴェル・リブレリー・ナショナル。 ウォード、メイジー(1952)。チェスタートンへの回帰、ロンドン:シード&ウォード。 ウェスト、ジュリアス(1915)。G. K. チェスタートン:批判的研究。ロンドン:マーティン・セッカー。 ウィリアムズ、ドナルド T (2006)、『単なる人間性:G. K. チェスタートン、C. S. ルイス、J. R. R. トールキンによる人間条件について』 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/G._K._Chesterton |
+++
Links
リンク
文献
その他の情報


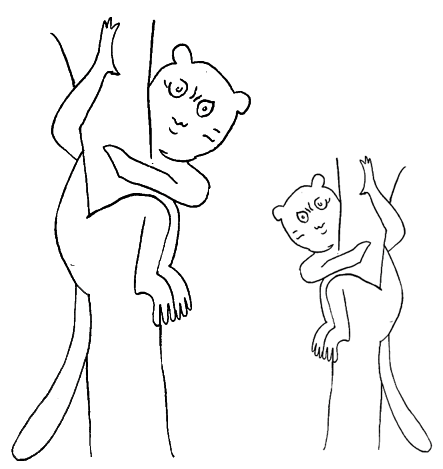
++
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆