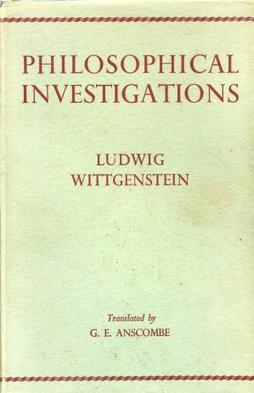
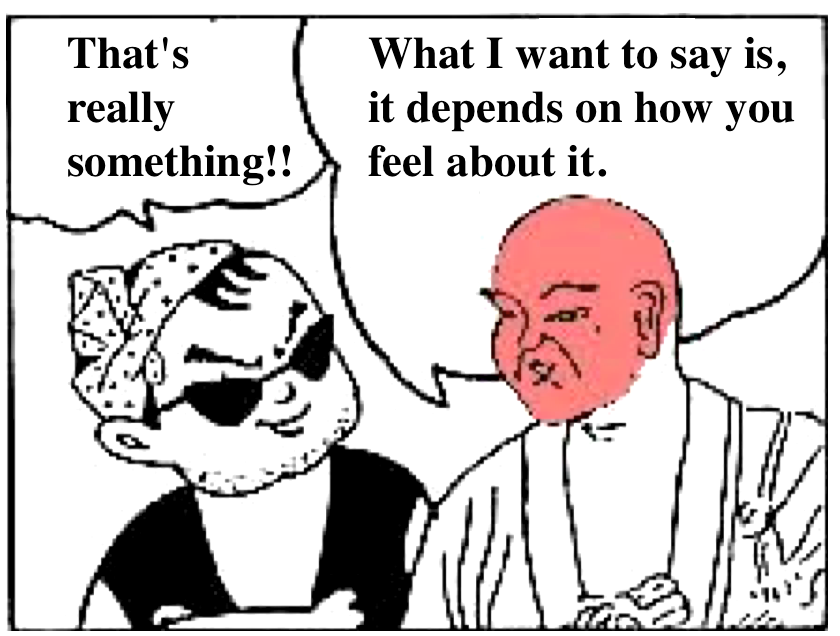
哲学探究
Philosophical Investigations, 1953
☆
『哲学探究』(PU)は、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの晩年の、2番目の主要著作である。この本は通常の言語の哲学の基本的な考え方を定式化して
いる。『哲学探究』は20世紀後半の哲学に多大な影響を与えた。とりわけ、ジョン・ラングショー・オースティンとサールの言語行為理論、およびエアランゲ
ン構成主義(パウル・ローレンツェン、クノ・ローレンツ)は、ここで展開された考え方に基づいている。カール・オットー・アペルの超越論的プラグマティズ
ムやユルゲン・ハーバーマスの普遍的プラグマティズムも、この考え方に大きな影響を受けている。この本は、理想言語哲学に反対するものであり、バートラン
ド・ラッセルやルドルフ・カナルプに加え、ウィトゲンシュタイン自身も最初の主要著作『論理哲学論考』
で提唱していた。
この本は1936年から1946年の間に書かれたが、その大半はヴィトゲンシュタインがノルウェーの自宅オーストレーリクに滞在していた時期である。しか
し、出版されたのは著者の死後2年が経過した1953年になってからであった。『論理哲学要綱』の厳格な体系構造とは対照的に、『哲学探究』は格言やメモ
の集まりであり、厳密な体系構造とは言えない。ウィトゲンシュタインによると、彼は「決して成功しない」と気づくまで、「自分の成果を全体として溶接し合
わせる」ことを繰り返し試みたという(序文)。
| Die
Philosophischen Untersuchungen (PU) sind Ludwig Wittgensteins spätes,
zweites Hauptwerk. Das Buch formuliert die Grundgedanken der
Philosophie der normalen Sprache. Die Philosophischen Untersuchungen
übten einen außerordentlichen Einfluss auf die Philosophie der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts aus; unter anderem die Sprechakttheorie bei
John Langshaw Austin und John Rogers Searle sowie der Erlanger
Konstruktivismus (Paul Lorenzen, Kuno Lorenz) bauen auf den hier
entwickelten Ideen auf. Auch die Transzendentalpragmatik von Karl-Otto
Apel und die Universalpragmatik von Jürgen Habermas sind maßgeblich
davon beeinflusst. Das Buch richtet sich gegen die Philosophie der
idealen Sprache, die neben Bertrand Russell und Rudolf Carnap vor allem
Wittgenstein selbst noch in seinem ersten Hauptwerk, dem Tractatus
Logico-Philosophicus, vertreten hatte. Das Buch ist in den Jahren 1936 bis 1946 entstanden. Zu einem erheblichen Teil verfasste es Wittgenstein beim Aufenthalt in seinem norwegischen Haus Østerrike. Veröffentlicht wurde das Buch aber erst 1953, zwei Jahre nach dem Tod des Autors. Im Gegensatz zu dem streng systematischen Aufbau des Tractatus sind die Philosophischen Untersuchungen eine mehr oder minder lose Sammlung von Aphorismen und Notizen. Nach Wittgensteins Aussage hat er mehrmals versucht, seine Ergebnisse „zu einem solchen Ganzen zusammenzuschweißen“, bis er einsehen musste, dass ihm „dies nie gelingen würde“ (Vorwort). |
『哲学探究』(PU)は、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの晩年
の、2番目の主要著作である。この本は通常の言語の哲学の基本的な考え方を定式化している。『哲学探究』は20世紀後半の哲学に多大な影響を与えた。とり
わけ、ジョン・ラングショー・オースティンとサールの言語行為理論、およびエアランゲン構成主義(パウル・ローレンツェン、クノ・ローレンツ)は、ここで
展開された考え方に基づいている。カール・オットー・アペルの超越論的プラグマティズムやユルゲン・ハーバーマスの普遍的プラグマティズムも、この考え方
に大きな影響を受けている。この本は、理想言語哲学に反対するものであり、バートランド・ラッセルやルドルフ・カナルプに加え、ウィトゲンシュタイン自身
も最初の主要著作『論理哲学論考』で提唱していた。 この本は1936年から1946年の間に書かれたが、その大半はヴィトゲンシュタインがノルウェーの自宅オーストレーリクに滞在していた時期である。しか し、出版されたのは著者の死後2年が経過した1953年になってからであった。『論理哲学要綱』の厳格な体系構造とは対照的に、『哲学探究』は格言やメモ の集まりであり、厳密な体系構造とは言えない。ウィトゲンシュタインによると、彼は「決して成功しない」と気づくまで、「自分の成果を全体として溶接し合 わせる」ことを繰り返し試みたという(序文)。 |
| Inhaltsverzeichnis 1 Die Gebrauchstheorie der Bedeutung 2 Sprachspiel und Lebensform 3 Einer Regel folgen 4 Die therapeutische Funktion der Philosophie 5 Privatsprache 6 Familienähnlichkeit 7 Zitate 8 Literatur 8.1 Ausgaben der PU 8.2 Sekundärliteratur 8.2.1 Allgemein 8.2.2 Sprache/Bedeutung 8.2.3 Regeln und Regelbefolgung |
目次 1 意味の使用理論 2 言語ゲームと生き方 3 規則に従うこと 4 哲学の治療的機能 5 私的言語 6 家族の類似性 7 引用 8 文献 8.1 PUの版 8.2 二次文献 8.2.1 一般 8.2.2 言語/意味 8.2.3 規則と規則の遵守 |
| Die Gebrauchstheorie der Bedeutung Wittgenstein richtet sich gegen die so genannte „realistische“ Theorie der Bedeutung, nach der gilt: „Jedes Wort hat eine Bedeutung. […] Sie ist der Gegenstand, für welchen das Wort steht.“ (PU 1). Dieser Theorie zufolge wäre die Bedeutung des Wortes „rot“ etwa ein abstrakter Gegenstand, die Farbe Rot. Für Wittgenstein ist dagegen die Bedeutung eines Wortes in den meisten Fällen durch seinen Gebrauch festgelegt: „Man kann für eine große Klasse von Fällen der Benützung des Wortes ‚Bedeutung‘ – wenn auch nicht für alle Fälle seiner Benützung – dieses Wort so erklären: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache“ (PU 43). Der Gebrauch eines Wortes wird durch Regeln bestimmt, ähnlich wie die korrekte Verwendung einer Schachfigur: „Die Frage ‚Was ist eigentlich ein Wort?‘ ist analog der ‚Was ist eine Schachfigur?‘“ (PU 108). Die Bedeutung des Wortes „rot“ zu kennen, bedeutet eine Regel zu haben, mit der man rote von nicht-roten Dingen unterscheiden kann. Ein Kaufmann, von dem man rote Äpfel verlangt, könnte beispielsweise die Äpfel neben ein Farbmuster halten, um festzustellen, ob sie rot sind (PU 1). Der enge Zusammenhang, den Wittgenstein zwischen der Bedeutung eines Wortes und den Regeln für seinen Gebrauch sieht, kommt auch in folgendem Zitat zum Ausdruck: „Wie erkenne ich, dass diese Farbe Rot ist. Eine Antwort wäre ‚Ich habe Deutsch gelernt.‘“ (PU 381). |
意味の使用理論 ウィトゲンシュタインは、いわゆる「現実主義」的な意味論に反対している。それによれば、「すべての言葉には意味がある。[...] 言葉が表象する対象である。」(『哲学論文集』1) この理論によると、例えば「赤」という単語の意味は、抽象的な物体である「赤色」となる。一方、ウィトゲンシュタインにとって、単語の意味はほとんどの場 合、その用法によって決定される。「『意味』という単語の用法の大部分については、その用法のすべてではないにしても、この単語は次のように説明できる。 単語の意味は、言語におけるその用法である」(PU 43)。 言葉の用法は、チェスの駒の正しい使い方に似た規則によって決定される。「『言葉とは何か?』という問いは、『チェスの駒とは何か?』という問いに類似し ている」 (PU 108)。「赤」という語の意味を知ることは、赤い物自体と赤くない物自体を区別するルールを理解することである。例えば、赤いリンゴを求められた商人 は、色見本とリンゴを並べて、それが赤いかどうかを判断することができる(PU 1)。ウィトゲンシュタインが言葉の意味と使用規則の間に密接な関係を見出していることは、次の引用文にも表れている。「私はどうやってこの色が赤である と認識するのか?一つの答えは、『私はドイツ語を学んだ』ということだ。」(PU 381) |
| Sprachspiel und Lebensform Die Regeln des Gebrauchs eines Wortes sind dadurch bestimmt, dass sprachliche Äußerungen im täglichen Miteinander eine bestimmte Funktion übernehmen. „Sieh den Satz als Instrument an und seinen Sinn als seine Verwendung.“ (PU 421). Diese Funktion kann jedoch in verschiedenen Situationen unterschiedlich sein. Für das Vorkommen von Sprache in konkreten Zusammenhängen verwendet Wittgenstein das Wort „Sprachspiel“: Wittgenstein gibt eine Reihe von Beispielen für Sprachspiele „Befehlen und nach Befehlen handeln – Beschreiben eines Gegenstandes nach dem Ansehen – Herstellen eines Gegenstandes nach einer Beschreibung – Berichten eines Herganges […] – Bitten, Danken, Fluchen, Grüßen, Beten“ (PU 23). Für die Gesamtheit der Handlungsmuster in einer Kultur verwendet Wittgenstein das Wort „Lebensform“. Die einzelnen Sprachspiele sind letztlich immer in eine Lebensform eingebettet: „Das Wort ‚Sprachspiel‘ soll hier hervorheben, dass das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit, oder einer Lebensform“ (PU 23). In diesem Sinne kann Wittgenstein sagen: „Und eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen“ (PU 19). |
言語ゲームと生活様式 ある語を使用する際の規則は、言語発話が私たちの日常的なやりとりにおいて特定の機能を持つという事実によって決定される。「命題を道具として、その意味 をその用途として考えてみよう」(PU 421)。しかし、この機能は状況によって異なる可能性がある。ウィトゲンシュタインは、特定の文脈における言語の発生を説明するのに「言語ゲーム」とい う用語を使用している。ウィトゲンシュタインは「命令を出すこと、命令に従うこと、物体を見てからそれを描写すること、描写に基づいて物体を製作するこ と、出来事を報告すること、質問すること、感謝すること、悪態をつくこと、挨拶すること、祈ること」(PU 23)など、言語ゲームの例を多数挙げている。 ウィトゲンシュタインは、ある文化における行動のパターンの全体を指して「生命体」という言葉を用いている。個々の言語ゲームは、究極的には常に生命体に 組み込まれている。「『言語ゲーム』という言葉は、言語を話すことが活動の一部、つまり生命体の一部であることを強調するものである」(PU 23)。この意味において、ウィトゲンシュタインは次のように言うことができる。「言語を想像することは、生命体を想像することである」(PU 19)。 |
| Einer Regel folgen Die Regeln des Gebrauchs eines Wortes lassen sich nach Wittgenstein durch Vor- und Nachmachen vermitteln: „Ich mach's ihm vor, er macht's mir nach; und ich beeinflusse ihn durch Äußerungen der Zustimmung, der Ablehnung […] usw. Denke, du wärst Zeuge eines solchen Unterrichts. Es würde darin kein Wort durch sich selbst erklärt, kein logischer Zirkel gemacht.“ (PU 208). Wittgenstein stößt jedoch auf die folgende Schwierigkeit: Eine Regel wird immer nur an endlich vielen Beispielen gelernt, soll aber letztlich auf unendlich viele Fälle anwendbar sein. Daraus ergibt sich, dass die Regel das zu lernende Handlungsmuster nicht festlegt, es gibt immer eine Vielzahl von Mustern, die mit ihr kompatibel sind: „Unser Paradox war dies: eine Regel könnte keine Handlungsweise bestimmen, da jede Handlungsweise mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen sei“ (PU 201). Wittgensteins Lösung für dieses Problem ist folgende: Die Tatsache, dass es eine Menge von Möglichkeiten gibt, die Regel fortzusetzen, heißt nicht, dass wir uns bewusst für eine dieser Möglichkeiten entscheiden. Sie drängt sich uns vielmehr unmittelbar auf: „Wenn ich der Regel folge, wähle ich nicht. Ich folge der Regel blind.“ (PU 219). Ein theoretisch möglicher Zweifel hat praktisch in dieser Situation keinen Platz. „Es war, unter Umständen, ein Zweifel möglich. Aber das sagt nicht, dass ich gezweifelt habe oder auch nur zweifeln konnte“ (PU 213). |
規則に従う ウィトゲンシュタインによれば、言葉の使い方の規則は模倣によって伝えることができる。「私が彼に示し、彼が私を模倣する。そして、私は承認や非承認の表 現によって彼に影響を与える。」このようなレッスンを目撃したと想像してみよう。言葉はそれ自体で説明されることはなく、論理的な循環は生まれない。」 (PU 208)。しかし、ウィトゲンシュタインは次の難題に直面する。規則は有限の例からしか学ばれないが、究極的には無限のケースに適用可能でなければならな い。つまり、規則は学習される行動パターンを決定するわけではない。常に、規則と矛盾しないパターンが多数存在するのだ。「我々のパラドックスはこうだ。 あらゆる行動は規則と一致させることができるため、規則は行動の方向性を決定できない」(PU 201)。 この問題に対するウィトゲンシュタインの解決策は次の通りである。規則を継続する可能性が多数あるという事実は、我々がそれらのうちの1つを意識的に選択 することを意味しない。むしろ、それは即座に私たちに提示される。「私が規則に従うとき、私は選択していない。私は盲目的に規則に従っているのだ」(PU 219)。理論上あり得る疑念は、この状況においてはほとんど意味を持たない。「特定の状況下では疑うことは可能だった。しかし、それは私が疑っていた、 あるいは疑うことができたということを意味しない」(PU 213)。 |
| Die therapeutische Funktion der Philosophie Diese Stelle exemplifiziert eine Argumentationsfigur, die typisch für die Philosophischen Untersuchungen ist: Nach Wittgenstein ergeben sich viele philosophische Probleme dadurch, dass Begriffe ihrem angestammten Kontext, ihrem Sprachspiel, entfremdet werden und ungerechtfertigt auf einen anderen Zusammenhang angewendet werden. Die Lösung eines philosophischen Problems besteht oft darin, eine solche ungerechtfertigte Übertragung aufzudecken: „Wir führen die Wörter von ihrer metaphysischen auf ihre alltägliche Verwendung zurück“ (PU 116). Beispielsweise ist der Zweifel ein Sprachspiel, das seinen eigenen Bedingungen und Regeln folgt und nicht in jeder Situation Platz hat. Durch diese Überlegung wird philosophischer Zweifel, der an allem zweifelt, als unsinnig entlarvt. „Aber das sagt nicht, dass wir zweifeln, weil wir uns einen Zweifel denken können“ (PU 84). Mit einem vergleichbaren Argument kritisiert Wittgenstein die Grundfrage des logischen Atomismus nach den Grundbestandteilen der Welt: „Auf die philosophische Frage: ‚Ist das Gesichtsbild dieses Baumes zusammengesetzt und welches sind seine Bestandteile‘ ist die richtige Antwort ‚Das kommt drauf an, was Du unter ‚zusammengesetzt‘ verstehst‘ (Und das ist natürlich keine Beantwortung, sondern eine Zurückweisung der Frage.)“ (PU 47). Die Frage nach einer Zusammensetzung ist ein Sprachspiel, das sich nicht auf einen derart abstrakten Kontext übertragen lässt. In ähnlicher Weise löst Wittgenstein das Induktionsproblem auf, bei dem die Praxis des Lernens aus Erfahrung in Frage gestellt wird: „Die Gewissheit, dass Feuer mich brennen wird, gründet sich auf Induktion. […] Ist die Zuversicht gerechtfertigt? Was die Menschen als Rechtfertigung gelten lassen, zeigt, wie sie denken und leben“ (PU 325). Letztlich gründet die Überzeugung, dass wir aus Erfahrung lernen können, in unserer Lebenswelt. Eine stärkere Rechtfertigung kann die Philosophie nicht liefern und auch nicht verlangen. In diesem Sinne sagt Wittgenstein: „Unser Fehler ist dort nach einer Erklärung zu suchen, wo wir die Tatsachen als ‚Urphänomene‘ sehen sollten. D.h. wo wir sagen sollten: dieses Sprachspiel wird gespielt“ (PU 654). |
哲学の治療的機能 この一節は、『哲学探究』の典型的な論旨を例示している。ウィトゲンシュタインによれば、多くの哲学上の問題は、用語が本来の文脈、すなわち言語ゲームか ら疎外され、正当な理由なく異なる文脈に適用されることによって生じる。哲学上の問題の解決策は、しばしば、このような正当化されない転用を明らかにする ことである。「私たちは、言葉たちを形而上学的な使用から日常的な使用へと戻す」(『哲学探究』116ページ)。 例えば、「疑う」という行為は、独自の条件と規則に従う言語ゲームであり、あらゆる状況に当てはまるわけではない。この考察により、あらゆるものを疑う「哲学的な疑い」の不合理性が明らかになる。「しかし、疑うことができるからといって疑うわけではない」(PU 84)。 ウィトゲンシュタインは、世界の基本的構成要素に関する論理的な原子論の根本的な疑問を、同様の論点で批判している。「この木の視覚的イメージは構成され ているのか、またその構成要素は何なのか」という哲学的な問いに対する正しい答えは、「『構成されている』という言葉が何を意味しているかによる」という ことだ(もちろん、これは答えではなく、質問の拒絶である)。(PU 47)。 構成の問題は、そのような抽象的な文脈に転用できない言語ゲームである。 同様に、ウィトゲンシュタインは、経験から学ぶという行為が問われる帰納法の問題を解決している。「火が私を燃やすという確信は帰納法に基づいている。そ の確信は正当化されるのか? 人々が正当化として受け入れるものは、彼らがどのように考え、生きているかを示している」(PU 325)。結局のところ、経験から学ぶことができるという我々の信念は、我々の経験に根ざしている。哲学は、より強力な正当性を与えることはできないし、 それを要求することもできない。この意味において、ウィトゲンシュタインは次のように述べている。「我々の誤りは、事実を『原型的な現象』として見るべき ところを、説明を求めるところにある。つまり、我々はこう言うべきなのだ。この言語ゲームは行われている、と」(PU 654)。 |
| Privatsprache Eine Privatsprache ist nach Wittgenstein eine Sprache oder Sprachspiel, bei welcher/welchem prinzipiell nur der Sprecher selbst um die Bedeutung der Worte dieser Sprache wissen kann. Der Fall eines Robinson Crusoe zählt nicht als Privatsprache, weil dieser prinzipiell in der Lage ist, die Bedeutung seiner Sprachelemente anderen mitzuteilen. Wittgensteins Beispiel ist eine Empfindungssprache: „Die Wörter dieser Sprache sollen sich auf das beziehen, wovon nur der Sprechende wissen kann; auf seine unmittelbaren, privaten Empfindungen.“ (PU 243) Im Privatsprachenargument zeigt er, dass die Verwendung von Wörtern einer Privatsprache sinnlos ist. Indem Wittgenstein sich gegen die Möglichkeit einer solchen Sprache wendet (PU 258), wendet er sich gleichzeitig gegen die These, dass in unserer eigenen Sprache Begriffe für Psychisches, wie z. B. das Wort „Schmerz“, auf solche privaten Episoden Bezug nehmen. Nach Wittgensteins Bedeutungstheorie lernen wir solche Wörter in intersubjektiven Sprachspielen. Ein rein privates Erlebnis lässt sich aber nicht intersubjektiv vermitteln, wohl aber der Umgang mit ihm. Diese These kommt in dem berühmten Käfer-Gleichnis zum Ausdruck: „Angenommen, es hätte jeder eine Schachtel, darin wäre etwas, was wir ‚Käfer‘ nennen. Niemand kann je in die Schachtel des Anderen schauen, und jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines Käfers, was ein Käfer ist. […] Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel, auch nicht einmal als ein Etwas, denn die Schachtel könnte auch leer sein“ (PU 293). Sprechen über psychische Vorgänge ist als Sprechen über äußeres Verhalten zu analysieren: „Ein ›innerer Vorgang‹ bedarf äußerer Kriterien“ (PU 580). |
私的な言語 ウィトゲンシュタインによれば、私的な言語とは、原則として、その言語の単語の意味を話者だけが知ることができる言語または言語ゲームである。ロビンソ ン・クルーソーの場合、彼は原則として、その言語の要素の意味を他人に伝えることができるため、私的な言語とはみなされない。ウィトゲンシュタインの例は 直観の言語である。「この言語の言葉は、話し手だけが知っているもの、すなわち、彼にとっての直接的な、個人的な直観を指すものとして想定されている」 (『哲学論考』243ページ)プライベート言語の議論において、彼はプライベート言語の言葉の使用は無意味であることを示している。このような言語の可能 性に反対することで(PU 258)、ウィトゲンシュタインは同時に、私たちの言語において、「痛み」という言葉のような心的現象を表す用語が、このような私的なエピソードを指して いるという命題にも反対している。ウィトゲンシュタインの意味論によれば、私たちはこのような言葉を相互主観的な言語ゲームの中で学ぶ。純粋に私的な経験 は相互主観的には伝達できないが、それに対してどう対処するかは伝達できる。この命題は有名な「カブトムシのたとえ」で表現されている。「もし、誰もが箱 を持っていて、その中に『カブトムシ』と呼ばれるものが入っているとしよう。誰も他人の箱の中を見ることはできないし、誰もが自分のカブトムシを見て、そ れが何であるかを知っていると言う。[...] 箱の中にある物自体は、言語ゲームにはまったく属さない。物としてでさえも、なぜなら箱は空である可能性もあるからだ」(PU 293)。 精神過程について語ることは、外部の行動について語るように分析されるべきである。「『内的過程』には外部の基準が必要である」(PU 580)。 |
| Familienähnlichkeit Kernpunkt von Wittgensteins Kritik an der Philosophie der idealen Sprache ist, dass sie mit ihrer Forderung nach Exaktheit die Unschärfe natürlichsprachiger Begriffe als ein Manko darstellt. Für diese Unschärfe prägt Wittgenstein den Begriff „Familienähnlichkeiten“. Er erläutert sie in PU 66 am Beispiel des Wortes „Spiel“. Es gibt nach Wittgenstein keinen gemeinsamen Zug, der allen Spielen gemeinsam wäre, sondern eine Familienähnlichkeit. Ein anderes Moment der Unschärfe (Sprache) liegt darin, dass unsere Begriffe nicht in jeder, sondern nur in gewöhnlichen Situationen verlässlich funktionieren: „Nur in normalen Fällen ist der Gebrauch der Worte uns klar vorgezeichnet; wir wissen, haben keinen Zweifel, was wir in diesem oder jenem Fall zu sagen haben“ (PU 142, siehe auch PU 80). Diese Ungenauigkeit macht aber unsere Begriffe keineswegs unbrauchbar „Aber ist es überflüssig zu sagen: ‚Halte Dich ungefähr hier auf‘“ (PU 71). Im Gegenteil wäre gerade eine übertriebene Präzision unzweckmäßig: „Wenn ich nun jemandem sage: ‚Du solltest pünktlicher zum Essen kommen […]‘ ist hier von Genauigkeit eigentlich nicht die Rede, weil man sagen kann ‚Denk an die Zeitbestimmung im Laboratorium […], da siehst Du, was ‚Genauigkeit‘ bedeutet‘“ (PU 88). Genau dies verkennt jedoch die Philosophie der idealen Sprache: „Je genauer wir die tatsächliche Sprache betrachten, desto stärker wird der Widerstreit zwischen ihr und unserer Forderung“ (PU 107). Aus diesen Beobachtungen zieht Wittgenstein das Fazit: „Die Philosophie darf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise antasten, sie kann ihn am Ende also nur beschreiben“ (PU 124). |
家族的類似性 理想言語哲学に対するヴィトゲンシュタインの批判の核心は、厳密性を求めることで、自然言語の用語のあいまいさを欠点として提示していることにある。この あいまいさについて、ヴィトゲンシュタインは「家族の類似性」という用語を考案した。彼はPU 66で「ゲーム」という語を例に挙げて説明している。ヴィトゲンシュタインによれば、すべてのゲームに共通する特徴はなく、あるのは「家族の類似性」だけ である。曖昧さ(言語)のもう一つの側面は、我々の概念はあらゆる状況で確実に機能するわけではなく、通常の状況においてのみ機能するという点である。 「言葉の使用法が明確に示されるのは、あくまでも通常のケースにおいてである。我々は、この場合やあの場合、何を言わなければならないのかを理解してお り、疑いを持っていない」(PU 142、PU 80も参照)。 しかし、この曖昧さによって我々の概念が使えなくなるわけではない。「しかし、『だいたいここにいて』と言うのは余計だろうか?」(PU 71)。それどころか、過剰な正確さは不適切である。「もし私が今誰かに『夕食にはもっと時間を守るべきだ』と言ったとしても、実際には正確さの問題では ない。なぜなら、『研究室でのタイミングを考えてみれば、正確さの意味が分かるだろう』と言うことができるからだ」(PU 88)。しかし、理想的な言語の哲学がまさに認識できていないのはこの点である。「実際の言語をより詳細に調査すればするほど、その言語と我々の要求との 間の対立はより顕著になる」(PU 107)。こうした観察から、ウィトゲンシュタインは次のような結論を導き出す。「哲学は、実際の言語の使用にいかなる形でも干渉してはならない。結局の ところ、哲学ができるのはそれを記述することだけである」(PU 124)。 |
| Zitate „Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt: Ein Gewinkel von Gässchen und Plätzen, alten und neuen Häusern, und Häusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge neuer Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern.“ (PU 18) „Und in dieser Lage befindet sich z. B. der, der in der Ästhetik oder Ethik nach Definitionen sucht, die unseren Begriffen entsprechen. Frage dich in dieser Schwierigkeit immer: Wie haben wir denn die Bedeutung dieses Wortes (‚gut‘ z.B.) gelernt?“ (PU 77) „Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache.“ (PU 109) „Es ist eine Hauptquelle unseres Unverständnisses, daß wir den Gebrauch unserer Wörter nicht übersehen“ (PU 122) „Die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfachheit und Alltäglichkeit verborgen“ (PU 129)  Fliegenglas „Einer Regel folgen, eine Mitteilung machen, einen Befehl geben, eine Schachpartie spielen sind Gepflogenheiten (Gebräuche, Institutionen). Einen Satz verstehen, heißt eine Sprache verstehen. Eine Sprache verstehen, heißt eine Technik beherrschen.“ (PU 199) „Der Philosoph behandelt eine Frage; wie eine Krankheit.“ (PU 255) „Was ist dein Ziel in der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.“ (PU 309) |
引用 「私たちの言語は、古い都市のようなものである。小路と広場が入り組んだ迷路、新旧の家屋、異なる時代に増築された家屋。そして、それらを取り囲むのは、まっすぐで規則正しい通りと単調な家屋が並ぶ無数の新しい郊外である。」(PU 18) 「そして、このような状況において、例えば、私たちの概念に対応する美学や倫理における定義を求める者は誰か。この困難に直面した際には、常に自問すべきである。私たちはどのようにしてこの言葉の意味(例えば「善」)を学んだのか、と。」(PU 77) 「哲学とは、言葉によって私たちの心を魅了するものに対する戦いである。」(PU 109) 「私たちの誤解の主な原因は、私たちが言葉の使い方を吟味しないことにある」(PU 122) 「私たちにとって最も重要な物自体の側面は、その単純さや平凡さによって隠されてしまう」(PU 129)  フライグラス 「規則に従うこと、主張すること、命令すること、チェスをプレイすることは慣習(用途、制度)である。文章を理解することは言語を理解することである。言語を理解することは技術を習得することである。」(PU 199) 「哲学者は質問をまるで病気であるかのように扱う。」(PU 255) 「哲学におけるあなたの目標は何ですか?ハエにハエ取りグラスの外への道を示すことだ。」(PU 309) |
| Literatur Ausgaben der PU Ludwig Wittgenstein: Philosophical investigations. Hrsg.: G. E. M. Anscombe. Blackwell, Oxford 1953, DNB 576937029 (deutsch: Philosophische Untersuchungen. Übersetzt von G. E. M. Anscombe). Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. Kritisch-genetische Edition. Herausgegeben von Joachim Schulte. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Frankfurt 2001, ISBN 3-518-58312-3. Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, Suhrkamp Verlag, 9. Auflage 2003, ISBN 978-3518223727 – Leseausgabe auf der Grundlage der kritisch-genetischen Edition von Joachim Schulte. Sekundärliteratur Allgemein Gordon P. Baker, Peter M. Hacker: Analytical Commentary on the „Philosophical Investigations“. Blackwell, Oxford 1985. (Mehrere Bände, der wohl gründlichste und umfassendste Kommentar zu den Philosophischen Untersuchungen, allerdings ohne die Behandlung von Teil II. Die Autoren sind die Wittgenstein-„Päpste“ und zerfielen über ihrem Hauptwerk in die weiter oben „therapeutisch“/„metaphysisch“ gekennzeichneten Lager.) Wolfgang Kienzler: Ludwig Wittgensteins „Philosophische Untersuchungen“. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, ISBN 978-3-534-19823-8. Ernst Michael Lange: Ludwig Wittgenstein. Philosophische Untersuchungen, eine kommentierte Einführung. Schöningh, Paderborn 1998, ISBN 3-8252-2055-9 (behandelt auch Teil II). Eike von Savigny: Wittgensteins „Philosophische Untersuchungen“. Ein Kommentar für Leser. Klostermann, Frankfurt am Main 1988 f., ISBN 978-3-465-03547-3. Severin Schroeder: Wittgenstein lesen. Ein Kommentar zu ausgewählten Passagen der „Philosophischen Untersuchungen“. Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2009 (legenda 5), ISBN 978-3-7728-2242-1. Meredith Williams (Hrsg.): Wittgenstein's Philosophical Investigations. Critical Essays. Lanham 2007, ISBN 978-0-7425-4191-7. Sprache/Bedeutung Wulf Kellerwessel: Wittgensteins Sprachphilosophie in den „Philosophischen Untersuchungen“: eine kommentierende Ersteinführung. Frankfurt 2009, ISBN 978-3-11-032850-9. Regeln und Regelbefolgung Edward H. Minar: Philosophical Investigations §§185–202. Wittgenstein's Treatment of Following a Rule. New York/ London 1990, ISBN 0-8240-5090-8. Saul A. Kripke: Wittgenstein über Regeln und Privatsprache. Eine elementare Darstellung. Frankfurt/Main 1987, ISBN 3-518-57832-4. |
文献 PUの版 ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン著『哲学探究』。G. E. M. アンコム編。Blackwell, Oxford 1953、DNB 576937029(ドイツ語:『哲学探究』。G. E. M. アンコム訳)。 ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン:哲学的探究。批判的生成版。ヨアヒム・シュルテ編。Wissenschaftliche Buchgesellschaft。フランクフルト 2001年、ISBN 3-518-58312-3。 ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン著『哲学探究』、訳者バートランド・ラッセル、G. E. E. エヴァンス(1964年) - ヨアヒム・シュルテによる批判生成版に基づく標準版。 二次文献 一般 ゴードン・P・ベイカー、ピーター・M・ハッカー著『「哲学探究」の分析的注釈』。Blackwell, Oxford 1985.(数巻からなる。おそらく『哲学探究』に関する最も徹底的かつ包括的な注釈書であるが、第2部は扱われていない。著者はウィトゲンシュタインの 「教皇」であり、彼らの主要な著作をめぐって「治療的」派と「形而上学的」派に分かれた。 ヴォルフガング・キーンツラー著『ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの哲学的探究』Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, ISBN 978-3-534-19823-8. エルンスト・マイケル・ランゲ著『ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン。哲学的探究、注釈付き入門編』ヘンリー・M・モリス訳(ニューヨーク:Harper & Row、1966年)。 アイケ・フォン・ザヴィニー著『ウィトゲンシュタインの「哲学探究」』。読者向け解説書。Klostermann、フランクフルト・アム・マイン 1988年以降、ISBN 978-3-465-03547-3。 セヴェリン・シュレーダー著『ウィトゲンシュタインを読む。「哲学探究」の抜粋部分に関する解説書』。フロムマン・ホルツブーク、シュトゥットガルト・バートカンシュタット 2009年(legenda 5)、ISBN 978-3-7728-2242-1。 メレディス・ウィリアムズ(編):ウィトゲンシュタイン『哲学探究』。批判的論文。ランハム 2007年、ISBN 978-0-7425-4191-7。 言語/意味 ヴルフ・ケラーヴェセル著『「哲学的探究」におけるウィトゲンシュタインの言語哲学:注釈付き初級入門』フランクフルト 2009年、ISBN 978-3-11-032850-9。 規則と順守 エドワード・H・ミナー著『「哲学的探究」第185~202項。ウィトゲンシュタインによる規則順守の扱い。ニューヨーク/ロンドン 1990年、ISBN 0-8240-5090-8。 ソール・A・クリプケ著『ウィトゲンシュタインの規則と言語私論』初歩的提示。フランクフルト・アム・マイン 1987年、ISBN 3-518-57832-4。 |
| https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophische_Untersuchungen |
|
◎私的言語(private language)
| ●私
的言語(private
language) 私的言語(してきげんご、private language)はルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインの後期の著作、特に『哲学探究』で紹介された哲学的主張。[1]私的言語論は20世紀後 半に哲学 的議論の中心となり、その後も関心を惹いている。私的言語論では、ただ一人の人だけ が理解できる言語は意味をなさないと 示すことになっている。 『哲学探究』では、ヴィトゲンシュタインは彼の主張を簡潔・直接的な形では提出しなかった。ただ、彼は特殊な言語の使用について記述し、読者がそういった 言語の使用の意味を熟考するように仕向けている。結果として、この主張の特徴とその意味について大きな論争が生じることになる。実際に、私的言語「論」に ついて話すことが一般的になってきた。 哲学史家は様々な史料、特にゴットロープ・フレーゲとジョン・ロックの著作に私的言語論の先駆けを見出している[2]。ロックもこの主張に目標を定められ た観点の提唱者である。というのは彼は『人間悟性論』において、言葉の指示する物はそれの意味する「表象」であると述べているからである。私的言語論は、 言語の本性についての議論において最も重要である。言語についての、ひとつの説得力のある理論は「言語は語を(各人の心の中の)観念・概念・表象へと写像 する」というものである。この説明では、わたしの概念はあなたのそれとは区別される(異なる)。けれども、わたしはわたしの概念を、我々の共通言語におけ る語に結びつけることができる。そして、わたしはその語を話す。それを聞いたあなたは、いま聞いた語をあなたの概念へと結びつける。このように、我々の概 念とはつまり(それ自体は各人において異なり、また心の中に匿されているという意味で)私的言語であるが、それは共通言語との翻訳を介して共有されてもい る、というわけである。こうした説明は、たとえば(ジョン・ロックの)『人間悟性論』、近年ではジェリー・フォーダーの思考の言語論に見られるものであ る。 後期ヴィトゲンシュタインは、私的言語のこうした説明は矛盾すると主張する。私的言語という考えに矛盾がある(成り立たない)として、その論理的な帰結の ひとつは、すべての言語はある社会的な機能の召使いにすぎない、とい うことである。このことは哲学と心理学の他の領域に重大な影響を与えることとなった。たとえば、もし人が私的言語を持つことができないのであれば、私的な 経験や私的な心的状態について語ることは、まったく意味をなさないことになる。 この主張は『哲学探究』第一部で述べられている。『哲学探究』第一部は順次番号づけられた「意見」の羅列よりなる。主張が中心的に述べられているのは第 256章及びその先だと一般的には考えられているが、最初に紹介されるのは第243章である。もし誰かが、かれ以外の誰にも理解できない言語を、理解するかのように振る舞うことがあったと したら、それこそが私的言語だということができよう[3]。とはいえ、その言語が単に孤立した言語である、つまりかつて翻訳されたことがな いというだけでは、十分ではない。ある言語がヴィトゲンシュタインのいう私的言語で あるためには、原理的に(通用する言語に)翻訳できない言語でなければならない。 たとえば、他人には窺い知ることができないような内的経験を記述する言語である[4]。ここでいう私的言語とは、単に「事実として」ただひとりが理解する 言語のことではなく、「原理的に」ただひとりにしか理解できない言語のことである。絶滅寸前の言語を話す最後のひとりは私的言語を話しているわけではな い。その言語はなお原理的に習得可能だからである。私的言語は習得不可能かつ翻訳不可能でなければならない。そして、にもかかわらず話者はその意味を理解 するかのようでなければならない(→「言語の翻訳不可論は論理的に破綻」→「言語とみなされるものは必ず翻訳可能性を獲得する」)。 ヴィトゲンシュタインは、感覚が起きたときにカレンダーに書いてある「S」という字と再帰的に起こってくる感覚を結びつけて考えている人を想像する思考実 験を行っている。[5] この場合はヴィトゲンシュタインの考えるような私的言語になっている。さらに、「S」が他の言葉で、例えば「マノメーターが上がったときに私が受けた感 覚」というように定義できないばあいを推定する。すると、公共的言語の中に「S」が位置づけられ、その場合「S」が私的言語であらわせないことになる。 [6] 感覚と象徴に注目して、「ある種の直示的定義」を「S」に適用する場合が想定される。『哲学探究』の最初のほうでヴィトゲンシュタインは直示的定義の有効 性を攻撃している[7]。彼は、二つの木の実を指さして「これは『2』だと言える」と言う人物の場合を想定する。これを聞いた人がこれを木の実の種類や 数、あるいはコンパスの指す向きなどではなく物品の数と結びつけて考えるということはどのように起こるのだろうか?一つの結論としては、これは、関係する ためには直示的定義が「生活形式」に必然的に伴う過程や文脈を理解していることが前提とされるということだとされる[8]。もう一つの結論としては、「直 示的定義は『あらゆる』場合に異なった意味で解釈され得る」ということがある[9]。 「S」の感覚の事例を出して、ヴィトゲンシュタインは、正しい「ように見える」ことは正しい「ことである」(し、このことは「正しさ」について語ることは できないことを端的に示している)ので、以上のような直示的定義の正しさの基準は存在しないと主張した[5]。私的言語を否定する正確な根拠に関しては議 論がなされてきた。一つの主張として「記憶懐疑論」と呼ばれるものがあるが、それは、ある人が感覚を間違って「記憶」すれば、その人は結果として「S」と 言う言葉を間違って使うことになるというものである。「意味懐疑論」というもう一つの立場では、こういうやり方で定義される言葉の「意味」を人は決して知 ることはないというものである。 一方の一般的な解釈は、人が感覚を間違って覚える可能性があり、それゆえに人はそれぞれの場合に「S」を使う確かな「基準」を持ちえないというものである [10] 。だから、例えば、私はある日「あの」感覚に注目し、それを「S」という象徴に結び付けたかもしれない。しかしその次の日、私は「今」持っている感覚が昨 日のものと同じであるかを知る基準を記憶の他に持たない。そして私は記憶を欠落しているかもしれないので、私には今持っている感覚が実際に「S」であるか を知る確かな基準が何もない。 しかしながら、記憶懐疑論は公共的言語にも適用できるので、私的言語だけに対する攻撃たりえないとして批判されてきた。一人の人が間違って記憶しうるなら ば、複数の人が記憶を間違えるということも完全に可能である。だから、記憶懐疑論は公共的言語に与えられう直示的言語にも同じ効果を及ぼすことができる。 例えば、ジムとジェニーがある日どこか独特な木を「T」と呼ぶことに決めたかもしれない。しかし次の日に「二人とも」自分たちがどの木に名づけたか記憶違 いをする。彼らが完全に記憶に頼っており、木の位置を書き記したり誰かほかの人に教えたりしていなかったならば、一人の人が「S」を直示的に定義した場合 と同様の困難が現れるであろう。そのため、こういった場合であれば私的言語に対して提出された主張が公共的言語にも同じく適用されるであろう。 ●意味懐疑論 もう一つの解釈として、例えばアンソニー・ケニーが提出した報告[11]で述べられているのだが、私的な直示的定義に関する問題は間違って記憶されること だけでなく、そういった定義は有意味な言明を導かないというものもあるということがある。 公共的言語における直示的定義の場合を考えてみよう。ジムとジェニーがある日どこか独特な木を「T」と呼ぶことに決めたかもしれない。しかし次の日に「二 人とも」自分たちがどの木に名づけたか記憶違いをする。この、通常の言語の場合は、「これが僕たちが昨日『T』と名付けた木だろうか?」と言う問いは意味 を成す。だから、人は生活形式の他の部分、ひょっとしたら論議に訴えることができる。「これが森の中のたった一本のオークだ。『T』はオークだった。だか らこれが『T』だ」というように。 日常的な直示的定義は公共的言語に埋め込まれていて、そのため言語がその中で生じる生活形式の中に埋め込まれている。公共的な生活形式に参加することで起 こったことを正すことができるようになる。つまり、公共的言語の場合には直示的に定義された言葉を別の方法で確かめることができる。私たちは直示的定義を 多かれ少なかれはっきりさせることで私たちの「T」という新しい名前の用法の正当性をしめすことができる。 しかし「S」の場合はこうはいかない。「S」は私的言語の一部だから「S」のはっきりした定義を与えることはできないことを思い起こそう。唯一の「可能 な」定義は「S」を「あの」感覚と結びつけるという私的・直示的なものである。しかしそれは「まさに問われているそのもの」である。「誰かがこういってい るのを想像しよう。『でも僕は自分の身長がわかっているんだ!』そしてそれを示すために自身の手を頭頂に乗せる」[12]。 ヴィトゲンシュタインの著作に繰り返し現れる主題として、意味を成す言葉や発話は疑い得るに違いないということがある。ヴィトゲンシュタインにとって、 トートロジーは意味をなさず、何も言っておらず、また疑いを挟み得ない。しかしさらに、他のいかなる発話も疑いを挟み得ないとすれば、その発話は無意味で あるに違いない。ラッシュ・リーズは、ヴィトゲンシュタインの講義の記録に、一方で物理的対象の実在性について議論しつつこう書いている。: 我々は「p → p」のようなトートロジーを記述する際に何かを同じように把握している。我々はそういった印象をまとめて疑い得ないように何かを把握している―たとえ意味 が疑いとともに消滅するとしても[13]。 ケニーの述べるところでは、「何かを『S』だと『間違って』考えるためにも、私は『S』の意味を知っていなければならない。また、これはヴィトゲンシュタ インの主張することが日常言語では不可能だということである」[14]。私的な直示的定義「の他に」「S」の意味(あるいは用法)を確かめる方法がないの で、「S」が意味すること「を知る」のは不可能である。意味は疑いとともに消滅する。 ヴィトゲンシュタインはさらに進んで、左手が右手に金銭をあげるという類推を用いている[15]。物理的な動きは存在するが、取引としては贈与の内に数え られない。同様に。ある人は一方で感覚に注目して「S」と言っているが、実際に名づけという作用が起こってはいない。 ●箱の中のカブトムシ 箱の中のカブトムシはヴィトゲンシュタインが彼が痛みを探求する文脈で紹介した有名な思考実験である[16]。 痛みはいくつかの理由から心の哲学で独特にして極めて重要な位置を占める[17]。一つには、痛みは現れ/実体の区別を崩壊させるように見えることがある [18]。もし事物があなたに赤として現れたなら、それは本当は赤ではないかもしれない。しかしあなたが痛みを感じているようであったなら、それは痛みを 感じているに違いない。同時に、人は他人の痛みを感じることはできないが、彼らの振る舞いや訴えから推測することだけはできる。 私たちが究極的にしかし排他的に知覚することのできるたった一つの心によって感じる特別なクオリアを認めるならば、自己と意識についてのデカルト的な視点 に立つことになる。私たちの意識は、やはり痛みについて、疑うことができないであろう。これに対して、ある人は自身の痛みの究極的な事実の存在は認めるが 他人の痛みについては懐疑論を主張する。あるいは、またある人は行動主義者の立場をとって私たちの感じる痛みは単に神経学的な刺激に振る舞う傾向が伴って いるだけにすぎないと主張する[19]。 ヴィトゲンシュタインは、人がめいめい「カブトムシ」の入った箱を持っているコミュ ニティーを想像するように勧める。「誰も他人の箱の中を見ることはで きず、皆が自分は『自分の』カブトムシを見ることによってのみカブトムシとは何かを知ると言っている」[16]。 これらの人々が「カブトムシ」と言う言葉を使っても、それは何物をも指 示しえない―何故ならばそれぞれの人が箱の中に入れているものが全く異なっているか、箱の中のものが常に変化していたり、箱の中が空だったということが完 全に可能だから。箱の内容はいかなる言語ゲームでも無意味となる。 類推によれば、人が他人の主観的な感覚を経験できないことは問題ではない。そういっ た主観的な感覚について語ることが公共的な経験を通じてできるようにならないならば、その具体的な内容は的外れである。語り得るものは全て、公共的言語で 語ることが可能なものである。 痛みの類推として「カブトムシ」を提供することでヴィトゲンシュタイン は、痛みの事例は本当は哲学者の使用に耐えないと主張している。「すなわち、私たちが『対象と意味』のモデルに則って感覚の印象の文法を解 釈するならば、対象は思考から滑り落ちて無意味になる」[16]。 ●規則に従うこと 一般的に人が従う規則を明文化したもので言語の用法が記述されるが、ヴィトゲンシュタインは相当詳細にこの規則について考えた。彼が、いかなる動作も与え られた規則に従うと言えると主張したことは有名である[20]。彼はジレンマを持ち出してこれを実行した。: これが私たちのパラドックスだった。:どの行動の成り行きも規則と調和すると言えるので、どの行動の成り行きも規則によって正確に決定できない。答えは: どの行動の成り行きも規則と調和すると言えるなら、それらがめいめい規則と矛盾するともいえる。そしてそこには調和も矛盾も存在しない[21]。 ある人はなぜ人が特定の場合に特定の規則に従うのかを説明できる。しかし実践に伴う規則に関するいかなる説明も、循環性を伴わずには規則を伴う言葉を与え られない。ある人は「彼女は規則Rに従ってXを行った」というようなことを言えるのは、聞き手が「彼女は規則R1に従って規則Rに従った」と言わない場合 に限る。聞き手がこう言う場合、さらにある人が「しかしなぜ彼女は規則R1に従ったのか?」と問い、無限に後退することに巻き込まれることになる。説明に は終わりがなければならない。[22] 彼の結論: このことが示すのは、「解釈」では「ない」が、私たちが「規則に従うこと」や「それに反すること」と実際の事例で呼ぶものの中で展開される規則を把握する 方法は存在する[23]。 そのため規則に従うことは実際に可能である。そしてさらに、人は自分が規則に従うことも従うのに失敗することもあると思っているので、人が規則に従ってい るという「考え」は規則に従うことと同一ではない。それゆえ、規則に従うことは私的な活動ではありえない[24]。 ●クリプキの解釈 1982年にソール・クリプキは著書『ウィトゲンシュタインのパラドックス──規則・私的言語・他人の心』でこの手の主張に対する新しくて革新的な説明を 発表した[25]。クリプキはこのパラドックスを201章で『哲学探究』の中心的な問題であるとして議論している。彼はこのパラドックスを発展させてグ ルーのパラドックスを作り上げ、帰納と同様に意味の懐疑論に陥ると主張した [26]。彼は、自身が「クワス算」(記号は⊕)と呼ぶ新しい足し算の形式を提起した。これは、足した結果が57より大きくなる場合を除いて全ての場合で 「プラス」と同一である。 そして彼は、誰もが私が「プラス」を意味すると思ったよりも前にそれを知ることができたならば、私は実際には「クワス」を意味することはないであろうと問 いかけている。彼は、自分の主張によって「我々が形作る新しい適用は暗闇の中の跳躍である。今ある意向は我々が選ぶいかなるものとも調和するよう解釈する ことができるだから調和も矛盾も存在しない[27]」ということが示されると主張している。 クリプキの説明はヴィトゲンシュタインの考えに忠実ではないと考える評論家もおり[28]、結果的に「クリプケンシュタイン」と言われている。 |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆