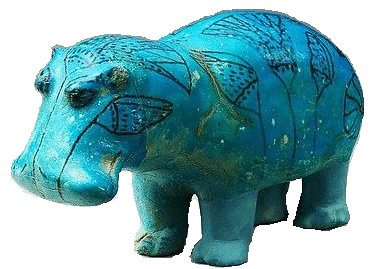
理由と人格
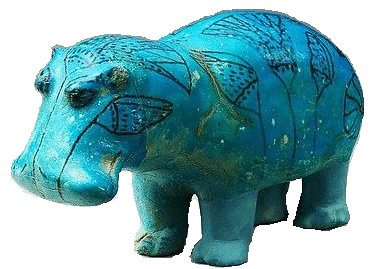
★デレク・パーフィット(1942-2017)については、こちらを参照してください。
☆ Derek Parfit, Reasons and Persons (Oxford University Press, 1984)「“私たちは自分たちが信じているものではない。それはいかにしてか” 私たちの実践的合理性は、帰結主義、自己利益説、常識道徳のどれによっ ているのか? 奇抜な思考実験を通して道徳理論が非人格的になるべきことを提唱しつつ、新領域を切り拓く。この1冊でパーフィットの名を世に知らしめた歴 史的名著。」人格の同一性、道徳性、合理性などにまつわる私たちの奥深い信念を揺るがす、現代倫理学からの挑戦。20世紀後半の最重要哲学書(書肆による説明)。
| Ethics and rationality Reasons and Persons Main article: Reasons and Persons In Reasons and Persons, Parfit suggested that nonreligious ethics is a young and fertile field of inquiry. He asked questions about which actions are right or wrong and shied away from meta-ethics, which focuses more on logic and language. In Part I of Reasons and Persons Parfit discussed self-defeating moral theories, namely the self-interest theory of rationality ("S") and two ethical frameworks: common-sense morality and consequentialism. He posited that self-interest has been dominant in Western culture for over two millennia, often making bedfellows with religious doctrine, which united self-interest and morality. Because self-interest demands that we always make self-interest our supreme rational concern and instructs us to ensure that our whole life goes as well as possible, self-interest makes temporally neutral requirements. Thus it would be irrational to act in ways that we know we would prefer later to undo. As an example, it would be irrational for fourteen-year-olds to listen to loud music or get arrested for vandalism if they knew such actions would detract significantly from their future well-being and goals (such as having good hearing, a good job, or an academic career in philosophy). Most notably, the self-interest theory holds that it is irrational to commit any acts of self-denial or to act on desires that negatively affect our well-being. One may consider an aspiring author whose strongest desire is to write a masterpiece, but who, in doing so, suffers depression and lack of sleep. Parfit argues that it is plausible that we have such desires which conflict with our own well-being, and that it is not necessarily irrational to act to fulfill these desires. Aside from the initial appeal to plausibility of desires that do not directly contribute to one's life going well, Parfit contrived situations where self-interest is indirectly self-defeating—that is, it makes demands that it initially posits as irrational. It does not fail on its own terms, but it does recommend adoption of an alternative framework of rationality. For instance, it might be in my self-interest to become trustworthy to participate in mutually beneficial agreements, even though in maintaining the agreement I will be doing what will, other things being equal, be worse for me. In many cases self-interest instructs us precisely not to follow self-interest, thus fitting the definition of an indirectly self-defeating theory.[11]: 163–165 Parfit contended that to be indirectly individually self-defeating and directly collectively self-defeating is not fatally damaging for S. To further bury self-interest, he exploited its partial relativity, juxtaposing temporally neutral demands against agent-centred demands. The appeal to full relativity raises the question whether a theory can be consistently neutral in one sphere of actualisation but entirely partial in another. Stripped of its commonly accepted shrouds of plausibility that can be shown to be inconsistent, self-interest can be judged on its own merits. While Parfit did not offer an argument to dismiss S outright, his exposition lays self-interest bare and allows its own failings to show through.[citation needed] It is defensible, but the defender must bite so many bullets that they might lose their credibility in the process. Thus a new theory of rationality is necessary. Parfit offered the "critical present aim theory", a broad catch-all that can be formulated to accommodate any competing theory. He constructed critical present aim to exclude self-interest as our overriding rational concern and to allow the time of action to become critically important. But he left open whether it should include "to avoid acting wrongly" as our highest concern. Such an inclusion would pave the way for ethics. Henry Sidgwick longed for the fusion of ethics and rationality, and while Parfit admitted that many would avoid acting irrationally more ardently than acting immorally, he could not construct an argument that adequately united the two. Where self-interest puts too much emphasis on the separateness of persons, consequentialism fails to recognise the importance of bonds and emotional responses that come from allowing some people privileged positions in one's life. If we were all pure do-gooders, perhaps following Sidgwick, that would not constitute the outcome that would maximise happiness. It would be better if a small percentage of the population were pure do-gooders, but others acted out of love, etc. Thus consequentialism too makes demands of agents that it initially deemed immoral; it fails not on its own terms, for it still demands the outcome that maximises total happiness, but does demand that each agent not always act as an impartial happiness promoter. Consequentialism thus needs to be revised as well. Self-interest and consequentialism fail indirectly, while common-sense morality is directly collectively self-defeating. (So is self-interest, but self-interest is an individual theory.) Parfit showed, using interesting examples and borrowing from Nashian games, that it would often be better for us all if we did not put the welfare of our loved ones before all else. For example, we should care not only about our kids, but everyone's kids. |
倫理と合理性 理由と人格(「理性と人格」※以下では「理由と人」とも記載) 詳細は「 理由と人格」を参照 『 理由と人格』において、パーフィットは非宗教的な倫理はまだ歴史が浅く、研究の余地が大きい分野であると示唆した。彼は、どのような行動が正しいか、ある いは間違っているかについて疑問を投げかけ、論理や言語に重点を置くメタ倫理学からは 距離を置いた。 パー フィットは『 理由と人格』の第一部で、自己矛盾した道徳理論、すなわち合理性の利己主義理論(「S」)と、2つの倫理的枠組み、すなわち常識道徳と 帰結主 義について論じている。パーフィットは、自己利益は2千年以上にわたって西洋文化において支配的であり、しばしば宗教的教義と結びついて自己利益と道徳 性を一体化させてきたと主張した。自己利益は、常に自己利益を最高の合理的な関心事とし、人生全体が可能な限りうまくいくようにすべきであると要求してい るため、自己利益は時間的に中立的な要求である。したがって、後に元に戻したいと考えるような行動を取ることは不合理である。 例えば、14歳の若者が、将来の幸福や目標(例えば、聴力が良好であること、良い仕事に就くこと、哲学の学問的キャリアなど)を著しく損なうと知りなが ら、大音量の音楽を聴いたり、破壊行為で逮捕されたりするのは不合理である。 とりわけ、利己主義理論では、自己否定行為や、幸福に悪影響を及ぼすような欲求に従うことは非合理的であると主張している。例えば、偉大な作品を書くこと を強く望む作家志望者がいるとする。しかし、そうすることで、うつ病や睡眠不足に悩まされる。パーフィットは、私たちが自身の幸福に反するような欲求を抱 くことはあり得ることであり、そうした欲求を満たすために行動することは必ずしも非合理的ではないと主張している。 自分の生活がうまくいくことに直接貢献しない欲望の妥当性という当初の主張はさておき、パーフィットは、利己主義が間接的に自己矛盾を引き起こす状況を作 り出した。つまり、当初は非合理的と想定していた要求を突きつけるのである。利己主義は、その主張自体が間違っているわけではないが、合理性の代替フレー ムワークの採用を推奨している。例えば、相互に有益な合意に参加するにあたり、信頼に足る人物となることは、私にとって利益となるかもしれない。合意を維 持するにあたり、他の条件が同じであれば、私にとって不利となることを行うことになるが。多くの場合、利己主義は、まさに利己主義に従わないよう私たちに 指示する。したがって、間接的に自己を敗北させる理論の定義に当てはまる。[11]: 163–165 パーフィットは、間接的に個人にとって自己矛盾であり、直接的に集団にとって自己矛盾であることは、Sにとって致命的なダメージではないと主張した。利己 主義をさらに葬り去るために、彼は利己主義の部分的相対性を活用し、時間的に中立的な要求とエージェント中心の要求を並置した。完全な相対性への訴えは、 理論が一つの実現の領域では一貫して中立であり、別の領域では完全に部分的であることができるかどうかという疑問を提起する。一般的に受け入れられている 妥当性の仮面を剥ぎ取り、一貫性のないことが示されれば、利己主義はそれ自身の価値で判断される。パーフィットはSを完全に否定する議論は提示していない が、彼の論述は利己主義をむき出しにし、その欠点が露わになる。それは擁護できるが、擁護者は多くの問題に直面し、その過程で信頼性を失う可能性がある。 したがって、合理性の新たな理論が必要である。パーフィットは、あらゆる競合する理論を包含できる包括的な理論として「クリティカル・プレゼント・エイム 理論」を提示した。パーフィットは、利己主義を最優先の合理的な関心事から除外し、行動のタイミングを極めて重要なものとするためにクリティカル・プレゼ ント・エイムを構築した。しかし、パーフィットは、最優先の関心事として「誤った行動を避けること」を含めるべきかどうかについては明確にしなかった。そ のような含みがあれば、倫理への道が開かれる。ヘンリー・シジウィックは倫理と合 理性の融合を切望し、パーフィットも多くの人が非道徳的な行動よりも非合 理的な行動を避けることを強く望むことを認める一方で、この2つを適切に結びつける論拠を構築することはできなかった。 利己主義が人格の分離を過度に重視するあまり、帰結主義は、人生において一部の人々に 特権的な地位を与えることによって生まれる絆や感情的な反応の重要性を認識できない。もし私たちが皆、シジウィックに従う純粋な善人であったとしても、そ れは幸福を最大化する結果にはなら ないだろう。人口のほんの一部が純粋な善人であり、他の人々は愛情などに基づいて行動する方が望ましい。このように、帰結主義も当初は不道徳とみなされて いた行為者に要求を課す。それは、依然として総体的な幸福を最大化する結果を要求しているため、自身の条件を満たしていないわけではないが、各行為者が常 に公平な幸福の推進者として行動することを要求している。したがって、帰結主義も修正する必要がある。 利己主義と結果主義は間接的に失敗するが、常識的な道徳は直接的に集団的に自らを破滅させる。(利己主義も同様だが、利己主義は個人の理論である。)パー フィットは興味深い例を挙げ、ナッシュのゲーム理論を援用しながら、愛する者の幸福を何よりも優先しない方が、私たち全員にとってより良い結果になる場合 が多いことを示した。例えば、私たちは自分の子供だけでなく、すべての子供たちのことを考えるべきである。 |
| Reasons and Persons |
『理 由と人格』 |
| Reasons and Persons is a 1984
book by the philosopher Derek Parfit, in which the author discusses
ethics, rationality and personal identity. It is divided into four parts, dedicated to self-defeating theories, rationality and time, personal identity and responsibility toward future generations. |
『Reasons and Persons』は、哲学者デレク・パーフィットが1984年に発表した著書であり、著者はこの本の中で倫理、合理性、個人の同一性について論じている。 この本は4つの部分に分かれており、自己矛盾理論、合理性と時間、個人 の同一性、そして将来の世代に対する責任にそれぞれ捧げられている。 |
| 1. Self-defeating theories Part 1 argues that certain ethical theories are self-defeating. One such theory is ethical egoism, which Parfit claims is 'collectively self-defeating' due to the prisoner's dilemma, though he does not believe this is sufficient grounds to reject the theory. Ultimately, Parfit does reject "common sense morality" on similar grounds. In this section, Parfit does not explicitly endorse a particular view; rather, he shows what the problems of different theories are. His only positive endorsement is of "impersonal ethics" – impersonality being the common denominator of the different parts of the book. |
1. 自己矛盾理論 第1部では、特定の倫理理論は自己矛盾をはらんでいると論じている。そ の理論のひとつに倫理的利己主義があるが、パーフィットは、これは「囚人のジレン マ」により「全体として自己矛盾をはらんでいる」と主張している。ただし、パーフィットは、これがその理論を否定するのに十分な根拠であるとは考えていな い。最終的には、パーフィットは同様の理由で「常識的な道徳」を否定している。 この章では、パーフィットは特定の見解を明確に支持することはせず、む しろ、さまざまな理論の問題点を示している。彼が唯一肯定的に支持しているのは「非人格的倫理」であり、非人格性は本書のさまざまな部分に共通する要素で ある。 |
| 2. Rationality and time Part 2 focuses on the relationship between rationality and time, dealing with questions such as: should we take into account our past desires?, should I do something I will regret later, even if it seems a good idea now?, and so on. Parfit's main purpose in Part 2 is to make an argument against self-interest theory. Self-interest theorists consider the differences between different persons to be extremely important, but do not consider the differences between the same person at different times to be important at all. Parfit argues that this makes self-interest theory vulnerable to attack from two directions. It can be compared to morality on one side, and 'present-aim theory' on the other. Parfit argues that our present aims can sometimes conflict with our long term self-interest. Arguments that a self-interest theorist uses to explain why it is irrational to act on such aims, can be turned against the self-interest theorist, and used as arguments in favor of morality. Conversely, arguments that a self-interest theorist uses against morality could also be used as arguments in support of 'present-aim' theory. |
2. 合理性と時間 第2部では、合理性と時間の関係に焦点を当て、次のような疑問を取り 扱っている。過去の欲望を考慮すべきか? 今良いと思えることであっても、後で後悔するようなことをすべきか? など。 パーフィットが第2部で主眼を置いているのは、利己主義理論に対する反 論である。利己主義理論の支持者たちは、異なる人々の間の相違は極めて重要であると 考えるが、同じ人物の異なる時点における相違はまったく重要ではないと考える。パーフィットは、このことが利己主義理論を2つの方向からの攻撃に対して脆 弱にしていると論じている。それは一方では道徳と比較することができ、他方では「現在志向理論」と比較することができる。パーフィットは、私たちの現在の 目的が長期的な自己利益と対立することがあると論じている。自己利益理論家が、そのような目的に基づいて行動することがなぜ非合理的であるかを説明するた めに用いる論拠は、自己利益理論家に対して向けられ、道徳を支持する論拠として用いられる可能性がある。逆に、自己利益理論家が道徳に対して用いる論拠 は、「現在の目的」理論を支持する論拠として用いられる可能性もある。 |
| 3. Personal identity Part 3 argues for a reductive account of personal identity; rather than accepting the claim that our existence is a deep, significant fact about the world, Parfit's account of personal identity is like this: At time 1, there is a person. At a later time 2, there is a person. These people seem to be the same person. Indeed, these people share memories and personality traits. But there are no further facts in the world that make them the same person. Parfit's argument for this position relies on our intuitions regarding thought experiments such as teleportation, the fission and fusion of persons, gradual replacement of the matter in one's brain, gradual alteration of one's psychology, and so on. For example, Parfit asks the reader to imagine entering a "teletransporter," a machine that puts you to sleep, then destroys you, breaking you down into atoms, copying the information and relaying it to Mars at the speed of light. On Mars, another machine re-creates you (from local stores of carbon, hydrogen, and so on), each atom in exactly the same relative position. Parfit poses the question of whether or not the teletransporter is a method of travel—is the person on Mars the same person as the person who entered the teletransporter on Earth? Certainly, when waking up on Mars, you would feel like being you, you would remember entering the teletransporter in order to travel to Mars, you would even feel the cut on your upper lip from shaving this morning. Then the teleporter is upgraded. The teletransporter on Earth is modified to not destroy the person who enters it, but instead it can simply make infinite replicas, all of whom would claim to remember entering the teletransporter on Earth in the first place. Using thought experiments such as these, Parfit argues that any criteria we attempt to use to determine sameness of person will be lacking, because there is no further fact. What matters, to Parfit, is simply "Relation R," psychological connectedness, including memory, personality, and so on. Parfit continues this logic to establish a new context for morality and social control. He cites that it is morally wrong for one person to harm or interfere with another person and it is incumbent on society to protect individuals from such transgressions. That accepted, it is a short extrapolation to conclude that it is also incumbent on society to protect an individual's "Future Self" from such transgressions; tobacco use could be classified as an abuse of a Future Self's right to a healthy existence. Parfit resolves the logic to reach this conclusion, which appears to justify incursion into personal freedoms, but he does not explicitly endorse such invasive control. Parfit's conclusion is similar to David Hume's bundle theory, and also to the view of the self in Buddhism's Skandha, though it does not restrict itself to a mere reformulation of them. For besides being reductive, Parfit's view is also deflationary: in the end, "what matters" is not personal identity, but rather mental continuity and connectedness. |
3. 個人の同一性 第3部では、個人の同一性に関する還元的な説明を主張している。すなわ ち、私たちの存在が世界に関する深い、重要な事実であるという主張を受け入れるのではなく、パーフィットの個人の同一性に関する説明は次のようである。 時間1において、ある人物がいる。 それより後の時間2において、またある人物がいる。 これらの人物は同一人物であるように見える。 実際、これらの人物は記憶や性格的特徴を共有している。 しかし、それらを同一人物とするような事実は、この世界にはこれ以上存在しない。 パーフィットのこの立場を支持する論拠は、テレポーテーション、人の分 裂と融合、脳の物質の段階的な置き換え、心理の段階的な変化など、思考実験に関する 我々の直感に基づいている。例えば、パーフィットは読者に「テレトランスポーター」に入ることを想像するように求めている。テレトランスポーターとは、乗 る人を眠らせ、その後破壊し、原子レベルに分解し、その情報をコピーして光速で火星に転送する機械である。火星では、別の機械が(炭素や水素などの現地の 資源から)乗る人を再構成し、各原子はまったく同じ相対位置に置かれる。パーフィットは、テレポーターが移動手段となりうるのかという疑問を投げかけてい る。すなわち、火星にいる人物は、地球でテレポーターに入った人物と同じ人物なのか? もちろん、火星で目覚めたとき、あなたは自分が自分であると感じ、火星に移動するためにテレポーターに入ったことを思い出し、今朝ひげを剃ったときにでき た上唇の切り傷さえ感じるだろう。 すると、テレポーターがアップグレードされる。地球のテレポーターは、 乗り込んだ人間を破壊しないように改良され、代わりに無限の複製を簡単に作り出すことができるようになる。その複製は皆、そもそも地球のテレポーターに 乗ったことを覚えていると主張するだろう。 パーフィットは、このような思考実験を用いて、同一性を決定する基準として用いるものはすべて欠如していると 主張する。なぜなら、それ以上の事実は存在しないからだ。パーフィットにとって重要なのは、単に「関係R」、すなわち記憶や性格などの心理的なつながりで ある。 パーフィットは、この論理をさらに推し進め、道徳と社会統制の新たなコ ンテクストを確立する。パーフィットは、ある人物が他の人物に危害を加えたり干渉し たりすることは道徳的に間違っており、そのような侵害から個人を守ることは社会の義務であると主張する。この考えを受け入れれば、社会には個人の「未来の 自己」をそのような侵害から守る義務があるという結論を導くのは容易である。 たばこの使用は、健康的な生活を送るという未来の自己の権利の侵害とみなすことができる。パーフィットは、この結論に達するための論理を展開しているが、 これは個人の自由への侵害を正当化しているように見える。しかし、パーフィットはこのような侵害的な管理を明確に支持しているわけではない。 パーフィットの結論は、デイヴィッド・ヒュームの束理論や仏教のスカン ダにおける自己観にも似ているが、それらを単に再定義するにとどまらない。パー フィットの見解は還元論的であるだけでなく、デフレ的でもある。つまり、結局のところ、「重要なこと」は個人の同一性ではなく、むしろ精神の連続性とつな がりなのである。 |
| 4. Future generations Part 4 deals with questions of our responsibility towards future generations, also known as population ethics. It raises questions about whether it can be wrong to create a life, whether environmental destruction violates the rights of future people, and so on. One question Parfit raises is this: given that the course of history drastically affects what people are actually born (since it affects which potential parents actually meet and have children; and also, a difference in the time of conception will alter the genetic makeup of the child), do future persons have a right to complain about our actions, since they likely wouldn't exist if things had been different? This is called the non-identity problem. Another problem Parfit looks at is the mere addition paradox, which supposedly shows that it is better to have a lot of people who are slightly happy, than a few people who are very happy. Parfit calls this view "repugnant", but says he has not yet found a solution. |
4. 未来の世代(→将来の世代に対する責任) 第4部では、人口倫理(population ethics)とも呼ばれる、未来の世代に対する私たちの責任に関する問題を取り扱う。生命を創造すること が間違っているかどうか、環境破壊が未来の人々の権利を侵害するかどうか、などといった問題が提起される。 パーフィットが提起する問題のひとつは、歴史の流れが実際に生まれる人 々に大きな影響を与える(実際に会って子供を作る可能性のある両親に影響を与えるた め、また、受胎時期の違いが子供の遺伝的構成を変えるため)ことを踏まえると、もし状況が違っていたら存在しなかったであろう未来の人々は、我々の行動に 対して不満を述べる権利があるのだろうか? これは非同一性問題と呼ばれる。 パーフィットが取り上げているもう一つの問題は、単なる足し算のパラ ドックスであり、これはおそらく、非常に幸福な少数の人々よりも、少し幸せな多くの人 々の方が望ましいことを示すものである。パーフィットはこれを「嫌悪すべき」見解と呼んでいるが、まだ解決策を見いだせていないと述べている。 |
| Reception Bernard Williams described Reasons and Persons as "brilliantly clever and imaginative", and commended it as part of a wave of work in analytic philosophy that deals with concrete moral problems rather than abstract meta-ethics.[1] Philip Kitcher wrote in his review of Parfit's On What Matters that Reasons and Persons "was widely viewed as an outstanding contribution to a cluster of questions in metaphysics and ethics".[2] Peter Singer included Reasons and Persons on a top ten list of favourite books in The Guardian, stating that "Parfit's penetrating thought and spare prose make this one of the most exciting, if challenging, works by a contemporary philosopher".[3] Writing for The New York Review of Books, the philosopher P.F. Strawson gave the book a positive review, stating "Very few works in the subject can compare with Parfit’s in scope, fertility, imaginative resource, and cogency of reasoning".[4] In an interview, David Chalmers said that he "loved" Reasons and Persons, saying that it gave him a "sense of how powerful analytic philosophy can be when done clearly and accessibly."[5] |
評価 バーナード・ウィリアムズは『Reasons and Persons』を「見事なほどに賢く、想像力に富む」と評し、抽象的なメタ倫理学よりも具体的な道徳問題を扱う分析哲学の潮流の一部として高く評価し た。[1] フィリップ・キッチァーは、パーフィットの『On What Matters』の書評で、『Reasons and Persons』は「形而上学と倫理学における一連の問いに対する卓越した貢献として広く受け止められている」と書いた。[2] ピーター・シンガーはガーディアン紙で『Reasons and Persons』をお気に入りの本トップ10に挙げ、「パーフィットの鋭い洞察力と簡潔な文章は、この本を現代の哲学者による最も刺激的で、挑戦的な作品 のひとつにしている」と述べている。 ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス誌に寄稿した哲学者P.F.ス トローソンは、この本に肯定的な評価を与え、「このテーマの作品で、パーフィトの作品に匹敵するものは、その範囲、豊かさ、想像力、そして論理の説得力に おいてほとんどない」と述べた。[4] インタビューの中で、デイヴィッド・チャーマーズは『理性と人間(理由 と人)』を「愛している」と述べ、この本は「明晰かつ平易に書かれた分析哲学がどれほど強力になり得るかを感じさせてくれる」と語っている。[5] |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Reasons_and_Persons | |
***
| 序 謝辞 凡例 I 自己破壊的諸理論 |
|
| 第一章 間接的に自己破壊的な諸理論 |
|
| 1 自己利益説 2 〈自己利益説〉はいかにして間接的に自己破壊的でありうるのか 3 〈自己利益説〉はわれわれに対して、決して自己否定的であってはならないと命ずるか? 4 〈自己利益説〉はなぜそれ自体の尺度において失敗しないのか 5 自らを不合理に行動させることは合理的でありうるか? 6 われわれは不合理に行動するのを避けられないということを〈自己利益説〉が意味するのはいかにしてか 7 〈自己利益説〉が道徳と衝突するときに〈自己利益説〉を斥ける議論 8 この議論はなぜ失敗するのか 9 〈自己利益説〉はいかにして自己抹消的かもしれないのか 10 〈帰結主義〉はいかにして間接的に自己破壊的なのか 11 〈帰結主義〉はなぜそれ自体の尺度において失敗しないのか 12 幻想の倫理 13 集団的帰結主義 14 責められない不正行為 15 不正に行動するのを避けることは不可能か? 16 自らを不正に行動させることは正当でありうるか? 17 〈帰結主義〉はいかにして自己抹消的かもしれないのか 18 硬直性を想定する反論 19 合理的であることや道徳的であることは単なる手段でありうるか? 20 いくつかの結論 |
|
| 第二章 実践的ディレンマ |
|
| 21 なぜ〈帰結主義〉は直接的に自己破壊的ではありえないのか 22 理論はいかにして自己破壊的でありうるのか 23 〈因人のディレンマ〉と公共財 24 実践的問題とその諸解決 |
|
| 第三章 道徳数学における五つの誤り |
|
| 25 全体のシェア説 26 行為の集合の影響の無視 27 小さなチャンスの無視 28 小さな、あるいは気がつかないほどの影響の無視 29 気がつかないほどの害や利益はありうるか? 30 多元的決定 31 合理的利他主義 |
|
| 第四章 直接的に自己破壊的な諸理論 |
|
| 32 〈因人のディレンマ〉において、〈自己利益説〉はそれ自体の尺
度で失敗するか? 33 道徳の別の悪い弁護 34 時刻間ディレンマ 35 〈自己利益説〉の悪い弁護 36 〈常識道徳〉はいかにして直接的に自己破壊的か 37 道徳理論の五つの部分 38 われわれはいかにして〈常識道徳〉を、それが自己破壊的にならないように改訂できるか 39 われわれはなぜ〈常識道徳〉を改訂すべきなのか 40 もっと単純な改訂 |
|
| 第五章 二つの可能性 |
|
| 41 〈常識道徳〉と〈帰結主義〉との間隔を縮小する 42 第一の可能性 43 なされるべき仕事 44 第二の可能性 |
|
| II 合理性と時間 |
|
| 第六章 〈自己利益説〉に対する最善の反論 |
|
| 45 現在目的説 46 欲求が内在的に不合理だとか、合理的に要求されるということがありうるか? 47 三つの競合する説 48 心理的エゴイズム 49 〈自己利益説〉と道徳 50 私の第一の議論 51 〈自己利益説論者〉の第一の回答 52 時間的中立性はなぜ〈自己利益説〉と〈現在目的説〉の間の争点ではないのか |
|
| 第七章 完全な相対性への訴え |
|
| 53 〈自己利益説論者〉の第二の回答 54 シジウィックの示唆 55 〈自己利益説〉はどうして不完全にしか相対的でないのか 56 シジウィックはいかにして道に迷ったのか 57 形式的レベルに適用されたこの訴え 58 他の主張に適用されたこの訴え |
|
| 第八章 時間への異なる態度 |
|
| 59 自己の過去の欲求に何の重みも与えないのは不合理か? 60 価値判断あるいは理想に依存する欲求 61 ただの過去の欲求 62 自分の遠い未来を気にかける程度が小さくなるのは不合理か? 63 自殺的な議論 64 過去あるいは未来の苦しみ 65 因果関係の方向 66 時間的中立性 67 なぜわれわれは未来へのバイアスを持つべきでないのか 68 時間の経過 69 非対称性 70 いくつかの結論 |
|
| 第九章 われわれはなぜ〈自己利益説〉を斥けるべきなのか |
|
| 71 将来の後悔への訴え 72 プロクシムスの敗北はなぜ〈自己利益説〉の勝利にならないのか 73 首尾一貫性の欠如への訴え 74 いくつかの結論 |
|
| III 人格の同一性 |
|
| 第十章 われわれは自分自身を何であると信じているのか |
|
| 75 〈単純な遠隔輸送〉と〈分岐線ケース〉 76 性質的同一性と個数的同一性 77 人格の同一性の物理的基準 78 心理的基準 79 他の諸見解 |
|
| 第十一章 われわれは自分たちが信じているものではない。それはいかに
してか |
|
| 80 心理的継続性は人格の同一性を前提とするか? 81 経験の主体 82 〈非還元主義的見解〉はいかにして真でありうるか 83 〈心理的基準〉に反対するウィリアムズの議論 84 心理的スペクトラム 85 物理的スペクトラム 86 混合的スペクトラム |
|
| 第十二章 われわれの同一性は重要なことではない。それはなぜか |
|
| 87 分割された心 88 何が意識の統一性を説明するのか? 89 私が分裂するとき何が起きるのか? 90 私が分裂するとき何が重要なのか? 91 二つの説得的な要求を満たしうる同一性基準が存在しないのはなぜか 92 ヴィトゲンシュタインとブッダ 93 私は本質的には私の脳か? 94 真実の見解は信じられるか? |
|
| 第十三章 重要なこと |
|
| 95 自我からの解放 96 身体の継続性 97 分岐線ケース 98 シリーズ―人格 99 私はタイプかトークンか? 100 部分的生存 101 引き続く自我 |
|
| 第十四章 人格の同一性と合理性 |
|
| 102 極端な主張 103 〈自己利益説〉に反対するよりよい議論 104 〈自己利益説論者〉の反論 105 〈古典的自己利益説〉の敗北 106 無分別の非道徳性 |
|
| 第十五章 人格の同一性と道徳 |
|
| 107 自律とパターナリズム 108 生の二つの境界 109 功績 110 コミットメント 111 人格の別個性と配分的正義 112 功利主義見解の三つの説明 113 原理の適用範囲を変える 114 原理の重みを変える 115 誰か別の者に利益を与えるだけのために誰かに不利益を負わせるのは正当でありうるか? 116 〈平等原理〉に与える重みを小さくする議論 117 もっと極端な議論 118 いくつかの結論 |
|
| IV 未来の世代 |
|
| 第十六章 非同一性問題 |
|
| 119 実際にはわれわれの同一性は、われわれがいつ受胎されたかに
依存している。それはいかにしてか 120 三種類の選択 121 われわれは未来の人々の利益にどれだけの重みを与えるべきか? 122 ある少女の子供 123 生の質を低下させることが誰にとっても悪化にならないかもしれない。それはいかにしてか 124 権利への訴えかけはなぜこの問題を解決できないのか 125 非同一性の事実は道徳上の相違をもたらすか? 126 遠い未来において予言できる破局を引き起こすこと 127 いくつかの結論 |
|
| 第十七章 いとわしい結論 |
|
| 128 もっと多くの人々がいる方がよいか? 129 現存する人々に及ぼす人口増加の影響 130 人口過剰 131 いとわしい結論 |
|
| 第十八章 ばかげた結論 |
|
| 132 いわゆる〈非対称性〉 133 理想的契約の方法はなぜ解決を提供しないのか 134 狭い人格影響的原理 135 われわれはなぜこの原理に訴えられないのか 136 二つの広い人格影響的原理 137 可能な諸説 138 受苦の総計 139 〈無価値レベル〉への訴え 140 辞書的見解 141 いくつかの結論 |
|
| 第十九章 単純追加パラドックス |
|
| 142 単純追加 143 われわれはなぜ〈平均原理〉を斥けるべきなのか 144 われわれはなぜ不平等への訴えを斥けるべきなのか 145 〈パラドックス〉の第一ヴァージョン 146 われわれはまだ〈いとわしい結論〉を受容するように強いられていない。それはなぜか 147 〈悪いレベル〉への訴え 148 〈パラドックス〉の第二ヴァージョン 149 〈パラドックス〉の第三ヴァージョン |
|
| 最終章 |
|
| 150 非人格性 151 議論の別々の種類 152 われわれは私の結論を歓迎すべきか、それとも嘆くべきか? 153 道徳的懐疑論 154 人類史も倫理学史も始まったばかりかもしれない。それはどうしてか |
|
| 補 論 |
|
| A ごまかしのない世界 B わたしの弱い結論がいかにして〈自己利益説〉を実際上打ち破るのか C 自己利益に関する諸説と合理性 D ネーゲルの脳 E 最近接継続者図式 F 社会的割引率 G ある人を存在させることはこの人に利益を与えることでありうるか H ロールズ的諸原理 I ある者の生を最もうまく行かせるもの J ブッダの見解 |
|
| 注 訳者解説 倫理学も進歩する 文献表 人名索引 |
|
リ ンク
文 献
そ の他の情報
cc
Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
☆
 ☆
☆