
はじめによんでください
病気と健康の日常的概念の構築主義的理解
Constructivist understanding of everyday concepts of illness and health in Japan
池田光穂・野村一夫・佐藤純一 (c)Mitsuho Ikeda, Kazuo Nomura, Junichi Sato,Dec.17,1997

医療社会学をめぐる状況は近年急速に変化している。それを的確にまとめたイギリ スの医療社会学者B・ターナー(Turner, B.)は「医療の社会学」から「健康と病いの 社会学」20)へと研究の全体像が移行したと指摘している34)。つまり次のような事態 が進行しつつある。
まず医療ならびに医科学の多様化と隣接科学への連携が重要視されるようになって きた。これは医科学内部の広がりと精緻化という内部的な展開と、生命倫理学にみら れるように隣接科学の発達が医療の遂行をより容易にすると同時に、その施行の内容 を社会水準に合わせて質を統制し、社会的合意を得ていくためには不可欠の事態であ った。
このことにより事実、医療の対象領域が広がった。これはサービスの向上という積 極的肯定的な面と、対象領域の肥大と統制力の強化による「医療化」(medicalization )という消極的否定的な面がある。
このような医療にまつわる現象の多様化によって、これを研究対象にする人文社会 科学領域も大きくその学問の方法論ならびに研究のスタイルを変えようとしている。 そのひとつは上に述べたように医療の隣接科学化を通して、多様化する医療に積極的 に関与し、柔軟に対処しようとする動きである。つまり研究対象の変化に即応して、 その方法論や理念を変化させようとしている。その動きの一連の例が冒頭にあげた B・ターナーやネトゥルトン(Nettleton, S.)である。
このような事態は医療人類学の下位領域においても起こりつつあり、その具体的な 例は米国における臨床人類学の理論的発展と、患者の文化的社会的背景を理解する民 族誌的な方法論の定着である。
本研究は、医療の実証的な分析に関する社会科学研究の海外の動向と軌を同じくし ているだけでなく「病気と健康の日常的概念」という新しい研究の認識論的な枠組み を提示する。そのことにより、「健康文化」に関する社会科学研究のための共通の土 台を得ることが可能になる。
1997年1月から12月までの研究期間の間に、次のような一連の作業を遂行した。こ れらの作業により得られた結果をもとにした論考が、以下の「結果と考察」である
(1)構築主義関連文献のみならず、ひろく世界の医療社会学に関する文献を渉猟 し、基本テキストならびに論文を、研究代表者ならびに共同研究者の間で共有した。
(2)電子メールによる共同研究者間の相互連絡を通して、新たな文献情報ならびに 研究理論上のアイディアを交換し、またその成果を研究代表者(池田)と共同研究者 (野村)がそれぞれ利用管理しているインターネット上のウェブページで公開した。 ウェブページの公開によって、この問題に関心をもった研究者ならびに学生と電子メ ールならびにそれを利用したメーリンググループ上で討論し、健康についての実際の 語りや理論構築上のアイディアを情報交換することができた。
(3)期間中に3回の共同研究会を開催し、研究の中間報告をおこない、かつ総合討 論した。また報告書作成や、今回の研究成果を基にした新たな研究の展開についての 方策に関する具体的な審議をおこなった。
「病気と健康の日常的概念」は、近代社 会において医療の専門職集団が構築する言 説に大きな影響を受けているが、独自の領域もまた存在する。我々は、その独自の領 域が、どこまで広がっているのか、その意味の再生産と実践が、どのような形でなさ れるのかについて大きな関心をもった。また「日常的概念」という視座は、医療の専 門職集団においても、同様の知識の再生産と実践がおこなわれているという認識論上 の相対化という効果を生み出すものであることを確認した。
以下に、I. 構築主義による健康文化へのアクセス、II. 身体の社会的構築、III. 健康の 日常的概念、という3点から考察を加える。
I. 構築主義による健康文化へのアクセ ス
本研究の目的は、日本の健康文化を構築主義の見地から分析することであり、本節 はその理論的準備作業にあたる。構築主義という分析視角の核心は、社会問題を「な んらかの想定された状態について苦情を述べ、クレイムを申し立てる個人やグループ の活動」と定義するところにある。「ある状態を根絶し、改善し、あるいはそれ以外 のかたちで改変する必要があると主張する活動の組織化が、社会問題の発生を条件づ ける」と考えるわけである27)。その焦点は「クレイム申し立て活動」(claims-making activity) にある[注1]。
構築主義は、ある状態が最初から「問題」と考えないし「客観的に」問題だと定義 することもできないとする。それは「問題」と定義するクレイム申し立て活動があっ て初めて「問題」となると考える。たとえば喫煙問題は、アメリカの反喫煙運動によ る「悪の創出」過程とそれに対する喫煙擁護勢力との「問題の定義」をめぐるせめぎ あいの社会史として記述されるべきものである32)。
社会問題論におけるこの視角は今日では「社会構築主義」(social constructionism) として各領域の経験的研究に採用されている。家族社会学では家族について語られる 言説によって当の家族が構築されるという視点からの研究がある7)。また、近年の日 本の教育社会学でも構築主義による研究がさかんである3.11.13.35)。
あらゆる知識は、社会的に偶発的 (contingent) であり社会的に構築される。これは医 学的知識もまったく同様であると構築主義は考える。医療社会学やそれを「健康関連 問題」 (health-related issues) に拡大させた「健康と病気の社会学」(sociology of health and illness) で近年「社会構築主義」に立つ実証研究が相次いでいるのは当然の流れと いえよう。
医療について社会構築主義がとられるようになったきっかけは四点ほどある。まず (1)1970年代に始まる精神医学批判。ゴッフマン(Goffman, E.)やサズ(Szasz, T.) やコンラッド(Conrad, P.)は、医学的知識の応用が技術的に中立な営みではなく政治 的な営みだということを強調した。次に(2)現象学的社会学の受容。これを応用し て、病気に対する人びとの態度や常識的観念が社会的に構築されたものとする研究が 現れる36)。そして第三に(3)『臨床医学の誕生』など一連のフーコー(Foucault, M .)の権力論とその方法論的基盤をなす言説分析がある。これに(4)社会問題の構築 主義論の系譜の研究が重なって、1980年代以降の社会構築主義的医療研究の隆盛にい たるわけである。
ネトゥルトンによると、社会構築主義的医療研究の主要論点は次の五点に整理でき る20)。
第一に、現実の問題化。病気はたんにリアルであるだけなく、社会的推論と社会的 実践の産物でもある。それは医学が一定の時間と空間のなかで実験室の試験と理論の 助けを借りて定義する仕方なのである。したがって、それは「発見されたもの」では なく、むしろ「製作されたもの」というべきだということ。
第二に、「事実」の社会的創造。医学の対象(病気と身体)は安定した現実ではな い。クーン(Kuhn, T.)の科学論によると、世界に関するあらゆる科学的「事実」は科 学的共同体の産物であり、フーコーによると、われわれが前提している安定した現実 はじっさいにはさまざまな言説的文脈の中で現実化されたものである。いずれにせよ 科学的事実の出現は科学的共同体と社会的文脈に関連する。
第三に、医学的知識が社会関係を媒介するということ。病気カテゴリーは現存の社 会構造を強化するために応用される可能性があり、その応用は社会関係をあたかも 「自然」であるかのように見せる。病気のことばは客観的であるとされており、その ためその社会的由来が見えにくくなるのである。
第四に、技術的知識の応用。医療専門家は、その本質的に卓越した営みゆえにヘル スケア分業内で優位な位置を獲得したのではなく、特定の技術的な手続きと実践の制 御手段を作りだし維持することに携わってきたゆえに、そうなのだということ。
第五に、医療化。医学は強力な社会統制の制度として作用する。老化・出産・アル コール依存・子ども行動といった、従来は医学の対象と見なされてこなかった生活領 域についての専門的知識にクレイムをつけることによって、医学は通常生活のさまざ まな側面を医学的問題として再定義する。
以上のネトゥルトンの整理によって明らかなように、社会構築主義的医療研究は、 「生物医学」(biomedicine) をメインパラダイムとする西洋近代医学への厳しい批判の もとに生まれた。医学は、身体を社会環境的文脈に位置づけるのに失敗しているにも かかわらず、その有効性が過度に強調され、その結果、専門家支配が強化されてき た。それに対して社会構築主義は医学に対するもうひとつの「身体の経験科学」たら んとする。私たちはそこに「身体の社会科学の誕生」を見る(II.で議論する)。
社会構築主義的医療研究の要衝は言説分析にある。フーコーが切り開いたこの手法 は、日本ではまだ経験的研究が始まったばかりである16.24)。健康をめぐる言説(以 下「健康言説」と省略)には、じつにさまざまなものがあり、その広がりと分節は、 類型設定の基準の取り方によって多様な相貌を呈する。詳細な展開にとって必要な部 分だが、試論的に四つの理念型を提示しておこう。
第一に、語る主体を基準に見た類型群。言説にはエージェントが明確なものと、そ うでないものとがある。後者は「〜といわれている」と受動態表現で語られることが 多い「匿名言説」である。前者については「だれが語っているか」によって言説の構 築効果と経過は異なる。各種の医療専門家による「専門家言説」、メディアによって 増幅される「メディア言説」、そしてクライアントによる「素人言説」の三種が考え られる。
社会構築主義の視角から現在の健康文化を眺めるとき、その重要な構成要素は「素 人言説」である(III.で議論する)。構築主義は、エキスパートの知識的世界とまった く同資格で素人の知識的世界を重要な変数と見る。民間医療や民俗宗教の壮大な世界 観・宇宙観が示すように、それはたんなる「医学的知識のうすめられたヴァージョ ン」ではない20)。
さらに「メディア言説」も重要である。メディアは現実を反映する鏡ではなく、そ れ自体が独自の現実であり、たえず社会的現実の構築に関与する。とくに注目してお きたいのは、メディアが言説に公共性を付与すること。メディアはできごとを公の場 で議論できるできごとに変換する機能をもっている[注2]。
第二に、「残余概念としての健康」か「積極的価値としての健康」かによる類型 群。まず健康は「問題状況の欠如としての健康」といえるが、健康の対概念となる問 題状況は病気だけではない。健康は病気でない状態としても語られるが、障害や老い や死やスティグマや不幸のない状態としても語られる。じつはこの広がりにこそ、専 門家の言説空間と素人の言説空間の大きな違いがあるわけで、あきらかに公衆衛生な どの専門家の言説のほうが健康に関する意味空間を狭くとる傾向がある。これは「総 体的スティグマ化の反転としての健康文化」を構築する。他方「積極的価値としての 健康」は、スポーツや肉体美やダイエットやファッションなど、消費文化の中で意味 づけられた身体についての言説が中心である。こちらは「肯定的身体文化としての健 康」を構築する。
第三の類型設定基準は「予防言説」(問題未然形)か「臨床言説」(問題対応形) かである。これは問題状況の時間的先行の有無による分類である。「予防言説」は健 康に対するリスク因子について語られたものである。「健全な環境」や「心の健康」 になると健康概念は限りなく包括的になり、かつ道徳的強制力を発揮する。他方「臨 床言説」は特定の疾患や症状に焦点が当てられた言説(痛みのことば)と焦点のあい まいな言説(癒しのことば)に分けられる。この類型群はさらに非健康な問題状況と の「闘争」か「共生」かによって分類できるだろう。
第四に、「個人意識の析出としての健康」か「社会の理想としての健康」か。健康 言説が言及する対象の焦点は何か、それによって表象されるものは何かという基準で ある。個人に焦点を当てる言説と社会に焦点を当てる言説、がある。前者の焦点は 「身体表象された自意識」(body consciousness)にある。つまり健康言説がアイデン ティティ構築にかかわる行為として機能するケースである。ここでは「問題状況とし ての身体がアイデンティティを構築する」という事態が生じている(II.D.で詳述する )。後者の「社会の理想としての健康」は公衆衛生的な言説や、感染症に対する社会 防衛論的言説に見られるもので、その裏側には逸脱の創出やレイベリング作用が存在 し、一定の道徳的効果をもつ。
以上、一見平板に見える健康言説の空間的広がりと分節の様子を理念型として提示 した。本節の終わりに、健康言説分析の課題を三点指摘しておきたい。
第一に、これらの健康言説が重要なのは「予言の自己成就」のメカニズムによって 健康文化の現実を構築するからである。「衛生」「養生」「清潔」「健康」「健全」 「元気」「スリム」「スポーティ」「癒し」と、人びとは健康を語ることによって健 康文化を構築し、自己言及的に拘束される。言語行為論の指摘するように、言説は指 示する行為であるとともに事実行為でもある。健康言説によって自己(そして他者) の身体についてのモニタリングとリアクションが生じることになろう。したがって、 言説の自己言及性に着目することが重要になる。
第二に、意味空間の輪郭が不明確で、しかも指示範囲の広い一連の健康言説類型に 注目する必要がある。上記の理念型においてそれぞれ対立項の一端に位置する「匿名 言説」「積極的価値としての健康」「予防言説」「社会の理想としての健康」がそれ である。これらはたんに健康を語るのではなく、健康を語ることを媒介に社会的な何 かを指示しているのであり、「自己への配慮」が相乗効果的に「支配の貫徹」を実現 するという、フーコー流の権力作用を考慮しなければならない。戦時中・エイズパニ ック時・バブル期などに健康言説の果たした「予言の自己成就」的役割に注目した い。
第三に、健康文化を構築するさまざまな「解釈の社会集団」23)のダイナミズムの探 求をすること。健康文化を構成する諸主体の内的過程と相互連関を浮き彫りにするエ イジェント別アプローチが必要である。とくにメディア言説の重要性を強調しておき たい 25)。その分析には社会史・文化史的なギアーツ(Geertz, C.)流の「厚い記述」6) が中心となる。
II. 身体の社会的構築
文化とは、人間社会の活動にみられる諸体系のことをさす。身体を構築するとは、 身体の形態・感覚・観念を造り上げたり、それらを維持するという人間の活動のこと をさす。この定義に基づけば、健康に関する知識のみならず身体もまた文化的に構築 されていることが示唆される。今日では、この見解が多くの人びとに認知されるよう になった。この身体は、生物医学が把握する「生物医学的身体」と異なるかのように 思われるために、「社会的身体」と呼んでおく。
身体の何気ない所作や身体に関する人びとの考え方が、文化的に規定されることを 先駆的に指摘したのはM・モース(Mauss, M.)である18)。彼の構想は、個人のあり 方は社会環境によって形成されると主張したE・デュルケーム(Durkheim, E.)の考え に依っており、社会は文化を通して人びとの行為や概念を規定するという「文化拘束 性」の議論が前提にある。身体あり方を社会の諸相のもとに解明しようとしたこれま での社会学的考察は、明示するしないにかかわらず、この見解を前提に取り込んでい る。日本の社会構造と身体のあり方に関する様々な議論はこの前提を採用した上で、 最も「文化拘束性」の度合いが強いと思われる現象を列挙し、それらを「日本人」の 身体構築の独自性の根拠としてきた。ここで、そのような身体構築に関する人びとの 通念を「身体観」と呼ぶ。
日本の社会構造と関係した身体観を整理すると、そこには反要素還元的で非自律的 な身体への指摘が多くみられる。漢方にみる、身体の健康を宇宙論的な調和と捉える 見方がその例である。病気の原因は個々の臓器の疾患にあるのではなく、臓器間の全 体的な不調であり、治療はそれらの間の調和を目指すことに主眼がおかれる。日本に おける臓器移植への抵抗も身体の損傷への恐怖も、この全体性が失われることから説 明される。
このような「全体論的身体観」は、身体の担い手としての個人の自律性を尊重しな いという事実にも関係している。例えば、身体の所有権が生前の個人にあるという考 え方は希薄で、臓器の摘出が生前の意思よりも家族の忖度に大きく影響されること は、身体の境界は個人のレベルよりも親族のレベルで区切るほうがより重要であると 人びとが考えているためとされる。患者の代わりに親族が医療者に相談し薬を処方し てもらう「患者代理」22)も、その身体観から理解することが可能になる。
ただし、上のような文化の解釈と、予め政治的な動機を以て誘導された詭弁論理は 区分しておく必要はあるだろう。日本医師会はインフォームド・コンセントは「合意 を得るための説明」であると解説したが、これはその思想的背景を無視した意図的な 誤訳である。また、この制度を日本の社会にそのまま導入するには無理があるとい う、日本文化特殊論——広義のナショナリズム的解釈——を「生命倫理学者」と称す る研究者が展開したが、これらは文化概念の無理解にもとづく誤謬である9)。ただ し、より客観性のあると信じられている文化の解釈もまた、その妥当性を外部の権威 に求めなくてはならないために完全に確実な解釈はありえないことも事実である。
身体観が必ずしも日本独特とは言えないのは、次の2つの理由による。つまり、身 体観には、(1)文化の多様性を超えて共通な——通文化的という——ものと、(2) 社会の近代化の結果生じたと考えられるものがあるからである。
通文化的にみられる身体観として、スティグマとしての病いや障害に陥った身体の 排除という現象が見られる。つまり、身体のあり方には社会の道徳的な価値観が投影 され、その価値基準から外れた身体は蔑まれたり、逸脱の刻印が押される。しかしな がら排除と寛容の度合いは、歴史的にも社会的にも多様な広がりがみられ社会構造と の関連性が指摘されている4)。排除され烙印を押される身体の属性について検討する と、排除の対象は恣意的かつ偶発的に決定されるのであって、排除される対象の属性 に普遍的な共通性があるわけではない。また社会的な権力作用によって排除されたも のが、別の権力作用によって受容されたり聖別されることもよく知られており、社会 から排除されている身体を政治問題化することで、社会にその身体を再びとり込む運 動が可能になることも明らかになっている2)。エイズ患者は、欧米社会において当初 極端なモラル・パニックの原因になったが、病気の規模の世界的拡大と患者救済の支 援運動の高まりによって、患者の意味づけが「恐怖の対象」から「支援と連帯の対 象」へと変貌をとげた。もちろんこれは一部の象徴的出来事に変わりはないが、ステ ィグマの恣意性・偶発性を証明して余りある。この傾向は時期的な遅れをとりながら も世界的な広がりをもち各地で生起しつつある28)。
近代化の結果生じたと考えられる身体観は、現代日本社会のみならず、欧米諸地域 ならびに第三世界の都市部においてもよく観察される。ここではその身体観を支える 4つの現象を指摘しておきたい。つまり、(1)人間の生活史において自然なものと見 なされてきた「出産」や「死」、あるいは治療が困難であり状態が固定的な「障害」 が近代医療の対象になるという医療化の現象、(2)病院を中心とする高度医療への受 診が市民生活において重要な出来事であると考える人びとの増加、(3)健康はたんに 病気がないだけでなく、個人の努力で積極的に獲得されうるものという観念の登場と 流布、そして(4)高度医療への受診と平行して行われる健康食品や民間療法の普及で ある10)。このような社会現象は数年から数十年という比較的短期間のうちに起こった ことである。
この節の冒頭で、「文化」は「人間社会の活動にみられる諸体系」と定義し、社会 は文化を媒介にして身体を構築するという見解に立って、日本における身体観につい て論じてきた。ところが、そこで不問にされていた前提がある。それは近代医療とい う「諸体系」は文化現象の外部にあるのか、それとも文化体系を構成する一要素なの だろうか、という疑問である。先の論理に立てば、この答えは「近代社会の医療体系 もまた文化体系の一部である」と言える。つまり生物医学が把握する「生物医学的身 体」は「社会的身体」に包摂されるべきものである。ところが現実生活の中に近代医 療が占める比重が増すにつれて、「生物医学的身体」こそが今日の「社会的身体」の 基盤になりつつあることも事実である。このジレンマは解消されるだろうか。このよ うな状況下においても「社会的身体」が存立する根拠があるということを以下におい て示したい(図.1)。
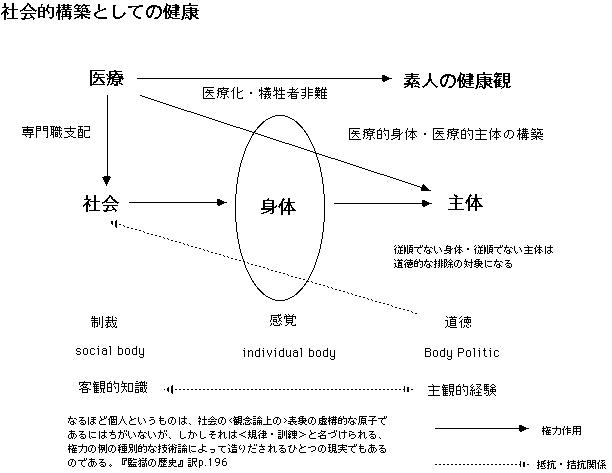
近代医療政策は身体の社会的構築に大きな影響を与えてきた。医療は専門職支配を 通して社会統制を実行する。医療の権威者は、自らの研究成果を健康の生物学的規範 という形で提示する。これは医療化の現象を促進させる。医療はそれ自体で固有の人 間観をもっているために、近代的主体に直接訴えかけることもおこなう。その典型例 は、健康を達成するための自己管理の強調と、そこから逸脱したことに対する道徳的 非難、つまり犠牲者非難のイデオロギーである。
他方、近代医療は歴史的に常に同じ水準と強度で社会の中に普及してきたわけでは ない。近代医療内部の発展と停滞や、医療を受容する人間主体の側の反応によって普 及の度合いは変化してきた。また、近代の情報化社会の中では、マスメディアが発信 する健康言説の影響も無視することができない。
医療が身体の管理技術を極限にまで拡張できないのは、人間が個別の身体をもつか らである。身体の個別性は主観的経験によって根拠づけられ、身体の「文化拘束性」 が限界をもつのは、これによる。社会を身体の隠喩として表象するという営為が、近 代社会においても衰退することがない事実は、社会を身体の完全な外部として把握す ることが人間にとってきわめて困難であることを示唆する。したがって「社会的身 体」とは、個人が身体を媒介して集合的な社会へ働きかける過程それ自体であり、モ ースがすでに指摘していたように同時に「人間の最も自然な道具」なのである18)。
このことは、近代社会の中で身体観はきわめて流動的であり、現状を固定的に見る のではなく、身体のあり様を過程として現状報告することが、研究者の態度としては 現在もっとも誠実なのだというE・マーティン(Martin, E.)の指摘に合致する17)。
III. 健康の日常的概念
「病い」や「患い」は経験であり、また「語られるもの」である。
この病いの経験性と物語性、つまり「病いの語り」(illness narratives)を、医療人 類学者は文化的表象と集合的経験との相互作用で形作られるという枠組みで分析する ことで14)、病気概念の社会的構築を明らかにした。しかし、臨床における「病いの語 り」に比べて、社会生活全般においては、「健康」が経験されるものとして直接的に 明示的に語られることは少ない。
このことは、「健康」の概念の分析を構築主義的アプローチで行おうとする本研究 が直面した困難に通じる。構築主義的分析は、冒頭で述べたように、社会問題の発生 と定立を、クレイム申し立てする個人・グループの活動に求める36)。ところが、一般 に健康は病気(=問題系)の欠如、つまり「非問題系」と見なされており、このよう に捉えられる「健康」概念の構築主義的分析は少ない。ネトゥルトンの研究は「健 康」概念の分析に、リスクと(リスクを回避する)ライフスタイルという、問題系と 見なせるカテゴリーを導入した20)。
本節では、IのC「健康言説の諸類型」で述べた、健康の素人言説を取り上げ、その 言説が、専門家言説、メディア言説との関係の中から、どのように構築されているか を見ていく。なお以下で、人びとと表記するものは、医療社会学でいうところの専門 職の範疇から排除されている素人(layman)のことをさす。
「健康」という言葉が「身体の良好な状態」を指すものとして日本語に登場するの は、1862年に英語のhealthの訳語としての用例が最初である12)。
この「健康」という用語は、仮名垣魯文の『安愚楽鍋』(1871)や福沢諭吉の『文明 論之概略』(1875)にも出てくるように、明治初期には作家や自由民権運動の思想家に よって使われ始める。しかし明治期においての身体の状態を指す言葉としては、江戸 時代から用いられていた「養生」、また長与専斎が『荘子』から引用した「衛生」な どの用語のほうが、より一般的であった30)。「養生」の一般的使用については、「あ る行為を避けることを通して、災厄から逃れ、身体の良好な状態を維持する」という 古典的な「養生の健康観」10)が、当時の人びとにとって支配的な健康概念であり続け ていたからと考えられる。
これに対して、1875年に近代的な言説の文脈の中で初めて用いられた「衛生」とい う術語は、「文明的」と同義的意味あいで使用され、まさに現在の「健康」や「環 境」という用語のように流行した。この「衛生」という用語が意味するところは、 「健康を積極的に目的とする装置・社会制度・システム」であった。明治政府が推し 進める衛生政策は、コレラやペストへの恐怖——それは排除と取り締まり自体への恐 怖にも連なる——を梃子に、「不衛生」は排除されるべき悪であると定義されると同 時に、「衛生的であること」は、それ自身が文明であり価値であるという啓蒙教育政 策も行われた1)。
つまり、日本の近代的健康概念の形成は、人びとの消極的健康概念(「養生の健康 観」)に対して、国家と医療専門家が「衛生」という近代医学的な積極的健康概念を 制度的また文化的仕掛けとして強制(攻撃)することから始まった。この「強制」に より、消極的な「養生の健康観」は、積極的により良き身体状態を追求する「獲得の 健康観」10)へと転換を始める。その転換の開始は大正期から昭和初期と考えられ、健 康文化においては大正期からの健康法流行(健康ブーム)に見て取れるが、この時期 は、歴史的にはナショナリズムが人びとの問題意識として浮上した時期でもあった。 この時期に、国家・医療専門職による強制が、病気を排除するという「衛生」から、 「富国強兵・殖産興業」を達成する兵士・国民の強健剛壮な身体を作る「積極的衛 生」に転換した。人びとが積極的により良き身体状態を獲得する術を求め、江戸末期 の造語であった「健康」という言葉が、「良好な身体状態」を表す用語として人びと に一般的に使われ始めたのである21)。昭和の初期に至って「健康」という言葉を冠し た一般向けの「健康雑誌」が続々と創刊され、先行していた健康法流行を広く世に伝 える「健康メディア」が成立した29)。
ここにおいて、健康言説を構成する「素人言説」「専門家(国家)言説」「メディ ア言説」の構図が成立し、様々な変化を経ながらも、この構図は今日まで続いてい る。
最初に述べたように、人びとが健康それ自身を経験として語る機会は現在でも少な い。しかし、「貴方にとって健康とはどのような状態か?」と、20代から50代の サラリーマンに聞いた調査では、「食欲がある」「病気をしない」「気力が充実して いる」「疲れない」「熟眠できる」が上位5位であった5)。これは、すでに大正期に 京都帝大の衛生学の教授が、健康の証拠として語った「めしうまい、かぜひかぬ、昼 元気よい、夜よく寝る」21)と指摘したことに一致しており、6−70年間の間にさほ ど変化していないことを示唆する。
また、「健康維持のため何をしているか?」という質問では、どのような調査で も、「食生活に気をつける」「休養・睡眠を十分に取る」の2つが、常に上位2位を 占めているが、ここ10年来の現象として、3位に「定期的に健診を受診する」とい う答えが入っていることが多くなってきており、健康の医療化傾向は比較的新しいこ とであることがわかる15.26)。
「日頃の生活の中で、悩み・不安を感じているか?」との質問には、悩み・不安を 感じている内容のトップが「自分の健康」で、2位が「家族の健康」である。同じ調 査で「生活で満足していること」のトップが「自分や家族の健康状態」であり、「生 活で不満を感じていること」のトップも「自分や家族の健康状態」である15)。これに 加え、様々な調査が「労働者にとって自分や家族の健康が最大の関心事である」こと を報告している。
このような調査によって浮かび上がってくるのは、人びとの健康概念の内包は、人 びとの語りによれば、ごく日常的な「あたりまえ」の行為の遂行と達成であり、また 加えるに、その遂行を阻害する病気の忌避である。つまり、健康とは人びとにとって 日常的秩序であるがゆえに、「健康」は最大の関心事となりえるのである。 同じく、 健康を得る術は、過労を避け睡眠・休養を十分取って健康を維持する「養生の健康 観」、健診受診を通して積極的に近代医学の介入を受け入れる「獲得の健康観」、そ して、「食事に気をつける」というその両者の健康観が交差している。これらは日常 的秩序維持のための人びとの戦略とみなすことができるが、「養生の健康観」と「獲 得の健康観」が相互に補完していることがよくわかる。
「経験として語られないもの」を通して得られた「健康」概念は、個別性や個体性 が捨象された平板で均質的なものである。たしかに、集団的秩序の表現形態として肯 定された「健康」は、「たった一つの顔しかない」31)。しかし、この平板で均質なも のとしてたち現れる「健康」概念が、一度人びとの個別性に中に巻き込まれると、そ の様相は一転する。
その試みのひとつとして我々が提示したいのは、集団秩序の表現形態としての健康 を、「集団的秩序を構成している日常的価値・規範・行為」の否定の否定(あるい は、不在の不在)として捉え直す視点である。病気と健康が対概念になっている健康 観からは、一般には健康は「病気の不在」として理解される。しかし、人びとの健康 に関する語りの多くは、病気という概念の介在なしに、または病気という経験の語り を経ないで、日常的秩序を語っている。人びとは、病気と健康の対概念を認めない。
健康が病気(否定)の専門家によって説明し尽くされない理由はここにあり、「健 康文化」の社会科学的研究はここに存在理由を見いだすのである。
この研究においては、将来の実証的な総合調査のための理論的な諸前提を確認する 作業に、その期間のほとんどが割かれた。理論の基本的な構成をなすのは、次の3つ の観点であった。つまり、I. 構築主義による健康文化へのアクセス、II. 身体の社会的 構築、III. 健康の日常的概念、である。
これらは、それぞれ、I. 相対化の作業としての構築主義的理解、II. 言説構築の臨界 点としての身体の再検討、III. 「健康」概念が、病気がないという「否定的な問題の否 定」という論理構成においても意味の構築においても、複雑で逆説に満ちた言説の構 成がおこわれているという経験的事実を確認することとなった。この一連の作業は、 「病気と健康の日常的理解」について理論化する際に必要で欠かすことはできない視 座を提供することが判明した。
注
[注1]構築主義的社会問題論については、中河伸俊19)。文献については中河伸俊に よる詳細な「構築主義社会問題論の文献」 (http://jinbun1.hmt.toyama-u.ac.jp/socio/nakagawa/biblio.html) を参照のこと。
[注2]メディアが独自の現実を構築する点については、議題設定機能研究や沈黙の螺 旋理論や培養分析で指摘されてきたことである。さらに公共性付与についてはタック マン33) を参照のこと。